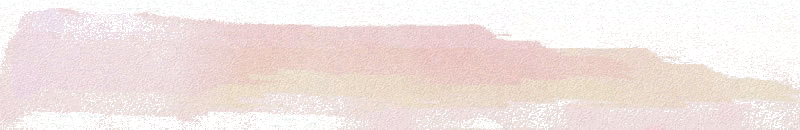創世記
日頃は静寂な聖域に興奮が渦巻き、人々はいつしか自他の区別を忘れて一つに溶け合っていく。火祭の火は神意に委ねられているかのように、人間社会の一切の効用を離れて、ただひたすら燃え続けるのです。 わが国では古来、四季折々にさまざまな火祭が催されてきました。
正月の注連(ちゅうれん)飾りなどを燃やす「どんど焼き」(左義長(さぎちょう))は、いまも各地でみられます。
奈良・若草山の「山焼き」(1月)や二月堂の「修二会(しゅにえ)」(3月)、和歌山・那智大社の「那智の火祭」(7月)、京都・大文字の「送り火」(8月)や由岐(ゆき)神社の「鞍馬の火祭」(10月)、志賀・太郎坊宮の「御火焚祭(おひたきまつり)」(12月)などは全国的にも有名です。「花火」や「ねぶた」や「灯籠(とうろう)流し」も、一種の火祭だと言えるでしょう。
火祭は世界各地でもみられる。太古の人々の心に芽生えた火に対する畏敬の念が、さまざまに形を変えながらも、火祭としていまも受け継がれているのです。
数々の優れた随筆を残した白洲正子(しらすまさこ)さんによると、京都・北山のはるか奥の花背峠を越えた保津川の川上に、原地という部落があって、古代のままの火祭が残っているそうです。
毎年8月23日に行われるその火祭を見物に訪れた白洲さんは、「まばゆいばかりの火の海」を目にします。
一間おきくらいに丈の高い松明のような「地松」が立ち、それが何千となく野山を埋めていて、それに一斉に火がついたために「火の海」が現出したのです。それにもまして感動を誘ったのは、「松あげ」だったと言います。
© Rakuten Group, Inc.