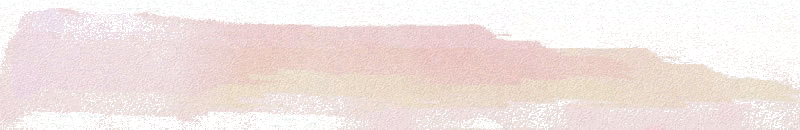全687件 (687件中 1-50件目)
-

ユーロポイドとモンゴロイド
パレスチナのカルメル山にあるタブーン洞穴の「女性」の骨格はネアンデールタール人の体の上に、丸くてずっと現代人的な頭がのっているという明らかに混成的なものであった。北部イラク山岳地帯のシャニダールの洞穴では、顔の上部全体が現代人的風貌をもつネアンデールタールの変種が見つかっている。それは4万5000〜44,000年前のものである。その近くのスリフル共同墓地から出土したものは、ネアンデールタール人よりもクロマニヨン人に近接しまた現生人誕生の前夜といえるまで進化したものであった。イスラエル北部のアームッド洞穴からは、頭はネアンデールタール人でありながら顔はホモサピエンスという、古いネアンデールタール人と現代人とのつながりを示すものが発見されている。その年代は40,000年前より前であるとされている。クリミヤ半島の突端のスタロセリエ洞窟でも、1〜2才の子供が埋葬されているのが発見された。たぶんにネアンデールタール人の特質を残しており、ネアンデールタール人とホモサピエンスの一種であるクロマニヨン人との中間的位置をしめるものとされている。このようにして確かめられた現生人類の祖先は、ほとんど現在のヨーロッパ人的なものであえうから、学者はこれを【ユーロポイド】と名付けたのである。これらは、西アジア、中央アジア、この地域で何故ヒトの進化がありえたのでしょう。当時、リス氷河期には、この地方では、気候が湿潤化し、広葉樹林、落葉樹林、そして多くの湖や河川、多種多様の食料源に恵まれるという人類の進化に最も適した地域だったからでした。この地域に現れたユーロポイドのことをアジア的ユーロポイドと呼んだ。彼らはやがて、被氷地ユーロポイドと、アフリカ地中海的ユーロポイドを生む。一方シベリアを見ると、ネアンデールタールじとホモサピエンスの過度期の型からホモサピエンスにまで進化したものが、バイカル湖にそそぐアンガラ川沿岸のマルタでも発見されたのである。これはシノ・シベリア的モンゴロイドと名付けられた。その他、ウラルの東、天山(テンシャン)の北にもモンゴロイドを見出し、これはツングースモンゴロイドと名付けられた。何故ここにも人類の進化が行われたのでしょう。その時期にあっては、アルタイ山地、サヤン山脈、ヤブロノイ山脈の北面には未だ氷原がまだらに残って寒気は厳しかったのであるが、その南面には樹林が茂り、その下草が萌え温暖であり、そしてその南には湖沼を連ね、緑に囲まれた東トルキスタンという盆地があったからである。したがって、この時期では、東トルキスタンの北壁と東トルキスタン、中央アジア、西アジアは、人類進化に絶好な環境に共通する一つの世界をなしていた。では、何故被氷地人類がこの進化に立ち遅れたのでしょうか。シベリアの中央高原が東西を隔離しているオビ川流域は氷原で、これもまた第2の隔離であった。ドン河とドニェプル河の線には未だ氷河が残っていて、それはアルプスに連なる欧州の山脈におよんでいた。その環境がホモサピエンスの出現をシベリアの南側・東パキスタン・中央アジア・西アジアの広地に限ってしまったのである。
2022/08/27
-

インダス人 アーリア人
インダス人の出自はメソポタミアのシュメール人。このシュメールの人々の出自を太古にまで遡ると少なくとも16万年前にアフリカを出発しインドネシア辺りのスンダ列島から北上した古代モンゴロイドの縄文人がベージリアンが冠水したためアメリカ大陸への行く手を阻まれ、その地に留まらざるを得なくなり、その津軽半島の大平山元で今から1万6523年前に世界最古の土器(無紋式)を発明して作り出しやがてアムール河を遡行してアジア大陸を南へ、そして西南へと移動し、時として北極までも追われ、そこで寒冷地に耐えることができました。その一部がその後長い年月を経て氷河が溶けて出来た当時の巨大なタクラマカン大湖を経由してアフガニスタンのバタフシャンのラピスラズリとともにインダス河口から海路シュメールへと移動し(オアンネス魚人神話)そこでもBC3300年頃、世界最古の文字である楔形文字を発明するなどの文明を創り出していったと考えられます。この高度の文明を有していたインダス人の末裔が征服アーリア人から虐げられ今日、南インドやスリランカにまで追われてしまったドラヴィダ人だったのです。インドに侵入したアーリア人の中にカッシート人が含まれていたことはヒマラヤ山脈のヒマラヤという言葉自体がカッシート語に見られます。シマーラヤ(雪山中の女王)から名付けられています。そしてアーリア人もかつて最後の氷河期の到来により北極圏経由してインドに至ったことは(寒冷地適応)サンスクリットで書かれたリグヴェーダに暗示されています。プロト拝火教は北極圏での夜の暗黒に対しての恐れに由来するもの寒さに対しての苦しみからの由来するものだったのです。
2020/03/31
-

日本民族を形成するアジア五加
古代の人類集団は、【トーテム】をもち、そのトーテムの名で呼ばれます。【牛】の原産地はメソポタミア。そのウルク期に於いて牛はウルと呼ばれていました。牛族が王族となったため、ウル王朝と呼ばれ、都市もまたウル市といわれました。それから34世紀経ったBC1世紀、古代満州の扶余に牛を部族名とする【牛加】が実在しました。【加】とは、人の意であり、部でもあります。【牛加】が官名であると同時に部族名でありました。 牛加には二種あり、一つはウル族、一つはシオ族。この【塩族・シオン族】は、BC2800年前後頃から、牛族のウルクと帯同して原郷のメソポタミアを離れ、インドでは釈迦の名で呼ばれ、殷では、【召方ショウホウ】と呼ばれました。【日本書紀】垂仁天皇二年の条の第一の一書にあった【額に角の有る人】という記述は 牛の角形のついた冠帽をかぶった人の形容で、これが【兜】になり、二本の牛の角のある【牛冠】をかぶる古代の習俗だったのです。【ツヌガアラシト】はツノガアルヒト(角がある人)であると共にアラシトは、後代実在した加羅の人名、また王号でもありました。【蘇】は【于斯うし】牛の朝鮮語のsoです。【牛冠】とは、人間の身分を表し、【王】のシンボルだったようです。BC2500年、アッカド王国では、ナラム・シン王がかぶっていました。BC800年、ウラルトゥ王国では、牛冠のスフィンクスが王座の一部でした。祟神・垂仁朝、牛冠をかぶっていたというウシキアリは王子でした。【日本民族を形成するアジア五加】馬族・・・・・アルタイ系種族(白人系)牛族・・・・・オリエント系種族・シュメール人(白人系)犬族・・・・・印欧系アーリア種族(白人系)鳥族・・・・・殷人(黄色人系)蛇族・・・・・原南洋人(オウストロネシア語族(黄色人系)縄文晩期の西日本は、原南洋人、オウストロネシア語族、蛇をトーテムとするオラン・ラウトの生活舞台でした。次いで弥生早期に洛東江流域から南加と原シナ人(鳥をトーテムとする猪加)という猪加とは、チュルク族、つまりトルコ人のことです。猪加というのは、扶余の王族である馬加の文化人が蔑んで名づけた名でした。黄色人同士、稲作農耕民であるところの二種族が西日本へ渡来しました。これが日本列島へ稲作文化を搬入した二加であり、原畿内人であり、銅鐸人であったと考えられます。次に、弥生中期になると、扶余の王族、高句麗の前期王族、そして、馬韓王の系譜につながる馬加を盟主とする連合軍が、まず北九州の松盧国に上陸し、以後しだいに先住の狗加、牛加、猪加、南加たちを制圧して九州に入りました。これが日本の天皇氏族であり、種族の系譜としては馬をトーテムとするアルアイ系人種、すなわち北方騎馬民族の一種です。また、馬加が西日本一帯を完全に制圧したのは、【三国志・魏志・倭人伝】によると、247年、九州の狗奴国(狗加の国)が邪馬壱国に敗北した時点になります。弥生時代の【弥生】という名は東京の本郷弥生町からとったものでありもとの地名は【向ガ岡】、ムコガ岡を語源学的に表記し直せば【馬加賀岡】。即ち、東大農学部構内の弥生土器が出土した地点には弥生後期、馬をトーテムとする人間集団馬加が小邑落をつくっていたのであり、そこから出土した弥生土器はアルタイ系人が使用してものでした。また、大森の久が原遺跡は、弥生中期、狗加族(くかはら)が住んでいた跡であり板橋の前野遺跡は馬拝(まへの)が住んでいた後期遺跡であって、日本中の古代遺跡跡地の【地名】は、みな、そこに住んでいた種族、アジア五加の名が付けられていたといいます。現在、地名がどんどん新しく改変されています。歴史の唯一の手がかりを惜しげなく消してしまっていいのでしょうか。
2017/04/19
-

ウルの人々~秦氏
"Ur"という言葉は、【非常に古い根源的なもの】を意味します。Urbefolkning ;原住民、先住民族Urkraft ;根源力、底知れぬ力Urkristendem ;原始キリスト教Urkund ;原本、原典Urminnes ;太古(以来)のUrtid ;原始時代、先史時代【ウルの牛(Uroxe)】は、原牛(古代に住んでいた牛)を意味するそうです。ウルは、アナトリアのチャタルフュイックの牛頭信仰に繋がっていると考えられます。アッカド人が現われる前のメソポタミアは、シュメール人とウル人が住んでいました。シュメール人は蛇を、ウル人は牛をトーテムとする人たちでした。そしてウル人がシュメール人を支配していたらしい。牛の頭に対する信仰【牛頭信仰】は、後の人類の歴史の中に系譜が遡れます。日本国のスサノオのミコトも牛頭大王という別名をもっていますし、牛頭天王というのは、古代天竺(インド)に居て、釈尊の教国の僧坊である祇園精舎の守護神だったといいます。牛頭神はヨーロッパにも見られ世界文明の主なる流れの最高神だった可能性があります。BC3000年頃からインダス河口が人々の移住を許すようになるとセム族に圧迫されながらエラム、ドラヴィダ系の人々が南下し、前2350年頃から、アッカドのサルゴン王家は河口のロートルに上陸し、筏に乗せて牛を揚陸させました。インダスに於いては牛が貴重品であったため支配者のアッカド人とウル人はドラヴィダ人に聖牛思想を教え、牛首のバァル神の崇拝を強制しました。それまで、ドラヴィダ人の祭神は【ヤオロチ】即ち蛇神であり、シュメールではサルゴン時代からバァル神とディルムン説話が生まれていたのです。したがって、これ以降インダスでは聖蛇信仰と聖牛信仰が併存しました。アッカド人とウル人はグート人に圧迫され、前2000年以前に、チベットから黄河沿いに下降して彩陶文化を残すのですがウル人はチベットのホータンを中心として月氏となります。月氏の前身はカッシート人といい、そのカッシートの前身がウル人だったのではと考えます。アナトリアで自然銅を加工する技術を最初に発見した人々が牛頭信仰のウル人であり、銅、後には錫や金・銀・鉄を探鉱するために世界に散り、あらゆる民族の基になったのではないか? なぜなら、彼らウル人の痕跡が北方ヨーロッパ各地にも残っているからです。シベリアや東アジア、アメリカ大陸にも鉱山を探しに移動しています。彼らの鉱物を需要していたのが、メソポタミアの広大な農場でありエジプト王朝だったらしい。インドは、それらを円滑に行うためのコンビナートであり、精神性を高め民族の宇宙観を極めていったスピリチュアルな聖地だったのではないかと思うのです。ウル人は、月氏であり、サカ族になり、倭人の中心的存在であったと考えます。サルゴンの後、リムシュ→マニシュトス→ナラムシンが継承します。【ウル第三王朝】BC 2190~2005 【前期イシン王朝】BC 2017~1794ダミクイリシュ王の時、イシン王朝は一旦滅び、一族(イシンの人々)はラルサのリムシンに征服された後、エジプトに逃れ、ヒクソス国家をたてた後、再びカナンの地に逃れ、エブス人となり、その地でユダヤ人に出会いました。メソポタミアでアラム族のイシン本国が亡び、アッシリアが栄え、中国大陸に支配が及ぶと中国のアラム族も圧迫され、南湾の凌河流域に後退して箕子朝鮮を建てました。イリのアルタイは、シルクロードで一番の金山でしたので、アラム人たちは此処を根拠に決めました。この人々の金姓は、ここから始ります。タクラマカン砂漠の北部、イッシク・クル湖からクチャを経て、カラシャール、トルファンにかけての地帯が箕子(シン王の従兄)またはシウ殷の故地でした。砂漠の南部、ホータンからチェルチェンを経てロプ湖畔の楼蘭に至る地帯が辰国=ウガヤ王朝の故地になります。この後、アッシリアに抵抗して亡命した海の国カルデラ人(サカ族)が西方のアラル海とアム河・シル河、両河に挟まれた原野地帯に扶余を建国し王家は昔姓でサカ族の王を称し、王号を【シウスサカ】といいました。月氏族で朴姓のアメニギ氏が辰国をたてて三国が擁立しました。ヒンドゥークシュ山中に源を発し中央アジアのアラル海に注ぐアム・ダリア大河流域にはかつてバクトリア王国が存在していました。この国はBC4世紀後半のアレキサンダー大王の東方遠征に伴ってつくられたギリシア人の植民国家でした。アレキサンダーの死後はセレウコス朝(シリア)、マウリア朝(インド)アルサケス朝パルティア(イラン)などの手に委ねられましたが、最後はBC145年頃、北方から侵入してきた遊牧騎馬民族のスキタイ(サカ)によって滅ぼされました。このスキタイ(サカ)は、かつて中国西北部の河西回廊から敦煌にかけて勇躍していた月氏(大月氏)のことですが、後にガンダーラからインドへと進出したクシャン族であったとも言われています。そのクシャン族がタリバンによって破壊されたバーミアンの大石仏を造営したのです。アショカ王の説話は彼らサカ族の扶余人が、コータンを支配するアメニギ氏(アッカドの末裔)系の月氏を憚って、サマルカンド南方のバクトリアに建国した事実を示します。BC256年、バクトリア知事ディオドトスが、クーデターによって政権を奪い、グレコバクトリア(大秦国・大夏国)を建て、ディオドトス1世と称しました。BC246年、ディオドトスは、バクトリアの統治を2世(胡亥)に任せ、自らは精強なペルシア軍団を率いて中国に至り、秦の始皇帝と名のり、諸国制覇に乗り出しました。BC239年、秦始皇帝の余波を受けて、申国(大夫餘)にいたウガヤ42代・解慕漱(かいぼそ)が東北(満州)へ逃れ、松花江河畔の農安に北扶余王朝(前期王朝)を建て王となりました。同じ頃、マレー海峡のヤーヴァ・ドヴィーバの移民たちが沖縄から移って建てていた中山国が滅び、国王・綽(しゃく)が蜀へ移されたため、遺民たちは遼東へ移動し、原ツングース(韓人)を従えて箕子朝鮮(智淮氏燕ちえしえん)を再興しました。BC221年、ディオドトス1世、秦王政が中国を統一して秦帝国を建て、始皇帝と称します。BC213年、秦始皇帝(ディオドトス1世)による焚書坑儒事件が起こります。箕子朝鮮の上将卓が帯方(月支)に辰国を建て、秦の亡命者は、慶州に馬韓の分国をたて辰韓と称しました。この時、箕子朝鮮系の馬韓人に従って渡来した倭人が【北倭】でした。北倭と秦の亡命者は、エビス王から鳥栖河と背振山脈の間の地、吉野ヶ里を譲られ倭奴国(秦王国)としますが、後に神武と公孫氏に敗れ、出雲経由で大和地方に【秦王国】を建てます。馬韓人に領土を与えたという【東表国王クルタシロス】が【倭面土国王師升】のことです。このシロス王は駕洛史では金官国の【首露王】になり、新羅史では金氏の祖の首留日本史では孝元天皇になっています。
2017/03/21
-

女系社会から男系支配へ
中東は、アジア、ヨーロッパおよびアフリカの三大大陸が結合する地球上でも珍しい地域です。それに紅海で裂かれたアラビア・プレートが、アジア大陸に衝突し、ザクロス山脈をつくっているところです。1億年以上前、そこは浅い海でした。海の底の藻類やバクテリアの死骸がゆっくりと沈み、地下奥深く堆積しました。そして、地熱の働きによって、石油へと変成したのです。その中東の資源は昔も今も多くの人々を惹きつけています。それは、初期の農耕によって生み出されました。 では、農耕はどのようにして始まったのでしょうか。ナイル川の畔に文明が誕生したのは、気象変化のためだったと考えられています。昔々、北アフリカは、今よりはるかに温潤で植物が多かった。最初に農業が開始されたのは、12500~10200年前に存在した地中海東部のナトゥフ文化といわれるパレスチナのエリコでした。 さらにエリコの人々はアナトリアのチャタルフュィックで自然銅を発見しその銅を加工する高温技術を発明したと思われます。特筆すべきは、アナトリアの女系性です。壁画、漆喰浮き彫り、石の彫刻、粘土製のおびただしい【女神】小象、すべて女性崇拝の品々が発掘されています。この現象は、おそらくエリコからすでにあり、6000年頃にはアナトリアから農業の伝播とともにメソポタミア、コーカサス南方、カスピ海南方、それまでは辺境であった地域にまた一方では南ヨーロッパへと拡大し始めます。この地母神は、クレタ島やキプロスにも海路によりつながっていったのです。【大いなる女神】が、ときに鳥の姿になったり蛇の【女神】になったりしながら、水の生命授与力を支配し、ヨーロッパとアナトリアでは雨を孕み、乳を与える、そういう文様が刻まれています。アナトリアのチャタルフユィックの遺跡からは、母系で妻方居住の社会構造が現れました。その構造は、チャタルフユィックからクレタに移住し、太古地母神《女神》と共に農業技術をもたらし、つづく四千年の間に、土器製作、織物、治金、彫版、建築、その他の技能およびクレタ独特の生々とした喜びに満ちた芸術様式の進歩がありました。そこでは富は、公平に共有されました。年上の女性ないし氏族の長が大地の実りの生産と配分をつかさどり、実りは集団の全員に属するものとみられていました。主要な生産手段の共有と、社会的権力は、すべての人の利益になるよう図られ、責任のもとに基本的に共同的な社会組織が生まれていました。これは、パレスチナの世界最古の町エリコナトゥフの人々が成功していた共同社会につながると思われます。太古地母神《女神》を中心に女も男も異なった人種の人々も・・・共通の幸福のために平等に協力して働いていました。母系による相続と家系、至高の神としての女性、現世的権力をもった女司祭と女王の存在はありましたが男性の地位が低いということはなく、両性は平等な協調関係を築いていました。男女仲良く手に手をとった姿は、今でも道祖神のなかに見受けられます。彼らは、たいへん自然に親しんでいて、アニミズム(精霊崇拝)はクレタだけでなく、ケルト民族にも伝わりました。太古地母神《女神》を中心にした文化はアナトリアを中核として地球一周しました。ストーンサークルやドルメン、メンヒルなど、これらの祭祀が彼らの残した足跡です。しかし、その女神崇拝文化も侵略され滅亡される時がやってきました。 最初、それは家畜の群の草を求めて彷徨う一見取るに足りない遊牧民の集団にすぎませんでした。数千年以上も、どうやら彼らは地球の端の誰も望まぬような厳しく寒く痩せたシベリアに住んでいました。その遊牧の集団が長い期間をかけて数と獰猛さを増しヨーロッパ北東からヨーロッパ大陸に群がり南下し侵略してきたのです。彼らは最初のインド・ヨーロッパ語族あるいはアーリア人といわれるクルガン人。あるクルガンの野営地では、女性住民のおおかたはクルガン人でなく、新石器時代の太古地母神《女神》崇拝の人々であったことが発掘資料から判明しています。このことが暗示しているのは、クルガン人が、その土地の男性や子供たちの大部分を虐殺し、女性たちのある者だけを助けて妻や奴隷にしたということです。遺跡から農機具のみで武器というものが見あたらない【平和】で【民主主義】な社会が営まれた《女神》崇拝社会が破壊され、男性的支配社会の始まりでした。インド・ヨーロッパ語族は、先の文明を築いていた太古地母神《女神》を崇拝する農耕民族を次々侵略していったのです。インドに於けるアーリア人、【肥沃な三日月地帯】に於けるヒッタイト人とミタンニ人アナトリアに於けるルヴィ人、東ヨーロッパに於けるクルガン人、ギリシアに於けるアカイア人および後のドーリア人、彼らは征服した土地や先住民の上に次第に自分達のイデオロギーと生き方を押し付けていったのです。このほかにも侵略者はいました。ヘブライ人と呼んでいるセム系の人々です。
2017/03/21
-

ミトラ 蘇我氏
カシート王朝から月氏王国、クシャン朝からサカ族~蘇我王朝につながる人々は交易においても重要な役割を担いました。中東は文明の十字路でした。数多の民族があらゆる方向からやって来て相争い、王朝を立てては滅んでいきました。「ムー」という雑誌の1999年12月号に「シャンバラ伝承と謎の古代文明クスターナ」という記事が出ています。シャンバラはシャングリラー。理想郷という意味です。またクスターナは、梵語で「大地の乳」を意味する言葉で、その後、クスタン、コタンと変化し、現在の新疆ウイグル自治区の町、ホータンだといいます。「ムー」の記事によれば、崑崙山脈から湧き出した清流が白玉川(ユルカンシュ)と黒玉川(カラカンシュ)という二本の川となってコタンの東西を流れ、その水が「大地の乳」なのだそうです。言い伝えによれば、コタンの町の近くにはアルティンタックと呼ばれる純金の山があり、無尽蔵の金が掘り出されていたといいます。さらに白玉川と黒玉川の両川からは、玻璃や瑠璃など玉が豊富に採れたともいいます。ラピスラズリの産地は、アフガニスタンの奥地、バダクシャンです。BC6000年頃から世界中に銅資源を求めて探し回った人々は、BC4500年頃には、東シベリアの銅や錫鉱石を採掘していた可能性が高く、それらの銅や錫は、メソポタミアまで運ばれていました。これらの銅や錫鉱石、ラピスラズリをメソポタミアに運んだ鉱山技術に優れた人々が、月氏=サカ族でした。彼らはイラン高原東部からバクトリア、ソグディアナ及び西北インドにかけてサカスタン王国を建てています。アケメネス朝ペルシアがパルティア帝国に滅ぼされた後のことでサカスタンは(サカ人の国)はペルシアの一部を引き継ぎました。BC6000年頃から世界中に銅資源を求めて探し回ったウルの人々が、文明の十字路クスターナを根拠に拡がっていったと考えられます。倭人には、北方性と南方性がありますが、南方性は弥生農民の文化です。倭人は、カルデラ人を中心とする南セム族であったのですが、バクトリア南部のシスターン(サカスターン)地域では既にサカ族の名になっていて、この地のサカ族は、ペルシアのキュロスの時、降伏して、ヒスタスペスの支配を受け、後ペルシア王統が乱れた時、ヒスタスペスの子がダリウス一世となっています。蘇我氏と、その一族が目指した方向というのは、仏教中心の政治でしたが、それは中国のものではなく、より西アジア的なものでゾロアスター教というより、もっと根源的なミトラ教的宇宙観でした。ミトラ教は、メソポタミアからペルシア、ユーラシア全域に広がった、太陽信仰・光明信仰でした。北メソポタミアの王国ミタンニがミトラ国という意味であり、ヒッタイト王国の王室も「聖なるミトラ」と名付けられ、日本の天皇も宇宙を統べる皇帝すなわち「ミトラの皇帝」と意味する『スメラミコト』と称される。ミトラは古代ペルシア語の一部の方言でミシアと呼ばれましたが、それがメシアとなりました。フリーメーソンの起源もミトラであり、弥勒菩薩もそうです。それに加えて鳥のシンボリズムもあります。蘇我氏のルーツサカ族は、アケメネス朝ペルシアがパルティア帝国によって滅ぼされた後、ペルシアの一部を引き継ぎ、イラン高原東部からバクトリア、ソクディアナおよび西北インドにかけてサカスタン王国を建てました。パルティアは470年ほども存続した巨大帝国でしたが、世界史上あまり知られていません。ペルシア帝国と同様、ミトラを国教とし、皇帝の名もミトラからとっています。パルティアを中国では安息国と呼びアンソクまたはアンキと発音しましたがそれが元来アサカ(アスカ)であったようで、日本の飛鳥につながります。シスターンに出来たサカスタン王国は、そのパルティアから、より宗教的に強い主張を持って【独立】した勢力でした。やがて彼らは東に移っていったのですが、シスターンに遺した彼らの貴金属の透かし彫りの技術は美しく精巧で学者の関心を惹いています。
2017/02/04
-

第三の眼 松果体
第三の眼。 二つの眼の間に位置する、もう一つの眼のことをいいます。仏像の眉間にある小さな丸いもの、これは衆生救済のための光を放射する「百毫」と呼ばれるものです。仏さまは、この第三の目を通して霊的世界に通じているといいます。ヨーガでは、体からエネルギーが発生する重要な部位を「チャクラ」といいます。これは人体に七個ありますが、そのうち一つが額の中央に位置する「サードアイチャクラ」です。この第三の目は「神の座」とされ、チャクラのなかでも特に重要視されています。驚くことに、私たちの遠い祖先も第3の眼を持っていたといいます。その痕跡は今も私たちの脳の中にあって、眉間から奥脳の中心辺りに光をキャッチしてメラトニンというホルモンを分泌する磁気センサーに相当する松果体という器官が第三の眼にあたります。松果体は珪素で出来ています。珪素(英語名シリコン)は宇宙では7番目に多い元素、地殻の約28%は珪素であり、酸素に次いで2番目に多い元素です。ケイ素の振動波が、宇宙の情報に通じると考えられます。太古の人々はテレパシーや透視力を日常の生活に取り入れていたそうです。テレパシー、透視力は右脳が開かれて宇宙の心と一体になったときの力です。古代人は岩石と岩石の間に自分を挟み宇宙人と交信していたとする壁画や遺跡で伝承されています。http://www.scribd.com/doc/16839498/Plasma-in-the-Lab-and-in-Rock-Art この宇宙の波動と共鳴・共振するときの入り口が「間脳」の中にある「松果体」という小さな器官です。松果体をヒーリングする事により、ひらめきやシンクロという宇宙からの情報を受け取ることで、生命力という情報処理能力を高めてくれるといいます。松果体は、さまざまな脳内ホルモンをコントロールしています。人間の肉体も意識も、この松果体によってコントロールされていますので松果体をコントロールすることができれば、宇宙の波動と同調することができると考えられます。【松果体】は脳の中にありながら、細胞レベルでは驚くほど眼、特に網膜の細胞と構造が似ているそうです。松果体になる細胞がごく若い胚の時期には、レンズ、色素上皮、網膜ニューロンなど、眼をつくる細胞になる可能性(分化能)、すなわち松果体は眼になる可能性を持ちながら、眼とはまったく別の器官に発達してきました。松果体の細胞はなぜ、眼になる可能性を秘めているのか?それは、サルより遥か昔に遡った人間の祖先にあるようです。 生物の眼は、進化の過程のごく初期に完成しました。動物には骨のある脊椎動物と骨のない無脊椎動物とがあり無脊椎動物が先に現れました。このうち背骨の前駆体の脊索をもつ原索動物がカンブリア紀頃脊椎動物に進化しました。現生の原索動物では、ナメクジウオが最も人間の先祖に近いとされます。ヒトとナメクジウオの遺伝子は少なくとも6割が共通しており、遺伝子の並び順も似ていることがわかっています。ナメクジウオは一つ目です。松果体は、太陽の電磁場エネルギーをメラトニンに変える働きをします。このメラトニン・ホルモン分泌の強力な影響によってバイオリズムを完全にコントロールし、女性の受胎力も与えられるようになっています。古代マヤやエジプト文明では、かなり詳しく研究されており太陽を受胎力の神として崇拝していました。彼らは地球や月、太陽、星などにも、同調して暮らしていたようです。生物は太陽なしには生きながらえることができませんでした。植物に比べ、動物は自分では太陽エネルギーを利用できずほかの生物のエネルギーを奪って生きる方向に進化した生物です。そのために最初に進化した動物の器官が腸です。腸の入り口が口、出口は肛門である単純なミミズのような生き物でした。そして腸を包む外側の細胞群のうち背側のものが板状になりやがて、餃子状に身体の内側に落ち込んで別の管をつくり、これが神経であり、脊髄になります。こうして、最も外側の細胞群が身体全体を包み込む皮膚になりました。腸の一部がふくらんだものが胃になり、胃に至るまでの部分が食道です。脊椎動物になると、ミミズのような管の口側の先端がふくらんで脳になり、この時に、それまで体の全長に散らばっていた光覚器官が頭のてっぺんと両側に集中し、間脳の背面がふくれ出しました。これが眼のような構造をもつ頭頂器官です。ナメクジウオの一つ目です。今ではニュージーランドのムカシトカゲしか見られない、第三の眼、頭頂眼です。高等脊椎動物では、大脳半球がふくれて頭頂器官は覆われ進化の過程で頸の動きが活発になると上の眼は不要になり結果、松果体は眼としての機能を失い、光に反応する内分泌器官となったのです。しかし、光に反応するメラトニンを分泌する松果体は宇宙の波動と共鳴するとされ、古代の人々、特にジャーマンは松果体を活性化し、太陽や月、星など宇宙と同調して超能力を発揮していたようです。松果体こそ人間の根源の働きを秘めたところでした。。松果体はとうもろこしの粒ほど小さな器官です。この器官は人間の体の中で一番最初に完成し、受胎後3週間ではっきり確認できます。36億年前、粘土(ケイ素+アルミの化合物)の海で、電気信号(雷)の刺激に因って生命が誕生したことから遺伝子DNAの源自体がケイ素でありました。ケイ素とアルミは結び易く、日本の河川の水が澄んでいるのは、岩から溶け出したケイ素が、直ぐにアルミと化合して粘土と成り、沈殿するからだそうです。現在の都会では、浄水場でアルミを投入し、汚れを沈殿させ浄化させているのだそうです。すると、ケイ素はアルミと化合して、水中から無くなってしまい、ケイ素の欠乏、逆にアルミの取り過ぎになってしまう。「アルミ」は、アルツハイマー病の原因の1つだそうですが、珪素が有害なアルミニウムの吸収抑制に働く物質ということから珪素不足は、 研究しなければばらない課題となりましょう。人間は、水道が整備されるまでは、山水や井戸水を飲んでいたので、体に必要なケイ素は不足することがありませんでした。 渡り鳥や回遊魚などの体内から、生体コンパスともいうべき磁性物質が相次いで発見され、人体にも同様の器官があるらしいということが解明されてきました。かつて人類も鳥や動物のように、地磁気を感知する能力をもち、採鉱をし宇宙と同調して暮らしていたことが鮮明になってきました。松果体は、硅素に拠って出来ており、「珪素」は、磁場に強く反応することから鳥が松果体に拠って時を計り、鳩は、遠くへ放たれても自分の巣へ帰り、渡り鳥は自分の体の内に羅針盤を持っていると考えられます。ヒトも植物同様に体内のケイ酸塩の圧電性から規則正しい波長を出し、どんな弱い波動でも分子や細胞と共振すれば、生命現象に大きな影響を与えます。樹木の葉は落葉され土壌菌によってケイ素が溶出され、川や海の魚類達は豊かなケイ素から豊かな魚場を形成するという正しい生態循環が自然に行われていた古代を生きていた人々の叡智は現代人を遥かに超えたものでしたでしょう。。
2017/02/04
-

溶け込んでいった古代ユダヤ王朝
日本人とユダヤ人のルーツについて、日ユ同祖論があります。半信半疑でしたが、調べれば調べるほど、その要素が濃く認めないわけにいかなくなってきました。確かに、彼らは、日本へ渡来し、日本国形成の重要な役目を担ったようでした。飛鳥時代から古墳時代がそうで、前方後円墳は、彼らの手によるものです。秦人といわれる彼らは、壬申の乱以後、影を潜めますが、そのパワーは、後の世の武士として蘇るのです。藤原氏に溶け込んだ秦人もいて、天皇家の側近に身を置き、今も連綿とつづいています。例えば雅楽部の方々がそう思われます。秦人は世の表舞台にでることは控え、芸術面などに広がっていったようです。能の世界、世阿弥などもそうです。世阿弥による【阿漕】という【能】は、九州日向国から伊勢国に参り、海人の亡霊に出会う内容になっています。阿漕は、三重県津市にあり【津】はシュメール語の【ツ】突き出た塊をいいます。越の【エ】は家、【ツ】は海岸線の突き出た塊(岬の入り江)などに海人が家を建てて拠点にしたことから【越】は拠点を意味します。これは【呉越同舟】の【呉人】と【越人】も倭人であるところからきています。海人は海岸付近で住み、先住民である縄文人のテリトリーを侵すことはせずに稲作農法を伝え、鉄の農具も与え、共存していたそうです。それが大黒・エビスへの親しみになったのでしょう。エビスと呼ばれた人達は、中国大陸では東夷(東のエビス)と云われたエブス人です。夷(てつ)の人で鉄部族ですが先住民と混血して蝦夷にもなったのでしょう。縄文人である先住民はメソポタミアに住んでいた苗族で、シュメール人の支配下にあったウバイト人(苗族)が、大移動を始め、パミール高原からアラル盆地、ウラル山脈沿いに北極まで行き、シベリア、モンゴル、満州、朝鮮、日本北部に拡がり、さらにベーリング海峡を渡ってアメリカに行き、インデアンになったと云いそれぞれ移動した地域によって各種族に形成したようです。バイカル湖のブリヤード人は、苗族が寒冷適応のツングース化した北方モンゴロイドで、さらに南方から来た倭人(南方モンゴロイド)と混血したのがアイヌ人、沖縄人も南方モンゴロイドなので同祖になります。『三郡誌』によると現在の津軽地方に最初に定住したのがアソベ族でその後、ツボケ族が大挙して渡来してきたといいます。好戦的なツボケ族により、アソベ族は、山辺に移ります。そして、大地震と火山の噴火でアソベ族は壊滅的打撃を受け、わずかに生き残った者もツボケ族の支配下に置かれます。伝承に「アソベ族 とツボケ族は同祖であり、アソベは西の大陸から、ツボケは東の大陸から東日流へやってきた」とあり、中南米にも「アステカ人は東方アジアからやってきた」という文献があって縄文土器も発掘されています。この伝承は、元々バイカル湖畔にいた種族が、一部は日本列島に渡ってアソベ族となり、一部は米大陸に渡った後に日本列島にやってきてツボケ族になり三内丸山遺跡を築き津軽古代王国造ったと思われます。この王国に、出雲の秦王国に敗れた長髄彦一族も亡命してきました。アソベ族・ツボケ族・長髄彦一族は混血し、新たに「荒吐族」(アラハバキ族)となり、倭人の王族だった長髄彦の一族が継承する事となり、幾度となく秦王国へと侵攻し崇神帝即位迄、次々と荒吐系の天皇を擁立したのです(孝安帝と開化帝)。 長髄彦の子孫は連綿と続き、奥州藤原氏(安倍氏の血を汲む)を輩出したのです。安倍氏は源義家によって滅ぼされましたが、長髄彦同様、棟梁が戦死しても嫡男は密かに宮城から津軽十三湊へと逃れ、安東氏として復活したのです。安東一族は「津軽の王」となり当時の有力氏族が所領を拡大する事に力を注いでいた 時、安東氏は、十三湊を「首都」に中国・朝鮮・沿海州から東南アジア・アラビア、遠く ヨーロッパまで交易し、莫大な収益を上げていました。当時の十三湊は、「津軽三千坊」 と呼ばれる程多くの神社仏閣が建ち並び、港には中国人は元より、インド人・アラビア人・ヨーロッパ人等が多数の異人館を営み、さながら幕末の横浜の様相を呈していました。 また、港には日本全国から常に二百隻以上の商船が停泊し、ヨーロッパ人の為にカトリック教会まで建っていました。更に、 安東氏は日本海を隔て た沿海州の至る所に、「安東浦」や、「安東館」(領事館)を持ち樺太・千島列島・カムチャツカ半島迄「領土」として支配していました。しかし、十八回もの大津波の被害により栄華も、終焉を迎えました。古代津軽王国が何度もリベンジしたという秦王国は、シルクロードから来たユダヤ十支族を含む弓月君の秦族が、シュメールの王=殷(辰王)の箕氏に従って中原(満州)~朝鮮半島~九州の鳥栖と吉野ヶ里に渡来した後、出雲へ移動し秦王サルタヒコを出雲大社に祀り、倭人の王、インドのナーガ族長髄彦と戦った後、近畿で秦王国を築き、白村江の戦いの後、新羅指令の元、神武・卑弥呼を祖とする倭国=九州の筑紫王朝と合体し日本国となって新羅の支配下に入りました。彼らは白村江の戦いの時に新羅方についたので優遇されました。やがて応神天皇の時、弓月君が120県の民を引き連れて、その時最初に上陸したのは赤穂市の尾崎の浜だったそうです。シュメール人を基層民とする秦人は高度な職能軍団で灌漑も得意とし、メソポタミアで小麦を育て、それを輸出していましたが、灌漑をやり過ぎたため塩害でウル第3王朝が滅んでしまい、この事も中国大陸に移動して殷を造った原因のようです。メソポタミア南部のような乾燥地帯で、灌漑を行い、大量の水を散布すると、灌漑用水は、一旦は土壌中の塩類を溶かしながら下方へと浸透しますが、やがて毛管現象により上昇し地表面にまで来ると、水分が蒸発するので、塩類だけが残る。そして、地表面に塩類が残留すると強い浸透圧により、植物は根から水を吸収できなくなり、枯れてしまう。これが塩害です。メソポタミアの刻文に「黒い耕地が白くなり平野は塩で埋まった」という記録があります。この経験を逆に活かして製塩の技術を取り入れたのか赤穂が製塩で有名なことと関連性が窺われます。また吉良家とは製塩業で競合していて赤穂製塩法の秘伝を乞われて断ったことからトラブって刃傷沙汰になったとの説もあります。古代イスラエルも日本も塩は撒いて邪気を祓う清めに使われています。相撲も古代イスラエルを起源とし、シルクロードを通ってモンゴル、朝鮮半島経由で日本に伝わったもので、土俵を清めるために塩が使われています。赤穂は養蚕、機織、蹉跌による製鉄にも適した土地で古くから秦氏系の人々の植民地でした。日本中の神社は、秦氏により建てられ、京都の本拠地、太秦はユダヤ、シメオン族系イスラエルの王国を現わすといいます。祇園祭りもシメオン族の祭りで葵祭(賀茂祭)、賀茂社も秦氏が関わり神社ばかりでなく仏教にも大きく貢献し東大寺建立にも尽力し立派な業績を残しています。しかし秦氏は政治家になる者はほとんどいないばかりか、歴史の表面にも積極的に出ない一族でありました。その反面、経師や絵師、能楽師などの芸術家、土木・建築の技術者また酒造りの技術など政治とは別の面で積極果敢に活躍した人々でした。日本のフリーメーソンと云われる所以です。世阿弥の母親は秦氏の出自であり、「猿楽」の祖は秦氏の首長、秦河勝、東義秀樹氏の祖です。斯様に日本に多大な貢献をしながら秦一族は平安時代を境に秦という名を消してしまいます。 生前はもちろん、死後に至っても徹底的に自分達の出自や素性を隠して日本に溶け込んでいったのでしょう。日本最大の支配階級として君臨してきた藤原氏、その出自も隠されています。藤原氏と秦氏は婚姻関係を結んでおり、藤原氏を秦氏が経済的に支援し、権力闘争や疫病で藤原氏が弱った時に、その一部が藤原氏に成り代わり、両者は、ほとんど融合し皇室を婚姻により包囲していったと思われます。
2017/02/04
-

双分制
天皇家は万世一系とはいえませんがシバの女王の時代から続くといわれるエチオピアの皇帝が1975年廃止してからは、アインシュタインをして【最も古く、最も高貴な家柄】と称させた世界最古の王家になります。日本人のルーツを調べていると、二系列の王族によって形成されていることに気づきます。それは、遙か古代アナトリアから始まり、中央アジアを通り、日本にも持ち込まれました。精神の王または最高位の祭司である天皇と、政治経済の実験を握る豪族、ある時は、蘇我氏であり、また、ある時は、藤原氏であったように。王が二重に存在して、精神の王と、現実社会に対する王、とが分かれるというのが西アジアの遊牧民の帝国に際立っていた双分制社会の大きな特徴でありました。これは、スキタイ・サカ族、匈奴らの大帝国に共通して特徴的に見られることでした。そして、もし両者が対立したら、精神の王が上位に来ることになっていました。中国の「史記」にも人間を創造した始原の神として伏犠氏と女カ氏があり蛇化した下半身が絡んでいる画が出土されています。日本の「古事記」の構成に於いても具体的な生成を行なう陰陽に分類された二霊、イザナギ・イザナミがあります。そして、これは、推測ですが、前方後円墳もこの流れを汲むのではないかと考えています。方墳と円墳の合体、これが当たっていたとしたら、すごい歴史の解明に繋がると思います。それは、遙か古代アナトリア~メソポタミアの人々が、円形の住居と方形の住居に分かれていることに起因しているのではないか?と、思うのです。フルリ語の粘土板文書がチグリス川の支流域のヌジ、ユーフラテス川沿いのエマルシリア方面のアララクやウガリトから出土しています。BC15世紀頃のもので、ヒッタイト王国の3代ムルシリ1世や5代スッピルリウマ1世がフルリ人国家を服属させたという記録があるそうです。このフルリ人はナーガ族と同じ蛇信仰をもっていましたが、ヒッタイト人に征服されウガリットでのフルリ人は天候神ダゴンと収穫神バールを崇拝しています。これはフルリ人の神が蛇神から征服者アーリア人の牛神に変わったことを表します。フルリ語は日本語と似ているとされていますが、フルリ人はシュメール人と同族だったようで妻のことを【妹】と言っていて、古代倭人も妻を呼ぶのに【吾妹わぎも】と言いましたので同習俗、同種族とされる理由になっています。フルリ人は【旧約聖書】で、ホリ人として登場します。フルリ人の【ミタンニ王国】がヒッタイト人によって征服された後、フルリ人の一部は北上し、アルメニアのヴァン湖畔に【ウラルトゥ】を建国しますがこのウル第三王朝~ミタンニ~ウラルトゥの流れが、満州の扶余に至る北回りルートで、【シルクロードの天皇家】となります。もう一つの南回りのルートは、シュメール~インド~ベトナム~満州という【シャキイ族】のルートです。これが【安冕あめ】氏と【阿毎あま】氏の二系です。ウラルトゥは、BC1300年頃のアッシリア碑文に初見されますが【ウラルトゥ】とは【ヴルトラ(蛇)】の意味で、【ナーガ族】の七頭の蛇との関わりがみれます。神社に張られるしめ縄は、男の蛇神と女の蛇神の交合を象った神の縄です。古代メソポタミアでは、この両蛇神を【ニンギジダ】と呼んでいました。しめ縄の原点であり【史記】の伏犠・女禍の神像は共に蛇身人首で両尾をしめ縄のようにからませています。有名な志賀島出土の【漢委奴国王】の金印は蛇紐です。【秀真伝ほつまつたえ】を作成した大物主家(公孫氏)の三輪氏(イッサカル族)は大和三輪山の蛇神を祀る神官の家柄なので、蛇紐金印の委奴国王家および蛇神信仰の新羅王家あるいは、亀神話のからんだ金官加羅の金首露王家と同族的な関わりがありました。ウラルトゥとしばしば戦いを交えたのがアッシリアで、シャルマネサル3世や4世が知られますが、彼らは、ウラルトゥを【ウルアトリ、ナイリ】と呼びました。アッシリアは、セムの2子、アシュルの流れでセム系とされていますが支配階級は、ハムの子、カナンの子孫、【旧約聖書】では、アララト王国となっています。中東の遊牧民族のなかにあって農業を主としており、この点シュメール人と同じです。【ウラルトゥ王国】は、BC9世紀始めにアラメによって建国され、アラメがアッシリアのシャルマネサル3世によって追放された後、次のシャルドウリシュ1世が国力を回復しアッシリア軍を撃退、以後、ウラルトゥとアッシリアは何度も交戦します。【ウルク】もバール信仰で、【ウル】の天神アンに敵対しましたが、もっと遡ればインドのナーガ族とアーリア人の敵対に端を発します。【フルリの王】と自称したシャルドウリシュ1世やメヌアシュ、アルギシュティシュ1世などの優れた王を出したウラルトゥもBC585年にアーリア系のアルメニア人が侵入し、首都ティシェバーナが没落、以後ウラルトゥ人はシルクロードに亡命することになりますが、このシルクロードのウラルトゥ人を中国の文献は【伯族】と称しています。【宮下文書】は、ウガヤ王朝が月読命(月氏)と同盟していたとしますが、このことはアナトリアのウラルトゥとシルクロードの月氏が同盟してアッシリアと戦った歴史を表しています。セム系の月氏は、ウラルトゥの時代にも天皇家と共にあったようです。この時の同盟関係が天皇家と月氏(藤原氏・秦氏)につながります。 ウラルトゥ王国はBC6世紀初頭のカルミール・プルーフの時代に滅亡してしまったとされますが、彼らはナボポラサルのカルデア王朝に従属し、その後アケメネス朝ペルシアの王族を王とし服していましたが、アレキサンダーによってペルシアが滅びた後、その一部が扶余を建てました。ウラルトゥ王国がスキタイなどの印欧語族に追われてキンメリ人やチュルク人と共にアフガン北部のバクトリアに逃れ、さらに華北に移動、ここで秦に伐たれたため満州に入って扶余前期王朝を建てたのです。
2017/02/04
-
秦の始皇帝
北朝イスラエルの人々はBC7世紀にはペルシャに移住し逃れ、弓月王国などを形成し商人、工人などして陸のシルクロードに進出し、そこでの交易を支配し、殖民、建国を繰り返していきました。BC328年、アレキサンダー軍は、ソグディアナの首都マラカンドを占領し、さらにシル・ダリヤの岸に達し町を築きましたが、スピタメンは、マラカンドを奪回し、さらにアレキサンダーの救援軍を全滅させました。このためアレキサンダーは、自ら軍を率いてマラカンドに向かい、スピタメンはマサゲト人を味方にし騎馬の大軍で迎撃しますが、その結果ソグド人は12万人殺害されました。スピタメンは、妻に暗殺され、妻は夫の首をアレキサンダーに献じますがアレキサンダーは彼女を夫殺しとして追放しました。BC324年、アレキサンダーは、バクトリアからシルクロードを経て長安に至り洛陽を建設し インド西部まで征服の範囲を大きく拡げます。BC323年、アレキサンダーがバビロンで病死したため、ペルシア帝国は分裂。アレキサンダー王の東征に従軍した南朝ユダ王国のシメオン族が現在のアフガニスタンにバクトリア王国を建国しソグドを支配します。この時の王が中国西域にバクトリアの分国を創り、BC222年皇帝になりました。これが秦帝国であり、この皇帝が秦の始皇帝でした。始皇帝は金髪碧眼だったといいます。中国の史書は漢民族のための「偽書」を漢王に強制されたユダヤ人の司馬遷がオリエント史を漢訳して、夏、殷、周、秦という諸国の歴史もアッシリア・ペルシアをモデルとした創作史でした。三国志もバクトリア国の内部抗争をそのまま中国史に置き換えた創作でした。BC213年、秦の始皇帝(ユダヤ人・シメオン族・ディオドトス)が思想・言論の自由を抑圧し、方士や儒者460人余りを生き埋めにする焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)事件が起こりました。この時、焚書坑儒の対象にされた孔子(ユダヤ人のラビ、エリア)・孟子系のユダヤ、ガド族は始皇帝のシメオン族とは敵対関係に入りました。結果、ガド族は南朝系に接近して北朝系と争うようになりました。この南朝、北朝系の争いは、日本国の天皇制になっても続き、室町時代、明治時代には、大きな政治的戦略につながったと思われます。初めて中国の史上に列島の倭人が登場するのは、BC1020年、周が建国した頃、列島は、縄文晩期にあたる。江南の会稽(かいけい)に住んでいた王充(おうじゅう)という人の「論衡ろんこう」という書に、周の初めの成王の時代、倭人が帳草(鬱金草ウコン)を献じてきたと、あります。帳草とは神おろしの儀式に使う酒に入れて香りを出す草といわれています。中国は、5000年の歴史といわれてきましたが、それは虚構であったようです。孔子はエリヤ、孟子はアモス、列子はプラトン、荘子はアリストテレス、儒学はユダヤ人ラビの「ジュウ学」、殷はシュメール人、周はアッシリア人、秦はバクトリア人のオリエント史がモデルです。司馬遼太郎は読売新聞紙上に、【漢民族は関中台地(陜西省)に流れこんでくる、インド・ペルシア系の流入者から、今の中国武術、曲芸、さらに仏教という形而上学を学んだ。秦の始皇帝陵の兵馬俑はギリシアの技術で作られたものであり、始皇帝の時代、ギリシア丈化はバクトリアを通じて中国の文化を支配していた】と書いたそうです。秦帝国はアレキサンダーが作らせたバクトリア王国(大夏国・大秦国)中国における植民地でした。歴史的にアレキサンダーの大遠征を完成しようというものでした。しかし、アレキサンダーが亡くなり、従軍していたデオドトスが秦帝国の皇帝の座に着きました。始皇帝がわずか一〇年で中国大陸を支配できたのは、秦の軍隊はアレキサンダーがバクトリアに残したギリシア兵団で、当時としては世界最強の戦力だったからです。始皇帝は、すでに造られていた燕と趙の長城を繋ぎ合わせ、さらに黄河沿いに新しい長城を築かせた(万里の長城)。楚と秦の戦いも司馬遷のフィクションで、始皇帝の死後、ギリシア人の将軍エウチデムス(史記の項羽)がクーデターを起こし、ディオドトス2世(胡亥)を追放して三世子嬰も殺し、宮廷も焼くと秦王国が滅亡させ、バクトリア王になり、ソグディアナから南進してヒンドゥクシュ山脈一帯を支配しました。極めてギリシア的ともいえる同族戦争の結果中国人の治め難さを知って、エウチデムス(項羽)は中国大陸を見捨ててバクトリアからインド大陸に転進したというのが真相。項羽が焼いたといわれていた始皇帝の地下宮殿も発掘され、兵馬俑が明らかにされたのは周知の事実。兵たちの像はギリシアやペルシャ様を成し、前300年頃、中国の西方にあったというバクトリアの軍隊でした。その後、劉邦らが「前漢」を建国して、秦の遺産を引き継ぎました。秦王政の余波を受けて大扶余にいた日本人のルーツウガヤ王朝が東北の満州に逃れ松花江河畔の農安に北扶余前期王朝を建てました。同じ頃、マレー海域のヤーヴァ・ドヴィーバー(五穀豊かな国)の移民たちが、沖縄から移って建てていた中山国が滅び、国王・綽(シャク)が蜀(四川省成都)へ移されたため、遺民たちは遼東(満州)へ移動し、原ツングース(韓人)を従えて箕子朝鮮を再興しました。秦の王族(シメオン族)たちは遼東(満州)へ逃れ、奇子朝鮮を頼って亡命しました。
2016/10/27
-
エラム族ペルシア(秦)史
BC627年に即位したアッシリアはカルデア人の王、ナボポラッサルの反乱に破れBC612年、メディアのキアクサレスによって滅びます。その後、メディア(楚)はスキタイ(越)と同盟してソグディアナ、後のソグド付近に移動しました。『史記』は、越(スキタイ)を夏王、禹(ウトヘトガル)はグート人とウルク人の混血なのでスキタイ族はグート・ウルク族です。その後、エラム族グループのなかのアケメネス・ペルシアがオリエントを支配しました。 エラム族はシュメール人やグート族と同系です。ペルシア人はアーリアンの一派ですが同じくイランを根拠地にしてエラム諸族と同盟していました。ペルシア王国の姉妹婚はエラム族の習俗であり、エラム語はペルシア帝国の公用語でした。ペルシア王キルスはカルデア人のバビロン王朝を滅ぼしてオリエントの覇者になりました。ペルシア史にBC519年、カスピ海の東方で尖冒サカ族が反乱し、ペルシア王ダリウス1世は自らカスピ海を渡って遠征したとあります。尖冒サカ族とはアッシリアの遺民を表わし王子を擁立してダリウスを攻撃したと考えられます。この後、ペルシア帝国は『ソグディアナのかなたのサカからエチオピアまで、インダスからサルディスまで』におよんだとありますから、ソグディアナの東方にあたる黄河上流の流域はペルシアの支配に服したことになり、従来のアッシリア系亡命者の支配地を奪ったことになります。アッシリア史はアッシュールウバッリトの敗走後を生死いずれも記録しないが、ウラルトゥに逃れた後、さらにサマルカンドまで逃亡したのです。
2016/10/27
-

チュルク
匈奴はチュルク族とキンメリ族の二系が率いる連合軍でした。チュルク族は歌が好きで、それは万葉歌にも示されていて、今でも天皇家の歌初めという儀式に残ります。なおチュルク族の一派がたてたウイグル王家の風俗はカラ・ホージャ壁画に残っていて平安貴族とよく似ています。日本史では、チュルク族の韓文化とサカ族の蘇我氏とユダヤ族の守屋氏(物部)が作った倭人文化は銅矛文化と銅鐸文化の対立という形で表されますが言語と文字の対立も見過ごせないものがあります。人類の文字は、エラム族が作った絵画配列に始まるとされます。エラム族はサカ族などの原型となり、この人々こそ中国の甲骨文字とメソポタミアの原エラム文字を作った人々といわれます。原フルリ人が後の倭人やユダヤ人になったということで、この後、ウルクを支配したシュメール人は膠着語を用いてスメル文字を作ります。フェニキア人はアルファベット式文字を作りました。これはウガリット文書に残っています。チュルク人は、はじめ独自の文字を作らずサカ族からプラフミー文字シュメール族からウルク文字を借用していました。扶余と箕子朝鮮の人々は、BC274~236年のアソカ王刻分にあるプラフミー文字を持っていました。扶余人は漢字受容後もこの文字を持ち続けて、上記文字やサンカ文字として残しましたが扶余と箕子系の人々はトカラ文書をニギ氏系の人々はコータン文書も残しています。チュルク人の一部は河西の北涼に合し、439年に北魏に滅ぼされたため西走し北涼がトルファン盆地に高昌国を建てるとチュルクの阿史那氏が加わりました。この人々がソグド人の古体ソグド文字を学び、チュルク文字やトルコ・ルーン体文字に発展させたといいます。ソグドとは蘇塗であって、アラム・サカ・ユダヤ諸族の商業基地をいいます。扶余のサカ族が東行し、一部がソグディアナ地域を中心にして、シルクロードの商圏を支配したキャラバン国家が成立したのでしょう。
2016/10/27
-

地球・生命誕生
今から遥か昔の約48億年前に銀河系の片隅で一つの星が命を終えました。「超新星」です。超新星とは、太陽のような恒星が一生の最後に起こす大爆発のことです。その「超新星」、消えた一つの星のおかげで、私達、生命体は誕生することができました。生命が誕生する為には、水素やヘリウムなどの軽い原子以外に、鉄以上の重い原子も必要で、それは、星の一生の最後である爆発の時にしか出来ないといわれているのです。その超新星と共に周りは明るく照らし出され、その残骸は吹き飛ばされ散りゞになりながら宇宙空間に放たれて行き、残された残骸を元に新しい恒星=太陽が作られました。太陽もまた、地球と生命の誕生には、必要でした。太陽の活動には周期があり、活動が強くなると太陽風にのってやってきた電磁波などにより磁気嵐などが起きます。生物の進化に太陽活動は影響を及ぼしたと考えられます。太陽は膨大な光と熱を発する天体です。それなしでは地球は暗黒に包まれた冷たい星に過ぎません。太陽無しに現在の地球と生命の姿はあり得ませんでした。約46億年前、誕生したばかりの地球の表面はマグマの海に覆われ、1億年後、地球がゆっくりと冷え始め、空の水蒸気が雨となって、いつ果てるとも知れない豪雨となり、海が生まれました。海が出来た後の大気は二酸化炭素で溢れていました。厚い雲に閉ざされ、僅かに届く太陽が空をオレンジ色に染め、灼熱の海に生命を作る材料が集められていきました。原始地球は成立の過程で互いの重力によりたくさんの隕石が衝突しながら大きさを増していきました。隕石にはアミノ酸をはじめ生命を作る材料が含まれ、また、雷や紫外線のエネルギーによる化学反応からも生命の材料ができていったのです。45億年前のある日の事、火星と同じ大きさの惑星が地球に衝突。この時に砕け散った一部が集まって月になりました。この衝突は海底にも大きな衝撃を与え、海底には地球内部の様々な物質を吐き出す「噴出口」のようなものが立ち並びました。原始の海に浮かぶ巨大な月、月と地球の距離は今の半分もありませんでした。遺伝子の誕生にも太古の海に浮かぶ巨大な月が関係しているといいます。原始の月の引力が引き起こす大きな潮の満ち引きが潮溜まりを作り、そこに遺伝子を作る物質が集められたとされます。生命の素材をいっぱい含んだ原始の海。打ち寄せる波が岩に砕け、細かい無数の泡が作られてゆきます。原始の海の泡は消えることなく岩にとどまります。そして、繰り返し打ち寄せる波は泡が作る薄い膜の中に周りの物質(アミノ酸等の生命の素材)が取り込まれていったと考えられています。このような密閉された環境(泡の膜)が無ければ、遺伝子の素材となる分子がただ拡散し薄まるばかりで、相互作用が出来ないので、生命が誕生する為には、膜に包まれた空間が必要だったのです。そして、深海底へ沈んでいったものが、「噴出口」で混合されて、原始生命が誕生していきました。膜の中に包まれ(細胞ができた)さらに高分子の合成が進んでいきます。その中で、効率の良いシステムの出来上がったものが残り、生命へと進化していくことになったのではないかといわれています。この膜は、脂肪からできています。この安定した膜の中で、生命につながる重要な化学反応が進んで生命が誕生し、互いに試行錯誤を繰り返し遺伝子DNAを作り上げていったと思われます。この単細胞生物のバクテリア達が私たちの遠い祖先なのです。その頃の海は、何百種類もの化合物が溶け込んだ薄いスープのようなものでしたが、全く酸素のない世界でした。寧ろ生命体にとって酸素は天敵でした。これは最近でも、医学会で、全ての疾病は「活性酸素」によると、発表されたことに通じます。生命体のルーツが誕生した海水の中は、全く酸素のない世界。このことは、とても重要でした。生命体のルーツは、酸素を嫌う「嫌気性」でありました。しかし数億年後、酸素が無かった原始の海の中にも植物のルーツになる藻(シアノ・バクテリアの一種)が誕生し、海の中で光合成を開始すると海中にも大気中にも酸素が発生していきました。酸素は殺菌力があり、原始生命体にとっては極めて猛毒であり、酸素毒によって、海中の原始生命体はあっというまに駆遂され、死滅していったのです。これが活性酸素の発生です。原始生命体は生き延びて行くために、酸素毒に対応できるよう、体の仕組みや姿、形まで変えていったのです。今の私たちの体を作る細胞は酸素が無くては生きていけません。最初は猛毒であったものが、生きていく上で欠かせないものになる。この大逆転は、どのように変化していったのでしょうか? 種の自己保全のため全く違う進化をした二つの生命体が、一緒になって新しい生命を作り出していったのです。酸素毒環境に順応した生命体と、酸素毒から逃げ回り生き長らえた生命体(酸素を嫌う「嫌気性」)が合体し、新たな進化を遂げ、2個のDNAを共有し、繁殖と分裂を繰り返し、増殖しました。酸素毒に挑戦し、順応していった細胞はミトコンドリアとなり、今も人体の細胞の中で酸素を調整して、細胞核やDNAを酸素毒から守る働きをしています。とっても興味深いことに酸素毒を嫌う「嫌気性」生命体から誕生した細胞の集まりは、消化器系の器官となり、酸素毒に順応していった細胞群は、代謝系の器官(肺、肝臓、心臓などの循環系器官、門脈(血管)など)に進化していったのです。人体では、口から入った空気(酸素)は気管を通って、すべて代謝系に流れ込み、消化器系にはいかない仕組みになっています。万が一、消化器系に酸素が微量たりとも侵入した場合には、細胞内のミトコンドリアが調整し、酸素毒を防ぐようになっています。消化器系の中には、100種、100兆個の微生物(腸内細菌)が棲息しており、それらは当然の如く酸素を嫌う存在です。この微生物(腸内細菌)が消化器系の中で生命活動に必要なあらゆるホルモンや酵素を生産し、人体内の60兆の細胞と代謝系の臓器の働きを支えています。この二つの生命体の合体した多細胞生物の誕生は、約10億年前です。微生物学者によれば、腸内の微生物(腸内細菌)は、進化の過程からみれば代謝系の臓器よりも古く、原始生命体の働きを受け継ぎ、微生物(腸内細菌)が代謝系の臓器(肝臓、腎臓など)を作ったとし、その具体例に、ミミズを例にあげています。ミミズの体内に臓器はひとつもなく、ミミズの体内に棲む微生物が、消化から代謝まで全てを行っています。「人体の消化器系はミミズです」と思えば分かりやすいとのこと。 酸素は病気の元凶です。しかし細菌やウイルスを退治して守ってくれるのも活性酸素、バランスが問題になります。そうしたことを踏まえて生物は単細胞から多細胞生物へ進化し、生物の形態も植物から自ら動く事の出来る動物の2種類に分かれ、各々に進化していきました。約5億7千万年前には三葉虫の全盛期を迎え、そして同じ頃に脊椎動物としては最初の魚類が誕生し、約4億年前には両生類へ、そして約3億年前には爬虫類へと進化し、陸上へと生活圏を広げました。植物は両生類が誕生した頃には既に陸上進出しており、爬虫類の登場と共に大森林を形成するようになり、地球は緑の惑星となりました。爬虫類は約2億4千万年前に哺乳類へと進化しましたが、ネズミ程の本当に小さな生き物でしたので、陸上の支配者は爬虫類となり、強大化した恐竜が、地球の王者となりました。爬虫類は陸上だけでなく、空中へも進出し、約1万5千万年前に鳥類が誕生、恐竜の中にも飛べるものが現れ始め、生物は地球上各地に広がりました。爬虫類は水中へも進出しましたが、魚類や哺乳類などによって水中の覇者にはなれませんでした。恐竜が地球上の覇者となって1億年近くが経とうとしていた約6500万年前に、メキシコのユカタン半島へ巨大隕石が衝突した事によって生態系は大きく変化します。衝突によって砂や塵などが空中に舞い上がり、そして地球全体を覆いました。結果、太陽の光は地上に届かなくなり、植物が絶滅し、続いて草食動物、そして肉食動物も多くが姿を消し、恐竜など巨大な生物はほとんど絶滅しました。体が小さかった哺乳類は、この大きな気候変動を生き延びる事ができたのです。生命誕生の不思議なことに、受精後、第5~6週のわずか1週間の間に,地球に初めて生命が誕生した35億年前の「魚類」から「両棲類」、「爬虫類」、そして約6500万年前に出現した「哺乳類」と、生物の進化過程の全てを辿ってくるそうです。羊水は原始地球の海水と、ほぼ同じ塩濃度を持ち,いずれも弱アルカリ性の液体であることも解っています。生命の誕生から、ずっと私達は、羊水に近い成分の大気の中で生かされてきたといいます。さらに、もう一つ、前に読んだ中村天風の本に書かれていたことを紹介します。生命が生まれ、育つには宇宙のエネルギー(気)が働いているそうです。植物の種子が発芽し双葉をだす時。蛙の卵が分裂する時。人間の場合も、子宮の中で受精卵が細胞分裂し、一番はじめに出来るのは「気」を存在させるための場所だそうです。四畳体(しじょうたい)といい、その下に間脳ができます。この「間脳」こそが、人間の正体だというのです。正体だけあって、この間脳を毛筋でピッと突いても死んでしまう。これが一番先に入れ物としてできる。それから今度は、「心」の働きを行うところの神経系統ができてきます。それから後に筋肉や細胞、その他の五臓六腑ができあがる。私たちが自分だと思っている肉体は最後にできあがるのだそうです。間脳が内臓を始め人体の諸器官のすべてをコントロールしているといいます。「潜在意識」といわれるのも、この「間脳」です。間脳に情報を入れると、間脳は入れられた指示通り、その目標に向かって進むのです。「潜在意識を活用して夢を叶える」というのも、あながち空言ではないのです。太古の海はシアノ・バクテリアが吐き出す酸素で溢れ始めました。それが海水の中の鉄分と反応して大量の赤錆を海の底に降り積もらせてゆき、海底の隆起によって地上に現れ、鉄鉱石の鉱山ができあがりました。今、世界で使われている鉄資源のほとんどは、この時シアノ・バクテリアが出す酸素によって海に沈殿したものだそうです。「鉄」は、人類文明の進歩に欠かせない素材であると共に、生物の進化や人間の生命に不可欠な金属でした。生命の起源となるタンパク質は、海底から噴出する炭素や水素などが結び付いてできたアミノ酸が、さらに結合することによって生まれたと考えられています。その合成で重要な触媒の役割を果たしたのが「鉄」でした。鉄は酸素と結び付いて、生物の体内を移動し、体内の至る所に酸素を運びエネルギーを生み出す役割を果たします。その鉄タンパク質の代表格が血液中の「ヘモグロビン」で、これは酸素呼吸する哺乳動物の象徴です。鉄は、タンパク質と結びつくことによって酵素を形成し、過酸化水素処理能力を持つようになり、こうした酵素を多く持つほど、生物としての寿命も長くなるのだそうです。「地球」は、鉄の星といわれるぐらい他の金属と比べて格段に多いのです。鉄は、宇宙の誕生と同時に始まった核融合の最終の姿で、構造的に最も安定した元素といわれます。古代の人々は、こうした叡智をすでに持っていたのかもしれません。陸や海のシルクロードから日本に渡来した人々も製鉄部族集団でした。
2016/10/23
-

ミトコンドリア
私たち人間は、エネルギーを得るために、2種類のエンジンをもっています。「解糖エネルギー」と「ミトコンドリア・エンジン」です。私たち生物が誕生したのは、酸素のない地球でした。その時の生物が使ったエネルギーは、酸素を必要としない糖を原料とした「解糖」という化学反応を用いたものでした。即ち、解糖エンジンでエネルギーを作り出していたのです。それから、海中に光合成生物「シアノバクテリア」が誕生し初めて酸素が生成されました。シアノバクテリアの光合成によって酸素が放出されると、海水中に溶けていた鉄イオンが酸化鉄となって海底に堆積しました。海水中の鉄イオンがすべて酸化鉄となると、海水中の二酸化炭素が余剰となるため大気中に放出されました。こうして地球の大気に、酸素が増えていきました。シアノバクテリアが地球の環境を変えたのです。地球の海にシアノバクテリアという酸素が増加し酸素を利用しないと進化できなくなりました。そこで、私たちの祖先の細胞が、好気的(酸素を好む)な細菌「アルファ・プロテオ細菌」を自分の細胞の中に取り込んでミトコンドリアにしました。その結果、動物細胞ができあがったのです。この「アルファ・プロテオ細菌」は、酸素を利用して莫大なエネルギーに変える特性をもっていました。ミトコンドリアは酸素を使って大きなエネルギーを生む「酸化的リン酸化」という反応を用いたのです。私たちの細胞のDNAは、一つの細胞にたった一つしか存在しませんが細胞内のミトコンドリアDNAは、1個のミトコンドリアに数百以上存在します。このことは、私たちの細胞とミトコンドリアの細胞とが本来は、「別もの」という証拠です。解糖エンジンの特徴は、急なエネルギー需要が生じた時に血中のブドウ糖を利用して瞬時にATPというエネルギーを作り出せることです。皮膚や筋肉は、解糖系のエネルギーで生きています。このエネルギーでは瞬発力が得られます。若い人は、もっぱらこの解糖系のエネルギーを使っているので、糖質の多い炭水化物を食べる必要があります。しかし、持久力を求められる中高年以降では、解糖エンジンがあまり必要でなくなってエネルギー系は解糖系からミトコンドリア系に移行しますので、糖を摂りすぎるとミトコンドリアエンジンの働きが弱くなります。ミトコンドリアは、日々食べる食物から得る栄養素と酸素を原料として、効率よくエネルギーを生み出しています。ところで、ガン細胞は、解糖エンジンでエネルギーを得ています。ガン細胞は、先祖返りした細胞で、エネルギーをミトコンドリアエンジンに変えればがん細胞は増殖できなくなるといいます。私たちの祖先の細胞は無酸素と低温の環境で生きていました。 そんな過酷な環境にあっても、祖先の細胞は、さかんに血管を伸ばして栄養を 摂っていました。ガン細胞と、そっくりです。 ミトコンドリア系のエンジンをうまく引き出すには、細胞の内部環境を温め 酸素を十分供給することです。適度な運動をし、温泉などで身体を温め 深呼吸をし、食べ過ぎないようにすることだそうです。
2016/10/23
-

平等社会から支配社会へ侵略者
都市文明は長いことメソポタミアの発明と考えられてきましたが実は長い間、時代にとり残された辺境の地域とみなされてきたパレスチナのエリコアナトリアのチャタル・フユィックの遺跡の方が先行する文明であったことが解かりました。そして、これらの最初期の文明は、地母神を崇拝する女性中心の文明でした。日本でも男性支配の家父長制度が課せられるのは大宝律令が制定されてからです。太古地母神《女神》は古代の農耕社会すべてに於いて崇拝されていました。女性的なるもの・・・その生物学的な性格から、大地と同じように子を産み育みそだてるもの・・・の神格化の証拠は、農業起源の三つの主要な中心、小アジアと南東ヨーロッパ東南アジアのタイそして後の中央アメリカに見出すことができます。《大いなる女神が》が、時には鳥の姿になったり蛇の《女神》になったりしながら水の生命授与力を支配しています。ヨーロッパとアナトリアでは、雨を孕み、乳を与える、そういう文様が土器に織り込まれています。アナトリアのチャタルフユィックの遺跡からは、母系で妻方居住の社会構造が現れました。その構造は、チャタルフユィックからクレタに移住し、太古地母神《女神》と共に農業技術をもたらしつづく四千年の間に、土器製作、織物、治金、彫版、建築、その他の技能およびクレタ独特の生々とした喜びに満ちた芸術様式の進歩がありました。そこでは富は、公平に共有されました。年上の女性ないし氏族の長が大地の実りの生産と配分をつかさどり、実りは集団の全員に属するものとみられていました。主要な生産手段の共有と、社会的権力は、すべての人の利益になるよう図られ、責任のもとに基本的に共同的な社会組織が生まれていました。これは、パレスチナの世界最古の町エリコナトゥフの人々が成功していた共同社会につながると思われます。太古地母神《女神》を中心に女も男も異なった人種の人々も・・・共通の幸福のために平等に協力して働いていました。母系による相続と家系、至高の神としての女性、現世的権力をもった女司祭と女王の存在はありましたが男性の地位が低いということはなく、両性は平等な協調関係を築いていました。彼らは、たいへん自然に親しんでいて、アニミズム(精霊崇拝)はクレタだけでなく、ケルト民族にも伝わりました。太古地母神《女神》を中心にした文化はアナトリアを中核として地球一周しました。ストーンサークルやドルメン、メンヒルなど、これらの祭祀が彼らの残した足跡です。最初、それは家畜の群の草を求めて彷徨う一見取るに足りない遊牧民の集団にすぎませんでした。数千年以上も、どうやら彼らは地球の端の誰も望まぬような厳しく寒く痩せたシベリアに住んでいました。その遊牧の集団が長い期間をかけて数と獰猛さを増しヨーロッパ北東からヨーロッパ大陸に群がり南下し侵略してきたのです。彼らは最初のインド・ヨーロッパ語族あるいはアーリア人といわれるクルガン人です。あるクルガンの野営地では、女性住民のおおかたはクルガン人でなく、新石器時代の太古地母神《女神》崇拝の人々であったことが発掘資料から判明しています。このことが暗示しているのは、クルガン人が、その土地の男性や子供たちの大部分を虐殺し、女性たちのある者だけを助けて妻や奴隷にしたということです。遺跡から農機具のみで武器というものが見あたらない【平和】で【民主主義】な社会が営まれた《女神》崇拝社会が破壊され、男性的支配社会のはじまりでした。インド・ヨーロッパ語族は、先の文明を築いていた太古地母神《女神》を崇拝する農耕民族を次々侵略していったのです。インドに於けるアーリア人、【肥沃な三日月地帯】に於けるヒッタイト人とミタンニ人アナトリアに於けるルヴィ人、東ヨーロッパに於けるクルガン人、ギリシアに於けるアカイア人および後のドーリア人、彼らは征服した土地や人々の上に次第に自分達のイデオロギーと生き方を押し付けていったのです。このほかにも侵略者はいました。ヘブライ人と呼んでいるセム系の人々です。
2016/03/17
-
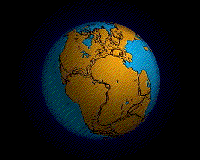
生命体
19億年前頃になると海の酸素は飽和状態になり、酸素は空中へ放散されていくようになりました。陸地の方は、25億年前頃にアークティカ大陸がつくられ、ウル大陸はほかの大陸とくっつき第2ウル大陸になりました。さらにまた大陸とくっついて大きくなり第3ウル大陸になりました。その後アトランティカ大陸ができ、大陸同士くっつきヌーナ大陸というさらに大きな大陸になっていきました。 ウィキペディアから地球はプレートの移動によって、18億年前頃に第3ウル大陸、ヌーナ大陸、アトランティカ大陸の3大陸となりました。すると地球の環境に大きな変動が起こりはじめ、地球はだんだん冷えていきました。そのことにより、海の栄養分は極度に不足していき、単細胞生物は次々死んでいってしまいました。単細胞生物は栄養分が充分あるときは、効率よく分裂して増えていけましたが、栄養分がないと簡単に死んでいきます。単細胞生物とは細胞の中に1組の遺伝子(DNA)しかないので分裂するときは、まずDNAがコピーされて同じDNAが二つになり、そして分裂していました。しかし、栄養分が得られにくい環境になって次々仲間が死んでいくうち、その環境を生き延びるために細胞同士がくっついて、一つになって生き延びようとするものがでてきました。二つの細胞がくっついたため、二つの遺伝子(DNA)を持つ単細胞生物が生まれたのです。二つのDNAを持った細胞が分裂をすると、分裂前とは違ったものができてきました。それまでの細胞は親というものはなく、同じDNAがコピーされて一つのものが二つに増えていくので数が増えるだけです。二つのDNAを組み合わせて、新いDNAが作られると親と子という関係ができてきたのです。それまでの生物は一つの細胞で、生命活動の何から何までやらなくてはならなかった単細胞生物です。多細胞生物になると何をする細胞、何々をする細胞と担当が分かれ分業して、全体として一つの生物として働くことが可能になりました。そうなると専門家の集まりとなれるので能力は高まり、体は大きくなりますが、この頃のものはまだ頭も足もない形らしい形を持っていないものでした。ところが今まで酸素によって死ぬ一方だったバクテリアの中から、死んだバクテリアを食料にする新しいタイプの生物が登場してきました。それまでの生き物は硫化水素で生きている嫌気性のバクテリアか、光合成する生き物なので、無機質の元素を取り入れるか、浮遊している有機物を食べて生きていました。新しい生物は、生き物の死骸という有機質を取り入れて生きていく生物です。この生物は酸素で呼吸することができるようになり、その後生きたバクテリアを食べるものがでてきたのです。この生物が登場したことにより食物連鎖が進展していくのです。酸素を使うと硫化水素を使うより20倍多くのエネルギーが作れるので、この生物は動き回る能力が高く、次々バクテリアを食べ始めました。今までのバクテリアは細胞膜を食いちぎられ、遺伝子を食い荒らされてしまいます。やがて食われてばかりだったバクテリアの中でお互いに身を寄せ合ってまとまり、遺伝子を真ん中に集め、これを膜で囲って守っていくものが出てきました。これまでのバクテリアは一つの細胞でできていて遺伝子(DNA)は一つです。酸素を使って動き回る運動能力に長けたバクテリアに対し、このバクテリアは遺伝子を集めた細胞核というデータバンクを持つことによって学習能力と知恵の分業で対抗していったのです。細胞核があると遺伝子情報をたくさん持つことができるようになります。細胞もそれまでの単細胞バクテリアより大きくなります。体も大きくなって強くなっていきました。そのおかげで、今までの生物と比べ物にならないくらい進化することが可能になったのです。でも酸素に弱いままでは生き続けていくことはできません。このバクテリアはその内うまい手を考えたのです。まず酸素から身を守るために核膜というバリアをつくって遺伝子を守り、細胞膜の中に酸素を吸って大きなエネルギーをつくれるバクテリアを取り込みました。酸素呼吸するバクテリアを自分の細胞に取り込んで、このバクテリアの廃棄物を使うという手です。酸素呼吸するバクテリアは酸素を取り入れてATP(アデノシン3燐酸)という物質をはきだします。このATPというのは生物のエネルギーの元になっている物質です。嫌気性のこのバクテリアは自分では大きな力が作れないのに、いくつかまとまって大きな細胞となり、その中に酸素呼吸して大きな力を作れるバクテリアを飼育して、そのバクテリアの作ったものを使って大きな力を得たのです。細胞の中に取り込まれてしまった方のバクテリアはミトコンドリアというバクテリアです。これが酸素毒に順応していった細胞群で、代謝系の器官(肺、肝臓、心臓などの循環系器官、門脈(血管)など)に進化していったのです。今も人体の細胞の中で酸素を調整して、細胞核やDNAを酸素毒から守る働きをしています。人体では、口から入った空気(酸素)は気管を通って、すべて代謝系に流れ込み、消化器系にはいかない仕組みになっています。万が一、消化器系に酸素が微量たりとも侵入した場合には、細胞内のミトコンドリアが調整し、酸素毒を防ぐようになっています。消化器系の中には、100種、100兆個の微生物(腸内細菌)が棲息しており、それらは当然の如く酸素を嫌う存在です。この微生物(腸内細菌)が消化器系の中で生命活動に必要なあらゆるホルモンや酸素を生産し、人体内の60兆の細胞と代謝系の臓器の働きを支えています。この二つの生命体の合体した多細胞生物の誕生は、約10億年前です。微生物学者によれば、腸内の微生物(腸内細菌)は、進化の過程からみれば代謝系の臓器よりも古く、原始生命体の働きを受け継ぎ、微生物(腸内細菌)が代謝系の臓器(肝臓、腎臓など)を作ったとし、この新しく生まれたバクテリアは、それまでのバクテリアと違って細胞核をもったものなので、真核生物として別のものとして分類されます。細胞の中にミトコンドリアと鞭毛性のバクテリアの二つを取り入れることに成功した生物はやがて動物へと進化していきます。
2016/03/17
-

古代フリーメーソン秦氏
フリーメーソンのマークコンパスと矩は平安時代には日食月食割り出しに陰陽師らは熾烈な戦いを繰り広げ、江戸の世では庶民が算学本を一家に一冊常備するまでに。和算は生活に役立てるので感動する。直角二等辺三角形の相似を利用して、木の高さを目測できます。 腰を90度に折り木のてっぺんが見える位置を探せばそこから木までの距離と木の高さが等しくなります。四つん這いになった人が、股の間から木を見通す。古代のフリーメーソンといわれる秦氏は、秦の始皇帝の末裔とされます。ルーツは、古代イスラエル。シュメール時代からの純粋な技術集団の彼らとロスチャイルドなどのマンモス財閥フリーメーソンとは繋がらない。現在、ユダヤ人といわれている白人は本来のユダヤ人ではなく、彼らは「ユダヤ教徒」に改宗した中央アジア人。考古学的には本来のユダヤ人はカナン人から由来するとされています。そして古代エジプト人、古代メソポタミヤ人、古代アナトリア人との人種混合が起こったとします。この人々が移動して日本国を造ったと考えられます。叡智のシュメール人。ユーラシアの北方にはアジアからヨーロッパまで坦々としたステップ地帯が連なっています。狩猟民族はマンモスや鹿を追いかけてユーラシア大陸を抜けて北東のシベリアへ進み、さらに南北アメリカに渡たりました。温暖の時は北方へ、厳寒になると南下して日本列島にも渡って来ました。彼らが縄文人なり、三内丸山遺跡の人々にもなったと考えられます。黄河より長江文明の方が早く1万4千年前より稲作と養蚕と機織が始まっていたことが最近分かってきました。同じ頃、パレスチナ(エリコ)辺りで最古の小麦農業は始まっています。その流れは、やがてメソポタミアの大農業につながります。BC6000年頃に始まった金属文化は、初めにヒマラヤ山麓をルーツとして小アジア(トルコ)のチャタルフユィックやタイのバンチェンに拡がりこれがモヘンジョ・ダロ(インド)を経てBC2500年頃までにはアファナシェヴォ文化(エニセイ川流域)に伝わりました。担い手は白鳥トーテムのチュルク族(白人)。アファナシェヴォ文化は南シベリアのエニセイ河上流と アルタイ地方に栄え、アンドロノヴォ文化という青銅文化につながりさらに南シベリアのカラスク文化に 代わりました。トルコからシベリア、日本まで広大な範囲を包括するチュルク族はウラル・アルタイ語族=ツラン族といい、さらに西に進んだ一部はイデル・ウラルとクリミア地方からバルカン南東隅まで、また他の一部はドナウ盆地にまで進出しました。彼らはシルクロード全域に亘って分布し、アレキサンダー大王が侵入するまで中原の支配者でした。彼らは、高句麗・ 百済・日本天皇家に繋がります。彼ら【白鳥族】は、日本列島の中央構造線に沿って九州から四国、紀伊、伊勢、信濃、鹿島など水銀(丹生)や瑪瑙、翡翠、琥珀など数多くの鉱物資源を採掘していきました。その周辺は地下で巨大なエネルギー が蓄積し、それによって誕生したいろいろな資源が採掘できました。だから、大和の勢力は鉄と鉱物資源を掌握し豪族の勢力争いが起きました。はじめは葛城氏が、次に蘇我氏が、最後に藤原氏が征服しました。東北征伐もして金など重要な資源を手中にした。中央構造線のラインは前方後円墳の分布とも見事に一致します。九州から関東地方にかけて分布するが、密集している地域は主に、北九州、日向、吉備、讃岐、近畿、中部、そして関東地域でした。埼玉県から群馬県にかけて密集しているのはなぜか?この地域に密集している所は、利根川の上流、山地から下るあたりの支流に沿っています。それは、たたら製鉄の産地でした。前方後円墳を造るには鉄器具を要します。製鉄には膨大な木材を必要とするので山に近く、それを運ぶために川を利用するので川 沿いに位置していました。利根川を下っていくと埼玉県と群馬県、千葉県と茨城県の県境に沿って流れ鹿島灘へ注いで、鹿島神宮と香取神宮に繋がっていました。利根川は、鹿島神宮と香取神宮の前にあった香取の海に流れ込み、銚子のあたりで鹿島灘に流れ出していました。やはり、鹿島・香取二つの神宮は重要な拠点に位置していました。ブームになっているパワースポットは、鹿島・香取神宮をはじめ中央構造線のライン上に重なります。地球の磁力の源が集中し、【ヴォルテックス(渦巻き)】と呼ばれるエネルギーが渦巻いています。特に磁力の源が集中し地表に放出されるエネルギーが強い場所。磁力の出入りは呼吸と同調し磁力が入っているとき人間は強く自信に満ち、磁力が出てゆくとき人間は弱くなり失望を生じるといいます。人によってはその波動を強く感じ取り、涙が溢れるなどの浄化(デトックス)作用を経験するといいます。こういう場所では植物も磁力の影響を受けて変わった成育をする事が多いらしい。古代、地球の全ての生き物が磁力を感じ、行動していました。白鳥などの渡り鳥も魚も方向感覚が優れているのはその機能を持っているから。磁場の歪みで地震を察知、逃避する動物もいれば、潮の動きで魚は食欲を左右されます。北半球のイワシなどの群れる回遊魚は、水槽に入れられると右回りに、南半球の魚は左回り。ウナギも方向を間違えず、エサも食べずにひたすらマリアナ海溝を目指すといいます。
2015/09/19
-

長州藩は忍者・諜報機関
長州藩が幕末から強固な支配体制を維持している理由は【忍者・諜報】機関が背後にいたと考えられます。そういうシステムが毛利藩に継承されていきました。というのは、長州をつくった毛利元就は最初は小さな勢力でした。ところが、中国地方10ヵ国を支配するような大大名に伸し上がったのです。それはもっぱら諜報と謀略活動で大きくなったのです。そのような性質を持った毛利藩が関が原の戦で負けて小藩になります。しかし謀略機関は維持されて、【忍者集団】になります。そのトップが【上忍】で、【中忍】【下忍】などのシステムができあがります。吉田松蔭は1829年、長州萩松本村に藩士、杉百合之助の次男として生まれました。松蔭は五歳にして藩学師範家・吉田家の仮養子となり翌年、叔父吉田大二郎賢良の跡を継ぐと、十歳より、藩校明倫館に出勤して家学の兵学を教授、彼は幼くして天才でした。1841年、叔父玉木文之進の松下村塾に入り塾生を教育する傍ら、自らも山田亦介から長沼流兵法を学び、進んで西洋の兵学まで修めました。1850年、九州に遊学して、翌年、山鹿流兵法の皆伝を受け、藩主にしたがって江戸に留学佐久間象山に師事しました。同年12月には水戸藩を訪れ、藤田東湖を訪ねましたが会えず会沢正志斉らと気脈を通じて、南朝正系を説く【大日本史】を学びました。松蔭は、この頃すでに長州藩ウラ毛利の【上忍】益田元宣に引き立てられて【中忍・・・佐官級情報員】となり元宣の子・親旋とも親交を深めていました。そして相共に尊皇攘夷をスローガンにし倒幕・南朝革命を目指す同志となっていたので、1854年3月、上忍・元宣の命を受けると最新の世界情勢を調べ、さらに情報収集をする目的で浦賀に於いて米艦に乗り込もうとしましたが失敗して下獄。同年10月は帰国して野山獄に入り、翌年12月、実家杉家で謹慎生活。こうして幽囚の身となった松蔭が【松下村塾】に顔を出し始めたのが1856年9月から、つづいて熱心な講義を始めたのが同年11月からであり、それを知って塾生も急激に増加し、優秀な人材が揃うようになりました。このことによって、いよいよ松蔭自らが指導する革命の実践活動に入る決意を固めたのは、翌年正月のことでした。1858年正月九日維新革命の実践活動に立ち上がることを誓い合い、門下生をはじめ藩政府当局などに宣言しました。萩藩当役は益田弾正親旋で撫育方(表向きは産業振興役実は秘密の倒幕用軍資金を守る忍者集団)の長官を兼ねていました。即ち、親旋は長州藩独特の制度・ウラ毛利の上忍(情報局長官)であり、その父、元宣の時から密かに援助していた松蔭を中忍として動かしていたのです。従って、松蔭の動向は単なる個人的なものではなく相当な忍者集団を動かしうる組織的なものでした。松蔭は、水戸学の南朝正系論を理念とし、後醍醐天皇の血統、大室寅之祐を擁護していました。また部落・賎民など被差別民解放。松下村塾出身の志士たちに指導された長州奇兵隊の中核を成していたのは、部落解放の夢に燃える賎民出身の若者でした。 奇兵隊のなかでも、特に注目すべきは力士隊、伊藤博文は、この力士隊の隊長でした。 この時代の力士隊というのは弾体制(同和)に従属していて部落と密接して関係しているかあるいは部落そのものでした。さらに力士隊のあった第二奇兵隊の屯所は、麻郷(おごう)近くの石城山にあり、ここ田布施町は、大室天皇家のあった場所で、明治天皇となる大室寅之祐が明治維新の前年まで過ごした地でした。因みに岸信介・安部晋太郎・晋三氏が出自もこの辺りです。伊藤博文などもこの辺です。興味深いことに、古くから石城山は【聖なる山】として崇められ、石城山を基点として【太陽の道】レイラインに神社が置かれています。レイラインとは、古代遺跡などを地図上で結んでいくと見えてくる一定の法則でつながっている ネットワークのことです。ライン上には何らかの強いエネルギーが流れているとの説もあります。 レイラインはよく、経絡とツボの関係にたとえられるのですが、レイラインが経絡だとすると パワースポットがツボになります。世界的にも遺跡・古くからの宗教施設・聖地などが直線的に配置されていることが分かってきました。これら遺跡・古くからの宗教施設・聖地などは、活断層に沿ってあることが分かりました。岩石、特に石英に圧力を加えると電磁波が発生します。活断層上でしばしば起こる圧電現象は強力な電磁場を生み出し、条件がそろえば大気をイオン化して球電光を形成することもあるので古代人は、断層線上で起こる発光現象を目撃し【神】の出現と考え神聖視し、そこの場所に巨石などを配置して聖地として敬ったのでしょう。イギリスでは、レイラインの多くは、ケルトあるいはそれ以前の時代にまで遡る遺跡を結んでいるといわれ、 そこには、ストーンヘンジや、ミステリーサークルの出現地なども含まれています。ストーンサークルの建造目的は土着信仰(ドルイド教)の宗教的儀式と関係があったのではないか。ところで、人間の脳にある種の弱い電磁波を加えると、幻覚・幻聴・気分の高揚・逆に落ち込み等が発生することも知られていますが、このある種の電磁波というのが、活断層で発生する電磁波とそっくりなのだそうです。昔の聖職者(シャーマン)などは、感受性が非常に強い人たちで、活断層の近くに来るとそこで発生している電磁波の影響を受けて幻覚・幻聴・気分の高揚などがおこり、神の啓示を聞いたり姿(光)を見たりして、聖地としたのかもしれません。日本のレイラインで最も知られたものの一つとして小川光三氏が発見した【太陽の道】があります。大和の地に存在する寺社や古墳や山の山頂が、北緯34度32分の東西の一直線上に並んでいるというものです。太陽や星の運行とも密接な関係があるとされ太陽の道に付随して、神社や古墳が形作る巨大な三角形などが発見されており、それらは春分や夏至などの特定の暦日に太陽が昇ったり沈んだりする地上の地点を示すために利用されたといいます。真弓常忠氏は【古代の鉄と神々】のなかで、このラインが採鉱・鉄冶業を生業とする集団によって日神祭祀の祭場とされた・・・・・と云っています。田布施町の国森古墳からも、副葬品に鉄矛、鉄斧、鉄削刀子等が出土し、古くから鍛冶屋衆がいたと推論されています。この周辺の地から何人も首相が出ているのは偶然でしょうか。
2015/09/18
-

祖先が取り込んだミトコンドリア
私たち人間は、エネルギーを得るために、2種類のエンジンをもっています。「解糖エネルギー」と「ミトコンドリア・エンジン」です。私たち生物が誕生したのは、酸素のない地球でした。その時の生物が使ったエネルギーは、酸素を必要としない糖を原料とした「解糖」という化学反応を用いたものでした。即ち、解糖エンジンでエネルギーを作り出していたのです。それから、海中に光合成生物「シアノバクテリア」が誕生し初めて酸素が生成されました。シアノバクテリアの光合成によって酸素が放出されると、海水中に溶けていた鉄イオンが酸化鉄となって海底に堆積しました。海水中の鉄イオンがすべて酸化鉄となると、海水中の二酸化炭素が余剰となるため大気中に放出されました。こうして地球の大気に、酸素が増えていきました。シアノバクテリアが地球の環境を変えたのです。地球の海にシアノバクテリアというに酸素が増加し酸素を利用しないと進化できなくなりました。そこで、私たちの祖先の細胞が、好気的な細菌「アルファ・プロテオ細菌」を自分の細胞の中に取り込んでミトコンドリアにしました。その結果、動物細胞ができあがったのです。この「アルファ・プロテオ細菌」は、酸素を利用して莫大なエネルギーに変える特性をもっていました。ミトコンドリアは酸素を使って大きなエネルギーを生む「酸化的リン酸化」という反応を用いたのです。私たちの細胞のDNAは、一つの細胞にたった一つしか存在しませんが細胞内のミトコンドリアDNAは、1個のミトコンドリアに数百以上存在します。このことは、私たちの細胞とミトコンドリアの細胞とが本来は、「別もの」という証拠です。解糖エンジンの特徴は、急なエネルギー需要が生じた時に血中のブドウ糖を利用して瞬時にATPというエネルギーを作り出せることです。皮膚や筋肉は、解糖系のエネルギーで生きています。このエネルギーでは瞬発力が得られます。若い人は、もっぱらこの解糖系のエネルギーを使っているので、糖質の多い炭水化物を食べる必要があります。しかし、持久力を求められる中高年以降では、解糖エンジンがあまり必要でなくなってエネルギー系は解糖系からミトコンドリア系に移行しますので、糖を摂りすぎるとミトコンドリアエンジンの働きが弱くなります。ミトコンドリアは、日々食べる食物から得る栄養素と酸素を原料として、効率よくエネルギーを生み出しています。ところで、ガン細胞は、解糖エンジンでエネルギーを得ています。ガン細胞は、先祖返りした細胞で、エネルギーをミトコンドリアエンジンに変えればがん細胞は増殖できなくなるといいます。私たちの祖先の細胞は無酸素と低温の環境で生きていました。そんな過酷な環境にあっても、祖先の細胞は、さかんに血管を伸ばして栄養を摂っていました。ガン細胞と、そっくりです。ミトコンドリア系のエンジンをうまく引き出すには、細胞の内部環境を温め酸素を十分供給することです。適度な運動をし、温泉などで身体を温め深呼吸をし、食べ過ぎないようにすることです。
2015/09/17
-

地球~生命誕生
地球・生命誕生 今から遥か昔の約48億年前に銀河系の片隅で一つの星が命を終えました。「超新星」です。 超新星とは、太陽のような恒星が一生の最後に起こす大爆発のことです。その「超新星」、消えた一つの星のおかげで、私達、生命体は誕生することができました。 生命が誕生する為には、水素やヘリウムなどの軽い原子以外に、鉄以上の重い原子も必要で、それは、星の一生の最後である爆発の時にしか出来ないといわれているのです。その超新星と共に周りは明るく照らし出され、その残骸は吹き飛ばされ散りゞになりながら宇宙空間に放たれて行き、残された残骸を元に新しい恒星=太陽が作られました。 太陽もまた、地球と生命の誕生には、必要でした。 太陽の活動には周期があり、活動が強くなると太陽風に のってやってきた電磁波などにより磁気嵐などが起きます。 生物の進化に太陽活動は影響を及ぼしたと考えられます。 太陽は膨大な光と熱を発する天体です。それなしでは地球は暗黒に包まれた冷たい星に過ぎません。 太陽無しに現在の地球と生命の姿はあり得ませんでした。 約46億年前、誕生したばかりの地球の表面はマグマの海に覆われ、 1億年後、地球がゆっくりと冷え始め、空の水蒸気が雨となって、いつ果てるとも知れない豪雨となり、海が生まれました。 海が出来た後の大気は二酸化炭素で溢れていました。 厚い雲に閉ざされ、僅かに届く太陽が空をオレンジ色に染め、 灼熱の海に生命を作る材料が集められていきました。 原始地球は成立の過程で互いの重力によりたくさんの隕石が衝突しながら大きさを増していきました。 隕石にはアミノ酸をはじめ生命を作る材料が含まれ、また、雷や紫外線のエネルギーによる化学反応からも生命の材料ができていったのです。 45億年前のある日の事、火星と同じ大きさの惑星が地球に衝突。この時に砕け散った一部が集まって月になりました。この衝突は海底にも大きな衝撃を与え、海底には地球内部の様々な物質を吐き出す「噴出口」のようなものが立ち並びました。 原始の海に浮かぶ巨大な月、月と地球の距離は今の半分もありませんでした。 遺伝子の誕生にも太古の海に浮かぶ巨大な月が関係しているといいます。 原始の月の引力が引き起こす大きな潮の満ち引きが潮溜まりを作り、そこに遺伝子を作る物質が集められたとされます。 生命の素材をいっぱい含んだ原始の海。打ち寄せる波が岩に砕け、 細かい無数の泡が作られてゆきます。 原始の海の泡は消えることなく岩にとどまります。そして、繰り返し打ち寄せる波は泡が作る薄い膜の中に周りの物質(アミノ酸等の生命の素材)が取り込まれていったと考えられています。このような密閉された環境(泡の膜)が無ければ、遺伝子の素材となる分子が ただ拡散し薄まるばかりで、相互作用が出来ないので、生命が誕生する為に は、膜に包まれた空間が必要だったのです。そして、深海底へ沈んでいったものが、「噴出口」で混合されて、原始生命が誕生していきました。 膜の中に包まれ(細胞ができた)さらに高分子の合成が進んでいきます。その中で、効率の良いシステムの出来上がったものが残り、生命へと進化して いくことになったのではないかといわれています。この膜は、脂肪からできています。この安定した膜の中で、生命につながる重要な化学反応が進んで生命が誕生し、互いに試行錯誤を繰り返し遺伝子DNAを作り上げていったと思われます。この単細胞生物のバクテリア達が私たちの遠い祖先なのです。その頃の海は、何百種類もの化合物が溶け込んだ薄いスープのようなものでしたが、 全く酸素のない世界でした。寧ろ生命体にとって酸素は天敵でした。これは最近でも、医学会で、全ての疾病は「活性酸素」によると、発表されたことに通じます。 生命体のルーツが誕生した海水の中は、全く酸素のない世界。このことは、とても重要でした。 生命体のルーツは、酸素を嫌う「嫌気性」でありました。しかし数億年後、酸素が無かった原始の海の中にも植物のルーツになる藻(シアノ・バクテリアの一種)が誕生し、海の中で光合成を開始すると海中にも大気中にも酸素が発生していきました。 酸素は殺菌力があり、原始生命体にとっては極めて猛毒であり、酸素毒によって、 海中の原始生命体はあっというまに駆遂され、死滅していったのです。これが活性酸素の発生です。原始生命体は生き延びて行くために、酸素毒に対応できるよう、体の仕組みや姿、形まで変えていったのです。 今の私たちの体を作る細胞は酸素が無くては生きていけません。 最初は猛毒であったものが、生きていく上で欠かせないものになる。この大逆転は、どのように変化していったのでしょうか? 種の自己保全のため全く違う進化をした二つの生命体が、一緒になって新しい生命を作り出していったのです。酸素毒環境に順応した生命体と、酸素毒から逃げ回り生き長らえた生命体(酸素を嫌う「嫌気性」)が合体し、 新たな進化を遂げ、2個のDNAを共有し、繁殖と分裂を繰り返し、増殖しました。 酸素毒に挑戦し、順応していった細胞はミトコンドリアとなり、今も人体の細胞の中で酸素を調整して、細胞核やDNAを酸素毒から守る働きをしています。とっても興味深いことに酸素毒を嫌う「嫌気性」生命体から誕生した細胞の集まりは、消化器系の器官となり、酸素毒に順応していった細胞群は、 代謝系の器官(肺、肝臓、心臓などの循環系器官、門脈(血管)など)に進化していったのです。 人体では、口から入った空気(酸素)は気管を通って、すべて代謝系に流れ込み、 消化器系にはいかない仕組みになっています。 万が一、消化器系に酸素が微量たりとも侵入した場合には、細胞内のミトコンドリアが調整し、酸素毒を防ぐようになっています。 消化器系の中には、100種、100兆個の微生物(腸内細菌)が棲息しており、それらは当然の如く酸素を嫌う存在です。この微生物(腸内細菌)が消化器系の中で生命活動に必要なあらゆるホルモンや酵素を生産し、人体内の60兆の細胞と代謝系の臓器の働きを支えています。この二つの生命体の合体した多細胞生物の誕生は、約10億年前です。 微生物学者によれば、腸内の微生物(腸内細菌)は、進化の過程からみれば代謝系の臓器よりも古く、原始生命体の働きを受け継ぎ、微生物(腸内細菌)が代謝系の臓器(肝臓、腎臓など)を作ったとし、その具体例に、ミミズを例にあげています。ミミズの体内に臓器はひとつもなく、ミミズの体内に棲む微生物が、 消化から代謝まで全てを行っています。 「人体の消化器系はミミズです」と思えば分かりやすいとのこと。 酸素は病気の元凶です。しかし細菌やウイルスを退治して守ってくれるのも活性酸素、バランスが問題になります。そうしたことを踏まえて生物は単細胞から多細胞生物へ進化し、生物の形態も植物から自ら動く事の出来る動物の2種類に分かれ、各々に進化していきました。 約5億7千万年前には三葉虫の全盛期を迎え、そして同じ頃に脊椎動物としては最初の魚類が誕生し、約4億年前には両生類へ、そして約3億年前には爬虫類へと進化し、陸上へと生活圏を広げました。 植物は両生類が誕生した頃には既に陸上進出しており、爬虫類の登場と共に大森林を形成するようになり、地球は緑の惑星となりました。
2015/06/20
-

好人物
【秦の始皇帝は、鼻は高くて蜂のようなかっこう、切れ長の目、猛禽のように突き出た胸 豺(サイ)のような声で、恩愛は少なくて虎狼のような心だ】と、始皇帝の武官、リョウは始皇帝のことを表現しています。この形容と白皙、碧眼であったという始皇帝は、ユダヤ人と思われます。ところで、中国史がオリエントの借史であるとして司馬遷らへの原史料の提供者はというと、アッシリアに囚われていた北朝イスラエルの人々【失われた10部族】を始めとして、バビロンの虜囚の一部かギリシアに移住してアレキサンダー王と共に東に進んだユダヤ人たちが考えられます。そもそも星占いは、オリエント、特にカルデアで発生してその裏づけとしてオリエント史を利用したものですから、オリエント流の占者たちが秦の時代に自分の国で占いの資料として使ったオリエント史をそのまま漢訳したようです。秦の始皇帝、ディオドトスの父、呂不偉は、ユダヤ人のシメオン族でした。【史記】を著した司馬遷が罪なくして宮刑に処せられたことは、中島敦の【李陵】という名作に詳しい。私は、この本に深い感銘を受けました。何をもって人が生きることをよしとするか、中島敦はこの作品で、李陵、蘇武、司馬遷という 3人の男を登場させて示しています。最後に救われたのは蘇武ですが、それぞれに生きる道を全うしているのであって、どれが正しいというものではない。真に生きるには、どの道も苦しいのだという問いを中島敦は、読者に与えているようです。 李陵は漢の国を脅かす匈奴討伐の願いを時の皇帝である武帝にゆるされて北征し、勇猛果敢に戦いに挑むも、内通者の手引きによって彼の軍は壊滅、自身も捕虜となるが、彼らのあくまで強き者に礼をつくすという気風や、武帝が彼の家族に対しておこなった処刑への恨み、そして国から離れることで見えてくる漢という国の思い上がりや腐敗の構図などの要因が、しだいに李陵の祖国への忠誠心を薄れさせていく。いつしか、彼は匈奴の人間として匈奴とともに生きる道を選んでいた。李陵が深く思い悩むことになるのは、同じように匈奴にとらえられしかしけっして彼らに組することを肯んぜずに厳しい捕虜生活をつづけている蘇武との出会いによるものだった。ただ純粋に祖国への、そして武帝への忠誠心を貫いていこうとする蘇武の態度に接した李陵は、自身のなかに打算的な、ものの考え方があることに気がついてしまう。そして気づいてしまった以上、彼ははたして自分が精神的に匈奴に降伏してしまったことが正しかったのかどうか、考えずにはいられなくなってしまいます。蘇武は李陵同様、匈奴に捕まるのですが、最後まで漢への忠誠を崩さず、ひたすら祖国、漢を慕い、極寒の北国にて餓死寸前の生活を送っても後悔せず、最後には許されて帰ります。 その信念はきわめて明快です。信念に徹して剛毅、英雄的な生きざまです。 そして司馬遷。漢の武帝の逆鱗のなか誰一人、李陵を庇うどころか好人物とされる人々も野次馬と化し、四面楚歌の李陵を弁護した、唯一の人物が司馬遷で、彼はそれがもとで宮刑(去勢の刑)を受けます。絶望しながらも【史記】を昼夜兼行で完成させます。読後に私が共感して、今でもその感が薄れずにいるのは司馬遷の好人物への怒り。武帝に対し将軍として果敢な匈奴と戦って捕虜となった李陵を漢の宮廷にあって李陵と友人でも係わりもなかった司馬遷が唯一人褒め称えたために宮刑(宦官)にされてしまった。そして宮刑を受けた司馬遷が呪うものは好人物であった。好人物は姦臣や酷吏よりも始末に悪い。何か事が起きても弁護もしなければ反駁もしない。その上反省もなければ自責もない。お人よしというのは阿諛迎合をしてもその自覚さえないのだと罵倒している。 周囲に「いい人」と言われて安心している人々。始末に悪いのは、そういう民衆。これは現代にも通じます。平時にはニコニコ親切な人も事が起きた時、人は、自分の損得を瞬時に判断し有利な立場に付くか、見て見ぬふりをすることが多い気がします。保身に右往左往し、多勢の意見に流される民衆の大きなうねりは、実はたいへん恐くその大きな波に歴史は流されていくのです。戦争は、その最たるもので気づくと、もう抗うことことができなくなっているのだと誰でもが思い当たると思います。
2015/05/09
-

日本人の祖形
縄文時代以前、旧石器時代末期に存在したとされる極めて高度な科学技術や 独自の哲学体系を持っていたことが、神代文字であるカタカムナ文字で記された 【カタカムナ文献】から推測されます。大自然、大宇宙の息吹を友としていた超古代人にとって、その直観力は、 現代人の想像も及ばないほど研ぎ澄まされており、宇宙の深淵、宇宙の背後に 隠されている何ものをも射抜くほどの力を持っていたようです。 古代日本に渡来した一派がカタカムナ人です。 彼らもまた、石英の多い山を利用して、全国各地に人工ピラミッドを造山しています。 そして、ミトロカエシの技法からも分かる通り、錬金術師でもありました。 カタカムナが伝える【ミトロカエシの秘法】は、【賢者の石】に関係するといいます。西洋のヘルメス学(錬金術)の文献には、【賢者の石】は、ガラス状に輝く ルビー のような化学物質と記されているとも言われています。1万2千年前、私たち日本人の祖形は、アルタイ山脈の西部と天山山脈の北麓の間の故地からジュンガリア廻廊を南下し天山南麓をつたわって西方に進んだようです。さらに、パミール高原の東麓に沿ってタリム盆地(今の新疆ウイグル自治区)の西方をぐるりと迂回し、パミール高原がおわるところで一部はカラコルムからヒマラヤに入り、また一部はアルティーン・ターグの北麓からヒマラヤに登りさらに他の一部はアルティーン・ターグの北麓をつたわって東方に行き青島のツァイダム盆地に出、バヤンカラシャン山脈を縫い、ついにはヒマラヤ登ったのです。彼らは同じ樹林帯にしてもシベリヤの針葉樹林対を捨ててヒマラヤは崑崙の常緑広葉樹林対に移動したのです。日本人の祖形であるツングース的モンゴロイドはアルタイ西部の故地ザイサン湖畔を離れ、ヒマラヤを越えて揚子江岸に下りシナ海に進出したものと考えます。その時、アルタイ西部の故地ザイサン湖畔に居残ったツングース的モンゴロイドの一部と、その故地で共存関係にあったイラン的ユーロポイド(白人)と雑婚したものが殷族であり、殷の部族連合を構成する連合内部族とその部民になったツングース的モンゴロイドがタリム・アラシャン・オルドスなど東に進出してきたものと考えます。
2015/04/12
-
サンカの人々の暮らし 1
サンカの人々 ぶらんここの原稿は岐阜県の教育家であった三宅武夫氏が、少年時代(明治時代)におけるサンカとの出会いを回想したものです。サンカという人々の生き方が少年の目にはどう映ったのか、また何を学ぶことができるか貴重な記録です。手書き私家版として発行されたものから転載。 韆(ぶらんこ) 三宅武夫著から 【風の草の団子杉】は古木である。すぐ南に一寸した湖沼があって秋にもなると渡り鳥が翼を休めていた。この古木の下に藤原と名乗る夫婦が娘を連れて毎年五月から十一月迄いた。 団子杉の夫婦はこの荷車の様な一輪車に一切のものを乗せて、押さずに引っぱって韋駄天走りに走ってどこかに行った。小母さんの向うには娘と犬を乗せて平均をとったのは珍しい。■初めに私は明智(注 岐阜県恵那郡明智町)在に生れた。明治卅六年暮のことだ。そこには“山窩”とよばれる人々が毎年五月から十一月まで、同じ時期に同じ所に渡って来ては住みついていたものだ。私が接したのは、鳳の草部落に住んだ藤原某の一家で、夫婦と娘一人の小屋である。 彼等には「生活」があり、「教育」があった。 生活=生命=いのち、いきる力、ねがい。教育=共育=足場をそろえたソダチ方。然し、この一家は間もなく一般人の中に入っていく(トケコミ)直前の人達だった。これは何度でも、人に語ったことだが、書いたことがないので、思いついて「書いてみる」ことにした。今度いつか浄書する時の素稿のつもりである。私一人が感心していても、外の人は、どう思うかも知らないが、私の最も尊敬する先輩野村芳兵衛先生が、褒めてくれたことのある説だということだけは言い添えておきたい。 昭和四十八年七月一日■ 鞦韆(ぶらんこ遊び・・・・・)ぶらんこ は 只の遊びである。その遊びに今誰が本気になって取り組んでくれるか。今日教育の危機を言うものは多いが、子供と共に育つことを忘れて押し付け教育をし、人間を数に換算して、その不合理を思わず、かつて我もされた教育の形を先ず離れようとしてくれる先生は滅多にいない。 昭和五十又一年九月廿一日記■ 親と子のぶらんこ遊び第一稿本 時は明治四十四年九月の末つ方。所は恵那郡明智城北東、大学鳳の草。団子杉の梅。 事は、ここに国籍不明の日本人夫婦とその娘の三人が、この木の根っこに住っており、私共とは全く異質の生活をしていたが、私共に分からん言葉を半分以上は混ぜて使って「竹細工」を渡世にしていた。村方を廻って歩いては、米麦、味噌醤油に、物々交換をしているといったふうだ。彼らのことを私共は、村人と共に、少し怖れながら、然しいつも興味深くみつめていた。彼等は、五月半には、いつの間にか来ており、昨年、冬前に截っておいていった竹を器用に剥いでこれを身辺用の諸家具に編み上げたり削ったり焼いたりして磨いて艶の出た様々な竹細工を持って一軒一軒訪ね歩いていた。私共は、彼らを「ポンス」とか、ポンスケとかいって、大分「軽蔑した気持ち」を含めて呼んでいたし、疎外しようとしていた。 私共が何となく彼等を怖れていたのには理由がある。 第一は彼らの国籍が分からん。第二は言葉が違う。第三は生活様式が違う。決して嘘を言わないし、器用だし、早いし、何も言うことはないのだが、どうも違和感が先に立って溶け合わなかった。それにもう一つ、ばかに足が早い。・・・・何するか分からんと思えたのである。顔形も、私共のように田舎臭くないし、所々分からん部分を除いては言葉だって上方風な上品なものだったし、着物も、いつも洗濯をして小ざっぱりしており、ちっともおかしくはなかった。小父さんは、いが栗頭で、大抵鉢巻をしていたが黒い髪で白い歯で、するどい眼で結構いかす男だった。盲縞の木綿の着物で角帯をきりっとしめていた。そのふところが、いつもふくらんでいたのは“うめがい”という「山刀」が胸に抱かれているからだと皆は言っていた。帯は角帯だが、そいつは小父さんが自分で織ったやつだということだった。滅多にものを言わないし、笑わない。只誰かに食べ物をもらって「ありがとさんどす」という時の笑顔が何とも可愛かった。 一人娘だったせいもあろうが私よりも四つ五つ年下と思われる女の子をとても可愛がっていた。が、何か教えたり、何か採ったりする時は、見ている私共が怖い程に真剣だったし、そのことが出来るまでは、いくらその娘が涙をこぼしても、べそをかいても道端に座り込んでしまっても決してゆるさない。「しっかりしなはれ・・・・・」と小母さんは言う。「おーっそーがい奴っちゃぞ。あいつら・・・・・」私共は、そういって遠く離れて、然し一生懸命に見ていたものだった。小母さんは、綺麗な人で「笹の家」(明智の料亭)の芸者なんかより「背が高いだけでもよっぽど美人だ」と、私共は思っていた。それに声がいい。「あんさん。ほんやんボンでっしゃろ・・・」と顎を少し右前に出して、にっこり笑ってくれたりすると、うちの叔母様達なんか、とても「かなん」と思ってみていた。
2015/03/02
-
サンカの人々の暮らし 2
ごはんの炊き方が、家のとは、ずいぶん変わっている。「鳳の草湖」の水で米をとぐのだが白い濁り水が出なくなると「フランネル」のような大巾の布に包んで水を切る。小母さんは、竹筒の端をとがらせて先をこがしたものを使って、器用に穴を掘る。二尺四方位の穴を、ほんに美しく手早く四角に掘ると、その底に頭位の大きさの平石を並べる。ついでに上手に四方の立壁部分にも、それを並べると「ぬれ蓆」をその中に拡げて今の米包みを、その上にそっと据える。私共の掌位の石を米包みの周囲に無造作に放り込むと先に敷いたぬれ蓆(むしろ)の片はしりを折り込むようにして、それで米包みを包んで、又その上に、小石、平石を並べる。枯れた杉の葉をとって来て、枯れ木の組上げられた下に、差し込む。器用に切火(かたい石と金とを切るように打つ)をして、火をたきつける。薪は、いつも、その五つ六つになったばかりの可愛い娘の仕事になっている風だった。娘は「団子杉」の根元の窪みに積んである薪を抱えてくるが、いつも同じ位だったから、一回の「めしたき分」が決まっていたのかもしれない。「おらよりゃ、えらいぞ・・・・・」と利君が感心する。何というのか分からん、地ごとの知れん歌を唄って、火壺の中の石ころを手返しなどしていると、突然どこかの端に「スウーッ」と音がして湯気がたつ。小母さんが見ていて、すぐ娘に何か言いつける。娘は立って小屋の隅っこの湯桶(直径二尺、高さ二尺位)に水を汲み入れる。小母さんが火に焼けて少し透明に近く紅くなった石を、竹で造った「もの挟み」で、竹のこげる匂いをさせながら、一つ宛、湯桶の水の中に放り込む。ジュ、ジュボーッと、水柱をあげながら石は湯桶の底に沈む。娘が手を入れながら湯加減をみているが「もういいよ」と声をあげる。小母さんは黙って、スノコの前に行って食事の用意をはじめる。娘は小母さんの脚元に、しゃがみ込んで着物をぬぐと、今沸かした湯桶に入って「風呂」をすます。小父さんが、どこからか戻って来ると何かボソボソとものを言って、すぐ、持って来た檜の枝をふところから出した山刀(うめがい)で「たらたら」と払う。実にそれは、よく切れる。音もたてずに、流れるように、枝は足元に、お行儀に並んで落ちる。山刀をふところに収めると、すぐ小父さんは、今、払い落とした檜の枝を一尺位の長さに折って揃えてしまう。あの軟らかい檜葉が生きていて、小父さんの言うことをきいて「自分で並ぶみたい」に見えるから不思議だ。小父さんは「火壺」の傍らにいくと赤く焼けた石を一方に寄せて、その上で尚、火を焚きつづけ長柄火壺の石を全部、そちらに移して、さて、初めに埋めた、ぬれ蓆を引き出す。さあっと湯気が立つと、それは大分熱いらしく、時々自分の耳朶をきゅっと、つまんだりしながら中の米包みを太い竹箸で引き出すと、 それを小母さんに渡す為に「竹すのこ」の上に持っていってやる。両手をのばして腰を引いて・・・・・ もう、辺りには、いかにも美味しそうな炊き立てのご飯の香りが、たちこめる。小父さんは、さっき枝を払った檜の五六尺もある、一寸丸太程のを立てて左手にもつと懐からお馴染みの山刀を引き出して眼にも止まらぬ速さで一尺余りの揃いの寸法に切ってしまう。上手な為か、器用な為か、その檜はバタッ バタッ バタッと、足もとの小石の並んだ上に頭を揃えて横になる。いきなり、一番初めに切り落とした「一つだ」を左手に拍子をつけてもつと小石の上に立てる。右手が小刻みに、たんたんたんと低い音をたてて、動く。それだけで神社の屋根の檜板の様に、薄い板になって小父さんの左膝の前に並べられて重なる。次の一つだを左手にすると、すぐ右手が動いて機械で割ったように揃った板になって並ぶ。一本の一寸径檜は、ほんのちょっとの間にそれぞれ五枚板位に割れて合計三〇枚位のものが、喜んで飛び上がってくるように、そこに並ぶ。見ていて面白い・・・・・ 小母さんがさっきから焼いていた石亀の中身をヤットコのような道具で引き抜くのが見える。白い「ひよこの丸ゆで」といったような形のものが、あの甲の中に入っていたことが分かる。「石亀って平たい身ではなしに、少し細長いな」と感心してみていると、小父さんは、すぐその甲羅を受け取って横向きに立てると、また山刀を「たんっ」と、打ちおろす。“がばっ”といった音を立て、亀の甲羅は、腹と背と二つに割れる。腹の方は平たくて、背の方は丸く掌の様に曲がっている。甲羅の中側は、一寸した「垣根」の様な形の境が出っぱっているが、それをついでに山刀がさらさらと欠きとっていく。ついでに小父さんが手元にあった檜の先の方の皮を削ると、その太い方をきれいに丸める。なんとも器用なもので、見る間にすりこ木が出来る。何とも感心するばかりである。炊きたての御飯を、この亀甲の背の窪みに入れると、その皮をむいた先の丸くなった棒は「すりこ木」になって小母さんの左掌に支えられたまま、廻る様に動くと右手の「すりこ木」は、ぐいぐいぐい、と上下に動いて見る間に、炊きたての御飯は餅の様につぶされる。小父さんは、その餅飯の一甲分をすぐさっきの檜の平板の画面に塗りつけ、押し付けて丁度神官のしゃくの様な形のものをつくる。火壺の回りに川原砂の様な砂が入れられていて、その串が刺される頃、娘が側に来て上手に手返しをする。小母さんが次の亀の甲に入れた御飯の一杯を練り上げる。小父さんが串にくっつける。娘が焼く。見る間に十五、六本の「しゃく」は、出来上がって一列に並んで立つ。小父さんが、すっとそこに立ち上がったのは、その小屋の屋根裏の巻藁から串さしの「変なもの」を取って来るためだった。小さな壺から、すくい出した、味噌と醤油のたれを別の器に練り上げながら、今、巻藁から抜き取ったカラカラのものを、さっき御飯を練り上げていた、亀の甲羅の中で、ボキ、ボキッと小さい音をたてさせながら、すり潰して、味噌と醤油のたれに練り上げ、作りあげる。小母さんは、左の小指につけて一寸なめてみる・・・・・。さっき巻藁から外したのは、どうやら「蛇」や「蛙」の骨らしい。「ごとむし」もいる。これは後になって小母さんから聞いたのだが「松の実」「落花生」「胡麻」「餌胡麻」時には「二ッケ」もすり込むのだそうだ。蛇や蛙は捕った時、その場で大抵そのまま食ってしまうが何匹も捕れた時、焼いて串にさして、巻藁にさしておくと「一年でも味は変わらんですよって・・・・・」と言っていた。こうして三人がかりで、あまりものは言わずに手際よく夕飯の支度は、出来ていく。親子三人の座席は、いつもきまっている。火壺は、私共の家でいえば「囲炉裏」である。中央正面の台石に藁製の円座のあるのが小父さん。二つ飛んで小母さん。また二つ飛んで娘。そして二つおいて小父さんの座になる。家族は三人だから座席の石は少し大きいのが三つ、間の少し小型のは食べ物など据える台石になるようだ。もう一つ。家族に犬が一匹いるがこれは娘の石、小父さんの左の石一つおいた台石に座らせていることが多かった。座布団代わりの円座は苗代の「残り苗」を乾かしたのを同じ藁で組み上げたので、これはいつもは、屋根裏の様な処の棚に据えられていた。もう一つ、大切なことを言い落としているが、この人達の「仲間」は「下馬木」の「柿の木平」にいたのだが、皆、天幕を張っていて、この三人よりは、もっと厳しい顔をしていたし、私共を決して近づけなかった。あれだけ、ものおじしない、利君だって「柿平の奴にゃ近づかん方がええぞ」と、いつも言っていた。
2015/03/02
-
サンカの人々の暮らし 3
ポンスケの「特徴」は1 天幕を持っていること2 「天人」という「自在鉤」をもっていること3 「山刀うめがい」という双刃の山刀をもっていること 鳳の草の親子は、天幕は、もっていたが使わなかった。「自在鉤」は使っていたが「テンジン」とはいわずジザイカギといっていたし、この山刀もウメガイとはいわないでヤマカタナといっていた。利君にきくと「柿の木平の奴んた、天幕の中に夫婦ごと、別々の暮らしをしていて地元の他人とは滅多に口をきかんし、怖い顔しとるし、足が速いで、何するか分からんで・・・・・」と、 おどした。 きくと、この ウメガイとテンジンと天幕は「あいつんたの三種の神器で触ったり、傷つけたりしたら、殺されるげなぞ」と威しては何度でも利君は、私に「得意相」にきかせた。あいつどこで聞いてくるのか何でもよう知ってる奴だ、と私は思った。彼らが住むのは、いつも本当は天幕の中である。少し傾斜の地を選んで天幕の大きさに合わせて四方に小さな溝を掘る。その長い方に天幕の裾を丸太か何かで圧えて雨水が流れこまない様にする。両端の三角の処が「出入口」になるのだが、その又、三角の部分に余分の幕がついていて、入口になる。その小幕を引き上げて中に入るのである。だから出入りは、はい込む形でされるが、幕の中は一段と低く掘り込まれて平になっておる。出入口左隅の処に、「天人穴」があって、これに自在鉤の支柱がたてられる。炊事や用便は、どこか近い川原とか岩かげとかを上手に使って人の目に邪魔にならんようにしている。あれらは、足が速いうえに、手先が器用で竹なんかとても薄く剥いでいくが、これは素晴らしい名人だ。それに紙よりも薄くする。ものを截(き)る事、割ることなどは神業かと思われる。巧いなどと云って見ていられるものじゃない。素晴らしい業だといつも思った。「食器」(茶碗一つと大鍋と丼が三つ)など幾つもありはしないし、鍋釜といったものも一ケあるのもないのもあって、ほんに簡便な暮らしである。 自分で薪も拾ってくるし山菜も採ってくる。味噌や醤油は出来ないのか、作り方を知らないのか。ざるなど作って持っていっては物々交換ということをして、金のかからない生活をしているようだった。持ち物は、その三種の神器と外は仕事の時に使う道具だが何でも必要なとき自分達で作って使うという方法でほんに限られた物持っとるきりだった。着物など一、二枚きり持っていないらしいのに、いつも意外に小ざっぱりしていたのは、お洗濯が好きな人々だったせいもあろう。朝鮮人のように平たい石の上に無黒子(むくろじ)という木の実を袋に入れて、天幕の裏などにぶらさげておいて、そのつど半透明の皮を石鹸の代わりに使っていたが、いつか利君にもらって使ってみたけれども「シャボンのようにはおちんで駄茶漢(ダメだ」ことになたものだ。が、それが何かの拍子に口に入ると、苦い苦い。いくら、唾を吐いても舌の奥から苦さが湧いて来るみたいだった。鳳の草の藤原某とかいう、この夫婦は、きっと京都か、あっちの方の人とみえて「ほんやのボンどすか」などと言ったことがあって、“上方”弁だった。利君が威したほど怖い人達とは思えなかったが、時々変な言葉使って私共に分からないことがあるので「ちいとおそがかった」持ち物の中で「山刀」という小型の山刀は小父さんきり持っていないものだが「大事なものだ」と言っていた。幅は一番広い所で二寸位厚さは三分位あろうか。白く光って、いつもピカピカだった。元の方が、ちいと細くなっていて、何かの皮でつくったと思われる鞘に横から挟む様に挿すので普通の刀とは大分違っとった。 出雲国の「火の川」という川の上流でとれるとかいう砂鉄を打って作ったものだと私共に威張ってみせて直径二寸位の枝を「タン」と音をたてる程に振り下ろすと一遍に截れてしまう。確かによう切れる奴に違いなかった。「やっ」といって投げると必ずその太い先の方が先になって「さされる」ということだ。「ににぎのみことさま、からのならわし」とも言って威張ってみた小父さんは本当に太い松の幹に投げて見せたりしたことがある。
2015/03/02
-
サンカの人々の暮らし 4
この人達の着物は本当に便利に出来ているので、いつも感心してしまった。そう、その着物だけど、上半分と下半分は別になっている。つまり一枚の着物が、上と下と別に作られているわけだ。上着は臍の辺から腰までくらいのところで終わり、下は乳の下からくるぶしまで、まるっきり袴か腰巻のようである。小父さんは藤つるか何かで自分が織ったと思われる角帯だったが小母さんも娘も紅い処のある帯をしめていた。その代わり村の娘達のように、お太鼓に絞めたりはしないで、いつも腹に巻いた形にしていた。手には手っ甲、脚には「キャハン」をつけていたし、いつでも手拭をかむって夏でも「カバチョキ」という(利君が名をつけた)半袖風の綿入れを背にあてていた。石の上でも土の上でも座る時に便利なように、その端に紐がつけられてていて、その紐を伸ばすと世話なしに座布団代わりになる。いらん時は荷物にかぶせたり、雨の時は頭にのせたりしていた。つまり、その本体の端についている紐を伸ばしたり縮めたりして尻の下に敷いたり背中へ引き上げたりするわけである。いつも何も持っていないから身軽で、いつでもさっさと「場移り」が出来るので便利だが、それでこの人達は「転場」ともいうのだと教えてもらった。「瀬振り」ともいうし「ポンス」とも「ポンスケ」とも「オゲ」とも「ホイト」とも「ノアイ」ともいうが、これは、その場その場で異なっている。矢作川流域では「ポンス、ポンスケ」付知川筋では「ホイト」。土岐川川端では「オゲ」美濃平野に出ると、「ノアイ・・・・」。日本中、きっと夫々の場で先に住んでいた人間共が多少軽蔑の意を含めて様々な名で呼んでいただろうと思う。 彼らは自分達だけに通用する文字のようなものを持っていたようだし、仲間同志だけに分かる数の読み方などもあったと思われるが私は、それはよく知らない。国学の平田篤胤という偉い人が「日文(ヒブミ)」というものを言い出して、漢字、仮名の外に「日本には昔から整文字として伝わっていたのだ」と言い出して残したものがあるが、それは「日文」というもので、こんなものだ・・・と吉田先生が教えてくれたことがある。この丸い鏡の表の「銘」にも書かれていて今も苗木の「神明神社」かなんかに伝わっているとかいう話だ。私が鳳の草の団子杉に小屋住みをしていた藤原夫婦に習った文字は、三十字位あったと思うが誰かの書いたものか、皆読める程にはなっていない。あの小母さんが『タテツケハズシ、カタドのト』と言って□(二と読む)の字の様な字を書いてみせてくれたことがある。コという「あんさんの片仮名」と同じだと言うて笑ってみせた。「カタドのト」というのは『□』というので日本の「ト」と同じ意味をもつのだ。と言ったのを覚えている。カタドのトは□に先ず と、一方の戸をたてて、コ(□)をつけたのが、ト(□)になるのだということだったように思う。十歳前後のことは、かなりよく覚えているが、この辺になると洵にあやしい。「キナイイツツノクニケイオウカミヨリカミシロクヘル」と読むそうだが「機内。五の国」「慶応一より、一四六九減る」ということで、機内五ヶ国では慶応元年(一八六五)よりも人数が千四百六十九人減った・・・ということだそうである。話をぐっと始めに戻して「鳳の草」の「団子杉」の根元の小父さん達は娘を一人連れていたが、持ち物は至って少しきりだったし、「し方」「はなし方」は皆、下馬木部落の柿木平の天幕組とは同じだと思われたが、どうしたものか天幕を張らないし仲間と離れて、この一家だけが住まっており、天幕の代わりに竹を二つ割にして上向きに並べ、その間を下向きので伏せて上手に雨を漏らなくしていた(仲間と外れて別に住む人を“トケコミ”といったが、そのトケコミの準備をしていたのかもしれない)それで日常に使う言葉の中にも時々分からんことがあったが、数のことはちいと覚えておる。 一、二、三、四と数えるのにカミ・ツギ・サン・シイ と言ったし「ぎ」と「ぐ」とを混用していた。「二月一日」という代わりに「キサユラグ、カミノヒ」というのである。「きさらぎちたち」といえば、すぐ分かるのに、きらゆらぐ、かみのひ、という類で私が困るのだ。これは三角寛という人の書いた何かにみえていたのだが仲間の人数調べの表があって、といったものが残されているそうです。メイチシサノトシキサユラグカミノヒ(めいじしさのとしきさゆらぐかみのひ)は、明治四十三の年。如月一日の日、「明治四十三年二月一日」というわけである。
2015/03/02
-
サンカの人々の暮らし 5
八、九歳だった私共は、様子を感心して見て来ると、すぐ同年のお友達を誘って「馬木坂峠」を車に越えた麓の「人造湖」のほとりに小屋を造って学校の帰りに寄っては一休みしていたのだが「庄次」さという老人に見つかってしごかれたりしたことがある。が、亀を焼いたり、蛇をつかまえたりは遂に誰もしてみなかった。「うまいかもしれんぞ」と利君はいつも言っていたが私の前では亀も蛇もつかまえなかったし、喰わなかった。従弟の寅三は器用な奴で「川の魚」を道上に立って外から見つけると「ざばざば」川の中に降りていって「ガマ」という河岸の石の窪みなどに逃げ込んだのを手つかみで捕ったりしてみせた。穴に逃げ込んだ川魚は、狭い穴の中では、方向が変わられないから、そのまま遊泳して徐々に後退して来る。そこに伸ばしていた寅三の手が待っていて魚のしっぽをきゅっと掴む。魚の奴びっくりして一旦は奥へつと逃げるというが辛抱強く待っているとまた指先に尾ひれがふわっと当たる。こうして一時間もすると遂々寅三の母指と人指との爪が、その尾っぽをしっかりつまみあげる。「やーい。子供んた、そんなとこで手づかみの魚とったりしとりゃ、ポンスと間違えられるぞ・・・・」道行く大人がちょっと立ち止まってそういう、いらん注意をしたものだった。 信州。平谷の在から瀬戸大曽根に通ずる。中馬街道が私の生れた家の前を通っており、後には裏手に代わって新道が出来たが、それでもそのおかげで「馬木洞」の十五、六軒の小部屋はしばしば飯田や岡谷や信濃路の文化と瀬戸名古屋の文化のようなものを持って来て私共村の者達は「子供の頃」過ごしたものだが、もっと直接には、この山窩や馬子衆や、そういう人々の「行動」によって養われていったように思う。 「やい。小僧。おしたちゃ、へんび、ようとるかいや。赤いのなら三銭。黒いのなら五銭。まむしなら十五銭で買ったるが、どうじゃ。捕ったら、火吹き竹ん中ん入れて手ぬぐいで、ふたしときゃ、ええわい岩村に「へんびかつ」ちゅう奴がおって、時々、こっちいも来るようで、うっかりすると取られちゃうぞ・・・」彼らは、何とかして、そのまむしの生きたのを捕まえさそうとし、黒蛇をつかまえさせようとしていたが、それをまた、このポンス達は、とても上手に捕まえたものだった。彼等は道を歩いていて、ふと足をとめると天をあおいで「スン ゝ ゝ」と何か嗅いでみるような風をしながら、しばらくそのまま立っているが、やがて一歩二歩その匂いの近くに脚を運んでやがて、ひょいと「長い紐」をつまみあげる。ぶらん・・しながら小父さんの腕にからみつく様にするが小父さんは首ねっこをつかんで口もとからシャツをぬがすように、するっ・・・と裸にむいてしまう。白光りに光る、その裸蛇は赤い血は出ないし、ほんに美しくきれいだが驚いたことに、そのまま手を伸ばして、そいつのしっぽから、ぐにゃぐにゃ横口に喰いきって「美味いもんでんがな・・」と、目を細めてみせたりするのには困った。 外のことには、大抵あの人達のすることに感心するのだが、この風態だけは、どうにも我慢ならん。 村の人達が怖がるのも「こんなとこ」みているからではないだろうかと私は思ったものだ。その喰い残りをあの小屋まで持っていって火にあぶって竹串にさす。それを巻藁に挿して保存しておくのである。「こいつ食って、自然薯掘ってくって、もう一つ松の実と地蜂の子、喰や病気なんかしまへんで・・・・・」と、威張ってみせたりするのには困った。地蜂は私も大好きだが、どうもあのぐにゃぐにゃの長蛇は苦手だった。いつやら、あの小母さんのくれた御幣餅だって素晴らしい美味い匂はしたけど、あの蛇のうごく姿とあの小父さんの生のまま喰っていく形を思い出して食べられなかった。包んでくれたのを家へ持ち帰って、おばあちゃんにやったのだが「どこの馬の骨とも分からんようなもんとこ、いよって、食うものむらってくるようなもんは、本屋の子じゃない!」と叱った。が、私は注意してみていたんだけど遂にそれを捨てる所は見なかったので「おばあちゃん、きっと喰ったな」と私は思った。その証拠に、その後の本屋の御幣餅のたれは近所でも格別美味いということになっていったものだ。然しどうも本屋では、蛇や蛙は入れなかったように思う。落花生を作り出したのは、その頃からのことだったのも証拠になりそうだ。このことを毎週書かされていた作文に書いて石田校長へ出したことがあったのだが、それについて夕食時の「他人の家の食べ物を覗いてみたりするもんじゃない」と、叱られたこともある。けれどもこの小父さん達はそういう意味で私とのかかわりがかなり深かったように思われる。
2015/03/02
-
サンカの人々の暮らし 6
その小屋には、いつも利君と二人で、そっと村人の目を盗んでは行ったものだが、或る日、その子供を「教え込む様子」を見て、ひどく感心したことがある。校長先生も批評の中に「それこそは、わしの唱導する「行動教育」そのものだ。今後も色々彼らのすることを見て来て、書き残してほしい」と言ったことがある。その「行動教育」は、石田校長先生の東方小学校でした「教育の根本原理」であるが、私が今、この親子がしていたことを書いてみようとする、そのことはもう、秋も半過ぎた頃の事だった。小川の川べりに、赤い平たい、大岩がある。その岩のそばへ、あの四つか五つきりならん娘を連れて行って夫婦して縄跳びを教えるところだった。その初めから私どもは、じっと見ていたのである。 小父さんは、小母さんの後ろについていく。娘の後ろ姿を見ながら長い長い藤つるを一抱えも一束にして肩にかつぐと、あの赤岩の側にやって来た。何か三人で話しながら三人は一列に並んだ。そして小父さんと小母さんとは石の両端に立って、その藤つるを引っぱった。綱引きするのかなと、思って見ていると、そうではない。 「カミーィ。ツギイ。サン・・・。シイ。イツ。ムナ・・・」数えているが、何と言っているか分からないが娘も真似て一生懸命大声で叫んでいる。そのうちに川柳の枝に小母さんの持ってた端をしばりつけると、小父さん一人で、くるっくるっと、廻してピタリ、ピタリと音をさせて藤つるを大岩の岩肌にたきつける。中央に立った、小母さんと娘とは、腰で調子をとっていたが、その中に、ひょいと子供を横抱きに抱いたまま、その綱の中所をまたいでひょいひょい、と飛び始めた。うまいもんだ・・・・・小父さんは大きく、ゆっくりとその藤つるを廻してやる。小母さんは、抱いた娘もろとも、やがてさっとその輪から出る。小父さんは相変わらず、くるっ、くるっと廻して輪をつくっている。その中にまた小母さんは娘を引っぱっていって今の、輪の側に立った。また跳ぶつもりだな。と思ってみていると、二人はしばらく腰で調子をとって藤つるが上に昇る度に、見上げては真剣な目つきになって見上げ見送る。つと、小母さんは、娘を前に押してやると、自分は、一歩後ろに出てしまった。 「あっ・・・・いっしょんとびやんのか?」と、思ったとたんに、あの小娘は上手に、その輪にのって、一つ、二つ、跳んでみせた。たった三回きり、跳べないで引っかかってしまったが、それで泣きそうにして、しょんぼりしている娘とは反対に小母さんも小父さんも真剣な顔をして一生懸命拍手を始めた。 「・・・・・」 分からないが、「跳べた、とべた」と褒めていることは、見ている私によく分かる。 「・・・・・」やがて、娘は立ち上がって小父さんの顔を見るといきなりその大きく廻っている藤つるの輪の側に歩いていった。二度、三度、腰をふるように動かすと、ひょいと、調子に合わせて、輪の中に跳び込んだ。見ていて、はっとした私は、何でもないのに、つい釣られて拍手してしまった。「やあ・・・跳べたとべた。偉いぞ・・・」私は、思わず、大声を出して叫んでやった。娘は、私の方を見ないままで七つ八つと跳んだが、小母さんは泣きそうな顔で私を見た。 九つめに、娘はつまづいて駄目になったが、それでも二人共、叱らない。「跳べるよ。とべるよ・・・・・ いいぞ・・・今度は、かあさんが跳ぶ・・・・・」 小母さんは、そう言って、娘の代わりに跳び始めた。「次ぎ。三。しい・・・・・」あっ。さっきの呼び上げは数だな。と私が思った頃は、もう小母さんの跳躍じゃ二十にもなっていた。 小父さんは、大ニコニコで大きい輪を作って、小母さんを跳ばせている。一跳び毎に、ぴたっ、ぴたっ、と藤つるは赤岩の肌をたたいて、音をたてるが、その度に外皮の赤褐色の渋皮が飛んでいって、中の白い皮の肌がみえる。そして間もなくたたかれてびろびろになった部分から芯の堅い部分が覗く小母さんが、廻す。娘が跳ぶ。小父さんが跳ぶ。 小父さんに代わってもらって小母さんが跳ぶ。娘が跳ぶ・・・・・しまいには、何か、分からん言葉で三人声を揃えて、唄いながら、跳びつづける・・・・・ やがて、芯と白い皮と、外側の赤茶色の渋皮がとれてしまうと小父さんは「かみやすみ・・・」と言って、川端の石に腰をおろした。娘を呼んで、抱いてやって、高く、さしあげて赤ん坊にする様にしてやって、褒めている。「よく跳べたぞ」と言っているだろうと、私はうらやましくなった。私の父も母も私と一緒に縄跳びをやってはくれなかったし、私の遊びが、出来たと褒めてくれたことは一度もなかったから・・「遊んでばっかけつがって・・」私は一度だって遊んで褒められたことはなかったのに・・・・・ そのうちに、ゆっくり腰を伸ばすと小父さんは手早く藤つるの芯を一尺位にきざんで薪の形にしばりあげると「これ、帰りに背負ってくんだよ」と、娘に言いつけて、自分には小母さんと二人、向かい合って、この藤の白い皮を両端から両掌の間に挟むように一方の端を左掌にのせると右掌をぐっと引いて、よりをかけ始めた。「左縄なんかなって、何するのかな」と私が思って見ていると、その縄は、よじれて段々段々短くなっていく。「・・・・・」と何やら合図したと思うと小父さんは、その端と小母さんの方の端とを揃えてうんと、引っぱった。とみると、忽ちパッと離す。藤つるの左縄は、生きものの様にくりくりっとうもて縄状によれて、川端柳の枝に、飛びつくような形で、縮まっていって見事な白い縄になって飛んでいった。が、それでもまだぴりぴりして動いている。小父さんは、それを川端柳から外すと一寸川の水につけてみて、ぴたりぴたりと岩をたたき出した。縄が少しばかり柔らかくなりかけた頃、もう一度、小父さんは、娘に笑顔をみせて「・・・・・」何やら言ってみてから、さっきの芯を切ったものを娘の背に負わせた。 小母さんは何も持たずに娘の後からついていくきり。・・・・・小父さんは、その縄の出来具合を見ながら、ごきげんで、小母さんの後ろについていく・・
2015/03/02
-
サンカの人々の暮らし 7
その日の午后。私は利君を誘って、もう一度彼らの小屋を訪ねてみた。私の陽足はぬるく、風は爽やかで、何とも気持ちがいい。・・・・・丁度、三人は出かける用意がすんだ所だったのでよかったなと思った。私達には、おかまいなしに、せっせとさっきの白縄と山刀とをもって三人は何かしきりに話し合い乍ら足早に前を歩いていく。私達を無視するようなことは、いつものことだし、私達も平気な顔をして、後れない様に小走りについていくことにした。先頭の小父さんは、川岸の竹藪の処で止まった。小母さんと娘とは、すぐおいついて小父さんと並んで何か話している。しきりに側の娘は合点をしているが、何を話し合ったのかは、分からない。只、悪いことでないだけは、三人共うれしそうな顔をしていることでよく分かる。「何するじゃろう?」利君は、いつもの顔で少しおでこを前に出す様に小首を傾けて私に言ったが勿論私に分かろう筈はない。「そう、あわてんなよ。そのうちに分かるよ」と私は言ってみたが、さっきから私達のことを少し気にし出していたのか小父さんが、こっちを向いて言った。「坊んた。わしらん、ついて来よって何すんかな?」私は、ひどく怒られた気がして、黙って立ったが利君は平気な顔で答えた。 「おまいた、おらたァ、いろいろ違ったことすっで、見せてむらうつもりだが、いかんのかあ」 「べつに、いかんというのじゃないけど、わてら、どこまで行くか、分からんのに、ついたいて、怪我でもされちゃ困るで・・・・・」小父さんは、そう言ったきり、すぐ竹の幹によじ登り始めた。 「うまいもんだなあ。まるきし猿じゃ」利君が何かつづけて言おうとした時分には竹は、小父さんの体重で曲がって先が地に届きそうになった。小母さんが、さ、さ、さ、と飛んでいって、その竹の先を両手で掴むと跳ね上がらんように、ぎゅっと引っぱった。。娘がさっきの藤縄を小母さんに差し出す。すぐ小母さんは、その竹のかなり先の方にしっかり藤縄をしばりつける。その縄はぐんと引っぱると隣の竹の元の方にくくりつけられて、はね上がらんようになる。小父さんがするすると降りてきて、ひょいと飛び降りる。ついでに数歩離れた所の竹によじのぼって、さっきと同じことをして、竹を身体の目方で曲げる。小母さんがその先を掴んで引っぱる。娘が藤縄の、もう一本の方を差し出す。小父さんがそこに縛り付ける。小父さんが降りてくる。小母さんはひっぱっている藤綱と、さっき竹の根っこにしばりつけておいた、初めの藤縄とを取られないように、両手で引きつけていると、その間に小父さんは、細い竹を切って二本同じ様に三尺位のものにする。その端を藤縄でしばりつけると黙って小母さんに渡す。小母さんは、その立った竹の伸びにつられて、ひょいひょいと引っぱられて身体が浮き上がるようになるが、手を離さないで耐えておる。小父さんは、初めにしばっておいた藤縄の方を外して今の三尺竹のもう一方に巻きつけてしっかりしばりつける。 「あ、分った。ブランコつくりよった」利君が言って私の顔を見た。きっと、あの娘にブランコ作ってやったのだろう、と思うと、私はちいと羨ましい気がした。私だって利君だって家の外でブランコなんか作ったら叱られるにきまっとるし、第一、親がブランコ作りに先にたってやってくれるなどということは、絶対になかったことだから。 思った通りだった。小母さんが、まずブランコの初乗りだった。二度程腰と膝との屈伸で調子をとるとブラーンブラーンと竹薮の外側へ向かってふってみせる。娘は真剣な眼つきでじっとそれをみている。勢いがついた。・・・・・ざあっ、ざあっと音をたてて、この二本の竹が曲がって伸びてあっちの川岸にとどくと小母さんは、もう一度膝と腰とで舵をとって大ゆすりにゆすってから、ひょいと身体を縮めて、ひらりと向う岸に下り立った。両手は、まだブランコの藤縄を掴んだままだから竹が伸びる時、ふらっ、ふらっと引っぱられて泳ぐ様に動く・・・・・。「面白いことしよるなァ・・・・・」二人は、感心してしまった。第一。ブランコの作り方が面白い。あの縄の作り方が素晴らしい。あの腰と膝の使い方が、実にうまい。 「おらも乗せてくれるだろうか?」利君は、もう乗せてもらうつもりでいる。小母さんは二度三度、同じ様にして、この竹のしないを利用しては川の向うにいったり、その反動でこっちに来たりして、形を見せていたが、やがてこちら側に、ひらりと降りた。「・・・・・」娘が呼ばれて、そのブランコに乗った。脚も腰も小母さんのような具合に強くはないので、なかなか、このブランコは小母さんの様に上手には、揺れない。小母さんは何やら言いながら娘の脚もとから下っている細紐をつんと引っぱって娘の腰の力を助けてやる。「あの紐、いつ付けた?」「不思議な奴らだなァ・・・」利君と二人で感心している間に娘のブランコは、段々調子がついて川の上を向こうに届いたり、こっちに戻ったり何回でもぶらあん、ぶらあんと動く。そのうちに小母さんが、何か言ったなと思うと娘は腰を曲げて止り木にしゃがむ形になったが、向こうにつくと一緒にひょいと飛び下りた。うまい・・・ブランコは、こっち側にぶらんと、戻ってかなり高い所へ上ってしまった。だけど、小母さんの手の紐は、ちゃんと握られているので、どこか遠くへ行ってしまったりしない・・・。「ちぇっ。やってけつかる・・・・・」利君は、もうすっかり感心のしっぱなしだ。「これで、どうするずら・・・」私がそう思った時、小父さんと小母さんはパチパチ手を打ってから、万歳の形をして娘を褒めてやっていた。 「あ、そうだ。川渡りの仕方を教えたとこだよ・・」やっぱり利君は、私よりも頭が良くて早く分かるようだ。「だけど、もう、あの娘あ、戻れんなっちゃうに・・・」私が心配をしてやると、今度は小父さんが乗っかって世話なしに、向う側にぴょんと渡る。娘を抱き上げて「きゃっ」「きゃっ」と言っているのは、きっと「上手に出来た」と褒めてやってるのだろうと私共には思えた。娘を乗せると、今度は小父さんは、向う側に残ってみている。 何度も何度も繰り返して、川渡りの方法を見せてくれたが「貸してやる」とも「乗ってみろ」とも遂に言わなかった。「坊。日い、暮れますっせ。はよ。帰らんと叱られるで・・・・・」小父さんは向う岸から大きい声を出して私達を追払いかけた。もう少し見ていて、あの藤縄をどうして取ってくれるか。その縄どうするか。見たかったけれども大分急に薄暗くなりかけていることに気づいて二人はほんに名残惜しくも、その場を下って道路に出て来た。あとの日に尋ねてみたが、この藤縄は、「折角努力して作ったものだから、もう一度水に浸けて、ほぐして糸のようにして幾晩もかかって「より糸」にして、小父さんのしている角帯のようなもんにするんだ」と小母さんは教えてくれた。 私は「教育の原点」というものを探したら、この「山窩の夫婦」のような「生活の実際」の中にみつかるのではないかと思って来た。この数年の後に、私が無官の大夫となる日が来る。そこで最初に手がけたいと思うのは「恵那地域の教育の原点等」であるが、それは、やはり、「原点」ともいうなれば、ここらにあると思えてならない。「行動」する、「労働」し、「労作」し、肉体を動かして「分る境地」におこうとした、「恵那の先人達の教育」は、やはりここを目指したものでは、なかったのか。いつぞや、芳兵衛先生は、その話をとても大切な話に聴いてくれたし、藤村老も、しきりに「いい話だ」と褒めてくれていた。 私も含めて、今時の教育の中に「共に行く」「共に生活して」「共に生き育つ」「共育」が無いのが悲しいことだと思うことから、残したい話の一つだ。(昭和四十八年六月十七日)
2015/03/02
-
サンカの人々の暮らし 8
方言注おーっそがい=おそろしい二ッケ=肉桂 殺されるげな=殺されるそうだ だちゃかん=駄目だ子供んた=子供達こきる、こいて=言っている、言って おし=おまえ こっちいも=ここらへも もんとこいょって=者の所へ寄って いっしょにとびやんか=一緒に飛ばないのか遊んでばっかけつがって=遊んでばかりいやがって もうて=まわって坊んた=坊やたち世話なしに=何の苦労もなく三宅武夫 1903年~1990年 岐阜県の教育家。岐阜県師範学校を卒業後、 教師になる。1943年中津町立第二中学校 初代校長に就任。以後中津川市教育長などを歴任。著書『おらあ先生になる』ほか家族単位で山の中や川辺で漂白の生活を送るサンカは、大自然を背景に親が子に自分の生活する姿を見せて生活している。教育者である作者の三宅武夫氏はサンカの家族に教育の理想を見たのだろう。その眼差しには優しさが溢れている。 三宅武夫は明治三十六年、岐阜県に生まれ、師範学校を卒業後地元の小学校に赴任、その後愛媛県の松山に転出している。この鞦韆(ぶらんこ)はその後に、生家に近い恵那郡の団子杉近くで目にしたサンカの家族のことを書いているが、この愛媛時代にもサンカを目撃してるという。 三宅氏が出版した『おらあ先生になる』という自伝の中にもその時の事が書かれているので、引用しておく。 ※その一つに、松山にいた時、担任の生徒を引率して、奉仕作業のためにと、市街の南を流れている石手の川原に行ったことがありました。そこには、ずいぶん沢山の天幕が張ってあってこの川原の右岸に、穴を掘って住んでいるらしく、竹細工をしている一群に逢ったことがあります。 『先生。ここにゃ、紀元二千年前からの人間がいますけ、気ぃつけにゃいけんぞな・・・・・巣に棲み、穴に住む人間が、かなり大勢いるのじゃけんな・・・・・』高橋という生徒がそう言ってきました。なるほど、見るとかなりの人数です。それは、 明らかに、かつて私が子どもの頃に見た、あのボンスケといった、同類の人達であることがすぐわかりました。私は、その彼らの天幕の前まで行って、昔「鳳の草」(明智在)の小屋にいた三人の暮らしを思いながら、あの時小母さんが教えてくれた彼ら独特の文字だといった、あの符牒を書いて見せたのです。(中略)。記憶をたどってみますと、これはどうやら昭和十四年の夏のことです。その後、彼らがどうなったのか、いつどこへ消えていったのか。それは知りませんが、その時の話の中に、今はその日その日の生活に、大分困っている話。いまに日本が戦争にでも突入すれば、その時はまっさきに志願して、軍人にしてもらい、天晴れ日本人になってしまいたいが、どこにいっても一般人、一般の子供迄が、冷たい仕打ちをして、自分たちを悲しませている。先生なら、その先生になる人々に私らだって人間だということをよく解るように話して聞かせ置いてほしいと言っていました。そして今、何とかして「溶け込み」をしたいと思い、この地に「居つきたい」と、それぞれ苦心している。と言っていました。 ※愛媛県師範では三宅氏は校長に生徒の五年間持ち上がりを要求し、県内の生徒宅を訪問して回るなど、たいへんに教育熱心な教師であったようだ。それはおよそ四十年近くも後の、このような後日談からも窺える。再び『おらあ先生になる』からの引用 ※それが昭和五十一年、私は、私の手記復刻版の『鞦韆(ぶらんこ)』という一冊を印刷してもらいましたので、当時教え子だった伊予路の校長たちに送りました。ところが、その中の三人もの校長から「私の学校のPTAの役員の中にそういう人びとがいますらい・・・・」と、教えてくれました。・・・それは、あの時、「溶け込み」を考えていた人達の子孫じゃないでしょうか。あの頃から「溶け込み」をはじめたにしても、あの全部が、あの辺りだけに落ち着いたわけでもなでしょうから、いずれ、松山近郊から西は西宇和、東は遠く香川、徳島、南は高知、北は瀬戸内の島島から、中国路にかけて、じりじりと沈潜・定着していったのではないかと思うのです。 ※中国・四国地方のサンカの出自を考察させる一節である。そうして三宅氏はその後を学習研究会で回ったりした時でも、日本全国いろいろとその土地土地で興味深い観察をしている。特に、京都で成長した小学校の教え子の女性達に「道楽」という料亭で竹焼料理をふるまわれた時の書いている内容が興味深い。 ※その「一節の竹」の上側の割り口は、和紙で貼られていて、竹の底側は、すこし焦げていました。口取りが出て、お吸い物が出て、お酒が出て、その張り紙がはがれますと、この一節の中には、一杯詰められた様々な山海珍味が納まっていました。一番上に・・・・(中略)。その「知久屋喜」は、まさに、彼らの秘法による、石焼料理、桶料理、竹筒料理と、みな同じ類型の料理だと思いました。東は秋田、西は山口、南の高知、内海の鹿島、そしてこの京都の「知久屋喜」、それに故郷明智の、鳳の草の小母さんの「手料理」も、同じ手法だったと、今も思っています。 ※このように三宅氏はサンカに向けて様々なアングルからのアプローチを試みているのだが、やはり「鞦韆」においての重要なテーマという「教育の原点」を「サンカの家族」に見出したということになるだろう。三宅氏は、彼らの生活の中にあった「子どもへの教育」が徹底した「行動中心教育」であるとし、その素晴らしさを「鞦韆」によって我々に伝えてくれている。 藤つるを取ってきて、それをぶらんこに作りあげてくまでのプロセス。そしてぶらんこが、出来上がってから親子三人で遊ぶ姿を見て、七十年近い昔、若かりし三宅氏は、共感と羨望の眼差しで三人の親子を見ていたに違いない。それは次の言葉にも明らかだ。 ※私の周辺にいた多くの人々の中にあって彼らぐらい、強烈に私の「教育行動」に影響した集団は、少なかったという気がしてなりません。(中略)彼らのような「生活即教育」「遊び即生活」の「共育」をすすめる、そういうものを忘れたくありません。何としても「子ども自身が自らの行動を律する力」が、自ら育つためになくてはならないことと、私は思うのです。 ※三宅氏の著作の中には「そっとみんなが溶け込んでいてくれますようにと願うわけです」という一節がある。サンカを好奇の眼で見る、あるいは研究の対象としてのみ見ようとする試みの氾濫する中、サンカに向けられた氏の眼差しの温かさは、その人柄を反映していることを窺わせる。“サンカ”へのオマージュとして「鞦韆」は文句なしに至高の存在だと言える。 最後に氏がサンカへの惜別の情を吐露した一節を引用しておわりにしたい。それはまさに、平成の現在“サンカ”という存在にロマンと憧れを持ってる、我々総てに共通する心情であるといえよう。 ※私の記録の中には、これら「消えていった人々を惜しむ」幾つかの記録がありますが、いつもこれを見る度に思いますのは「その後どうなったか、もうわからない」という惜別の情です。それでいて、イツの日にか、 まさに私の心の底深くに食いいって離れない、それらの人々の人柄、暮らしの実態、いささかの高ぶりもない親切、独特な語り。そしてその中にあった珍しい、それでいてまことに「平凡」な何でもない、しかも、またここになくてはならない「文化」「生活」「教育」の実態等々、回想するたびに、涙のながれるほど懐かしく、切実に感じるものがあるのです。彼らが一般人社会、周辺の人々の世界に溶け込んだとしても、どこかで、あの純粋だけは残していてほしいとそう思うのです。
2015/03/02
-

黄色人種
黄色人種と呼ばれるのは、体の表面がケラチン (角質)の薄い皮膜で覆われているからだそうです。ケラチンは硬タンパク質であり、髪の毛や爪や動物ではツノ、ヒヅメなどになる物質です。どうして、ケラチンが全身にまで被覆したのでしょう。それは、日本人の先祖が中央アジアのアルタイ山脈南部に起源をもつからです。現世黄色人種の祖先が形成される時期は、少なくとも4万5千年前から4万年前という、ネアンデルタール人からホモ・サピエンスが出現する以前の時期まで遡ります。そして、数万年という時間をかけての、この時期での環境適応の結果がケラチンの全身皮膜なのでした。人類の皮膚の色まで変化させる壮絶な環境とはいったい何だったのでしょう。4万年といえば氷河期です。人類が等しくこの試練を受けたとはいえ白人種と黄色人種の祖型では、その影響の受け方がちがっていたようです。氷河の近くに住んでいた、とくに北欧人などは、太陽の紫外線を吸収しようとして皮膚に太陽光遮断の役目をもつ色素などもたない体質に、白人とは色素が白いのではなく、無色人種なのだそうです。黒人は紫外線の強かった地中海地域に住んでいたため遮断するために色素、メラニンを全身にはり巡らし黄色人種は、わたしたちの先祖は黄砂を避けるために山岳の樹林地帯に逃げ込むより道がなく、その原生林の中でもそう楽ではなく、樹皮の刺傷や虫害を防ぐためにも黄砂の嵐のなかと同様に角質でもって全身を覆うよりほかなかったといいます。こうしてユーラシアの大陸、なかでもアジア大陸の内陸と呼ばれる広大な地域にあって日本人の先祖は自然の猛威から逃げに逃げ、移動に移動を重ねるうち皮膚の色まで変色していったのだといいます。そして、またこの移動という側面が、日本民族の形成に大きく関係してくるのです。日本民族の祖型も漢民族の祖型も、新石器時代に入る前まではうっそうとしたシベリア原生林の中で狩猟一本槍の生活だったと認められます。もっとも樹海を貫いて流れる大河のほとりとか、点々とする湖水のほとりでは漁撈もしていたでしょうし、獣肉や魚肉のほかに野生植物、果実、根なども食していたでしょう。また彼らはトナカイを飼育し移動の際の運搬に牽かせたり乗り物にし、また乳を飲用に、肉を食用に、しかもトナカイは草を食べずに森林地に生えるコケ類を食用とするので願ってもない家畜でした。ところが氷河期が終わったところで、いよいよ原住地のほかの仲間が新石器時代文化をつくろうとするとき、一部の人類が、この故地を捨てて移動に踏み切ります。これが日本人の祖型と漢民族の祖型になります。間氷期において、タリムとアラシャンとゴビとオルドスという広大な湖水群が氷河湖となり、ほかの地域の表土がこの氷河湖の底に堆積し、氷河湖が乾燥して干上がって砂漠化してくると、その黄土がシベリアの寒冷型移動性高気圧に巻き上げられて、東ばかりでなく北に飛散してくると、彼らはどうにも防ぎきれなかったので移動を始めたのです。また移動せずに原生地に残された日本民族の祖型は、一部はモンゴル的モンゴロイドの中に編入され、一部はトルコ的モンゴロイドと混血し、さらに他の一部はイラン的ユーロポイドで、後に大月氏のまたは禹氏の祖であるトハリ族と部族連合をなしたという痕跡を残します。日本人の祖型の主流は樹林帯の棲息した狩猟民族の姿のままで、よりよい樹林帯をつたって南下したしたと考えられます。アルタイ山脈の西部と天山山脈北鹿の間の故地からジュンガリア廻廊を南下し天山の南麓をつたわって西方に進み、さらにパミール高原の東麓にそってタリム盆地の西辺をぐるりと迂回し、パミール高原がおわるところで一部はカラコルムからヒマラヤに入ったと考えられています。ほかにも行き方は何通りかあったようですが、彼らはヒマラヤに登り、崑崙の常緑広葉樹林帯に移動したのでした。ちなみに漢人の祖型はカラコルムから南へ移動し、黄河上流のデルタをめざしたようです。また一部は揚子江にくだって野生の稲をみつけるという幸運な恵まれています。日本民族の祖型にも四川から揚子江へと漢人と同じ道をくだった一隊もあり、二民族の交錯もあったとおもわれますが、ただ日本民族の祖型は、トナカイの代わりにカモシカを伴侶としながら照葉樹林対の山岳地帯の緑辺を辿って大巴山脈から山東の泰山山系に行きついたことが漢人の祖型とちがっていました。そして中国大陸にあって、日本人の祖型は漢人から【夷族(異民族)】とされたのです。こうした移動は1回や2回ではなく何回も何回も数家族単位で連続して居住地を移行していったようです。7千年~8千年前頃、旧石器時代の終わり頃に始まったとされ、その頃の人口はそれほど多くなく、人口の増加は新石器時代の農耕文化が定着集落をつくりだして以後のことでした。
2014/07/04
-

カタカムナ人は旧石器人?
35,000年前頃に中央アジアで、ユーラシア族に突然変異が起こった ポーロと名付けられた、M45東と西にT字型に分かれて、広大なステップを移動した人々は東はシベリアのバイカル湖、そしてずっと後にはアメリカまで、西はヨーロッパへ。男系M45の連れ合いはヨーロッパの母系Nの子孫エウロペの五番目の娘U5。彼らは、パレオ・ユーロペオイド的(白人)だったと考えられています。彼らは、新石器時代の後期、BC3000年紀の初めにかけて南シベリアのイェニセイ河上流とアルタイ地方に、アフナシェバ文化を起こし西シベリアのソンスク地方にBC1750年~1200年の間分布したアンドロノヴォ文化という青銅文化につながり、さらにBC2000年紀末南シベリアのカラスク文化 と中央アジア北部のダザバギャプ文化につながります。 カラスク文化は、殷の青銅文化と同様に、西アジアに発達した金属文化の東方流入によって発達したといわれます。M45が派生したと同じ頃、テンシャン山脈の北側に沿って移動しジュンガル盆地を利用して現在の中国にたどり着いたグループがいました。大半のユーラシア族が侵入をあきらめたルートです。このジュンガル盆地は、後にジンギス・カンが中央アジアを侵略するのに利用したルートで、この盆地は、中国やモンゴルから中央アジアへの抜け道になっているのでしょう。このグループは、西アジアとヨーロッパには全く見られないY染色体マーカーM175の子孫を残しました。M175の系統は、その後ヒンズークシ山脈とヒマラヤ山脈より東に住むアジア人の大多数を占めるほど大いに繁栄し、東アジア族と定義されます。しかもこのM175の分岐時期、35,000年前という時期は、まさに日本列島に【最初の日本人】が出現した時期と一致しているのです。日本列島には、旧石器文化の3万年前から1万4千年前頃に、鋭い黒曜石やサヌカイトの刃物に柄をつけた文化的な工具をもって彼らが渡来しています。この時代の石器はヨーロッパの旧石器文化と共通であって隣国の中国大陸の文化とは似てないといいます。ヨーロッパからやってきて日本列島で誕生した旧石器文化と考えられています。これが縄文時代につながります。 日本人〈カタカムナ〉人の手先の器用さは旧石器時代の石器に遡るといいます。
2014/06/30
-

旧石器人・縄文人からカタカムナ技術
日本列島に渡来した日本人の起源は、3万年以上前の前期旧石器時代まで遡れるそうです。 ★旧石器文化 ・ 第1期10万年前を遥かに超えるような古さから3万年前ぐらい迄日本列島で行われた文化。この頃の石器は、手で握る石の刃物でした。★旧石器文化 ・ 第2期3万年前から1万4千年前頃になると鋭い黒曜石やサヌカイトの刃物に柄をつけた文化的な工具となりました。この時代の石器はヨーロッパの旧石器文化と共通であって隣国の中国大陸の文化とは似てないといいます。どうもヨーロッパからやってきて日本列島で誕生した旧石器文化と考えられています。★旧石器文化 ・ 第3期1万4千年前頃から1万2千年前頃には、細石刃が使われこれは日本で発生したものでなく、シベリアからやってきた文化で広く北欧から沿海州そしてアラスカまで広がっていました。宮城県薬莱山に住み着いた住民の年代は、第2期を下らないと考えられ、この薬莱山の文化は旧石器から縄文時代に続く日本人の最古の足跡とされています。例えば近くのタカ族、タカギなどの地名のある部落の鎮守は延期式の飯豊神社。この神社は古墳時代の神社とは違って山の中腹に磐境(いわさか)があり、その中に磐座(いわくら)と神籬(ひもろぎ)があって注連縄で飾られています。磐境とは、神を祭る神域で、もともとは岩で囲んでいたものらしく縄文時代のストーンサークルを思わせます。磐座とは、神の御座の意味で神の鎮座する所。神籬とは、往古、神霊が宿っていると考えた山・森・老木などの周囲に、常盤木を植えめぐらし、玉垣を結って神聖を保った所。一本の木を植えた事もあって、その木が老木となったのが神籬とされることもあったと思われます。こうして宮城県では座散乱木遺跡など前期・後期旧石器時代から縄文初頭までの文化が重複して発掘され、日本の歴史が3万年以上の前期旧石器時代まで遡れることが証明されたのでした。3万年前には既にシベリア・バイカル湖文化センターがあったことが分かっています。旧石器人、それに続く縄文人などは漸次そこからやって来たようです。太古時代、バイカル湖に住んでいた古モンゴロイドの一部が北と南に散っていき長い間に北方系、南方系という、やや異なった遺伝子をもつ種族になったといいます。 北はエスキモー、アメリカインディアンとなり南は中国、台湾、フィリッピンとなり、その北と南の古モンゴロイドの一部が日本列島に入って来ているといいます。北と南の古モンゴロイドが、再び日本列島で出会い、やがて、もとの同族となっていったということで、それは2万年前にも遡ります。宮城県では座散乱木遺跡出土の動物型土壌品は、チェコスロバキアのドルニ・ベストニッシュ遺跡(2万3千年前頃)に類品があり座散乱木遺跡は、これに次ぐ世界で2番目に古い動物型土製品です。2万年前からバイカル湖などからやって来た人々が次第に日本列島に定着して縄文文化を築き、その間たえず人々は大陸と日本列島の間を往来し、また情報に接していたようです。 縄文時代以前、旧石器時代末期に存在したとされる極めて高度な科学技術や 独自の哲学体系を持っていたことが、神代文字であるカタカムナ文字で記された 【カタカムナ文献】から推測されます。大自然、大宇宙の息吹を友としていた超古代人にとって、その直観力は、 現代人の想像も及ばないほど研ぎ澄まされており、宇宙の深淵、宇宙の背後に 隠されている何ものをも射抜くほどの力を持っていたようです。 古代日本に渡来した一派がカタカムナ人です。 彼らもまた、石英の多い山を利用して、全国各地に人工ピラミッドを造山しています。 そして、ミトロカエシの技法からも分かる通り、錬金術師でもありました。 カタカムナが伝える【ミトロカエシの秘法】は、【賢者の石】に関係するといいます。西洋のヘルメス学(錬金術)の文献には、【賢者の石】は、ガラス状に輝く ルビー のような化学物質と記されているとも言われています。楢崎氏は、戦前の製鉄研究で、材料も技術も同じなのに、ある場所の製品はいつも優秀であるが、ある場所のものは不揃いで不良品が多く出るという生産する場所の違いで鉄の出来上がりが異なることに気づいていました。この原因を突き詰めると、樹木の繁栄しているところと荒地の差であることが判明し、【土地には良い土地と悪い土地がある】というのが経験になりました。戦後、農業科学に関わることにより、生産に向いた土地と不向きの土地の測定に向かい、この途中でカタカムナ文献に出会い、カタカムナ人も良い土地(優性地)をイヤシロチ、悪い土地(劣性地)をケガレチと呼んでいたことを知りました。これを科学的に分析し、ケガレチのイヤシロチ化を含む様々な改良、農業技術の革新に取り組みました。 楢崎氏はミトロカエシの技術により、原水爆の核エネルギーを無力化する技術を 開発し、無償で国家に献上しています。 ミトロカエシとは「カタカムナ文献」の楢崎氏によれば、超古代には【ミトロカエシ】と称される原子転換 の技法が伝承されていたといいます。【ミトロ】は気相・液相・固相の三相、【カエシ】は還元を意味します。楢崎博士の研究によると、この「ミトロカエシ」は物質の物性を変換させたり、新たな物質や生命を発生させる技法といわれています。全国各地の「ドロカエシ」「トロカエシ」などの名のつく池や沼には、生命誕生の伝承などが存在しており、そのことを比喩しているのではないかといわれています。楢崎氏によれば「ミトロカエシ」には原子転換 だけではなく、生命の自然発生という現象も伴うといいます。これは【潜象から現象へ出現する正の波動と共に、現象から潜象へ 還元していく逆波動が存在する」というカタカムナ科学に基づいたもの で、放射能(電磁波α・β・γ)を中性化させる「反電磁波」を出す物質だとされます。数学的に符号をつけると、電磁波は+の電気エネルギーで、 反電磁波は-の電気エネルギーを表します。潜象世界(虚数の世界)から現象世界(実数の世界)に無尽蔵に流れ込んでくる 超光速粒子アマハヤミは(-)の世界のエネルギーであり、それらのアマハヤミが 90度の角度で衝突すると電気エネルギーが発生することを発見したのが、 天才物理学者ニコラ・テスラでした。 テスラはこの原理を使って、地中から無尽蔵の電力を無料で取り出す装置を発明し モルガン財閥に潰されたといいます。 【-×-=+】になるのは、アマハヤミ×アマハヤミが電気エネルギーになることを表しこの(-)のアマハヤミ(超光速粒子)を物理学でタキオンといいます。そして人工的にタキオンを取り出し、コロイド状物質に貫通させると元素転換が起こります。 コロイドとは 一方が微小な液滴あるいは微粒子を形成し(分散相)、他方に分散した2組の相から 構成された物質状態です。膠質(こうしつ)と呼ぶこともあります。 一般的な物では、バター、牛乳、クリーム、霧、スモッグ、煙、アスファルト、インク、塗料 のりそして海の泡などがコロイドです。
2014/03/09
-

ケバラン人から
中東地域に現れた最初の人間と考えられるケバラン人が姿を現すのがBC1万8000年頃。 それは、ヨ-ロッパの氷河期の最盛期に当たっていました。ヨ-ロッパは氷河期に一度ほとんど無人化した可能性があります。 寒冷化から逃げなければならなかった彼らの行き先は南にしかありませんでした。 彼らケバラン人は、中東、パレスチナに現れその後の文明の主流になりました。約1万5000年前、地球の温暖化が始まり、不毛の砂漠だったシリアの北部に草原や森林が広がりました。新しく出現したシリアの環境は、木ノ実や小動物など豊富な食糧を供給し、周辺の狩猟採取民族が、ハルーラという場所で定着生活に入ります。しかし、約1万1000年前に、地球的規模の寒気の揺り戻しがありました。シリア北部の自然環境は、もはやかっての生産性豊かなものではなくなり人類史上最初の定着生活を始めていた人々は、人口の増加をもたらし、そこへ突如襲った環境の激変と、それに伴う食糧の減少は村落の住人を窮地に追い込んだに違いありません。しかし彼らは、未曾有の困難に敢然と立ち向かったらしい。この時代の地層の考古学的発掘が興味深い事実を発見しました。約150種類の植物の種が発見されたのです。 中には、クローバーの種など、とうてい食用に耐えない植物の種も含まれていました。 明らかに彼らは、危機に直面して、ありとあらゆる可能性を探ったとおもわれます。 彼らにとって幸いだったのは、その中に小麦が含まれていたことです。 小麦は比較的寒さに強い。さらに現代の専門家の研究によって、小麦の驚くべき性質が明か になりました。野性の小麦は、たった10年程度の繰返し栽培でも、その性質を見る見る変え粒が大きくなり殻は柔らかくなって、食用に適したものになったのです。この小麦の変幻自在の性質が、その後の文明の発展に決定的な影響を与えました。しかし、初期の農業村落のほとんどは、大きな規模の町に発展する前に消えていきました。 初期農業村落の幼児死亡率は高かったのです。BC1万1000年頃、中東に現れたナトウフ人は、ケバラン人の系譜につながります。 世界最古の農業は、BC1万年より少し下がった頃、カルメル山の周辺に溯ります。エリコの町は天然のオアシスで、エリシャの泉は、遊牧民たちの水飲み場でした。 人が集まりやすい場所だったのです。エリコの最初の住民ナトウフ人が、北西のカルメル山の山麓からやって来たと考えられています。その周辺には、現在の大麦や小麦の先祖の野生 種が自生していて、最初は、野生の麦を動物の骨の柄に石の刃を埋め込んだ原始的な鎌で採取し始めたと思われます。農業は通常の採取経済に比べて50倍もの生産性をもつといいます。カルメル山からエリコへ移り、農業を始めたナトウフの人々は、共存共栄の元に平等に暮らし生産性を高めましたから幼児死亡率を減らし2000人ほどにも人口を増やしました。エリコの最初の文明は約1000年続きました。しかし、農業が安定し、穀物を貯蔵し、エリコが繁栄し豊かになると外敵が出現し、城壁を造らなくては、ならなくなったと思われます。ナトウフの人々は、アナトリアへ、武器を探しにいったようです。黒曜石です。その時に、農業技術の情報もアナトリアへ、流れたと考えられます。しかしBC7000年頃、その文明は急に終わります。新しい人たちがやって来たのです。エリコとともに、パレスチナのいくつかの地点が同じ運命を辿りました。 侵入は、かなりの規模で行われたのでしょう。 新しい侵入者は北シリアからやって来たと考えられています。この人々は、アナトリア方面から入って来たらしい。エリコのそれまでの円形の家は方形の家にとって代わりました。その方形の家の床の壁は、磨かれた「しっくい」で覆われていました。この方形で磨かれたしっくいの床の家という、かなり特徴のある家が アナトリアのチャタルフュイックの遺跡で発見されています。 円形は、長頭の地中海人~エブス~フェニキア~ユダヤ~公孫氏~卑弥呼につながります。黒曜石の原産地は、アナトリアですが、大きく分けて二つあり一つはカッパドキア周辺、もう一つは、ヴァン湖の北岸地帯にありました。カッパドキア系とヴァン湖系の分布は比較的はっきりと分かれており前者はアナトリア南部からパレスティナにかけての地域、 後者はチグリス川とユーフラテス川流域が中心になります。しかしヴァン湖系の分布は、一部がカッパドキア系の範囲(パレスティナとチャタルフュイック)を中心としたアナトリアの一部)に混在しています。 一方、ヴァン湖系の黒曜石の産地は多数あり、チグリス川およびその支流地域を中心に ユーフラテス川沿岸そしてイラン南西部のスーサ辺りから出土しています。と、いうことは、パレスチナ(カナン)のエリコの人々の地域にヴァン湖系が侵略し範囲を拡げたということです。そのヴァン湖系の人々が、アルメノイドだと思われます。ハッティ・ミタンニ・フッリ族などが、アルメノイドに組み込まれます。BC5100年から4300年までにバビロニア北部でハラフ文化が展開しました。この文化の特徴は彩文土器、銅、円形のトロス(祠堂)、押捺印章などで【分業】がはじまり、金属細工人、陶工、石工が生まれ、銅鉱石が交易されて、 農村の自給経済を変容させました。この頃から銅鉱石を採集してハラフ農民と交換した人々が後にセム族 特にアッカド人として歴史に現れます。 北部にハラフ文化が展開しつつあった時、バビロニア南部ではエリドゥ期で沼沢地に農耕社会が形成されました。シュメール人が現れる1000年も前のことです。エラム族は、インドのドラヴィダ族と共に、地中海からインダスに至る広範囲な地域を移動し、その一部はアルメノイドと混じりながらシュメール人となってBC3500年頃、ウバイド人がいたバビロンの地に侵入しました。 「史記」の伏犠氏は、この人々です。アルメノイドとは、アナトリア東部のヴァン湖の北岸地帯にいた人々です。それは、黒曜石の分布図で現在も解析できるようです。黒曜石は、火山性ガラスで、ナイフな ど鋭利な刃として、中東では銅化合物に取って代られるまで使われました。エラム族は、ジグラットを作り、そこに月神シン(このシンが後々まで名付けに関連する・・秦・辰・晋・清)を祭り、部族同盟を作り、西はザクロスに至り、東は中国大陸に現れ中国史では、燕人となって、アラム族(のちのウラルトゥなど)の祖でもありました。この部族同盟は、族外婚という特徴に変化して、サカ族の末裔である蘇我氏でも行なわれていました。 人類の文字は、エラム族が作った縦、または横の絵画配列に始まります。エラム族は、サカ族などの原型となりますが、この人々が、中国の甲骨文字と メソポタミアの原エラム文字を作った人々でした。
2014/03/09
-

エラム文明
氷期の終わりの約1万2千年前頃に温暖化していくなかで急激な戻り寒冷期がありました。ヤンガー・ドライアス事件と呼ばれている現象です。北アメリカにあった巨大な氷河湖(氷河が溶けて出来た水が堰き止められて形成された湖)が崩壊して、大量の淡水が一気に海に流れ込んだ結果、海流が乱されて地球規模の熱の移動が滞ったのです。中近東ではこの時の寒冷化によって採取できる食物が減り、それを補うために農業技術が進歩したと考えられています。 人類は地球が温暖化すると知的停滞し寒冷期の方が前頭葉が進化するようです。現人類の祖、ホモ・サピエンスも寒冷化・乾燥化した時期に獲物を求めて、アフリカから西アジアやインドに進出しています。最初に農業が開始されたのは、12500~10200年前に存在した地中海東部のナトゥフ文化といわれるパレスチナのエリコでした。 さらにエリコの人々はアナトリアのチャタルフュィックで自然銅を発見しその銅を加工する高温技術を発明したと思われます。アナトリアではエリコの人々のチャタルフィックと北部のヴァン湖付近に高地農耕が進みます。ヴァン湖の人々は、気候の激変により北方(ヨーロッパ)から南下してきたと考えられます。 やがて彼らは農耕に最適な環境のメソポタミアに進出し、一方、銅を求めて移動していった人々との間に交易が始まり、それは、めざましい成長を遂げるのです。古代メソポタミアで重宝された石にラピスラズリという石があります。瑠璃色のきれいな石ですが、この石を原産地のアフガニスタン北東部からメソポタミアに運ぶ道が【ラピスラズリの道】と呼ばれています。フェルメールの『真珠の耳飾の少女』の絵画で使われた鮮やかな青、ヒヤシンス・ブルーともいわれる顔料のラピスラズリーです。その【ラピスラズリ】の道は、ラピスラズリのほかにも金・銀といった貴金属が運ばれたようです。この道は、トランス・エラム文明と呼ばれるイラン高原に存在した商人都市の交易ネットワークであり、このネットワークに連なる形でインダス文明や海上ルート上にペルシャ湾岸の古代交易都市が開発されていったようです。この文明は、スーサを首都に置き、メソポタミア文明から穀物を輸入し、東方で採掘した鉱物を輸出していたようです。これを原エラム文明と呼びます。ところが、紀元前27世紀の末、シュメール人の都市国家の一つであるキシュに首都のスーサを奪われてしまい、エラム文明は、首都を奥地のシャハダードに移転します。新しいエラム文明は、メソポタミア文明との交易を続けながらも、新たな穀物の輸入先を求めインダス川流域に、新しい文明を現地人に作らせたと考えられます。事実、メソポタミアの特産品であるクロライト製容器が、インダス川河口付近の湾岸やモエンジョ・ダロ遺跡の下層から見つかっています。このことは、インダス文明成立以前にトランス・エラム文明の商人がインダス川流域を訪れ、交易を行ったことを示唆しています。物資を運ぶには、陸路を通るよりも、河川や海などの水路を使う方が便利です。そのため、やがてトランス・エラム文明は、バーレーン島に進出し、水路ネットワークを活用するようになりました。陸路が衰退することで、インダス文明は最盛期を迎えます。メソポタミアのすぐ近くに興った交易都市スーサ(原エラム文明) → そこからイラン高原の都市シャハダード(トランス・エラム文明) → そして海上のウンム・アン・ナール島(ウンム・アン・ナール文明)へ商人の拠点を移動していきます。 インダス文明は、この商人都市の穀倉地帯としてトランス・エラムの商人によって開発されその際に、現地の原住民、ドラビィダ人を使役したようです。純朴で勤勉な原住民のドラヴィダ人を教育して組織化し、高度な支配体制によってメソポタミアへ輸出する製品ための工房都市として機能させたのがイラン高原一帯に拡がったエラム文明であり、インダス文明だったのではないでしょうか。興味深いのは、エラム文明~インダス文明が繁栄した、この一帯は後々の歴史に、物質的にも精神的にも影響を及ぼしていることです。様々な民族が混在した十字路であり、豊かな河川、水路想像を超える精神性が此処には繁栄していたと感じられます。太陽神・ミトラ・・・シリウス、古代の人々の深い想いに届きたいと思うのです。
2014/03/09
-
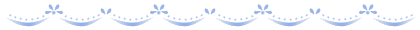
メソポタミア文明以前
メソポタミア文明以前、BC1万8000年頃からBC7000年頃まで、パレスティナを中心に、一つの「文明」が「継続的」に発展してきたことが解かっています。BC7000年に何があったか分かりませんがパレスチナは衰退し文明はアナトリアに移行しここで自然銅の発見により、さらに銅の採集のために人類は世界へ散っていったと考えられます。私が気になるのは、アナトリアでの黒曜石採掘の民族の分布です。アナトリアは黒曜石の原産地ですが、大きく分けて二つあり一つはキズル・イルマク川の南岸のカッパドキア周辺またもう一つは、アナトリア東部のヴァン湖の北岸地帯です。さらに詳しく見ると、カッパドキア系の黒曜石にも二系統ありチフトリックとアシゴルに分かれます。両者は数十キロメートルしか離れていませんがチフトリック産の黒曜石は、キプロス島の南部、死海の南、アナトリアのチャタルフュイック、メルシンなどの地域で発見されていますが、これらの地域では、別の産地の黒曜石と混在しています。チフトリック産の黒曜石は、アナトリアでは余り発見されず、もっぱらイェリコを初めヨルダン川流域で発見されていることから、チフトリックは、イェリコを中心としたパレスティナ系の人々によって開発された可能性が高い。アシゴル産のオブシディアンの分布はチャタルフュイック、およびその西方、ハシラーに至る地域でのみ発見されています。興味深い点は、チャタルフュイックからチフトリック産とアシゴル産の両方の黒曜石が半々発見されていることです。 一方、ヴァン湖系の黒曜石の産地は多数あります。しかし、とくに重要なのはヴァン湖の西岸のネムルト・ダグとスファン・ダグです。これらの黒曜石はチグリス川およびその支流地域を中心に、ユーフラテス川沿岸そしてイラン南西部のスーサ辺りから出土しています。カッパドキア系とヴァン湖系の分布は比較的はっきりと分かれており前者はアナトリア南部からパレスティナにかけての地域後者はチグリス川とユーフラテス川流域が中心です。しかしヴァン湖系の分布は、一部がカッパドキア系の範囲に混在しています。それは、パレスティナとチャタルフュイックを中心としたアナトリアの一部です。この場合、どんな推理ができるのでしょう。 初めて農業に着手したエリコを中心としたパレスティナ人の社会に、次第にライバルが現れるようになったのでしょうか。そこで彼らは、カッパドキアまで出掛けて行き、黒曜石を採取し武装することを余儀なくされた。この段階で、アナトリアへ農業技術が伝わったのでしょうか。パレスティナ文明圏はアナトリアまで範囲を広げ、その中からチャタルフュイックが発展してくる。しかし、やがて、ヴァン湖の黒曜石が開発されるようになる。どうやら、それは、パレスティナ系とは別系統の人種によって行なわれた? 彼らは、だんだんとパレスティナ系を圧倒していった。チャタルフュイックは最初チフトリック産の黒曜石を開発したパレスティナ系の人々が 住み着いたが、後になってアシゴル産の黒曜石の利用者が取って代った。分布の地域性からして、ヴァン湖地域の黒曜石が、ハスナ期以降の北メソポタミアの興隆に密接に関係していたと考えられます。ここで重要なのは、ヴァン湖周辺といえば、我々のルーツウラルトゥ=フツリ人の故地だということです。チャタルフュイックは、BC6850年頃からBC6300年頃まで人間が住み着いていたといいます。自然銅を拾い始めるとすると、川の少ないアナトリア高原よりも、支流の多いチグリス川流域の魅力が増します。この流れで考えると、北メソポタミアに現れたもっとも古い土器文明、ハスナが現在の北イラクのモスル周辺に位置している点が興味深い。原ハスナから発展したと考えられるサマラ期の文明がBC6300年頃からBC6100年頃ですからハスナ期はもう少し古く、チャタルフュイックがまだ存在していた時代に起源を持っていると考えられます。あるいは、ハスナ期には、チャタルフュイックの出店的存在だった北メソポタミアがその後サマラ期になると、なんらかの理由で、本部のチャタルフュイックの勢力が全体として移動してきて、アナトリアを空洞化するとともに、メソポタミア文明の原動力になったのではないか。ェリコからチャタルフュイックへ、そしてメソポタミアへと、文明の継続性は保たれていたのです。そこで農耕をする人々と農耕をしないで採鉱をし運搬をする人々に分かれるのです。採鉱をする人々は遊牧民族となり農耕する人々との交易が始まり海に陸へと商人になって大きく貿易が発展して彼らは移動していったのです。その出発点がアナトリアだったことは間違いないように思います。
2014/02/27
-
古代インド アンコールワットのクメール
インドは地球上で最も歴史の古い地域の1つです。最初に、チベット・ビルマ系の言語グループがインド北部に住み着いたと考えられています。 次にオーストロ=アジア系の言語グループが住み着きました。このグループは後に移動してきたグループに同化され、または山中に追いやられました。この系統とされるクメール民族の文化はカンボジアのアンコール遺跡とされます。クメール族は「日本書紀」に、神武の軍団に大来目がいたと書かれている大来目です。彼らの文化の特徴は、樹木や蛇の文様などで、これらのモチーフはその後の様々なインド・東南アジアの文化に引き継がれて、繰り返し現れています。 次にインドに現れたのが、ドラヴィダ系言語グループです。彼らは地中海沿岸地方からインドに入ってきたと考えられています。ドラヴィダ系言語は今日も北インドのガンジス河の流域に残っています。しかし、今のドラヴィダ人は南インドに集中しています。この事については、後にインドに侵入したといわれるアーリア人に押されて南インドに移動したとか、海路を直接南インドに入り定着したとか、いくつかの説があります。このドラヴィダ系グループがインダス文明の担い手であったと考えられています。 次にインド亜大陸に住み着いたのは、インド=アーリア系グループです。彼らの進出は BC1000年頃ガンジス河の流域に進出して来たと考えられています。彼らはBC3000-2000年頃にロシア南部にいて、BC2000年頃インド系とイラーン系に分裂し、移動を開始しました。気候変動などに影響されて、より生活し易そうな土地に徐々に移り住んだのでしょう。彼らはロシア南部からカスピ海北辺へ、そこから東部イラーンを経てアフガニスタンへ。そしてそこからインド・パンジャブ地方には入り、BC1000年頃、ガンジス流域へと進出しました。そしてその地に農耕社会を出現させました。これにつれて、ドラヴィダ系は徐々に南部に移動しました。アーリア人の最も重要な財産は牛であり、農産物としては大麦の栽培が中心であったようです。
2014/02/12
-
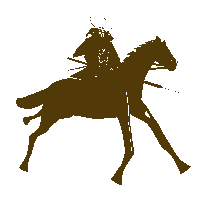
人類と馬との出会い
新年あけまして おめでとうございます。今年も良い年になりますように。 、BC2000年あるいは、その少し以前の時代からギリシャに北方からやってきた人々がいました。彼等はクルガン人と呼ばれています。クルガンというのは、ロシア語で土饅頭という意味です。死者を深い縦坑に埋めその上を土饅頭で覆ったためそう呼ばれるようになったのです。クルガン人はBC3500年からBC2300年頃、南ロシアからダニューブ川流域に住んでいた半遊牧民族です。彼等がBC2300年頃からギリシャ本土へ侵入してきたという説があります。そして彼等は最初のインド・ヨーロッパ族であり、また最初のギリシャ人だと考えられています。クルガン人の到来とともに、ギリシャでも馬の骨が出土するようになりました。彼等は、馬とともに縄文土器もギリシャにもたらしました。 BC2300年頃からギリシャに現れたクルガン人は、どこからやってきたのでしょう。ギリシャに北からやってきたとすると、黒海の西岸を南下してきた以外に考えられない。当時のヨーロッパには原始的な人間を除くとほとんど人が住んでいなかったからです。黒海北岸で発見されているもっとも古い遺跡は、ドニエプル川を少し遡ったデレイフカの遺跡です。スレドニー・ストグ文化に属するこの文化はBC4400年頃からBC3500年頃まで続きました。デレイフカの遺跡から発見されている食料とされたと思われる動物の骨のうち74%が馬の骨で、残りは19%が牛、7%が羊です。中央アジアのステップは、一般に雨が少なく、夏と冬の気温の変化が激しすぎるので農業には向いていない、にもかかわらず、スレドニー・ストグ文化に属する人たちは家畜を伴っていました。クルガン人はBC3500年頃からBC2300年頃まで南ロシアのステップ地帯からダニューブ川沿岸にかけて住んでいたといいますから、スレドニー・ストグ文化に属する人たちの子孫だった可能性が、たいへん高い。スレドニー・ストグ文化人は、BC4400年頃どこからきたのでしょうか。BC4500年頃中央アジアのアラル海のアムダリア河口にも穀物生産と家畜を帯同した人たちが現れています。かなり古い時代から東方、エニセイ川とオビ川の上流、アルタイ山脈の北側に初期的な農業を携えた人たちが遺跡を残しています。この地域は現在でも鉱山地域です。現在のキルギスタン共和国からタジク共和国に掛けての地域と並んで古代の銅鉱山の遺跡が発見されています。人類が 牛に出会ったのは、おそらく数万年前に遡ります。BC7000年あるいは、それより少し後、アナトリア南部のタウラス山脈の麓チャタルフュイックの遺跡では、牛頭信仰の起源と思われる牛の首が壁に掛けてありました。そしてこのチャタルフュイックの住人は、その後BC6000年の半ば頃から徐々にメソポタミアへ進出してウル人となり、そこからさらに、青銅時代に入ったBC3500年以降銅を探して世界に散り今日の世界の多くの民族の祖先になった人々と考えられるのです。それに比べると、人類が馬に出会ったのは、かなり後になります。場所は南ロシアでした。馬の源生地もまたその辺だったと考えられています。最初馬は人間の食料だったらしい。しかし、やがて人は馬に乗り、馬に車を引かせるようになりました。銅の冶金技術の起源は、BC6000年頃北シリアからタウルス山脈の辺りで発明されました。銅は貴重な資源とされましが、大規模農業の最適地メソポタミアには銅はなく銅を求めるためには、遠方まで出かけて行かなければなりませんでした。BC大5世紀の半ば頃、黒海の北岸から遠く遙か東のアルタイ山脈の北方に姿を現した人々はメソポタミアから銅を求めて北へ出かけて行ったウル人たちだと考えられます。その時代は、まだ青銅技術が発明される前です。しかし既に文明の主流を担う人々はBC5200年頃ペルシャ湾の南岸に達していました。 ウルという言葉が中東起源、あるいはメソポタミア起源であることはかなりハッキリしています。スウェーデン語のウルは、絶滅した牛、そして原始的つまり非常に古いという意味があります。スウェーデン人の祖先は、まだメソポタミアに都市国家が誕生する前北方に銅を求めて出かけたウル人ではなかったでしょうか。
2014/01/01
-

人類の進化は西アジア、中央アジアで起こった
ネアンデルタール人は、3万5千年前に姿を消したとされている。しかしながら、中央アジア、西アジアにいた一部は、その血統を現代人の先祖に伝えているようです。ネアンデルタール人の性格を具えていながら現代人の性格も兼ね備えている中間種の骨が発見されたのは、ことごとく中央アジアと西アジアからでした。★ケバラン洞窟で、ネアンデルタール人の成人男子の化石が発見されています。この化石には「モシェ」という愛称がつけられましたが、この化石が発見された層ではムスティエ文化型のフリント石器が発見され、これは6万年前と測定され、このケバランの石器文化は、パレスチナのナトゥーフ文化に引き継がれます。★パレスチナのカルメル山にあるタブーン洞穴で発掘された女性の骨格はネアンデルタール人の身体の上に丸くてずっと現代人的な頭がのっているという明らかに混成的なものであったとされます。 ★北部イラク山岳地帯のシャニダール洞穴では4万5千~4万4千年前の顔の上部全体が現代人的風貌をもつネアンデルタール変種が見つかっています。その近くのスリフル共同墓地から出土したものはネアンデルタール人よりもクロマニヨン人の近接し、また現生人誕生の前夜といえるまで進化したものであったそうです。★中央アジア周辺でも西アジアにあたるアームッド洞穴では頭はネアンデルタール人でありながら、顔はホモ・サピエンスという古いネアンデルタール人と現代人とのつながりを示すものが発見されています。しかもその年代は、4万年より前であるとされています。★クリミヤ半島の突端、スタロセリエ洞窟でも1~2才の子供が埋葬されているのが発見されました。この子供の骨格を研究した結果、現代人の【人間】型に属するが依然として歯の大きなこと、頬骨が太いことなど、多分にネアンデルタール人の特質を残しており、ネアンデルタール人とクロマニヨン人(ホモ・サピエンスの一種)との中間的位置をしめるものとしています。このようにして確かめられた現生人類の祖先はほとんど現在のヨーロッパ人的なものであるから、学者は【ユーロポイド】と名付けました。ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの過渡的な遺骨が見いだされたタブーン洞穴やアームッド洞窟は西アジアで、子供の遺骨を見出した西トルキスタンは中央アジアです。ヨーロッパ人的であるユーロポイドでありながら、過渡期的人骨が発見されたのは、ことごとく中央アジアと西アジアからであって、ヨーロッパからではありませんでした。なぜ、このように、西アジア、中央アジア地域でのみヒトの進化がありえたのでしょうか。それは、この時期、リス氷河期には、この地方では気候が湿潤化し、 広葉樹林、落葉樹林多くの湖や河川、多種多様の食糧源に恵まれ、人類の進化に最も適した地域だからでした。 中央アジア(トルキスタン)は、ユーロポイド(ヨーロッパ人種)とモンゴロイド(モンゴル人種)の2大種が分布した境界領域をなしていますが、古くはトルキスタンの殆んど全域がユーロポイドによって占拠されていて、ユーロポイドの厚い人種的基層が存在しました。そのなかで、シベリアでもネアンデルタール人とホモ・サピエンスの過渡期の型からホモ・サピエンスにまで進化したものが、バイカル湖にそそぐアンガラ川沿岸のマルタで発見されました。これは、現生シノ・モンゴルの骨格に似ていることから、学者は【モンゴロイド】と名付けました。その他、ウラルの東、天山の北にもモンゴロイドを見出し、これは現生トルコ人の骨格に似ていることから、【ツングース的モンゴロイド】と名付けられました。これと区別するためにマルタの人骨を【シノ・シベリア的モンゴロイド】としました。何故ここにも人類のこのような進化が行われたのでしょうか。その時期にあっては、アルタイ山脈、サヤン山脈、ヤブロイ山脈の北面には、未だ氷原がまだらに残って寒気は厳しかったのですが、その南面には樹林が茂り、その下草が萌え温暖であり、その南には湖沼を連ね緑に囲まれた東トルキスタンという盆地があったからでした。したがって、この時期では、東トルキスタンの北壁と東トルキスタン、中央アジア、西アジアは人類進化に絶好な環境に共通する一つの世界をなしていたのでした。この辺りは、後に日本人のルーツにあたる月氏、チュルク、スキタイ・サカなどが躍動した地域でもありました。では、なぜ、他の地域の人類が、この進化に立ち遅れたのでしょうか。シベリアの中央高原が東西を隔離しているオビ河流域は氷原で、これも隔壁になりました。ドン河とドニェプル河の線には未だ氷河が残っていて、それはアルプスに連なる欧州の山脈におよんでいました。その環境がホモ・サピエンスの出現をシベリアの南側・東パキスタン中央アジア・西アジアの広地に限ってしまったのでした。日本列島には、旧石器文化の3万年前から1万4千年前頃に、鋭い黒曜石やサヌカイトの刃物に柄をつけた文化的な工具をもって彼らが渡来しています。この時代の石器はヨーロッパの旧石器文化と共通であって隣国の中国大陸の文化とは似てないといいます。ヨーロッパからやってきて日本列島で誕生した旧石器文化と考えられています。
2013/11/01
-

伊勢神宮 出雲大社 ダブル式遷宮
今年は出雲大社・伊勢神宮の史上初、ダブル式年遷宮。 皇室の氏神である伊勢神宮には謎が多いです。伊勢神宮は元から今の場所にあったわけではなく「太陽神」である「天照大神」は東から西に天を巡る性質があるので太古の「天照大神」は日本各地を巡っていたそうです。それが三重県 伊勢市を最後に動かなくなってしまいました。20年に一度の遷宮は「巡る宮」の名残り、社殿だけ移して「巡った」ことにしてしまおうという策だったのでしょうか。 地球から見た場合、太陽は常に移動をしています。公転によっても自転によっても太陽と地球の関係は変わります。この「太陽は常に動く」ということが太古の学問としてあり、それに合わせるようなかたちで宮は移動をしていたと思われます。そして「旧事本紀」に「天照大神」を祀ったのは伊雑宮が最初であり、皇大神宮の内宮・外宮よりも社格を上にするとハッキリ記述されていたので1681年、皇大神宮の神官は激昂し、「旧事本紀」は発禁、伊雑宮の神官は流罪されました。 これはガド族+神武 VS シメオン族+エブス加羅国の古代史と重なります。 すべては秦始皇帝による焚書坑儒・儒者弾圧に始まります。 BC213年、秦始皇帝に焚書坑儒された孔子・孟子の子孫、ガド族は、燕王公孫氏(南朝系イッサカル族)の一部勢力と連合して移動開始します。BC86年朝鮮半島を南下して対馬に至り天照神社を祀り、対馬から船出して糸島半島へ移動して吉武高木に【旧伊勢国】を建て、金属製造所をつくり鉄鐸・銅鐸文化圏を創始します。猿田彦2世は日代宮を平原王墓(遺跡)に築き八咫鏡ほか神鏡・鉄剣・勾玉などの【三種神器】を奉納しました。BC74年、辰韓(秦韓)にいた秦の 始皇帝の子孫、シメオン族らは、鳥栖と吉野ヶ里の地に委奴国を建てました。 委奴国の王はシメオン族々長の大国主命であり、弟のグループは日本海側の敦賀に上陸して奈良盆地に入り、大和(奈良盆地)にユダヤ人亡命者のコロニーがつくられました。さらに、この時、ユダヤ人亡命者集団の先遺隊は関東地方にまで進出して、利根川河口付近にコロニーをつくったのです。 147年、後漢に圧された高句麗が委奴国および東表国を攻撃しました。当時の東表国(エブス王朝)は、朝鮮半島の金官加羅国とワンセットの文化圏とする海人族の千年続く【天の王朝】で、委奴国は同盟国でした。これより、東表国は、 高句麗と敵対関係になり東アジアの覇権を競う【倭の大乱】が始まりました。 163年、東表国エビス王海部知男命は、シメオン族倭奴国大国主命と連合して高句麗と同盟していたガド族猿田彦らの旧伊勢国を攻撃し、吉武高木・平原遺跡および太陽神殿を破壊して古墳内の超大型青銅鏡を悉く破砕しました。 大国主命に神聖な神殿を壊され、旧伊勢国(筑紫国)を奪われた猿田彦5世らは二手に分かれて亡命移動しましたが、その一隊は、日本海沿いに北上して山陰地方の島根県に至り、同族ガド族の先遺隊であった牛頭天王(スサノオノ命)のガド族とイッサカル族の連合移民団リーダー【出雲王朝】へ参入しました。次に、別働隊の遺民は瀬戸内海を東遷する途中、海沿いの各地には、旧伊勢国遺民の一部ずつ割いてコロニーを作り、香川県の森広遺跡・奈良県三輪山の日代宮遺跡・大阪府の利倉遺跡と池上遺跡に鉄鐸・銅鐸遺跡を残し、周防灘の徳山湾(遠石八幡宮の地)にコロニーを作り、楊井水道の大畠瀬戸に至り、旧伊勢の日代宮(御神体は八咫鏡)を遷社して柳井市に【天照神社】を建てました。瀬戸の浜辺に【磯の神】を祀る石上神社を建て、その元宮として旧い周芳神社(柳井市日積の諏訪神社)が再建されましたが、この天照大神(内宮)の神霊は、のちに志摩半島の伊雑宮(伊佐和宮)に遷社されています。中国・四国・近畿にやって来て各地に彼らのコロニーを作り、さらに紀州・熊野に移動して伊国を建て、志摩半島に移動して新伊勢国(伊雑宮・伊勢神宮の元宮)を建てました。奈良大和にも約1300人が移動して鮭文化圏を整え、東テイ国(纏向遺跡が中心)を建てています。ガド族と連合していたイッサカル族は、三輪山を中心に定着しました。筑紫の三輪(福岡県朝倉郡三輪町)から移ってきた三輪氏などであり、彼らが祭祀を担いました。なお、纏向の太田地区などには大田氏系の先祖も居住しました。連合していたゼブルン族は、葛城などに定着しました(葛城氏など)5代目猿田彦の弟の系列が建国した東テイ国(奈良)と地方との交通・交易の状況は、東テイ国(当時の奈良盆地・鮭文化の国)の出土品によって東海・北陸・山陰・河内・吉備・関東・近江・瀬戸内海・播磨・紀伊と交易がされていたことが解っています。東テイ国は鉄鐸・銅鐸文化で、水と火の祭りが三輪山を中心に行われていました。三輪山は、縄文・弥生時代から旧い御神体で、本殿がありません。縄文港川人や弥生苗族人の蛇信仰に彩られた【鉄と水稲】文化を育む聖山です。 しかし、これらガド族の神殿は、のちに神武勢力に敗れ、亡命・東遷した時シメオン族によって、徹底的に破壊されました。210年、扶余王ケイ須(神武)が南下を始め、九州博多に上陸して橋頭堡を築きました。橋頭堡を守るためと、約50年前(163年)に旧伊勢国を追われたガド族猿田彦らの仇を討つため、大国主命(シメオン族)たちの委奴国を攻めました。神武らに敗れたシメオン族の土師氏らは博多湾志賀島から乗船して出雲へ逃れ、先住していた猿田彦らのガド族及びイッサカル族を駆逐して新しい出雲王朝を建てました。土師氏らは新しい四本柱の大社を建て、その祭神を大国主命とし、併せて八百万の神々(ユダヤ12部族の神々+倭王たちの氏神)を祀りました。熊野山中には100キロメートルにも及ぶ石垣が存在しますが、これはガド族がシメオン族との戦いに備えて築いたものです。やがて秦王国の人々と東表国の人々は相協力して古周芳国および古周芳の石上神社(楊井水道)の領域を占領し、秦王国の分国【周芳国】を作りました。この時、周芳神社(柳井市日積・諏訪神社)の【たたえ祭り】 神事が猿田彦の亡命と共に、縄文人たちの故郷・信濃の諏訪神社へと伝承されそれが今日まで伝わる長野県諏訪神社の【たたえ祭り】になります。伊勢神宮は日本中央構造線の真上に建てられています。このゼロ地盤は地下から磁場、磁気が出ています。人間の身体が70%鉄分ということから、パワースポットに行くと磁化され パワーを頂けるようです。
2013/06/18
-

世界最古の王朝
日本の天皇家は世界最古の輝かしい歴史を持つ王朝です。オリエントでアッシリア帝国と覇を争い、キンメリ人と連合してシルクロードを東遷したウラルトゥ王朝の末裔であり、後に扶余王となって満州の地に君臨し、ソロモンとシバの女王の子、メネリケの子孫である大物主一族(公孫氏)と同盟して邪馬壱国を建て、さらに百済国を建てました。この陸・南海シルクロードを駆けた壮大な歴史は、【記紀】によって抹殺され、忘却されてしまったのは残念なことです。扶余には、月氏+ウラルトゥ王朝のシルクロード系の前期王朝とインド経由の穢国・南海系の後期王朝がありました。共に製鉄部族です。箕子朝鮮が滅亡した後、南海系穢族の王アグリイサトは扶余前期王朝に合流しやがて穢族は強力になり扶余後期王朝になり、東明王と称しました。そのため、月氏+ウラルトゥ王朝のシルクロード系の前期王朝は、・エゾの地へ移動し東扶余を建て、その子孫に仇台が出て九州に渡来して神武天皇になりました。残念ですが天皇家は万世一系とは言い難く、幾つもの民族の歴史をつないできたものでした。 天の王朝(東表国・豊日国・金官加羅国) BC800年頃、タルシシ船でコーサラ国を経て九州に東表国(オッフルの植民地)を建てた日本最古の王朝。エビス王クルタシロス(首露王)のエビス王朝ですがクルタはタルシシ船支配者の意味。エビスはエレサレムのエブス人です。エブス人もオッフル人(現ソマリア)も紅海とアラビア海の海人でした。のち邪馬壱国に敗れるまで、九州全域を1000年間支配し、譲った後、朝鮮半島の弁辰地域の金海を飛地として支配し駕洛国・金官加羅といわれ、その王家は金氏と中臣氏になりました。この王家は【記紀】では孝昭、孝安、孝霊、孝元、開花とつづき、後の倭の五王に至ります。この王家から金氏が分離して【新羅】をたてます。ニギハヤヒの多羅王朝この一族は、かつてディルムンを本拠としたシュメール人とカルデラ人の子孫でした。後にソロモンのタルシシ船に参加したヒッタイトの製鉄カーストをも吸収し、アラビア海のヤードゥ族を従えてプール国をたて、ガンジス河口のコーサラ、マガダ両国のシャキイ族となってマレー半島を越え、モン族の地を支配し、ベトナムに文郎国をたて、後に河南省の宛に製鉄コロニーをつくって魏と韓に属していましたが後に、秦に追われて奇子朝鮮をたより、穢国をたてました。穢国王アグリナロシは奇子朝鮮を滅ぼした衛氏朝鮮に復讐するため漢に協力しましたが漢は衛氏を滅ぼすと奇子朝鮮を再興させず、楽浪、玄メンの二群にしてしまい欺かれたアグリナロシは自刃したため、その子アグリイサシは遼東太守を殺害して北扶余前期王朝と合体し、その庶子が王位を奪って北扶余後期王朝をたて東明王と称しました。穢国の王族はシャカ族で国民はチュルク族でした。ニギハヤヒの姓、余の「アグリ」はドラヴィダ族の一派というゴードン族のなかのサブカーストのアガリアという鉄工部族をさします。そして、この一族後期王朝の陝父(ニギハヤヒ)が南下して熊本に多婆羅国をたて後に、神武・卑弥呼の邪馬壱国に吸収されました。 【ウラルトゥの歴史】 カッシート人がウラルトゥ地方に侵入する前から、アナトリアには原ヒッタイト族、カルトヴェリ族ハヤシャ族などが住んでいました。フツリ人はエジプトやカナンから、この地に拡散してきたのですが、ヒッタイト資料は、この地方を【フツリ人の国】と記しています。フツリ人は、BC2000年紀半ばには、ミタンニ王国に従事し、ヒッタイト王シュビルリウマシュ以降はヒッタイト王国に従属していました。ヒッタイト崩壊後、いくつかの少国家がヒッタイトの伝統を継ぎ、重要都市のカルケミシュはハッティ国、オロンテスはハッテナ国となりました。そこに、ヒッタイトのムシュ族やカスカイ族が入ってきたのです。このようにウラルトゥは、当初からミタンニやヒッタイトのフツリ人、カッシート人チュルク人などからなる、いくつかの部族の連合体でありました。カッシート人は月氏になりインドに移ってクル国のなかにも混在しました。従ってウラルトゥとクル国は同族であり従属した同盟者といえるでしょう。約3000年前に、フェニキア人とヒッタイト人の混血によって、ウラルトゥ人が生まれました。この時、ウラルトゥ人によって小アジア(トルコ)のヴァン湖周辺に建国されたのがウラルトゥ王国であり、その初代王となったのが、アマテラス(男神)です。BC1013年、イシンの末期に、フェニキア人のマカン(海の国)がウラルトゥと共にアッシリアと戦いました。その結果、アッシリア王の攻撃でイシン(殷の本国)が滅んだため、番韓のヤードゥは海に浮かんでインドに逃れ、ウラルトゥは、北方ヴァン湖に退き、シャキイ族は、南下して後の穢国になりました。この時、カルデア人は、アッシリア軍に捕らえられていたイシン王族の子叔箕しゃ(ししゅきしゃ)を奪い返し、遥々航海して渤海湾に至り、遼東半島に上陸してその地に国を建て、【奇子朝鮮】と名付けました。BC781年、ウラルトゥ王アルギシュティシュ1世=ウガヤ王朝初代・衰子餘よ(すいしよ)または申侯が、アッシリア王を破ります。同じ頃、ドーソン(銅鼓)文化の拡散始まります。インド太陽王朝のマラ族と月神王朝の連合軍が銅鼓文化を持ってジャワ島、バリー島セレベス島などに入りました。アッシリアを滅ぼしてから300余年を経てBC6、5世紀になるとウラルトゥは二分して匈奴(キンメリ)と連合するものと、ペルシア(秦)に従属するものとになりました。秦は、この後、益々強くなり燕(フェニキア)も強化されたので、奇子朝鮮は、ついに満州に移って大凌河を国境とし河西の地を譲って東遷しました。神武以下の扶余の百済王朝朱蒙は東扶余(北扶余前期王朝)に追われて、北扶余後期王朝(穢国)の陜父らと共に卒本に逃れて高句麗をたて、北扶余を奪って高句麗国をたてました。このために陜父らは九州に亡命し多婆羅国をたてるのです。扶余王家は、167年頃、夫台が高句麗と戦い、その子仇台は、高句麗と和解し高句麗の養子になりその王族と化してケイ須といいました。後に自立し、公孫氏と同盟して、その宗女を娶り、公孫度は逆に扶余の王女を娶りました。公孫氏が南下して帯方郡をたてるとケイ須もその地に至って伯済国をたてた後に百済王仇首といいました。この仇首が伊都国王イワレヒコ・神武であり、その妃、卑弥呼は公孫度の宗女で日向にいました。高句麗は新大王の長子、発岐が公孫氏と同盟し涓奴部を率いて遼東に都したため、三子、延優らは輯安に移って新国をたてました。後に魏によって公孫氏が滅亡した時、発岐一族の旧国は新国に合流しました。扶余王家は仇台、位居、麻余と続き、依慮はその末王であり、百済の近肖古王になって鮮卑の慕容カイに討たれて亡命南下し、伊都国の王、祟神になりました。
2013/06/12
-
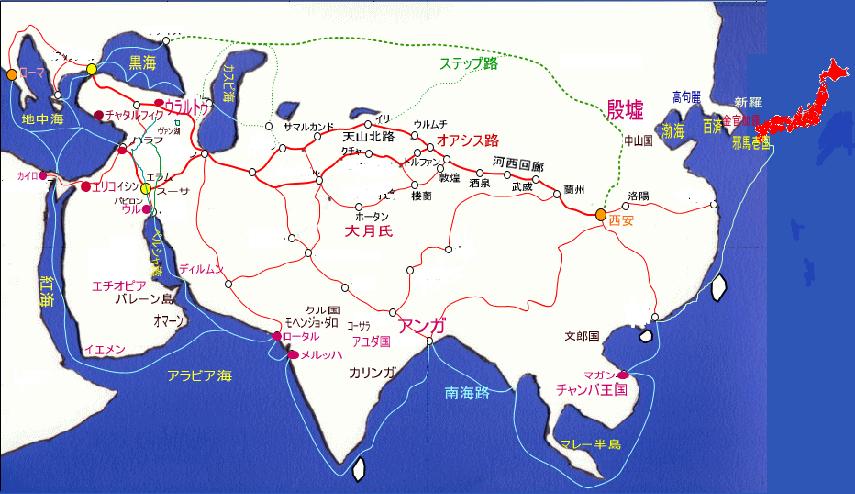
金官加羅
日本最古の王朝、【天の王朝】とは、インド十六王朝の日神系のことです。【東表・豊日国】のことで、朝鮮の狗邪韓国(駕洛国・金官加羅)を飛地としていました。即ち、この王家は北九州を本国として朝鮮半島の弁辰地域を飛地として支配したのです。【東表国】とは元来、東方のオッフル(サマリア)国を表します。サマリアのオッフル国の植民市、九州の豊国、朝鮮南部、金官加羅でありました。東表国の王はエビス王の【クルタシロス】といい、金官加羅の首露王のことですが【クルタシロス】とは、タルシシ船を意味し、【シロス】は、治政者、王を意味しソロモンの製鉄コロニーでありました。ソロモンの父、ダビデが建国した当時エルサレムを支配していたエブス人は、エジプトから撤退した、かつてのヒクソスでヒクソスになる以前はアビシニアでした。アビシニアとは元来【混血者】の意味で日本のエビス(エミシ・夷)もアビシニアの意味です。BC8、7世紀にアビシニア(エブス)人と現在のソマリアにいたオッフル人の植民地が北九州東部の豊国地方の東表国で、駕洛国または金官加羅国にも飛地したのです。金官加羅の王姓は金氏、または中臣氏です。奈勿王の時に独立して新羅を建てその子孫が蘇我氏になります。北宋版【通典】は倭国王師升(しろす)の国を【倭面土国】とし、『釈日本紀解題』は これを【倭面国】としています。 【北倭記】と【桓檀古記】を総合しますと『箕子朝鮮が亡びたとき、その上将卓が馬韓に逃れて、辰韓の王となった。後に東表国(倭面国)エビス王クルタシロスから鳥栖河と背振山脈の間の地を譲られた』箕子朝鮮の上将卓が帯方(月支)に辰国を建て、秦の亡命者(イスラエルの南朝ユダの人々)は、慶州に馬韓の分国をたて辰韓と称しました。この時、箕子朝鮮系の馬韓人に従って渡来した倭人が【北倭】でした。北倭と秦の亡命者は、エビス王から鳥栖河と背振山脈の間の地吉野ヶ里を譲られ倭奴国(秦王国)としますが後に神武と公孫氏に破れ、出雲経由で大和地方に【秦王国】を建てます。鴨緑江の流域に前方後円型古墳の原型が発見されましたが、これは箕子朝鮮の古墳になります。馬韓人に領土を与えたという【東表国王クルタシロス】が【倭面土国王師升】のことです。 このシロス王は駕洛史では金官国の【首露王】になっていますし、新羅史では金氏の祖の首留日本史では孝元天皇になっています。インド史を整理すると、BC1000年にインドは十六王朝の時代となりカッシュ人を中心とする月神王朝とアラビア海の海商を中心とする日神王朝系に分かれていました。BC1500年頃~1200年頃、エブス人たちの海人は、レバノンのアルワドからインドのロータルに移住し、デリーを経てマガダ近くまで移動し、インド十六ヶ国時代、コーサラ国アンガ国などの日神王朝諸国になりました。日神系のなかにはアンガ、コーサラ、マツラなどの諸国がありましたが、アンガ国はソロモン王のタルシシ船の移民の地でありコーサラ国はフェニキアのアルワド人の植民市であり、マツラ国はアラビア海のメルッハ人の国家でした。釈迦は、コーサラ国のなかの王族でした。駕洛国の王は、金首露で、王妃はアウド国の女【許氏】で、【許】がアウド国の別名コーサラを指します。皇統譜のなかの孝昭孝安の実体は東表国、即ち駕洛国の王でした。この人々が天の王朝で、白村江の戦いの後に彼らが賎民化されて【八の民】となるのですが、これはボルネオの八河の民ということで【山海経】では八匹の蛇になっています。記紀神話では八岐の大蛇。マガダの都は、ガヤというところにあって、中国人は、これを加耶と書くのですが、朝鮮半島にできた、そのマガダの人々のコロニーが加羅になります。チャンバをたてたチャム人のコロニーは、ベトナム南部の林邑国に始まってボルネオの八河地帯のバンジェルマシン(耶馬堤国)、それから公孫氏の燕国につながり九州の日向と南朝鮮の咸安になって、ともにアンガ人、チャム人、または安羅人になります。ボルネオのダワヤク族を経由したアッサムのボド族が我が国の山窩になります。ニギハヤヒ命というのは、カーシ国の鉄カーストの王です。オリエントのウルという海商国家が初めで、インド十六王朝の時代にウルのカルデア人やマラ族などの古代の海人たちがガンジス流域でカーシ国という海商国家をたてました。それがマレー半島を経て河南省の宛に入ってきて【宛の徐】氏といわれました。この人々は魏と同盟した製鉄部族ですが、魏が秦に伐たれたため、満州に逃れて穢国をたてました。これがニギハヤヒ王朝です。穢国の王姓はアグリ(余)というのですが扶余、百済もそうです。天皇家も、そういうことになります。中国史では堕羅国とか吐火羅と書きますが、後に河南省南陽の宛という所に移動しさらに朝鮮で穢国をたて、扶余と合体して、その涓奴部(けんぬべ)になった後、熊本と南朝鮮に多羅国または多婆羅国というコロニーをたてています。多羅は多羅加羅とも多婆羅ともいいますが【タタラ(製鉄部族)ノガヤ】ということです。ドヴァラヴァティの王家はサカ族で人民はモン族ですがモン族は、またの名をタライン族といいます。漢字で書けば多羅殷(夷)です。熊本に田原坂があります。♪ 雨は降る降る人馬は濡れる。越すに越されぬ田原坂 ♪ という唄がありますがこの地方には製鉄遺跡がありますから、田原というのは田んぼではなくタタラのことだったのです。【隋書】の阿毎氏というのは、このチャム人のことですが、元来インド洋の海民でもありこの人々がインドシナ、インドネシア、ボルネオなどに基地を持ちました。後にボルネオのバンジャルマシンに倭寇の基地があったのですがここは耶馬堤国で天の王朝の基地でありました。朴・昔・金の人々は、高句麗の故国川王が沖縄を支配しようとして、発岐と同盟したことに抵抗し、後に大隈から日向に侵入し、邪馬壱国を攻伐しました。新羅王家の紋章は【三つ巴】ですが、沖縄の尚王家の紋章も同じ【三つ巴】で朴昔金を表します。高句麗の紋章が【ニつ巴】なのは、昔氏が神武と一緒に九州に渡来してしまったからです。
2013/06/12
-
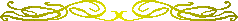
北倭 南倭
数万年前まで日本列島は中国大陸とつながっていてシベリヤのバイカル湖あたりから古モンゴロイドと呼ばれる人々が今の日本列島の地へと移ってきて、一万年近く続いた縄文時代の担い手になりました。彼ら古モンゴロイドの言葉がアイヌ語にわずかに残り、それはそのまま韓語にも通じるといいます。むしろ韓国語のほうが日本語よりアイヌ語に近いといえます。(日本語) (アイヌ語) (韓語) 神 Kamui カム、コム川 nai ネ寒い chamusi チュブまたアイヌ語はネイティブアメリカンの言葉にも近いとされます。ユーラシアの北方にはアジアからヨーロッパまで坦々としたステップ地帯が連なっています。狩猟民族はマンモスや鹿を追いかけてユーラシア大陸を抜けて北東のシベリアへ進み、さらに南北アメリカに渡たりました。温暖の時は北方へ、厳寒になると南下して陸続きの日本列島にも渡って来ました。約一万年前に大陸の端っこの陸地が海面上昇のために分断され日本列島が出現しました。朝鮮半島と日本列島をつないだのは船でした。半島からイカダを出せば海流に乗って簡単に列島に流れ着いてしまうのです。韓国・釜山市にある東山洞貝塚は5千年前の朝鮮半島と日本列島の絆の地でした。そこからは九州産と見られる縄文土器や有田の黒曜石などが出土しています。一方、対馬や九州北部の遺跡からは当時の朝鮮半島産の土器が出土しています。釜山市辺りは昔、金官加羅国があった所で、砂鉄を生産し周辺諸国と鉄貿易が盛んでした。 金官加羅は、九州の国東半島に本国があり、釜山はその出先機関もしくは植民地でありました。これを【面土国】といったのは【九州は四面あり】というように、四面土国を省略した言い方で九州国というほどの意味でした。九州北東部にあった東表国(豊国)の倭人は【南倭】といわれ、日本の天皇家(南朝)はこの国家の王家とは直接の関係はありませんが、史書のうえでは、東表国の王が孝昭から開化までの天皇(北朝)になっています。ところで、【晋書】は【卑弥呼は宣帝の平げる公孫氏なり】と述べます。原文は、【漢末倭人乱攻伐不定。乃立女子為王。名日卑弥呼。宣帝之平公孫氏也......】この卑弥呼が、記紀では事代主命の娘、神武妃ヒメタタライスズになっているのですが記紀は大物主の軍団に【大來目】がいたと記しますから、遼東の公孫氏にはクメール人(古コメル族)またはその支派の瓦族がいたことは間違いなくこの時、満洲と朝鮮に残留したクメール人または北倭が、後に扶余王依羅(崇神)が倭の地に逃れたあとで、唐に敗れた高句麗人を収容して渤海国をたてさらに外蒙古では蒙瓦室韋となり、後に蒙古族になりました。ですから、ジンギス汗はもともと北倭の王だったのです。 南倭もまたBC1000年頃、ガンジス河口から採鉱のために、タルシシ船に乗って九州にやって来たエビス族の一派でした。国東半島の重藤遺跡によれば、彼らがこの地に上陸してトーテツ文の土器や青銅器を作り、これを殷に運び、また盛んに砂鉄を採って製鉄を行っていたことが判ります。 【北倭記】は国東の倭国を【東表国】として【殷(箕子朝鮮)と姻たり】とするのですが、後にこの国は面土国といい、駕洛国といい、金官加羅ともいったのです。この金官加羅の王族から分れたのが新羅の金氏であり、後の蘇我氏になります。穢国の(扶余後期王朝)の王、ニギハヤヒは熊本にあった多婆羅国の王で、これが後に新羅の昔氏になりました。また沖縄の狗奴国の王・南解次々雄または長髄彦は新羅の朴氏になりました。神武天皇は実は扶余(前期王朝)王、仇台(神武)のことで扶余と公孫氏が連合して、多羅婆国を併せて邪馬壱国を作ったのです。なので日本史で倭人と云うのは、大別して、九州の金官加羅国の【南倭】と公孫氏の分国であった邪馬壱国の【北倭】を指します。このうちの【南倭】が朝鮮半島南部の駕洛地方に展開していたのでした。東表国または金官加羅国の王家は箕子朝鮮のカルディア人と対婚したアラビア海の海人で、インドのガヤに中間基地があったらしい。この人々はBC1000年頃、ソロモン王のタルシシ船でマレー海域から北上して、北九州の国東半島で製鉄基地を築いたのですが、タルシシ船にはヒッタイトの鉱人がいて、ハットウサの地名によって宇佐八幡と名付けられました。この国の人民は猪族と南倭で、南倭の方はカーシ族の信仰を維持していました。宇佐の原神はバンコとトウビョウであったといいますが、バンコは猪族の犬神信仰でしたしトウビョウはもともとカーシ族のトウレンという蛇神信仰でした。 【旧唐書】は倭国と日本国を別の国として扱って『倭国は古の倭奴国である...-四面に小島、五十余国あり。その王は阿毎氏であった。一大率を置いて諸国を検察し、みなこれに畏付する--・・衣服の制はすこぶる新羅に類する』と述べていますが、【新羅に類する】というのは当然で、新羅は面土国または金官加羅国から分れた国だったからです。【四面に小島がある】というのは、いにしえの九州を四面といったからです。ここで委奴国(秦王国)というのは九州北東部にあった面土国の金官加羅国が馬韓に領土を分けて作らせた国で、後に邪馬壱国に征服されて秦人は去り、邪馬壱国のなかの奴国になります。邪馬壱国は福岡の伊都国、吉野ヶ里の倭奴国(奴国)、熊本の多婆羅国、日向の安羅国などの連合国家であって、この内、多羅婆国の王がニギハヤヒでしたが、王姓を阿毎氏といいました。記紀は『神武が十種神宝とともにこの姓をニギハヤヒから貰った』と書いています。
2013/06/08
-

人類移動経路
ミトコンドリアDNAは、母親からのみ伝えられY染色体は、父親からのみ伝えられるといいます。この二種の遺伝子は、混ざり合うことなく次世代へと変化することなく受け継がれるため私たちの祖先を遡り、最初の哺乳類、それ以前のものにまで辿っていけるのだといいます。このようにして一つは父方、一つは母方の遺伝子の二つの系統樹をつくることができます。すると、この男系、女系の遺伝子系統樹は、それぞれ、ただ一つの系統がアフリカからやってきたことを示しているといいます。私たちにつながる出アフリカは、たった一度しか成功しなかったということです。その前に、アフリカを出て行った先人類たちは、死に絶えてしまったといわれています。 男系、女系とも、ただ一つの共通の遺伝子上の祖先をもち、それぞれ世界すべての父となり、母となったのだといいます。 女系のミトコンドリアから調べると、この成功した南ルートの少数をイヴ一族としています。イヴはやがて二人の娘からそれぞれ女系一族をつくりました。一つはM、もう一つをN、Nは、ヨーロッパ人の唯一の母になりました。Mはアジア人のなかだけにみられます。南アラビアとパルチスタン沿岸にMとNの根源と早期の分枝がみつかっていてただ一度の出アフリカ移動が、まず南アジアへ進んで行ったことの証になっています。イヴ一族は、インド洋沿岸を周って東南アジアやオーストラリアへ突き進んでいきました。彼らはヨーロッパが殖民されるよりずっと以前の6万年以上前にはオーストラリアへ到着していました。オーストラリアの母系各族とマレー半島の先住民の遺伝子を調べるとMとNのDNAに属しているといいます。Nの子孫は温暖期に入った5万1000年以上前、インド湾岸からザグロス山脈の中腹に沿って中央アジア~肥沃な三日月地帯~トルコを通って、最初の南からの最古のヨーロッパ進出を行いました。一方、イブの連れ合い男系の遺伝子標識名をM168と呼びます。ユーラシアのアダム、今日生きているすべての非アフリカ系男性の父になります。M168の集団の一部がユーラシア南部からオーストラリアへの旅に出発した後に、まだアフリカに留まっていた集団の中に、45,000年前頃、M89という遺伝子の変異を持つ男系が出現します。このM89の子孫が現生人類で初めて中東方面に入植した痕跡を残します。東へと移動を始めたM89の系統に、40,000年前ごろ、イランか中央アジア南部の平原の辺りで、もうひとつの遺伝子マーカーが出現し、M9と名づけられ、このM9の子孫は、以後3万年間に亘って地球の果てまでその領域を拡大することになる現生人類の主要な系統です。このM9というマーカーを持っている人々をユーラシア族と呼びます。このユーラシア族が、さらに東へ、内陸部に進もうとしたとき、これまでの移動で初めての、最も深刻な障壁に遭遇します。それは中央アジア南部の山岳地帯でした。天山山脈やヒマラヤ山脈は標高7千メートルにもなって立ちはだかり、彼らは二つの集団に分かれるはめになったようです。 タジキスタンあたりで南に向かったM20マーカーの一族と(インド定住派) ヒンズークシ山脈の北へと移動し、中央アジアへ向かった集団です。 35,000年前頃になると中央アジアで、ユーラシア族にもう一つの突然変異が起こりました。 M45の出現です。ポーロと名付けられた、このM45こそ東と西にT字型に分かれて、広大なステップを移動した人々です。東はシベリアのバイカル湖、そしてずっと後にはアメリカまで、西はヨーロッパへ。男系M45の連れ合いはヨーロッパの母系Nの子孫エウロペの五番目の娘U5。彼らは、パレオ・ユーロペオイド的(白人)だったと考えられます。彼らは、新石器時代の後期、BC3000年紀の初めにかけて、南シベリアのイェニセイ河上流とアルタイ地方に、アフナシェバ文化を起こし、西シベリアのソンスク地方にBC1750年~1200年の間分布したアンドロノヴォ文化という青銅文化につながり、さらにBC2000年紀末南シベリアのカラスク文化 と中央アジア北部のダザバギャプ文化につながります。 カラスク文化は、殷の青銅文化と同様に、西アジアに発達した金属文化の東方流入によって発達したといわれます。M45が派生したと同じ頃、テンシャン山脈の北側に沿って移動しジュンガル盆地を利用して現在の中国にたどり着いたグループがいました。大半のユーラシア族が侵入をあきらめたルートです。このジュンガル盆地は、後にジンギス・カンが中央アジアを侵略するのに利用したルートで、この盆地は、中国やモンゴルから中央アジアへの抜け道になっているのでしょう。このグループは、西アジアとヨーロッパには全く見られないY染色体マーカーM175の子孫を残しました。M175の系統は、その後ヒンズークシ山脈とヒマラヤ山脈より東に住むアジア人の大多数を占めるほど大いに繁栄し、東アジア族と定義されます。しかもこのM175の分岐時期、35,000年前という時期は、まさに日本列島に【最初の日本人】が出現した時期と一致しているのです。日本列島には、旧石器文化の3万年前から1万4千年前頃に、鋭い黒曜石やサヌカイトの刃物に柄をつけた文化的な工具をもって彼らが渡来しています。この時代の石器はヨーロッパの旧石器文化と共通であって隣国の中国大陸の文化とは似てないといいます。ヨーロッパからやってきて日本列島で誕生した旧石器文化と考えられています
2013/05/05
-

アーリア人
カテゴリ:カテゴリ未分類 ネアンデルタール人とクロマニヨン人との混血で中央アジアで発生したものがヨーロッパ人の骨格と似ていることから、これを【ユーロポイド】といいます。 おそらく後のアーリア族であったと考えられます。日本人のルーツにはアーリア人も関係しています。アーリア人は、どのように形成されていったのでしょう? 中央アジア(トルキスタン)は、ユーロポイドとモンゴロイドの二大人種の分布した地域の境界領域をなしていました。古くはトルキスタンの殆んど全域がユーロポイドによって占拠されていて、ユーロポイドの厚い人種的基層が存在しました。中央アジアのアジア的ユーロポイドは、新石器時代の直前にはすでにインド的ユーロポイドとイラン的ユーロポイドに分化しています。イラン的ユーロポイドは、パミールの西方、アラル海の東方という中央アジアにいました。パミールの東のタリム、アラシャン、ゴビ、オルドス、中央アジアは砂漠化しましたが彼らは新石器時代に入って、農耕、家畜の飼育と銅器文化やがて、青銅器文化を開花させ始めました。さて、中央アジア以前には、彼らは、どこにいたのでしょう。これは私の推測です。 氷期の終わりの約1万2千年前頃に温暖化していくなかで急激な戻り寒冷期がありました。ヤンガー・ドライアスと呼ばれている現象です。中近東ではこの時の寒冷化によって採取できる食物が減りそれを補うために農業技術が進歩したと考えられています。 最初に農業が開始されたのは、12500~10200年前に存在した地中海東部のナトゥフ文化といわれるパレスチナのエリコでした。 さらにエリコの人々はアナトリアのチャタルフュィックで自然銅を発見しその銅を加工する高温技術を発明したとされます。アナトリアではエリコの人々のチャタルフィックと北部のヴァン湖付近に高地農耕が進みます。ヴァン湖の人々は、気候の激変により北方(ヨーロッパ)から南下してきたと考えられます。 やがて彼らは農耕に最適な環境のメソポタミアに進出し一方、銅を求めて移動していった人々との間に交易が始まりそれは、めざましい成長を遂げるのです。メソポタミア北方の山地を廻る肥沃なる三角州を極めて早期に占領したのはナトゥフ文化の流れを汲む地中海人種ののエリコの人々でした。 長頭型の地中海人種はさらにスーサに於ける早期の住民を形成しインダス文明に先行する時期に北部インドを占領しました。アナトリア北部ヴァン湖付近にいたアルメノイドは地中海人種にやや遅れてスーサやインドへ進入しました。シュメール、ハッティ、ミタンニ、フルリ、エラムなどがアルメノイドに属し、彩陶文化の担い手でした。したがって肥沃なる三角州文明は早期から長頭型の地中海人種と高短頭型のアルメノイドの混血された人種によって形成されスーサでは最古のスメリア文明でした。アルメノイドのフルリ人は、後のアーリア=印欧語族になったと考えられます。エラムには数多くのフルリ人が関与していた記録が残されており、 ヒッタイト帝国と交流があった事が分かっています。フルリ人は、メソポタミアのシュメールとアッカドからアナトリアとヒッタイト王国までの間の広いエリアを支配していました。フルリが、アーリア人かインド・ヨーロッパ語族起源であったと考えられます。エラム各地にフルリ人が移住しており、エラムの諸都市にはフルリ人の王を頂く都市が多数出ていて彼らの王たちはインド・ヨーロッパ語族の名前をもっていました。そして、彼らの軍隊と騎兵用語は、インド・ヨーロッパ語族から生じています。フルリ人は、文化的、宗教的にヒッタイト人に影響を与え、ヒッタイトの神話が、フルリに由来することも解ってきました。紀元前1300年、大規模な移住と侵略の圧力の中で、フルリは自らの王国の北東の部分へ退き、バン湖の近くで彼らの新しい首都を創出して、彼らの王国をウルアルトゥ(アララト)と呼びました。スキタイ・サカ族とは、約6000年前、今のトルクメニア地方に興ったナマヅカ文化という彩文土器文化の担い手で、牧畜と農耕を営む遊牧民のルーツともいうべき複合民族でした。ナマヅカ彩文土器文化が熟成期を迎えた頃、アムダリヤ上流のバタフシャン産ラピスラズリを商い、羊トーテムのサカ族と牛トーテムの月氏の隊商が、馬や船などによって旅を続けバビロンの【スサ】から【ウル】に入りました。彼らは後に、壇君教団グループと番韓(海の国交易商人・マカン人)の主力となりました。彼らはユーロポイドと考えられます。 やがて、ナマヅカの彩文土器文化は、サカ族によって東西に運ばれ、イラン高原に於ける【プロト・エラム文化】に大きな影響を与えました。ラピスラズリが、ハラッパ文化以前のコト・デイジ遺跡から発見されていることからサカ族がインダス文明の原形をつくっていたことが分かっています。またイラン高原文化を受容したナマヅカ文化が黄河流域のヤンシャオ文化あるいはカラスク文化となりました。約5100年前には、イエニセイ河上流とアルタイ地方にアフナシェヴァ文化と呼ばれる青銅器文明が起こりました。この文化の担い手はクルガン人でしたが、その高塚墳墓の板石には、カラスク文化と中国のトーテツ文様に似た【鷹と人面像】が刻まれていて、クルガン人は、すでに車輪付き馬車を使用していました。 彼らはコーカサス地方に侵入して黒海に進み、インド・ゲルマン的特徴の混合文化が生まれ、このアーリア人こそ、後にインド・ヨーロッパ語族となった人々 とおもわれます。同じ頃、小麦が、ドナウ河流域とライン河流域、および黒海の西海岸一帯と南ロシア全域に広がり、5000年前頃には、小麦からパンを作る文化が、ヨーロッパ全域を覆いました。クルガンとは、日本列島や朝鮮半島に見られる古墳と同種と考えられます。この古墳文化は、アジアからアナトリア、東ヨーロッパ~スカンジナビア半島までユーラシア大陸全体にありました。同様にインド・ヨーロッパ言語もユーラシアからヨーロッパにかけて広がっています。即ち、クルガンを建設し、人々がインド・ヨーロッパ語族のルーツであると考えられます。
2013/05/01
-

女系社会から男系支配へ
中東は、アジア、ヨーロッパおよびアフリカの三大大陸が結合する地球上でも珍しい地域です。それに紅海で裂かれたアラビア・プレートが、アジア大陸に衝突し、ザクロス山脈をつくっているところです。1億年以上前、そこは浅い海でした。海の底の藻類やバクテリアの死骸がゆっくりと沈み、地下奥深く堆積しました。そして、地熱の働きによって、石油へと変成したのです。その中東の資源は昔も今も多くの人々を惹きつけています。それは、初期の農耕によって生み出されました。 では、農耕はどのようにして始まったのでしょうか。ナイル川の畔に文明が誕生したのは、気象変化のためだったと考えられています。昔々、北アフリカは、今よりはるかに温潤で植物が多かった。最初に農業が開始されたのは、12500~10200年前に存在した地中海東部のナトゥフ文化といわれるパレスチナのエリコでした。 さらにエリコの人々はアナトリアのチャタルフュィックで自然銅を発見しその銅を加工する高温技術を発明したと思われます。特筆すべきは、アナトリアの女系性です。壁画、漆喰浮き彫り、石の彫刻、粘土製のおびただしい【女神】小象、すべて女性崇拝の品々が発掘されています。この現象は、おそらくエリコからすでにあり、6000年頃にはアナトリアから農業の伝播とともにメソポタミア、コーカサス南方、カスピ海南方、それまでは辺境であった地域にまた一方では南ヨーロッパへと拡大し始めます。この地母神は、クレタ島やキプロスにも海路によりつながっていったのです。【大いなる女神】が、ときに鳥の姿になったり蛇の【女神】になったりしながら、水の生命授与力を支配し、ヨーロッパとアナトリアでは雨を孕み、乳を与える、そういう文様が刻まれています。アナトリアのチャタルフユィックの遺跡からは、母系で妻方居住の社会構造が現れました。その構造は、チャタルフユィックからクレタに移住し、太古地母神《女神》と共に農業技術をもたらし、つづく四千年の間に、土器製作、織物、治金、彫版、建築、その他の技能およびクレタ独特の生々とした喜びに満ちた芸術様式の進歩がありました。そこでは富は、公平に共有されました。年上の女性ないし氏族の長が大地の実りの生産と配分をつかさどり、実りは集団の全員に属するものとみられていました。主要な生産手段の共有と、社会的権力は、すべての人の利益になるよう図られ、責任のもとに基本的に共同的な社会組織が生まれていました。これは、パレスチナの世界最古の町エリコナトゥフの人々が成功していた共同社会につながると思われます。太古地母神《女神》を中心に女も男も異なった人種の人々も・・・共通の幸福のために平等に協力して働いていました。母系による相続と家系、至高の神としての女性、現世的権力をもった女司祭と女王の存在はありましたが男性の地位が低いということはなく、両性は平等な協調関係を築いていました。男女仲良く手に手をとった姿は、今でも道祖神のなかに見受けられます。彼らは、たいへん自然に親しんでいて、アニミズム(精霊崇拝)はクレタだけでなく、ケルト民族にも伝わりました。太古地母神《女神》を中心にした文化はアナトリアを中核として地球一周しました。ストーンサークルやドルメン、メンヒルなど、これらの祭祀が彼らの残した足跡です。しかし、その女神崇拝文化も侵略され滅亡される時がやってきました。 最初、それは家畜の群の草を求めて彷徨う一見取るに足りない遊牧民の集団にすぎませんでした。数千年以上も、どうやら彼らは地球の端の誰も望まぬような厳しく寒く痩せたシベリアに住んでいました。その遊牧の集団が長い期間をかけて数と獰猛さを増しヨーロッパ北東からヨーロッパ大陸に群がり南下し侵略してきたのです。彼らは最初のインド・ヨーロッパ語族あるいはアーリア人といわれるクルガン人。あるクルガンの野営地では、女性住民のおおかたはクルガン人でなく、新石器時代の太古地母神《女神》崇拝の人々であったことが発掘資料から判明しています。このことが暗示しているのは、クルガン人が、その土地の男性や子供たちの大部分を虐殺し、女性たちのある者だけを助けて妻や奴隷にしたということです。遺跡から農機具のみで武器というものが見あたらない【平和】で【民主主義】な社会が営まれた《女神》崇拝社会が破壊され、男性的支配社会の始まりでした。インド・ヨーロッパ語族は、先の文明を築いていた太古地母神《女神》を崇拝する農耕民族を次々侵略していったのです。インドに於けるアーリア人、【肥沃な三日月地帯】に於けるヒッタイト人とミタンニ人アナトリアに於けるルヴィ人、東ヨーロッパに於けるクルガン人、ギリシアに於けるアカイア人および後のドーリア人、彼らは征服した土地や先住民の上に次第に自分達のイデオロギーと生き方を押し付けていったのです。このほかにも侵略者はいました。ヘブライ人と呼んでいるセム系の人々です。
2013/04/30
-

人類の進化は西アジア、中央アジアで起こった
★ケバラン洞窟で、ネアンデルタール人の成人男子の化石が発見されています。この化石には「モシェ」という愛称がつけられましたが、この化石が発見された層ではムスティエ文化型のフリント石器が発見され、これは6万年前と測定され、このケバランの石器文化は、パレスチナのナトゥーフ文化に引き継がれます。★パレスチナのカルメル山にあるタブーン洞穴で発掘された女性の骨格はネアンデルタール人の身体の上に丸くてずっと現代人的な頭がのっているという明らかに混成的なものであったとされます。 ★北部イラク山岳地帯のシャニダール洞穴では4万5千~4万4千年前の顔の上部全体が現代人的風貌をもつネアンデルタール変種が見つかっています。その近くのスリフル共同墓地から出土したものはネアンデルタール人よりもクロマニヨン人の近接し、また現生人誕生の前夜といえるまで進化したものであったそうです。★中央アジア周辺でも西アジアにあたるアームッド洞穴では頭はネアンデルタール人でありながら、顔はホモ・サピエンスという古いネアンデルタール人と現代人とのつながりを示すものが発見されています。しかもその年代は、4万年より前であるとされています。★クリミヤ半島の突端、スタロセリエ洞窟でも1~2才の子供が埋葬されているのが発見されました。この子供の骨格を研究した結果、現代人の【人間】型に属するが依然として歯の大きなこと、頬骨が太いことなど、多分にネアンデルタール人の特質を残しており、ネアンデルタール人とクロマニヨン人(ホモ・サピエンスの一種)との中間的位置をしめるものとしています。このようにして確かめられた現生人類の祖先はほとんど現在のヨーロッパ人的なものであるから、学者は【ユーロポイド】と名付けました。ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの過渡的な遺骨が見いだされたタブーン洞穴やアームッド洞窟は西アジアで、子供の遺骨を見出した西トルキスタンは中央アジアです。ヨーロッパ人的であるユーロポイドでありながら、過渡期的人骨が発見されたのは、ことごとく中央アジアと西アジアからであって、ヨーロッパからではありませんでした。なぜ、このように、西アジア、中央アジア地域でのみヒトの進化がありえたのでしょうか。それは、この時期、リス氷河期には、この地方では気候が湿潤化し、 広葉樹林、落葉樹林多くの湖や河川、多種多様の食糧源に恵まれ、人類の進化に最も適した地域だからでした。中央アジア(トルキスタン)は、ユーロポイド(ヨーロッパ人種)とモンゴロイド(モンゴル人種)の二大種が分布した境界領域をなしていますが、古くはトルキスタンの殆んど全域がユーロポイドによって占拠されていて、ユーロポイドの厚い人種的基層が存在しました。そのなかで、シベリアでもネアンデルタール人とホモ・サピエンスの過渡期の型からホモ・サピエンスにまで進化したものが、バイカル湖にそそぐアンガラ川沿岸のマルタで発見されました。これは、現生シノ・モンゴルの骨格に似ていることから、学者は【モンゴロイド】と名付けました。その他、ウラルの東、天山の北にもモンゴロイドを見出し、これは現生トルコ人の骨格に似ていることから、【ツングース的モンゴロイド】と名付けられました。これと区別するためにマルタの人骨を【シノ・シベリア的モンゴロイド】としました。何故ここにも人類のこのような進化が行われたのでしょうか。その時期にあっては、アルタイ山脈、サヤン山脈、ヤブロイ山脈の北面には、未だ氷原がまだらに残って寒気は厳しかったのですが、その南面には樹林が茂り、その下草が萌え温暖であり、その南には湖沼を連ね緑に囲まれた東トルキスタンという盆地があったからでした。したがって、この時期では、東トルキスタンの北壁と東トルキスタン、中央アジア、西アジアは人類進化に絶好な環境に共通する一つの世界をなしていたのでした。この辺りは、後に日本人のルーツにあたる月氏、チュルク、スキタイ・サカなどが躍動した地域でもありました。では、なぜ、他の地域の人類が、この進化に立ち遅れたのでしょうか。シベリアの中央高原が東西を隔離しているオビ河流域は氷原で、これも隔壁になりました。ドン河とドニェプル河の線には未だ氷河が残っていて、それはアルプスに連なる欧州の山脈におよんでいました。その環境がホモ・サピエンスの出現をシベリアの南側・東パキスタン中央アジア・西アジアの広地に限ってしまったのでした。日本列島には、旧石器文化の3万年前から1万4千年前頃に、鋭い黒曜石やサヌカイトの刃物に柄をつけた文化的な工具をもって彼らが渡来しています。この時代の石器はヨーロッパの旧石器文化と共通であって隣国の中国大陸の文化とは似てないといいます。ヨーロッパからやってきて日本列島で誕生した旧石器文化と考えられています。漢民族の祖型と、日本民族の祖型は、途中から別々の道を選択したのです。
2013/04/22
-

シュメール以前
中東地域に現れた最初の人間と考えられるケバラン人が姿を現すのがBC1万8000年頃。 それは、ヨ-ロッパの氷河期の最盛期に当たっていました。ヨ-ロッパは氷河期に一度ほとんど無人化した可能性があります。寒冷化から逃げなければならなかった彼らの行き先は南にしかありませんでした。彼らケバラン人は、中東、パレスチナに現れその後の文明の主流になりました。約1万5000年前、地球の温暖化が始まり、不毛の砂漠だったシリアの北部に草原や森林が広がりました。新しく出現したシリアの環境は、木ノ実や小動物など豊富な食糧を供給し、周辺の狩猟採取民族が、ハルーラという場所で定着生活に入ります。しかし、約1万1000年前に、地球的規模の寒気の揺り戻しがありました。シリア北部の自然環境は、もはやかっての生産性豊かなものではなくなり人類史上最初の定着生活を始めていた人々は、人口の増加をもたらし、そこへ突如襲った環境の激変と、それに伴う食糧の減少は村落の住人を窮地に追い込んだに違いありません。しかし彼らは、未曾有の困難に敢然と立ち向かったらしい。この時代の地層の考古学的発掘が興味深い事実を発見しました。約150種類の植物の種が発見されたのです。中には、クローバーの種など、とうてい食用に耐えない植物の種も含まれていました。明らかに彼らは、危機に直面して、ありとあらゆる可能性を探ったとおもわれます。彼らにとって幸いだったのは、その中に小麦が含まれていたことです。小麦は比較的寒さに強い。さらに現代の専門家の研究によって、小麦の驚くべき性質が明かになりました。野性の小麦は、たった10年程度の繰返し栽培でも、その性質を見る見る変え粒が大きくなり殻は柔らかくなって、食用に適したものになったのです。この小麦の変幻自在の性質が、その後の文明の発展に決定的な影響を与えました。しかし、初期の農業村落のほとんどは、大きな規模の町に発展する前に消えていきました。初期農業村落の幼児死亡率は高かったのです。BC1万1000年頃、中東に現れたナトウフ人は、ケバラン人の系譜につながります。世界最古の農業は、BC1万年より少し下がった頃、カルメル山の周辺に溯ります。エリコの町は天然のオアシスで、エリシャの泉は、遊牧民たちの水飲み場でした。人が集まりやすい場所だったのです。エリコの最初の住民ナトウフ人が、北西のカルメル山の山麓からやって来たと考えられています。その周辺には、現在の大麦や小麦の先祖の野生種が自生していて、最初は、野生の麦を動物の骨の柄に石の刃を埋め込んだ原始的な鎌で採取し始めたと思われます。農業は通常の採取経済に比べて50倍もの生産性をもつといいます。カルメル山からエリコへ移り、農業を始めたナトウフの人々は、共存共栄の元に平等に暮らし生産性を高めましたから幼児死亡率を減らし2000人ほどにも人口を増やしました。エリコの最初の文明は約1000年続きました。しかし、農業が安定し、穀物を貯蔵し、エリコが繁栄し豊かになると外敵が出現し、城壁を造らなくては、ならなくなったと思われます。ナトウフの人々は、アナトリアへ、武器を探しにいったようです。黒曜石です。その時に、農業技術の情報もアナトリアへ、流れたと考えられます。しかしBC7000年頃、その文明は急に終わります。新しい人たちがやって来たのです。エリコとともに、パレスチナのいくつかの地点が同じ運命を辿りました。侵入は、かなりの規模で行われたのでしょう。新しい侵入者は北シリアからやって来たと考えられています。この人々は、アナトリア方面から入って来たらしい。エリコのそれまでの円形の家は方形の家にとって代わりました。その方形の家の床の壁は、磨かれた「しっくい」で覆われていました。この方形で磨かれたしっくいの床の家という、かなり特徴のある家がアナトリアのチャタルフュイックの遺跡で発見されています。黒曜石の原産地は、アナトリアですが、大きく分けて二つあり一つはカッパドキア周辺、もう一つは、ヴァン湖の北岸地帯にありました。カッパドキア系とヴァン湖系の分布は比較的はっきりと分かれており前者はアナトリア南部からパレスティナにかけての地域、後者はチグリス川とユーフラテス川流域が中心になります。しかしヴァン湖系の分布は、一部がカッパドキア系の範囲(パレスティナとチャタルフュイック)を中心としたアナトリアの一部)に混在しています。一方、ヴァン湖系の黒曜石の産地は多数あり、チグリス川およびその支流地域を中心にユーフラテス川沿岸そしてイラン南西部のスーサ辺りから出土しています。と、いうことは、パレスチナ(カナン)のエリコの人々の地域にヴァン湖系が侵略し範囲を拡げたということです。そのヴァン湖系の人々が、アルメノイドだと思われます。ハッティ・ミタンニ・フッリ族などと共にエラム族もアルメノイドに組み込まれます。BC5100年から4300年までにバビロニア北部でハラフ文化が展開しました。この文化の特徴は彩文土器、銅、円形のトロス(祠堂)、押捺印章などで【分業】がはじまり、金属細工人、陶工、石工が生まれ、銅鉱石が交易されて、農村の自給経済を変容させました。この頃から銅鉱石を採集してハラフ農民と交換した人々が後にセム族特にアッカド人として歴史に現れます。北部にハラフ文化が展開しつつあった時、バビロニア南部ではエリドゥ期で沼沢地に農耕社会が形成されました。シュメール人が現れる1000年も前のことです。エラム族は、インドのドラヴィダ族と共に、地中海からインダスに至る広範囲な地域を移動し、その一部はアルメノイドと混じりながらシュメール人となってBC3500年頃、ウバイド人がいたバビロンの地に侵入しました。「史記」の伏犠氏は、この人々です。アルメノイドとは、アナトリア東部のヴァン湖の北岸地帯にいた人々です。それは、黒曜石の分布図で現在も解析できるようです。黒曜石は、火山性ガラスでナイフなど鋭利な刃として、中東では銅化合物に取って代られるまで使われました。地中海人種は、シリアからペルシア湾に至るメソポタミア北方の山地を廻る肥沃なる三角州を極めて早期に占領し、スサに於ける早期の住民を形成しました。肥沃なる三角州文明は、早期から長頭型の地中海人種と高短頭型のアルメノイドの混血人種によって形成され最も古いスメリア文明が発生していたのでした。私は、地中海人種をパレスチナのエリコから来た人々、アルメノイドをバン湖付近にいた人々と考えます。彼ら混血したスメル人(シュメール・ウル人牛頭)は、四方に散り、小アジア(トルコ)、メソポタミア文明、クレタ文明、インド文明、エジプト文明にも共通の文化を及ぼしました。彼らが中央アジアのトルキスタンに現れた最古のユーロポイドと考えられます。
2013/03/29
-

スキタイ・サカ族 金属文化
日本民族の祖型は中国の史家によって三つの名前で呼ばれています。古くヒマラヤを下り四川に出たものは【荊蠻けいばん】さらにシナ海沿岸に達したものは【東夷】または【准夷】青海から陜西に入り、前2千年紀に黄河のデルタ地帯に進出したものは【戎狄】とされます。シュメール、ハッティ、ミタンニ、フルリ、エラム などがアルメノイドに属し彩陶文化の担い手でした。前1世紀に彩陶文化の道をオルドス→山西→冀北→遼東→北朝鮮へと移動したものは【東胡】とされます。そのなかで、とくに満州、ことに東満、南満に定着したものを【扶余】といいます。この【扶余】こそが、実は弥生日本期の列島植民の主役となるのです。 タリム、アラジャン、オルドス、甘粛、陜西にとどまって、前8世紀の【前期綏遠青銅器文化】につづき、鉄器文化をその金属文化に加えたもの、所謂、前4世紀以降の【後期綏遠金属文化】を出現させたものは、イラン系トハリ=月氏でした。アルタイの西部にいたのはウスン(鳥孫)です。前2千年紀のヴォルガ川上流、ウラル西南の樹林草原綴接地帯で栄えた青銅器文化のアバシェヴォ文化、そしてウラル山脈中央西部カマ川のセイム・テュルビノ文化はともにウラル語族の白人文化でした。そして、オビ川、イルティッシュ川、イェニセイ川上流のそれぞれ、アファナシェヴォ文化現在のアチンスク市を中心とするアンドロノヴォ文化、またカラスク文化としたものはいすれもイラン・ツングース、またはイラン・チュラン系文化でした。これが後に鉄器文化につながります。それは、ずっと後、前5世紀から前4世紀以降にしぼると、カラスク文化は鉄を含めたタガルスキー文化に吸収され、アンドロノヴォ文化はアルタイ西部に新しくおこったマイエミルスカヤ金属文化に吸収されほぼ二つの大金属文化地帯を形成するにいたっています。そうなった理由として、一つには鉄鉱・銅鉱という資源の関係であり二つにはイラン民族の選択にもとづく通婚・共棲によるものでした。アルタイ西部とパミールの資源を手中におさめたイラン種は、通婚・共棲の相手として東胡系を選んでいます。このイラン種はミヌシンスクのアファナシェヴォから出たスキタイを源流とするイラン種です。彼らは・シベリア南部、ミヌシンスク盆地からエニセイ川を下りアチンスク、トムスク、ノヴォシビルスク、セミパラチンスクを経てアルタイ山脈北麓を迂回しオビ川上流イルティッシュの流域に乗り換え、こうしてアルタイ山脈の西南部にマイエミルスカヤ文化をつくって、アンドロノヴォ文化を吸収したのです。彼らは七河地方セミレチェからジュンガリア廻廊を通って東トルキスタンに入り、パミールの金属資源を掌握し、タジク、ウズベク、ソクドとの部族連合をつくりました。この支配部族を【サカ】といいます。前8世紀から前3世紀までのことです。
2013/03/17
-

ウラルトゥ王朝
皇紀元年は西暦紀元前660年、神武天皇即位してから今年で2670年ということでしょうか。しかし、2670年前には、日本という国も神武天皇も未だ生まれていませんでした。その頃の日本人のルーツは、遙か遠く中央アジアのアララト山を見上げる高原地帯であるヴァン湖周辺のビバイナという名の小さな国にありました。当時、オリエント周辺にあった数多くの種族国家が過酷なアッシリアの圧政下に喘いでいました。彼らは、BC1200年の昔に滅んだ人類史上初の【鉄の帝国】ヒッタイトの人民の主流を形成していたフルリ人や、ヒッタイト帝国東部辺境にいてヒッタイト化していたハッティ人と同種族であり、帝国滅亡後の同朋難民でした。 その周辺部から、製鉄の業を会得した新しい勢力が幾つか台頭し、その一つがアララト山を聖地とし、ヴァン湖周辺を根城に勢力を延ばしていたグループでした。ビバイナ国の初代の王は、アラメと言う名でした。彼は即位して国土を掌握するやいなや、自ら太陽女神アラメアであると自己主張し当時のオリエント世界の支配者であるアッシリア帝国に真っ向から抵抗しながら自らの小王国ビバイナを、そしてやがて名実ともに帝国となってアッシリアが名付けたウラルトウを建国していくことになります。ウラルトゥは、その当初からミタンニ人やヒッタイト人のフツリ人、カッシュ人、チュルク人から成る、幾つかの部族の連合体でした。アルメニア高地には、古くから原ヒッタイト族、カルトヴェリ族、ハヤシャ族などが住んでいました。そこへフツリ人がエジプトやカナーンの地から流入して来たのですがヒッタイトの資料はこの地方をフツリ人の国と記しています。フツリ人は、BC2000年の半ばには、アーリア人の国であるミタンニ王国に従属しシュッビルウマシュ王以降は、ヒッタイト国に従属するようになったといいます。ヒッタイト崩壊の後、幾つかの小国家がヒッタイトの伝統を継ぎカルケミシュはハッティ国、オロンテスはハッティナ国と名乗りました。そこにヒッタイトのムシュキ族やカスカイ族などが入ってきたのです。最初、貧しい山岳地域の小国にすぎなかったビバイナは、滅亡したヒッタイト帝国の製鉄技術者達を、何らかのきっかけで多人数取り込むことに成功し、同朋難民を吸収してふくれ上がっていったと考えられます。彼らはやがて大帝国アッシリアの言うことを聞かなくなり反撃してくるアッシリア軍の討伐を避けて、国ぐるみで山奥を延々と逃げ回ったようです。 ヴァン湖周辺のナイリの諸国、更に小アジア寄りにあったハイーク諸国や西方の森の国ムサシルなどを次々と併呑し、やがて失われたイシン帝国の祭儀と意志を受け継ぐウラルトウ帝国として、急速に勃興していったのです。なぜイシン帝国かといいますと、このウラルトゥの人々は、後期イシン王朝末裔になるからです。遡ることBC1018年、後期イシン王朝滅亡後、幾つかの小国家に分かれビト・アデイニ王国とラケーの人々は、エラム王朝を倒した後、東方の支配を目的としシルクロードによってバルハシ湖に注ぐイリ河に進み黄金の眠るイシク・クルに箕子国を建国します。イシク古墳から発掘された【黄金人間】といわれる黄金の衣を着た16~18歳の少年被葬者こそ箕子国の王でありました。彼の黄金の上衣はアルタイの金山から採った金塊で作られ、副葬品はバクトリアの扶余から届けられたものでした。後に、この地域を支配したウイグル人は、日本の平安時代の王族とまったく同じ風俗をもっていましたが、両者は共に箕子国の文化を受け継ぐ韓人王朝でした。
2013/02/15
全687件 (687件中 1-50件目)
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- 楽天ブックス
- 今日、誰のために生きる?
- (2024-10-31 16:55:10)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 荒川農園で親父殿と対面、さらに驚き…
- (2024-11-01 07:06:38)
-