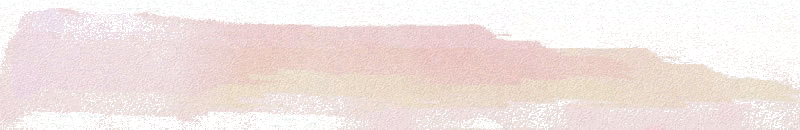サンカの人々 ぶらんこ
この原稿は岐阜県の教育家であった三宅武夫氏が、少年時代(明治時代)におけるサンカとの出会いを
回想したものです。サンカという人々の生き方が少年の目にはどう映ったのか、
また何を学ぶことができるか貴重な記録です。
手書き私家版として発行されたものより活字化しました。
韆(ぶらんこ) 三宅武夫
【風の草の団子杉】は古木である。
すぐ南に一寸した湖沼があって秋にもなると渡り鳥が翼を休めていた。
この古木の下に藤原と名乗る夫婦が娘を連れて毎年五月から十一月迄いた。
団子杉の夫婦はこの荷車の様な一輪車に一切のものを乗せて、押さずに引っぱって
韋駄天走りに走ってどこかに行った。小母さんの向うには娘と犬を乗せて平均をとったのは珍しい。
■初めに
私は明智(注 岐阜県恵那郡明智町)在に生れた。明治卅六年暮のことだ。そこには“山窩”とよばれる人々が毎年五月から十一月まで、同じ時期に同じ所に渡って来ては住みついていたものだ。私が接したのは、鳳の草部落に住んだ藤原某の一家で、夫婦と娘一人の小屋である。
彼等には「生活」があり、「教育」があった。
生活=生命=いのち、いきる力、ねがい。教育=共育=足場をそろえたソダチ方。然し、この一家は間もなく一般人の中に入っていく(トケコミ)直前の人達だった。これは何度でも、人に語ったことだが、書いたことがないので、思いついて「書いてみる」ことにした。今度いつか浄書する時の素稿のつもりである。私一人が感心していても、外の人は、どう思うかも知らないが、私の最も尊敬する先輩野村芳兵衛先生が、褒めてくれたことのある説だということだけは言い添えておきたい。
昭和四十八年七月一日
■ 鞦韆(ぶらんこ遊び・・・・・)
ぶらんこ は 只の遊びである。その遊びに今誰が本気になって取り組んでくれるか。今日教育の危機を言うものは多いが、子供と共に育つことを忘れて押し付け教育をし、人間を数に換算して、その不合理を思わず、かつて我もされた教育の形を先ず離れようとしてくれる先生は滅多にいない。
昭和五十又一年九月廿一日記
■ 親と子のぶらんこ遊び第一稿本
時は明治四十四年九月の末つ方。所は恵那郡明智城北東、大学鳳の草。団子杉の梅。
事は、ここに国籍不明の日本人夫婦とその娘の三人が、この木の根っこに住っており、私共とは全く異質の生活をしていたが、私共に分からん言葉を半分以上は混ぜて使って「竹細工」を渡世にしていた。村方を廻って歩いては、米麦、味噌醤油に、物々交換をしているといったふうだ。彼らのことを私共は、村人と共に、少し怖れながら、然しいつも興味深くみつめていた。彼等は、五月半には、いつの間にか来ており、昨年、冬前に截っておいていった竹を器用に剥いでこれを身辺用の諸家具に編み上げたり削ったり焼いたりして磨いて艶の出た様々な竹細工を持って一軒一軒訪ね歩いていた。私共は、彼らを「ポンス」とか、ポンスケとかいって、大分「軽蔑した気持ち」を含めて呼んでいたし、疎外しようとしていた。
私共が何となく彼等を怖れていたのには理由がある。
第一は彼らの国籍が分からん。第二は言葉が違う。第三は生活様式が違う。決して嘘を言わないし、器用だし、早いし、何も言うことはないのだが、どうも違和感が先に立って溶け合わなかった。それにもう一つ、ばかに足が早い。・・・・何するか分からんと思えたのである。顔形も、私共のように田舎臭くないし、所々分からん部分を除いては言葉だって上方風な上品なものだったし、着物も、いつも洗濯をして小ざっぱりしており、ちっともおかしくはなかった。小父さんは、いが栗頭で、大抵鉢巻をしていたが黒い髪で白い歯で、するどい眼で結構いかす男だった。盲縞の木綿の着物で角帯をきりっとしめていた。そのふところが、いつもふくらんでいたのは“うめがい”という「山刀」が胸に抱かれているからだと皆は言っていた。帯は角帯だが、そいつは小父さんが自分で織ったやつだということだった。滅多にものを言わないし、笑わない。只誰かに食べ物をもらって「ありがとさんどす」という時の笑顔が何とも可愛かった。
一人娘だったせいもあろうが私よりも四つ五つ年下と思われる女の子をとても可愛がっていた。が、何か教えたり、何か採ったりする時は、見ている私共が怖い程に真剣だったし、そのことが出来るまでは、いくらその娘が涙をこぼしても、べそをかいても道端に座り込んでしまっても決してゆるさない。「しっかりしなはれ・・・・・」と小母さんは言う。「おーっそーがい奴っちゃぞ。あいつら・・・・・」私共は、そういって遠く離れて、然し一生懸命に見ていたものだった。小母さんは、綺麗な人で「笹の家」(明智の料亭)の芸者なんかより「背が高いだけでもよっぽど美人だ」と、私共は思っていた。それに声がいい。「あんさん。ほんやんボンでっしゃろ・・・」と顎を少し右前に出して、にっこり笑ってくれたりすると、うちの叔母様達なんか、とても「かなん」と思ってみていた。
ごはんの炊き方が、家のとは、ずいぶん変わっている。「鳳の草湖」の水で米をとぐのだが白い濁り水が出なくなると「フランネル」のような大巾の布に包んで水を切る。小母さんは、竹筒の端をとがらせて先をこがしたものを使って、器用に穴を掘る。二尺四方位の穴を、ほんに美しく手早く四角に掘ると、その底に頭位の大きさの平石を並べる。ついでに上手に四方の立壁部分にも、それを並べると「ぬれ蓆」をその中に拡げて今の米包みを、その上にそっと据える。私共の掌位の石を米包みの周囲に無造作に放り込むと先に敷いたぬれ蓆(むしろ)の片はしりを折り込むようにして、それで米包みを包んで、又その上に、小石、平石を並べる。枯れた杉の葉をとって来て、枯れ木の組上げられた下に、差し込む。器用に切火(かたい石と金とを切るように打つ)をして、火をたきつける。薪は、いつも、その五つ六つになったばかりの可愛い娘の仕事になっている風だった。娘は「団子杉」の根元の窪みに積んである薪を抱えてくるが、いつも同じ位だったから、一回の「めしたき分」が決まっていたのかもしれない。「おらよりゃ、えらいぞ・・・・・」と利君が感心する。何というのか分からん、地ごとの知れん歌を唄って、火壺の中の石ころを手返しなどしていると、突然どこかの端に「スウーッ」と音がして湯気がたつ。小母さんが見ていて、すぐ娘に何か言いつける。娘は立って小屋の隅っこの湯桶(直径二尺、高さ二尺位)に水を汲み入れる。小母さんが火に焼けて少し透明に近く、紅くなった石を竹で造った。「もの挟み」で、竹のこげる匂いをさせながら、一つ宛、湯桶の水の中に放り込む。ジュ、ジュボーッと、水柱をあげながら石は湯桶の底に沈む。娘が手を入れながら湯加減をみているが「もういいよ」と声をあげる。小母さんは黙って、スノコの前に行って食事の用意をはじめる。娘は小母さんの脚元に、しゃがみ込んで着物をぬぐと、今沸かした湯桶に入って「風呂」をすます。小父さんが、どこからか戻って来ると何かボソボソとものを言って、すぐ、持って来た檜の枝をふところから出した山刀(うめがい)で「たらたら」と払う。実にそれは、よく切れる。音もたてずに、流れるように、枝は足元に、お行儀に並んで落ちる。山刀をふところに収めると、すぐ小父さんは、今、払い落とした檜の枝を一尺位の長さに折って揃えてしまう。あの軟らかい檜葉が生きていて、小父さんの言うことをきいて「自分で並ぶみたい」に見えるから不思議だ。小父さんは「火壺」の傍らにいくと赤く焼けた石を一方に寄せて、その上で尚、火を焚きつづけ長柄火壺の石を全部、そちらに移して、さて、初めに埋めた、ぬれ蓆を引き出す。さあっと湯気が立つと、それは大分熱いらしく、時々自分の耳朶をきゅっと、つまんだりしながら中の米包みを太い竹箸で引き出すと、それを小母さんに渡す為に「竹すのこ」の上に持っていってやる。両手をのばして腰を引いて・・・・・ もう、辺りには、いかにも美味しそうな炊き立てのご飯の香りが、たちこめる。小父さんは、さっき枝を払った檜の五六尺もある、一寸丸太程のを立てて左手にもつと懐からお馴染みの山刀を引き出して眼にも止まらぬ速さで一尺余りの揃いの寸法に切ってしまう。上手な為か、器用な為か、その檜はバタッ バタッ バタッと、足もとの小石の並んだ上に頭を揃えて横になる。いきなり、一番初めに切り落とした「一つだ」を左手に拍子をつけてもつと小石の上に立てる。右手が小刻みに、たんたんたんと低い音をたてて、動く。それだけで神社の屋根の檜板の様に、薄い板になって小父さんの左膝の前に並べられて重なる。次の一つだを左手にすると、すぐ右手が動いて機械で割ったように揃った板になって並ぶ。一本の一寸径檜は、ほんのちょっとの間にそれぞれ五枚板位に割れて合計三〇枚位のものが、喜んで飛び上がってくるように、そこに並ぶ。見ていて面白い・・・・・
小母さんがさっきから焼いていた石亀の中身をヤットコのような道具で引き抜くのが見える。白い「ひよこの丸ゆで」といったような形のものが、あの甲の中に入っていたことが分かる。「石亀って平たい身ではなしに、少し細長いな」と感心してみていると、小父さんは、すぐその甲羅を受け取って横向きに立てると、また山刀を「たんっ」と、打ちおろす。“がばっ”といった音を立て、亀の甲羅は、腹と背と二つに割れる。腹の方は平たくて、背の方は丸く掌の様に曲がっている。甲羅の中側は、一寸した「垣根」の様な形の境が出っぱっているが、それをついでに山刀がさらさらと欠きとっていく。ついでに小父さんが手元にあった檜の先の方の皮を削ると、その太い方をきれいに丸める。なんとも器用なもので、見る間にすりこ木が出来る。何とも感心するばかりである。炊きたての御飯を、この亀甲の背の窪みに入れると、その皮をむいた先の丸くなった棒は「すりこ木」になって小母さんの左掌に支えられたまま、廻る様に動くと右手の「すりこ木」は、ぐいぐいぐい、と上下に動いて見る間に、炊きたての御飯は餅の様につぶされる。小父さんは、その餅飯の一甲分をすぐさっきの檜の平板の画面に塗りつけ、押し付けて丁度神官のしゃくの様な形のものをつくる。火壺の回りに川原砂の様な砂が入れられていて、その串が刺される頃、娘が側に来て上手に手返しをする。小母さんが次の亀の甲に入れた御飯の一杯を練り上げる。小父さんが串にくっつける。娘が焼く。見る間に十五、六本の「しゃく」は、出来上がって一列に並んで立つ。小父さんが、すっとそこに立ち上がったのは、その小屋の屋根裏の巻藁から串さしの「変なもの」を取って来るためだった。小さな壺から、すくい出した、味噌と醤油のたれを別の器に練り上げながら、今、巻藁から抜き取ったカラカラのものを、さっき御飯を練り上げていた、亀の甲羅の中で、ボキ、ボキッと小さい音をたてさせながら、すり潰して、味噌と醤油のたれに練り上げ、作りあげる。小母さんは、左の小指につけて一寸なめてみる・・・・・。さっき巻藁から外したのは、どうやら「蛇」や「蛙」の骨らしい。「ごとむし」もいる。これは後になって小母さんから聞いたのだが「松の実」「落花生」「胡麻」「餌胡麻」時には「二ッケ」もすり込むのだそうだ。蛇や蛙は捕った時、その場で大抵そのまま食ってしまうが何匹も捕れた時、焼いて串にさして、巻藁にさしておくと「一年でも味は変わらんですよって・・・・・」と言っていた。こうして三人がかりで、あまりものは言わずに手際よく夕飯の支度は、出来ていく。親子三人の座席は、いつもきまっている。火壺は、私共の家でいえば「囲炉裏」である。中央正面の台石に藁製の円座のあるのが小父さん。二つ飛んで小母さん。また二つ飛んで娘。そして二つおいて小父さんの座になる。家族は三人だから座席の石は少し大きいのが三つ、間の少し小型のは食べ物など据える台石になるようだ。もう一つ。家族に犬が一匹いるがこれは娘の石、小父さんの左の石一つおいた台石に座らせていることが多かった。座布団代わりの円座は苗代の「残り苗」を乾かしたのを同じ藁で組み上げたので、これはいつもは、屋根裏の様な処の棚に据えられていた。もう一つ、大切なことを言い落としているが、この人達の「仲間」は「下馬木」の「柿の木平」にいたのだが、皆、天幕を張っていて、この三人よりは、もっと厳しい顔をしていたし、私共を決して近づけなかった。あれだけ、ものおじしない、利君だって「柿平の奴にゃ近づかん方がええぞ」と、いつも言っていた。
このポンスケの「特徴」は
1 その天幕を持っていることと
2 「天人」という「自在鉤」をもっていること、
そして小父さんが
3 「山刀うめがい」という双刃の山刀をもっていることだそうが、鳳の草の親子は、天幕は、もっていたが使わなかった。
「自在鉤」は使っていたが「テンジン」とはいわずジザイカギといっていたし、この山刀もウメガイとはいわないでヤマカタナといっていた。利君にきくと「柿の木平の奴んた、天幕の中に夫婦ごと、別々の暮らしをしていて地元の他人とは滅多に口をきかんし、怖い顔しとるし、足が速いで、何するか分からんで・・・・・」と、おどした。きくと、このウメガイとテンジンと天幕は「あいつんたの三種の神器で触ったり、傷つけたりしたら、殺されるげなぞ」と威しては何度でも利君は、私に「得意相」にきかせた。
あいつどこで聞いてくるのか何でもよう知ってる奴だ、と私は思った。彼らが住むのは、いつも本当は天幕の中である。少し傾斜の地を選んで天幕の大きさに合わせて四方に小さな溝を掘る。その長い方に天幕の裾を丸太か何かで圧えて雨水が流れこまない様にする。両端の三角の処が「出入口」になるのだが、その又、三角の部分に余分の幕がついていて、入口になる。その小幕を引き上げて中に入るのである。だから出入りは、はい込む形でされるが、幕の中は一段と低く掘り込まれて平になっておる。出入口左隅の処に、「天人穴」があって、これに自在鉤の支柱がたてられる。炊事や用便は、どこか近い川原とか岩かげとかを上手に使って人の目に邪魔にならんようにしている。あれらは、足が速いうえに、手先が器用で竹なんかとても薄く剥いでいくが、これは素晴らしい名人だ。それに紙よりも薄くする。ものを截(き)る事、割ることなどは神業かと思われる。巧いなどと云って見ていられるものじゃない。素晴らしい業だといつも思った。「食器」(茶碗一つと大鍋と丼が三つ)など幾つもありはしないし、鍋釜といったものも一ケあるのもないのもあって、ほんに簡便な暮らしである。
自分で薪も拾ってくるし山菜も採ってくる。味噌や醤油は出来ないのか、作り方を知らないのか。ざるなど作って持っていっては物々交換ということをして、金のかからない生活をしているようだった。持ち物は、その三種の神器と外は仕事の時に使う道具だが何でも必要なとき自分達で作って使うという方法でほんに限られた物持っとるきりだった。着物など一、二枚きり持っていないらしいのに、いつも意外に小ざっぱりしていたのは、お洗濯が好きな人々だったせいもあろう。朝鮮人のように平たい石の上に無黒子(むくろじ)という木の実を袋に入れて、天幕の裏などにぶらさげておいて、そのつど半透明の皮を石鹸の代わりに使っていたが、いつか利君にもらって使ってみたけれども「シャボンのようにはおちんで駄茶漢(ダメだ」ことになたものだ。が、それが何かの拍子に口に入ると、苦い苦い。いくら、唾を吐いても舌の奥から苦さが湧いて来るみたいだった。鳳の草の藤原某とかいう、この夫婦は、きっと京都か、あっちの方の人とみえて「ほんやのボンどすか」などと言ったことがあって、“上方”弁だった。利君が威したほど怖い人達とは思えなかったが、時々変な言葉使って私共に分からないことがあるので「ちいとおそがかった」持ち物の中で「山刀」という小型の山刀は小父さんきり持っていないものだが「大事なものだ」と言っていた。幅は一番広い所で二寸位厚さは三分位あろうか。白く光って、いつもピカピカだった。元の方が、ちいと細くなっていて、何かの皮でつくったと思われる鞘に横から挟む様に挿すので普通の刀とは大分違っとった。
出雲国の「火の川」という川の上流でとれるとかいう砂鉄を打って作ったものだと私共に威張ってみせて直径二寸位の枝を「タン」と音をたてる程に振り下ろすと一遍に截れてしまう。確かによう切れる奴に違いなかった。「やっ」といって投げると必ずその太い先の方が先になって「さされる」ということだ。「ににぎのみことさま、からのならわし」とも言って威張ってみた小父さんは本当に太い松の幹に投げて見せたりしたことがある。
この人達の着物は本当に便利に出来ているので、いつも感心してしまった。そう、その着物だけど、上半分と下半分は別になっている。つまり一枚の着物が、上と下と別に作られているわけだ。上着は臍の辺から腰までくらいのところで終わり、下は乳の下からくるぶしまで、まるっきり袴か腰巻のようである。小父さんは藤つるか何かで自分が織ったと思われる角帯だったが小母さんも娘も紅い処のある帯をしめていた。その代わり村の娘達のように、お太鼓に絞めたりはしないで、いつも腹に巻いた形にしていた。手には手っ甲、脚には「キャハン」をつけていたし、いつでも手拭をかむって夏でも「カバチョキ」という(利君が名をつけた)半袖風の綿入れを背にあてていた。石の上でも土の上でも座る時に便利なように、その端に紐がつけられてていて、その紐を伸ばすと世話なしに座布団代わりになる。いらん時は荷物にかぶせたり、雨の時は頭にのせたりしていた。つまり、その本体の端についている紐を伸ばしたり縮めたりして尻の下に敷いたり背中へ引き上げたりするわけである。
いつも何も持っていないから身軽で、いつでもさっさと「場移り」が出来るので便利だが、それでこの人達は「転場」ともいうのだと教えてもらった。「瀬振り」ともいうし「ポンス」とも「ポンスケ」とも「オゲ」とも「ホイト」とも「ノアイ」ともいうが、これは、その場その場で異なっている。矢作川流域では「ポンス、ポンスケ」付知川筋では「ホイト」。土岐川川端では「オゲ」美濃平野に出ると、「ノアイ・・・・」。日本中、きっと夫々の場で先に住んでいた人間共が多少軽蔑の意を含めて様々な名で呼んでいただろうと思う。
彼らは自分達だけに通用する文字のようなものを持っていたようだし、仲間同志だけに分かる数の読み方などもあったと思われるが私は、それはよく知らない。国学の平田篤胤という偉い人が「日文(ヒブミ)」というものを言い出して、漢字、仮名の外に「日本には昔から整文字として伝わっていたのだ」と言い出して残したものがあるが、それは「日文」というもので、こんなものだ・・・と吉田先生が教えてくれたことがある。この丸い鏡の表の「銘」にも書かれていて今も苗木の「神明神社」かなんかに伝わっているとかいう話だ。私が鳳の草の団子杉に小屋住みをしていた藤原夫婦に習った文字は、三十字位あったと思うが誰かの書いたものか、皆読める程にはなっていない。あの小母さんが『タテツケハズシ、カタドのト』と言って□(二と読む)の字の様な字を書いてみせてくれたことがある。コという「あんさんの片仮名」と同じだと言うて笑ってみせた。「カタドのト」というのは『□』というので日本の「ト」と同じ意味をもつのだ。と言ったのを覚えている。カタドのトは□に先ず と、一方の戸をたてて、コ(□)をつけたのが、ト(□)になるのだということだったように思う。十歳前後のことは、かなりよく覚えているが、この辺になると洵にあやしい。「キナイイツツノクニケイオウカミヨリカミシロクヘル」と読むそうだが「機内。五の国」「慶応一より、一四六九減る」ということで、機内五ヶ国では慶応元年(一八六五)よりも人数が千四百六十九人減った・・・ということだそうである。話をぐっと始めに戻して「鳳の草」の「団子杉」の根元の小父さん達は娘を一人連れていたが、持ち物は至って少しきりだったし、「し方」「はなし方」は皆、下馬木部落の柿木平の天幕組とは同じだと思われたが、どうしたものか天幕を張らないし仲間と離れて、この一家だけが住まっており、天幕の代わりに竹を二つ割にして上向きに並べ、その間を下向きので伏せて上手に雨を漏らなくしていた(仲間と外れて別に住む人を“トケコミ”といったが、そのトケコミの準備をしていたのかもしれない)
それで日常に使う言葉の中にも時々分からんことがあったが、数のことはちいと覚えておる。
一、二、三、四と数えるのにカミ・ツギ・サン・シイ
と言ったし「ぎ」と「ぐ」とを混用していた。「二月一日」という代わりに「キサユラグ、カミノヒ」というのである。「きさらぎちたち」といえば、すぐ分かるのに、きらゆらぐ、かみのひ、という類で私が困るのだ。これは三角寛という人の書いた何かにみえていたのだが仲間の人数調べの表があって、といったものが残されているそうです。
メイチシサノトシキサユラグカミノヒ(めいじしさのとしきさゆらぐかみのひ)は、明治四十三の年。如月一日の日、「明治四十三年二月一日」というわけである。
八、九歳だった私共は、様子を感心して見て来ると、すぐ同年のお友達を誘って「馬木坂峠」を車に越えた麓の「人造湖」のほとりに小屋を造って学校の帰りに寄っては一休みしていたのだが「庄次」さという老人に見つかってしごかれたりしたことがある。が、亀を焼いたり、蛇をつかまえたりは遂に誰もしてみなかった。「うまいかもしれんぞ」と利君はいつも言っていたが私の前では亀も蛇もつかまえなかったし、喰わなかった。従弟の寅三は器用な奴で「川の魚」を道上に立って外から見つけると「ざばざば」川の中に降りていって「ガマ」という河岸の石の窪みなどに逃げ込んだのを手つかみで捕ったりしてみせた。穴に逃げ込んだ川魚は、狭い穴の中では、方向が変わられないから、そのまま遊泳して徐々に後退して来る。そこに伸ばしていた寅三の手が待っていて魚のしっぽをきゅっと掴む。魚の奴びっくりして
一旦は奥へつと逃げるというが辛抱強く待っているとまた指先に尾ひれがふわっと当たる。こうして一時間もすると遂々寅三の母指と人指との爪が、その尾っぽをしっかりつまみあげる。「やーい。子供んた、そんなとこで手づかみの魚とったりしとりゃ、ポンスと間違えられるぞ・・・・」道行く大人がちょっと立ち止まってそういう、いらん注意をしたものだった。
信州。平谷の在から瀬戸大曽根に通ずる。中馬街道が私の生れた家の前を通っており、後には裏手に代わって新道が出来たが、それでもそのおかげで「馬木洞」の十五、六軒の小部屋はしばしば飯田や岡谷や信濃路の文化と瀬戸名古屋の文化のようなものを持って来て私共村の者達は「子供の頃」過ごしたものだが、もっと直接には、この山窩や馬子衆や、そういう人々の「行動」によって養われていったように思う。
「やい。小僧。おしたちゃ、へんび、ようとるかいや。赤いのなら三銭。黒いのなら五銭。まむしなら十五銭で買ったるが、どうじゃ。捕ったら、火吹き竹ん中ん入れて手ぬぐいで、ふたしときゃ、ええわい
岩村に「へんびかつ」ちゅう奴がおって、時々、こっちいも来るようで、うっかりすると取られちゃうぞ・・・」彼らは、何とかして、そのまむしの生きたのを捕まえさそうとし、黒蛇をつかまえさせようとしていたが、それをまた、このポンス達は、とても上手に捕まえたものだった。彼等は道を歩いていて、ふと足をとめると天をあおいで「スン ゝ ゝ」と何か嗅いでみるような風をしながら、しばらくそのまま立っているが、やがて一歩二歩その匂いの近くに脚を運んでやがて、ひょいと「長い紐」をつまみあげる。ぶらん・・しながら小父さんの腕にからみつく様にするが小父さんは首ねっこをつかんで口もとからシャツをぬがすように、するっ・・・と裸にむいてしまう。白光りに光る、その裸蛇は赤い血は出ないし、ほんに美しくきれいだが驚いたことに、そのまま手を伸ばして、そいつのしっぽから、ぐにゃぐにゃ横口に喰いきって「美味いもんでんがな・・」と、目を細めてみせたりするのには困った。
外のことには、大抵あの人達のすることに感心するのだが、この風態だけは、どうにも我慢ならん。
村の人達が怖がるのも「こんなとこ」みているからではないだろうかと私は思ったものだ。
その喰い残りをあの小屋まで持っていって火にあぶって竹串にさす。それを巻藁に挿して保存しておくのである。「こいつ食って、自然薯掘ってくって、もう一つ松の実と地蜂の子、喰や病気なんかしまへんで・・・・・」と、威張ってみせたりするのには困った。地蜂は私も大好きだが、どうもあのぐにゃぐにゃの長蛇は苦手だった。いつやら、あの小母さんのくれた御幣餅だって素晴らしい美味い匂はしたけど、あの蛇のうごく姿とあの小父さんの生のまま喰っていく形を思い出して食べられなかった。包んでくれたのを家へ持ち帰って、おばあちゃんにやったのだが「どこの馬の骨とも分からんようなもんとこ、いよって、食うものむらってくるようなもんは、本屋の子じゃない!」と叱った。が、私は注意してみていたんだけど遂にそれを捨てる所は見なかったので「おばあちゃん、きっと喰ったな」と私は思った。その証拠に、その後の本屋の御幣餅のたれは近所でも格別美味いということになっていったものだ。然しどうも本屋では、蛇や蛙は入れなかったように思う。落花生を作り出したのは、その頃からのことだったのも証拠になりそうだ。このことを毎週書かされていた作文に書いて石田校長へ出したことがあったのだが、それについて夕食時の「他人の家の食べ物を覗いてみたりするもんじゃない」と、叱られたこともある。けれどもこの小父さん達はそういう意味で私とのかかわりがかなり深かったように思われる。
その小屋には、いつも利君と二人で、そっと村人の目を盗んでは行ったものだが、或る日、その子供を「教え込む様子」を見て、ひどく感心したことがある。校長先生も批評の中に「それこそは、わしの唱導する「行動教育」そのものだ。今後も色々彼らのすることを見て来て、書き残してほしい」と言ったことがある。
その「行動教育」は、石田校長先生の東方小学校でした「教育の根本原理」であるが、私が今、この親子がしていたことを書いてみようとする、そのことはもう、秋も半過ぎた頃の事だった。小川の川べりに、赤い平たい、大岩がある。
その岩のそばへ、あの四つか五つきりならん娘を連れて行って夫婦して縄跳びを教えるところだった。その初めから私どもは、じっと見ていたのである。
小父さんは、小母さんの後ろについていく。娘の後ろ姿を見ながら長い長い藤つるを一抱えも一束にして肩にかつぐと、あの赤岩の側にやって来た。何か三人で話しながら三人は一列に並んだ。そして小父さんと小母さんとは石の両端に立って、その藤つるを引っぱった。綱引きするのかなと、思って見ていると、そうではない。
「カミーィ。ツギイ。サン・・・。シイ。イツ。ムナ・・・」数えているが、何と言っているか分からないが娘も真似て一生懸命大声で叫んでいる。
そのうちに川柳の枝に小母さんの持ってた端をしばりつけると、小父さん一人で、くるっくるっと、廻してピタリ、ピタリと音をさせて藤つるを大岩の岩肌にたきつける。中央に立った、小母さんと娘とは、腰で調子をとっていたが、その中に、ひょいと子供を横抱きに抱いたまま、その綱の中所をまたいでひょいひょい、と飛び始めた。うまいもんだ・・・・・小父さんは大きく、ゆっくりとその藤つるを廻してやる。小母さんは、抱いた娘もろとも、やがてさっとその輪から出る。小父さんは相変わらず、くるっ、くるっと廻して輪をつくっている。その中にまた小母さんは娘を引っぱっていって今の、輪の側に立った。また跳ぶつもりだな。と思ってみていると、二人はしばらく腰で調子をとって藤つるが上に昇る度に、見上げては真剣な目つきになって見上げ見送る。つと、小母さんは、娘を前に押してやると、自分は、一歩後ろに出てしまった。
「あっ・・・・いっしょんとびやんのか?」と、思ったとたんに、あの小娘は上手に、その輪にのって、一つ、二つ、跳んでみせた。たった三回きり、跳べないで引っかかってしまったが、それで泣きそうにして、しょんぼりしている娘とは反対に小母さんも小父さんも真剣な顔をして一生懸命拍手を始めた。
「・・・・・」
分からないが、「跳べた、とべた」と褒めていることは、見ている私によく分かる。
「・・・・・」
やがて、娘は立ち上がって小父さんの顔を見るといきなりその大きく廻っている藤つるの輪の側に歩いていった。二度、三度、腰をふるように動かすと、ひょいと、調子に合わせて、輪の中に跳び込んだ。見ていて、はっとした私は、何でもないのに、つい釣られて拍手してしまった。「やあ・・・跳べたとべた。偉いぞ・・・」私は、思わず、大声を出して叫んでやった。娘は、私の方を見ないままで七つ八つと跳んだが、小母さんは泣きそうな顔で私を見た。
九つめに、娘はつまづいて駄目になったが、それでも二人共、叱らない。「跳べるよ。とべるよ・・・・・
いいぞ・・・今度は、かあさんが跳ぶ・・・・・」
小母さんは、そう言って、娘の代わりに跳び始めた。「次ぎ。三。しい・・・・・」
あっ。さっきの呼び上げは数だな。と私が思った頃は、もう小母さんの跳躍じゃ廿にもなっていた。
小父さんは、大にこにこで大きい輪を作って、小母さんを跳ばせている。一跳び毎に、ぴたっ、ぴたっ、と藤つるは赤岩の肌をたたいて、音をたてるが、その度に外皮の赤褐色の渋皮が飛んでいって、中の白い皮の肌がみえる。そして間もなくたたかれてびろびろになった部分から芯の堅い部分が覗く小母さんが、廻す。娘が跳ぶ。小父さんが跳ぶ。
小父さんに代わってもらって小母さんが跳ぶ。娘が跳ぶ・・・・・しまいには、何か、分からん言葉で
三人声を揃えて、唄いながら、跳びつづける・・・・・
やがて、芯と白い皮と、外側の赤茶色の渋皮がとれてしまうと小父さんは「かみやすみ・・・」と言って、川端の石に腰をおろした。娘を呼んで、抱いてやって、高く、さしあげて赤ん坊にする様にしてやって、褒めている。「よく跳べたぞ」と言っているだろうと、私はうらやましくなった。私の父も母も私と一緒に縄跳びをやってはくれなかったし、私の遊びが、出来たと褒めてくれたことは一度もなかったから・・「遊んでばっかけつがって・・」私は一度だって遊んで褒められたことはなかったのに・・・・・
そのうちに、ゆっくり腰を伸ばすと小父さんは手早く藤つるの芯を一尺位にきざんで薪の形にしばりあげると「これ、帰りに背負ってくんだよ」と、娘に言いつけて、自分には小母さんと二人、向かい合って、この藤の白い皮を両端から両掌の間に挟むように一方の端を左掌にのせると右掌をぐっと引いて、よりをかけ始めた。「左縄なんかなって、何するのかな」と私が思って見ていると、その縄は、よじれて段々段々短くなっていく。「・・・・・」と何やら合図したと思うと小父さんは、その端と小母さんの方の端とを揃えてうんと、引っぱった。とみると、忽ちパッと離す。藤つるの左縄は、生きものの様にくりくりっとうもて縄状によれて、川端柳の枝に、飛びつくような形で、縮まっていって見事な白い縄になって飛んでいった。が、それでもまだぴりぴりして動いている。小父さんは、それを川端柳から外すと一寸川の水につけてみて、ぴたりぴたりと岩をたたき出した。縄が少しばかり柔らかくなりかけた頃、もう一度、小父さんは、娘に笑顔をみせて「・・・・・」何やら言ってみてから、さっきの芯を切ったものを娘の背に負わせた。
小母さんは何も持たずに娘の後からついていくきり。・・・・・小父さんは、その縄の出来具合を見ながら、ごきげんで、小母さんの後ろについていく・・
その日の午后。私は利君を誘って、もう一度彼らの小屋を訪ねてみた。私の陽足はぬるく、風は爽やかで、何とも気持ちがいい。・・・・・丁度、三人は出かける用意がすんだ所だったのでよかったなと思った。私達には、おかまいなしに、せっせとさっきの白縄と山刀とをもって三人は何かしきりに話し合い乍ら足早に前を歩いていく。私達を無視するようなことは、いつものことだし、私達も平気な顔をして、後れない様に小走りについていくことにした。先頭の小父さんは、川岸の竹藪の処で止まった。小母さんと娘とは、すぐおいついて小父さんと並んで何か話している。しきりに側の娘は合点をしているが、何を話し合ったのかは、分からない。只、悪いことでないだけは、三人共うれしそうな顔をしていることでよく分かる。「何するじゃろう?」利君は、いつもの顔で少しおでこを前に出す様に小首を傾けて私に言ったが勿論私に分かろう筈はない。「そう、あわてんなよ。そのうちに分かるよ」と私は言ってみたが、さっきから私達のことを少し気にし出していたのか小父さんが、こっちを向いて言った。「坊んた。わしらん、ついて来よって何すんかな?」私は、ひどく怒られた気がして、黙って立ったが利君は平気な顔で答えた。
「おまいた、おらたァ、いろいろ違ったことすっで、見せてむらうつもりだが、いかんのかあ」
「べつに、いかんというのじゃないけど、わてら、どこまで行くか、分からんのに、ついたいて、怪我でもされちゃ困るで・・・・・」小父さんは、そう言ったきり、すぐ竹の幹によじ登り始めた。
「うまいもんだなあ。まるきし猿じゃ」利君が何かつづけて言おうとした時分には竹は、小父さんの体重で曲がって先が地に届きそうになった。小母さんが、さ、さ、さ、と飛んでいって、その竹の先を両手で掴むと跳ね上がらんように、ぎゅっと引っぱった。。娘がさっきの藤縄を小母さんに差し出す。すぐ小母さんは、その竹のかなり先の方にしっかり藤縄をしばりつける。その縄はぐんと引っぱると隣の竹の元の方にくくりつけられて、はね上がらんようになる。小父さんがするすると降りてきて、ひょいと飛び降りる。ついでに数歩離れた所の竹によじのぼって、さっきと同じことをして、竹を身体の目方で曲げる。小母さんがその先を掴んで引っぱる。娘が藤縄の、もう一本の方を差し出す。小父さんがそこに縛り付ける。小父さんが降りてくる。小母さんはひっぱっている藤綱と、さっき竹の根っこにしばりつけておいた、初めの藤縄とを取られないように、両手で引きつけていると、その間に小父さんは、細い竹を切って二本同じ様に三尺位のものにする。その端を藤縄でしばりつけると黙って小母さんに渡す。小母さんは、その立った竹の伸びにつられて、ひょいひょいと引っぱられて身体が浮き上がるようになるが、手を離さないで耐えておる。小父さんは、初めにしばっておいた藤縄の方を外して今の三尺竹のもう一方に巻きつけてしっかりしばりつける。
「あ、分った。ブランコつくりよった」利君が言って私の顔を見た。きっと、あの娘にブランコ作ってやったのだろう、と思うと、私はちいと羨ましい気がした。私だって利君だって家の外でブランコなんか作ったら叱られるにきまっとるし、第一、親がブランコ作りに先にたってやってくれるなどということは、絶対になかったことだから。
思った通りだった。小母さんが、まずブランコの初乗りだった。二度程腰と膝との屈伸で調子をとるとブラーンブラーンと竹薮の外側へ向かってふってみせる。娘は真剣な眼つきでじっとそれをみている。勢いがついた。・・・・・ざあっ、ざあっと音をたてて、この二本の竹が曲がって伸びてあっちの川岸にとどくと小母さんは、もう一度膝と腰とで舵をとって大ゆすりにゆすってから、ひょいと身体を縮めて、ひらりと向う岸に下り立った。両手は、まだブランコの藤縄を掴んだままだから竹が伸びる時、ふらっ、ふらっと引っぱられて泳ぐ様に動く・・・・・。「面白いことしよるなァ・・・・・」二人は、感心してしまった。第一。ブランコの作り方が面白い。あの縄の作り方が素晴らしい。あの腰と膝の使い方が、実にうまい。
「おらも乗せてくれるだろうか?」利君は、もう乗せてもらうつもりでいる。小母さんは二度三度、同じ様にして、この竹のしないを利用しては川の向うにいったり、その反動でこっちに来たりして、形を見せていたが、やがてこちら側に、ひらりと降りた。「・・・・・」娘が呼ばれて、そのブランコに乗った。脚も腰も小母さんのような具合に強くはないので、なかなか、このブランコは小母さんの様に上手には、揺れない。小母さんは何やら言いながら娘の脚もとから下っている細紐をつんと引っぱって娘の腰の力を助けてやる。「あの紐、いつ付けた?」「不思議な奴らだなァ・・・」利君と二人で感心している間に娘のブランコは、段々調子がついて川の上を向こうに届いたり、こっちに戻ったり何回でもぶらあん、ぶらあんと動く。そのうちに小母さんが、何か言ったなと思うと娘は腰を曲げて止り木にしゃがむ形になったが、向こうにつくと一緒にひょいと飛び下りた。うまい・・・ブランコは、こっち側にぶらんと、戻ってかなり高い所へ上ってしまった。だけど、小母さんの手の紐は、ちゃんと握られているので、どこか遠くへ行ってしまったりしない・・・。「ちぇっ。やってけつかる・・・・・」利君は、もうすっかり感心のしっぱなしだ。「これで、どうするずら・・・」私がそう思った時、小父さんと小母さんはパチパチ手を打ってから、万歳の形をして娘を褒めてやっていた。
「あ、そうだ。川渡りの仕方を教えたとこだよ・・」
やっぱり利君は、私よりも頭が良くて早く分かるようだ。「だけど、もう、あの娘あ、戻れんなっちゃうに・・・」私が心配をしてやると、今度は小父さんが乗っかって世話なしに、向う側にぴょんと渡る。娘を抱き上げて「きゃっ」「きゃっ」と言っているのは、きっと「上手に出来た」と褒めてやってるのだろうと私共には思えた。娘を乗せると、今度は小父さんは、向う側に残ってみている。
何度も何度も繰り返して、川渡りの方法を見せてくれたが「貸してやる」とも「乗ってみろ」とも遂に言わなかった。「坊。日い、暮れますっせ。
はよ。帰らんと叱られるで・・・・・」小父さんは向う岸から大きい声を出して私達を追払いかけた。もう少し見ていて、あの藤縄をどうして取ってくれるか。その縄どうするか。見たかったけれども大分急に薄暗くなりかけていることに気づいて二人はほんに名残惜しくも、その場を下って道路に出て来た。
あとの日に尋ねてみたが、この藤縄は、「折角努力して作ったものだから、もう一度水に浸けて、ほぐして糸のようにして幾晩もかかって「より糸」にして、小父さんのしている角帯のようなもんにするんだ」と小母さんは教えてくれた。
私は「教育の原点」というものを探したら、この「山窩の夫婦」のような「生活の実際」の中にみつかるのではないかと思って来た。この数年の後に、私が無官の大夫となる日が来る。そこで最初に手がけたいと思うのは「恵那地域の教育の原点等」であるが、それは、やはり、「原点」ともいうなれば、ここらにあると思えてならない。「行動」する、「労働」し、「労作」し、肉体を動かして「分る境地」におこうとした、「恵那の先人達の教育」は、やはりここを目指したものでは、なかったのか。いつぞや、芳兵衛先生は、その話をとても大切な話に聴いてくれたし、藤村老も、しきりに「いい話だ」と褒めてくれていた。
私も含めて、今時の教育の中に「共に行く」「共に生活して」「共に生き育つ」「共育」が無いのが悲しいことだと思うことから、残したい話の一つだ。(昭和四十八年六月十七日)
方言注
おーっそがい=おそろしい
二ッケ=肉桂
殺されるげな=殺されるそうだ
だちゃかん=駄目だ
子供んた=子供達
こきる、こいて=言っている、言って
おし=おまえ
こっちいも=ここらへも
もんとこいょって=者の所へ寄って
いっしょにとびやんか=一緒に飛ばないのか
遊んでばっかけつがって=遊んでばかりいやがって
もうて=まわって
坊んた=坊やたち
世話なしに=何の苦労もなく
三宅武夫 1903年~1990年
岐阜県の教育家。岐阜県師範学校を卒業後、
教師になる。1943年中津町立第二中学校
初代校長に就任。以後中津川市教育長などを歴任。著書『おらあ先生になる』ほか
家族単位で山の中や川辺で漂白の生活を送るサンカは、大自然を背景に親が子に自分の生活する姿を見せて生活している。教育者である作者の三宅武夫氏はサンカの家族に教育の理想を見たのだろう。その眼差しには優しさが溢れている。
三宅武夫は明治三十六年、岐阜県に生まれ、師範学校を卒業後地元の小学校に赴任、その後愛媛県の松山に転出している。この鞦韆(ぶらんこ)はその後に、生家に近い恵那郡の団子杉近くで目にしたサンカの家族のことを書いているが、この愛媛時代にもサンカを目撃してるという。
三宅氏が出版した『おらあ先生になる』という自伝の中にもその時の事が書かれているので、引用しておく。
※
その一つに、松山にいた時、担任の生徒を引率して、奉仕作業のためにと、市街の南を流れている石手の川原に行ったことがありました。そこには、ずいぶん沢山の天幕が張ってあってこの川原の右岸に、穴を掘って住んでいるらしく、竹細工をしている一群に逢ったことがあります。
『先生。ここにゃ、紀元二千年前からの人間がいますけ、気ぃつけにゃいけんぞな・・・・・巣に棲み、穴に住む人間が、かなり大勢いるのじゃけんな・・・・・』高橋という生徒がそう言ってきました。
なるほど、見るとかなりの人数です。それは、
明らかに、かつて私が子どもの頃に見た、あのボンスケといった、同類の人達であることがすぐわかりました。私は、その彼らの天幕の前まで行って、昔「鳳の草」(明智在)の小屋にいた三人の暮らしを思いながら、あの時小母さんが教えてくれた彼ら独特の文字だといった、あの符牒を書いて見せたのです。(中略)。記憶をたどってみますと、これはどうやら昭和十四年の夏のことです。
その後、彼らがどうなったのか、いつどこへ消えていったのか。それは知りませんが、その時の話の中に、今はその日その日の生活に、大分困っている話。いまに日本が戦争にでも突入すれば、その時はまっさきに志願して、軍人にしてもらい、天晴れ日本人になってしまいたいが、どこにいっても一般人、一般の子供迄が、冷たい仕打ちをして、自分たちを悲しませている。先生なら、その先生になる人々に私らだって人間だということをよく解るように話して聞かせ置いてほしいと言っていました。そして今、何とかして「溶け込み」をしたいと思い、この地に「居つきたい」と、それぞれ苦心している。と言っていました。
※
愛媛県師範では三宅氏は校長に生徒の五年間持ち上がりを要求し、県内の生徒宅を訪問して回るなど、たいへんに教育熱心な教師であったようだ。それはおよそ四十年近くも後の、このような後日談からも窺える。再び『おらあ先生になる』からの引用
※
それが昭和五十一年、私は、私の手記復刻版の『鞦韆(ぶらんこ)』という一冊を印刷してもらいましたので、当時教え子だった伊予路の校長たちに送りました。ところが、その中の三人もの校長から「私の学校のPTAの役員の中にそういう人びとがいますらい・・・・」と、教えてくれました。
・・・それは、あの時、「溶け込み」を考えていた人達の子孫じゃないでしょうか。あの頃から「溶け込み」をはじめたにしても、あの全部が、あの辺りだけに落ち着いたわけでもなでしょうから、いずれ、松山近郊から西は西宇和、東は遠く香川、徳島、南は高知、北は瀬戸内の島島から、中国路にかけて、じりじりと沈潜・定着していったのではないかと思うのです。
※
中国・四国地方のサンカの出自を考察させる一節である。そうして三宅氏はその後を学習研究会で回ったりした時でも、日本全国いろいろとその土地土地で興味深い観察をしている。特に、京都で成長した小学校の教え子の女性達に「道楽」という料亭で竹焼料理をふるまわれた時の書いている内容が興味深い。
※
その「一節の竹」の上側の割り口は、和紙で貼られていて、竹の底側は、すこし焦げていました。口取りが出て、お吸い物が出て、お酒が出て、その張り紙がはがれますと、この一節の中には、一杯詰められた様々な山海珍味が納まっていました。一番上に・・・・(中略)。その「知久屋喜」は、まさに、彼らの秘法による、石焼料理、桶料理、竹筒料理と、みな同じ類型の料理だと思いました。東は秋田、西は山口、南の高知、内海の鹿島、そしてこの京都の「知久屋喜」、それに故郷明智の、鳳の草の小母さんの「手料理」も、同じ手法だったと、今も思っています。
※
このように三宅氏はサンカに向けて様々なアングルからのアプローチを試みているのだが、やはり
「鞦韆」においての重要なテーマという「教育の原点」を「サンカの家族」に見出したということになるだろう。三宅氏は、彼らの生活の中にあった「子どもへの教育」が徹底した「行動中心教育」であるとし、その素晴らしさを「鞦韆」によって我々に伝えてくれている。
藤つるを取ってきて、それをぶらんこに作りあげてくまでのプロセス。そしてぶらんこが、出来上がってから親子三人で遊ぶ姿を見て、七十年近い昔、若かりし三宅氏は、共感と羨望の眼差しで三人の親子を見ていたに違いない。
それは次の言葉にも明らかだ。
※
私の周辺にいた多くの人々の中にあって彼らぐらい、強烈に私の「教育行動」に影響した集団は、少なかったという気がしてなりません。(中略)彼らのような「生活即教育」「遊び即生活」の「共育」をすすめる、そういうものを忘れたくありません。何としても「子ども自身が自らの行動を律する力」が、自ら育つためになくてはならないことと、私は思うのです。
※
三宅氏の著作の中には「そっとみんなが溶け込んでいてくれますようにと願うわけです」という一節がある。サンカを好奇の眼で見る、あるいは研究の対象としてのみ見ようとする試みの氾濫する中、サンカに向けられた氏の眼差しの温かさは、その人柄を反映していることを窺わせる。
“サンカ”へのオマージュとして「鞦韆」は文句なしに至高の存在だと言える。
最後に氏がサンカへの惜別の情を吐露した一節を引用しておわりにしたい。それはまさに、平成の現在“サンカ”という存在にロマンと憧れを持ってる、我々総てに共通する心情であるといえよう。
※
私の記録の中には、これら「消えていった人々を惜しむ」幾つかの記録がありますが、いつもこれを見る度に思いますのは「その後どうなったか、もうわからない」という惜別の情です。それでいて、イツの日にか、まさに私の心の底深くに食いいって離れない、それらの人々の人柄、暮らしの実態、ささかの高ぶりもない親切、独特な語り。そしてその中にあった珍しい、それでいてまことに「平凡」な何でもない、しかも、またここになくてはならない「文化」「生活」「教育」の実態等々、回想するたびに、涙のながれるほど懐かしく、切実に感じるものがあるのです。彼らが一般人社会、周辺の人々の世界に溶け込んだとしても、どこかで、あの純粋だけは残していてほしいとそう思うのです。
© Rakuten Group, Inc.