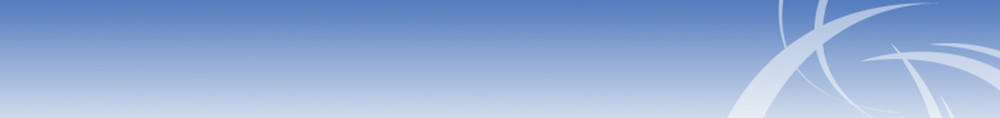全538件 (538件中 1-50件目)
-
「鬼の筆」 春日太一
脚本家、橋本忍の評伝。40年以上前の大学生時代に映画に熱中したことがある。地方の大学なので鑑賞する環境はあまり良くなかったが、名画鑑賞会のようなものもあり、年によっては100本ぐらい観たこともある。黒澤明の「羅生門」「七人の侍」「生きる」や「砂の器」はリバイバル上映で観た。封切りで観た作品はないものの脚本家、橋本忍の名前は強く印象にあった。そんな時期(1982年)、橋本忍脚本、監督の「幻の湖」という作品の予告編が映画館で流れた。今風に言えばレジェンドである橋本忍が脚本だけでなく監督も担当する作品ということでいやが上にも期待は高まった。ただ予告編を観ても、どんな内容なのかさっぱりわからないものではあった。結局、「幻の湖」が地方の映画館で上映されることはなく、酷評だけが聞こえてきた。その後、橋本忍の名前が話題になることはなかった。2018年、100歳まで生きられたのに、である。本書を読むと、橋本忍を生んだ環境や仕事ぶりが見えてくる。そしてなぜ「幻の湖」が失敗したのかもわかる。「幻の湖」は、人の才能には偏りがあり、批判、否定する人がいるという緊張関係がなければプロジェクトはとんでもない失敗をする危険があることを示している。「砂の器」については共同脚本で関わった山田洋次が書いているものをずいぶん前に読んだことがあるが、本書で書かれていること(山田洋次がインタビューに応えている)と若干違うニュアンスだったと記憶している。他の作品についても関わった人たちの証言が食い違ったりしているが、著者は公平なジャッジをするように心がけていて好感が持てる。人の記憶には何らかの(自分に都合のいい方向が多いだろう)バイアスがかかるものであるし、単なる記憶違いもあるだろう。実はその食い違いが興味深い。
2024.02.24
コメント(1)
-
現在休止中です
ブログを2カ月ほど更新していないのだが、実はその間に記事をアップしようとして失敗したことが2回ある。操作ミスなのだろうが、原稿からのコピーではなく直接入力しているので回復することはできなかった。たいした内容ではないので書き直す意欲もないまま、現在に至っている。時々閲覧していたブログの多くが休止している中で、続ける意味があるのかとも思うのだが、今のところやめるという判断もできずにいる。いちいち報告する必要もないと思うが、そんなこんなでこのブログは現在休止中です。
2024.01.29
コメント(0)
-
ヘアアイロンを押し当てるのはパワハラではない
宝塚歌劇団で団員が自死したと言われる事件で、長時間過密労働に加え、上級生によるパワハラがあったことが原因ではないかと報道されている。中にはヘアアイロンを額に押し当てたという証言もある。なぜかメディアは「パワハラ」と報道しているが、事実ならそれは暴行または傷害事件だ。パワハラももちろん犯罪で、暴行・障害より重いとか軽いとかというものではない。しかし、別の犯罪であることは間違いない。言葉は正確に使うべきだ。宝塚歌劇団における上下関係の厳しさは、むしろ美点のように言われてきたように感じる。もちろん上下関係を主な動機とする規律とパワハラは別ものだとは思う。しかしその上下関係がパワハラを誘発したのであれば、むしろ非難されるべき体質だと言わざるを得ない。
2023.11.25
コメント(0)
-
首相の報酬は上げるべきだ
支持率低下対策が露骨な減税案を出した直後に大臣の報酬引き上げを決めたことで岸田首相が批判を受けている。国債を原資にした減税が愚策なのは言うまでもない。他人に借金でおごって、その借用書の連帯保証をさせるようなものだ。一方、大臣の報酬引き上げはどうか。引き上げても返納すると首相は言っているが、返納する必要はない。議員報酬もそうだが、優秀な政治家を育てるために報酬は高くするべきだ。あんなつまらない議員や大臣に高い報酬は必要ない、という向きもあるだろうが、報酬にふさわしい議員や大臣を選ぶのが有権者のなすべきことだ。報酬が低ければ、ジバン、カンバン、カバンを引き継ぐ世襲議員でもなければやってられない。報酬を引き上げ、優秀な若者が政治家をめざせるようにすべきだと思う。
2023.11.20
コメント(0)
-
溺れる犬を打つ
ジャニーズ事務所を擁護するつもりは全くないのだが、ここのところのメディアの取り上げ方には気持ち悪さを感じる。あることないこと、憶測を含めて言いたい放題の非難がジャニーズ事務所に向けられている。ジャニーズ事務所が芸能界を支配するほどの権力を持っていた(のだと思う)ころは、未成年者に対する性加害にも目をつぶっていたメディアが、もはや廃業せざるを得ないところに追い込まれるととことん叩く。溺れる犬を打つような、いじめと同じ精神性としか思えない。こんなことを言うと、ジャニーズを擁護するのかと批判されるかもしれない。そうだとしたら、それもいじめと同じ構造だ。
2023.10.08
コメント(0)
-
ジャニーズ
ジャニーズを擁護するつもりはない(そもそも関心が薄い)し、被害者はどんな形であれ救済されるべきだと思うのだが、最近の騒ぎにはやや違和感がある。ジャニー喜多川氏の性癖については過去にも告発があり、いわば公然の秘密であった。所属タレントを含め、業界関係者が知らなかったということはあり得ない。一方で多くの人気タレントを抱えるジャニーズに忖度して、メディアが批判してこなかったことが問題とされている。しかし、そもそも芸能界というのはそんなにきれいな世界だったのか。山口組の田岡組長の葬儀に芸能人が多数参列したり花輪を贈ったりしたのは1981年のこと。暴力団との関係を問うインタビュアーに大物歌手が「芸能人はみんなお世話になっているんだ」と恫喝するシーンを覚えている。芸能人が暴力団に「お世話になる」ことが明確に悪とされたのは1992年の暴力団対策法施行からだろう。それ以前であればお笑い芸人の闇営業も問題にはならなかったはずだ。性加害、とりわけ男性に対する行為が犯罪とされたのは2017年の刑法改正からに過ぎない。それ以前にも強制わいせつ罪に問える可能性はあったし、性加害に対する世間の目は時代とともに厳しくなってきていたのだが、暴対法の場合と違い、明確に悪とされたのがいつなのか、線引きが難しい。どの時点からメディアは性加害を問題とすべきだったのか。セクハラ問題などを報じた文春をジャニーズ事務所が名誉棄損で訴えた裁判で、セクハラについて事実と認定した高裁判決が確定した2003年とするのが妥当かも知れない。いずれにしても違和感があるのは、メディアが大きく取り上げなかったとは言え、高裁判決は決して隠されていた出来事ではないことだ。海外メディアが問題にするまで、多くの日本人が知らなかった話ではないはずだ。
2023.09.09
コメント(0)
-

セクハラ
セクハラについてではなく、セクハラという言葉について前回書いた映画「クライマーズ・ハイ」の中で、社長の振るまいについて「セクハラ」という言葉が使われていたことに違和感を持った。Wikipediaによると「セクハラ」という言葉が日本で初めて使われたのは1986年ということなので、作品の舞台である1985年には使われていない可能性が高い。ぼくが社会人になったのが1985年で、たまたま翌年に雇用機会均等法が改正されるという時代の変化を直接知っているので、そのあたりが気になったのだが、たぶん多くの人は気にしないだろう。自分にとっての一つの節目であった1985年が舞台で、携帯電話もパソコンもないという時代性を特に意識したので、言葉の時代性に引っ掛かりを感じただけのことだ。ただ製作者はそんなことはわかっていてセクハラという言葉を使ったのだろうと思う。言葉は何かを伝えるためにある。その時代に使われていない言葉であっても適切に言い表せるものであれば使って構わないだろう。時代劇のセリフが必ずしもその時代に使われていた言葉ではないように。ちなみに原作には「セクハラ」という言葉は使われていない。一方で、当時は一般的ではなかった「過労死」という言葉が出てくる。ただしこちらは一般的ではなかったものの言葉としてはあったようだ。クライマーズ・ハイ/横山秀夫【3000円以上送料無料】
2023.09.02
コメント(0)
-
映画「クライマーズ・ハイ」
劇場公開時に観ているし、原作も読んだことがあるのだけど、あらためてBS放映を録画で観て、時代の変化の大きさを感じた。原作は2003年に発表、映画は2008年に公開されているが、舞台は1985年。携帯電話もパソコンもない時代だ。作品は日航ジャンボ機墜落直後の地元新聞記者の苦闘を描いている。無線機を持たない記者は民家で電話を借りて口頭で記事を送る。受け取る方も手書きでメモを取る。今なら現場でデジタル入力された記事が、校閲を受けてデジタルで割りつけされ、そのまま新聞紙面に載るのだろう。新聞製作はずいぶんと楽になったことだと思うが、一方でSNSで誰でもが情報を発信できるようになり、新聞は社会的にも経済的にも大きく地位を後退させている。墜落原因を事故調査委員会が特定したという情報の裏取りを試みた社会部記者からの、ほぼ大丈夫だが確証はないという報告を聞いた全権デスクはダブルチェックを重視し掲載を断念する、というのがクライマックス。結果的には毎日新聞に抜かれてしまうことになる。こういう葛藤は今でもあるのだろう。たとえ結果的に誤報になることがあったとしても、プロとしての矜持、公器としての使命感、そういう葛藤のもとに記事は社会に出される。一方、SNSでは何の葛藤もないまま、気楽に情報が発信される。多くは発信元を知られることもないため、誤報だろうがお構いなしだ。もう紙のメディアの衰退は避けられないだろう。10年後に戸別配達の新聞があるとは想像できない。ただ気楽に誰でもが情報発信できる時代だからこそ、報道機関の役割は重要だと思うのだが。
2023.08.23
コメント(0)
-

「ハンチバック」市川沙央(第169回芥川賞受賞作)
出生前診断によって、障害児が生まれる前に堕胎されることがカジュアルになったのだから、「堕胎するために孕もうとする障害者がいてもいいんじゃない?」と主人公は考える。 堕胎がカジュアルなものになっているという認識が正しいのか。出生前診断の結果に多くのカップルは苦悩し、どちらを選んでも苦しい決断を迫られるのではないのか。 主人公はモナ・リザを汚したくなる理由を「壊れずに残って古びていくことに価値のあるものがたちが嫌いなのだ」というが、歴史的建造物や絵画は古びていくことに価値があるわけではない。 そのように主人公の主張には、自分の論理に合わせるための事実のすり替えがある。もちろん主人公に共感できない作品がすべてつまらないというつもりはないが、これはつまらない露悪趣味のように感じる。 ただ障害者にとって紙の本を読むことがいかに困難なことか、など当事者でないとわからないことをいくつか気づかされ、興味深いところもある。 ハンチバック [ 市川 沙央 ]
2023.08.20
コメント(2)
-

「検証 ナチスは『良いこと』もしたのか?」岩波ブックレット
「ナチスは良いこともした」という言説が散見されるとは感じるが、問題にするほど広がっているとは思わない。ウェブではいわゆる逆張りの意見が実際以上に大きく取り上げられがちだが、実態としてはごく少数だからだ。 一方でナチスの犯罪について以前ほど言われなくなっているとも感じるので、「ナチスは良いこともした」という言説が広がる危険性がないとは言えないのかも知れない。 それで本書だ。ドイツ経済を回復させたとか労働者保護政策を実施したとか、ナチスがしたとされる良いことを取り上げ、一つ一つ否定してみせている。一刀両断という感じではなく、研究者らしく丁寧に検証してみせる。ナチスの功績としてよく挙げられるアウトバーン建設は前の政権が計画したものであること、雇用創出効果は限定的であったことが論証される。 「ヒトラーは民主的に選ばれた」という説については、ナチ党が国会の過半数を占めたことはないという事実を挙げている。経済危機に対処できない政府に対する幻滅による共産党の躍進という状況のもとでヒンデンブルク大統領がヒトラーを首相に指名し、右派連立政権が成立したこと、その後は親衛隊、突撃隊を使った暴力、陰謀による共産党弾圧を通じて全権委任法を成立させたことなど、間違っても民主的な政権獲得とは言えない。 残念ながらこういった文章はウェブには向かない。ウェブ向きにするのならもっと刺激的で短絡的な文章にした方がいいだろう。タイトルは「『ナチスは良いこともした』の大嘘」とでもした方がいいかも知れない。検証 ナチスは「良いこと」もしたのか? (岩波ブックレット 1080) [ 小野寺 拓也 ]
2023.08.12
コメント(0)
-
党首公選が必要だとは思わないが
前回(と言ってもずいぶん前になってしまったが)の記事で、松竹伸幸氏を共産党が除名したことを批判したのだが、私は必ずしも松竹氏の主張に賛同しているわけではない。松竹氏は党首公選制を主張しているが、共産党ぐらいの規模の政党で党首選挙を行う意味はないと思う。旧民主党系などの政党はそもそも雑多な思想の寄り集まりだから党首は選挙で決めるしかない。自民党の党首選挙は小泉の時の例外を除けば、ほぼ派閥の力関係や思惑で当選者が決まっている。安全保障政策について言えば、松竹氏の主張に賛同できるところは多い。ただ例えば自衛隊合憲を党の方針にすれば、かなりの支持者が離反するだろう。そこは理想論と現実の間で中間的な方針を取らざるを得ないし、その意味で今の共産党はぎりぎりのバランスを取っていると思う。話は変わるが、中国を「社会主義をめざす国」と規定した綱領(今の綱領ではその規定は削除されている)を批判して共産党を離れた人がいる。民主集中制のもとでは、党外でそれに反する発言をすることは許されない。そのことに強い反発をしたらしい。民主集中制が悪いとは思わない。どんな政党でも採決に際しては党議拘束をかけるのだから、やっていることは変わらない。ただ、意見の違いを党外に持ち出してはならないという共産党のやり方は厳格に過ぎる。松竹氏除名の理由もそこにあったのだが、小選挙区制の衆議院はもちろん、今の時代はある程度広い層の支持を得なければ議席を取ることは難しい。党内に意見の相違、考え方の幅があると明らかにすることはむしろ必要なのではないかと思う。
2023.04.24
コメント(1)
-
松竹伸幸氏の除名
共産党が松竹伸幸氏を「分派活動」を理由に除名するらしい。共産党にとってのメリットは内部の引き締めだろうと思う。デメリットはイメージの悪化だ。もともと偏狭で排他的、中央集権的で言論の自由がない、云々というイメージがあり、そのかなりの部分は誤解だと私は思うが、このようなことがあれば擁護のしようがない。自公政権やその亜流でしかない維新ではダメだと思う有権者は少なくない。国民民主党は自公にすり寄り、存在意義を失った。立憲も腰が据わらない。そう考える有権者にとっての選択肢として共産党は存在し続けるだろうが、それ以上にはなり得ないのではないかと心配する。
2023.02.06
コメント(0)
-
松竹伸幸
松竹伸幸氏のブログは時々見ている。ずいぶん前にブログか何かのプレゼント企画で著作をもらったことがあり、その頃に保険医協会が企画した講演会で話を聞いたこともある。 松竹氏はかつて日本共産党の国政選挙候補者であり、本部の勤務員である。考え方の違いから退職してからも、ヒラの党員として活動しつつ発言をしている。 最近の主張は日本共産党のトップを党員による投票で選ぶべきだということと、安全保障政策を見直すべきだということが主だ。 その主張をまとめたものが「シン・日本共産党宣言」(文春新書)として出版された。内容は賛同できるところとそうでないところがあるが、それは今は触れない。 気になったのはその内容よりも共産党の側の反応だ。 「シン・日本共産党宣言」が出されてすぐに共産党は機関紙で「規約違反」などと批判した。個人名による署名論文なので党の正式見解ではないということなのかも知れない(後に常任幹部会が論文を的確なものと確認したようだ)が、ヒステリックにも見える反応は共産党のイメージを悪くするだけではないかと思う。機関紙なので党内向けに引き締めを図ったものなのかも知れないが、発行部数の少ない機関紙といえどもウェブで拡散される可能性はある。 党員が対外的に党の見解に反する発言をすることが規約違反(本当にそうなのかは知らない)なのだとしても、党員ではない者が同じような発言をする場合もある。党員でない者に対して規約違反という批判はできない。主張に反論するならもっと丁寧にするべきだろう。
2023.01.30
コメント(0)
-
問題は小選挙区制だ
立憲民主党の元国政選挙候補が自民党から県議選に立候補する件。 子育て支援などの政策を実現するために自民党入りを決めたということについて批判されるのは当然。 衆議院選挙に小選挙区制が導入された1996年以来、2年ちょっとの民主党政権の時期を除けば自公が政権を担っている。何らかの政策(自らの利益のためかどうかは問わず)を実現しようと考えれば、自民党あるいは公明党を頼るあるいは利用する方が手っ取り早い。そして見返りに選挙で協力する。与党の権力基盤はますます強化されるということになる。(民主党政権がもっと続いていたら、あるいは何度か政権交代が起きていたら、こんな構造にはなっていないだろうが) 政治改革と銘打って小選挙区制が導入されたのは、政権交代可能な2大政党制を実現するという理屈だった。2大政党制の是非は別にして、四半世紀が経っても2大政党制が実現していないという事実は、その理屈が間違っていたということだ。 拮抗する野党が存在しない状況での小選挙区制は与党が圧倒的に有利になる。ますます政権交代は起きにくくなり、さらに与党の権力基盤は強化される。内閣支持率がどんなに下がっても、政権交代は起きない。次は与党の誰かに交代するだけだ。これでは多くの日本人が忌み嫌う1党独裁の国と変わらない。 問題は小選挙区制なのは明らかなのだが、なぜかそんな世論は盛り上がらない。
2023.01.23
コメント(0)
-
安倍元首相銃撃事件
「民主文学」誌には現在が描かれない(まったくということでないにしろ)という議論があり、その例として安倍元首相銃撃事件をあげる意見を聞いた。 そこで事件を小説にできるかどうかを考えてみたのだが、すぐに行き詰ってしまった。 事件の経過については報道でほぼ明らかになっている。銃撃したのは別人だとするような陰謀論もあるが、説得力はない。 容疑者についてはいろいろ報道されていたが、鑑定留置されていることもあって、無責任な憶測記事は比較的少ない印象がある。父親の自殺や母親の入信からの生活の困窮、本人の自殺未遂などといったことは、どこまで正確かは別にして情報はある。 父親の自殺などがあって母親が統一教会にのめりこみ、多額の献金で家庭が崩壊する。それを恨んだ容疑者が統一教会の後ろ盾と考えた安倍元首相の殺害を計画した。というわかりやすいストーリーが想定される。 ところが、ひっかかるのは容疑者の年齢だ。1980年生まれの41歳(事件当時)。ふつうは家や親にわずらわされる年齢ではないだろう。 ただし3年間の任期制で海上自衛隊に入ったのが2002年という就職氷河期世代だということは、無関係ではないという気がする。
2022.12.12
コメント(0)
-
ブログは終わったのか
このブログも更新が滞っているので他人のことを言っている場合ではないのだが、ぼくが定期的に閲覧していたブログの多くが更新されなくなっている。今年に入ってから楽天ブログはアプリでの更新ができなくなった。もうブログの時代は終わり、サービスレベルの低下は仕方ないということなのかも知れない。ブログを始めた時は映画の感想を書くのが主で、しだいに読書の感想や時事問題について書くことが増えてきたのだが、今は思いついた時に更新する程度でジャンルも定まっていない。当然アクセスが増えることもないわけで、このまま止めてしまっても良いようなものなのだが、止める決心もつかないでいる。ようするに更新を止めたわけではないというお知らせでした。
2022.11.19
コメント(0)
-
マイナンバーカード
マイナンバーカードの普及が進まない中で、2024年に健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化することが検討されている。 私はマイナンバーカードを持っていないし、持ちたいとも思わないのだが、実のところマイナンバーカード的なものに必ずしも反対ではない。所得を総合的に把握し適正な累進課税をするためには、個人別番号で管理するしかないと思うからだ。 しかし今進められているマイナンバーカードについてはそのような用途は説明されていない(少なくとも強調されていない)。まるで商品の説明をせずに特典ばかりを宣伝しているような感じだ。そんな商品を信用して買う気にはならない。 強調されるのは保険証や運転免許証と一体化されて便利になるというようなことばかりだ。一体化されると、紛失したとき(あるいは盗難にあったとき)にいずれも使えなくなるということであるし、そこに紐づけられた情報すべてが漏洩する危険性があるというである。 意義を説明せずに健康保険証と一体化という強制手段をとること自体が、推進する側の後ろめたさを表しているように思える。
2022.10.12
コメント(0)
-
ゴルバチョフ死去
ゴルバチョフが亡くなった。ソビエト連邦の共産党独裁を終わらせ、東欧の民主化の端緒をつくったとして、西側からは一定の評価がありながら、当のロシアでは大国ソ連を解体し、経済を混乱させたということで人気がない。しかしゴルバチョフが登場しなくても、ソ連経済は遠からず破綻していただろう。そこから立ち直るのにおそらく計画経済は役に立たず、長い混乱を招くことになったのではないだろうか。ゴルバチョフがソ連(ロシア)経済を破綻させたわけではなく、すでに破綻していたものを白日のもとにさらしただけだと思う。振り返って日本の現状を見る。旧ソ連と比べるつもりはないが、日本の経済も相当悪い状態にある。政府はGDPの倍以上の借金を抱え、その半分を中央銀行が引き受けている。中央銀行が株価を買い支え続けたために、上場企業の大株主になっている。通貨が下落したため国際市場で買い負け、商品調達もままならない。すでに日本経済は破綻しているように見える。今の政権がいつまでも続くわけではないだろう。次を担う政権はゴルバチョフがそうであったように、ずいぶんと重い負債を背負わざるを得ないと思われる。
2022.09.02
コメント(0)
-
映画「MINAMATA-ミナマタ」
Netflixで映画「MINAMATA-ミナマタ」を観た。2年前の劇場公開の時には日程が合わず見逃していた。今、劇場の映画料金は1900円。2回分でDVDソフトが買える。配信サービスも充実してきていることを考えると高すぎる。もちろんポイント還元や各種割り引きがあるので実態を平均すれば1500円を切るのだろうが、それなら割り引きや還元率を下げてでも通常料金を下げるべきだと思う。閑話休題「MINAMATA-ミナマタ」はジョニー・デップが製作主演した作品。水俣病を世界に告発した写真家ユージン・スミスを描いている。ストーリーはわりとありがちな展開をする。報道写真家としてピークを過ぎて厄介者扱いされているスミスが、のちに配偶者となるアイリーンに導かれて水俣に行くところから始まり、被害者家族や住民運動にふれ、暴力による妨害にあいながら写真を発表するまでが描かれている。終盤に有名な写真「貞子と母の入浴」を撮影する場面がある。ここは涙なしには見ることができない。病に侵された娘を抱き抱えて風呂に入れる母の姿が写される。裸を写しているために否定的な意見もあるようだが、水俣病の現実とともに母親の愛情を強く表現した渾身の作品は聖母子像のようだ。
2022.08.29
コメント(0)
-
映画「御法度」
BSで大島渚の「御法度」を観た。新選組に若い美貌の剣士が入隊したことで起きる事件を描いている。閉ざされた男だけの世界ではありがちなことと想像できるが、若い剣士を巡って男同士の鞘当てが起きる。やがて同性愛の相手が殺害される事件が起きる。男同士の三角関係をずっと見せられても退屈なのだが、恐ろしい人間の本性が終盤に明らかにされ感嘆した。主演の松田龍平は映画初出演、ビートたけしもまだ素人っぽいし崔洋一も決して上手くはない。その出演者たちのぎこちなさが、むしろ作品の味になっていると感じる。
2022.08.08
コメント(0)
-
「まがね」64号発行しました
まがね文学会(民主文学会岡山支部)の同人誌「まがね」64号を発行した。第1号の発行は1977年(結成は前年)だが、当時を知る会員は少なくなり、今号の執筆者13人のうち4人は2年以内の入会者になっている。小説は7編。検察審査会というなじみの薄い題材を取り上げた「七月の十三人」(石崎徹)、コロナ禍で閉鎖を余儀なくされた介護施設を描いた「事業所閉鎖」(桜高志)など力作が揃っている。ぼくは昨年亡くなった元会長の諸山立さんの面影を題材にした(ただし完全なフィクション)「思い出酒場」を書いた。購読申込みは会員へ、または「まがね文学会」ホームページのメールフォームからお願いします。
2022.07.31
コメント(0)
-
理屈の後づけはひかえるべき
安倍元首相が銃撃されて亡くなった事件。選挙の最中であり、言論を暴力で封殺することは絶対に許せない。しかし今明らかにされている範囲で言えば、犯人には政治的意図はないようだ。殺された側からすれば、事故のようなものと言ったら語弊があるかも知れないが、安倍さんの無念を思えば、そうとしか言えないように思う。この事件に関して、安倍さんの行いに原因を求めるような言説もあれば、メディアの過剰な安倍批判が原因だとする言説もある。安倍政権がいくつもの疑惑がありながら歴代最長を記録したという事実からして、後者は被害妄想としか考えられないが、前者も憶測の域を出ない。いろいろな場面でぼくは安倍さんを批判してきたし、今でもその考えは変わらないが、今回の事件の原因について後づけであれこれ言うのは間違っていると思うのだ。
2022.07.10
コメント(0)
-
電力自由化
梅雨が早々とあけ、もはや猛暑の様相にある。特に関東では、3月の福島の地震で火力発電所が停止していることもあって電力供給が逼迫している。当然、全国的にも原発の多くは止まっているわけで、電力の逼迫は予想できたことではあるのだが、根本は電力自由化の問題という指摘がある。自由化前であれば、電力会社が余剰設備を抱えても総括原価方式で、電気料金に被せることができた。しかし自由競争となれば当然、余剰設備をできるだけ減らそうとするようになる。その結果が現在だということ。電力自由化の論議が起きたころ、左翼(自称しているからそうなのだろう)の環境活動家(これも言わば自称だが)が、再生可能エネルギー普及のために、総括原価方式をやめて、発送電を分離し、電力自由化すべきだと主張していたことを思い出す。生活の重要なインフラを自由競争に任せるという発想はおかしいとぼくは意見したのだが、すると環境問題に無理解な人間だと決めつけられることになった。それ以来、ぼくは環境問題を声高に叫ぶ人を信用しないことにしている。
2022.06.27
コメント(0)
-
映画「パスカヴィル家の犬」
テレビドラマ「シャーロック」の劇場版。原作コナン・ドイルというクレジットがあるが、テレビ版がそうだったように、アイデアのいくつかを拝借しているだけでほぼ別もの。原作にそっているのは富豪の遺産相続争いがあること、土地に魔犬伝説があること、血縁関係に秘密があること、主人公が名探偵と助手であることぐらいか。別にドイル原作でなくても良いと思える。過去の事件が絡んだ複雑な謎解きはおもしろい。富豪が資産を不自然な場所に隠しているという設定には無理があると思うのだが、そうでなければ事件が成り立たない。これはミステリーにありがちなことかも知れない。
2022.06.19
コメント(0)
-
防衛費
防衛費をGDP比2%に引き上げろと安倍元首相あたりが声高に主張している。モリカケサクラ疑惑から逃げ続けている小心者が何を偉そうに言うか、と思うが、それは置くことにする。2%と簡単に言うが、現在の2倍、10兆円余りである。そもそも税収が60兆円ほどしかない国が戦時でもないのに10兆円以上を防衛費に使うというのは異常だろう。それだけで周辺国の脅威になり得る。世界情勢が悪化しているから、防衛力を強化しなければならないという論理を認めるとしても、何をどれだけ強化するのかが先にあるべきで、それにどれだけ費用がかかるのかは結果としてあること。。防衛費を倍増して自衛官と装備を2倍にするということではないだろう。結局、アメリカの言い値で新しい装備を買わされるための倍増だとしか考えられない。
2022.06.08
コメント(0)
-
誤振込
平日の昼間にテレビをつけていることが多いのだが、ここしばらくワイドショーでは阿武町がコロナ給付金を誤って1人に振り込んだ事件が長時間取り上げられていた。振り込みの間違いから始まり、いったんは返却すると言った男が態度を翻したこと。短期間に口座から大金が動かされ、所在不明であること。その後、『決済代行業者』(これも正体不明)から返金されたことなど不思議なことが多い。結局、わからないことが多く、テレビで「専門家」がしゃべっていることも推測の域を出ない。当然反対の推測を述べるコメンテーターもいたりするのだが、どちらも説得力ある根拠を持っていないため、あからさまに同じ話が繰り返される場合もある。素人が推測で、ああだ、こうだと言い合っている、井戸端会議もしくは居酒屋の放談と同じことが公共の電波を使って行われている構図だ。一方で放送時間を何らかの企画で埋めなくてはならないテレビの側の事情もあるだろう。この手のネタは都合が良いのだろうとも思う。
2022.05.25
コメント(0)
-
映画「流浪の月」
映画「流浪の月」を見た。本屋大賞受賞の原作はけっこう売れているらしいが読んでいない。女児誘拐の罪で服役した男と「被害者」が大人になって再会するドラマ。たとえ女児が望んだとしても家に連れて帰れば誘拐とみなされるだろう。しかし状況を包み隠さず話せば、女児の家庭に問題があることは明らかになり、少なくとも実刑にはならないのではないかと思う。というのは分別くさい大人の理屈であって、現実はそんなものではないのかもしれない。ただ、大人になった「被害者」が婚約者からDVを受けるというのは作りすぎで、かえって平凡な展開にしてしまっていると感じた。終盤に「誘拐犯」が児童性愛者ではないという証拠が示されるのだが、話をきれいに収めるための場面のように見えた。あの場面はない方が人間の複雑さや多様性を考えさせるものになったのではないだろうか。
2022.05.19
コメント(0)
-
映画「シン・ウルトラマン」
「ウルトラマン」の放映が始まったのは、ぼくが4歳の時、というのは調べたからわかることで、その時の記憶がはっきりあるわけではない。ドラマの内容も、薄れた記憶が再放送などで上書きされたものなのだと思う。返還前の沖縄から上京した金城哲夫が脚本を書いていた、ということは大人になってから知ったことで、ドラマ作りに込められた思いなど、当時はまったくわかっていない。閑話休題「シン・ウルトラマン」を見た。「ウルトラマン」を知っているか否かは関係なく見られるようになっている。それはシリーズの約束ごとが必ずしも踏襲されていないからでもある。約束ごとを無視したようなゾフィーのふるまいはオールドファンを逆撫でするのではないかと思う(少なくとも僕の気持ちは逆撫でされた)。ただ約束ごとはないものとして、異星人(作品では外星人と呼んでいる)が地球をめぐって争う物語だと思えば、あり得ない展開ではなく、むしろリアルだと言えるかもしれない。一方で、禍特対(科特隊ならぬ)が本部から現場へあっという間に移動したりなどリアリティに欠けるというよりも手抜きのように思えるところもある。CGは素晴らしいし、役者もうまい。あまり理屈っぽく考えずに見るべき作品かも知れない。
2022.05.19
コメント(0)
-
作品のタイトル
同人誌の編集をしている。PDFで版下を作るところまでやるのだか、初めてのことなので取り掛かりから試行錯誤している。ただ前任者が細かい手引を作ってくれているので、暗中模索というほどでもなく、何とかなりそうではある。先日は提出した作品のタイトルを考えてくれ、という同人がいて困った。考えた末に見てくれの良いタイトルを思いついたのだが、果たして作者が作品に込めた意図に合っているのかわからない。まあ、書いた本人にも意図がはっきりしないからタイトルがつけられないのだろう、と思うことにする。自分が小説を書く場合、ほぼ先にタイトルを決めている。最終的に変える場合もあるのだが、一応はタイトルの持つ感覚にそって書く。書き終わってからタイトルを変えた場合は、全体を見直してタイトルの持つ感覚に外れていないかを点検する。と、えらそうなことを言っているが、タイトルをつけるのはあまり得意ではない。格調あるタイトルなど思いつきもしないのである。アメリカン・ニューシネマ時代の映画で「明日に向かって撃て」「夕陽に向かって走れ」という作品がある。原題を直訳すると前者は「ブッチ・キャシディーとサンダンス・キッド」、後者は「ウィリー・ボーイはここにいると伝えろ」であり、昔はよくあった配給会社が興行的につけたタイトルだ。どちらもロバート・レッドフォードとキャサリン・ロスが出ているので、前者のヒットにあやかって後者のタイトルがつけられたのだと思う(ただし実際の公開時期はあまり違わない)のだか、特に後者は作品内容にあっていない。そんなタイトルをつけられた作品は不幸だという気がする。
2022.05.10
コメント(0)
-
暴力はいけない
アカデミー賞授賞式でウィル・スミスがプレゼンターに平手打ちした件。妻の病気をネタにされたことに怒っての行動にはある種のかっこよさを感じた。余談だが、平手打ちする姿が絵になるのもさすがにハリウッドスターだと思った。いや、やはり暴力はいけない、と思い直したのはそのちょっと後のことだ。もちろん暴力はいけない。世論もどちらかと言えばウィル・スミスに厳しいように見える。中にはロシアのウクライナ侵略になぞらえて批判する向きもある。だが、ウクライナは先にロシアを攻撃してはいない。件のプレゼンターは、意図したかどうかは別にして、攻撃したのだ。ロシアは民間施設をも攻撃対象として、民間人を含む多数の死者を出している。件のプレゼンターは負傷してもいない(それどころか公演チケットが高騰しているという話もある)。暴力はいけない。それは間違いではない。しかしすべての暴力を同列に論じるのは間違っていると思う。
2022.04.03
コメント(0)
-
「値上げしない」への懸念
今日の新聞に、イオンが自社ブランドのトップバリュ5000品目について6月末まで値上げしないと全面広告を出している。原油や小麦価格の高騰があって2月ごろから値上げの動きが目立っていたが、ウクライナ情勢の悪化によってさらに値上げが加速しそうな中で、2カ月とは言え、値上げしないと表明するのは市場に影響を与えるかもしれない。消費者としては歓迎したいところだが、懸念もある。上方硬直性という言葉が正しいのかわからないが、欧米と比べると日本の物価は上がりにくい。円安傾向の中で原価の値上がりは欧米よりも大きいと思われるにもかかわらずである。原価が上がっているのに販売価格が上がらないのは、下請けや労働者にしわ寄せしているからではないか。下請けいじめが欧米より酷いか否かは比較しようがないが、賃金が30年前から上がっていないことは事実であるし、大企業の利益が減っていないのも事実だ。「値上げしない」を素直に受け止めることができないのは、天邪鬼だからだけではないと思う。
2022.03.24
コメント(0)
-
核共有(ニュークリア・シェアリング)にあきれる
核兵器保有国であるロシアがウクライナを侵略したことを受けて、安倍元首相や維新の会あたりから、日本も「核共有」をすべきだという主張が出ている。ウクライナが核兵器を持っていればロシアは侵略できなかったはずだ、という理屈のようだ。どう考えても核戦争に勝者はいない。桁外れの死者と放射能汚染しか残らない。だからこそ核兵器は廃絶すべきである。しかし核保有国は単純には核兵器を手ばなさない、という現実の下で多くの国がギリギリ妥協したのが「核拡散防止」だ。ソ連時代に配備されていた核兵器がウクライナから撤去されたのも「核拡散防止」の為だった。核兵器の保有を米露英仏中の5カ国には認め、その他の国が保有することを禁じるという不公平を合理化する理屈があるとするならば、5カ国なら核兵器を理性的に管理することができるということしかない。そのうちのロシアが核兵器による威嚇を隠すこともなく、ウクライナを侵略しているのだから、この理屈は成り立たない。このことからも必要なのは核拡散防止ではなく、核廃絶であることは明らかだ。少なくとも削減をめざすべきだ。核保有ではなく「核共有」と目先を変えても新たな核配備であることに違いはない。こんな時に戦争被爆国である日本の政権党や主要政党から核拡散防止すらも踏みにじる発言が出ることに怒りというよりもあきれてしまう。
2022.03.05
コメント(1)
-
殺すな
たとえ声が届かないとしても僕は言い続ける殺すな
2022.02.26
コメント(0)
-
映画「ドライブ・マイ・カー」
アカデミー賞にノミネートされたためだろうが、封切時に上映していなかった映画館で上映していたので観た。(封切時には時間が合わなかったので観ていない)上映時間がほぼ3時間あり、とにかく長い。長いから映画館としてもプログラムを組みにくいのではないだろうか。今回もあまり良いとは言えない時間帯での上映だった。村上春樹の原作は単行本で49ページの短編。原作に忠実に映像化(可能かどうかは別にしてだが)すれば1時間半程度に収まるのではないだろうか。原作からの変更点はいくつもある。細かいことでは、車が黄色のコンバーチブルから赤のサンルーフ車になっていたりする。原作では主人公の家福が酒気帯び運転で事故を起こし、緑内障による視野欠損の疑いもあるため運転が禁じられたことで運転手を雇う。映画では家福が演出する演劇祭の主催者が、事故によって演出家が離脱することを避けるために運転手をつけるという設定に変更されている。しかし演出家にだけ運転手をつけるというのは不自然だ。実際、家福は東京から演劇祭の開かれる広島まで車を運転している。また役者の一人が稽古期間に事故を起こす。東京都内で展開する原作を広島での物語に変えるために捻ったのだろうが、そんな原作からのいくつかの変更が無理を感じさせる。広島に舞台を変えた意図もよくわからなかった。作品全体としては人間の多面性を描いているのだと思う。その点は共感する。また運転手を演じた三浦透子はなかなか魅力的だと感じた。
2022.02.20
コメント(0)
-
まず手洗いを
新型コロナの流行で、外食の機会が減った。特に酒を外で飲むということはまったくなくなった。 それでもたまには外食をすることがある。 ほぼすべての店で求められるのが手の消毒なのだが、手を洗わずに消毒することに気持ち悪さを感じる。意味がないとは言わないが、手の汚れ具合によっては効果がかなり落ちるだろう。手を洗って乾かしたあとにアルコール消毒をするのでなければ、きちんとした効果は得られないはず。 入口に手洗い場所を作るような水回りの変更は簡単ではないから、仕方なくやっているのだろうけど。
2021.08.09
コメント(0)
-
東京オリンピック
賛否両論というより世論の過半数が反対する中で東京オリンピックが始まった。 安倍前首相が雑誌の対談で「反日と言われるような」人たちが反対していると発言していたらしい。しかし開催直前の世論調査でも6割以上が反対していた。安倍さんは事実から物事を判断する能力を持たず、思い込みだけで発言する人なのだろう。 オリンピックが始まれば、それなりに盛り上がる。「反対していたのに盛り上がるのはおかしい」という批判もある。 しかし、多くの国民はオリンピックが嫌いだから反対していたわけではない。オリンピックは見たい。しかしコロナパンデミックが危惧される現状で開催すべきではない、という極めてまともな反応をしていたのだ。 だから反対していた人たちがオリンピックで盛り上がったとしてもおかしなことではない。
2021.08.01
コメント(1)
-
リモート会議
以前もリモート会議というのはあったのだが、コロナ禍でZOOMによるリモート会議がすっかり定着してきた感がある。 そこでコロナ禍が終息してもリモートは活用すべきだという意見も出てくる。確かに地理的に離れていても会議に参加できるというのは大きなメリットだと思う。 一方で集まることによって得るものは多いという意見もある。確かに雑談などから大切なことを知ったという経験は少なくない。 おそらくコロナ後には会議の性格や地理的な条件によって使いわけることになるのだろう。 ところで現状のリモート会議は旧来のものをそのままリモートで行なっていることが多いように思う。人数が多くなく、ある程度気心が知れた関係ならそれで構わないとも思うのだが、閉鎖空間で集中せざるを得ない状況で行われる会議とリモート会議ではやはり条件が違う。映像作品に例えると、閉鎖空間である映画館向けと家庭のテレビ向けでは違うものになるはずである。 時間の短縮、議題の整理など検討すべきことが多いと思う。
2021.07.31
コメント(0)
-
緊急事態条項
加藤官房長官が、コロナ禍が憲法に緊急事態条項を創設する論議をすすめる「絶好の契機だと考える」と発言したという報道があった。 国民が苦しんでいる状況を「絶好の契機」と表現するセンスがこの国の政府のレベルを示している。 もとより問題なのは憲法ではなく、政府の能力であることを明らかにしたのが昨年からの事態だ。 新型コロナ感染症が広がり始めた時の安倍首相の狼狽ぶりは、いつもの勇ましい言動がいかに薄っぺらな虚勢によるものであったかを明らかにした。 狼狽したあげく、専門家の意見を聞かずに学校を休校にしたり、布マスクを配ったりしたが、前者は少なくともその時点では百害あって一利なしであったし、後者は「アベノマスク」と揶揄され、発注先への疑惑もある。 政府が適切な対応ができなかったのは緊急事態条項がないからではなく、緊急事態に対応できる能力がないからだろう。 結局、安倍首相は体調を崩して退陣する。体調のことについては同情する気持ちもあるが、体調不良による退陣は二度目でもあり、彼のストレス耐性の弱さを表しているだろう。 今の菅首相にしても、虚ろな態度で、野党やメディアからの質問をはぐらかすことで何とか精神のバランスを保っているように見える。 この人も緊急事態に直面して決断や行動ができる器ではないだろう。 それを憲法のせいにするのは筋が違う。
2021.06.12
コメント(1)
-
後悔
携帯電話が鳴った 諸山立、と表示された 嫌な予感がしたのかどうか 覚えていない 着信ボタンを押した 声がよく聞こえない いつも聞き取りやすい声なのに よく聞こえない それだけで異常事態だと感じる 医者に危篤と言われた 肺がん 断片的な言葉で事態を理解した がんばってください 的はずれな言葉しか出てこない こんなこと言われて あなたも困るよな 優しい気づかいに 言葉が返せない 三日後に訃報が届いた あの時、ぼくが言うべきことは たったひとつだったのに ありがとう その一言だったのに
2021.04.07
コメント(0)
-

「醤油・味噌・酢はすごい」小泉武夫
醤油・味噌・酢はすごい 三大発酵調味料と日本人 (中公新書) [ 小泉武夫 ] 著者は農学博士で、専門は醸造学、発酵学、食文化論と奥付にある。 醸造、発酵に関する記述は興味深いが、本書の重点は食文化にあるようだ。 確かに醤油、味噌、酢が生まれなければ日本食は成り立たなかっただろうが、本書を読むとそれがある時に奇跡的に生まれたわけではなく、あちらこちらで散発的に作られ、淘汰、発展してきたものだとわかる。 ただ、情緒的な記述や素人にもわかる間違いが散見され、あまり厳密さを求めたものではない印象を受ける。食文化に関する部分は著者の偏愛を吐露したものと思った方が良いだろう。 味噌と酢について、保健的機能性という項目で身体への効果に触れている。 発酵食品だから身体に良い、という乱暴な話ではなく、各成分がどういう働きをするのかを書いている。エビデンスはあやしいが一般に言われているようなことでもある。 しかし人間の身体は複雑なのであまり単純化するわけにはいかないのではないか。例えば本書で味噌に含まれるリノール酸がコレステロールを下げると紹介しているが、現代の食生活ではリノール酸を取りすぎているという説もある。やはり重要なのはバランスなのだ。 またコレステロールに関してはHDLをHLDと間違えて表記しているところが気になった。 保健的機能性云々に関して、著者は専門外なのだろう。
2021.03.20
コメント(0)
-
発酵食品は健康に良い?
発酵食品は健康に良いとか、発酵食品だから健康に良いとか、マスメディアでよく言われる。 特定の食品が健康に良いなどあり得ないと前の記事で書いたが、発酵食品は特定の食品ですらない。 納豆、テンペ、ヨーグルト、味噌、醤油、酢、酒、紅茶、烏龍茶、鮒寿司、世界一臭い食べ物と言われるシュールストレミングも発酵食品であるし、味の素(うまみ調味料)も発酵によって作られている。世に発酵食品は数えきれないほど存在するのだ。 「発酵食品は健康に良い」というのはこれらを一括りにして、健康に良いと言っているようなものだ。 その伝でいけば、酒は発酵食品だから健康に良いとか、味の素(うまみ調味料)は発酵食品だから健康に良い、などということもできる。(味の素ほどの企業がそんなバカなことは言うわけはないと思うが) もし「〇〇は発酵食品だから健康に良い」という宣伝をしていたら、疑った方がいい。 食品で健康を保つ方法は、栄養バランス良く、適量を食べるということにつきる。加えるなら規則正しくということぐらいだろう。 ところが、そんな真っ当なことを言ってもウケない。〇〇が健康に良いと単純化した方が本は売れるし、視聴率は取れる。だからいつまで経っても、怪しげな健康情報は尽きない。 ちなみに僕個人のことで言えば、納豆は20年以上、ほぼ毎日食べている。ヨーグルトを毎日食べるようになったのは2年ほど前からだが、発酵食品だからと思って食べているわけではない。
2021.03.14
コメント(0)
-
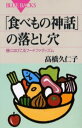
健康情報
健康に不安がない人はあまりいないだろう。そのため世の中に「健康に良い」という情報はあふれているし、次々と更新されている。 かつてフジテレビ系列で「あるある大事典」という番組があった。何かが健康に良いとかダイエットに良いとか番組が取り上げるたびに商品が売り切れるという異常事態が起きた。 食品以外にもマイナスイオンが身体に良いというのもこの番組が言い出したこと。鉱石のトルマリンや観葉植物のサンスベリアがマイナスイオンを出すなどと紹介し、宝石的価値のない安物のトルマリンが高値で売れたり、サンスベリアが欠品になったりした。そんなことはあり得ない(そもそもマイナスイオンとは何かも明らかにされていない)のだが、まともに批判する人も多くはなく、今でも滝のそばなどに行くと「マイナスイオンがたっぷりで気持ちいい」などと使われたりする。 食品の話に戻るが、そもそも特定の食品が健康に良いということなどありえないので、ほぼ全部が嘘だと推定できる。 ある食品が健康に良いと注目されて爆発的に売れる状況を、群馬大の高橋久仁子名誉教授はフードファディズムと批判したが、専門家の多くは、こんな現象があまりにアホらしいのでコメントしない。 そのせいでもあると思うのだが、件の番組のインチキが露呈して打ち切りになった後も、テレビ番組が健康に良いと取り上げるたびに、その商品がバカ売れするという現象は起きている。 ある食品が特定の人の健康のために良い、ということはあるだろう。しかし、栄養状態は人によって違うし、血圧が高い人もいれば低い人もいる。血糖値が高い人もいれば低い人もいる。皮膚や腸内の常在細菌などは千差万別だろう。それを無視して、健康に良いなどと言えるわけがない。 今どき「ヘルシー」と言えば低カロリーの食品を示すことが多い。しかし明らかに痩せすぎで栄養失調気味と見える人までが、それをありがたがる現実があることに、僕はぞっとする。 「食べもの神話」の落とし穴 巷にはびこるフードファディズム
2021.03.13
コメント(0)
-
映画「記憶にございません」
三谷幸喜作品を録画で鑑賞。 コメディに細かいことは言わない方が良いかもしれないが、総理大臣が病院を抜け出すのをSPが逃してしまうという件は、何らかの仕掛けが必要だと思う。 ただ、記憶を失った総理大臣が、消費税を下げるために法人税を上げればいい、とか当たり前の感覚を持つようになる展開はおもしろい。 当たり前のことが通らない今の政治を皮肉っているのだろう。
2021.03.11
コメント(0)
-
映画「すばらしき世界」
西川美和監督の新作。 前科10犯で人生の大半を刑務所で過ごした男(役所広司)が刑期を終えて出所する。身許引受人の弁護士夫婦に助けられながら社会復帰をめざす物語。 暴力団と刑務所しか知らず、身体は年相応に弱り、高血圧を患っている男が社会に溶け込むことの困難はわかる。親身になってくれる弁護士夫婦、野心的なテレビマン、テレビ界からドロップアウトしたお人好しの作家、仕事熱心でまじめなケースワーカー、人の良いスーパーの店長など彼を取り巻く人物配置がうまく、当て書きなのかも知れないが配役もこれ以上ないほどはまっている。 世の中そんなに悪いことばかりじゃない、と希望を抱かせてくれるが、そんなに甘くもないということも忘れさせない。そんな作品だった。
2021.03.07
コメント(0)
-
映画「ファーストラヴ」
直木賞を受賞した原作は未読だが、始まってから30分ほど経ったところで、知っている話だと気がついた。 後で調べたらNHKがBSでドラマ化しているので、それを観たことがあるようだ。 (一応ネタバレを避ける) ちょっと不自然な事件で、関係者の言動も理解しにくいところがある。そこを納得させるのが脚色や演出なのだが、そこがうまくいっていないと感じた。原作がどう描いているかは知らないし、NHKのドラマがどうだったかも覚えていないので比較することはできないが、事件を謎めかせる(ややこしくする)仕掛けが過剰ではないかと思った。 作品は事件とともに、心理士の女性と兄弟の三角関係を描いている。そこのバランスの問題のような気もするが、だとしたら観る側の受け取り方しだいなのかも知れない。
2021.03.06
コメント(0)
-
「人新生の『資本論』」
斎藤幸平「人新生の『資本論』」を読んだ。 環境危機を解決するためには脱成長経済が必要だという主張には一理あると思う。資本主義では駄目で、成長を前提とする史的唯物論に立脚するマルクス主義でも駄目だという指摘も、その主張から導かれるものとして理解はできる。 そこで斎藤氏は晩年のマルクスが史的唯物論を否定して脱成長を考えていたのだと言う。 文献にあたる能力のない僕は「そうなのか」と思うしかないのだが、結局マルクス主義ではないところのマルクスの考えに従うべきだというのが本書の主題になるのだろう。(つまり、いわゆるマルクス主義は完全否定される) そうすると、そもそもマルクスにこだわる意味があるのかと疑問に思うのだが、めざす方向性として所有の問題に言及しているところにこだわりの意味があるのかもしれない。 しかし所有形態が変わっただけで物事はうまくいかない、ということは旧ソ連を見るまでもない。協同組合的なものも規模の拡大などによってやがて企業化するということも明らかなことだ。 環境問題の解決に、脱成長という方向があるということは理解できる。しかし脱成長などと言えるのは先進国である程度裕福な層に属する人だろう。それより貧しい層は経済成長を欲するはずであるし、そのために公正な市場を求めるはずだ。 環境問題の解決には脱成長が必要と考えることは、環境問題の解決は不可能だと言っているようなものではないか。
2021.01.16
コメント(2)
-
コメントについて
このブログのコメント欄は承認制にはしていません。 管理人が不快に感じるコメントがあったとしても、削除することは"今のところ"していません。 ご承知おきください。
2020.11.21
コメント(0)
-
さよなら
美人で才能があるのに、おとなしくて控えめな女の子。若い頃、自意識過剰な僕はそんな女の子には声をかけられなかった。年をとって少し恥知らずなことができるようになっても、やはり意識してしまってうまく話せない。旭爪あかねさんはそういう人だった。 僕が民主主義文学会に加入した頃、若手グループには渥美二郎さんや横田昌則さんといった才能のある人たちがいて、旭爪さんは浅尾大輔さんとともにそのトップランナーだった。 その後、僕が「まがね」に発表した「瓦解」という民主文学にしては変わった作品を評価して、「民主文学」に転載してくれたり、全国研究集会の分科会で取り上げたりしてくれたのが旭爪さんだった。 倉敷で開催した中国地区研究集会に講師として来てもらったこともある。 いろいろお世話になったのに、きちんとお礼を言ってなかったような気がする。訃報から一週間近くたってそんなことを思っている。 ありがとうございました。 そして、さよなら。
2020.11.13
コメント(2)
-
アメリカ大統領選挙
ようやく次のアメリカ大統領が決まった。トランプ大統領は開票作業に難癖をつけ続けているが、騒げば騒ぐだけアメリカ合衆国を貶めているのだと気がつかないのだろうか? 「馬鹿につける薬はない」と日本流に言っておこう。 4年前の大統領選挙でトランプが勝つとは思わなかった。トランプを選ぶことは彼の国の利益にならないのは明らかだからだ。トランプが大統領になって経済は良くなった(経済は様々な要因が絡むのでトランプのおかげかどうかはわからない)かも知れない。しかし差別と分断が進み、人権と地球環境を軽視したアメリカの国際的な地位は後退した。 バイデンには独自性が見えない。副大統領になるハリスの方が魅力的にも思えたりもする。それでも常識的な選択であることは間違いない。
2020.11.09
コメント(0)
-
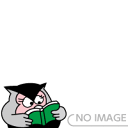
「眩 くらら」朝井まかて
本作を3年ほど前にNHKが単発でドラマ化している。主人公は葛飾北斎の娘、お栄(葛飾応為)。ドラマの印象が強く残っているため、頭の中で宮崎あおいに置き換わってしまう。 文庫で400ページを超える長編であり、当然ドラマでは大幅にカットされているのだが、うまくまとめていたと思う。(もっとも原作を先に読んでいたら、あれもこれも描かれていないと不満を持ったかも知れないが) 火事と聞いてお栄が走り出す。その疾走感のまま、物語が展開していくのが気持ち良い。 オランダ人医師に納入する注文絵の出来に不安を隠せない弟子たちを北斎は「三流の玄人でも、一流の素人に勝る」それは恥をしのんで作品を「世間の目に晒す」からだと叱る。職業絵師としての北斎の矜持を表している。 かつて妻ある身と知りながら恋に落ちた善治郎との別れの場面が切ない。 眩 新潮社 朝井まかて / 【中古】afb
2020.11.08
コメント(0)
全538件 (538件中 1-50件目)
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 購入|「THANK YOU SO MUCH (完全生…
- (2025-02-22 20:18:46)
-
-
-
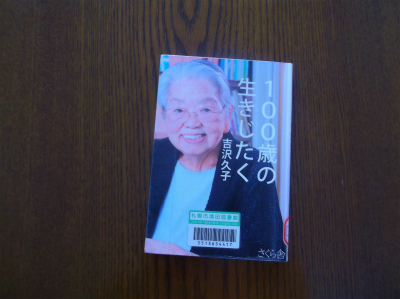
- 本のある暮らし
- 吉沢久子「100歳の生きじたく」/肉ま…
- (2025-02-22 05:18:11)
-
-
-

- 楽天ブックス
- ★【サンプル画像】 #今森茉耶1st写真…
- (2025-02-25 18:37:08)
-