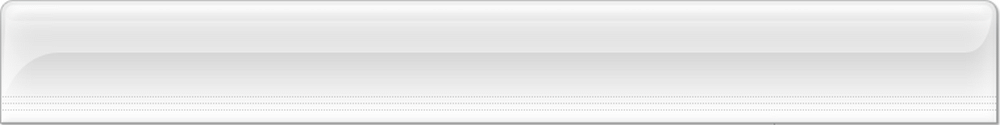カテゴリ: 病気についてあれこれ
日経新聞速報
すごいすごい。良いなぁ!
どうかうまくいきますように。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
iPS細胞で心臓治療了承厚労省、阪大に条件付きで
2018年5月16日 12:32
厚生労働省の専門部会は16日、大阪大学が申請していたiPS細胞を使った心臓病の臨床研究計画を条件付きで了承した。阪大は2018年度中に患者への治療を始め、1年かけて安全性や効果を調べる。iPS細胞による再生医療は14年に始まった目の難病に続く。心臓病は命にかかわる病気で治療のハードルは高いが、実現すればiPS医療は新たなステージに入る。
計画は阪大の澤芳樹教授らが3月、厚労省に申請した。有識者を集めた再生医療評価部会で16日、臨床研究の手順や安全性を確認。対象となる患者の選定基準をすでに実用化されている再生医療製品とそろえるなどの条件をつけた上で、了承した。今後、厚労相が認めれば治療が始まる。
臨床研究の対象は、血管が詰まるなどで心臓の筋肉(心筋)に十分な血液が届きにくくなる「虚血性心筋症」で重症心不全になった患者3人。
心不全は心臓の機能が低下し、息切れをしたり疲れやすくなる病気。日本人の死因では第2位に入る。重症だと補助の人工心臓や心臓移植で置き換える。だが、人工心臓は合併症などのリスクがあり、心臓移植は提供者(ドナー)の数が少ない問題がある。
iPS細胞を使った心臓治療の臨床研究計画を審議する厚労省の部会を終えた阪大の澤芳樹教授(16日午前、東京・霞が関)
阪大の治療で十分な効果が確認できれば、こうした課題の解決につながる可能性がある。5年後をメドに一般的な治療としての普及を目指す。
iPS細胞による臨床研究は、理化学研究所が14年9月に目の難病である「加齢黄斑変性」の患者で世界で初めて実施した。心不全は患者の生命に関わる病気のため、目の病気に比べハードルが高い。心臓の治療には大量の細胞が必要になるうえ、目のように外から直接経過を観察できない。
患者本人ではなく他人の血液から作ったiPS細胞を使うため、移植した後に拒絶反応が起こらないよう免疫抑制剤を使う必要がある。万が一、細胞ががん化したときの処置も難しい。
iPS細胞による治療は今後、パーキンソン病や脊髄損傷などでも計画されている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
下垂体チームもがんばれー!
すごいすごい。良いなぁ!
どうかうまくいきますように。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
iPS細胞で心臓治療了承厚労省、阪大に条件付きで
2018年5月16日 12:32
厚生労働省の専門部会は16日、大阪大学が申請していたiPS細胞を使った心臓病の臨床研究計画を条件付きで了承した。阪大は2018年度中に患者への治療を始め、1年かけて安全性や効果を調べる。iPS細胞による再生医療は14年に始まった目の難病に続く。心臓病は命にかかわる病気で治療のハードルは高いが、実現すればiPS医療は新たなステージに入る。
計画は阪大の澤芳樹教授らが3月、厚労省に申請した。有識者を集めた再生医療評価部会で16日、臨床研究の手順や安全性を確認。対象となる患者の選定基準をすでに実用化されている再生医療製品とそろえるなどの条件をつけた上で、了承した。今後、厚労相が認めれば治療が始まる。
臨床研究の対象は、血管が詰まるなどで心臓の筋肉(心筋)に十分な血液が届きにくくなる「虚血性心筋症」で重症心不全になった患者3人。
心不全は心臓の機能が低下し、息切れをしたり疲れやすくなる病気。日本人の死因では第2位に入る。重症だと補助の人工心臓や心臓移植で置き換える。だが、人工心臓は合併症などのリスクがあり、心臓移植は提供者(ドナー)の数が少ない問題がある。
iPS細胞を使った心臓治療の臨床研究計画を審議する厚労省の部会を終えた阪大の澤芳樹教授(16日午前、東京・霞が関)
阪大の治療で十分な効果が確認できれば、こうした課題の解決につながる可能性がある。5年後をメドに一般的な治療としての普及を目指す。
iPS細胞による臨床研究は、理化学研究所が14年9月に目の難病である「加齢黄斑変性」の患者で世界で初めて実施した。心不全は患者の生命に関わる病気のため、目の病気に比べハードルが高い。心臓の治療には大量の細胞が必要になるうえ、目のように外から直接経過を観察できない。
患者本人ではなく他人の血液から作ったiPS細胞を使うため、移植した後に拒絶反応が起こらないよう免疫抑制剤を使う必要がある。万が一、細胞ががん化したときの処置も難しい。
iPS細胞による治療は今後、パーキンソン病や脊髄損傷などでも計画されている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
下垂体チームもがんばれー!
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[病気についてあれこれ] カテゴリの最新記事
-
成長ホルモンの新薬 February 10, 2022
-
男性ホルモン補充とエムラパッチ January 5, 2020 コメント(3)
-
hcgとFSHの補充開始 July 27, 2018
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Comments
© Rakuten Group, Inc.