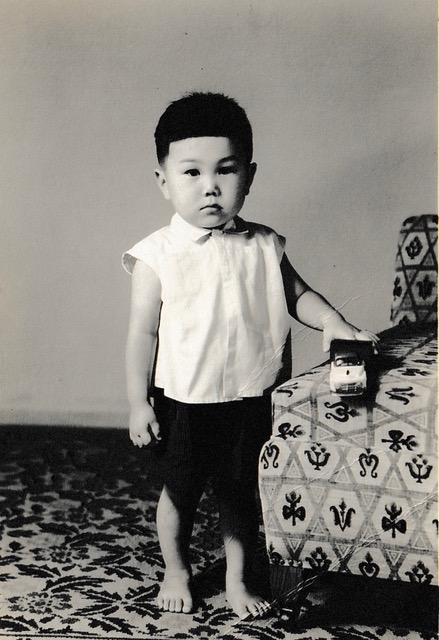カテゴリ: ファッションビジネス
大学2年の冬、私は父の勧めで老舗テーラー山形屋の子会社、紳士服マスマーチャンダイジングのギンザヤマガタヤ取締役竹田勲さんを表敬訪問しました。当時竹田さんは米国ショッピングセンターの情報通であり、洋服店のチェーンオペレーションを指導していました。竹田さんとの出会いが、ロンドンのサビルロー修行をニューヨーク移住に進路変更し、私が家業のテーラーを継がなくなったきっかけです。
ギンザヤマガタヤ応接室で竹田さんを待つ間、これまで見たこともない繊研新聞という新聞ファイルが目に留まりました。新聞タイトルの下に問い合わせ電話番号の表記、それをメモして翌日購読を申し込みました。ここから私と繊研新聞の長い付き合いが始まります。1974年正月明けのことです。
その3ヶ月後学生ファッション研究団体F.I.U.を設立、大手繊維会社ユニチカからマーケティング調査の委託を受け、年に4回調査データから読み取った若者の生活価値観や消費行動の変化をユニチカ幹部と共に記者発表するようになります。大型コンピューターからアウトプットしてもらった数字の羅列、これと睨めっこしながら変化の兆候を読み取る、結構楽しい作業でした。私はメディアにデータを詳しく説明したりインタビューを受けたり、時にはマーケティングレポートを寄稿しました。購読し始めた繊研新聞はアパレル業界担当の松尾武幸デスク、織田晃ファッション担当記者、営業担当古旗達夫さんと交流が始まりました。
渡米後サラリーも原稿料の類いも送金されない状態を見かねた男子専科志村敏編集長は、ニューヨーク特集号を制作するという名目でわざわざ様子を見に来てくれました。そして繊研新聞と通信員契約を結ぶようアドバイス、繊研とは東京で交渉してくれました。志村さんから話を聞いた松尾デスクは社内上層部の了解を取りつけ、そこから引き上げるまでの7年半私は繊研新聞特約通信員として現地デザイナーや市場変化などをレポート、年2回帰国してニューヨークセミナーを担当しました。セミナー開催は帰国の機会を与えてやろうという松尾さんの親心です。
繊研新聞で記事を書き始めると今度は紳士服見本市NAMSB展を主催する全米紳士スポーツウエアバイヤー協会から日本担当マーケティングディレクターを委託され、米国商務省が提唱する「バイ・アメリカン運動」の推進を手伝うことに。私の役目は日本のバイヤーのNAMSB展視察者を増やし、視察者に米国市場の方向性をセミナーで伝え、対日輸出をアップすることでした。
この関係で日本側の窓口になってくれたのが繊研営業部の古旗さんです。日本での米国視察者集めのほか、繊研も独自にニューヨーク視察ツアーを企画、そのツアコンまで自ら担当。ほかにも米国商務省が東京で仕掛けるイベントなどを古旗さんがあたかも事務局スタッフのように支援しました。おかげで米国商務省や大使館から繊研新聞への広告出稿は増え、私の通信員契約分以上の収益が繊研新聞社にもたらされました。
年2回の繊研ニューヨークセミナー以外にも私の東京出張はシーズン追うごとにどんどん増え、気がつけば年5回も帰国するようになりました。その中にはNAMSB絡みもあればバーニーズニューヨークの買い付けもあり、帰国するたび松尾さんと古旗さんは歓待してくれました。午後5時に日本橋浜町の小料理屋に始まり、人形町の居酒屋などを回ってその後銀座へ、全部で5つの店をハシゴして帰宅したのは午前5時、いま思えばよく身体がもったなあという飲み会もありました。
古旗さんが業界人のツアーを引率してニューヨークに到着したシーズン、松尾さんもパリからニューヨーク入り、連日深夜まで飲み歩きました。このとき松尾さんのホテルの部屋で1枚60文字の専用原稿用紙にものすごいスピードで記事を書く松尾さんにびっくりしました。それまでの私は読者が記事を読む場面を想像してしまい、どうしても慎重になって何度も書き直し、時間をかけて原稿を仕上げていました。
まるで速記者のようなスピード、松尾さんに訊ねました。読者のことをいちいち気にしていたらスピードは落ちる。新聞記者には輪転機の締め切り時間があるので作家みたいにのんびり原稿を書いていられない。事実を素早く正確に読者に伝えるのが新聞記者の使命、と。それまで400字原稿用紙1枚書くのに1時間も費やしていた私でしたが、松尾さんの姿を見てからは1時間もあれば原稿用紙4枚は書けるようになりました。
ブログやSNSで私と繋がっている多くの方から「太田さん、原稿を書くのがはやいですね」とよく言われますが、それは松尾さんから学んだからでしょう。学生時代、私は男子専科の志村編集長から「最初に結論を書き、起承転結をしっかり組み立てなさい」と雑誌の特集記事の書き方を教わりましたが、松尾さんからはニュース原稿を書くスピードも重要と学びました。

(私の手前が松尾武幸さん)
繊研新聞ニューヨーク通信員として業界で認知されると、ニューヨーク出張時に私に会いたいという申し出が編集部や営業部に来るようになり、直接私に国際電話してくる人も出始めました。それを全部受けていたら仕事になりません。そこで、松尾さんが選んだ人だけは面談あるいは会食するとルールを作ってくれたおかげで助かりました。
松尾さんの一番の助けは、私の書いた記事に対するクレーム対応でした。直球勝負で正直にコレクション記事や見本市取材記事を書くと、米国ブランドと提携する日本企業やショーを開いたブランド企業、ときには大臣秘書官を名乗る人からも、「あいつを通信員から外してくれ」、「今後繊研には広告を出さない」とたびたびクレームが入りました。
しかし、松尾さんを筆頭に繊研新聞社の幹部は「太田が書いた記事は間違っていますか」、「通信員から外すかどうかはうちが決めること」といつも突っぱねてくれました。帰国するたび、「太田くん、こんなクレームが◯◯社から来てたよ、ガハハッ」と大笑いしながら話してくれましたが、松尾さんがガードしてくれなければストレートなコレクション記事は掲載されなかったでしょう。
1985年5月ニューヨークコレクション最終日翌日、繊研ニューヨークセミナーのために帰国した私に東京ファッションデザイナー協議会設立の話が持ち上がり、松尾さんには相談しました。このとき「業界の発展とキミがやりたいことが先だ、繊研の後任通信員のことは心配するな」と応援してくれました。そして同年7月デザイナー協議会が正式に発足すると、真っ先に仮オフィスに陣中見舞いに来てくれたのは松尾さんと古旗さんでした。
2009年12月、競馬の有馬記念の朝、松尾編集局長にかわいがられた朝日新聞編集委員高橋牧子さんから「ご存知かもしれませんが、松尾さんの葬儀が今日あります」と電話が入りました。繊研を退職してかなり時間が経っていたので、ひょっとして連絡が私に届いてないのではと心配して高橋さんが教えてくれたのです。慌てて電車に飛び乗った私は天国に旅立つ恩人の導きと語呂合わせのつもりで「ドリームジャーニー」(夢の旅)の馬券をスマホで注文、なんと馬券は当たりました。きっとあの世でいつものガハハッ顔でいまも見守ってくれていると思います。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.11.18 15:30:45
[ファッションビジネス] カテゴリの最新記事
-
かつてお手本企業のいま 2024.06.22
-
交友録83 世間は狭い 2024.06.08
-
黎明期日本流通業を彷彿させる 2024.06.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.