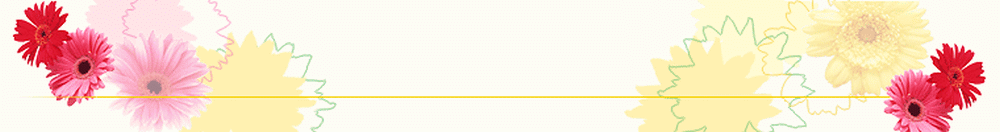PR
X
フリーページ
カテゴリ: カテゴリ未分類
2012年7月
「みおつくし」8月号「平成新聞」8月号原稿より
執筆 新田論
平成新聞社説
アメリカ経済の状況は一向に改善する気配がない。
社会的な問題も山積している。
国債発行限度額引き上げを巡る党派の争いはひどいものだ。
かつてのような輝きをアメリカ社会は失いつつあり、崩れつつあるアメリカン・ドリームについてある報告が発表された。
白人と黒人、ヒスパニック系アメリカ人の所得格差が過去最大にまで拡大したというものである。
額は1万2124ドルであった。
一方、2009年には白人の純資産額は11万3149ドルと減少しているが、これは金融危機による株安や住宅価格の下落が響いているからである。
これに対してヒスパニック系の家計の純資産額は6325ドルにまで減少、黒人家計の場合、5677ドルと同様に半分以下に減っている。
減少率で見ると、白人家計は16%減、ヒスパニック系家計は66%減、黒人家計は53%減であった。金融危機とそれに続く不況がいかにアメリカ人の大き
な影響を与えたか分かる。
そのなかでヒスパニック系への打撃が一番大きい。
いずれにせよ、白人家計もヒスパニック家計、黒人家計も大幅に資産額を減らしたわけだが、その結果、白人家計との間の資産格差はさらに大きく拡大してい
るのである。
貧富の格差は、確実にアメリカ社会の基盤を蝕みつつある。
アメリカ社会を道徳的に支えてきたのがアメリカン・ドリームであった。
アメリカン・ドリームには様々な定義がある。
ンキを塗った家を持つ」という言葉で表現されてきた。
そうした希望がアメリカ社会の活力になってきた。
だが、今やアメリカで語られているのは、もはやアメリカン・ドリームは多くの人にとって遠い夢物語になりつつあるということだ。
ある調査では、「アメリカン・ドリームはいまでも存在していると強く信じている」と答えた人は1986年の32%から17%に低下している。
逆に、「もはやアメリカン・ドリーム存在しない」と答えた人は11%から17%に増加している。
これに対して、可能性は小さいと答えた人は52%に達している。
子供たちは自分たちよりも高い生活水準を手に入れると考えている人は26%と比べると、自分たちよりも悪くなると答えた人は46%と圧倒的多数を占めて
いる。
アメリカ社会を支える価値観は、急速に崩れつつある。
その最大の原因は、急速に進む貧富の格差にあることは間違いない。
ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツ・コロンビア大学教授は、貧富の格差では「アメリカはロシアやイラン並みになってしまった」と指摘し
ている。
現在、トップ1%の富裕層が国民の全所得の25%、富の40%を占めている。
25年前は、その比率は12%と33%であった。
過去10年間にトップ1%の富裕層の所得は18%増えたが、高卒の資格しか持たない労働者の所得は12%減っている。
スティグリッツ教授は「こうした不平等は富裕層でさえ嘆くほどのものである」と、アメリカの貧富の格差の深刻さを指摘する。
アメリカには「海水の水位が高まれば全てのボートも浮き上がる」という根強い発想がある。
社会が豊かになれば、全員が豊かになる。
豊かさは全ての国民に恩恵をもたらす。
ポール・クルーグマン・プリンストン大学教授は、戦後のアメリカの状況を「私が育った時代は“アメリカの中産階級”だった。その社会では極端な富裕層も
貧困層も存在せず、友が広く社会に共有されていた。それは強力な労働組合と最低賃金制、累進課税があり、不平等の拡大を阻止していた」と、良き時代のア
メリカを語っている。
だが、それは今や幻想になりつつある。貧困層は海底に取り残され、決して浮上することはないように見える。
不平等はアメリカ社会を至るところで歪めているのである。
アメリカン・ドリームを支えてきたのは中産階級の勝利であった。
また中産階級こそがアメリカ社会の中核を形成してきた。
だが、貧富の格差の拡大と同時に中産階級の崩壊も始まっている。
白人労働者は成人人口の48%を占める。
その大半が高卒で、大卒労働者は10%を占めるに過ぎない。
彼らは子供たちにアメリカン・ドリームを託し、懸命に働いてきた。
だが、素朴にアメリカン・ドリームを信じるには、現実は彼らにとってあまりにも過酷な状況になっている。
何がアメリカン・ドリームを壊してしまったのか。
スティグリッツ教授は「経済学者は不平等の拡大を十分には説明できない」と断りながら、三つの理由を挙げている。
まず労働節約的な技術革新で多くの中産階級、労働者の職が奪われたこと。
次は、グローバリゼーションで海外の低賃金労働との競争を強いられたこと。
そして、労働者の権利を守る労働組合の衰退である。
ニューディール時代には9割を越え、1980年代でも40%台だった組合参加率は現在では12%にまで低下している。
しかも比較的高賃金の製造業の雇用の減少は続き、低賃金のサービス業の雇用が大幅に増えていることも、中産階級の所得減少の要因となっている。
現在のアメリカの労働組合にはかつてのようなエネルギーは失われてしまっている。
最も戦闘的と言われたUAW(全米自動車労組)も、GMなどの自動車メーカーの経営危機で完全に牙を抜かれてしまっている。
GM国有化を実施した政府との交渉でUAWは新規採用の労働者の賃金の50%切り下げを認めさせられるなど、もはや労働者の権利を代表する力さえ失いつ
つある。
その一方で業績を回復したGMのダン・アッカーソンCEO(最高経営責任者)は900万ドルの報酬を手にしている。
ウイスコンシン州では、保守派の議員たちは公務員の団体交渉権を剥奪する動きを強め、それは他州にも拡大する様相を呈している。
さらに貧富の格差の拡大を加速したのが、1980年代のレーガン政権以降の税制政策と規制緩和政策であった。
共和党政権はトップ1%に奉仕してきただけでなく、政党を越えて政治全体が富裕層の利益の代弁者になっている。
スティグリッツ教授は「実質的に上院議員の全員と下院議員の大半がトップ1%の富裕層に属し、彼らからの政治献金で議員の地位を確保し、議員を辞めた後
も、彼らのお金で仕事にありついている。経済政策や通商政策に携わる政府高官もまたトップ1%の富裕層出身なのである」と指摘している。
トップ1%の富裕層の権力を前提にアメリカ社会のシステムは動いており、貧富の格差は構造化されているのである。
そうしたアメリカ社会に歯止めを掛けることを期待されて登場したのがオバマ大統領であった。
「仕事なし、指導力なし、オバマの大きな失敗」(ハッフポスト・ビジネス、2001年6月3日)と題する記事の中で、オバマ大統領に与えられた任務は中
産階級のアメリカン・ドリームを取り戻すことであったが、「落胆すべき失敗に終わった」と言う。
選挙公約に掲げた富裕層の税優遇措置を廃止することもできず、アメリカン・ドリームのベースである住宅問題も解決することはできなかった。
国民の反対にも拘わらず金融機関救済を進め、巨額の報酬も規制できなかった。
大統領はトップ1%の富裕層の1人であり、その利益の代弁者に過ぎなかったのかもしれない。
スティグリッツ教授は中東で起る民主化の動きを見ながら、「いつ民主化の動きはアメリカに来るのだろうか。重要な点で、我が国は遠い、問題を抱える国と
同じような国になってしまった」と、歯止めの止まらない貧富の格差の拡大の深刻さを指摘している。来年の大統領選挙でオバマ大統領の命運を決するのは白
人労働者の動向である。彼らは、どんな判断を下すのだろうか。【平成新聞編集部平成24年8月号新田論記】
(その二十三)
一番深い支配者の森はグレート・ブリテン島にあるだろう。
近代社会になって大帝国をはじめて構築した場所だ。
大航海時代はポルトガル、スペイン、オランダなどが尖兵を切ったが、第一次産業革命における蒸気機関の発明によって国威をつけたイギリスが、最終的には
大英帝国を築き上げた。
近代社会の幕開けであった。
近代社会の三種の神器であるルネッサンス、宗教改革、産業革命の中で、ルネッサンス、宗教改革で遅れを取ったイギリスだったが、蒸気機関の発明により一
気に勢いづいたイギリスの産業革命はフランス、ドイツ、イタリアなど他の追随を許さない圧倒的なものだった。
まさに、
古代ローマ帝国以来の大帝国は、分裂した西ローマ帝国でも東ローマ帝国でも神聖ローマ帝国でもオスマン・トルコ帝国でもなく大英帝国に他ならなかったの
である。
イギリス延いてはアメリカが、他の西欧諸国、すなわち、大陸ヨーロッパ諸国と一線を画する立場を強調してきた所以は、“我々(イギリス・アメリカ)こそ
古代ローマ帝国を再現でき得る国家である”という自負心にあった。
表向きには冷戦に勝利したアメリカが強力な軍事力にモノを言わせた国家であることは、まさに、カルタゴを破った以後のローマ帝国と酷似している。
だが、
イギリスから独立を勝ち得た頃のアメリカには、古代ローマ帝国に対する郷愁など微塵もなかったし、第一次世界大戦までその考え方は変わらなかった。
モンロー主義、すなわち、日本の江戸時代の鎖国主義と同じ立場を第一次世界大戦の終戦間近まで維持してきたアメリカが突然ヨーロッパ戦線に軍隊を派遣す
ることを決定した。
その瞬間(とき)からアメリカもイギリスと同じ深い支配者たちの森に迷い込んだのである。
アメリカの原風景はやはりグレート・ブリテン島にあり、メキシコ湾流を共通項にした風土という点では、ニューヨークにその原風景が残っている。
大西洋文明はメキシコ湾流の恩恵によって成立したと言っても過言ではないだろう。
古代エジプト文明はナイル川の恩恵により、メソポタミア文明はチグリス川とユーフラテス川の恩恵であり、インダス文明はインダス川の恩恵であり、古代中
国文明は黄河の恩恵であったように、西洋文明はまさに大西洋の恩恵によるところ大であり、中でもメキシコ湾流が北半球を縦断しているため、太平洋におけ
る同じ緯度の場所でも、遥かに温暖な気候に恵まれていた。
ロンドンの緯度は北海道北部と変わらないのに、気候は東京と変わらないし、ニューヨークの緯度は青森と同じだ。
古代、中世では南欧と中東地域が先進地域で、僻地に過ぎなかった西欧社会が近代に入って先進国になり得たのは、一重にメキシコ湾流という暖流がこの地域
を流れていたからである。
オランダ人が先に入植した結果、ニュー・アムステルダムと呼ばれていた場所を、敢えて、ニューヨークとしたのは、やはり、ニュー・ヨークシャーからであ
ることは明白である。
大英帝国を語る上で欠かすことのできないのが、イングランドとスコットランド、ウェールズ、アイルランドとの関係であろう。
一哉はエリザベスからスコットランドをイングランドから独立させたウィリアムス・ウォーレスの話を訊いて感動した。
まさに、イエス・キリストと同じ体験をしていた勇者だった。
「ウィリアムス・ウォーレスは花嫁に対する愛のために戦ったのよ!」
「イエス・キリストもマグダラのマリアに対する愛のために戦ったのよ!」
「愛とはそんなものなのね・・・」
バイオレット色という不思議な瞳を輝かせて彼女は一哉に言った。
「イングランドの王は、スコットランド人の結婚直後の新婦の初夜権をイングランドの貴族に与えるというひどい法律を定めたの・・・・」
「ところが、ウィリアムス・ウォーレスの花嫁はそれを拒否したため、喉を掻き切られて殺された・・・ひどいでしょう?」
男性社会の典型が大英帝国の前身であるイングランドにあり、イングランドのアンチ・テーゼの立場に置かれたスコットランドを筆頭にウェールズやアイルラ
ンドは、女性社会こそ自然に則した社会であると信じてきた。
イングランドの王が制定した「初夜権」がまさに男性社会の本質を露呈していたのである。
初夜とは女性の純潔性を犯される儀式に他ならない。
言い換えれば、
”男性に犯されるのが女性の本質である”
男性社会の本質がここにある。
そして、
差別・不条理・戦争を繰り返す社会こそ男性社会である所以がここにある。
ところが、
21世紀に入って、特に先進社会から変化が起きはじめた。
男性と女性の逆転現象が起きはじめたのである。
まさに、
男性が女性に犯される社会になってきたのだ。
では、
男性が女性に犯される社会こそ女性社会到来の予兆だと言うのだろうか?
まさか、
女性による初夜権の行使が為される時代がやってくると言うのだろうか?
だが、
その事態はイギリスという国で既に起こっていたのである。
歴史は皮肉だ。
支配者による被支配者の新婦に対する初夜権の行使が為されるという卑劣な慣習をつくったのもイギリスなら、支配者による被支配者の新郎に対する初夜権の
行使が為されるという醜悪な慣習をつくったのもイギリスという国だったのである。
アメリカという国は、まさに、イギリスという国の文字通りの申し子だった。
アメリカ合衆国というだけに、世界のありとあらゆる人種の坩堝と化したような国に一見思われるが、実は、アングロサクソンの国なのである。
アメリカの特権階級をエスタブリッシュメントと呼ぶ一方で、WASPと他方呼ばれる所以がここにある。
WASPとは(White、Anglo‐Saxon、Protestant)の略だ。
そういう意味では、19世紀と20世紀の世界はアングロサクソンの時代であったと言えるわけだ。
言い換えれば、
人種差別意識のルーツはアングロサクソンにあったと言える。
逆に言えば、
古代ローマ帝国時代にラテン人から野蛮人だと差別を受けたゲルマン人には人種差別意識は希薄だと言える。
ラテン系の中でも特にアングロサクソンにその意識が強い。
その理由は、アーリア系ゲルマンに白人のルーツがあり、且つ、西洋社会の依り処としてのイエス・キリストのルーツであることに対する劣等意識の反動に他
ならない。
差別の根本的原因は、差別されることに対する反動(アンチテーゼ)にあることを、21世紀の人類は肝に銘ずるべきだ。
やはり、
支配・被支配二層構造の本質は、支配する者が支配される者で、支配される者が支配するものであるという構図にある。
この真理に気がついた瞬間(とき)、人類は人間は支配・被支配二層構造社会が無意味であることを理解する。
その瞬間(時)、支配者たちの森は被支配者たちの森と化す。
「みおつくし」8月号「平成新聞」8月号原稿より
執筆 新田論
平成新聞社説
アメリカ経済の状況は一向に改善する気配がない。
社会的な問題も山積している。
国債発行限度額引き上げを巡る党派の争いはひどいものだ。
かつてのような輝きをアメリカ社会は失いつつあり、崩れつつあるアメリカン・ドリームについてある報告が発表された。
白人と黒人、ヒスパニック系アメリカ人の所得格差が過去最大にまで拡大したというものである。
額は1万2124ドルであった。
一方、2009年には白人の純資産額は11万3149ドルと減少しているが、これは金融危機による株安や住宅価格の下落が響いているからである。
これに対してヒスパニック系の家計の純資産額は6325ドルにまで減少、黒人家計の場合、5677ドルと同様に半分以下に減っている。
減少率で見ると、白人家計は16%減、ヒスパニック系家計は66%減、黒人家計は53%減であった。金融危機とそれに続く不況がいかにアメリカ人の大き
な影響を与えたか分かる。
そのなかでヒスパニック系への打撃が一番大きい。
いずれにせよ、白人家計もヒスパニック家計、黒人家計も大幅に資産額を減らしたわけだが、その結果、白人家計との間の資産格差はさらに大きく拡大してい
るのである。
貧富の格差は、確実にアメリカ社会の基盤を蝕みつつある。
アメリカ社会を道徳的に支えてきたのがアメリカン・ドリームであった。
アメリカン・ドリームには様々な定義がある。
ンキを塗った家を持つ」という言葉で表現されてきた。
そうした希望がアメリカ社会の活力になってきた。
だが、今やアメリカで語られているのは、もはやアメリカン・ドリームは多くの人にとって遠い夢物語になりつつあるということだ。
ある調査では、「アメリカン・ドリームはいまでも存在していると強く信じている」と答えた人は1986年の32%から17%に低下している。
逆に、「もはやアメリカン・ドリーム存在しない」と答えた人は11%から17%に増加している。
これに対して、可能性は小さいと答えた人は52%に達している。
子供たちは自分たちよりも高い生活水準を手に入れると考えている人は26%と比べると、自分たちよりも悪くなると答えた人は46%と圧倒的多数を占めて
いる。
アメリカ社会を支える価値観は、急速に崩れつつある。
その最大の原因は、急速に進む貧富の格差にあることは間違いない。
ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツ・コロンビア大学教授は、貧富の格差では「アメリカはロシアやイラン並みになってしまった」と指摘し
ている。
現在、トップ1%の富裕層が国民の全所得の25%、富の40%を占めている。
25年前は、その比率は12%と33%であった。
過去10年間にトップ1%の富裕層の所得は18%増えたが、高卒の資格しか持たない労働者の所得は12%減っている。
スティグリッツ教授は「こうした不平等は富裕層でさえ嘆くほどのものである」と、アメリカの貧富の格差の深刻さを指摘する。
アメリカには「海水の水位が高まれば全てのボートも浮き上がる」という根強い発想がある。
社会が豊かになれば、全員が豊かになる。
豊かさは全ての国民に恩恵をもたらす。
ポール・クルーグマン・プリンストン大学教授は、戦後のアメリカの状況を「私が育った時代は“アメリカの中産階級”だった。その社会では極端な富裕層も
貧困層も存在せず、友が広く社会に共有されていた。それは強力な労働組合と最低賃金制、累進課税があり、不平等の拡大を阻止していた」と、良き時代のア
メリカを語っている。
だが、それは今や幻想になりつつある。貧困層は海底に取り残され、決して浮上することはないように見える。
不平等はアメリカ社会を至るところで歪めているのである。
アメリカン・ドリームを支えてきたのは中産階級の勝利であった。
また中産階級こそがアメリカ社会の中核を形成してきた。
だが、貧富の格差の拡大と同時に中産階級の崩壊も始まっている。
白人労働者は成人人口の48%を占める。
その大半が高卒で、大卒労働者は10%を占めるに過ぎない。
彼らは子供たちにアメリカン・ドリームを託し、懸命に働いてきた。
だが、素朴にアメリカン・ドリームを信じるには、現実は彼らにとってあまりにも過酷な状況になっている。
何がアメリカン・ドリームを壊してしまったのか。
スティグリッツ教授は「経済学者は不平等の拡大を十分には説明できない」と断りながら、三つの理由を挙げている。
まず労働節約的な技術革新で多くの中産階級、労働者の職が奪われたこと。
次は、グローバリゼーションで海外の低賃金労働との競争を強いられたこと。
そして、労働者の権利を守る労働組合の衰退である。
ニューディール時代には9割を越え、1980年代でも40%台だった組合参加率は現在では12%にまで低下している。
しかも比較的高賃金の製造業の雇用の減少は続き、低賃金のサービス業の雇用が大幅に増えていることも、中産階級の所得減少の要因となっている。
現在のアメリカの労働組合にはかつてのようなエネルギーは失われてしまっている。
最も戦闘的と言われたUAW(全米自動車労組)も、GMなどの自動車メーカーの経営危機で完全に牙を抜かれてしまっている。
GM国有化を実施した政府との交渉でUAWは新規採用の労働者の賃金の50%切り下げを認めさせられるなど、もはや労働者の権利を代表する力さえ失いつ
つある。
その一方で業績を回復したGMのダン・アッカーソンCEO(最高経営責任者)は900万ドルの報酬を手にしている。
ウイスコンシン州では、保守派の議員たちは公務員の団体交渉権を剥奪する動きを強め、それは他州にも拡大する様相を呈している。
さらに貧富の格差の拡大を加速したのが、1980年代のレーガン政権以降の税制政策と規制緩和政策であった。
共和党政権はトップ1%に奉仕してきただけでなく、政党を越えて政治全体が富裕層の利益の代弁者になっている。
スティグリッツ教授は「実質的に上院議員の全員と下院議員の大半がトップ1%の富裕層に属し、彼らからの政治献金で議員の地位を確保し、議員を辞めた後
も、彼らのお金で仕事にありついている。経済政策や通商政策に携わる政府高官もまたトップ1%の富裕層出身なのである」と指摘している。
トップ1%の富裕層の権力を前提にアメリカ社会のシステムは動いており、貧富の格差は構造化されているのである。
そうしたアメリカ社会に歯止めを掛けることを期待されて登場したのがオバマ大統領であった。
「仕事なし、指導力なし、オバマの大きな失敗」(ハッフポスト・ビジネス、2001年6月3日)と題する記事の中で、オバマ大統領に与えられた任務は中
産階級のアメリカン・ドリームを取り戻すことであったが、「落胆すべき失敗に終わった」と言う。
選挙公約に掲げた富裕層の税優遇措置を廃止することもできず、アメリカン・ドリームのベースである住宅問題も解決することはできなかった。
国民の反対にも拘わらず金融機関救済を進め、巨額の報酬も規制できなかった。
大統領はトップ1%の富裕層の1人であり、その利益の代弁者に過ぎなかったのかもしれない。
スティグリッツ教授は中東で起る民主化の動きを見ながら、「いつ民主化の動きはアメリカに来るのだろうか。重要な点で、我が国は遠い、問題を抱える国と
同じような国になってしまった」と、歯止めの止まらない貧富の格差の拡大の深刻さを指摘している。来年の大統領選挙でオバマ大統領の命運を決するのは白
人労働者の動向である。彼らは、どんな判断を下すのだろうか。【平成新聞編集部平成24年8月号新田論記】
(その二十三)
一番深い支配者の森はグレート・ブリテン島にあるだろう。
近代社会になって大帝国をはじめて構築した場所だ。
大航海時代はポルトガル、スペイン、オランダなどが尖兵を切ったが、第一次産業革命における蒸気機関の発明によって国威をつけたイギリスが、最終的には
大英帝国を築き上げた。
近代社会の幕開けであった。
近代社会の三種の神器であるルネッサンス、宗教改革、産業革命の中で、ルネッサンス、宗教改革で遅れを取ったイギリスだったが、蒸気機関の発明により一
気に勢いづいたイギリスの産業革命はフランス、ドイツ、イタリアなど他の追随を許さない圧倒的なものだった。
まさに、
古代ローマ帝国以来の大帝国は、分裂した西ローマ帝国でも東ローマ帝国でも神聖ローマ帝国でもオスマン・トルコ帝国でもなく大英帝国に他ならなかったの
である。
イギリス延いてはアメリカが、他の西欧諸国、すなわち、大陸ヨーロッパ諸国と一線を画する立場を強調してきた所以は、“我々(イギリス・アメリカ)こそ
古代ローマ帝国を再現でき得る国家である”という自負心にあった。
表向きには冷戦に勝利したアメリカが強力な軍事力にモノを言わせた国家であることは、まさに、カルタゴを破った以後のローマ帝国と酷似している。
だが、
イギリスから独立を勝ち得た頃のアメリカには、古代ローマ帝国に対する郷愁など微塵もなかったし、第一次世界大戦までその考え方は変わらなかった。
モンロー主義、すなわち、日本の江戸時代の鎖国主義と同じ立場を第一次世界大戦の終戦間近まで維持してきたアメリカが突然ヨーロッパ戦線に軍隊を派遣す
ることを決定した。
その瞬間(とき)からアメリカもイギリスと同じ深い支配者たちの森に迷い込んだのである。
アメリカの原風景はやはりグレート・ブリテン島にあり、メキシコ湾流を共通項にした風土という点では、ニューヨークにその原風景が残っている。
大西洋文明はメキシコ湾流の恩恵によって成立したと言っても過言ではないだろう。
古代エジプト文明はナイル川の恩恵により、メソポタミア文明はチグリス川とユーフラテス川の恩恵であり、インダス文明はインダス川の恩恵であり、古代中
国文明は黄河の恩恵であったように、西洋文明はまさに大西洋の恩恵によるところ大であり、中でもメキシコ湾流が北半球を縦断しているため、太平洋におけ
る同じ緯度の場所でも、遥かに温暖な気候に恵まれていた。
ロンドンの緯度は北海道北部と変わらないのに、気候は東京と変わらないし、ニューヨークの緯度は青森と同じだ。
古代、中世では南欧と中東地域が先進地域で、僻地に過ぎなかった西欧社会が近代に入って先進国になり得たのは、一重にメキシコ湾流という暖流がこの地域
を流れていたからである。
オランダ人が先に入植した結果、ニュー・アムステルダムと呼ばれていた場所を、敢えて、ニューヨークとしたのは、やはり、ニュー・ヨークシャーからであ
ることは明白である。
大英帝国を語る上で欠かすことのできないのが、イングランドとスコットランド、ウェールズ、アイルランドとの関係であろう。
一哉はエリザベスからスコットランドをイングランドから独立させたウィリアムス・ウォーレスの話を訊いて感動した。
まさに、イエス・キリストと同じ体験をしていた勇者だった。
「ウィリアムス・ウォーレスは花嫁に対する愛のために戦ったのよ!」
「イエス・キリストもマグダラのマリアに対する愛のために戦ったのよ!」
「愛とはそんなものなのね・・・」
バイオレット色という不思議な瞳を輝かせて彼女は一哉に言った。
「イングランドの王は、スコットランド人の結婚直後の新婦の初夜権をイングランドの貴族に与えるというひどい法律を定めたの・・・・」
「ところが、ウィリアムス・ウォーレスの花嫁はそれを拒否したため、喉を掻き切られて殺された・・・ひどいでしょう?」
男性社会の典型が大英帝国の前身であるイングランドにあり、イングランドのアンチ・テーゼの立場に置かれたスコットランドを筆頭にウェールズやアイルラ
ンドは、女性社会こそ自然に則した社会であると信じてきた。
イングランドの王が制定した「初夜権」がまさに男性社会の本質を露呈していたのである。
初夜とは女性の純潔性を犯される儀式に他ならない。
言い換えれば、
”男性に犯されるのが女性の本質である”
男性社会の本質がここにある。
そして、
差別・不条理・戦争を繰り返す社会こそ男性社会である所以がここにある。
ところが、
21世紀に入って、特に先進社会から変化が起きはじめた。
男性と女性の逆転現象が起きはじめたのである。
まさに、
男性が女性に犯される社会になってきたのだ。
では、
男性が女性に犯される社会こそ女性社会到来の予兆だと言うのだろうか?
まさか、
女性による初夜権の行使が為される時代がやってくると言うのだろうか?
だが、
その事態はイギリスという国で既に起こっていたのである。
歴史は皮肉だ。
支配者による被支配者の新婦に対する初夜権の行使が為されるという卑劣な慣習をつくったのもイギリスなら、支配者による被支配者の新郎に対する初夜権の
行使が為されるという醜悪な慣習をつくったのもイギリスという国だったのである。
アメリカという国は、まさに、イギリスという国の文字通りの申し子だった。
アメリカ合衆国というだけに、世界のありとあらゆる人種の坩堝と化したような国に一見思われるが、実は、アングロサクソンの国なのである。
アメリカの特権階級をエスタブリッシュメントと呼ぶ一方で、WASPと他方呼ばれる所以がここにある。
WASPとは(White、Anglo‐Saxon、Protestant)の略だ。
そういう意味では、19世紀と20世紀の世界はアングロサクソンの時代であったと言えるわけだ。
言い換えれば、
人種差別意識のルーツはアングロサクソンにあったと言える。
逆に言えば、
古代ローマ帝国時代にラテン人から野蛮人だと差別を受けたゲルマン人には人種差別意識は希薄だと言える。
ラテン系の中でも特にアングロサクソンにその意識が強い。
その理由は、アーリア系ゲルマンに白人のルーツがあり、且つ、西洋社会の依り処としてのイエス・キリストのルーツであることに対する劣等意識の反動に他
ならない。
差別の根本的原因は、差別されることに対する反動(アンチテーゼ)にあることを、21世紀の人類は肝に銘ずるべきだ。
やはり、
支配・被支配二層構造の本質は、支配する者が支配される者で、支配される者が支配するものであるという構図にある。
この真理に気がついた瞬間(とき)、人類は人間は支配・被支配二層構造社会が無意味であることを理解する。
その瞬間(時)、支配者たちの森は被支配者たちの森と化す。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.