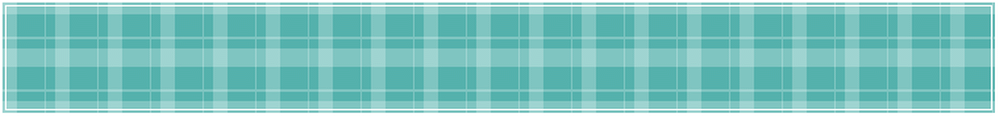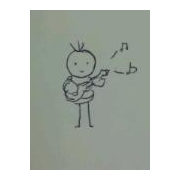PR
X
カレンダー
カテゴリ
10行エッセイ もしくは未分類・未編集
(236)10-line essays
(453)音楽10行エッセイ
(92)ライブレポ
(187)Music 10-line essays
(59)お知らせ Information
(46)お気に入り・お勧め紹介
(29)Favorite, recommendation
(90)自己紹介・ブログ紹介代用バトン
(21)日記代用バトン
(213)バトン置き場
(420)フリーページ
カテゴリ: ライブレポ
本編のみ
レポはお正月休みに下書きテキストファイルを打っておいたものの、他は1月2週目位まで打ったり削除したりしていました。
6.5KB超えに付き色文字少なめ
(2022年12月25日、浜松市福祉建立センターホールより生配信)
( 1~3 )
佐藤竹善 "ようこそいらっしゃいました"
クリスマスライブ9年目にして初の浜松+本日ファイナル
静岡のAMラジオの番組を持ってすぐコロナで自宅収録となった
→客席証明を要望 "トークの時はこの明るさ。コンセプトは笑点"
9年前、クリスマスアルバムを作り始め、それと共にコンサートも…
―が、今年は最多の11本。バンドやデュオの形式が混在する中、ファイナルはバンドスタイルで
これだけ人が入ったら来年もココで開催できる?
"皆さんが一人ずつ連れてきたらこの会場には入り切れないんだから"
クリスマスアルバムにはオリジナルを必ず入れる―が、洋楽に近いアプローチなのが SING LIKE TALKING との違い
ギターチューニングのため江藤に振る―が、"ようこそ…"と挨拶している間にチューニング終わり
"MCはポンコツですから"
→ 松重豊 参加のミュージックビデオの楽曲―を日本語バージョンで
4. Another Christmas Time
( 5 )
"おしゃべりの時間になってしまいました"
Winter Wonderland 」…いろんなジャンルで取り上げられるクリスマスソングだが、自分はブルーアイドソウル的なアプローチ
「(2) All I Want For Christmas Is You 」…実は「 29歳のクリスマス 」のドラマ主題歌で日本だけのヒット
当時、女は24までに結婚しないと価値が下がるというクリスマスケーキに喩えられており、29歳で独身なんておかしいんじゃないの、という風潮だった
―だが、楽曲はいいので色んなアーティストがカバーしている
Do You Hear What I Hear 」…クリスチャン系の学校などではスタンダードでは? ケルトロックのアレンジ
"何を喋りたいってワケじゃないけど、おしゃべりしたい"
「(5) Please Come Home For Christmas」 … イーグルス が取り上げて大ヒット。
元々黒人のドゥーワップグループの曲だが、当時、黒人と白人の軋轢が大きく、そんな中でその曲を取り上げたイーグルスは画期的
音楽は世界は変えられないが、世界を変える人は作れる。
<メンバー紹介>
ドラム:ジャズの第一人者とのコラボが多い… 江藤良人
"トナカイの被り物をすると「せんとくん」になる"
実はコージー・パウエルを敬愛
ベース:アメリカのスーパースターとも共演、直近では大西ユカリと朗読などのステージ
最近、EXILEのライブを観に行って"テレビで見るよりカッコいい、今度生まれ変わったらこれがいい"と思った話で寄り道した末に… 井上陽介
ピアノ:今回のツアーから一緒。かつて" 東にカシオペア・T-Square、西にナニワエキスプレス "
青柳誠
今回、何本かドラム・ベースがいないデュオのステージがあり、当然アレンジが違うので青柳が混乱した話
→"女性のジュリー" フランス系の女性という設定
色々大変な事があるけど、クリスマスにはきっと良い事あるよ、という歌
6. ジュリー
「 Radio JAOR~Cornerstones 8~ 」をリリース。カバーも最近は当たり前になって、日本も成熟したな…と思った。
山下達郎曰く "カバーもできない奴がオリジナルはできない"…表現されたものがイコール作品
ビートルズが「のっぽのサリー」をカバーしてくれなかったら自分はあの曲は好きになれなかった…チャック・ベリーは自分の代には濃厚過ぎる
「 Cornerstones 7 」はジャズオーケストラ、「 Cornerstones 6 」は日本フィルハーモニーと共演
次のカバーシリーズはそろそろJ-Popを、と要請されていた折、シティポップが再評価され始めた。
ユーミン、山下達郎、初期のオフコースなど…が、海外で日本語のまま評価されている (以下「Live With The Cornerstones 22~It's My JAOR~」でのお話と同じなので、手抜きにて失礼いたします)
この話の続きはレコード部屋でゆっくりと…
→カバーというと、大ヒットした曲を取り上げがちだが、 自分のスタンスは「自分に影響が大きくてDNAに残る曲」というのは一貫
今回は2000年代の楽曲が2つ、うち1つが KAN の。普段はひょうひょうとしているが、ミュージシャンの間でもファンが多い
非常に高い音楽性がありつつ、それをさりげなく出している感じが良い…
7. カレーライス
"優しい歌ですね"
KANからデュエットを持ちかけられたが、アレンジが竹善がメインになるように作られた
曰く"ボクねぇ、時々自分の歌唱力を超えた曲を書いちゃうんですよ。だから竹善さんに歌ってもらえて嬉しい"
KANはコントも書く…"何度も練習させられたことが一番印象に残った"
「 太陽にほえろ! 」のコントの話…セリフも覚えさせられた上、BGMも
曲よりコントのリハーサルの方が長かった
オフコース 。"♪ラーラーラー、ララーラー~もう~~"
現在、 小田和正 は76歳。小田がソロになった頃、突然コーラスに呼ばれ、"お前よくフェイクやるんだろ、アドリブ"と言われ、
指定された箇所で2テイク程歌ったところ、その部分をいきなり譜面にして"これを今思いついたようにやって"と言われ絶句…
有名になる前の「2人のオフコース」時代があるが、3枚目のアルバムでサウンドの方向性が変わった。
その頃のプロデューサーが後にSLTのプロデューサーとなる武藤さん
8. ワインの匂い
9. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
オフコースの「 Junction 」などシティポップの名曲の宝庫…
小田とのエピソードを、曲中に思い出し笑いしていたが、歌い終わったら忘れた
"脳がなくても手は動く…もとい、働かなくても"
→ クリスマスの月の下、頑張っていることを称え合う歌
10. Christmas Moon
青森ではクリスマスの頃はいつも雪なので、東京では晴れの日が多いのにびっくり
松尾芭蕉が青森の手前でUターン
青森は8月2~6日がねぶた祭で、短い夏を満喫。8/7に入るともう秋の空気
一説によると、源義経が頼朝に追われて奥州に逃れた末に自害したが、実はさらに奥に逃げ、少人数でどうやって頼朝軍をやっつけるかという作戦が「ねぶた」のルーツだったという伝説まである
また、青森にはキリストの墓が6つ位あるという伝説・津軽弁とヘブライ語に共通した語もある話まで…
気が付いたら1時間半経過。
シティポップというと洋楽の影響があるが、ドメスティックに発展したのがJ-Pop。
wacci がこの曲をリリースした当時は売れていなかったが、その翌年に武道館ライブを成功させ、2022年のレコード大賞に
11. 歩み
"こんばんワッチー""あの~、拍手しなくていいと思います"
wacciは素晴らしいプレイヤー揃い。ジャンルの垣根を感じさせない曲が増えたらと思う。
大先輩の曲。…の前に、浜松にまつわるお話
SLTが初めてストリングスを入れることになり、武道館の前に浜松公演で初めて顔合わせ、アンサンブルを固めてから武道館へ。その浜松公演の打ち上げで飲みまくって一体感が…
→"達郎です"
4枚目のアルバムのリリースの頃、竹善がコーラスに誘われた。
当時、アーティストとして売り出しているのにコーラスをやったら「値が下がる」と周囲から反対された中、勉強になると思って参加
バンドメンバーは名うてのミュージシャンばかりで、皆楽譜も読めるが、自分は読めないので音を全部覚えないといけない
+ ♭13thという、和音の中にない音も…
コーラスのリハーサルの日、その音が歌えず1人クビになったことを聞かされた…厳しいと同時に面白い人でもある
「青森で五木ひろしの乗ったタクシーの運転手の無線でのやり取り」のモノマネをさせられた話、ウルトラマンのかぶり物で「♪Let's dance baby~」
まだ売れていなかった頃の「 Go Ahead 」から。
達郎の曲はなかなかOKが出ない…が、この度カバーの許可が出た。
この曲のエピソードを話そうと思ったら、この曲を削らないといけない (もったいないし悪いけどこちらも本編だけでログアウトした方が良さそうだ、でないと開演前におかずは作っておいたとはいえ夕食の時間を過ぎそうだから…と、開始1時間後位に帰宅して視聴に合流した夫と合意)
12. 潮騒
"「たけよしの津軽弁はホンモノなんだよ」…当たり前じゃん"
ツアーグッズのコースターの話。2023年はデビュー35周年だが、"こんなダサいデザインは見たことがない"
もう1曲2000年代。 コーヒーカラー の15年前の曲
コースターのQRコードを読み込んだらこの曲が流れるはずが、自分で試したら「雨のリグレット」が流れた話
かつてサラリーマンの応援歌だったが、忘年会シーズンのイメージが強い。
1年間頑張ったね、来年も仲良くね…という。クリスマスと忘年会は、実はコンセプトは同じかも
シャンソン的な曲でシティポップとはちょっと違うが…いい曲であればいい、という話
ホントは間奏の「♪Silent night~」を歌ってもらいたいところだが…一言位いいだろうってことで「カンパーイ」の掛け声を要請
13. 人生に乾杯を
パリなかやま は現在「流し」になり、(昭和的なものではなく、むしろストリートに近い)
飲んでいる人々への目線が悲喜こもごも…
2時間で終わらなければいけないのに既に2時間10分
→「We Are The World」を四畳半のアパートでコピーした話…声マネで歌う (それなら、これもセットリストに入れたら?)
その頃イギリスでは Band-Aid が。 様々な形で苦境に置かれている人々はクリスマスが来たってことが解ってるんだろうか …という曲。
クリスマスの時期には光を灯して闇を打ち払おう、でも祈ろう、そんなことを思っていられないような人のために…みんなが楽しんでいるのに難しいかもしれないけれど。
窓の向こうには (テレビの画面という解釈も可能) 恐れと不安の世界がある。そこで流れる鐘は破滅の音…「でも、彼らのためにも、グラスを掲げようぜ」
コーラスデモンストレーション。さらにパート分けまで…女子は左右でソプラノ・あると、さらに男子パート
+「それぞれの神(概念的なもの)に感謝しよう、何故なら苦しんでいる人々はあなたの代わりかもしれないから」
イントロで"ラジオ体操第1!"
14. Do They Know It's Christmas? (Feed The World)
「 We Are The World 」やBand-Aidは世代的にリアルタイムではないのですが、 中学3年の英語の教科書に載っていて知っておりました。
9歳年上の夫曰く、 同じ目的で作られたのに「Feed The World」は「We Are The World」にばかり注目が集まっているのと比べるとあまり知られていないのは不満 …と。
なので、この曲には夫も満足だったようです。
考えてみたら商業施設かどこかでクリスマスBGMで流れていたような…サビのメロディーに聞き覚えがあったので。
しかし、「We Are The World」は両親がレコードを持っている一方「Feed The World」は私もあまり聞いたことがないような気がするので、
この日、竹善さんが取り上げてくれて、曲の背景や意味を知ることができ、
こういうこともカバーの意義の1つ …と、竹善さんが語ってきたことがだんだん理解できつつあります。
また、「 Your Christmas Day 」1枚目の1曲目が「 Once A Year 」だったことともダブりました。
その竹善さんのクリスマスアルバムとライブの企画が始まって、2022年末で気が付けば9年ですか…
今回のツアー会場の1つが和歌山の「 デサフィナード 」。
この会場での、東日本大震災復興支援単独行脚「 北郷想 」 (途中でタイトルが変わって「 故郷想 」) を観に行っています。
なんでも当時、竹善さんにとっては初の和歌山でのライブだったそうで。
この「故郷想」はまだ全都道府県終了していないし (近畿地方を見ても大阪だけがまだ) 、再開にもつい期待してしまいます。
そんな折、本年2度目の竹善さんの「 Sunday Musical Voice 」で、今年の目標として 映画鑑賞(DVD含む)50本を宣言、また映画などを観に行った後に楽曲やアレンジを書くと不思議と進む …という旨のお話も。
では、いい映画をたくさん観たらそれだけ名曲が生まれると想像がつくので、
SLTの皆様が還暦を迎える ( 西村智彦 さんだけ年をまたいで2024年に、ですが) +デビュー35周年という節目となる今年ならではの充実した活動にも期待が高まります。
ついでに私も、昨秋まで2年間まともに読書できておらず、テレビがないためDVDをパソコンで見るのがやっとということもあって映画はあんまり…ですが、
良い映画や文学作品(漫画も)は人物や心情の描写が良いというので…読書を増やしてみようかな…
パンデミックをきっかけにライブ配信が当たり前になってきて、遠方で行けない・諸事情で外出が難しいといった場合も楽しめるのはありがたい事です。
既述のとおり夫がクリスチャンで、パンデミック第1波の時に通常の礼拝が中止となって2020年4月から日曜礼拝が配信されるようになりました。 (既に集合礼拝は再開されているが、並行して配信も継続。また礼拝の形式は様変わりした)
とりわけご高齢のメンバーが多い教会だと、ご病気・施設に入所中などの事情で礼拝に出席できない方もいらっしゃるので、礼拝の配信のニーズが多いのは想像に難くありませんが、
宗教活動によって集団感染を起こしたら教会・教団は社会から受け入れられなくなるため、やむを得ずネット配信しているものの、あくまで礼拝は「集まること」が大前提 、というのが教会側のスタンスのようです。
それと同様とは言えないでしょうが、 ライブもやっぱりリアルと配信は同じというわけにはいかないようですね…
竹善さんの楽しいトークはライブの売りではありますが、 配信で観ている側には長丁場だとそれなりに負担もあるため、
配信するなら、ビルボードのような「施設側の時間枠が厳しい会場」からの方がいいと思います。
レポはお正月休みに下書きテキストファイルを打っておいたものの、他は1月2週目位まで打ったり削除したりしていました。
6.5KB超えに付き色文字少なめ
(2022年12月25日、浜松市福祉建立センターホールより生配信)
( 1~3 )
佐藤竹善 "ようこそいらっしゃいました"
クリスマスライブ9年目にして初の浜松+本日ファイナル
静岡のAMラジオの番組を持ってすぐコロナで自宅収録となった
→客席証明を要望 "トークの時はこの明るさ。コンセプトは笑点"
9年前、クリスマスアルバムを作り始め、それと共にコンサートも…
―が、今年は最多の11本。バンドやデュオの形式が混在する中、ファイナルはバンドスタイルで
これだけ人が入ったら来年もココで開催できる?
"皆さんが一人ずつ連れてきたらこの会場には入り切れないんだから"
クリスマスアルバムにはオリジナルを必ず入れる―が、洋楽に近いアプローチなのが SING LIKE TALKING との違い
ギターチューニングのため江藤に振る―が、"ようこそ…"と挨拶している間にチューニング終わり
"MCはポンコツですから"
→ 松重豊 参加のミュージックビデオの楽曲―を日本語バージョンで
4. Another Christmas Time
( 5 )
"おしゃべりの時間になってしまいました"
Winter Wonderland 」…いろんなジャンルで取り上げられるクリスマスソングだが、自分はブルーアイドソウル的なアプローチ
「(2) All I Want For Christmas Is You 」…実は「 29歳のクリスマス 」のドラマ主題歌で日本だけのヒット
当時、女は24までに結婚しないと価値が下がるというクリスマスケーキに喩えられており、29歳で独身なんておかしいんじゃないの、という風潮だった
―だが、楽曲はいいので色んなアーティストがカバーしている
Do You Hear What I Hear 」…クリスチャン系の学校などではスタンダードでは? ケルトロックのアレンジ
"何を喋りたいってワケじゃないけど、おしゃべりしたい"
「(5) Please Come Home For Christmas」 … イーグルス が取り上げて大ヒット。
元々黒人のドゥーワップグループの曲だが、当時、黒人と白人の軋轢が大きく、そんな中でその曲を取り上げたイーグルスは画期的
音楽は世界は変えられないが、世界を変える人は作れる。
<メンバー紹介>
ドラム:ジャズの第一人者とのコラボが多い… 江藤良人
"トナカイの被り物をすると「せんとくん」になる"
実はコージー・パウエルを敬愛
ベース:アメリカのスーパースターとも共演、直近では大西ユカリと朗読などのステージ
最近、EXILEのライブを観に行って"テレビで見るよりカッコいい、今度生まれ変わったらこれがいい"と思った話で寄り道した末に… 井上陽介
ピアノ:今回のツアーから一緒。かつて" 東にカシオペア・T-Square、西にナニワエキスプレス "
青柳誠
今回、何本かドラム・ベースがいないデュオのステージがあり、当然アレンジが違うので青柳が混乱した話
→"女性のジュリー" フランス系の女性という設定
色々大変な事があるけど、クリスマスにはきっと良い事あるよ、という歌
6. ジュリー
「 Radio JAOR~Cornerstones 8~ 」をリリース。カバーも最近は当たり前になって、日本も成熟したな…と思った。
山下達郎曰く "カバーもできない奴がオリジナルはできない"…表現されたものがイコール作品
ビートルズが「のっぽのサリー」をカバーしてくれなかったら自分はあの曲は好きになれなかった…チャック・ベリーは自分の代には濃厚過ぎる
「 Cornerstones 7 」はジャズオーケストラ、「 Cornerstones 6 」は日本フィルハーモニーと共演
次のカバーシリーズはそろそろJ-Popを、と要請されていた折、シティポップが再評価され始めた。
ユーミン、山下達郎、初期のオフコースなど…が、海外で日本語のまま評価されている (以下「Live With The Cornerstones 22~It's My JAOR~」でのお話と同じなので、手抜きにて失礼いたします)
この話の続きはレコード部屋でゆっくりと…
→カバーというと、大ヒットした曲を取り上げがちだが、 自分のスタンスは「自分に影響が大きくてDNAに残る曲」というのは一貫
今回は2000年代の楽曲が2つ、うち1つが KAN の。普段はひょうひょうとしているが、ミュージシャンの間でもファンが多い
非常に高い音楽性がありつつ、それをさりげなく出している感じが良い…
7. カレーライス
"優しい歌ですね"
KANからデュエットを持ちかけられたが、アレンジが竹善がメインになるように作られた
曰く"ボクねぇ、時々自分の歌唱力を超えた曲を書いちゃうんですよ。だから竹善さんに歌ってもらえて嬉しい"
KANはコントも書く…"何度も練習させられたことが一番印象に残った"
「 太陽にほえろ! 」のコントの話…セリフも覚えさせられた上、BGMも
曲よりコントのリハーサルの方が長かった
オフコース 。"♪ラーラーラー、ララーラー~もう~~"
現在、 小田和正 は76歳。小田がソロになった頃、突然コーラスに呼ばれ、"お前よくフェイクやるんだろ、アドリブ"と言われ、
指定された箇所で2テイク程歌ったところ、その部分をいきなり譜面にして"これを今思いついたようにやって"と言われ絶句…
有名になる前の「2人のオフコース」時代があるが、3枚目のアルバムでサウンドの方向性が変わった。
その頃のプロデューサーが後にSLTのプロデューサーとなる武藤さん
8. ワインの匂い
9. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
オフコースの「 Junction 」などシティポップの名曲の宝庫…
小田とのエピソードを、曲中に思い出し笑いしていたが、歌い終わったら忘れた
"脳がなくても手は動く…もとい、働かなくても"
→ クリスマスの月の下、頑張っていることを称え合う歌
10. Christmas Moon
青森ではクリスマスの頃はいつも雪なので、東京では晴れの日が多いのにびっくり
松尾芭蕉が青森の手前でUターン
青森は8月2~6日がねぶた祭で、短い夏を満喫。8/7に入るともう秋の空気
一説によると、源義経が頼朝に追われて奥州に逃れた末に自害したが、実はさらに奥に逃げ、少人数でどうやって頼朝軍をやっつけるかという作戦が「ねぶた」のルーツだったという伝説まである
また、青森にはキリストの墓が6つ位あるという伝説・津軽弁とヘブライ語に共通した語もある話まで…
気が付いたら1時間半経過。
シティポップというと洋楽の影響があるが、ドメスティックに発展したのがJ-Pop。
wacci がこの曲をリリースした当時は売れていなかったが、その翌年に武道館ライブを成功させ、2022年のレコード大賞に
11. 歩み
"こんばんワッチー""あの~、拍手しなくていいと思います"
wacciは素晴らしいプレイヤー揃い。ジャンルの垣根を感じさせない曲が増えたらと思う。
大先輩の曲。…の前に、浜松にまつわるお話
SLTが初めてストリングスを入れることになり、武道館の前に浜松公演で初めて顔合わせ、アンサンブルを固めてから武道館へ。その浜松公演の打ち上げで飲みまくって一体感が…
→"達郎です"
4枚目のアルバムのリリースの頃、竹善がコーラスに誘われた。
当時、アーティストとして売り出しているのにコーラスをやったら「値が下がる」と周囲から反対された中、勉強になると思って参加
バンドメンバーは名うてのミュージシャンばかりで、皆楽譜も読めるが、自分は読めないので音を全部覚えないといけない
+ ♭13thという、和音の中にない音も…
コーラスのリハーサルの日、その音が歌えず1人クビになったことを聞かされた…厳しいと同時に面白い人でもある
「青森で五木ひろしの乗ったタクシーの運転手の無線でのやり取り」のモノマネをさせられた話、ウルトラマンのかぶり物で「♪Let's dance baby~」
まだ売れていなかった頃の「 Go Ahead 」から。
達郎の曲はなかなかOKが出ない…が、この度カバーの許可が出た。
この曲のエピソードを話そうと思ったら、この曲を削らないといけない (もったいないし悪いけどこちらも本編だけでログアウトした方が良さそうだ、でないと開演前におかずは作っておいたとはいえ夕食の時間を過ぎそうだから…と、開始1時間後位に帰宅して視聴に合流した夫と合意)
12. 潮騒
"「たけよしの津軽弁はホンモノなんだよ」…当たり前じゃん"
ツアーグッズのコースターの話。2023年はデビュー35周年だが、"こんなダサいデザインは見たことがない"
もう1曲2000年代。 コーヒーカラー の15年前の曲
コースターのQRコードを読み込んだらこの曲が流れるはずが、自分で試したら「雨のリグレット」が流れた話
かつてサラリーマンの応援歌だったが、忘年会シーズンのイメージが強い。
1年間頑張ったね、来年も仲良くね…という。クリスマスと忘年会は、実はコンセプトは同じかも
シャンソン的な曲でシティポップとはちょっと違うが…いい曲であればいい、という話
ホントは間奏の「♪Silent night~」を歌ってもらいたいところだが…一言位いいだろうってことで「カンパーイ」の掛け声を要請
13. 人生に乾杯を
パリなかやま は現在「流し」になり、(昭和的なものではなく、むしろストリートに近い)
飲んでいる人々への目線が悲喜こもごも…
2時間で終わらなければいけないのに既に2時間10分
→「We Are The World」を四畳半のアパートでコピーした話…声マネで歌う (それなら、これもセットリストに入れたら?)
その頃イギリスでは Band-Aid が。 様々な形で苦境に置かれている人々はクリスマスが来たってことが解ってるんだろうか …という曲。
クリスマスの時期には光を灯して闇を打ち払おう、でも祈ろう、そんなことを思っていられないような人のために…みんなが楽しんでいるのに難しいかもしれないけれど。
窓の向こうには (テレビの画面という解釈も可能) 恐れと不安の世界がある。そこで流れる鐘は破滅の音…「でも、彼らのためにも、グラスを掲げようぜ」
コーラスデモンストレーション。さらにパート分けまで…女子は左右でソプラノ・あると、さらに男子パート
+「それぞれの神(概念的なもの)に感謝しよう、何故なら苦しんでいる人々はあなたの代わりかもしれないから」
イントロで"ラジオ体操第1!"
14. Do They Know It's Christmas? (Feed The World)
「 We Are The World 」やBand-Aidは世代的にリアルタイムではないのですが、 中学3年の英語の教科書に載っていて知っておりました。
9歳年上の夫曰く、 同じ目的で作られたのに「Feed The World」は「We Are The World」にばかり注目が集まっているのと比べるとあまり知られていないのは不満 …と。
なので、この曲には夫も満足だったようです。
考えてみたら商業施設かどこかでクリスマスBGMで流れていたような…サビのメロディーに聞き覚えがあったので。
しかし、「We Are The World」は両親がレコードを持っている一方「Feed The World」は私もあまり聞いたことがないような気がするので、
この日、竹善さんが取り上げてくれて、曲の背景や意味を知ることができ、
こういうこともカバーの意義の1つ …と、竹善さんが語ってきたことがだんだん理解できつつあります。
また、「 Your Christmas Day 」1枚目の1曲目が「 Once A Year 」だったことともダブりました。
その竹善さんのクリスマスアルバムとライブの企画が始まって、2022年末で気が付けば9年ですか…
今回のツアー会場の1つが和歌山の「 デサフィナード 」。
この会場での、東日本大震災復興支援単独行脚「 北郷想 」 (途中でタイトルが変わって「 故郷想 」) を観に行っています。
なんでも当時、竹善さんにとっては初の和歌山でのライブだったそうで。
この「故郷想」はまだ全都道府県終了していないし (近畿地方を見ても大阪だけがまだ) 、再開にもつい期待してしまいます。
そんな折、本年2度目の竹善さんの「 Sunday Musical Voice 」で、今年の目標として 映画鑑賞(DVD含む)50本を宣言、また映画などを観に行った後に楽曲やアレンジを書くと不思議と進む …という旨のお話も。
では、いい映画をたくさん観たらそれだけ名曲が生まれると想像がつくので、
SLTの皆様が還暦を迎える ( 西村智彦 さんだけ年をまたいで2024年に、ですが) +デビュー35周年という節目となる今年ならではの充実した活動にも期待が高まります。
ついでに私も、昨秋まで2年間まともに読書できておらず、テレビがないためDVDをパソコンで見るのがやっとということもあって映画はあんまり…ですが、
良い映画や文学作品(漫画も)は人物や心情の描写が良いというので…読書を増やしてみようかな…
パンデミックをきっかけにライブ配信が当たり前になってきて、遠方で行けない・諸事情で外出が難しいといった場合も楽しめるのはありがたい事です。
既述のとおり夫がクリスチャンで、パンデミック第1波の時に通常の礼拝が中止となって2020年4月から日曜礼拝が配信されるようになりました。 (既に集合礼拝は再開されているが、並行して配信も継続。また礼拝の形式は様変わりした)
とりわけご高齢のメンバーが多い教会だと、ご病気・施設に入所中などの事情で礼拝に出席できない方もいらっしゃるので、礼拝の配信のニーズが多いのは想像に難くありませんが、
宗教活動によって集団感染を起こしたら教会・教団は社会から受け入れられなくなるため、やむを得ずネット配信しているものの、あくまで礼拝は「集まること」が大前提 、というのが教会側のスタンスのようです。
それと同様とは言えないでしょうが、 ライブもやっぱりリアルと配信は同じというわけにはいかないようですね…
竹善さんの楽しいトークはライブの売りではありますが、 配信で観ている側には長丁場だとそれなりに負担もあるため、
配信するなら、ビルボードのような「施設側の時間枠が厳しい会場」からの方がいいと思います。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ライブレポ] カテゴリの最新記事
-
佐藤竹善 Presents Cross your fingers 25 2025.06.08
-
Shiho 50th Birthday Live with special g… 2025.04.01
-
佐藤竹善 Your Christmas Night 2024 大阪 2025.01.04
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.