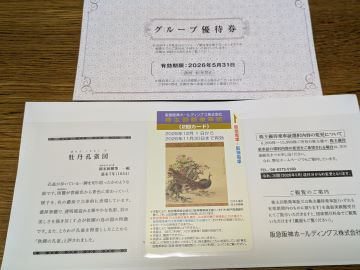2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
住宅ローン減税大幅拡充 長期優良住宅ならさらに恩恵 提供:エヌピー通信社
麻生太郎首相の鶴の一声で大幅に拡充されることになった住宅ローン減税制度。平成21年から同25年までの取得・居住について、最大控除額が大幅に拡大することになります。 一般住宅の場合、同21年から同22年までに居住したケースでは、住宅借入金などの年末残高の限度額が5千万円、最大控除額が500万円。また、同23年は年末借入残高の限度額が4千万円で最大控除額400万円、同24 年は年末借入残高の限度額3千万円で最大控除額300万円、同25 年は年末借入残高の限度額2千万円、最大控除額200万円。いずれも控除期間は10年、控除率は1%です。 これが長期優良住宅になると、同21年から同23年に居住した場合には、最大控除額が600万円と過去最大に。住宅借入金などの年末残高の限度額は5千万円です。さらに、同24年は年末借入金残高の限度額が4千万円で最高控除額が400万円、同25年では年末借入金残高が3千万円で最高控除額が300万円。控除期間はどの年も10年です、控除率は同21年から同23年までが1.2%、同24年から同25年が1%となっています。 これまで、住宅ローン減税は縮小傾向にありました。昨年末で期限切れを迎えた現行制度では、最大控除額が160万円。期間は10年と15年を選択できるものの、住民税からは控除できません。住民税から控除できるのは、税源移譲のあった平成18年末までに居住の用に供している納税者のみでしたが、今回の改正では住民税からの控除も認める方向です。(エヌピー通信社)
2009/01/30
コメント(0)
-
インフルエンザ予防接種費は損金計上OK
「新型インフルエンザ・パンデミック」の脅威が伝えられています。厚生労働省の試算では、もし日本国内で流行り出したら全人口の約25%がり患し、病院で受診を受ける患者数は2500万人、死亡者は64万人に達するとしています。 この新型インフルエンザ・パンデミックの怖いところは、有効なワクチンがまだ完成していないということ。ウィルスは現在、鳥からヒトへの感染ですが、これがヒトからヒトへ感染できるようになると、基本的にすべての人間がウィルスに対する免疫をもっていないため爆発的に流行する危険性があります。 では、われわれはどのような対策をとればよいのでしょう。厚労省によると、個人・事業者が実施できる具体的な感染予防策として ヒトとの距離の保持、 職場の消毒、 通常のインフルエンザワクチンの接種-などを挙げています。 通常のインフルエンザを接種した場合、その費用の一部もしくは全額を会社が負担した場合、会社は福利厚生費などとして処理することが可能です。国税当局では、「会社には従業員の健康管理に配慮する責任がある」とし、「接種を希望する社員一律に費用負担するようなルールがあるのであれば、全額を負担したとしても予防接種として常識的な金額の範囲内であれば、福利厚生費とすることができる」としています。 一方で、個人がインフルエンザ予防接種など疾病の予防のために要した費用は、原則として医療費控除の対象外。ただし、B型肝炎ワクチンの接種費用などにおいて患者と同居する親族に限り医療費控除の対象とすることが認められています(所得税法施行令207条、昭63直所3-23)。
2009/01/29
コメント(0)
-
20年度 確定申告 改正項目
20年度 確定申告分 改正事項はココからどうぞ
2009/01/29
コメント(0)
-
欠損金の繰戻還付 復活へ 赤字転落企業に朗報
黒字から赤字に転落した企業にとっては朗報です。平成21 年度与党税制改正大綱に、中小企業を対象とした「欠損金の繰戻還付」の復活が盛り込まれたのです。 今回は期限付きの復活で、同21 年2月1日以後に終了する各事業年度で生じた欠損金額からがその対象となります。資本金1億円以下の法人のほか、公益法人、協同組合、人格のない社団などもその対象に含まれます。 「欠損金の繰戻還付制度」は、前事業年度は黒字で法人税を納めた企業が、次年度赤字に転落した場合に、その欠損金を前事業年度の所得に繰戻して、納めた法人税のうち、納めすぎとなった部分を還付請求することができるというものです。 現在は「設立後5年以内の中小企業」など、一部例外を除いて適用が停止されていますが、実現すれば同4年4月以降、実に16年ぶりの復活となります。 注意したいのは、「ずっと赤字の企業」は使えないということです。国税庁の発表によると、同19事務年度で申告のあった法人件数は279万9 千件。黒字申告割合は32.3%です。つまり、7割の赤字企業は同制度を適用することができないといわけです。
2009/01/18
コメント(0)
-
「賄い」にご注意を
飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意を!■課税されないための要件は?(1)役員や従業員が「食事の価額」の半額以上を負担していること(2)会社が負担した金額(食事の価額-従業員等の負担額)が、月額3,500円(税抜き)以下であることこれらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。たとえば、500円の仕出し弁当に対し従業員が200円だけ負担した場合には、差額の300円が給与所得になります。また、従業員が半額の250円負担していたとしても、会社の1か月間の負担額が累計で3,500円を超えてしまうと、会社負担額全額が給与所得として課税対象になります。■食事の価額とは(1)飲食店の賄いや社員食堂のように自社で調理した食事を提供している場合には、食材や調味料等食事を作るのに直接かかった費用の合計額(2)仕出し弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払った金額■課税されない場合もある!(1)残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事(2)深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で食事代を補助する場合で、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を給与に加算して支給する場合(3)社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用は会議費ですので、通常は給与課税されません。
2009/01/13
コメント(0)
-
飲酒運転撲滅と企業の取り組み
■厳罰化でも悲惨な事故は後をたたず 今年も一年が過ぎようとしています。忘年会や新年会を控え、お酒を飲む機会も増えてきます。飲酒運転事故はひところに比べ減少しているものの、罰則強化にもかかわらずあとをたちません。少しくらいなら大丈夫、自分は大丈夫という気持ちが、なかなか撲滅されない理由かもしれません。■飲酒運転防止に努める 飲酒はプライベートなことですが、社員が事故をおこせば会社は影響を受けないわけにはいかないでしょう。 就業規則の服務規律に飲酒運転を禁じる条文を規定する企業も増えてきました。それは懲戒処分をするために規定されるものではあるのですが、社員の意識の中に交通違反をしてはならないという自覚と会社や家族、社会に対する責任意識を持たせるためとも言えるでしょう。この時期、社内文書やメールで回覧する等して、一層の共通の事故防止意識を啓発していくことが大事でしょう。■自動車事故と企業責任 飲酒運転に限りませんが、社有車を社員に使わせて事故を起こした場合は、企業は使用者責任と運行供用者責任を問われます。社有車をプライベートな用事に使わせていたときの事故も同様です。 社有車は業務上の使用に限るべきでしょう。さらに、マイカーを社用に使わせていた時の事故も、企業責任が問われます。 どうしても通勤等でマイカーを使わせなければならないならば、任意保険証券を提出させるなどして、十分な補償額が掛けられているか確認をする必要があるでしょう。 いずれにしても、車両管理規程を作り社員に周知させ、安全運転を心掛けるよう社内で取り組むことが大切です。
2009/01/09
コメント(0)
-
裁判員制度 日当・旅費は雑所得
今年5月から裁判員制度がスタートします。そこで最高裁ではさきごろ、国税庁に対して「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて」と題した照会を行いました。 国税庁の回答によると、裁判員や裁判員等選任手続きで出頭した候補者などに対して支給される旅費・日当・宿泊料は、「その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する」とされました。 雑所得の計算では、必要経費を差し引くことができますが、この場合は「実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額」を必要経費とできるとされています。 日当などが雑所得に当たることで注意が必要なのは、日当などのほかに雑所得がある場合です。雑所得には、年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが含まれます。裁判員制度の日当などとこれらを合計して、必要経費を差し引いた雑所得の所得金額が20万円を超える場合は会社員でも確定申告が必要となるのです。 ちなみに、裁判員の日当は一日最高1万円です。また、裁判員には選ばれなくても、候補者として裁判所へ出向いた場合は、最高8千円の日当が支払われます。
2009/01/08
コメント(0)
-
平成21年1月の税務
1月13日●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付2月2日●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>●源泉徴収票の交付●支払調書の提出●固定資産税の償却資産に関する申告●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>●給与支払報告書の提出-----------------------------------------------○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
2009/01/07
コメント(0)
-
オードリー
最近はまっている漫才コンビオードリーはココでお楽しみ下さい!
2009/01/02
コメント(0)
-
癒しの音楽
癒しの音楽はココからどーぞ
2009/01/02
コメント(0)
-
明けましておめでとうございます。
厳しい年になりそうですが、本年もよろしくお願いします!まさかあのトヨタが連結で営業損失を計上するとは‥来年度の生産計画も白紙の状態では、下請けはまったく生産計画が立ちません。ジャストインタイム方式では、下請けは、受注前に1~3ヶ月程度は製品在庫を自社の責任でかかえなければなりません。生産前には、当然、材料も発注しておくので、下請けは製品在庫と材料在庫を抱えています。製品が納入できず、かつ材料費等の支払や人件費の支払がくれば‥まさに、今年こそ生き残りをかけた厳しい年になりそうです。そんな状況でも気持ちは前向きにがんばらなければなりません。経営者が気持ちで負けてしまったら‥その会社に未来は無いのかもしれません。そんな後ろ向きな気持ちに負けないようにECHO&THE BUNNYMEN NEVER STOP と OVER THE WALL(壁を越えて)
2009/01/01
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1