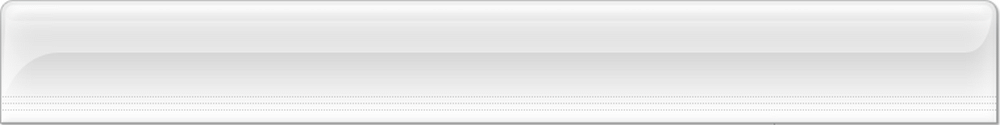全114件 (114件中 1-50件目)
-
告知みたいなもの
すっかり更新をしていませんが・・・ライブドアの方のブログでは、ぽつぽつと続けております。http://blog.livedoor.jp/mac02quackey/何かと使い勝手がいいのであちらがメインになってます。ただ、運営母体そのものがどうなるか・・・?こちらのログはとりあえずこのまま置いておきます。
February 20, 2006
コメント(76)
-
萬狂言金沢定例公演@石川県立能楽堂
はじめて狂言を見に行ったのは約1年前。そのときは橋掛り脇の一番後ろの席の券をもらったのだったが、今回はフンパツして、自腹で舞台正面3列目の座席をゲットした。今回はいろんな記念の公演らしい。八世野村万蔵追贈九世野村万蔵襲名披露公演増田秋雄傘寿記念ということで、「祝」をテーマにした三曲。●三番叟 三番叟:野村万蔵/面箱:炭哲男 大鼓:佃良太郎/小鼓:牧野唯士・住駒充彦・河原清/笛:吉野晴夫 万蔵さんが小気味よく舞う。喜びが全身から溢れる感じが好印象。目の前だったので迫力も満点だ。大鼓は元気でキレがあって気持ちよい。この手の音楽もいいモノだとはじめて実感した。 ただ、小鼓は終始ばらついて聞こえ、鈴の段では鈴の音が小鼓から少しずつ遅れていたのが気になった。・・・それとも、こういうものなのか?□小舞「宇治の晒」野村虎之介(九世万蔵長男)「住吉」野村祐丞 「小舞」というモノをはじめてナマで見た(汗)。 なんとなく、地謡の方に興味が沸く。●しびり 太郎冠者:野村拳之介(九世万蔵次男) 主人:増田秋雄 拳之介くんは昨年「伊呂浪」で見た。そのときはす~す~という息遣いが少々目立ったが、今回はそのようなことはなかった。増田秋雄さんは傘寿(80歳)とは思えぬ壮健ぶり。しびりが切れたと仮病を使って言い付けを拒むが、振る舞いがあると知ると治ったと言い、ならば買い物に行けと言われるとまた痛がる・・・わかりやすい筋で微笑ましく楽しんだ。●二人袴 聟:野村太一郎(八世万蔵長男)/親:野村萬 舅:野村祐丞/太郎冠者:野村扇丞 聟入りの日、気弱な聟は父親に付き添ってもらったところ、舅に父親も座敷に上がるよう勧められた。ところが袴はひとつしかなく、しかたなく親子で交互に穿き替えながら一人ずつ舅の前に出る羽目に。やがて両人一緒に座敷に来るよう誘われ、困った挙句、袴を二つに裂いてそれぞれ前に当てて座敷に出た。しばらくは何とかそれでしのいでいたが、舞を披露することになって、太郎冠者に見つかり赤っ恥。 とにかく爆笑の連続。聟が袴を持て余しぎこちなく歩くさまなど、太一郎くんは身体は大きいが純粋朴訥とした青年で、それがかえって世間知らずなムコどのらしかったし、何より萬さんの飄々とした感じが、訳知りのようで抜けている父親にハマっていた。舞を勧められたときに思わず親子で顔を見合わせるところなど、なんとも言えない表情は最高。太郎冠者の野村扇丞さんも間が絶妙で、達者なものだと感心した。 帰り道、少しの間だが久々に石引の並木を眺めて歩く。やや値は張ったが、いい秋の休日だったかな、と悦に入る。
October 16, 2005
コメント(2)
-
シンデレラマン
アメリカンドリーム。サクセスストーリー。米映画の王道。誰でも楽しめて、ふつうに感動する。おしまい。・・・これだけじゃあ、あんまりだからもう少し詳しく書く(汗)。まるでひねりはないものの、つくりはとても丁寧。貧困の描写とか、息子との約束とか、マネージャーの献身的な友情とか、随所に魅せるシーンが効果的かつ緻密に無駄なく展開される。中でも、クライマックスでボクサーの主人公が最後には勝つのだろうとは思っていても、いや本当に殺されてしまうんじゃないかと思ってしまうほどの迫力はすごかった。そして、何よりこれが実話だということ自体がすごい。でも、正直、涙を流すほどでもなかったな~あまりにもフツーの展開ということもあるけど、チャンスを掴んだ主人公がぬけぬけと「この国は素晴らしい」とぬかしたのに興醒めしたので・・・。このいかにもアメリカ的なのがハナについて素直に受け取れなかった。でも、この映画、アカデミー最有力らしい。そうか、そういうものなのか・・・
September 23, 2005
コメント(4)
-
「電車男」最終回
そうか、「卒業」をクライマックスにもってきたのだな。いやあ、よくできていた。家庭環境や交友関係などを扱ってエルメスのエピソードは増えているとはいえ、やっぱり主戦場はネットであり、主演はネットの住人たちと電車男・伊藤淳史であった。1000までのカウントダウンも(ありえないけど)この手法は感動的。とにかく、よくぞここまで膨らました。ネットの住人もそれぞれキャラを確立させ、白石美帆や豊原功輔はどんどんキャラを増幅させていった。母親に戸田恵子を登場させたり、小ネタも嬉しい。でもこの電車男、じゅうぶん饒舌だとは思う。・・・まあ、いいか。
September 22, 2005
コメント(0)
-
義経#37「平家最後の秘密」
う~む、ますますわからん。今回の大河では、義経は終始苦悩に満ちながらも、思慮深くものわかりのよい人物として描かれていたはずである。軍事のみならず、人の感情の機微にいたるまで大局的に大胆かつ繊細にみわたせる非常に優秀な武将として扱われていたようにみえる(と皮肉のひとつもいいたくなる)。こうした優等生的な人物設定にはまったく共感はできないものの、それが作り手の描きたかった世界なのだろうと思い、その設定を受け入れてきたつもりだ。ところがそんな思慮深いはずの義経が、平家から奪還した神器をあっさりと朝廷に返納し、そのことで頼朝の理解が得られないといじけて涙を流す。・・・おいおい、この期に及んで急にそんなおバカさんになられても困るぞ。頼朝が目指すのは武士自身が政事を仕切る世の中だということを義経自身が頼朝の口から聞いていたはずではないか。義経は都育ちゆえ頼朝とは朝廷に対する畏敬の度合いが違うのだ!というのであれば、そういう説明が必須であるのに、それらしき描写は一切ない。前回、戦後の無常感を漂わせまくっていた以上、戦勝に浮かれて理性を失ったなどということもありえない。弁慶あたりが一言忠告でもしていればそれなりのエクスキューズもあろうが、これまでの郎党たちのふるまいからわかるように、今回の彼らは弁慶ですら単に盲目な義経の追っかけに過ぎない。したがって、なぜ兄はわかってくれないのだと義経が涙を浮かべても、さっぱり説得力がなく、まったく共感できない。頼朝でなくとも「九郎は何もわかっておらん!」と怒りたくもなる。もうひとつ言うなら、安徳帝のすりかえ作戦の顛末もお粗末きわまりない。もっとダイナミックな展開になるかと期待したのに、単に平家の血筋がつながった、めでたしめでたし、ということなのか? それを義経が見逃したのは平家に対するシンパシーがあったからだ、ということを言いたいのかもしれないが、今さらそれを語ってどうする? 平家に恨みはありません、戦いは宿命だったのです、とても哀しいです、すりかえのことは見逃すから水に流してくださいとでも言いたげだ。この大河、役者さんはおおむね素晴らしいのだ。心配されていた滝沢くんですら、このところようやくさまになってきていると思う。映像はもともときれいだ。とにかく、脚本がどうにもこうにも。。。
September 18, 2005
コメント(0)
-
「がんばっていきまっしょい」最終回
くるぞくるぞ~と予測される王道の展開がことごとくまんま繰り出され、終始むずがゆ~い感じで、オッサンが見るにしてはなんともこっぱずかしいお話なんだけれども、結局なぜだか全話欠かさず見てしまった(汗部活ものっていうのがやはりどうにも気になってしまうのだな。若いときに完全燃焼した経験のない僕にとっては、ひとつのことに打ち込みそれゆえあれこれ思い悩む姿がどうにもまぶしく思えてしまう。それゆえ、前回の大杉蓮の台詞「俺は満足ぞ!」に全面的に共感し、涙腺をあっさりやられてしまうのである。う~む、完全にオッサンの感想だ・・・まいったな(苦笑)。だが、女子高生の明るく爽やかな青春物語でありながら10時台という比較的深い時間に放映したのも、秘かに見入っているオッサンがいることを思えば、あながち間違ってはいなかったのだろう。このお話で印象的だったのは、登場人物の呼び方。「悦ネェ」「リー」「ダッコ」「ヒメ」「イモッチ」 あ~書いてるだけで恥ずかしい(笑)。「ブー」 ブーいうな!「中田三郎」 なぜか彼だけフルネーム。中田三郎は、内くんのままだったらなあと残念に思う。あの騒動のおかげでたぶん2話ほど圧縮されただろうし。しかし、この出演者たちは今後どんどん一線に出てくるだろうね。鈴木杏はもともと実力あるけど、錦戸亮は硬派な感じがいまどき貴重だし、「リー」の相武紗季などは大抜擢もありそう。特に「ヒメ」の佐津川愛美は大注目。映画「蝉しぐれ」でふくの少女時代を演じるらしい。予告編を見る限り、実によろしい。・・・などと書いてて、やはりこっぱずかしいオッサンであった。。。
September 13, 2005
コメント(4)
-
「海猿」最終回
夏八木艦長の最後の訓示・・・絶対諦めるな!愛する者のために生きて帰ってこい!しびれた~!!丁寧なつくりで、壮大で、骨太で。ある意味予定調和的でオーソドックスだが、実に見応えのある良質なドラマだったと思う。映画も原作も知らないが、充分楽しめた。おお、来年「海猿2」が公開とな!?これは要チェックだっ!
September 13, 2005
コメント(2)
-
世界柔道閉幕
二日目以降、キューバの選手のタックルとか、ストレスがたまる試合多し。油断ではないのだろうが、一瞬にして勝負が覆る。厳しい世界だ。そんななか、薪谷選手の金メダルは感動的だった。勝って流す嬉し涙、負けて流す悔し涙。いずれもそれまでの過程で力を尽くしてきたからこそ。ただただ流されるまま生きている僕のようなナマケモノには、決して味わうことのできない尊い涙だ。
September 12, 2005
コメント(0)
-
衆議院総選挙
自民圧勝。というか、民主惨敗。勝ち組の皆様にとってはますます都合の良い世の中になるだろう。おめでとうございます。それにしても候補者の選挙活動をみるにつけ、つくづくあんな恥ずかしいことはできないと思う。
September 11, 2005
コメント(0)
-
義経#36「源平無常」
総集編?大半が回想。壇ノ浦で予算を遣い過ぎたとみえる。存在価値が不明だった後藤真希に見せ場がきた。無難にこなしたのには感心。安徳帝を生存させる設定は思わせぶりだけど、うまく活かされるのだろうか。
September 11, 2005
コメント(2)
-
「容疑者 室井慎次」
ものすごく楽しみにしてたのに・・・脚本にも演出にもおおいに問題あり。個々の役者さんの演技は申し分ないだけに残念。室井本人の心情を追うことについてはそれなりに成功していると思うが、彼を取り巻く人々の立場とか相互の関係が一見して分かりにくすぎ。警察庁と警視庁とどっちだかわからなくなる。観覧車に乗っていたおっさんは誰?新城の父?物語の進展についても、それぞれの展開に説得力をまったく欠いている。たとえば、新宿北署の刑事たちが室井のために尽力する理由がわからない。彼らのリーダー格たる工藤刑事(哀川翔)が室井に心を寄せていった過程が全く描かれていないせいだ。灰島の自滅も、それを誘うもっともらしいきっかけがないため、いかにも安直なオチにしかみえない。今までの「踊る」シリーズなら、コメディの一環として笑って許されようが、今回のような終始シリアスな展開では違和感しか残らない(その意味でスリーアミーゴスも浮いていた)。ただし、ラストでの新城の振る舞いは、筧利夫がキャストのトメであった理由を明らかにした。室井は青島化し、新城は室井化するのであろう。ちゃっかりと、続編への布石は打たれていたのである。
September 9, 2005
コメント(2)
-
世界柔道第一日
そんなに注目していたわけではないが、見始めたら意外に結構ハマる。●女子78kg超級:塚田真希【銅】 準決勝の中国の選手、強かった・・・完敗だ。しゃあない。●女子78kg級:中澤さえ【銀】 決勝では豪快にやられたが、きびきびと気持ちいい戦いぶりだった。 イキのいい娘が出てきたねえ。ちょっとグランパスの楢崎に似てる。●男子100kg超級:棟田康幸【銀】 決勝は残念。あんな形から投げられるとは。。。 でも、それまでの戦いは、背が低いのに切れ味抜群で完璧。 特に準決勝の投げ技(名称不明・汗)はものすごくカッコよかった! あと、お辞儀がとても心がこもっていて丁寧。ナイスガイだ!●男子100kg級:鈴木桂治【金】 明らかに調子悪そうだった。息があがってて体調不良なのかと思ったが、 やはり井上康生不在というのはすんごいプレッシャーだったんだね。 しかし・・・気合いで見事優勝!男泣き!加藤晴彦も泣いた!思いがけず、明日も見てしまいそう・・・
September 8, 2005
コメント(2)
-
碇知盛!~義経#35「決戦・ 壇ノ浦」
久々の「義経」レビュー(苦笑)。もはや「義経」に関しては深く考察することはやめ、なるべく自然体で受け入れることにしているが(その方が精神衛生上よろしい)、その意味では今回は素直に楽しめた。やはり物語のひとつのハイライトであるだけに、制作サイドも気合いが入っていたのだろう。さすがにちゃんとロケを敢行し(新選組!とはえらい違い)、演出も気合いが入っていた。やはり何と言っても義経vs知盛。金粉舞う中での格闘といい、八叟跳びといい、実に美しく効果的で、伝説の一戦にふさわしい。金粉は余計だとか、なぜ相手が教経でないのだとかクレームはあるだろうが、そういう批判もこの画の前には色褪せる。特に素晴らしかったのは阿部ちゃんの知盛。侍大将としての凛々しさ、殺陣の迫力、すべてがカッコよく、圧巻は最期。碇を抱え身体に巻き付けて背面から仰向けのまま海中に落ちて行く。歌舞伎「義経千本桜」の「渡海屋」「大物浦」にもそういう名場面(=碇知盛)があるらしいが(まだ実際に見たことがない)、それを充分意識し、そうとうこだわったシーンだったに違いない。NHKのガイド本によると義経が頼朝に追われ摂津から逃走するところで知盛の亡霊が現れるシーンがあるかもしれず、だとすればまさに「義経千本桜」の踏襲としてこのシーンはおおいに布石となるのではないか。そして、女官たちの入水も忘れてはならない。順々に海へ飛び込むところが誠に悲哀たっぷりで、特に松坂慶子扮する時子の最期の笑みにはぐっと胸にくるものがあった。なお、安徳帝替え玉説を採用しているが、これも「義経千本桜」に通ずるのか?つっこみどころはいくらでもあろうが、今回のように、キレイな映像だとかお気に入りの役者さんの演技だとか、良かったと思えた回は素直に讃えたい。そうすれば、今後も結構楽しめる・・・かも。
September 4, 2005
コメント(4)
-
十一代目市川海老蔵襲名披露@こまつ芸術劇場うらら
10ヶ月ぶりの歌舞伎ナマ観賞。しかし、この地方巡業直前に團十郎さんが再び体調を崩され休演。残念。●源平布引滝「実盛物語」斎藤別当実盛:市川海老蔵葵御前:市川右之助瀬尾十郎:片岡市蔵小万:市村家橘「実盛は今は平家方だが、秘かに源氏に心を寄せている」とか「女が握りしめていた源氏の白旗が平家方に渡らぬよう実盛がその腕を切り落としたが、その女は葵御前を匿っている九郎助の娘の小万だった」とか「実はその小万は平家ゆかりの捨て子だった」とか「瀬尾が小万の死骸を足蹴にしたため小万の子太郎吉に討たれるが、瀬尾こそが小万の実の父親であって、瀬尾は自分の孫である太郎吉に手柄を立てさせるためにわざと討たれた」とか「手柄を立てた太郎吉は葵御前が産んだ駒王丸(のちの木曽義仲)の家来になるが、その太郎吉こそ、のち実盛を討ちとる手塚太郎光盛である」・・・などなど、登場人物どうしの関係がかなり複雑。プログラムで筋書きをじっくり確認した上で観賞する。何といってもお目当ては海老蔵さんであるが、期待に違わずカッコイイ! 今回はわりと席も前の方だったので、お顔がよく見えて大満足。声も伸びやかで実に気持ちよい。やはりスターだなあと感服。なお、太郎吉が実は結構大事な役で、準主役といってもいいくらいだったが、演じる子役(ダブルキャストのどちらなのかは不明)が思いもよらず上手で感心した。出産を覗こうとして止められるところとか、ハナをたらして拭いてもらうところとか、実盛の真似をして馬のおもちゃに乗って得意になるところとか、実盛との絡みが実に微笑ましくてよい(子役に対しては得てしてそういう感情になってしまうが)。実盛の海老蔵さんもこれを余裕で懐深く受け止める。印象深かったのは、最終盤での実盛の台詞。太郎吉は成人したら母の仇の実盛を討つと言うが、その頃には実盛は白髪で顔が変わっているかもしれないと九郎助に指摘されたのを受けて。「その時は実盛が鬢髪を黒に染め、若やいで勝負をとげん。 坂東声の首とらば、池の溜まりで洗うて見よ。 いくさの場所は北国篠原、加賀の国にて見参~見参」この台詞で客席に大拍手が巻き起こり、一段と盛り上がったのである。実盛が加賀の地で最期を迎えるというのは、実盛の首洗い池など実盛の最期の逸話に関する史跡が実在する当地では(しかもこういうお芝居を見に来る人にとっては)周知の話であるが、その逸話がずばりそのまま予告されるドラマチックな展開におおいに興奮した。と同時に、やはり地元民だけに、みんなこのお話に愛着があるのだなあと不思議な感動を覚えた。#このあたり、当「実盛物語」で義太夫を勤められている竹本葵太夫さんもご自身のホームページで同じような感想を述べられている。やはり演者の方もそのように感じておられたことを知り、何となく嬉しい。●口上團十郎さん不在のため、海老蔵さんがすべてを仕切ってご挨拶。期待していた「にらみ」がなく、わりとあっさり終了。残念。ただ、「実盛物語」で瀬尾を演じた市蔵さんが、瀬尾は悪い奴と決まっているが「実盛物語」の瀬尾だけが唯一もどりでいい役になるので嬉しかったと述べられ笑いを誘う。そういえば「俊寛」に出ていた憎たらしい役人も瀬尾だったと思い出す。●お祭り團十郎さんが演じられる予定だった演目。代役として海老蔵が鳶頭を勤め、また、右乃助さんと家橘さんが芸者、市蔵さんが若い鳶で加わる。鳶頭の團十郎さんがおひとりで踊るはずだったのだけれども、構成自体を変えたのだろう。何となく眺めているうちに幕。「実盛物語」がきわめて濃厚だっただけに、いささか物足りない気も。まあ、舞踏というのはそういうふうに気を張らずにふわふわ眺めて楽しめばいいかと思うが、それでも正直なところ、團十郎さんの踊りを見たかったというのが本音。「待ってました!」の掛け声に「待っていたとはありがてえ」と答えるのは、やはり病気を克服した團十郎さんであってほしかった。今は、養生してまたいつか元気なお姿を見せてほしいと願うばかり。
September 3, 2005
コメント(0)
-
ガンダムとSWと。
#ニックネームをひっそりと変更している。特に意味はない。先日NHK-BS2で放映された「まるごと!機動戦士ガンダム」。9時間半の録画を数日に分けて見終えた。最初のうちは、シャアとセイラが兄妹だということすら忘れていたが、見ていくうちにあれこれ急速に思い出し、いつしかのめりこんでいった。アムロとララアの哲学的問答や、シャアのアイロニカルな台詞などは、当時中学生だった僕にとっては、いかにも知的でクールな響きであり、それまでのロボットアニメとは全く違うカッコよさを感じたものだった。今にして思えば、その理屈っぽさは少々気恥ずかしいのだけれども。映画三部作の合間に多彩なゲストが登場。みなほぼ同年代(苦笑)。錦織健がTVシリーズのエンディング曲を熱唱する。そういえばこんな曲あったなあ。すっかり忘れていた。「永遠にアムロ」というタイトルだったのか。・・・などとしみじみしながらも、一緒に口ずさめる自分に驚く。**********その勢いで「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」を観にいく。このEP3、単体の作品としても充分堪能させてもらったが、やはり、長年続いた一連の物語がつながったということが何より感慨深い。アナキンがベイダーに変貌する瞬間こそが見どころであり、それを確認し、得心すること自体が最大の主題であった。思えば個人的にSWに関して最も盛り上がっていたのは、高1の夏であった。ガンダムで壮大な宇宙戦記に魅了された後の、自然な流れだったかも知れぬ。「ジェダイの復讐」(=EP6)が劇場公開された年である。もっとも、それ以来、SWに特に注意を払っていたわけではなかった。後年上映されたEP1もEP2も、映画館では観ていない。ところが今回のガンダム祭りで当時のことを思い出したせいか、無性にSWを振り返りたくなった。EP6では、ベイダーが息絶える間際にアナキンとしての素顔を見せる。アナキンは、いかにしてベイダーとなったのか――それがEP3で語られるのであれば、何としても観たいと思ったのだった。それにしても、ガンダムといいSWといい、夢中になっていたのは、ゆうに20年以上も前のことであった。そのことに自分自身いちばん愕然としている。
September 2, 2005
コメント(2)
-
あれから1年
今日の「義経」は第33回。「第33回」といえば・・・そう、昨年の「新選組!」の第33回はあの「友の死」であった。あれから1年か・・・。毎日のように「新選組!」のことを考えて、ワクワクしていた昨年がなつかしい。今年の「義経」はいちおう見るには見ているけれども、そうした興奮はまったく感じられないだけに、余計にそう思う。・・・DVD、買っておいて良かった。
August 21, 2005
コメント(2)
-
出費の夏
16年モノの愛車シティをついに買い替え(というか廃車)。16年といっても特に遠出するわけでもなく、通勤にも使っておらず、週1ペースで近くに買物に行く程度しか乗らないため、走行距離はたった2万キロちょい(!)であった。ところが、ふだん屋根なし駐車場に放置してあるせいか腐食が進み、マフラーが腐って排気口がぼろりと落ちたのである。で、修理に出してみたら他にもあちこち悪い所が見つかり、修理に15万円かかるという。さすがは16年モノ。いや、感心している場合ではない。今15万円費やしてこの場を凌いだとしても、来年はまた車検で相当の出費を余儀なくされるであろう。クルマにはまるでこだわりはないが、ないとやはり不便だ。さすがにもはや年貢の納め時かとようやく買い替えの決断をした。新車は16年間世話してもらっているディーラーの担当者の薦めるままに、ホンダフィット1.3A。僕が決めたのはボディーカラーだけ。ビビッドブルー・パール。今週末、納車予定でございます。そんな中、愛機iMacが壊れた。突然電源が入らなくなってしまったのである。販売店に持ち込むと、よくある症状らしく、そのままご入院。この日記は家族のPCを借りて書いている。購入したのは4年前で保証期間はとうに過ぎていたため、修理費は実費。およそ5万円程度とのこと。・・・ああ、出費が続く。痛すぎる。
August 2, 2005
コメント(2)
-
九代林家正蔵襲名披露・特選落語名人会
でっかい仕事が終わった~!封印していた娯楽を解禁するのじゃ~!で、本日は「林家こぶ平改メ九代林家正蔵襲名披露・特選落語名人会」。場所はまたもやこまつ芸術劇場。仕事を早退し、電車で小松へ向かう。9月には歌舞伎の海老蔵襲名披露巡業にも行く予定であるし、昨年のこけら落とし以来、準ホームになりつつあるかも。~開演~●林家きくお(林家木久蔵師匠の息子さん)山で遭難した男が桃太郎に助けられ、現代に生きるさまざまなおとぎ話の登場人物たちと遭遇する創作落語。若いだけに勢いはあるが、一本調子なので聞いていて少し疲れる(汗●春風亭小朝「試し酒」ある大店の主人が客先で話をしていたところ、主人が連れてきた下男は酒豪だという話になった。客先の旦那はたいそう面白がって、その下男を家に上がらせ、酒を五升飲んだら小遣いをやろうと言う。下男は少し考えると言っていったん中座したが、やがて戻ってきて見事五升飲み干した。客先の旦那はその下男に、中座して何をしてたんだと尋ねると、「どれだけ飲めるかわからねえから、向いの酒屋で試しに五升飲んできた」。貫禄充分、バリバリの古典落語。田舎者の下男のどうにも憎めない感じが楽しく、さすがの名人芸だと感服。●林家木久蔵独特のすっとぼけたキャラクターが炸裂。飄々と観客を爆笑の渦に巻き込んでいく。ついには伝家の宝刀・先代正蔵のモノマネが繰り出され、気が付けば結局まくらだけで充実の終了(笑)。小朝師匠とは違った意味の味わいを堪能。~休憩~●襲名披露 口上司会(?)はいっ平くん。小朝師匠と木久蔵師匠がご挨拶。歌舞伎とは違って、襲名する本人はここでは何も語らないのね。最後は木久蔵師匠の音頭による三本締め。「よお~」という合いの手は「祝おう」という意味だと初めて知った。●林家いっ平 武骨な豊臣七人衆が、作法を知らぬがゆえに茶席で右往左往する創作落語。唯一茶の湯の心得のある細川忠興を頼りに、その振る舞いを加藤清正、黒田長政、池田輝政、浅野幸長、加藤嘉明が次々と真似ていき、福島正則がひねってオトす。展開が練られており、テンポのメリハリもよくなかなか聞きごたえがあったが、サゲが安易なのが残念。●林家正蔵「子はかすがい」大工の熊五郎は大好きな酒を断ち、今は真面目に仕事に励んでいるが、以前、吉原の女に入れこんで、妻子に家を出て行かれてしまっていた。ある日、熊五郎は偶然息子の亀に出くわし、その成長ぶりに感激する。母には内緒だと言って亀に多額の小遣いをやり、翌日一緒に鰻を食べに行く約束をしてその日は別れた。ところが、亀は持って帰った小遣いを母親に見つかってしまう。母親は亀が盗みを働いたのだと思い込み、金槌で亀をぶとうとするので、とうとう亀は父から貰ったのだと白状した。逆に、母親は熊五郎が一人で真面目に働いていると聞き、気が気でない。翌日、亀を鰻屋に送り出した母親であったが、どうにも落ち着かず、鰻屋の前を行ったり来たり。ついには鰻屋に上がり込み、熊五郎と再会を果たした。熊五郎は過去の経緯を詫び、妻もそれを受け入れ、結局親子三人は元のさやに収まることに。母が「こうしてまた一緒に暮らせるのも亀がいたからこそ。子はかすがいですねえ」と感慨深げに呟くと、亀が言う。「おいらがかすがいだって? 道理で昨日、金槌でぶつと言った」。人情噺の王道を真正面から堂々かつ丁寧に見せてもらった。テレビの中の「こぶちゃん」しか知らなかったが、さすがに大名跡を継ぐだけのことはあるとその芸をおおいに見直した。う~ん、大満足の一夜であった。
July 22, 2005
コメント(2)
-
恥ずかしながら、戻ってまいりました。
2か月以上も更新しておりませんでした。その間やたらと仕事が忙しく、そのわりにまるで出来映えに満足できず、報われる実感のないストレス満載の日々でありました。そんな僕を救ってくれたのは、TBSドラマ「タイガー&ドラゴン」でした。リアルタイムではとても見られないものの、毎回録画して4回も5回も繰り返し見ていました。毎日仕事は深夜まで及び、へとへとになって帰宅するのですが、仕事のことが気にかかりすぐ寝付けるわけでもなく、そうしてついつい録画を見直すのです。たたみかけられる数々の笑いや、時おり突然訪れる感動シーンは、いつの間にか仕事のことを忘れさせてくれました。睡眠時間は大幅に減ったものの、精神の疲れは確実に癒されました。昨年の「新選組!」に匹敵、あるいはそれ以上に、「タイガー&ドラゴン」にハマりまくりました。「義経」がまったく期待外れだっただけに、この番組があってくれて本当によかったとしみじみ思います。毎回元ネタをあたりしっかり予習をし、金曜日が来るのが首を長くして待っておりました。先日の最終回、ああ、もうこれで終わりなのかと寂しさを覚えつつ、その分、万感の思いを胸に、おおいに堪能させていただきました。「タイガー!タイガー!じれっタイガー!」まさか、文字にするといかにもふざけたこのギャグ(しかもコール&レスポンス)で大団円を迎え、その上、そいつに泣かされるとは思いもよりませんでした。仕事はあと3週間くらいこの状態が続きます。深夜の帰宅後、当分はまた「タイガー&ドラゴン」を見直すことになりそうです。それなら、何とかこの辛い日々も乗り切れることでしょう。
June 26, 2005
コメント(1)
-
タイガー&ドラゴン#01「芝浜」
【元ネタ「芝浜」】魚屋の熊五郎はいつも酒ばかり飲んでいる怠け者。女房に尻を叩かれて渋々商売に出かけ、芝の浜でサボっていたところ、大金が入った財布を拾った。家に帰った熊五郎は、これでもう働かなくてもいいと喜び、また酒を飲む。ところが翌朝目がさめると財布がない。女房は財布を拾ったのは夢だと言い、商売に励むよう諭す。熊五郎もそんな夢を見るなんてロクなもんじゃないと改心し、仕事に精を出し始めた。やがて商売は軌道に乗り、きちんと正月を祝えるようになるまでなった。その大晦日、女房は、例の財布を熊五郎の前に差し出す。熊五郎が財布を拾ったとき、また働かなくなるのを危惧してとっさに隠しておいたのだった。熊五郎は女房の気遣いに感謝しつつ、安心して酒をすすめる女房の盃を拒む。「また夢になるといけねえ」。**********前回のSP「三枚起請」はきっちり元ネタをなぞった筋書きだったが、今回はちょっとひねりがあった。リサが財布を拾ったこと自体はサクッと処理しておいて、これをトリガーとしつつ、リサが財布の持ち主の銀次郎に一目惚れしたことが夢だったと竜二が諭すという構成に仕立てている。で、健気にまた働き出したリサが不憫になった竜二は、銀次郎と再会させる、と。う~ん、なかなか面白い。しかも、その間に、「芝浜」に感銘を受けた虎児が、本業の取り立てに絡めつつ不器用ながら稽古していくさまやら、虎児と竜二の互いの境遇に関する感情の衝突やら、それを知り抜いた上でのどん兵衛の思いの爆発やら、メグミを巡る男たちのドタバタ恋愛劇の予感やら、てんこ盛りの内容が淀みなく進んでいく。そして、それらを最後に虎児が高座でまとめあげるのである。いやあ、実によくできている。でも、高座の噺と劇中劇が行ったり来たりして、かつ、その筋がストーリーとリンクして進行するなんて展開が、混乱せずすんなり受け入れられるかというと・・・厳しいだろうなあ。一般受けはしないだろうなあ。視聴率、また、よろしくないのかなあ。。。
April 17, 2005
コメント(1)
-
阿修羅城の瞳
染五郎さんの初主演映画だったから、興味はあった。でも、それ以外の予備知識はゼロ。好評だった舞台の映画化らしいけど、そういうことも無論知らない。たまたまシネコンの付近に用事があり、かつ、数時間ポッカリ空いたところ、その時間にやっていたのがこれ。じゃあ・・・と、軽い気持ちで観てみることにした。そんないい加減な気持ちで観ていたわりにはそれなりに収穫はあった。何といっても、染五郎さんが最高!歌舞伎のシーンはもちろん、キレのある殺陣、しなやかな立ち振る舞い、粋な仕草、ビシッと決まる台詞回し・・・どれをとっても実にカッコいい。時おり見せるエロい表情もとても色気がある。まさに「染ちゃん、傾奇いた!」と感服した。ただし、映画としては全般的につくりがあまりにチープ。まあ、CGを多用する伝奇ものは得てしてそうなりがちではあるのだが、樋口可南子や内藤剛志あたりの芝居は、この映画のテンションと妙な温度差があり、それがまたチープさをいっそう際立たせる。染ちゃん以外にこの映画のテンションにハマっていたのは小日向さんくらいか。う~ん、どこがどうとはうまく指摘できないけれども。惜しかったのは宮沢りえ。阿修羅になる前までは、めちゃめちゃ綺麗でめちゃめちゃ切ない。だが、阿修羅になってからの感情移入が難しい。特にラストの殺陣は・・・あらららら。一挙に興醒め。結局、専ら「染ちゃん」の格好よさを堪能する映画、という感じでしょうか。「阿修羅城の瞳」公式サイト
April 16, 2005
コメント(2)
-
いちおう犀川の桜
今日までに納品しなきゃならない仕事があったため、土日とも出勤でぐったりしていたのだが、おかげで今日はヒマ。職場から犀川が近いので、お昼に河原をぶらぶらと出歩いてみた。金沢地方気象庁によれば、金沢は本日が桜が満開だということらしい。で、いちおう写真を撮ってみた。う~む、ケータイのカメラのせいか、僕の撮影のへっぽこぶりのせいか、あまりキレイではないな・・・(汗)。まあ、天候も悪かったのだが。。。
April 11, 2005
コメント(2)
-
ぼんやりとした日々
このところ仕事がたて込んでおり、しかもまったく手応えがない。プロ野球シーズンが始まったが、まだまともに中継を見られない。そのわりに時おり泥酔し、翌日は二日酔いの自己嫌悪。何かこう、文章を書くという態勢に入れない。「義経」か~。いちおう毎回見ているのだけど、とりたてて書きたくなるような面白みがあるわけでもなく、さりとて文句ばっかり言うのも、自分自身、正直いい気はしない。ただ、この春から放映される「タイガー&ドラゴン」だけは、ひそかに激しく期待しておるのだ。・・・僕は何を言いたいのだろう?
April 7, 2005
コメント(2)
-
情愛・知略・勇気、あるいは嫡流・庶流~義経#11「嵐の前夜」
山奥で遭難した藤原泰衡を、義経は無事救い出す。父親が本心から我が子を見捨てるはずがないと親子の愛をひたすらに信じ、北斗星から自らの現在地を割り出しつつ木に残された刀傷を冷静に辿り、馬を巧みに操って急坂を駆け降りた。情愛と知略と勇気。もものふとしての器量を兼ね備えた涼やかな御曹子に、秀衡は「無謀だが、見事!」と感服し、藤原一族も心から頭を下げた。なかなかに爽快な場面である。だが、ここでも五条大橋と同様、「重要シーンの2話ぶった斬り」という物語構成上致命的な過ちを犯してしまっている。ここはやはり、藤原氏一同が義経に平伏したところまでをひとくくりとして一話を完結させるべきであった。そうすれば、視聴後の爽快感は義経の英雄性にまたひとつ伝説を加えるであろうし、今後の展開としても、これで義経が奥州藤原家にすっかり受け入れられたという共通認識を明確に視聴者に植え付けることができたはずである。つくづく惜しいことをしたものだ。とはいえ、こういった姑息な構成手法は別にすると、全体的には、前回あたりから含みのある味わい深い展開になりつつある。今回でいえば、泰衡救出の際の急坂下りは当然一の谷に繋がるのであろうし、鹿ヶ谷の陰謀に加担した後白河法皇に向けられる清盛の伶俐な視線や、それに対する後白河法皇の怯えようは、両者の緊張関係の高まりが鮮明に表現されていた。ここはさすがに名優同士である。若手役者の演技に関しても、朝ドラ「ほんまもん」のときは目も当てられぬ程にダイコンであった海東健は、今回の佐藤忠信ではそこそこ健闘していたと思われ、上戸彩についても、うつぼの存在意義自体はまだ良くわからない部分はあるものの、義経の立場を慮って都に去っていくさまはなかなかに切ないものがあり、少し見直した。また、前回はネタ系だけでお茶を濁したため言及しなかったが、平家、源氏、藤原氏それぞれの嫡男の振る舞いが実に興味深い。当代の武家における「嫡流」の重みが強烈に提示されている。父の重荷を引き受けると心に決めた重盛は、義経が奥州に去ったと能天気に胸をなで下ろす宗盛とは違い、奥州に対する警戒をいっそう深める。流人として潜伏中の頼朝は、親から言い聞かされた自らこそが嫡流だとの誇りを胸に、義経をあくまで「庶流だ」と当然のように突き放す。人は好さそうだが事なかれ主義の泰衡は、やがて義経への情と家名存続の宿命との板挟みとなって、悲劇を巻き起こす張本人となるのだろう。そして、義経は――厳然と「庶流」であるにもかかわらず、不幸にしてそういった区別をする思考を持ち合わせてはいない。自分は「源氏の棟梁の血を引く者」であるという事実が、彼にとっての唯一無二の行動指針である。それゆえ、源氏以外の者に対しては警戒を怠らないが、源氏所縁の者やこれを慕う者たちはすべからく味方だと信じて疑わず、盲目的に情愛を傾ける。しかしながらそのことが、「嫡流」に絶対の価値を置く頼朝とは相容れず、悲劇を生むのは周知の通りである。
March 20, 2005
コメント(2)
-
【ネタ系】義経#10「父の面影」より
タッキーの喋り方が少々イラっとくると思っていたら、リズムとか抑揚の付け方が、「ヒロシ」っぽいことに気づいた。ヒロシです・・・こんな景色を見ていると・・・なにゆえ争いごとが起こるのかわかりません!ヒロシです・・・父・義朝の名、昔語りは耳にしましたが・・・父の姿形は存じません!ヒロシです・・・ヒロシです・・・ヒロシです・・・今日のところはこれくらいで。内容的には、今回はけっこう良かったと思いますよ。
March 13, 2005
コメント(0)
-
怒濤の急展開、その意図は~義経#09「義経誕生」
前回までのまどろっこしい展開から一転、今回は物凄いスピードで話が進む。鞍馬を脱出したかと思ったら、次のシーンでは一気に尾張まで飛び、家来を次々と抱えつつ、結局平泉の手前まで行ってしまった。この目まぐるしい流れのおかげで、今日は居眠りせずに済んだ(苦笑)。最近「義経」についてボロクソに言い過ぎた嫌いがあるので、せめて珍しく退屈しなかった今回くらいは、好意的にこの物語を捉えてみたい。前回までののんびりした話の運び方から比べると、今回の怒濤の急展開は異常である。だが、これほど徹底した詰め込みようは、かえって意図的なものを感じる。つまり、今回は鞍馬脱出から始まり、盗賊の襲撃、初めての殺生、烏帽子親のいない元服・・・という数々のエピソードとともに、喜三太、弁慶、伊勢三郎、駿河次郎ら主要な家来が集結していく実にドラマティックな話であって、膨らまそうと思えば3話くらいは軽く作れる内容である。にもかかわらず、あえてそれらを1話でまとめたということは、2005大河「義経」は、そういった血沸き肉踊る冒険活劇的物語などは指向していないとの宣言にほかならない。すなわち、2005大河「義経」は、実父を失い、母と離れ離れになり、父と慕う清盛とは敵対せざるを得ない義経が自らの運命に翻弄されながらあくまで人との絆を希求し続ける悲哀に満ちた生涯を、じっくり丁寧に描くナイーブな物語なのである。それゆえ前回までの遮那王の苦悩はくどいほどに厚く描き(描き切れたかは別として)、今回の奥州道中はびっくりするほどあっさり済ませるのも、制作意図がそういうものだとすれば、なるほど整合性は認められよう。いみじくも今回、義経がどうあっても平家は敵かと呟いた。そして弁慶がその覚悟を決めさせ、自らもその運命を共にすると誓うと、義経は目を見張った。それはまさに義経が自身の中にあった迷いと決別した瞬間であり、この描写によって、今まで義経が思い悩んでいたことの中核が平家への未練であったことが明らかになった。ようやく前回までの退屈な描写が一瞬にして意味を与えられ、もやもや感がやっと消化された気がする(ならば今までのくどくどとしたじれったさは無意味だったのかと問われれば身も蓋もないが)。義経のもとに続々と家来が集まってくる。そして義経は彼らを悉く召し抱える。義経自身、身近な人との縁が薄く、それゆえ縁を求める者の気持ちがよくわかるのであろう。この点も、義経の孤独ゆえの人恋しさを示すものとして非常に象徴的であった。なお、遮那王出奔を知った平家が追捕命令(宗盛は「ついほ」と言っていたが「ついぶ」では?)を出したにもかかわらず、義経たちに遭遇することすらできなかった。これは当時の平家の強力な軍事力を考えると奇跡的であり、急な命令だったため軍備が整わなかったからだと解釈するほかない。だとすれば、前回までの遮那王に対する平家の警戒に至っては、実はまったく切羽詰まったものではなく、包囲網もほとんど機能していなかったのであって、前回まで遮那王が京都近辺でぐずぐずしていられたということも、そう考えれば合点がいく(ということにしておく)。もっとも、こういったことは今回ようやく納得できたことであって、本来ならその場面場面でその都度きっちり共感させてほしいものである。その意味で、依然として完全に信頼するには到底至らず、手放しでワクワクする気にはなれない。今後の展開をクールに見守るばかりである。#「好意的」と捉えてみたいと言いながら、結構皮肉っぽい語り口になってしまった。まだ充分懐疑的だと自覚。
March 6, 2005
コメント(1)
-
語れない~義経#08「決別」
父と慕った清盛との苦渋の決別、そして母・常盤との再会と別れ・・・物語上、大きな見せ場となるはずの今回であったが、またしても肩透かしを食わされた。観ていて感情が震わされるわけでもなく、語りたくなるような感想も特に思い浮かばない。実際、今日までこの日記に何も書くことができていない。言いたかぁないが、僕にとってこの「義経」は(少なくとも現時点では)まったく退屈である。なぜなのだろうと考えたところ、たぶん義経(遮那王)に魅力を感じないからではないか。心理描写が決定的に不足しているうえ、タッキーの台詞回しや表情が一本調子なため、まるで感情移入ができないのだ。これでは「北条時宗」の和泉元弥の二の舞いだ。それでも僕はまだ希望を捨て切れずにいる。だって、題材的には絶対面白くなるはずなのだから・・・。きっと来週の日曜夜も、結局NHKにチャンネルをあわせていることだろう。
March 4, 2005
コメント(4)
-
狂言の現在2005~野村万作・萬斎狂言会@金沢市文化ホール
●墨塗大名:野村万之介/太郎冠者:高野和憲/女:石田幸雄曲目で既にネタバレしているし、ここでこういう行動をとるのだろうなということも丸わかりなのに、果たしてその通りまんまと笑わされる。おそらくそういった動きやら間やら表情が絶妙なためで、まさにこれが芸というものなのだろう。とりわけ、万之介さんの表情が豊かで印象に残った。●武悪武悪:野村萬斎/主:野村万作/太郎冠者:深田博治公演前に萬斎さんが今日の曲目の解説をしてくれたが、「墨塗」がお子様ランチだとすると「武悪」は骨のある本格料理だとのこと。なるほど、たしかにお芝居ふうで劇的な曲であった。武悪の成敗を命じる主の迫力や、太郎冠者が武悪に襲い掛かる悲痛な覚悟など、前半は狂言らしからぬシリアスな緊迫感がみなぎる。だが後半は、一転して笑いの要素がたたみかけるように次々と投下される。ぐいぐい調子に乗ってくる武悪と、これに応ずる主のやりとりがたまらなく可笑しい。今日は両親を連れていったのだけど、実はいままで狂言を見に行ったことがなかったそうだ。ところが、両親は、聞き覚えがあるフレーズがが多かったと言う。どうやら祖父や祖母がしょっちゅうこういった言い回しをしていたらしい。こういう話を聞くと、あらためて「空から謡いが降ってくる」という金沢の土地柄をしみじみと実感するのであった。
March 2, 2005
コメント(2)
-
じれったい~義経#07「夢の都」
前々回あたりから、遮那王に対する平家の警戒が強くなってきている。その様子を見て、金売り吉次も奥州行きを勧めている。弁慶や静との運命的な出会いも既に済ませた。しかし、まだ遮那王は京に居る。遮那王が幼い頃、清盛を父と慕い、清盛が福原に抱いた夢に深く共感しているということは承知している。こうした思いと自分の運命との間で揺れ動く遮那王の葛藤も、それが必須の描写であるということもわかる。そして、福原の海を目の当たりにしてようやく自分と清盛との間にある隔たりを悟るという流れも、それ自体はまあ納得できないでもない。だがそうやって遮那王が迷っていられるということは、実はまだそれほど遮那王の身に危機が迫っているわけではないという印象を与えないとも限らない。特に今回は清盛が福原へ行ったり、徳子の入内が決まったり、乗合事件があったりして、平家としても遮那王どころではない様子である。そのため、遮那王が追い詰められているような切迫感(=奥州行きの理由付け)はむしろ弱まっているのであって、奥州行きの意志を固めたという今回の展開は唐突な感が強く整合性を欠く。結果、どうもすっきりと受け入れることができない。そもそものちの義経が電撃的な軍事作戦を得意としたことを考えれば、本来なら、遮那王の奥州行きも電撃的に決断する方がふさわしいような気がしてならない。それとも、今回の義経はひたすら慎重で思慮深い設定だとでもいうのだろうか。(そんなことはないとは思うが)もしそうだとしたら、今までの滝沢君を見る限り、彼の一本調子の演技では、申し訳ないがそのような微妙な味わいは出せそうもない。先週書いたこととも重複するが、まず先に清盛とは敵同士であるという自らの運命に充分葛藤させるべきかと思う。そしてその後に遮那王に対する警戒が急激に強まり、そこで遮那王が自らの処遇を一挙に決断し、疾風のごとく京から姿を消すという展開の方がしっくりくる。そうすれば、遮那王のナイーブな苦悩と、源平が再び対峙していく緊迫感がスピード感をもって両立し、物語上もメリハリがつくように思えるのだが・・・。僕のこの生意気な物言いが単なるいちゃもんであってほしいと思う。のとのち、ああ、あのときのシーンはこういう展開の伏線だったのか、と後悔させて欲しい。しかしながら、現状では、制作者がこの物語をどうしたいのか、僕にはどうもまだよくわからないのである。
February 20, 2005
コメント(3)
-
中井頼朝、期待大。~義経#06「我が兄頼朝」
源頼朝が清盛に捕われたのは14歳のとき。毅然とした顔つきが印象的だった若武者は、偽物の太刀を手にして、何食わぬ顔で髭切りの太刀に相違ないと答えていた。そして今、流刑地の伊豆にある彼は、流人の分際でありながら、かつての家来筋が身の回りの世話を焼き、愛人とともに穏やかに暮らしている。かと思えば、激しい気性を全開にする北条政子を軽くあしらい、都の情勢に関しては逐一情報を送らせて思念を巡らせている。満を持して中井貴一が登場した。子役の頼朝が存外に凛々しかったのとは対照的に、中井貴一の頼朝は、クネクネとした物言いで、のらりくらりと流人生活に甘んじている。それがまた深謀遠慮がありそうで、実に油断ならない男であることを含んでいる。頼朝の言動に異常な反応を示す北条政子との対比も面白く、これを演じる財前直見とともに、中井頼朝、期待大である。他方、遮那王は。平家の警戒が徐々に強まる中、遮那王は父と慕った清盛を敵とする踏ん切りが付かない。平家の内部もまた、幼少の頃親しく遊んだ知盛や重衡は遮那王を敵視する気が起こらず、何より清盛自身が遮那王への愛慕の念を感じ続けている。結果、遮那王に対する決定的な処断はまだ下されない。このあたり、本来なら、もっとスピードアップして遮那王への捕獲の手が矢継ぎ早に下された方が、追い詰められ感が出ていいかとも思う。だが、前述のように、遮那王も、清盛をはじめとする何人かの平家の者も、互いを憎からず思っており、敵だと確信するには至っていないのである。そして、そういった遮那王と平家の特殊な関係がこの物語のキモである以上、それでも戦わざるを得ない運命を受け入れる彼らの葛藤のプロセスを描き切らないうちは、先には進めないのであって、その意味で、この期に及んではスローダウンしてしまうのもやむを得ない面はある。もっとも、そうした葛藤を描きつつ一挙にスピードアップして切迫感を煽るべく、エピソードの順序を変えるという手もなかったわけではなかろうに・・・という口惜しさは依然として残る。
February 13, 2005
コメント(0)
-
名シーンを冒頭に配置する愚挙~義経#05「五条の大橋」
五条大橋である。義経が弁慶と初めて出会う伝説の場面である。このドラマでは「月」が象徴的に使われているが、この夜も月の光が京の桜を静かに照らし、幻想的な雰囲気を醸し出していた。ワイヤーアクションも思ったほど不自然ではなく、遮那王の殺陣に盛り込まれた洒落た仕草が伝説性に彩りを添える。弁慶を打ち負かした滝沢遮那王は、もの寂しげでありつつも凛々しい顔つきがキマっており、なかなかいいシーンに仕上がっていたと思う。・・・が、こういう名シーンを、回の冒頭にもってくるのは断じてやめて欲しかった。ミステリーもののように「この次はどうなるの!?」と展開の意外性自体を楽しむドラマならば、視聴者の関心を引き付けるためにこの後の話の筋を隠して次回まで引っ張る手法も理解しないでもないが(個人的には好きではないが)、これは大河ドラマ「義経」なのである。五条大橋で義経が弁慶を打ち負かす、なんてことは、このドラマを見ようとしている者なら誰でも知っている。話の筋を隠す必要など毛頭ないのである。この場面でいえば、前回、母と清盛との関係を知った遮那王が心乱れた状態で弁慶と遭遇し、その流れのまま弁慶と対峙すべきであった。ならばこそ、母から貰った笛を鴨川に落としてしまったアクシデントも同情を誘い、遮那王の去り際の台詞も心に響くはずである。そして、弁慶が悔しさとともに驚愕の念を抱きつつうずくまるのを背に、遮那王がこともなげに凛と去っていくところで終われば、五条大橋の伝説は一話の物語として完結するのである。今回の五条大橋のシーン自体は完成度は高かったとは思うが、前回とふたつに分断してしまったことで、心乱れているはずの遮那王に感情移入する間を失ってしまっている。何ともったいないことか。そんなことを考えていたら、今回の最後もまた「引っ張り」パターンだ(呆)。平家の武士に唆されたならず者たちが遮那王をおびき出したところで終わったが、どうせ彼らは遮那王に返り討ちに遭うのだろう。そんな見え見えの流れを次回まで引っ張ってどうするというのだ。そんな姑息な手段を使おうと頭を巡らす余裕があるのなら、遮那王が彼らに襲撃されるところまでをきちんと見せて、源氏残党に対して平家の警戒心がいよいよ強まってきたという今回の重要な流れをビシッと強調してもらいたかった。場面場面はそれなりにいい出来のモノも多いのだが、変に間延びしていたり、逆に無駄な盛り上げ方を講じてみたり、どうも全体の構成のメリハリの付け方がまったく間違っていると思う。ああ、もったいない・・・!
February 6, 2005
コメント(6)
-
ようやく手応えあり。~義経#04「鞍馬の遮那王」
日曜日は、20時からの総合に続き、22時からのBSでも見たものの、いずれも途中で寝てしまった。単に僕自身が疲れているだけなのか、それともやっぱり退屈なつくりなのか。正直言って少々萎えかけていたのだが、後日時間を作って録画をもう一度見てみたところ、ようやくある程度の感触を得た。遮那王は成長してタッキーに代わったが、自らの生い立ちを聞かされた幼い頃の衝撃が、今でもずっと尾を引いていた。かといって、鞍馬山中にあってはそれを確かめる術はなく、解決の糸口もない。そもそも何をもって解決というのかもわからない。かえって苛立ちがますます募るばかり。鬼一法眼にその思いをぶつけ、閉塞を紛らすかのような鍛練の日々を送る――ある意味、実に説得的な流れだ。義経という人物を語るには、彼の人格形成に大きな影響を及ぼしたはずの鞍馬時代の描写が不可欠となろうが、この物語においてはそれが今回の話で一気に果たされた。鞍馬時代が義経の戦闘能力および軍略の基礎を作ったということが示され、また、そうした鍛練の動機付けとなった自らの苦悩は、今後彼に絶えずつきまとうであろうということも予感させる。どうやらこの物語では、「悲劇のヒーロー」という最も支持が得られそうな義経像にストレートに迫ろうとしているようだ。実をいえば僕自身が義経に対して抱いていたイメージというのは、「軍事以外はまったく幼稚ないし痴呆」というどちらかといえばネガティブなもので(司馬遼太郎が書いた「義経」がいちばんしっくりくる)、このドラマの捉え方とは異なる。たとえば、遮那王が兵法を独学するシーンがあったが、僕のイメージからすれば、彼はあくまで戦場での一瞬のひらめきが勝利を呼び込む正真正銘の「天才」であって、書物で学ぶという行為とはまったく無縁であるように思える。しかしながら、こういった個々人の固定観念がすっかり覆されるくらいきっちりと人物像が表現されていなければ、ドラマとしてとりあげる意味がない。その意味で、今後の方向性をずばりと示した今回は、ドラマ的にはとても意味のある回だったと思うのである。タッキーも、台詞回しというかカツゼツにやや難があるものの、「わかりやすい理由に真正面から悩む青少年」を誠実に演じている姿勢には好感が持てる。何といっても、ジャニーズらしく身のこなしがしなやかで、今後の戦闘シーンにも期待が持てそうだ。主要人物のキャラ設定が如実に表れていたという点では、松平健はさすが。重厚、老獪、忠実など弁慶を語るには幾つかのパターンが考えられるが、マツケン弁慶は喜怒哀楽が分かりやすく、実に人間臭い。比叡山と平家の諍いの中で陥れられ憤るさまや、平家の公達から刀を奪って無邪気に喜ぶさまなどは愛嬌たっぷり。平家を敵視する理由付けも明快だ。松平健も従来のハマり役というべき凛としたお殿さまとはがらりと様相を変え、おおいにイキイキと演じているようで気持ちがいい。このドラマの弁慶はこれでいくのだ!ということが一発で理解できた。前回までとの連続性があまり感じられなかった点は少し残念だが、今回は単体でも充分手応えを感じることができたといえる。今後の展開に光明が射してきた気がする。やはり、日曜日の本放送時に寝てしまったのは、単に疲れていたに過ぎなかったのだろう。
February 5, 2005
コメント(0)
-
もっと面白くなるはずなのに~義経#03「源氏の御曹子」
母・常盤との別れ、鞍馬寺での暮らし、覚日律師や鬼一法眼との邂逅、そして、自らの出自の判明――と、物語上大きな転機となる出来事が次々と盛り込まれた今回であったが、またもや期待外れに終わってしまった。遮那王の心の乱れが伝わらず、まったく感情移入できないのである。神木くんには申し訳ないけれども、無邪気なだけの牛若時代ならカワイラシさだけで充分通用したものの、鞍馬山に預けられた遮那王は少し重荷だったと思わざるをえない。もっとも、子供ながらに頑張っている神木くんにその責めを問うのは酷だろう。そこそこ演技を知っているふうなのが裏目に出てしまった感もある。それよりも糾弾すべきは、新宮十郎義盛(行家)や金売り吉次の登場の仕方があまりにも唐突すぎることだろう。彼らは遮那王を巡って思惑をうごめかせている連中である。その点についてあらかじめもっときちんと説明がなされていれば、遮那王が背負わされた運命を思い、同情し、こうした視聴者の想像力の助けを得ることによって、遮那王にぐっと感情移入できたのに・・・と思ってしまう。お徳に遮那王の運命を予告させた場面も、これではうまく活きてこない。タッキーを早く登場させたいためかしらないが、この端折り方は実に残念だ。ここらへんの話はもっと面白くなるはずなのに、何とももったいない。だが、今回の「義経」は、視聴率は結構いいらしい。タッキーが出た今週はさらによくなるのだろうか。う~む、何か釈然としない。
January 23, 2005
コメント(2)
-
脱落注意~義経#02「我が父清盛」
この展開のヌルさでは、視聴者が飽きるのではないかとおおいに危惧している。話の筋としてはそれなりに興味深いものがあるはずなのに・・・なぜだろう?屏風絵の落書きを巡る牛若と清盛のやりとりはよかった。屈託なく目を輝かせて「我が父清盛」を慕う神木くんと、牛若の伸びやかな心根を包み込むような父性たっぷりの渡清盛。だが、心に響くような台詞があったかというと・・・(略)。せっかくのいい場面なのに、もっと盛り上げられなかったか。牛若と清盛の子供達とのかかわりの描写も、バランスがいまいち。宗盛のヘタレぶりをこれほど強調する必要があるのだろうか。たしかに宗盛はやがて平家の総帥として源氏と戦う際、戦闘能力の欠如(というか無関心)を露呈することになるのだが、そこを対比の軸にもってきても「義経」を語るドラマとしてあまり意味があるとは思えない。それよりも、いずれ実際に合戦の矢面に立つ知盛や重衡との心の交流を、少なくとも宗盛と同程度に扱った方が、戦場であいまみえるときの悲哀の伏線になってよりドラマチックなのではないか。全体の雰囲気としては今まで馴染んでいた大河チックで、決して嫌いじゃないのだが、なんとなく淡白というか、ぐっと惹き付けるような決め手に欠ける。神木隆之介くんと稲森いずみさんの新鮮さ、あるいは渡哲也さんの懐の深さといった、個々の役者の魅力で今のところ何とかもっているという感じ。役者頼みのつくりでは、来週からタッキーが出てきたところで状況は変わらないおそれがある。ただ、そろそろ牛若も深刻な場面に直面するようになるはずなので、そうなれば嫌が応でも盛り上がってくるだろう・・・と、まだ希望は捨てまいぞ。
January 16, 2005
コメント(0)
-
義経#01追記
先日、「違和感あり」との記事を書いたが、今日再度見直してみて、ちょっと補足(ないし訂正)したい。別にどこからも文句がきたわけではないが(苦笑)。全編を通しては、大御所の役者さんが雅びな衣装を身にまとい、時代劇らしい言葉を使い、そこかしこに伝統的な美術や芸能がちりばめられ、ナレーションが語り口調で歴史背景を説明するなど、実にいわゆる大河ドラマらしいつくり。雰囲気としては「花の乱」や「北条時宗」に近いものがある。その意味での「違和感」はまるでない。冒頭の一の谷の場面は意図したほどにはまるで効果的ではなかったとは思うけど、これも「違和感」という表現は少し違うかも。オープニングについて。義経の一生を象徴しているということはわかった。銀河がうず潮に投影され、その激動から現れた白馬(当然、義経のこと)は、鞍馬っぽい山々をバックに、桜並木(五条大橋?)や緑の林中(奥州?)を駆け抜け、なんだかんだあって、厳島神社(平家を表す?)での舞、静御前らしき切り絵、文書(腰越状?)などが挿入されつつ、白馬は再び森に帰っていく・・・みたいな。なお、切り絵は「宮田雅之」氏の作品と判明。この名前を見て、10年くらい前のNHK金曜時代劇「天晴れ夜十郎」にも宮田氏の切り絵が使われていたことを思い出した。そういえば当時はキャッチ的な使われ方が実に装丁ふうで非常に印象的だった。今回の切り絵はおそらく静なのだろうが、それ単体ではとてもいい感じだとは思うけれども、やはり統一感という点ではしっくりこない。う~ん、残念。本編では、やはり今回は清盛と常盤の心情に尽きる。清盛に対面した常盤であったが、ここでの常盤は、三人の子が処刑されるのは仕方ないとは思わない。子らが殺される姿を見たくないから先に自分を殺してくれとも懇願しない。気丈にも、義朝に託された子供らの延命を乞う。そんな常盤の健気さに清盛は心惹かれる。そして、美貌に目を奪われたというのではさすがに生々しいが、清盛の実母に似ているという情けの部分が強調され、頼朝助命の経緯とも相まって、本作で語られるであろう清盛の父性ないし包容力がここで表現されていたのであった。もっとも、こういった描写が再度見直さなければわからないというのはいかがなものか。まあ、単に僕自身の感受性が鈍かっただけかもしれないが・・・。あと、特記すべきは平家嫡男の重盛。一本芯の通った良心派であるだけに、勝村政信というのはちょっと線が細いかと思われたが、案外悪くない。ただし、「口の端」(くちのは)を「くちのはし」と言っていたのは聞き逃さないぞ。なお、実に魅力的な神木くんであったが、彼はタッキーよりむしろ上戸彩に似ている。これはどうでもいいことですが(笑)。
January 11, 2005
コメント(2)
-
違和感あり・・・だがまだ評価は早い:義経#01「運命の子」
物語は、一の谷の坂落としから始まる。だが、この点にまず違和感あり。義経が一躍名を高めた象徴的な合戦であるので、これを冒頭にもってくるというチョイス自体は悪くない。しかも、「新選組!」ではとんと見られなかった合戦シーンのロケであり、一瞬、期待した。ところが、実際に見てみるとさっぱり迫力がない。そもそもこの合戦は、圧倒的に少ない軍勢が遠回りをして一気に敵の背後を突くという壮大ではあるが困難を極める軍略を立てたこと、難所を克服してその着想を勇敢に実行したこと、そして結果的に華々しい戦果を挙げたことで、義経の軍事的天才性を端的に示すものであるが、そうした前提がないままでは、伝説的な「奇襲」の緊迫感が伝わりにくい。そうでない以上、せっかくのロケを活かして映像で魅せてくれるのならばいうことはないのだが、残念ながら映像上もあまり効果が現れていない。逆落しの迫力もいまいちだし、敵兵が慌てふためく描写も中途半端で切迫感が薄く、第一、義経主従の戦いぶりがあまり強そうに見えない。最近NHKの何かの番組で、尾上菊之助(現・菊五郎)が主演した大河「源義経」の一の谷の場面を放送されていたが、それの方が白黒であるのに全然迫力があった。せめて初回視聴者向けに義経主従の顔見せをしたかったかというと、いくら早暁だとはいえ暗くて人の顔がよく見えず、とりわけ彼らの人となりを示す言動があったわけでもなく、人物紹介としての効果も果たしていない(この点、「新選組!」は初回冒頭の架空の事件で各登場人物を端的にキャラクターづけする言動があったのだが・・・と、ついつい比べてしまう)。ここで、ナレーションが入る。この合戦に参陣していた宗盛、知盛、重衡らと義経は一緒に過ごしていたんだよというようなことが語られる。その設定自体は構わないのだが、彼ら三兄弟はこの坂落としには直接関わっていないので、リンクとしては弱い。それをもって時代をさかのぼるきっかけにするのはちょっと強引すぎるような。う~む・・・先行きが不安になってきた。オープニングも微妙。音楽は総じて美しい。終盤ややまったり気味なのが気になったものの、前半の荘厳な感じなどはスケールの大きさを感じさせる。だが、映像は詰め込み過ぎの感あり。白馬は義経を象徴しているのだろうけど、銀河から飛び出てきたり、突然切り絵風の絵が挿入されるのがよくわからない。いずれ物語が進めば納得できるようになるのだろうか・・・。本編も全般的に地味で、間延び気味。たしかに清盛が頼朝や牛若らの処刑を思いとどまったという事実は必須だし、そういう決断に至るまでの清盛の心情を押さえることも大事。そして、清盛が実は情に厚く、それゆえ義経との間に葛藤が生まれるというのがこの物語のキモなのだろうとは思う。だが、この一連の描写は必ずしも視聴者が次回以降も見たい!と思わせるような展開にはなっていない。どうせなら、平治の乱の経緯とか義朝の非業の最期をもう少し丁寧に描き、すっかり没落した源氏の無念というものを視聴者に植え付けた方が効果的だったように思う。いかん、いかん。せっかくの初回なのだから、苦言ばかりでなく、いいところを探そう。今若に先を歩かせ、乙若の手を引き、牛若を抱く常盤が、雪の中に都を落ちていく。この姿は義経記の描写というか、何かで見た錦絵から飛び出たようで、侘しくも美しい悲劇の始まりを予感させる。幼い子たちの衣装も綺麗。牛若の屈託のなさがよい。赤ん坊の牛若も実にいいカットを押さえたと思うし、何より五歳になった牛若を演じる神木くんがピカイチ。期待値は高いぞ。で、予告編が一番面白かったかも(苦笑)。さすがに滝沢君は凛々しいし。まだまだ評価を決めつけるべからず。これからきっと面白くなる(と期待する)。とりあえず、次回も見ます。
January 9, 2005
コメント(0)
-
書けてない
2か月近く更新してなかった~。年も明けてしまった。仕事もそれなりに忙しかったが、それだけのせいじゃないのだ。単に、書くという作業をしなかっただけ。ひたすら見たり読んだりすることが楽しかった。「新選組!」は当然最後までじっくり拝見しましたよ。何度も何度も見返したし、総集編もアンコールも見た。レビューも実は46回と47回は書き上がってる。でも、肝心カナメの48回「流山」と最終回「愛しき友よ」をこそ書かねば自分の中で完結しないと思い、されどさらっとは書き流すのにはもったいなくて、結局いまだ公開できてません。正月は能・狂言・歌舞伎のテレビ番組が多いということを初めて知った。当然、見まくったし、それに関する背景を知りたくて本やネットを読みまくった。その他、物凄く待望していた映画「ハウルの動く城」やNHK「大化改新」も見た。これらは期待ほどには面白くなかったけど、年末年始はフツーにバラエティ番組も無邪気に楽しんだ。明日TVで放映される「鉄道員」を前に、浅田次郎の著作も読み返してみたり。で、そんなことをしてるうちに、いよいよ2005年大河の「義経」がもう始まってしまう。ここ最近は平家物語や義経関連書籍を読みあさり、すっかり義経モード。インプットとアウトプットの両立が今年の目標。うまくバランスをとって荷重にならないように。「新選組!」の最終レビューは、いずれ機を見て書き上げられれば、ひっそりとアップいたしまする。。。
January 8, 2005
コメント(2)
-
タイトルだけで涙~新選組!#45「源さん、死す」
総合、BSに引き続き、録画したビデオも含めて4回繰り返し観たが、タイトルに「第45回 源さん、死す」と出るだけで、そのたびにぐっとくる。初回視聴時は前回の予告編を、2回目以降は訪れるその瞬間を瞬時に思い出し、今まで観てきた在りし日の源さんの人柄を思い重ねては、いずれも冒頭からいきなり胸が締め付けられるのである。タイトルだけでここまで感情を揺すぶられるとは何としたことか。今回の話は鳥羽伏見の戦いという幕末のクライマックスともいうべき大事を扱ってはいるが、それがタイトルになるのではなく、紛れもなく「源さん」が主題であった。派手さはまったくないが人望の厚い一人の実直な男との壮絶な別れであった。それだけに、やはりあの弾丸を弾き飛ばすCGは興醒めだ。あちこちのブログで言い尽くされているが、言及せざるを得ない。公式サイトの特集「源さんへのオマージュ」で説明してある通り、一瞬の奇跡を源さんに与える演出意図は理解できる。CGを使用すること自体も否定はしない。だが、効果的に見えてこそのCGである。あれではあまりにも仕上がりが悪く(酷なようだがこの場面に限っては小林さんの演技プランも含め)、まったくの逆効果だ。源さんの花道を飾るというなら、今こそロケを敢行してほしかった(淀千両松でやらずにどこでやる)。だが、その後の隊士たちの演技がすべてを救ってくれた。歳三が「勇も総司もいないのにと何やってんだ・・・!」と、島田が「魂が抜けないようもっと強く抱き締めろ」と滂沱の涙。とどめは斎藤。「激烈な喪失感」とでもいうべきか、何とも言えない表情を見せ、咆哮しつつ薩摩兵に突進して斬りまくる。他方、大阪城の勇のもとに霊となって源さんが現れるCGは、発想としては安易ではあるが、またCGかよという違和感は一瞬で、その後の源さんの語りかけがたまらなく心に響いてくる。源さんが死んだということを悟ったときの勇もまた絶妙である。涙を溜めながら微笑み返す勇に対し、深々と頭を下げ消えゆく源さん。安易だろうと何だろうと、二人が別れの挨拶を交わせたことは本当に良かったと思う。源さんは逝った。食い詰め浪人や百姓上がりらの吹きだまりのような荒んだ新選組にあって、ひとり穏やかに彼らを見守り、父親のように慕われた朴訥な男が逝った。歳三は言う。「刀の時代は終わった」と。源さんは「寂しいこと言わんでください」と珍しく血色ばむ。源さんという縁の下の良心を失った新選組は、ますます凋落の一途を辿っていく。
November 17, 2004
コメント(3)
-
半月ぶり
日記、滞りがち。ネタがないわけじゃない。むしろちょくちょくエンタメウォッチを楽しんだ。書きたいレビューも多い。だが、仕事が忙しくなってきたこともあいまって、書くことまで手が回らなかった。まずはプロ野球日本シリーズでのドラゴンズ。50年ぶりの日本一に向け気合いを入れて注視していたが、あえなく栄冠を逃す。これでしばらく立ち直れない日々。あとは映画。「笑の大学」と「隠し剣 鬼の爪」を観た。どちらもなかなかの佳作。特に「笑の大学」では役所広治さんの演技に唸らされた。とはいえやはり「新選組!」の偉大さには叶わない。レビューは第41回から3回分中断しているが、そのどれもが素晴らしく、おおいに感動している。ざっとポイントだけ述べると、「観柳斎、転落」は個人的には今まで最大のサプライズ。このレビューに関しては、8割方書いたところで筆が止まっている。「龍馬暗殺」は直球勝負。最終場面で勇が涙を流すところがこの「新選組!」のキモ。そして「決戦!油小路」。凄いのひとこと。あの「友の死」を凌ぐとさえ思う。何といっても、谷原章介さん、中村勘太郎さんの迫真の演技。あとは歌舞伎。今日11/3のことだが、金沢で「勧進帳」を観た。弁慶は松本幸四郎さん。重厚かつキレのある弁慶を堪能。ラストの飛び六方はさすがキマっていた。爽快!とまあ、こんな感じでさらっと振り返れたら書き溜めることもないのだろうけど、いちいちこだわりたいというのが元凶。困った性分だ。
November 3, 2004
コメント(0)
-
スウィングガールズ
見終わった後、間違いなく幸せな気分になれる。だが同時に、何とも口惜しい感覚に捉われてしまう。全般的には欠陥だらけのダメダメ映画なのだ。なのにこんなに感動的な爽快感が残るのはなぜなのか。吹奏楽部との邂逅にそもそも大いなる無理がある。ジャズバンドを結成する動機付けや、それに傾倒していく心情の表現も甘い。上達していく過程の説得力はまったくもって乏しい。「スウィング」というキーワードをもっと前面に出すべきであろう。随所に見られるありえない展開は、コメディとしての演出(イノシシ撃退など)で処理されているならば問題ないのだが、それがなされぬまま放置されるのは単なる不自然なご都合主義であり、不愉快にさえ思える。時間的制限もあるのだろうが、それにしても構成がとにかく雑すぎるのである。しかしながら、クライマックスにおけるガールズたちの演奏がそういった欠陥をすべて帳消しにしてしまう。これがたった数ヶ月練習したにすぎない演奏とは・・・! 吹き替えなしだという話が俄かには信じがたいほど上手だ。ブラスバンド(トランペット&フルート)をかじった経験のある僕としては、4ヶ月という練習期間を聞けば、なるほどぎりぎりリアルな成果だということがわかる。さぞかし必死に練習したのだろうなということが想像され、彼女たちの頑張りには素直に感動を覚えざるを得ない、本編でも、初めて楽器に触れたのが夏休みで、演奏会本番が豪雪の冬と期間的には合致する(が、だからこそ、そのリアルさを裏付けるべき描写の不足が惜しまれる)。観客が思わず総立ちになって全員でスウィングするという展開は容易に予想できたものの、その予定調和を快く受け容れられることが嬉しい。ビッグバンドジャズの魅力、おそるべし。この映画を見る際の心構えはただひとつ。彼女たち自身が演奏していることを事前に知ることである。それさえ知っていれば、この演奏も展開の延長線上、どうせ吹き替えなのだろう・・・などと白けてしまうことを防げる。終わりよければすべてよし、と純粋に楽しめること請け合いである。褒めているのか、けなしているかと問われれば、断然褒めているのである。#スーパー店員の大倉孝二さん、吹奏楽部部長の高橋一生くん。「新選組!」フリークとしては、河合耆三郎や桑名藩主松平定敬を想起して思わずニヤリとしてしまう・・・よくないことだ。
October 16, 2004
コメント(2)
-
萬狂言金沢定例公演 ~真似づくし~@石川県立能楽堂
「初」狂言ですっ!わくわく!といっても、実はタダ。地元新聞のチケットプレゼントに応募したところ運良く当選したのである。萬狂言金沢事務局から送られてきた封筒には「野村扇丞」の印。おおっ!我が自宅から徒歩10分程度のところに金沢和泉流の狂言師さんが住んでおられるとは!(もしかして中学校の後輩になるのかも?)と、妙なところに感激しつつ、仕事をそうそうに切り上げ、やはり狂言初観賞の友人とともに本日出かけていったのであった。思えば中学校の授業以来の能楽堂。当時はまったく興味がなく、そのとき何を見たのかさっぱり記憶がない。今日の座席は最も橋掛り寄りの一番後ろ。最後部のいちばん左座席といえば、サッカー日本代表のバスならば、昔はカズ、今はヒデが座る王様シートであるが、能舞台では上等な席とはされていない。本舞台は真横から見ることになる。まあ、タダなので文句を言う筋合いではないし、むしろ、歌舞伎では幕見席がほとんどの僕にとっては、役者さんの表情がはっきりとわかるほど近い(揚げ幕はまさに目の前!)ことに充分満足である。で、開演。ブザー以外にとりたてて合図もないうちに、役者さんが揚げ幕からしずしずと橋掛りを歩いてくる。客席の照明は落ちない。これが狂言の始まりなのだと軽い驚き。能の合間に演じられるものだということをあらためて実感する。●蚊相撲 大名:野村扇丞/太郎冠者:炭哲男/蚊の精:野村与十郎 最初は聞き慣れない台詞回しに一瞬戸惑ったが、じき慣れてきた。やはり表情が見えるのはよい。 太郎冠者といえば若造の家来というイメージだったが、炭さんという人は扇丞さんより随分ご年配。しかし、最後に大名に投げられるところでは、若い主人の無体さが出ていて、それはそれでいい感じだったと思う。 ●伊呂浪 子:野村拳之介/親:野村萬 お子さまものには無条件で頬が緩む。(悪い癖?) 一句一句ごとにす~す~と息を吸い込むのが気にはなったが(そういうものなのかな?)、それもまた可愛げ。●止動方角 太郎冠者:野村与十郎/主人:野村萬/伯父:野村祐丞/馬:吉住講 「寂蓮童子六万菩薩、静まり給えへ止動方角」。 う~ん、いい調子♪ 主が傲岸に威張り散らすところが見どころだそうだが、果たして、萬さんは凄い迫力だった。太郎冠者に先を行けと命令されて、揚げ幕付近まできたときは、その表情やキレのある動きやらをまさに目の前で見ることができ、ぎょっとするほど怖かった。与十郎さんの太郎冠者も、だんだん腹が立ってきて、やがて調子に乗っていくさまに、いいぞいいぞと思う。そして最後のシーン、太郎冠者がつい主人の背に跨がってしまう絶妙のタイミング。この下げを知らなかったこともあり、思わず大笑い。いやあ~堪能した。総じてお声がとてもよく通り心地よい。なにより間が絶妙で、みなさん愛嬌がある。いずれの下げもじんわりとほのぼのした気分になった。ドシロートは最初はなんでも感服しちゃうのだけれども(第一、筋を知らないし・苦笑)、まあ、今のところは、このいい気分に素直に浸らせてくださいな。萬狂言金沢定例公演 ~真似づくし~TMD Network
October 12, 2004
コメント(3)
-
「藤堂」ではなく「へーすけ」~新選組!#40「平助の旅立ち」
三谷「新選組!」の魅力は数あれど、特筆すべきはその緻密で親近感溢れるキャラクター設定であろう。近藤勇は従来、抜群に胆力が据わり、コワモテで無骨な男として描かれることが多かった。もちろん当作品でもそういった面はあるのだが、この勇はとにかくひたすら人が好く、人の話をふむふむと聞いてはうじうじと思い悩む。その姿はまるで剛毅とは言い難く、よく言われているように池田屋以降舞い上がって傲慢になるようなこともなく、一貫して、親身になって仲間たちを励まし、ともに苦労をしながらも懸命に率いてくれる、ちょっと頼れる兄貴のような存在である。主役として扱うなら、言われてみればそのように人間臭く設定する方が、若者の苦悩を描けるため確かに妥当だ。総司もそう。飄々と人を斬る天才剣士であるが、独特の雰囲気を醸し出し何故か人に愛される男というのが従来のイメージ。草苅正雄(古い!)の陰りのある総司、あるいは「壬生義士伝」で妖しげな狂気を発していた堺雅人扮する総司が、極端ではあるが、「特異な人」という従来からのイメージに近い。ところが当作品の総司はまことに幼く、不治の病に対する振る舞い方もまったく普通の人のそれである。たしかに腕も立つが、初めて人を斬る時には恐れ、実際人を斬った後は興奮し、悔やむさまも隠さず描かれる。一言でいえば、みな未熟なのである。未熟なまま激動する時流に身を投じ、一様に悩み、挫折し、苦しむのであり、それゆえ一般人の我々が容易に感情移入できるのである。で、平助である。藤堂平助の従来の描かれ方はこんな感じか。伊勢藤堂家ご落胤との噂もあり、どこか高貴な匂いがする武士である。北辰一刀流の名門伊東道場で鍛えただけあって、時勢にも聡く、ある種嫌味な面さえあり、当然プライドも高い。試衛館一派には友誼を感じてはいるが、自身の信念に基づき決然と新選組を去る。だが、この作品では、あの幼い総司よりもさらにオミソな役割を担っている。常に劣等感に苛まれ、しかし勇に認められたことに感激し、誠実な彼は必死に頑張って成長しようと健気に日々奮闘している。そして今、敬愛するふたりの師の間で揺れに揺れるのである。そもそも従来の物語で彼は「藤堂」と表記されることが多いように思う。ところが、当作品では常に「平助」と下の名で呼ばれている。むしろ「へーすけ」とひらがなふうに口に出したいくらいである。それほど親しみやすく愛すべきキャラクターである。それだけに、今回の別れは心に沁みる。総司が死を目前としていたことを知り、平助は自分の甘さを思い知る。総司も、決心の鈍っていた平助の背中を押す。親友であり目標でもある総司との爽快な別れである。「旅立ち」というのも何とも深いタイトルではないか。総司も平助も、大人への階段を一つ上がった。ただしそれが死に向かう階段であったのが、何とも言えず悲しいのである。「つらくなったら戻って来い」。平助に対する勇の別れの言葉も、それが叶わぬことを知るだけに、いっそう彼の非運を嘆くのである。なお、平助についての分析は、白牡丹さんのblogにて今までの各話にわたって極めて綿密に検証されている(藤堂平助くんを分析っ その1、その2、その3)。ひじょうに読みごたえがあるので、ぜひご一読されたい。
October 11, 2004
コメント(1)
-
嗚呼、試衛館~新選組!#39「将軍、死す」
原田左之助がまさちゃんと夫婦になった。試衛館以来の仲間たちが久々に集まり、これを祝う。烏合の衆の新選組を法度で締め付けるしかない立場の歳三は微妙。心根を知り尽くしている試衛館以来の同志に関してはそのような法度で縛る必要もないのであって、それだけに彼らに対しては後ろめたい思いでいる。この点に関して最近衝突を繰り返していた永倉とは、とりわけ顔を合わせづらい。そんな歳三を、永倉は「悪いわけがどこにある」と、わだかまりを見せずに迎える。河合の切腹処分の一件で、歳三が山南の死を重く受け止め、自らの役割を果たそうと憎まれ役に徹していることを永倉は思い知った。鬼には鬼の苦労がある。永倉は「愉快愉快」と試衛館当時の雰囲気を再現することに心を砕き、「今夜は鬼の副長と、俺はゆっくり飲みたいんだ」と歳三に酒を酌む。江戸っ子の潔い心遣いに、歳三も照れくさそうに気を許す。左之助は終始、上機嫌だ。意中のまさちゃんと一緒になれたことはもちろん、何より試衛館の仲間たちが集まって飲めることが楽しい。まあ、いつも通りの光景なのだが、その変わりなさが皆には頼もしい。周平が浅野薫に唆されて脱走騒ぎを引き起こした。逃げる浅野を発見したのは斎藤。だが彼は、その哀願するさまを見て斬らずに逃がす。何の感情も見せずに人を斬り続けていた斎藤にも、変化が起こっていた。悪い夢にうなされ、河合の介錯をためらい、脱走を企てた谷三十郎にもいったんは翻意を促す。理不尽な理由で死にゆく者たちを目の当たりにするうちに、人の命を奪うことの重みをひしひしと自分の痛みとして感じ始めていた。仏を彫ることでかろうじて精神の平衡を保つほかなかった。斎藤のことを、粛々と任務を遂行するだけのキャラクタだと捉えていた僕の考えはまさにアサハカなり。迷い始めた斎藤とは対照的に、総司の生命への嗅覚は研ぎ澄まされていく。かつて人を斬ることに躊躇していたとき、斎藤に「お前はモノを食うのにいちいち何かを考えるのか」とダメ出しされたが、その斎藤に対して今夜の殺気の無さを指摘し、浅野を逃がしたことを看破する。自らの生い先が長くないことを悟った総司は、その生きざまがますます苛烈だ。不逞浪士への斬撃は魔物のように鋭く、弱味を見せるものに容赦はない。周平に対しても。可能性があるのにそれをモノにできない不甲斐なさが歯痒くてならない。もはや自らは天然理心流を継承し試衛館を守っていくことができそうもないだけに、近藤家を継ぐべき周平の自覚の無さに我慢がならない。生き急ぐ総司には、弱者の痛みを汲み取る余裕はない。総司に責められる周平の姿が、平助にはかつての自分のように映る。劣等感に悩む苦しみは身に染みて味わってきた。しかし平助は、勇なら、その苦しみを包んでくれることも知っている。己の器量の中で存分に生きることが尊いと信じることができる。だからこそ、今では自信を持って「私は剣の道に生きます!」と試衛館の先輩たちに力強く宣言できる。周平を全身全霊で庇う源さん。試衛館当時から長らく勇に尽くしてきた源さんは、肥大していく組織を寂しく思いつつも、近藤家の跡取りを育て上げることに自分の役割を見い出していた。勇の度量を知るだけに、その後継者の重圧も理解している。養子縁組を解消することで周平の助命を嘆願するが、勇がその意を汲んでくれるであろうとも信じていた。勇の度量の大きさ。香取慎吾も今回はなかなか頑張ってその威厳を表現してくれた。周平との養子縁組は解消したものの、「周平」の名はを引き続き名乗るよう命ずる。試衛館を率いる近藤家は「周平」でなくてはならない。そして、勇は依然として周平に期待している。平助に対したのと同様に、勇は周平が人の痛みを知る人間だということを知っている。「俺はお前を信じている」。試衛館の頃から変わらず、勇は人を信じ続ける。
October 9, 2004
コメント(0)
-
彷徨える悲しみ~新選組!#38「ある隊士の切腹」
河合耆三郎は往生際が悪かった。だが、それが本来自然な態度。今にでも飛脚が届くのではないかと淡い望みを抱く姿は実にリアルで、その等身大の感情は現代の我々にも容易に想像がつく。それだけに河合の切腹は痛々しく、心痛は重い。観柳斎も100%私利ではなく、怒りの鉾先をすべて彼に向けるのも憚れる。切腹の理由はまったく理不尽であるが、もはや自分たちは法度から逃れられない。そのように自分たちで自分たちを規定してしまったのだ。罪深き我が身を痛感し、島田が、左之助が激しく嗚咽する。歳三はすでにその覚悟はできていたが、我ながらあまりにも酷い決着に思わず柱に頭を打ち付ける。斎藤は悪い夢にうなされていた。すべてを悟りきっているかのようだった男も、その重みに耐え切れなくなってきている。悲しみはどこへもぶつけられず宙を彷徨う。受け止めてくれるべき局長はこの場にいない。
September 30, 2004
コメント(5)
-
ネタ備忘
この土日、ワケあって(?)東京&千葉へ。本来の用件ではすっかり疲れてしまったが、書きたいネタはそれ以外のこと。○浅田次郎「天切り松 闇がたり」 往復の車中にて痔1巻「闇の花道」と第2巻「残侠」を読む。 胸のすくような痛快話。涙なしでは読めぬ人情話。 文句なく大傑作。遅読の僕が夢中になって文庫2巻を読破。 →もちょっとだけ詳しい感想もどき○九月大歌舞伎「菊薫縁羽衣(きくかおるゆかりのはごろも)」 土曜日にちょいと歌舞伎座まで足を伸ばし幕見席にて。 成駒屋の坊ちゃんたちが勢ぞろい。 微笑ましくって顔がほころびっぱなし。○新選組!#38「ある隊士の切腹」 日曜日の深夜に帰宅し、録画しておいたものを見る。 どんなに疲れていてもコレだけは絶対見なけりゃならぬ。 すると、予想以上に重い展開、何とも胸を締め付ける。後二者については、後日項をあらためて。
September 26, 2004
コメント(2)
-
守る者と攻める者~新選組!#37「薩長同盟締結!」
新選組の限界、ということをこのところ痛感する。既成の枠組みの中で物事にあたろうとする者と、その外側で新たな枠組みを生み出そうとする者の勢いの差は明らかだ。守る者と攻める者の構造的な宿命か。自分が斬った浪士の妻のために、松原忠司は愚直にも心を尽くし、刺されてもなお女を庇った。松原と隊の名誉のために、斎藤は松原の介錯をし、未亡人を斬り捨て、その責は歳三が一身に引き受けた。「最後まで女を救おうとした松原の想い。その松原の仇を討った斉藤の想い。そして、すべてを自分のせいにして収めたお前の想い。それぞれの想い、しかと受け止めた」。新選組は自己犠牲による「鉄の結束」をもってこの難局を乗り切ろうとする。処分を受けるいわれはないという長州の誇りを、竜馬は薩摩に認めさせた。長州と組んで幕府に歯向かうための逃げ道が欲しい薩摩に対しては、帝のためにという大義を与えた。「自分のところが一番大事じゃき。それでええがじゃ」。竜馬は薩長両藩がともに藩益を主張するのは当然だといわんばかりに平然とこれを受け容れ、両藩が互いに利益を享受できる「大人の付き合い」を提案する。新選組は相変わらず隊内統制に手を焼いている。「俺たちは今まで以上に一つにならなければならない」。勇は悲痛な覚悟を口にする。その一方で、坂本竜馬は薩摩と長州の同盟を鮮やかに成立させ、その瞬間、形勢は一挙に逆転した。「難しい話をまとめるがは、面白いのう!」竜馬は爽快に笑い飛ばす。新選組はますます硬直化し、竜馬はますます軽やかだ。だが、だからといって、薩長が正で新選組が邪だとか、竜馬は優れているが勇は愚鈍だなどと決め付けることには躊躇する。勇たちはみなそれぞれ自らの使命に忠実であった。彼らは彼らなりに懸命に想いを巡らせ、真摯に自らの信念に取り組んでいた。河合耆三郎は、自分の裁量で左之助のために五十両を融通する。あくまでも自らの職務と仲間のために誠実に。歳三は悪者になることを厭わず、総司はそんな歳三が心配でならない。勇は松本良順に長州攻めの参加を咎められ、「よからぬ企みがありそうだというだけで、何の証しもないまま一国を攻め滅ぼそうとしている」との指摘に一瞬考え込むが、もはやどうにもならない。彼らの信念は時勢に合致しておらず、防戦一方の中で無理が無理を呼び、結果的に非道な結果を招く。哀れといえば、哀れであるが、崩れゆく秩序の中で自らの立場を全うせんと奮闘する姿は尊くもあり、彼らを一概に非難する気にはなれないのである。
September 22, 2004
コメント(4)
-
内向きの火種の向こう岸で~新選組!#36「対決見廻組!」
今回新選組が「対決」する相手は見廻組。京の治安維持という同じ目的をもつ幕府の機関どうしの主導権争いである。だが、そんなことで争っている場合ではないのである。長州も薩摩も藩論をひそかに攘夷から開国に転換し、幕府に対抗する新たな手立てを探り始めている。そして坂本竜馬は、双方が実利を享受できる「ビジネス」という大着想をもって、両者を同盟させるべく画策を開始したのである。そんな動きがあるとも知らず、新選組は火事の始末を巡って見廻組と対立している。そしてその内部では、相変わらず内向きの火種がくすぶり続けていた。近藤周平は彼に対する男の嫉妬と戦っている。谷三十郎は自身の処遇に不満を募らせている。伊東甲子太郎の最新兵学講義は大盛況で、甲州流軍学はすっかり時代遅れとなった。武田観柳斎の存在感が次第に薄らいでいく。松原忠司は、自分が手をかけた長州藩士の妻のことが今でも気にかかっている。親しみを込めて「まっちゃん」と呼ばれる心優しい男は、斎藤の忠告も無視して、その女がいるであろう火の中へ身を投じていった。古株の幹部隊士も膨張する組織を持て余し始めている。自らの考えが及ぶ範囲での課題消化に汲々としている。源さんは、大所帯になった新選組に感慨も深い。だがその一方で、自分の立場のありように戸惑っている。勇にお茶を汲み、勇の身の回りの世話をし、常に勇の傍で勇のためだけに奉仕していた頃が懐かしい。それが叶わぬ今、せめて勇の跡取りとなる周平の力になってやりたいと願う。総司は寺の宝探しに興味をそそられる。でも誰も相手にしてくれない。変わりゆく新選組に一抹の寂しさを感じるが、源さんのように別の使命を見出せるほど大人ではない。左之助と平助が加わってくれてホッとする。江戸を発つ前、この三人で居酒屋で酒を飲み、粕屋新五郎の剣技に無邪気に感嘆した日のことが懐かしい。「ヤンチャ三人衆」に名を連ねた平助だったが、彼は彼で苦悩の中にいた。伊東は隊内での勢力拡大に余念がなく、かつて門下生だった平助も当然自分の勢力下にあると信じて疑っていない。平助自身、伊東のことは確かに尊敬しており、伊東と行動を共にできることを嬉しく思う。勇と伊東、敬愛する二人の師の下で働けると思えばこそ、伊東を勇に引き合わせたのだった。だが、伊東の秘められた野心にも薄々は気づいており、その漠とした不安が最近ますます現実味を帯びていくように感じる。勇に対する伊東の評価。伊東が勇と距離を置いていることを実感し、心が痛んだ。伊東は勇に心酔している平助に充分配慮したつもりだったが、その想いの深さをまったく測り違えていた。講義に遅刻した平助を叱責する伊東。彼にとっては門人に対するいつも通りの対応であって、特にさしたる他意はない。だが平助は、その態度に居心地の悪さを覚えざるをえなかった。自分が伊東を引き入れたのは間違いだったのではないか――平助は自責の念に苛まれ、たまらず総司の誘いに救いを求めた。とはいえ律義な平助は、師と仰いだ伊東のことを見限ることはできない性分だった。かくして平助は、板ばさみの苦しみを誰にも言えずにひとりで抱え込む。長州の裏で暗躍する「天狗」は捨助だった。「あいつは尊皇でも攘夷でもないはず」と歳三は訝るが、実は長州自体がいまや「攘夷ではない」のである。「捨助も不思議な人生を歩んでいるのだなあ」と勇は言う。確かに勇は見事な采配で火災の混乱を収めた。勇の威厳あふれる姿は佐々木只三郎を感嘆せしめた。だが、警察・消防レベルを超えた勇らの想像の及ばない「不思議」な事態が、現実に進行しているのである。おそらくは三谷氏が皮肉を込めてつけたこの「対決見廻組!」というタイトル。身内の闘争に終始するうちに、大きく動いていく時代から取り残されていく。これが新選組の限界であった。もっとも、これを愚かだと揶揄することはできない。動乱の世にあって、警察・消防の役割を立派に果たしているのである。ただ不運だったのは、内向きの火種の向こう岸で、ひとりの天才がその瞳を激しく燃やし始めたことだった。#捨助が火事を起こした「萬屋」って中村獅童さんの屋号だね。偶然?
September 12, 2004
コメント(2)
-
「恋女房染分手綱 重の井」~九月大歌舞伎@歌舞伎座
東京出張の帰り、幕見にて観覧。前回の海老蔵のときとは違い、幕見席は空いていた。●恋女房染分手綱 重の井(こいにょうぼうそめわけたづな しげのい)・重の井:中村芝翫・腰元若菜:中村橋之助・三吉:中村国生・調姫:中村佳奈・本田弥三左衛門:坂東弥十郎幼い調姫が江戸への輿入れを嫌がり、乳母の重の井は困り果てていたが、馬子の三吉が持っていた道中双六で遊ぶうちに調姫の機嫌が直る。重の井は三吉に褒美を取らせ、自らの名を教えたところ、三吉は我が母ではないかと言う。実は確かに三吉は、重の井が以前不義密通した家中の者との間の子だった。そのことに重の井も気づいたが、姫の乳母に馬子の息子がいるとなれば縁談に差し障る。重の井は母とは名乗らぬまま、泣く泣く三吉と別れた・・・というお話。やはりドシロートとしては、どうしても華やかな子役たちに目が行ってしまう。まずは調姫役の中村佳奈ちゃん。福助さんの娘さん。「い~や~じゃ~、い~や~じゃ~、い~や~じゃ~わ~い~な~」と繰り返すのがあどけなくてかわいい。お人形さんみたい。で、何と言っても、じねんじょの三吉役の中村国生くんが大注目。台詞は多いし、踊りも歌も盛りだくさんでびっくり。国生くんは、僕自身歌舞伎を見たことがなかったときから橋之助&三田寛子夫妻のワイドショー的ドキュメンタリー番組でよく見てたせいもあって、あらあらこんなに大きくなって・・・しかもこんな大役を堂々と演じるようになったんだねえ・・・と、赤の他人のくせに感慨深い。精一杯の見栄や童らしい仕草のかわいらしさに観客も沸く。胡座をかくのが難しいらしく、しきりに足をもう片方の足の上に乗せようとしていたのもご愛敬。一生懸命に演じてるさまは、かえって母を恋しがるいじらしさを感じさせる効果も。重の井の裾に取りすがろうとしているところとか、重の井に呼び止められて、だーっと全速力で駆け寄りヒシっと抱きつくところなんぞ、思わずじぃ~んとしてしまった。もっとも全体的には、子役たちの微笑ましさに目尻が下がりっぱなしだった。子別れという悲しいお話なので、本来のお芝居の意図とすればどうかという気もするが、初々しさは何者にも勝るということか? ただ、今回はじめて地唄と三味線(義太夫っていうの?)が効果的だったなあと感じた。#余談。この幕を見た後に金沢への帰途についたところ、台風の影響により直江津以西の列車が全面不通。やむなく直江津で一泊することに。これを見ずにさっさと出立していれば、まだその時間帯なら列車は運行していたため、その日のうちに金沢に帰れたのだが。まあ、国生くんを見れてじゅうぶん楽しめたのでヨシとしよう。
September 7, 2004
コメント(0)
-
まったりした展開の中、小ネタを拾う~新選組!#35「さらば壬生村」
全体的にまったり進む。やや物足りない嫌いもあるが、仕方ない面もある。これまで八木家とのかかわりをけっこう丁寧に描いていた以上、「なお、西本願寺への引っ越しも終わったわけだが・・・」みたいに挿入エピソード的にあっさり片付けるわけにもいかず、やはり八木家を去っていく様子も独立して取り上げたいところ。だが、それ自体には歴史上これといったエピソードがあるわけでもなく、物語のテーマとして仕立てるのはやはり難しい。山南事件の衝撃とは比べるべくもなく、前回のようなしっちゃかめっちゃかバナシを2話続けるのも憚れよう。そのせいかどうかは知らないが、今回は政局が急転換しそうな雰囲気を漂わせつつ、いくつかの「フリ」(伏線というほどでもないかな)を施し、また、今までに転がっていた小ネタを適宜処理するなど、今後の展開へのブリッジ的構成となった。自然、物語は断片的な印象もあったが、まあ、そういう回もある。うどん屋に扮装していた桂。つゆを入れずに麺だけ出す。こんな商品で仙波甲太郎への祝儀になるほどの金を稼げるはずはない。仙波に気を遣わせないための方便だろう。それにしても、第1話で桂は江戸の蕎麦のつゆにさんざん文句をつけていた。いざ自分でつゆを作ってみようとしたものの、納得できるものができず、そんな不味いものをだすくらいなら、いっそのことつゆは出さない!とでもいうのか。潔いというか、なんというか(←僕の妄想です)。捨助、追い詰められた末、奇跡の脱出を果たす。口ほどにも強くない観柳斎が相手だったのがツイていた。おまけに、そのもみ合いの拍子にすっ飛んだ刀が斎藤の顔面をかすめ、斎藤をして「できる・・・!」と警戒せしめた。この勘違い、今後に活きてくる・・・のかな?(笑)松原忠司、仙波甲太郎を斬る。忠実な男は仙波の最期の願いを叶えようと決めた。忠実で何事にも真剣というキャラ設定があったからこそ自然。そして悲しいかな、彼の死への前段。だが、この未亡人と心中するのか、これに絡んだ隊規違反で切腹するのか、現時点ではいずれの説にも展開可能。西本願寺での引っ越し作業。せかせかと取り仕切る平助。ぼーっとして役に立たない浅野。インテリ会話で不機嫌な住職をなだめ得意げな伊東。ご近所への挨拶のための手拭いを安くあげたい河合。周平の部屋割りに文句をつける谷三十郎。う~む、どれもこれも「フリ」に見えてしまう。捨助はまだハタキを岩倉に届けていなかった。お登勢さんにハタキを折られ、新品を持っていくが、それでは何の意味もない。その場に居合わせた西郷が密書をハタキに擬した例があると話すのを聞き、驚愕する捨助。さあ、どうする、捨助?竜馬は中岡慎太郎と密談。新選組が西本願寺への屯所移転という勢力拡大を実感している最中に、歴史は再び動こうとしている。このへんのコントラストは巧妙。竜馬の中ではすでにシナリオはできつつある。あとひとつのピースはどこに? 思考がフルスピードで動く。中岡が思わず叫ぶ。「早いがぜよ!」 笑うところではあるが、実際は凄い台詞。孝明帝と容保公の会話は唐突。このシーンの必然性は? 年齢を尋ねるくだり、あとで何か意味を生じるのだろうか。隊士たちの前に出ることを拒むお幸。前回のつねさんとの約束の帰結。そのかわり、勇に妹のことを語る。これもフリですね。ラスト、八木家との別れ。歴史上さほど意味はないとは言ったが、伊東四郎さん、さすがじぃーんと締めてくださる。八木家の息子ともお別れ。彼の書いた日記が後世に新選組を伝える。そういえば、芹沢事件の時も彼はしっかり目撃していた。そして、やはり触れざるを得ない総司とひでちゃんの別れ。さして長くはない命を剣の道に生きたいという総司の決意、わからないわけではない。でも、最後にどうしても総司がここいた証が欲しいと願う。始終微妙な表情だった総司も、彼女の想いをようやく受け止めた。二人の周りには桜が散っていた。このドラマ、意外と効果的に草花を使っている。明里の菜の花は記憶に新しい。芹沢はお梅と紅葉を見た。斎藤は血の色だと言う。浪士組として上洛した芹沢は、桜の枝を折りながら勇に凄んだ。そう、京に到着し、八木家に来たときも桜が咲き乱れていたのだった。そのときは箒が逆さに立て掛けられていた。だが、八木家にとって新選組はもはや無用の客ではない。前回みつさんがに彼らは「悪い人たちじゃないですよ」と言ったとき、八木夫妻が笑って同意していたのが思い出される。まっすぐきちんと立て掛けられた箒を見やり、勇は八木邸を後にした。こんな温もりがある日々が、これからどれほどあるのだろう。
September 5, 2004
コメント(0)
-
三谷氏@スタパ見逃し&第34話と「王レス」~新選組!雑記
見逃しちゃった・・・三谷幸喜氏出演のNHK「スタジオパークからこんにちは」。8/31も9/2(今日)もテレビ欄を確認したのに、9/1だけ見落とした。ああ、ショック。【参考(←何の?):新選組!キャスト出演時のスタパ視聴戦績】○見た!(録画で) 優香さん/堺雅人さん/藤原竜也くん/八島智人さん○見た!(土曜スタパで) 山本太郎さん/石黒賢さん/山本耕史さん×見逃した・・・ 相島一之さん/中村勘太郎くん/三谷幸喜さん※これ以外の出演の有無は不明で、当日はどんな話だったのかをどうしても知りたくて、いろんなblogを漁ることとする。けっこう記事は豊富だ。やはりみんな抜かりはないのだなあと感心。ついに全49話を脱稿されたとのこと。う~ん、いよいよ終わりに近付いていくのだなあ。三谷氏は、佐藤浩市さんファンの司会の黒田アナをいじったり、第34話の斎藤は落ち込みすぎとダメ出ししたり、いろいろやってくれたようだ・・・やはり見たかった。その中に気になるキャスティング情報が。僕がよく拝見しているれいこさんのblog「baddreamfancydresser」の9/2のエントリ記事によると、残る重要キャストであった徳川慶喜役は、今井朋彦さん(→写真)とのこと。おおっ!「HR」の村井先生だっ!「HR」では、情熱はあるがどこかズレてる轟先生(香取くんね)に対し、クールな現実派、都合が悪くなるとさっさと逃げちゃう先生だった。勇と慶喜っぽいぞ、と思わずニヤリ。いわゆる大物俳優ではなく、またまた舞台中心の役者さんだが、三谷氏のキャスティングには全面的に信頼しているので、おおいに期待。#個人的には、最近、唐沢寿明なんかどうかと予想してた・・・。**********第34話「寺田屋大騒動」について追記。これまた僕のお気に入りの(というかおそらく「新選組!」関連屈指の充実ぶりで有名な)白牡丹さんのblog「白牡丹のつぶやき」では、エントリ「第34話『寺田屋大騒動』と第5話『婚礼の日に』比較」にて、興味深い指摘を見つけた。『王レス』第6話、小野武彦さん(大河ドラマ『新選組!』では、小島鹿之助さん)演じるレストランの接客責任者を訪ねて、別れた奥さんが息子を連れてやってくる話と状況がよく似ている。そして、別れた奥さんが再婚することを知って、自分だけ幸せになることに後ろめたい思いを抱かせたくないと思う元夫とその仲間たちがドタバタと状況をでっち上げた挙げ句、「恋人」がふたりも出現して、それをカバーアップするための、またもドタバタ。 あ~、そうでした。僕自身三谷氏お得意のパターンだとは思いながら、具体的にどの話だったかまでは思い出せなかったが、これですっきりした。「王レス」は昔、全回録画してたやつが家のどこかにあるはず(苦笑)。探し出して、今度見直してみようっと。
September 2, 2004
コメント(3)
全114件 (114件中 1-50件目)
-
-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画
- 12.5 全国公開「みらいのうた」予告…
- (2025-11-20 09:49:17)
-
-
-

- 東方神起大好き♪♪ヽ|●゚Д゚●|ノ
- 東方神起 20th Anniversary LIVE TOU…
- (2025-08-16 16:45:05)
-
-
-
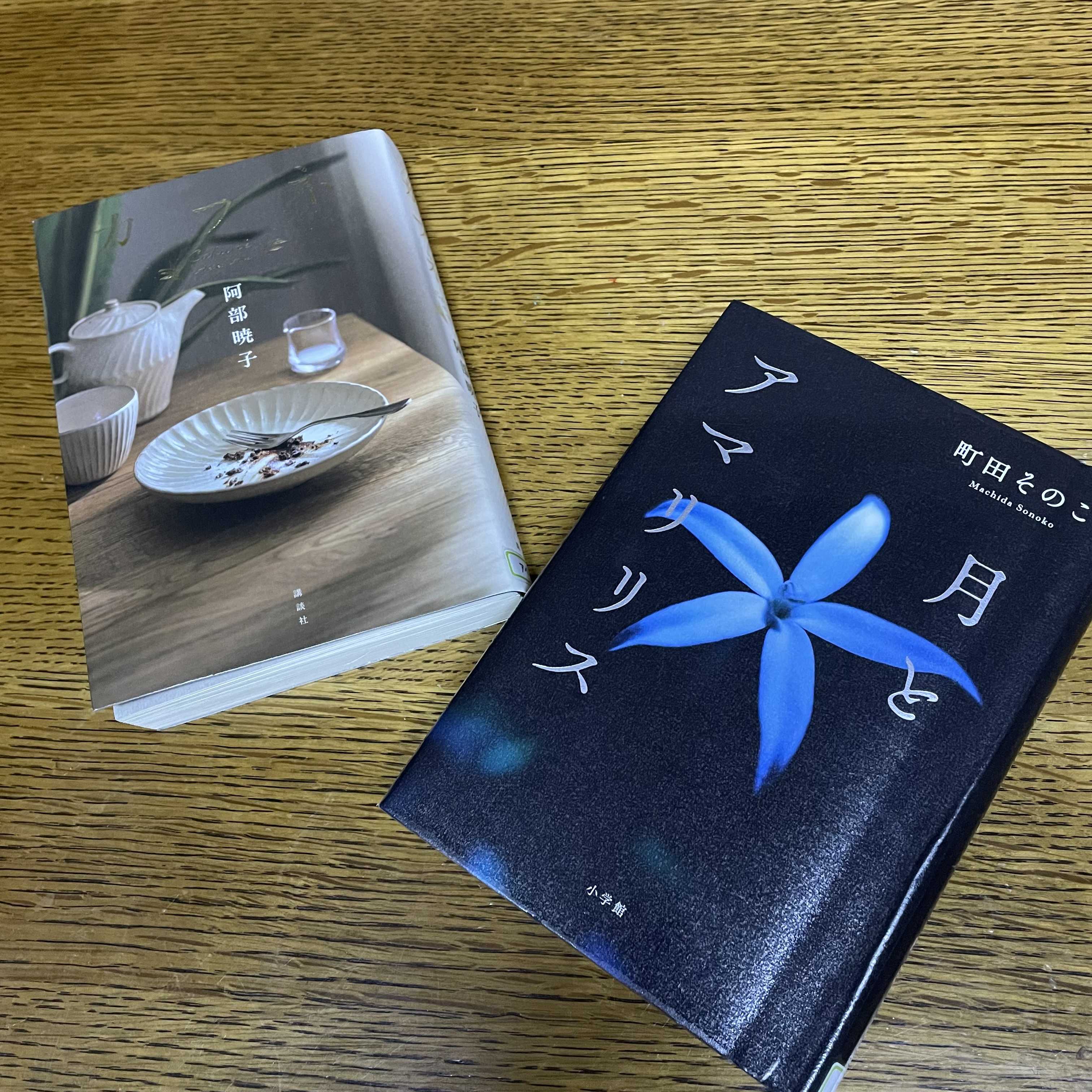
- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪
- ハピバ☆ ・「カフネ」
- (2025-08-18 23:53:31)
-