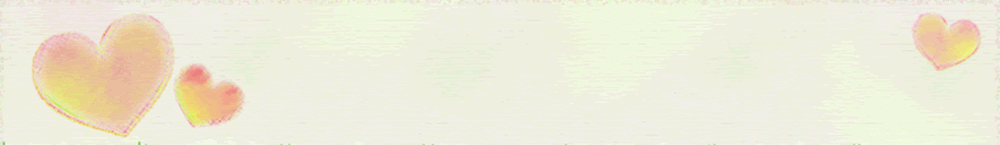-
1

寒蘭トヨ家 ちびっ子広場
寒蘭トヨ家 ちびっ子広場 11月に小学生に徳島市の八万公民館で 小学生に阿波と古事記のお話を することになっているので, 寒蘭トヨ8739さんの息子さんにお願いして 寒蘭トヨさんのご自宅に近所の小学生を 集めて予行演習をさせていただいた。 子供13人が集まった。父兄2人。 さすがに,小学生に話をするのは大変でした。 どこまで話していることがわかっているか 手探りで話をすすめ無ければなりません。 しかし,予想以上にいろんな事を知っていて おおよその感覚を掴むことができました。 全員にお菓子やジュースを配りながら また,クイズ形式でプレゼントなど 引き付けながら話を続けました。 ドラゴンボールを見せることはできませんでしたが, 寒蘭トヨ8739さんありがとうございました。
2006.10.18
閲覧総数 11
-
2

阿波の国学者 池辺 真榛(イケベ マハリ)
チャンスの今日が やって 来ました。 12月8日今日もいい天気 私が,「古事記」を学び始め,しばらくしてから 徳島藩士 ・ 国学者に 池辺 真榛(イケベ マハリ)という人が 居るのを知った。 彼の詠った和歌を知り,それ以上に彼のことは知らないが, その後,私は,彼の代弁者として今日まで「阿波と古事記」を 学び語ってきたつもりでいた。 そして約20年たち 池辺真榛顕示会の副会長さん等が訪ねてこられた。 昨日で2度目になる。 最初は,何のことかわからなかったのですが, 昨日は,とんとん拍子に話が進んだ。 来年の一月に 池辺真榛顕示会主催で, 「知ろう! 阿波の国学者 池辺真榛」を開催することとなった。 午後から 最後のドクターエンドーでの「聖書読書会」があった。 最後ですから,信者の方がお一人だけ参加してくれました。 議論は,白熱して有意義な最後の読書会になりました。 今日も 楽しい一日が始まります。 【 チラシ制作 ギャラリー とき 】 舞踊組曲【母子慕情】-阿波の祈り
2011.12.08
閲覧総数 710
-
3

千引 の 岩(ちびきのいわ)看板 説明文
4月の桜の花が咲く頃に,徳島県那賀郡相生町内山の大岩の前に立てる予定の 看板に書く説明文ができた。 千引 の 岩(ちびきのいわ) イラストは,まさこさんからお借りしました。 この大岩は,『古事記や日本書紀』に書かれた「千引岩(ちびきのいわ)・千人所引磐石(ちびきのいわ)」に推定される。 日本最古の歴史書『古事記』によると,国造りの途中で亡くなった妻,伊邪那美命(いざなみのみこと)を追って黄泉(よみ)の国,比婆山(ひばやま)へ会いに行った伊邪那岐命(いざなぎみこと)は,「見てはいけない」と言われた醜い妻の亡骸を見たため妖怪達に追われるはめとなった。逃げる途中に投げつけた髪を束ねた葛や櫛が,山葡萄や竹の子に変わり,それを追っ手が食べている間に逃げのびたが,なおも追ってくるので坂本にあった桃の実を投げつけると追っ手達は逃げ帰ってしまった。最後に伊邪那美命(いざなみのみこと),自身らが追いかけてきたので,伊邪那岐命(いざなぎみこと)は,千引の岩で道を塞いだ。 黄泉の国から逃げ帰った伊邪那岐命(いざなぎみこと)が,竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘の小門(をど)の阿波岐原(あわきはら)で,禊(みそ)ぎ祓(はら)いをすると天照大御神(あまてらすおおみかみ)と月読命(つきよみのみこと)と須佐之男命(すさのおのみこと)が生まれたと書かれている。『古事記』に書かれたこの物語は,現在の徳島県内の地名に当てはまる所が多く,徳島県山川町から阿南市見能林町までの地域を舞台として繰り広げられた物語と考えられるのである。伊射奈美(いざなみ)神社は,『延喜式(えんぎしき)神名帳』(平安時代九二七年)に阿波国に一社のみ記録され,ほかの県にはありません。『古事記』の物語は,この式内社 伊射奈美(いざなみ)神社がある穴吹町舞中島から始まり,高越山(こおつざん)を経て「カズラを投げたら実が生った」と書かれる。上勝町雄中面(おなかずら)・生実(いくみ)。「くし櫛の歯を投げると竹の子が生えた」竹ガ谷・(旧やつら八面神社に竹を型取った,灯ろうがある)「桃を投げた」丹生谷(にゅうだに)地域には,百合(もあい)・桃の木坂・桃付等の地名があり,神社には桃を型取った木彫りがある。また,相生町には,昔からヨミ坂と呼ばれる坂もある。黄泉(よみ)の国から逃げ帰った伊邪那岐命(いざなぎみこと)が,四国の東端の阿南市見能林町柏野で,禊(みそ)ぎ祓(はら)いをすると天照大御神(あまてらすおおみかみ)と月読命(つきよみのみこと)と須佐之男命(すさのおのみこと)が生まれた。以上が,『古事記』等に書かれる「千引岩(ちびきのいわ)」に関わる物語である。
2005.02.03
閲覧総数 867