私の参考書籍

| 障害を理解するために | 『発達障害の豊かな世界』 杉山登志郎著 のび太・ジャイアン症候群 司馬理英子著 『ひとり、ひとり こころを育てる』 メル・レーヴィン著 『自閉を超えて』 石井聖著 『アスペルガー症候群と高機能自閉症の理解とサポート』 杉山登志郎編著 自閉症―私とあなたが成り立つまで 熊谷 高幸 (著) |
|---|---|
| 発達障害児の学習について |
『自閉性障害者の発達と教育』 西田清・高橋宏・別府哲・藤本文朗編著 『LD児サポートプログラム』 竹田契一監修 太田信子・西岡有香・田畑友子著 『教科別にみる学習障害児の指導』 平山 論・江田祐介・西川公司編 『長所活用型指導で子どもが変わる』 藤田和弘監修/熊谷恵子・青山真二編著 『学び方がわかる本』 L.ロン ハバード著 『親を困らせる子どもを上手に伸ばす』 ロス・W・グリーン著 『さあ、どうやってお金を稼ごう?』 デイル・S・ブラウン著 |
| 2004 July
『さあ、どうやってお金を稼ごう?』デイル・S・ブラウン著
LDでADHDもあって身障者雇用の大統領委員会のスタッフとなったアメリカ人が書いた本だ。障害の有無にかかわらずこれから社会に出る若い人のためにどうすればいいか、どう取り組む必要があるかについて、よく書かれている。そして、LD特有のハンデにどう取り組むかがうまく絡んでいて、とても参考になる。中・高校生の軽度発達障害に悩むご本人に特におすすめ。 ・・・詳細 2004 July
『発達障害の豊かな世界』 杉山登志郎著
一言で言えばすごく興味深い本。 自閉症の特異性をこれ程よく伝えてくれる本は私には初めてだ。 自閉症児が成長して、就労に当たって直面する課題についても、詳しく書かれているが何より自閉症の特異な感覚を理解する上でおすすめ ・・・詳細 2004 July
『のび太・ジャイアン症候群 司馬理英子著』
ADHD/ADDについて特にいじめ問題と絡めて分かりやすくまとめられている。 著者は自身もADDのお子さんを持つ医師。私はADHDというのは教室から飛び出していってしまうような衝動性を持った障害だと思っていた。タイトルの通り目に付き易い多動性、衝動性を持たない場合もあるのが分かる。 ・・・詳細 2004 July
『ひとり、ひとり こころを育てる』 メル・レーヴィン著
著者はTEACCHで有名なノースカロライナ大学の教授で児童の発達、学習の専門家。レーヴィン氏も学習障害やAD/HDの診断は何の問題解決にもならないと述べている。理由は多くの発達障害の診断名が外に現れた症状からくくられたものであって、それを引き起こす原因によるものではないからだそうだ。この本では知能を7つの機能に分け、その中をさらに3から5つくらいの項目で分析し、その弱点をどうカバーするかを考え、子供にも教えるべきと説く。 ・・・詳細 2005 Jan
『自閉を超えて』 石井聖著
著者は長年、知的障害児の療育に携わり、現在はココロETセンターといる療育期間を主催している石井聖氏だ。氏が提唱しているココロ・メソッドは行動療法を基本としているが、氏自身が本の中で述べている通り、風当たりは強いらしい。負の因子として時には児童の頬をはたくというようなことも書かれているから、受け入れられない人も多いだろうと思う。 ・・・詳細 2004 July
『アスペルガー症候群と高機能自閉症の理解とサポート』杉山登志郎編著
アスペルガー症候群と高機能自閉症について、医師の杉山氏だけではなく、療育者、親、そして本人の記載を集めた本。それぞれの視線を理解する上でおすすめ。 2004 Aug
『親を困らせる子どもを上手に伸ばす』 ロス・W・グリーン著
よくかんしゃくを起こす子ども、柔軟に問題解決に取り組めない子どもにどう対処するか。”ばくはつ”した後ではいかなる罰、説教も意味がない。ばくはつに至る前でどのように回避するかを分かりやすく紹介している。 ・・・詳細 2006 July
『自閉症―私とあなたが成り立つまで』 熊谷 高幸 著
周囲の気持ちが読めない、こだわりが強い等の自閉症の特徴を紹介した本は多いけれど、この本は、どうしてやりとりができないのか? どうして文字や機械が好きなのか? というように自閉児の特徴的な行動がどういう原因からもたらされるかに焦点をあてている。ある程度、理屈が分かったほうが安心して子供に接することができると思う方にお薦め ・・・詳細 2004 Aug
『自閉性障害者の発達と教育』
.....................西田清・高橋宏・別府哲・藤本文朗編著 自閉症児の発達と教育について親と教師の立場で成人するまでを書いている。いくつか紹介されたケースから重度の自閉症の子供の心が育ち、社会とかかわれるようになっていく様子が分かる。西田先生は自閉症の教育の黎明期から特殊教育に携わってこられた方でその視点、姿勢には学ぶものが多くあった。 2004 July
『LD児サポートプログラム』
.....................竹田契一監修 太田信子・西岡有香・田畑友子著 友達とのかかわり、勉強について、つまずきのポイントとその対応を分かりやすくまとめてある。小学校低学年までならおすすめ。 2004 July
『LD児の言語・コミュニケーション障害の理解と指導』
.....................竹田契一・里見恵子・西岡有香著 前述のLD児サポートプログラムと同じメンバが参加しているので書き方は共通点が多いが、こちらはコミュニケーション障害により焦点をあてている。どちらの本もポイントはよいのだけれど、具体的な対応の詳細がもう少しあればな、と思う。 2004 Aug
『教科別にみる学習障害児の指導』
.....................平山 論・江田祐介・西川公司編 小学校、中学校の教科別のつまずきのポイントを紹介している。書字に関してはかなり具体的。 IEP については分かり易く、ここは参考にさせてもらった 2004 July
『長所活用型指導で子どもが変わる』
.....................藤田和弘監修/熊谷恵子・青山真二編著 認知処理が継次処理、同時処理のどちらに強いかで指導法を紹介。認知処理の傾向が明らかな場合には参考になるかも 2004 July
『学び方がわかる本』 L.ロン ハバード著
LDの子供本人が自分の問題点と向き合うための本だがこの本を読んだだけで対応できる子は少ないのではないかと思う。誰かが問題点を理解させるための資料として使うなら役立つかも。 |
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 塾の先生のページ
- 強制的(自発的)に“後発追い込み(…
- (2025-11-27 11:29:30)
-
-
-
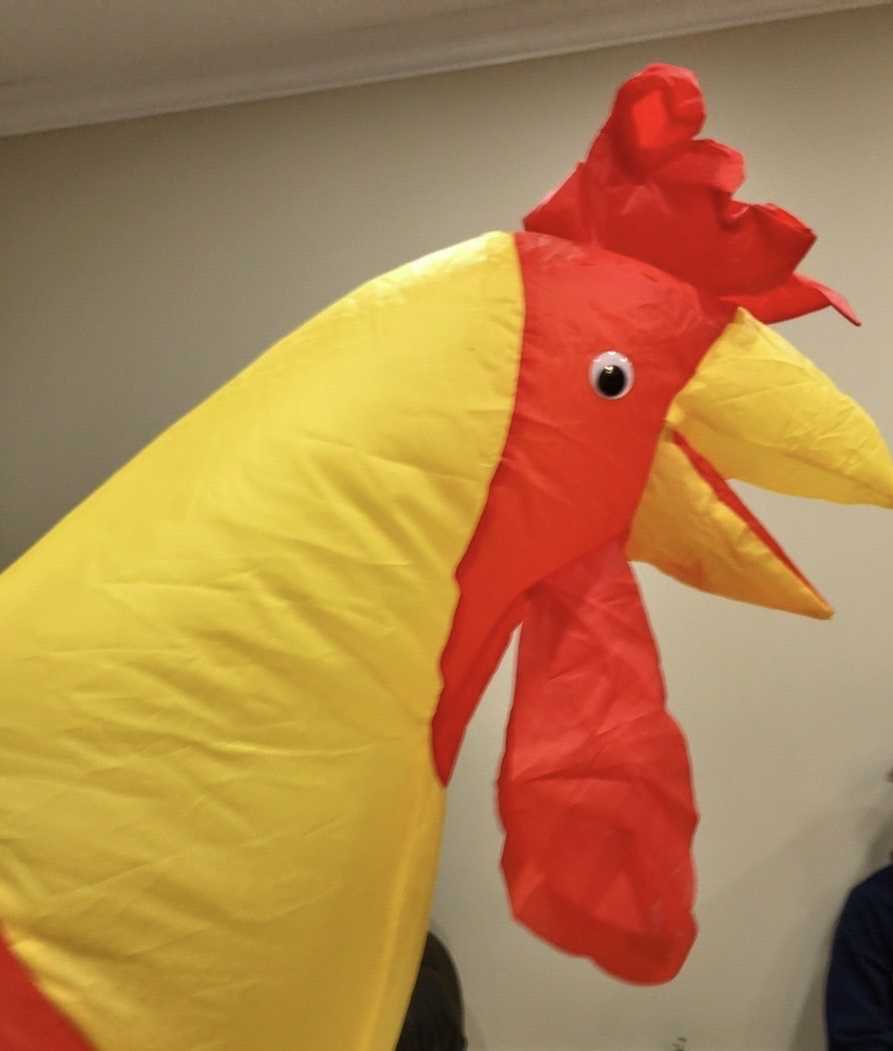
- 働きながらの子育て色々
- ZOOM
- (2025-11-27 07:00:04)
-
-
-

- 子供服セール&福袋情報★
- 【2026年新春福袋】Jeans-b【ジーン…
- (2025-11-26 12:04:06)
-
© Rakuten Group, Inc.


