-
1

続・冬の野鳥シリーズ② シジュウカラ
博物館のすぐ隣の下部リバーサイドパークの木々には、いま、いろいろな野鳥が見られます。今回は、つがいと思われるシジュウカラたちです。つかず離れずして、しきりに獲物を探しついばんでいるようすが見られました。 「ネクタイ」とよばれる喉元からお腹にかけての黒いラインがシジュウカラの特徴の1つですが、それが太めのこれ、オスの個体だろうと思われます。 同じソメイヨシノの木の枝のかたわらにいた、もう1羽、ネクタイが細い。これは、メスの個体ではないかと思われました。 近くのヤマボウシの木に移りましたが、枝の表面にかくれている小さな虫などをついばもうとしているシーンです。
2022.02.09
閲覧総数 113
-
2

赤い汁を出すカメノコテントウ
一昨日の土曜日、夕方の足湯掃除の時間に、足湯の板の間に、かわった虫が見られました。床板にしっかりへばりついていて、無理やり動かそうとしたら、赤い汁を出しました。びっくり。 さらに手で取り上げようとしたとき、いやがって足を出し、動き出しました。 足湯の中では、いろいろと不都合なので、ちかくのサザンカの葉の上にお移り願いました。 今回の虫は、あとで調べたところ、カメノコテントウという、少し大きめのテントウムシの1種でした。刺激を受けると忌避剤として赤い汁を出すのだそうです。この赤い液は、カメムシのようなくさい匂いがあり、あまりよろしくない、よって手を出しにくい、という仕組みだそうです。 カメノコテントウは、クルミハムシ(クルミにつく虫)の幼虫などを食べ、冬は樹皮の隙間などで成虫で越冬するようです。 そういえば、この3月5日が「啓蟄」で、虫たちが冬ごもりから目ざめ、活動を始めるということでした。このカメノコテントウも冬ごもり開けで、でもちょっと寒かったので、あたたかな足湯の中にお出ましになった、そんなことが考えられました。
2021.03.08
閲覧総数 1045
-
3

紅葉していくツタの葉
博物館から少し出た、下部川の対岸の県道脇でのスケッチです。赤くきれいに紅葉したツタの葉がきれいだったのでパチリしました。まだ緑の葉もありながら、緑から赤へのグラデーションもいい感じでした。 ツタ。それは右側から左側に伸びて伝(ツタ)うもの。秋に葉が緑から赤に伝うもの・・・。だからツタ?!
2019.11.27
閲覧総数 221
-
4

またまた金色の毛虫・・・
先日のことですが、博物館スタッフのI部さんが、枯れ葉を一枚プレゼントしてくれました。その枯れ葉に、金色の毛虫がのっていたのです。というか、この毛虫を見せてくれたのですね。 はじめ、この写真の背景にある湯之奥金山博物館の建物前で、それを受け取ったのですが、その時点で日が陰っていたので、日差しを求めてメロディーブリッジの上に移動して写真に収めたのです。太陽の光を受け、金色に見えるリンゴドクガの幼虫でありました。 ちなみに、リンゴドクガの幼虫の、このブログへの登場は2回目で、前回はこの10月28日のことでした。
2018.11.29
閲覧総数 586
-
5

こがね色のキノコ 発見!
今日の夏休み自由研究は、キノコです。それも金山博物館にとてもふさわしい黄金色をしたキノコです。どうです、ちょっと かわいいでしょ。 そのキノコ、どこで見つけたかというと、金山博物館の正面玄関の前に並べてあるマリーゴールドのプランターの中で、だったんです。 最初に見つけたときに、マリーゴールドの花の色によく似ていたので、マリーゴールドの分身かと思ってしまうほどでした。 まだ生まれて間もない黄金色のキノコです。 インターネットで調べてみると、まず名前がわかりました。コガネキヌカラカサタケというものでした。名前のはじめにつく「コガネ」は、たぶん黄金色からくるのでしょう。 それから、お里がわかりました。お里というのは、出身地というか、キノコなので原産地のことです。それが何と、熱帯地域なんだそうです。熱帯地域のキノコがどうしてプランターの中に生えてきたのでしょうか。 とてもかわいいキノコだったので、お顔を付けてあげたくなりました。 こがね色したキノコについての自由研究のまとめ!!①なまえ; コガネキヌカラカサタケ②もともとの育つところ; 赤道に近い熱帯気候の地域③プランターに生える理由; プランターで植物を育てるときに、よく腐葉土を使いますね。 いまの園芸用の腐葉土は、多くが熱帯気候の地域で生産されているそうです。 葉っぱも大きくよく育ち、落ち葉になってから腐葉土になるまでの時間がとて も短く、効率のよい腐葉土の生産に適しているからそうした地域でつくられて いるということで、腐葉土をつくっているときに、キノコの菌が飛んできて、 日本に出荷される腐葉土に菌が紛れ込むからだと考えられています。④このキノコの子どもと大人; 今回見たコガネキヌカラカサタケは、「幼菌」つまり子ど もだそうです。大人のキノコ「成菌」になると、色が少し薄くなり、からかさ (唐傘)みたいな形になるようです。⑤参考となるWEBサイト; 一例として・・・森林総合研究所九州支所 きのこシリーズ11
2017.08.13
閲覧総数 2102
-
6

くろーずあっぷ・ハルジオン②
ふたたび、ハルジオンの花のクローズアップです。この写真の見どころは、まわりの白い花びら一つひとつからなる舌状花のほかに、中央部の黄色の筒状花のようすをジックリ見るところにあります。真ん中の黄色のつぶつぶは、一つひとつがつぼみです。外寄りの黄色の筒状花、星形に開いているのも注目です。 上の1つめの写真は、筒状花が開き始めたばかりの若い花ですが、こちらは、筒状花が外側から中心に向かって咲き進んだ状態で、それを横から見ています。筒状花の黄色のしべが、長く突き出ているのがわかります。
2019.05.16
閲覧総数 102
-
7

博物館の建物にはりついてきたカメムシの仲間 オオトビサシガメ
博物館の通用口付近において見られたカメムシの仲間で、カメムシ目サシガメ科に分類されるオオトビサシガメです。あまり親しみを感じられない昆虫の部類にはいりますが、それでも小さなお目々は、とてもかわいい・・・。 こちらも寒くなってきたので、どこかによい越冬場所はないかと、やってきたのかと思ってしまいました。 たいへんゆったりとした動きで、すこしずつ移動をしていました。 これを見つけた博物館スタッフは、さかんにこいつも臭いにおいを出すのか、木にしていましたが、ネットの情報では、バナナに似たにおいを出すことが知られました。 ※この記事の作成に当たって次の記事を参考にしました。 「オオトビサシガメのバナナ臭」https://blogs.yahoo.co.jp/ho4ta214/36424207.html
2019.10.29
閲覧総数 2659
-
8

意外と見られるヤマトシジミ
博物館の通用口近くのプランターに植えられているラベンダーの葉の上で日光浴してたヤマトシジミです。ずいぶんと翅表の色が濃いので、別なシジミチョウかと思いましたが、最終的にヤマトシジミでよいと思われました。夏型なのかな・・・。 こちらのヤマトシジミは、博物館の裏手で見たものですが、ツユクサの葉の上にとまり、すぐそのとなりに顔を出していたハキダメギクの花に吸蜜管(口吻)を差し込んでいるところでした。 ハキダメギクにも蜜ってあるのかな、あまりおいしそうではない見た目だけど・・・。 この夏前までには、博物館周辺には、ヤマトシジミはあまり見られないとか思ってたのですが、思ったよりたくさんいましたね。
2020.09.04
閲覧総数 558
-
9
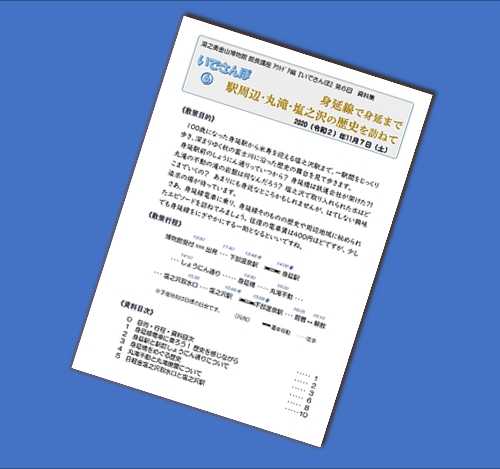
いでさんぽ⑥話題 表紙だけ出来た!
第6回いでさんぽが、いよいよ今週末にせまってきました。早く資料集を仕上げないといけません。目下、悪戦苦闘中・・・。やっと表紙だけできました。
2020.11.04
閲覧総数 42
-
10

小さなバイカウツギの木に花咲く
前回のシャクガを見た場所の続きで、草むらの中に白い花を見つけました。何の花だろう。 シダの仲間や、草本類に埋もれるようにして生えているのでしたが、花の特徴からバイカウツギだと考えられました。こんな小さな木でも、にぎやかに花を咲かせていて、ちょっとすごいなと思われました。
2020.06.01
閲覧総数 39










