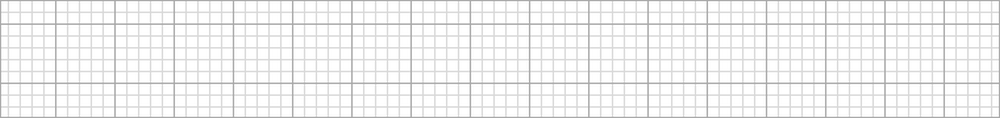脳死について
脳死について
| |
|---|
第1章 脳死の概念の歴史的背景 |
| 第2章 脳死の定義・基準 |
| 第3章 脳死と植物状態 |
| 第4章 脳死と臓器移植 |
| 第5章 脳死をめぐる様々な問題 |
| 第6章 資料など |
| 参考・引用文献・関連サイトリンク集 |
目次へ
第1章 脳死の概念の歴史的背景 (*2) (*3)
1-1 心臓死と脳死
医学において、従来から 呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大・対光反射喪失という"死の三徴候" によって
法律上の死の判定がなされている。しかし、この三徴候を満たしているからといって、組織・器官・細
胞の機能喪失が認められている訳ではない。実際に死体からの角膜移植や腎臓移植は可能であり、死体
から細胞を採取し、増殖させることも可能である。
このように個体死、臓器死、細胞死というものは同時に起こることはほとんどない。これが"死"がポ
イントではなくプロセスであるという所以であろう。これまでは、死の判定とは個体死を意味していた。
これは心臓が停止することにより、生命が維持できなくなることから心臓死とよばれる。
しかし、医療技術の進歩、特に生命維持法の発達により、心臓が機能を失ってしまっても生命活動を
人工的に行なうことが可能になってきた。これは脳に関しても同様であり、脳機能を喪失し、心臓や肺
のコントロールが出来なくなっても、人工心肺により個体死を防ぐことが出来る。人間にとって、脳は
心臓、肺とともに生命を維持する為に最も重要な器官である。脳が機能を喪失してしまった場合、たと
え心拍、呼吸が維持されていても、それは自発的なものではなく 「生きた体に死んだ脳」 と呼ばれる状態
になる。これが脳死という概念の源である。
1-2 脳死の概念の導入
1900年前後は近代脳神経外科学の黎明期であり、まだ脳死という言葉はなかった。その頃にいわれて
いたことは、主に脳疾患に陥った場合の心停止と呼吸停止との時間的関係についてである。
H.クッシング(米)は1902年にクッシング症候群に関する論文を発表した。この中で脳腫瘍の患者の呼
吸停止から心臓停止までの時間差があったことが記されている。これは呼吸停止後に人工呼吸を行なっ
為であり、それにより心停止まで時間があったのである。これがいわゆる"脳死"状態の最初の記述であ
る。竹内一夫氏によればこれは人工呼吸器ではなく、心臓マッサージによるものである為に現在の"脳死"
状態と区別して、「脳死以前の脳死」と呼ぶこともある。
1950年代後半には脳波の測定法の発達が見られた。1957年にR.テントラー(米)は平坦脳波19分後の蘇
生例を報告し、これを皮質死(cortical death)と呼んだ。但し、この症例では患者は回復しているので、
現在の脳死とは異なるものである。
1959年にはモラレとグロン(仏)が超昏睡(coma de’passe’)という記載をしている。彼らは植物状態と
脳死との見分け方を明らかにした。この時期から脳死についての研究が盛んに行なわれるようになって
きた。
第2章 脳死の定義・基準 (* 2) (*3) (*7)
2-1 脳死の定義と判定基準の変遷
医療技術の発達、特にベンチレータの普及によって世界中でいわゆる脳死状態にある患者数が増加して
きた。そのような中、アメリカ合衆国では1968年にハーバード大学においてこの問題を検討する委員会が
結成され、その審議結果は現在では ハーバード基準 として知られている。その後1971年の ミネソタ基準 、
1977年の 米国国立衛生研究所(NIH)の共同研究 などを経て、1981年に 大統領委員会の報告 が発表された。
この大統領委員会の報告は脳死の判定基準ではなく死の判定基準とされている。
日本では1968年、日本脳波学会の脳死委員会により、初めての脳死の定義が決められた。これは 新潟宣
言 と呼ばれており、「脳死とは回復不可能な脳機能の喪失をいう。脳機能には大脳半球のみでなく、脳幹の
機能も含まれる。」というものであり、脳幹の機能喪失が挙げられている点が重要である。
新潟宣言から6年後の1974年に日本脳波学会による脳死の判定基準( 脳の急性一次性粗大病変における脳
死の判定基準 )が発表された。これは後の厚生省脳死研究班による判定基準のもとになったものである。
1980年代前半あたりには上記のように欧米先進国においても基準が次々と発表された。これには新しい免
疫抑制剤の出現も影響しているといわれる。そして1983~1985年の3年間に厚生省「脳死に関する研究班」
が組織され、1985年に厚生省研究班による現在の 脳死の新判定基準(竹内基準)
が発表された。
2-2 脳死の原因
脳死に至る過程には大きく分けて2つの場合がある。1つは脳出血や脳挫傷のように一次性の障害が脳
にある場合である。もう1つは二次的な脳障害によるものであり、元々障害されていなかった脳が心臓停止
などにより脳に血流が送られなくなり、酸素供給が途絶えるために脳無酸素症(anoxia)が起こる。すると
脳の毛細血管壁の透過性が亢進し、血管内の液体成分が外部ににじみ出し、脳がむくんで脳浮腫が生じ
る。頭蓋内の容積はかぎられているため、脳の容積が増加した場合には頭蓋内の圧力が上昇する。頭蓋内
圧が高まると脳の一部がわずかな隙間に押し出され、脳ヘルニアと呼ばれる状態になる。この状態が長く
続いた場合に脳死の状態になり、やがては個体の死につながっていく。
目次へ
第3章 脳死と植物状態 ( *4) (*10)
3-1 植物状態とは
重篤な脳障害の後に、外界からの刺激に対しての反応が極端に乏しい間々で長期間生存する場合があ
る。これは遷延性植物状態、あるいは失外套症候群と呼ばれており、一般の人から見ると脳死状態と混同
してしまうことがある
植物状態の定義とは、大脳皮質のうち新皮質や辺縁皮質の機能が遮断される、あるいは欠落しているし
ていることである。人間の脳が動物と大きく異なっている点は、新皮質が他の動物と比較して大きく発達
していることである。しかし、この新皮質は最も傷つきやすく、抵抗力も弱い。それに対して脳幹のよう
な古い脳は最も抵抗を示す。したがっていろいろな状況において、新皮質の機能が脱落した状態、すなわ
ち単純に生きている、あるいは生かされているという状態が出現して植物状態となる。
脳死の場合は脳幹を含む全脳の付加逆的機能停止のことを表わしたものである野に対し、植物状態の場
合には脳幹の機能が温存されていることを表わしている。このように 脳死と植物状態 とは、医学的に明ら
かな違いがある。植物状態の患者は回復する可能性もあり、障害が進行することにより脳死状態に至るケ
ースもある。
3-2 カレン事件
1975 年4月,アメリカ合衆国ニュージャージー州で21歳の女性カレン・クィンランは昏睡状態で病院に
運び込まれ、持続的な植物状態に陥った。彼女はレスピレーター(人工呼吸器)によって生き続けていが
両親はこのレスピレーターを含む人工的な生命維持装置の取り外しを主治医に対して求めた。しかし主治
医はこれを拒否。父親のジョゼフ・クィンランが、「娘の生命過程を維持している通常外の方法のすべて
を打ち切ることを認許する明示的な権能」を付与するよう裁判所に求めた。
この事件について、はじめはカレンさんは脳死状態であると報道されていたが、レスピレータ-をはず
した後にも自発呼吸を続けていたことから植物状態であることが理解されるようになった。
アメリカにおいては、1968年にハーバード大学脳死特別委員会が 脳死の判定基準 を定義している。した
がって、医師などの専門家の間では脳死ではないことが明らかに分かっていたのだが、一般の人々の間に
はまだあまり理解されいなかった。日本では1985年に 竹内基準 が発表され、現在でも脳死関連の報道が多
くなっているが、一般の人々は脳死と植物状態の違いを理解しているのであろうか。ある団体が大阪・京
都・神戸・東京で2000年9月に約5000人を対象に行なったアンケートでは以下のような結果が得られてい
る。 ( 参考
)
Q1.脳死状態と植物状態の違いがわかる 分 か る→1.373人 26.4%
|
Q3. Q2の内、脳死状態と植物状態の違いがわかる
分 か る→248人 37.3% 分からない→417人 62.7% |
|---|---|
| Q2. ドナーカードを持っている人
665人 12.8%
|
*ドナーカードを携帯している人
208人 4.0%
|
この結果からは、現在でも脳死状態と植物状態とを混同している人の割合が多いことが分かる。
目次へ
第4章 脳死と臓器移植 (*5) (*7) (*9)
4-1 臓器移植法の成立
脳死状態の人体からの移植用臓器の摘出を合法化する目的で、1994年4月に衆議院に提出された「臓器
の移植に関する法律案」(以下、法案とする)は、あまり審議がされないまま1996年6月の一部修正を経て、
同年9月の衆議院解散によっていったん廃案になった。しかし、総選挙後の同年12月、6月の修正案をふ
まえた新法案が再度提出され、1997年4月の衆議院通過後、参議院での再修正を経て、1997年6月17日、
「臓器移植に関する法律」として成立した。
なぜ脳死状態の人からの臓器移植が必要なのだろうか。塩見戎三氏は著書の中で『なぜ脳死という概
念を容認しなければならないのか。それは臓器移植との関連で、心臓死に至らない生命作用の強い新鮮
な臓器が入用だからにほかならない』と述べている。
臓器移植問題の背景にある他の要因としては、医療経済論からくる推進力があるという意見がある。
集中治療などによる生命維持には高額の医療費を必要とする。これらの患者に「死の宣告」をすることに
より医療費を抑制することができる。腎臓移植を例にすれば脳死状態の患者の生命を維持するよりも、
臓器を移植された患者の手術費と免疫抑制剤費の方が社会全体が負担する医療保険の負担が少ないとい
うものである。ただし、日本において現在保険適応になるものは腎臓移植のみであるという事実も脳死
臓器移植論議の背景にあることを理解しておく必要がある。
4-2 日本初の心臓移植(世界で30例目)
新潟宣言が発表される2ヶ月前の1968年8月8日、日本初の心臓移植手術が札幌医科大学付属病院にお
いて実施された。手術を行なったのは胸部・心臓血管外科教授の和田寿郎氏。手術自体は成功したが、
その後様々な疑惑が浮上し、 和田心臓移植 事件 として報じられることとなり、現在の脳死・臓器移植論
議にも取り上げあられている。
この事件の疑惑としては、レシピエントの心臓移植の適応性やドナーの脳死判定に関するものがある。
レシピエントの適応性について、最初に担当した同大第二内科のM教授は「内科的治療で3年間、弁置換
手術では10年の生存」を見込んでいた。その後胸部外科に転科され移植手術を受け、後に死亡した。
遺体は病理解剖が行われたが、切除心は6ヶ月間行方不明となり、発見後の病理学的所見では心臓移植の
適応とは認められなかった。また切り取られた4つの弁のうち1つは他人のものであり、血液型も異なっ
ていた。その他にも和田教授に拒絶反応や免疫抑制剤に対する知識や経験がほとんどなかったことや、
同大の病理学教授や内科学教授による論文と和田教授の報道発表や胸部外科から発表されていた臨床経
過との間の食い違いなども指摘された。
この事件は様々な疑惑を含んでいたものであったため、人々の脳死・臓器移植に対する不信感を増大
させ、現在でもその後遺症が残っているといわれる。
第5章 脳死をめぐる様々な問題
脳死についての問題には、医学的な問題、法的・倫理的問題、社会的問題などがあるが、ここでは法的
問題や倫理的、社会的問題を主に書いていく。
法的な問題の一つに1997年10月16日から施行された「臓器の移植に関する法律」(以下、移植法とする)の
内容に関する問題がある。この法律によると、一般の人は三徴候によって死を判定されるが、患者が自己
決定により脳死状態からの臓器移植の意志を表示している場合は、臓器提供を前提にして脳死の判定が行
われる。家族もこれを拒まない限り、脳死を死の基準とみなすとしている。この時点で三徴候による基準
と脳死による基準のダブルスタンダードが発生している。
脳死状態の人を「患者」として扱うか「死体」として扱うかは、医学的にも社会的、法的にも重大な効果
をもたらす。医学的には「死体」に対しての治療は行なわないし、刑法上は殺人罪や傷害罪の保護の対象
から死体損壊罪の対象とされる(前述の和田教授は殺人罪で起訴された)。また民法上は財産権を失い、
相続が開始するとともに家族は遺族として生命保険や遺族年金の支払請求権が発生する。
-
-

- 糖尿病
- 「オセンピック」という気持ち悪くな…
- (2025-10-13 13:53:35)
-
-
-

- 入浴後の体重
- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…
- (2025-06-30 17:00:00)
-
-
-

- ダイエット!健康!美容!
- ♥️ 【30%OFF&ポイント20倍】BLACK F…
- (2025-11-23 06:10:03)
-