全729件 (729件中 1-50件目)
-

ひさびさのブログは、趣味のお話し…?!
日本人の健康志向の高まりか、はたまた自転車アニメの影響か、自転車が人気だ。かくいう私も、ロードバイクをはじめて10年ほどになる。現在の愛車は50歳の誕生日に自分自身に贈ったイタリア製のクロモリ(鉄)バイク。組んで1年くらいはホイールやサドルを替えたりしていたのだが、その後は自分の好みに仕上がったこともあって、ここ何年かは、消耗品の交換程度しかしてこなかった。特別、走りを意識しているわけでもないし、思い立った時に気の向くままにふらりと走りにいくことができるのが自転車の魅力だと思っている私にとっては、それで十分だったから…。そんな中、今回「もっと楽に坂道を登りたい」と思い、8年ぶりにスプロケット(後輪のギア)を交換した。一番軽いギアが25枚から27枚になったので、計算上で言えば、いままでよりも楽に登坂ができるハズだ。私がそんな気持ちになったのは、最近、仲良くさせていただいている自転車仲間の影響が大きい…?!体力に自信のない私が「自転車って、みんなでも楽しめるものだ!」と再認識した際に、仲間についていくためには、道具に頼るしかないので…(笑50代も後半を迎え、仕事も年齢もさまざまな仲間と知り合えたことが貴重だと思うし、これからも“Strength of Weak Ties(弱い結びつきの強さ)”を大切にしていきたいと思う。何はともあれ、「スプロケット交換の効果がどの程度のモノなのか?!」早く試してみたいな〜!!
2016.08.11
コメント(0)
-

ハーバードでいちばん人気の国・日本
〜佐藤 智恵〜新聞の書籍広告に載っていた「テレビ番組で紹介、お茶の間でも大反響!」「書籍ランキング1位」のキャッチコピーに、「“ニッポンすごい系番組”の書籍版かな…?」と興味をそそられて読んでみた。ちなみに私は、「“ニッポンすごい系番組”チョッピリ多すぎかも…?」と感じはするものの、それに対する批判のコメントを目にして、「目くじら立てて批判する…?」とちょっぴり引いちゃう様な輩です。書籍の内容はタイトルの通り、ハーバード大学の授業で教材として扱われる日本や日本企業の事例の紹介を通して、日本や日本企業の人気の理由が丁寧、且つわかりやすく書かれている。事例自体は、私たち日本人が知っているものが多いけれど、それをハーバード大学の教授陣が「どんな視点でどう評価しているのか?」という観点で書かれているのが読みやすい。ちなみに、学生たちが卒業までの2年間で学ぶ約500本の事例のうち、必修科目(2014年)で学ぶ日本の事例は、トヨタ自動車(テクノロジーとオペレーションマネジメント)、楽天(リーダーシップと組織行動)、全日本空輸(マーケティング)、本田技研工業(経営戦略)、日本航空(ファイナンス)、アベノミクス(ビジネス・政府・国際政治)の6本ということなので、数よりも質で勝負ということの様…。そんな中、印象に残ったのは、同大学で何十年も教えられている、トヨタ自動車と本田技研工業のケース。トヨタ自動車の事例で言えば、『謙虚なリーダー像』。1980年代、日本の製造業が飛躍を遂げた際、当時の米国では「日本のメーカーが強いのは、日本人と米国人の労働者の能力の差だ」というのが一般的常識だった。ところが、日本企業を研究するにつれ、「米国人労働者の生産性が低いのは、米国企業の経営者、役員、管理職のリーダーシップにも問題があるからだ」とわかってきた。そこで注目されたのが、日本人経営者の「謙虚さ」。グローバル企業では、経営者が決めたことを部下はそのとおりに実施するのが当たり前だったが、日本のメーカーの経営者は、下からの意見を聞いて一緒に考える。それが「学習する組織」を形成し、強さの源泉となったという分析だ。本田技研工業の事例で言えば、ホンダの米国進出に『論理的な戦略』はなかったということ。1959年に米国進出後、15年で米国のオートバイ市場の43%を占めるまでに成長したホンダについて、ボストンコンサルティングは「いかに素晴らしい競争戦略で米国市場を制したか」を論理的に分析したが、それは結果論。ホンダは欧米流の合理的な戦略を描いて米国に進出したわけではないことがわかったとのこと。そもそもホンダは、「資本主義の牙城、世界経済の中心である米国での成功なくして国際商品にはなりえない」という理由だけで米国進出を決めたのであって、米国の潜在市場がどの程度で、どのようなニーズがあるかなどを事前に把握していたわけではない。ホンダの成功は、机上で論理的に考えた戦略が功を奏したのではなく、偶然や現場学習の積み重ねによって達成されたものだったということだ。ただ、1981年にボストンコンサルティングが日本進出した際、欧米流の意図的戦略も必要だと考え、最初の顧客になったのもホンダだったというのも見逃してはいけない。ということで、「書籍ランキング1位の理由」も「アマゾンのレビューが高評価」なのも納得の内容だったけど、多くの事例は、過去の日本が高く評価されているということ。ハーバードの学生たちが学んでいるとの同じように、私たちも「しっかり事例から学ばなくっちゃ!!」と考えさせられた一冊でした。
2016.04.26
コメント(0)
-

専業主婦になりたい女たち
〜白河 桃子 著〜ちょっと古い話になるけれど、2009年の内閣府発表の“家庭観”調査によれば「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と答えた女性は、年代別で60代がトップ(40.2%)、次いで20代が第2位(36.3%)だったことは、衝撃だった。そんなこともあって、学生と話をする際は、意識して学生たちの“家庭観”を聴く様にしてきた。実際に話を聴く中、「専業主婦志向の強い女子学生って多いかも…」「パートナーには、家にいて欲しいと思っている男子学生も少なくない…」と感じていたこともあり、本書を手にとってみたというわけ。で、本書の内容だが、『専業主婦という安定ほど危険なものはない-!?』という帯に記された挑発的なコピーの根拠を、若い女性や専業主婦・独身男性等、様々な人へのインタビューや座談会の内容をモチーフに説明している。セレブ妻(?)のインタビューでは、人も羨む様な専業主婦生活を送るには、「夫の所得が高ければOK」というのではなく、「夫のやさしさと理解が必要条件となること」が説明されている。また、20代独身男性の座談会では、参加者の多くが配偶者の専業主婦生活を望んでいるにも関わらず、「それに必要な所得を明示されるや、自身の考えに現実味が無い」と気づかされる場面などが記されている。さらには、離婚や夫のリストラ、給与カットといった結婚後のリスクに直面した際、“専業主婦である女性が復職すること”が非常に難しいことを具体的な事例を示して説明し、「専業主婦は貧困女性を量産するシステムである」と結論付けている。労働市場の現場で、具体的な事例に接してきた私としては、「確かにそうだよな~」と頷きつつ、「若い学生等に気付きを与えるには良い本だよな~」という評価を下させていただいた。そんな中、最近、趣味化している他の読者のレビューを見ると…。「兼業主婦や兼業家庭のリスクもある。どちらのリスクが大きいと考えるかは各個人次第」「統計データが足りず、リスクの定量評価がされていない」等、著者に対しての批判的なコメントが少なくないことも興味深い。この話をややこしくしてしまうのは、「母は専業主婦で、私を愛情いっぱいに育ててくれた。私たちも子供には同じようにしてあげたい」等、自分の両親や祖父母世代の「良妻賢母」像を家族のロールモデルとしている人たちが少なくないことにあるんじゃなかろうか。産業構造や社会環境の変化などにより、好むと好まざるに関わらず“専業主婦は減っていく”ハズ。世の中の変化を認識しつつ、将来を俯瞰する力をつけることが大切だと感じさせてくれた一冊だった。
2015.12.25
コメント(2)
-

Your time is limited
本日、父親の一七回忌、祖母の十三回忌の法要を行いました。法要の前に、住職から「今日一日が満足できる一日だったかを振り返り、悔いの無い人生を送ることが大切」というお話しがあり、お経をあげていただいている間、父が亡くなった当時のことを思い起こしていました。父は、私が中学にあがった頃から社会人になるまで、単身赴任のサラリーマン生活を続けました。その後、私は結婚して所帯を持ったこともあり、父との会話の機会が少なかったことを、今でもとても残念に思っています。とはいえ、父の死が私のその後の人生を大きく変えたのも事実です。父は私が41歳の時に、68歳で肝硬変を患って亡くなりました。当時、私はとある人材ビジネス会社の取締役として、再就職支援事業のコンサルティングと離職者に対するカウンセリングに従事していました。上場企業のリストラのコンサルティングをする中、『ひとつの会社に入ったら一生安泰という時代ではない』ということを肌で感じ、次世代(娘や息子の世代)の若者たちに「こんなはずじゃなかった」と言わせてはいけないと考えていました。そんな時期の父の死でした。実は、父の祖父も父と同じ肝硬変を患って亡くなっています。同じ血を継いでいる私は、「68歳—41歳=27年、あと27年か…」と計算したのを覚えています。私にとって、死がグッと身近になった瞬間でした。“人生は一度きりであること、人間には寿命があること”を前提にこれからどう生きていこうかを考えた上で、2年半の準備の後、はじめたのがキャリア・クリエイトです。起業した際に創ったMissionは、『わたしたちは“経営へのコンサルティング”と“社員のキャリア開発支援”を両輪に、“企業と個人のWin-Win”をサポートします』で、現在も名刺の裏にはその言葉を綴っています。私の人生に於いて仕事は重要な位置を占めていますし、今後もそれは変わらないとは思いますが、最も大切にすべきは“人生のタイムマネジメント”だとも思っています。そんな中、周囲を見渡してみると、「日々の忙しさにかまけて、自分のキャリアビジョンを考えることを蔑ろにしていないか?」と感じさせる人は少なくありません。ということで、受け売りで恐縮ですが、英語の苦手な私にも解かるスティーブ・ジョブズの名言を…Your time is limited,so don’t waste it living someone else’s life. (あなたの時間は限られています。だから、本意でない人生を生きて時間を無駄にしないでください)うわっ、今、気づいてしまいました。計算上では、あと11年じゃないですか…(汗
2015.12.06
コメント(0)
-

フリーランスの生き方
~静岡県立大学“キャリア概論”にて~10月末のとある水曜日、静岡県立大学のキャリア概論という授業で、“フリーランスの生き方”をテーマにお話をさせていただいた。私が、フリーランスという働き方を選んで起業したのが2002年。その2年後の2004年に同大学の津富先生にお声掛けいただいたのがはじまりで、以来10年にわたりこのような機会をいただいている。呼んでいただいたことに感謝すると共に、「(今回のテーマでもある)フリーランスという働き方で、よく続けてこられたな~」などと、物思いに耽ったりして…(遠い目で、今回の授業なのだが、フリーランスという働き方を選んだ人を出来るだけたくさん紹介することを心がけた。というのも、「就職するなら、絶対、正社員じゃなきゃイヤ!」と言っている学生に「正社員以外の選択肢は?フリーランスって知っている?」と質問すると、「わかりませ~ん?」と答えるケースがほとんど。いろいろな選択肢があることを知る中で「やっぱり、正社員!」だったら解かるけど、何の根拠もなく「絶対、正社員!」と考えている学生(親も含む)に「何かの気づきが与えられたらいいな~」と考えたワケ。紹介するフリーランサーについて、最初は「“学生たちと比較的年齢が近い若手”や“話題性のある人”もアリかな~?!」とも思ったのだが、いろいろ考えて“現在の仕事で、ちゃんと食べている人(?)”にアンケートを通して、フリーランスになったキッカケや現在の気持ち等をお聴きすることにした。今回お声がけした6名は、みなさん私の友人・知人なので“現在の仕事”は、知っていたが、フリーランスになったキッカケは“会社の倒産により、やむを得ず…”“自分の居場所がなくなったと感じて…”“自分のやり方で仕事をしたいと独立”等様々、且つ素晴らしいコメントを寄せてくれた。この内容であれば、学生たちが「こんな働き方(選択肢)もあるんだ!」と認識してくれるだろうと、満を持して授業に臨んだ。• 終了後の学生達のレポートを読むと「人生は一度きりであること、人間には寿命があること、更には会社にも寿命があることを知りました。フリーランスは、全てが自分に返るというのがとても納得できました」「“安定”は自分自身で創るもの、他力本願の“安定”は存在しない。たいへんでも自分の選んだ仕事をすることで、生きていることを実感したい!」「一度就いた仕事は一生続けて行かなければならないと思っていたが、一度しかない人生なのだからその時“やりたい”と思ったことを選べばいいんだと前向きな気持ちになれた!」「フリーランスの方々の話を聞いて多くの人が“やりがい”という言葉を使っていました。仕事をする上で収入はとても大切なものだけど、それ以上に“やりがい”は自分の人生にとっても大切なものだと感じました」等、我が意を得たりのコメントもあったのだが…。その一方で、「フリーランスで成功しているみなさんは、好きな事を仕事にしていて楽しそう。選択肢の一つに加えようと思った」「無理して企業に雇われ続けなければならないわけじゃない事が分かったので、気が楽になった」などのコメントも多かった。う〜ん、雇われる働き方以外の選択肢があることまでは、伝わっている様なのだけど…。今回紹介したみなさんは、私も含み成功者なんかじゃないし、好んでフリーランスを選んだ人ばかりでもない。とはいえ、今は“もがき続けて生きること”を楽しめている人達。だからこそ、フリーランスのアンケートには「もし、時間を遡って同じ岐路に立ったら、きっと同様の決断をするだろう」などというコメントをいただけたのだと思う。学生達との間に、齟齬を感じた理由は“最低限、生きていかなくてはならない”という前提条件が共有出来ていなかったからなんだろう。そんな中、私が今後、学生に“フリーランスの生き方”を伝える際のヒントになると思えた学生の感想が…“フリーランス”というのは、最初「ひとりひとりが社長のようだな」と思いましたよく考えたら“フリーランス”は、自分で自分の人生をマネジメントしているのだから、自分が人生におけるコンダクターであり社長であるのだと感じましたこの感想を読んで、「フリーランスだから、自分の人生のコンダクターなの?」という素朴な疑問が沸いた。フリーランスだろうとサラリーマンだろうと、自分の人生のコンダクターは自分自身だよね!ということで、「今後も“働くこと”について、学生達に問題提起を続けていこう!」と決意を新たにした次第です。To continue
2015.11.14
コメント(0)
-

僕が18年勤めた会社を辞めた時、後悔した12のこと
~和田 一郎 著~タイトルに惹かれて手に取ったこの本は、こんな書き出しで始まる。大学を卒業後、僕はひとつの会社に18年勤めた。残念ながら、僕の会社人としての人生は失敗だった。40歳くらいの時、高い壁にぶち当った。あろうことか四方をその高い壁に取り囲まれ、にっちもさっちもいかなくなった。そして、42歳の時に、僕は会社を辞めた。もちろん、周囲には前向きな退社であることを強調したけれど、本当のところは、どうしても会社に自分の居場所が見つからず、負けて、傷ついて、ボロボロになって、逃げるようにして辞めたのだった。著者のプロフィールを読むと、「1959年3月生まれ。京都大学農学部卒、大手百貨店18年勤務、42歳で退職し、アンティーク・リサイクル着物の販売を始める」との記述が…。おぉ、同級生。且つ18年勤めた会社を辞め40代前半に起業したのも、周囲の人は前向き退職だと思っていたが、本人は会社に居場所が見つけられずに辞めたというのも私と同じだ。同世代で共通点が多そうな和田氏が、「会社を辞めた時にどんなことを後悔したのか?」に俄然興味が湧いた。で、実際の12の後悔だが“入社初日から社長を目指して全力疾走すればよかった”“会社のカラーに染まりたくないなんて思わなければよかった”“ゴルフを始めてワインをたしなめればよかった”“信念なんてゴミ箱に捨てればよかった”等々…。“旧来型の大企業での処世術が身につけられなかったこと”の後悔が綴られており、読み進めていく中で、私の興味は少しずつ薄れていった。アマゾンのレビューに“驚くほど同じ後悔”“重みのあるウンチク本”等々、高評価のコメントが多いのを見ると、まだまだ“旧来型の大企業”が生き残っているんだな〜と感じると共に、「果たして共感している人たちの会社が今後も人員削減することなく、社員を守り続けてくれるだろうか?」などといらん心配をしてしまいました。この本に共感できる人は、将来、会社が人員削減しないことを祈りつつ“在籍中の会社にしがみつく術”を体得する必要があると感じました。
2015.11.14
コメント(0)
-

アドラーに学ぶ部下育成の心理学
〜 小倉 広 著〜ここ数年、「自己啓発の源流」と言われブームの様相を呈しているアドラー心理学。遅ればせながら、最近、興味を持って勉強しております。ということで、『アドラーに学ぶ部下育成の心理学』の備忘録を…。アドラー心理学を一言で語るのであれば、『課題の分離』。例えば、アドラー心理学では、母親が子どもに「勉強しなさい」と強制するのは、人間関係のトラブルに繋がると考えます。何故なら「勉強をするか?否か?」は、母親の課題ではなく、子どもの課題だから…。人の課題に土足で踏み込むことが、人間関係トラブルの原因になるということです。また、会社組織において、多くの上司は自身の部下が難易度の高い目標を達成した場合、「ほめる」という行動に出ますが、アドラー心理学では「ほめる」ことを否定します。「ほめる」ことは、上から目線であり、「相手の自律心を阻害し、依存型人間を作る」と考えるからです。上司と部下の間柄であるにせよ、上下関係はあくまでも役割上のもの。いくら職位に上下があったとしても人としての尊厳は対等です。上司のほめ言葉には、仕事だけでなく、人間としての存在に関わる要素も含まれており、それを感じた部下はカチンと反応してしまう場合もあると考えるわけです。ということで、この様なケースでは、上から目線で「ほめる」のではなく、「横から目線」の「勇気づけ」が重要だと説いています。『自律と共生』を標榜する(?)私にとって、部下育成に際し「ほめない」「叱らない」「教えない」というアドラー心理学のスタンスは、す〜っと腹に落ちました。まぁ、考え方と実践の差を埋めることは容易ではないのでしょうが…(苦笑
2015.09.19
コメント(0)
-

後期授業、はじまりました
~大学入学後、半年経った学生たちは何を思っているのか?~縁あって講師を務めさせていただいている静岡県のとある大学での後期授業がスタートしました。いま、授業終了時に出席簿代わりに提出してもらう『感想』(第1回分)を読み終わったので、感じたことを備忘録代わりに書き留めておこうと思います。『感想』を書いてもらっているのは、1年生を対象とした『キャリア開発論』という授業。低学年時に『1.将来の目標や生き方のイメージを持つこと』『2.学生時代に何をすべきかを考え具体的な行動を起こすこと』によって、4年間の大学生活を有意義なものにすることを目的とした授業です。この時期の1年生、入学当時の志と現状のギャップに一抹の不安を感じつつも、居心地のいい(?)大学生活に流されているケースも少なくない様です。ということで、例年『本学入学の目的』と自身の書いた『入学の目的』を読んで感じたことを書いてもらった後、グループでメンバー相互の情報を共有してもらうワークに時間を割いています。グループ内での情報共有に聞き耳を立ててみると、「教師を目指して入学したが、頓挫。これからどうしようか悩んでいる」「絵が上手くなりたくて入学したが、絵の技術を高める以外の授業が多いのがストレス」「なんとなく入学し、なんとなく学生生活を送ってしまっている」等々…。話の内容自体は想定の範囲内なのですが、時間を切らなければ話が延々と続きそうなところが想定外。きっと、心の中では「このままじゃいけない」と思っていたんでしょう…。そんなワークの後、私からは「当初の入学の目的がどうだったかは別にして、これからどういう学生生活を送るかが大切」「充実した学生生活を送ることが、視野や可能性を広げる」等の話を、私自身の経験も織り交ぜながら話しました。で、学生達の『感想』を抜粋すると…•思い通りに出来ている人は多くないとわかって安心した。自分に出来ること、自分が好きなことを一生懸命がんばればいいんだと思った。その過程が自分にとっての財産になるハズ。•当初の目的が頓挫し落ち込んでいたけれど、「目標や自分の中で決めたことが変化するのはおかしくない」と聴いて、気持ちが楽になった。•やることの意味を感じないことでも、いつの日か役に立つかもしれない。やる気を持って臨もうと思った。等々のコメントにニンマリ!また、就活に関する『感想』も…•価値観は自分の経験から生まれ、変化するモノだとわかった。大学生のうちにいろんな経験をすることが大事。自分の考えを持てる様にしたいし、就活する時もそこを見られるのだと感じた。•「大学4年間でがんばったことは?」と聴かれたとき、部活動などをあげる人がいるが、それが単なるネタが無くて取り上げたのか、ほんとうにがんばったのかは聴く人には判ってしまう。ハッタリではなく、自信を持って充実した4年間だと言えるようにしたい。•今まで就活をするために1年生の頃から何かやっておいた方がいいのかと考えていた。しかし、先輩からは1・2年生の時は自分の好きなことをして充実させていくことが大切だと言われていた。今日の話を聴いてその理由が理解できた。•授業初日、「正直、私には関係なさそう」と思っていたが、その重要性をあらためて知ることが出来た。世の中を知ることも必要なことだと思うので、今後授業をより身につけていきたい。一生懸命話したこともあってか、授業への期待のコメントをたくさんもらいました。“期待に添わなければというプレッシャー”に負けない様、15回、はりきって参ります。
2015.09.17
コメント(0)
-

“納得”するまで就活をがんばる?!
〜 新卒内々定率、8月末69% 民間調査、1カ月で12ポイント上昇 〜 マイナビが10日発表した「大学生就職内定率調査」によると、8月末時点の内々定率は69.1%と前月末より12.1ポイント高くなった。選考解禁日の8月1日を境に一気に内々定率が伸びた。ただ、内々定をまだ持たない学生を含め、就職活動を継続すると答えた学生は全体の52%に達した。出所:2015年9月11日 日本経済新聞 朝刊 -----------------------------------------------8月末時点の内々定率が前月末と比較して12.1ポイントアップし、69.1%となったって…。記事には「選考解禁日の8月1日を境に一気に内々定率が伸びた!」って書いてあるけれど、これって多くは7月末以前に個々の企業と学生の間では既に共有できてた内々定なんだろうね…(笑それはさておき、気になったのは、69.1%の内々定率だというのに就職活動を継続する学生が全体の52%いるという事実(私の周りには「就活1年以上も続けてもう疲れちゃった」という学生も多いので、ちょっぴり意外な数値だ…)。むろんまだ内々定が出ていない学生には頑張って欲しいし、既に内定が出た学生にも“納得”いくまで就職活動を続けてもらいたいと思う。実際に会社に入るといろんなことがあって、「あの時、あっちの道を選んでおけば…」なんて後悔することも少なくないから…。そんな中、既に内々定が出ていても就職活動を継続する学生には、「あなたにとって“納得”できる企業選びの基準は…?」というのは聴いてみたい。「企業規模、知名度、成長性、他…」いろんな答えが返ってきそうだけれど、私自身、どんな答えを聴かせてもらえたら「この学生は“納得”して就活を終了するんだ!」と腹落ちできるのかイメージできない。5年・10年~30年ってスパンで考えたら、いまいい会社がず~っといいとは限らないし、成長している会社も時間の経過を経て陳腐化したり無くなっちゃったりすることだってあるわけだから…。そんなことを考える私は、「どの会社に入るか?じゃなく、何かの縁で入った会社でどう頑張るか!?」が重要だと思ってる。人生の岐路に立った時、「あの時、あんだけ悩んで決めた会社なんだから…」と、他人のせいにしない様にするために、“納得”するまで就職活動をすればいいんじゃないだろうか!?
2015.09.11
コメント(0)
-

若手社員 職場定着セミナー 終了
~自身のキャリアビジョンを描いてみよう!~7月下旬に沼津・浜松・静岡で実施した若年者向け『職場定着セミナー』が終了したので、備忘録を…。このセミナー、若者の早期離職が社会問題化している中、とある経済団体のご依頼を受け、会員企業の入社3年以内の若手社員の職場定着を目的に実施しました。内容は、毎年少しずつ更新しているけれど、最初にご依頼いただいてから、かれこれ7年くらいになるでしょうか…。タイトルに『職場定着』と銘打っているし、実際に会員各社にとって社員の早期離職は、労働力不足につながる痛手なわけだけど、私自身はあくまで参加者サイドに立ち「辞めなきゃいいってわけじゃないでしょう?!意欲を持って仕事に取り組むのが大事!!」というスタンスでメニューを創っとります。セミナーは2部構成。第1部は「どんな職業人生を送りたい?」と称し、自身の会社しか知らない若手社員に「他社の同期はどんな仕事をしていて、日々、どんなことを思っているのか?」「昨今の日本の労働市場はどうなっているのか?」等を認識してもらうことに時間を割きました。第2部は「自身のキャリアビジョンを描いてみよう!」と称し、第1部で知った環境変化を認識した上で、キャリアビジョンを描くことの意味とビジョン作成時の考え方を知ってもらうことに時間を割きました。時間の関係もあるのだけれど、“ビジョンを描く方法”よりも、“ビジョンを描くこと”の大切さを認識してもらうことが重要だと考えたメニュー運営を意識しました。グループワーク中心のセミナーを心がけていたこともあり、参加者からは「“居酒屋で同期が愚痴、言い合う”みたいになっちゃってるんですが、いいんですか?」などという質問も出ましたが、それこそ「我が意を得たり!」で、「いい~んです!」。多くの若者は、自分の会社しか知らないので、「自分ばかりが辛い目に合っているんじゃないか?」「もっと自分にあった会社があるんじゃないか?」と悶々としていることが多い…。他社で若い社員がどんな仕事をどんな気持ちで続けているかを知るのは、とっても重要なことなのです。でないと、結果的に先の見通しも立てないまま早期離職してしまう。冒頭、早期離職が会社の痛手であることはコメントしたけれど、私はそれ以上に“早期離職した若者のその後”が心配です。人材派遣や職業紹介等の人材ビジネスに携わる中、離職後に苦労する若者たちを見てきた私にとって、離職ばかりをクローズアップするマスメディアの情報発信には、少なからず違和感があるのです。ということで、3時間半のセミナー終了後の参加者のアンケート内容を見ると…。「今の会社、すぐにでも辞めたいと思っていたけど、もう少し続けてみようと思った」「仕事のことで悩んでいたけれど、ちょっと違う角度から考えてみようと思った」「辞めさせないためのセミナーだと思っていたけど、そうじゃなかったみたい。楽しかった」「自分のキャリアを自分で創っていくって大切なんだと感じた」等々、「私の伝えたかったコト、伝わったかな!?」と手ごたえを感じられるアンケート結果となりました。
2015.07.28
コメント(0)
-

今秋、就活をはじめる高校生とお話ししました
~就職に対する心構え~先日、某女子高校の先生より、秋口から就職活動を始める高校生に「“就職に対する心構え”について話をして欲しい」旨のご依頼を受けました。こちらの高校からは、毎年この時期に同様のご依頼を受け、社会に出ることの不安を取り除くべくメニューを考えお話しさせていただいているのですが…。今年は、例年に加え「学生と社会人の違いを考えてもらうためのワークを入れたい!」とメニューを考えました。「なんでそんなことを考えたのか?」と言いますと…。とある大学のグループ討論の講座で「学生と社会人の違いをあげよ!」というテーマで討論をしてもらったところ、大学生たちが出した答えに衝撃を受けたからです。大学生たちがあげた違いは、「1.社会人は失敗が許されない」「2.社会人は縦社会をわきまえている」「3.社会人は主体的に行動する」等々…。私は「違いをあげて…」と言っているのに、出てきた答えは「全て主語が社会人で、且つ社会人ってすごいじゃん?!」というもの。私自身、「失敗しない社員は、チャレンジしない社員だ!」と思っているし、「縦社会をわきまえた行動しかしないんだったら、中途で経験者を採った方がいいじゃん!」「私は、主体性のない社会人をたくさん知っているよ!」等々、突っ込みどころ満載の答えに、唖然としちゃったわけであります。で、講習当日。女子高校生たちに同じテーマで社会人になることをイメージしてもらったところ、「年齢や性別、様々な人たちと出会える」「お酒が飲める(←「お酒は20歳になんなきゃ飲めないよ!」とツッコミを入れましたが…)」等々、社会に出ることに前向きなコメントが多く、ウキウキしてしまった次第です。同じ現象でも、とらえ方により行動の中身も結果も大きく変わります。「前向きな気持ちを持つことって大切だよな~」と高校生から教えられました。
2015.06.18
コメント(0)
-

「こんなハズじゃなかった!?」とならないための仕事研究
~OB・OGの話に耳を傾けてみよう~学生の就職相談や、企業の人事担当として学生のエントリーシートを読んだり面接したりする中、「この学生、会社(←しかも知名度や世間体が基準)に入ることが目的になっていないか?」「安心して定年まで働ける会社や組織を探しているんだろうな〜?」等々、「そもそもそもそもスタート時点でボタンの掛け違いがあるんじゃないの?」と感じることは少なくありません。※ここまでは、前回のブログと同じ…(笑そんな中、お世話になっている大学の先生から「大学のOB・OGに、現在の仕事内容に触れながら学生時代を振り返り、自身の職業選択について語ってもらうってどうだろう?!」とご相談をいただきました。“目標とした会社に入ったにも関わらず「こんなハズじゃなかった?!」と離職してしまったり、仕事のグチばかり言っている人”“なんとなく入った会社だったけれど充実した職業人生を送っている人”等、いろんな人を見ている私は「それ、やりましょうよ…!」。ということで、コーディネーターを務めさせていただくことになりました。OB・OGについては、「入社後5~10年程度が経過し、会社の全体像が見えてきている人」「業種・職種は様々に…」「出身学部や性別は出来るだけ様々に…」等の条件で人選していただきました。で、後輩のために一肌脱いでくれたのは、“研究や開発の仕事に就く友人が多い中、鉄道関係の会社に入った理系学部出身のM君”“本当は、ファッション雑誌を創りたかったのに広告営業を経て人材コンサルタントをしているAさん”“就活時は大手志向が強かったのに大手の内定が取れず、先輩の誘いに運命を感じメディア開発の会社に入ったN君”の3名のOB・OGとなりました。M君は愛知県出身。都市と田舎のバランスがよく、雰囲気や気候も気に入った静岡県での就活を優先したとのこと。また、当初は学部の友人と同様に食品メーカーの開発職等をターゲットに活動していたものの途中から路線変更。業種の枠を決めない就活に切り替え、現在の会社に入社しました。当初は漠然と「グループ内の介護事業を希望していたが、現在までに4つの部署異動を経験するも、未だ介護事業への配属にはなっていないとのことですが、どの部署もオモシロかったとのことでした。静岡が好きという割に静岡のことを知らない学生は多い「掘り下げていくとオモシロいよ!」とのアドバイスが印象的でした。Aさんが会社を決めた理由は、「ここで働きたいと思える会社かどうか?」の一点。自身の直感を信じた会社選びだったようです。「営業は大変だと覚悟していたけれど、ここまで大変だとは…!?」とのコメントがあったので、「そんなに大変だったのに何故、辞めなかったの?」と質問すると、間髪入れずに「いい仲間、いい上司に恵まれたから…!」と答えてくれました。現在は、異動になった職業紹介の部署で人材コンサルタントの仕事をしていらっしゃいます。先輩の誘いに運命を感じ現在の会社に入ったN君の配属先は住宅関連メディアの営業職。営業では、「お客様に喜んでいただきたい!」と好成績を上げるための努力を続けてきたとのこと。昨年、社内のFA制度を利用して管理部門への異動を宣言、念願かなって希望部署への異動を果たしました。「現在は、次なる目標(←将来は経営者になりたいって仰ってました)に向けて張り切って仕事をしてます!」とキッパリ語ってくれました。その後、3人のOB・OGを囲んでの質問タイム。少し歳は離れているものの、母校の先輩ということもあってか、学生たちからは“就活での苦労話”や“社会人になることの意味”等々、様々な質問が出ていました。「就活は学生にとって、人生初とも言える大きな転機!!」、なはずなのに多くの学生は入学試験の延長線上で「どの会社に入るのか?」ばかりに目が行ってしまう。選択のポイントは、“周囲に自慢できる”“知名度が高い”“地元を離れなくていい”等々、首を傾げちゃう理由も…。“生き方を選択する機会”と捉える学生にはめったに会えません。今回お手伝いいただいたOB・OGだって、就活時には“生き方を選択する機会”なんて考えて現在の仕事を決めたんじゃなく、縁だったり、成り行きだったりで就職先を決めたのも事実だけど…。「振り返ってみると就職活動って人生の大きな転機だったんだ!?」と気づくんですよね。ということで、今回の講座が学生たちの“気づき”のきっかけになったのであれば幸いです。
2015.06.16
コメント(0)
-

就活をじっくり考えるセミナー
~就活本番前にやるべきコトは?~学生の就職相談や、企業の人事担当として学生のエントリーシートを読んだり面接したりする中、「この学生、会社(←しかも知名度や世間体が基準)に入ることが目的になっていないか?」「安心して定年まで働ける会社や組織を探しているんだろうな〜?」等々、「そもそもスタート時点でボタンの掛け違いがあるんじゃないの?」と感じることは少なくありません。そんな中、とある大学のキャリア支援室から、「就活前の3年生・M1生に対し、就活のコトをちゃんと考えさせるセミナーをお願いしたい」とのご依頼を受けました。セミナーのタイトルも「“就活をじっくり考えるセミナー”でどうでしょう?」との提案を受け、張り切ってメニューを作成し、セミナーの当日を迎えた次第です。セミナーは、“働く目的”や“会社とのつきあい方”について考えてもらう『心構え編』と“業界や会社に対する知識”や“企業の採用時にどこを見ているか”等の『知識・情報編』の2つのフェイズに分けて実施。講師が一方的に教えるというのではなく、「いろいろな問いかけを通して、これから社会に出て働くことを考えてもらう」ことを意識したメニューをつくり、実施しました。終了後のアンケートでは、「就活について勘違いしていた様だ」「焦って大切なモノを見失っていたような気がする」等々、自由記載欄にうれしいコメントをたくさんもらえました(←こういうの、素直にうれしいですネ…笑)。学生達には、メディアや親や学校や先輩たちから多くの情報や雑音(?)が入って来るわけで…。その中から、「何が正しい情報なのかを自分の頭で考え判断する術を見つけて欲しい!」と、私自身があらためて感じさせられた“就活をじっくり考えるセミナー”でした。
2015.06.14
コメント(0)
-

How Google Works
〜エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ 著〜Googleの現会長エリック・シュミットと CEO 兼共同創業者ラリー・ペイジのアドバイザーのジョナサン・ローゼンバーグの共著で、Google の経営ポリシーが書かれた本。21世紀に、成長・進化し続ける組織づくりのヒントが、文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションという章立てで書かれている。Googleの成長と成功を支える核心は、「スマート・クリエイティブ」と呼ばれる新種の知識労働者であり、彼らを惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることが、唯一の道であると結論づけている。ここで言う「スマート・クリエイティブ」とは…。自分の“商売道具“を使いこなすための高度な専門知識を持ち、経験値も高い。分析力に優れている。ビジネス感覚に優れている等々…。要約すると、「ビジネスセンス、専門知識、クリエイティブなエネルギー、自分で手を動かして業務を遂行しようとする姿勢」が基本的要件にある人材と定義される。そもそも「そんな人材をどんな風に集めてくればいいのか?」「採用できたとしても、どうすれば惹きつけ続けることが出来るのか?」等々、疑問満載ではあるが、以下に疑問解決のためのヒントとなる部分を備忘録という視点で残しておこうと思う。“ワークライフ・バランス”について…ワークライフ・バランス。先進的経営の尺度とされるが、優秀でやる気のある従業員は屈辱的に感じることもある要素だ。このフレーズ自体に問題がある。多くの人にとって、ワーク(仕事)はライフ(生活)の重要な一部であり、切り離せるものではない。最高の文化とは、おもしろい仕事がありすぎるので、職場でも自宅でも良い意味で働きすぎになるような、そしてそれを可能にするものだ。だからあなたがマネージャーなら「ワーク」の部分をいきいきと、充実したものにする責任がある。従業員が週40時間労働を守っているか、目を光らせるのが一番重要な仕事ではない。最近、大学生の集団討論Workで“ワークライフ・バランス”についての考えを聴く機会が多い。学生達が、「仕事は苦痛なモノ」「仕事と生活(多くの場合、家庭)のバランスが必須」等のオンパレードに辟易している私としては、「我が意を得たり!」の内容だ。会社を経営する人間として、従業員の労務管理を蔑ろにするつもりは全くないし、仕事人間になって欲しいとも思わないが、昨今の「仕事も生活もそこそこでいいよね」的なワークライフ・バランス論には首をかしげてしまう。個々人がどんなバランスで仕事をするのかを考えることは大切だと思うし、マネージャーは、部下の意志を尊重しなくてはならないとも思っているが、そもそも仕事は楽しいもの(←私はそう思っている)だし、それを伝えることがマネージャーの重要な役割だと思う。採用について…経営者の場合、「あなたの仕事のうち一番重要なものは?」という問いへの正解は「採用」だ。あの日、ジョナサンを面接していたセルゲイは、真剣そのものだった。ジョナサンは当初、それは自分が幹部候補で、入社したらセルゲイと仕事をする機会が多くなるためかと思っていた。だが入社して、グーグルの経営者はすべての候補者を同じくらい真剣に面接することを知った。相手が駆け出しのソフトウェアエンジニアであろうが、幹部候補であろうが、グーグラーは最高の人材を確実に採用するために最大限の時間と労力をかける。「う〜ん、全く異論なし!」。加えて、本書には…。最も優秀な人材を採用し続けるには、産業界ではなく学術界のモデルを見習う必要があることを理解していた。大学は通常、教授に採用した人間を解雇しないので、専門委員会を立ち上げ、教員の採用や昇進の検討に膨大な時間を費やす。私たちが採用はヒエラルキー型ではなく、委員会によるピア型が好ましいと考えるのはこのためで、候補者の経歴が空きポストと合致するか否かにかかわらず、とにかく優秀な人材を採用することに集中する。「大学教授級の人材を採用するわけじゃないんだから、通常の会社だったら、ヒエラルキー型の採用でいいんじゃない?」などという声が聞こえてきそうだが、採用した従業員には、中長期にわたって仕事のやりがいを感じられる環境を用意すべきだし、厳しい解雇規制がある現実を考えると、通常の採用の場面でも、大学教授を採用するのと同じくらいの労力をかけてもいいのではないかと思う。また、情熱と知性、誠実さと独自の視点を持った理想の候補者を見つけ出し、獲得するかについて、発掘、面接、採用、報酬の4つのプロセスについても書かれている。グーグルでは、発掘時の作業を「絞りを広げる」と表現している。絞りを変えることで、カメラの画像センサーに入る光量が変わる。採用担当者の多くは絞りを狭くする。いま求められている仕事をきちんとこなせそうな、特定の分野で特定の仕事に就いている特定の人の中から候補者を探そうとする。だが優秀な採用担当者は絞りを広げて、当たり前の候補者以外から適任者を探そうとする。絞りを広げる方法の一つは、候補者の「軌道」を見ることだ。グーグルの元社員、ジャレド・スミスは最高の人材はキャリアの軌道が上向いていることが多い、と指摘する。その軌道を延長すると、大幅な成長が見込める。優秀で経験豊富でも、キャリアが頭打ちになった人はたくさんいる。こうした候補者については、どんな成果を期待できるかがはっきりしている(これはプラスだ)が、予想外ののびしろがない(これはマイナスだ)。年齢と軌道に相関はないことも指摘しておくべきだろう。また、自分で事業を経営している人、あるいは型にはまらないキャリアパスを歩んでいる人には、軌道という指針は当てはまらないこともある。確かに、採用の際、絞りを狭くしてしまうことはあるかもしれない。候補者の伸びしろを見る目が重要であることに気づかされる。併せて「自分自身のキャリアが頭打ちになっていないか?」と考え、反省!?次に面接について…。ビジネスパーソンが磨くべき最も重要なスキルは面接スキルだ。質の高い面接をするには、準備が必要だ。それはあなたが平社員であろうと、経営幹部であろうと変わらない。きちんとした面接をするには、自分の役割を理解し、候補者の履歴書を読み、そして一番重要なこと−何を聞くか−を考えなければならない。面接の目的は、応募者とあたりさわりのない会話をすることではなく、相手の限界を確かめることだ。とはいえ、過剰なストレスをかけるのは避けよう。最高の面接は、友人同士の知的な会話のようなものだ。質問は間口の広い、複雑なものにしよう。正解が一つではないので、相手のモノの考え方や議論の組み立て方を見られる。確かに。面接では、面接をする側も候補者に評価されていることを知っておく必要があるだろう。次に採用について…。質を重視するからといって、採用プロセスに必ずしも時間がかかるわけではない。むしろ、これまで説明してきたグーグルの仕組みは、採用を迅速にするためのものだ。面接時間は30分。ひとりの候補者につき最大5回まで。面接官には、面接が終わったらすぐに採用担当者に合格か不合格かを知らせるように義務づけている。採用には、絶対に侵してはならない黄金律がある。「採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストはない」だ。速さか質か、という二者択一を迫られる場面は必ず出てくるが、必ず質を選ばなければならない。現場のマネージャーから、「このままでは、仕事が回らない!」と懇願されると、「質を犠牲にしてでも…」という誘惑にかられることは少なくないが…。一緒に働く仲間を見つけるのだから、採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストは無いことを再確認。最後に報酬について…。首尾よくスマート・クリエイティブを獲得したら、今度は報酬を払わなければならない。ケタはずれの人材には、ケタ外れの報酬で報いるべきだ。一方マネージャーは、破格の報酬を支払う対象を破格の働きをした人材に限定するよう心掛けるべきだ。相手はプロフェッショナルであり、リトルリーグのコーチをするのとはわけが違う。すべての人間には基本的人権があり、生まれながらにして平等だ。しかし言うまでもなく、それは全員が仕事において同じような能力があるという意味ではない。だから、あたかもそうであるかのように報酬を払ったり、昇進させたりするのはやめよう。職位や入社年次にかかわらず、その人の成果に見合った報酬を支払うことが重要。この当たり前を適正に運用することが、経営に求められることをあらためて認識させられた。ということで、従業員を惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることの重要性を再認識させてくれた“How Google Works”でした。推敲ベタなため、長文の備忘録となってしまった…(苦笑
2015.04.29
コメント(0)
-

ファミマ、ユニー統合交渉
国内コンビニエンスストア3位のファミリーマートと、同4位のサークルKサンクスを傘下に持つユニーグループ・ホールディングス(GHD)は経営統合に向けて交渉に入る。実現すればコンビニ事業の売上高は首位のセブン―イレブン・ジャパンに次ぐ2位に、店舗数では肩を並べる。両社のコンビニ事業は不振が続いており、規模の拡大によって競争力の確保を目指す。(中略)ファミマとサークルKサンクスの13年度の全加盟店ベースの売上高は合計で2兆8100億円と、1兆9400億円のローソンを抜き、セブンイレブン(3兆7800億円)に次ぐ規模になる。ファミマとサークルKサンクスの合計の店舗数は14年11月時点で計1万7400店程度と、セブンイレブンの1万7100店を上回る。国内最大規模のコンビニ店舗網を持てば、資材や商品の調達量が増えて仕入れコストが減らせる。その分、共通商品の開発や販売促進などに投資できる。(中略)国内のコンビニの店舗数は5万店を超え、顧客の奪い合いが激しさを増している。セブンイレブンは独自開発したプライベートブランド(PB=自主企画)の食品などが消費者の支持を得て既存店売上高のプラスが続くが、ローソン以下はマイナス基調だ。(後略)出所:2015年3月6日 日本経済新聞 朝刊 -----------------------------------------------私もほぼ毎日お世話になっているコンビニエンスストアにも、大きな変化が起こっているという記事ですね。私は20年ほど前に、前職のグループ会社で雑誌の取次会社を立ち上げ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKの(バイヤーとの)営業窓口を担当していた。そんなこともって、大手コンビニエンスストアの動向は、興味深く観察している。当時から、大手コンビニエンスストアの中でもセブンイレブンの競争力は図抜けていて、私は新しい商品が出ると「先ずはセブンイレブンのマネージャーへの商談」を鉄則にしていた。理由は2つ。1つ目は『セブンイレブンの販売チャンネルが強力だったこと』。2つ目は、他のコンビニチェーンに商談に行くと『セブンイレブンは何部納入するの?』と聞かれるから…。要は、販売チャンネルが強力なのは、単に店舗数が多いとかいうことではなく、商品に対する戦術・目利きが図抜けていたということだ。今回のファミリーマートとサークルKサンクスの統合は、消費者目線で見ると、セブンイレブンの一強他弱状況から“健全な競争状態を創る”ということで、好ましいことなのだが…。セブンイレブンコーヒーを愛飲し、nanacoのチャージをしている自分(←完全にセブンイレブンの抱え込み戦略に取り込まれている…汗)を振り返りつつ、規模拡大だけでは、「一強の牙城を切り崩すことは簡単じゃないだろうな~」とも思ってしまう。ということで、今後のファミリーマートとサークルKサンクスの統合から目が離せません!!
2015.03.07
コメント(0)
-

損保ジャパン日本興亜、仏再保険に1100億円出資
~海外収益を拡大~損害保険ジャパン日本興亜は再保険世界大手の仏スコールに出資する方針を固めた。2015年度中に1100億円超を投じて同社株15%程度を取得し、持ち分法適用会社にする。損保ジャパン日本興亜としては過去最大の海外出資となる。スコールが強みを持つ生命保険の再保険市場に参入して海外での収益力を高め、人口減で頭打ちが見込まれる国内の損保事業を補う考えだ。(中略)昨年9月に損害保険ジャパンと日本興亜損害保険が合併して誕生した損保ジャパン日本興亜は、単体では保険料収入で国内最大手になった。ただ、グループでは欧米での積極的なM&A(合併・買収)で海外事業を伸ばした東京海上ホールディングスが上回る。損保ジャパン日本興亜も海外事業の強化に向け、14年に英中堅損保のキャノピアスを1000億円弱で買収した。今回の大型出資と合わせて、保険市場の規模が大きい欧米で存在感を高める考え。少子高齢化で国内の損保市場の高成長が見込みにくいなか、大手損保による海外M&Aの動きは今後も続きそうだ。出所:2015年3月6日 日本経済新聞 朝刊 ---------------------------------------------------------損害保険ジャパン日本興亜が、仏スコールに出資だって…。損保ジャパン日本興亜の前身、損保ジャパンは2002年に安田火災海上保険と日産火災海上保険の合併で出来た会社。私は合併に伴いお仕事をさせていただいたこともあり、かなり気になる記事だ。昨年9月の合併により保険料収入で損害保険ジャパン日本興亜は国内最大手になったとはいえ、今後の国内市場の成長イメージが持てない中、次なる戦略は必然的に海外事業強化になるんだろう。昨今、私の知る中小企業でも、海外進出する企業は少なくない。大手企業に限らず、“国内市場だけでは成長イメージが持てない”ということなんだろう。であれば、この記事を他人事として捉えるのではなく自分に置き換えてみることが大切だ。「仮に、自分の会社が海外進出をするのだとしたら…」「閉塞感があるのに現状のまま何も対策を講じなかったとしたら…」等々をイメージし、自分たちはどう振る舞うのがいいのかを考え、行動に移すことが大切なんじゃないだろうか?学生のみなさんであれば、『大手金融系だから「安定」「高収入」』(ちなみに2014年2月の日経新聞 就職人気企業ランキングで、損害保険ジャパン・日本興亜は第6位でした)なんて考えるんじゃなく「縁あって損害保険ジャパン・日本興亜に入社したとしたら、その後は…」とか「日本企業の海外進出は、今後、自分にどんな影響があるのか?」等をイメージして、将来を俯瞰することが大切なんだろう。周囲で起こっている環境変化を自分事と捉えて観察・行動することが大切だ!!
2015.03.06
コメント(0)
-

キャリア・クリエイト14年目がスタートしました!
2015年2月22日、本日はキャリア・クリエイト14年目スタートの日となります。「“企業と個人のWin-Win”をサポートする」をコンセプトにはじめた事業を継続することが出来る『ご縁』と『運』に恵まれたことに心より感謝です。そんな中、昨日は、某大学キャリア支援サークルの就活支援イベントのお手伝いをしておりました。学生たちと一日一緒にいる中、起業に至った原体験を反芻しておりました。1990年代、バブル経済の崩壊後、企業のリストラクチャリングがすすむ中、私はアウトプレイスメント(再就職支援)のコンサルタントをしておりました。終身雇用・年功序列等の雇用慣行の崩壊を目の当たりにする中、退職を余儀なくされたみなさんが、「こんなハズじゃ無かった!自分の職業人生は何だったんだ?」と肩を落とすのを見て、次世代の職業人が「同じ思いをして欲しくない」との想いから起業を決めたことを再確認した次第です。この13年間、活動の裾野も広がり、当社での活動以外にも大学講師、しずおかオンライン取締役(←設立日が同じで、本日22年目のスタート)等を通してコンセプトの実践に携わることが出来ることを嬉しく感じています。私の理想とする“企業と個人のWin-Win”実現までの道のりは遠く、これからも暗中模索を繰り返すことになるのだろうと思いますが、「初心を忘れずにやっていこう!」と思う14年目の朝でした。
2015.02.22
コメント(0)
-

正社員消滅時代の人事改革
〜今野浩一郎 著〜戦後40年以上にわたり世界の注目を集めてきた日本的雇用慣行(終身雇用制・年功制・企業内組合…)が崩壊しつつある(崩壊した?)と言われて久しいが、次なる人事管理のモデルは見えてこない。そんな状況の中、『正社員消滅時代の人事改革』というタイトルと帯に記載のあった『「制約社員」を活かす会社になる』という言葉に誘われて読んでみた。全体は、8章で構成されており、大まかには『現状の人事管理』~『今後の予測』~『新たな人事管理の仕組み』の3つのフェーズに分けて以下の様なことが書かれている。先ずは、『現状の人事管理』について。高度経済成長期には、「作れば売れる」市場環境を前提に、組織メンバーの管理は、明確な数値目標とプロセス管理をすればよかったが、市場の不確実性が増す中、最終成果に関わる目標に変化させる必要性が生まれてきた。結果として、昨今は自営業に似て裁量的になる仕事の進め方が要求される様になってきており、「任せるから責任を取りなさい」に変化してきている。また、『今後の予測』につては、「制約社員」が多数派になり、企業は「制約社員」の増加を前提とした人事管理が必要になってくる。ここで言う「制約社員」とは、「無制約社員(イメージは、かつて総合職と呼ばれてきた男性中心の基幹的社員)」が会社の指示や業務上の都合に合わせて場所・時間・仕事を柔軟に変えることが出来るのに比べ、何らかの制約を持つ社員のことを指す。正規・非正規社員の別に関わらず、多くの女性は家事や出産・育児等の時間制約があるし、男性だって親の介護の時間や場所の制約がある、定年後に再雇用された高齢社員は時間や場所の制約・障害者は労働機能面での制約がある等々、「制約の無い社員の方が少ないんじゃないの?」ということだ…。とここまでは、すべて納得なのだが…。一番重要な『新たな人事管理の仕組み』については、いろいろな角度からいろいろな案が提示されてはいるものの、残念ながら「なるほど~!」と納得できるような新たな仕組だと思える様な提案ではなかった。そんな中、筆者は著書の最後で「人事管理の新しいモデル、それも世界に発信できるようなモデルを作り上げたいと意気込んでみたが、本書を書き終えてみると、それには到底及ばないものになってしまったようだ」と正直な感想で結んでいるのが良心的。そもそも万能な人事管理の処方など存在するはずもないワケで…。「現在の日本の人事管理の課題についてはわかりやすく整理されている良書かな?」というのが読了後の印象だ。
2014.12.22
コメント(0)
-

大学3年生に気づきは与えられたかな…?
~今年の授業、終了しました~ここのところ、「書かなくっちゃ、書かなくっちゃ…」と思いつつ、ブログの更新をさぼっておりました。ということで今回は、一昨日終了した今年の大学での授業(年明けにあと2回ありますが…)の中で、本年度から担当した「職業・キャリア教育」についての雑感を…。この授業のテーマは「労働者保護は、どうあるべきか?」。昨今、日本の労働市場では「就職できない若者の増加」「低賃金非正規労働者の増加」他、多くの課題を抱えている。そんな中、「これから就活に臨む学生たちが、知名度や条件だけで企業や団体を選択して欲しくない!」との思いから、既存の『労働者保護の法律』についての理解を深めると共に、『採用内定取消・解雇規制』『非正規社員』『男女間の賃金・待遇格差』他をテーマに、毎回、討論をしてもらっている。で、今年最後の授業(第13回)のテーマは、『高齢者雇用』。高年齢者雇用安定法の概要説明をした後、「みんなは、自分には関係ないと思っているかもしれないけれど…」と前置きし、「定年制があった方がよいと思うか?」を討論してもらった。各グループの話に聞き耳を立てていると、「高齢者の継続雇用で若者の就労機会が減るのは困るけど、ウチの親父60だし、自分が卒業するまでは頑張ってもらわないと…」「そもそも何で定年制が出来たんだろう?」等の内容が聞え、気になったコメントは他のグループにも共有してもらうことを意識した。以下、出席簿代わりに書いてもらっている感想の一部。「高齢者雇用について、私には殆ど関係ない話だと思っていたけれど、話は全てつながっていることに気付いた。選挙のこと(←私が「選挙行けよ!」と話したので…)もそうだけど、私は制度・政治等に無関心すぎる。もっと、なぜこの制度が出来たのかなどの視点で見ていくことが出来ないと、人生損する気がした。」「一人ひとりそれぞれの立場によって、モノの見方や考え方は変わるからこそ、自分自身の視野を広げたり、価値観を高めるべきだと思った。」「何が良い悪いということではなく、世の中の制度はもう決まっているのだから…と思ってしまうのではなく、自分にも関係があり、今後生きていく上で損をしないためにも、いろいろな立場の人の様々な意見や考え方を知ることが必要であるということです。正直、今回もこの話し合いをしなければ、女性である自分に定年制のことはあまり関係ないと感じ、気にもしていませんでした。しかし、今回の授業ではじめて考えることなどもあり、他人事ではないと思いました。」私は、学者じゃなく人材ビジネスの実務家だということも影響(?)してか、学生のコメントの中に「損をしないためにも…」といったコメントが見られるけれど、コレも大切なこと。学生たちが、「自分たちの身の回りで起こっているコトやルールはすべて自分にも関係しているということ」「自分も社会の一員であること」を理解し、自分事として捉えはじめてくれていることが嬉しい感想でした。
2014.12.19
コメント(0)
-

長~いタイトルの申し合わせ?!
~企業等の協力を得て取り組むキャリア教育としての学内行事実施に関する申合せ~去る9月16日、国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校で構成する就職問題懇談会(座長:浜口道成 国立大学協会教育・研究委員会委員長(名古屋大学長))が、「企業等の協力を得て取り組むキャリア教育としての学内行事実施に関する申合せ」を取りまとめ、文部科学省のHPにて発表された。要約すると、2016年卒の新卒より、広報活動の開始時期は卒業・修了前年度の12月だったものが3月に、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の4月だったものが8月に後ろ倒しされることが決定している。その決定を受けて、(一社)日本経済団体連合会(以下、経団連)は、広報活動開始前(3月以前)においては、「大学が行う学内セミナー等への参加を自粛する」ということだったが、学校として「大学等のキャリア教育において、学生の産業や職業に関する理解を深める取組の実効性を高めるためには、学内セミナー等への企業の参加は必要で協力いただきたい」旨を話したところ、経団連も趣旨に賛同し、採用選考に関する指針の手引きの改定を行ったとのこと。尚、ここでいう学内セミナー等とは、あくまでキャリア教育の一環なので、企業の採用を目的とした「企業説明会」でないことは共有しましょうという内容だ。う~ん、わかりにくい…。で、私なりに更に要約(解釈)すると「学校としては、採用活動の後ろ倒しにより、学生の企業情報収集に遅れが出ることが心配だ(抜け駆けする企業や学校もあるだろうし…)。学生の就活モチベーションを維持・UPさせるためにも、企業には是非とも学内セミナー等に協力して欲しい。但し、あくまで採用目的はNGですよ!?」ということを就職問題懇談会で申し合わせ、経団連も賛同してくれたということの様だ。申し合わせの内容はわかったけど、結果的に当初の“就活後ろ倒し”の目的だった「大学生等の学修時間の確保、留学等の促進」は実行できるんだろうか?この手の話、悩ましいのは、善し悪しとは別に「流れに乗らないと損をしちゃう!?」というジレンマに陥る可能性大であるということ。民間の就職支援会社が学内セミナー他、いろんな部分で知恵(?)を出して“際の部分の新サービス”を編み出しそうな気もするし…。老婆心ながら「就職活動の早期化と長期化を助長するコトにならなきゃいいんだけど…」などと考え込んでしまいまいした。
2014.09.19
コメント(1)
-

非正規から正社員、4~6月100万人
~企業、人材囲い込み 若者世代の登用進む~非正規社員から正社員への転換が進んでいる。転職や社内登用で正社員になった人が今年4~6月期は前年同期比2割増え、ほぼ100万人となった。人手不足の小売りやサービス業は人材を囲い込むため、パートらを転勤のない限定正社員などに切り替える。「就職氷河期」で非正規が多かった若者世代が正社員に登用されており、賃金の押し上げなどで景気の下支え効果も期待できそうだ。総務省の労働力調査から、正社員として働き始めた人のうち前職が非正規だった人の数を調べた。4~6月期に正社員となった人のうち、転職や自社登用で非正規から転換した人の数は99万人と前年同期に比べ22%増えた。リーマン・ショック後の雇い止めなどで非正規の転職が盛んだった2009年7~9月期の104万人以来の水準だ。正社員に転換した99万人を年齢別にみると、15歳~34歳が64万人と65%を占める。前年同期は50万人で全体に占める割合は62%だった。30代の就職氷河期世代は新卒採用が少なく、非正規社員として働き続けてきた人も多い。こうした世代で正規雇用に移る動きが強まっているのが特徴だ。(中略)働く人全体でみると、前職が正社員だった人が新たに非正規社員で働き始める人も多い。60歳で定年退職してから非正規で働く人が多いためだ。4~6月期に正社員から非正規へ転換した人は、119万人と前年同期から11%減ったが、正社員に転換した99万人を人数では上回る。ただ新卒なども含めると正社員の数は増えており、労働者全体の中で非正規の比率は減っている。正社員と非正規を合わせた4~6月期の雇用者数は5235万人と増えており、労働参加の裾野は広がっている。出所:2014年9月9日 日本経済新聞 朝刊 -------------------------------------------------------------------非正規社員から正社員への転換が進んでいるという記事だ。労働市場が活性化する中、企業は魅力ある労働条件を提示する必要があり、正社員採用の枠を拡大しているということなんだろう。4~6月期に正社員に転換した99万人を年齢別にみると、15歳~34歳が64万人で全体の65%を占めるとのことだ。新卒採用が少なかった就職氷河期世代の若者が辛酸を嘗めた状況を考えると、非正規社員だった若者が正規雇用に移る動きが強まるのは喜ばしいことだと思う。一方、働く人全体でみると、正社員から非正規社員へ転換した人119万人に対し、非正規社員から正社員に転換した人が99万人と、非正規社員に転換した人数の方が多い。主な理由としては、60歳で定年退職してから非正規で働く人が増えているためだ。年金受給年齢の繰り下げが行われる中、「まだまだ引退っていうわけにはいかない」というシニアが増えているということなんだろう。ということで、労働市場のパイが増えると共に、「正社員から非正規社員、非正規社員から正社員と『雇用の流動化』が進んでいる」風(?)なのは、悪いことじゃないけれど…。今回、正社員化を進める企業が積極的に導入を進めているのは、働く時間や場所を限る「限定正社員」。へそ曲がりな私は、それはそれでアリだと思うけど、この機会に『「そもそも正社員って何?」「正社員と非正規社員という区分は必要?」等を議論してもいいんじゃない?』なんて考えてしまった。
2014.09.09
コメント(1)
-

「転職検討」20代男性51%
〜男性、給与水準に不満 女性、人間関係で悩み 本社など調査〜20代男性の半数以上が転職を検討していることが、日本経済新聞社とNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションの「NTTコムリサーチ」が共同で実施した転職意識調査でわかった。20~50代のビジネスパーソンを対象とした調査で、全体では転職希望者は38%だった。転職の理由は男性に「給与水準」が多いのに対し、女性は「職場の人間関係」をあげる人が多かった。20代男性で「転職を検討している」と回答したのは47.1%。「すでに転職の準備を進めている」(4.3%)と合わせて51.4%と半数を超えた。30、40代は約4割で、50代は27.5%だった。企業が応募する際に年齢制限を設けていることが多いためか、年齢が高くなると転職希望者の割合は低くなる傾向が見られた。(中略)転職結果に不満があるとの回答者にその理由を3つまで選んでもらったところ、「給与水準」が78.9%を占めた。給与水準の引き上げを目指して転職しても、満足な結果を得られないケースが多くあるようだ。転職活動について感じることを自由回答してもらったところ、転職前の情報と入社後とのギャップに対して不満の声が多かった。「入ってみないとわからないのがいつも不満」(30代男性)、「募集要項だけでは細かい待遇や条件がわからず、検討しにくい」(20代女性)などの声が上がった。人手不足のなか、中途採用者を貴重な人材確保の戦略と位置づける企業では、より職場の実態にのっとった情報提供が優秀な人材確保のカギになりそうだ。一部の回答者は「働きながらの転職活動は(理解を得られず)面接日の調整が難しい」(20代男性)、「転職に伴う手続きなどで、日本は終身雇用を前提とした仕組みが残っていると痛感」(40代男性)、「転職=悪という意識が世間にまだ残っている」(40代男性)などの声も目立った。転職者を戦力ととらえる企業が増えており、転職に対する理解度は高まっているものの、なお一部の理解の薄さに戸惑いを感じるケースは根強く残っているようだ。出所:2014年8月19日 日本経済新聞 朝刊 ----------------------------------------------------------なんと、「20代男性の半数以上が転職を検討している!?」という記事だ。採用現場の実感としても若手求職者の応募書類が増えているのは実感しているけれど、「20代男性の半数以上が、現状の仕事に全力投球できていない可能性大?」とも言い換えられそうで、少なからず驚きだ。景気の低迷が続く中、転職しようにも魅力的な求人案件が見当たらない?という時期が続いた反動もあるのかもしれないが…まっ、私自身、転職自体については、否定も肯定もしないけど、役員を務めさせていただいている会社の面接では、「何故、転職するのか?」について、いろんな角度から根掘り葉掘り(?)聴くことを心がけている。(私の質問の仕方がいいのか)「給与が不満」「労働条件が不満」「人間関係が不満」等、いろんな「不満」が聴き出せるし、話を聴けば「それじゃ、辞めたくなるのも無理ね〜や!?」って思える内容が多いのも事実。ただ、採用する側は、「応募者の前職への不満」を聴きたい訳じゃないことを理解することも大切だ。だって、不満ばかりの求職者は「うちに入社しても、また不満ばっかり言うんだろうな〜?!」などと否が応でも想像しちゃうでしょ。「辞めたい理由」じゃなく、「貴社に入社したらこんなコトしたい、将来はこんな風になりたい!」って自分の言葉で語れることが大切だ。そのためには、自分の今の力量がどの程度なのかを客観視しなくちゃならないし、応募企業はどんな会社でどんな人材を求めているのかをちゃんと研究する必要がある(不明点は、面接で質問すればいい)ということだ。まぁ、記事にもある様に、「募集要項だけではわからない…」というのはもっともなので、企業はより一層の工夫が必要だけど…企業は「自社への理解を深めてもらう努力をすること」、応募者は「相手(採用企業)の立場に立ってものを考えることが出来ること」が、双方が納得のいく採用・求職活動の必要条件なんでしょうね!?
2014.08.19
コメント(0)
-

『若手社員 職場定着セミナー』終了!
〜若者の早期離職が社会問題化している!?〜7月下旬、県内3会場で開催した『若手社員 職場定着セミナー』。入社3年以内の若手社員100名強に参加いただきました。当該セミナー、タイトルから見て取れるように若者の職場定着支援を目的に実施しました。まぁ、私自身、転職自体を否定する者ではないので、厳密に言うと、目的は『定着支援』ではなく、『働きがいを見つけてもらう』ことなのですが…。セミナーは二部制。第一部は「昨今の労働市場の実体を知る」ということで、若年者の労働市場がどうなっているのかを統計データを使って解説したり、同世代の他社の社員が「現在の仕事についてどんな悩みを抱えているか?」を相互に共有したりしました。で、「現状に流されること無く、一人ひとりがキャリアビジョンを描くことが大切だよね!?」ということで休憩に…。第二部は「キャリアビジョンを描いてみよう」ということで、先ずは「自分はどんな職業人になりたいのか?」(←そもそも、「そんなこと考えたことも無い」という人がほとんど)を客観視するため、いくつかのアセスメントツールを使ったワークを実施。最後に、キャリアビジョンを考えるプロセスを具体的事例を交えて解説しました。そんな中、実施内容よりも、受講者がどう感じたかの方がず〜っと重要だと思うので、終了後のアンケートの紹介を…。「会社を辞めさせないためのセミナーだと思って参加したが、そうではなくてよかった」「転職を考えていたが、辞めるのが目的の転職はNGだとわかった」「転職について、もう少し仕事を続けて見て決めていきたい」「目先のことばかり見ていたが、広い視野で先々のコトを見ていきたいと思う」「現在、自分が抱えている問題について解決の糸口を見つけられたような気がする」「他者の意見を聴くことは大切ですね」等々…「私が伝えたかったことが、伝わったかな?」と思えるアンケート内容に「ほっ…」としております。各会場、開始時の転職意向を問うアンケートで、『現在、ぜひ転職したい』と答えていた社員がいました。その参加者が、「辞めるのは目的の転職はNG」と書いてくれたのであれば、すご〜く嬉しいですね。特に若手社員の場合、社会経験・会社経験が浅い分、「自分が今いる会社の今いる部署の中だけがすべてだ!」と考えてしまいがち。いろんな立場のいろんな人と言葉を交わすことの重要性をあらためて感じさせられたセミナーでした。
2014.07.31
コメント(0)
-

「妻は専業主婦」希望4割
〜20〜40代男女意識調査〜明治安田生命福祉研究所が発表した20代〜40代の結婚などに関する意識調査によると、「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」との考え方を支持する人の割合が、男性で39.3%、女性で43.0%に上った。政府は「女性の活躍」を成長戦略の目玉に掲げて社会進出を促しているが、男女とも約4割が「妻は専業主婦」を望んでいる実態が浮き彫りとなった。調査によると「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」との考え方に、「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答した割合は、未婚男性では34.2%、未婚女性では37.9%。既婚男性は42.5%、既婚女性は46.1%で、男女とも既婚者の方が回答が多かった。調査担当者は「意外な多さだったが、女性が産後も働き続けられる環境が十分でないとの考えが根強いためではないか」と話している。「こどもが小さいうちは、妻は育児に専念すべきだ」との考え方を支持する割合も、男性64.4%、女性70.9%に上った。調査は全国の20歳以上49歳以下の男女を対象に、3月下旬、インターネット上で行った。回収数は3616人。出所:2014年7月13日 静岡新聞 朝刊 ----------------------------------------------------男女とも約4割が「妻は専業主婦」を望んでいるって…。政府の成長戦略の目玉である『女性の社会進出』に水を差すような調査結果だ。特に、男女問わず、未婚者よりも既婚者の方が「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」という回答が多いのが、少なからずショックだ。結婚すると、男性は「俺が帰ったら『お帰りなさい』と迎えて欲しい」と思ったり、女性は「ご主人の稼ぎだけで生活出来たら幸せ…」なんて考えての結果なんだろうか?とはいえ、調査担当者は「意外な多さ…」とコメントしているけど、この調査結果に驚かない自分がいるのも事実。学生たちと働くことについて議論すると、この調査結果と似たような話に遭遇することは珍しくない。『仕事にやりがいを感じている両親』のもとで成長した学生は「早く社会に出て働きたい」というけれど、『仕事の愚痴ばっかり言っている両親』のもとで成長した学生は「出来れば仕事をしたくない」といい、実は後者のパターンは少なくない…。『女性の社会進出』の促進に『女性が産後も働き続けられる環境整備』は、必要条件ではあるけれど、先ずは「『出来れば働きたくない』と思っている人は少なくないかも…」というところから、仮説を立ててみることも必要なのかもしれない。
2014.07.15
コメント(0)
-

トヨタ対VW 2020年の覇者を目指す最強企業
~中西孝樹 著~トヨタとVW。クルマ好きの私としては、大量生産のメーカーのイメージが強いこの2社は、興味の対象になる存在ではなかったのだが…。そんな私ですら「自動車業界、何かが変わりはじめている?!」と感じる中、タイトルに惹かれて読んでみた。トヨタとVW、創業家支配の自動車メーカーという共通点はあるものの、経営に対するスタンスが全く違うことに驚かされる。トヨタの経営思想はじっくりと同じ価値観を共有できる文化や仕組みを育てるという信念にあり、まさに日本のモノづくり、人づくりのビジネスモデルとなる会社。一方のVWは、戦略的に企業買収を進め、マーケティング、デザイン、ブランドを含むソフト面のマネジメント能力を駆使することにより、製品の平準化や同一化のリスク管理を行い差別化の維持が出来る会社であり、私の概念にある自動車会社の枠をはるかに超えている。読んでいるうちに、「この本、単に『トヨタ対VW』というんじゃなく、2020年に日本の製造業のビジネスモデルは生き残れるのかを占う本なんじゃない?」なんて考えてしまった。まっ、僕は日本人なので「2020年にはトヨタが自動車業界の覇権を握ってくれてるコト」を期待しちゃいます…!?
2014.07.09
コメント(0)
-

リクルート、新入社員の定着後押し ウェブで状態調査
リクルートホールディングスは1日、新入社員の定着を支援する企業向けクラウドサービスを始める。新入社員が簡単な質問に回答を入力すれば、精神状態や業務の達成度を測定できる。上司は結果から新入社員に適切な助言につなげる。人手不足が深刻になるなか、新入社員の離職を防ぐ。初年度は1万人の新入社員の利用を目指す。子会社のリクルートキャリア(東京・千代田、水谷智之社長)が始める。新入社員は2か月に1回、ウェブ上で質問に選択式で回答する。不安や疲労を感じるかなどを聞く。5段階の回答から自動的に精神状態を評価する。社会人としての基礎力を早期に身につける機能もある。毎月、「自分で考えて行動する」など目標を選択し、達成度を振り返る。上司は新入社員の自己評価をもとに、助言する。料金はサービス導入時に3万円、利用する新入社員1人当たり1万5千円。出所:2014年7月1日 日本経済新聞 朝刊 ---------------------------------------------------------------------社会問題化している“新入社員の早期離職”対策として、リクルートホールディングスが職場定着支援サービスをスタートするという記事だ。新入社員の職場定着は、会社を経営する者としても採用コンサルティングを生業とする者としても、悩みがつきないテーマだ。記事の内容を読む限り、それなりの引き合いもあるだろうし、効果も見込めるんだろうけど…。この問題を語る際、「職場定着しないと企業にとっては損失だ!」とか、「じっくり腰を落ち着けて仕事をする若者が増えないと日本の産業は衰退する!」等、ほとんどが企業や社会から見た視点で語られる様に感じてしまうのは、私だけだろうか?まぁ、課題解決策をビジネスモデルに落とし込むとこんなカタチになっちゃうのは、いたしかたないことなんだろうけど…。やっぱりお金を払う企業からの視点じゃなく、当事者である若者の視点で考えてみることが大切なんじゃないかと思う。私は、系統だったビジネスモデルの提案は出来ないけれど、早期離職を考える若者に対しては、日本の労働市場では、劣悪な労働条件や職場の閉塞感が理由で会社を辞めたとしても、“根気の無い若者”としか見られないし、職務経歴としてもカウントされないことを伝えたい。現状を否定したくなったら、それと並行して、次に繋げるために“将来を俯瞰”することも大切だ。自分のキャリアは自分で創ることを前提に、“善し悪し”ではなく“損得”を基準に判断することも必要であることも伝え続けていきたい。ということで、7月下旬に“職場定着セミナー”を実施します。<若手社員職場定着セミナー開催のお知らせ>概ね入社3年以内の若手社員を対象として、早期離職の背景を探るとともに、継続して業務を行う重要性を説明し、職業意識の形成、将来ビジョン等のグループディスカッションを行い、仕事を通じての人間形成と職場定着に対する理解を深めるセミナーを開催致します。■概要・お申し込みhttp://jinzai.siz-sba.or.jp/company■チラシhttp://www.siz-sba.or.jp/info/20140616teityaku_annai.pdf■お問合せ静岡県中小企業団体中央会 労働対策課 菊池まで(〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1)TEL:054-254-1511 FAX:054-255-0673 e-mail:jinzai@siz-sba.or.jp
2014.07.06
コメント(0)
-

自己分析講座を開催しました
~大学生の就職活動~とある大学のご依頼を受け、6月中旬から6回(同じ内容)にわたり、大学3年生を対象とした自己分析講座を実施した。2016年卒からは、就職活動解禁時期が12月1日から3月1日に繰り下げになるというのに、「こんな時期から自己分析講座…?」なんていう声が聞えてきそう。まぁ、就職活動解禁時期の繰り下げは、採用側にも学生にも多大な混乱を招く可能性は大だけど、学生から見れば競争相手が変わるわけじゃないんだし…。就活時期がいつになろうと就職するにあたっての重要なポイントは変わらない。むしろルールが変わることばかりに意識が向かい、大切なポイントを見落とすことの方が心配だ。そんな想いを込めて自己分析講座を実施した。そもそもボクは、『自己分析』という言葉が好きじゃない。理由は、『自己分析』っていうと多くの学生は『たった20年程の過去を振り返り、企業にアピールできる長所を探すこと』と考えちゃうから。ということで、今回も「就活本番前にやるべきことは?」という副題をつけさせていただいた。で私が、学生たちに就活本番前の『自己分析』でやって欲しいことだが…。第一は、『「約1年9ケ月後には社会人になる」という現実を認識する』こと。加えて、就活の目的は「どっかの会社に入ることじゃなく、職業人生のスタートラインに立つための活動であること」を理解することだ。第二は、『「相手」(企業)がいることを認識する』こと。多くの学生が「やりたい仕事がわからない。行きたい会社が見つからない」と言うけれど、彼らは驚くほど「世の中にどんな会社があるのか(だけじゃなく、どんな仕事があるのかも…)」を知らない。先ずは、世の中にある会社に興味を持つことからはじめるべきだろう。また、「相手(企業)が自分に何を求めているのか?」を推察することも大切だ。てなことを盛り込んで、90分のメニューを実施した。終了後のアンケートには、「自己分析のやり方を教えてくれると思ったのに…」というコメントもほんの少しあったけど、「世の中にある会社を全然知らないことがわかった」「採用者側の意識が理解できてよかった」「やるべきことがわかった様な気がする」等の好意的なコメントがほとんどだった。「ボクの伝えたいこと、少しは解かってもらえたようだ!?」と、「ホッ…」と一息の自己分析講座だった。※画像と本文は、無関係です。
2014.06.27
コメント(0)
-

社長は少しバカがいい
~エステー株式会社 会長 鈴木喬 著~著者は、消臭力等で有名なエステー会長の鈴木喬氏。1年程前に買って積み重ねておいた本のうちの1冊。テレビ出演でべらんめー調で受け答えする氏に興味を持って読んでみた。書かれている内容は、いたってまともというよりも、経営指南書として参考になることがてんこ盛り。トップは何を考え、どう振る舞えばいいのかを考えさせられる。特に、東日本大震災時の判断についての件(くだり)なんかを読ませていただくと、「この人、すげ~! 会社が公器であることが体に染みついているんだ~?!」などと感服してしまう。「創業家出身の社長だから、こんな風に出来るんだ!?」なんて、陰口をたたく人もいるかもしれないけれど、僕はこんな経営トップを支持しちゃう!! 内容は濃いけれど、2~3時間あれば読めるし、とっても読みやすい。居酒屋でたまたまとなりに座ったおじさんから、「すっごくいい話、聴けた~!!」と満足しながら帰路につく時に似た読後感…。「タイトルに、偽り大あり!?」の本でした…(笑
2014.06.16
コメント(0)
-

年収は「住むところ」で決まる
~エンリコ・モレッティ 著~「イノベーション都市」の高卒者は、「旧来型製造業都市」の大卒者より、稼いでいる!?の帯に釣られて読んでみた。現代の製造業がそうであるように、多くの産業では、グローバル化と技術の進歩によって、雇用の大半は低賃金の国に出ていってしまうと考えるのが一般的。少なくとも私はそう思っていた。にも関わらず、アメリカ経済の新たな成長エンジンであるイノベーション産業では、グローバル化と技術の進歩が、雇用を増やす原動力になっており、結果的に、成長する都市の高卒者の給料は衰退する都市の大卒者の給料よりも高くなるという現象が起きている。イノベーションに取り組む企業にとっては、人件費やオフィス賃料等のビジネスをおこなうためのコストが格段に高くても、『生産性の高い働き手』が集まっている土地に拠点を置き続けるのが合理的であるというのが、その理由だ。では、『生産性の高い働き手』が集まる要因は…?著者は、超一流の交響楽団や美術館などの文化施設を擁するクリーブランドやライフスタイルの面では魅力的なイタリアが、新しい経済基盤を築くことが出来ていないことを例に出し、『魅力的な町というだけでは、地域経済を支えられない。結局、必要なのは、雇用を創出することだ』といっている。『ものごとの原因と結果を混同してはならない』ということだ。雇用創出というと、行政の産業政策や補助金による企業誘致等が真っ先に思い浮かぶが…。著者は、『地方政府は、その土地の強みと専門性を活用することを考えなくてはならない。その際、雇用創出のために税金を投入するのは、市場の失敗が放置しがたく、しかも自律的な産業集積地を築ける可能性が十分にあると判断できる場合に限るべき。』と警鐘を鳴らしている。また、『どの産業が勝者になるかを前もって予測することは、政策決定者にとって容易ではない。』とも…。『私たちの仕事の環境と社会の基本的骨格は、グローバル化とローカル化という、21世紀の2つの潮流によって根本から様変わりしようとしている』という言葉で結ばれているこの本、示唆に富む、良書だった。
2014.06.13
コメント(0)
-

学生の県外就職支援
~県立大、全国10大学と連携 求人情報など共有~静岡県立大学は横浜市立大学や大阪市立大学など全国10大学と連携し、静岡県外での学生の就職活動支援を始めた。県外企業の情報は入手しづらいため、連携する大学から地元企業の求人情報などを得られるようにした。静岡県立大を含めた11大学は4月に就職支援に関する協定を締結し、6月に運用を始めた。学生からの要望に応じ、各大学の地元企業の求人や会社説明会の情報を公開したり、就職相談に応じたりする。各大学の就職支援スペースのパソコンなども利用できる。今後は11大学の就職説明会に学生が相互参加することなども検討する。静岡県立大の担当者は「学生だけでなく、企業にとっても、県外の優秀な学生を採用するチャンスが増える」(キャリア支援室)としている。出所:2014年6月3日 日本経済新聞 地域経済・静岡 -------------------------------------------------------------------他県の大学と連携し、県外企業の求人情報の共有がスタートしたという記事ですね。文部科学省の学校基本調査によれば、静岡県の県外進学率(=県外大学への進学者数÷全大学進学者数)は、平成7年の0.86から平成22年の0.73へと減少を続けている。子を持つ親であり学生の就職相談に乗る私の経験から推察するに、減少の理由は「親の経済的負担が大きい」「若者の地元志向~マイルドヤンキー化?」などがあげられる。個人的には、ことわざの『可愛い子には旅をさせよ』にある様に、「若い頃の苦労は、のちの人生にとってきっと役立つことがあるハズ。甘やかしてそばに置くのではなく、外の世界を見られる機会を増やすことが大切!」と考えているので、この調査結果には少なからず不満が…。そんな中、県外進学率減少のもう一つの理由として、県外の大学に進学した際に「地元企業の求人情報入手手段が減ってしまうコト」があげられる。「旅に出たものの、戻るべき地元に自分を受け入れてくれる企業があるのかわからない?」という不安を抱えたまま、他県へ進学したくないという心理が働くということ。学生の就職相談を受ける中、「県外出身学生の地元の情報が欲しい!」という相談に十分に応えられていないという私の実感だ!一度、地元を離れて外の世界に触れた若者が、視野を広げて地元に戻ってくる(別に、大学卒業してすぐに戻ってくる必要はないと思いますが…)。その経験やネットワークを活かして地元で活躍する。そんなシナリオが描けたら素晴らしいですね。ということで、今回の静岡県立大学を含む全国10大学の就職支援に関する協定(就職支援パートナーシップ制度)には、『注目』です!?
2014.06.03
コメント(0)
-

「ブラック企業」取り締まり強化
〜労働時間規制緩和へ準備〜出所:2014年5月27日 静岡新聞 朝刊「政府が過重労働や賃金不払いなど労働環境が劣悪な『ブラック企業』の具体的な取り締まり方針を年内にも策定する」という記事だ。で、策定の背景には労働時間規制を一定の条件に合う労働者に限って撤廃する『ホワイトカラー・エグゼンプション』の導入に向けた環境整備があるということなのだが…。そもそも、『ブラック企業』取り締まりと『ホワイトカラー・エグゼンプション』導入の環境整備をいっしょくたに語ることの意味がわからない。まぁ、「『ブラック企業』は労働時間規制緩和を悪用し合法的に社員を酷使しかねない!」ってコトなんだろうけれど…現在、想定している労働時間規制緩和の対象者は、「年収が一定額以上で仕事の成果が計り易い金融機関の為替ディーラーやコンサルタントといった一部のホワイトカラー」。で、ここでいう一定額とは、民間議員の意見では年収1,000万円以上、厚労省はさらに年収が高い人を想定していて、且つ管理職じゃないサラリーマン。ボクの周りには、対象者に該当しそうな人はいないので、確証を持って言える訳ではないけれど…。そんなスーパーサラリーマン(?)が「経営者や上司に酷使されている場面」をイメージするのは難しいなぁ〜。まぁ、この労働時間規制緩和がキッカケとなって対象範囲が拡大していく可能性だってあるので、『悪用』の危惧が無いとは言わないけれど…。ただ、その際の危惧は「制度策定の趣旨自体」ではなく「趣旨から逸脱した運用」だと思うんだけど…。ということで、やっぱり『ブラック企業』取り締まりと『ホワイトカラー・エグゼンプション』導入の環境整備を同じ土俵の上で論じることの意味がわからない。劣悪な労働環境の会社に意欲あふれる人材は集まらないし、真っ当な企業経営者にとって『働きがいのある職場づくり』が企業経営成功の必要条件であることは、自明の理だ!?
2014.05.29
コメント(0)
-

ワーク・シフト
〜孤独と貧困から自由になる働き方の未来図 リンダ・グラットン著〜「ビジネス書大賞2013大賞受賞、全世代必読!「働き方」の決定版」という帯に惹かれて読んでみた。大雑把に言えば、「テクノロジーの発展」「グローバル化」「人口構成の変化と長寿化」「個人、家族、社会の変化」「エネルギーと環境問題」という5つの変化によって、2025年の職業人は、地球規模で「下流民」と「自由民」に二極分化する。「自由民」になるためには、ワーク・シフトが必要ですよ!という本。で、どんな風にシフトするかというと…1. ゼネラリスト→連続スペシャリスト2. 孤独な競争→みんなでイノベーション3. 金儲けと消費→価値ある経験へのシフトが必要だとのこと。う〜ん、リンダ・グラットン氏の予測どおりになるかは分からないが、好むと好まざるとにかかわらず、10年後の働き方が現状と大きく変わり、二極分化する方向に進んでいることは間違いなさそうだ。競争社会自体は否定しないけれど、「自由民」になれる人がほんの一握りになってしまうかもしれない世の中が、果たしていいのだろうか?という疑問も沸いてくる。まぁ、グラットン氏は、そういう未来の是非を論じているんではなく「その中でどう生きるのかを考えましょう!」と言っているのだが…。そんな中、備忘録がわりに琴線に触れた箇所を抜粋しておこう。私にとって重要なことがあなたにとって重要だとは限らないし、私が望む働き方があなたの望む働き方と同じだとも限らない。私たちは、一人ひとりが自分なりの働き方の未来を築いていかなくてはならない。私たち一人ひとりにとっての課題は、明確な意図をもって職業生活を送ることだ。自分がどういう人間なのか、人生でなにを大切にしたいのかをはっきり意識し、自分の前にある選択肢と、それぞれの道を選んだ場合に待っている結果について、深く理解しなくてはならない。「普通」でありたいと思うのではなく、ほかの人とは違う一人の個人として自分の生き方に責任をもち、自分を確立していく覚悟が必要だ。うん、私たちの働き方が変化していく中“自分の人生に責任を持つ覚悟”が必要なことだけは、間違いなさそうだ。
2014.05.18
コメント(0)
-

労働時間規制除外
~働く者の立場が心配だ~出所:2014年5月8日 静岡新聞 朝刊 ----------------------------------------------------------------政府の産業競争力会議が、残業代の支払いなど労働時間規制の適用を除外する「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入を検討していることに対し警鐘を鳴らす記事だ。この記事に限らず、誰かの主張に耳を傾ける際に注意しなくてはならないと思うのは「論点は何か?」を明確にすること。そんな観点でこの記事を読むと「政府がルールを作ること」と「労働時間規制除外自体(個人が長時間働くこと)」の2つの是非を混同して論じている様な気がするのだが…。で、ひとつ目の論点「政府がルールを作ること」。労働市場を野放図な状態にしないためには、政府主導でルールづくりをしなくちゃならない場面も出てくるのだろうけれど…。私は、今回の「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入も含み「政府がルールを作る」のではなく極力労働市場の原理に任せて欲しいと思っている。もうひとつの論点「労働時間規制除外自体(個人が長時間働くこと)」について。記事ではエジソンを例に「発明王エジソンはワーカーホリック(仕事中毒)であり、彼のような創造的な仕事に専念できた人は例外」ということを前提に論を進めている。「好きな仕事であっても長時間労働が続けばやがて苦痛に変わる」と決めつけてしまうことに違和感がある。たまたまかもしれないけれど、私の周りには仕事が大好きな人は少なくないし、へそ曲がりな私なんかは、「好きでやっているのにいらんお世話だ!ワーカーホリックの何処が悪い!?」なんて思っちゃう。もしかしたら「経営者やフリーランスとサラリーマンは違う!」とか、中には「仕事したくないからサラリーマンやっているんだ!」なんて反論する人もいるかもしれない。でも、好むと好まざるにかかわらず、サラリーマンがフリーランスになるコトだって、その逆だってある訳で…。記事では、労働時間規制の適用を除外することにより、「誰もが名ばかりの『ホワイトカラー』となって、見返りのない長時間労働を強いられる『残業残酷物語』の悪夢がよぎる」と結んでいるけれど、これにも違和感を感じちゃう。真っ当な経営者であれば、社員が『長時間会社に居ること』を期待するんじゃなく、『高付加価値の仕事』をしてくれることを期待していると信じたいし、そうあって欲しいと強く願う!!
2014.05.11
コメント(0)
-

20歳のときに知っておきたかったこと
〜スタンフォード大学 集中講義 ティナ・シーリグ著〜著者のティナ・シーリグ氏は、マイケル・サンデル教授で有名なNHK「白熱教室」海外版の第2弾の特別講義をしていたので、ご存じの方も多いのでは…。この本、著者の息子ジョシュが16歳の誕生日を迎えた際、「大学進学まであと2年しかない。自分自身が実家を出たとき、社会に出たときに知っていればよかったと思うことを伝えておきたい」と思ったことをリスト化した内容をベースに書いたとのこと。著書についての大雑把な印象は、ジョン・D・クランボルツ博士の計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)の著者の実体験版という感じでしょうか…。自身の体験に則り、自身の言葉で語ってくれているので、決してクランボルツ博士の二番煎じなんて感じはしないけれど…。そんな中、特に記憶に留めておきたいのは、第10章:新しい目で世界を見つめてみよう。種明かしをすると、これまでの章のタイトルはすべて、「あなた自身に許可を与える」としてもよかったのです。わたしが伝えたかったのは、常識を疑う許可、世の中を新鮮な目で見る許可、実験する許可、失敗する許可、自分自身で進路を描く許可、そして自分自身の限界を試す許可を、あなた自身に与えてください、ということなのですから。じつは、これこそ、わたしが20歳のとき、あるいは30、40のときに知っておきたかったことであり、50歳のいまも、たえず思い出さなくてはいけないことなのです。多くの人は(もちろん、私も…)、意識しないままに他者のつくったルールを破らないことを第一義に物事の判断をしてしまう傾向がある様に思う。自分の人生の主人公は自分自身。この本を読んで、『自分自身に許可を与える』といういたってシンプルで当たり前のコトが、如何に大切かということを再認識させられた。スティーブ・ジョブズの2005年のスタンフォード大学卒業式でのスピーチ(伝説のスピーチ)なんかが事例として取り上げられているのも、ちょっぴりうれしい本でした。
2014.05.05
コメント(0)
-

出産後も9割就労希望
〜女性新入社員〜出所:2014年4月28日 静岡新聞 朝刊 ----------------------------------------------------日本能率協会が、協会の新入社員向けセミナーや研修に参加した社員に行った調査によると「女性社員の89.8%が出産後も仕事を続けたいと考えていることがわかった」という記事だ。取締役を務めている会社の新卒採用面接で、「大きなライフイベント(結婚や出産)と仕事のバランスをどう考えている?」と質問した際に、ほとんどの女子学生が「出産後も働きたい」と答えてくれるのとも合致する内容だ。9割弱の女性が、出産後も仕事を続ける意志を持っていてくれるのであれば、危惧されている「少子高齢化による労働力不足解消の大きな助けになるかもしれない!?」などと期待が膨らんでしまう。とはいえ、「出産後も仕事を続けたい」という答えの中には、「自己実現したい」「社会貢献したい」から「そもそも配偶者の所得だけで生活が成り立つハズないじゃん」などという現実的な答えまで、いろんな要素が含まれているハズ。と考えると、昨今、女性が仕事を続けること自体はむしろ必然なのかもしれない。そんな中、平成25年度静岡市女性の労働実態調査によると、働く女性の中で「管理職にないたい」人は7%、「管理職になりたい」と思わないという人が85%という結果が出た。全国でも「管理職になりたい」人は10%と静岡市とほぼ同様の結果を示している(出所:労働政策・研修機構)。別に「管理職になりたい」と思って欲しいわけではないけれど、「昇進意欲は、仕事への熱意がある可能性が高そう?」なんて感じもするし…。わたし的には、労働人口が増えるだけじゃなく「付加価値が高い仕事をしたい!!」という人が増えることを希望しちゃいます。高い付加価値の仕事は、組織にとっても個人にとっても利益をもたらすし、何より心地いいですからね〜!!
2014.04.29
コメント(0)
-

起業希望者が半減
〜中小企業白書〜政府は25日、2014年版の中小企業白書を閣議決定した。起業を希望する人が12年は約84万人で、1997年(約167万人)から半減したと指摘。「起業大国」の実現には、事業を始めた当初に税制優遇を受けられる制度の導入に加え、起業家の体験談を小学生の段階から聞く機会を設けるなど教育面の対策も必要だと指摘した。(中略)開業率が低い理由を起業に関心がある人に聞いた調査では「生活が不安定になる」「失敗した際の安全網が整備されていない」などと生活面の不安を指摘する回答が多かった。(中略)また、起業はリスクが高い印象が強いが、自宅で少ない費用により事業を始める場合も多いと説明。起業後の収入を安定させるため、本業を続けながら新事業を副業として手がける方法も選択肢として示した。出所:2014年4月26日 静岡新聞 朝刊 ---------------------------------------------------------------------1997年との比較で半減か〜?!まぁ当時、バブル経済がはじけて以降「たった一度の人生、会社に依存するんじゃなく自分らしい生き方をするんだ!」なんていって起業するサラリーマンも多かったし…まぁ、起業を推進するんだったら、小学生の頃から起業家の話を聞くのは効果があるかもしれないね。そんな中、起業に関心がある人の「生活が不安定になる」「安全網の整備が必要なのでは…」という回答もよくわかる。私も会社をはじめて1〜2年は結構しんどかった。だからというわけじゃないけれど、本気で起業したい人は応援したいと思うものの、起業を勧めることはしないな〜。だって、覚悟が必要だし、たいへんだから…とはいえ、サラリーマンを続けたとしてもリスクがないわけじゃない。一番怖いのは、変化を臨まない姿勢が最も高リスクだということを認識していないこと。もし、政府が起業を推進するのであれば、先ずは、制度設計をする人自身が起業してみるっていうのはどうだろう?政策は、実体をよく知る人が作成するのが一番!?「最も起業に縁遠い人が、政策を作成している」なんていうことにならないためにも…、ネ!?
2014.04.26
コメント(0)
-

大卒求人数25%増
〜15年卒 6年ぶり、中小要因〜リクルートワークス研究所が24日発表した2015年卒業予定者の大学生・大学院生の求人動向調査によると、民間企業の求人数は前年比25.6%増の68万2500人で、6年ぶりに増加した。景気回復で中小企業の求人が急増したことが要因。就職希望者1人当たりの求人件数を表す求人倍率も1.61倍と、0.33ポイントの大幅改善となった。求人を規模別にみると、300人未満の中小企業で44.5%増の37万9200人となる一方、5千人以上の企業は4万5800人と5.0%にとどまった。豊田義博主幹研究員は「大手志望者の就職は依然として厳しく、学生と中小企業のマッチングが課題だ」と指摘した。(後略)2014年4月25日 静岡新聞 朝刊 ---------------------------------------------------------------------景気回復で民間企業の求人数が、前年比25.6%増!ということで、企業の採用活動も例年以上に早期化を進めている様だ。実際、私が取締役を務める会社の採用面接で学生の話を聴く中でも、内定獲得のタイミングは例年より半月以上早まっているんじゃないかと感じる。そんな中、私が心配するのは現時点で内定獲得出来ていない学生たちのこと。確かに、求人倍率のUPにより企業の採用競争がエスカレートし一部の学生が例年より早いタイミングで内定獲得しているものの、それが新卒採用マーケット全体の動向を表してるわけじゃない。実際、多くの企業の採用活動はこれからが本番なんだから…というわけで、お世話になっている大学で“就活なんでも相談会(就活巻き返し講座)”を実施させていただいた。本日の参加者は6名。「就活マニュアルを参考に書類を書くのだが、書類選考が通らない」「面接で自分らしさが出せずに悩んでいる」等々、就活の第一ラウンドで躓いて、果たして今のやり方のまま前に進んでいいものか?との悩みを抱える学生たちだ。講座では、自己分析・応募書類作成・面接等、自分自身の今までの就活を振り返り、良かったコト・直すべきコトを話し合ってもらうと共に、私自身が採用担当者の視点で応募する学生たちに対し、どんなことを感じるかをフィードバックさせていただいた。講座開始時には、不安そうな表情をしていた学生たちだが、終了時には「採用する側の視点が理解できた。頑張ります!」と明るくコメントしてくれたことがとても嬉しかった。昨今の就活は、就活産業のエスカレートやマスメディアからの情報の氾濫等々、雑音(?)が多すぎる。学生たちには、それらの雑音に翻弄されることなく、「企業や社会がどんな人材を求めているのか?」「自分はどんな職業人生を歩みたいのか?」「企業や社会がどんな人材を求めているのか?」を考えて活動して欲しいと切に願う。
2014.04.25
コメント(0)
-

大学生がやって来たYah Yah Yah!?【続編】
~プレゼンテーションしてくれました~先日、ブログでも紹介させていただいた常葉大学「職業・企業研究」。実地調査の終了後、12月10日・17日に8チームの学生たちがプレゼンテーションしてくれました(1月7日にあと3チーム)。視察させていただいた企業は、旅行業・スーパーマーケット・美術館・不動産業・パン屋さん等、バラエティーに富んでいましたし、「プレゼンテーション終了後、内容に関するクイズを出し、正解者にはプレゼントが当たる!」などという奇抜なアイデアを取り入れてくれるチームがあったりと、楽しいモノになりました。※ご協力いただいた企業のみなさまには、この場を借りて、御礼申し上げます。そんな中、「今から、授業でのプレゼンテーションが楽しみだ!」と書かせていただいた、『あのチーム』がどんなプレゼンテーションをしてくれたのかを紹介させていただきます。プレゼンテーションの構成は…1.SOLとは?2.一体どんな仕事をしているの?3.取材について4.どんな人々が働いているの?5.会社はどんな人を求めている?6.いい会社とは?7.これからのSOLの豪華(?)7本立て!仕事内容については、「お客様の求める情報を載せられるか、否かは、すべて営業の足にかかっている」「現場での営業経験は、自分が上司になった際、部下にアドバイスが出来て、とても役に立つ」…。どんな人が働いているかについては、「文・理さまざまで、今の仕事に直結するような勉強はしてこなかった人たちばかり。裏を返せば、『これがやりたい!』と思うことがあればいくらでも就職の可能性は広がるのでは」…。期待人材像については、「仕事では、当たり前だけど責任が伴う。会議などで、自分が思ったことを発言しない人は、ハッキリ言って仕事をしていない人。自分が思ったことを発言することが大切!」等々、視察で聴いた話を自分たちの言葉で語ってくれたのが嬉しいですね。その中でも、私が最も感銘を受けたのは、「いい会社」について。学生たちは、「仕事がたいへんでも周りの支えがあり、自分が成長出来て、社員の頑張りにより成長できる会社であれば、きっとそこはいい会社なんだと思います。」と結んでくれました。対応してくれたS課長からは、「学生たちが、自分が語った以上に会社のこと、仕事のことを深く理解してくれている様子が伝わり、とても驚きました。」というコメントを寄せていただきました。いや~、本当にいいプレゼンテーションでした。充実した視察にするための必要条件は2つ。1.学生たちが、本当に欲しい情報を聴き出したいと取り組むこと。2.企業が、学生に何を伝えることが大切なのかを理解し、受け手の心に響く言葉で伝えてくれること。なんだと、あらためて感じました。※ご協力いただいた企業のみなさまには、この場を借りて、御礼申し上げます。
2013.12.20
コメント(0)
-
大学生がやって来たYah Yah Yah!?
~ 職業理解を深めるために ~一昨日、取締役を務めさせていただいているしずおかオンラインに、スーツ姿の6名の大学2年生がやって来た。彼らの訪問の目的は、「職業・企業研究」の授業の一環で実施する実地調査。数年後には就職活動を経て職業人生のスタートを切る学生が、直接、企業にアポイントを取って訪問・面談することで、職業理解を深めることを目的としたものだ。実は、彼らは私が講師を務めている常葉大学の教え子たち(狭いエリアで、複数の草鞋を履いてシゴトをしていると、この様なニアミスは結構あるのです…汗)。講師の私が、窓口となり説明するんじゃ「授業と何ら変わらない?!」ということで、管理部門のS課長に対応をお任せすることに…。面談の予定時間は60分。任せたとはいうものの、学生のことが気にならないわけもなく、終了予定時間の15分ほど前に面談会場となっている会議室を覗きに行ってみた。S課長からのひととおりの説明は終了しており、学生から「学校で勉強したことで活かせていることは?」「社内で思うように仕事を進めるためのポイントは?」等々の自分目線での活発な質問が飛び交っていた。結果、面談時間は60分の予定が90分と大幅延長に…。最後に学生たちがどんな感想を持ったのかを聞きたくて、私から「感想を聞かせて?」とのリクエストをしたところ、「勉強だけでなく、サークル活動やアルバイト等も含む学生生活を充実させることが大事だと感じた!」「どんな会社に入るのか?ばかりが不安だったが、縁あって入社した会社で頑張ればいいと思った!」等のコメントがもらえた。このあと、12月下旬~年明け1月初旬にかけ、彼らを含む11チームの学生が、訪問した企業の視察内容を整理してプレゼンテーションしてくれる予定だ。彼らには、「形式には拘らなくていいから、今日感じたことを他の学生たちと共有できる様なカタチにしてくれることを期待しているよ!」と伝えて終了となった。学生たちに素晴らしい気付きを与えてくれたS課長に感謝するとともに、学生たちの面談が表面上の会社研究だけに終わらなかったことが、私をうれしい気持ちにさせてくれた企業訪問だった。う~ん。今から、授業でのプレゼンテーションが楽しみだ!!
2013.11.30
コメント(0)
-

LEAN IN(リーン・イン)
~シェリル・サンドバーグ 著~FaceBookの最高執行責任者 シェリル・サンドバーグ氏の著書。サブタイトルの「女性、仕事、リーダーへの意欲」等の記述を見ると、ジェンダー論なんかが綴られているんじゃないかと思う人もいるかもしれないけれど…。氏の主張は、女性が社会で力を発揮しようとする際に『社会に築かれた女性の外の障壁』があることは認識しつつも、もっと大切なことは「『自分の内なる障壁』を打破することだ!」というものだ。ここで言う『内なる障壁』とは、自信のなさから、一歩踏み出すべき時に引いてしまうこと。家事や育児や夫の世話のために多くの時間を確保しようとして、自分に対する期待を低めに設定してしまう傾向のことを指している。多くの女性が、思い切って二歩も三歩も踏み出すことによって、現在の慣習も変化し、多くの人に道が拓けるだろうと言っている。私自身は、性別に限らず「リスクをとること、成長に賭けること、チャレンジすることは素晴らしい!」と考えているし、私の知人には、そんな女性が沢山いるので、氏の主張はすっごく腑に落ちてしまう。とはいえ、どのへんが腑に落ちたのかを上手く伝えられる自信は無いし、たぶん「上手く伝わっていないだろうな~」と思う。ということで、「こんな書評じゃ、どんな本なのか全くわからないじゃないか?!」と思う人にこそ、読んでもらいたい一冊でした。
2013.10.12
コメント(0)
-

『若手社員 職場定着セミナー』スタートしました!
本日は、先般ご案内させていただいた『若手社員 職場定着セミナー』の講師として浜松に行って参りました。参加いただいた若手社員は、約40名。県内3ケ所で実施するセミナーの初日であること、昨年の内容を、一部リニューアル(?)したこともあり、若干緊張気味(?)でのセミナー開始となりました。内容は、二部で構成。第一部では、会社経験の浅い参加者が、自社内の視点だけでモノを見るのではなく、社会全体を俯瞰して欲しいとの想いから、「日本の労働市場がどう変化しているのか?」「若者たちがどんな意識で仕事に向かい合っているか?」をデータ等で示しながらお話しました。第二部では、前述した社会環境変化の中で、自分自身が「何をすべきか?」「何が出来るか?」「何をやりたいか?」を考えた上で、自分にとって有意義な人生を送るために「これから意識すべきこと」「身につけるべきこと」等について、グループで議論してもらいました。いろいろな受講者がいる中で、すべての人に私の想いが伝わるとは思ってもいませんが、修了後のアンケートを確認する中、「ただ漠然と日々の仕事をこなすのはもったいない」「仕事について、今までと違った角度から考えることが出来た」等々のコメントも見られ、チョッピリ責任を果たせたかな?と「ホッ…」としております。三島・静岡での残り2日のセミナーも張り切って参ります!!
2013.09.12
コメント(0)
-

創造するミドル
~金井 壽宏 米倉誠一郎 沼上幹~本書は、第1部「創造的なミドルのインタビュー」と第2部「3名の著者それぞれの提言」で構成されている。第1部は、企業に所属しながらも、自分らしく生き生きと仕事を創造している11人のインタビューとなっており、それなりに魅力的は感じるのだけれど…。1994年初版ということで、「事例が少々古いかな~」と感じた。第2部の3名の著者のミドル論は、各々の個性が出ており、すっごく楽しめる。米倉先生は、大企業では独立心や企業者精神は発揮できないと思い込んでいる人に、「そんなこと無いよ!」との直接的なメッセージが綴られているし、金井先生は、キャリアアンカーとキャリアエンジンが自身のキャリアを醸成する際の両輪であることをクルマにたとえて、わかりやすく説明してくれている。米倉先生・金井先生だったら、「きっとこんな風に言ってくれるんだろうな~!」という私の期待通りの提言で気持ちいい。そんな中、特に印象に残ったのは、沼上先生の、以下の2つの提言。第1は、会社も社会も学校も非決定論的な世界(どこかに<答え>が隠されていたり、誰かが<答え>を持っているわけではない)であるはずなのに、決定論的世界観が蔓延している。自らの眼前に非決定論的な世界を切り拓けるように「概念的なスキルを身につけよう!」という提言。第2は、企業の研修に関わる者へのメッセージで、「個の自立性獲得」や「企業の活性化」は、【社員の意識転換】によって行うものではなく、【社員の知識開発】によって行う必要があるという提言。「自立が大切!」と何百回も唱えるよりも、知識開発により足りない部分を客観視する方が、よほど現実的だと、何度も頷いてしまった。沼上先生の著書を読むのが、はじめてだったこともあるのだろうが、強い感銘を受けた。『創造するミドル』というタイトルから、ミドルに向けた書籍の様に感じ取られてしまうかも知れないが、ミドルはもちろん、企業で働き始めた若者や就活をはじめる学生にもオススメの一冊だ。
2013.09.10
コメント(0)
-

職務経歴書、作成指導…?【後編】
~10年ぶりに求職者にお会いしました~1週間後、市内のとある喫茶店。Yさんとお会いするのは10年ぶり、既に40代後半だが、人なつっこい印象はまったく変わらず、すぐにご本人だとわかった。簡単な近況報告の後、聴いてみたかった質問をぶつけてみた。ポイントは、現職の満足度と今後のキャリアの方向性だ。先般の電話では、スカウトを受けている会社は、首都圏の外資系企業とのこと。地方都市とはいえ、上場企業の管理職(海外営業)、ご家族(妻、高校生・中学生のご子息)のことも踏まえた上で、Yさんがどんなキャリアを指向しているのかをお聴きしたかったのだ。Yさんからは、「現職にはやり甲斐も感じているし、家族のこともあるので、最初にスカウトの誘いを受けた際は、断った。提案されている会社の仕事は、自身のセールスポイントと若干ずれているし…」「ただ、もっと成長したいし、この機会に職務経歴の棚卸しをしてみようと思った」とのお答えが返ってきた。「う~ん、当にキャリアカウンセリングのお手本の様な事例だ…」などと思いつつ、今日は(「こんな方向性は危険かも…」なんとか修正してあげられないか等々…)いらん心配しながら、話を聴く必要はなさそうだと、心の中でホッとした。そんな中、Yさんからは「僕の職務経歴書、どうですか…?」という質問が…。先日、お電話いただいた際、「職務経歴書の作成指導はしないが、書かれた書類の感想だったらお話し出来ますよ」とお伝えしたので、事前に今回書かれた書類と以前私が指導した職務経歴書(ずっと取っておいてくれていたことは、嬉しかった)をメールで送っていただいていたのだ。10年間、頑張ってきただけにYさんの職務経歴書には、売上げや開拓してきた顧客、他多くの実績が並んでいた。ただ、何故、実績を上げることが出来たのかがさっぱりわからない。そのことを質問すると…。Yさんは、「う~ん、僕にもわからない。職務経歴書に書けるような、特別な技術や資格があるわけじゃないし…」とおっしゃる。「でも、実績はあげてますよね?」と更に質問すると…。「いや~、僕はついているんですよ!」とおっしゃる。世界各国での取引なので、政治・経済、生活習慣や風土は千差万別、だまされる日本人も少なくないのだけれど、自分の場合は、顧客が知り合いを紹介してくれたりするので、ビジネスでの失敗はほとんど無いと言う。また、ある国で、詐欺にあったのだが、その際も友人が助けてくれたのだそうだ。う~ん、話を聴けば、確かについているのだけど…。世の中には、幸運を引き寄せるのが上手い人とそうでない人がいる。そして、幸運を引き寄せるのが上手い人はそれなりのプロセスを踏んでいるものだ。Yさんには、「何故、幸運を引き寄せ続けられるのか?」を自分なりに整理して加筆すればいいと提案し、クランボルツ博士の『その幸運は偶然ではないんです!』を紹介し、雑談終了。こんな絵に描いたような相談は、滅多にない。ただ、少しずつだけど、「自分自身のキャリアは自分で創っていくものだ!」と考える人が増えてきていると感じられたことがうれしい1時間だった。※2013ニュル24h クラス2位LFA(本文とは無関係です)
2013.09.03
コメント(0)
-

職務経歴書、作成指導…?【前編】
~10年ぶりに求職者にお会いしました~先日、「以前、職務経歴書作成指導でお世話になったYですが…」と、わたし宛に一本の電話が入った。一瞬、「誰なんだろう?」と思ったが、すぐに10年ほど前に職務経歴書の作成指導をさせていただき、結果、再就職を成就したYさんだとわかった。転職先は、現在では上場しYさんは、部長の役割についているという。電話の要件は、外資系の人材紹介会社からスカウトの話が持ちかけられており、一度は断ったモノの一度、話を聞いてみようと思っている。ついては、先方に提出する職務経歴書の指導をお願いしたいということだった。とはいえ、当社は、起業から3年ほどは、職業紹介事業・職務経歴書作成指導に力を入れ、それなりの実績をあげていたのだが、講師などの仕事が忙しくなってきたこともあって、現在はYさんが期待されるサービスは提供していない。職業紹介の許認可も5年ほど前に返納してしまった。そのことを伝えると、Yさんは「私の職務経歴書が、指導を受けて、見違えるようになった。魔法にかかった様だったことを昨日のことの様に覚えている!!」とおっしゃる。さすが、営業マン、話が上手い。「そんなワケないだろう?!」と思いつつも、悪い気はしない。30代後半から10年を経た現在、Yさんが、どの様に変身しているのかにも少し興味があったし…。ということで、ビジネスでお会いするのではなく、友人として相談事に耳を傾けるということを条件に、1週間後、お会いすることを約束した。(続く)※ツインリンクもてぎ NSXペースカー(本文とは無関係です)
2013.08.31
コメント(0)
-

「そこそこ派」で働きたい
~独身女性、仕事を続けるなら… 出世より長続きを選ぶ ~官民挙げて女性活用の重要性が叫ばれ始めた。若い女性の間でも「結婚して働き続けるのは当たり前」という意識は確実に広がっている。ただ、働くとしても総合職より一般職、バリバリ働く「バリキャリ」ではなく、私生活も大切にしたい「ゆるキャリ」志向も根強い。そんな「そこそこ派」の本音に迫った。「バリバリ働いて出産後も育休明けに職場復帰する。就活を始めた頃はそう考えていた」という京都女子大学4年生のA子さん(22)。だが、狙っていた金融系のエリア総合職はすべてダメ。小さくても安定した企業の事務職を探すようになって考えが変わった。「子どもができたら専業主婦になり、余裕ができたらパートでも構わないから仕事に就ければいい」。大手企業でなければ、育児休業制度などを利用しにくいのではないかと思うからだ。結婚しても働き続けるだろう、と考える女性は増えている。電通が独身女性を対象にした2012年の意識調査では、理想として「結婚して専業主婦になる」「働き続ける」と答えた女性はそれぞれ3割となった。だが、現実には「結婚して専業主婦になる」と思う人はわずか9%にとどまる。一方「働き続ける」と考える人は48%いて、10年の調査より20ポイントも跳ね上がった。(中略)社会人3年目のB子さん(27)は連日の猛暑の中、ヘルメットに長袖・ズボンの作業着姿でビルの建築現場に立つ。東京の女子大から国立大学の大学院に進み、街づくりの研究をした。就活では苦戦したが大手ゼネコンに総合職で入社し、1年目から現場監督を務めた。朝は7時半から現場に出て午後7時~9時半まで働き、家に帰ればぐったり。仕事にやりがいはあるが「こういう生活がずっと続くのはこたえる」。結婚したら本社の設計部門で働きたいと思う。両立が困難になれば一般職に移る道もある。昇進よりも欲しいのは1級建築士の資格だ。「結婚相手の転勤などで会社を辞めざるを得なくなっても、次の仕事を得やすいから」と働き続けるための方策を考える。政府の後押しで経済界は女性総合職の採用増を進めるが、女性たちの間では尻込みする人も少なくない。(中略)「競争」より「協調」を重んじるゆとり世代。「出産後すぐに職場復帰し、ファーストクラスで海外出張」といったバリキャリ出世物語など彼女たちの心には響かない。「自分にちょうどいい働き方のバリエーションを求めている」(電通・西井さん)。そんな女性たちがいるのも確かだ。出所:8月26日 日本経済新聞 夕刊 ---------------------------------------------------------------------昨今、官民挙げて女性活用の重要性が叫ばれ、経済界では「女性総合職の採用増」「女性管理職登用の数値目標」なんかを掲げているけれど…実際、新卒採用の場面でも「結婚しても働き続けたい」という女子大生がほとんどだけど、「どんな働き方をしたい?」と質問すると、口ごもってしまう学生は少なくない。まぁ、企業の立場からすれば「会社の牽引役として、出産後もバリバリ働きたい!」などと言ってくれる学生に高いポイントを付けたくなっちゃうわけだけど、学生たちに言わせれば「企業のコトなんか信用できません。将来のコトをリアルにイメージしたら、夢みたいなコトばかり言っていてもしょうがないでしょ?!」ってことになっちゃうんでしょう。「限られた収入でやりくりし、家計を守らなくては…」という学生たちのスタンスは、“ゆとり世代”という呼称のイメージとは、大きく乖離している。「あなたの将来は、あなた自身の努力で切り拓いていくものなんだよ!」などと、自信を持って言い切れない自分が口惜しい。
2013.08.28
コメント(0)
-

転職支援35歳以上に的
~即戦力、企業間で橋渡し~インテリジェンスやパソナグループなど人材大手が相次ぎ、35歳以上の「ミドル層」を対象にした転職支援サービスを始める。多くの人材を抱えながら活用し切れていない企業と、即戦力を求める成長企業の間を橋渡しする。安倍政権も成熟産業から成長産業への労働移動を促す方針で、ミドル層の転職需要を取り込む動きが広がりそうだ。(中略)インテリジェンス、パソナはともに経済産業省から事業を受託。人材の成長産業への移動を促す「人活支援サービス」として事業化する。初年度は参加企業から費用を徴収しないが、来年度以降は手数料を得て事業展開する見通しだ。(中略)中途採用の雇用状況はリーマン・ショック前の水準を回復。ただ、当時と傾向は変わっており「07~08年は25~35歳の層が大半だったが、現在は45歳以上の層まで各世代にまんべんなく広がっている」(インテリジェンス)のが特徴だ。出所:8月26日 日本経済新聞 朝刊 ---------------------------------------------------------------------なになに、ミドル層を対象とした転職支援に的だって…?!転職市場では、俗に言う「35歳転職限界説」なるものがあり、それを気にする求職者を見てきた私にとっても気になる記事だ。まぁ、私自身は「採用は年齢だけで決まるわけじゃない」と思っているし、今までも多くのミドル層の転職をサポートさせていただいてきたので、「35歳転職限界説」については、否定派なのだが…。とはいえ、ミドル層の就職相談会やセミナーで求職者と接する機会に、多くの方が「たいした準備もしないまま、年齢を言い訳にミドル層の転職の難しさをアピール(?)する」のを聞かされると、「ここから修正していかないと、採用されないだろうな~」と感じることも少なくない。ミドル層については、若年者の様な「ポテンシャル採用」は行われないので、採用側の「ニーズを察知すること」が必要条件になるわけで…。いずれにしても、インテリジェンスやパソナといった民間の人材ビジネス会社が、ミドル層に的を絞ったというのは、よいことだと思う。気になることと言えば、当該事業が経済産業省の委託事業ということ。これって、公益財団法人 産業雇用安定センターのサービスとどう違うんだろう…?何はともあれ、スタートは、委託事業だったとしても、コレをフックにビジネス化の流れを創ってくれることを期待しています。
2013.08.27
コメント(0)
-

『若手社員職場定着セミナーのお知らせ』です
~経営者・人事担当者の皆様へ~本日は、静岡県内3か所で9月中旬に開催される『若手社員職場定着セミナー』のお知らせです。小職が講師を務めさせていただきます。昨今、七五三転職に代表される様に、若者の早期離職が社会問題化しています。早期離職は、会社にとっての大きな損失であるのはもちろんのこと、若手社員自身にとっても社会人としての成長機会が失われるということでたいへんな課題です。とはいえ、若手社員が職場定着をすれば問題解決するといった類の課題では無いのも事実。タイトルは、『若手社員職場定着』とさせていただきましたが、主題は『個人のキャリアビジョン構築と自律』です。経営者・人事担当者のみなさまにおきましては、セミナーの趣旨をご理解いただき、お申込みいただければ幸いです。↓詳しくは、コチラ【お申込・お問合せ】静岡県中小企業団体中央会 労働対策課 TEL054-254-1151 FAX054-255-0673
2013.08.26
コメント(0)
-

派遣継続 選択に幅
~厚労省改革案、制度分かりやすく 正社員の雇用維持 課題~労働者派遣制度の見直しを議論していた厚生労働省の研究会は20日、派遣労働者が仕事を続ける選択肢を増やす改革案を盛り込んだ報告書を決定した。月末から労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で制度を設計し、来年の通常国会に改正労働者派遣法案を提出する。わかりづらい規制をなくし、人材派遣会社・派遣先企業・労働者の3者にとってわかりやすい制度を目指す。専門26業務を撤廃、職種の格差解消今回の見直しではまず派遣期間に上限のない「専門26業務」の区分を撤廃する。現在、26業務以外の派遣社員は最長3年で派遣期間が打ち切りになるが、26業務は例外として期間制限がない。26業務には通訳や秘書のほか、ファイリングや取引文書作成などが指定されている。かつては専門性の高い業務を指定したが、時代の流れで専門性が失われたものがあるほか、26業務に該当するかどうかがわかりづらいという問題があった。特に近年は、2010年2月に当時の民主党政権が作った「専門26業務派遣適正化プラン」による混乱が広がっていた。26業務と認める範囲を従来より厳格化する内容で、実際26業務で働く派遣労働者の数は09年から10年の1年間に、90万人から75万人へ激減した。派遣業界はこのプランの撤廃を強く求めていたが、「専門26業務」という概念そのものが廃止されることで問題は解消される。派遣の規制を強化した民主党政権時代からの政策転換と言える(後略)。出所:8月21日 日本経済新聞 朝刊 ----------------------------------------------------------------------労働者派遣法の改革案に関する記事ですね。今回案の「専門26業務」という概念そのものの廃止により、労働者派遣法の“運用”という観点では非常にわかりやすくはなるだろうけれど、ここでは“運用”の問題ではなく“政策転換”ということに的を絞って考えてみたい。みなさん、日本の人材派遣の黎明期、先頭を走っていた会社のひとつに株式会社テンポラリーセンターがあるのをご存じだろうか?現、株式会社パソナグループの南部 靖之氏が興した会社だ。テンポラリー(temporary)とは、「一時の」とか「臨時の」とかを意味する言葉で、1986年7月の労働者派遣法施行時の派遣社員の立場は、あくまで「正規社員(permanent)の業務を一時的に補う人」であったことがよくわかる。で、その際、「誰でも出来る仕事だったら、アルバイトさんやパートさんで代替えできるハズだから、派遣が出来る専門業種を特定しよう!」ということで専門業務を特定することになったわけ。そんな中、時代の趨勢と共に労働者派遣法も(主には緩和の方向で)変化を続けてきたのだけど、民主党政権時代に、緩和の方向に急ブレーキがかかり大きな混乱が生じたということだ。前政権の労働政策のベースは、「正規社員至上主義?」。日本国民みんなが身分保障の強い正規社員になれれば(若しくは、アルバイトの最低時給が1,000円になれば…?)、幸せになれるハズというもの(私がそう感じたということで、ニュアンスが違っていたらごめんなさい)。まぁ、それで企業が利益を上げ続けられるのであれば、何の問題も無いのだけれど…。それと比較して今回の「『専門26業務』という概念を撤廃」は、人材派遣をテンポラリーワーク(一時的な仕事)と位置づけないという方向性(言い回しが微妙…?)なのだと思う。当に私が、“運用”の問題ではなく“政策転換”として考える必要があると思った理由だ。私自身は、“個人の働き方や生き方の選択肢が増えていくこと”は、社会の要請だと思っているので、今回の改革案の方向性については賛成だ。ただし、人材派遣会社は、江戸時代の人身売買業(口入屋)と揶揄されてきた歴史があるのも事実。派遣元である人材派遣会社、派遣先である企業のモラル維持が必要条件であるのはもちろんのこと、派遣社員の自立が求められることも知っておく必要があるだろう。派遣社員に限らず、どんな就業形態で働く場合でも、仕事を選ぶ際は「自分の意志で決める!」という自覚が大切だ。
2013.08.26
コメント(0)
-

スクールカースト
~鈴木翔 著~スクールカーストとは、主に中学・高等学校のクラス内で発生するヒエラルキーのことで、いじめや不登校の原因になるとも言われてきた。とはいえ、「社会問題化したこともなく、曖昧でよくわからないので、検証してみよう」という内容。概要は、こんな感じ…。サンプル(大学生:10名、教師:4名+α)は少ないものの、生徒・教員への聞き取りからは、生徒・教員共にスクールカーストの存在を認めており、現象についての認識も一致している。ただ、スクールカーストについての受け取り方については、生徒が「スクールカーストは、『権力』で出来ており、自分の力で変えるコトは難しい」と考えているのに対し、今回の聞き取りに応じた教師は「スクールカーストは、『能力』を軸としたヒエラルキーだ」と考えており、大きな違いがある。ここで教師の言う『能力』とは、「生きる力」や「コミュニケーション能力」「リーダー性」のこと。教師は、スクールカーストの上層にいる生徒は「悪ガキ」であろうが「ギャル」であろうが、社会に出てもまあまあうまくいくだろうが、スクールカーストの下層にいる人は社会に出てからちゃんと就職できるか不安なのだという。で、教師は「これから社会に出て行く生徒は、自分の『能力』の足りない部分を「努力」や「やる気」で改善していく必要がある」と考え、足りない部分を客観視できるスクールカーストを肯定的に捉えているというワケ(サンプルの教師数が+αとなっているのは、スクールカーストを問題視し、途中辞退の教員もいたため)。そんな中、アマゾンのレビュー等を見ると、「サンプルが少なすぎる」「学術的な根拠に欠ける」等のコメントも多いのも事実なのだけど…。スクールカーストの存在については、多くの人が感じてはいるモノの、今まではっきりした定義もなく学術的に検証しようという動きがなかったのも事実。中学・高等学校での体験は、キャリア形成に大きな影響を与えるワケで、それを「ささいなこと」として片付けるのではなく、「重要なトピック」として課題提案したことには「大きな意義があるんじゃないの…!?」と感じさせてくれる本でした。
2013.07.28
コメント(0)
-

法と経済で読みとく雇用の世界
~大内信哉・川口大司 著~法学者(労働法)の大内信哉 氏と経済学者の川口大司 氏の共著で、『雇用』を労働法と経済学の両方の視点から抉っている。なんて書くと、学者の書いた小難しい本の様に感じるかもしれないが…テーマは、採用内定取り消し・解雇規制・最低賃金・非正規社員・サービス残業・男女間格差・障害者雇用・服務規律違反・高齢者雇用・労働組合…等々。各章冒頭の導入部分に、当該テーマをモチーフにしたストーリー(これが、結構おもしろい)が書かれており、「う~ん、こんな話あるある!」とテーマに現実味を持たせ、労働法をより身近なモノに感じさせる。「労働者の賃金はいくらが妥当か?」「どれだけの労働者が企業に雇われるのか?」といった労働問題は、労働市場での取引があることを前提に語られるべきだと思っている私にとっては、「う~ん、なるほど…」と思える内容ばかりだった。また、法学者と経済学者の共著というのに、どこからどこまでをお二人のうち、どちらが書いているのかがわからないのも驚きだ。「学者ってすごいな~」と感心してしまった。こういうのを『学際的な書籍』とでも言うんだろうな~!?「エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10」第1位(『日本経済新聞』2012年12月30日付)に選ばれたというのも納得の一冊でした。お勧めです。
2013.07.20
コメント(0)
全729件 (729件中 1-50件目)
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 令和7年度宅建試験 合格発表 デー…
- (2025-11-26 23:43:33)
-
-
-
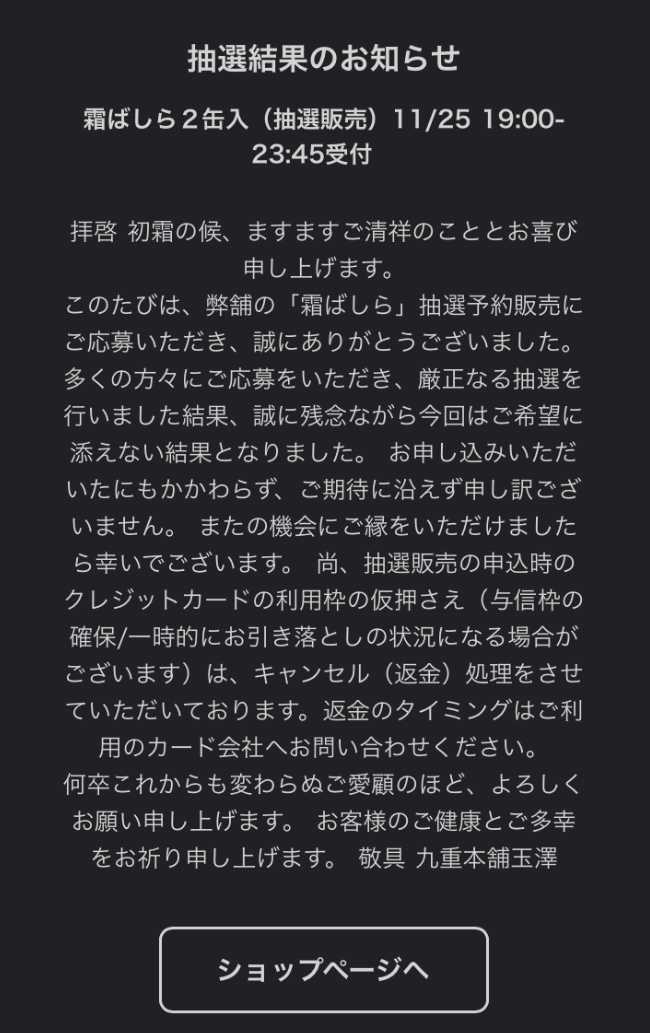
- 株式投資日記
- またまた上がってきた日経平均株価
- (2025-11-27 07:00:05)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- 「TOKYOタクシー」 ~11/26の日記~
- (2025-11-27 08:34:57)
-








