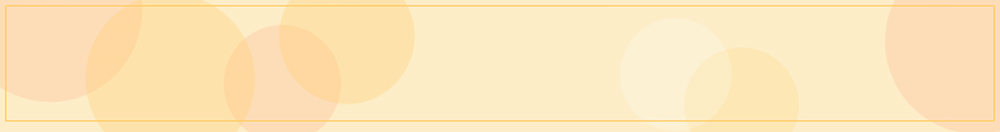全107件 (107件中 1-50件目)
-
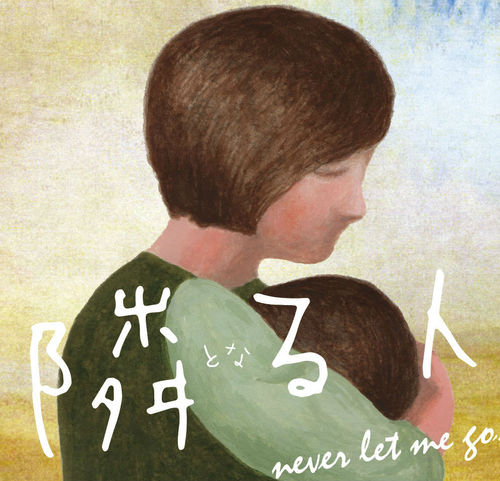
映画「隣る人」を見て
ごく当たり前に起きて、朝ごはんを食べて、学校に行って、帰ってきて宿題をして、遊んでから夕食を食べて、歯磨きをして、本を読んでもらって、布団に入り、眠る・・・・その繰り返しの毎日・・・ でも何かが違う・・自分の家族(血のつながった家族)が周りに誰もいない・・そのことを痛いほど、胸がちくちくするほど、感じ取っている子どもたち、の生活は当たり前ではとてもすまされないし、かといって特別なことにはしてほしくない、と心の中で訴えているかのようでもある。何か違うという感覚そのものはこれからもきっと消えはしないだろうし・・ついて回るものなんだろうと思う。だからこそ 自分にとって、大切な人、をもつことの意味。 それは親子であり、愛する人であり、何があっても自分のそばにいてくれる人の存在こそがその子の生きている証になっているのだろう。人として、今、自分がこの時間生きていることを、息をしていることを、喜び、悲しみ、怒り、淋しさを感じていることを何かに悩み、何かを考えていることを「知って、一緒に感じたり、考えたりする人」が、ここにいる・・ことを。そんな感想を持ったのですが・・実際に児童擁護施設で働く方々がこの映画を見られてどのような感想を持たれたのかをお聞きしたいと思いました。私が施設実習巡回で伺う児童擁護施設は様々です。規模の大きな施設で内容は少人数グループでの生活を送っているケース、グループホームで最初から一軒の家を借りて、少人数で過ごしているケース、などなどがある。それぞれに何かしら悩みがあったり、どうしたら子どもたちが生き生きと暮らせるか、と日々様々な出来事が起こる中で苦労なさっているのではないでしょうか? そう・・・耳を澄ませ、その方々の声を真摯に聞いていきたい・・と思った。
August 31, 2012
コメント(0)
-
保育は「感情労働」だと思いますか?
今、ゼミの4年生の卒論のテーマ「あなたは保育が感情労働であると思いますか?」このテーマは、自分に正直に向き合うこと・・から考えることだ。「保育者はいつも笑顔で、明るく元気で」といわれているが実際現場で、あるいは実習で「それって、できるの?」と思ったことありませんか?人間なら誰しも「喜怒哀楽」があって、自然なこと。生きているから、感情がある。そして、感情演技も要求される。あるときは大げさに喜び、あるときは深い悲しみを表現し、あるときは怒ることを演技して伝えることをしっかり伝えようとする・・・この感情演技も保育の専門性であるといえる?もともとこの学生は「保育園の保護者に対する保育士の感情」を取り上げて卒論研究にしたいと思ったことがきっかけである。それは保護者が長時間子どもと離れることを「かわいそう」という気持ちで保育していないか?それゆえ自分だったら子どもを小さいときから保育園には入れないなんて思って保育をしていないか?そんな気持ちで子どもを見ている保育士って多いのでは?という素朴な疑問から・・「感情労働」に行きついた。これは非常に興味深いテーマ・・学生のときからこのことをしっかり考えていることに敬服した。これから学生たちにアンケートをするので結果が楽しみである。
July 9, 2012
コメント(0)
-
「待機児」ではなく、保育需要児童数でしょ!
政府もマスコミもお願いしますよ「待機児、待機児」って、使わないで!なにかというと「待機児」と新聞の一面に出る・・ 大体、待機ってなんなの? 入れない=保育園がない、という意味でしょ。 潜在待機児って、それって際限のない話しで 恒久的な保育需要児童数でしょ。 保育園を作れといわれても お金がない(一般財源化)地方自治体にばかり、押し付け 政府は、「規制緩和しろ」「増やせ」と旗振りだけやってんじゃない~ 待機って、何さ!今の保育園に入れないのが悪い 、ことを攻め立ててる言葉にも聞こえてくるしだから、もっと入れろ式に、迫って、結局2割増しで入れちゃうわけ それどころか現実は行き場のない未認可の園にしわ寄せ的状況を作る そして、認可の基準をゆるくするべき論がまた復活 この議論が、政府の思惑通りかと思うほど・・循環し・・、保育とは、子どもの権利とは?を問うものではなくお金の出所の話しに言及し、羅針盤のない航路ですすんでいく。 これって、そもそも国がすべての責任をとる話しなのでは? 保育園の設置基準をさげるのではなく 子ども手当てで票稼ぎをするのでなく 子どもにとって居心地のよい、最適な環境で 保育内容も勿論充実した保育園を作る ことにもっとお金をかける話しに、国自体が、どうしてならないの?仕分け?でお金を捻出して、使うべきことに使うのなら、一番に保育でしょ。 それこそ、未来の日本の行く末に投資することでしょ。 ところが、「待機児」という言葉をいつまでも使うことで、 やめない限り本論を回避しているわけですね。
March 28, 2010
コメント(1)
-
映画「風のなかで」上映会をします!!
映画「風のなかで・・・ むしのいのち くさのいのち もののいのち」上映会 ~ 遊んで遊んで遊びたおす 遊ぶことは生きる知恵・・~ (シンガーソングライター大貫妙子さんのメッセージの抜粋です) 日時:2月9日午後6時半から9時まで 会場:セシオン杉並 視聴覚室 自主上映のために、限られた上映会しかないですので この機会にぜひ、ごらんになってください。 保育士、幼稚園教諭、教師、そして子どもにかかわる多くの大人に見て いただきたい映画です。 都内の杉並にある中瀬幼稚園、年長児クラスの2009年3月1ヶ月を カメラがとらえました。 「子どもたちの 輝く瞳を おいかけて 見えてきた、かけがいのない、いつもの暮 らし」 http://www.kazenonakade.com/ ホームページを、ぜひごらんくださいね。 参加申し込みは以下にお願いします。 メールで info@ikuji-hoiku.net に件名 上映会申し込み 氏名 と連絡先(電話又は携帯)・・・をお知らせ下さい。 参加費は当日会場で徴収します。 会場の案内はhttp://www.yoyaku.city.suginami.tokyo.jp/HTML/0030.htm 丸ノ内線東高円寺駅下車徒歩5分 青梅街道を荻窪方面に歩き、環7との交差点をそのまま直進し、 わたったら、環7の歩道を左に(南方面)100メートルくらいです。
February 1, 2010
コメント(0)
-
映画『風のなかで・・・」
今夜は杉並区にある中瀬幼稚園の自主制作の映画を学生を連れて 見に行った。http://www.kazenonakade.com/ 今年2月から3月の卒園児たちを追っかけた映画で 脚本の無いドラマでも、この映画の子どもたちはまるで 脚本でもあるかのように、主人公を演じてるように次から次へ 動き、喋り、画面狭しと演じ?きっている、本当にすごい! 舞台は幼稚園の日常の生活なのですが、全てがドラマ・・ 中瀬幼稚園という存在そのものが子どもの育つ場で 別世界そのもの、そこが宇宙船のように? ぽっかり浮かんでいるように感じた。 日常であって、日常でないような・・不思議な感覚。 ノスタルジックで・・ 昭和の時代にタイムマシーンに乗ってもどったような そしてなんとも一人ひとりが少し大人に見えた しっかりそこで、その場を生きている子どもだ。 泣いても、喜んでも、自信に溢れている顔 失敗を恐れない、躊躇しない顔 ケンカ、日常茶飯事? そして思いやりもぐちゃぐちゃの中で自然に起こる。 全て大人が教えることではない・・ことも 伝わってきて・・ 感動したというより、とにかく「ザ・子ども」に驚いた映画!
December 4, 2009
コメント(0)
-
なぜ、公立保育士の給与が問題になる?保育を知らない経済学者の記事
学習院大の鈴木亘氏は保育コスト分析を以前からなさっていますが、今回もダイヤモンド誌に掲載しています。http://blogs.yahoo.co.jp/kqsmr859/30365160.html 全くお門違いの議論で、世間の皆様に大きな誤解を生んでいる。公立保育士の給与体系は行政職級(公務員行政職の一番低い等級)である。それがなぜ悪い、つまり保育士ごときに公務員の給与をあげてはいけない、といわんばかりです。そもそも、公立直営の職員ですから、雇用形態は当然公務員でしょう。しかも庁舎内とは全く条件が違います、食堂で昼食をとれる、具合が悪ければ保健室で横になれる、何かの手続きは休み時間にすませる、そういう条件は全く無いですよ、保育士は。まずシフトで、拘束されていますから、休暇は簡単にとれません、毎日お弁当で、自費負担そのものですよ。社内食堂のある企業とも別ですし、休み時間にとにかく、外に出かけるのも時間がなく、郵便局すらなかなかいけそうにないです。職場を離れることは難しいのですよ、当然。私立保育士の給与が安く抑えられていることの方を大問題にすべき!本末転倒ですよ。保育を知らない学者に言われたくない!と思います。そもそも民営化がスタートする前には駒村氏、鈴木氏などの経済学の論文が盛んに出され、保育コスト分析の中で、ここに書かれていることは網羅されていました。法人の認可園の保育士の給与は低すぎることは事実、低くしないと経営が成り立たないほどの運営コストの方に問題ありですね。0歳児3対1ですから、人件費がかかって当たり前、それを5対16対にすれば当然費用は安くすみます。しかし、それで保育はできません。泣いてもほっとくしかないですね、ミルクを飲ませるのも抱っこではなく、顔の横に哺乳瓶を傾けるようにして一人で飲んでもらうしかありません。そんなことを経済学者は知る由もないでしょう。公立保育士は公務員として一番低いランクで庁内の公務員の方とは全く待遇が違います。公務員の平均年齢と公立保育所のコストの問題は比例していますので、そこを特化しているだけだと思っています。私立保育園は補助金がらみで、6・7年までのベースアップしか保障されていないのです。だから経営コストが安く済んでいるわけで、民営化論はそこから出ていると思ってもほぼ間違いないですよね。私立園の保育士の給与をもっと上げる運営コストで計上して報告していただきたいです。フランス、イタリアも公営の保育所が多いですよね。イタリアのビストイア市の例でも引用してほしいです。子ども手当て以上に保育行政にもっとお金をかけてください!そういう報告や論文をもっと社会に出してください、本当に!!なんなんだろう、日本という国は!!!!!
November 22, 2009
コメント(0)
-
待機児と言う言葉はもう、なくそう!!
待機児は解消できるのか!先日の某局の特報首都圏を見ました。現厚生労働大臣は年金問題には詳しいけれど、どうも保育園問題はこういっちゃなんですが、沖縄の基地移転の問題と一緒で長年あれも考え、これも調査して皆さんで揉んできた策をよく理解せず、いわば安易に口にして、雲行きを怪しくしてしまったすすめ方が全く手馴れていない・・今回のマニフェストで、待機児解消に学校の空き教室を利用し改造する策を出したようだが、テレビ局の調査では空き教室は23区ないにひとつもない中央区に作った空き教室改修の保育園の設置費用は2億円を越える・・10個作っただけで、もう子ども手当て相当の予算に達する。区には表に数字としてあらわれている待機児数よりもはるかに多い潜在的な待機児(申し込みには行ってはいないが、保育園に入れるのなら、働きたいと思っておる母親の子ども)がいることすら、把握していなかった・例が報告されていた。もう待機児対策なんて、やめてほしい。待機児って用語、おかしいですよ。子どもの育ちと家族や地域の問題のひとつ、子どもが育つ居場所の問題なのですよね。街づくり全体の、社会のありようを問われている問題なのですよね。都会であればこそ、数作ればそれでいいんですか?都会のようなところで育つ子どもの居場所はどうあればいいのでしょうか保育園でも幼稚園でも、自然を取り入れ、緑豊かな場所で、世代を超えた交流のできる場所が子どもには必要なのではないでしょうか?駅中や駅前などの荷物預かりのように考えられた園や若い保育者ばかりを集めて人件費を安くして、運営費を削っているような園(実際にあります)保育園を作るのなら、子どもの育つ場所としての大切な用件を満たせるような公的予算をきちんと補助し、保育料は乳児の場合は一定の金額たとえば経費の半分負担(人件費がかかるため、0歳児一人当たり10万以上になっている・・)は最低の保育料としてしっかり徴収し、生活保護所帯などは無償、幼児以上は無償化する方向でどうか・・。保育料はしっかり徴収するそのためには質を維持、向上させる園の保育にかかってくる。安かろう、悪かろうの作り方はこんりんざい、やめてほしい!!家庭的保育室を増やすためには、家庭的保育室を引き受ける所帯への優遇措置、特典をつける。収入を多くする。地域の保育園と連携する方式で最初から作る、家庭的保育者が休暇をとるときは保育園の一時保育を無料で利用できるようにする(保育料は市町村が出す)、小児科医師などとの連携、など地域の中での孤立しないような交流型の保育室を作る。とにかく、民主党はぎこちなさすぎる、総務省レベルの理解で決めては無知蒙昧としかいいようがない。厚労省がここまで現状を分析して、現場に近いスタンスで努力してきたことを真っ向から崩そうとしているような気がする。厚労省、頑張れ!!
November 1, 2009
コメント(0)
-
待機児と言う言葉はもう、なくそう!!
待機児は解消できるのか!先日の某局の特報首都圏を見ました。現厚生労働大臣は年金問題には詳しいけれど、どうも保育園問題はこういっちゃなんですが、沖縄の基地移転の問題と一緒で長年あれも考え、これも調査して皆さんで揉んできた策をよく理解せず、いわば安易に口にして、雲行きを怪しくしてしまったすすめ方が全く手馴れていない・・今回のマニフェストで、待機児解消に学校の空き教室を利用し改造する策を出したようだが、テレビ局の調査では空き教室は23区ないにひとつもない中央区に作った空き教室改修の保育園の設置費用は2億円を越える・・10個作っただけで、もう子ども手当て相当の予算に達する。区には表に数字としてあらわれている待機児数よりもはるかに多い潜在的な待機児(申し込みには行ってはいないが、保育園に入れるのなら、働きたいと思っておる母親の子ども)がいることすら、把握していなかった・例が報告されていた。もう待機児対策なんて、やめてほしい。待機児って用語、おかしいですよ。子どもの育ちと家族や地域の問題のひとつ、子どもが育つ居場所の問題なのですよね。街づくり全体の、社会のありようを問われている問題なのですよね。都会であればこそ、数作ればそれでいいんですか?都会のようなところで育つ子どもの居場所はどうあればいいのでしょうか保育園でも幼稚園でも、自然を取り入れ、緑豊かな場所で、世代を超えた交流のできる場所が子どもには必要なのではないでしょうか?駅中や駅前などの荷物預かりのように考えられた園や若い保育者ばかりを集めて人件費を安くして、運営費を削っているような園(実際にあります)保育園を作るのなら、子どもの育つ場所としての大切な用件を満たせるような公的予算をきちんと補助し、保育料は乳児の場合は一定の金額たとえば経費の半分負担(人件費がかかるため、0歳児一人当たり10万以上になっている・・)は最低の保育料としてしっかり徴収し、生活保護所帯などは無償、幼児以上は無償化する方向でどうか・・。保育料はしっかり徴収するそのためには質を維持、向上させる園の保育にかかってくる。安かろう、悪かろうの作り方はこんりんざい、やめてほしい!!家庭的保育室を増やすためには、家庭的保育室を引き受ける所帯への優遇措置、特典をつける。収入を多くする。地域の保育園と連携する方式で最初から作る、家庭的保育者が休暇をとるときは保育園の一時保育を無料で利用できるようにする(保育料は市町村が出す)、小児科医師などとの連携、など地域の中での孤立しないような交流型の保育室を作る。とにかく、民主党はぎこちなさすぎる、総務省レベルの理解で決めては無知蒙昧としかいいようがない。厚労省がここまで現状を分析して、現場に近いスタンスで努力してきたことを真っ向から崩そうとしているような気がする。厚労省、頑張れ!!
November 1, 2009
コメント(0)
-

ようこそ激動の21世紀の日本へ
今週新しい命が誕生!ようこそこの日本、東京へ、はじめまして・・よく飛び出してきたね、たくましく、生きていくんだよ・・予定日より2日早く、血圧が高くなり、急遽入院。臨月になって、足がむくむと心配していたが・・もちろん子宮口が開いていないわけだから子宮口を開かせる処置をして、翌朝から陣痛促進剤の点滴開始。先週出産間近になった娘にぜひ読んでほしいと届けた本、「ダーリンは外国人」というシリーズの出産編、これホントにリアルで、予備知識に必読、と思ったのでそしたら、自分も読んで、夫くんにも読んでもらったと・・これがやはり良かった・・お産のイメージがシュミレーションされたようです。26日夜から不規則に始まった陣痛は全く眠れないほど強かったようで朝から陣痛促進剤で拍車をかけたから、痛みがピークに達してそれでもぐっと我慢をして8時間以上頑張ってこらえて夕方やっと生まれた、そうだ。最後赤ちゃんの心拍数が落ちてきたので、帝王切開になるかもと言われていたそうだけど、なんとか無事生まれアプガールスコアも8点位だったようで、一安心。娘からの携帯電話で、車を飛ばして、夜の7時過ぎに到着。昨今は分娩台の上の本人から電話をさせるらしい。この日の主人公ちゃんは、何事もなくケロッとした穏やかな表情で眠っていた・・夫くんの胸に抱かれて・・。ところがこれが、ツワモノだった・・すやすやと眠っているので、そっと箱の中におろした、とたんうぐ、うぐっと始まり、小さな声だが、「まだ、まだ眠っていましぇん」とぐずぐず始まり、今度は私が抱っこ・・また、しばらくすると眠っているので、ゆっくりと下ろしても、またまた・・「ちょっと、この子生まれたばかりで、自己主張してるよ、もっと抱っこしてなさい!」あらあ、一筋なわではいかないって予感する・・口をパクパクして、咽が渇いたサインを送っているし「看護師さんが今夜はまだ何もあげなくてもいいんだって言ってた」それにしても、この口は欲しがっている口だお産で疲れ果てた新米ママを尻目に、この新しい命はこの21世紀の荒波をくぐる元気や力をつけて生まれて来た感じ・・とても頼もしい・・、よしよし、これ位自己主張しないと生きていけん、その調子で頑張れ!
October 29, 2009
コメント(0)
-
スウェーデンやフランスとは税率が違う・・
子ども手当てが無条件で拠出され、年間30万ほどの収入が増えることになる。このような手当ては北欧、フランスなどではすでに行われており日本でも当たり前のようになってほしいと思っていた・・でもすでに拠出されている各国は国民一人ひとりの税率が違う消費税もはるかに高い・・・つまりそれだけの財源をとって、配分される・・・日本は無駄遣いを削るお金から出す・・本当にそれだけで、お金が保障されるのか最終的にだれの首を絞めるのか子どもなくては国の将来はありえないし、大いに投資してほしいでも、子どもにかかわる教育者、保育者の待遇はどうだろう大事にされているといえるのかぎりぎりの人数で保育をして、午前中に一休みもありえない!仕事の量は増える一方で・・・毎日追われているのが現状だ!本当に・・子ども手当てさえだせばいい子どもが育つのか・・・よ~~~~く、考えてほしい
September 6, 2009
コメント(0)
-
今日から教員一年生です!
あっ雨だ!結構、落ち着いていけるかも・・GOO!今日から大学の教員一年生・・新たな再出発の日になるのかな?あれこれ思うことはあるけど、まずは学生さんたちとの出会いが楽しみ!そして、新鮮な気持をいつまで持ち続けられるかということも来週から授業で、その前に色々準備が必要だ・・あてがわれた研究室はまだ、がらんとして何もない先日少しばかりの本を持参して並べたときに隣の研究室に明かりがついていたので、ご挨拶したら本で埋もれているような感じでした・・さあ、今日から私にできることを少しずつやっていくしかないファイティーン!
April 1, 2009
コメント(0)
-
子どもを可愛いって、言わないこと
わが会の機関紙エデュカーレ、今号の記事より 「かわいい」って言わない! という特集がある。A短大のS先生に取材したもの・・・「保育の現場でやたら保育者は子どもをかわいい、を連発する。 それは無意識に大人にとって扱いやすい子どもを 期待しているということではないでしょうか?」 と述べられている。(そうかなあ?可愛いとかいうかしら?)学生にも実習でかわいいは禁止しているそうです。 かわいい、という言葉を使わずに他の言葉に置き換えてみるが、結局、それに代わる言葉を見つけられないことが多いと、先生は話す。保育学生は違う言葉を捜すことで、子どもとの付き合い方が変わるという 結果が出たのだそうです。何かこの話しは少し、ボタンが掛け違っていないでしょうか私自身にかえて考えてみたとき 子どもと話しをしていて、子どもに向かって可愛いということってあるかしら?と思うのです。大人同士の話しとして、可愛いねとはいうけれど。多分、子どもを上から目線で見ているとそういう言葉が 自然に口をついて出てくるのだろうと思う。 私の場合は子どもと大体対話をしていることが多いので 使うことはまずない・・ 子どもに向かって、かわいい、なんていったら その後、どういうふうな子どもとの会話になるのだろう 不自然な感じでギクシャクしてしまう その短大の先生はきっと学生の見方を言っているのでしょうね毎日子どもと生活していたら、何をするのも当事者間の関係なので人を眺めているような「可愛い・・」にはならないはず。
January 9, 2009
コメント(0)
-
家庭的保育の法制化
かねてから国会に提出していた家庭的保育の法制化が 11月に決定され、いよいよ補助金が拠出され 普及のため市町村での研修が始まる。 夏にモデル研修をして、今は研修のマニュアル作りの作業分担執筆で作成の依頼が来ているのだが・・ 諸事情ですぐにはとりかかれない、遅くとも2月半ば完成!! 4月からなので・・大急ぎ!なのだ。 心配なのは、今までのように有資格ではなく、 研修を受ければ、一般の方でも家庭的保育ができるということ 政府のもくろみは、もちろん女性の労働力確保で待機児解消なわけ。 これからしっかりしたガイドラインを作ると言っているけれど。 その研修が継続的なものであればよいが 短期の研修でゴー^サインになる可能性大、 あとはきっと、ほとんどノーチェック?事故や問題が起きてから対策では・・・。現在の家庭福祉員の方々は、大ベテランの方が多く 乳児保育の質が保たれているが・・。 なし崩しの法制化にならないよう 子どものため、保護者のため、日本の将来のため乳児保育の「とりで」はしっかりと固めていきたい。
December 6, 2008
コメント(0)
-
保育園は変わる?変わらない?今が正念場!
保育指針が大きく改定され、 保育内容は幼稚園教育要領と同じになった。では保育園はどこを変えるのか、幼稚園の幼児教育と何が違うのか?保育の中身を丁寧に見直したり、整理をし、新たにやらなければならないこと何かとこれまでにない熱い議論をしている。まず保育園と幼稚園は保育する時間が大きく違う(今までは)保育史上、幼稚園保育の「短時間保育」至上主義に対論がないまま 現在に至っている。これまで保育園は幼稚園に近づけ、 という暗黙の意識で社会が、保育士自身がいたのではないか? 子どもの「生活」そのものが保育の質である、と書かれた論文がある。私もそう思う。 教育の時間だけ熱心で、生活は手を抜いていい、という ことではない、子どもにとっていまや「生活」の場は 社会が、家庭が求めている人間形成の場になりうる。 教育は幼稚園がモデル、あるいは幼稚園の保育に近づけ のような風潮が長く、いまでもある。 その通説を覆す! 「生活」を組織し、教育の概念として確立していく、 このことが実現できれば、保育園保育の活路ができる。
November 7, 2008
コメント(0)
-
子どもの育ちと環境
『子どもの育ちと環境』 ~今だからこそ、子どもの育ちと環境を考える~ 連休のど真ん中ですが・・研究会仲間でシンポジウムをしますので 関心のある方はご参加くださいね。保育・幼児教育、子育てには“環境”が大事と言われます。でも、環境という言葉が指す範囲はとても広いし、それをどのように考え構成していけばよいのか…日々保育実践・子育てにあたっている方でも大いに悩むところです。私たち“子どもの育ちと環境を考える会”では、先日の本の刊行に引き続いて、今回はこの道の先達をコメンテーターにお迎えして、シンポジウムという形で会場の皆様とともに考えを深めたいと思っています。連休の中日ではありますが、どうぞお越しくださいませ。 (子どもの育ちと環境を考える会代表/塩野谷斉) 主催 子どもの育ちと環境を考える会 後援(予定) こども環境学会、臨床育児・保育研究会、保育者の専門性研究会、ひとなる書房 日時 2008年11月2日(日) 18:00~21:00会場 杉並区 産業商工会館(東京都杉並区阿佐谷南3-2-19) JR中央線阿佐ヶ谷駅より徒歩5分 地下鉄丸の内線「南阿佐ヶ谷駅」より徒歩3分 定員 100名(申し込み順)参加費 1,500円 (当日会場にて) 『子どもの育ちと環境~現場からの10の提言~』(ひとなる書房)をお持ちの方はご持参ください。 なお、会場内でも販売しますので、お持ちでない方はぜひご利用ください。 プログラム(予定)-----------------------------総合司会 塩野谷斉(日本福祉大学)1.話題提供(18:00~19:10) 子どもを取り巻く環境の課題や、日々、創意工夫を重ねた活動を続ける中から見えてくる新しい視点など、様々な専門、立場、視点から話題の提供と主題の解題を行います。塩野谷斉(前掲) 子どもと環境--保育環境を総合化する試み木村歩美(こども環境学会) 運動場よりも園庭--築山「なかよし山」とその役割依田敬子(響育の山里くじら雲/長野県) 毎日遠足、毎日探検--繰り返しの自然の中で育つもの 宮武大和(札幌トモエ幼稚園/北海道) 親参加の幼稚園--育ち合い・支え合いで楽しく子育て溝口義朗(認証保育所ウッディキッズ/東京都) いま保育が家庭にできること--矛盾をつつみこむ家庭支援井上 寿(環境デザイン研究所) 元気な子どもを育む保育環境とは--子どもの育ちをめぐる今日的課題をふまえて今井豊彦(日本保育協会) 人的環境としての保育者--保育士資格と研修のあり方を中心に 2.討 論 (19:15~21:00) 子どもが育つ環境づくりの課題と方向性--自ら意味づけることができる環境の保障 汐見稔幸先生が、本書最終章で環境を4つのジャンルに分けられましたが、これをもとに『自然環境』『自然-人工環境』『コミュニケーション環境』『制度・保育者環境』という4つのキーワードを設けました。これらをきっかけに、前掲の話題提供者とコメンテーター、そして会場の皆様で次世代を担う子どもたちの育ちに必要な環境づくりの課題や展望について、ディスカッションを進めていきます。 コメンテーター 仙田 満(放送大学教授・日本学術会議会員・こども環境学会会長) 汐見稔幸(白梅学園大学学長・こども環境学会副会長) ※プログラムおよび話題提供者は一部変更になる場合があります【申し込み方法】-----------------------------E-mailもしくはFaxにて必要事項(氏名、所属、連絡先電話番号、E-mailアドレス)をご記入の上、お申し込みください。定員となり次第、締め切りとさせていただきます。なお、定員に達しない場合は当日も受付いたしますので、直接本シンポジウム事務局にお問い合わせ下さい。開催日前に定員に達した場合は、受付に漏れた方のみご連絡を差し上げます。【申し込み・お問い合わせ先】(本シンポジウム事務局)環境デザイン研究所 担当:井上寿〒106-0032 東京都港区六本木5-12-22E-mail: inoue@ms-edi.co.jp Tel:03-5575-7174 Fax:03-5575-7178
October 31, 2008
コメント(0)
-
家庭的保育
フランスなどでは乳児の保育は家庭的保育制度がすすんでいるそうですが、日本でも今後待機児解消をさらにすすめる政策で厚労省は積極的に取り入れようとしているそうです。その関係で先日、モデル研修の講師をしてきました。この家庭的保育、行政がしっかりバックアップする仕組みがないと大変だなと思いました。受講者の方から、質問などでわかったのですが、入園時に健康診断書、あるいは何か病気がある場合の診断書母子手帳を確認するなど、面接時の子どもの健康状態を確認する方法が行政によってまちまちなのです。中には先天的な病気があるお子さんの保護者の方は診断書も説明も家庭的保育者に説明もしないことがあって、保育しているときに状態がどうも変だなと改めて保護者から聞き、驚いたケースもあったそうです。感染症などの治ってからの登園の確認もなかなか難しいそうですし、もちろん嘱託医もいないわけで医師とのやりとり、主治医との連携も難しいのだそうです。病児は預からないことになっていても、色々な事情で預からざるを得ない場合も多いうようで本当に大変だと感じました。家庭的保育は乳児にとって少人数の暖かい雰囲気で保育を受けられる場で、拡大すること自体はいいとは思うのですが、現実何かあったときの責任は個人になるのだしもっと行政が色々と制度化して、保育者が安心して子どもを預かれるようにしてほしいとつくづく思いました。
September 23, 2008
コメント(0)
-
幼保、幼保っていうけど、研修会は別って変?
夏はあちこちで研究会の夏のセミナーやらシンポジウムやらが 開かれている。 でも保育園の保育士の大会と幼稚園の教諭の方々とは それぞれ別な会が多いのです。 最近、幼稚園の教諭対象のセミナーやシンポで 幼保一体の園や認定子ども園、幼稚園での2歳児保育などから 乳児保育や保育園の保育の話題がめっきり多くなってきていると 感じています、保育園関係者を話題提供者にしたり・・。 でも、そういった会の参加者は保育士はほとんど参加して いませんね。 私はあまりこだわらずに参加しているのですが。 先日参加した会のシンポである幼保園の園長先生が 軽い気持ち?なのか、それともそういう実態を知って 怒りを感じて発言したのか、はわかりませんが 「預かるだけの保育ばかりしている保育園が多い」と繰り返し おっしゃって・・・。保育士の参加が少ないからって お願い、そんなこと壇上で言わないでほしい、と思って いまいました。 もちろん実態はいい保育園ばかりではないし、 ピンきりなのはわかっていますが、そういう場であえて強調することで 幼稚園の先生たちに返って偏見を持たれてしまうのではないか 危惧してしまいました。 乳児保育に関心を深めていただけるのは嬉しいのですが もう少し公平な見方、広い見地で発言していただかないと 分断が起きてしまいかねません。 保育士も幼稚園教諭もフラットな関係で、そろって参加できる会を 作ってみたいなあ~~、いや作らねば、と思った一日でした。
August 11, 2008
コメント(0)
-
森のようちえん
8月1日~4日まで清里へ。清里にある森のようちえんで、大人たちが体験保育・・・してきました。そこでは不定期に「森のようちえん」を開いているという定員25名の親子、土日に宿泊して森や自然の中で遊び、雨、雪、夜も・・・色々な楽しい企画、発見の連続生き物すべて、草、木、太陽、月、水、土、色々なものが全部が遊びにつながって、無限大に展開されているよう!写真をとって、子どもの様々な表情、動き、しぐさをとらえ見せてもらった。子どもの生き生きした姿に本当に感動!素晴らしかった・・・でも、あまりに現実とかけ離れていることが私は最後まで心の中にひっかっかていました。確かに自然は大事だし、そういう環境があればぜひ子どもに経験させたい、でも都会の中で、しかも親が働いて休暇を十分にとれない条件の子育てで何をどうすれば、いいのか、ともっと自分に引き寄せた問題として考えねば、保育の中で今、そういった子どもの輝きをどうしたら、たくさん作っていけるのか子どもがあんなにのびのびと楽しめるようにするにはどうしたら、よいのか、と・・・特定のだれか、特定の場所でない保育って日常のこと、生活のことなのだから。
August 6, 2008
コメント(0)
-
携帯泣き止ませ大賞のリプレイ
以前、NHKの赤ちゃん番組のアイデア大賞に「携帯で自分の子どもの泣き顔を撮影してその泣き顔の写真を、泣いた本人に見せたら泣きやんだというアイデア」が選ばれた。そのことでは本人に理由を問う前に泣き止ませるのに、携帯の泣き顔の写真を見せることそれ自体は今はやりの裏技のひとつではあっても奨励してもよいのか、赤ちゃん本人の気持ち、また親のかかわり方、親子の心理状態などの問題をとらえれば大賞にしていいわけはない、という抗議にも近い批判があった。少し問題の方向性が違う観点ではあるけれどこういった情報の発信側と受け手側の問題に絞って考えると情報を選別する力の弱さ、また何でも自己責任をとことん追及する社会問題が根底にあるように思う。子育てに自信が持てない、周囲とコミュニケーションがとれないそこで行き詰って、情報収集に走る、とりあえずやってみるうまくいく場合といかない場合があるうまくいかなかった場合はまた情報収集に・・・周囲に相談するのは問題がもう深刻になりかかって、どうにもこうにもならない時点でやっとどこかにたどりつく子育てはあなたの責任、子どもがそれぞれ違えばうまくいった成功例のアドバイスも自分には該当しないとあきらめてしまう・・そして、また自分を追い詰めるその結果、その場しのぎの方法であっても一時的にでも救われる方法をとりつづけるしかない一時しのぎにはまったら確かにおかしな事態であるけれどね。でも実際育児はそうひとつの方法がいつもいつも有効ではないですよ結局悩みは元にもどって、また深刻になるこのなんというかジレンマ、ここに何かサポートすることってできないだろうか、この自己責任を追及する社会が親を追い詰めていってしまう現実の背景的な問題も含めてね・・・・これという回答はないかもしれないけれどね。
July 16, 2008
コメント(3)
-
保育の「原石」を探しに
昨日の一日は私にとって「保育の原石」を探しに行ったような・・ そんな一日になりました。 夕方、園の裏山に駆け上がっって、房総の海と夕陽の輝きを見た瞬間 ・・・もろもろのことを全部忘れてしまいそうになり・・・ 言葉が飛び交わない保育の奥底にあるもの それが子どもの姿から自然ににじみ出ているようで・・・、 改めて「保育」って、とシンプルに考えるための、 スイッチを押してもらったような衝撃が体に走りました。 長い保育経験はあるけれど、 もう一度、ゆっくり子どもたちの姿を見ながら、 自分の巻き戻しをしてみたい、とつくづく思える一日でした・・。 大きな瓦屋根、日本家屋の特徴である、縁側を広くとっている造り 縁側には戸がない、庭から、玄関から入ってきたヒトは 必ず縁側を通る、子ども・親・先生(先生とは呼んでいない)が そこで必ず交叉する。声をかける、よけながら会釈をする、 そんなヒトとヒトの光景をなつかしく、眺めていた・・ ゆっくりとした時がすぎてゆく・・ 夜、見学者20人、職員22人で広い保育室をぐるっと イチジュウするように輪になって、見たまま、感じたままを 率直にしゃべってきた。 子どもの表情が生きている、ああ、笑ってる、 あ、泣いてる、怒ってる、泣きを見せまいとしている、 そんな子どものいくつもの表情の重なり、 遊びに夢中になっている後姿も・・・ 走馬灯のようにめぐって思い出せる一日だった。 度量の広くて深い園長の表情、しわを横目で見ながら このヒトでしか語れない一言一言をかみしめて聞いた。 窓から入ってくる風が頬に心地よい あともう少し時間があったら、と思いながらバスに乗ったけれど 職員の方々の静かな熱意を背中に感じながら、 帰路についた・・・。
July 5, 2008
コメント(0)
-
横浜の過酷な子育て競争(今週のアエラの記事)
今週のアエラの記事「横浜で産めない、育てられない」を読んだ。 横浜の出生率は全国一。生理が遅れて、産科の病院受診をためらって いるうちに、満月はあっと言う間に予約がいっぱいで、どこの病院も 出産予約がとれない、そうなのだ!熾烈な競争・・・ 無事に出産したら、今度は入れる保育園がない・・・ 育児休業が3年になったって、そんなのんびり休んでいたら どこの保育園にも入れなくなってしまう! 保育園の数が急激に増えつつある横浜 この3年で8000人超の定員増を図った。 なんとか入れるようにはなったようだが、民営の園 の内情は人手不足。保育士のヘッドハンティング 状態だという。アルバイトは10ヶ月限定なので 一年勤めないので、卒園のときにはいない、 もちろん担任持ち上がりも少ない。 アルバイトに頼って、結局は保育士の給料は 低賃金になる。学童保育の例では平均収入が 287万・・、これでは家のローンも組めない、 子どもを生むのも考えてしまう。 市は民営の内容についてはあまり触れずに 待機児解消策としてすすめていると書かれている。 最近、前副市長の○○さんが横浜の保育園を紹介している本を 出版?されるそうだが、いい保育をしているところばかりを 集めているようだ。 民営を急速にすすめ裁判沙汰になったが、民営園はこれほど いいというアピールとも受け取れる。 もちろん民営園はピン、キリと思うし、いいところはとても 質が高い、公立がいいとはいえないと私自身思っているけれど。 これまで保育を積み重ねてきた経緯のある園は それなりに、かなり考えられているが、この待機児対策に よって新しく参入してきた園の経営、人材などにはまだまだ 議論の余地がたくさんある。 自治体はその実態をしっかり考え保育政策をすすめてほしいと 切実に思う。このままでは保育士の社会的な評価がなりゆき まかせになってどんどんさがっていくばかり・・先細りの現実だ。 子どもの未来も先細りだ!(叫びたい!!)
July 2, 2008
コメント(1)
-

光の子どもたち・ブラジルのカノアから
「 ブラジル・カノアの光の子どもたち」 ~子どもたちの心の底からの笑顔に支えられて、9年~ 私が事務局をしている保育研究会の7月の会は遠くブラジルから 帰国され、現地の保育園の活動の様子を話していただきます。 関心のある方は直接会場にいらしてくださいね。会費は1000円 です。 また今年2008年はブラジル日系移民100周年、という記念すべき年 です。1999年、鈴木真由美さんはブラジルカノアの村にホームステイし 7人の子どもたちを自宅で保育したことがきかっけで、1年後再び カノアに・・。そして、本格的に活動を開始し、6年経った時、 日本のNGOからの支援がなくなり、その後独立して、大変厳しい 運営の中ですが、現在まで活動を続けています。今では現地で結婚し、 家族と幸せな生活を送りながら、カノアの子どもたちの笑顔に救われ、 頑張って活動を続けていらっしゃいます。 日時:7月8日(火)午後6時半から 話題提供:鈴木真由美氏(光の子どもたちの会・代表) 場所:杉並区産業商工会館 地下和室 主催:臨床育児保育研究会 会場は阿佐ヶ谷駅南口、改札口を出て左側です。 ターミナル前の中杉通りを南へまっすぐに歩いて、3つ目の信号を右 に入り、細い通りを20メートルほど歩くと左にある建物です。 右に曲がる角はペッパーランチというファーストフードの小さな店が目印です。 https://www.yoyaku.city.suginami.tokyo.jp/HTML/0032.htm 杉並区阿佐谷南3-2-19 03-3393-1501
June 27, 2008
コメント(0)
-
おもちゃと絵本
雨が多くなると室内遊びが必然的に多くなる。そもそも天気に関係なく、子どもの遊びが豊かになるような保育環境、心地よく生活できる保育環境は保育園という子どもが長時間過ごす場ではもっとも重点的に考えなくてはいけないことだ・・。ところが、普通家庭によってさまざまある環境と同じように色々な考えや習慣、生活の仕方や、おもちゃの使い方や遊びの展開のさせ方そして子どもが自由にのびのび遊べる場として保育を実践していくためにはそれ相当に時間をかけて議論をしなければならない。保育者が10人いれば10通りあるような・・もので簡単に作れるものではない。基本に保育方針がある場合はその方針に基づいた一定の環境の作り方があって、方針を理解することで環境を作る議論の一致が早い・・ところがそういった独自の保育方針がない、公立保育園などの場合はあれもいい、これもいい、それはよくない、やっぱり変えようとか毎年保育者(担任が変われば、あるいは園長が変われば・・)が変わるごとに喧々囂々になる場合もある。重点項目であることは皆の共通理解はあるが、その作り方になかなかコンセンサスを得られない大きな悩みを抱えている。先週園内研修で、ある企業の園長をしている方に環境について実践するための戦略的な話を聞かせていただいた。要は「ツボ」を心得ているのだ。長年公立の園長を務めていただけある、つまり金もヒトもなかなかくれない20年、30年というベテランを前にコンセンサスをどうとるか・・・そういった克服しなけらばならない山のような課題に果敢にチャレンジしてきたノウハウなのだと思った。講師の話はほとんど網羅されている?とも思えるがこれなくしては、というものがあると思う。決定的な事実・・・だと私は思う。たとえば子どもの目線で環境を、といっても保育者にその感性が乏しければどうなるのだろう。玩具や絵本をいかに多様性のあるものにしていけるかあるいは子どものさまざまな遊びの創造性をどう援助していけるか議論のテーブルに自ら近づいて話ができないのでは?と思う。そこは(保育者の感性)保育者のアキレス腱だと思う。本来もっているものだが、自分の保育生命がそこにある・・という自覚を持つべきかもしれないなあ~~と勝手なことをつぶやいている(正直嘆いているのかもしれない)。
June 22, 2008
コメント(0)
-
日本の乳児保育は世界に誇れる!
今回の指針はこれからの保育園、幼稚園のあり方 すすむべき方向性を示唆できうるものとして 作成されたことは理解しているつもり 故に認定子ども園のあり方などは 幼稚園型でも保育園型でもどちらでも 活用できる、という理解もしている 私はそこを視野にいれて、押さえているからこそ 乳児保育を浮き彫りにすべきだった論、なので。 保育士は乳児担当で、幼稚園教諭は幼児担当、預かり保育 時間外、当番は保育士、夏休みも保育士担当など の職業分断にもなっている現実も見てきて・・ 行政の保育に対する浅い見方で押し通されると (育児と保育のどこが違う?と現に保育担当部署の行政マンが 質問している、つまり無資格者でも全然いいじゃない、という考え方、 コストを下げてもokの分野であると確実に言いたいのだ!) 社会主義国以外は乳児保育の歴史は浅いのです。 日本は独自の路線で乳児保育を積み上げてきました。 女性開放運動、労働運動に重なる歴史も確かに長かった と思う。研究者の思想性に問題を感じて、反発されている 研究者もかたや多い中、ここ10年の間に乳児保育を 地道に研究し、確立していこうという動きも 社会(政府も)の乳児保育の要請の中で 高まってきて・・・事実そういった研究の成果も 色々な方面であがっている。 私自身はといえば一昨年から取り組んできた 乳児保育の成り立ちや現状、これからの方向性などを 先行研究をもとに現場調査もしながら事実の分析を 少しずつすすめ、あれこれと思っている次第・・・・ 幼児教育の分野ではよくわからないが 乳児保育の分野では日本は世界の中で 相当高いレベルで、そこに日本の保育の特色が出ている といっても過言ではないと私は思っています・・・ 流れに棹差さずんば、という奮い立った思いをもつ 委員がなかったのは選定から意図あり、と 思わざるを得ない・・・。 私は・・このまま託児化していく可能性のある 乳児保育(2歳児まで)に、日本の将来そのものに 危機感を感じています。 このことをどれだけ認識して、こういう指針を立てたのか 考えれば考えるほど「むちゃくちゃや~!」と叫びたい。
June 6, 2008
コメント(0)
-
保育指針の解説書はできたけれど・・・
保育指針の解説書には詳しく書かれていても やはり、私は保育指針に乳児保育の項を設ける枠組みがなかった ことに非常に失望しています。 保育内容で幼稚園教育要領にスライド?させて、教育的な価値を 意味づけ、格上げしていただけた指針でも何でもいいけれど・・・・ 保育所指針に乳児保育の項を明示すべきチャンスだったと 思っていたので・・口惜しいばかり。 「内容の配慮事項」、そこではじめて3歳未満児という言葉で 語られる。 幼稚園教育要領は冒頭から、幼児と明示している 指針をそれを避け、全体「子ども」というぼかした表現になっている。 ああもこうも考えてもただ空しさが残ります。 乳児保育のアイディンティティは何処へ行った?
June 6, 2008
コメント(0)
-
ふしぎを育てる、遊びの中で学びを育てる
定年退職後、保育士への転進をはかった数理物理学の教授であった浅野功義先生、現在は保育園で日々子どもたちとともにふしぎの世界をゆっくりと歩きながら、大人にはない子どものさまざまな発想、創造する心に出会い、おおいに感動され、毎日楽しんで仕事をされているそうです。子どものふしぎの芽をたくさん育てることの大切さ勝手に大人の考えを押し付けて、その小さな芽をつんでいまわないよう・・・子どもが五感をフルに働かせて、様々な遊びを楽しんでいけるような保育、環境を大人たちが作っていくことの責務を浅野先生が示してくださっているようです。朝日新聞の「ひと」欄で紹介され、今回(6月の研究会)は私どもの研究会でもお話してくださる予定です。数理物理学のような数式で解明する世界から数式ではとても解明できない世界へ、わくわく、どきどきする世界を私も先生と探検できるような気分? です。先週、郊外の保育園の子どもたちと散歩に出た とき、公園の木製の遊具(滑り台とか)のまわりに てんとう虫の幼虫が集団(その数は公園の遊具という遊具の下 木の根っこのまわり、あるゆる場所にとても数えきれないほど) 発生していて、中には殻を脱皮している最中の虫もいましたが なんか、胸がどきどきしました。今その瞬間なんだ、とか・・ 子どもたちを一緒にじ~と見入ってしまいました。 めがねがなかったので、私が子どもと子どもの間っこから 顔を近づけている姿は結構笑えたかも・・・
May 24, 2008
コメント(1)
-
地域に根付いた認証保育園
認証保育園といえば、駅型、小規模のイメージ。私のよく知っている園はいつも満杯、どうしてか?親のニーズに柔軟に応じて朝早く、夜遅くでもきちんと見てくれるから。早朝や夜遅くでも園長が残ってみていてくれる・・限りなく優しい。玄関を入ると小さな台所、テーブルと椅子がありお茶セットが常時セッティングしゃれTいる食堂になっていて、アットホームで居心地がとてもよい。保育にはポリシーがある、色々な勉強をしているのでここはこうしたい、と環境や遊具を手作りで整え、要所要所はおさえながら自由にのびのびと保育している。企業がやっている認証とは全く違うと思う。そして学童もやっているし、このたび赤字覚悟で新しい園舎を建てた。今日見学に行ってきた。部屋の真ん中に暖炉とえんとつ、これが園長のメッセージ!北海道でもないのに・・・そして親のための喫茶コーナーも・・。親も少しほっとしてから家路に着くように・・・地域のセーフティーネットとして認証だからといって、簡単にやめるわけにはいかない経営は決して楽ではない、借金も多いとこぼしているが・・・きて今ではもう、地域にはなくてはならない園今日は一番大きい子どもたちと公園をさんぽした。風がさわやか、緑がやわらかい、土のにおいが身体にしみこむたまらなく優しい気持ちになって、身体も心も芯からほぐれた・・・
May 21, 2008
コメント(0)
-
三社祭りの洗礼?!
三社祭で始めて神輿かついだ長男、両肩を見てわあ~~!すごい、真っ赤、そして擦り傷で皮膚がめくれてさらに痛々しくなっている。長女が昨年、浅草神社のお引き合わせか、三社祭の神輿をかついでいた彼と出会い、なんとその一年後の今日、自分でいうのもなんですが、めでたくゴール到着!!結構年の二人なので、運命だ~~などと言っているけれどね!そんなわけで、今年の三社祭に長男に彼が神輿を初体験させたという次第。まあ、すごい、これが洗礼ってことなのですね!まあ、大学院も今年で卒業、就職もなんとか内定したので来年は本社のある名古屋に行くらしいのでいい思い出になったでしょう!それにしても、神輿ってみんなこういう風に烙印つけてかつぐ世界なんでしょうね、妙にその痛々しいあとを見て感動してしまった・・・息子には悪いけど!ところで二人は今日入籍し、来週引越し、式はもう少し先なのですがやれやれ、私もやっとほっとしました。私は先週中ごろから保育学会で、半徹夜が続きくたくた~、そして今日は短大の授業でした。新幹線で帰宅し、深夜重いまぶたをこすり、授業資料を作り・・・全身筋肉痛の重いからだで 大学のTAが1時間目からなので朝早くでかけていった長男をみて、疲れたなどとぐちをこぼしてはいられず、やるしかないけど・・
May 19, 2008
コメント(4)
-
幼小連携、現実は・・・
連携のプログラムを協同で立てて互恵性のある幼小連携という 研究のまとめの報告を聞いて、本音で思ったこと・・・ 小学校はあえて連携をする必要をどれだけの教員が 感じているか、ほとんどいないのではないか・・・ 本にまとめられるほどの実践であっても 学校教育には結果的にあまりメリットがない・・ 教員の方も公立小であれば異動するわけですし 毎日追われている教員の現実の問題としても・・・ 今後学習指導要領が変わり、そのとおりにすすめようとするならば 幼小連携を本格的に取り組むことになるのですよね...。 連携の研究対象であっても幼稚園の授業参観には 学担はまったくでかけられない? かろうじて専科の担任が数名・・・ それは私の区でも保幼小公開保育・授業に まったくといっていいほど学担はこなかった 授業を何かの専科に変えてでも 45分捻出してこれないものか、と思った・・。 そこまでする必要性があるのだろうか 疑問視している教員が多いということではないだろうか それと、教育課程の目標、これが現実をそのままあらわしている。 たとえば幼稚園の教育課程のねらい 考える子は 小学校の教育課程指導の目標 自ら学ぶ子に相当するとして 流れを示して立てているので、双方を比べてみると 1年生「よく話を聞き、考える」 年長「自分なりに課題をもち、探求することを楽しむ」 「状況に応じて自分がどうすればよいかを考えて動こうとする」 これではまるで小学校と幼稚園を逆転させたもののようで これだけ読んだひとは間違い?ではと思うのではないか もちろん教科ごとの到達目標、5領域の指導目標は別にあるわけだが こういうことが現実でも、教員はあまり疑問にも思わない? それって発達を考えていますか?など生意気なこと 言いたくなってしまう・・・ 文科省が連携の教員のコーディネーター役を各学校に1名 派遣する予算をとるか、はたまた年長だけでも 教育実習に組み込み、幼児教育への関心を強める策を 早い段階から準備するとかしなければ まだまだ絵に描いたもち、のような感じが否めないなあ~。
May 14, 2008
コメント(0)
-
保育室の環境を変えたら、子どもが落ち着きました!
今年度になって保育園の環境を変えたら、子どもが落ち着いた!ぜひ、見に来てください!と 園長の依頼をうけ、でかけてきた。 その保育園は3~5歳の各クラスの規模が56名という 人数で、以前までは3~5歳の3クラスをそれぞれ二つに分けて保育し、部屋も分かれていた。 今回、行ってみると各クラスの二部屋の一部屋を ロッカールーム、着替え室に変えていて もう一部屋をプレイルーム(食事も)として使用していた。 一部屋に56名の子どもの机といすがびっしり隙間なく 設定されていた。机と机の間に低めの棚をおき、人数のわりには種類も 数もわずかな玩具を並べてあった。 園長は、生活の流れに秩序ができてきた。 まず、一部屋(ロッカールーム)の側で登園すると、その部屋の入り口でノートにシールを貼る、その次にロッカーにかばんをおく、着替えをするなどの 一部屋にしたことで流れがスムーズになり、子ども同士のトラブルも減り とてもよくなった・・生活面で落ち着きが出てきた、と。そうかもしれないが部屋の広さは、横長の最低限のスペースの部屋で 2割増しの人数を入園させているので、 おそらく、全員がプレイルームで遊ぶとなると、いったん すわったらもう歩けないくらいの状態になる。 私には遊びの内容の豊かなイメージはまったく想像できなかった 「一斉がたの保育から子どもが遊びを自分で見つけられ るようになった」園長はそう話された。 そうなのか・・・何を選んでどうやって遊んでいるのか?自由に何かを創造する遊びはどこでするのか?説明を詳しく受けても、今ひとつ子どもの姿は浮かんでこなかった・・
May 11, 2008
コメント(1)
-
学生を感動させた!保育実践
授業で多くの学生を感動させた頭金さんの保育の実践 彼女のエピソードはいつも必ず保育の反省的な振り返りが 中心です。 子どもへのメッセージの送り方にその振り返りのできる保育者の 心がにじみ出ているからだろうと思います。 子どもとの対話は保育者が自分と向き合う姿と半ば重なっているので はないかと思います。そこにくどくどした言葉ではなく 彼女なりの独自な(人間性)センスやユーモアあふれる言葉のあらわれ、 が子どもに響いている場合が多い・・・ 加藤繁美先生はこの本のあとがきを書かれていますが、昨年出された 『対話的保育カリキュラム』の中でも彼女の実践を引用して 子どもの活動要求と保育者の教育的な活動要求が 保育の経験の履歴を作り出していると書かれています。 昨日学生に読んでもらった事例もそうでした、自分の子どもへの 思いはあるものの、子どもの気持ちをくみとりきれずにいる 保育者の微妙な心の動きがありのまま書かれているので 真に迫るものがあったと思うのです。 結果的に子どもが保育者の意図を理解し、保育者主導ではな 子ども自身で自己決定していく事例に保育者である自分も そこから学ぶものをきちんと記録にとり、二度同じことを 繰り返さないようにしているのだと思います。 保育実践の力量をつくづく感じます。
May 4, 2008
コメント(2)
-
学生の素直な心に胸が熱くなりました!
今日の授業 2コマぶっつづけ、今日はPWもビデオもないので私の 話しをひたすら聞くだけの授業で、大変だろうなと思っていました。 2コマの後半の授業では 発達が気になる子の事例で具体的な対応の話しや保護者の不安な 気持ちや色々な話しをしましたら、みんなもう真剣!じーっと 聞いてくれました。 最後はきっと飽きてしまうだろうと思って、頭金さんの本「気持ちい い保育み~つけた!」の中のりょうくんの実践の話しをあらかじめプ リントして配布してあったので、それをリレー式に学生さんに音読 してもらいました。 おしゃべりは誰も一言も発しないし、目が私の方をみつめていました。 そして、授業最後、いつものミニレポートを書いてもらいました。 提出するとき、学生さんたちは「先生、今日の授業すごいよかっ た!」「私、涙でちゃったよ!」とか、私に声をかけてくれました。 感想もすごい!!もう全員がびっしりと書いてました。 それを授業終了後に講師室で読み、私まで胸があつくなりました。 頭金さんのような保育者になりたい、と保育士の仕事を改めて いい仕事だな~と深く感じたという感想もたくさんありました。 最初はおしゃべりグループに閉口しましたが、 私もだんだん元気がわいてきました。 なんだか嬉しくて、学生さんの素直な心にとても癒されるようで・・。 子どもたちとの毎日のやりとりがなくなって急に寂しい毎日でしたが 学生さんたちと接していると共通の話題で話しができる仲間を見つけ たよう・・・!つくづくいいなあ、若いヒトに接するってと思いまし た。
May 1, 2008
コメント(0)
-
先生も一年生!
いつの間にか、街は葉桜の季節に・・・退職後後任が欠員のため、急遽前任園で仕事をするハメになり(退職のつけ!ともいえる・・けどそうは思いたくないなあ~)なんと3つの職場を掛け持ちするという恐ろしく忙しい4月になり・・・ということで日記の更新が全くできずにいました。始めての授業で学生に新米教員だと伝え、みんな、色々と教えてね!から始まった最初の授業。一部の学生が、教室に入っても「きゃ~わ~」の雰囲気のまま、座席に座る。授業中もおしゃべりを続けているので、ふ=、そうか、これが現実。さあ、2回目からおしゃべり封じ込み作戦。レジュメはメモをとるように空白で、項目だけ!回ごとのミニレポートが評価の大きなウエイトがあることは事前に知らせてあったので、授業内レポートは授業内容を必ず入れて書いて提出すること。そのかわり10分くらい早く終わる。これで2回目からは少し真剣な目つきになって、おしゃべりがぐ~~んと減ってきた・・・私の目標は参加型の授業、今日で3回目なので来週はそろそろグループに分かれてディスカッションも入れよう・・。好評なのは保育園の保護者のビデオレター!現場の話になると真剣になる、ましてや保護者の方の言葉はとっても説得力がある。保育士になりたいのは子どもが大好きだから、という学生もそうか、保護者と一緒に子どもを育てていくんだ、と改めて感じてくれてみんなとってもいい感想を寄せてくれた。早速ビデオレターのご本人に感想を届けたら、とても喜んで下さった。授業が終わり、帰途につくとぐったりと疲れている自分を感じる。フルスイング、全力投球だものね、年も年だし。
April 24, 2008
コメント(0)
-
保育園と小学校の連携どうなっていますか?
真新しいランドセルに期待を膨らませてピッカピッカの一年生に・・・どうしてるかなあ~~入学式を終えたばかりだけれど・・4月はじめは保育園から学童保育へとお弁当を持って、春休みを過ごしている子どもたち・・・「元気に学童へ通っていて、もうお友だちが出来たって喜んでいるそうよ」少し気になっていたお子さんの情報が入ってきて、送り出した側の私たち、ちょっとほっとしました。実際小学校と保育園の連携はなかなか大変。保幼小という協議会のようなものがあるにはありますが、形式化していて普段のやりとりとはほど遠いものです。年に一度開かれるイベントで、公開保育と地域ごとの分科会でテーマを持って話し合うという内容ですが、なかなか現場の担任をもつ先生は出られず校長先生、副校長先生レベルでのやりとりになることが多く、子どもの「就学前後の生活などの問題」に話しが集中し教訓的なご意見を最後に頂くという流れです。いい意味での連携という視点がなかなかもてずに不消化な感じです。最も年に一度程度ではそうなりますよね。その他地域によりますが、年長児と一年生の交流会を持つなどして学校が年長児の様子を観察?する場もあります。子どもたちは学校を始めて知るいい体験ですが、それもせいぜい一回?くらいでぎりぎりの時期にしか持てない感じです。今回改訂される指針の第4章保育の計画・評価では小学校との連携について、より積極的な姿勢で交流・連携をするよう求められています。 小学校と保育園の連携で地域の現状を調査しまとめられている「保育所と小学校の連携のあり方に関する調査研究」の報告でも如実に差が出ていました。いいスタートが切れたところでは模索しながらも、忙しい中互いに距離を縮めながら情報交換や小学校の先生が保育園で研修をするなど理解を深め合う手立てを打っているようです。こればかりは両者、行政が前向きな姿勢で、なんとか取り組んでいくしかない問題です!
April 6, 2008
コメント(0)
-
新米教師として、はじめまして
入学式の後、教員の顔合わせ会に始めて参加してきました。専任教員と非常勤の教員とで、丸いテーブルを囲んで和やかに顔合わせをしながら、初任者の紹介やら大学や学生への要望などを伝え合うという会でした。大学側の姿勢がとてもていねいで学生への心配りもあり雰囲気がアットホームでいい感じの大学だなと思いました・・。ただ、やはりいまどきの学生たちなので授業中のエピソードはどの先生もこぼしていましたが長年学生の立場でしたから、私はどちらかといえば学生側の気持ちに近いので・・微笑ましく聞けました。その後、今度は全員の交流会、100人以上の方々の前で壇上に上がり、新任者の紹介にはびっくり・・・そこまでしてくださらなくても、と引けてしまいましたがええ~い!と覚悟を決めて・・・壇上に上がり、理事長さんや学長さん、教授の方々の前で今、保育界は非常にたくさんのことが押し寄せてきて現場は大変です、と・・生意気なことを言ってしまいました。現場をもっと知って学生さんに保育を教えてほしいと・・・その後会食の席で、隣の心理学の教授??にあなたのその誠意は学生に伝わるかどうか疑問です、というコメントをいただきました。手厳しい現実がありますよ、という感想、あるいは一途すぎては学生がついていけないですよ、と言う意味?もっとトーンを落とした方がいいという意見と受け取りました。そうですね、確かフルスイングの先生もそうでした。私の身体から発している何か、それは多分「Belief」なのでしょう。最初からそんなものを教壇には持ち込むと学生との距離ができてしまいかねない・・そう思います。学生さんたちが今、何を思っているのか考えていることが何なのか知ることからはじめます。これからの現実という未知の世界への不安、迷いや悩みも自分の言葉にして発信してもらえれば嬉しい、私からも普通の言葉で対話ができるような授業をしたいとしみじみと思いました。
April 3, 2008
コメント(0)
-
淡々とカウントダウン
とうとう残すところあと数日になりました。 送別会も終えて、31日朝辞令を頂きに役所へ。 万感の思い・・・ですが 心はとても静寂のなかにいます。 いつもの朝、いつものおはよう、いつもの子どもたちの 元気な声、事務室の電話のベルが鳴り・・・ 廊下からは掃除機の音、給食室の匂い テラスの朝のまぶしいくらいの陽の光 庭を急ぎ足で通り過ぎる保護者の方たちの 「行ってきま~す」の声・・・ この日常の繰り返しの中で31年間 今、淡々と過ぎてゆく残りの時間 心の中でカウントダウンを数えても いつもの朝といつもの夕方で いつもの勤務と同じように 最後を締めくくるつもりで・・・
March 29, 2008
コメント(2)
-
保育指針改訂・4月からどうなる?その1
保育指針改訂問題は現場の立場で最後まで言っておきたいよく「改訂されても、結局実際の保育はかわらない」と話す大学の先生は多い。特に幼稚園教育要領をそっくりそのままスライドさせた保育内容、という下りでは正直何年もかけて大御所がお役所に集まって検討会をした意味がどこにあるのか、大いに疑問・・・怒り心頭なのは、保育園の特色である乳児保育は内容の部分で配慮事項、とくくられてしまったこと。?解説書で詳しくするから大丈夫・・それって何なんですか!とつくづく思います。位置づけの問題を言っているのです。指針上配慮事項にしてしまった・・とりかえしのつかないことだと思います。乳児期からの保育は今の日本の保育園の一番の特色です。歴史も大変長く(諸外国に秀でています!)明治半ば託児所保育として救済から始まって大正、戦前の昭和と続き、そして保育所となった戦後・・と。明治から大正にかけて公立の託児所は手探りで乳児保育の勉強会をしたようです。私の修論のテーマなので、国会図書館につめて乳児保育の歴史を一通り調べ上げたので・・・私には偉い方のお考えがはかり知れないくらい、の思いで、無念です。乳児保育は指針の中にきちんと一項位置づけるべきでした。さらに・・保育士の非正規化が急速に進んでいます。どの保育園も指針の告示化の義務付けで、非正規が何人いようと内容を地域の子育て支援、小学校との連携も含めて質的に維持できる計画・実施・評価を徹底する?本当にそんなことができるの?正規であれば保育計画、月案、週案、日案、児童票から日誌、職員会議、リーダー会議の資料作成、保護者会資料、ケース会議資料発達支援ルールで連携機関との交渉から会議への出席、資料、記録各種行事から食育など保育上必要なプロジェトの運営、計画立案から実施反省、記録、地域の子育て支援、出前保育、育児相談PR活動、それらの実施記録と反省勿論日々の連絡帳、保護者との個人面談、記録それを正規以外の保育士が分担すれば給料の差をどこでつけるのか、また、自己評価でマニュアル化がすすむ恐れが大きい。保育はその場その場で起きた物語りの連続であって人と人のやりとりがページをめくるように積み重ねられている100あれば100通りのやりとり同じことをやって人が違えば同じになるわけではない。仕事の手順のようにはいかない。(つづく)
March 23, 2008
コメント(0)
-
「保育は人なり」
春3月、真っ白なこぶしの花が満開になりました。いよいよ、別れのとき・・が迫っています。まる31年も勤務したので、さすがに万感の思いです。子どもの笑顔の傍らにあって、笑ったり、怒ったり・・・涙したり嬉しいことも、悲しいことも、悩むこともみんな出会いがあったから・・子どもとの出会いは、まさに人と人の出会いそのもの、です。「保育は人なり」と心から思います。どんなに幼くても、しっかりこちらは見られています。本当にそうなのです!赤ちゃんの視線を感じます。面接で出会った赤ちゃんたち、澄んだ瞳がじっとこちらを観察していました・・見透かされていそうでなんだかこわかった!(「よ・よ・よろしくね・・・」とアイコンタクトで返したけれど、わかってもらえたかしら??)保育は、人と人が作った「空気」の中のドラマ。空気は人の起こす風?和やかな風、騒然とした風・・・人と人の風、そうやっぱり空気ですよね。31年かかって、そんなことを今まだ、つぶやいている私なのです。
March 20, 2008
コメント(0)
-
第三者評価員検定制度を作ってほしい!
保育園の第三者評価結果がネットでUPされた。昨年からこの第三者評価については考えるところがあり評価機関(評価者)が保育園、あるいは保育についての専門知識をどれだけ持っているか、甚だ疑問に感じ、最終的に、評価機構(大元)に意見、あるいは要望を出していこうと思っていた。それは、評価者の検定制度を作ってほしい、ということ!東京都の場合、評価項目、評価内容が詳細にわたっていて一つひとつの項目に事例を示して、資料を用意し一日のヒアリングの際に口頭でも説明している。経営面(組織マネージメント)、保育面(サービス提供)でそれぞれ70項目にわたる・・・評価員は午前中観察(といより視察、園内見学の域を出ない)午後がそのヒアリングで、最低3人~4人の評価員に回答するのはほとんど園長1名もしくは主任(副園長)で喋りっぱなしの状態。途中水が入るが、双方相当神経を使って、やりとりをする。用意した資料の中身は(事前にもかなりの資料を提出している)パラパラと読む程度、ある、なしを確認するようなもの。具体例の確認については園長の説明、その内容を評価者がメモにして持ち帰る。相当要領よくすすめないと、5時には終わらない。第三者評価の実態は「内容のレベルを問うものではなく、あるかないかやっているか、いないか」数多くの事例を用意しても中身ではなく評価項目にそった内容であれば{あり」評価者はプログラムされた評価者用のシートに「あり」を入力すると自動的に評価の段階が表示される仕組みだ。評価機関(評価業者)は経営コンサルから資格専門学校、福祉のNPO団体まで様々な分野が手をつけている。評価者はネットでも見れるが、企業の経営コンサル経験者、企業の退職者(分野はかなり広い)保育園長の退職者福祉のNPO活動を主にしている人、編集者など多岐にわたるが、保育園に対応する評価者は不足しているので副評価者として評価機関が外部から雇っている場合が多い。主はその評価機関の正社員で、元々の専門分野に長けた方がなっている保育園の評価は経営面、保育面もバランスよく熟知された方が主の評価者であるべき、そして評価の初心者と経験者の違いは明らか。インターンもなく、いきなり3人の一人として評価者になる。説明会で見えた初心者の方は研修を受けたはずだが、児童票も知らなかった。評価項目それぞれの理解も浅い。評価される側はたまったものではない・・・。しかし文句を言える筋合いはなく、大元の評価機構に具申するしか方法はない。今後ますます評価が必要とされ、業者の許容範囲をかなり超えてやらなければな追いつかないだろうと思う。評価員をあちこち回して対応するのが現状だろうと思う。元来お役所仕事の機構がどこまで、評価の質に迫れるか私は検定制度を作るべきだと思う。保育園評価の主の評価者は検定○級以上、副は○級保持者・・・この制度を作ればかなり評価の質に迫る手立てになるのではないかと思う。
March 18, 2008
コメント(0)
-
子どもの主体性を生かす保育環境と企業の保育
今週、ある有名な企業が経営する保育園を見学してきた都内で一番に公設民営で名乗りを上げた企業である。当時は企業という言葉、その会社名だけでアレルギーになっていた正直、企業の保育をまだまだ信用できない・・という気持ちだった。その関連企業は子ども研究のサイトを持っているのでそこを見ている限りでは、かなり子ども中心主義であることはわかっていた・・以前からアメリカの心理学、教育学分野から学ぶ資料が多く掲載されていて、最近の「対立から学ぶ教育」~幼児期におけるCR教育~はとても参考になった。http://www.crn.or.jp/LIBRARY/NY/0003.HTMその園の保育環境と保育方針は子どもの主体性を尊重するというもので子どもが遊びをじっくり集中し、展開できることを考えた保育環境作り。乳児クラスから幼児クラスまで、ほぼ一貫していた。案内をしてくださった園長先生は理路整然と説明されていた。具体的な工夫の例が次から次と立て板に水が流れるように、口をついて出てくるのには本当に脱帽だった。保育環境の改革を実行したその園長先生、公立園の園長から転身し企業園の園長に。公立時代から環境を徹底して取り組む方だと私の園までうわさが聞こえるほどの先生でそういえば、お名前をお聞きしたこともあった・・・。その先生が全てを指揮し、子どもが主体的に落ち着いて遊べることをメインにそのための雰囲気作りを、とかなり努力されたことが伝わってきました。工夫の仕方に上品なセンスが感じられ、女性ならではの心配りがそこここにあった。保育士たちもその環境をベースにした保育を実践しているようだった。公立で培った様々なノウハウの粋を今まさに結集し、全体に実行できているのではないかとすら感じました。こういう環境と保育のコラボレートを創り上げるリーダーシップの実力を持った人材は、なかなかいないのではないかと思うが・・・公立園では今、団塊世代の園長が次々退職、ぜひこういう民間園に卓越した経験の知恵を皆さん、発揮していただければ、と日本の保育の質は確実に上がると思うのです・・・。
March 15, 2008
コメント(0)
-
家庭的保育
子どもと家族を応援する日本、重点戦略会議の中で議論になっている家庭的保育、フランスなどでもかなり取り入れているが、日本はなかなか成り手がない・・・昨日開かれた『乳児保育の基本』の公開研究会で特に話題に取り上げられたのがこの家庭的保育のことでした。0先生は熱意を持って今その会議の委員長として頑張ってくださっているのです。0先生は優しくて強い!母親たちにとても頼もしい存在です。2歳までの3人の子どもを保育する、この家庭的保育。その保育者の資格、報酬、2人制にすることあるいは保育園と家庭的保育を繋いでサテライト方式することなどの論議がまだ十分されていない段階だそうで・・。厚労省の方々もそれ相応に勉強はしていると思うのだけれど、『母親」経験者ならだれでも保育ができるとして、安易に考え普及させようとしていたらこわ~いです。厚労省は今児童福祉法を変えて、この家庭的保育をすすめようとしています。厚労省のヒアリングを受けたある先生が家庭的保育のように女性が携わるケアワークは専門性を軽視しがち・・ということが会議資料で書かれていた。本当にそうです・・、ああいう会議に出ている偉い方々、がっかりしてしまうことがとても多い。家庭的保育はこれからの時代の乳児の保育、あるいは学童保育などでもっともっと活用され、地域で子どもが育つネットワークとして広まるといいなあと以前から思っておりました。厚労省側ももっと事実をよく見て、議論をすすめてほしい・・
March 7, 2008
コメント(0)
-
啓蟄
今年の啓蟄は3月5日なのですが 今日夜7時くらいに園を出て、住宅街の道を同僚と 歩いていると、道端に大きなヒキガエル じっと動かずにいるので、もしや踏み潰されて しまったのか、と思わずじっと覗き込んだ あっ、生きてる、目を動かしてこっちを見たような・・ よかった、としばらく歩いていくと、きゃっ! 今度こそ、ヒキガエルが誰かに踏まれたのか 仰向けにひっくりかえって、つぶされたような感じで・・ 二匹ともに結構大きいので、なんとも・・・ 園の周囲は結構古い住宅街で、庭が広い家ばかり きっと家の立替でもなければ、結構代々住み着いて いる蛙たちなのかもしれない せっかく冬眠から目覚めたのに、道にでるなよ、蛙君
March 3, 2008
コメント(0)
-
オンエア・すくすく子育て
以前収録した某テレビ局の「すくすく子育て」今夜オンエア画面を見て、ど素人振りがなんとも、穴があったら入りたいほどの心境でした。司会の天野さん、つるのさんの流暢なお話しに、助けられやっとなんとかせりふを言っているのが誰にもありありとわかってしまう・・恥ずかしい限りでした。子育て中のママ、パパに少しでも育児のつらさや不安をやわらげたいという気持ちそれだけを精一杯こめてお話しできれば、と出演を承諾したのですが。そんな気持ちだけはなんとか、と思いましたが足はがくがく、口元がぴくぴく・・・でした。でも、まあ終わってほっとしました。夫や3人の子どもたちから鋭い批評、それでもちょっぴり褒めてもらい・・こんな場合はそんな感じでお茶を濁してもらうことが、なんだかとっても嬉しく思えて。本当によい経験になりました・・・(笑)
March 1, 2008
コメント(0)
-
フルスイング・・・4月から私も
保育園という職場に30余年、いよいよあと一ヶ月を残すばかり・・・ 少し早く退職し、4月から新たな出発、新米教員になります。 といっても、大学院の卒業を1年延ばして、まだまだ掛け持ちでは ありますが・・学び足りないものが山ほどあるので 学びながらの教員生活・・・学生さんと同じ立場でもあり、 この年齢で、とかなり引けてしまう自分ではありますが 色々な思いを膨らませています。 肩肘はらず、いつも自然体で、リラックスしながらも 元気が沸いてくる不思議なパワーが感じとれる授業をと・・ 欲ばりなことばかり考える自分なのです。 ここ何回かテレビドラマ「フルスイング」を見て なんだか自然に涙ぐんでしまって・・ 主人公は人柄が豊かでおおらかでなんとも素晴らしい 人だったようですので・・(実話)おこがましいのですが 要は残りの人生を、という部分に、私なりに思いを馳せています。 静かにフルスイングなスタートを切れるといいいなあと 少しどきどきしながら・・・そのときを待っています。 そして 残りの時間は子どもたちと思いっきり、たっぷり楽しもうっと!
February 24, 2008
コメント(4)
-
「赤ちゃんはおもしろい」乳児保育の講演会があります!
育児や乳児の保育に関心をお持ちの方へ ====================================================== 赤ちゃん保育研究会・公開研究会 ~『乳児保育の基本』をめぐって~ 昨年12月にフレーベル館より『乳児保育の基本』という本が出版されました。赤ちゃん保育研究会のメンバーである汐見稔幸氏、小西行郎氏、榊原洋一氏、大日向雅美氏らが執筆し、豊富な写真やイラストを使い、大変読みやすく役にたつ本として、今全国で話題になっています。当研究会では、本の執筆者でもある会のメンバーに、これからの乳児保育にとって、どういうことが大事になっているのかを語り合っていただくことを企画しました。この本の解説とともに、新たな時代に求められる乳児保育を大いに語り、討論し合ってみたいと思います。お誘い合わせの上ぜひご参加下さい。※参加費は無料です。◇語るひと:汐見稔幸 小西行郎 榊原洋一 大日向雅美(※) 佐伯裕子(ゲスト)◇日時:2008年3月6日(木)18時30分~20時50分◇場所:お茶の水女子大学共通講義棟2号館102教室 地下鉄丸の内線茗荷谷駅下車 徒歩7分 地下鉄有楽町線護国寺下車徒歩5分 『乳児保育の基本』 フレーベル館創立100周年記念出版として出されたもの。増大する乳児保育のニーズにもかかわらず、その原理は必ずしも明らかになっていない現実を克服する目的で編まれている。赤ちゃんについての最新の知識から、保育の実際、色、音などの環境づくりの原理、育児支援の実際、幼い子どもの障がいと保育、子どもの病気と園での対応に至るまで、乳児保育が直面する問題がほぼ押さえられています。
February 21, 2008
コメント(0)
-

蜜柑の香りと餃子の話し
年末、紀州は和歌山県新宮の蜜柑が送られてきた。箱を開けると、南国の何ともいえないコクのある甘い香り!箱を開けるたびに紀州の香りが漂う年始には伊豆の稲取から大きな蜜柑!箱を開けたとき、伊豆半島の段々畑の空気と酸味の強い蜜柑の香りが何とも言えず伊豆だった・・・一昨日は土佐戸波の文旦がいっぱい!この乾いたような香りは土佐、高知の風と土!いい香り! その土地土地の土と風のにおいがなんともいえない我が家はしばらく蜜柑談義、食後に蜜柑を向きながらその時々の話題に花咲かせる。今は冷凍餃子の話題・・学校給食、ファミレス、ファーストフード、老人の介護施設がその中国製食材を使用!今、全て輸入ストップになっているのですね・・・・・。近くの野菜、肉は高い、人件費も高い、ならば船賃郵送費をかけてもなお安い中国製餃子、というわけなのね・・・。我が家はもっぱら自家製冷凍餃子。3人の子育て中でも生協の餃子は注文しなかった・・・。我が家流の冷凍法は、作った1個1個の餃子を長方形のような弁当のふたを使って、そのふたの上に1個1個間隔をあけて餃子を並べ、一旦凍らしてから1回に焼いて食べる分量の個数を小分けに袋に入れて冷凍保存しておく!よく一列に並べて冷凍して、そのまま焼く、あれは見事にくっついて、お尻が破れることが多いので×。1回に100個、150個は作っている。餃子やさんになりきって、テレビを見ながら手先だけ動かして、作る。さて、これからは文旦談議、話しはどう続きますやら??・・・。
February 10, 2008
コメント(0)
-

子どもはトイレで育つ?!
トイレで遊んじゃだめ! トイレは汚い!そんなトイレのイメージを変えて、トイレに行くことが楽しみ、トイレこそきれいな場所!そんなポリシーを持って保育園のトイレのイメージを変える仕事をしている方に先日出会った。ある大学の先生の研究室で初対面で意気投合してしまい肝心の先生の用事をそっちのけで話に夢中になり帰りも一緒にバスに乗って話し込み、のらなければいけない駅を通り越し2つ先の駅まで・・・トイレの改修、設計から園と話し合い室内にトイレを作り、普段は遊具や椅子が置かれているように見えても、引っ張り出すとトイレに変身とか・・部屋のコーナーで、目隠しもあり、隣の洗面台はお・しゃ・れ!手もきっと何度でも洗いたがる雰囲気。2歳ごろなるとトイレに行っておしっこが出るようになるところ1歳台でトイレに自分で行き、オムツの取れるのが早くなったとか部屋の中に作るので、掃除も簡単、スリッパもない・・便器がまるごと部屋に出ているオープントイレもありますがお会いしたトイレプランナーというかアドバイザーの方が関わったところはいや~~面白い・・今の園のトイレの中ももっと変えられる可能性はきっとあるはずトイレを子どもたちの素敵な空間に・・
February 8, 2008
コメント(0)
-

新しい保育の本(写真がいっぱい)が出ました。
ここ数年保育園の0歳児入園希望が増えています!ベビーブーム?と思うほど、園の保護者が第二子を出産するので翌年の0歳児希望がすでに埋まっているという状態なのです。これはここ何年か子育て支援政策で企業などが少しは動き出してきたことまた、支援スポットの活動がかなり充実してきたこと、フランスなどの子育て家庭への優遇措置を改善する政策を世論が押し上げてきていることなどなど雇用環境でワークシェアリングなどの思い切った改革的な動きはないものの、M字型は幾分改善されそうな見通し・・・?そんな社会状況で、保育園の乳児保育が一挙に拡大していく様相があります。とはいえ、規制緩和は相変わらず、施設や保育の質に関する条件は整備はされていないので、先行きの不安は免れない。『乳児保育の基本』はそのような時期に人間の一番基礎、土台を作る時期、乳児期の育ちをあらゆる分野から見ていく必要を説き経験と科学を十分に生かしながら保育をしていく必要があると保育学、小児科学、心理学、脳科学、教育学などの分野からそれぞれの専門家が執筆し、編纂された本です。保育者も育児をする親にも読みやすく、写真も多く使用されて作られています。 http://item.rakuten.co.jp/book/5272114/ 乳児保育が今後ますます広がっていくことは明らかです。 子どもへの責任として、人生の第一歩を親ではない人、保育に託す のなら、より質の高い保育をと切に願うばかりです。
January 27, 2008
コメント(0)
-
笑い・子どもたちのユーモア詩と増田修治先生
笑う角には福来る!穏やかなお正月でした。5日朝、読売新聞(関東版?)の3面を開くと、あれ?増田先生が・・・。朝霞の小学校の教員をしていて、ずっと前から担任した子どもたちに日々生活詩を書かせる授業実践をされているので、そのことが記事になっていました。家族との生活の中で感じた様々な出来ごと、親子の笑いあふれるやりとりがリアルに詩になって表現されています。増田先生は普段は友だちのように子どもたちの言葉を受け止めていても行き詰ったり、子どもの詩の中に読み取れる微妙な感情にも細やかに対応したり、時には詩の中の子どもの様子が心配になってくると相談相手になったり、とユーモアを介して人間としての大事なものは何かを伝えようとしていると思っています。数年前、ぜひ保育者にもその詩の話しをしてほしいと保育研究会の講師をお願いして、今ではあちこちでひっぱりだこ、いつだったか徹子の部屋にも主演したり、NHKの「人間ドキュメント」にも出演したり昨日は新聞の3面記事と子ども同士や親子、教師と子ども、大人と子どものコミュニケーションが上手くできない世の中、ユーモアというゆとりを持って周りを見回しながら、人間のことを考えてみようと教えてくださっていると思っています。めがねの奥の優しいまなざしに子どもは安心して心を開いていると思います。子どもの言葉を書き留めておき、改めて子どもの感性の素晴らしさを感じたいなーと・・つくづく思いました。
January 5, 2008
コメント(2)
-
認証保育所200箇所設置し、園児を1万5千人増加
2007年12月22日12:38 都の10年後の東京のプランとして 子育ての応援事業の中で女性の特殊出生率を上げるために 認証保育所を200箇所以上増やす計画を21日に発表した。 全国一低い特殊出生率をなんとか上げたいというプラン の目標だそうである。 もともと未認可の保育施設の底上げ、あるいは企業の保育事業参入を すすめるために、規制緩和を早くからしいて、ビルの中、駅中という足 の便利な場所で保育施設を設置させる条件をつけている。 ここ数年ビルの中も庭のない保育所も色々と見てあるいてきた。 保育士は無資格者が半分というところもあった、 25人0歳の赤ちゃんから満3歳の子どもまで一部屋というところ あるいは5歳まで一部屋というところもあった。 今まで0歳は0歳室、1・2歳はそれぞれの部屋、あるいは庭も・・・ 必須条件だったが、そこが変わった。 昔から未認可で、アパートの一室でという小規模な保育所は あるにはあったが、それはその条件では保育が難しいから 行政に助成金を申し入れる運動、バザーなどで資金を調達する 保護者との共同の子どものための保育運動につなげていた。 今はそのままの保育施設の条件で半分公的に設置が認めれている。 未資格者であっても運営上の資金を低コストに抑える ためには当然のようになったし、 有資格者でも一年間の契約雇用も多くなり、ボーナスを 支給は対象外となり、結果的に保育士の年間収入の全国平均額は 低くなる一方である。 保育という子どもを中心に考えている職場だからこそ あがりこそすれ、低くなる一方なんてとんでもないと 思う。子どものことをいつも頭において考えて、 保育暦を積み重ねてきた この専門家集団としてのアイデンティティは一体どこへ行くのか 子どもの発達を重要視した保育の環境条件の整備は だれの課題なのか、何も見えてこない・・プランだ。
December 22, 2007
コメント(0)
全107件 (107件中 1-50件目)
-
-

- 子供服ってキリがない!
- 【全国送料無料】 お歳暮 冬ギフト …
- (2025-11-29 00:10:04)
-
-
-

- ミキハウスにはまりました
- ミキハウス好き限定!10%OFF+30%OF…
- (2025-11-28 16:10:05)
-
-
-

- 小学生ママの日記
- 衛生管理者1級を受験したい私
- (2025-11-28 17:00:07)
-