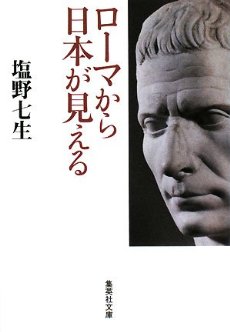
『ローマは一日してならず』
『郷に入っては郷に従え』
などが挙げられる。
古代ローマという国家のことは全くの無知でこれまで人生を過ごしてきた。
世界史を専攻していたわけでもなかったし、古代に滅んだ国家のことなんてどうでもいいじゃん、俺は日本人なんだから日本のことだけ知れればそれで充分。
そんな考えで今の今まで過ごしてきた。
では何故この本を手にしたかと問われれば、知人から薦められるともなく薦められてきたからである。
発刊からもうすぐ3年が経過しようとしている、足掛け3年でようやく私もこの本を読んでいるわけだ。
紹介してくれたことに感謝する
悪意に満ちた人はこの本のことを「ローマ人の物語」を売り出すためのプロパガンダ本だという。
それは、そうだ。
この本を読んで、素直に思ったのは「ローマ人の物語」を読んでみよう!ということだったから。
ただ、この本はローマ人たちの歴史を詳らかにすることが目的ではない。
悪意に満ちたレビューをしている人らは見落としている
「歴史は積み重ねられていく」、というたったそれだけのシンプルなことを。
私は今は一兵卒に過ぎないし、このまま一兵卒で終わるんだろうな、という諦めのようなものに襲われることも増えてきた。
でも、ここで諦めてしまってはいけないよな。
せめて軍団長くらいにはなりたいし、その資質は0ではないだろう、とも思う。
ともかく、一兵卒は一兵卒の職務を全うしなければならないが、上に立つ者の視点なり、考え方なりを得ようとする努力を惜しんではいけない。
英雄ではない者が英雄譚を読んでしまうと却って毒にもなりかねない。
的確な例えかどうか、ヤクザ映画を観て映画館を出てヤクザのように振舞えば身を持ち崩す、そんな感じ。
薬とするにはヤクザの世界を知ること、毒になるのはヤクザになろうとすること。
それからすれば、英雄の真似をすることは毒であり、英雄の考え方や行動動機を知ることは薬である。
うまくこの「薬」のエッセンスを取り出してくれているのがこの本。
システムの話が非常に興味深い。
佐野元春が1989年に出した「ナポレオンフィッシュと泳ぐ日」の中に「愛のシステム」という曲がある。
その詩に「正しいというとき、間違いと言われる」
この詩から、私は当時の佐野さんが音楽業界の中での常識が佐野さんの非常識に映り、邦楽の未来を憂えていたんだろうな、ということ。
システムというものは常に時代によって、環境によって変えなければならない。
素晴らしいシステムであっても、時の変遷、内的環境、外的環境により老朽化していく、という指摘、その根拠にローマという国家を例に取って教えてもらい、頷きながら読み進めた。
その他にも沢山インスパイアされる教えがあるはず。
志を持とうとする世代にも是非読んで欲しい。
第1章 なぜ今、「古代ローマ」なのか
第2章 かくしてローマは誕生した
第3章 共和政は一日にしてならず
第4章 「組織のローマ」、ここにあり
第5章 ハンニバルの挑戦
第6章 勝者ゆえの混迷
第7章 「創造的天才」カエサル
第8章 「パクス・ロマーナ」への道
第9章 ローマから日本が見える
【特別付録】 英雄達の通信簿
-
男の肖像 2011.10.03
-
チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる… 2011.07.11
-
男たちへ フツウの男をフツウでない男に… 2011.05.24








