「メビウスの輪」13
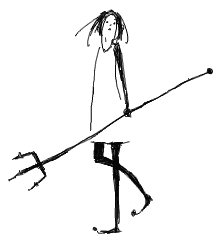
仕事に夢中になって、彼とあまり連絡とらなくなっていた。
よく「仕事と恋愛どちらが大事?」と言うけど、
男女が逆だよね。
彼のことが嫌いになったわけではないけど、
離れてても心は通じてると信じてる。
そう思ってるのは私の方だけかもしれないけど。
スクールカウンセラーの仕事は大変だけど、遣り甲斐がある。
とても他人事とは思えないけど、自分で背負ってはいけないんだよね。
客観的に見ることは難しい。
つい相談者の女子高生と自分を重ねてしまうのだ。
先日訪ねてきた美羽は、
なぜかあれ以来やってこない。
もう自分で解決できたのだろうか。
私は必要とされていないのかな。
その方が美羽にとってはいいはずなのに、
私は自分のために、美羽に来て欲しいと思ってるのだろうか。
少しでも手助けできたらいいと思ってはいるが、
自分の存在意義を求めてるような気もする。
それにしても、こんなんでいいのかな?
この部屋はただの溜り場じゃない。
私は娯楽室の管理人ではないのだ。
3年の女子高生達が入り浸ってるせいで、
美羽のような相談したい子が来れないのでは?と
常連の子達に出て行ってと言いたい衝動に駆られるが、
この子達はこの子達で、実は問題を抱えてるのかもしれない。
傍目からは幸せそうな子達に見えるけど、
本当に幸せだったら、こんなところにたむろしてないよね。
「ねえ、相談があるんだったら、何でも乗るよ。」
ダメ元で、ためしに声をかけてみる。
「えー、そんなのないよ。ただ暇だから来てるだけだよ。」
「それだったら悪いけど、今日はこの辺で帰ってくれないかな。
もしかしたら、本当に相談したい人がくるかもしれないし。」
穏やかに言ったつもりだったけど、
この子達にはきつく聞こえたかも。
「先生、相談したい子はこんなとこに来ないよ。
本当のカウンセリングとかに行くんじゃん?」
私より、この子達の方が、よっぽどきつい。
「でも、なんとなく悩んでる子は、
そういうこところに行きにくいんじゃないかしら?」
「そうかもね。先生くらいの人の方が気楽かもね。」
喜んでいいのか、悪いのか・・・。
先生と言いながら、私をカウンセラーと認めていないのが分かる。
「もし、何かあるんだったら、話相手になるけど?」
「ないから帰るよ。帰ろ、帰ろ!」
リーダー格の子が、他の子に呼びかける。
気に障って、もう来ないかな。
「また来ていいんだよ。」
少し下手に出てみる。
「いいよ。もう来ないよ。うざいな。」
完全に怒らせちゃったみたい。
「まあ、用が無いなら来なくてもいいけど。」
私も大人気ないな。
「いつでも話は聞くからね。」
それでも、一応念は押しておかないと。
ぞろぞろと帰る子達の最後に、
こちらを振り返りながら、
何か言いたそうな目をした子がいた。
ドアが閉まって、足跡が消えていく。
私は今までの相談に目を通そうと、
引き出しから書類を出していた。
突然、小さなノックの音。
「すみません。」
辺りをはばかるような囁き声。
「どうぞ。」
するりとドアをすり抜けるように入ってきたのは、
やはりさっき最後に振り返っていたあの子だった。
「どうしたの?」
「あの・・・」
下を向いたまま、口ごもっている。
「何か話があるの?」
「そうじゃなくて・・・。」
「じゃあ何?」
ちょっときつかったかな?
「なんでもいいから、こっちにきて座ったら?」
手招きすると、素直に来た。
「どうぞ」と椅子を勧めると、
手前にちょこんと腰掛けた。
まるでいつでも逃げ出せる体勢を取るように。
そのくせ、もう動けないという感じで、
ぐったりしてるのだ。
「何かあったの?」
「別に・・・。」
と言いながら、目はおどおどして落ち着かない。
この子は、さっきのグループの子だけど、
なぜか異色な雰囲気なのだ。
他の子達は、明るいというより、
傍若無人な感じだけど、
この子だけ、私の顔色を窺っている感じ。
前から気になってはいたんだよね。
「何でもいいよ。話したくないなら話さなくてもいいし、
話せることから話してみたら?」
努めて優しく言ってみる。
意を決したように
「実は、いじめられてるんです。」
と一気に吐き出した。
「いじめられてるって、誰に?」
「さっきのグループ全員から。」
「どんなふうに?」
「最初はパシリだけだったんだけど、
このごろは、トイレで・・・」
言葉が詰まってしまった。
無理に聞き出しても言えないだろう。
「いいんだよ。言いたくないことは言わなくても。
いじめなんて、辛かったね。」
そう言うと、堰が溢れたように、
彼女は泣き出してしまった。
私は立ち上がって、彼女の肩に手を置き、
「可哀想に。でも、よく話してくれたね。
もう大丈夫だよ。」と話しかけていた。
しばらく泣きじゃくっていたけど、
ようやく落ち着いて、話せるようになったらしい。
「すみません。つい・・・」
「いいのよ。泣きたいだけ泣いて。」
「もう泣かないって決めてたのに。」
「泣くのも心のためにはいいのよ。」
「でも、泣いたら負けみたいな気がして・・・。」
「勝ち負けじゃないよ。心が安らかになればいいのよ。」
「そうなのかなあ。」
なぜか、遠い目をして、窓の外を見た。
私もつられて、同じ方を見る。
「負けたくないっていう気持ちは大事だよ。
こういうふうに相談しに来てくれたってことは、
いじめに負けたくないからなんでしょ。」
「そうですね。でも、いじめられてる事自体、
もう負けてる気がする。それでもいいやと思ってたの。」
「でも、泣かないって・・・。」
「泣いたって、何も変わらない。
泣けば、ますますいじめられるんだ。
あの人たちを喜ばせるだけ。」
今度は無表情になってしまった。
「そう。人間は弱い動物だから、
自分より弱い人間を見るといじめたくなるのよね。
それでしか自分を強いと感じられないから。」
つい、日ごろ思ってることを口に出してしまった。
いじめを肯定してるわけじゃないけど、
いじめや差別は、いつの時代でも存在するから。
「そうだね。私だって、子供の頃いじめたことある。」
「じゃあ、いじめる気持ちも分かるの?」
「だから、抵抗しても無駄だと思ってた。
私以外にターゲットが見つかるまでと我慢してきたけど、
今のグループには、いそうにないんだよね。」
「そう。グループを抜けるわけにはいかないの?」
「そんなこと許されるわけがない。
それに傍目には仲良しグループなんだ。
私は単にパシリなだけ。」
「それだって、十分いじめでしょう。」
「どのグループにだって、パシリくらい居るさ。」
だんだんこの子も、言葉遣いが悪くなっていく。
地が出てきたということか。
「どうして、パシリだけではなくなってきたの?」
「具合の悪いときがあって、
どうしてもパシリが出来ないと断ったときがあったんだ。」
「そんなときも許されないの?」
「学校を休めばよかったのに、無理してきたから、
それほど悪いわけじゃないだろうと言われた。」
「休めばよかったね。」
「でも、休むと仮病じゃないかとか、不登校とか言われるんだよね。
私が休むとパシリが居なくて、困るんだろうよ。」
吐き捨てるように言う。
「休んでも、来ても、辛いということね。」
「休んで、家まで迎えに来られたときがあったんだ。
母親までコロっとだまされて、優しい友達ね、だと。」
「お母さんに言えば良かったのに。」
「言ったって仕方ないよ。学校や先生にチクられたら、
もっといじめられる。」
「じゃあ、私には?」
「先生は、教師じゃないからね。関係ないからいいのさ。」
「ただの相談相手ということ?」
「だから、担任には黙っててよ。」
「じゃあ、意味がないじゃない。」
「いいんだよ。吐き出したかっただけなんだから。」
「私に出来ることはないの?」
「今のところはね。」
無力感に襲われた。
私はどうしたらいいのだろうか?
呆然としてる私を見て
「話を聞いて、泣かせてくれただけでいいよ。」
まるで私を慰めるように言ってくれた。
立場が逆だな。
「あいつらに何も言うなよ。
これは私の問題なんだから。」
「分かったわ。
何かして欲しいことがあったら、言ってね。」
「泣きたくなったら来るよ。」
「哀しいこと言わないで。」
私の方が泣きたくなってしまう。
「泣いてもいいって、言ったじゃない。」
「そうだね。いつでも泣きに来て。」
「そんなに泣きたくないけどね。」
かすかに笑ってくれた。
少しは役に立てたのかな。
「じゃあね。ありがとう。」
その言葉が何より嬉しい。
「また来てね。」
「そのうちにね。」
また、美羽のように、
もう来ないのだろうか。
そういえば、名前を聞いていなかった。
「待って。名前は?」
「真砂(まさ)。」
「どういう字?」
「真実の砂だよ。」
「いい名前ね。」
「そうかな。」
真砂は、はにかむように言った。
「先生の名前は?」
初めて名前を聞かれた。
「幸恵よ。」
「ふーん。どんな字?」
「幸せに恵まれる。」
「幸せそうでいいね。」
「そうでもないけど。」
幸せだと思ったことはないな・・・。
「名前負けか。」
「そうかもね。」
「私もだよ。」
「真砂って、どういう意味なの?」
「まさごとも読むけどね。
砂浜なんかの砂みたいだよ。
でも、母親は鴎外の『うたかたの記』とか
こだわって付けたみたいだけどね。」
「小説はよく知らないけど、
お母さんの思い出なのかしら?」
「そうかもね。父親とあまり仲良くないから、
初恋の人との思い出とか言うんじゃない?」
「素敵ね。いい名前よ。」
「あんまり有難くないけどね。
それじゃもう帰るね。」
「気をつけてね。
また何かあったら来てね。」
「いつかね。」
真砂はそう言って、
今度は振り返らずに出て行った。
大丈夫かな?
またグループで来たときは、
どう対応したらいいだろう。
でも、あのリーダーの態度では、
もう来ないかもしれない。
そう願ってしまう弱い私だった。
続き
© Rakuten Group, Inc.






