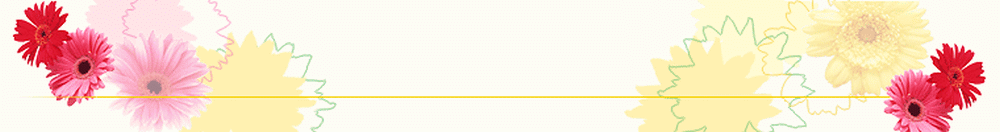奈良旅行「まひるの月をおいかけて」3日目
体の痛みは多少ありましたが、8時30分には、山辺の道ウォーキングを始めようということでホテルをチェックアウトしました。ホテルのご主人がウォーキングコースの紹介をしているホームページを印刷しておいてくれたので、ガイドブックと両方を持って出発です。
天理教の街だけあって(何度もいいますが・笑)朝出会う人達は半数以上が、「天理教」と背中に書かれた作務衣を着てました!高校生も高校の名前が袂に入ったものをコート代わりのように身につけていました。
二人でマックを探したのですが見つからず、さんざん彷徨った後、天理病院の前にあった朝からやってる!焼き肉屋さんでほぼ一日歩くことを考えてたくさん食べました(寒かったのもあって、朝から石焼きビビンバを食べてしまいました。)
天理教の本部を目指して歩いていくと、友人と私以外に信者はいないんじゃないだろうかと思うくらい天理教の作務衣を着た人たちがぞろぞろいて、ここはホントに日本?と心細くなりました。多分、何かの行事があったんだと思いますが全国各地から信者の方々が集まってるようでしたし、作務衣を着た高校生もたくさんいました。宗教というのはすごいですね。
天理教の立派な本殿やたくさん点在している宿泊坊を見ながら、山辺の道のスタート地点である石上神宮を目指します。天理教関連の敷地がもの凄く広くていくら歩いても神宮が目に入ってこなかったため、だんだん心配になってきましたが、とりあえず看板や敷石にはめこまれている「山辺の道」のマーク、道路に書かれている白い矢印(誰が書いてくれているのか不明ですが・・)に従って歩いていくと神社に続いていそうな道に入れました。静かな森の中にあるとても立派な神社です。
この石上神宮は、鶏が放し飼いされていることで有名だそうですが、思っていたより鶏たちがうろうろしていなくて、ちょっとがっかりしました(笑)。由緒ある神社で趣のある社殿が印象に残りました。物部氏の武器庫をかねていたという話もあったようです。
ここからがいわゆる山辺の道のスタートです。境内にある東屋のようなところで、ハイカー姿のおじ様、おば様達が地図を見ながら相談していたので、覗いてみると数パターンの行程表が置いてありました。私たちも一つもらって出発することにしました。もちろん、お社にお参りをしてからですが。
神社のある森の中を通り過ぎると、左手に池が見えてきます。釣り堀のようになっているようで会員になっていない人のつりは禁止だという看板が立っていました(この禁止の看板は行く先々で目にしました。奈良ではやたらに釣りをしてはいけないということなのか、時代がそのようになってきているのか、わかりませんが・・)。
細い道を進んでいくと民家の脇を通り、山の中へと道が続いています。ここからは、上りの道がだらだらと続いて、膝やふくらはぎが重く感じるようになりました。途中に内山永久寺の跡(太平記にも登場する坊舎50余を数える大寺院だったそうですが、明治4年に廃寺されており、現在は池しか残っていません。桜の名所だそうなので、やはり春に訪れたらよいのかも)、竹ノ内環濠集落、萱生環濠集落を通り抜け、柿やミカンの畑を見ながら、ひたすら歩きます。
念仏寺、中山大塚古墳、柿本人麻呂が妻の遺体を東側の山並みのどこかに埋葬したときの歌が書かれた碑の前を通過して、長岳寺に到着です。その前におみやげ物屋さんがあったので、抹茶のソフトクリームを購入しました。濃厚な味でおいしかったです。長岳寺はお花で有名だということでしたが、季節が季節だったため、あまり見る花がなかったのですが、庭にある紅葉の木が紅葉していてきれいでした。ハイカー達がたくさんいたのと、子ども連れの方がいたのも印象的でした。ここは、弘法大師の時代には周辺一帯が寺院だったそうですが、明治の廃仏き釈で衰え、今はほんの一部しか地所は残っておらず、兵どもが(というより僧ですか)夢の跡といった感じでした。入り口は藤原期の楼門で立派だったんですけど。
続いて、山の中の道を進んでいくと黒塚古墳、崇神天皇陵、景行天皇陵と古墳群が目の前に現れます。景行天皇はヤマトタケルのお父さんですね。この辺りで昼食をとっているハイカー達が何人かいました。私たちは、足のくたびれ具合は蓄積されていましたがなんとか歩き続けました。その後、卑弥呼庵という地元の方が自宅を開放してやってらっしゃる休息所で休憩したのですが、足がくたくたでした。ほうじ茶をいただいて休憩していると、ご主人か「ここから三輪さんが見えるんですよ。今日は天気もいいし、よく見えますよ」と教えてくれました。霞がかかることもあるそうですが、それはそれでいい雰囲気なのだそうです。地元の方は、三輪さんと親しげに呼ぶようです。
再び、山辺の道へ戻り次は穴師座兵主神社(あなしにいますひょうずじんじゃ)と檜原神社を目指します。穴師座兵主神社へ行く途中に草餅や甘酒を売っていたおじさんのところで休憩をとることにしました。昔は小屋を建てていたそうですが、景観保護条例に引っかかるということで青空の下での店開きです。それはそれでいいと思うのですが、おじさんは面倒だと・・草餅はおいしかったです。私たちが買った分で無くなってしまいましたが・・
穴師座兵主神社は、巻向山を登った所にあり、眺望が素晴らしいです。くたびれましたけど(笑)。昔はもっと山頂に近いところにあったそうですが、祭神などは不明です。一の鳥居横には相撲神社もありました。
檜原神社は、拝殿はなく三輪鳥居が立っているだけです。三輪山山中の磐座をご神体とするようですが、とても不思議な感じでした。昔は三輪山がご神体だったそうですね。伊勢神宮に天照大神が鎮座する前にここにいたということで、元伊勢とも呼ばれているようです。
三輪山へ向かうため山の中の道を歩き続けると、玄賓庵というお寺があります。謡曲「三輪」の舞台になっているそうですが、無教養のため「三輪」がわかりません。静かな雰囲気のお寺でした。年取ってこんなところに隠居するのもいいなと思いましたが、とにかく山の中です(笑)ここまでに至る道が一番大変だったかも・・足が痛かったし、細道だし。でも、途中で里芋から作ったおもちを食べたりしましたが・・温かくておいしかったです。
くたくたな状態で狭井神社へ。気が付くと大神神社(三輪山)に入っていました。この大神神社の祭神は、大国主大神ほか2神です。神話に登場する聖なる山である三輪山をご神体とするので神殿はありません。酒造、製薬、方除けの神としても名高いそうで、たくさんの参拝者がいました。ちょうど七五三シーズンだったのもあると思いますけど。
本当は、桜井駅まで歩く予定だったのですが、もう十分だということになり、三輪駅を目指しました。歩いて10分くらいのところにありましたが、すごく小さい駅でちょっとびくり。駅前も三輪そうめんのお店はありましたが、他に休めそうなところはなくて、お腹がすいていなかったので、駅のベンチでやすむことに。とにかく足が痛かったです(笑)。
電車ではあっという間に天理駅についたのですが、あの距離(12キロくらいですか)を頑張って歩いたのかと思うと自分をほめたい気持ちでした。天理駅で荷物をロッカーから出して電車に乗るかどうか悩みましたが、奈良駅までのバスが出ていることに気が付き、もう乗ってしまおうということになりました。周遊パスが使えなかったら、それまでだと思っていましたが、ちゃんと使えてラッキーでした。
ホテルにチェックイン、このチェックインのときに予約が一日ずれていて焦りましたが、早めにホテルに着いたので空いている部屋が一つだけあるということで事なきを得ました。本当によかったです。しかし、体中が痛み、またも友人と二人でマッサージ店を探して、足裏マッサージを受けてしまいました(私は、くたびれすぎて熱心ではなかったのですが、友人が携帯を駆使して探してくれて感謝です。)。
夕食は何故か中華料理。くたびれていたせいか、あまり食欲を感じませんでした。マッサージ師さんに聞いたんですが、奈良は名産というか、名物がないそうなんです。確かにそうでした(笑)。それでも、老舗で奈良漬けを購入してお土産としましたが・・
© Rakuten Group, Inc.