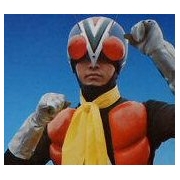PR
X
カレンダー
こどもの日
らるごenらるごさん
「岐阜県立加茂農林… 美濃加茂市さん
ジジくら♪ノヴァくら Tae.Tさん
大バーゲン 大(だい)さん
Kabocha's Diary Kabochaさん
ゆるーいロード乗り goukidさん
ハンサポの自閉症Dia… ハンサポさん
春風接人の花日記 春風接人2018さん
《兎菊》 ウサコと… 兎菊さん
ゆみんこ日記 ゆみんこchanさん
「岐阜県立加茂農林… 美濃加茂市さん
ジジくら♪ノヴァくら Tae.Tさん
大バーゲン 大(だい)さん
Kabocha's Diary Kabochaさん
ゆるーいロード乗り goukidさん
ハンサポの自閉症Dia… ハンサポさん
春風接人の花日記 春風接人2018さん
《兎菊》 ウサコと… 兎菊さん
ゆみんこ日記 ゆみんこchanさん
コメント新着
2025年05月
2025年04月
2025年03月
2025年04月
2025年03月
2025年02月
2025年01月
2025年01月
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 日々の出来事
最近、学校や施設との交渉にお悩みの方が何人かおられました。
こんなことで援護射撃になるかどうかはわかりませんが、少しでも交渉の際に役に立ちそうなネタをまとめておきたいと思います。
参考になりそうな資料として、
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/tokusyu/LDetc.pdf
美しくまとまった資料です。
管理職にそっぽを向かれないためにもぜひ!合わせて持参したい資料。
特別支援教育の推進について(通知)
具体的な支援方法はコチラ
先生が子どもたちのために明日からできること
※12・17追記
先生に渡す資料は、こんな書き方だとわかりやすい!
A-typeで行こう!~自閉症スペクトル一家の愉快な生活~
具体的な手だてについて、よくまとまっている文章はコレ
■特別支援教育の指導の工夫■
8月22、23の両日、国立女性教育会館で行われたワークショップ「発達障害と不登校」から、障害の理解と明日から役立つ指導の工夫などをまとめた。
■教室での対応は「できる範囲の工夫」から
「TTなどを含めた全校体制の下で、子どもが大部分の時間を過ごす通常の学級の中で、障害の特性に応じて授業者が毎日対応する。これだけでも6.3%の児童生徒のほとんどの面倒を見ることができる」。そのポイントは、刺激の調整と指示の工夫。
私たちの脳は意識しなくても、手前に見えているもの(図)とその背景(地)を区別している。聴覚も同様で、私たちは話をしている先生の声だけを自然に聴き分けることができる。図と地の区別ができない子は、廊下を歩く子どもの声や自動車の騒音など必要のない音まで、すべて拾ってしまう。音に過敏な子どもが多いのも特徴だ。
授業に集中しにくい子どもは、教室の座席を一番前にする。刺激が強いため窓際の席は避けたい。黒板の周囲には、学習の目当てなどの掲示物が張ってあることが多いが、これらを、例えばカーテンで隠し、掲示物はその子よりも後ろの範囲に張ると、板書に集中することができる。
運動会の時季は、毎時間のように、校庭などで練習が行われるために落ち着きがなくなってしまいがちだ。本人はこの期間、とてもつらい思いをしていることがある。刺激を少なくする方法としては、徒競走のスタートの合図を旗を振って行ったり、あらかじめ使う曲を知らせておくこともよい。
テストを行う際には、1枚に1問を提示し、それを問題の数だけ用意して、1枚ずつ解かせる。用紙はうすい水色の罫線のあるものがよいという。
■指示の出し方の工夫
指示は、1回で1つの動作を求めるのが原則。ただ、これだけでは、担任は授業中に何度も指示しなくてはならなくなる。そこで、「1回の指示で2つのことができるようにする」のが目標となる。
帰宅した子どもに、母親が制服を着替えてほしい場合、どのように指示したらよいのだろうか。「○○ちゃん。おうちの服に着替えてね」では、どのような行動をとるかというと、制服の上に、自宅用の服を重ねて着てしまう可能性がある。そこで、「○○ちゃん。制服をハンガーに掛けておいてね」と言う。制服を脱いで、裸のままでいることがない子であれば、ハンガーのそばに置いておいた服に着替えることができる。これで、1つの指示で「脱ぐ」「掛ける」「着替えの服を着る」の3つの動作ができたことになる。より効果的な指示を出せるようになるために先生自らが自分の指示を録音し、聴いて確かめてみるとよい。
子どもに指示を聴く姿勢ができても、その内容があいまいでは、子どもはどのように行動していいか分からない。また、言葉に含まれた意味をくみ取れず、言葉通りの意味にしか受け取れない傾向がある。授業中に、視線が宙を浮いていて落ち着かない子に、先生が「横を向くな!」と言ったら、横は向かないものの、上を見たり下を見たりと、相変わらずキョロキョロしていた事例がある。
自閉の子どもたちは、書いてあることに気を取られてしまい、問題行動を起こすことがある。校内の火災報知器のボタンを押してしまう子どもがいた。書いてあることをやってしまい、そのあとのことまで考えられないのが障害の特性だ。赤くて丸い消火栓の中央の透明なプラスチックに「おす」と書いてある。これにつられて報知器を鳴らしてしまっているのだ。
■本人の望む方法で学習に見通しを持たせる
1日にやることを一覧にして見ることができるようにすると、安心する子がいる。その一方、一覧になっているとかえって落ち着かず、やるべきことがめくり型にまとめられ、めくると次の内容が出てくる方を好む子もいる。これらは、視覚的に確認できることで安心感を得ている例だ。
ADHDの子は忘れ物が多い。担任が持ち物リストのメモを取らせるが、それをどこにしまったのか忘れてしまうくらいだ。このような場合には、担任は必ずそのメモをランドセルの決まったところに入れ、それを確認してから帰す。保護者もそのメモを確認するといった、学校と家庭の連携が必要だ。授業の時間ごとの持ち物リストをつくり、チェックさせることも重要だ。
■即時評価を取り入れ自己肯定感を高める
問題解決型の学習が苦手な子が多い。学習の場面で何をしたらよいか分かりにくいからだ。授業を進める際には、1コマを、例えば20分ごとに国語、算数といった具合にモジュール化して取り組ませると、本人は気分の切り替えができて学習に取り組みやすくなる。
評価活動は、50分授業であれば10分を5コマにわけて行うのがよい。ただし、50分トータルで評価をひとくくりにして行うと、5つの目標のうち1つでも達成できないと、本人は反省しなくてはならず、意欲が低下しやすくなる。10分ごとにその1コマをその場で評価する即時評価を実施すれば、授業内にあと何回か目標達成の機会が残り、達成できたときには自己評価とともに授業者の評価、同級生からの評価が得られ、自己肯定感を高めやすくなる。
こんなことで援護射撃になるかどうかはわかりませんが、少しでも交渉の際に役に立ちそうなネタをまとめておきたいと思います。
参考になりそうな資料として、
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/tokusyu/LDetc.pdf
美しくまとまった資料です。
管理職にそっぽを向かれないためにもぜひ!合わせて持参したい資料。
特別支援教育の推進について(通知)
具体的な支援方法はコチラ
先生が子どもたちのために明日からできること
※12・17追記
先生に渡す資料は、こんな書き方だとわかりやすい!
A-typeで行こう!~自閉症スペクトル一家の愉快な生活~
具体的な手だてについて、よくまとまっている文章はコレ
■特別支援教育の指導の工夫■
8月22、23の両日、国立女性教育会館で行われたワークショップ「発達障害と不登校」から、障害の理解と明日から役立つ指導の工夫などをまとめた。
■教室での対応は「できる範囲の工夫」から
「TTなどを含めた全校体制の下で、子どもが大部分の時間を過ごす通常の学級の中で、障害の特性に応じて授業者が毎日対応する。これだけでも6.3%の児童生徒のほとんどの面倒を見ることができる」。そのポイントは、刺激の調整と指示の工夫。
私たちの脳は意識しなくても、手前に見えているもの(図)とその背景(地)を区別している。聴覚も同様で、私たちは話をしている先生の声だけを自然に聴き分けることができる。図と地の区別ができない子は、廊下を歩く子どもの声や自動車の騒音など必要のない音まで、すべて拾ってしまう。音に過敏な子どもが多いのも特徴だ。
授業に集中しにくい子どもは、教室の座席を一番前にする。刺激が強いため窓際の席は避けたい。黒板の周囲には、学習の目当てなどの掲示物が張ってあることが多いが、これらを、例えばカーテンで隠し、掲示物はその子よりも後ろの範囲に張ると、板書に集中することができる。
運動会の時季は、毎時間のように、校庭などで練習が行われるために落ち着きがなくなってしまいがちだ。本人はこの期間、とてもつらい思いをしていることがある。刺激を少なくする方法としては、徒競走のスタートの合図を旗を振って行ったり、あらかじめ使う曲を知らせておくこともよい。
テストを行う際には、1枚に1問を提示し、それを問題の数だけ用意して、1枚ずつ解かせる。用紙はうすい水色の罫線のあるものがよいという。
■指示の出し方の工夫
指示は、1回で1つの動作を求めるのが原則。ただ、これだけでは、担任は授業中に何度も指示しなくてはならなくなる。そこで、「1回の指示で2つのことができるようにする」のが目標となる。
帰宅した子どもに、母親が制服を着替えてほしい場合、どのように指示したらよいのだろうか。「○○ちゃん。おうちの服に着替えてね」では、どのような行動をとるかというと、制服の上に、自宅用の服を重ねて着てしまう可能性がある。そこで、「○○ちゃん。制服をハンガーに掛けておいてね」と言う。制服を脱いで、裸のままでいることがない子であれば、ハンガーのそばに置いておいた服に着替えることができる。これで、1つの指示で「脱ぐ」「掛ける」「着替えの服を着る」の3つの動作ができたことになる。より効果的な指示を出せるようになるために先生自らが自分の指示を録音し、聴いて確かめてみるとよい。
子どもに指示を聴く姿勢ができても、その内容があいまいでは、子どもはどのように行動していいか分からない。また、言葉に含まれた意味をくみ取れず、言葉通りの意味にしか受け取れない傾向がある。授業中に、視線が宙を浮いていて落ち着かない子に、先生が「横を向くな!」と言ったら、横は向かないものの、上を見たり下を見たりと、相変わらずキョロキョロしていた事例がある。
自閉の子どもたちは、書いてあることに気を取られてしまい、問題行動を起こすことがある。校内の火災報知器のボタンを押してしまう子どもがいた。書いてあることをやってしまい、そのあとのことまで考えられないのが障害の特性だ。赤くて丸い消火栓の中央の透明なプラスチックに「おす」と書いてある。これにつられて報知器を鳴らしてしまっているのだ。
■本人の望む方法で学習に見通しを持たせる
1日にやることを一覧にして見ることができるようにすると、安心する子がいる。その一方、一覧になっているとかえって落ち着かず、やるべきことがめくり型にまとめられ、めくると次の内容が出てくる方を好む子もいる。これらは、視覚的に確認できることで安心感を得ている例だ。
ADHDの子は忘れ物が多い。担任が持ち物リストのメモを取らせるが、それをどこにしまったのか忘れてしまうくらいだ。このような場合には、担任は必ずそのメモをランドセルの決まったところに入れ、それを確認してから帰す。保護者もそのメモを確認するといった、学校と家庭の連携が必要だ。授業の時間ごとの持ち物リストをつくり、チェックさせることも重要だ。
■即時評価を取り入れ自己肯定感を高める
問題解決型の学習が苦手な子が多い。学習の場面で何をしたらよいか分かりにくいからだ。授業を進める際には、1コマを、例えば20分ごとに国語、算数といった具合にモジュール化して取り組ませると、本人は気分の切り替えができて学習に取り組みやすくなる。
評価活動は、50分授業であれば10分を5コマにわけて行うのがよい。ただし、50分トータルで評価をひとくくりにして行うと、5つの目標のうち1つでも達成できないと、本人は反省しなくてはならず、意欲が低下しやすくなる。10分ごとにその1コマをその場で評価する即時評価を実施すれば、授業内にあと何回か目標達成の機会が残り、達成できたときには自己評価とともに授業者の評価、同級生からの評価が得られ、自己肯定感を高めやすくなる。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[日々の出来事] カテゴリの最新記事
-
あけましておめでとうございます。 2014年01月02日 コメント(1)
-
自分の職場の「待機訓練」が紹介されてい… 2013年11月26日
-
姪っ子達と遊んできました。 2013年11月09日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.