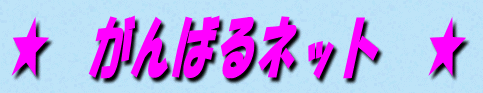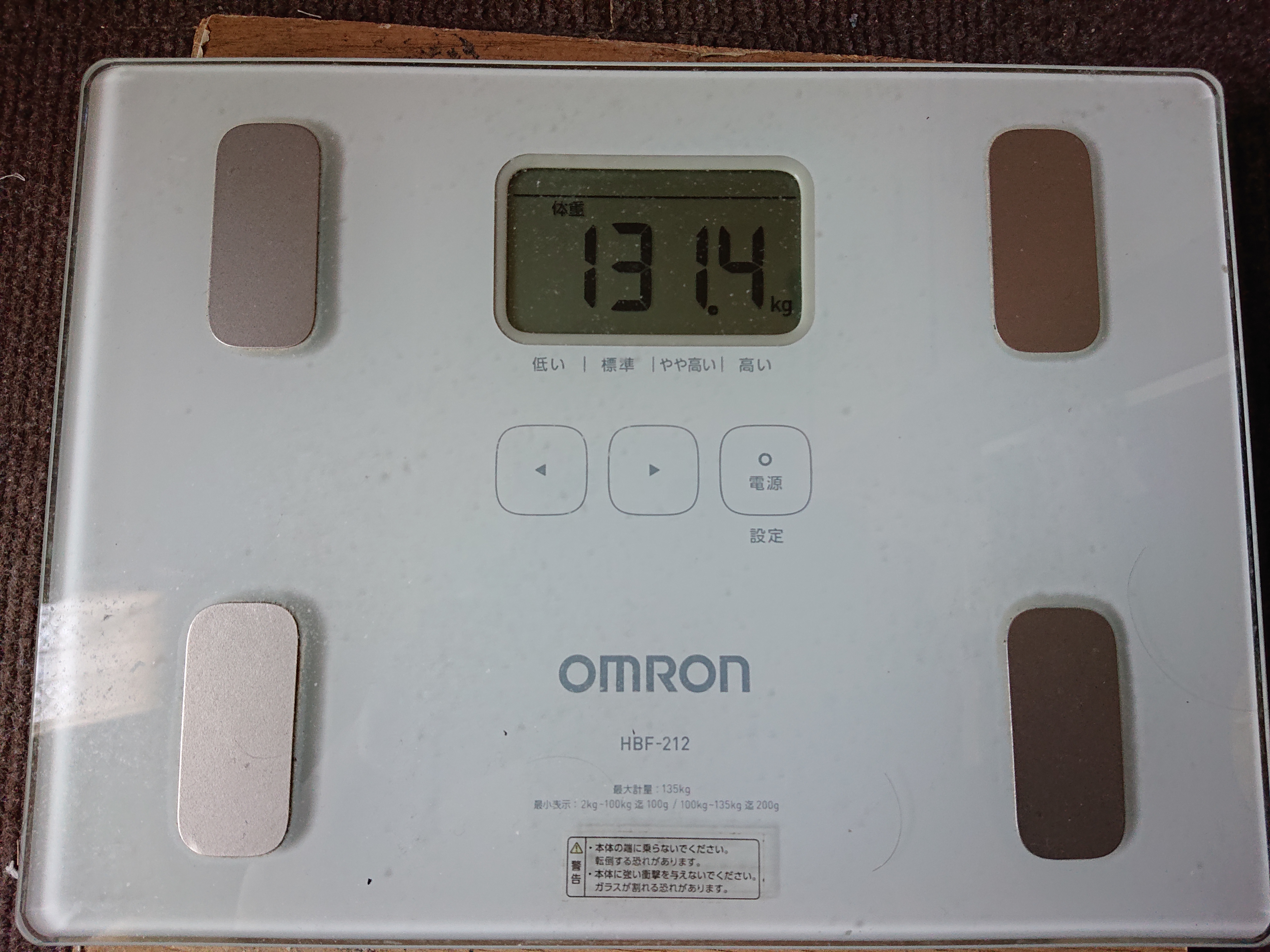『あなたの話はなぜ「通じない」のか』
http://plaza.rakuten.co.jp/sumsum/diary/
『あなたの話はなぜ「通じない」のか』 山田ズーニー (2) 04月24日(土)
★「うそで相手を操作してよいと思った時点で、すでに相手への尊敬はない。」(p23)
★「人と通じ合えないとき、新鮮な痛みを感じ続けられる人は、志が高い。」(p26)
★「「問い」なら通じ合える。」(p80)
★「表現されない自己は、無に等しい。」(p122)
【サラっとく?】
●あなたの話は「通じて」いますか? 「もっと論理的に話したい」、
「自分をうまく表現できない」、「聞き上手になりたい」、「信頼を得たい」…。
コミュニケーション能力の大切さが益々叫ばれるようになった現代において、
この本は1つの指南書になりえるかもしれません。
●コミュニケーション論について書かれた本は数多くあるのになぜ本書が?
それは、上辺だけのテクニックに留まらず、「コミュニケーション」の本質に
切り込んでいるから。「ゴールをはき違えた技術は虚しい」。まずは、
自分が相手と通じることによって何を得たいのか、それを明確にしていきたいです。
●話が「通じ合えない」といって嘆いている人はダメな人なのでしょうか?いや、
むしろ内面で関われないことに、深い悲しみを覚える人こそ本当に志が高い人だと、
著者はいいます。就職活動で面接官と通じ合おうとした時、告白して好きな人と
通じ合おうとした時、そこには誠実に相手との繋がりを求めた自分がいたはずです。
●では、通じ合うためにはウソをついたって、何したって構わないのか?著者は
実体験から、これを痛烈に批判しています。例えばウソで面接に受かった所で、
そこには、ウソで騙していい人間、そして実際に騙された愚かな人間、さらには、
己の気持ちにウソをついた自分しか存在しない。そんな職場で働く気がおきますか?
【突っ込んどく?】
●「「問い」なら通じ合える」。前半の【サラっとく?】がどの段落も、「問い」から
始まっていたのに気がつきましたか?始めに「問い」の共有化を図ることで、遥かに
論理展開がしやすくなっています。試しに初めの1文を抜かして読んでみて下さい。
●とても分かりづらいですよね。日本人は押しなべて
この「問い」をあやふやにして話を続けてしまう傾向にあるそうです。
先日、電車の中でOLのこんな会話を耳にしました。
A「○○の彼って背ー高くてカッコィィよねぇ」 B「うんうん、180あるとか言ってたよ」
A「うちの(会社の?)□□はちっこいけど可愛いよね」 B「んーそうだねぇ」
A「そーいえば、△△の彼がダイビングの資格取ったって。」 B「へー・・・」
●隣で聞いていた僕は「おいおい、なんでそこでいきなりダイビングやねん!」
と・・・思わず突っ込んでしまいたくなりました。Bさんも会話読めないで、
なんか一方通行んなってるし! 始めは○○の彼の話をするのかと思いきや、
ちっこい□□君がでてきて・・・「おっなんだ背の話か」と思ったら今度はダイビングが。
●これ、後の展開を聞くと「魅力的な男とは」ってテーマだったんです。
話の初めに「ステキな男いないかなぁ」とか「どんなのがカッコイイって思う?」
といった「問い」と共有していればBさんもそれなりのコメントができたはずです。
●「問い」の共有をせずに論議を始めると言うのは、サッカーゴールの設置もなしに、
いきなりドリブルを始めるようなものです。議論が迷走し、手痛い怪我を
負わないためにも、お互いしっかり「問い」は確認しましょう。
オススメ度★★★★★ 満点!
→コミュニケーション能力を磨きたい方
→プレゼン能力の向上を図りたい方
→あなたの話を「通じさせたい」方
『必ずこれからこうなる だからこう対処しよう』 船井幸雄 (1) 04月21日(水)
★「2012年12月23日に向けて時間は螺旋状に加速していく」(p66)
★「生命誕生のもととなったシューマン共振の周波数が急上昇している」(p94)
★「過去何十回とポールシフトが起きていることが証明された」(p78)j
★「ツキ、運をつけるためには長所に注力すればいい」(p205)
★「リストラ・解雇=短所是正は企業のツキを失わせる」(p213)
【サラっとく?】
●著者は、日本最大級のコンサルティング会社、船井総研の名誉会長です。
「経営指導の神様」としてビジネスの第一線で活躍するとともに、
これまでなんと200冊以上もの本を出版してきました。
●多くの識者や専門家と関わってきた経験からでしょうか、
その深遠な知識と鋭い洞察力に大変驚かされます。マクロの予測には大変強く、
これまで10年、20年先の予測については見事に的中させてきました。
●現代日本のノストラダムス、といったところでしょうか。
そんな著者が、「これから20年以内に起こる地球規模の大変革期を
いかに乗り切るか」という至上命題にフォーカスして書かれたのが本書です。
●始めて船井さんの著作を読む方には、少々異質に感じられるかもしれません。
「そんなばかな」と鼻で笑い、「それは違う」と反例を並べたてるのは簡単でしょう。
凡人と成功者について1つ言えることは、異質なものを突きつけられた時、
前者がまず否定材料を探すのに対し、後者は純粋な好奇の瞳を投げかける事です。
【突っ込んどく?】
●「2012年12月23日」この日に時間の加速が極限に達し、世界は変革を迎える。
これはテレス・マッケンナという研究者が提唱した「タイムウエーブ・ゼロ理論」
と呼ばれるもので、時代が進むとともに時間の流れが加速しているという説です。
●新しい文化や技術が登場するテンポは年々速くなっており、(ITを見れば顕著)
スポーツなどの記録が塗り替えられるまでの時間や、(最近は毎回出てますね)
流行・ファッションなどのサイクルも日を追うごとに速くなっています。
●これに関連して、絶滅種数の変遷を調べてみたら面白いことがわかりました。
恐竜時代は1年間に0.001種絶滅、1万年前には0.01種、1000年前には0.1種、
100年前には1年間に1種という具合に、絶滅への流れはどんどん加速しています。
現在はどれくらいだと思いますか?
●なんと今は1日に約100種の生物が絶滅しているとの事。
100年で約4万倍以上のスピードになっているんですね。
2012年には、1割近い生物がこの地球上から姿を消す計算になってしまいます。
●この「2012年」ですが、驚くべきことに、マヤ暦もグレゴリー暦に換算すると、
この2012年12月22日で終わっているのです。高度な天文学と数学の知識を持つ
マヤ人が完成させた、精緻な暦と言われるだけに、無視できない事実ですね。
タイムウェーブ・ゼロ理論とマヤ暦の予言日の奇妙な一致は何を示すのでしょう。
オススメ度★★★☆☆
→将来を見据えたい方
世界の危機を案じている方
変革期を乗り切る力を身につけたい方
『チャイナ・インパクト(前半)』 大前研一 04月12日(月)
★「中国の崩壊はもはや始まりようがない」(p40)
★「日本に流入してくる中国産の工業製品や農作物は、実は中国に進出した
日本メーカーや開発輸入を得意とする日本の商社が持ち込んできている。」(p12)
★「インドネシアの華僑たちは、絶対にインドネシアの政府にみつからないように、
そっと中国に投資をしはじめている。」(p112)
★「間接業務のユニクロ化」(p146)
【サラっとく?】
●以前、『斎藤隆のアイデア革命』の書評で紹介したy=f(x)の公式を覚えていますか?
フレームとなるfに要素xを組合す事で無数にアイデアyが生まれる・・・。
本を書くにしても、企画を練るにしても、高度なfをどれだけ持っているかが
重要になってくるという話でした。
●その点、大前研一氏のもつfは広範かつ高度であり、そこから生まれる
政策提言や将来予測には定評があります。マッキンゼーで培った分析能力、
経営学のシナリオ・プランニングの手法。中国の見方を根底から覆すような、
衝撃の内容が妙に説得力を帯びてみえるのも、偏にそのfのおかげでしょう。
●著者は米カリフォルニア大で公共政策を専門に、教授としても活躍しています。
その核となる「地域国家論」というフレーム(f)に中国という要素(x)を加え、
「中華連邦」という斬新な視点で、見事に現代中国を描ききったのが本書。
●本書が発行されたのは2年前。しかしその内容が以前として新鮮さを失わないのは、
それだけ現代中国の本質を突いているからでしょう。本書の中で、将来栄えると
指摘された地域では、早くも外資企業の誘致合戦やインフラ工事が本格化しています。
あなたの中国観は今のままで大丈夫ですか?
【突っ込んどく?】
●中国の崩壊はもはや始まりようがない・・・序盤で崩壊論者の意見が覆されます。
中国はもはや一つの国家ではなく、いくつかの地域国家からなる連邦と捉えるべき。
上海周辺の長江デルタ、香港・深釧周辺の珠江デルタなどがその代表例です。
●こういった地域が互いに競争しながら外資を呼び込んでいます。中国は賢明にも、
外資が工場を設置する際、研究所開設を条件に、中国人技術者の養成を図っています。
瞬く間に技術をキャッチアップしていく姿にも納得がいきますね。
●このように外資を巧みに利用する「貸席経済」方式で経済発展しているの現状。
ちなみに、世界を見渡すと繁栄中の国は、
アメリカを筆頭にほとんどが、こういった「貸席経済」体制で伸びています。
●対して、島国かつ単一民族国家の日本は・・・? 外資ホテルや銀行に対する反応は、
さながら自習中の教室に入ってきた教師に向けられる様な、排除的なものです。
政府についても、数年前のセーフガードの例を見ればその姿勢の固さが窺えます。
●「間接業務のユニクロ化」とはパソコンの入力業務やコールセンター業務など、
生産部門だけでなく、間接部門も人件費の安い中国に移転してしまうという構想。
これが実現できるのは中国の中でも日本語が堪能で、歴史的につながりの深い
○○省だけ。中国を利用して「勝ち組」になりたい方はゼヒ本書でお確かめを☆
(ページ数はそれほど多くはありませんが、内容がとっっても濃いぃので
2回にわたり取りあげます。後半をお楽しみに。)
『チャイナ・インパクト(後半)』 大前研一 (4) 04月15日(木)
★「この繁栄はあと10年が経過すれば終焉を迎える可能性が高い。」(p176)
★「空洞化するということは産業にとって極めて健康なことだ。」(p266)
★「中国に行って失敗した会社のほうが、うまくいった会社よりも多いわけで、
そのトラウマが、われわれの中国を見る目を曇らせている。」(p287)
【サラっとく?】
●前回に引き続き、大前研一著「チャイナ・インパクト」をご紹介します。
大まかな構成としては、前半で中国の競争力と、それを支える6つの
地域国家(工業地帯)について分析が行われます。
●これらは、その構成単位がそれぞれ1億人規模といわれています(ちなみに、
日本は現在1億2千万超)。さらにGDPで見ても、長江デルタなどは、
既にタイやインドネシアを抜き、台湾に肉薄する勢いです。
中国を一つの単位としか見ないことの愚を感じさせられます。
●後半では、中国という国家をアジアとの繋がり、さらには日本との関わりといった
視点から読み解いていきます。大前氏ならではの政策的な観点が
盛り込まれていて、非常に読み応えのある部分になっています。
●政策についていえば、「道州制」は氏が10年以上一貫して唱え続けているものです。
そもそもボーダレス社会、ネットワーク社会において中央集権の制度にムリがあり、
先進国でこれを維持しているのは今や日本だけです。遠くない未来、
「道州連邦」として日本が生まれ変わる日がくるかもしれませんね。
【突っ込んどく?】
●多くのチャイナ・ウォッチャーも「北京五輪までは」このまま発展が続くとしています。
逆に10年後は、発展が鈍化し、矛盾が噴出している可能性が高いということ。
具体的には、不良債権問題・失業問題・都市と農村の格差問題など。
ただこういったものは昔からあるし、日本だって同じような問題を抱えています。
●著者が中国特有のリスクとして挙げているのが「一人っ子政策」の弊害です。
生まれた子供はいわゆる「小皇帝」として溺愛されて育っているため、
今の中国人に備わっているようなハングリー精神がないとのこと。
●こういった子供が成長し、産業の担い手となるのが10年後なのです。
現に多くの経営者達は、今の新入社員を見て「中国はあと10年で全てやり尽くす
必要がある」と述べているようです。
●「空洞化が産業にとって健康」?? どういうことでしょうか。 空洞化を
<国税による助けを求めず、自ら国外で活路を見出していけるような競争力のある
企業があるということ> と捉えると分かりやすいかもしれません。
世界中で活躍するネスレ・グループを例にしましょう。
●ネスレの工場は世界50カ国にあり、スイスにある本社では研修機能があるのみ。
それでも国や街が衰えているといった印象は全く無いとのことです。
よく考えれば付加価値の一番高い部分を国内で行っているのだから当然ですね。
目の前の悲観論・崩壊論に囚われず、本質を見抜く力を身につけたいものです。
オススメ度★★★★★ 満点!!
→経営者、幹部の方
学生・ビジネスマン
チャンスにのっチャイナ!
『中国株で資産5倍』 今井きよし 04月18日(日)
★「注意深い楽観、そんな視線が投資者にとって肝心である」(p35)
★「極端な強気も極端な弱気も当たらない。これが歴史の教訓であろう。」(p95)
★「中国特需で一番潤っているのは海運業、造船業かかもしれない。」(p118)
【サラっとく?】
●「中国株」と聞いて胡散臭いイメージを持つことが多いのではないでしょうか。
一昔前までは多くのチャイナ・ウォッチャーやエコノミストも頭ごなしに
否定していましたが、ここに来てどうやらある共通の認識が生まれたようです。
それが前回書いた「今後10年、中国は経済成長を続けるだろう」というもの。
●根拠として、まず1つに「世界の工場」としての中国から「世界の一大市場」への
変遷が挙げられます。安価な労働力を武器に低価格商品を生産する中国は、
これまでデフレ工場として世界中に恐れられてきました。それが現在は、
原材料をはじめ、石油や部品などをも大量輸入する一大消費地となったのです。
●ちなみに日本の輸出の7割以上が中国向けです。中国の食欲旺盛ぶりは、
IEAが(国際エネルギー機関)が、「中国の大量輸入によって、
石油価格が高止まりするのでは」というレポートを出していることからも
見て取れます。まさにインフレをもたらす世界の巨大胃袋といったところですね。
●二つ目の理由は、北京オリンピックと上海万博という二大イベントを抱える事。
プライドの高い中国人のことですから、
国家と民族の威信をかけて国際舞台を演出するはずです。
ならばインフラや製造業を中心に急成長が見込まれることは間違いなし。
●そういえば、これと似たような記憶がありませんか?
64年にオリンピック、70年に万博という二大イベントを迎えたのち、
未曾有の経済成長を遂げた国がどこかにもあったような気がします。
【突っ込んどく?】
●極端な強気も極端な弱気も当たらない・・・歴史を見ればその通りかも。
1970年代に日本が急成長したときはどうだったのでしょう。実はこのときも、
ブレジンスキーの『ひ弱な日本』に代表される悲観論と、エズラ・ボーゲルの
『ジャパン・アズ・ナンバーワン』に見られる楽観論が錯綜しました。
●結果はどうかというと、高度成長を遂げるも、バブル崩壊とともに長期停滞に…。
どちらも当たっていたといえばそうだし、外れといえば外れです。
時を超え、現在も中国に関して、大前研一氏が『チャイナ・インパクト』を、
ゴードン・チャン氏が『やがて中国の崩壊が始まる』を発行しました。
●極論に凝り固まるのではなく、変化に合わせて柔軟に思考する姿勢が大切ですね。
「中国特需で一番潤っているのは・・・」というのは日本企業のことです。
中国向けの物資輸送が劇的に高まると、まず海運業界が盛り上がります。
すると今度は船自体が不足し始め、造船業界が大忙しという具合です。
●造船各社のドックは、現在なんと3年先まで受注済みになっているといいます。
○○汽船などはこの1年で株価が3倍近くに!!(どこかは買ってチェック笑)
このように、中国特需の影響は様々なところに波及するでしょう。株もやはり
最終的に大事なのは想像力ですね。高度成長期をよくよく思い出せば活路は見える?!
オススメ度★★☆☆☆
→投資家
年金などアテにせず暮らしたい方
シルバーライフをエンジョイしたい方
© Rakuten Group, Inc.