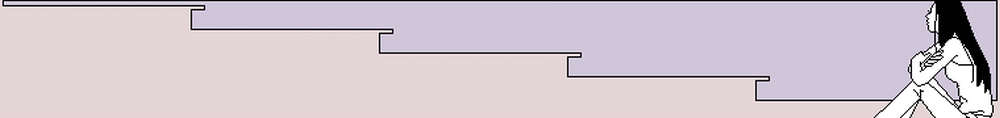お気に入りの本など

My 本棚の一部。
後ろに長塚節、前には大江健三郎、辻邦生、太宰治、「転向」前の吉本隆明等。
ふりかえれば、いつもそこに。
V.ウルフによると、人間を成長させるものはBooks and Relations。
つまり、本と人間関係であるらしい。(この本というのは教育という意味でもあるんだけど。)
私に関する限り、これは正しい。
嬉しいとき、悲しいとき。
人生のそれぞれの過程のポイントポイントで、常にその時その時の自分にあった本たちがそばにいてくれた。
私にとって本を読むというのは、毎日の生活の中で意識せずに行う習慣の一部であり、ごく自然なことだ。
My favorites(このページを完成する前に力尽きたので、本当にごく一部。大好きな日本の作家は
あとでつくろうと思ってたので、ここには入ってないし。
おいおい増やしていくよ~。
| The Unbearable Lightness of Being(存在の耐えられない軽さ) /Immortality(不滅)/ The Books of laughter and forgetfulness(笑いと忘却の書) |
| 一気に3つ載せるのはいかがなものか。と思いつつ、好きなんだもん。 しかし、なぜか英語で読んだから邦題をはじめてみたけど 「不滅」って違う気がするな~。 anyway。あの黒い下着姿の女の映画のポスターのせいで、ずっと誤解してました。この映画のこと。 だって当時濃厚なラブシーンばっかり話題になってたんだもん。映画もそれなりに良かったけど(ダニエルルイスが)、 やっぱり原作は映画のせいで損してると思う。デュラスの「愛人」みたいに。 でも、去年の夏かな。彼が「これは絶対君が気に入る本だよ」 と言って「存在の…」をくれたのは。すごく良かった。 もっと早く読めばよかった。その後、「笑いと…」以下貪り読みました。 「パリが占領下にあった時,あのときほど僕らは自由を感じたことはない。何故ならそれは僕らに唯一残されたものだったからだ。」云々はサルトルのお言葉。 要するに人間の尊厳も教育もあたりまえの暮らしも失ったそのときこそ、精神の自由、只ひとつ残された自由を毎日痛いほど意識して生きたのだ。という、ことで、あの頃は良かったという意味ではない。 この「存在の…」は、かなしくも痛ましい愛の話である。 どんどん差し迫っていく 状況。ヒトとしての自由,尊厳,何もかも奪われて,その状況下での絶えられないほどの自分という存在の軽さ。 人間の尊厳,自由,ヒトを愛するということ。こんなにも切ない愛の話。読んでくれい。 |
| Being foreign coutry means walking a tightrope high above the ground without the net afforded a person by the country where he has his family, colleagues, and friends, and where he can say what he has to say in a language he has known from his childhood. In Plague she was dependent on Tomas only when it came to the heart; here she was dependent on him for everything. What would happen to her if he abandoned her? Would she have to live her whole life in fear of losing him? |
| |
| 絶対でると思ったカミュ。何故かすごい好き。もちろん異邦人の衝撃から入ったけど。カミュが自動車事故で亡くなった日に、ある批評家が新聞に寄せて「何よりもある偉大なる劇作家がこの世を去った。」と書いたらしいが,私も彼の戯曲は一時かなりはまった。 カリギュラが好きでねえ。当時ホントに好きだったヒトに贈った記憶があります。「不条理」をひたすら追い求めていくカリギュラの絶望と狂気。自我のぶつかり合い。 激しい物語。と,ここまで書いて自己嫌悪。ちゃちい映画の宣伝みたい。こんな言葉では語れない何かがあるね。 ちなみに異邦人と幸福な死は、結構衝撃だった。既成の価値観にとらわれない、価値観の再マッピングみたいのがかなり新鮮で。要するに規定のモラルの中身のなさ、空々しさを鋭く突いてるところが。 彼はモダニズム文学の旗手。不条理文学の旗手とも言われるね。 現代に生きる人間が運命を何か目に見えない手に握られる<不条理>。人間がつくりだし、前述のように私たちを厳然と縛るモラル=価値観(特にヨーロッパ的なバイナリ-(二項対立的/キリスト教的価値観)の再マッピング。サルトルの影響で、哲学にも手を伸ばしたりした。「反抗の倫理」(?)は個人主義的な「反抗」によってのみ真のレジスタンスは可能だと言う彼の甚だ観念的な思想に対し、実践主義的哲学者であるサルトル(が最初に手を出したのではないが)が反論。有名な論争が勃発。長くなったので、この辺で。 何れにせよ、要所要所で、感覚と言うかそういうものがすごくしっくり来ることがあって、言葉の一つ一つが胸に染みて、ふとした拍子に手に取る作家の一人。 ちなみに今アマゾンで調べてみたら、カミュの手帳も反抗の論理も在庫切れ!!どうなってるの。日本の出版社(怒)。 |
| 旅の価値をなすもの,それは恐怖だ。その証拠に自国や自国の言葉からあまりにも遠くにいるとふとした瞬間に僕らは漠とした恐怖にとらわれ本能的にもとの習慣に避難したくなる。それはまごう事なき旅の収穫だ。そんな時には僕らは熱っぽく、だが多孔質になる。どんなに小さな衝撃にも体の奥底まで揺すぶられてしまう。滝のような光に遭遇するとそこに永遠が出現する。 それだから楽しみのために旅をするなど言ってはいけない。 永遠の感覚という僕らの最も奥にある感覚を研ぎ澄ますことを教養というなら、旅をするのは自分自身の教養を広げるためだ。パスカルの気晴らしが彼を神から遠ざけるように,喜びは僕らを自分自身から遠ざける。 ひとつのより大きな深甚な知恵としての旅は僕らを自分自身に連れ戻してくれる。 |
| |
| 辻邦生については昔ばあチャルさんの掲示板で語ったことがあって、そこから引用。 ああ。辻邦生。私は辻邦生についてなら数時間ノンストップで語っても良いのです~。 ところで,ワタクシ辻邦生について前回ちこっとばあチャルさんがおっしゃってたことってあたってると思うんですよね。 大好きなんですけど、女性という観点から見ると、辻邦生の創る女性ってちょっと綺麗すぎるかな~、お人形さんぽい(それこそ芸術作品っぽい?)っていうのかな。生々しくない。という感じがすることもたびたびあります。 前にも書かせていただいたように、彼は時々生の楽しみを歌うのですが、特に後期の作品についてちょっとTooMuchというか、ワタクシのような凡婦は おいおいおい。奇麗事ばっかり言って、君は今そう達観して楽しく生きてるかもしれないけどさ。人生ってもっと苦しいもんだぜ。 と反感を感じ(笑)(しかも長塚節とか読んだ後だと、更に深みがない!!と感じることがある。白樺派を馬鹿にして、逆から読んでバカラシ派と呼んだ人のような気持ち(笑))一時遠ざかっていたこともありました。 でも、どうしてその後また彼の本に戻ってきたかというと。 まず「西行花伝」がすごく良かったこと。 (ああ、後期のいくつか、どう考えても今だに馴染めない(全く共感できない)作品たちも、このために在ったのね。と思えた。) あと、これがすごく大きいんですが,イギリスに留学していた時に、あちらでは毎週毎週常に何冊ものリーディングを抱えていてそれをこなすことに追われるばっかりで(それはそれで非常に得るものが大きかったですが)日本の本を1年位全然読まなかった時期があったんですよね。それがあるとき,ふっとのどが渇いたように狂おしく日本の本が読みたくなったことがあって。で、何故かそのときに一番頭に浮かんだのが, 辻邦生が読みたい。 でした。 それでいてもたってもいられずに、実家からいくつか送ってもらったんです(ちなみに夏の砦と嵯峨野妙月記。当時最新刊の西行花伝でした。) それで、読んだときにず~っと英国、欧州の作品にばかり触れた後に読んでみると,勿論自分の母国語であるというのも大きいのでしょうが,乾いた土に水が染み込んでくるように(笑)、うわって圧倒的な色彩豊かなイメジャリーみたいのが流れ込んできた(くさい表現ですが)んですよね。 言葉の美しさに,その文章から匂うようなきめ細やかな情感に酔いしれちゃったわけです。 |
| 引用を入れる。 |
| |
| ボーヴォワールについても昔ばあチャルさんの掲示板で語ったことがあって、そこから引用。 で、ボーヴォワールなんです。第二の性などの書はとりあえず置いておいて,小説では、彼女の「招かれた女」、「他人の血」、「美しい映像」は私の読書歴の中でもかな~り高い位置に入るんです。 ああああ。ちょっと書いてるのがもどかしくなってきた。サルトルとの関係の中で,もしくは自身の思想を純化していく中で、人間として、女として苦悩や嫉妬などから目をそらさず、特に女であることを真摯にとらえ、文学作品として昇華した「招かれた女」等の前期の作品から、ぐっと老成してう~ん人間の孤独、を怖くなるほどに見つめた「美しい映像」、「危機の女」など後期の作品まで。 まあ、ワタクシのようなへなちょこが言うのもおこがましいのですが,時々怖いほど共感できるんですよね(多分もっと熟成したらもっと共感できるんだと思う)。 それら全部を乗り越えてたどり着くもの。「第二の性」で示された彼女の思いも、小説の中でより鮮やかに咲き誇ってると思うのです。 ちなみに、かな~り晩年に撮られた二人のドキュメンタリー(というかメインはサルトル)を見たことがあるんですが,もうすっかり年老いて思うように話せない(というか何いってるのか分からない)サルトルの横で,ボーヴォワールが通訳のように彼の思想を代弁し,労わって,共感というにはあまりにも強い同志愛みたいのがあるんですよね。それもまた印象的でした。 ちなみに、作品の完成度としては「美しい映像」などが一番高いと思うし、「招かれた女」はもはや私のバイブルだ。 しかしながら、最後のシーンの美しさで、「他人の血」が今の私の心を妙に打つ。絶望的に運命的に只一人の男を愛する女。男が参加するフランスのレジスタンス運動の組織に参加し、「活動」中に敵の襲撃を受けたのがもとで死にかけている女。その死の床の横で悔恨と苦悩の中、手に顔をうずめる男。そんなシーンで始まるこの本は、美しい。 最後の女の言葉を単に あ。実存主義ね。 と、とらえてはいけない。何故ならこの言葉の響きは、単に実存主義というのを超えた「女性であること」「人を愛すると言うこと」という普遍的な響きを持つからだ。 奢らないで。私に関して自分を責めるのはあなたの奢り。 自分が私を引き込んだと思わないで。あなたのせいで、私はこの活動に参加したんじゃない。あなたのせいで死ぬんじゃない。 私は私の意志であなたを愛したの。私がこの活動に加わることを決めたの。私の意志の結果、私は死んでいくの。 うんちゃらいうのがラストだったような。 |
| 引用を入れる。 |
| Jeeves&Woosterシリーズ/Lord Emsworthシリーズ |
| 一昨年から去年にかけてあたしの中で大ブームのコメディシリーズ。もういかにもイギリスらし~い喜劇で、特に万能のJeevesはAsk Jeeves!と言う名前のネットサーチエンジンがあるくらい有名。 神がかってみえるほど万能にして、格式を重んじ威厳に満ちたGentleman's gentleman(侍従とでも言うのかしら?執事的なことから主人の身の回りのこと割となんでもこなす)のジーブス(趣味はスピノザを読むこと)と、大金持ちで気立てがよいが賭け事に目がなくその人の良さと英国の坊ちゃんにありがちな馬鹿げた騎士道精神からすぐに厄介ごとに巻き込まれてしまうバーティ・ウースター二人のコンビが織り成す珍騒動。といったトコ。 それがねえ。いかんせん面白い。病み付きになる。「頭の中がおかしい」「どっかネジが抜けてる」「ジーブスはあなたの侍従どころかお目付け役ね」等々口うるさい叔母さん連中に白い目を向けられながらも、呑気にふらふらしてるバーティ(本質的に可愛いやつなのだ)と、滅多に感情を表に出さず、なすことなすこと全てパーフェクト、主人が厄介ごとに巻き込まれるたびにやすやすと助け出すジーブス。 この二人のやり取りはウィットに富み、もう抱腹絶倒。上流階級を揶揄するお得意のパターンね。 ちなみにこれはBBCでシリーズ化され、かなりの人気になりました。ヒュー・ローリーがバーティー、スティーブン・フライがジーブス役でホントにどっちもはまり役。DVD持ってるもんね。 |
| http://www.phill.co.uk/comedy/jeeves/ |
| まじめが肝心 /理想の夫/つまらぬ女/ウィンダミア夫人の扇/ |
| ワイルドも喜劇4つ選んでみる。ワイルドも高校生くらいのときにすんごいはまって青土社から出てる全集ばか高いのを無理して買いました。その後、英語版のCompleteWorksも買った。以来、ちょっとものが読みたいときとかコンスタントに手にとるかも。彼はエッセイとかも良い。芸術至上主義者の彼らしいエッセイ。Art for Art's sakeね。 ワイルドだけに、彼自身についてのドラマ、映画も多いし、彼の作品も最近特に、映画化、ドラマ化よくされるね(最近のルパート・エヴェレットが出てる「理想の夫(日本ではなぜか理想の結婚という映画になってた)はかなり良いぞ)。劇はロンドンに行けばどこかで一作は絶対やってる。あたしも6,7回位はいったよ。 まあそれはともかく、自分的には劇だったらやっぱりまじめが肝心かな。いかにもワイルドらしい、大らかでウィットに富んだ喜劇。舞台でもいくつか見たけど、やっぱり戯作は舞台で見るとまた一段と映える。 お気楽で茶目っ気たっぷり(というと聞こえがよいが…)芸術化肌のアルジャーノンと、彼の友人で堅実で生真面目なジョン。この二人それぞれの恋愛模様。喜劇にありがちないわゆるドタバタもの「取替え劇」だが、それもワイルドにかかると「あ。やられたぜ。」と思わずクスリニヤニヤしちゃう台詞でいっぱい。アルジー大好き♪。 ちなみにあたしはこの劇は幾つかの場面、引用いっぱいできるほど読みました。中でもセシリーの台詞は、一時面白がって自分の中でセシリーふりして生活する一人遊びをしてたのでかなり頭に入ってます(笑)。やばいね。 ちなみに、ワイルド自身についての映画なら上記↑ジーブス役のスティーブンフライがやったやつが一番いいね。 http://www.oscarwilde.com/ |
| これに関しては、かんなりいいHPを発見。映画を見た人は御覧あれ。 http://britannia.cool.ne.jp/cinema/title/tiobe.html |
| ハワーズエンド /眺めのある部屋/インドへの道 |
| どうでもいい話だが、カズオイシグロの小説を読んだ時、あ、フォスターに似ている、と思った。まあ、それはともかく。中庸を重んじ過度に走らなかったり、静かな抑えた美しい表現といい日本人好みのする小説家じゃないだろうか。(あと辻邦生にも似てると思う。ギリシアの体験が深い意味を持っているところなんかも。) フォスターには忘れられない思い出がある。(前書いたけど) 青春の1ページなんだよね。 まあそれはとにかく。フォスターはハワーズエンドの見開きの言葉、Only Connect!が示すように、異なるもの同士(国、階層、人種、男と女)をどう結びつけるのか。に、より思いをよせた人。 ハワーズエンドでは、階級、貧富、散文と情熱(性)(prose and passion)、等の 間の掛け橋を、眺め~では主に階級、新旧社会、インド~では国、人種、文化の間の掛け橋をかけることは可能か? そうであるならば、どのように可能か?が主要なテーマだ。(ちなみにハワーズエンド・眺めのいい部屋、どちらも映画化に関して非常に幸運だった、という共通点もある。ヘレンボナムカーターがいい!)。 炭鉱労働者の息子のローレンスのお友達だし、多分にロレンスの影響が見られるんだけど、あくまで富裕階級に批判的であったロレンスと違って、フォスターはもっとう~ん、他者への理解みたいな視点から書いてるかな~、とおもうのですが。どうでしょう? もう一つ。場所の力、場所の持つ霊みたいなのもポイントの一つ。ハワーズエンドでは、分別のある姉メグと多感な妹へレン(分別と多感やね。)を中心に話は進むけれど真の主人公はミセス・ウィルソンの愛したハワーズエンド、その土地であることは明らかだ。初期の短編ではギリシャが、後期ではイタリアが、人が真の自分を解き放ちこころのままに生きるきっかけとなる「土地の霊」との触れ合いがの瞬間がいとも美しくかかれている。(私がすきなのは、眺めの…のフィレンツェの広場のシーン。 Anyway,最後のもう一つ。ヘレンは大好きだ。多分最も好きな女性キャラクターの1人。それくらい大すき。 |
| Only connect! |
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- マンガハックさん閲覧数総まとめして…
- (2025-11-17 11:55:02)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0933 最強の経営者
- (2025-11-19 00:00:13)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 薬屋のひとりごと 9 日向夏
- (2025-11-19 15:40:42)
-
© Rakuten Group, Inc.