-
1
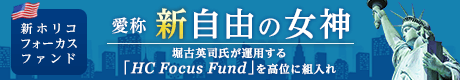
第358回 「治療が問題よりも悪くなってはならない」
“We cannot let the cure be worse than the problem itself.” (治療が問題よりも悪くなってはならない)これはアメリカの株式相場が安値を付けた3月23日の前後、トランプ大統領がツイッターで複数回に渡って発信したメッセージです。どういう事かというと、新型コロナウイルスは大きな問題だが、ロックダウンによって経済にそれよりも大きな問題をもたらしてはならない、という意味です。私を含め、このメッセージに安堵した人は多かったのではないかと思いますし、実際、3月23日以降株式相場が大きく反発している大きな要因の一つだと思います。 今、医療現場や薬の開発、必需品・サービスの供給に携わっている方々は英雄であり、尊敬の念しかありませんが、同様に政治に携わっている方々も大変だと思います。何故なら、新型コロナウイルスという未知の敵に対して、感染拡大阻止を優先すれば経済面の不安を感じた国民から批判が出るし、逆の立場を取れば人の命を犠牲にして経済を優先するのか、という批判が出て、さらに後になってから結果論で批判するのも簡単だからです。 とりわけニューヨークは中国・武漢よりも酷い状況となり、何よりも人の命を最優先しなければならない状況に陥りました。災害で言えば、災害後72時間の、全資源を人命救助に向けなければならない状態が、今回の場合は数週間続く見込みです。しかし災害時と同様、いつまでも自粛をしていては、国民生活の基盤である経済の方がやられてしまいます。災害は非常に不幸な出来事ですが、その後の自粛によって経済活動がストップしてしまえば二次災害に発展してしまうのと同様、人命救助を最優先する期間が過ぎれば、出来るだけ早く経済活動を元に戻さなければなりません。トランプ大統領が「その点は十分認識している」と世間に知らしめたのが上記ツイッターでのメッセージでした。 幸い、ニューヨークでの人命救助のための医療資源のピークは4月8日に過ぎたようです(米ワシントン大学IHME予想)。全米ベースでも4月11日がピークとなる見込みで、今後トランプ大統領は徐々に経済活動を意識した方向に政策を転換していくと見られます。恐らく今月のどこかで経済活動正常化への道筋は示されると見られますが、上記の通り「人の命を犠牲にして経済を優先するのか」という批判をするメディアは必ず出て来るでしょう。しかし経済は国民生活の根幹であり、こちらも人の命そのものであるという事を忘れてはなりません。 私はもちろん感染症の専門家ではないので私見になりますが、このバランスを取るには、政府に頼ることなく、民間の力で高齢の方と慢性疾患のある方を徹底的に守る以外方法は無いのだと思います。日本でも緊急事態宣言が発令され、39兆円(大々的に「108兆円」と発表するのは粉飾決算に近い行為だと思いますが)の経済対策が発表されましたが、財政に制約のある日本がいつまでも経済の負担を負えるはずがありません。新型コロナウイルスについてはまだ分からない事が多くありますが、少なくとも予防策としては風邪やインフルエンザと同様であり、そもそも普段から、高齢者や慢性疾患のある方にこれらの病気を移さないように気を付けなければならないのですから、今回を機に、民間ベースでこれを徹底するしかないのだと思います。それが出来れば経済を犠牲にする必要など無いのです。そして現在のような緊急を要する時期が過ぎれば、新型コロナウイルス対策は徐々にその方向に向かっていく可能性が高いと考えています。 さてそれを前提に、「新型コロナウイルス後」の市場を考えてみたいと思います。ここ数十年で、市場には様々な「ショック」と呼ばれるイベントがありました。その中で今回の新型コロナウイルスを位置付けるとすれば、「少し長めの一時的ショック」に他ならないと思います。何故ならリーマンショックを含め、歴史的にアメリカに約10年に1回に訪れるバランスシート調整のような、需要を先食いしてしまってその回復に数年かかるような性質のものではなく、需要は一時的に人工的に止められているだけであって、これは新型コロナウイルスの収束と共に必ず戻る性質のものであるからです。 もちろん一時的に失業率は急上昇し、経済成長率は大きく落ち込みますが、これらも新型コロナウイルスの収束を先行指標として回復することはほぼ確実であり、バランスシート調整のような厄介な問題ではありません。リーマンショック時のようなモラルハザードが無い分、景気対策も2兆ドルというとんでもない金額で実施できますし(アメリカのこの数字に粉飾決算はありません)、連銀はほぼ無制限の流動性供給に乗り出すことが出来ます。1日にダウが1000ドル以上も上下する状況が続く中、短期的な動向を予想する事にあまり意味は無いと思いますが、少し先を見た場合、史上最大規模の財政・金融政策が実行される中、株式が再び高値を回復するのに1年もかかることは無いのではないかと考えています。 むしろこれだけ無制限に流動性が供給され、財政政策が伴っている中、遂にインフレが起こる可能性が高まってきたと見るべきでしょう。インフレ懸念から長期金利が上昇しても短期金利は比較的長い間据え置かれる可能性が高く、イールドカーブの勾配が急になり、不良債権の増加が懸念される金融セクターはむしろ狙い目かと思います。また世界的に積極的な財政・金融政策が発動され、通貨の相対的価値が下がる中、ゴールド(金)は高値を目指すのではないでしょうか。まだまだ落ち着かない相場展開が続くと思いますが、このように市場が冷静さを失っている時こそ、色々な所に意外な投資機会が提供されている段階でもあると考えています。 (2020年4月9日記)
2020.04.09
閲覧総数 17542
-
2
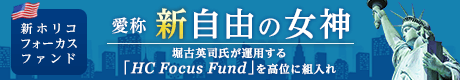
第359回 米国株、5つの質問にお答えします
先週の楽天証券21周年セミナーでは、事前に非常に多くのご質問をいただきました。興味深かったのは、これらご質問のほぼ全てが大きく、下記5つのテーマに当てはまるという事でした。ですので今回は、これら5つのテーマについて私なりの考えをお示ししておきたいと思います。 ① 経済と株式相場の乖離について最も多かったのが、来週発表されるアメリカの第2四半期GDPはマイナス35%予想、失業率も10%を上回る状況が続いている中、何故株式相場はほぼ高値を回復しているのか、というご質問でした。簡単に申し上げれば、株式というのは永久証券なので、如何なる経済ショックであってもそれが比較的短期のものであれば、本来株価に大きな影響があってはならない、という事になります。歴史的に見てみますと、リセッション時に株価が大きく下がるのはその通りなのですが、アメリカの場合ほとんどのリセッションは、需要を先食いしてしまってその後回復に何年かかるか分からない、という状況を嫌気するパターンです。その点で今回の新型コロナウイルスは恐らく、少し長めの短期的ショックという珍しいパターンなので、経済と株式相場の乖離を疑問視されている方が多くいらっしゃるのかもしれません。ちなみにこの点について、私は3月に相場が大きく下落する前からずっと申し上げてきており、むしろ株式相場を短期的ショックと結びつける3月の方が異常な状態だったと考えています。 ② 二番底はあるのか現在、S&P500指数は3月の安値から45%以上高い水準にあります。①の疑問や高所恐怖症もあって、この水準ではなかなか手が出ない、二番底があるならそれまで待とう、と考える方が多いのも理解できます。もちろん相場の事なのであらゆる可能性に対してゼロとは断言できませんが、私は限りなくゼロに近いだろうと考えています。というのは、安値を付けた3月23日の状況を思い出してみて下さい。感染者が爆発的に増加し、それに対する医療のキャパシティーが足りない、有効な治療薬も無い、ワクチンの開発など着手されていない、そもそもコロナの正体も分からない。経済活動はストップされ、生活の補償も無ければスーパーで生活物資も売り切れ続出、という真っ暗闇の状況です。逆に言えばこの先二番底が来るとすれば、これらの条件が全て整わなくてはなりません。同日FRBが空前の流動性供給に乗り出し、3月27日には2兆ドル超の経済対策が成立して現在実行中である事等も勘案すると、例え今後コロナ第二波が訪れようとも、再びあの水準を見る事は無いと考えるべきだと思います。 ③ どのような業種が狙い目か私は大きく5つのグループに分けて考えるようにしています。A. ほぼ無借金で、コロナがむしろサポート材料になる(ハイテク等)B. ほぼ無借金だが、コロナによる打撃は受ける(広告等)C. 借金があり、コロナによる打撃も受ける(半導体、住宅建設、金融等)D. 借金が多く、コロナにより大打撃(航空、ホテル、クルーズ等)E. コロナ前から厳しい(エネルギー、商業不動産等)現在はAからCが「投資適格」で、コロナ感染状況によってより積極的に(AよりB、BよりC)、と考える状況かと思います。米国政府の積極的なサポートにより、早ければ年内にもワクチンが利用可能になる見通しですが、そうなれば負債の状況を精査した上で、D.にも着手して良いかと思います。E.は長期投資には向いていないでしょう。 ④ 為替の動向株式相場と違い、為替は経済動向、とりわけ雇用情勢を反映していく可能性が高いと考えています。何故なら為替の大きな変動要因は金利であり、金利の大きな変動要因は雇用情勢であるからです。金融危機時に失われた雇用は800万人強ですが、現時点でかなり取り戻したとはいえ、ネットで約1300万人が雇用を失った状態です。FRBが2022年末まで現状の金融政策を変更しないと見通している通り、超緩和政策はかなり長く続くでしょう。金融危機後、ドル円は70円台を目指すことになりましたが、本格的な円高の進行は、2009年3月にアメリカが金融危機のピークを付けた後からでした。その点では当面、円高に対する警戒は強めておいた方が良いかと思います。幸い日米金利差は殆ど無くなっているため、為替のヘッジコストは気にしなくてよくなりました。米国株投資による為替リスクが気になる方は、状況に応じて各自で為替ヘッジされることをおすすめします。 ⑤ 大統領選挙の株価への影響ざっくりとした予想になりますが、現在優勢とされているバイデン候補が法人税減税の解消を提唱していることから、バイデン勝利の場合S&P500指数の2021年一株利益は150ドル、トランプ勝利の場合は170ドルと予想しています。現時点ではバイデン勝利の確率が約60%なので、市場は2021年一株利益158ドル((170-150)*0.4+150=158)を織り込んでいる事になります。ここから、バイデン勝利の場合、S&P500指数は5%下落(1-150÷158)、トランプ勝利の場合、7.5%上昇(170÷158-1)という影響が推測できます。ただ逆に言えば、株式相場への影響はたかが数%程度だという事になります。2016年の大統領選挙結果があまりにサプライズだったので警戒する向きが多いのは理解できますが、このように考えると大統領選挙の影響を過大視する必要は無いように思います。 (2020年7月24日記)
2020.07.27
閲覧総数 19081
-
3
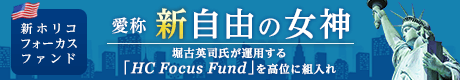
第360回 木を見て森を見ず
(この原稿は大統領選挙前々日の11月1日に執筆したものです)予想されたことではありますが、選挙が近付くにつれてメディア報道は大統領選挙一色となり、これによって市場も上下する展開となっています。とりわけ10月初めにはトランプ大統領自身が新型コロナウイルスに感染するというビッグ・サプライズが飛び出した事で、ますます注目度が高まっています。しかし市場への影響を考えた場合、恐らく現在、市場は大統領選挙の結果がもたらす影響を過大評価していて、実はもっともっと大きな市場のサポート材料を見過ごしているように見えます。まず選挙戦についてですが、2016年同様、メディアの9割は民主党候補支持の姿勢を示しているほか、世論調査を見てもオッズを見てもバイデン氏が優勢であることは間違いありません。さらに2016年の選挙で、サプライズとなったトランプ氏の勝利を正確に予想していたいくつかの指標も、今回はバイデン氏の勝利を予想しています。しかし2016年大統領選挙の経験から、市場には「やはり結果は蓋を開けてみなければ分からない」という不安が台頭しているようです。これはS&P500の変動率指数に表れていて、大統領選挙4日前の変動率指数は38という高水準を示しています。もちろん市場は選挙のような不透明要因を嫌がるものですが、金融危機と時期が重なっていた2008年以外では、大統領選挙4日前の変動率指数は概ね20前後に過ぎません。ちなみに2016年でも22.5で、今回は歴史的に見ても、如何に投資家の不安心理が高まっているかが分かります。感覚的には10%強程度のリスクプレミアムが織り込まれている形となり、要すれば大統領選挙が終了し、普通に結果が判明するだけで、(どちらが勝利したかにかかわらず)その後10%強程度のリターンは期待できる状態となっていると言えます。次にそれぞれの候補の勝利となった場合、株式市場にはどの程度の影響があるのでしょうか。両候補は様々な公約を掲げていますが、仮にそれがそのまま実現されると考えた場合でも、株式市場に大きな影響を与えるのは法人税率とキャピタルゲイン税率の変更くらいではないかと考えています。ただ法人税率とキャピタルゲイン税率の変更はいずれも、企業が株式で資金を調達する際の資本コストに影響を与えるため、影響は小さくありません。例えば税引き前利益が100円で、1,000円で取引されている株式があったとします。現行の税制では、法人税率は21%、キャピタルゲイン税率が23.8%ですから、法人レベルで21円の利益が差し引かれ、残った79円がそのままキャピタルゲインに結びついたとすると、キャピタルゲイン税19円(79円の23.8%)が差し引かれ、投資家には60円の利益が残る事になります。この結果、企業が投資家から資本を調達しているコストは10%(100円÷1,000円)、投資家が得ているリターンは6%(60円÷1,000円)という事になります。もしバイデン候補が勝利すると共に、上下院で民主党が過半数を取り、バイデン候補の提唱する法人税率28%への引き上げ、及びキャピタルゲイン税率最高43.4%への引き上げが実現したらどうなるでしょうか。キャピタルゲイン税を引いた後に投資家の元に60円残るためには、企業は106円(60円÷(1-43.3%))の税引き後利益を上げなければなりません。これは税引き前利益として147円(106円÷(1-28%))上げなければならないことになります。この結果、企業が投資家から資本を調達しているコストは14.7%(147円÷1,000円)となります。要するに、バイデン候補が勝利して公約通りの法人税率、キャピタルゲイン税率が適用されるようになると、企業の資本コストは10%から14.7%に上昇し、いわば企業にとっては資本の「利上げ」が行われるような状況になります。この5%近い資本コストの上昇は株式にとって小さな問題ではありません。公約通りの税制が実施されるのであれば、やはり中長期的にはトランプ大統領の方が株式市場に優しいと言えるでしょう。ただそもそも、アメリカの株式市場には退職金など非課税の資金、年金、外国人の資金などが大半を占めており、キャピタルゲイン税率が上記の通り適用されるのはごく一部の投資家のみと見られます。またキャピタルゲイン税率の上昇を見込んで株式を売却したとしても、その資金は再び株式市場に流入してくる性質のものと見られることから、キャピタルゲイン税率上昇の影響はそれほど大きくないと見て良いと思います。この結果、弊社では法人税率とキャピタルゲイン税率の変更による中長期的な株式市場への影響については、12%程度と試算しています。現在の市場は、いわゆるトリプルブルー(大統領-上院-下院の全てが民主党)を既に6割程度織り込んでいますから、トリプルブルーの場合は株式市場にとって4.8%(12%X40%)の下落要因、トランプ又は議会いずれか共和党勝利の場合は7.2%の上昇要因となります。これに先の、選挙が終わることによるリスクプレミアム低下分を加えると、トリプルブルーでも選挙後は5~10%の上昇が見込める計算になります。要するに重要なことは、これだけ騒がれている大統領選挙ですが、株式市場に影響を与える要因を積み上げていっても、たかが数%に過ぎないということです。そして現在市場は、このたかが数%しか影響を与えない「木」を注目し過ぎているように見えます。それでは「森」とは何でしょうか。それは今年3月以降実施されている超低金利政策であり、空前の流動性供給です。「森」の影響は中長期的に少なくとも数十%、場合によっては100%以上の株価押し上げ要因だと考えていますが、こちらは選挙のような不透明要素はなく、今後数年続く事がほぼ確実です。たかが数%しか影響が無い不透明な「木」ばかり見て、それを大きく上回る確実な「森」を見失わないことが重要な段階と考えています。(2020年11月1日記)
2020.11.02
閲覧総数 15337
-
4
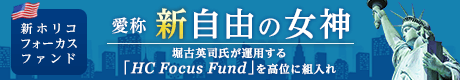
第361回 2021年の10大予測
2020年の株式市場は新型コロナウイルスの感染拡大状況に振り回され、当初は最も大きな注目材料になると考えられていた大統領選挙でさえ、相対的には小さな材料となってしまいました。ましてや新型コロナウイルス感染が拡大を始めた後でも、株式市場が一時的とはいえ35%もの下落を示すというのは大きなサプライズでした。このように市場というのは、あらかじめ予測できなかった事象に対してより、大きく反応するものです。その点では現時点で出来る予測というのは、そもそも限界があるものだと思います。その点を理解いただいた上で、現時点で2021年に向けた私なりの予測を示させていただきます。あくまで頭の体操程度にとらえ、皆様の2021年資産成長の参考にしていただければと思います。 1. S&P500指数は2021年後半に4300の高値を付けた後、4050で年末を迎える超低金利、空前の流動性供給に支えられて、アメリカの株式相場は引き続き堅調な展開。ただ景気の回復と共に金利の上昇が株式上昇の足かせとなる場面もしばしば訪れる。グロース株の多いナスダックのリスクは上昇サイドにあり、2万ドルを超えるなどのサプライズも想定しておく必要がある。2. 株式市場の変動率は年を通じて15を下回る場面は無く、ほぼ20を上回って推移世界的な超低金利を受けて、これまで株式市場にいなかった資金が株式市場に流入してくる。これらの資金は本来、リスクに耐えられないか、非常に敏感な性質の資金。「上がれば買う、下がれば売る」の動きを助長しやすいため、これまでの8年間あったような「ほぼ20以下」という変動率ではなくなる。3. 新型コロナウイルスの感染拡大は現在の第3波が最後、2021年初から減少に転じるアメリカの一日当たり新型コロナウイルス感染者数は2021年1月に50万人台(発表ベースで30万人台)でピークを打ち、減少に転じる。日本は検査が不十分な分、一日当たり感染者数は2021年2月に6万人台(発表ベースで3万人台)にまで急増するも、その後減少に転じる。世界的に見ても2月がピークとなる。4. ワクチンが一般に利用可能となるのは2021年6月、但し万能ではないファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンエンドジョンソンが開発した新型コロナウイルス・ワクチンは2021年春から一般に順次利用可能となり、希望者に対する接種は2021年秋以降の流行期までには間に合う。但しインフルエンザ同様、変異した、又は違ったタイプのウイルスには対応できず万能ではないため、各製薬会社は順次改良を迫られる。5. 2021年を通じて雇用の回復は400万人にとどまり、FRBの金融政策変更は無し新型コロナウイルスをきっかけに失われた「一時的雇用」のほぼ全ては2021年中に取り戻すものの、一時的でない雇用の回復は先延ばしとなる。「雇用の最大化」使命を課されたFRBは2021年中に超低金利、大規模な量的緩和の手を緩める事ができず、むしろ更なる緩和策を模索する状況が続く。6. 資産インフレが顕在化、金価格は年末に2500ドルを付ける 経済が正常化していくに従って、ドルの実質マイナス金利を嫌気した資金が株式市場や商品市場をはじめ、様々な市場に流れていく。金価格は年末に2500ドルを付ける。しかし雇用市場が厳しい状況では賃金の上昇は限定的なため、コアのインフレ率上昇にはつながらず、資産インフレとモノのインフレとの乖離が拡大していく。FRBはこの状況を容認する。7. ドル円は2021年前半に106円台を付けた後、年後半には95円方向新型コロナウイルスの感染拡大ピークに向けてドル円は堅調推移となるものの、せいぜい106円台が精一杯。感染が減少に転じると超低金利、空前の流動性の影響が為替相場にも出てきて、年後半にドル円は95円を付ける。しかし今回はアメリカだけでなく、日本やヨーロッパでも積極的な流動性供給が実施されているため、2011年のような大幅な円高にはつながらない。8. バリュー株は折に触れて見直されるものの、年を通じてグロース株のパフォーマンスが上回る経済の正常化を受けて、旅行、エネルギー、景気敏感、不動産、金融などのバリュー株が折に触れて見直される場面はあるものの、上昇は「回復」の域を出ない。2021年春には、一部バリュー株とされる企業が存続の危機に直面する場面も。低金利下でのグロースの価値は非常に大きいため、年を通じたパフォーマンスはグロース株がバリュー株を上回る。9. 2021年6月末のストレステスト後に銀行株が上昇銀行の貸倒償却額のピークは2021年4-6月期(決算発表は7月)に訪れるが、銀行は既にそれを大幅に上回る貸倒引当金を積んでおり、FRBは各銀行から提出された殆どの資本計画をそのまま承認する。2020年に増配・自社株買いが停止されていた分、2021年のストレステスト後に発表される株主還元策は大きく、銀行株は素直に反応、上昇する。10. 米10年物国債利回りの上昇は1.3%台までが精一杯、1%絡みの取引が続く経済の正常化と共に米10年物国債の利回りは堅調推移となるものの、上昇した場面では積極的な買いが入る。とりわけ、マイナス利回りで取引されている債券総額が史上最高の17兆ドルに上る中、米国債の1%超えは相対的に魅力的に映り、年を通じて1%絡みの取引に終始する。この結果実質金利はマイナスの状況が続く。 (2020年12月6日記)
2020.12.06
閲覧総数 22289
-
5
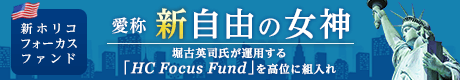
第362回 「ニンフレ懸念」~インフレを怖がり過ぎるリスク~
新型コロナウイルスワクチンが広く普及したアメリカで、現在株式市場にとって最も大きなリスクとされているのはインフレ、そしてそれに伴う量的緩和の縮小や長期金利の上昇でしょう。一般に、株式市場にとって大きなリスクとされているものであっても、それが材料として織り込まれてしまえば、下落要因にはなりません。従って現在大きなリスクとされているインフレのケースでも、実はインフレ動向そのものよりも、インフレがどれだけ市場に織り込まれているかを把握する方がずっと重要です。確かにインフレや、それに伴う量的緩和の縮小や長期金利の上昇は株式市場にとってマイナス要因ですが、現在、それらの織り込み具合は非常に面白い状況にあると思います。 2月に米10年物国債利回りが1%から1.5%に急騰したこともあり、長期金利の動向は市場の関心事のナンバー1と言ってもいいでしょう。そこでよくあるのが、市場関係者に向けたアンケートで「年末の米10年物国債利回りの水準は何%か?」というものです。通常、市況に関するアンケートというのは、サンプル数が十分にあるという条件の下では、現在の相場水準を中心に、釣り鐘型の分布図になるものです。相場の水準というのは市場参加者の総意を反映したものですから、当然と言えば当然です。実際、為替やダウ平均の年末の水準を問うようなアンケートは今でも、現在の相場水準を中心に、釣り鐘型の分布図になるものばかりです。 しかし最近、「年末の米10年物国債利回りの水準は何%か?」という問いに限ってはそうならないという特異現象が起こっています。予想の平均が2.0%前後に集中しており、釣り鐘型ではなく、高利回り方向に歪んだ分布になるのです。現在米10年物国債の利回りは約1.6%です。2.0%を予想する人がいるのであれば通常、それと同じ数の、1.2%を予想する人がいなければ相場は1.6%での取引にはなりません。理論上、市場参加者の総意が反映された結果が市場価格になるはずだからです。しかし現在、米10年物国債利回りに限ってはそうならないのです。これは何を意味するのでしょうか?私はこれは、市場がインフレ、そしてそれに伴う量的緩和の縮小や長期金利の上昇を織り込み過ぎるほど織り込んでしまっている証左だと考えています。インフレを怖がり過ぎるリスク、です。 この半年ほどの長期金利の上昇には、大きく2つの局面が挙げられます。第一に昨年11月、ファイザーが新型コロナウイルスに有効なワクチンを開発し、経済再開への期待が高まった局面です。このワクチン開発によって経済再開への道筋が立ち、期待インフレ率が上昇するに伴って、それまで1%を割っていた米10年物国債利回りは1%台前半にまで押し上げられました。ただ期待インフレ率が高まったと言っても、コロナ以降のディスインフレが正常化する程度であったことを忘れてはなりません。 第二の局面は2月以降、当初成立は困難と見られていたバイデン大統領による1.9兆ドルの景気対策成立の可能性が高まっていった局面です。この局面では米10年物国債利回りは1%台前半から一時1.8%まで上昇しました。これは同時にメディアを中心に「インフレ懸念が本格化してきた」と騒がれていた局面でもあります。確かにワクチン開発後、期待インフレ率は少しずつ上昇してきていましたが、この局面における長期金利の上昇の主役は期待インフレ率の上昇ではなく、実質金利の上昇であった点に注意が必要です。要するに、この局面での長期金利上昇は1.9兆ドルの景気対策によって一時的に債券市場の需給が崩れたのが原因であって、本質はインフレ懸念ではなかったということです。これは今後の株式相場の展開を占う上で非常に重要なポイントです。 昨年、コロナがもたらしたリセッションを私は「ニセッション」(偽のリセッション)と呼んでいました。何故なら通常のリセッションで起こるようなバランスシート調整は無いし、政府によるサポート等もあって、通常のリセッションで経験する個人所得の減少も無く、だからこそ今回のリセッションにおいては過去例を見ないほどいち早く株式市場が回復し、経済も正常化してきたのです。残念ながら「ニセッション」は流行語大賞の候補にも選ばれませんでしたが、コロナ後のリセッションが「ニセッション」だという判断は、その後、通常のリセッションでは有り得ない急回復となった株式相場を占う上で非常に重要だったと思います。 同様に、現在市場に蔓延しているインフレ懸念を、私は「ニンフレ懸念」(偽のインフレ懸念)と呼んでいます。コロナがもたらしたディスインフレの反動で物価が上昇しているだけなのに、これを持続的なインフレと勘違いし、それが量的金融緩和縮小や長期金利の急上昇につながる等の懸念が行き過ぎることによって大事な市場の動きを見逃してしまうことを指しています。ニセッションがそうであったように、こちらも流行語大賞の候補には入らないかもしれませんが、現在市場が抱いている懸念がニンフレ懸念だと認識できるかどうかによって、今後投資のパフォーマンスには大きく差が出てくると考えています。 つまり、現在市場が最も懸念しているリスクであるインフレ、そしてそれに伴う量的金融緩和の縮小や長期金利の上昇が起こらなかった時、又は先送りになった時、長期金利の上昇を待って待機していた大量の資金は置き去りにされることになります。そしてそれらの資金は結局、年後半に向けて株式相場を押し上げる大きな原動力になっていくと見ています。 (2021年5月31日記)
2021.06.01
閲覧総数 11536










