2019年03月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
松宮孝明『刑法各論講義』(成文堂,第5版,2018年)
西田典之(橋爪隆補訂)『刑法各論』(弘文堂、第7版、2018年)と比較してみる。頁数は、前掲・西田各論よりやや少ないが、文章は柔らかく、前掲・西田各論よりも言葉を尽くして説明しようとするところがある。前掲・西田各論よりも、更に進んだ議論を展開しており、論争的で、難易度はやや高い。アカデミックな講義で、アカデミックに使用されてこそ、真価を発揮する本だと思う(逆に言うと、講義で教科書指定されていないにもかかわらず、独自に本書を選んで勉強を進めるのは、学習段階によってはかなり辛いかもしれない)。なお、著者は、必ずしも独自の見解を採用してばかりというわけではない。前掲・西田各論と同じく、条文を逐一紹介してくれるのが嬉しい。法学部はもとより法科大学院でも、本書を基本書にしている学生は、少なくとも私の周りでは一人も見かけなかったが、関西では状況が異なるのであろうか。
Mar 31, 2019
コメント(0)
-
椎橋隆幸ほか『ポイントレクチャー刑事訴訟法』(有斐閣、2018年)
印象を一言でまとめると「法学部生向けの教科書」。頁数は、宇藤崇ほか『刑事訴訟法』(有斐閣、第2版、2018年)より100頁ほど少ないにもかかわらず、少年手続について、まるまる1UNITを費やして解説するなどしており、読者が刑事手続にまつわる知識をバランス良く(受験対策一辺倒ではなく)身に付けることを期待しているようである。もっとも、共著者全員が「相当な期間(8年から18年)司法試験考査委員を務めた」(はしがき)とアピールしているとおり、近年の司法試験で問われた論点にはことごとく言及している。論点に関する解説は、総じて主流派を意識した穏当な内容にまとまっている。時折、渥美東洋が見え隠れするものの、せいぜい複数ある学説のひとつといった趣にとどまっている。学説の引用元などの文献を明記しているのがとても嬉しい。最近の代表的な教科書である前掲・宇藤ほかや、酒巻匡『刑事訴訟法』(有斐閣、2015年)では、これらが全て省略されているため、発展的学習が困難になっている。教科書の宿命ともいうべき問題だが、著者がある結論を採用する根拠が十分に記述されていないことがあり、そうした箇所は、講義などで補われることが望ましい。
Mar 31, 2019
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-
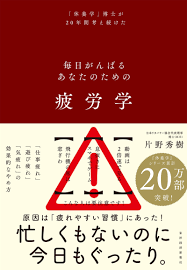
- 読書
- 「疲労学」 片野 秀樹
- (2025-11-22 05:00:05)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0936 僕が若い人たちに伝えた…
- (2025-11-22 00:00:14)
-







