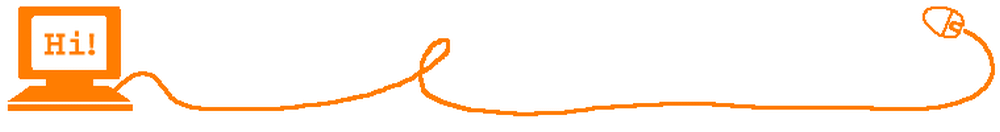おてつだい
私が幼い頃、私達家族はほんの短い間、父の実家に同居していた事がある。
父の妹達はまだ実家にいて、8人という大人数での生活だった。祖母は私をたいそう可愛がってくれたが、母との関係は決して良好とは言えなかった。ピリピリした雰囲気は子どもでも分かるものだ。
その家はダイニングキッチンと居間が廊下を隔てて離れており、皆が食事を終えたあと母が1人台所に残り後片付けをするのが常だった。
それは当然といえることなのだ。しかし私には、茶碗を洗う母のうしろ姿が寂しそうに見えた。子どもは、どんなにおばあちゃんが好きでも、お母さんのことが一番だ。
ある日、食事のあとひょっこり台所をのぞいてみると母がいない。流し台には8人分の食器が山になって置いてある。それを見て私はすばらしい事を思いついた。
お母さんの代わりにお茶碗を洗ってあげよう―。母が喜ぶだろうと思うと、それだけで心が躍った。やったことの無い事をするのにも興味がそそられた。大丈夫。母が洗うのをいつも横で見ているからやり方はわかる。
椅子を流し台に寄せてその上に立ち、スポンジに洗剤をしみこませてギュッギュッと握ると泡がわいてきた。洗い桶の一番上にある、祖父の大きな茶碗を手にとってスポンジをこすり付けてみる。
悲劇は次の瞬間に起きた。小さな手には余りある茶碗が、するりと滑って流し台の底に勢いよく落ち、いやな音と共に真っ二つに割れた。それを見た私は絶望的な気分になり大声で泣き出した。
茶碗が割れる音と泣き声に驚き、母が台所に駆け込んできた。
「どうしたの!怪我したの?!」
母が私の手を取り、怪我していないか確かめている間も私は声を限りに泣き続け、しゃくりあげながらも話そうとした。
「お手伝い…したかっ…たのに。おばあ…ちゃんに…おこられる。」
「大丈夫、大丈夫。誰もみさこちゃんをおこったりせんよ。」
「ちが…う…。おかあさんが、おばあちゃんにおこられる!」
そのとたん、母の目に涙が浮かんだ。
「みさこちゃん、お母さんのお手伝いしようとしてくれたとやね。ありがと。ありがと。大丈夫よ…。」
母が気持ちを分かってくれたことと、大丈夫と言われたことで安心した。落ち着いて考えると、確かに祖母が私に怒ることはなさそうだ。そこで事の起こりを忘れて言った。
「みさこちゃんが割ったことにしときぃ。ね?」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 大好き無印良品
- 流行りの無印良品から高級のベルト✨
- (2024-11-26 21:07:04)
-
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- najimuiさんのクリスマスポストカー…
- (2024-11-27 18:25:38)
-
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- [送料無料] ダーツ & はんこ & …
- (2024-11-21 14:32:00)
-
© Rakuten Group, Inc.