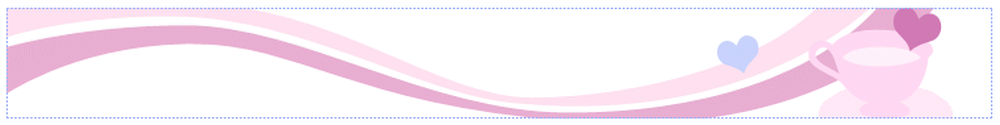◆音楽療法の部屋◆
◆知的障害者(成人)へ ダルクローズ・メソードを用いて進退運動を表出させる方法
Ⅰ障害の理解 <事前に対象者の特徴を把握しておくことが重要>
◇知的障害についての特徴の理解と援助について
●障害の特徴
①認知の低さからくる適応力の弱さ
②判断力の弱さ
③自立性の弱さ
④学習に時間がかかる。
⑤反復や固執性を持つ。
⑥コミュニケーションが上手に出来ない。
⑦感性が鈍い。
⑧感覚に異常さを持つ場合がある。
(成人前期 中期 後期) 運動機能の発達は学習の進歩と深いつながりを持つ。
前期:30代前半までの時期・・児童期に比べ、能力の伸長が見られる時期をみる
中期:40代半ばまでの時期・・精神面でも興奮や多動などが幾分落ち着いてくる。
後期:50代の時期・・早い場合は高齢期の兆候が見られてくる。個人差はあるものの、身体的に加齢現象が見られてくる。
成人前・中・後期を過ぎた高齢期「知的障害者は青年期から一足飛びに高齢期へ移行する。」という言葉がある。それほど高齢期の到来が早いとされる。 特にダウン症郡では非ダウン症郡より更に老化が早いことが認められている。
Ⅱ 障害と身体運動
身体運動を与えるからには、その身体運動の意味、もたらす作用を考え、理解しておかなければならない。
適度な疲労が快感へ。 運動に意味がないと疲れるだけである。
<知的障害者に対する治療目的>
音楽療法の中に、運動機能を促す為に音楽を用いた身体活動は知的障害者の音楽療法活動で中心的なものとなっている。
音楽療法の中で運動を取り入れた場合のこうかについて。
Ⅲダルクローズ・リトミックを取り入れた身体運動
導入・小さな動き・大きな動き・整理運動・知的障害者の身体運動を促す指導・手段の一つにダルクローズのリトミックの応用を考える。
●ダルクローズの教育法
「真の音楽教育は単に聴覚だけではなく、すべての感覚・神経筋肉によって
全身で完治するものでなければならない」
リズムを伴った運動の目的
1.運動性を高める 2.感覚性を養う 3.情緒性を育てる
4.学習の意識性を養う 5.身体の意識性を養う 6.社会性を育てる
などがあげられる。
運動障害をもつ障害者にはリトミックを取り入れたセッションによって知覚の対象として(音・色・形)の感覚の発達を促し、身体認知・バランス・身体の操作・移動などの粗大運動や、注意集中を促すことで眼球運動などの微細運動の発達を促す事が可能となる。加えてリラクゼーションにより今まで活発に動いていた身体動作の変化・改善を与える事が出来る。
Ⅰ障害の理解 <事前に対象者の特徴を把握しておくことが重要>
◇知的障害についての特徴の理解と援助について
●障害の特徴
①認知の低さからくる適応力の弱さ
②判断力の弱さ
③自立性の弱さ
④学習に時間がかかる。
⑤反復や固執性を持つ。
⑥コミュニケーションが上手に出来ない。
⑦感性が鈍い。
⑧感覚に異常さを持つ場合がある。
(成人前期 中期 後期) 運動機能の発達は学習の進歩と深いつながりを持つ。
前期:30代前半までの時期・・児童期に比べ、能力の伸長が見られる時期をみる
中期:40代半ばまでの時期・・精神面でも興奮や多動などが幾分落ち着いてくる。
後期:50代の時期・・早い場合は高齢期の兆候が見られてくる。個人差はあるものの、身体的に加齢現象が見られてくる。
成人前・中・後期を過ぎた高齢期「知的障害者は青年期から一足飛びに高齢期へ移行する。」という言葉がある。それほど高齢期の到来が早いとされる。 特にダウン症郡では非ダウン症郡より更に老化が早いことが認められている。
Ⅱ 障害と身体運動
身体運動を与えるからには、その身体運動の意味、もたらす作用を考え、理解しておかなければならない。
適度な疲労が快感へ。 運動に意味がないと疲れるだけである。
<知的障害者に対する治療目的>
音楽療法の中に、運動機能を促す為に音楽を用いた身体活動は知的障害者の音楽療法活動で中心的なものとなっている。
音楽療法の中で運動を取り入れた場合のこうかについて。
Ⅲダルクローズ・リトミックを取り入れた身体運動
導入・小さな動き・大きな動き・整理運動・知的障害者の身体運動を促す指導・手段の一つにダルクローズのリトミックの応用を考える。
●ダルクローズの教育法
「真の音楽教育は単に聴覚だけではなく、すべての感覚・神経筋肉によって
全身で完治するものでなければならない」
リズムを伴った運動の目的
1.運動性を高める 2.感覚性を養う 3.情緒性を育てる
4.学習の意識性を養う 5.身体の意識性を養う 6.社会性を育てる
などがあげられる。
運動障害をもつ障害者にはリトミックを取り入れたセッションによって知覚の対象として(音・色・形)の感覚の発達を促し、身体認知・バランス・身体の操作・移動などの粗大運動や、注意集中を促すことで眼球運動などの微細運動の発達を促す事が可能となる。加えてリラクゼーションにより今まで活発に動いていた身体動作の変化・改善を与える事が出来る。

ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 子供服セール&福袋情報★
- 【2026年新春福袋】Jeans-b【ジーン…
- (2025-11-26 12:04:06)
-
-
-

- 子育て奮闘記f(^_^;)
- ☆ブランコ式ハンモック☆
- (2025-11-27 22:32:59)
-
-
-
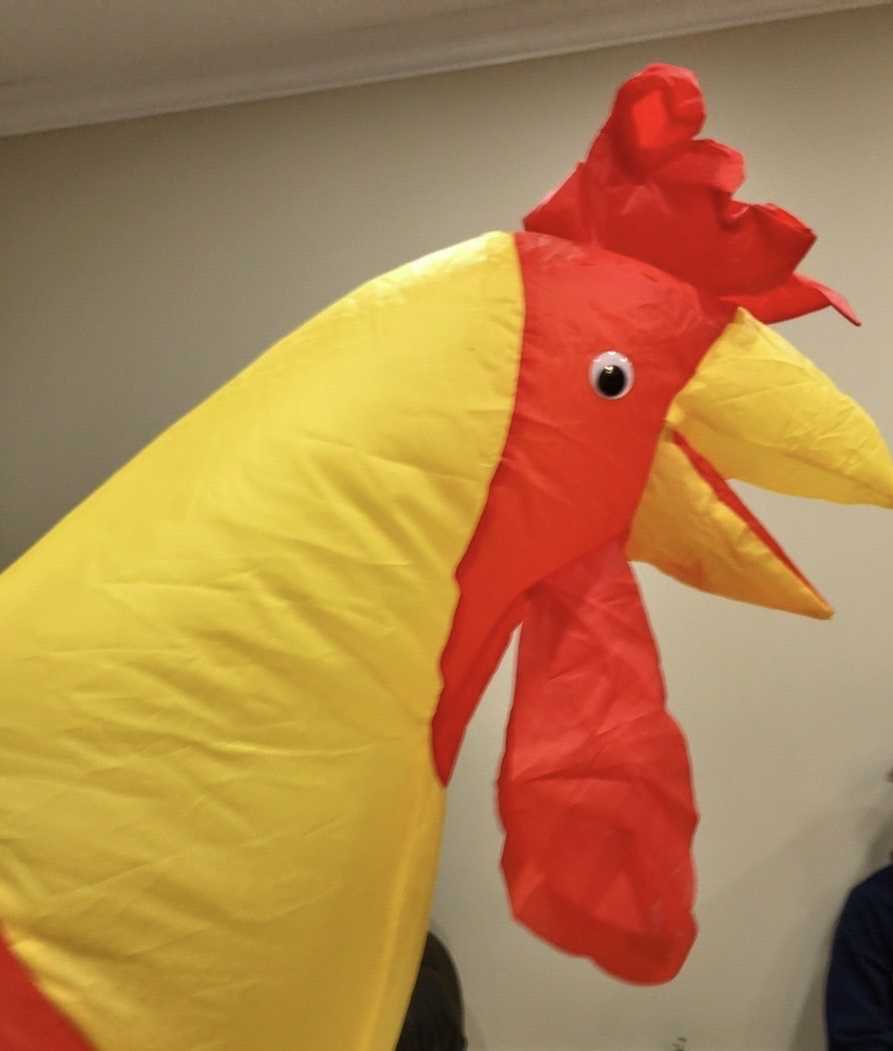
- 働きながらの子育て色々
- ZOOM
- (2025-11-27 07:00:04)
-
© Rakuten Group, Inc.