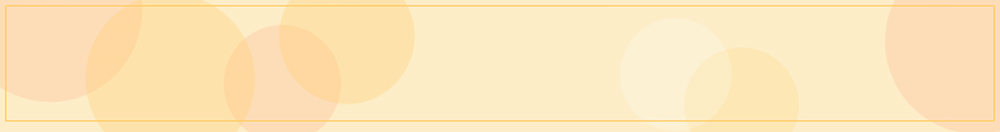カテゴリ: カテゴリ未分類

先生いつものごとく教室に10時15分頃入室されて握手を求める。素敵なグレー系のスーツに身を包んで笑顔のまま一人一人に握手する。
皆さんはどれだけ幸せですか。
根っこが土の中に入って誰が根っこを作ったのか。
緑に包まれお日様に恵まれる生活。
こんなすばらしい自然の中に置かれているのに
毎日いらいらしながら不安なのか。
自然の深さと量と大きさ
その気づきを感じ、喜びを知ってください
性犯罪の番組が何度もテレビで放送されています。
テレビの視聴率を高くするために放送していますが、
見る対象が若い人だと犯罪の検討材料になってしまいます。
まるで犯罪を勧めているかのような放送です。
刺激、推奨され、アクセルとなって犯罪を推奨しています。
世間のレベルが低いのです。
お金があって自分の事だけ考えても決して幸せになれません。
欲得楽の世間体が見えます。
現代は情報化社会。
だけど声なき声に耳を傾けるのが大切である。
声なきとは、無言でなく自然がいっぱい声を出しています。
ピーピーかおはようか
葉っぱは生きているから変わる。
自然の緑に対して感謝。
言うべき時を知る人は黙する人である。
内観がない 直感がない・・
自然の御手にあるのに、情報の中にあるのではない。
我々ではない。私は一人一人だけなので、みんな違うから役立つ
学校教育は何で情報を押しつけるのか。
洞察力が無くなる。
先生は何を預かっていますか?
ロボットを預かっているようです。
ほんとは一人一人違うことが教育なのに
洞察力がない。情報に巻き込まれる。
その原因は見えているところだけ報道している。
例えば、高いところから落ちた。これでは原因が見えていない。
なんの為に生きているの。
自分の考え方で、努力している人が常識と思うこと。
自分は自分のもの?生かされているのに。自然に。
神と仏について 見えないものをウパーヤ これはすばらしい方便手段です。
私たちは生かされている。生かしている意志を思っている。
70億の人口、魚、植物、動物。
意志を持っている。
生かされている実感がない内観がない。
今日神の御手 自然の中にある。
春芽が出て花が咲き秋に実をつけ冬枯れる。
輪廻は繰り返される。
今日、ほうもんどうを究(まなび)で自分を作っている。
天地有情我浄土する
私を生かす自然の法則に従って生きて行こう
春風が吹いてきたら芽を出し
秋風が吹いてきたら枯れる
自然の意志にしたがって。
年取りたくない人手を挙げてください。
手を挙げた人は自然に反則しています。
自然のドラマを知る。
若い者はその途中にすぎない。
プロセスの途中にすることは布施である。
どういう人に施すの?
すべての人にというのは偽善である。
全部の人にはできない。
例えばお姉ちゃんがケーキをもらってきた。
弟一人がいる。かわいそうだから分けてあげるという考えは傲慢である。これなら憎らしい人には施せない。
代償をもとめている行為が布施ではない。
やったら自分がうれしいからやるのが布施ですとはならない。
やったのに返さないと文句が出る。
かわいそうだからやる。
代償を求める。
命もお金も地位も人に与えて預かっているのにすぎない。
自分が大きく喜んで施しができるようでないと人に布施ができない。
人に是非もらってもらいたいと施すのが布施である。
うれしくて行うのが布施。これでないと縁が良くならない。
無財の七施がある 7以外にいっぱいあるのです。
愛語施
和顔施 赤ちゃんの笑顔です
慈眼施
身施
心施
舎房施
謙譲施
もらってもらう気持ちが大事です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考 慈悲の実践~無財の七施~
http://ichigu.net/pillar/service02.html
「ありがとう」「おかげさま」の気持ちを行動で表す身近な実践として、『雑宝蔵経』(ぞうほうぞうきょう)に説かれる「無財の七施」(むざいのしちせ)があります。
仏教には、人々が人間形成に努めて幸せや安らぎの境地に至る道として六波羅蜜(ろくはらみつ)の行があり、その第一番目が布施です。布施の「布」は分け隔てなく、あまねく、「施」は文字通りほどこすという意味です。万人に等しく、施しをする人はもとより、受ける人の心も清く、布施の内容も清らかであることが大切であると説かれています。世間一般の損得勘定では、与えた人よりも与えられた人の方が得をするようなイメージですが、布施は、ほどこした人の方が幸せな気分になり、与えられた人よりも与えた人を幸せにするのではないでしょうか。『雑宝蔵経』に無財の七施を行うことで「大いなる果報を獲(え)る」と説かれている通りです。
私たちの日常生活においてお金がなくても、物がなくても周りの人々に喜びを与えていく、少しでも喜んでいただける方法がある、それが「無財の七施」の教えです。このような身近な奉仕や実践によって、自己を高めることができるとともに、世の中の人々の心を和ませることができるのです。
あらゆるものがつながりあってこの世の中は成り立っています。人との出会いやつながりはもちろん、お互いの助け合い、支え合いの中で私たちは生きているのです。伝教大師は「悪事は己に向かえ、好事は他に与え、己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」と説かれるように、取ったり、もらったりのTake・テイクだけでなく、小さな行いでもいいから、恩返しや御礼をしましょう。周りの人に喜びを与えて(Give・ギブ)いきましょう。私たち一人ひとりのささやかな行いが、周りの幸せのためになり、行いを通じて自分も幸せな気分になります。
1.眼施(げんせ) やさしい眼差(まなざ)しで人に接する
「目は口ほどにものを言う」といいますように、相手の目を見ると、その思いはある程度わかります。相手を思いやる心で見つめると自然にやさしい眼差しとなり、人は安心します。自らの目を通して相手に心が伝わって、相手も自分の気持ちを理解して、お互いが打ち解けることができることでしょう。
2.和顔悦色施(わげんえつじきせ) にこやかな顔で接する
眼施と同様、顔はその人の気持ちを表します。ステキな笑顔、和やかな笑顔を見ると幸せな気持ちになります。そして周りにも笑顔が広がります。人生では腹の立つこともたくさんありますが、暮らしの中ではいつもニコニコ、なごやかで穏やかな笑顔を絶やさぬよう心がけたいものです。また、メールの顔文字も一工夫してみてはいかがでしょうか。
3.言辞施(ごんじせ) やさしい言葉で接する
言葉は人と人との関係を円滑にするコミュニケーションの大事な方法です。私たちは言葉一つで相手を喜ばせたり、逆に悲しませたりする場合があります。相手を思いやるやさしい言葉で接していきましょう。「こんにちは」「ありがとう」「おつかれさま」「お世話になります」など、何事にもあいさつや感謝の言葉がお互いの理解を深める第一歩です。
4.身施(しんせ) 自分の身体でできることを奉仕する
重い荷物を持ってあげる、困っている人を助ける、お年寄りや体の不自由な方をお手伝いするというような身体でできる奉仕です。どんなによいことと思っても、それが実行できなければ意味をなしません。よいことを思いついたら実行し、自ら進んで他のために尽くしましょう。その結果、相手に喜んでいただくと同時に、自己の心も高められるのです。
5.心施(しんせ) 他のために心をくばる
心の持ち方で物事の見方が変わってしまうように、心はとても繊細なもので、自分の心が言葉遣いや態度に映し出されます。自分だけがよければいいというのではなく、心底からともに喜び、ともに悲しむことができ、他の痛みや苦しみを自らのものとして感じ取れれば言うことはありません。慈悲の心、思いやりの心から自然とやさしい顔や眼差しにも表れてくることでしょう。
6.床座施(しょうざせ) 席や場所を譲る
「どうぞ」の一言で、電車や会場でお年寄りや身体に障害を持っている方に席を譲ることです。座席だけでなく、全てのものを分かち合い、譲り合う心が大切であるという意味が含まれています。何事も独り占めはいけません。少なくとも電車やバスのシルバーシートは本来の意義に従って利用しましょう。場合によっては自分の地位を譲って後のことを託すという意味も含まれるでしょう。
7.房舎施(ぼうじゃせ) 自分の家を提供する
四国にはお遍路さんをもてなす「お接待」(おせったい)という習慣が残っています。人を家に泊めてあげたり、休息の場を提供することは様々な面で大変なことですが、普段から来客に対してあたたかくおもてなしをしましょう。平素から喜んでお迎えできるように家の整理整頓や掃除も心がけたいものです。また、軒下など風雨をしのぐ所を与えることや、雨の時に相手に傘を差し掛ける思いやりの行為も房舎施の一つといえるでしょう。
いかがですか。一日一善といいますように、私たちも普段の生活の中で、この「無財の七施」の中の一つでも真心のこもった布施を実行できれば、自ずと他のこともできるようになっていくのではないでしょうか。そうすれば、周りの人たちと仲良くでき、自らの心は安らぎ、ともに幸せに暮らすことができるに違いありません。
国連で住民の困っている数だけ食糧援助しようとしたら,現地から僧侶の数だけ引いて請求が来ました。坊さんにあげるのは国民から坊主に出すならわしだからです。
人を憎み自分を駄目にするのは自分である。
不幸な人が回りには多いが、
自業自得の結果なんだ。ほんとはみんな幸せなんだ。
愛
慈悲=仏様
恵=神様・天地自然を言う
自然の恵みが自分に命令する。
人間に善悪はない。
行った行為に対してウパーヤ 方便として与えた。
どれだけ近づくか今日行う行為による。
近づくことをするのが布施です。
自然はあなた方に対して命令する。
あなた方は年を取る
涅槃の境地を与えるために、布施を行うのです。
64歳以下8000万人の人口です。
この人口で国の1200兆円の借金 GDP240%に当たるを返済します。
年金を無くすしかない。
ヨーロッパでは67~68歳から年金支給です。
医療保険は病名によって他は使わせない。
若いとき老境に生きる布施に近づきなさい。
因果律
自然の法則
原因が結果する。
天網は漏らさない。
自然法爾(じねんほうに)は絶対法則 最後に解説有り。
棚からぼた餅とは
棚にいいぼた餅を上げる。
ぶす餅を揚げてはいけないのです。
プロセスが目的を作る
いい人生いい老人
所業仏業
いきていることの行いが仏業である。利得を得る。
善縁善果
悪縁悪果
私たちは仏子なり知らないことが最大の罪なり。
犬、ペットでなく仏の化身である。
すべての森羅万象は仏の化身である。
普段食べているお米は天地の力を宿した米。
食べなさいと言うとき命をいただきます。
供養して身のうちに入れ、感謝がどれだけ深いかでお米が生きる。
昔は海山のものを食べ余計なものは取らなかった。
今もうけるために全部取る。
そのため自然を狂わした。
自然の法則と違う
人間が作った状況に対して供養の心が大切である。
善は、バランスよく行う。
涅槃の境地を生きられるように布施を能力の範囲内で行う。家族の範囲だけでもいいので近づいていきます。
身口意 このうち意が大切です。
先生 合掌。
参考
自然法爾(じねんほうに)~親鸞聖人のおしえ~
「物事は自然になるようになっていくし、それが一番いいことである」
日本には四季があるが、
春になれば自然に温かくなり、自然に花が咲く。
それは自然にそうなるのであって、
だれかが努力してそうなっているわけではない。
それは、自然にそうなるべくして、そうなるのである。
そして、その自然の営み、物事の移り変わりこそ、
仏の働きであり、仏の姿そのものである。
大体、この自分という存在を考えてみても、
生まれようと思って生まれでたわけでもなく、
育とうと思って育ったわけではないではないか。
そう考えると、こうして生きておるのも、
すべては仏さまのお慈悲、ご加護のおかげである。
だから「ああか、こうか」と考えるのをやめて、
その日、一日一日をただ精一杯生きよ。
喜びと感謝をもって事を為せ。
あとはすべて仏さまにお任せせよ。
もともとお前自身はお前のものではなく、
仏さまのものである。
それを勘違いして我がものとして執着していただけのこと。
仏さまのものは仏さまにお返しして、
心配することなく毎日を楽しく生きよ。
(親鸞聖人御消息「自然法爾の章」より)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.