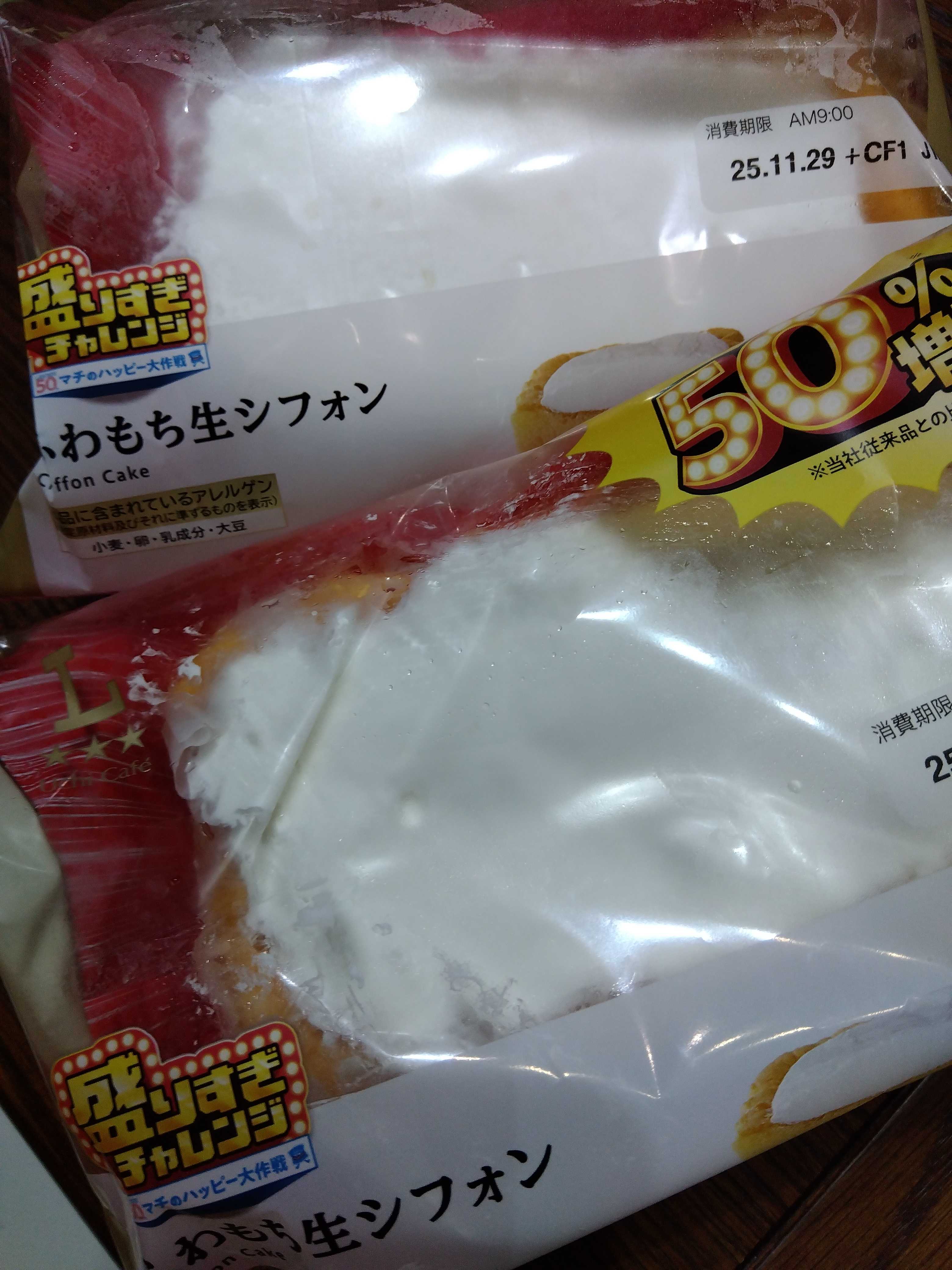全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
祖父の生きる力
すっかり時間が経ち過ぎてしまいました。その間に、祖父は一度、危うく命を落としそうになりました。 お年寄りは、皮膚の感覚が鈍くなり、お風呂に浸かっているとのぼせてしまうことがあるようです。祖父は熱湯の中で意識を無くし、危うく溺死する所を叔父が発見、間一髪で助かりました。 じいちゃん、まだ死なんで!!!本当危なかった。助かって安心しました! すっかり自信を無くしてしまったのか、足も痛み病気も増え、数年前のじいちゃんの姿が嘘のようです。あんなに元気だったのに。 それでも、私の渡した中国の本を一生懸命ルーペで覗きながら読んでいる姿を見ると、何かしら執念みたいなものを強く感じます。 久しぶりに顔を出しに行くと、「最近も中国へ行っとるんか。」と、気にかけてくれています。机には、当時の軍歌の本や私の渡した本がありました。 もう一緒に行くことは難しいのですが、私が代わりに行くことはできます。私が行かなければいけない。 じいちゃんは91歳で、体も思うようにいかないけど、今生きています。それは、私が太原に行くのを待っているからだと思うようになってきました。かすかな望みが、じいちゃんの生きる力になっていると感じます。じいちゃんはまだ死ねない。生きるパワーを振り絞って待ってくれている。人生で、悔いが1つ残っているとするならば、きっと中国に対する思いではないかと思います。青春時代の納得のつかない戦争というものに対しての思い。あれ程強烈ですさまじい人生での体験は無かったと思います。 あと、北京オリンピックも楽しみにしているのかもしれません!じいちゃん、まだまだ見るものがたくさんあるから、力振り絞って生き続けて下さい。 中国の旅行会社の方と今はメールで簡単にやり取りができ、実は行くことなんてとっても簡単なことです。日本語ガイドさんの依頼も、旅のコーディネートも任せられます。値段も高くはありませんでした。あとは、私の気持ちを奮い立たせることと、優先順位の見直しが必要です。 必ず、9月終わりまでに行く!必ず行きます。
2008/06/02
コメント(0)
-
心に残る一言
祖父にあれこれと聞き、最後に別れる時に祖父は言った。「ありがとな。」祖父にとっての戦争がどういうものだったかを聞くことが、祖父にとってありがたいことだということが伝わってきた。私があれこれ用意していく本や話に祖父はとても興味を持った。唯一、中国の話題を話せるのが私だった。祖父にとっての戦争とは、自分が生きた時代であり、自分の過ごした人生の紛れも無い事実であるということを実感した。加害者である面について、どう思っているかはまた次回聞いてみたい。過酷な最前線で戦い抜いて帰還された方々とは心境は違うと思うが、祖父にとっての戦争を知ることで、私も戦争について、より深く考えていけるようになりたいと思う。
2007/04/15
コメント(0)
-
私の地元では
私の実家は岐阜の山奥にある小さな村である。ここからも多くの人々が戦地に赴いた。1904年(明治37)日露戦争 104人(内15人死亡)1933年(昭和 8) 満州事変 47人(内 2人死亡)1937年~1945年(昭和12~20)日中・太平洋戦争 700人以上(内日中戦争では23人、太平洋戦争では93人死亡) 今でも元気でいるのは、祖父含め、もうわずかしかいない。
2007/04/15
コメント(0)
-
祖父が徴集された時代
随分更新が遅れてしまいました。祖父に聞いた話を書いていきたいと思います。 祖父は第一次世界大戦勃発2年後の1916年(大正5)生まれ、今年91歳を迎える。1937年(昭和12)8月25日に招集された。祖父が21歳の時だった。 この時代は、1931年に満州事変を起こし、翌年には傀儡政権「満州国」を成立させた頃だった。日本政府は多くの満州移民団を送り出した。・日本の満州支配維持・日本国内の土地不足や人口過剰問題を解決するため・ソ連との戦争に備えるため・石炭や鉄などの豊かな資源確保のため・行き詰まった経済を打開するため敗戦までに満州へ渡った総数は29万人と言われる。 次に狙ったのは資源豊富な華北だった。第二の「満州国」をつくるため、華北分離工作を進めていった。親日政治家たちをかつぎあげ傀儡政権樹立をもくろみ、中国国民政府の勢力を華北から排除しようという政策だ。不当に土地を奪われた中国人の不満は高まり、各地で抵抗運動が激化していった。 そしてついに、1937年7月7日、日本軍は北京郊外で盧溝橋事件を起こす。中国軍が不法に射撃したからだと口実をつけ、一挙に華北占領を目論む日本軍。祖父が徴集されたのはまさにこの時だった。 同じ太原でも、奥村さんが徴集された時は敗戦に近い頃。いよいよ日本軍の戦況も苦しくなっていた時だったが、祖父が中国に渡った時は、日本軍が次々領土を広げ、日本中が沸き立っている頃だった。 盧溝橋から約1ヶ月半後の1937年(昭和12)8月25日、とうとう祖父も動員された。 当時の日本の徴兵制度を調べると、1889年(明治22)の改正徴兵令と、これを引き継いだ1927年(昭和2)の兵役法では、「国民皆兵」の原則がうたわれていた。満17歳から40歳までの男子のほとんどは、何らかの形で兵役につかなければならなかった。20歳になると、徴兵検査が行われた。体格、健康に応じて分類させられた。最も体格が良く健康なものが、最前線に送られていった。 祖父が中国へ渡った昭和12年の2月、軍拡態勢に入っていた日本は、徴兵検査の身長基準をそれまでの「1.55m以上」から「1.50m以上」に引き下げた。祖父は小柄で、満20歳の時には幸い検査不合格となり徴兵を免れたのだが、この改正により、中国行きが決定した。 先に行った敦賀(福井県)師団はとても強く、危険とされる所へ送られたようだ。祖父の配属された師団は、兵役検査に落ちた人からなるもので、主に物資供給など、後方支援が目的だった。どうりで、祖父の中国回想には、重々しい雰囲気がそこまで感じ取れないと思ったが、ようやく理解できた。もちろん、大変な苦労はあったが、もっと過酷な立場の人々がいたのだ。祖父が中国を思う姿は、若い青春をあの広い大地で過ごしたという、懐かしさも入り交じるような複雑な思いに見えた。小さな村で育った祖父は、中国のスケールの大きさ、建物や城壁のすばらしさに圧倒されたと言っていた。外国の情報など入ってこなかった時代に、確かに相当驚いたと思う。戦争下ではあるけれど、ある種の感動興奮を持ったのだと思う。そんなことを言えば不謹慎かもしれないが、当時の日本は着実に領土を広げ、波に乗っていた時代である。その時は、侵略戦争という気持ちで中国で過ごしたわけではなかったと思う、逃れようのない男たちの勤め、選択肢のない人生であった。 思い切って質問した。『じいちゃんも人を殺す訓練や試験を受けた?』そんなことはなかったそうだ。あくまで防御する立場だったとのこと。なんて恵まれていたのか…。同じ中国に渡った人でも、場所や時期や任務によって、こうも差があるのか。 けれど、絶えず危険にさらされてはいた。襲撃を受け、仲間の中でも殺された人は多くいた。峠では、共産党軍(八路軍)は犯罪を起こした中国人の囚人たちをくくりつけ、銃を持たせ攻撃させたと言う。 祖父が通ったルートを聞いてみた。まず瀬戸内海の方から船に乗り、どこへ着くかも何も知らされぬまま今の韓国の釜山に入った。そこから列車で朝鮮・満州を通り、天津まで移動。北京の少し南東である。そしてひたすら太原を目指し、歩いて進んでいった。あの広大な大地を、敵に囲まれながら徒歩で向かったとは…、すごい距離である。直線距離でも少なくても420kmはある。まず南に向かって、多くの街を通りながら行ったというのだから、実際はそれよりもかなりの距離だ。山がないことに驚いたという。どこまでも広い広い大地が続き、祖父は中国という国に圧倒された。 太原を拠点にして、祖父の属する師団は主に物資を調達したり管理補充していた。つまり村々に入って行き、食料などを盗んだり、住民から徴集するのである。日本軍を恐れた民衆は、祖父たちが着く頃には逃げて村々はほとんど無人だったようだ。太原では、日本軍は中国の民衆と隣り合わせで生活していた。閻錫山率いる地元の軍制を金で買収し、うまく折り合いをつけていたようだ。協力体制のもと、八路軍と戦っていた。 祖父は太原城壁の東門近くにある民家に寝泊まりをしていた。そこで不思議にも毎日顔を出してくる女がいたと言った。よくついて来るので、日本軍は食べ物を与えたりしていたそうだ。また、中国人の出しているお店の饅頭がうまかったと言っていた。交流、と言っていいのか分からないが、反抗しない民衆とは、やりとりがあったことが分かる。 そして、これも聞かなければいけない質問、思い切って尋ねた。『やっぱり慰安婦もいたの?』緊張しながら聞く私とは裏腹に、あっさり答える祖父。「ぎょうさん(たくさん)おったなぁ。」祖父も行っていたと言う。各師団に一緒について行動を共にする慰安婦たちが大勢いた。朝鮮人だったという。兵士たちは、わずかな給料をもらっていた。そのお金でタバコを買ったり女を買ったりして暮らしていた。慰安所は軍が管理しているため、結局払った給料が軍に戻ってくる仕組みだ。女の人たちは強制的に従事させられていた、兵士が払った金が彼女たちのもとへ渡ることはなかったか、あってもわずかだったと思う。結局、祖父が日本に引き揚げる前には、彼女たちはいなくなり、どこへ行ったのか…と祖父は当時を思い出していた。ずっと行動が一緒なため、慰安婦たちにきっと情もわいていたんだろうと思う。『きっと、じいちゃんは帰ることができたけど、彼女たちは故郷には帰れなかっただろうね…』と私は言った。 祖父は中国で2年と4ヶ月程を過ごした。1940年(昭和15)1月6日帰国。青島まで列車で行き船に乗った。青島には租界地域があり、西欧列強の近代的建物が並んでいた。あれは立派だった、と当時受けた衝撃を語ってくれた。 ところで、どうして祖父が帰ってくることができたか、という所だが、ここにはカラクリがあった。祖父は帰ってから、恩給をもらうことができなかった。それは、3年以上の兵役につかないと、補償されないという軍の仕組みがあったからだ。軍の態勢もうまくできている…。3年経たない内に国に戻し、また新しい若者を送るのだ。「そういえば、こんなもんもらったな。」と祖父はゴソゴソと棚から取り出した。SEIKOのいかにも立派そうな金色の懐中時計だった。軍はその時計を名誉として与え、祖父たちの訴えを却下し黙らせた。売って金にすることもなく、今でも一応大事そうに保管していることを知り、やはりあれは祖父にとっては「お国のため」の戦いだったのかなと思った。許されることではなかったけれど、時代が時代であり、やられるかやるかの選択しか無かった。全てを否定すれば、自分自身の過ごした若い時を、中国で過ごした過酷な日々も、全てに理由がつかない。戦争時代を生きた人々は、複雑な心境を抱え、変わり行く時代を見つめていたんだと思う。 祖父は帰国する前には、伍長(ごちょう)というランクに昇格していた。それは、次に戦地へ行けば、伍長金という給料がもらえる仕組みだ。しかし祖父はもう行きたくはないと心の中で願い、幸いにも再度徴集されることは無かった。帰ってからは、岐阜から大阪へ行き、軍事ワイヤー工場で1年程働いた。そして大工に弟子入りし、終戦後故郷に戻り、大工の仕事で生計を立てた。それから62年が経ったが、もう一度中国へ行ってみたいと思いながら、今日に至る。
2007/04/15
コメント(2)
-
祖父の姿
先月末、かなりの量の重い本を持ち込み張り切って帰省しました。実家は母方の家なので、父方祖父とは一緒に暮らしていません。ですが、すぐに隣の家なので、いつでも行き来ができます。 早速、大量の本を持って祖父の所へ伺うつもりが、祖父の方から用事で家に顔を見せました。そこで衝撃を受けました。祖父の帰っていく姿が、あまりにゆっくりで、足が不自由そうだったのです。明らかに私が思っていた祖父の姿よりもヨロヨロとしていました。月日は流れていました。元気だった姿ももう昔の話。力ないそのうしろ姿を見て、これは…まずい、用意周到で行かないと説得も実現も無理だ、と感じました。 本気を見せたくて、そして実現可能だということを知ってもらうため、パスポートが家の最寄りでどのように取れるか、空港までの所要時間、ルート、飛行機の便、現地観光事情、そんな所まで調べていったのですが…。その前にまず、これは…、自分がより綿密に太原へ行く計画を立て、戦争についても深く理解をしてから祖父に話をよく聞くことが先決だと思いました。その中でだんだんと思い出してもらって、その気にならないかを見計らいながら、周囲の家族から説得をし、本人の同意を得る。そうする必要があると考え直しました。 大量に持ち込んだ重い本も、これをいきなり全部持ち込んだらびっくりするなぁ…とふと我に返りました。もしかしたら、思い出したくない話なのかも…?でも割と、中国の話になると反応が悪くなく、興味深く、タブーというわけではないように感じていました。とりあえず、たくさんの情報をいきなり持ち込みすぎても良くないと思い、本と情報を絞っていくことに。蟻の兵隊の映画のパンフレット、奥村和一さんの本、そして講談社の「昭和二万日の記録4日中戦争への道 昭和10-12年」と3冊のみに厳選。そして現在の太原の様子。観光地となっている資料や話。自分が何を伝えたいかを整理して。まずは、蟻の兵隊という映画があって奥村さんという人に会ったということ、そこを切り口にしていこうと思いました。一度前に、「じいちゃん、やっぱり中国に行きたい?行こうよ、一緒に行くからさ。用意も全部簡単にできるよ。」と言ったことがあります。「行けるもんなら行きたいけどなぁ…」と言葉を詰まらせた祖父。一緒に暮らしている叔父さんには、「年やで無理や。あんたは優しい子やなぁ。ありがとな。」とそれで話が続かなくなってしまったことがあるので、やはり一緒に行こうとなると、慎重に話さなければいけないと、改めて祖父のうしろ姿を見て考えさせられました。すぐ隣の家に祖父がいるのに、すぐに行けないもどかしさ。あぁこの間にも時間は流れていく…。じいちゃん、元気でいてください。
2007/03/14
コメント(1)
-
資料準備
実家に帰る前に、近くの区の図書館で関係資料の本をたくさん借りてきました。けっこう、たくさんあるんですよね。貴重な写真がいっぱい載った分厚い本、何年前の!?というくらい昔の本。こうしてたくさん資料が残されていたんだな、と改めて気付きました。祖父が興味を持つかと思い、写真がたくさん載った本を中心に借りました。毎日新聞社の「別冊1億人の昭和史 日本陸軍史」、これは私の生まれた年に発行された本です。 この頃は、戦争体験者もたくさんいて、健在で、正確な情報も入手しやすかったのかなと思います。けれどもしかしたら、まだまだ語るには、口を開くには、社会的にどうだったのかな…。今は、戦争体験者がどんどん少なくなっている時、生きている内に、これを伝えなければ、そう思って重い口を開く人も多くて、貴重な話だからこそ聞く側も真剣に聞く、という所があるのではないかと思います。「蟻の兵隊」が今これだけ多くの人に応援されているのも、人生を懸けて奮闘している80歳を超えた奥村さんの姿があるからこそ、というのも理由の一つだと思います。 戦後61年、8月で62年目に入る今、あの時戦争へ行った人々は80歳以上、あの時子供で記憶に残っている人々でも70歳前後。戦争体験者がゼロになる日がいつかは来ます。本当にゼロになってしまう日が。私たちはもうちょっと危機感を感じなければいけないのではないか、と思います。ゼロになったら、戦争は、戦争は、と恐ろしさも虚しさも間違っていることも、伝えてくれる人がいない、過ぎ去ったただの歴史のことになってしまう。そうなった時、私たちはまた間違いを起こしてしまわないでしょうか。 日本の、世界の未来を考えると、漠然と皆が不安に思うこの時代。資源埋蔵量は決まっていて無くなる日も近いというのに、一向に私たちの大量消費、資源を食い荒らしていく生活は止まるどころか増長されていっている。発展途上国はより良い生活を手に入れるため、先進国の後を追う。新たな資源戦争はどんどんうまれる。人間は自分たちの愚かさにいつになったら気付くのでしょうか。 今、戦後世代の私たちは、戦争にイエスともノーとも言わない世代だなと思います。イエスとはもちろん言わないのですが、ノーとも言えない。国民全員がノーと言える人々なら、もうちょっとこの国はまともになっていると思います。まともじゃないことも、外から見て日本がどうなのかも分からない、これで良いと思ってる。じゃあノーと言える日本人になっていくには…、何でノーと言わなきゃいけないのか…、やっぱり戦争の本当の恐ろしさ、実態を知るということ、これは大事なことです。原爆のこと、沖縄のこと、被害の面だけを強調する教え方では不十分です。加害を知ってこそ、両面を知ってこそ、戦争とはどんなものなのかが見えてくる。クリント・イーストウッドがアメリカ側、日本側、両側から映画を製作してくれて良かったなと思います。そういう試みが大事だと思うのです。 そして、今世界で起こっている戦争の実態を知ること、声なき人々の声を届けていくこと、力を持った者たちの情報コントロールに惑わされない確かな目を養っていくこと、それらがとても大事なことだと思うのです。
2007/02/28
コメント(1)
-
『蓋山西(ガイサンシー)とその姉妹たち』
山西省一の美人を意味する「蓋山西(ガイサンシー)」と呼ばれた、侯冬娥(コウトウガ)。 その呼び名は、彼女の容姿のことだけでなく、同じ境遇に置かれた幼い姉妹たちを、自らの身を挺してまで守ろうとした、彼女の優しい心根に対してつけられたものであり、その後の彼女の人生の悲惨を想ってのものだった。 「蓋山西(ガイサンシー)」という名は、やがて山西省の人びとの間で、人間の尊厳を表す言葉となる。 この映画は、班忠義監督が9年の歳月をかけ、中国の大地に侯冬娥(コウトウガ)と、運命を同じくした女性たちの姿を追い続けたドキュメンタリーである。 日中戦争時、日本軍から性暴力を受け、幼くして人生の全てを奪われた女性たちの現在の記録であり、同時に、私たちの明日に向けて語られる物語である。 東京では、4月25日(水)21:00より下高井戸シネマにてレイトショー&プロデューサー山上徹二郎氏トーク予定。 順次、秋田、兵庫、大阪、北海道にて上映予定。http://www.cine.co.jp/gaishanxi/index.html
2007/02/20
コメント(1)
-

『蟻の兵隊』
『蟻の兵隊』 http://www.arinoheitai.com/ 今日は下高井戸で映画上映後、池谷薫監督と奥村和一さんのトークがありました。今日この機会にお会いできたことを本当に嬉しく、また貴重だったと心から感じました。奥村さんの人生を懸けた一言一言に強い信念を感じ、闘い続けているその姿に深い感銘を受けました。生き抜いてきた力を見ました。 トーク後、奥村さんとお話ができました。「私の祖父も太原に行っていました。今90歳です。今度一緒に太原へ行くつもりです。」奥村さんの鋭い目線が私に向けられた。そして優しい表情になりました。「おじいさんに話を聞いた方がいいよ。太原は変わったよ。大変だから気をつけて行きなさい.。」と、微笑んでくれました。何故か分からないが涙があふれ、もっと話をしたいのにそれ以上できませんでした。監督は、涙ぐむ私に配慮してくれたんだと思います、「麺がおいしいよ。」と言ってくれました。 祖父は今年91歳、去年祖母が亡くなってから、ガクっと元気が無くなってしまったように思う。戦争の話など、子供の頃は聞いたこともなかった。過去を誰に話すわけでもなく、ただ毎日を懸命に生きていた。 直接ではなく家族から聞いた、じいちゃんは中国に戦争に行ってたんだよ、と。そしてばあちゃんともう一度中国に行くためにお金を貯めているんだよ、とも。けれど生活は決して楽ではなかった。夢を叶えられないまま91になった。 私は仕事で中国に行くようになった。それまであまり興味も無かった中国。こんな時代だから、私はいとも簡単に行けてしまった。中国東北部、旧満州へ行った時には、祖父のために写真を撮った。何かを考えながら何度も眺めていた祖父の姿、吐き出されていく言葉、まるで60年以上も前にタイムスリップしたかのように鮮明に記憶を語ってくれた。祖父の目はあの時を見ていた。何年の何月何日に、どこどこで、日付までしっかりと覚えていた。脳裏に焼きついて離れない記憶、あの2年間は祖父にとって深く心に切り刻まれているのだと思った。『じいちゃんも人を殺したの?』これは聞けなかった言葉。『戦争が終わった時はどう思った?』「やれやれ、と思ったな。」じいちゃんは戦争が終わり帰ってくることができた。私はそれは当たり前のことだと思っていた。 けれど、帰れなかった人々がいる。奥村さんはじめ、2,600人の残留兵。あの時、同じ山西省、同じ太原で。戦争が終わってもまだ戦わなければならなかった。国を信じ、騙され、550人は亡くなった。生きて帰って幸せに暮らせたはずの人々の死。奥村さんは終戦後も中国内戦で戦い、その後6年2ヶ月もの抑留生活を送り、1954年、戦後9年も経ってようやく帰還。しかし、待っていたのは脱走兵としての扱い、非道な国の対応だった。そしてその闘いは今なお裁判という形で続く。「偽りの歴史は残してはならない。」力強く奥村さんは言った。国を信じ命を懸け、その国に裏切られた気持ち。私の祖父も奥村さんになるかもしれなかった、そうしたら私は今ここにはいなかった。『戦争は一度行ったら死ぬまで離してくれない。死ぬまでつきあわなければならない。』闘い続けている人々がいる。私たちはその声を直接聞ける最後の世代。時間との闘い、残された時間はない。私はずっと思っていた、祖父を中国に連れていってあげたいと。祖父の体の調子、生活、現実的に難しいと一度は諦めた。代わりに太原に行って、写真やビデオを撮って見せよう、と妥協した。けれど、やっぱり祖父を連れて一緒に行かなければ、そう思った。それを私は勝手に自分の指名のように感じている。行かなければ後悔する、祖父が亡くなったら私は一生後悔する。奥村さんに、そして監督に、今日はパワーをもらった。まずは知識を深め、祖父に話を聞く、ここから始まる。なかなか会えない祖父に、来週実家へ帰って話を聞こうと思う。
2007/02/18
コメント(1)
全8件 (8件中 1-8件目)
1