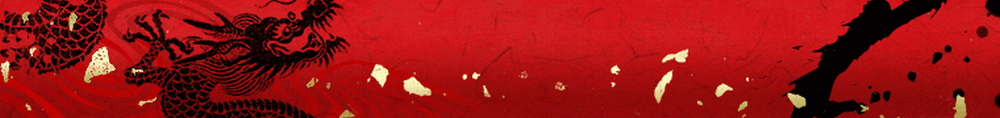* 昼過ぎから、発熱が始まって、風邪がぶり返したので、寝てばかりになった。今日の71は、帰りの国生みだが、やさしいこじき講座の紹介だけになった。
* 今回追加(再録)
* 宇摩説のブログは多岐に渡るためにほとんどのブログ記事には関連のURLが載っている。しかも、iza!のURLである。これで、引っ越すと、全て、使用不可になる。
つまり、私のiza!のブログは、別サイトに移行すると、記事の全てのURLの変更が必要である。移行しないとどうなるのか、よく判らないが、産経新聞の無責任な決定である。
宇摩説の「大人の古事記講座」71、国生み、吉備など
やさしい古事記講座40 国生み 帰途、吉備など
http://kabu003himiko.iza.ne.jp/blog/entry/405160/
<原文>
古事記原文
然後、還坐之時、生吉備児島、亦名言、建日方別
。
次生、小豆島、亦名言、大野手比売。
次生、大島、亦名言、大多麻流別。
次生、女島、亦名言、天一根。
次生、知可島、亦名言、天之忍男。
次生、両児島、亦名言、天両屋。
既生国
竟。
以上で、国生みが終わる。今日は、最初の一行が少し長くなるが、国生みの最後まで原文を載せておいた。
読み下し
シカル後、還りますの時に、
吉備の児島
を生む。亦の名を、 建日方別
(たけひかたわけ)と言う。
次に、 小豆島
(あずきしま)を生む。亦の名を、 大野手比売
(おおのてヒメ)と言う。
次に、 大島
(おほしま)を生む。亦の名を、 大多麻 流
別
(おおたまるわけ)と言う。
次に、 女島
(ひめしま)を生む。亦の名を、 天一根
(あまのひとつね)と言う。
次に、 知可島
(ちかしま)を生む。亦の名を、 天之忍男
(あまのおしを)と言う。
次に、 両児島
(ふたごしま)を生む。亦の名を、 天両屋
(あまのふたや)と言う。
通説の解釈
通説では、神名の解釈が、「名義未詳」となっている。だから、島の解釈だけがある。
吉備児島(きびのこじま) 岡山県の児島(元は島だった)。
小豆島(あずきしま) 香川県の小豆島(しょうどしま)。
大島 山口県の大島(屋代島)であろう。
女島(ひめしま) 国東半島の北にある姫島だろう。
知可島(ちかのしま) 長崎の五島列島をさす。
両児島(ふたごしま) 長崎五島列島の南の、男女群島の男島・女島であろう。
この最後の2島に比定されている島々には、異説があり、定まってない。後で検討する事にする。行った最初が淡路島なので、私は全て、瀬戸内海の島だろうと、思っている。
<以上>
* 帰りは、吉備・小豆島・大島・姫島と、瀬戸内の島になっている。淡路島、伊予の二名島から始まった国生みである。宇摩説の高天原四国中央説を裏付けるものであろう。
* あとの二つは、史学が長崎というが、朝廷の迷彩であろう。または、言葉の「近い島・両児島」では、全国至る所にあるから、各地の芝居の伝承地の島をまとめて加えた可能性もある。
< やさしい古事記講座40のコピー >
イザナギ・イザナミが大八島国を生み終えて、帰る時にも国生みがある。これを見ても、途中、8番目で切ったと思われる。さて、帰りの国生みで、最初の国は、 吉備児島
で、亦の名、「 建日方別
」と言う。
古事記原文
然後、還坐之時、生吉備児島、亦名言、建日方別
。
次生、小豆島、亦名言、大野手比売。
次生、大島、亦名言、大多麻流別。
次生、女島、亦名言、天一根。
次生、知可島、亦名言、天之忍男。
次生、両児島、亦名言、天両屋。
既生国
竟。
以上で、国生みが終わる。今日は、最初の一行が少し長くなるが、国生みの最後まで原文を載せておいた。
読み下し
シカル後、還りますの時に、
吉備の児島
を生む。亦の名を、 建日方別
(たけひかたわけ)と言う。
次に、 小豆島
(あずきしま)を生む。亦の名を、 大野手比売
(おおのてヒメ)と言う。
次に、 大島
(おほしま)を生む。亦の名を、 大多麻 流
別
(おおたまるわけ)と言う。
次に、 女島
(ひめしま)を生む。亦の名を、 天一根
(あまのひとつね)と言う。
次に、 知可島
(ちかしま)を生む。亦の名を、 天之忍男
(あまのおしを)と言う。
次に、 両児島
(ふたごしま)を生む。亦の名を、 天両屋
(あまのふたや)と言う。
通説の解釈
通説では、神名の解釈が、「名義未詳」となっている。だから、島の解釈だけがある。
吉備児島(きびのこじま) 岡山県の児島(元は島だった)。
小豆島(あずきしま) 香川県の小豆島(しょうどしま)。
大島 山口県の大島(屋代島)であろう。
女島(ひめしま) 国東半島の北にある姫島だろう。
知可島(ちかのしま) 長崎の五島列島をさす。
両児島(ふたごしま) 長崎五島列島の南の、男女群島の男島・女島であろう。
この最後の2島に比定されている島々には、異説があり、定まってない。後で検討する事にする。行った最初が淡路島なので、私は全て、瀬戸内海の島だろうと、思っている。
宇摩説の解説
まず、最初の吉備の児島は、吉備があるから、岡山に間違いは無いだろう。亦の名は、「建日方別」とある。これで思い出しと、国生みでは、四国の土佐が、「建依別」とあった。次は九州で、熊襲の国が、「建日別」であった。
また、九州で肥の国が、「建日向日豊久士比泥別」と、九州南部に、二人の「建の別」がいた。この九州の、「建日別」より、吉備の児島は「方」が多いだけで、類似した名前である。
そして、このように多い「建」は、「 たけ・たか
」と呼ばれた一族だと説明した。つまり、「 建は、建族
」だ、「 日は日之族
」と説明した。
この「建日方別」を、文字のままに理解すると、「建族・日の方・分け」となる。これは、建族の中で、高天原に協力した集団を意味している。つまり、高御産巣日神の縁者と日之神の夫婦に出来た子となろう。
纏めると、国生みの建族は、四国の南西に居た、「 建依別
」、筑紫に居た、「 建日別
」、「 建日向日豊久士比泥別
」、今回の吉備に、「 建日方別
」と、四人の建族が居る。そして、これ等の意味を、宇摩説だけが全て解いた。
また、「 天
」は高天原の神で、「 大
」、「 神
」は、近畿(大和)だろうとも書いている。これにしたがって、見直すと、この、6島は、「天」が三箇所。「大」が二箇所。「建」が一箇所になっている。
四国は、三国であって、北四国側の 伊予(予言の指導者)
つまり、高天原の卑弥呼を意味していた。そして、東南の近畿側になる「 アワに、大の神
」。西南の九州側の「 ウワに、建の神
」が居た。
四国も、高天原の、「天・日の神」と、建族の神・大族の神に分けられていた。このように、配分された族まで、宇摩説は解明を進めている。
この後、国生みを終えた二人は、神生みを始める。この中にも、「建雷神(たけみかづち)」と、建族の神が居る。
<以上>
-
修正>宇摩説の「大人の古事記講座」75… 2014年03月15日 コメント(4)
-
修正>宇摩説の「大人の古事記講座」74… 2014年03月15日
-
修正>宇摩説の「大人の古事記講座」73… 2014年03月14日
カレンダー
コメント新着