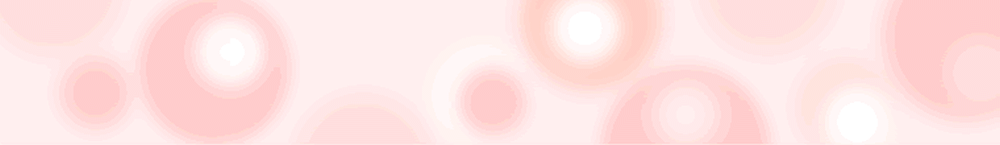♪ 古典のルールとちょこっとしたこと
その名の通り、古典です。(笑)高校でやってたノートをふと見返したのがきっかけです。
もともと古典はけっこう好きな教科(得意とは別!!)でした。
縦書きになれへんけど、まぁしかたないか・・・
間違えているところがあればごめんなさい。
2004年度、2005年度、の教科書です。
●本文=黒 訳= 青
本文中の()=(歴史的仮名遣い/ 現代仮名遣い )
途中から書いていません・・・
~古典の最低限のルール~
1. 語頭以外の「は」、「ひ」、「ふ」、「へ」、「ほ」は/ 「わ」、「い」、「う」、「え」、「お」 )です。
例)思ふ→思う、いらへん→いらえん。
2. 長音
a. やうやう → ようよう ( [Y]au → o)
b. てふてふ → ちょうちょう ( [T]e[H]u → yo )
c. きふしょ → きゅうしょ ( [K]i[H]u → yu )
3. ワ行
・(古典)わ・ゐ・う・ゑ・を
・(現代)わ・い・う・え・を
■ ア行:あ・い・う・え・お
■ ヤ行:や・い・ゆ・え・よ
●文学史
・上代(奈良時代)
・中古(平安時代)
・中世(鎌倉時代、室町時代)
・近世(江戸時代)
☆ 伝記物語
竹取(たけとり)物語→落窪(おちくぼ)物語→宇津保(うつほ)物語
☆ 歌物語
伊勢(いせ)物語→大和(やまと)物語→平中(へいちゅう)物語
★ 伝記物語と歌物語が合わさって、源氏物語(:作り物語)となる。
●「をかし」の文学:『枕草子』清少納言
・成立年代:1001~1003年(平安時代)
・ジャンル:随筆
●「あはれ」の文学:『源氏物語』紫式部
・成立年代:1008年
・ジャンル:作り物語
●古典3大随筆(随筆=エッセイ)
・枕草子:清少納言;1001~1003年に成立
・方丈記:鴨長明 ;1212年に成立
・徒然草:吉田兼好 ;1331年に成立
☆ 日記文学の流れ
土佐日記(935年頃、紀貫之、女流日記文学)→
蜻蛉(かげろう)日記(975年以降、藤原の道綱母)→
和泉式部日記(1007~1008年)、紫式部日記(1011年)→
更級日記(1059年頃、菅原の考標女)→
讃岐典侍日記(1108年頃、藤原長子)→
十六夜日記(1280年頃、阿仏尼)
●徒然草
・成立年代:1331年(文学史上、中世である鎌倉時代)
・作者:吉田兼好(兼好法師)
・古典三大随筆の内の一つ。随筆=エッセイ。
・徒然(暇、手持ち無沙汰の意味)
●竹取物語
・作者:未詳。
・成立年代:だいだい9世紀後半(800年代) ~ 10世紀初め(900年代)。
・現存する日本最古の物語。
・ジャンル:伝記物語
●「伊勢物語」
・ジャンル:歌物語(和歌を中心に、その内容を短い話として完結させ、その小説を集めたもの)
・成立年代:平安時代
・作者:未詳
・主人公:在原業平(ありわらのなりひら:平安時代前期の代表的歌人:六歌仙=和歌の名人、のうちの一人)を主人公とした歌物語(和歌の前書き=詞書、を広げて物語風に作ったもの)。
・恋愛を中心とした内容
・平城天皇―阿保親王―業平
・別名:在五が物語、在五中将物語 (※ 在原五位中将)
・伊勢物語の各段の冒頭の表現:昔、男ありけり。
●「十訓抄(じゅっきんしょう)」
・訓:教訓の意。
・抄:テキスト、教科書の意。
・ジャンル:説話
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-19 16:55:20)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 円安が進行
- (2025-11-20 15:15:12)
-
-
-

- 株式投資日記
- 資産状況(2025/11/20)
- (2025-11-20 16:18:24)
-
© Rakuten Group, Inc.