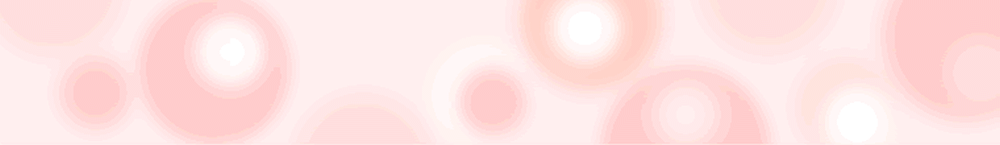『文字一つの返し』/十訓抄(説話)
『文字一つの返し』/十訓抄(説話)宮中の女性に御簾の中から手紙を渡されて、返事しようとしたら偉い人が来ちゃって、はやくどっかいかないとあかんから、機転をきかせて一文字だけかえることで返事したっていうお話。_(._.)_
急いでてもそうしようと思いつくところがすごいなぁ(・。・)
●十訓抄
・訓:教訓の意。
・抄:テキスト、教科書の意。
・ジャンル:説話
●成範
・ 藤原通憲の子
・ 平清盛の長女と婚約したが、解消した。
● 平治の乱(1159年)
■ 白河院政で、院政下、院近臣である藤原通憲が実権を握っていたが、
その時に平治の乱が起こった。
■ 平治の乱は伸西の専制強化による院近臣による対立で、保元の乱
(1156年)で戦功のあった平清盛と源義朝の勢力争い。
[結果&意義]
源氏が失脚し、平清盛による平氏政権の成立で、政治の実権が武士の手に移った。
・ 勝ち 平清盛(父)、平重盛(子)、藤原通憲
・ 負け 源義明、藤原信頼、藤原義平、源義朝、藤原成範
『文字一つの返し』/十訓抄(説話)
成範の民部卿 (しげのりのみんぶきょう) 、事ありて後 (のち) 、召し返されて、内裏 (うち) に参られたりけるに、昔は女房の入立(いりたち)なりし人の、今はさもあらざりければ、女房の中より、昔を思ひ出でて、
{ 成範の民部卿は事(=事件:平治の乱、権力者:平清盛、後白河上皇)があった後召還されて、宮中に参上なさった時に、昔は女房の入り立ちであった人が今はそうでもなかったので、たくさんいる女房の中からある女房が昔を思い出して、 }
雲の上はありし昔に変はらねど見し玉だれのうちやゆかしき
{ [歌意]
雲の上(宮中)は、以前(あなたがいた頃)と変わらないけれど(あなたが)見た、玉だれの中が見たいですか。 }
と詠み出だしたりけるを、返り事せんとて灯炉 (とうろう) の際に寄りけるほどに、小松の大臣 (おとど) の参りたまひければ、
{ と歌を詠んで(御簾の下から)出したので、返歌をしようと灯炉のきわに寄った時に、小松の大臣が参上なさったので、 }
急ぎ立ち退くとて灯炉の火のかきあげの木の端にて、や文字を消ちて、そばに、ぞ文字を書きて、御簾のうちへさし入れて出でられにけり。
{ 成範は急いで立ち去ろうとして(成範は配流の後に召還された身であり、既に入り立ちの身ではない上に、時の権力者は清盛の長男である重盛にかわっていたため、分不相応だから急いで立ち去ろうとした)、
灯炉の火のかきあげの木の端で、「や」という字を消して、そばに「ぞ」という文字を書いて、御簾の中へ差し入れて出て行かれた。 }
女房取りて見るに、文字一つにて返しをせられたりける、ありがたかりけり。
{ 女房がそれを取ってみると、文字一つで返歌をされていたのはめったにないことだった。 }
{ 文字一つで意味がどう変わったかは
・女房→成範
「うちやゆかしき(内がみたいですか)」:「や」は疑問の係助詞
・成範→女房
「うちぞゆかしき(内がみたいですよ)」:「ぞ」は強意の係助詞
・一文字を変えただけで問答になり、成範の機転の良さがうかがえる }

十訓抄

十訓抄の敬語表現についての研究
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 同情されて癒されていても仕方ないの…
- (2025-11-22 08:17:37)
-
-
-

- 楽天写真館
- 22 日 ( Saturday ) の日記 焦り…
- (2025-11-22 07:50:38)
-
-
-

- 楽天市場
- 【2025年最新版】「Nintendo Switch …
- (2025-11-22 11:48:35)
-
© Rakuten Group, Inc.