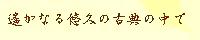おちくぼのあかね姫 5
「神子様、よろしいのですか? 今宵も友雅殿はおいでになります。3日間は通い続けるのが習いですから。そして、3日連続で通った日には、結婚したことになるのです。」
「……泰明さんは、『問題ない』って言ってたわ。」
「神子様のお気持ちが知りたいのです。」
確かめたい! 藤姫は強く思った。物語を進めたいだけで言うのか、本気なのか。
あかねの心にも迷いはあった。陰体の内とはいえ、友雅と夜を共にするのである。泰明は問題ないと言ったが、そこはやはり……。
あかねは顔を上げた。そして、きっぱりと言った。
「友雅さんが好きよ。前からずっと気になっていた。天真くんは、お上手を言ってるだけだから、と、心配していたけど、昨夜、私に本気だと言ったわ。私、友雅さんを信じたい。」
藤姫は、その言葉を聞いて、心を決めた。
露が、永泉からの文を持ってきていた。
「わたくしは、とある受領の家にやっかいになっています。
貴種の人間がうれしいらしく、何でも役立ちたいと言っています。
イノリ殿が、私の従者として一緒にいます。
神子は不自由していませんか。必要なものがあれば、何でも言付けてください。」
文にあったとおり、文使いにイノリが来ていた。
「あかねもここにいるのか? どうしてる?」
「ご不自由なお暮らしですわ。大変なことになってしまって……」
藤姫は、どこまで話していいのかわからなかった。
「とりあえず、少しでもお楽になっていただきたいのです。イノリ、永泉様に文を書きますから、届けてください。」
藤姫は、筆をとった。
「御文、うれしく拝見いたしました。
何一つ持たずにこちらに参りましたから、お召し物一つにもご不自由しておいでです。
お手元に、三尺の几帳がありましたら、お貸しください。
それから、あたたかいお召し物がありましたら、それもお貸しください。」
藤姫は、文をイノリに託すと、あかねの身支度にかかった。
単衣は、昨夜友雅がおいていったものを着せた。
袴は、三の君への出仕用に支給されたものをはかせた。
姫の持ち物としてわずかに残っていた鏡と櫛の箱を見栄えよく飾った。
そんなこんなで忙しくしているうちに、永泉から品物が届けられた。こちらが思うとおりの几帳と、紫苑色の綿入れの衣だった。藤姫は早速、衣をあかねに着せ、几帳を据えると、薫き物を取り出した。
「先日、四の君の御裳着のお式の残りといって三の君がくださったのですわ。いただいておいてようございました。」
こうしてすっかり支度の整ったところへ、友雅が頼久と共にやってきた。
「藤姫、神子姫のご機嫌は?」
いつもの友雅らしくなく、心配げな問いだった。
「泣いておいでになりましたわ。」
藤姫は、友雅の出方を見ようとした。どれくらい本気なのだろう……
友雅の顔色がさっと変わり、動揺の色が濃く見えた。
「私のせいなのだな……今宵は逢ってくださるだろうか。」
「……お逢いになりますわ。お部屋でお待ちです。」
藤姫には、友雅の心が読めた。これだけ本気なら大丈夫。たとえ元の世界であかねの心がこの出来事を思い出しても、本気で愛されているなら動揺しない……。
昨夜と違って、美しくしつらえられた部屋に、友雅は驚いた。
あかねも、昨日とうってかわって美しく装っている。恥ずかしさがなくなったからか、あかねの様子にもどこか落ち着きが見られた。
「私が差し上げた単衣を身につけていてくれたのだね、いとしい人……。」
友雅はゆっくりとあかねに近づき、抱き寄せた。どこからか、薫香の香りが漂ってくる。
あかねはゆっくりと目を上げて友雅を見た。二人の目と目が合う。あかねの目に深い信頼の色があった。
「友雅さん……。私、信じるわ。あなたのことを信じるわ。だから……」
「では、私と契ってくれるのだね? それでいいんだね、神子姫……」
あかねはこっくりとうなずいた。唇と唇が触れ合った。友雅の手がゆっくりとあかねの衣を脱がせ、あかねを優しく床に横たえた……。
頼久は苦しかった。
「神子殿は私の主、男として神子殿の前に立とうなど、おこがましい考えだ! でも、私は気づいてしまった。私の心の中で、どれほど神子殿の存在が大きくなっているか。
あの方のためなら命も捨てようが、あの方なしで生きていくことなど、私にできようか……。」
藤姫も、頼久の苦しみには気づいていた。あかねが頼久を外出の供に選ばなかったときの頼久の落胆ぶりを見ていたから、頼久が気づくより前に、頼久の恋には気づいていた。
「頼久。神子様は、友雅殿をお選びになったのです。これは、神子様のお気持ちなのですよ。」
「それはわかっております。こうなっても、あの方は私の主。今まで通り、警護もいたしましょう。今まで以上にお守りいたします。ですが……」
「あきらめましょう。かなわぬ恋なのです。私だって……」
藤姫の頬を涙が一筋伝った。兄のように慕っていた友雅の少将。鳴神におびえた自分をやさしく守ってくれた。支えられていると気づいたのはいつ頃だったろう……。
恋人達には短く、待ち人達には長い夜が明けようとしていた。
頼久は、あかねの部屋の外で軽く咳払いをし、友雅に迎えが来たことを知らせた。
「車が来たようだ。ああ、このままあなたをさらって連れて行きたいが……」
「……だめなの?」
「まだ時が熟していないのでね。」
あかねは友雅の胸に顔を埋めた。侍従の香りを胸一杯にすいこんだ。
「藤姫が、3日間通うのが結婚の作法だと言ってたわ。今夜も逢えるの?」
「もちろん、姫が望むなら。私でいいのかい?」
あかねは、答える代わりに両腕を精一杯伸ばして友雅にしがみついた。友雅は、あかねをしっかり抱き返した。
「今宵また。待っていておくれ。」
友雅はあかねに軽く口づけすると、部屋を出ていった。
次へ
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 競馬予想
- エリザベス女王杯、△は10と15。頭は…
- (2025-11-16 11:36:57)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- LEGO ‐ Star Wars ‐ | レゴブロック…
- (2025-11-15 21:55:46)
-
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-
© Rakuten Group, Inc.