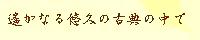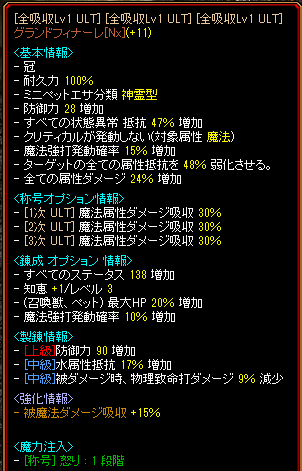全760件 (760件中 1-50件目)
-
割烹民宿 まきの
7月の宿変更。ご飯がおいしそうだからここで1泊。ただし、同行者付き。 割烹民宿 まきの
2015年05月17日
コメント(0)
-

重慶飯店 麻花 6本入り
海老名のSAでお土産の保険で買ったんだけど、自分がやみつきになった。お取り寄せできるなら常備おやつにする~。 重慶飯店 麻花 6本入り
2015年03月04日
コメント(0)
-
雨宿 (友雅×神子) 後編
通された部屋は友雅のよく知る部屋だった。が、主の姿はない。「主はお方様の御前です。私が申しつかっておりますので。」 門前に宿る人影の報を仕える貴人の前で聞いたのだろう。助けてくれようというのは心根からか、或いは場の空気からやむを得ず、か。 女童が設えてくれた座に腰を下ろし、友雅は部屋主の記憶を辿っていた。心ざまはどんなだったろうか、なぜ、通うのをやめたのだったか……。「お召し物を乾かしますから、どうぞこちらへ。」 女童が神子を部屋の奥に几帳を立て回した中へ誘っている。どこまで言いつけられているのか、どうやら几帳の中には女物のひと重ねが用意されているらしい。今着ている物を脱ぐように言われて神子が戸惑いの声を上げた。「神子殿、こちらからは見えないから安心していいよ。」「友雅さん!!」 声がとがっている。「そのままではお風邪を召されてしまいますからどうぞご遠慮なく……」 促されてしぶしぶとかどうかはわからないが着替えを始めたらしい。衣が擦れる音が几帳の中から聞こえてきた。 見ないようにしていることなど神子には見えまいが、友雅は体を庭に向けた。夜更に訪れて日の昇る前に去るのだったから、この家の庭を明るいうちに眺めるのは初めてだった。家主はかなりの趣味人と見える瀟洒な作りの庭だ。女房の部屋に面した部分でこれだから、母屋の方はいったいどれほどか。(何かの遊びに招かれたのだったはずだが……) 朧な記憶からは何も思い浮かばない。自分から求めて通ったのではなく、何かのはずみでそうなったはずだ。おそらく、この部屋主の方から文がつけられて、何となく興惹かれて返り事をして、そして。 調度に見覚えがあるのだからかなり足繁く通ったのだろうに、なぜ覚えていないのか……。 はたはたと足音がして、手元に衣装箱が置かれた。「少将様もどうぞお着替えなさいませ。」 女童が持ってきたのだった。開けてみると、いかにも友雅の好みそうな色目の真新しい装束がひとそろい入っていた。 驚きの目を女童に向けると、得意そうに鼻をうごめかせて言った。「見事なできばえでしょう? 私もお手伝いさせていただけてうれしゅうございました、少将様。こうしてお役に立つ日が来て、主もとても喜んでおります。」 衣まで縫って待っていた……自分はこんなに忘れているというのに。 几帳の影から声がした。「友雅さんの恋人でしょう? この子のご主人って。」「ああ…そのようだ。」「そのようだって……違うんですか?」「別れたのだよ……いつだったかも忘れるほど前にね。」「忘れちゃったんですか!?」「ああ、またそんなに声をとがらせて。京の姫君はそんな声を出すものではないよ、神子殿。」 からかう顔を女童に向けると、目にいっぱい涙をためているのが見えた。泣きそうなのをこらえて女童は言った。「主に……少将様がお部屋にお入りくださったと伝えて参りますから……どうぞお召し替えくださいませ。」 どこまで伝えるのかと問う暇も与えず、女童は部屋を後にした。友雅は仕方ないねと嘆息して着ている物の紐をほどき始めた。心当たりが見つかったような気がしていた。もし自分の勘が間違っていなければ、自分が通わなくなった理由を女はよくわかっているはずだと思った。ちょっとしたすれ違い、どちらが悪いというわけでもなく、自然と消えてしまった恋だと友雅は思っていたのだが……。 濡れて少し重さを増した直衣の紐を解いた。単衣も湿って雨臭かった。衣装箱のひと重ねは心憎いほどに友雅の好みに合わせてあったから、若干心が痛まないわけではなかったけれど、友雅は遠慮なく濡れた物すべてを脱ぎ捨てた。「さて、と……」 一人で着られないこともないが、手伝いの手があった方が望ましい。後朝の名残に人目を避けて帰るならともかく。 手伝いと言っても結びにくい紐を見栄よく結んでくれればいいので、先ほどの女童でもと思っても女主の元へ行ったまま戻ってくる様子もない。(猫の手よりはましかな) 異世界の少女だが、紐の結び方くらいは知っているだろう。毎朝自分で着て出てくるのだから。「神子殿。すまないが、少し手伝ってはもらえまいか。君がいつも結んでいるようにこの紐を結んでくれればいいのだが。」 友雅が近寄る気配を察してか、几帳の内から悲鳴があがった。「いや、だめ、来ないで、友雅さん!」「どうして。」「ダメ、いやなの、近寄らないで、お願い! 恥ずかしいから!」 何を恥ずかしがっているのかは想像できた。いつもの服装と違うことが面映ゆいのだ。「かまうことはないよ、今ひとときの借り着だろう? 君が嫌だというなら無理は言わないつもりだが、この紐を自分で結ぶとどうにも見栄えが悪いから、こんな昼間に女性の屋敷で何をしてきたかとまた余計な浮き名が立つのも面倒でねえ……」 大げさな嘆息をまぜて几帳の内へ言ってみた。どのような衣装を着て神子がどんな風に変わったかを見てみたかった。 友雅の思惑通り、几帳の端がもぞと動いた。神子の小さな頭が少しだけ布端から覗いた。「友雅さん、困ってるんですか?」 笑い出したいのをこらえ、困り切った顔をわざと作って、友雅はうなずいた。「そうだよ。こんな昼間から着崩れた姿では外へ出られない。助けてもらえまいか、神子殿。君の力が必要なのだよ。」 着ている物を隠すように尼削ぎの頭が几帳から出てきた。神子にとっても、身仕舞いのできていない友雅は初めてだ。だらしなく直衣がたるんでいる姿に驚いたのか、隠れることを忘れたように几帳から急いで出てきた。「どこ、結んだらいいんですか?」 こことこことと指さして教えた。言われるままに丁寧に蝶結びしていく神子を、友雅は黙って見下ろしていた。それなりの年齢なのに童女のように切り揃えてある髪の先がゆらゆらと袿の襟元にかかっている。神子のいた世界では髪を長く長く、身の丈に余るほどにも伸ばすことはないのだそうだ。その若さで出家したかと思われるような髪と華やいだ撫子色の衣の不釣り合いさは最初こそ友雅の目には滑稽だったが、今こうして改めてみるとかえってかわいらしく、どこか友雅の好色心をくすぐる危うさまでも感じさせる。(これが龍神の神子たる所以かな。) 手の届くところまで近づいている不用意な体を抱きしめてしまいたい衝動。そしてそれを押さえる自分でも笑い出したくなるほどの自制心。そんなものが自分にあったとは思えなかったが、どこかからわいてきたにしろ外から与えられたにしろ、それはきっと龍神やこの少女のもつ力のせいだろう。 直衣の前垂れの下で帯を結べば終わり。おぼつかない手では無理だろうと前垂れをたくし上げておくのを神子に頼み、友雅は帯を締め上げた。締めにくかろうと後ろから友雅を抱えるようにたくし上げている神子の手は衣の重みに負けて下がり、帯を締める友雅の手に触れてしまう。その感触にびくっと怯えてまたすぐに戻るが、どんな顔をして持っているのかと思うと自然にくすりと笑える。 飾り帯を着けるのももどかしく、友雅は神子の手を捕らえた。逃げようとする手をしっかりつかみ、体の向きを変えて神子の顔をのぞき込んだ。 案の定、恥ずかしさに真っ赤に染まった顔。(可愛い……) 口づけてしまいたい衝動が突き上げる。逃れようと身をもがく神子の体をすくい上げ、強く抱きしめたその時。「神子殿!」 よく知る声が庭から聞こえた。友雅の手から力が抜けた。慌てて逃れる神子の顔には安堵の色があからさまに見える。華やいだ撫子の重ねの愛しいものは、あんなに友雅の目に触れることを嫌がったのに、迎えに来た武士の前には何事もないように出て行くのだと見える。(妬いているのか? 私は。) 自分の心の動きの一つ一つが不思議だった。友雅の所行を目にしただろう武士は友雅には警戒心に満ちた視線を向けるが、神子のことはついぞ見せたこともないだろう優しい瞳で見下ろしている。見上げる神子も信頼しきった目で武士を見つめている。この二人の関係も神子とそれを守る八葉であることに変わりないのだが、それ以上の想いを通じ合ってはいないか?(だとしたらどうだと言うんだい?) 自分はいったいどうしたいのだと自問自答する。普段ない屈託はつい外へ出てしまうものか、神子が怪訝そうに友雅を見た。「どうかしたんですか? 友雅さん。」 ……君のせいだよ。 こぼれた屈託を拾い集め、いつもの余裕を努めて前に出す。「……お迎えも来たようだ。失礼しようか、神子殿。」 借りた衣装のことを気にする神子を促し、車に向かった。「どうして頼久さんがお迎えに来てくれたんですか?」「友雅殿の御車が空でどこかへ行くという知らせがありましたので、藤姫様が私にお命じになりました。」 あの小さい姫君は聡すぎると友雅は苦笑した。出かけた衣装と異なる姿で館に戻ったならどうなることか。 友雅は空を仰いだ。降り止まぬ雨が冷たい。「馬を。」 従者が引いてきた馬に跨がった。 神子を乗せた牛車が静かに進み出した。共に乗らなかったからか武士の警戒の色が少し薄らいだように感じられる。牛車からも大きな安堵のため息が聞こえた気がした。(嫌われたものだねえ……) ふふと笑むと、友雅は馬を駆けさせた。この訳のわからない想いを振り捨ててしまいたかった。お待ちくださいと止める従者の声は遠かった。
2012年01月20日
コメント(0)
-
雨宿 (友雅×神子) 前編
雨宿「おや。」 ぽたりと袖を打った雨粒に、友雅は空を見上げた。さっきまで抜けるようだった青空が暗く曇って、こらえきれないとでもいうように大粒の雨がぼたりぼたりと道をぬらし始めた。「神子殿。」 あわてて走り出そうとする少女を呼び止め、広袖にかくまうように抱いた。恥じらう神子が身じろぎ逃げだそうとするのを押しとどめ、抱えるように走って近い屋敷の門の屋根下に雨宿り、供人に車を取りに行かせた。 広袖の中の神子の震えが止まらない。「寒いかい?」 神子は首を振った。雨宿ったのだから不要だとばかりに広袖から逃げ出した。「ふふ……かわいいね。」 神子は真っ赤になった。警戒心をあらわにして友雅と距離を取った。「どうしたの。そんなに離れたら濡れるよ。」「大丈夫です。ここ、まだ屋根がありますから。」 好きにさせるさと友雅は目をそらした。視線は自然に雨宿った屋根に向いた。(……見覚えがあるような。) そこにあったから飛び込んだ屋根だったが、確かな記憶にはなさそうだった。従者のひとりが神子を気にしながら告げた。「……ここは、以前……」「ああ……」 前に通っていた屋敷だったらしい。どういうわけで別れたのかも忘れた。通い始めたきっかけも朧だった。やりとりしたはずの文も、肝心の女の声も顔も忘れかけて、隣にいる神子や館で待つ姫君が目を剥いて怒りそうな、そんな戯れの跡のようだ。 どうしたものかと思ううちに、門扉の横の小さなくぐりがぎ…と開いて、こざっぱりした衣を着せられた女童が顔を出した。よくしつけられているのか、気後れすることなく友雅に近づき、「そんなところではお困りでしょうからどうぞ中へと主が申します。」と、はきはきと告げた。 友雅は少し躊躇したが、隣の神子は気の強い風を見せながらも肩は寒そうに震えているし、止みそうにない雨は更に強く屋根下にも降り込んで、気づけば神子も自分もすっかり濡れていたのだった。「お言葉に甘えましょうとご主人に。」「はい、ではこちらへ。」 案内するというので友雅は神子を見返った。「神子殿、行くよ。どうやらここは私の知人の家だったようでね。」「知人?」 先ほどからのこそこそしたやりとりが耳に入っていないはずはない。神子の眉がいぶかしげに顰められる。友雅は悪戯にくすりと笑った。神子の眉根が今度がきっとつりあがって友雅をにらみつけた。「ふふ、全く君は……見ていて飽きないね。」「どういう意味ですか!?」「ああ……君の相談役をアレに頼んだのは私の失策だったようだ。」 神子の眉がますますつり上がるので友雅はおかしくてたまらなかった。からかいがいのある娘だ。いい退屈しのぎになる。しかし、遊んでばかりはいられない。「すまないね。しかしこのままでは車が来るまでにずぶ濡れだ。お言葉に甘えることにしよう、神子殿。彼女に連れて行ってもらおう。」 友雅が指す方向に可愛い女童を認めて神子の顔は和んだ。女童がまたいかにも愛らしく微笑むから、神子の機嫌はすっかり直った。「行きましょう、友雅さん。」 先に立って歩いて行くのがおかしくて友雅はまたも吹き出しそうになったが、ぐっとこらえて後に従った。
2012年01月20日
コメント(0)
-

初夏(友あか:まだ絆が深まらない頃の)
初夏(まったく、私らしくないねえ。) こんなにも君の背中がまぶしいなんて。 その背を抱きしめて、振り向かせて口づけを。 軽くあらがう君に目隠しをあてがってどこか遠くへ連れて行こう。 君のためなら空も飛べる。月の迎えなど来ないよう、光の道をふさいでこよう。君が私だけを見ているように、闇の帳が二人を優しく包むように。 言の葉だけは胸の内でいくらでも紡がれるのに、口に出すことができない。 どれも今の神子にはふさわしくなく、どれも自分の本心ではない。いや、もともと本心などないのかもしれないが。 目の前を藤姫と笑い合って歩く神子。 京の衣服に似た神子の世界の衣。(浴衣と言っていた。) 湯浴みの後に着るから名付けられたのだと神子は屈託なく語った。(まったく、どういう想像をさせるのだろうねえ。) 無邪気この上ない。 しかし、こんな少女の他愛ない一言にこんなに動揺するというのは実に自分らしくない。(まったく、どうしたというのだろうねえ。) 遠くでイノリが神子を呼び立てる。今日は東寺の縁日に来たのだ。庶民の暮らしぶりや鄙ぶりの食べ物は貴族である友雅には珍しく、日常から外れたこんな空気が、友雅の平常をも奪っているのかもしれない。「友雅さん、こういうの、食べたことありますか?」 神子が目の前に差し出したのは、串に刺して焼いた鮎だった。「旨いぜ、食ってみろよ。」 鮎は旬の食べ物だから食膳に上らぬことはないが、串刺しのままかぶりつくのは初めてだ。 どこから食せばいいのかと戸惑い顔の友雅を、イノリが不思議そうに見上げた。「友雅でも知らねえことあるんだな。」「このように食することはないからね。」 藤姫には神子が食べさせていた。指でほぐして口元に運ぶ。おそるおそる口に入れた藤姫から感嘆のため息が漏れる。「おいしいですわ、神子様。鮎というのは魚だったのですね。」「鮎は魚だぜ、そんなことも知らなかったのか?」「神子様がしてくださったような形でお膳に載ってくるのですもの……」 半ば呆れ顔で鮎の講釈を始めるイノリの横で、友雅は串のまま、鮎をほおばってみた。香魚の名の通り、しっとりした香りが鼻腔に広がる。焼きたての香ばしさ温かさも舌に心地よい。「友雅さんにはこれも欲しいでしょう?」 神子が徳利を差し出した。「ふふ、気が利くね。」「だって、今日はお祭りですもの。」 ふわりと笑って、神子は行ってしまった。藤姫やイノリと連れだって。 渡された徳利を広袖に隠して、友雅も後を追うように歩き出した。見失って間違いでもされてはかなわない。土御門の公務で出かけられなかった頼久や検非違使の補佐役の「ばいと」に出ている天真に何を言われるかわからない。(くわばらくわばらというやつだからね。) 神子の背中を見逃すはずはなかった。何しろ今日はどうしたわけか殊更に輝いて見えるのだから。(まったく、何がどうしたというのだろうねえ。) 神子がもたらした一掬の酒がそうしたとでもいうことにしておこうか。 今度は餅菓子の屋台で立ち止まっている一行に、友雅はゆるりと追いついていた。
2011年06月11日
コメント(0)
-
【友藤】 目が離せない人
篠突く雨の音が友雅を浅い眠りから揺り起こした。(雨……) 手近にある柔い温みをいつもの習いで抱き寄せた。主の求めに抗わない伽の温みを気のない手つきで弄ぶ。艶めいた小さなうめきがあがっても、友雅がそれに動かされることはない。それは単なる習慣に過ぎないから。「あ……」 若様、と呼ぶ前に友雅は伽をうち捨てた。立ち上がり、妻戸を押し開け、夜着のまま廂へ出た。 激しい雨音と雨の匂いに満ちている。友雅は目を上げ、庭を見た。雨の中に混ざるかすかな香り……救いを求めるような。(私を待って……いるのだろうねえ。) 友雅は黙って部屋に戻った。几帳の外に控えていた伽に衣の用意を言いつけた。かしこまりましたと差し出された衣に袖を通し、友雅は後ろ髪を束ねた。「出かけるよ。」 呼ばれて庭へ控えた従者が困惑顔で友雅を迎えた。「この雨の中をどちらへお出かけですか、若様。雷まで鳴り出しましたが……」「だからこそ出かけなくてはならないのだよ、約束をしたのでね。」「では……」 友雅を乗せた網代が動き出した。友雅は重ねた袖の端を少しばかり御簾の外へはみ出させた。女車の振りをして門番の目をごまかすつもりだった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆(来てくださるのでしょうか。) 几帳の陰で震える小さな影は、友雅の約束を覚えていた。(まるで後朝の別れのようだと言ったらあなたの乳母殿に叱られそうですね。) あの夜、冗談めかして笑いながらこの単衣を脱ぎ置いていった、優しいけれど悲しそうな色の目をした人。怖いことがあったらこの単衣を抱きしめていなさい、その香りが消える前にきっとあなたを守りに来ましょうと言った。(恋人をしょっちゅう取り替えるような人です。私との約束なんかきっと覚えてなどいらっしゃいません。) それでもこの小さな姫は単衣にくるまらずにはいられなかった。歳よりも大人びたこの姫は、怖いからと仕える者を呼び立てることをよしとしていない。大雨も鳴神もしばらくすれば去る。本当に危険なときは乳母も頼久もきっと助けに来る。怯えに取り憑かれるのは己の修練が足りないから。けれど、怖いものは……怖い! 侍従の香りがほのかに薫る単衣をぎゅっと握りしめ引きかぶり、姫は几帳の陰に隠れた。暗闇を裂く稲光も静寂を打ち破る雷鳴も几帳を立て回した奥なら耳目に入るのはほんの少し。我慢できると思った。そのときまでは。 昼とも見まがうばかりに庭が白く光った。続いて地を引き裂かんばかりの雷鳴。(ひっ……) 叫びたくなるのをぎゅっと食いしばって堪えた。侍従の単衣をいっそう強く引き被った。ぴりと絹の裂けるような音がしたがそんなことは気にならなかった。今はとにかく、あの鳴神から、身を、守りたい。逃げたい。避けたい。(怖い……!!) 堪えきれない声が食いしばった唇から漏れる。堪えた分は涙に変わって目から溢れる。堰が切れたらもう我慢はできなかった。姫は泣き出した。激しい雷鳴は姫の声をかき消すほどだったから、姫はもう堪えることをしなかった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 藤の馥郁とした香りが姫の目を覚まさせた。 あの激しかった雷雨がなかったかのように外は穏やかな光に満ちているようだった。姫は潜り込んでいた衣からおそるおそる顔を出してみた。(あら……?) 確かに引き被り潜り込んでいたと思った衣は、明らかにはじめの物と異なっていた。なのに薫きしめられた香はあの衣と同じ匂いを漂わせている……あの衣よりも新しく濃く。(何があったのでしょう……何も覚えておりません。) 立て回した几帳は一つも変わらず、変わっているのは確かに隅で小さくなっていたと思うのに、中央に敷かれた寝衾に常と変わらず横たわっていたことだった。そして上からすっぽりとかけられていたこの衣。昨夜引き被いた衣は桜を思わせる淡い紅だったのに、今手にしているのは姫の好む藤の色を映したかのような紫苑色だった。「お目覚めですか?」 乳母が顔を出した。姫は尋ねた。「これは?」「あら、覚えていらっしゃらないんですか? 昨夜遅くにおいでくださいましたのに。」 あの雷鳴の中を乳母を訪ねてきた振りをしてやってきたのだと乳母が話した。几帳の奥で震える姫を抱え上げて寝衾に運び入れ、懐深く抱きしめて何度も背をなでていたと。「ご覧なさいませ。」 文机の上に置かれた硯箱の中から、乳母が文をとりだして見せた。 開けて読むなり、姫は耳たぶまで赤くなった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 土御門から文というので友雅は起き上がった。(まるで後朝の文のようだね。) 乳母にはその心づもりがあるのかもしれないなとちらり思いながら、友雅は文を開いた。彼の姫の言の葉が歳よりも大人びた筆跡で、しかし多少の動揺を隠しきれずに並んでいた。(ふふ。) かわいいねと、友雅は文を文棚にしまった。文殻として捨てる気にはなれなかった。どういうわけでこんなに心にかかるのか不思議なほどだった。(これを「縁」と言うのだろうかねえ……。) まだ年端も行かぬ少女だというのに。友雅は持ち帰った単衣を横目で見やった。桜色のそれは一部湿りを帯び、袖の縫い目がほころびていた。さぞかし怖かったのだろう、小さな手は血が出はせぬかと思うほどに固く握られ、友雅の力でも容易にほどけぬほどに強ばっていた。呼ぶまで来るなと言われていると手をこまねいていた乳母が狼狽するほどに蒼い顔をして、震えていた。我を失っている姫をどうしてあれほどに愛しく思えたのか。何か温かい、しかし恋よりもずっと持ち重りのする感情を、なんと呼ぶのだろう。 我を失った姫を抱きかかえ、背をなでて添い寝した。清らかな乙女に暗い情欲など似合うはずもなく、寝息が穏やかに整うのを聞き届けて友雅は几帳を出てきた。激しかった雷雨もその頃にはすっかりなりを潜め、西の空低く輝く月がもの言いたげに友雅を見下ろしていた。(目を離せぬとね。) 誰が誰にと独りごちて、友雅は文机に向かった。今宵行くよとさらりしたため、昨夜自分を駆り立てた藤の花穂に引き結んだ。 友雅はぱんと手を打った。御前にと従者が顔を出した。「使いをしておくれ。土御門の小さな姫君に。」。 どんな顔で出迎えてくれるのか楽しみだった。お出かけですかと女房が差し出す衣に手を通した。
2011年05月22日
コメント(0)
-
君の楽にぞ惹かれてむ(舞一夜ベース 友あか)
つんつんと袖を引かれてあかねは自分が寝ていたことに気づいた。はっと周りを見回すと、心配げに見上げる藤姫と目があった。「神子様、お疲れですか?」「あ、ううん、大丈夫。そういうわけじゃないんだけど……」 藤壷中宮に誘われて出席した、御所の管弦の遊びだった。帝の御前でもあるし、楽人の中には友雅もいるし、眠っていい場面では決してないのだが、ゆったりした雅楽の音色は思いの外心地よく、ちょっと油断して目をつぶっていたらそのまま寝ていたらしい。 御簾の向こうの舞台から視線を感じる。うつらうつらと影が動いたのを見られはしなかっただろうか。たどれば友雅がそこにいると知っているから、あかねはそちらを見なかった。打ち物の楽人の姿勢が改まり、新たな曲の始まりを知らせる龍笛が響いた。友雅の音色だと藤姫がうっとりとつぶやいた。あかねは、ここへ出席することになった顛末を思い出していた。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ その日も、あかねは琴の練習に余念がなかった。「精が出るねえ、神子殿。」 いつも通り、さぼる口実にあかねの部屋に隠れに来ていた友雅が呆れたように言った。「だって、面白いんですもの。」「そうかい? さっきから同じところばかり繰り返しているようだけれど、よくも飽きてしまわないものだね。」「弾けないと悔しいです。友雅さんは悔しくないんですか?」「私かい? そうだねえ……」 友雅はやおら身を起こしてついとあかねのそばへ寄った。あかねが身を翻すようにして座を移るのをふふと苦笑いで見送って、琴爪をはめた。 あかねが苦労していた節をいともあっさり弾いてのける。 しかも、華やかなきらきらしい音色で。(すごいな。) あかねが寄せる感嘆の視線が心地よい。友雅が奏でる様子を食い入るように見ている姿がかわいくて、友雅は同じところを幾度か繰り返してみた。「どうしてそんな風に弾けるんですか? 友雅さんも練習……」「そんな面倒なことを私がすると思うかい?」「……思いません。でも……」「嘘だよ。小さい頃は私も人に劣るのはいやだったらしくてね、少しはがんばっていたのだと思うよ。でも、極めようとかさらに磨こうとかそういう気にはなれなくてね、そういうのも、飽きたと言うのだろうねえ。」 次々に恋人を取り替える今の友雅とイメージがかぶった。きっと同じように、次々と挑戦する物をかえていったのだろう。 友雅が琴の前を空けたので、あかねはまた琴の前に座った。友雅の手の通りに弦に指を置き、弾いてみた。(あ?) 音が変わったと思った。「おや、なかなか飲み込みがいいね。素直だからかな。」 友雅が横から手を出してきた。「そう、もう少し軽くね。弾くというより掻く感じかな。」 無駄に力を入れていたところがこつを得て抜けたのだろうか。軽々ときらきらと弾けるようになってきたから、あかねの瞳も輝いてきた。「最初から弾いてごらん、神子殿。今ならきっとできるよ。」 友雅が蝙蝠を開いて立ち上がった。あかねの奏でる音に合わせて舞い始めた。(え?) あかねはあっけにとられた。嗜みなのだから友雅が舞えないはずはなかったが、管弦の才の方が目立つのか、所望されることもなければ自ら舞うなど言うはずもない。それが、あかねの琴に合わせて舞って……いる。「友雅さん、急にどうしたんですか?」「さあ、どうしたのだろうね。君の琴を聴いていたら、体が動いてね。」 やめないでとあかねに言い、友雅は舞い続けた。 体の中から何かが突き上げてきたのだ。呪でもかけられたかのように蝙蝠を開き、手舞を始めていた。不思議な心地よさを感じた。音に抱かれ、音を抱きしめる。面はゆいほどだった。自分のどこからこんな情熱がわいてくるのかと。 友雅が自分の演奏で舞ってくれるから、あかねもうれしかった。間違えて友雅が困らないようにと懸命に弾いた。友雅が打ち鳴らす蝙蝠のリズムに合わせて夢中で弾いた。「少将殿が舞ってらっしゃいますわ!」 廊下で声がした。とたんに、周りの部屋から女房たちが集まってきた。「おや。」 舞の手が止まった。がっかりした声が上がった。「ではね、神子殿。」 ぱちんと蝙蝠を閉じると、友雅は部屋を出て行った。もっと舞ってほしかったとねだる声に「またね、姫君方」といつも通りに流す声が遠くなっていく。「ねえあなた、どうして少将殿は舞ったの?」「あなたの琴がよほどすばらしかったのかしら、ねえ、私にも教えてくださる?」「もっとお弾きなさいよ、戻ってらっしゃるかもしれなくてよ。」 口々に言う声にあかねは困惑しながらも言われるままに琴を弾き続けた。押さえる手に弦の跡がくっきりついて痛かったけれど、友雅の舞姿を思い出すと、弾く手は止まらなかった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「実に参ったね、御達の噂話ときたら、あの後すぐにお召しがあって参上したらもう帝のお耳に届いていた。」 管弦が終わった後の宴で、友雅が近くに寄ってきて言った。「居眠りしていたね、神子殿。」「……ばれてました?」「耐えられないというようにかくんと首が落ちたからね。笑いを堪えるのに苦労したよ。」 やっぱり見られていた……あかねは首まで赤くなった。「ごめんなさい、寝ちゃうつもりなんかなかったんですけど、なんかすごく気持ちよくて……」「いいよ。よい楽の音はよい眠りを連れてくる。酒と同じさ。あの楽が君に眠りをもたらしたのなら光栄だね。」 友雅が満足そうに言った。そのとき。「橘少将、今宵は舞わないのかしら?」 中宮の声だ。参ったねと友雅は蝙蝠の先でこつんと額をついた。「仰せのままに。」 中宮の意向が楽人に伝えられたらしく、舞台の楽が「青海波」を奏で始めた。「少将殿が舞われるぞ」と舎人が呼ばわる声がした。 翻り翻る袖。篝に照らされた友雅の顔は翳りを帯びていつにまして美しい。 ほうっというため息が庭に満ちた。「今宵は珍しい物が見られることだね。これも神子殿の人徳かな。」 帝の声に、あかねはまたかあっと赤くなった。
2011年01月24日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 満月(友雅×あかね)
夕焼け小焼けで 日が暮れて 公務を終えて帰宅した友雅の耳に入ってきたのは、あかねの澄んだ細い歌声だった。友雅の知らない歌。おそらく、あかねのいた異世界の楽なのだろう。 まるい大きなお月様(お月様、ね……) 声をかけようとしたところへちい姫の声が聞こえたから、友雅は言葉を引っ込めた。妻戸の陰に隠れて、垣間見の姿勢を取った。気づいた女房が何か言いそうにしたのをしいっと制した。「お母様、月にはウサギさんがいるのでしょう?」「そうだよ、ほら、月に模様が見えるでしょう?」 東の空に浮かぶ月にはくっきりと兎に見える黒い影が見える。くまなく明るく光る月を見上げて話しているのだろう。とすればかなりの端近、直衣の端でも見えてはと、友雅は壁にさらに身を寄せた。「お父様が、月には姫君がいるとおっしゃいました。お母様、お月様からいらしたお姫様の物語を聞きたい。」 吹き出しそうになるのを友雅は必死で堪えた。月の姫はちい姫になんと答えるのか。「お父様が……?」 困惑げなあかねの声音。(いったい、友雅さんは誰の話をしたんだろう。嫦娥のことか、かぐや姫か、もしかして……!?)「はい、では、絵巻をお持ちしましょうね。」 乳母の声に友雅は大きく嘆息した。あかねには大きな助け船だったろうが。(しかたないねえ……) 友雅は蝙蝠をぱちんと鳴らした。心得ましたと控えていた女房が妻戸を開ける。「あ、お帰りなさい。」 極上の笑みが二つ、友雅を迎えた。一つは大きく手を広げてかきついてくる。「お利口にしていたかい? ちい姫。」「あい、お父様。お父様、月のお姫様のお話をして。」「ふふ、すっかり気に入ったようだね。」 友雅はあかねに背を向け、ちい姫を膝に置いて低い声で話し始めた。「お父様が帝のお召しで出かけるとね、空が不思議な色に光っていたんだ。八色の光というのをお父様は初めて見たね。何の徴だろうと思っていたら、空を割って、一人の姫君が降りてきたんだ。従者を二人連れてね。」 あかねの顔がみるみる赤くなった。「友雅さん、それは……!?」「何だね? 私は姫にちょっとした昔語りをしているだけだよ。」「だって、昔語りって、それ、その話は……!」「止めるかい? 姫が続きを聞きたがっているのだけれどね。」 ちい姫の期待に満ちた丸い目に、あかねは口をつぐんだ。友雅の目から見たその話を聞くのは初めてかもしれないと思った。 心のかけらの話、札を集める話、そして、最後の戦いの話。「お父様もそのお姫様とがんばったの?」「ああ、時々しかられてしまったけれどね。」「しかられるって……お父様はまじめではなかったの?」「はは、対の男があまりにもまじめすぎるからだよ。時には肩の力を抜かないとうまくいかないこともあるというのにね。」 年端も行かない姫に何を教えるのかと眉が上がるのを、傍らの少納言が止めた。確かに、友雅にブレーキをかけられて救われたことが何度もあった。「急いては事をし損じると申します」と頼久さんが頭をかいていたっけ。「……それでそのお姫様は?」「さて、どうされたかな。月に帰られたかそれとも……姫の近くにいるかもしれないね。」 友雅はあかねの方を見返った。慌てたあかねはつんを居住まいを正した。「……こんなに冴えた月の宵は、何かを思い出したりしないかい?」「何を?」「ふふ、そうだね、君にはそういう感覚がなかった。時々忘れてしまうよ。」 月を割って降りてきたとしか見えない少女だったが、あかねは白い光に満ちてはいても何もない世界から押し流されて来たと言った。 ちい姫が不思議そうにあかねを見た。「月からいらしたの……お母様?」 あかねはちい姫に腕を伸ばした。うれしそうに寄ってくる小さな体を抱きしめた。「帰らないよね?」「え?」「月にはお帰りにならないよね? ずっとここにいるよね?」 目が熱く潤む。あかねはちい姫をさらに固く抱いた。「ここにいるよ、ずっと。私はちい姫のお母様だもの。」「うん……約束。」 約束と抱く腕に力を込めるのに、友雅がほおっとため息をついた。「すっかりお株を取られてしまったねえ……」 にじり寄り、母子共に広袖の中に抱き込んだ。「私のためにも残ってもらえるのかい? 神子殿。」「当たり前じゃないですか……」 大寒の夜寒の空を照らす月が白い。まもなく、あかねが来て何度目かの春が巡ってくる。 庭の隅で、梅が一輪ほころびる……そんな気がした。
2011年01月20日
コメント(0)
-
【満月に寄せて遙か1】 雲間隠れのゆかしきに
(まったく、元気のいいことだねえ……) 友雅は嘆息した。ふと思いついて立ち寄ったのだったが、かなりの早朝だったというのにあかねの姿はとうになく、藤姫が朝の勉めと手習いをしているばかりだったから。「札探しかい? 精の出ることだね。」「神子様はどなたかと違ってまじめでいらっしゃいますから。」 何を感づいたのか、御簾の内の藤姫の態度も冷たい……のはいつものことかと友雅は苦笑いしていつもの高欄に凭れた。「久しぶりに、筆跡を見て差し上げましょうか、藤姫。」「結構です。もう書き慣れたお手本ですから。」「では、新しい手本はいかがかな? 見飽きたでしょう。」「まだ飽きてなどおりません。」 とりつく島もないとはこのことだろう。何をそう不機嫌なのか、心当たりがないでもなかったが。 袂に投げ入れられた文殻をはたはたと振り落とし、一つ一つに薫きしめられた薫りをそれとなく香る。御簾の内から視線がくすぐったい。見ないように見ないようにでも気になって仕方がない視線。(かわいいねえ……だから、かな。) 蝙蝠をはたとならして女房を呼び、文殻を渡した。「姫君がごらんになりたいそうだ。御前に。」「誰も申しておりません!」「おや、そうですか? 先ほどからずいぶん気にしておられたようだが。」「存じません!」 破顔して庭に目をやると、よく知る顔が眉をひそめて立っていた。「おや、鷹通。」「友雅殿、今日はずいぶんお早いのですね。」「ああ、昨夜から休んでいないのだがねえ、これも早起きというのかい?」 鷹通の顔が一気に引きつった。「どちらかの御殿で御宿直でしたか。お勤めご苦労様です。」 口調がとげとげしい。「何か言いたそうだね、鷹通。」「ええ、友雅殿ですから!」「対である君にまで信じてもらえないとは情けない。帝の御前を先ほどようやく退出させていただけたばかりだというのに。」 疑いの目を向ける鷹通に、友雅は肩をすくめて見せた。「……ほんとですか?」「……君の想像にまかせるよ、鷹通。」 端正な顔がさっと紅潮するのを、友雅は見逃さなかった。友雅がもっとも気に入っている瞬間だったから。「ふふ、かわいいね。だから君のことを放っておけないのだよ、鷹通。」「友雅殿、あなたという人は!!」「はは、まいったまいった、降参だよ。まったく、君たちにはかなわない。」 蝙蝠の陰で大きな欠伸を一つして、友雅は座を立った。沓がざりっと庭の敷石を踏みしめる音に、知らん顔し続けていた藤姫もさすがに目を上げた。「また来ますよ。神子殿によろしく。」 ふわり立ち上る薫りに、藤姫はこわばらせていた表情をゆるめた。「お伝えしますわ。友雅殿も、どうぞ首尾よく白虎の札を見つけてくださいませ。」「ええ、心しましょう。この堅物の対の君にもよくよくお願いしておくこととしてね。」 厳しい表情を崩さない鷹通の横を、蝙蝠を打ち鳴らし小声で催馬楽を歌いながら通り過ぎた。(……!) 鷹通の顔も、申し訳なさにゆがんだのを、友雅は見なかった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆(さて……神子殿はどちらへお出かけかな。) 朱雀の札というからには京の南の方角か、大内裏から遠いはずれは時に賊も現れるという。(あの二人だけではおぼつかないからね。) 頼久の姿も見えないから、きっと警護に就いているに違いない。(手柄を独占させるほど心広くない、か?) 殊に心奪われるほどの魅力がある娘ではないけれど、何故か心にかかるものがある。まるで雲井の月が隠した雲を照らす光に心惹かれるとでもいうように。見えないから見たい。異世界から来たという物珍しさか、それともこれが宝玉のなせる技なのか。 友雅は笛を取り出した。先ほどまで奏でていたそれはまだ少し湿りを帯びて、朝露の湿りと共に指にひんやりと心地よい。唇に当ててひょうと奏でた。朝ぼらけの光の中に澄んだ音色が吸い込まれる。 浄められる。 友雅には新鮮な感覚だった。あの少女が自分を変えていく。不思議にも心地よい感覚に、ふと酔いそうになっていた。
2011年01月19日
コメント(0)
-
【幸鷹誕2011】 薫り香る香りの(幸鷹×神子)
御簾の隙間からそっと差し入れられた箱に、幸鷹はしばらく見向きもしなかった。 嗜みとはいえ、薫きしめられたその薫りが、送り主の正体を告げていたからだ。(何のつもりだ。) 贈り物を受け取る理由など何もなかった。が、使いの者が「四条の尼君のお屋敷から」と伝えてきたから、突き返せとも言えずにそこに置かれてしまったのだ。(姑息な。) 正面からでは決して受け取らないと知るからこその仕業。よりによって、紫姫や神子の名を騙るなど。 御簾の合間に置かれた箱は少なからず人の出入りの邪魔をする。幸鷹を訪ねる部下たちが、いちいち怪訝な顔で箱を眺め幸鷹を眺めるが、幸鷹があたかも何もないかのように振る舞うので「いかがいたしましょう」とも聞けず、箱はずっとそこにあった。 日の暮れる頃、幸鷹の身の回りをする女房が掃除のついでに箱を手に取った。「殿様、これは……」「捨てておいてくれ。」 吐き捨てるように言われた言葉に女房は驚きの顔を隠さなかったが、言われるままにどこかへ下げに行った。 幸鷹はほうっと息をついた。部屋の中に染みついた穢れがようやく祓われたかのような気分になった。 するとそこへ、先の女房が慌てて戻ってきた。「殿様、本当に捨ててもよろしいのですか?」「本当に? どういうことだ。」「尼君様の許においでの姫君様からの御文が入っておりました。」「紫姫から?」 渡された文を幸鷹は半信半疑でつまみとった。小さく結ばれた結び目を爪の先でほどくと、確かに紫姫の筆跡だった。 神子様のお頼みで御文をいたします。 神子様のいらした世界では、一人一人の生誕を言祝ぐ習慣があるのだそうでございます。 こちらではそういうことはいたしませんと申し上げましたらとても残念に思われて、お気の毒なほどでございました。 何でも、お祝いの言葉を申し上げ、贈り物をするのが習わしとか。どうかお受け取りになって、神子様のお望みをかなえて差し上げてくださいませ。「箱の中には文の他に何か入っていたのか?」「はい、美しいお色目のつややかな布子が。」「布子?」「ええ、手巾と呼ぶには少し小さくて。」 幸鷹はそれを持ってこさせた。手に取った瞬間、幸鷹にはそれの使い道がわかった。(眼鏡拭き。) どうしてわかったのか、幸鷹にもわからなかった。そして、それがどうしてあの薫りを纏ってきたのかも皆目わからなかった。 幸鷹は立ち上がった。訪ねるのが一番早いと思った。*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。「本当に助かりました。香合わせは貴族の姫の嗜みと、お祖母様も教えてくださるのですが、香木を砕いて粉にするところはどうしても力が足りなくて。」「ふふ、お役に立てたならうれしいねえ。楽しかったかい? 神子殿。」「おもしろかったです。ちょっと粉を増やすだけですごく薫りが変わって。」 幸鷹の誕生祝いに、絹の端布を眼鏡拭きにして花梨は準備していたのだが、めざとく見つけた翡翠が「香を薫きしめたらどうか」と提案し、幸鷹好みの侍従の香を合わせることになったのだ。「翡翠さんの言うとおりに合わせたんだけど、幸鷹さんの好みに合うかな。」「大丈夫だと思いますわ。でも、幸鷹殿の侍従とは少し趣が異なるような。」「それは、神子殿のお好みということでいいのではないかな? 合わせる者の手加減で異なる物だからね。」 ふふと含み笑いの翡翠に、花梨は一抹の不安を覚えた。「翡翠さん、何か企んでませんか?」「おや、企むとは人聞きの悪いことを言うねえ。何も企んでなどいないよ。」「ほんとですか?」「疑うのかい?」 じろりと見下ろされる視線に、花梨は肩をすくめた。「……まあ、楽しみにしていなさい。きっとおもしろいことが起こるから。」 起こっていない証拠に花梨の頭をぽんと一つたたいて、翡翠は部屋を出て行った。紫姫は女房を呼んで幸鷹あての贈り物を言付けた。そうして、箱は幸鷹の屋敷へ届いたのだった。*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。 花梨の部屋を訪れた幸鷹は、そこに翡翠の姿がないのにほっと胸をなで下ろした。「よかった、神子殿、私は……」 息せき切ってやってきたのを隠しきれない幸鷹に、花梨の方が驚いた。「幸鷹さん、どうしたんですか?」「どうしたって……あの薫りですよ。」「ああ、あれ……」 花梨がほのかに頬の色を染めるから、幸鷹はまた、かっと熱くなった。「神子殿、まさかあの海賊と……あれは危険な男だと言ったはずだ。」「危険って……何も危ないことなんかしてませんよ?」「じゃあ、あの薫りは!」「気に入りませんでしたか……?」 花梨の目が潤んできたのを見て幸鷹は慌てて言葉の調子をゆるめた。「……あの薫りは、どうしたんですか?」「作ったんです。翡翠さんと……」 眉根がぎりっと上がって睨みそうになるのを幸鷹は懸命に押さえた。花梨の言葉を最後まで聞かなくてはと思った。「……紫姫と3人で。」 3人で! 幸鷹はほうっと大きく息をついた。「幸鷹さんの好きな侍従の香を作ろうと思ったんです。紫姫が作り方を教えてくれて、でも、香木をつぶすのにすごく力がいって、そしたら翡翠さんが手伝ってくれて、それでそのとき、幸鷹さんはこれくらいの感じが好きだって、翡翠さんが合わせ方を加減してくれたんです。ね、翡翠さん。」 同意を求める花梨の声に、幸鷹は目をむいた。「翡翠さん……!?」「おや、君にさん付けで呼んでいただけるとは光栄だねえ、別当殿。」 くつくつと、堪えきれないというように笑いながら翡翠が壁代の向こうから姿を現した。幸鷹の顔はこれ以上赤くなれないと思われるほどに紅潮した。「気づかなかったのかい? 君ほどの人が、よほど動転していたとみえる。」「私が、どうして!」「ああそうか、風向きが悪かったのだな。私には君の薫りがありありとわかったけれどね。」 幸鷹の顔がどんどん険しくなるので、花梨はいたたまれない思いだった。「あの、翡翠さん、けんかはやめてください。」「けんか? 誰と誰が?」「翡翠さんと幸鷹さんがです!」「けんかなどしてはいないよ。おもしろくてたまらないだけでね。」「何もおもしろくなんかありません!」「そうかい? 私には、別当殿が慌てふためいてこの部屋に入ってくるのがこの上なくおもしろく感じられたけれどね。滅多に見られない光景だと思わないかい? 神子殿。」 花梨は勢いよく立ち上がった。笑いを止めない翡翠の横をつんと通り過ぎて、幸鷹のそばへ寄った。「こんな翡翠さんは放っておいて、どこかへ行きましょう、幸鷹さん。」 幸鷹はうなずいて立ち上がった。翡翠の笑いは止まらなかった。「翡翠殿。」 花梨と幸鷹を見送りにきた紫姫が静かに翡翠を睨み付けた。翡翠は軽く肩をすくめただけで、満足そうな笑みを消さなかった。*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。 幸鷹が件の絹の端布を出して眼鏡を拭いたので、花梨はびっくりした。「どうしてわかったんですか?」「こうして使うのではありませんでしたか?」「合ってますけど……びっくりしました。」「そうでしょうね。私も驚いています。この布を見たとき、こういう使い方しか思い浮かばなかった。」 幸鷹は花梨の瞳をのぞき込んだ。そうするといつも、幸鷹の脳裏に同じ風景が浮かぶ。京の建物とは似ても似つかぬ無機質な、目眩を覚えるほどの高層な建物群、牛車とは比べものにならないほど速く走る金属製の車。数え切れないほどの人が忙しげに行き交い、赤や青の明かりがともる機械が人の波を仕分けている……。 幸鷹はいつもの頭痛が襲ってくるのを感じた。 苦しげにこめかみを押さえた幸鷹を、今度は花梨がのぞき込んだ。「大丈夫ですか?」「ええ、すぐに収まります。ご心配かけて申し訳ありません、神子殿。いつものことなのです。」 そう、あの夢を見るといつも感じる、目眩のする吐き気、締め付けられるような頭痛。苦しさに飛び起きるとそれらは嘘のようにかき消されて、何事もなかったかのように眠りにつけるのが常だった。(これの使い道が即座にわかったのも、この夢に関係があるのだろうか。) 見たとたんに、「いつも使っているなじみの物」という感じがしたのだ。眼鏡は単衣の端か懐紙で磨く物と思い込んでいて、それ用の布を使うなど思いもよらなかったのに。 花梨の手が、ぎゅっと広袖の端をつかんだ。その手を取り、抱きしめたい衝動を幸鷹はぐっと抑えた。(まだ早い。) 何が早いのかはよくわからなかったが、わき上がる暗い欲望を抑え込むには十分だった。自分はあの海賊とは違う……そういう自負もあった。「帰りましょう。あなたが冷えてしまう。」 幸鷹の言葉に花梨は素直に従った。西の空にかかる細い月を見上げながら帰った。沈む夕日に山々の峰や建物がくっきりした影になって、夜寒を避ける雁が鳴いて渡る、そんな宵だった。「ありがとうございます。」 幸鷹がつぶやいた言葉に、花梨はうれしそうにうなずいた。心まで凍てつきそうに冷えていたけれど、今夜は暖かく眠れそうだと思った。
2011年01月15日
コメント(0)
-
守りたいもの(風早×千尋)
(千尋……どうしてあなたは……) 時の螺旋をぐるり回して、あなたがまだ誰のものでもない時空に戻したのに。 風早は悩んでいた。役目が終わるまで、永遠にでも千尋と共にあらねばならぬという白き龍との誓約とは別の次元でわき上がる熱い物を、最近、風早は持て余しぎみだった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 常世での日々は、風早には苦しみ以外の何ものでもなかった。 千尋の心は日に日に常世の皇子に傾き、それは中つ国にとっては恒久的平和を約束される悦ばしきことだったが、その熱き想いに政治的思惑など何の関わりもなく、「千尋を我がものとせよ」と風早を嘖む。(それは俺には許されていない……) 常世と中つ国は政治的手段として婚姻を結んだ。今の常世の混乱が収まるまでの形式的なものとして皇子も了解していた。婚姻の実質は伴わない、と。 ところが、それは日々形を変え、いつか千尋の中で恋に変わっていた。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 千尋は、皇子の妃として別室を与えられていた。 千尋が風早を手放すのを拒んだから、風早は今まで通り妃づきの武官として、そして、次の間を控え室にするという別格の扱いを受けることになった。 結婚は困ったことだが禍日神を倒して中つ国に帰るまでの方便と千尋が考えているうちはよかった。中つ国にいた頃、橿原の借家にいた頃と同じように、風早は思うままに千尋の側にいられた。 ……抱きしめればわかる。 千尋が何を考えているのか。 黒い悩みの影が広がる。 時が訪れたのを風早は知った。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ その夜も、リブが千尋に茶を淹れに来た。 穏やかな眠りを誘う茶を、遠夜も千尋に用意していたが、アシュヴィンのための茶はリブが準備していた。ある日、アシュヴィンがどんな茶を飲んでいるのか知りたがった千尋がリブにねだり、それを千尋はいたく気に入ったところから、千尋の寝しなの茶はリブが淹れることになってしまった。 そんな頃からだった。千尋の様子が少しずつ、目に見えて変わってきたのは。 風早がいればすっきり落ち着いていた瞳が、時々誰かを探すように泳ぐ。アシュヴィンの姿を認めると慌てて逸らす。まったく興味を示さなかったのに、常世の……アシュヴィンの日常を知りたがったり……。(恋を、してしまったのですか、千尋……?) 中つ国のため、中つ国の将来のため、人の世と人の本質を見極め、白き龍に報告するのが我が身に科せられた白き龍との誓約……。 言い聞かせても荒立つ心は抑えかねる。ふと顔に出たのを千尋が見とがめた。「どうしたの、風早?」「え、いえ、何でもありませんよ、千尋。」「どこか痛いの? 遠夜を呼ぼうか。」「大丈夫です。そんなに俺、具合悪く見えましたか。」「ううん、ちょっとね、苦しそうだったから。」 この姫にはすべて見透かされる。 そんな会話を思い出していたら、目の前に千尋が立った。 何か言いにくそうに、でも、何かをはっきりと決めた目で、風早に告げた。「アシュヴィンにお茶を届けてくる……」 言ったとたんに耳まで赤くなった千尋を見て、風早の心は物狂おしく揺れた。引き留めたかった。全力で止めたかった。(いけません、千尋。行ってはいけない。) あなたを愛しているのは俺ですと、幼い頃から慈しんできた小さな手を握りしめ、腕の中に引き寄せて! 行かせてなるかと身動きもできないほど固く抱きしめて、本当に、それができるならどれほどいいか! 引き留める権利などないのを風早は知っていた。「……わかりました。」 努めて平静を装ったつもりだったが、千尋はきっと何かを感じたに違いない。何よりも愛しいと思うその唇が「ごめんなさい」という言の葉を紡ぐのを風早は見た。小さな足音が外へ出た。ドアがぱたんと閉まったその瞬間に、風早はきっと唇を引き締めた。 時の螺旋が音を立てて巡る……◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 経巡った時空でも、風早は千尋の手を取ることはできなかった。 鳥船の中での千尋の常の居場所は、自室でも堅庭でもなく、書庫だった。「ここに書いてあるのはほんとに事実なの?」「ええ、我が君。竹簡は何でも教えてくれます。我が君のこれから歩かれる道、既定伝承です。」「それを変えることはできないの? 柊、あなたは……」「私の将来に何が待ち受けていようと、それが私の既定伝承です、我が君。」「そんな……」 千尋の蒼い目から大粒の涙がこぼれ落ちる。何が書かれているのか、風早はよく知っていた。(その男は危険すぎます、姫。) あなたを連れて常世へ向かったなら、きっとあなたは悲しい目に遭う。その男と一緒にいてはいけない。引き離さなければ。 しかし、近づけば近づくほど、千尋との距離が遠くなる気がした。柊の隻眼が自信ありげににやりと微笑む。(これも既定伝承というものですよ、風早。) 千尋が柊の言う既定伝承にない運命を選択したと知った瞬間、風早の意思は迷いもなく時の螺旋を巡らせた。今度こそ、千尋がこちらを向く運命へたどり着くのだと……◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「風早、風早!」 千尋の声がする。 風早は閉じていた目を薄く開けた。この家でもっとも日当たりの悪いあげくに窓際まで本棚を置いた部屋は昼間でも薄暗いが、それでも千尋が開けたカーテンから細く朝日が射し込んで、新しい1日が始まったことを告げている。「ねえ、起きて。朝だよ! 遅刻するよ!」 いつもの仕返しとばかりに激しく揺すり起こす千尋に、風早は容易に応えようとはしなかった。これが望む運命でなければ、すぐにでも時を巡らせる……。「ほっとけば? 先生が遅刻するなら僕たちには好都合だし。」「そんなのダメだよ! ちゃんと起こすって約束したんだもん。」(那岐、ですか……) 風早は渋い顔をして寝返りを打った。揺り起こしていた千尋の手がはっと止まった。気まずい空気が流れる。布団に触れた指が小刻みに震え、怯えたように離れるのを感じた。部屋を出る足音が重く響いた。「……どうしたの。」「何でもない。」 強がる声が涙を含んでいるのを感じて、風早は体を起こした。(俺が泣かせたんですか? 千尋を。) 耳を澄ませた。「風早の朝が不機嫌なのはいつものことじゃないか。どうせ昨夜も遅くまで本を読んでたんだろうし。寝不足だよ。」「でも……あんな風に避けられたの初めてだもん。」「千尋の気のせいだよ。たまたまだろ。」「違う。気のせいなんかじゃない!」「じゃあ、いつまでもそうやって悩んでれば? 勝手に思って勝手に決めて、千尋はバカだ。」「バカじゃないもん!」 そのまま声が聞こえなくなった。風早はゆっくりと起き出した。すぐにも行って抱きしめたいところだったが、那岐の言うとおり寝不足の頭は思うように体を動かしてくれない。「僕はもう行くよ。とばっちりで遅刻くらっちゃ敵わない。」「私も行く、待って、那岐!」「ごめんだね。千尋はあいつと来ればいいだろ。」「もう、那岐!!!」 風早の足取りが止まった。千尋の心が今度は那岐に傾いているのを感じた。(俺の姫はあなただけなのに……あなたは私だけのものではいてくれないんですね、千尋。) 白き龍との誓約が頭をかすめた。(そういうこと、か……) 守りたいもの。守るべきもの。それは、人として愛の対象とするのではなく、神として守護するということ…… 玄関の戸が閉まる音。風早はようやく台所に立った。千尋の用意したと思われる朝食を食べ、上着に手を通して家を出た。 畝傍山から遠雷に似た音が聞こえる。(ああ、またあの日……) 今度はどの運命を辿ることになるのか。 小さな印も見逃すまいと、風早は注意深く、学校への道を歩いていった。
2010年11月11日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ友あか】 ちい姫袴着
京に涼風が立つようになった頃。 友雅はいつも思い出すのだった。 大堰の山荘で迎えたあの息苦しい夜。 守るだの支えるだの言葉にはしても、何もすることができず拳を握る、自分の無力さを思い知らされた夜。 そしてもたらされた大きな喜びに思わず涙する己に絶句し、守るべき者を得た自分がいかに変わったかを改めて感じた朝。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「友雅さん♪」 愛しくてならない者が目の前にある。「おとうちゃま。」 そしてもう一人、かけがえのない宝。 友雅は宝を抱き上げた。あかねが時々嫉妬するほどの優しいとろけそうな笑みを浮かべて。「もう、ふたとせか……姫は三つになるのだね。」 生まれた年を1才と数えるのが京の習わしなら、二度目の誕生日を迎えた姫はこれで3才になったことになる。「袴着のことを、そろそろ考えなくてはならないねえ……。」 東宮妃にと約されている姫だった。気兼ねのいらない大堰の山荘住まいで、五十日や百日といった誕生の儀式を簡単に済ませてしまっていたから、そろそろきちんとその手の儀式を執り行って、橘の家にこの姫有りと世間に示しておかなければならない。鄙育ちの姫よと軽んじられないために洛中に邸を構えたのだ。面倒だなどと言っている場合ではなかった。 土御門では昨年、その東宮となるべき親王の袴着が行われた。祖父である左大臣が袴親を勤め、土御門の威信翳ることなしと世間に知らしめた。そのまねをする気は更々ないが、「あの橘友雅」に、親王と釣り合いのいい娘有りと世間に知らせておくのは、姫の入内後の障害を取り除く布石になる……ちい姫が後宮ですぐれてときめくための。 急に黙り込んだ友雅の顔を、あかねがのぞき込んだ。(友雅さんは変わった……) 出会った頃とはまったく違う。あかねが知らなかっただけかもしれないが、あかねの知る友雅はいつも飄々として、どこか投げやりな感じまでするほどだった。「変えたのは君だよ。」と友雅はいつも言うが……(ほんとに友雅さんを変えたのはこのおちびさんだわ。) 土御門では決してみせることのなかった顔。「それはそうでございましょう、お方さま。お殿様も橘のお方ですわ。」 少納言が言った。「どういうこと?」「お方さまもご存じであられましょうが、橘は古く南都からつながるお家、土御門の藤原と並び称されるお家柄でございます。ところが、藤原がうまく立ち回ったおかげですっかり日陰に周り、今では『落ちぶれた』とまで言われる家になってしまいました。」 あかねは静かに頷いた。学校で習った歴史の項目がちらと頭をよぎった。「袴着を、するのね? 友雅さん。」「ああ……面倒だがね。」 渋い顔を見せる友雅に、よく知っている友雅を見て、あかねはほっと安心した。「君にもいろいろ頼まなければならないけれど、少納言とよく相談して……」「心得ております。」 少納言がとんと胸元を叩いて微笑んだ。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ しかし、友雅が大きく宴を張ることはなかった。 源平籐橘と並び称されるとはいえ、皇室につながる源平ならともかく、今の「藤」の威勢はあまりに強大だった。橘友雅個人の威勢だけで何とかなるものではない。それは、八葉の勤めを終えてもぴくりとも動かない友雅の位階がはっきりと物語っていた。(土御門もこういうところは辛辣だからね。) 慰労として俸禄が多少増やされたほどで、役職もそのままだった。もっとも、昇進させてやると言われても友雅の方から断っただろうが。 ちい姫の袴親を、友雅は自ら勤めることにした。藤壺中宮から是非にとお声掛かりがあったが、丁重に辞退した。口ではわがままめいたことを言っても友雅の難しい立場を理解していないわけではない中宮だから、多くの祝いの品を名代の女房に持たせて寄越された。「その女房を、そのままちい姫づきにしてちょうだい。入内の後も困らないように。」 友雅はありがたく受けた。女房は衛門と呼ばれて、西の対でちい姫に仕えることになった。和漢の学に秀で、楽もそれなりにこなす女房だったから、ちい姫の手ほどき係にうってつけだった。 どんなに大きな宴になるのかと北の方あかねはドキドキしていたが、御所から祝いの品が届いたのを聞きつけた公家仲間が挨拶に来たくらいで、宴と言っても連なったのは藤姫と鷹通、その他は庭で和気藹々と、まるで大堰の山荘そのままの宴になった。「これでいいの? 友雅さん。」「いいさ。袴着だからね。」 西の対の畳を積み上げた上にちい姫を立たせ、きゅっと袴の紐を結んでやって、友雅はちい姫に「とんと降りてごらん」と促した。友雅の膝ほどの高さの畳だったから、ちい姫は嬉しそうに頷いて元気よく飛び降りて見せた。「うん、いいね。これで元気に育つ。」 得意顔のちい姫の頭を撫でてやりながら、友雅も満足げに頷いた。 今まで単衣だけでいたものが、小さな袴をつけ、脱げないようにと袴紐を両肩で華やかに結んでいる様子は、あかねの世界のジャンパースカートのようだった。「可愛い。」 大人の着ける袴と違って、丈短く、足が抜けるようにしてあるから、今までと変わらずに、おぼつかない足取りながらよちよちと歩いて、あかねのところへやってくる。少し幅広に仕立ててもらった袴紐を蝶の羽のように広げてやるとそのかわいさは更に増した。「まあ、なんて可愛い! 私にもこういう妹が欲しかったのですわ!」 あかねから藤姫を抱き取って、藤姫が言った。六条に友雅が邸を構えてから、暇さえあればここに来ているから、ちい姫もすっかり藤姫に懐いている。「妹とは……いずれ藤姫も母上になられるのではないのかな? そろそろそういうお話があってもよい頃だ。」「存じません!」「おや、いろいろ聞いていますよ。私が中宮様の妹姫に近しいと聞きつけて相談を持ちかける公達が引きもきらずでねえ……」「友雅殿!」 きっとにらみつけるのを、あかねと鷹通が止めた。「この姫の入内の頃に、友雅殿がどんなお顔をしておいでか、是非とも拝見したいですね。」「さて、入内と恋は違うからね。」 言葉の底に、ひやりと冷たいものを感じて、あかねは背中がぞくんとするのを感じた。「友雅さん……?」「ああ、大丈夫。ちい姫が不幸になるようなことはさせないよ。ちい姫には嫁ぐお方がどなたよりも大切で愛しいお方だ。誰よりもときめき、誰よりも愛されて後宮に君臨する、最高の姫君に育てなくてはね。」 鷹通が力強く頷いた。それでもまだ不安そうなあかねに、藤姫が囁いた。「東宮様以外の男君なら決してこんな風にはおっしゃいませんわ。友雅殿は本当に変わられた……神子様のお力ですわ。」 ちい姫はよちよちと縁まで歩いていっては庭の仲間に愛嬌を振りまいている。イノリなどが「可愛いなあ、ほんとに可愛いぞ、あかねそっくりだ!」と叫んでいる。その声に喜んで庭に降りてしまいそうになるのを乳母が慌てて抱きとめている。(最高の姫君に。) 明日からちい姫には后がねとしての手ほどきが始まることになっていた。日常の起居、手習い、楽、絵、香……基礎を学び、極めるべきことが山ほどある。13,4歳で成人の式である裳着を行うのだというから、あと10年ほどで、そのすべてをある程度身につけ、さすがと言われるほどのレベルになっていたいとすると。しかも、裳着の直後におそらく入内のことが待っているのだとすると。 あかねは身震いした。どう考えても、自分のしてきた程度のことでは間に合わない。「大変だ……」 ぽつりもらしたため息に、友雅も、鷹通も反応した。「大丈夫だよ、あかね。京の姫君なら当たり前のことだ。私と君の姫なのだしね。」「だから心配なんじゃない……」「お任せください、神子殿。私もお力添えをいたしますから。」 鷹通の言葉にあかねは安心して頷いた。「まったく、未だ信じていただけないのかねえ……」 友雅の嘆息にあかねは少し慌てた。「違うの、友雅さん、あの子の半分は私だから!」「だからどうだっていうんだい? こちらへ来てからの君の飲み込みの早さは目を見張るものがあったよ。さすが龍神の神子だと舌を巻いたからね。」「でも、でも、まだできないことがいっぱいあるし……」「全部できなくてもいいのだよ、中宮様だって決してすべてに長じておられるわけではない。そうだね、藤姫。」「ええ、神子様。姉上にもできないことはたくさんおありですわ。」「中宮様が優れて見えるのはね、周りに優秀な御達を多く侍らせているからだよ。君の少納言と同じでね。」 少納言の目でしっかり者の乳母をつけ、中宮様からは衛門を賜った。友雅の才、鷹通の知。ちい姫に不足するものは何もない。 夜もすっかり更けていた。 庭の篝火が、ちい姫を見守る者の顔を、赤く照らしていた。
2010年11月06日
コメント(0)
-
【小さい藤姫と友雅殿のお話】 星逢瀬2010庚寅
星の逢瀬を雲の隠さむ かさりと御簾が動いた音に、藤姫は気づかなかった。 壁にむけて置かれた文机に被るように座る手には細い筆が握られていて、行きつ戻りつ、何かを書き付けている。 そして藤姫は書くことに夢中で、近づく衣擦れの音にも薫き物の香りにも気づかなかった。「何を熱心に手習いしているのです?」 深く響く美声に、藤姫は飛び上がった。筆を放り投げるように置き、手元の料紙を慌てて隠した。「隠すことはないでしょう? 見せてご覧なさい。久しぶりにあなたの筆跡を見たくなった。」「上手に……書けておりませんから……」「では、お教えしましょう。こちらへお出しなさい。」 藤姫は真っ赤になって声の主から手習った紙を守ろうとする。背に隠した料紙を、声の主はふふっと笑って背後に回り、のぞき込むようにして手を伸ばすとあっさりと料紙を取り上げてしまった。「友雅殿!」「恥ずかしがることはないでしょう? 最近、私の筆跡を手習いの手本にしていると聞きますよ。師匠に筆跡を見せないという法はありますまい。」 藤姫は詰問するように側に控える乳母を見た。乳母はとぼけた顔で空見をした。友雅が下がるように合図すると、心得顔に頷いて壁代の向こうに消えた。藤姫は後を追いたそうな顔つきを見せたが、友雅がじっと見つめるのでつんと居住まいを正し、でも落ち着かなげに隠れ場所を探す風だった。(可愛いねえ……) 友雅はおもむろに藤姫の手習いを広げた。素直な性格そのままに、友雅の筆跡によく似てきた筆跡がつづっていたのは、 想ひわび 濡れたる袖を隠すにや 逢ひ逢ふ星を雲の隠しつ 待ちかねのまたの逢瀬のはづかしきや 雲の陰なる宵の月星(これはこれは。) 藤姫がついと立ち上がったと思ったら、裾を翻して几帳の陰に隠れた。「おやおや。あなたまでが雲隠れですか、藤姫。」 友雅はあえて追おうとせず、几帳から少し離れた柱に凭れて空を見上げた。藤姫の嘆くとおり、少し前から美しく煌めいていた夕星も、指折り数えた夕月も、にわかに湧いた雲にすっかり隠れて、昨夜交わした星逢瀬を眺める約束は果たせそうにない。 友雅は懐から笛を取り出した。調子を見るように軽く吹いてみた。几帳の奥から身じろぎの気配が伝わってきた。「楽の音に感応して雲が晴れたという話は聞きますが……」 雲井に届けと吹きすましてみた。藤姫の好む節回しを取り混ぜておもしろく吹くから、藤姫はじっとしていられなくなった。 几帳の端からそっとのぞいた。月のない薄闇にぼんやり浮かぶ白い直衣の後ろ姿。空にむけて吹き鳴らすその姿はいかにも端正で、藤姫の幼い目もつい見とれてしまう美しさだ。 にじり寄る衣擦れの音を友雅は小気味よく聞いていたが、知らぬ顔で笛を吹き続けた。小さな息づかいまでが聞こえるほどに近づいた頃を見て、友雅はやおら体の向きを変え、藤姫の方に手を伸ばした。 藤姫はとっさに体をずらしたが、友雅の手は抱き取ると見せかけて横にそれ、部屋の隅に寄せてあった箏の琴にかかり、手元に引き寄せた。「弾きませんか?」 藤姫の手元に差しだしたが、あっけに取られた藤姫はすぐには手を出そうとしない。さっきの仕打ちに声も出ない様子に、友雅は思わず噴きだした。「……もしかして、期待したのかな?」「そんなこと……ありません!」 大好きな笛の音にほだされておめおめと出てきた私がバカでしたわ!と、藤姫は勢いよく立ち上がった。手近に置かれていた箏の琴に着ていた細長の裾がかかってざらんざらんと音が出た。「おやおや、ご機嫌を損ねてしまったのは私の落ち度だけれど、楽器に当たるのはよくないねえ。」「当たってなどおりません! 裾が触れてしまっただけです!」「おお怖い。すっかり怒らせてしまったようだ。」「存じません!」 部屋を去るかと思いきや、裾を翻した藤姫の行く先は、元の几帳の陰。友雅は苦笑した。藤姫の揺れる心が丸見えだ。すっかり嫌われたわけではないらしい……。 たまさかに逢ひ逢ふ恋や 秘めたるを見現せじと 雲の隠さむ 几帳の奥からは何の手応えもない……ことはなく。懸命に気配を消そうとしてかえってありありと伝わっているのを藤姫は少しも気づいていないようだった。友雅は再び笛を手に取った。少し苛めすぎてしまったようだ。気持ちの整理がつくまで、今はこのままに。 先ほどと同じ藤姫好みの節が響く。「同じ手には乗りませんわ。」と小さく呟く声が聞こえた。
2010年09月12日
コメント(0)
-
【友雅×神子】 四六時中
※直接的な表現はございませんが、大人の雰囲気ですからご承知を。※(まいったねえ……) 腕の中の柔柔としたものは甘く疼く細い声を上げていたけれども、友雅の手の動きにいつも以上に熱がなく、ただ習慣的に喘がせているだけだった。「少将様……」 声の主がじれったそうに小さく囁いた。「ああ……」 表敬的な口づけ。それでも腕の中のものは満足したらしく、熱い体を友雅にすりつけてきた。身に澱む欲を吐き出すためだけに愛撫を加える。友雅の思惑など知りもしない体は更に高ぶった喘ぎをもらし、感極まった小さな叫びとともに小刻みに体を震わせたところを見ると、どうやら極に達して果てたらしかった。ぐったりと力をなくした体に遠慮なく欲を吐き捨てる。気怠さの後に残る物は……むなしさ。何一つ満たされない……。(まったく……) 欲しい物はこれではないと不満げに呟くもの。封じるように忘れていたこれが最近とみに存在を主張し始めた。おそらく、これは龍神の神子のしわざ。集めでもの「心のかけら」とやらを熱心に集めるから……。 しかし、それを迷惑と感じるかと言えばそうでもなかった。彼女に世話を焼かれる……一生懸命になっている様子を見るのはどこか心地よかった。しかしどうして、それがこのような身を去らぬ想いと変わるのか。 快楽の余韻に浸っていた体が不意に頭をもたげて、ねだるように顔をすりつけてきた。「少将様……」 無遠慮に悪戯を仕掛ける指先が疎ましい。冷たくはねのけた手に、相手は少々ひるんだようだった。でもあきらめきれずにおそるおそる挑んでくる指を、友雅は無視した。寝返りを打ち、背を向けた。「……」 ここで泣くような女を選んではいない。明らかに興ざめしたという空気を纏って、相手は体を起こした。「お方さまがお呼びだわ。」 身支度する音。遠ざかる衣擦れの音。 友雅も静かに身を起こした。(夜が明ける……) 土御門へと急かすものが心に巣くっている。龍神の神子が空を割って京に降り立って初めて感じた、不思議な感情。こんなものは自分にはないと思っていたのに。(逢わずにはいられない……この私がね。) 友雅は鎖骨の宝玉に手をやった。神子はぐっすりと寝入っているのだろう、宝玉はしごく穏やかな波動を友雅に伝えていた。 この宝玉がはずれたら、京の危機とやらを救ったなら、龍神の神子は無事元の世界に還御し、自分の生活も心情も元通りになる。こんな物思いはそれで終わりだ。これは宝玉のなせる技。神子を心の底から守りたいと願わせ、八葉の勤めを全うさせようという龍神の思惑だ。 友雅は静かに庭へ降り立った。有明の月の光が友雅の被衣を蒼白く染めた。
2010年09月04日
コメント(0)
-
大人の特権(友あか)
大人の特権 天真はいらいらしていた。「いったい、どこへ行きやがったんだ。」 息抜きにと連れ出したのは藤姫から聞いていた。貴族だから、徒歩ではなく牛車で連れ出したのも百歩譲って理解する。そして貴族だから、従者がそれなりの人数ついているということも。「ええ、ですから、神子様をお出ししたのですわ。そうでなければ友雅殿と二人きりでお出かけなど心配で心配で。」「そうだろう、そうだよな、藤姫! あいつと二人きりなんて絶対あぶねーよな!」 こくんこくんと力強く頷く藤姫は、心の中では失敗したかとひやひやしていた。確かに天真の心配するとおり、二人の帰りはいつになく遅かった。日暮れまでに帰る約束が、もう日はとっぷりと暮れ、空には夕闇も広がって、一つ二つと見える星が増えていた。(人払い……という方法がありますから……) 二人きりになると何がどう危ないのかは藤姫にはよくわからなかったが、天真の様子から何かとても危険なことに思えた。友雅が女房たちを訪ねている時の様子が脳裏をよぎった。友雅が何をしていたのか乳母に聞いても乳母は口を濁すばかり、はかばかしい返事もなく話を逸らすのは、藤姫に聞かせたくない何かなのだろう。「その辺りまで見て参りましょうか。武士団の者にも声をかけましょう。」 頼久が言うのへ、藤姫は頷いた。顔には出さないが、頼久も天真と同じほどに怒っていることを知っていたから。 行き先を聞いておかなかったのが悔やまれた。聞いておいたとしても気まぐれな友雅のこと、本当にそこに行っているのかどうかも怪しいが。 じっとしてなどいられるかと、天真も頼久についていった。僕も行くよと、詩紋も出かけた。イノリくんにとひとりごちる声が聞こえたから、きっと話に行くのだろう。(本当に、友雅殿には困ります……。) 神子のために整えた庭に目をやって、藤姫は大きく嘆息した。表に牛車の音がしないかと耳をすませた。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 友雅の牛車は、まもなく四条の通りにかかるところだった。 藤姫の心配をよそに、神子は友雅の膝の上でぐっすりと寝入っていた。(まったく、無防備なことだ、ねんねさん。) 車の振動で体がもっていかれるからと膝に抱き取ったのだった。最初こそ、男の胸に抱かれる不安からか緊張した面もちだったが、遠出の疲れにだんだんと瞼が重くなり、「着いたら起こすよ」と一言囁き込んだら、あっさりと夢の国に旅立ってしまった。(君にとって、私は何なのだろうねえ……。) ぷっくりと柔らかそうな唇にそっと指を乗せてみた。そのまま引き寄せて口づけたい衝動を理性で押し込めた。龍神の鼻先からかすめ取るには時期が悪すぎた。京を救うのは帝の命。 代わりに、柔らかな重みを伝えるその体が、膝から落ちてしまわないよう抱きなおした。安心しきって身を委ねる様子はまるで幼子のようで、どうしてこの娘にこんなに惹かれるのかと友雅自身不思議に思うほどだった。(龍の宝玉の成せる技…かな。) そう思うならそういうことにしておけばいいと晴明殿も言った。人を恋うのに理由がいるのかと笑った。取り立てて美しくもなく、人に優れた才があるわけでもない凡庸なこの娘に惹かれる自分が不思議だっただけだ。この娘が他人と異なるのは、龍神に選ばれた神子であり、自分がその八葉であるというただその一点のみ。 考えても詮無いことと、友雅は扇を鳴らした。御前に、と、従者が御簾の元へ立った。「土御門に先触れを。神子殿がお帰りだと伝えよ。」「は。」 従者が立ち去るより早く、友雅は外に不穏な空気を感じた。何か固い物が投げつけられた様子で、従者たちが色めき立った。友雅はぱちんと扇を大きく鳴らして静まらせた。「ふふ、どうやらお迎えが来たようだね。」「てめ、友雅、どこ行ってやがった! 今、何時だと思ってやがる!」 御簾の外には、イノリが顔を真っ赤にして立っていた。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「だからイノリくん、そんなに怒らないで、寝ちゃったのは私も悪いんだから……」「そんなこと怒ってねえよ。あかねをこんなに疲れさせるくらい、どこへ連れてってたんだって!」 廂の柱に凭れた友雅は、ぱちんぱちんと扇を鳴らすだけで何も語らない。それがいよいよ、イノリをいらだたせるようだった。 詩紋がおろおろとあかねの顔を見ている。天真もぶすっと押し黙ったきり何も言わない。頼久が庭で警護しているのはいつもと同じだが、友雅の言動次第では剣を抜きかねない殺気が感じられる。「あの、友雅殿……」 おそるおそる、藤姫が口を開いた。先触れの従者の口上で事を知った藤姫が頼久に連絡を取り、皆を土御門に帰らせたのだった。「夜のしじまは、神子様にどんな穢れをもたらすかわかりません。ですから、お戻りは日のあるうちにとお願いをしておりました……。」 友雅は薄く笑ったが、やはり何も言わなかった。「てめ、何とか言ったらどうだ!」 天真が拳を振り上げた。頼久の手が柄にかかった。あかねがびくんと肩をふるわせた。「暴力はやめて。あかねちゃんが怖がってるよ。」 詩紋が止めた。「だいたい、あかねもあかねなんだ。もう帰ろうとか遅くなるとか、言えなかったのかよ。」「……だって、すごく綺麗だったから……」「お前、それが友雅の思うつぼだって、わかんねえのかよ。」「思うつぼって……友雅さんはそんな悪い人じゃ……」「お前、本当に何もわかってねえのな。こいつがどれくらいひどいタラシかって……」「友雅さんのことを悪く言わないで!」 振り向いたあかねの剣幕に、天真は一瞬引いたが、負けずに言葉を継いだ。「……だまされてんだぞ。知ってるか?」「だまされてなんかない。友雅さんは悪くない!」「あかね……」 あかねの顔は涙でくしゃくしゃにゆがんでいた。 友雅がふいに立ち上がった。あかねの側に座し、単衣の袖を引きだしてあかねの涙を拭った。「私のために泣いてくれるのかい?」 あかねはこくこくと頷いた。「優しいね、神子殿は。だから私は、こんなにも君に惹かれるのかもしれないな……。ありがとう、神子殿。今はそれで十分だよ。」 座の空気が色めいた。が、友雅がそれ以上あかねに何もせず、ついと立ち上がって御簾をくぐるから、振り上げた拳の行き先に困ってしまったようだった。「あの、友雅殿……?」 藤姫がそっと声をかけた。「また来ますよ。次からは少し自重しましょう。可愛い姫君の涙のためにね。」 悠々と立ち去る友雅の後ろ姿に、天真やイノリは何も言葉が出なかった。「なんだあいつ……」「……なんかむかつく。」「くそ!」 悔しいけれど、何か手を出せない。殴りかかっても軽くいなされそうで、怖いというのは絶対違うが、妙に敵わない空気が辺りに満ちていて、天真もイノリも、庭の頼久でさえも、歯がみして悔しがるしかなかった。「あれが、大人の貫禄ってヤツか……?」 拳をぎゅっと握りしめた。手のひらの汗がきゅうっと鳴る音がした。
2010年06月22日
コメント(0)
-
涙が出るとき(友藤)
涙が出るとき 何の前触れもなく、つ…と落ちた涙を藤姫は拭わなかった。 なぜ落ちてきたのかもわからない、しかし、落ちてきたときに何を想っていたかは覚えていた。(私……どうしたのでしょう。) 薄暗い殿舎の片隅にひっそりといけられた空木の花を見ていたのだ。(「紫陽花?」と。) 神子様の世界にある花とよく似ていたという。花には花に託された言葉があって、紫陽花の花言葉は「移り気」というのだと、そして、この花をどなたかに贈りたい、贈るべきだと二人で笑い合っていたとき、いきなり御簾をくぐって……(待ってなどいません。) 神子様がいらした頃は、八葉のおつとめのために足繁くいらしていたのです。それも時折は気がもめるほど間遠になったときもあるほどなのに、おつとめがなくなった今はもう……。(私は……) 友雅と浮き名を流した女房たちのあの顔この顔。どれもつんと取り澄ました美しいけれどひやりと冷たい印象だった。あれが友雅の好みなのだとすれば、自分の顔はほど遠い……。 などと考えて、藤姫ははっとかぶりを振った。(友雅殿なんて!) どの女房とも真剣につきあったことなどない。ああ見えて実のある方と思ってはいるが、どうも、仕事と向き合う友雅と、恋と向き合う友雅はまるで別人であるらしい。(友雅ぁ? あんなのまともに相手にするんじゃねえ。) 神子様に天真殿がしょっちゅう言っていた。妹の蘭殿の恋にも真剣に反対していた。あの頼久でさえ、露骨に嫌な顔をするときがある。鷹通殿からは嘆息しか聞こえない……。(どうしてあの方がこんなに気になるのでしょう。) 激しい雷雨の夜に、一人怯えていたところを助けてくれた。それからも折に触れて訪ねてきてくれた。年端もゆかない自分の話を真剣に聞いてくれて、八葉の勤めもそれなりに果たしてくれて……。 思いあぐねた顔をふと上げると。 藤姫はかあっと紅くなった。どうしてその姿がそこにあるのかと慌てた。 風向きが反対だったから、近づく薫りにもまったく気づかなかった。その薫りは潜め忍んで本当にけぢかく……藤姫の目の前にあったのだ。 大胆な広袖が軽々と藤姫を抱き上げる。「何をそんなに思い詰めているのです? そうやって眉根を顰めているお顔も見慣れず可愛いけれど。」 抱きすくめられた腕の中でいやいやと体を揺すっても、すっぽり抱き込まれた腕の中で何ができるわけでもなく。しかし、実は待ちこがれていたその膝の上に収まってしまえば、待たされていた間のとりとめもない悩み事はみるみるうちに消えてしまって、こうして訪ねてくれたうれしさだけが胸をいっぱいにする。「私に会えなくて、寂しくはありませんでしたか?」 思い切り首を振って返事する。「寂しくなんかありませんわ。」 強がってはみても、友雅にはすぐに見破られる。ついさっき、拭わずおいた涙の跡を見つかってしまうから。 友雅の指が涙の跡を伝い、次に唇で……乾いたそれを拭う。 ささくれていた心がすいと潤んで、新たな涙がじわり瞼をぬらした。 友雅の唇が吸い取る。わき出る物を一滴も逃すまいと。「寂しかった……。」 どうしてそういう言葉が出るのかわからない。でも、伝えずにはいられない。「待たせてしまいましたね……。」 友雅にも、どうしてこの小さな姫が気にかかるのかわからない。土御門にお気に入りの女房が多いわけでもないのに、つい、この館に足が向いてしまう。そして、この姫を訪ねてしまう。もう、龍神の神子はなく、八葉の任も解かれたというのに。 小さな体を直衣の胸に抱き込んで、友雅はほうっと息を吐いた。(まるで己の姫を得たような。) こんな年頃の姫があったとておかしくない年齢だった。しかし、この感情は父性とは違うと思った。恋ではない。もちろん欲情などではない。もっと慕わしい、しかし穏やかな、落ち着いた感情……これをいったいなんと呼んだものか。 真木の柱に凭れて、夜空を見上げた。 星が一つ、流れて消えた。
2010年06月16日
コメント(0)
-
涙のかけら(友あか)
あかねは友雅の涙が気になって仕方なかった。 友雅が泣くことなどないと思っていた。そもそも、大人の男が泣くところを見たことがなかった。あかねの父も、周りの大人も、あかねに涙を見せたことなど一度もなかったから。(何があったんだろう……。) ただごとではない。堪えても涙が溢れるほどのできごとが、心のかけらと一緒に友雅に戻ってきたのだろう。自分のためになくした物を取り戻そうと、そのためだけに心のかけらを探していたのだが、もし、友雅にとって忘れていた方が幸せなことなのだったら……。 誘われて出かけた散策だった。新緑の東山は風も心地よく、のどかな景色は友雅の言う「息抜き」にぴったりの場所だったが、戻り道のあかねの心は重かった。友雅は何事もなかったかのように御簾の外に目をやり、扇を鳴らしながら催馬楽を口ずさんでいる。その姿も、何かをごまかしているように思えて、あかねにはつらかった。 ふと、友雅の顔がこちらを向いた。あかねは慌てて憂い顔を引っ込めた。が、牛車の暗がりでも、友雅の目の方が一瞬早かった。「疲れたかい? すまなかったね。少し遠出が過ぎたかな。」 あかねは大きく首を振った。特上の笑顔を作った。友雅を心配させてはいけないが、友雅を心配していることも知られたくなかった。 「本当かい? 何だか気分が沈んでいるように見えるよ、神子殿。」「そ、そんなこと、ありません! 今日はとっても楽しかったし、疲れてなんか!」「そう。では、その顔は、恋をしている顔、なのかな?」「な……!」 あかねはぱっと顔を隠した。みるみる頬が熱くなり、耳まで火照ってくるのがわかる。 友雅はふ…と微笑んだ。がたがたと揺れる牛車で移動するのも友雅には慣れた技、あかねがとびすさるより早くそばに寄り、膝の上にあかねを据えてしまった。「と、友雅さん……!?」「そんなにつれなくするものではないよ。慣れないうちは牛車の揺れに体を取られて気分が悪くなるものだ。私に寄りかかっておいで。」 確かに、友雅に抱えられていると安定して、座った膝ががたがたと床に当たることもないから安心して乗っていられる。 友雅の鼓動が、背中から伝わる。大きな広袖に隠れた指先が、そっとあかねの頬に触れた。友雅の吐息がふっと耳たぶをかすめる。あかねの鼓動が早くなった。「瞳が潤んでいるよ、神子殿……」 どういうつもりかと身を固くするあかねの耳に、くつくつと笑う声が響く。「からかってるんですか!?」「おやおや、今度は怒っているのかい?」「当たり前です! 私が、こんなに心配してるのに!」「おや、誰の?」「友雅さんに、決まってるでしょう!」 言ってしまってから、あかねははっとして口を噤んだ。友雅は一瞬「意外だ」という表情を見せたが、すぐにいつもの余裕のある笑顔に戻った。「光栄だね、神子殿に心配していただけるとは。私のどこが、そんなに心配になったんだい?」「……友雅さんが、泣くから。」「泣いた? 私が?」「……随心院で。」 ああ、と友雅は手を振り仰いだ。「そんなつもりはなかったのだがねえ……私としたことが、不覚だったな。」「何があったんですか? よければ、話してください。」「……神子殿に聞かせる話ではないよ。」 困ったような寂しげな笑顔。あかねは、同じ顔をどこかで見たと思った。(嵯峨の野宮でも、確か……) 過去を話したがらない友雅だった。土御門の女房たちの噂話の種にならない日はない友雅だったが、過去のことは誰もよく知らなかった。友雅しか知らない、ひた隠しにされている過去。浮き名を流す以前かその中に、よほどつらく苦しい想い出があるのだろう。そしてそれは、心のかけらと一緒にあるいはそのものとして、友雅の心から消えていたのだろう……。「ごめんなさい……。」「どうして謝るの。」「私が心のかけらなんか集めたりしなければ……。」「それは違うよ、神子殿。」 友雅の大きな手が、あかねの頭を撫でた。一粒溢れた涙を指先が拭った。「こんな大事なものを、私は忘れていた。思い出させてくれたのは君だよ、神子殿。君が心のかけらを集めてくれたおかげだ。」「大事な……もの?」「そう。人が人として生きていくにはきっと、ね。」 もうすぐ着くよと、友雅は手近な御簾を少し上げて外を見せた。空はあかねと同じ名の色に染まり、西の空低く大きな一番星が輝いていた。「神子殿、もし許してくれるなら……」 友雅は何か言いかけて口を閉じた。あかねが不思議そうな顔を向けると、ふふと笑った。「いや、やめておこう。まだ時が来ていない。気にしないでくれまいか。君の大事の前に口にすることではないからね。」 友雅の言葉の意味を考えているうちに、車は土御門の車宿りに引き入れられた。「神子様!」と出迎える藤姫の声が聞こえた。
2010年06月05日
コメント(0)
-
祭見物(友あか)
目覚めると、藤姫が笑いたいのを必死に堪えている顔で座っていた。「神子様、今朝は友雅殿がお迎えに来ていらっしゃいますわ。」 麗らかな皐月の青空が広がる朝だった。意味ありげな藤姫の表情を不思議に思いながら身支度をすませて居間へ出ると、見慣れぬ正装の男が馴れた風で蝙蝠を使いながら座っていた。向こうを向いているから顔は見えないが、蝙蝠の風で漂う香りに覚えがあった。 男は振り向きもせずにふっと笑った。あかねは確信した。「やあ、神子殿。お目覚めかい?」「友雅さん、どうしたんですか、その格好!」「おかしいかい? 今日は早朝からのお召しでねえ。」 窮屈だけれど、まだ脱ぐわけにはいかないから参ったねと困り顔で微笑んだ。「どうして参っちゃうんですか?」「さあ、どうしてだろうねえ。それはもうすぐわかる、かな。」 友雅はぽんぽんと手を打って従者を呼んだ。準備はできておりますと言う声に大様にうなずいた。「さあ神子殿、おいで。今日はいいところへ連れて行ってあげよう。」「どこへですか?」「ないしょ。もし一人では信用できないとおっしゃるなら、藤姫もご一緒にいかがですか?」 そばで控えていた藤姫の顔がうれしさ半分困惑半分に輝いた。「よろしいのですか?」「ええ、いいですよ。その方が神子殿もご安心でしょうし。」 ちらりとあかねの方を見るから、あかねは慌てて手を振った。「そ、そんなこと、ないですよ。友雅さんと二人が怖いなんて、私、言わないです。」「ほほう、私と二人は怖いって? それはまた嬉しいことを言ってくれる。」「ど、どうしてですか!」「少しは期待してもいいということかな、神子殿。」 手を取ってそっと唇を寄せるから、藤姫がきっと見とがめた。「友雅殿!」 友雅は笑ってあかねの手を離した。藤姫はあかねのそばにさっと寄って、ぎゅっとあかねの手を握った。「冗談です、神子殿を攫ったりはしませんよ、藤姫。出かけるでしょう?」 たまには息抜きも必要だと、友雅が腰を上げた。あかねと藤姫はしっかりと手を取り合って後に続いた。車宿りには友雅の牛車が待っていた。3人乗ると膝をつき合わせる狭さ。あかねは藤姫が一緒なのに心からほっとした。(だって、最近の友雅さんったら……) 出会った頃はまるで興味がない風だったのに。優しい大人だ、ああ見えて頼りがいがあると甘えて油断していると、さっきのように妙な行動を取る。藤姫がいなかったならどうなっていたか。想像すると顔がかあっと火照ってくる。「ふふ、何を考えているのかな、神子殿は。」「な、何も考えてなんかいません!」 つれないねと流し目をくれるから、あかねの顔は火照るばかりだった。隣の藤姫があかねの手を強く握り、友雅の顔をきっとにらんだ。友雅は苦笑して御簾の外に目を移した。新緑が眩しい。 牛車は静かに動き出した。きいきいと車のきしむ音が響く。牛飼い童の牛を追う声、従者の先触れの声。ごとごとという揺れに体を取られてぐらり傾くと、友雅に寄りかかる形になってしまうから、あかねは必死で木枠に捕まっていた。「遠慮せずに寄りかかったらいいのに。何もしないよ。」「ダメです! そんなこと。」「おやおや、よほど信用されていないのだねえ。まあ、それでもかまわないけれどね。」 ふふと含んだ笑い方が怖いほど不気味で、あかねは身をすくませた。(こんな友雅さんと、この先やっていけるのかしら……) なるべくお供をお願いしないようにしようと思ったときに、外から声がかかった。「このあたりでようございますか。」「ああそうだね。ゆらさないように気をつけて立てておくれ。」 車の向きがぐるりと変えられた風だった。牛の大きな鼻息が車の横を通り過ぎて、前の御簾が半分ほど巻き上げられた。「神子殿、おいで。ここならよく見えるだろう。」「何がですか!?」「そんなに人を警戒するものではないよ。もっともそれは私のせいなのだろうけれどね。ほら。」 藤姫はもうどこへ来るのかわかっていたようだ。きらきらした目をして前の方へ出てきた。「神子様、お祭りですわ。斎王様が賀茂のお社にご挨拶に行かれるのです。」「それって、葵祭?」「はい。友雅殿の挿頭でもしやとは思っていたのですが、本当に連れてきていただけるなんて!」 目を輝かせて前に出てきた藤姫に座を譲って、友雅は車の後部に下がった。「神子様」と呼ばれてあかねも藤姫の隣に座した。御簾が上がっているから、往来がよく見える。行列が通るという道の両側には同じような牛車がずらり立て並べられて、浮き立つ笑顔がそこかしこに溢れている。 はしゃぐ藤姫と一緒に外を見ていると、どうやら行列が近づいたらしく、周囲がざわめき始めた。先触れの使者が通っていく。この日のために整えられたであろう鮮やかな装束。勅使の乗る牛車は薫り高い藤の花房や艶やかに咲き誇る山吹に彩られて実に優雅に美しい。「気に入っていただけましたか、姫君たち。」 背後からかかる声に、上機嫌の笑顔を返した。ふふと嬉しそうに笑う顔は、後部の御簾を引き上げてのぞいた顔にかき消された。 なにやら指示を仰ぐらしい小声。普段見せないまじめな顔は少し眉をひそめて、少なからずやっかいな気配を感じさせる。蝙蝠で顔を隠してしばらく考え、短くいくつか指示したようだった。のぞいた従者の顔はぱっと明るくなり、いそいそと車を後にした。(あれがお仕事してる友雅さん……) 胸がどきんとした瞬間に、友雅と目があった。あかねはさっと目をそらした。何か言いたげな含み笑い。からかわれる前にあかねは体の向きを変えた。勅使が通り過ぎて、斎院の代理を務める使者の女行列が始まったところだった。「美しいご衣装ですこと。」 藤姫がほうっとため息をついた。とりどりに華やかな衣装を見て藤姫と一緒にはしゃぎながらも、あかねは背後を気にしていた。穏やかでも何か不思議な熱を感じる視線……友雅の。 そわそわと落ち着かない気持ちに、あかねは戸惑った。何か話さないとこの場にいられない気分だった。そんなあかねを見透かすように、また友雅が笑った。あかねは更に落ち着きを失った。藤姫が不審に思うほどに。「どうかなさったのですか? 神子様。お顔の色が赤いですわ。」「な、なんでもないよ、藤姫。ほら、今日の藤姫の着物の色が映ってるんじゃない?」「そうでしょうか。何だか汗ばまれて、お熱でもあるような。」「熱なんかないって。暑いからだよ。ねえ、今日ってすごく暑いよねえ。藤姫、暑くない?」「私はそれほど暑いとは思いませんが……扇いで差し上げましょうか?」「う、うん、助かるよ、藤姫。へええ、檜扇って結構風来るんだねえ。」 蝙蝠の影でくつくつと笑い転げる声に、聡い藤姫はぴんときた。「友雅殿!」「はいはい、ご機嫌を損ねてしまう前に御屋敷へお送りすることといたしましょう。」 行列を見送って去る車の順番を待って、友雅の牛車も出発した。後片付けの指示が必要なようだからと、友雅は馬を連れてこさせて乗り換えた。牛車の供につく形で隣を歩かせているらしく、かつかつという蹄の音が遠く近く聞こえる。ひとりでに胸が熱くなるのをあかねは止められなかった。ぎゅっと胸を押さえているから、藤姫が心配そうに顔をのぞき込んだ。「神子様、ご気分が悪いのですか?」「え、あ、うん、大丈夫、心配しなくていいよ。」「ならよろしゅうございますが……」 心配顔の藤姫に笑顔を向けて、あかねはじっと外を見ていた。この胸に宿った想いはなんなのだろうと考えていた。
2010年05月21日
コメント(0)
-

星逢瀬(翡花)
星逢瀬 暮れなずむ空に見え始めた星を見上げる花梨の頬を涙が一筋伝ったのを、翡翠が見逃すはずはなかった。 寄り添う肩を抱く腕に力を籠めた。「どうしたの。」「ううん、何でもない。」 応える声が潤んでいないのに少し安心したが、伝う涙が止まる様子はなく、翡翠は花梨の瞼に口づけた。あふれる涙を吸い取った。瞼が震える。「私、どうしちゃったんだろう……」 唇を離すと、困ったように笑う花梨の顔があった。「悲しいことなんかないんだよ。ほらあの、」 西の空を指さした。「昨日は、三日月と金星がすごく近かったのに、今日はこんなに離れてるでしょ? 私と翡翠さんも……」 花梨の瞳が不安に揺らぐ。いたたまれなさを感じて、翡翠は花梨を強く抱き締めた。「余分なことは考えなくてもいい……私が君を手放すと思うのかい?」 何が彼女をこんなに不安にさせるのか。出逢う前の遊んだ記憶が翡翠を嘖む。刹那、楽しければいいと思っていた日々。何も拘泥せず、執着もせず、風に任せ波に委ねて心の儘に摘み取り摘み捨てた恋。澱んだ過去が穢れとなって、今、この何にも代え難い宝を苦しめている……。(私の白菊。私の大事な人。) 私が君から離れることはない。生まれて初めて、こんなに人を愛しいと思った。心から。私が君から離れるとしたら、それは君が私から離れていくときだ。君がここにいる限り、私は君を愛し続けるだろう。いつまでも、いつまでも、永遠に…… 腕の中の花梨が小さな身じろぎをする。固く抱いた腕の中でもがく小鳥。そっと腕を緩めると、大きな息を吐いて翡翠を見上げた。信じていると穏やかな光をたたえて、まっすぐに見つめる瞳に、翡翠はもう一度唇を近寄せた。両の瞼に一度ずつ、そして柔らかい花の唇に……決して離れないと誓いを籠めて。 空に残る光が少しずつ薄れ、暗い闇が覆う。明星ばかりが目立っていた空に星々が溢れる。花梨の世界では希少な降るような星空。 吹く風の涼しさに、花梨がくしゅんとくしゃみをした。 二人を取り巻く空気が、ふわり暖かくなった。「戻ろう。」 促す翡翠に、花梨は素直に従った。(暖かい船室で、愛を交わそう。君が二度と不安になることがないように。) 花梨の頬が赤く染まった。
2010年05月17日
コメント(0)
-
【小さい千尋と風早のお話】 春うらら
「風早、風早、引いてるよ!」 「ありがとうございます、姫。」 千尋のお弁当のために、釣れた魚を料理しようとあれこれ準備しているから、急いで来ても間に合わない。 引き上げたときには、餌だけとられて針は空。 「ああ、逃げられてしまいましたね。」 「風早が来るのが遅いからだよ。」 「すみません。ちょっと手が離せなくて。」 千尋は不満そうに風早を見上げていた。そもそも、今日は、この間羽張彦のせいで中止になったのの埋め合わせにと連れてきたのだった。がっかりさせないように、楽しい思いだけするように、あれこれ言葉をかけて出かけてきたのだった。 と、千尋の顔が急に輝いた。目がいたずらっぽく笑った。可愛い唇が開いた。 「今度引いたら、私が上げてもいい?」 言うだろうとは思った。想定内の展開だ。 「大丈夫ですか? 池に落ちたりしたら……」 「大丈夫。気をつけるから。」 風早は心配そうに千尋の顔を見た。手入れをしてきたとはいえ、自分で使うつもりで準備した竿は千尋の小さな手にはずっしりと重い。しかし、ここで駄目を出せば、千尋の不満は募るばかり。なんのために出かけてきたのかわからなくなりそうだ。 風早は大きく嘆息した。「仕方ありませんね。」 竿が抜け落ちてしまわないように、竿受けの根元に紐を掛けた。竿の尻を深く地面に差し、そこを支えに竿を上げればよいようにした。「なるべく竿の先を持つようにしてくださいね。そうすれば、姫の小さな手でも持ち上げることができますから。」「わかった。」 千尋の顔が笑顔に変わったのを見届けて、風早は竈を作りに戻った。石はほとんど積み上がっていたから、後は火をつけるだけ。火起こしを手に取った。千尋から目を離さないように、しかし、火の熾った隙も見逃せない。「風早ぁぁぁぁ!!!」 千尋の悲鳴と続いて聞こえた大きな水音に、風早の顔が青ざめた。「千尋!」 先ほどまで見えていた姿が見えない。池に落ちたのに違いない。水音は更に激しくなる。「風早、風早、早く来て!」 言われるまでもなく、千尋の元へ急いだ。水辺に来た風早が目にしたのはしかし溺れる千尋ではなく、何かをしっかり抱えて水中でもがく千尋だった。「何をしてるんです?」「捕まえたの、お魚捕まえたの、手伝って!」 足の届く範囲だったのが幸いだった。倒れさえしなければ溺れることはない。波が千尋の危うい平衡を狂わすことがないように、風早は慎重に、しかし急いで千尋の側へ寄った。「見て!」 得意そうに千尋は抱えていた物を見せた。灰銀色の鱗が日に映えてきらりと光った。丸まると太った鯉だった。千尋の腕の長さほどもある、かなり大きい。魚は逃れようとして体をくねらせた。逃すまいと抱き締めた千尋の体が大きくぐらつく。風早はさっと腕を出して千尋を支えた。鯉はまだ針を飲み込んだままだ。風早は自分の広袖を網代わりにして、千尋に鯉を入れさせた。「私が捕まえた!」「竿を持ち上げなかったんですか?」「持ち上げたけど、届かなかったもん。暴れて怖かったし。」 だからと言って水に入らなくてもと風早は呆れる言葉を飲み込んだ。ぐっしょり濡れた千尋を水から引き上げる方が先だ。竿の先をぐいとつかみ、埋め込んだ竿尻を引き抜いた。竿を回すようにして岸へ向かい、まずは千尋を安全な場所へ下ろして、鯉の針をはずした。広袖に鯉を包み込んで、千尋の手を取り、竈を築いた場所へ行った。「濡れた服を乾かしましょう。怪我はしていませんか?」 千尋の捕まえた鯉は、風早の用意していた魚籠でぴちぴちとはねている。満足そうにいつまでもそれを見ている千尋を促して、衣服を脱がせた。傷がないか確かめながら柔らかい布で小さな体を拭くまではよかったが、風早は途方に暮れていた。着替えを用意してこなかったのだ。池に落ちることを想定しなければならなかったのに。 急いで水に飛び込んだとはいえ、長身の風早の衣服は、袴はともかく上着はほとんど濡れていない。鯉を包んだ広袖の先が少し濡れているだけだ。風早は上着を脱ぎ、それで千尋をくるみこんだ。「風早は寒くない?」「平気です。今日はこんなに暖かいから。」 麗らかな春の日差しが眩しいほどの日だったから、千尋を外へ連れだしたのだ。「千尋は寒くありませんか?」 千尋は小さく首を振った。しかし、その肩がぶるんと震え上がったのを、風早は見逃さなかった。風早は千尋の体を引き寄せ、抱き締めた。「こうすれば、暖かいですね……。」 腕の中でこくんと頷く。「ごめんなさい。」とくぐもった声が聞こえた。「どうして謝るんです?」「だって……」「千尋は悪くありませんよ。大きな魚を捕ってくれたのでしょう? そうだ、少し待っていてください。こちらを見ないように。」 風早は千尋を下ろして、鯉を見に行った。千尋に見えないように体で隠して鯉をさばき、樫の焼き棒に差して竈に立てかけた。 焼き上がるのを待つ間に、千尋の体も暖まるだろう。思いの外暑い春の日差しは、千尋の小さな軽い衣服などすぐに乾かしてしまうだろう。「いい子で待っていましたか?」 もういいの?と振り向く千尋を、思う様抱き締めた。煌めく水面を二人一緒に眺めた。この幸せがいつまでも続くといい……風早の中の白麒麟が独りごちた。
2010年04月24日
コメント(0)
-
【風千】 酔夢(ちょっと大人向け)
(今日も風早、遅いのかなあ。) 今日の食事当番は那岐だったけれど、面倒だからと押しつけられた。そのときはぶんむくれたけれど、那岐のためにはともかく、風早のために食事を作ることは千尋にはむしろ嬉しいことだったから、表面はしぶしぶながらも内心喜んで引き受けた。那岐が作るとろくな物が出てこない。ものすごい偏食で食べられるものが限られているから、その範囲でしかも簡単に調理できる物になる。「スーパーの値札に一喜一憂する生活」と常世の皇子に揶揄されたけれど、千尋はそれが嫌いではなかった。風早がどんな思いをして決して多くはない月々の給料を手にしているか、身近に暮らしていればよくわかる。楽しそうに笑顔でいるが、学校生活はいいことばかりではない。たくさんの悩み事、ケンカ、心のすれ違い。風早は「話せる先生」と思われているから、時に千尋がやきもちを焼きたくなるほど大勢に囲まれていることもある。その一つ一つに、風早は親身になって話を聞き、修復の手助けをしている。 でも今夜は、成績の処理をするのだと言っていた。千尋や那岐に見えないように職員室で片づけてくるから、待たないようにと言われた。だから千尋は、風早の胃に負担にならない軽い物を準備するつもりだった。(にゅうめんとか、いいかな。) そうめんはゆでて置いておけるし、めんつゆも作り置きできる。風早が帰ってきたら温めて、白髪ネギをのせて、生姜をすり込んで……。 ちりめん山椒を混ぜ込んだ小さなおにぎりをいくつか握った。味見がてら、那岐と一緒に先に済ませた。那岐はいつも通り自室に上がってしまったから、千尋は一人、階下でテレビを見ていた。そしていつか、眠ってしまった。 玄関先でどっと何かが倒れる音に、千尋は飛び起きた。(何!?) おそるおそるのぞいてみると、風早が倒れ込んでいた。びっくりして助け起こした。「風早、風早、どうしたの!」 吐く息が酒臭い。どうやらどこかで飲んできたようだ。(飲めないのに……) あきれ顔半分心配顔半分で、千尋は台所へ急ぎ、冷たい水でタオルを濡らした。汗ばんだ風早の額や頬をそっと拭いた。「う……ん……」 風早の目が薄く開いた。「千尋……? ということは、オレは無事に家に着いたようですね……」「そうだよ。どうしたの、どこで飲んだの。」「仕事が一段落した打ち上げに、つきあってきました。たまにはそういうつきあいもしなくてはね。」「そうかもしれないけど、風早、お酒飲めないのに!」 風早は返事の代わりに微笑んだ。姫にはわかりませんよと言われているようでしゃくに障ったが、目の前で倒れている風早を放ってはおけず、冷たいタオルをぴしゃんと額にたたきつけるように貼り付けて鬱憤晴らしにした。「那岐、那岐、手伝ってよ。風早運ぶんだから。」「何だよもう、そんなのそこに捨てといたらいいだろ?」「ダメだよそんなの、風早風邪ひいちゃう!」 仕方ないなあとふくれ面で下りてきた那岐に手伝ってもらって、支えれば何とか立てた風早を部屋まで連れて行った。風早がベッドに倒れ込んだのを見届けた那岐は、「もういいだろ」と、また自室へ眠りに行ってしまった。 千尋は風早の上着を脱がせにかかった。べろべろに酔ってはいるがまだ少しは意識があるから、千尋の脱がせやすいように少しぐらいは体を動かしてくれる。ネクタイをほどき、カッターシャツのボタンをいくつかはずした。腰を締め付けているベルトも緩めれば楽になるだろうけれど、触れるのが戸惑われた。(……男の人の匂いがする。) 恥ずかしかった。でも、少しでも楽になって欲しいと赤面しながら伸ばした。 その手を、風早が止めた。「俺がしますから……。」 ぼうっとしたまま、ベッドに起きあがった。「俺の部屋着を取ってください。」 千尋が向こうを向いているうちに器用にズボンを脱いだ。千尋の目に触れないようにシーツにもぐり、千尋が手渡すパジャマに着替えた。「すみませんね……」 無理に見せる笑顔があんまり情けないから、千尋はそれ以上怒れなくなった。出雲の時と同じだと思った。でもあのときと違うのは、今では千尋も、風早にしてもらいっぱなしではなくて、たくさん風早にしてあげることがあるということ。例えば今夜のご飯だって……。「風早、お腹空いてない?」 少し飲むとすぐにへろへろになってしまうから、あんまり食べてないと思った。「すみません、食事より、眠るのが先のようです……」 そう言う言葉尻がすでに眠りに落ちていた。ぐっすりと眠り込んでしまった風早を少し不満に思いながら、千尋はそっと毛布をかけた。タオルをもう一度絞ってきて、額にのせた。風早の眉間が気持ちよさそうにゆるんだ。千尋はふうっとため息をついて、風早の仕事机の椅子に座った。そしてそのまま、机に凭れて眠ってしまった。 深夜、風早は目を覚ました。 酔いはまだ少し残っていたが、寝不足のような程度で気になるほどではなかった。寝ぼけた目で見回すと、机に突っ伏して眠っている千尋が目に入った。「千尋……。」 家に帰ってからの記憶が朧によみがえる。しまったという反省の気持ちが半分、面倒を見てくれた感謝の気持ちが半分、風早は立ち上がり、千尋のそばに寄った。 規則正しい寝息は、千尋がぐっすり眠っていることを告げている。起こさないようにそっと抱き上げた。う…ん……と小さく声が出たが、小さい頃からの習慣は千尋の目を覚まさせない。 そのまま横抱きにベッドへ運んだ。さっきまで自分が寝ていた布団に千尋を横たえた。 普段着のままで眠ってしまった千尋の衣服を緩めた。風早の手は遠慮などしない。従者として姫のお世話をするのは当然だと、あっさりと衣服を脱がせ、手近にあった自分のトレーナーをパジャマ代わりに着せた。 最近、しっとりと丸みを帯びてきた千尋の慕わしい感触が、風早の酔った頭の何かを疼かせる。風早は激しく頭を振った。穢れは振り落とさなくてはならない。立ち上がり、風呂へ向かった。 ヒトの体とはやっかいなものだと風早は舌打ちした。男の部分が反応してしこっている。これが穢れの元凶だと、風早はいつも通り、熱いシャワーをあてながら手をあてがった。洗い流すように幾度かこすると、しこったものはあっさりと中の「穢れ」を吐き出しておとなしくなる。吐き出す瞬間に立っていられないほどの快さを感じる。(千尋……) 黒い欲の混ざった声で呟くこともある。風早はくっと唇を噛んだ。決して知られてはならない。こんな欲を抱いたまま、千尋に触れてはいけない。この想いは、千尋を穢す。人間の罪深い欲望。龍神の神子の血筋を絶やしてはならないが、その役目を自分が負うことができるとは風早は思っていなかった。この体はそれを許されてはいない。あくまでも従者。中つ国の王族の血に混じることは身分に反する。それくらいは弁えて……いる。 タオルで雫を拭き取ると、余分な火照りまで冷めていくような錯覚に囚われる。 風早はパジャマを着て、部屋に戻った。何も知らない千尋が、幸せそうな寝息を立てている。(この幸せな眠りを妨げてはいけない。) 小さい頃したのと同じように、そっと隣に寄り添い、細い体を抱え込んだ。傍目には無防備とも思えるほどに千尋は易々と風早の胸に納まる。無意識にではあろうが、自ら頬を埋め、甘えるような仕草を見せる。風早の中の男がまた目を覚ます。(千尋……) 歯を食いしばって耐えた。なめらかな額に口づけを落とし、静かに目を閉じた。髪の甘い香りが鼻腔をくすぐる。その香りに包まれるだけで幸せだ。こうして腕の中に千尋を閉じこめておけることに感謝しよう。 規則正しい寝息は千尋の子守歌。 風早はいつか、千尋を抱いたまま眠っていた。
2010年03月09日
コメント(0)
-
【景望】 二人だけの
(今日もまた日没終了かなぁ……) 指輪をもらってから初めてのデート。沈む夕日を見つめながら、望美は思っていた。 高校の卒業式も終えて、夜遅くなる理由がなくなった。自然、暗くなってから一緒に歩くこともなくなって、たまに約束してデートしても、日が沈むまでに春日家の玄関に送り届けられる。「せっかくもらった信用を反古にしたくはないからさ。」 景時の言うことはもっともだが、何か寂しい。日のあるうちのデートが不満だとか、イケナイことをしたいとか、そういうわけではないのだが、せめて夕暮れの浜で一緒に沈む夕日を見送るとか、しっとりした春の香りの風を感じながら極楽寺の切り通しを歩いてみるとか……。「どうしたの。」 優しい瞳が見下ろしている。望美は赤面した。せっかく時間を作って一緒にいてくれているのに、仏頂面になってはいなかっただろうか。望美は特上の笑顔を景時に向けた。景時が安心したようににっこり笑った。 極楽寺の駅を下りて、当然家の方へ向かうと思ったら、景時は反対側へ足を向けた。「景時さん?」「たまには、いいでしょ?」 いたずらな笑顔。本当に大丈夫なのだろうか。「少しだけ。」 極楽寺の切り通しを長谷の方へ歩いていく。心にふと浮かんだ小さな望みを見透かされたようで、望美は少し面はゆかった。しっかりと握られた手が温かい。どこへ行くというのか、望美は連れて行かれるままについていった。たまにはいいというなら、いいのだろう。景時はそれだけ、春日の両親に信頼されたのだろうから。 星月夜の井の前で、景時は立ち止まった。こちらの世界に合わせて小さく作り替えた式銃を取り出した。 バシュン…… 何かが飛び出して、とぷんと井戸の中に落ち込んだ。「今のは?」「うん、ちょっと気になったからね。」 しばらくすると、景時のサンショウウオが何かを銜えて上がってきた。小さな紙片は、いつかの人型を思い出させた。望美の体に震えが走ったのを、景時がやんわりと抱きしめて止めた。「大丈夫だって。」 サンショウウオから紙片を受け取った。何か書き付けてあるのを、景時は目を凝らして読んだ。が、その顔は終始穏やかで、望美が心配するようなことは何もないようだった。「もう少し、つきあってくれるかな。」 望美の手を引いて、更に歩を進めた。あたりはとっぷりと暮れて、薄明かりの残る空には一つ二つと星が輝き始めている。「ねえ、本当にいいの?」「大丈夫だよ、オレを信じて。」 しばらく歩いて、小さな踏切を渡り、御霊神社の鳥居をくぐった。望美は景時の想いがようやくわかった。「ごめんね、君と詣でておきたかったんだ。でも、こんなに遅くなってからでなくてもいいのにね。」 神前で手を合わせた後、景時が言った。望美は首を横に振った。何か思うところがあったのだろう。わざわざ約束を曲げて来たのだから。 いいよという言葉に力を得て、景時は話した。「大丈夫だとは思ったんだけどね、君とこれからずっとこっちの世界で暮らすんだから、確かめておきたかったんだ。荼吉尼天の脅威が本当に消えているのか。式が持ってきた物には、何も問題ないとあった。でもやっぱりオレ、怖いからさ……」 望美はくすりと笑った。景時も照れくさそうに笑って肩をすくめた。「ご先祖様のお力を、借りておこうと思ってね。梶原の血筋は、オレがちゃんと守りますって。君と一緒に……いいかな。」 望美は、景時の目をじっと見つめた。見下ろす景時と視線があった。手を取り合い、もう一度神前に進んだ。二人一緒に拝礼し、二人一緒に柏手を打った。 景時の腕が、望美の方に伸びてきた。抱き寄せ、固く抱きしめる。「結婚式……二人だけの。」 誓いの……キス。 だから、こんなに暗くなってから、誰もいない時間に、やってきたのだ……。 極楽寺坂をもう一度登って、家に帰った。 家に入る前に、もう一度抱き合った。「もうすぐ……。」 囁く景時の言葉に、望美はうんとうなずいた。 桜が咲いたら、八幡様で本当の式を挙げる。それから先は、有川家の離れでずっと一緒に暮らせる。二人の気持ちが変わらないのを確かめたから、有川家のご両親が景時の親役をかって出てくれたのだ。スミレおばあちゃんが繋いだ縁だろうと言って。「うちの息子たちのどちらかじゃなかったのが残念だわ」と付け加わったが。 春日家の裏庭へ続く砂利を踏んでいく景時。足音が少しずつ遠ざかる。「おやすみなさい。」 抱きしめられた温もりが冷めないように、望美は急いで家に入った。幸せに火照る体を自ら抱きしめた。
2010年03月08日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 春宵
友雅はふと、手にした杯を置いた。 空にかかる十六夜の月が気にかかった。(まったく……) 小さな姫君という縁も得たのだから、そんな心配など無用のものだと思うのに、今夜のように月の明い夜は小さな不安がよぎる。 春の朧に霞む月。乙女が空を割って落ちてきた。 向こう側に、迎えの車が透けて見えはしないか。 杞憂だと思うのに、目を凝らしてしまう。唇が名を呼ぶ。「あかね……?」 命婦ネコが心得顔ににゃあんと鳴いた。「どうしたの? 命婦。」 愛しい影。駆け寄り、抱きしめたいのを堪える。ふっと薄く笑い、また、杯を手に取った。 にゃあんと鳴く声が得意げに響く。ご褒美だと顎の下をくすぐれば嬉しそうに身じろぎする。ごろごろと喉をならし、心地よさげ寝そべる。 命婦に導かれて近づいてくる温もり。「私を呼んだんじゃなかったの?」 猫に向かって無邪気に伸びる手。抱き上げようとする手を友雅は逃さなかった。奪い取るように捉え、強く引き寄せれば、愛しい重みは膝の上に落ちる。乱れた袿で包み込んだ。不意をつかれた体が暴れる。強く抱きしめればそれは徐々に静まり、甘くとろけた瞳がじっと友雅を見つめる。幸福で胸がいっぱいになる。「呼んだよ……」 頬を近寄せ、口づける。求め合う唇は離れてもまた互いを探す。あかねの腕が友雅の頸に巻き付く。引き寄せ、引き寄せられ、飽くことなく互いを求め、求められ……。「愛してる……」 耳元に囁きこまれる愛の言葉。暖かく体を流れるものは、友雅の知らなかったもの。突き動かされるように更に固く抱きしめた。あかねの唇から小さなあえぎが漏れた。煽られる。狂おしいほどの口づけ。「愛しているよ……」 どこにもいかないで。ずっと、私のそばに……。 あかねが、くすりと笑った。「変な友雅さん。私の居場所はここなのに。」 自ら懐深く潜り込んできた。細い腕が胴にまかれ、ぎゅっと抱きしめられる。愛される喜びが全身を駆けめぐる。満たされる。 抱きしめ合い、溶け合ってしまうかに思えるほどの……陶酔。「酔ってるの?」「ああ……そうかもしれないね……。」 ……君に。 囁く声に耳元まで赤く染まる。可愛い、愛しい、何ものにも代え難いもの。 傾く月に、梅の香が香る。 神子はもう、月には帰らない……。
2010年03月07日
コメント(1)
-
【10万ヒット御礼:翡花】 如月星夜
先日は(かなり前になりますが)10万足跡ありがとうございました。アンケートを採らせていただきました結果、「翡花」が堂々の1位!バレンタインにふさわしく(?)甘い翡花、お届けいたします。※先日の「遙か十年祭」にて、武道館では披露されなかった、 翡翠さんの語りからちょこっと、ちょうだいしております。 真ん中に。 こんなシチュの、語りだったんですよ~※☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 星のきれいな夜だった。 花梨は一人、縁の手すりに凭れて空を見上げていた。(翡翠さんも、この星、見てるかな……) 如月の十四日、花梨のいた世界ならバレンタインデーで恋人たちには特別な意味のある日だったが、今、花梨がいる世界は龍神の加護する京。バレンタインデーはおろか、チョコレートすら手に入らない。 花梨はため息をついた。想いを伝える手段はそれに限ったことではなかったが。 高台にある翡翠の館からは、遠く海が見渡せる。遠くに篝火を焚くあの船が、翡翠の船だろうか。今日は、夜行で海を渡る水先案内の依頼を受けたと言っていた。夜間の航行は物騒だからと、部下にまかせず自ら出かけた……依頼を完璧に遂行するために。 潮の香りが穏やかに花梨の頬を撫でる。星灯りが優しく花梨を包む。 花梨は手すりに凭れたまま、いつしかぐっすりと眠り込んでいた。「お方さま?」 侍女が声をかけたが、目を覚ます様子もない。侍女は困った顔をしながらも、奥から翡翠の大きな衣を持ってきてふわりと花梨に着せ掛けた。衣に残る移り香は、花梨をいよいよ、深い眠りに引き込んだ……。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 目を覚ますと、花梨は翡翠の船の上にいた。(あれ?) 眠り込んだときと同じに、手すりに凭れている。しかし、目の前に広がる景色が全く違っていた。見渡す限り広がる大海原、足元はおぼつかなく揺れる船の甲板。「目が覚めたかい? 何を見ているの。」 大好きなあの香り、あの温もりに包まれた。背後から聞き慣れた優しい声。「翡翠さん。」 体の向きを変え、抱きついた。唇が熱を帯びた柔らかい物に押し包まれる。守られている幸福感に胸がいっぱいになる。「妬けるねえ……君の眼差しを独り占めしている。」「え?」「海が、だよ。愛しい人。」 もう一度、しっとりと湿った温かな唇が落ちてきた。「君の瞳には私だけを映していて欲しいというのに……まったく、君という人は。」「だって、この海も、翡翠さんの大事なものでしょう?」「比べものにならないよ。君は私だけのもの、私の……可愛い白菊だ。」 真っ赤になってうつむく花梨を、翡翠は静かに抱き上げた。「行こう。」「どこへ?」「私たちの場所。私たちが二人きりで居られる場所へ。」 花梨は翡翠の肩に顔を埋めた。上品な侍従の香りが、潮の香りと混ざる。「愛しているよ……」 静かに歩を進める翡翠の足は、頭に用意された船室へ向かっている。花梨の頬は熱く赤くなった。熱を増した花梨の体を抱く翡翠の腕に力が籠もった……。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆(ふう……) 大きなため息をついて、翡翠が部屋に戻ってきた。 髪をかき上げ、表着を脱いだ。傅く侍女が、困った顔をして翡翠を見上げた。「奥方は?」 侍女は困った瞳を縁に向けた。翡翠の衣を被いて眠り込む花梨の姿が見えた。 やれやれと、翡翠は小さくため息した。愛しげな眼差しを花梨に向け、そっと近寄った。「風邪をひいてしまうよ……愛しい人。」 耳元で囁くと、優しい光を帯びた瞳がうっすらと開いた。周りを見回して驚いていたが、翡翠の顔を認めるとその顔は一瞬で喜びに輝き、胸元に飛び込んできた。「……どうしたの。」「夢を……見てた。夢の中でも翡翠さんと一緒だった……」 可愛くてたまらないと、翡翠は花梨を両腕にかき抱いた。手放すことなど思いも寄らない掌中の宝。冷え切ったその体を温めようと、固く固く抱きしめた。腕の中で花梨がほうっと大きな息を吐いた。唇を求めた。花梨の吐息をすべて我が物にしようとでも言うような長い長い口づけ。二人を包む空気が、甘く溶ける。(チョコより甘い……) 夢うつつの中で花梨は自分が翡翠に溶かされていくのを感じた。「おいで……」 抱えられ、姫抱きに持ち上げられるから、まだ実体があると感じる。柔らかい茵が花梨の体を支える。翡翠が花梨に被さった。安らかな温もりが花梨を包んだ。「あ……」 唇から漏れる甘い吐息に、翡翠が満足げに微笑んだ。 二人きりの夜が始まる……。
2010年02月13日
コメント(0)
-
【道臣×千尋】 中つ国のクリスマス
風早の教育のよさなのか、千尋が疑うことを知らないのか。 千尋は未だに、サンタクロースの存在を信じていた。 クリスマスイブの夜、良い子で早くやすんだ子には、サンタクロースがプレゼントを持ってくる。「……まったく、千尋は単純なんだから。」 とっくの昔に葦原家のサンタの正体を見抜いている那岐が、ふふんと鼻先で笑う。「千尋が幸せな証拠ですね。」 風早が微笑む。 そして今年も、千尋はサンタクロースの訪れを待っていた。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 千尋の唇から漏れる歌声が、道臣の耳をとらえた。(知らない歌だ……。) 中つ国の楽とも異なる、しかし、心が浮き立つその調べ。千尋を介して聴く遠夜の歌とも異なるようだ。しかも、それを口ずさむ千尋はとても幸せそうで、道臣の心も一緒に浮き立ってくる。 声をかけようかどうかためらっていると、千尋と目があった。「道臣さん。」 楽しそうな歌声が止んで、笑顔が道臣の目の前にあった。「楽しそうですね、姫。今のは何の歌ですか?」「やだ、聞こえちゃったんだ。」 照れて赤くなる千尋を、道臣は心から愛おしいと思った。さっきの笑顔をもっと見たいと思った。「教えていただけませんか? もし、よろしければ。」「うん、いいよ。」 千尋が口ずさむ調べについて歌う。目と目が合う。心がほっこりと温かくなる。 もっと一緒にいたい欲がわく。道臣がそれを押さえなくなって久しい。共にいることが千尋の心に適うことと知ったから。 懐から笛を取り出して覚えた調べを奏でた。千尋が更に嬉しそうな顔をした。道臣が奏で、千尋が歌う。「おや、楽しそうですね。」 聞きつけた風早が竪琴を持ち出した。「ねえ風早。鳥船にもサンタさん来るかな。」 ひとしきり3人で楽しんだ後、千尋が聞いた。「来ますよ。千尋がいい子にしていたらね。」 千尋が見せたとびきりの笑顔を、道臣は見逃さなかった。しかし、サンタとはいったい何なのだ。来ると言うからには、人なのだろうか。「風早、鳥船に客人なのですか? サンタさんというのは……」 千尋がぷっと吹き出して、しかし、すぐに、しまったと顔を改めた。「ごめんね、道臣さん。知らないよね。」「中つ国の風習ではありませんからね。千尋のいたあの世界の催しですから。」「催し事なのですか。」「ええ、クリスマスという、ね。」 サンタというのは夜中に訪ねてくるのだと聞いて、道臣は眉をひそめた。(妖の類ではあるまいな。) 千尋のいた世界では、安全なものだったかもしれない。風早が千尋に近づけるのだから、きっとそうだったのだろう。しかし、もしそれが、荒魂に変わっていたらどうするのだろう。風早は脳天気に笑っているが、そういう危険がないとは言い切れまい。 道臣はその夜、千尋の部屋の前で寝ずの番をすることに決めた。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 深夜。(そろそろ、サンタとやらが現れる刻限のはずだ。) 道臣の視界の端に、赤と白の見慣れない衣服を身に纏い、白ひげを長く伸ばした老爺が入ってきた。「何者だ!」 誰何した道臣を、老爺は指を立てて制した。「何者であろうと、姫の部屋に立ち入ることは許されない。早々に立ち去りなさい。」 言いながら道臣は老爺に近づいていった。やけに背が高い……金色の瞳……?「あなたは……!」「俺です。どうか千尋には内緒にしてください。夢を、守ってやりたいんです。」「しかし……!」 心にむくむくとわき上がる黒い感情。それが嫉妬と気付くのに時間はかからなかった。道臣はうらやましかった。当たり前の顔をしてあっさりと深夜の千尋を訪ねられる風早が憎かった。従者としての立場からそれは当然のことだったが、道臣が今、心から欲しかったのは、その、いつでも自由に姫の側にいられる権利だった。 風早の金色の瞳が、道臣をじっと見た。心を見透かされているようで、道臣は少しひるんだ。嫉妬などという武人にあるまじき感情を抱いている自分を恥じた。「……代わりたい、ですか?」 道臣は首を振った。風早がにっこりと微笑んだ。「代わってください。その方が千尋はきっと嬉しいでしょうから。」 風早は赤白の衣服を脱ぎ、道臣に差し出した。「どうしてですか?」「わかるんですよ。千尋のことは何もかも、ね。」 寂しげな微笑み。道臣は断らなかった。赤白の衣服を身に纏った。風早が差し出す贈り物を預かった。「……内緒にしてくださいね。」 道臣はうなずいた。千尋の部屋の扉を、音がしないようにそっと開けた。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 穏やかな寝息に、道臣の心は高鳴った。 心臓の音が聞こえて、千尋が起きてしまわないかとドキドキしながら、道臣は千尋の臥所に近寄った。 目覚めさせないようにそっと、枕元に贈り物を置く。千尋がほしがっていた、温かい毛の上着だった。ふわふわとした長い毛足が千尋の頬をかすめて、眠っているはずの千尋が顔を顰めた。道臣ははっとして、上着を手に取り、枕元ではなく、千尋の横たわる体にかけた。(この方が温かいですね、姫……) よほどぐっすり眠っているのだろう。千尋は目を覚まさなかった。寝顔を、道臣はじっと見つめた。長い睫毛が愛らしい。ふっくらと柔らかな唇が……悩ましい。 道臣は自分を押さえられなかった。 眠り姫の眠りを妨げないように、そっと……唇に指先を触れた。 そしてその指を、静かに自分の唇に触れた。 道臣は静かに臥所から離れた。それ以上は、道臣の武人が許さなかった。(姫が目を覚ましたら……) 外はしんしんと雪が降り始めていた。見渡す限り広がる雪野原に、この上着を纏った姫を連れて馬を駆ろう。誰もいない遠いところまで出かけて、そして……。 体の芯が熱くなり、あらぬ情熱があふれそうになるのを感じて、道臣はあわてて姫の部屋を後にした。
2009年12月26日
コメント(0)
-
【アシュ千】 発熱 その3(終)
アシュヴィンは千尋の部屋のドアを勢いよく開けた。「騒がしいですね。」 一番見たくも聞きたくもない姿と声がアシュヴィンをとがめた。アシュヴィンはかまわず、千尋の枕元へ行った。 千尋は目におびえたような色を浮かべたが、すぐにつんと目をそらした。「私の従者だから、私のいいようにする。」 アシュヴィンの顔にさっと怒りの色が上った。「そういうわけにはいかないな。」「どうして!」「根宮の秩序が乱れる。」「じゃあ、幽宮へ行くわ。」「そういう問題じゃない!」 ふふと余裕の笑い声が聞こえるから、アシュヴィンのいらいらはますます増大する。「すぐに下がらせろ。」「いやよ。」「お前の世話は釆女たちがする。」「風早じゃないとできないこともあるのよ。」「ふうん、例えば?」「……」「こういうことですよね、千尋。」 風早が千尋の手を取り、自分の頬に押し当てた。開いた片手で千尋の額に触れ、熱を計った。「千尋が一番欲しかったのは、遠夜の薬でも釆女の差し出す滋養のある食事でもない。愛情ですよ、アシュヴィン。」「そんなことはわかっている。」「わかっているなら、どうして側にいてあげなかったんです? そうすれば、千尋が俺を喚ぶこともなかったでしょうに。」 風早のすることはいちいち気に障るが、もっともだから仕方がない。釆女の懇願を冷たく退けている己の姿が瞼に浮かんだ。あの時すぐに出向いていればと、悔やまれた。「言ったはずですよ。千尋を泣かせたら承知しないと。」 風早の言葉は容赦ない。本気の怒りを感じる。逆らいがたい怒り。鎮めなければこちらの身が危ないと思えるほどの。「……風早、やめて。」 千尋が止めた。「どうして止めるんです? 千尋。」「いいの。もういいんだから、やめて。」「千尋が言うなら、やめますよ。でも、それなら……」 風早はそっと千尋の髪をすくい上げ、頭の後ろに手を当ててそっと抱きしめた。「千尋は選ばなくては。こうして俺の腕の中にいるか、アシュヴィンの手を取るか。」「……!?」 これで千尋がアシュヴィンの手を取るなら、風早はもう二度と人界へは降りて来られないのだった。それが白龍との誓約だった。千尋の声に矢も楯もたまらず降りていこうとする白麒麟が交わした。誰にも告げることはできないが。 千尋は迷った。どちらも千尋には大事だった。そして、風早とはもう二度と会えない予感がした。しかし、アシュヴィンは……。 中つ国の未来。それは千尋の未来。アシュヴィンと歩く未来は、中つ国の平穏へと続いている……。 千尋は知っていた。アシュヴィンが、千尋の熱にとても戸惑ったことを。どうしていいかわからないとき、アシュヴィンはことさらにいつも通りに振る舞おうとする。アシュヴィンが自分を愛しているのを千尋は心の底から感じていた。おそらく、自分がいなくなったら生きていけないほどに深く、愛されていることを。 千尋はそっと、風早の胸から頬を離した。静かに身を起こし、アシュヴィンの方へ手を伸ばした。アシュヴィンはもう意地を張らなかった。差し出された手を取り、引き寄せ、堅く抱きしめた。「すまなかった……」 風早が寂しそうに笑ったようだった。そしてあたりはまばゆい黄金の光に包まれ…… 夜明け。 千尋の苦しげな息づかいがアシュヴィンの眠りを妨げた。(どうしたんだ……) 触れてみると、火のように熱かった。(奥方?) アシュヴィンはそっと体を起こした。天蓋の帳を少しだけ持ち上げ、呼び鈴を鳴らした。すぐに近寄ってきた釆女に遠夜を呼ぶよう言いつけた。「それからリブに、今日の執務はお前が代わりにやれと伝えろ。」 アシュヴィンはそれだけ言うと帳を下ろし、熱い千尋の体をそっと抱きかかえた。(俺が、治してやる……) こんな千尋を置いて出かけても、きっと仕事など手につかない。中つ国との戦も終わり、禍日神が去った常世には恵も戻って、あとは辺境の小うるさい連中を黙らせるだけだ。そんな仕事はわざわざアシュヴィンが手を下さずとも、リブやシャニ、ナーサティヤが取り仕切る。平和な世で、皇がすべき仕事は少ない。皇の最も大切な仕事は、皇妃の幸せを守ること。 アシュヴィンは燃える千尋の唇に口づけた。病など、全部己の身に吸い込んでしまおうと思っていた。
2009年12月02日
コメント(2)
-
【アシュ千】 発熱 その2
しかし、千尋の部屋に戻ったアシュヴィンは、部屋に入ることができなかった。 そこには風早がいて、遠夜と一緒にあれこれと千尋の世話を焼いていた。「どうしてお前がここにいる。」「俺は千尋の従者です。千尋が呼べばどこにでも来ますよ。」 千尋は眠っていますから静かにしてくださいと、風早はアシュヴィンの鼻先で部屋の扉を閉めた。あまりのことに、アシュヴィンは二の句を継げなかった。禍日神との戦いを終えた後、すべてを見届けた風早は、中つ国に戻ったはずだった。千尋は風早から離れがたかったようだったが、常世の皇妃たる者が身近に男の従者を、しかも常世の国の者でない者を側近く置くというのは問題多く、千尋は泣く泣く、風早を手放して中つ国に帰らせたのだった……いや、帰らせたはずだった。(どういうことだ?) すごすごと戻るのも腹立たしかったが、具合の悪い千尋の枕元で争い事を起こすのも本意ではなく、アシュヴィンはいらだちにまかせて足音高く執務室へ帰った。が、怒りに目がくらんで執務に戻るどころではない。「リブ!」「御前に。」「后の部屋にあいつがいる。后の従者はすべて中つ国に帰したはずなのに、あれは何だ。」「は?」 リブは面食らった。アシュヴィンが「あいつ」と呼ぶ千尋の従者は風早しか思いつかず、そして、風早が、柊や忍人といった常世の面々と共に黄泉比良坂を越えていくのを、確かにリブは見送っていたから。「遠夜は何をしているんだ。巫医の力が及ばぬ病などなかろう。遠夜の力で不足ならエイカを呼べ。すぐにだ!」 珍しく感情的なアシュヴィンの指示に従うべく、リブは執務室を出た。まずはアシュヴィンの見たものを確かめなくてはならない。いくら元従者であり、友好国の人間とはいえ、無断で入ってきているのはゆゆしいことだ。 千尋の部屋のドアをノックした。ややあって、ドアを開けに来たのは遠夜だった。「二ノ姫様は?」 遠夜は無言でドアを閉めようとした。リブは食い下がった。「や、殿下がお怒りなのです。二ノ姫様のお部屋に、無断で入った者がいると。」 遠夜の顔が困った表情になった。中に入って確かめたいところだが、例えアシュヴィンの腹心とはいえ、無断で踏み込むことはリブにもできなかった。双方困り果てて立ちつくしていると、釆女が千尋の意思を伝えに来た。「リブ殿に中へお入りいただきたいとのことです。」 リブは中に入った。中には確かに、アシュヴィンの言ったとおり風早がいて、忙しそうに立ち働いていた。リブは目を疑いながらも、千尋の側へ寄った。千尋は目を覚ましていた。リブが体調を尋ねると、遠夜の薬のおかげでずいぶんよくなったと微笑んだ。 リブは、聞かなくてはならないと思った。それが、アシュヴィンの意思だから。「や、二ノ姫様、彼はどうして……」「わからない。目が覚めたら、いたの。」 代わりに風早が返事をした。「千尋が、喚んだんですよ。」「え? 私、呼んでないよ。」「ひどいですね。確かに俺の耳にはあなたが喚ぶ声が聞こえたのに。」 あなたが喚べばどこへでも来ますよと、風早は笑ってさらりと言った。(神子は、喚んだ。風早を喚んだ。) 遠夜が言った。千尋にしか聞こえなかったが、千尋が驚いて遠夜を見上げるので、皆にもそれとわかった。(神子がアシュヴィンを呼んだ。釆女が呼びに行ったが、アシュヴィンは来なかった。神子は泣きながら眠った。眠りに落ちる間際に、風早と喚んだ。)「私……。」「ね、だから言ったでしょう? あなたが俺を喚んだと。」 ややこしいことになったとリブは頭を抱えた。すべては、アシュヴィンがいらぬ意地を張ったからだ。最初から素直に出かけていればいいものを、それのおかげで二ノ姫様を怒らせ、この方を、喚ばせてしまった。おそらく、今回は素直に帰るまい。他ならぬ二ノ姫が、彼を喚んだのだから。 風早は嬉しそうに千尋の世話を焼いている。多少困惑ぎみながらも、千尋も嬉しそうだ。帰れとはきっと……言わないだろう。アシュヴィンが千尋の心をほぐさない限り。 リブは重い足取りで執務室へ帰った。アシュヴィンの鋭い視線がリブを迎えた。「いただろう。」「はい。」「理由は? どこから侵入した?」「や、それは……」 下手なことを言うと千尋の立場が悪くなる。リブは言葉に詰まった。「お前も思ったほど役にたたんな。丸め込まれでもしたか。」 アシュヴィンは冷たく笑った。千尋の容態を尋ねた。リブが「よくおなりです」と報告すると、アシュヴィンは席を立った。「殿下、どちらへ……」 リブはおそるおそる聞いてみた。「決まっている。」 ドアを開けたアシュヴィンの足取りは、まっすぐ後宮へ向かう。リブは、何事もないようにと祈るばかりだった。
2009年12月01日
コメント(0)
-
【アシュ千】 発熱 その1
夜明け。 千尋の苦しげな息づかいがアシュヴィンの眠りを妨げた。(どうしたんだ……) 触れてみると、火のように熱かった。(奥方?) アシュヴィンはどうしていいかわからなかった。いつもなら起きる時間だった。アシュヴィンはとりあえず、いつものように起きあがった。「う…ん……」 千尋が目を覚ました。アシュヴィンの顔に、一瞬安堵の色が浮かび、ついで心配そうな色になり、しかしそれはすぐに消えた。 大儀そうながらも、千尋の顔が不満の色に変わった。「起きちゃうの?」「なぜ聞く。執務の時間だ。休めるか。」「だって、私……」「遠夜を呼んでおく。それでいいだろう。」 天蓋をめくっていつも通り外へ出ていった。衣服を着る音、佩剣を身につける音、いつも通りの朝の音が一通り聞こえた後、扉が開いて、カツンカツンと響く長靴の音が遠ざかる。 千尋は納得いかなかった。アシュヴィンが千尋の体調に気付いているのは明らかだったのに、どうしていつも通りに振る舞えるのだろう。(風早だったら……) 大げさに思えるほどにも手を尽くしてくれるだろうに。少しでも目を離すと千尋が黄泉の国の住人になってしまうとでも思っているみたいに。遠夜を呼んで、それで、終わり……? 千尋は目の奥が痛くなった。じわりとあふれる物を我慢はしなかった。(神子、泣いているのか?) いつの間にか遠夜が来ていた。千尋の額に手を当てた。(大丈夫、すぐに良くなる。) 持参した薬草から症状に合う物を選び、煎じて千尋に飲ませた。しばらくするとじんわりと汗ばんできて、千尋の気持ちも落ち着いてきた。(アシュヴィンのことは気にしない方がいい。) 千尋はうなずいた。優しく握る遠夜の手に癒されて、千尋は眠りに落ちていった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ わざと足音高く寝室を後にしたものの、アシュヴィンの心が平静であるわけがなかった。 平気な顔をしていつも通り執務しているように見せかけてはいたが、隠しきれない不安は不機嫌という形を取って表面に現れる。 一番被害を被っていたのは、リブだった。「リブ、茶だ。」「は、ただいま。」 何がアシュヴィンを不安定にしているのかリブには見当がつかなかったが、不安を落ち着ける茶をしきりに淹れては勧めていた。(もうこれで10杯目のお茶です。殿下に何があったのでしょう?) 何も言わないのは以前からのことだ。何も手に着かないのを無理に隠しているのを、リブは見抜いていた。 そこへ、千尋付きの釆女が足早にやってきた。アシュヴィンの顔色がさっと変わった。(ははん、お后様、ですか。) またケンカでもなさったのだろうかと思ったが、そんなことで釆女が来たことはない。(お加減が悪くなられた……) リブの顔色も少なからず曇った。釆女の報告する声は小声でよく聞き取れないが、なにやらアシュヴィンに懇願する風だった。アシュヴィンの表情は動じることがない。釆女もついに根負けして、前を下がった。見かねてリブは口を開いた。「殿下、おそばについて差し上げてくださいませんか。」「何のことだ。」「二ノ姫様の……お后様のお加減が悪いのでしょう?」「余計なことを。お前には関係ない。」 関係ないことはないでしょうという言葉をリブは飲み込んだ。言葉とは裏腹に、アシュヴィンの心が平静でないのがわかったから。「寝ている者のそばにいたところで意味がないだろう。」 執務机から一歩も立ち上がることなく、アシュヴィンは書類に目を通し、署名し、部下を呼びつけて指示を続ける。しかし、幾枚かそれを続けた後、アシュヴィンは急に立ち上がり、ドアへ向かった。「殿下、どちらへ。」「用足しだ。」 リブは丁重に見送り、そしてそっと微笑んだ。長靴の足音は明らかに休憩室の反対側……後宮の方へ向かっている。(まったく、もう少し素直になられればよいものを。) リブは、執務机の上の書類を片づけた。控えていた部下に、詰所へ戻るように言った。おそらく、アシュヴィンは戻らない。明日の朝……もしかすると、千尋の容態が安定するまで。
2009年11月30日
コメント(2)
-
祝10万アクセス御礼申し上げます。
ありがとうございます。先日、めでたく10万アクセスを記録いたしました。これも、ひとえにみなさまが足を運んでくださるおかげ。私のつたない二次創作を読んでくださってありがとうございます。お礼のしるしに、CP人気投票など。@nifty 投票:楽天ブログ10万アクセス記念。あなたが読みたいはどのCP?よろしければ、クリック、してやってくださいませ~。見事1位に輝いたCPのお話を、喜んで書かせていただきます。
2009年11月27日
コメント(2)
-
【景望】 浮夢 その3(終)
数日後。「ちょっと……一緒に来てくれないかな。」 いつになく真剣な顔の景時の顔に、望美は多少たじろぎながらもついていった。 いつも通りつないでくれる手も、どこかぎこちなさを感じるのはどうしたわけだろう。 景時は何も言わず、どんどんと歩いていく。いつもなら休んでいこうと誘う喫茶店も通り過ぎ、鳩に餌をやっていく鶴岡八幡宮の前さえ通り過ぎた。夕闇迫る中、絶えることない観光客の人並みもなく、街が静かに夜の時を迎えようとしている時間。(どこへ行くんだろう……) 細道を急に曲がった。(ここの突き当たりは……) 大蔵御所の跡地の向こうの……頼朝墓。景時は、正面の階段をものもいわず上っていった。「望美ちゃん。」 静かに手を合わせ、望美の荒い息が収まった頃、景時はようやく口を開いた。「オレの話、聞いてくれるかな。」 望美の心はひやりとした。あのときのことは忘れていない。荼吉尼天を倒して、いよいよ元の世界へ帰るというその日、二人で来た……。 景時の腕が伸び、そっと望美の肩を抱いた。突然の事に、望美は大きく目を見開いたまま固まった。「ごめんね……ここでなら言える……いや、きっとここでしか言えないんだ。もしも、君の気持ちがあのときと変わっていないなら……」 望美は見開いた目で景時を見上げた。あのときとは全く違う、穏やかな、でも少し緊張した面もちがそこにあった。「オレと……結婚してくれるかな。」「景時さん!」 変わってなどいない。変わっているはずがない。この日を待ち焦がれていた。 望美は景時を抱き返した。思い切り力を込めて抱きしめた。「私の気持ちが……変わるはず、ないじゃないですか……!」「望美ちゃん……。」 折れるかと思うほどに抱き返されて、望美は息が止まるかと思った。甘い陶酔。景時の唇が望美の唇を探す。望美は自分から景時の唇を迎えに行った。思う様舌を絡ませて、愛を……伝える。この時を、待っていたと。 いつの間に? 左の薬指に、指輪が光っていた。景時の鎖骨の間で光っていたのと同じ色の。 いぶかしげに見つめる望美に、景時が言った。「気に入らない?」「ううん……でも、これ……?」「ええと、こっちの世界ではこうするんじゃないの? こういうとき。」「こういうときって……ええ!?」「え? 違うの? 確か、この間、『てれび』で……」「違わない、違わないけど、景時さん、これ……」「うん。オレの気持ち。幻術じゃないよ。もらいものだけど、さ。」 譲を手伝って蔵を片づけていたときに見つけたのだ。祖母のものだと譲は言った。きっと、例の夢見で予感していたのだろう、「景時さんに必要な物だろうと思うから取っておいてください。」と言った。「その方が祖母も喜びます。」と付け加えて。「スミレおばあちゃんの……。」 景時と縁をつないでくれた、星の姫。 指輪をじっと見つめる望美の肩を、景時が抱いた。暗くなった道を、二人並んで歩いた。吹く風は冷たいのに、全然気にならないほど暖かい。二人、一緒。幸せだから。 春日の家の前で別れるとき、もう一度、キスした。離れがたいと思ったけれど、望美は自分から体を離した。薬指の指輪は、もうすぐ景時といつも一緒にいられる約束の印。我慢しようと思った。これから歩む道を、汚すことのないように。「じゃあ、また。」「うん!」 明るく手を振って別れた。有川家の玄関へ向かうかと思いきや、景時の足はそのまま春日家の裏庭へ向かった。有川家の離れへの近道だ。望美はまるで景時が自分の家の敷地の中に住んでいるような錯覚に陥った。(もう、景時さんたら。) 遠くない。遠くない。それはまるで、同じ家の別の部屋にいるのと同じ。 望美は元気よく玄関の扉を開けた。「お母さん、見て!」 景時さんからもらったのと、指輪を見せた。晩酌していた春日の父が寂しそうに笑った。
2009年11月26日
コメント(0)
-
【景望】 浮夢 その2
「熱、下がったみたいだね……」 景時は独り言を言った。 眠る望美の呼吸は穏やかで、眉間に寄っていたしわも消えていた。 景時は布団の中に手を入れ、そっと望美の手のひらを探った。 ぼうっと熱を帯びていた手も、今はすっかりいつもの温度に戻って、かすかに汗ばんでいる様子だった。 景時はその手をそっと引き出し、熱い湯でしぼったタオルで拭いた。さらりとした感触に戻ったその手に、愛しそうに頬を寄せた。(望美ちゃん……) 昨夜何度もメールしたのに、具合が悪いなんて一言も言わなかったのはどうしたわけだい? こんなときくらい、オレを頼って欲しいなあ。こんなことくらいしかしてあげられないんだから。 でも…… 二人で交わした約束を思い出して、景時は心が痛んだ。 望美に遠慮させてしまったのに違いない。(いつも、君は気にしてたんだもんね。) 迷惑をかけちゃいけない、心配させちゃいけない、いつも、オレが気持ちよく過ごせるように……君の願いを、オレはいつも退けていた。君は本当は、もっとオレの近くにいたかったはずなのに。(ごめん……) 熱い物が望美の手にしたたり落ちた。景時は大急ぎでタオルで拭った。知られてはいけない。また、望美に気遣わせてしまう。「いいよ、景時さん……」 望美の声に景時は飛び上がった。静かに見つめる望美の瞳と視線がぶつかった。「え? ええと、何がいいのかな? 望美ちゃん。」「……。」 望美は何も言わずに、じっと景時を見つめている。「どこか、痛い?」 望美は首を振った。「もう、いいよ……」「だから、何がいいの。」「うつっちゃうから……」 景時の顔が泣き笑いにゆがんだ。「うつるなら、とっくにうつってるよ。だから君は心配しないで。」 今度は望美の顔が泣き笑いになる番だった。望美が伸ばした腕を、景時が引き寄せてぐいと抱きしめた。「君の風邪なんか、オレが全部引き受けちゃうからね。」 熱いキス。本当に、風邪を全部吸い込んでしまおうかというほどの。 唇を離した後、幸せそうにくったりと身を預ける望美の重さに、景時は悟った。 時が来たのだ、と。 望美が落ち着いたのを見届けて階段を下りてきた景時に、春日の母は深々と頭を下げた。「望美を……お願いします。」 景時の方が面食らった。それは、景時の方こそ言うべきせりふだったから。「オ、オレの方こそ……こんなオレでよかったら。」 春日の母は静かに微笑んだ。有川家の遠縁であるということ以外、何もわからない男だった。しかし、望美が景時に全幅の信頼を置いていることを、春日の母は知っていた。有川家の兄弟も、景時には一目置いているように見えた。誠実で、約束したことは必ず果たす。信じていいと思った。この人はきっと、望美を幸せにする。 景時は春日の母に深く礼を返した。「きっと、幸せにします。」 春日の母はうなずいた。景時は静かに春日家を後にした。
2009年11月25日
コメント(0)
-
【景望】 浮夢 その1
(どうして……?) 人の気配にだるい目を開けたとき、そこに景時の姿を見つけて、望美は不思議に思った。(ここ、私の部屋だよね……) 暗くなったら逢わない約束と一緒に、互いの部屋も訪ねない約束をしていた。逢うときは必ず外、と。それは激情に流されないための予防線。 しかし今、確かに景時がそこにいて、温かい大きな手で自分の額を包んでいる。ドキドキと高鳴るはずの胸も今は熱に侵されてそんな余裕もないらしい。(ま、いいか……) どうして?と尋ねる気力もない。だるくてたまらない。景時がそばにいてくれるなら、いっそ心強い……。 目が合った瞬間、景時の口が何か言いそうに動いたけれど、望美のだるそうな瞳の色に言葉を飲み込んだらしかった。大丈夫だよと優しく微笑んで、そっと髪を撫でた。望美は静かに目を閉じた。額が心地よくひんやりしたのは、景時が冷たいタオルでも乗せてくれたのか……◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 望美が病んでいることを景時に教えたのは譲だった。 景時は意外に思った。少し意地悪かと思ったが、聞いてみたくなった。「ねえ、オレになんて教えていいの? 君の大事な先輩でしょう?」「先輩にとって一番大事なのは景時さんですから。」 先輩の幸せが、俺の幸せなんです。それは、景時さんも同じでしょう? ほら、早く行ってあげてください、先輩が今一番会いたいのは景時さんでしょうから。(譲くん……) 心のどこかがちりりと痛んだ。譲の想いがどれほどのものか知らない景時ではなかった。思えば、望美が景時を選んだときから、譲の痛みは続いていたのだ。譲の大切な物を、取ってしまった……。「ごめん、譲くん。」「どうして謝るんです?」「オレは、君を傷つけて……」「何言ってるんですか。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。いつまでもぐずぐずしてるんなら、俺、怒りますよ。」「でも……」「いい加減にしてください。くだらない約束なんかして。こんな時はそんなもの反古にすればいいんです。春日のおばさんに頼まれたんですよ。先輩が景時さんを呼ぶからって。」 景時の顔色が変わった。「うわごと……?」「そうだと思います。だいぶ、熱、高いみたいですよ。」 景時はダッシュで春日家の玄関へ向かった。出迎えた春日の母は、すぐさま景時を望美の部屋へ案内した。「看病してあげてくれるかしら。あなたにそばにいて欲しいみたいなの。」 景時は力強くうなずいた。得意の軽口も出なかった。それほどに春日の母の顔は深刻で、望美の具合は悪かったのだ。
2009年11月24日
コメント(0)
-
【風早と千尋のお話】 インフルエンザ 風早編
千尋が治るのを見届けて安心したように、風早が熱を出した。 ちょうど千尋がインフルエンザにかかった頃、クラスでも何人か同じように倒れていて、蔓延を心配した学校はしばらく休校を決定したところだったから、千尋は風早の看病に専念することにした。「すみませんね。」「謝っちゃいやだ。私がうつしたんだから。」 赤い顔で、すまなそうに微笑む風早に、千尋は言った。自分が拾ってこなければ、風早がかかることはなかったと思っていた。学校でも流行っていたけれど、風早は自分の発症と同時に休暇を取って一緒に居てくれたのだから。(夜もずっと一緒だったし……) 毎晩添い寝してもらったと、千尋の顔も風早に負けないくらい赤くなった。風早がそれを見とがめた。「どうしたんです? 顔が赤いですよ。」「な、なんでもないよ!」「心配だな、また熱が出てきたんじゃないですか?」「大丈夫、そんなんじゃない。風早は休んでて!」 千尋は、がんばるぞとばかりにエプロンをつけた。風早ができない分、自分が全部すると思っていた。 洗濯から掃除から、家事の一切をやってのける千尋を、風早は半分熱に浮かされながらも微笑んで眺めていた。(大きくなりましたね。) こちらの時空に飛ばされたときは、風早自身もなじむのに大変だったけれど、千尋はもっと大変だったようだ。何もかも、風早が世話をするのが習慣だった中つ国と、何でも自分でするのが当たり前のこの時空ではあまりにも違いすぎて、千尋には戸惑うことばかりだった。服を着ること、髪を編むこと、一つずつ、手を取って教えた。千尋は賢いからすぐに覚えて、学校にも通い始め、少しずつ笑顔が戻ってきた。でも、例えば赤い夕焼けを見ただけで、すぐに涙を流すほど心は不安定で、しかし、記憶は常世の皇子の術で封じられているから千尋には理由がわからなくて、思い出す必要を感じなかった風早は記憶の封印が解けないよう細心の注意を払いながら千尋を落ち着かせ、抱きしめ……。 すっかり独り立ちしてしまいそうな勢いの千尋を見て、風早は嬉しかった。 湯気の立つ何かを、千尋が運んできた。「ご飯、ちゃんと食べないと。」「作ってきてくれたんですか。」「当たり前でしょ。」 インスタントスープにご飯を入れてことことと炊いてきたらしい。アツアツのそれを、風早がスプーンで掬い取ろうとしたら、千尋の手が止めた。「震えてる。こぼしちゃうよ。」 千尋がスプーンを取り、スープ粥を少し掬って、ふうっとさました。あーんしてと風早に口を開けさせ、一口ずつ、一口ずつ、食べさせた。「何だか嬉しいですね。不思議な気分だ。」 急に目が合ったから、千尋はすいと目を逸らした。風早の手が伸び、千尋の顔を包んだ。吐息が近づき、唇に触れる……と思ったら、すっと遠のいた。「うつしてしまいますね。」 風早はそっと目を閉じた。食後に飲んだ薬が効いてきたのだろう。すぐに聞こえてきた規則的な寝息に、千尋は静かに部屋を出た。今のはどういう意味だろうと測りかねてドキドキする胸を押さえながら。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ カレンダーは、11月11日を示している。(お誕生日だ。) 肝心の本人が発熱している今、いったい何ができるだろう。 風早がぐっすりと眠っているのを確かめて、千尋はエプロンを取った。買い物かごを持ち、外へ出ようとした。「出かけるの?」 うっそりと起きてきた那岐が聞いた。「うん、今日は風早の誕生日だから。」「でも、あいつ、寝込んでんだろ?」「どうして知ってるの。今起きてきたばかりなのに。」「眠りこけてたわけじゃないからね。」 あんなキンキンした声で「熱!」とか叫ばれたら、僕ならがまんできないねと言うから、千尋の顔が険しくなった。「それに、ガーガーと大きな音で洗濯機回したり、傍若無人な掃除機の音とか……せっかくの休みが台無しだ。」「だって、仕方ないでしょ? しなくちゃいけないんだもん!」「そうかもしれないけどさ。」「もう、那岐のわからず屋!」「どこが。」「全部!」「う……ん……」とうなるような声が奥から聞こえたから、千尋は肩をすくめて那岐を睨み付けた。「行けよ。買い物だろ?」「うん……」「見ててやるよ。」 ありがとうと手を振って千尋は表に出た。 口当たりのよさそうな、滋養のあるものを。 いつものスーパーで選んできた。本当は家にいなければいけないのかも知れないけれど、保護者たる風早が倒れてしまったのだから仕方がない。同級生にも何人か会った。「風早先生、大丈夫?」「うん、今寝てるよ。」 答えると、同様に、少し眩しいような照れくさいような不思議な顔を見せる。その表情はすぐに消えるが、千尋は少し面はゆかった。家族なのはみんなが知っているのだから、何も恥ずかしがることはないのだが。「大変だね、千尋も。」「うん、でも、いつものお返しだから。」「がんばって。」 リゾット用のインスタントスープを、味に飽きが来ないように幾つか選び、フルーツコーナーへ行った。風邪にはビタミンCをと、どこかでしきりに言っているのを思い出したから。(りんごの皮、上手に剥けるのを見せたら、風早、びっくりするかな。) いつも作ってくれたウサギりんごを、目の前で作ってあげよう。りんごをすり下ろしたジュースもよさそうだ。 旬を迎えたりんごは、甘い匂いを売り場中に漂わせている。値も手頃だったから、風早も許してくれるだろう。 ジュースにしても大丈夫なほどりんごを入れたかごは重たかったけれど、千尋はうんと持ち上げて家まで運んだ。風早の喜ぶ顔が見たかった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 家に帰ると、風早はベッドに起きあがって本を読んでいた。「ダメじゃない、起きてちゃ。」「大丈夫ですよ、千尋のおかゆと薬ですっかりよくなりました。」「もう、那岐が見ててくれるって言ったのに。」「俺が那岐を部屋に帰したんですよ。うつるといけないし、退屈そうでしたからね。」 仕方ないなあと、千尋は買い物かごをキッチンに置きに戻った。「いい匂いですね。りんごですか?」「うん、安かったし……食べる?」「ふふ、千尋が剥いてくれるんですか?」「まかせて!」 りんごを一つ、よく洗って、フルーツナイフと一緒に持って風早の傍へ行った。 心配そうに見守っても、風早は手を出さないことにした。 りんごを二つに割り、更に小さく割っていく手元は風早が思うよりしっかりしていて、危なっかしいところは一つもないようだった。「なかなか上手ですね。」「ふふっ。」 器用に芯を取り、皮に斜めに切れ目を入れた。反対側から薄くナイフを入れ、皮を取り除いた。二つのとんがりの根元まで剥きあげ、耳がぴんと立つように持ち上げた。「おや、やりますね、千尋。」「上手になったでしょう。」 得意げに差し出すりんごを、風早は嬉しそうに受け取った。「もっと剥いてあげるね。」 得意げに二つ目に手を出したが、果汁に濡れた手が滑ったのだろう、フルーツナイフが今度はあらぬ方へ滑った。「あっ?」 千尋の顔が痛そうにゆがんだ。風早がとっさに手を出した。千尋の手からナイフを取り上げ、指を口に含んだ。 まだ熱があるのだろう、風早の口内はぼうっと熱かった。風早は千尋の傷を丹念に舐めた。血の味が薄れたのを確かめて口から出し、手元のティッシュでぎゅっと押さえた。「しばらく、押さえててください。」 少しかすれた声で言うと、ベッドから立ち上がった。ふらつきながらも居間へ行ったらしく、救急箱を取って戻ってきた。 箱の中から消毒液を取りだして、ティッシュの上から千尋の傷にたっぷり振りかけた。ティッシュごとぬぐい取り、用意したばんそうこうで傷口をしっかりふさいだ。「ごめんなさい……」「謝らなくてもいいんですよ。」「だって、風早、具合が悪いのに。」「平気ですよ、これくらい。」「だめなの! 今日は風早の誕生日だから!」 風早は少し驚いた目で千尋を見た。「祝ってくれるんですか?」「当然じゃない。」 当然ですかと、風早は苦笑する思いだった。必要上、方便で決めた誕生日だったのに。 風早は千尋の肩に手を回した。静かに抱きしめた。「ありがとう……」 自分がここにいることを喜んでくれる千尋。千尋こそが、自分が存在する意味。風早は、白龍の意志などすっかり忘れていた。記憶の片隅に追いやっていた。もう、中つ国になんか戻れなくてもいい。このまま、ずっと、こっちで……。 腕の中の千尋がもぞもぞと動いた。風早はそっと腕を解いた。見上げる瞳は少し戸惑いの色を浮かべて、風早の瞳をじっと見つめてくる。その唇に唇を触れたい衝動を、風早はじっと堪えた。代わりに、額にそっと……唇を置いた。「……休んでて。」 真っ赤な顔で命じるように言う千尋に、素直に従った。(もうしばらく、この部屋には来てもらえないかもしれませんね。) キッチンから、何かをすり下ろすしゃかしゃかという音が聞こえる。今度は何を作ってくれるのでしょうねえと、風早は目を閉じた。 瞼の裏に、遠い日の金の葦原が浮かんだ。
2009年11月11日
コメント(0)
-
【風早と千尋のお話】 インフルエンザ 後編
効き目はあらたかと言うだけあって、千尋の熱は夕方には概ね下がっていた。「治りかけが肝心ですからね、まだ寝ていなくてはいけませんよ。」 自分の布団に戻りたがる千尋を、風早は許さなかった。油断したときに何かことが起きる。あの薬が処方されている間、風早は千尋を自分の部屋へは戻さないと決めていた。もちろん、学校にも欠勤届を出した。日ごろからたっぷりと課題プリントは作り貯めてあるから、毎日一枚ずつ学生にさせてくれと言い置いて1週間。「そんなに休んで授業大丈夫なの?」「千尋が心配することではありませんよ。」 確かに、好きな範囲だと脱線してとどめをしらない風早の授業だから、1週間程度休んだからと言って支障はなさそうだが。 自分の部屋に戻らせてもらえないのには千尋は不服だった。「もう小さい子じゃないんだから。」 夜もこのままかと思うとドキドキした。さっきまではぼうっとしていて、眠れれればどこでもよかったから何も気にしなかったし気にする余裕もなかったが、気づいてしまえば、風早のほのかに煙草の薫る布団は、すっぽりと風早に抱かれてしまっているようで少々気恥ずかしい。「そうですね。でも、あの薬を飲んでるうちは、俺の目の届くところにいて欲しいんです。」 風早はそう言って注意書きを千尋に見せた。千尋は渋々諦めた。こんなことを言われれば、仕方ない。 風早は2階から千尋の布団を下ろしてきた。ベッドに敷いていた自分の布団を床に敷き直し、ベッドに千尋の布団を広げた。「これならいいでしょう?」 千尋は頷いた。風早のベッドを取ってしまったのが心苦しかったけれど。「千尋を床に寝かすわけにはいきませんからね。」 小さい頃からそうだった。いつもいつも千尋が一番、千尋が大事と。那岐が拗ねてそっぽを向くほどに。「プリン買ってきた。」 玄関の戸が開いて、那岐が帰ってきた。「わあ、プリン、食べたい!」 飛びつく千尋を、那岐が眩しそうに見た。心配したが、もう良さそうだ。 千尋のことを那岐に任せて、風早は夕食の厨房に立った。玉子をたっぷり使った雑炊を作るつもりだった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 深夜。 昼間よく眠ったせいか、千尋は寝付けなかった。「眠れませんか?」 風早の心配そうな声が聞こえた。「うん……やっぱり、自分の部屋じゃないし……」 口に出しても許してもらえそうもないことだが。 風早は起きあがった。 ベッドの端に静かに腰掛けた。 そっと千尋の額に手を当てた。「熱は下がっていますね。」 風早はそのまま体を寄せ、額に額をつけた。吐息が混ざる。千尋の心臓は大きくとくんと打ったが、押し寄せてきたのは大きな安心感だった。 布団の上から抱きしめられた。この腕の中は安心だと告げる声がする。「目を閉じて……あなたが寝入るまで、こうしていますから。」 安心感は睡魔を連れてくる。千尋の心臓が騒ぐことはなかった。幼い日から続くこの腕の中の温もりに、素直に身を委ねた。大きな欠伸は眠りへの合図。風早は、千尋を抱く腕にそっと力を込めた。 寝息が少しずつ規則的にゆるやかになっていく。寝入ったのを確かめても、風早は千尋を抱く腕を解かなかった。愛しい宝を手放すことなどない、と。 夜明け、千尋を心配した那岐は、そっと風早の部屋を覗いた。 抱き合って……いや、千尋を抱いて眠る風早の姿に、小さく舌打ちした。(ま、わかってるけどさ。) 中つ国のことを那岐は覚えていたから。この時空でも忠実な従者であり続ける風早に、那岐は複雑な思いを抱いていた。それがどういう感情なのか説明はできなかったが、風早が千尋に親密な様子を見せるたびに、心が無意味に波立つのは明らかだし、それを那岐は疎ましく感じていた。(だから、一緒に来たくないって思ったんだ……面倒だって。) 何が何だかわからないうちに、吹き飛ばされるようにこの時空に辿り着いていた。見知った顔は風早と千尋しかいなかったし、見た目の年格好から、風早ほどの年長者とは一緒にいないと奇異の目で見られるから、仕方なく一緒にいることにした。一緒に住めば余分な感情に曝される。それは、もう二度と味わいたくない悲しみを連れてくるかもしれない……。 千尋の寝息が安定しているのだけ確かめて、那岐はまた部屋に戻った。 早くこの家の、風早の「庇護」から逃れたいと思った。 明日また何か言付けを頼まれたら思い切り断ってやると、那岐は呟いて二度寝の夢に入っていった。
2009年11月10日
コメント(0)
-
【風早と千尋のお話】 インフルエンザ 前編
朝、千尋が真っ赤な顔をして起きてくるから、風早は少々慌てた。「熱を測ってください、千尋。」 手渡された体温計を、千尋は素直に脇に挟んだ。正直、階段を下りてくるのも辛かった。足元がふわふわして地に着いた気がしない。視界はぼうっと霞んで、まばたきをしようものなら瞼を引き上げるのに容易ならぬ力がいる。 体温計がピピッと鳴った。 表示された温度を見て、千尋は気が遠くなるようだった。力無い声で、朝食の準備をしている風早を呼んだ。体温計の数字を見て、風早の顔も緊張した。「やはりね。今日は学校を休んでください、千尋。」「風早は?」「俺も休みます。あなたを病院に連れて行かなければならないし……そんな体では昼食にも困るでしょう?」 食べられるならちゃんと食べて、体力をつけておかないとと、風早は台所からスープを持ってきた。「こういうものならいいでしょう?」 スープを、千尋はゆっくりと口に運んだ。風早が言うから飲んでいるけれど、さっぱり味がしない。 風早が高校に、千尋の欠席と自分の欠勤の連絡をしている声が聞こえた。那岐がぶうっとふくれて登校した。くらっとしたと思ったら、大急ぎで寄ってきた風早に抱きとめられ、ベッドに運ばれた。「俺の布団で寝ていてください。その方が目が届くから。」 うんと頷いて、千尋は目を閉じた。頭に氷枕があてがわれた。ひんやりとした心地よさに、千尋は深い眠りに落ちていった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 千尋の病はインフルエンザだった。 噂の、思春期には要注意な薬を処方されたので、風早はかなり不安だった。(俺の姫に間違いはないと思うけれど。) 飲ませれば確実に効くと評判の薬。しかし、異常な行動をとる子どももいて、目を離してくれるなと注意書きが出るような例の薬。 風早はしばし考えて、でも、やはり飲ませることにした。 キッチンの隣の自分の部屋で、つきっきりで居れば大丈夫。 朦朧とした千尋を病院から連れて帰り、鍋焼きうどんを作って食べさせた。 そして、おそるおそる、その薬を飲ませた。 食べながらもうとうととする千尋をそっと抱き上げ、寝衣に着替えさせてベッドに入れた。 穏やかな寝息が聞こえてくるのを確かめて、風早はベッド下にちゃぶ台を広げた。そこで仕事をするつもりだった。パソコンを広げ、何やら打ち始めた。時折目を上げて千尋の様子をうかがい、氷枕を確かめ、また、仕事を続けた。「ただいま。」 那岐が帰ってきた。「千尋は?」「眠ってます。」「ふん。」 預かってきたと、風早が出した課題プリントの束と千尋の友達からの見舞いの手紙をどんとテーブルに置いた。眉を顰める風早を後目にとんとんと階段を上り、ややあってまたどんどんと下りてきた。がらがらと玄関を開ける音がするから、風早は立ち上がって那岐を咎めた。「どこへ行くんです。」「どこでもいいだろ。あんただけにさせとくわけにはいかないんだ。」「何をです。」「千尋。」 ぶっきらぼうな言い方の中に、那岐の真意を読み取って、風早は矛先を引っ込めた。何か、口当たりのいいものでも探してこようと言うのだろう。帰りの荷物が予想外に増えて重かったから、一度荷物を置きに来たのに違いない。「すみませんね。」 労う言葉に、那岐は不機嫌そうな顔で応えた。ふふっと笑って風早は戸を閉めた。大急ぎで千尋の傍に戻った。 千尋は変わらず、風早の布団でぐっすり眠っている。風早はほうっと安堵の息を吐いた。
2009年11月09日
コメント(2)
-
【蛍シリーズ】 「流感」 後編
次にあかねが目を覚ましたときには、友雅が隣にいた。「目がさめたかい?」 大きな手が額を包んだ。測るように押し包むその手はひんやりと冷たくて、あかねはまた、心地よい眠りに引き込まれるような気がした。「ふん……」 大丈夫だよと撫でる手に、心から安らぐ。「友雅さんに、うつっちゃう……」「またそういう強がりを。君がくれるものなら何でもありがたくいただくよ。それがたとえ高熱を発する風邪でもね。大っぴらに休む口実もできるし……」「もう、友雅さんったら!」 あかねは軽く打つ真似をした。友雅はさっと避けて、笑いながらあかねを抱きしめた。「ふふ、そんな元気があるなら大丈夫だ。永泉様のお薬が効いたようだね。」 御室で君の祈祷をしてくださるそうだと言った。泰明からも、病平癒の護符が届いていた。それを友雅は小さくちぎって湯に溶かした。「お飲み。体の中から効くそうだ。」 紙が喉を通っていくのは余り気持ちのいいものではなかったけれど、友雅が湯に甘葛を溶かしてくれたから、薬湯よりはよほど飲みやすかった。少し汗ばんだあかねの額を、友雅は清い布で拭った。腕の中でくったりと、全てを任せきって甘えるあかねが愛しくてたまらなかった。 厨房から何やら強い匂いが漂ってきた。あかねの食欲をくすぐる香り。しかし、この時空にはおよそ似つかわしくないと思われる、懐かしい香り。「ふふ、詩紋は事を成したようだね。」 内裏から下賜された薬草の数々を見せたら、詩紋の目が輝いた。手に入らないものと思っていたと。あかねがきっと大好きな美味しい物を作るから分けてもらえないかと言うから、欲しいと言う物を全部渡してきた。その結果が、この香りというわけだ。「カレーだ……」「ほう、この香りの正体をあかねは知っているのかい?」「大好き! 詩紋くんが作ってるの?」「ああ、きっと君が好きだからと言ってね。どうだい? 食べてあげるかい?」「もちろん! ……ああ、熱が下がらないと。」「そうだね。それは詩紋も心配していた。大丈夫、いいようにしているだろう。」 内裏からの下賜品は、詩紋には極上のスパイスだった。この香ばしい香りは、炒ってカレー粉にでもしているのだろう。あかねは力が湧いてくる気がした。詩紋のカレーを食べられるなら、どうあってもこの熱を下げてみせると思った。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 薬が効いたのか、気合いが効いたのか、護符や祈祷のおかげか。 あかねの熱は2日ほどで平熱に戻った。 厨房からは約束通り、京には似合わぬエスニックな香りが漂ってきていた。「おいしい?」「うん、とっても!」 体を温める大蒜も入っていたから、詩紋は小麦の粉と合わせてルーを作って、こうしてカレーライスを食べることができたのだ。「うまいなあ。さすが詩紋だな。」 この調子でハンバーガーとか作れねえかという天真の誘いに、詩紋は大きく頷いた。スパイスはたくさんあったから、まだまだ何か作れそうだった。「あるところにはあるものなんだねえ……」 あかねが感心して呟いた。「市とか行くと結構見かけたんだけどね、やっぱり、高くて。」「そうだよね。『唐渡り』だもんね。」 友雅が珍重する「唐渡り」。難破の危険を冒して運ばれてきた輸入品は高価で、そう簡単には手に入らない。「あかね、お前、時々風邪ひけ。そうしたらまたカレーが食える。」「天真先輩、ひどいよ。そんなのあかねちゃんがかわいそうだよ。」「ばっか、冗談に決まってるだろ?」 友雅さんも食べてみる?と差し出されたカレーライスを、友雅は口に含んでみた。口一杯に広がる未知の辛みに、友雅は目を白黒させた。天真がぷっと吹きだした。「なんだいこれは。香りは良いけれど、味は……」「口に合わなかった?」「辛いね。こんな辛い物を、君は好きなのかい?」「慣れちゃえばこの辛さが美味しいんだけど……」 舌を刺す辛みは、京育ちの友雅には不慣れなものだろう。「好きにするさ。辛みは体を温めると言うからね。さぞかし温まって、風邪などどこかへ飛んでしまうだろう。」 好きなだけお上がりと、友雅はその場から去った。あかねたちが「かれえ」と呼ぶ香りが、いつまでも衣から匂うようだった。(まいったね……) 悪くはないが、好みではない。 しかも、数日は屋敷から抜けそうにない強い香りだった。 友雅は苦笑して、空薫きの香炉を取り上げた。 好みの侍従の香を、いつもより大目にくべた。 香炉から薫る煙を、友雅はじっと見つめていた。
2009年11月08日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 「流感」 前編
あかねの異変を最初に気づいたのは友雅だった。 寝む前はいつもと変わらぬほの温かい体が、目覚めたときにはぽおっと熱を帯びていた。息づかいも少し荒く、明らかにあかねは、病んでいた。「あかね……?」 額に手を当てれば火のように熱い。手を打って女房を呼び寄せた。「いかがなさいましたか。」 いつも側近くに控えている少納言の君がすぐさま駆けつけてきた。友雅が掲げた御帳台の帳から漏れる空気がただならぬことを、少納言はすぐに覚ったようだ。すぐに御格子を上げ、あかねの傍へ寄った。「お熱でございます。すぐにお薬湯と冷たい水を。」 お殿様はいかがなさいますかという問いに、文の支度をと答えた。出仕など休むつもりだった。「友雅……さん?」「起こしてしまったかい?」 苦しげに眉を寄せて目を開けたあかねを、友雅はそっと抱き寄せた。「寝ていなさい。すごい熱だよ。」「うん……」 熱で潤んだ瞳を、あかねは友雅に向けた。友雅の顔が心配げにゆがんだ。「お仕事……」「今日は君の傍にいるよ。こんな君を一人で置いてはおけない。」「ダメだよ、お仕事休んじゃ……友雅さんが休むと、中宮様にわかってしまうでしょ?」 確かにそうだと友雅も思った。大事になるのは本意ではない。しかし、あかねのことも心配で堪らなかった。 曇る友雅の頬に、あかねが手を触れた。じっとりと汗ばんだ熱い掌を、友雅はそっと外し、両手で包み込んだ。「大丈夫だから……少納言がいるから。」 言い出したらきかないあかねのこと、友雅は仕方なく起きあがった。その気配を察したか、外で控えていた少納言が帳の隙間から薬湯を差し入れてきた。あかねの背に手を添えて起きあがらせ、薬湯を口に含ませた。苦さにあかねはぎゅっと眉を顰めたが、友雅が優しく背をさするのに励まされて飲み込んだ。 ひと椀の薬湯をあかねが飲み干すのを見届けて、友雅は御帳台から出た。出仕の支度にと遠ざかる足音を、あかねは夢うつつに聞いた。 額に冷たい感触。少納言が冷やしてくれているのだろう。あかねはそのまま、また眠りに引き込まれていった。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 促されて出仕はしたものの、仕事など手につくはずがない。 幸いお召しもなかったので左近衛府に控えてはいたが、取り立てて何かすることもなければ、あかねの病状ばかりが気になるのは仕方のないことだ。「北の方の容態は」は、文を出す。「お変わりございません。」と少納言のそっけない返事。変わりないのはよいことだが、文使いが往復する間に何か変事はとまた気になって、すかさずまた文を書く。返り事に無事を確かめて安堵し、また文を……「もうご勘弁下さい、殿。」 文使いが悲鳴を上げた。さしたる距離ではないが、しきりの往復は人目に立つ。友雅は苦笑して筆を置いた。(まったく、私らしくないと人が笑う。) 龍神の神子を得てから人が変わられたと。よいのか悪いのかは未だわからぬが。「お召しでございます。」 御前へという使い。友雅は「仕方ないねえ」と腰を上げた。「神子殿が病んでおられるとは本当か、友雅。」 情報の早さに友雅は面食らった。間者でも放っておいでなのだろうか。 御簾の向こうに静かに座しておいでなのは藤壺中宮だろう。おそらく、六条の女房の誰かから土御門へ、土御門から宮中へと、女房の情報網で伝わったに違いない。朝起き抜けにくしゃみをしたら、出仕した先で「お大事に」と労られたという冗談のような話があるほどだ。「さすがでございます。隠し事などできませんね。」「いかがなのか。お悪いのか。」「安心できる者に任せておりますから。その者が『大丈夫』と太鼓判を押しております。」 御簾の向こうで小さなため息が聞こえた。少納言はいつだかあかねについて参内したことがあったから、中宮も見知っていた。「私と中宮から、見舞いの品を。そして、友雅はもう下がってよい。神子殿についていてあげなさい。」 神子殿が本復されるまで出仕は必要ないと言われて、友雅は嬉しいような照れくさいような気分だった。広盆に山と積まれた薬草を押し頂いて、友雅は御前を辞した。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 体温計などない時空で、体温など測る術はないけれど、少納言が額の布を取り替える早さで、あかねは自分の熱を測っていた。(すぐあったまっちゃうんだ……) なら、微熱どころではあるまい。神子の仕事をしていた頃、頼久の風邪がうつって一度だけ熱が出たことがあったけれど、今度はそれくらいでは済まないらしい。しかもあれは…… 思い出して、あかねは更に身内の熱が上がる気持ちだった。初めてのキス。友雅はそれを知っているからもう何も言わないけれど。(だめだめ。) かなり熱が高いのだろう、横になっていても体がふわふわする。とろとろとした眠りがあかねを包む。心地よいような……どこかに引き込まれそうで怖いような。「神子様……」 懐かしい声が耳元で聞こえる。「藤姫ちゃん、来てくれたんだ……」「ええ、神子様がお加減悪いと聞いて。」 友雅殿も間もなくお戻りですわと聞いて、あかねはふうっと力が抜けた。強がって出仕させたものの、やはり、あかねは友雅に傍に居て欲しかった。間もなく戻ってくるということは、藤姫の元から内裏へ知らせが行ったのだろう。中宮様に聞こえてしまったけれど、友雅を下がらせるためにと藤姫が考えてくれたのならそれはそれで嬉しかった。「あかねちゃん、大丈夫?」 厨から詩紋のプリンが届いた。それをお口直しにお薬湯をと少納言に言われて、あかねは渋面を作った。でも、藤姫にも見守られていてはがんばるしかない。永泉から届いたという薬湯を、あかねは顔を蹙めて飲み干した。詩紋のプリンが今までで最高に甘かった。
2009年11月07日
コメント(0)
-
身分違いと言われても (翡翠×紫姫) 終
伊予からの迎えの船は、滑るように川を下っていく。 紫姫は名残惜しげに、遠くなる京の山並みを見つめていた。「寂しいかい?」 翡翠が傍に寄り、話しかけた。「いいえ。」 紫姫は翡翠の胸に頬を寄せた。翡翠は肩に掛けていた袿を脱いで紫姫をくるみ込み、そっと抱き上げた。「寒いだろう?」「いいえ、ちっとも。こうしてくるんでいただきましたもの。翡翠殿こそ、お寒くはありませんか?」「私かい? 私は、平気だよ。あなたとこうしていられればね。」「まあ……」 昨夜、四条の屋敷から、盗むように連れ出してきた。尼君にはこっそりと事情を明かしておいた。尼君は寂しがったが、紫姫の様子をここ何年も見続けて心を痛めていたから、咎めるようなことは言わなかった。ただ、この幸薄い姫を幸せにしてくれと、それだけを何度も繰り返した。 もちろん、不幸になどするつもりはない。翡翠は腕の中の宝物を大切そうに抱いた。紫姫がくすぐったそうに身を捩った。「行こう。暖かくしてあげるよ。」 無邪気に頷く姫を抱えて、翡翠は天幕の帳を上げた。 伊予への長い旅路の始まりだった。
2009年10月22日
コメント(0)
-
身分違いと言われても (翡翠×紫姫) 陸
「本気ですか!? 四条の姫君を伊予に迎えると!?」 幸鷹が頓狂な声をあげた。信じられないことだった。「おや、そんなに不思議かね? 私と彼女の仲をまんざら知らないわけでもあるまいに。」「そのために、橘の遺産も受け継ぐことにしたと言うんですか。」「姫君一人養うのに、資産は多い方がいいからねえ。」「信じられません。あなたは貴族を嫌っていたはずだ。」「ああ、嫌いだよ。大嫌いだ。しかし、君と彼女は特別でね。」 すいと流した目で見るから、幸鷹はぽおっと赤面した。動揺を隠せないままに言葉を続けた。「と、とにかく、私は反対です。紫姫が伊予で暮らしていけるわけがない。」「おや、不自由はさせないつもりだよ。そのために気の進まない貴族の称号も引き継いだのだからね。それとも、君が紫姫に執心していたとでも?」 幸鷹の顔がますます赤くなった。「ほほう、図星のようだ。」「わ、私はそんなつもりは……!」「恋文の中には藤原宗家の若君のものもありましたと、乳母が惜しそうに言っていた。君のことかい?」「な……!」 翡翠はふふと笑って、手にした杯を置いた。「ともかく、決めたのだからね。明朝、石原の里から船出する。よければ見送りに来たまえ。」「誰がお前なんかを……!」「ふふ、その憎まれ口も懐かしいねえ。しばらく聞けないとは残念だ。彼の家司殿にはここを危急の際のよりどころと教えておいたから、よろしく頼むよ。」「……!」 憤慨きわまりない幸鷹に向かって後ろ手で手を振り、翡翠は幸鷹の屋敷を去った。 幸鷹は、翡翠の残した杯を手に取った。「勝手な……」 腹は立ったが、何だか清々しかった。あの自由さが羨ましかった。幸鷹にとっても、伊予の想い出は忘れられないものだったのだ。持ち帰った木を今でも大事に庭に植えているほど。あの木を持ち帰ると言ったとき、あの海賊は一瞬目を丸くして、それから呆れたように高笑いした。あの時も、自分は今と同じように怒っていたと、幸鷹は懐かしく思い出していた。
2009年10月21日
コメント(0)
-
身分違いと言われても (翡翠×紫姫) 伍
「あなたは……!」 紫姫付きの古い女房は、翡翠を覚えていた。「姫様、姫様、おいでになりましたよ!」 あわてふためくように奥へ引っ込んでいく様子が物語る。やはり、紫姫は待っていたのだ。翡翠の訪れを。「翡翠殿……!」 待ちきれずに御簾をくぐり迎えに来た姿は、もはやあの頃の小さな姫君ではなく。 いかにもろうたげに、しっとりと落ち着いたゆかしき姫君だった。「紫……姫……?」 駆け寄る柔らかな体を、翡翠は抱きとめた。抱きしめずには居られなかった。今一度。腕の中に戻ってきたこの優しい温みを、もう一度手放すなど思いも寄らなかった。余りにも今までの自分とかけ離れた心持ちに戸惑いながらも、翡翠は紫姫を思う様かき抱いていた。「お待ちしておりました。いつかきっと、海を見せに迎えに来てくださると。」「それにしては、あなたは文一つ寄越さなかった。」「お出ししておりました。お手元に届かなかったのですか? 紫こそ、お返事一つ下さらないと恨んでおりましたが、きっと、翡翠殿には海のお仕事がお忙しいのだろうと、我慢をしておりましたのに。」 翡翠は横の乳母をちらりと見遣った。乳母は落ちつかなげに目を泳がせた。おそらく、これは乳母の仕業。海賊風情に大事の姫君はやれないと、翡翠が去るのを幸いその仲を隔てにかかったが、姫があまりに一途なのと、多分、翡翠の出自を小耳に挟んだのだろう。翡翠の耳に紫姫の噂が届くように画策した。そうでなければ、こんな風に尼君の屋敷に易々と通れるはずもない。「ああそうだ。迎えに来たよ。あなたに海を見せにね。来てくれるかい?」 返事の代わりに懐深く潜り込む姫を、翡翠は軽々と抱き上げた。乳母が一瞬顔を強ばらせたが、翡翠の足の向かった先は外へ向かう階ではなく、昔、神子の居た、奥庭に面した部屋だった。「今からではありませんの?」 紫姫が不満げな声をあげた。翡翠は軽く笑って紫姫の顎を持ち上げ、口づけを落とした。「すぐにと言いたいところだが、生憎と野暮用の最中でね……船の支度ができるまで、ここであなたと過ごしたい。だめかい?」 神子が居た昔と同じに、廂の柱にもたれて月を眺める。気まぐれなこの月が今度こそ本当に約束を守るようにと、紫姫は翡翠の衣を握る手に力を込めた。
2009年10月20日
コメント(0)
-
身分違いと言われても (翡翠×紫姫) 肆
先代の地の白虎も橘だったそうだ。 翡翠が橘の血に繋がるものと聞きつけた者が教えたらしく、とうに血の絶えたその家を預かる有能な家司が、資産を是非お返ししたいと奇特にも申し出てきたのだ。 翡翠は再三断った。いくら血の繋がりがあったとしても、同じ地の白虎だったとしても、貴族の暮らしはまっぴらだった。国司として赴任する京の貴族に、翡翠は飽き飽きしていた。軽蔑していた。唯一面白く、信じられる存在だったのは彼の別当殿だけだった。 余りにも伊予が国司の手に余るので、今までにも何度となく、要と目される翡翠を傀儡しようと京から何か言ってきていたが、翡翠は全く見向きもしなかった。今回のそれも、きっとその手合いだろうと思えたが、余りにもしつこく、余りにも面倒なので、いっそ京へ上ってその気はないとはっきり片づけてこようと、そう思ったのだ。 煩雑な手続きを踏んで目指す相手に辿り着き、また何度も同じことを繰り返しては同じことを告げる。「有能な家司」は有能なだけに頑固者で、なかなか翡翠の言い分を聞き入れなかった。(本家もさぞや手を焼いたのだろうな。) どういう経緯で彼の手にこの資産が残ったのかはわからないが、どうやら先代は橘本家には決して渡すなとこの家司の祖先に言い置いて居なくなったらしく、家司は、その遺言めいた言い置きが、今回の翡翠のことを予見していたのだと言い張るのだ。 予見していようがいまいが、翡翠にはそんなことは関わりのないことだ。一旦は受け取るが、長の留守居の報酬として取ってほしいと言っても、そんなことを聞き入れる相手ではない。長い長い押し問答に、翡翠はほとほと疲れ果てていた。 そんなやりとりのなかで、翡翠は、四条の尼君の孫の姫の噂を聞いた。(待っている……と?) 尼君とてしかるべき身分の方だから、深苑は懇意にしていた藤原宗家の肝煎りで既に元服し、院にお仕えしていると聞いた。姫君の後見を申し出る殿上人・公達も後を絶たないが、姫は言い寄る文を全てうち捨てて、ただひたすら誰かを待つ風に、夜毎、琴をかき鳴らしている……と。(まさか……ね。) 何年も経つのだ。さぞかし美しい姫君に育ったことだろうが、まさか、幼い頃の小さな約束を信じて待っているほど、あの姫は愚かではあるまい。「いつかあなたをお連れしますよ。あなたがもう少し大きくなったらね。」「ええ……」 膝の上で大きく頷いたやわやわとした重みが甦ってくる。見知らぬ海の話に聴き入る素直さに、つい口から出てしまった言葉。それほど惹かれるなら見せてやりたいと思った一言を、まさか、いまだに……。 翡翠の足は自然に四条へ向いていた。 今宵も響く琴の音に導かれ、案内を乞うた。
2009年10月19日
コメント(0)
-
身分違いと言われても (翡翠×紫姫) 参
しかし、いつまでも伊予を留守にしているわけにもいかない。 翡翠は、迎えに来た部下たちに乞われるままに、伊予へ戻った。「京の姫さんをお迎えなさると聞いておりやすが?」 留守を預かっていた男の問いに、翡翠は首を振った。京にいるうちに何人か、知り人から縁を取り持つ話をもらったが心に適う姫はなく、唯一心に適った姫は海賊暮らしに縁がない。(興味深そうに聞いていたが、彼の姫にここの暮らしはそぐわないよ。) 天に帰ったあの娘ならば、面白がってついてきただろうけれどね。 海風に曝される暮らしに紫姫が耐えられるとは思えず、だからといって、自分がずっと京にいるわけにもいかず。 久しぶりに吹かれる海風に、翡翠はらしくない執着を吹き払わせようとしていた。思う様船を操り、海と戯れた。(忘れよう。) 京が見せた小さな夢。八葉を務める翡翠へのささやかな報酬。紫姫という彩りで、京での暮らしは楽しかった。去りがたいと思わせるほど。 しかし、想いが止まることはなかった。翡翠は忘れたつもりだったが、温暖な伊予の気候にも咲く秋草の陰にふと懐かしい気配を感じて、翡翠は戸惑いを隠せなかった。(紫姫……) 深苑が禁じでもしたのだろうか、京からの文もない。 こうして少しずつ消えていく物なのだ、無用の執着はみっともないと自分を戒めて、時を過ごした。 いくつもの冬が、いくつもの春が巡り、想い出ももうとうに痛みを伴わなくなった頃。 翡翠はまた、京へ上る機会を得た。 誰にも言わず隠し通していた「橘の血」が、翡翠を京へ招いたのだった。
2009年10月18日
コメント(0)
-
身分違いと言われても (翡翠×紫姫) 弐
きっかけは、神子が出かける支度をしている僅かな時間だった。 神子を待つ時間を退屈そうにしている翡翠に、紫姫が声をかけたのだ。「伊予の話など……京の姫君にお聞かせするようなことはありませんよ。」「でも、私、外の世界など見たくても見られませんもの。聞きとうございますわ。」 神子には話しているのだ。海がどれほど広く、どれほど美しいか。頭上にどこまで広がる星空、たゆとう波の心地よさ。紫姫は、翡翠の口から直に聞きたいと思った。実際に見た目で感じたことを。「まったく、海賊の話に興味を示されるとは、四条の姫君はとんだやんちゃ姫とみえる。」 それではと語る翡翠の話に、紫姫はうっとりと聴き入った。準備のできた神子が戻ってくればそこで中断するのだが、翡翠が来るたびに、紫姫は続きをせがんだ。 せがまれれば、翡翠の方も悪い気はしない。神子を待つ時間では短いと、いつか、神子を送り届けた後になり、神子が翡翠を供に選ばなかった日はそのまま屋敷に留まって紫姫と一日過ごすような、そんな風になっていった。長く時を過ごせば情も移る。始めは紫姫を正面に見て話していたものが、いつの間にか紫姫を横に置き、横に置けば小さなその体をそっと膝に置きたくもなる。翡翠と紫姫の間に親密な時間が流れ始めるのに、時間はかからなかった。(ふふ、私ともあろうものが、こんな小さな姫君に気を取られるとはね。)「どうしたんですか?」と神子に顔を覗き込まれて、翡翠は苦笑した。戻ったら今日は何の話をしようかと考え込んでいたのだ。守るべき者として神子を愛しく思っていたが、紫姫の愛らしさはそれ以上だった。不覚だった。幼い姫と高をくくっていたのが、思わぬ落とし穴にはまったらしい。 傍らで見ていた幸鷹が苦い顔をした。「……神子殿とご一緒の時くらい、真面目に働いていただきたいものです。」「おや、別当殿。私が真面目でないとでも?」「何に惚けておいでになるのか。あなたらしくありません。」「ふふ……そうかもしれないね。君の勇敢さに見とれていたとでも言っておこうか。」「な……っ」 そんな会話もあったと、翡翠は一人小さく笑った。膝に置いた紫姫が不審そうな目を向けるのへ、小さな口づけを落とし黙らせた。嬉しそうに体を捩らせるのが愛おしい。翡翠は紫姫の体をしっかりと抱え直した。この掌中の珠は自分だけの物だと言わんばかりに。 語り尽くしたと思うほどにも、海の話を聞かせてやった。海に映り込む月の美しさ、広がる星空、その星が落ちたかのように海一杯に広がる夜光虫。凪いだ海も、荒れた海も、海賊の日常まで。「人が思うほど、日々船を襲っているわけではないのですよ。狭い海峡を通り抜けるに必要な知識を売ったり、必要なら案内したりね。」「そうですの?」「ふふ、毎日襲撃などしていたらこの身がいくつあっても足りません。依頼を受けて護衛していたのがたまたま襲われたとかね。まあ、たまにはこちらから仕掛けることもありますが……」 紫姫の顔が心配そうに曇るので、翡翠はその小さな体を優しく抱きしめ、額にもう一つ口づけた。「安心していなさい。君を置いて、私はいなくなったりしないから。」 紫姫は嬉しそうに微笑んだ。 月が中天にかかるのを見て、翡翠は紫姫を抱き上げたまま立ち上がった。紫姫は嫌々をするように身じろぎをしたが、翡翠は少しも意に介さず、紫姫を御帳台に運び、茵に横たえて帳を閉めた。「お休み、姫君。また明日来ますよ。」 愛しいとは思っても、それ以上踏み込むつもりなど翡翠にはなかった。まだ年端もいかぬいたいけな乙女に何をしようというのか。ただ相手のせがむままに、その小さな体を温め、優しい言葉を囁きかけ、それで紫姫が満足しているのだから、それでよかった。 しかし。 神子が去ってからも、まだこうして京に留まり、紫姫を膝にかき抱く、そういう生活が続くとは思わなかった。去る神子を追って流す紫姫の涙が翡翠を京に止めた。星の一族は神子あってのもの、神子が不在の時はただひたすらに龍の宝玉を守り、次の神子が訪れるのを待つのだと聞いた。先の神子が訪れたのは100年の昔。次の神子が訪れるのは、いったいいつのことか。 このまま、この姫が朽ちていくのかと思うと、翡翠はいたたまれない思いだった。幸せにしてやりたい、ただそのことだけが思われた。そんなに人に執着するなどらしくないとどれほどうち消しても、その思いは後から後から湧きだし、翡翠の心にあふれかえるようだった。 膝に残る残り香が、小さな重みの記憶が、そうさせるのだとわかっていた。しかし、一度知った物を知らない昔に返すことができないことも同じほどにわかっていた。(乗りかかった船、ね……) こうなったら漕ぎ出すよりないのだろう。行方も知れぬ……恋の船旅へ。(恋……? この想いを恋と呼ぶか。あの小さな姫君に、ね。) 翡翠は苦笑した。まさか自分にこんな恋が訪れるとは思わなかった。いったい、あの幼い姫のどこが自分をこんなに惹きつけるのか。
2009年10月17日
コメント(0)
-
身分違いと言われても (翡翠×紫姫) 壱
神子様がご自分の世界にお帰りになって、私、決して泣くまいと思っておりましたのに、涙が勝手に後から後からあふれていたのです。 それを優しく拭ってくださったのが、あの方。 私もう、あの方なしでは生きていけません……。「また来ておるぞ。」 深苑が、苦虫をかみつぶしたような顔で告げに来た。紫姫の顔がぱっと明るくなった。それを見た深苑の顔は更に渋くなった。「いったい、あれは何をしに来るのだ。八葉の務めはもう終わった。そもそもあれが八葉に選ばれること自体、私は歓迎していなかったのだ。人の身でどうのこうのと言えることではないのはわかっているが、龍の宝玉はどうしてあれを八葉に選んだのかと……」「どなたのことをおっしゃっておいでなのです? 兄様。」「あの海賊のことに決まっておる! なぜあれはいつまでもこの屋敷に来るのだ。」 紫姫の顔が困ったようにゆがんだ。翡翠が紫姫を訪ねてきていることは、深苑には極秘中の極秘だった。表向きはおばあさまのご機嫌伺いに、しかしその実は、紫姫に逢いに……。 翡翠が貴族の血を引くものであることを、紫姫は神子から聞かされていた。「深苑くんには内緒だよ。何だか翡翠さん、知られたくないみたいだったから……」「はい、お任せ下さいませ。」 こっくりと頷いたあの日のことを、紫姫ははっきりと覚えていた。「おや、深苑殿。私がこの屋敷を訪ねるのがそんなにご不満かな?」 女房が案内したのだろう、廂から翡翠の声がした。紫姫の顔がぱっと明るくなるから、深苑は大きく舌打ちして部屋を出ていった。「兄さま……?」「放っておきなさい。君が私を歓迎する以上、彼も私の訪問を遮ることはしないだろうからね。君の泣き顔を見たくはないだろうから。私と同じでね。」「まあ……。」 今日も、伊予の海のお話をお聞かせくださいましと、紫姫は翡翠の前に座った。もっと近くでと、翡翠は紫姫を抱き上げ、膝に乗せた。甘えるようにもたれかかる柔らかい頬をそっとなで、翡翠は伊予の波音のように寄せては返す低い甘い声で紫姫に囁き始めた。
2009年10月16日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 初誕生
その日のことを、友雅はありありと覚えていた。 虫集く大堰の山荘で、あかねを見舞う八葉たちと一緒に、姫の誕生を待っていた。 離れた産室から時折聞こえるあかねのうめき声に、幾度立ち上がったことか。 そのたびに、誰かに止められ、いらいらと座して、我が身の力なさに呆然とし。 あんなに自分を情けないと思った日はなかった。そして、あかねがどれほど愛おしいかを、思い知らされた……。「どうしたんですか? 友雅さん。」 ふいに聞こえたあかねの声に、友雅は我に返った。「ああ……」 手を伸ばし、抱き寄せた。急なこととあかねは少し抗ったが、すぐにすっぽりと胸の中に収まる。己の半身とめぐり逢えた安堵感が訪れる。「……少し、疲れてしまったようだ。こうしていると、気持ちが休まる……。」 顎を持ち上げ、口づけた。あかねの唇から甘い吐息が漏れた。 ちい姫の誕生を祝う宴があったのだ。 こぢんまりとちい姫に縁の者だけでしようと思っていたのが、土御門の藤姫から中宮様に知れ、そこから帝にも知れてお祝いの品など届くものだからやはり、橘少将殿の一ノ姫のと披露せざるを得なくなり、訪れる公達や殿上人をもてなしているうちに、いつしか大きな宴になってしまっていた。 表には友雅一人が出ていればよかったから、あかねは奥で、イノリや頼久や蘭といった、宴席に連なれない仲間たちとゆっくり過ごせた。普段から友雅を煙たく思っている彼らにはその方がよかったようだが。「申し訳ありません、神子様。私がついうっかりと口を滑らせてしまったために……」 藤姫が瞳をうるうるさせて謝った。「いいよ、藤姫。本当なら、こうしなくちゃいけないんだから。」 この屋敷にこの姫有りと聞こえ渡るのも必要なこと。しかし、それはちょっとした危険も伴うからねと、友雅が冗談交じりに言っていた。姫がそういう年頃になったなら、未だ逢わざる姫に心を懸けて文を寄越す公達が数多いることだろう、妃がねの姫君として、文の一つもこないというのは張り合いのないことだけれど、盗み出される心配もしなければならなくなるからねえ……。「はん! 友雅の言えることか。」「確かに。己の所行から出てくる判断としか思えん。」 もてなしの酒でほろりと酔ったイノリと頼久がぼそり言った。「神子殿、ご安心を。神子殿の姫君は、この頼久が必ずやお守りいたします。」「ありがとう、頼久さん。」 友雅とあかねがこの六条の屋敷に移ってきたとき、頼久は土御門に暇乞いをした……というか、藤姫が間に入って、土御門の猶姫であるあかねの警護に就くよう、配属替えをしてもらった。土御門の警護をする者は頼久でなくても腕の立つ者は居たから、元龍神の神子であるあかねを警護するのは、元八葉の頼久が最もふさわしいと、藤姫から推してもらったのだ。 以来、頼久はずっと、侍頭としてこの六条橘家の警護をしている。あの性格から、この屋敷の警護を仕切るのに不安を感じるなど一言も口に出さなかった天真は思い切りほっとした。蘭もこちらへ越してきたので、あかねは蘭を早速自分付きの女房にし、蘭と頼久の娘の小督はいずれちい姫付きの女童になるということにして、楽しく過ごしていたのだった。「もう……お殿様のことを悪く言うものではないわ、頼久さん。」 蘭がたしなめた。蘭とて、友雅のことを素直に認めているわけではなかったが、他ならぬあかねが選んだことだし、あかねの幸せ一杯の笑顔を見ていれば辛かったあの恋も癒えてくる。頼久という伴侶を得て、蘭も幸せ一杯だった。時折、頼久があかねに向ける苦しげな視線を見ないことにすれば。「でもさ、友雅さんって、すごく怖いお父さんになりそうじゃない?」「そうね、今はメロッメロだけれど、その歳になれば。」「電話とかかかってくるとね、何も言わずに切っちゃうんだよ。」「そうそう、クラスの連絡網だから回さなきゃイケナイのに、パパが切っちゃうから回せなくて、次の日すごく怒られた。」「内緒で文使いなんかしようもんならひどい目に遭いそうね。」「あの、腰に下げてる太刀、実は本物だもんね~。」 桜木の精との対決の時の様子をつぶさに見ていたイノリがふと目を上げ、何か言いたそうに口がもごもご動いたが、頼久に代わりの酒を注がれて黙った。(言うな。神子殿がまたお心を痛められる。)(わかってらい。まったく、友雅のヤツ、すっかりあかねをたらし込みやがって。)(お子までなされた仲なのだ。それはもう言うまい。)(そりゃ、そうだけどさあ……) 表から聞こえてきていた管弦の音が止んで、代わりに牛車の轍の音が聞こえ始めた。「宴が……果てたようです。」「もう遅い時間なのですね。では、私もおいとましませんと。」 藤姫が立ち上がった。お見送りいたしますと頼久も立ち上がるから、イノリも仕方なさそうに立ち上がった。表の方で客人の世話の仕事があってゆっくりと話ができなかった天真や詩紋のところへ行くと言った。 蘭も、西の対でちい姫と一緒に休んでいる小督を迎えに行った。 急に静かになった部屋で、あかねは一人、月を眺めていた。 あかねにとっても忘れられないあの夜。 自分は必死でよくわからなかったけれど、後から、友雅がどれほど落ち着きなく取り乱していたかを聞いた。 そしてその時、自分がどれほど愛されているのかを……知った。 友雅の腕の中で、あかねは幸せだった。 この世界に残ってよかったと、心の底から思った。 離れた時間が長くても、一人の時間が多くても、自分は守られていると思わせてくれるこの腕の温もり。心が安らぐ……それはあかねも同じに感じていることだった。 友雅があかねを抱き上げ、いつも通り御帳台へ運ぼうとした時。 遠くから聞こえていた巡視の足音が、不意に止んだ。(……まったく、監視されているようだねえ……) 息を殺し、奥の気配を伺う空気が一瞬だけ流れた。(本人は、主への気遣い以上の何事でもないと言うだろうけれどねえ……) あれではあれの奥方が気の毒というものだと、友雅は小さく嘆息した。忠義一途の源の武士が土御門の肝煎りで侍頭に就任してから、夜の庭の空気が変わった。天真は友雅のいるところへは寄りつかなかったから、夜の奥向きは本当に友雅とあかねだけの世界で、気心の知れた従者が交代で離れたところに控えているだけだったのだ。「頼久さんに、こっちへは来なくていいって言いましょうか?」 あかねが小さく聞いた。友雅は微笑んで首を振った。たとえあかねの言葉でも、頼久が警護の足を止めるとは思わなかった。様子をうかがって、むやみに踏み込んで来ないだけよしとしよう。あかねをただ一人の主を仰ぐ、その忠誠心がさせていることなのだから。(……私もその「賊」の一人になりかねないというだけでね。) ふふっと笑って、友雅はあかねをしっかりと抱え直し、御帳台の帳をくぐった。 ちい姫の生まれた夜と同じ明るい月が、ゆっくりと西に傾いていった。
2009年10月11日
コメント(0)
-
【景望】 約束
学校祭が近くなると、望美の帰りはどうしても遅くなる。 約束の「日暮れまで」に逢えない日が続いて、望美は寂しかった。 土曜日曜も文化祭などの買い出しで友だちと約束する日が多くて、それに景時の休みとも合わない。(逢いたいな。) 学校祭が終わればあとは受験に向けての準備が始まるだけ。受験が終わって、卒業すれば。 景時との約束も、期限切れになるはずだった。(高校が終われば。) 景時と二人暮らせるなら、高校で終わりにしてもいいと思った。就職もしなくて、近くのスーパーかコンビニでアルバイトして。「それはだめだよ、望美ちゃん。」 いつだかそう言ったら、景時にたしなめられた。 景時は今自分ができることのスキルを人材派遣会社に登録して、単発の仕事を掛け持ちしている。イベント会場でマジックを見せるとか、店頭の実演販売のマネキンとか。安定した収入など望めないが、今の景時にできることはそれくらいだった。有川家のやっかいにならない程度に生活していくにはもう少しスキルアップしたい。しかし、そのためにはこの時空では資金がいる。「望美ちゃんはこの時空で仕事を得やすい場所にいるんだから、ちゃんと最後までしなきゃ。ご両親もがっかりしちゃうでしょ。」 自分のために、望美の一生が中途半端になるのは嫌だと景時は言った。「わかったよ。」 正しいことを言われているのはわかっているから、景時の言うことに従わざるを得ない。「慌てないで。オレはずっと、望美ちゃんの傍にいるから。」 早く二人で暮らしたいのは景時も同じだ。あとは、そうできる条件を満たすだけ。(でも、あの調子じゃ、高校出ても約束は約束だよね、きっと。) 学生でいるうちはだめだよとか言って延長されそうだった。(景時さんって、結構真面目だったんだ。) 真面目だからこそ、大倉御所の意向と八葉の務めとの板挟みになって悩んでいたのだが。果たさねばならない任務の前で、景時は常に従順だった。きっと、今、望美と暮らすために安定した生活を得ることと、望美の両親の揺るぎない信頼を得ることが、景時には重大な任務に感じられているのだろう。 極楽寺の駅を降りたときには、もう暗くなっていた。 家までの道も、住宅街が続いてかなり暗い。ちょっと嫌だなと思いながら駅舎を出ると。 思いがけない人影に、望美の胸は躍り上がった。「景時さん!」 暗くなったから、もう逢えないと思っていたのに。「迎えに来たよ。大丈夫、ご両親のお許しは得てあるよ。夜道が暗いから心配だって。オレが毎日迎えに行きますって言ったら、すごく喜んでくださったよ。」「じゃあ、これからは毎日逢えるの!?」 望美は景時の胸に飛び込んだ。人目なんか気にならなかった。景時に逢えた、ただそのことがうれしかった。 飛び込んできた望美を両手で受け止め、景時はそっと望美の髪を撫でた。「でもね、だからと言って、わざと遅くなるのはだめだよ。学校から帰るときはメールして。待ち合わせて、一緒に帰ろう。」「うん、そうする。」「家までの直行だよ。寄り道はなし。」「ええー!?」「但し、途中でおやつだけは許してあげようかな。」 景時の目が悪戯っぽく微笑んだ。望美の顔がうれしそうにほころんだ。景時の仕事は鎌倉駅とか藤沢駅とか大きな駅の近くが多いから、そこで待ち合わせることになるのだろうか。「じゃあ、帰ろっか。」「うん。」 景時がさしだした手に、望美は自分の手を滑り込ませた。久しぶりに包まれる温かさ。寂しかった心がすうっと溶けて、優しい温もりに満たされる。 まるい月が蒼白く照らす道を、二人手をつないで帰る。「十六夜の月だね。」「うん。きれいだね。」 これからどんどん月の出は遅くなって、夜道もどんどん暗くなるけれど、景時が迎えに来てくれると思えば平気だった。 楽しい時間は早く過ぎる。 もう、有川家の門が見えてきた。 景時の足がふと止まった。「望美ちゃん……」 電信柱の影、街灯の光の届かない暗がりに隠れて、望美をそっと引き寄せた。 近づく顔に目を閉じる。 唇が触れ合う。景時の舌先が優しく望美の唇をなぞり、そっとこじ開けて中を探った。「ん……」 久しぶりの感覚。気が遠くなるような快感を覚えながら、望美は景時の舌を迎えにいった。絡み合い、強く吸われる。痛いほどの快さにぼうっとする。 唇が離れ、堅く抱きしめられた。「……これが、おやつ。」 悪戯に囁く声。望美は景時の胸に額を擦りつけた。「行くよ。」 去り際に必ずという約束。望美は素直に従った。春日家の玄関で別れた。「ありがとう、景時さん!」 家の中に聞こえるほど大きな声で、景時にお礼を言った。送ってもらったとわかるように。 キッチンから、「すみませんねえ」と景時をねぎらう母の声がした。
2009年09月12日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 日差しの中で
今年も、京に暑い夏がやってきた。 大堰から六条へ渡ってきて初めての夏。山麓に川を控えた大堰の里は、冬は凍えるほど寒かったけれど、夏は開け放てば涼風がどこからか吹いてきて快適だった。それでもあかねは暑い暑いとだだをこねて、女房頭の少納言を困らせていたけれど。 六条の屋敷は、大きな池を設えて水を流し、涼やかに作ってはあったが、山から吹き下ろす風があるわけではなく、町中のよどんだ空気が、生ぬるく覆っているだけだった。(大堰に戻るって言えばよかったかなあ……) あかねは後悔していた。友雅はこうなることを見込んで、あかねに、大堰の山荘へ避暑に行くよう勧めてくれたのだった。しかし、そうするとまた、友雅と別れ別れの暮らしになってしまう。あるいは、友雅が遠い道をまた馬を駆って内裏へ通うか。どちらもあかねには寂しく心苦しいことだった。「いいよ。ここに居ます。」「いいのかい?」 あかねは元気よく頷いた。せっかく、友雅が自分とちい姫のために用意してくれた洛中の館だ。北の方としての務めがたっぷりあるというのに、本当は嫌いな内裏務めを自分のために堪えてくれている友雅を置いて自分だけ避暑に行くなど、考えられない。 それを口にしたら、友雅は嬉しそうに抱きしめてくれた。たくさんの愛の言の葉と一緒に。 思い出して、あかねは一人でぽっと赤らんだ。傍であかねの髪を梳いていた少納言が不審な目を向けるので、あかねは慌てて居住まいを正した。 しかし、口ではどんなに強がっても暑いものは暑い。あかねは涼を求めて西の対へ出かけた。階の近くまで水を引き入れてあるそこはちい姫の館になっていて、風通しも寝殿よりよく、このところあかねはしょっちゅうそちらへ出かけていた。 いつもの居間を覗くと、そこにちい姫の姿はなかった。いつもなら出迎えて案内する女房の姿もない。どこへ行ったのかと耳をすますと、遠く、対の屋の南の端から、小さな歓声が聞こえた。あかねはそちらへ歩いていった。 遣り水の小さな流れの畔に幔幕を張り、その中から歓声が聞こえてくる。 傍にいた女房があかねに気づいて迎えた。「あまりにお暑うございますので、本日は姫様には行水を。」「わあ、いい考え。気持ちよさそうだね。」 幕を上げてもらって中に入ると、ちい姫が目ざとく見つけて駆け寄ってきた。「ああ、姫様、濡れたままおいでになっては。」 乳母が急いで寄ってくるのをあかねがやんわりと止めた。ふふっと悪戯に笑って、袴の紐に手を掛けた。乳母が驚いて目をむいた。「お方さま、何を遊ばされます。」「だって、あんまり気持ちよさそうなんだもの。私も一緒にいいでしょう?」「おやめ下さいませ、お方さまの湯浴みはお湯殿にご準備させましょうから。」「え~? いいじゃない。こうやって幕も引いてるんだし。誰も見に来やしないって。」 とは言うものの少し気が咎めて、着いてきていたお付きの女房に、湯帷子を持ってくるようにあかねは言いつけた。かしこまりましたと女房が去るのを見て、乳母は不承不承ながらもあかねのためにもう一度湯を運ぶように西の対の御達に頼んだ。「まったく……殿様がお聞きになったらなんとおっしゃることか。」「大丈夫、友雅さんはそんなこと気にしないよ。一緒にしたいって言うんじゃない? ねえ、ちい姫。」 ちい姫が嬉しそうにぱしゃぱしゃと盥の水しぶきをあげる。夏の日差しがしぶきに反射してきらきらと七色に煌めく。(カメラ、欲しいな……) ちい姫の可愛いしぐさも、この綺麗な水しぶきも、何一つ思い出を残せない。だから、せめて、たくさんの思い出を共に。 夏は必ずプールに入っていたのだ。大堰でも、内緒でしょっちゅう池で泳いでいた。本当にこの六条の池でも泳ぎたいけれど、ここは余りにも人目が多すぎてできない。ちい姫の行水に便乗するのは、またとないチャンス。 湯帷子も届き、盥には新しい湯が足され、あかねは袴と羅の単衣を湯帷子に着替えて、盥に飛び込んだ。大人が一緒に、しかも母が一緒に入るなど思いもつかなかったのだろう、ちい姫の目が丸く大きく見開かれて、次の瞬間には大きな笑い声を立ててあかねの胸に飛び込んできた。 思う様抱きしめ、湯をかけてやり、小さな体をこすってやり。乳母が洗ったのはよくわかっていたが、すみずみまで自分の手でこすってやりたい、柔らかい小さな体。ちい姫もあかねを真似て、大好きな母のおっぱいを小さな手でこすってみたりするようだった。 幔幕の外が急にざわついた。必死で止める声を振り切って、幕が開かれた。「ふふ、良い眺めだね。」「友雅さん!」 朝参が終わって戻ってきたのだろう。友雅の顔が覗いていた。あかねは慌てて向こうを向いた。ちい姫がせいいっぱい小さな腕を広げて父を呼んだ。友雅は乳母から体を拭く布を受け取り、それでちい姫をすっぽりと包んで抱き上げた。「ご機嫌だね。湯浴みは楽しかったかい? 姫君。」 頷いてちい姫は父の頬に自分の頬を擦りつけた。友雅はくすぐったそうにそれを受けながら、穏やかな目をあかねに向けた。あかねは、友雅の眼がちい姫に向いているうちにと急いで体を拭いている最中だった。女房の一人が友雅の視線からあかねを守るように布を広げているので、友雅は残念だと言うように肩をすくめた。「殿様、おいたも程々にして差し上げてくださいませんと。」 友雅を追ってきていた少納言が、呆れたように言った。「……人目につくようなところで湯浴みをしていた北の方にお小言はないのかい?」「……この暑さでございます。お留めすることはかないません。」「ああ……」 あかねは京の暑さに弱い。あかねがいた世界では、夏は部屋を冷やす道具があって、それで暑さをしのいでいたと言うから、毎年、あかねの夏越は大変なのだ。(だから、大堰へ行けと言ったのだがねえ……) 身仕舞いをして、すましてその場にいるあかねに向かって、友雅は苦笑した。あかねはつんと横を向いた。ちい姫が不思議そうに両親を見るので、友雅は笑ってちい姫ごとあかねを抱きしめた。「……ひどいわ。気持ちよかったのに。」「続けていればよかったのに。なかなか素敵だったよ。めったに見られないお姿だったからね、奥方様。」「だって、恥ずかしいでしょ!?」「恥ずかしい? どこが?」「もう!」 ちい姫を間に挟まれているから、叩きたくても思うように叩けない。あかねはちい姫を抱き取って、友雅の腕の中でくるりと体を翻した。追う手をくぐり抜けて乳母にちい姫を渡し、さっと幕を上げて外へ出てしまった。「ご機嫌を損ねてしまったな。」 言葉とは裏腹に、友雅の表情は自信たっぷりだった。夏の煌めく日差しの中、思う様水に戯れる楽しさを知らない友雅ではなかった。あかねが喜ぶことを一つ見つけた。 友雅は寝殿に戻ると、急ぎ家司を呼びつけた。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 数日後、西の対の釣殿の先で、何やら普請が始まった。「聞いてないわよ?」 何の普請かと尋ねるあかねに、友雅はふふと笑って答えなかった。 更に数日後、友雅はあかねを伴って西の対の先へ出かけた。 普請はもう終わっていて、白木の板塀で囲った小さな板葺きの小屋ができていた。促されて扉を開け中へ入ると、小上がりの上は小さな部屋になっていて、そして更に奥には……「お風呂!?」「そうだよ。あんな風に幕を張って行水するくらいなら、この方がいいだろう?」 檜の香りがぷんと薫る、新しい木の湯船。深さはあかねの膝ほどのようだが、広さは脚を伸ばしてくつろげるほどだった。ちい姫が一緒に入っても安全だろう。背後は壁になっているが、目の前は素通しに開けて、庭の一部を囲みこんだそこは白い玉砂利が敷かれ、引き込んだ遣り水で水遊びもできるようになっていた。 あかねは無言で友雅を振り返った。黙ってじっと抱きしめた。見なくてもわかる。あかねは涙ぐんでいた。「どうしたの。気に入らない?」「ううん、嬉しいの。何も言わないのに、こんなにしてくれて……」 友雅はあかねの顔をすくい上げ、口づけた。「……愛しい君のためならね。」 ちい姫が、乳母に連れられてきた。新しい湯殿に目を丸くした。「おいで。」 あかねは涙を拭いてちい姫を呼んだ。遣り水の傍へ連れて行き、そっと水に触らせた。ひんやりした感触にちい姫は歓声を上げて、嬉しそうに遊び始めた。 手で水を掬っては一緒に戯れるあかねを、友雅も嬉しそうに眺めていた。
2009年08月08日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 雲間 その3(最終回)
「しょおしょぉ~~~!」「お元気でいらっしゃいましたか、宮様。」 乳母の手をふりほどくようにして、幼い宮が友雅の懐めがけて駆けてきた。友雅はやんわりと宮を受け止めた。 影の守り役として御所でのご機嫌伺いを欠かさないから、宮はすっかり友雅に懐いている。ひとしきり抱きついて甘えた後で、宮の目はふと、友雅の背後に控える女房の腕に抱かれた小さな女の子に吸い寄せられた。 幼い目に、互いがどう映ったのか。 宮は、ゆかりの姫を見るなり、嬉しげに手を伸ばした。 ゆかりの姫も、興味津々と言った様子で宮をじっと見つめていた。「友雅殿の姫君ですよ。」 宮の乳母がそっと教えた。宮は大きく頷いて、ゆかりの姫の手を握った。ゆかりの姫も嬉しそうに握り返した。 先触れがあって、別室で話し込んでいた中宮様とあかねが渡ってきた。「まあ、二人ともすっかり仲良しね。」 茵を敷き詰めた床にお座りし、無心に遊ぶ二人に、中宮様は目を細めた。あかねと友雅も、隅に畏まって二人の姿を見ていた。あかねの心に嬉しさがあふれる。 友雅も嬉しそうな表情は作っていたが、目は笑っていなかった。(これで最初の関は越えたか。) あかねは土御門の猶子だから中宮様には妹の一人ではあるが、実質は中宮様の友という宮中では特殊な立場の母を持つこの姫は、おそらく今までの誰よりも東宮に近しく育つだろう。乳母子でもなく、もちろん兄妹でもない、幼なじみという立場で。あかねがちい姫を連れて頻繁に参内すれば、二人が共に過ごす時間も長くなる。そして、その機会はおそらくこちらが思う以上にしばしば訪れる。今日のお召しはその皮切り。子連れの参内がかなうと知れば、中宮様は遠慮なくあかねをお召しになることだろう。ちい姫の顔を見せてと。 友雅の脳裏には、十数年後の入内の様子が浮かんでいた。東宮様にとっては唯一の、なくてはならぬ姫として入内するちい姫の姿だった。幼い頃からの恋が叶って、並びなき寵愛を一身に受け、後宮一ときめく存在になる。父は橘の家の出だが、決して藤原の家の姫にひけはとらない。いや、とらせることなどない。そのためには……(昇進を断るわけにはいくまいな。) 面倒が増えるのが嫌さに、今まで帝の仰せ事を辞退してきた。八葉の任を無事務めた功績にと位階を進める話があったときでさえ。 父の身分は後宮では必須。 友雅の頬から思わず苦笑いが漏れた。「どうなさったの? 友雅殿。」「失礼いたしました。お気になさらず。」 ちい姫と親王様が声をたてて笑っている。中宮様とあかねも久しぶりのおしゃべりを楽しんでいる。 梅雨の晴れ間の瑠璃色の空が友雅には眩しかった。
2009年07月07日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 雲間 その2
「ちい姫ぇ~~~♪」 とろけそうな笑顔で迎えられたのが自分でなくちい姫だったのが、友雅には少し不満だった。「私をお呼びだと聞いたがねえ、奥方様。」「だって、奥向きのお仕事がいっぱいあって、今日はまだちい姫に会ってなかったんだもの。」 京の街中に居を移してから、あかねの身の回りも格段に忙しくなった。召し使う家人も増えたから、少納言や家司が取り仕切るとはいうもののそれぞれの決済はあかねが目を通さねばならず、見てもよくわからないものだから当然時間もかかる。重要な行事が立て続けにあるときなどは、友雅が宿直で留守にしていたりすると寝る間も惜しんで見ているほどだったから、心配した少納言と乳母の勧めで、あかねの仕事だった授乳も、ちい姫の離乳食が始まると共に止めてしまったほどだった。寂しかったが、北の方たる者は邸を支えていく家刀自の役目の方に重きを置くのが京の貴族の常識だと言われればそれに従わざるを得ない。 水無月に入ったから、家人の夏の衣料の支給や晦日の祓えの支度がある。もちろん、友雅の夏の料も整えなくてはならない。それだけでも目が回りそうなのに、今日は土御門から公式の文が来た。藤姫の私信ではなく、本邸の……中宮様から。「お里下がりをしておられるのですって。親王様をお連れになって。」 そういえば、と、友雅も思い出した。中宮様のお里下がりは友雅の役目ではなく、左大臣家が取り仕切ることになっているから、お召しはなかった。しかし、内々で守り役を仰せつかった親王様もご一緒だから、ご機嫌伺いをして帝にご報告申し上げる役目がある。面倒だとつい忘れがちになっていたが、お文が来たとあれば知らぬ顔もできない。「では、お伺いしなければならないねえ。いつ、行くんだい?」「うーん、迷ってるんだけど……」 ちい姫も連れてとのご注文があったのだという。「お任せ下さいませ。」 乳母の君がぽんと胸を叩いた。「ちい姫様のご衣装の心配なら遊ばしますな。すぐにでもご用意いたしますよ。」「ありがとう。じゃあ、すぐにお返事を書くわ。友雅さんはいつでもいいの?」 微笑んで頷く友雅に、じゃあ、明日にでも伺いますと書くわねと、あかねは料紙を選びに奥へ向かった。ちい姫を抱きしめて頬ずりするのは忘れなかったが、ちい姫を抱く友雅には軽く手を振っただけだった。(まったく……) 寂しいような嬉しいような、複雑な気分が友雅を支配する。崩された文字に途方に暮れていた顔、ましてやその文字を書くなど思いもよらず、しかしこの世界に残ったからにはと友雅の書いた手本で思い詰めたように手習いをしていた大堰の日々が甦る。早く慣れるようにと乳母子の少納言を傍付きに頼み、彼女の訓育であかねは友雅の望むとおりの京の北の方になった。そしてその結果が、これだ。 つれないねという言葉を珍しく友雅は飲み込んだ。激情が穏やかな愛に変わっていく。 友雅はちい姫を抱きなおした。嬉しげな笑い声が上がった。
2009年07月06日
コメント(0)
-
【蛍シリーズ】 雲間 その1
「ちい姫様、姫様!」 西の対から賑やかな声が響く。這子を追う乳母の声だ。友雅とあかねの間に生まれたゆかりの姫はすっかり大きくなって、覚えた這い這いで思う様動き回り、時には高欄の縁につかまって立つほどにもなったので実に目が離せない。 今日も、対を訪ねた友雅をめざとく見つけて、回らぬ舌で呼びながら勢いよく這ってくる。後から乳母が慌てて追いかけてきた。「ふふ、まったくやんちゃな姫君だ。」 近寄って抱き上げ、友雅は姫に頬ずりした。「ちゃあ!」と手を挙げて喜び、甘えてくるのが愛おしい。「申し訳ありません、御端近には出られませんようにと気をつけておりますのに。」「いいよ、まだまだ頑是無い年頃なのだから。北の方が、あまり奥深く籠めずに日の光を見せてやって欲しいと言っていた。聞いていないかい?」「承っておりますが、それでは姫様のお肌が日に焼けて。」「それは私も思わないではないがね、日に当たった方が丈夫に元気に育つと言われれば、うなずける点も多くてね。」「そういうものでございますか。」「言っているご本人が一番の証拠だろう?」 異世界からやってきて、心身共に疲れることが多かったろうに、風邪もひかず、熱も出さず、毎日元気に怨霊退治に明け暮れていたのはきっと、彼女がそのように育ってきたからだろうと、イノリや天真を見るのと同じ目で友雅は考えていた。 あえかで消え入りそうな深窓の美姫というのは確かに友雅のような色好みの食指を動かす存在だったが、ゆかりの姫に求められているのは東宮妃としての素質だった。美しいだけではやっていけない後宮の生活は、多少のことでは動じない体力と知力を要求する。弘徽殿皇后が藤壺中宮に押されぎみなのはお体がお弱いのにも一つ原因があるという説が、上達部の間で囁かれていた。後宮政治に乗り出そうとする貴族たちの中には密かに、生まれた姫君をわざと田舎住まいさせて、鄙の童と同じに育てている者もあると聞く。 友雅は腕の中のちい姫を愛しげに見つめた。 何にも代え難い掌中の珠。同じことならば国母の位にまで昇り詰めさせてやりたい。そのためには…… 抱かれているのに飽きたのだろうか、ちい姫が友雅の胸にうんと腕を突っ張った。「おやおや、すっかり力持ちさんにおなりだ。」 友雅は笑って姫を廂の間に敷かれた茵の上に下ろした。身動きを許された嬉しさに這って去るかと思いきや、茵の上にお座りして、にっこりと笑った。 乳母が懐から気に入りの布子を出して差し出すと、嬉しそうに手にとって弄び始めた。立ったままの友雅を不思議そうに見上げ、座れと言わんばかりにとんと床を叩いた。「ふふ。」 側付きの女房が設えた円座に腰を下ろした。安心したように布子に夢中になるちい姫を見る目が、信じられないほど優しい。「お父様を大好きでいらっしゃいますから……」 お務めのお邪魔ではないかと気遣う乳母に、気にするなと手を振った。決まりきった内裏の公務など、優秀な部下たちが決まり通りに進めている。自分がどうしても出向かなければならないときは腹心が使いを寄越す。何も言ってこないということは恙なく物事が進行しているということ。今は未来の東宮妃のお相手をすることが友雅には最も重要な公務だ。「殿様、お方さまがおいでを賜りたいと。」 寝殿から女房が呼びに来た。わかったと腰を上げる友雅を、ちい姫が不安そうに見上げた。顔がくしゃっとゆがみ、今にも降り出しそうな雨空といった風情を見せる。「姫もお母様に会いに行くかい?」 お母様という言葉に敏感に反応した。降り出しそうな曇り空は一瞬で晴れ渡り、友雅の直衣の裾にぎゅっとつかまって立ち上がった。「だっ、だっ、」と、回らぬ舌で抱っこをせがむ。 友雅は片手で軽々と姫を抱き上げた。「ちゃあ!」と嬉しそうな声をあげる姫君と、渡廊を寝殿へと向かった。
2009年07月05日
コメント(0)
全760件 (760件中 1-50件目)