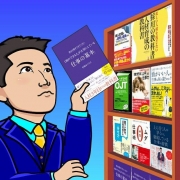(この日記は9/4に書いてます)
後半、夏休みの宿題をあわただしくしていたご家庭もあったでしょうか?
僕が子どものころはタップリ宿題があったのですが、
ウチの子の学校は宿題はとても少なく、時代は変わったなぁ・・・と思います。
また、宿題自体も随分変わったのか、
私の子どものころは自由研究や工作などは、
親が手伝うのではなく、子どもがやるのが当たり前
でした。
ところが、ウチの子の工作の宿題は、
「親が手伝ってあげてください。(ただし、全部親がやらないでください)」
と学校から言われました。
2学期が始まると、展示会があるのですが
親の見得の張り合いのおかげで、力作ぞろい
だそうです(笑)
それって、意味あるの? と思ったのですが、僕なりの解釈はこうです。
「工作を通じて親子のコミュニケーションをとりながら、
ひとつの目標を立てて一緒に達成して行きましょう!」
という目的があるのではないか?
そんなビジネスチックな目的があるとは思えないけど
そういう風に捉えることで、
同じ何かを作るにしても学びが変わってきます。
単なる親同士の見得の張り合いではなく、
意味ある宿題になるのではないでしょうか?
中尾語録189
一皮むくと味が出る

たまねぎは、畑で取れたときは泥だらけ。
でも一皮むくと、中から
みずみずしくて甘くて
おいしいたまねぎが出てくる。
見た目は汚くたって
中身はそうじゃない
んですね。
でも、たまねぎは 自分で皮をむくことはできない
んです。
誰かがむいてあげなければ、
その内に秘めた本領は発揮されない
んです。
最初の外見だけで判断しないで
中身を見てあげて、開花させてあげればいいんじゃないかな。
一皮むくと味が出る
-
中尾語録2898 景気回復基調も採用環… 2013年04月07日
-
あけましておめでとうございます。 2013年01月01日
-
中尾語録1910 リアルさは言葉や文字… 2011年05月11日
PR
カレンダー
フリーページ
Oh!おっちょこ克服… かんろですさん
しあわせカフェ&シ… Coo-Cooさん
商品紹介 いつもプラス思考さん
FROM21★今ここ… ティーンズ応援団長さん
テラッチ☆笑顔力~ふ… テラッチ!☆笑顔力さん
くま蔵のファンタジ… くま蔵2003さん
幸せ日記 みぽりん@ごきげん&ほほえみプレゼンターさん
【しあわせお父さん】 ツイてる☆とっさん!!さん
MY THOUGHTS もぐもぐりすさん
コメント新着
2025年10月
2025年09月
2025年07月