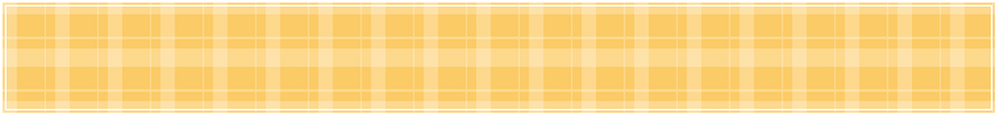全159件 (159件中 1-50件目)
-

新型コロナウイルスの影響、「虐待しそう」相談窓口
新型コロナウイルスの影響で、外出自粛が求められる中、「子どもを虐待してしまいそう」という相談が増えています。本日(2020年4月24日)の朝日新聞に「『虐待しそう』相談急増」という記事がありました。「ストレスで夫とけんかしてしまう」とか「このままでは子どもを虐待してしまいそう」などという相談が急増しているのだそうです。新型コロナウイルス関連で、家庭内暴力(DV)が増えているという報道は、少し前から特に海外で増えてきました。夫や子どもと顔を突き合わせている時間が増え、ストレスが増えているのです。この記事では、NPO「あなたのいばしょ」が3月に立ち上げたチャット相談に寄せられる悩みを紹介しています。「下の子が小さいのに小学生の上の子が休校で家にいるから、ストレスが大きい」とか「家事が増え、ストレスがたまり夫とけんかしてしまう。外出もできない。」とか。相談者の9割超が女性といいます。このチャット相談は、電話ではなく声を出さなくていいので、周囲をきにせずやりとりできるところがいいです。大学生らがインターネット上で24時間体制で運営しています。これ以外にも相談窓口はいくつかあると思うので、「子どもを虐待しそう」だと心配になったら早めに相談するといいと思います。NPO「あなたのいばしょ」のチャット相談は「https://talkme.jp/chat/」です。チャット相談 あなたのいばしょ ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ「介護の誤解」へ
2020.04.24
コメント(0)
-

新型コロナウイルスが心配な中、三女の秋子も巣立ち
この春、三女の秋子も家を巣立ちました。秋子は関東の私大に進学しました。長女の進学先(北陸→関西)、次女(関西)の進学先と比べて、実家から最も離れた場所に出ていきました。三人娘の大学受験はどれも楽ではありませんでした。長女は国公立大学後期試験で進学先が決まり、次女は一浪ののち3月の私大の後期日程まで粘って進学先が決まりました。そして、三女の秋子。長女と次女の頃とは少し事情も変わってきていて、国公立大学の推薦入試も増えてきています。三女の秋子は、国公立大学の推薦入試に挑戦しました。一次試験は通り二次試験まではいったものの、最終的には合格できませんでした。センター試験では得意科目の英語や国語は想定通りに得点でき、苦手科目の数学などは苦手なりの得点となり、全体的には想定していた程度の得点が取れました。結果から考えれば、ここで欲を出してしまったのが不合格につながったのでしょう。推薦入試を受けた大学からさらに難易度の高い大学を受験することにしてしまったのです。センター試験と模擬試験を組み合わせたドッキング判定も決して悪くはありませんでした。自分がしたい学問分野に近い先生がいるか、定員数はどうか、センター試験最終年で多くの受験生が安全志向になっていること、これまでの模擬試験で記述式の試験の結果が良かったこと、あれこれ考えて決めていました。志望校を変更することを、親も先生も積極的には賛成していませんでした。色々な事情があるにせよ、これまで第一希望と考えてきたところを受けたほうが合格の可能性が高いと考えたからです。予備校の判定ももちろんそうでした。しかし、秋子は挑戦するほうを選びました。二次試験の手ごたえも、推薦入試のときよりいい感じでした。結果は不合格でした。センター利用の私大は2校合格していました。国公立大学の後期試験は願書を出していたものの「受けに行きたくない」と秋子は泣きながら私に訴えました。そんな秋子を説得して、秋子はともかく後期試験は受けに行きました。その時点で秋子は私大への進学をほぼ決めていたと思いますし、私もそれはそれでいいと考えていました。後期試験で不合格になる可能性ももちろんあったわけですが、後期試験で合格を勝ち取って大学受験を終わらせたかったのです。この時の秋子には逃げたい気持ちもあったでしょうから、それを克服してほしかったですし、「一人旅してくれば」というような気持ちも私にはありました。娘たち三人の大学受験はどれも大変でした。この4月、新型コロナウイルスの関係で大学は入学式を中止し、講義も一部オンラインのものを除き始まっていません。クラブやサークルなどもどうなるのかよく分かりません。大学に登校しないので大学の新しい友人もまだできず、家の周囲に知り合いもいない中で、三女は一人暮らしを始めています。銀行の口座を開いたり、いろいろな手続きをしたり、自炊なども頑張っているようです。生活費の多くをアルバイトで稼いでいた次女のアルバイトも、新型コロナウイルスの関係でなくなり、我が家の家計も心配です。次女と三女の大学生活が重なるこの2年を何とか乗り切らなくてはなりません。長女は実家から車で1時間弱のところに就職することとなり、長女への仕送りがなくなったのが救いです。2年以上更新していませんでしたし、書きたいことはたくさんあるのですが、今日のところはこの辺にしておきます。書き忘れていましたが、国公立大学の後期試験は合格でした。秋子の挑戦は、長い人生の中で必ず糧になると信じています。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ「介護の誤解」へ
2020.04.20
コメント(0)
-

子どもたちも大きくなりました (3)三女
子どもたちも大きくなりました。 三女の秋子は、高校1年生になりました。 私は子どもたちへの英語の早期教育は考えていませんでしたから、長女の春子、次女の夏子には、中学入学以前の英語教育はしていませんでした。 ただ、三女については事情が違いました。 小学校からの英語教育が必須となったからです。 三女は小さいころからコミュニケーション能力の高い子でした。 祖父母が近くにいてくれたことも関係しているかもしれません。 祖母に話しかける。同じ話を祖父がまた聞いてくれる。 たいていは私や妻にも話しているから、4度話すわけです。 家族で旅行に行ったときにも、知らない人に話しかけて友だちになっていたり。 幼稚園にあがる前後の話です。 この子のコミュニケーション能力を生かすためにも、そして、小学校で英語学習が始まった時に、得意意識を持たせるためにも、秋子だけは英語学習を少し早めに始めました。 小学校3年生から公文で英語だけ習わせたのです。 いや、4年生だったかな。 我が家の三人娘たちは、みな中学受験をしましたが、我が家の方針で、「塾には1年間」ということで、小学校5年生の冬休みから中学受験の塾に通いました。 三女の公文の英語はその間も続けました。 高校に入るころには公文の最終教材まで行き、英語の得意な子になりました。 現在では、かなり難関の大学も狙えそうな感じです。 娘が「あれはよかったと思う」と時々言うのは、「声に出して読みたい日本語」です。 2009年2月の記事「声に出して読みたい日本語」を書いていますが、毎朝子どもたちと10分程あれを音読したのです。 たくさんの名文の音の感触が残っているようで、特に古典の学習に生きているようです。 もちろん、国語の基礎力となっていることだと思うのですけれど。 ただ、数学や理科は少し厳しくなってきました。 私も妻も文系で(私は体育会系かな)、数学や理科の楽しさをうまく教えてやることはできませんでした。 長女の春子は理系科目があまり得意ではない「一応理系」に進みましたが、次女の夏子、三女の秋子は文系です。 いえ、秋子はまだ分かりません。 春子の大学生活を見ていて、「楽しそうだな、ああいうのもいいな」と感じるところもあるようで、また読書の趣味も春子と合うようで、理系の選択も全くないわけではありません。 文系理系という分け方で考えなくていいとも思っていますが。 英語を得意にしてくれた公文の先生方やそのシステムには感謝しています。 ただ、これもすべて順調だったわけではありません。 中学1年生の秋だったか、公文の先生から、「最近来ていないですけど、どうされましたか」と電話がかかってきたのです。 「えっ」と思いました。秋子はきちんと行っていたからです。 でも、私が間違っていました。 実は「行ってきます」と言って、行っていなかったのです。 どこかでさぼっていたのです。 どうやら1か月近く行っていなかったようでした。 もっと早く電話してほしかった、という気持ちもありましたが、1か月近く気づいてやれなかった自分も反省しました。 問い詰めたりはしませんでした。 妻にも問い詰めないようにと言いました。 子どもを育てていくというのは、本当に難しいものです。 でもそれも今では懐かしい。 三女の学生生活ももうしばらく続くけれど、長女は22歳、次女は19歳。 私の子育ても、いよいよ終盤となってきました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ「介護の誤解」へ
2017.12.26
コメント(0)
-

子どもたちも大きくなりました (2)次女
子どもたちも大きくなりました。 次女の夏子は、予備校に通っています。 もうすぐ2回目の大学受験です。 超難関校に挑戦しての浪人ではありません。 もちろん難関大学も受験していますが、昨年はのべ7校受験して全滅。 いわゆる「すべり止め」と考えた大学も受験しましたが、そこも不合格となりました。 なかなか甘くはありません。 浪人しても成績が伸びるとは限りませんが、夏子は高校3年生まで運動部を続けたので、浪人して成績が伸びる可能性もあると考えました。 が、これもそうは甘くありません。 都会の予備校に2時間近くかけて通っていますので、朝早くに出かけ、夜遅くに帰ってきます。 日によって違いますが、だいたい6時半に家を出て、夜の10時半に帰宅です。 夏子も頑張っています。 「大学受験に失敗する経験は、人生において大変貴重な経験となる」というようなことを心理学者の河合隼雄さんが何かに書いていたと思います。 浪人生活は決してマイナスにはならないと私も考えています。 でも、今年の受験もなかなか厳しい受験になるのではないかと思っています。 受験するのはすべて居住している県ではなく、県外ばかりです。 私にも妻にも、生まれ故郷を離れ外に出ていく血が流れているようですから、仕方ありません。 というより、子どもたちが小さいころから、「出ていったらいいよ」と言っていました。 寂しいけれど、夏子がこの3月に家を出ていけますように。 次女の大学生活はこれからだけれど、長女は22歳、三女は16歳。 私の子育ても、いよいよ終盤となってきました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2017.12.26
コメント(0)
-

子どもたちも大きくなりました (1)長女
5年半ぶりの更新です。 子どもたちも大きくなりました。 長女の春子は、大学4年生、来年4月からは某国立大学の大学院に進学します。 高校3年生の時に第1希望にしていたけれど、成績がとても届かなかった大学です。 春子はこつこつと努力できる子で、よく頑張ったと言ってやりたい。 高校3年生の時、第2希望の国立大学は、今から思えば推薦で出願していれば行けた可能性もありました。 でも、「安易に推薦で進学しない方がいい」という親の言葉を守って、一般受験して、センター試験でなかなか思い通りには点数が取れず、結局選択肢には入れていなかった大学に進学したのでした。 2009年1月の記事に「1に体育、2に音楽」を書いていますが、春子はその考えがうまく伝わった子でした。 中学では運動部でしたが特別運動能力が高いわけではありません。 でも遠くまで歩くような体力はあり、食事もしっかりしていました。高校では学習面での不安から音楽関係のクラブに入るのを我慢したようですが、大学では本格的な吹奏楽と楽しみ重視の音楽サークル両方に入り、楽しい大学生活を送りました。 食べることに関心が高い春子は、アルバイト先の料理屋でもかわいがってもらいました。 短期留学や研究のための海外経験もでき、いい4年間だったと思います。 春子が通ったのは北陸にある大学で、これまで縁のなかった北陸地方との縁ができ、家族にとってもいい4年間となりました。 私や妻も、どんよりした曇り空のイメージしかなかった北陸でしたが、食はここが一番と思えるほどの気に入りようになりました。 4年前、私の車一台に乗せられるだけの荷物で引っ越しをして、今日から春子の一人暮らしが始まるという日、3月といっても路上には雪が残り、大変寒い日でした。 「元気でやれよ。じゃあ行くよ。」と別れた時の寂しい気持ちは、自分が親元離れた時とは全く別物でした。 長女の学生生活はもうしばらく続くけれど、次女は19歳、三女は16歳。 私の子育ても、いよいよ終盤となってきました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2017.12.25
コメント(0)
-

お食い初め
家族6人そろっての夕食の時間に、「お食い初め」の話になりました。 我が家の居間には、お食い初めの時の写真が飾ってあるのです。 三女の秋子が1歳くらいでしょうか。 おじいちゃんが、秋子に魚を食べさせようとしていて、秋子はそれを食べようと口をあけている写真です。 おじいちゃんもおばあちゃんも嬉しそうな顔をしています。 「夏子のときだったかな。お食い初めの時に、よだれをだらだら流していて、ああご飯が食べたいんだな、ご飯を食べさせてあげないと」と思った、と妻が懐かしそうに言います。 春子、夏子、秋子と三人全員、お食い初めはしました。 そのおかげかどうかは分かりませんが、三人ともよく食べて、元気に育っています。 人生の中で、楽しいこともたくさんあったけれど、もう一回させてあげる、と神様が言ったとしたら、「では、子育ての経験をもう一度させてください」と言うでしょう。 やり直しをしたいというのではありません。難しいこともたくさんあったけれど、楽しかったし、幸せだったと思います。 子どもの成長を見るのは楽しいものです。 孫がかわいいというのもよく分かります。 でも孫は自分の子とは違いますからね。 可愛がり過ぎてしまわないように、気をつけないといけないかもしれません。 小さい赤ちゃんがいるママ、パパ。ぜひ「お食い初め」をしてあげてください。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2012.05.24
コメント(0)
-

PTA役員(3)
三女の小学校のPTA役員をすることになって読んだ川端裕人さんの『PTA再活用論』(中公新書ラクレ)には、興味深いことがたくさん書いてありました。 その一つは、PTAというのが、大人の学びの場として始まったということです。 終戦直後の1946年のことです。民主的な意思決定に慣れない成人(両親と教師)が、「両親と教師の会」(今のPTA)を通じて民主化するというシナリオがあったというのです。 PTA活動が「子どもたちのため」というのはすぐ分かると思いますが、「成人教育」という側面はあまり気付かないかもしれません。でも、「なるほど」と思います。 ただ、時代の流れでみんなが忙しくなっていることや、「これをやってみよう」「これもあったほうがいい」と新しい試みが積み重なってきたこと等が原因となって、「義務と負担と強制」の団体になってしまっているのも事実なのでしょう。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2012.05.18
コメント(2)
-

PTA役員(2)
「PTA役員って何をしたらいいの。」 「仕事を休まなくっちゃいけないの。」 次から次へと色々な疑問が頭に浮かび、不安が募ってきます。 夢の中で運動会のあいさつを考えています。 こんな状態で来年の会長が務まるのだろうか。 子育てや教育に関心があるとはいえ、学校行事の多くは妻に任せていたので、夏休みのプール当番のことなども、私はほとんど分かりません。 不安の多くは知らないことから来るのだと考えて、少しPTAのことを勉強しようと思いました。 「まあ、何とかなる」とはあまり思えないたちなもので。 そこで、まついなつきさんの『まさかわたしがPTA!?』(メディアファクトリー)を買って読みました。これはマンガなのですぐに読めます。PTA活動の苦労などが分かります。 そして、川端裕人さんの『PTA再活用論』(中公新書ラクレ)。これは、二度読みました。ほかにも何冊かのPTA関連本を購入して、不安を和らげようと努めました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2012.05.17
コメント(0)
-

PTA役員(1)
PTA役員をすることになりました。 三女が通う小学校のPTA本部役員です。 任期は2年。 ここのPTAでは、副会長のうち1人は次年度の会長となる副会長で、そのくじに大当たりしたというわけです。 くじを引いたのは妻です。2月に役員を決める会議に出て、青い顔をして帰ってきました。「当たっちゃった」と。そして、「やってくれない?」と。仕事の事情も家族の事情もありますが、「断れる雰囲気ではなかった」と。 正直私も不安でいっぱいでしたが、「会長なんてめったにできるものでもないからやってみよう」と考えました。 「妻が体調を崩すくらいなら私が体調を崩すほうがましかな」とも考えました。 結局私が引き受けたので、私は今も不安でいっぱいですが、妻はほっとしています。 「こんな時には1億円当たるかな」と妻は宝くじを買いに行きました。 当たりませんでしたけど。1万円しか。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2012.05.16
コメント(0)
-

俳句の練習(2)
俳句の練習、その2です。 子どもと公園に遊びに行って、子どもがぶらんこに乗り、その背中を押した。子どもが成長して、それも遠い日の記憶となってしまった。公園のぶらんこを前に、一人たたずむ。 ぶらんこや押す背も今はなくなりき 俳句の教えに「説明するな」というのがあるそうですね。あれこれ説明するようではいけないようです。 「ぶらんこ」が春の季語ですが、春の季語であり、子どもの遊び道具である「ぶらんこ」が持つ雰囲気と、子どもが成長して親の手を離れた寂しさとが合わなくてよくないのかもしれません。 素人が勝手に作って楽しむ分にはいいでしょうけれど、上手になろうと思ったら、やはり先生に教えてもらう必要がありそうです。 自分で勉強することも大事ですが、何でも上達するには先生の存在って大きいですね。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.11.06
コメント(0)
-

正倉院展
正倉院展に行ってきました。 9時からということで9時ちょうどに奈良国立博物館に着きましたが、すでに長蛇の列。入場券は持っていたので、すぐに並びましたが、それでも「ここから60分待ち」よりも、もう少し後ろのところでした。 実際には約30分待ちで、9時半頃には入場できました。 金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんそうのからたち)や、碧地金銀絵箱(へきじきんぎんえのはこ)などの宝物を見てきました。 今回は実は子どもを連れて行ったのではありません。 子どもを連れて来ていた家族も結構いました。 小さい子どもに一生懸命解説しているお父さんも見かけて、嬉しくなりました。 予備知識があるらしい中学生が、得意げにお父さんに解説している場面も見かけ、嬉しくなりました。 先入観かもしれませんが、来ている(「連れて来られている」かもしれませんが)子どもたちは、賢そうに見えました。 正倉院展は11月14日、月曜日まで、奈良国立博物館でやっています。 お子さんを連れて、いかがですか。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.10.30
コメント(0)
-

Z会について思う
通信添削のZ会は、よく知られています。 東京大学の合格者のうちのかなり多くがZ会経験者だともいいます。 うちでも小4の三女がやってみました。が、続きませんでした。 算数が難しいと思いました。 ほかの教科は自分で進めていけるのですが、算数は自力では難しい。 あれを自力でやっていける子どもなら、元々東京大学にいける力が備わっている、と思いました。 それか、お父さんかお母さんが上手に教えてあげたり、スケジュールをきちんと管理してあげられる余裕と能力がある、そんな家庭なのだろうと思いました。 私の知っている子で、国立大学の医学部を目指していて、合格しそうな子がいますが、彼も小学校時代にZ会をやったことはあると言っていました。しかし、続かなかったと。 問題もいい問題だと思いますし、きちんと復習できるような作りになっているのですけどね。 計画通りに進められないからといって、親ががみがみ怒ってばかりいては、いけませんものね。 友達と遊びながら学ぶことも多い、と自分に言い聞かせて、ほかの教材などで、ぼちぼち励ましながらやっていこうと思っています。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.10.21
コメント(0)
-

奈良に行ってきたよ
昨日、奈良に家族で行ってきました。 昨日10月10日は「東大寺ミュージアム」の開館の日でした。 9時半に開館で、その10分くらい前から並びました。 もちろん見てきましたよ、不空羂索観音像と日光・月光菩薩。 大仏殿も久しぶりでしたが、改めてその大きさを感じました。 大仏殿も大仏も。 南大門の仁王像もよかったです。 仏像の関係で一番印象に残ったのは、興福寺の国宝館です。 有名な阿修羅像や木造仏頭が素晴らしかったです。 今までにも何度か見たのかもしれませんが、あまり興味がなかったせいか、それほど見た記憶がありません。 楽しかったのは春日大社の萬葉植物園です。 三女の秋子と一緒に入ったからでしょう。 秋子は植物のことを私よりもよく知っていて、私にいろいろ教えてくれます。 でも、一番楽しそうだったのは池のコイにエサをやっていた時かな。 見ているこちらも楽しくなりました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.10.11
コメント(0)
-

ごんぎつねの彼岸花
「ごんぎつね」の作者である新美南吉が生まれ育った愛知県半田市の堤防が、彼岸花で真っ赤になっています。 「ごんぎつね」に彼岸花が登場する場面にちなんで、地元の人たちが20年ほど前に球根を植え、手入れを続けているものらしいです。 東西約1.5キロにわたって堤防が真っ赤になっていて、壮観です。約200万本の彼岸花なのだそうです。 我が家では、新美南吉の作品では、何といっても「手ぶくろを買いに」が思い出の絵本です。 以前書いた「手ぶくろを買いに」をどうぞ。 半田市岩滑(やなべ)の矢勝(やかち)川堤の彼岸花についての問い合わせは、新美南吉記念館(0569・26・4888)へ、と新聞にありました。 子どもを連れて見に行くのもいいですね。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.10.02
コメント(0)
-

写真を撮りに行く散歩
今朝は5時半に起きて、三女の秋子と写真を撮りに行きました。 5時45分に家を出て、6時半には帰ってこなくては、小学校に間に合いません。 車に乗っている時間が30分。写真を撮る予定のスポットは3か所。 昨日下見をしているから迷うことはないけれど、1か所あたり5分。 コスモス畑とアメジストセージと彼岸花の群生の3か所です。 コスモス畑に着いたころに日の出の時刻で、まず日の出を撮りました。 日の出の方向にはコンビニがあり、二台のトラックが止まっています。 秋子は日の出と人工的なトラックをセットで撮ろうというのです。 それも面白いなと思いました。 次はコスモス畑です。私はコスモス畑の全景と少しアップにしたものを撮りました。 秋子は下半分にコスモス畑、遠景に建物を入れています。これも意識して人工的なものを入れて、自然と人工を対比させているようです。 次はアメジストセージ、別名メキシカンセージという紫の花です。 私は例のごとく、一株全体を撮り、アップにして撮り……。 秋子は「生え際の茎のところが力強い」と言って生え際を中心に撮ります。 面白い目の付けどころだと思いました。 最後は彼岸花です。縦10メートル、横20メートルの彼岸花畑といった趣で群生しています。こんなに一か所にたくさん咲いているのは、このあたりでは目にしません。 撮った写真をアップしたら、もっといいブログになるのでしょうけれど。 予定通り6時半には帰宅できて、秋子はきちんと食事もして小学校に登校しました。 大人の常識で「こんなふうに撮るといいよ」とあれこれ言わなくてよかったと思っています。 「楽しかった。また行こう。」と秋子は言っていました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.09.30
コメント(0)
-

竹林がなくなる
近所の竹林が伐採されています。 長女の春子と10年くらい前に探検した竹林です。 あれは、春子が小学校1年生の頃だったでしょうか。 薄暗い竹林の中を、イノシシが出るか、ヘビが出るかと、びくびくしながら探検した竹林です。 イノシシが出るほどの竹林ではないのですけれど。 整地され、福祉施設か何かが作られるようです。 思い出の場所が一つなくなって、寂しい感じです。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.09.30
コメント(0)
-

俳句の練習
久しぶりにブログを見ました。 ちょうど1年ぶりでした。 少し俳句の練習でもしてみようかと思っています。 松尾芭蕉や正岡子規は好きですが、俳句を特別に学んだことはありません。 素人の気安さで書いてみようと思います。 もちろん子育てや子どもの成長を意識してですが、季節の移ろいを気に留めるだけでもいいかなと思っています。 玄関の外にポツンと置いてある一輪車が錆びている。 もうしばらく使っていない。 三人の娘たちそれぞれと一輪車に乗る練習をした日々が懐かしい。 家族の黄金期と考えている子どもの小学生時代。 三女が小4となり、その黄金期も残り2年余りとなった。 秋風や玄関わきの一輪車 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2011.09.29
コメント(0)
-

子育てと食事時間
子育てにとって、食事に時間をかけるのは大切なことです。 最近の傾向で、気になることがあります。 「面倒くさいからご飯はあまり食べない」という若者が増えていることです。おそらく男子に多いです。回りを見回してみると、思い当たる人が一人や二人いるのではないでしょうか。 「魚の骨を取りながら食べるのが面倒だ」とか「ブドウを一粒一粒食べるのが面倒だ」とか、そういうレベルではなくて、ご飯を食べること自体が面倒だと言うのです。 これも推測でしかありませんが、パソコンに向かっている時間の長い人に多いような気もします。 ここでいう食事の時間というのは、食事の準備、食べる時間、後片付けの時間も含めます。 アメリカでは平均して1日の食事時間が1時間を切ると聞いたこともあります。 パソコンに向かいながらハンバーガーやピザやポテトチップスを食べているイメージです。 コンビニができたことも一因でしょう。宅配ピザやファミレスが増えたことも一因でしょう。 「今日は手抜きしてファミレスで」とか、「弁当は作ってくれなくていいよ。コンビニで適当に食いたいもん買うから」というセリフがあちこちで吐かれていることでしょう。 生死に関わる「食」に関することを面倒だと感じる感性が広がってしまったのも、世の中が便利になったことと無縁ではありません。 食べるのが面倒で、子育てが面倒でないはずがありません。 少し前にあった幼児虐待事件の公判でも、父親母親から「自分のことを優先させた」「面倒なことから逃げていた」という言葉が聞かれました。 子育て中のママ、パパ、頑張って食べることに時間を費やしましょうね。 これから子育てに入る人、食事を面倒だと感じたら、便利な生活から離れてみることを一生懸命やってみるといいと思います。それがきっと子育てにつながります。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2010.09.29
コメント(0)
-

運動会の場所取り
「小学校の運動会の場所取り、今年は私が行く。」と長女の春子(中3)が言います。 「一人で3時くらいに行くわ。」と言うのです。場所取りですから、もちろん午前の3時です。 何を言い出すか分かりません。 ありがたい申し出ですが、中3の娘を夜中の3時に一人で場所取りに行かせるわけにはいきません。 「じゃあ、お父さんと一緒に行こうか。」ということで、長女と一緒に次女三女の小学校の運動会の場所取りに行くことになりました。 学校の規模がけっこう大きく、毎年熱のこもった運動会になります。 トラックの周囲の半分は児童の席と本部席、約半分が保護者の応援席です。 応援席は、地区ごとに場所が決められており、毎年一つずつずれていきます。 正門に近いほうの入り口と、正門から遠い入り口と、二か所に場所取りに来た人たちが並びます。私は毎回、遠いほうの入り口に並びます。 毎回と言っても、昨年は場所取りをしませんでした。 7時に門が開きます。一昨年の様子からすると、6時に並ぶのではすでに50人近く人がいて、いい場所が取れるとは限りません。3時に行けばさすがに一番でしょうが、5時過ぎに行くことにしました。5時半までに行けば、10番には入れるだろうと考えました。 私は5時に起きました。 春子も5時に起きました。 私の準備は顔を洗ってトイレに行って着替えるくらいですから5分ほどです。 春子はさすがに5分では準備ができません。10分くらいはかかります。 結局5時20分くらいに小学校に行って並びました。2番でした。前にはおばあちゃんが並んでいました。 場所を取るために敷くシートを持って。そして、小型のイスを持って。こんな時、小型の折り畳みイスは便利です。 春子にコンビニに食料の調達に行かせました。クリームパン二つと桃のジュース一つを買ってきました。パンを一つずつ、ジュースは半分ずつ飲みました。ジュースも二つ買ってくればいいのに、何を勘違いしたのか一つしか買ってこなかったので。 私はラジオも持っています。本も持っています。春子は何も持っていません。 私は前のおばあちゃんと時折話します。後ろの人にこの地区の応援席はどの場所かを尋ねたりします。 しかし、春子は黙って座っています。辛抱強いというか、することがなくて我慢できないということはありません。「iPodがあったらこんな時いいのに」と言っていましたが、持っていません。 小学校の先生方も6時前には準備を始めています。 7時前になると、係の先生が門のところに来て言います。 「入るとすぐに段差がありますから気を付けてください。毎年何人か転んでいますから。」 10秒前からはカウントダウンが始まります。 「10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、パーン」 スタート用のピストルが開門の合図です。 座っていたイスと敷くためのシートを持って走ります。リュックを背負っています。 トラックに近い一番前の席を確保できました。春子と一緒にシートを敷いて、イスをおもりがわりに置きました。 ビーチパラソルをセットする人も多いですし、校舎の近くの日陰になる場所を確保する人もいます。 1時間半、何をするわけでもなく座っていただけですが、ちょっと楽しい時間でした。 春子もちょっと楽しかったようです。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2010.09.23
コメント(0)
-

小学校での英語必修化
小学校での英語必修化についてどう考えますか。 「小学校 英語 必修化」で検索してみると、「小学校での英語必修化 あなたはどう思う? 英語タウン投票結果」がトップページの最初に出てきて、賛成47%、反対44%となっていました。 どちらの意見ももっともだと思うものの、私はどちらかと言えば反対です。 小学校での英語必修化については、1年以上前になりますが、「小学校での英語必修化 賛成? 反対?」で触れました。そこでも触れましたが、英語を学ぶことに反対なのではなく、小学校での必修化によるマイナスの面が心配と言う方が当たっているかもしれません。 最近、安河内哲也さんの『子どもを英語嫌いにしない11の法則』(学研新書)を読みました。 安河内哲也さんは、東進ハイスクール等の講師を務める「カリスマ講師」と呼ばれる人です。 この本の題からもうかがえるように、安河内さんは「子どもを英語嫌いにすること」を心配しています。私の周辺の様子からも、英語嫌いはすでに増えてきていると感じられます。そして、小学校での英語必修化が始まったら、ますます英語嫌いは増えると思われます。 「幼児・小学校の間は助走期間」だと安河内さんは言います。それだといいのですが、親や教師がついつい焦ったり、力が入りすぎてしまったりすることもきっと多いでしょう。中学から本格的な学習が始まった時に、「小学校の英語は楽しかったけど、中学の英語は楽しくない。英語が嫌いになった。」という生徒が続出することが予想されます。 文部科学省の狙っていること自体は間違っていないようにも思いますが、ゆとり教育がそうだったように、狙い通りにはおそらくいかないでしょう。 安河内さんの本には「まず日本語を豊かに育てる」のように、共感するところがたくさんあります。 「これから子どもの英語学習をどうしていこうか」と悩んでいる多くの方に、参考になればと思い、何回かに分けて、安河内さんの勧めを紹介します。 今回はその第1回です。 安河内さんは「小学校までは英語の種まき」と言います。 その「種まき」の一つとして英語の読み方の基本ルール「フォニックス」を導入するといいと勧めています。フォニックスを学ぶと、アルファベットの組み合わせによる発音の基本ルールが分かり、つづりを見ただけで発音できるようになると言います。 子どもと一緒に、ゲームのように楽しく繰り返すといいと思います。子どもを英語嫌いにしない11の法則価格:756円(税込、送料別) 「フォニックス」については、『英語のきほん フォニックス 発音のルール』(NiKK映像)などを紹介していますが、楽天ブックスでは品切れでした。「子育て応援広場」のほうでなら注文できます。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ「子育て応援広場」の『英語のきほん フォニックス 発音のルール』へ 前回「吉野の桜」で、「続きはまた今度」と書いていたのに、続きがなくてすみません。
2010.09.20
コメント(0)
-

吉野の桜
吉野の桜を家族で見てきました。 4月4日でしたので、まだ時期的に早く、下千本は6分から8分くらい咲いている感じでしたが、中千本や奥千本はまだまだでした。 朝の4時に家を出ました。 7時に下千本の駐車場が開くので、そのころに着くようにと思って出たのですが、6時30分ころに着きました。 途中田舎道を走りましたので、暗い中でシカに出会いました。 小鹿でした。道に迷って車道に出てしまった感じでした。しばらく私の車の前をうろうろして、林の中に逃げて行ったので、1分くらい見ていることができ、子どもたちも大喜びでした。 いえいえ、「子どもたち」ではありません。三女の秋子がです。 長女の春子はクラブの試合があって連れて行きませんでしたし、次女の夏子はぐーぐー寝ていました。「シカだよ。シカ、シカ。」と言っても、ぐーぐー寝ていました。 下千本の駐車場には係の人がいて、「ここは7時からだから中千本の駐車場に止めてもいい。9時にくらいになったらここから中千本への道はバスしか通れなくなる。」と言うので、「早く来てラッキー」と思って中千本の駐車場まで行き、そこに駐車しました。 中千本の駐車場から歩いて上千本、さらに奥千本の奥の方にある西行庵まで歩きました。 考えれば当たり前ですが、吉野山という山なので標高が高く、上のほうは結構寒いのです。到着した7時ころの気温は下千本あたりでも0℃でした。 77歳の私の母も一緒に行き、山道をたくさん歩かせてしまいました。 フランスのモン・サン・ミッシェルも母にとっては大変だったと思いましたが、吉野山を中千本から奥千本の西行庵までというのは、その何倍も大変でした。 今日はこの辺にして、続きはまた今度書きます。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2010.04.17
コメント(0)
-

山本潤子コンサート
山本潤子さんのコンサートに行ってきました。 私は体育会人間ですので、音楽界や芸能界にあまり縁がないのですが、ハイ・ファイ・セットは大好きでした。 山本潤子さんの生の声で「卒業写真」や「竹田の子守唄」や「翼をください」が聞ける。そんな機会があるとは思ってもいませんでした。 「十円木馬」「朝陽の中で微笑んで」などハイ・ファイ・セットの歌で私が好きな歌は、たくさんあります。 長女の春子がピアノで「卒業写真」を弾いているのを聞くと、懐かしさで胸が熱くなることさえあります。 ああ、いい一日だったなあ。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2010.03.13
コメント(1)
-

久々の更新です
ブログの更新ができずに1か月以上経ってしまいました。 病気をしていたわけではありません。 悠々と長期海外旅行に行っていたわけでもありません。 サボりといえばサボりです。 元々パソコンの前に座るのが得意ではない私のことです。 ブログを始めてから、紙の日記は書いていません。ブログに書くものと、日記に書くものとでは、おのずと違ってきますので、両方書けばいいのですが。 更新していなかった間は、紙の日記を書いていたかというと、サボっていました。 まあ、日記が長く続かないのは、よくあることですが。 これまでも、サボってはまた気を取り直して始め、またサボっては気を取り直して始め、の繰り返しです。 でも、更新していなかったのには、理由があります。 子どもと接する時間を確保するためです。 次女の夏子(小5)の勉強をみてやる時間はけっこうありました。 三女の秋子(小2)と散歩する時間もけっこうありました。 職場でもパソコンに向かっている時間が増えているので、あまりパソコン画面を見ている時間が長いのも問題あるかなという気がして。 そんなことは、ブログを始める前から考えていたことではありますが。 頻繁に更新できなくても、細々とでも続けていこうと思っていますけれど。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.12.08
コメント(0)
-

『間違いだらけの教育論』
『間違いだらけの教育論』(諏訪哲二、光文社新書)という本を読みました。 『声に出して読みたい日本語』の斎藤孝さんや、百ます計算などで有名な陰山英男さん、「ヤンキー先生」こと義家弘介さんの教育論を、バッサバッサと斬っていきます。 「まあ、そこまで言わなくても」と思えてくるほどです。 「歯に衣着せぬ」とはこういうことかと思います。 6章のタイトルを見ただけでも、その雰囲気が分かります。 6章のタイトルは、「義家弘介さんは典型的な自己チュウ教師だ(「ヤンキー」としての教育)」となっています。 8章で取り上げているワタミ社長の渡邉美樹さんについては、そのタイトルで「渡邉美樹さんは教育を経済で捉えている(「産業人」としての教育)」となっていて、私もそのタイトルのように考えていましたが、斎藤孝さんや陰山英男さんに対する諏訪さんのぶった切り方と比べると、諏訪さんはかなり渡邉さんを評価しているように感じられます。それでもやはり批判的ですけれど。 議論を正確にという気持ちからでしょうが、諏訪さんの文章はカッコが多く、豊富な語彙を駆使しているので、読みにくい印象を持たれる方も多いかもしれません。 それでも私は以前から諏訪哲二さんの言葉には耳を傾けるべきだろうと考えています。 「以前から」というのは、別冊宝島129『ザ・中学教師 子どもが変だ! 』が出た1991年からです。 この「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」でも「子どもたちの惨状」という記事で諏訪哲二さんの『オレ様化する子どもたち』(中公新書ラクレ)を紹介しています。 斎藤孝さんや陰山英男さんも、もちろん紹介していますけれど。 『間違いだらけの教育論』。 子どもたちの将来を左右する教育がどうなっているか。無関心ではいられませんね。間違いだらけの教育論 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.23
コメント(0)
-

「鉄道の駅まで歩く」の最終回
「鉄道の駅まで歩く」の最終回を今日してきました。 「鉄道の駅まで歩く」は、我が家の家族行事の一つで、私が子どもと二人で、最寄りの大きい鉄道の駅まで歩く行事です。 「歩け! 歩け! 」という記事で紹介しましたので、そちらも見ていただけるとうれしいです。 長女の春子(中2)も次女の夏子(小5)も、小学校の1年生か2年生の時にしました。 そして今日、三女の秋子(小2)としました。 片道約1時間45分です。 秋子は散歩が好きで、最近も私とよく散歩します。 秋子はおしゃべりなので、歩きながらでもずっと話をしています。 往復で3時間半くらいですので、たくさん話せました。 話題で多かったのは植物の話です。 私が教えるのではありません。 たいていは秋子が私に教えてくれるのです。 今の季節は、キンモクセイの甘い香りが漂ってくるところが多く、そこかしこでキンモクセイを見ました。 今回は駅の近くのたこ焼き屋で、お昼を食べてきました。 たこ焼きと焼きそばを食べましたが、たこ焼きが特においしくて、追加注文したので時間がかかり、9時前に出たのに帰ってきたのは午後1時半でした。 秋子には友だちと遊ぶ約束があったので、最後の1時間は何度か走りました。 これも私が走り秋子が追ってくるのではなく、秋子が走り私が追いつくという具合でした。 これくらい歩くのはへっちゃら、という感じでした。うれしいことです。 またしてもいいのですが、これで三人の娘たちそれぞれと駅まで歩きましたので、一応この行事は最終回ということになります。 楽しい4時間半でした。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.18
コメント(0)
-

MIND-子どもの心を育てるために
「Mind-子どもの心を育てるために」というサイトがあります。 「Mind-子どもの心を育てるために」を運営しているのは、高校教師をされている高橋健雄さんです。 「佐々木正美先生のコーナー」「子育て協会」「子育てと『しつけ』」など、子育てのヒントがたくさんあります。 佐々木正美先生は、子育て中の方や、これから子育てされる方たちに、私が最もおススメしたい先生です。 この「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」でも、「おしっこが青い? おむつの話」や「読書案内(1)」などで、佐々木正美先生の本には触れてきました。 「Mind-子どもの心を育てるために」というサイト、子育てのヒントをきっと与えてくれると思いますよ。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.17
コメント(0)
-

新聞を読もう
子育てに新聞が必要か、と思われるかもしれませんが、子育てに新聞は必要だと思います。必要と言わないまでも、あったほうがいいです。 インターネットの普及に伴って新聞を取らない家庭が増えているとか。 「ニュースはネットで見たい時に、興味のあるニュースだけを見るほうが効率的だし、経済的だし」ということでしょうか。 確かにそのほうが効率的で、経済的かもしれません。 しかし、親が新聞を読む姿を子どもに見せ、子どもにも小さいころから新聞に親しませるのは、子育てにとって意味あることだと思います。 活字に親しむことができるかどうかは、子どもの知能の発達に決定的ともいえるほどの差を生むのではないでしょうか。 絵本などの読書とはまた別の意味を新聞は持っています。 月々の数千円をけちって、子どもの将来の可能性を狭めてしまっては、「幸せな子育て」からは遠いと言わざるを得ません。 新聞を読む人が減り、日本人全体の知的レベルが下がる傾向が残念ながら進んでいくような気がして心配です。 大げさでしょうか。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.10
コメント(0)
-

台風に備えた つもりだったのに
台風18号の接近に伴って、「備えはもうすみましたか。」「備えをしておく姿勢を子どもに見せるのは、子どもの教育にとって、意味のあることのように思います。」と前回の「台風接近中 備える姿を子どもに見せる」に書きました。 昨晩、台風18号の暴風圏に入り、20分か30分ほどですが停電しました。 妻と三女はもう寝ていました。 長女は子ども部屋で勉強していました。 母と私と次女は、母の部屋で「女性版SASUKE」を見ていました。 いよいよ残った3人が最終ステージに挑戦し、完全制覇なるか、という時に、ブチッとテレビが消え、家中の電気が消えました。 真っ暗な中、母はいつもの通り食器棚に置いてあった懐中電灯を、なんなく取り出しました。 その懐中電灯の明かりで、私の寝室に置いてある懐中電灯を取りに行きました。 「懐中電灯はもうないかな。」と言う私の言葉に、「あっ、あそこにある。」と次女は、どこからか自家発電できる電池不要の懐中電灯を持ってきました。 そして、ろうそくをつけました。 私は非常持ち出し袋にしているリュックサックから携帯ラジオを取り出そうとしましたが、見つかりません。 しばらくすると、私の寝室に置いてあった懐中電灯の明かりが弱くなってきました。 電池がなくなってきたのです。単一の電池を4つ使うタイプの懐中電灯です。 「非常持ち出し袋の中に電池もあったはずだ」と思い探しましたが、単二電池が二つしかありません。 他にもすぐには持ち出さない非常用品を入れた段ボールがあるので、そちらを見に行きましたが、単一の電池は一つもありませんでした。 台風に備えたつもりでしたが、備えは少しも万全ではありませんでした。 真っ暗な中、すぐに懐中電灯を取り出した母は立派でした。 電池不要の懐中電灯のありかを覚えていて取りに行った次女も立派でした。 「備えはもうすみましたか」の私の備えは、不十分でした。トホホ。 今日になってリュックサックをもう一度見てみると、携帯ラジオは、リュックサックの脇のポケットにありました。 30分ほどの停電でしたが、少し家族に緊張が走り、ろうそくの明かりに頼り、いい時間でした。 被害のあった方もいらっしゃるので、言いにくいですが、私の周辺に関して言うと、幸い大きな被害はありませんでした。 まだこれから台風の影響を受ける地域の方、懐中電灯の電池は大丈夫ですか。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.08
コメント(0)
-

台風接近中 備える姿を子どもに見せる
台風18号が、明日10月8日(木)に近畿から東海にかけて接近上陸しそうです。 備えはもうすみましたか。 NHKのニュースを見ても、風や雨が激しくなってから屋外に出るのは危険なので、その前に植木鉢を移動させるなどの備えをするように勧めています。 植木鉢ではなかったかな。 風に飛ばされそうなものを、室内に移動させたり、低い位置に置いたりということです。 ろうそくやラジオ、懐中電灯、乾電池などの備えはできていますか。 世界的に異常気象が目立つようになってきて、日本でもゲリラ豪雨が時々あります。 ゲリラ豪雨に襲われたら、道路が寸断されたりして、食料や日用品が手に入らなくなる危険性もあります。 道路寸断の可能性のある地域に住んでいる場合は、食料や日用品の備えもしておいたほうがいいかもしれませんね。 以前のように停電したり断水したりということは、めったにないでしょうけれど。 でも、もし電気が来なくなったら、水道の水が来なくなったら、ガスが来なくなったら、と想像して、備えをしておく姿勢を子どもたちに見せるのは、子どもの教育にとって、意味のあることのように思います。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.07
コメント(0)
-

台風接近中 早めの備えを
非常に強い台風18号が、接近中です。 私は気象に詳しくはありませんが、知り合いの話では、規模も50年前の伊勢湾台風に近く、進路も伊勢湾台風に近いから、大変な被害が出るかもしれない、とのことです。 気象庁は暴風や高波への厳重な警戒を呼び掛け、7日中に避難経路の確認など防災準備を、と言っています。 小さいころに床上浸水を経験しました。 畳が濡れてしまわないように、父が畳を高い所に移していました。高いところといっても、2階はありませんでしたから、テーブルの上だったような気がします。 床下の水位がじわじわと上がってきて、恐怖を感じたのを覚えています。 でも、ああいう一種の危機の場面の父は、頼りになってかっこよかったな。 世の中が豊かになったり、便利になったりして、かっこいい父親の姿を見せる場面が減ったように思います。 そのことも、子育てにとっては向かい風です。 ともあれ、明日中にできるだけの備えをしておかなくては。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.06
コメント(0)
-

うれしい一日
今日はうれしい一日でした。 いいことが3つありました。 一つ目は、朝食を長女が準備してくれたこと。 ピザトーストやサンドウィッチ、スープも準備してありました。 昨晩、「明日は私が朝ごはん準備するよ。」と言っていた長女は、朝6時前に起きてスープもあとはお湯を注ぐだけ、というところまでしっかり準備していました。 今日はみんなゆっくり寝ていて、家族が起きてきたのは9時くらいでしたけれど。 みんなが起きてきたらすぐに作れるようにと、準備していたのには感心しました。 準備した後、二度寝していましたが。 二つ目は、三女と散歩に行ったこと。 近所をぐるっと回ってくる散歩コースですが、途中公園のブランコに乗って、いろいろ話ができました。 「タバコは体に悪いのに、どうして売っているのかな。」 これは長女も何年か前に私に聞いてきたことです。 三女は、絵本の中にあったその問いに対する一つの答えを私に話してくれました。 三女の能弁ぶりにはいつも感心します。ただのおしゃべりかな。 三つ目は、家族みんなで包んだギョーザを晩ご飯に食べたこと。 我が家ではよくギョーザを100個作り、ホットプレートで焼いて食べます。 ギョーザを包む家族の時間も楽しいひと時です。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.04
コメント(0)
-

読書案内(9)
子育ての本や、読み聞かせの絵本などで、これまでに触れてきたものを振り返る、読書案内の9回目です。 読書案内では、5冊ずつ振り返っています。番号は、これまでの通し番号です。 これまでは、著者名、書名、出版社の順で書いていましたが、今回は、書名を最初に書くようにします。41 『英語はいらない!? 』(鈴木孝夫、PHP研究所)42 『僕たち、どうして勉強するの? 』(古市幸雄、マガジンハウス)43 『勉強する理由』(石井大地、ディスカヴァー)44 『日本で一番わかりやすい体育の本 かけっこが速くなる! 逆あがりができる! 』(下山真二監修、池田書店)45 『赤ちゃん学を知っていますか? 』(産経新聞「新・赤ちゃん学」取材班、新潮文庫) 41の『英語はいらない!? 』は、「小学校での英語必修化 賛成? 反対? 」で触れました。反対派の鈴木孝夫さんの著書です。藤原正彦さんら反対派の主張のほうに、より説得力があるように思います。 42の『僕たち、どうして勉強するの? 』と43の『勉強する理由』は、「僕たち、どうして勉強するの?」で触れました。『勉強する理由』では、「『役に立つかよくわからない』学部と『すぐに役立つ』学部との間には深い断絶がある」というところが特に印象に残っています。「僕たち、どうして勉強するの?」では、「小学校での英語必修化」についても改めて触れていますので、是非読んでみてください。 44の『日本で一番わかりやすい体育の本 かけっこが速くなる! 逆あがりができる! 』は、「逆上がりができる」で紹介しました。子どもに自信をつけさせる一つのきっかけが逆上がりや一輪車です。逆上がりやかけっこを子どもに教えるコツが分かります。 45の『赤ちゃん学を知っていますか? 』は、「赤ちゃん学を知っていますか? 」で触れました。2002年に産経新聞に連載された「新・赤ちゃん学」をまとめたものです。6年経っていますので、最新とはいきませんが、赤ちゃんに関する研究の成果が分かります。 42 僕たち、どうして勉強するの?43 勉強する理由44 かけっこが速くなる!逆あがりができる!45 赤ちゃん学を知っていますか? 41の『英語はいらない!? 』は楽天ブックスでは売り切れです。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.10.03
コメント(0)
-

『勝てる子供の脳』
『勝てる子供の脳―親の裁量で子供は伸びる』(吉田たかよし、角川書店)という本を読みました。 著者の吉田たかよしさんは、NHKのアナウンサーとして活躍された後、医師免許を取得され、現在は学習医学を応用した受験生外来のクリニック「本郷赤門クリニック」の院長として受験生とその親に勉強法の指導をされています。 吉田さんの勧めている学習法の一つが「プレゼン勉強法」です。 親に向かって何かを話す、という勉強法です。その効果や実施する際の注意点なども教えてくれます。 ごく簡単に言うと、ネタを集める過程で知識が増える、ネタ集めをする姿勢が身に着く、話すために考えをまとめる訓練になる、などの効果が期待できます。 子供がそれを嫌がることは、当然予想されるので、まず「名詞を答えさせる」という段階から始める、というように、具体的なやり方も教えてくれます。 吉田さんが勧めている勉強法のもう一つは「歩きメデス勉強法」です。 「歩きながら勉強しましょう」ということです。 「できるだけ子供と散歩をする機会を増やして、歩きながら話しかけるのが脳の発育にとっては効果的」と言います。 「そもそも、街を歩くという行為自体が、ものすごく勉強になるものです」とも言っています。 この「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」でも、「散歩のすすめ」は、何度もしています。「散歩のすすめ(1)」「散歩のすすめ(2)」「『春を見つけに』 子どもとの散歩」や「歩け! 歩け! 」などの記事を読んでいただけるとありがたいです。 「街を歩く」についても前回の「街へ出よう」などで触れてきました。 『勝てる子供の脳』では、「メディアが脳に及ぼす影響」などにも触れています。 子供の幸せのために、一読の価値があると思います。勝てる子供の脳 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.29
コメント(2)
-

街へ出よう
子どもたちを街へ連れ出すことはいいことだと思います。 あれこれ言わなくても、子どもたちは世の中の何かを感じ取ります。 シルバーウィークは、特に家族そろってのお出かけはしませんでした。 でも、小5の次女と小2の三女を連れて、一度だけ街に出ました。 街に出たといっても、実際には牛丼の吉野家に行ったのです。 学生時代にはお金がありませんでしたから、安く食事ができる大学の学食や吉野家でよく食事をしました。 休日の朝といっても、吉野家で働いている人もいるし、これから働きに行きそうな人もいるかもしれないし、これからお出かけの人もいるかもしれないし。 娘たちが大きくなって吉野家に行く可能性はあまり高くはないでしょう。 吉野家のお客さんで女性は圧倒的に少ないはずです。まして一人で来ている女性となるとほとんどいないのではないでしょうか。 客は断然男が多い。おそらく一人で来ている男性が多い。 そういうところを、今のうちに見せておこうと思ったのです。 実はその前日に朝早く吉野家に行く機会があって、子どもたちを連れてこようと思い立ったのです。ちなみに店員さんは2人いましたが、どちらも女性でした。 休日の朝早くに連れ出すために、少しゲーム感覚を取り入れました。 7時過ぎに家を出て7時半くらいに吉野家に着く。その時、お客さんが何人いるかを当ててみよう、というゲームです。 カウンター席が15席位、4人座れるテーブル席が2つあるということは、子どもたちに教え、予想をさせました。 次女の予想は4人、三女の予想は3人でした。 実際には12人のお客さんがいました。 私は納豆定食。子どもたちは焼き魚定食。どんぶり飯は食べきれないだろうと思い、子どもたちのご飯は半分にしてもらいました。 子どもたちは全部きれいに食べました。 実はもう一つ子どもたちに言っていたことがありました。 それは、私たちがお店に入る前にいるお客さんが、食事の後どこへいくのかを想像してみようということです。 私の人生がかけがえのないように、他人にもかけがえのない人生があるということを、子どもたちがいつか感じとってくれたら、という願いがあるのです。 私の頭には、写真家の星野道夫さんのことがありました。 一枚の写真から、アラスカで生きている人たちに思いをはせて、アラスカにわたって活動した星野道夫さんです。 もちろん、私が望んでいるようにはならない可能性も大です。 でも、いいんです。 もし、次女か三女が「小さい時、お父さんと吉野家に行ったよね。なぜ休みの日の朝早くに吉野家に行ったのだろう。」と考えてくれたり、他人の人生に思いをはせ、他人も自分と同じように大切に思えるようになってくれたりしたら、うれしいです。 結果はどうなるか分かりませんが、楽しみです。 「みしのたくかにと」です。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.23
コメント(0)
-

熱性けいれん 泣き入りひきつけ
先日ラジオで「熱性けいれん」についての話をしていました。 ラジオをつけたら途中でしたので、どんな話だったか詳しくは分からないのですが、最後に「子どもが熱でけいれんを起こしても慌てないことが大事ですね。」とまとめていました。 しかし、子どもがけいれんしているのに慌てないでいるなんて、普通はできないのではないでしょうか。 我が家では長女が2歳のころに、「泣き入りひきつけ」を起こして慌てたことがありました。何かがきっかけで大泣きし、泣いて泣いて泣いて、息をはききって息がとまり、顔が紫色になって、ぐったりして、ひくひくとけいれんしました。 私はもちろん大慌てで、子どもの意識を戻そうと、抱っこしたまま、必死に長女の名前を呼びました。 「ああ、死んでしまうかもしれない。」と思いました。 長く感じましたが、おそらく1分弱だったのではないでしょうか。 「泣き入りひきつけ」というのは、その後に知りました。 「憤怒けいれん」とも言うそうです。 普通は1分から2分でおさまり、たいていは後遺症などの心配もいらないようです。 「熱性けいれん」を調べてみると、けいれんが15分以上と長かった場合や、けいれんに左右の差があった場合など、いくつか心配な場合もあるようで、そのような場合には、脳波検査などを受けるのがいいようです。 「熱性けいれん」にしても「泣き入りひきつけ」にしても、そういうものがあると分かっていても、慌てずにはいられないと思います。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.22
コメント(2)
-

幸せな子育てを実践している加藤さん
ご近所に住む加藤さん一家を見かけると、「幸せな子育て」を実践されているなと感心します。 加藤さん一家には、小学校6年生の女の子を筆頭に3人の子どもがいます。 幸せそうなのは、まず、ご主人がよく子どもたちと遊んでいることです。 遊んでいるだけではありません。夏休みの盆踊りのときなどは、踊りの輪に入って、子どもたちと一緒に踊っていますし、盆踊りの練習会にも行くほどです。 「幸せな子育て」かどうかの私の判断の一つは、子どもが不機嫌そうな顔をしていないかどうかです。 加藤さん一家の子どもたちは、いつ見ても機嫌がよさそうです。 先日加藤さんの奥さんについての話を耳にしました。 奥さんは「子どもが元気でいてくれたらそれでいいじゃないの。大人があれこれ心配ばかりしていたら、子どもたちが大人になりたくないと思ってしまうじゃない。大人が楽しそうにしていなくちゃ。」と言っているというのです。 そういえば、加藤さん一家は、子どもたちもですが、ご主人も奥さんも楽しそうにしていることが多いです。 元々の性格の明るさもあるのでしょうけれど、心がけてもいるのですね。 前回の「幸せなお母さん」でも触れた「死から考える」を実践しているようです。 こんな家族が増えたらいいな、と思います。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.21
コメント(0)
-

幸せなお母さん
「朝日おかあさん新聞」というのがあります。 あまり注意していなかったので、月に一度なのかどうかよく分かりませんが、「2009年9月号」とありますから、月に一度なのでしょう。 「朝日小学生新聞」に入っていました。 今日の一面の記事は、「『いいお母さん』より『幸せなお母さん』」という記事でした。 ノンフィクションライターで、自己尊重トレーニングトレーナーの北村年子さんのお話です。 北村さんの勧める「親も子もハッピーになれる魔法の呪文」をお教えしましょうか。 それは、「まぁ、いいか」です。 親はどうしても子どもの悪い面ばかりに目が行きがちで、「何やってるの」とか「早くしなさい」とか、言ってしまうものですが、そんな時に「まぁ、いいか」と口に出して言ってみるのです。 子どもにどのように声をかけるかは、子育てにとってとても大事です。 これはこの「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」の初めのほうで触れた「死から考える」に通じるように思います。 「死から考える」というと、すごく重々しい感じがしますが、要は「子どもが元気に生きていてくれることがありがたいことだ」という気持ちで、子どもに接するということです。 北村年子さんには、『子どもを認める「ほめ方・叱り方」』(PHP研究所)などの著書があります。私はまだ読んでいませんが。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.20
コメント(0)
-

『子育ての鉄則』
『子育ての鉄則』(星幸広、大修館書店)という本を読みました。 星幸広さんは、元警察署長で、現在は千葉大学大学院講師を務めていらっしゃいます。 大学では「学校危機管理」の講義を担当していらっしゃるそうです。 それで、この本でも「はじめに」として「『危機管理』としての子育て」を説いています。子どもが非行に走ったり、子どもが犯罪に巻き込まれたりすることを「家庭の危機」ととらえるのです。 多くの少年犯罪に関わってこられた星さんならではの視点です。 内容は、子どものほめ方・叱り方、幼稚園や学校との付き合い方などです。 ケータイ・ゲームの与え方、子育てのための家庭作りなどもあります。 特に印象に残っているのは、「子どもと一緒に詫びる方が効果的」というところです。 「うちの子のどこが悪かったんですか」と学校の先生にくってかかるような「闘う親」より、「ウチの子が本当に申し訳ありませんでした」と「詫びる親」のほうが効くのだ、ということです。 我が家でも、長女が小学校2年生の時に、傘を振りまわしていて止めてあった自動車に傘が当たって傷を付けたかもしれないということがあり、私が長女と一緒に謝りに行ったことがありました。その時のことは、「子どもが問題行動を起こした時」で紹介しました。 「ケータイ・ゲームはルールを作ってしっかり守らせる」。これはこの本の帯にもあるのですが、よく言われることですね。私はケータイ・ゲームについては警戒心が強いです。 「脳内汚染」で少し触れましたが、自分の意志ではやめられなくなることも多く、結局「どうして約束が守れないの」と怒る羽目になってしまう危険性が高いと思います。 子どもをケータイやゲームから完全に引き離すことは難しいにしても、少しでも時期を遅らせ、なるべく接触時間を少なくする。そのことに、かなりの神経を使うべきではないかと考えています。 『子育ての鉄則』。読んでみてはいかがでしょうか。 「幸せな子育てのヒント」がたくさんありますよ。子育ての鉄則 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.12
コメント(0)
-

巨峰の食べ放題
我が家には多くの家族行事があります。 これまでにも「パパとデート」や「過激な家族行事 断食」などを紹介してきました。 夏休みも終わりに近づくと、「ああ、とうとう夏休みも終わってしまう」と、残念な気持ちになるものですが、その頃のお楽しみがあります。 それが「巨峰の食べ放題」です。 これは6年ほど前から毎年続いている恒例の行事です。 現在は同居している私の母が、毎年8月の終わりになると、以前住んでいたところに、巨峰を買いに行くのです。8月も終わりごろになると、巨峰が安くなります。 安くなるといっても巨峰ですから、それなりの値段がしますけれど。 巨峰を10kg買って送るのです。 10kgといったら結構な量です。 翌日には宅配便で届けられます。 その日の晩に「巨峰の食べ放題」をするのです。 一人ひと房ずつ食べます。 母は一度にひと房も食べきれません。 妻も「無理して食べてももったいないから」といって半分は残しておきます。 三女の秋子(小2)もまだひと房全部は一気に食べきれません。 私と長女の春子(中2)と次女の夏子(小5)は、一気にひと房食べます。 ぜいたくなことです。 思いっきり食べるのは、その一日だけですが、10kgあると、しばらくはたくさん食べられます。 夏の終わりの楽しい家族行事です。 今年もいつものように「巨峰の食べ放題」をしました。 おいしかったー。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.11
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(10)
ヨーロッパ家族旅行も7日目。いよいよ帰国です。 朝パリのホテルを出て、バスでシャルル・ド・ゴール空港へ行きます。 飛行機でドイツのフランクフルトまで飛び、日本行きの飛行機に乗り換えです。 行きは日本からの直行便でしたが、帰りは直行便ではないのです。 それも子どもたちには、いい経験でした。 空港での手荷物検査や出国検査などは、子どもにとっては緊張するものです。 便利で何でも簡単にできるような感覚になりやすい現代の子どもたちには、いろいろな不便や手間を味わわせてやりたいものです。日本の便利さや快適さが当たり前ではないのだということを、感じさせる機会を少しでも多く持ちたいです。それが「幸せ」への一つの方法だと思います。 行きは12時間半のフライトでしたが、帰りは風の関係で11時間半くらいです。 機内のビデオは行きのものと同じプログラムです。 三女の秋子(小2)は喜んでビデオを見ています。普段はテレビを見る時間をけっこう制限していますが、機内ではそれほど制限しませんでしたので、たくさん見ていました。 機内食を食べているか、寝ているか、ビデオを見ているかです。 新聞や雑誌を読んだり、音楽を聴いたりということもありますが、まあ、ほとんどの人が同じように過ごしています。 妻は「パリがよかった。また絶対来る。」と張り切っています。 長女の春子(中2)と次女の夏子(小5)も、「パリがよかった。」と言っています。こちらは、もう少しお土産屋さんでゆっくり買い物がしたかったようです。 芸術や海よりも山が好きな私は、天候には恵まれなかったものの、スイスの山の空気がよかったです。 私の母は、あの高さまで登ったのだという達成感がよかったようで、「モン・サン・ミッシェルがよかった。」と言います。 そして、三女の秋子に今回の旅行でどこが一番良かったかと尋ねたら、「うーん、飛行機の中かな。」だって。 がっくり。 そうは言いましたが、いい経験にはなったはずです。 飛行機も日本の空港に着陸態勢に入りました。 「さあ、いよいよ着陸だ。」と思った瞬間、飛行機は上昇を始めました。 これまで10数回、もしかしたら20回以上飛行機に乗っていますが、着陸をやり直すのは初めてです。 「○○のために着陸をやり直します。」というアナウンスがありました。 何かトラブルがあったのかと緊張します。「○○」の部分もきちんと言っていましたが、忘れてしまいました。 上空をしばらく旋回したのでしょうか、何分かして再度着陸態勢に入りました。 「頼む。無事着陸してくれ。」と祈りました。 今、こうしてこれを書いているのですから、無事着陸できたわけですね。 秋子の怪我や夏子の鼻血に始まった今回のヨーロッパ家族旅行も、こうして無事帰国することができました。 「珍道中」でしたが、いい経験になりました。家族の楽しい思い出が一つ増えました。 楽しい思い出を確かなものにするためのアルバムも作りました。 何度も何度もそのアルバムを見ています。 これからも何度も見るでしょう。 ノイシュバンシュタイン城のおみやげに買ったスプーンも、アイスを食べたりするときに使っています。もちろん、家族そろってアイスを食べ、旅の思い出話もしながら。 上の写真は、ノイシュバンシュタイン城のすぐ横にある、ホーエンシュバンガウ城(ドイツ)です。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.08
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(9)
ヨーロッパ家族旅行も6日目です。 7日目には飛行機に乗り帰国の途に着きますから、実質上の最終日です。 「西洋の驚異」と称される巡礼地、モン・サン・ミッシェルです。 上の写真が、モン・サン・ミッシェルです。 パリから約370kmあります。バスで5時間半かかりました。 「右手に見えてきました。あれがモン・サン・ミッシェルです。」と添乗員さんが教えてくれてから、30分以上はかかったでしょう。近くまで行ってから渋滞が大変だったのです。 それもそのはず、添乗員さんが「僕は30回くらい来ていますが、こんなに混んでいたのは初めてです。」と言うくらい、大勢の観光客で賑わっていました。 いろいろなショップが立ち並ぶ修道院への参道「グランド・リュ」も大混雑。大晦日の明治神宮のような感じです。なかなか前へ進めません。 到着が午後1時くらいだったので、早速名物のオムレツを食べました。シンプルなふわふわのオムレツです。 修道院の中では、付属の教会や僧侶たちの仕事場である「騎士の部屋」、瞑想の場である「回廊」などを見て回りました。 修道院までの参道も、修道院の中に入ってからも、階段が多く大変でしたが、子どもたちも私の母も、元気に上りました。 行きも帰りもトイレ休憩が大変でした。 サービスエリアが少ないので、観光客がどっと押し寄せるのです。日本のように広くはなく、トイレの数が限られているので、長蛇の列です。男性用のほうも女性が使わないと、女性の列は少しも短くなっていきません。 「行けるときにトイレに行っておかなくては」とか、「トイレに行きたくならないように水分を控えよう」とか、子どもたちも子どもなりに考えているようでした。 モン・サン・ミッシェルにいたのは約3時間。午後4時過ぎに出て、パリにもどったのは9時を過ぎていました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.07
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(8)
ベルサイユ宮殿へのオプショナルツアーは、集合時間に何とか間に合いました。 ヨーロッパ家族旅行の5日目の午後は、フリータイム。本体のツアーから離れて、別の会社のオプショナルツアーに参加して、ベルサイユ宮殿に向かったのでした。 ルーブル美術館のすぐ近くのマイバス社を2時少し過ぎに出ました。バスに乗ること約40分、世界遺産のベルサイユ宮殿に到着しました。 ガイドさんは、京都に3年ほど留学したことがあるというフランス人の男性でした。 ここでも切符を買う人の長蛇の列です。(「ここでも」というのは、エッフェル塔やオルセー美術館にも長蛇の列ができていたからです。そのことについては、これまでに書いていませんけれど。) しかし、団体客は別の入り口から入ります。待ち時間はありますが、それほど長くはありません。10分ほどです。 バスの中で渡された無線のイヤホンで、ガイドさんの案内を聞きます。 見学はヘラクレスの間から始まります。ヘラクレスを題材にした絵が描かれた天井を見上げます。そして、ルイ16世とマリー・アントワネットの婚礼が行われた王室礼拝堂を見ます。 見学は順路に従って、ヴィーナスの間、マルスの間、メリクリウスの間と続きます。 どの部屋も混雑しています。三女の秋子(小2)と私の母が迷子にならないように注意しながら、それぞれの部屋で豪華な内装を写真に撮りました。 ふと気がつくと、イヤホンからのガイドさんの声が小さくなっていました。 妻は近くにいます。母もいます。秋子もいます。しかし、ガイドさんや一緒に来た人たちは見当たりません。あわてて、次のアポロンの間、戦争の間に行きましたが、イヤホンから聞こえる声は小さくなるばかり。 迷子になりました。 長女の春子(中2)と次女の夏子(小5)の姿は見えません。夏子が泣いている姿が頭をよぎりました。「ガイドさんと一緒にいろよ。」と祈りました。 どんどん先を探していくと、とうとう出口に出てしまいました。 イヤホンからは時々ガイドさんの声が聞こえてきます。 一本道のような順路ではぐれるのもおかしいと思い、出口から係の人の制止を振り切って、私ひとり逆に戻って行きました。しかし、すぐにまた出口に戻り、出口を出たところで待つことにしました。そこに出てくるでしょうから。 待つこと約10分。イヤホンから聞こえるガイドさんの声が少し大きくなりました。 私が出口から建物の中をのぞくと、ガイドさんの近くを歩く夏子が笑って手を振っています。 「どこ行ってたの? 」 「迷子になっちゃって。」 夏子も春子もケロッとしていました。ちゃんとガイドさんに着いて見学していました。 ベルサイユ宮殿の見学の順路は、コの字型の回りをぐるっと回るような感じなのですが、コの字の右側の部分が有名な鏡の回廊で、その次の見学場所である王の寝室は、コの字の内側に入っていくような感じなのです。(分かりにくいと思いますが。) 私はあわてて王の寝室を見ないで、次の順路のほうを探しに行ってしまっていたようです。春子と夏子は少しもあわてることなく「ガイドさんに着いていけば大丈夫」と落ち着いていたそうです。 子どもの成長を感じた「親のほうが迷子になったベルサイユ宮殿」でした。 上の写真はベルサイユ宮殿の「鏡の回廊」です。マリー・アントワネットとルイ16世の婚礼舞踏会が開かれた場所です。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.09.05
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(7)
「えー! 間に合いません! 」 驚いたのは添乗員さんだけではありません。私たちも焦りました。 ヨーロッパ家族旅行の5日目。午前のセーヌ川クルーズを終えて、エスカルゴの昼食を食べにレストランに着いたときに、どうも様子がおかしいぞと感じた私が「13時45分にマイバス社に行きたいのですけれど。間に合いますか。」と尋ねたときの焦りは今もよく覚えています。この日の午後はパリでのフリータイムです。 ここでは本体のツアーから離れて、別のオプショナルツアーに参加してベルサイユ宮殿に行くことになっていました。ルーブル美術館のすぐそばの「マイバス社」に13:45に集合です。集合時間に間に合うか心配だったので、旅行前に確認していましたが、昼食、解散は三越になるだろうとのこと。三越をパリの地図で調べてみるとルーブル美術館からそれほど遠くありません。集合場所のマイバス社まで歩いて5分、ゆっくり歩いても10分ほどだろうと見当をつけていました。 ところが当日、セーヌ川クルーズを終えて昼食に向かう私たちのバスは、ルーブル美術館をどんどん離れていきます。しかし、パリの地理に明るくない私は、どちらの方角に向かっているのか分かりません。不安を覚えながらも添乗員さんに聞けずにいました。 レストランに到着して初めて添乗員さんに尋ねたときの添乗員さんの答えが「えー! 間に合いません!」でした。 「昼食を食べていたら間に合いません。急いでエスカルゴだけ出してもらいますから、1時10分には出てタクシーで行ってください。」 私たちはエスカルゴだけ食べさせてもらい、1時10分になったら添乗員さんが「それでは行きましょう。」と言って、タクシー乗り場まで一緒に行ってくれました。5分ほど早歩きで歩きました。ところがタクシー乗り場にはずらっと人が並んでいます。 「もう間に合わないか。」と私は思いましたが、とにかくその列に並びました。 並んでいる人々はどんどんタクシーに乗っていきます。列は短くなっていきます。 「大丈夫です。タクシーに乗れば10分くらいで着きますから、1時45分には間に合うでしょう。私からマイバス社には電話しておきます。」と添乗員さんは言って、すぐにマイバス社に私たちが遅れるかもしれないということを電話してくれました。 ほどなくして、私たちの順番になりました。整理係の人にチップを渡し、行き先を書いた紙を渡し、私たち6人は2台のタクシーに分かれて乗りました。10分くらいで到着、10ユーロ弱でした。 その日の行動予定をもっと早く添乗員さんに伝えておけば、こんな事態にはならなかったでしょう。私のミスでした。 本体のツアーも、この日の午後は、オプショナルツアーでベルサイユ宮殿に行くことになっていたのです。本体を離れて、別のオプショナルツアーに参加するのが申し訳ないという気持ちもあって、添乗員さんに言い出しにくかったのです。 とにかく集合時間には間に合って、無事ベルサイユ宮殿に向かうことができました。 しかし、「ヨーロッパ珍道中」は、この後も私たちに「試練」を与えてくれました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.31
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(6)
ヨーロッパ家族旅行の5日目はパリです。 スイスのインターラーケンからジュネーブまでバスで行き、ジュネーブから新幹線に乗ってパリに行きました。これが4日目の夜です。 パリの1日目は、午前中がパリ市内観光。午後はベルサイユ宮殿です。 まずは、凱旋門やコンコルド広場などを車窓観光し、エッフェル塔のよく見える場所で撮影タイムです。上の写真がエッフェル塔ですが、これも光の関係であまりきれいには撮れていませんね。 パリ市内の観光では、添乗員さん以外にガイドさんがついてくれて、案内してくれました。パリ市内の大きなゴミ箱やゴミ袋が緑色に統一されていることも教えてもらいました。「あそこにアランドロンさんが住んでいるんですよ。あれ、今日は不在のようですね。よく手を振ってくれているんですよ。」などと楽しく案内してくれます。 市内観光の後は、セーヌ川クルーズで、船に乗ってたくさんの歴史的建造物を見て楽しみます。ルーブル美術館、オルセー美術館、ノートルダム大聖堂、アレクサンドル3世橋と世界遺産のオンパレードです。 三女の秋子(小2)は、右手にペン、左手にメモ帳を持って、ちびっこ記者のようです。 「コンシェルジュリってマリーアントワネットが投獄されたところだよね。」とびっくりするようなことを言います。 旅行前に少しでも勉強しておこうと妻がネットで『ベルサイユのばら』(池田理代子、集英社)を買って読んでいましたが、妻の次に熱心に読んでいたのは秋子でした。それで、コンコルド広場がマリーアントワネットの処刑された場所だということも知っていました。 私のほうは勉強不足で、クルーズ中もどの建物が何なのか、よく分かりませんでした。もちろん日本語による音声ガイドがあるので、ある程度は分かりますが、事前に勉強しておいたらもっと味わえただろうにと思いました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.28
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(5)
ヨーロッパ家族旅行の3日目、ノイシュバンシュタイン城を観光したあと、ドイツらしいソーセージの昼食を取り、スイスに向かいました。 途中一部オーストリアも通り約400km、工事による渋滞もあって、7時間近くバスに乗りました。 スイスでの滞在はインターラーケンという町です。 夕方7時半ごろ、インターラーケンに着きました。 7時半と言ってもまだまだ外は明るいです。 ホテルに到着する少し前、ヘーエマッテ公園からユングフラウヨッホが車窓からきれいに見えました。数秒だけでしたが、翌日またじっくり見られます。その時きれいな写真を撮ろうと思いました。 インターラーケンは、夏場に涼しい保養地、日本でいえば軽井沢のようなところといったらいいでしょうか。そして、ヨーロッパで最も高い標高3454mに駅があるユングフラウヨッホへの玄関口です。 しかし、今回の旅では、私の母や小2の三女のことを考えて、ユングフラウヨッホには行きませんでした。高山病が怖かったからです。 今回の旅行を決心するきっかけを与えてくれた知人は、ユングフラウヨッホに行ったとき、子どもが高山病になったと言っていたからです。 ユングフラウヨッホへのオプショナルツアーが高額だったこともあります。一人3万円近くします。我が家は6人と大人数ですので、それだけで18万円になってしまいます。 それに今回の旅行は、町歩きをするフリータイムがあまりないので、ここで町歩きをしようと考えたのです。 天気に恵まれた今回の旅行でしたが、この4日目のスイスだけは雨が降りました。 旅行中、添乗員さんは常に「雨具と上着を」と言っていましたが、特にインターラーケンは山と湖に囲まれた場所ですから、天気が変わりやすいのですね。 インターラーケンでは、ケーブルカーで少し高い山に登ったり、インターラーケン・オスト駅の近くのコープ(みやげ物店ではなくスーパーマーケットのような店)でおみやげを買ったり、ウンターゼーンという中世の町並みが残っている場所を見たりして過ごしました。 上の写真は、ウンターゼーンの教会です。 雨にたたられたので、この日は周囲の高い山々が見えず、ユングフラウヨッホが見えたのは前日の車窓からのあの数秒だけでした。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.23
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(4)
ノイシュバンシュタイン城は、ドイツ観光のハイライトです。 ディズニーランドのシンデレラ城のモデルです。 上の写真は、ノイシュバンシュタイン城の全景です。 現在外壁工事中で、残念ながら「白亜の城」という感じが少し薄れています。 反対側から写した写真が光の関係上きれいなのですが、ここで紹介するのは、全体が一番わかるこの写真にしました。 この城は、断崖(だんがい)の上にあるため、建築には困難を極め、17年の歳月を費やしたそうです。 バイエルン王ルードヴィッヒ2世の夢を現実化した白亜の城です。 1時間ほど城に上って豪華な内装も見ました。城から外の景色を撮影するのはいいのですが、内部は撮影禁止です。 ここで売っている絵葉書には、スタンプが押してあります。このスタンプが押してあるのは、ノイシュバンシュタイン城の中で売っているものだけだそうで、価値があります。 スプーンなども売っています。銀のもの、銀箔(ぎんぱく)のもの、錫(すず)のもの。 スプーンやフォークは、家族旅行の自分へのお土産としていいと思います。 アイスクリームやプリンを食べるときにそのスプーンを使う。そうすると、みんなで旅行した時のことが話題になります。「ノイシュバンシュタイン城はきれいだったね。」と話がはずみます。 果物を食べるときにそのフォークを使う。そうすると、やはり旅行のことが話題になり、家族共通の思い出がよみがえり、頭に刻みつけることになります。 家族旅行の思い出をよみがえらせるものとして、おみやげにフォークやスプーン。いかがでしょうか。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.21
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(3)
今回の旅行全体を通じて印象的だったことの一つは、水の確保とトイレの心配でした。 水についてですが、食事の時に水が出てくることはあまりなく、ビールやワイン、オレンジジュースやリンゴジュースを頼むことが多かったです。メニューには水もあるのですが、なんとなく水は注文しませんでした。食事は全部ツアー料金に入っていましたが、食事の時に頼むドリンク代とチップ代に意外と出費しました。 バスの中で販売していたミネラルウォーターをよく買いました。ホテルには自由に使える冷蔵庫はありませんでしたが、とにかく水を確保しておかなくてはと思い、毎日バスを降りるときには、水を何本か買っていました。 バスで売っていた水は日本でも売っている「エビアン」。1ユーロ(140円位)でした。食事の時にメニューにある水は、ビールなどより高いこともあり、4ユーロ(560円位)ぐらいすることが多かったです。 今回の家族旅行は、「ヨーロッパ周遊8日間」のツアー旅行でしたが、ヨーロッパ(ドイツのフランクフルト)まで行くには、飛行機でも12時間ほどかかりますので、1日目は移動日、7日目も移動日、8日目の朝に日本に帰国、という日程で、観光の時間としては2日目から6日目までの5日間です。 8日目の朝に帰国というのは、時間がもったいないと思っていました。確かに8日目がないような印象ですが、大人数(家族6人)で行ったこともあり、家に帰って洗濯ものを出したり、荷物の整理をしたり、といったことを考えると、朝の帰国も悪くはないな、よく考えられているのかな、と思えました。 少しでも長期間だという印象を与えたいという旅行社の思惑は、もちろんあるでしょうけれど。 帰国して昼食を取って、家に着いたのは午後3時頃でした。 その5日間でドイツ、スイス、フランス3カ国の主要な観光地を回るのですから、どうしてもバスに乗ったりする移動の時間が多くなります。それは覚悟していました。 旅行シーズンだったので、ノイシュバンシュタイン城も、ベルサイユ宮殿も、モンサンミッシェルも混んでいました。 観光地でもサービスエリアでも、トイレがたくさんあるわけではないので、トイレはいつも長蛇の列でした。男性用のほうも女性が使って混雑を緩和することがしばしばでした。 日本での普段の生活の中では、「水を確保する」とか「行けるときにトイレに行っておく」とか、そのような心配をする経験はめったにないので、その点でも今回の旅行は、子どもたちにとっていい経験になったのではないかと思っています。 上の写真は、2日目に行ったローテンブルク(ドイツ)の城壁です。ローテンブルクは、ロマンチック街道最大の見どころとも言われ、旧市街では、おとぎの国のような風景が楽しめました。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.20
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(2)
ヨーロッパ家族旅行の2回目です。 日本の空港を午前10時半頃に出発し、ドイツのフランクフルトを目指します。12時間のフライトです。 この12時間のフライトが最初の心配の種でした。 おばあちゃんは大丈夫だろうか。三女の秋子(小2)は大丈夫だろうか。 エコノミー症候群にならないように、数時間おきにトイレに行ったり、席を立って少し歩きまわったりして、予防しました。 飛行機に乗って2時間くらいすると昼食が出ました。 それからまた5時間くらいして軽食のサンドウィッチを食べた後のことです。「お父さん、鼻血が出た。」次女の夏子(小5)は、よく鼻血が出るのです。 今回の旅行でも、その鼻血に備えて、夏子のリュックには常にティッシュを箱ごと持たせていました。預けた私のスーツケースには、予備のティッシュも用意してありました。 夏子の鼻血は出血の量が多いのです。ティッシュを鼻につめてしばらくすれば止まるレベルの鼻血ではありません。ひどい時にはドクドクと血が流れて、出血多量になってしまうのでは、と心配になるほどです。 幸いこのときは、それほどひどい鼻血ではなかったので、ほどなくして止まりました。 日本とドイツの時差は8時間です。日本が午前7時の時、ドイツは前日の午後11時です。サマータイムの期間は時差が7時間になります。今回はもちろんサマータイム期間ですので、時差は7時間です。 日本を出発して12時間、日本時間では夜の10時半ごろ、フランクフルトに到着しました。ドイツでは昼の3時半です。(ここからは現地時間で書きます。) 心配していた12時間のフライトは、夏子の鼻血程度で済み、何とか乗り切りました。 空港からバスに1時間ほど乗り、午後6時頃、1日目のホテルに到着しました。 部屋に荷物を置いて一休みして、午後7時頃からホテルの周辺を散歩することにしました。 サマータイムだと夜の9時頃まで明るいのです。 しかし、午後7時は日本時間の翌日の朝2時です。秋子は眠くて仕方がありません。秋子とおばあちゃんはホテルに残ることになりました。 1時間ほどドイツの町を散歩して、ホテルの部屋に戻ってきたら、「お父さん、鼻血が出た。」夏子の二度目の鼻血です。 旅行の初日から二度も鼻血が出るなんて。 「ヨーロッパ珍道中」の初日は、「鼻血」でした。 しかし、翌日も二度の鼻血に見舞われるとは、このときは予想もしていませんでした。 上の写真は、ドイツ最古の大学があるハイデルベルグの町並みです。ハイデルベルグ城から撮影しています。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.19
コメント(0)
-

ヨーロッパ家族旅行(1)
3年前から計画していた家族旅行。 思い切ってヨーロッパへ行こうと思ったのは半年前でした。 今回の家族旅行は、私たち夫婦と三人娘と私の母と6人での旅行となりました。 私たち夫婦は、自分たちで宿や交通の手配をするような不便な旅を中国で何度もしているので、どちらかというとそういう旅のほうに面白味を感じますが、小2の三女や私の母のことを考え、今回は添乗員が付いてくれるツアー旅行にしました。 集合時間には当日の朝家を出ても何とか間に合いそうでしたが、余裕がほしかったので、空港近くのホテルに前泊しました。 三女の秋子(小2)は、ホテルに着くと、はしゃいでベッドの上をぴょんぴょん飛び跳ねていたらしく(6人が2部屋に分かれたので、その時は、私がそこにいなくて止められなかった)、ベッドとベッドのすきまに足をはさんだようで、足の甲を怪我してしまいました。私が三女の足の甲を見たときには少し腫れていて、旅行中三女が自分の足でしっかり歩けるか心配になりました。 「これから旅行が始まるという時に何をしているんだ。」と思いましたが、初日から怒っていたのでは、せっかくの旅行が楽しくなくなってしまいます。怒るのは我慢して、「少しでも良くなるように、湿布薬を買いに行こう。」と言って、夕食を食べに行きがてら、空港内の薬局で湿布薬を買いました。 ツアーは約30人。旅行の途中で、20歳代の娘と一緒に参加していた上品な女性から、「子育て上手ですね。」と妻が言われていて、とてもうれしかったです。「いえいえ、おばあちゃんのおかげです。」と妻は答えていました。その通りです。 どういう点をさして「上手な子育て」と言ってくださったのかはよく分かりません。三女の秋子が愛想を振りまいていたからか、秋子がメモ帳を取り出して時々メモを取っていたからか、次女の夏子(小5)が、「おばあちゃん、これはこういうふうにするんだよ。」とおばあちゃんをサポートしていたからか、長女の春子(中2)の無口なのが落ち着いて見えたからか。 いずれにしても出発前から三女が怪我をするというアクシデントから、今回の「ヨーロッパ珍道中」は始まりました。 上の写真は、ヴィースの巡礼教会です。世界遺産です。 ドイツのロマンチック街道の終点の町フュッセンの近くにあります。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.18
コメント(0)
-

ただいま、無事帰りました。
ただいま。ではなく、数日前に帰っていたのですけれど。 それでも、「ただいま。」 家族でのヨーロッパ旅行から無事帰国しました。 新型インフルエンザの関係で、帰国後1週間は発熱などに気をつけるようにという印刷物を、空港で入国時に渡されました。 まだ1週間は経っていませんが、今のところ家族に発熱も風邪の症状もありません。 「無事帰国」と言ってもよさそうです。 とは言うものの、時差ボケで昼間に眠気に襲われたり、写真の整理に追われたりしています。 楽しい旅行でした。珍道中でもありました。 旅行の一部を、次回から何回かに分けて紹介していこうと思います。 ランキングに参加しています。よろしかったらクリックして応援してください。「新米ママ・新米パパに贈る、幸せな子育てのヒント」トップページヘ「子育て応援広場」へ
2009.08.17
コメント(0)
全159件 (159件中 1-50件目)
-
-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…
- 4~5店舗目 このみみ2月のバレンタイ…
- (2025-04-26 21:04:48)
-
-
-

- 大学生母の日記
- 大学生の娘と一緒にお風呂に入るのは…
- (2025-04-17 20:46:57)
-
-
-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…
- 京都占い・魔法使いの家
- (2025-04-17 10:30:11)
-