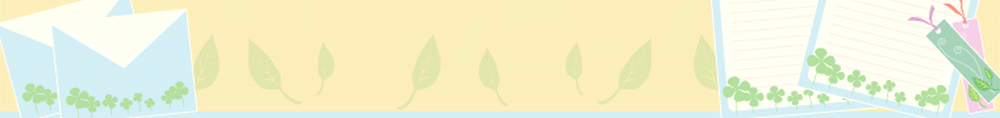今回のお話は生写朝顔話(しょううつしあさがおばなし)
今回のお話は生写朝顔話(しょううつしあさがおばなし)
ふと知り合い恋に落ちた男女が、運命のいたずらからすれ違いを繰り返し、男を追って家出し、家老の娘からついには盲目の門付け芸人にまで落ちぶれた深雪の数奇な運命を描いている
(豆知識)
時代設定は鎌倉時代で、主人公深雪が一目ぼれする宮城阿曽次郎は大内家の家臣となっているけれど、英雄が大立ち回りをするということではなくて、すれ違いのメロドラマという感じで、時代ものでも世話物でもない微妙なお話。この話は16段からなっている長いお話で、全編を公演するには長すぎるので、面白い所をビックアップしての公演になっている。涙と笑いが適当に入り混じって、観客を飽きさせない工夫をしている。
(前提)
割愛された段で、大内義興は周防の国の大名だが、悪臣にそそのかされて鎌倉で放蕩三昧の生活をしている。藩の儒学者駒沢了庵は、これではいけないと甥の宮城阿曽次郎を自分の跡取りとして、藩主に諫言させようと考えている。
宇治川蛍狩りの段(二人の出会い)
阿曽次郎は京都に儒学を学びに来ている。ある日友達の僧月心と宇治川へ蛍狩りに出かけた。よい景色だからここで和歌を一首という月心のリクエストで、さらさらと短冊に和歌を書いた阿曽次郎。その短冊が宇治川に夕涼みに来ている屋形船へと風で飛ばされてしまった。屋形船からは三味線ときれいな歌声が聞こえてきている。
屋形船の戸が開けられて、飛ばされた短冊を手にした娘(安芸の国の家老秋月弓乃介の娘深雪)があたりを見回している。(この短冊を書いたのはこの人かしらと阿曽次郎見つめる)そして、 ふたりは互いに心をひかれあってしまったのだった。
そこに酩酊した浪人者が登場、女ばかりの船だと思い 深雪の船に乗り込んで、酌をしろとか一緒に飲もうとか無理を言いはじめる。岸でその様子をみていた阿曽次郎が止めに入り、浪人どもを追い払う。
深雪はものすごく喜んで是非お礼にと、屋形船に招く。乳母の浅香は気を利かせて船頭を呼んでくるからその間用心のため一緒にいてやってと二人にする。深雪は自分の扇に阿曽次郎から「朝顔の歌」を書いてもらう。( 屋形船の戸がここで閉められるのは非常に意味深 )
そこへ阿曽次郎の下男が伯父さんからの急ぎの手紙というのをもって駆け付けてくる。今すぐ鎌倉へもどれという知らせだった。阿曽次郎は急用ができたのでこれで失礼すると船をでる。
深雪はもう少しいてほしいと必死になって止めるが、そうもいかず。戻ってきた浅香の説得もあって、必ず後日深雪の屋敷を尋ねると言う約束で別れるのであった。
(この間さきほどの浪人がまたもどってきて打ちかかり、阿曽次郎に川に投げ落とされ、水の中で、あっぷあっぷするという滑稽な場面がある)
真葛ヶ原茶屋の段(笑える場面)
秋月家出入りの医者桂庵は、弓乃介から宮城阿曽次郎という人間の事を調べてほしいと頼まれていた。しかし桂庵は仲間の医者祐仙を茶屋に呼び出し、「お前が阿曽次郎になりすませば、秋月家に婿入りできるぞ。ついては紹介料30両を出せ。」と言っている。
祐仙はそんな立派な家に婿入りできるなら、金はいくらでも出すと大喜び。しかし祐仙は、色黒、獅子鼻、タレ眉毛という残念な顔立ち。せめてもう少し男ぶりをあげなければと髪結いどこに去っていく。
そのあと桂庵は茶店の女お由に言いつけて、鍋底のこげをもってこさせてそれを粉にして、紙につつむ。そして、お由に「わしが合図をしたら、さっきの男に惚れたふりをするのだ。」と命令する。
祐仙が髪結いどこから帰ってくる。桂庵は「ここに、これをふりかければどんな女でも、振りかけた男に惚れるという秘伝の薬がある。15両だせば譲ってやる。」とこげを粉にした薬を売りつける。薬を買った祐仙は試しに、茶屋のお由に薬をふりかける。桂庵の合図に従いお由は、祐仙に抱きついたり。太ももをさすったり。首に手をまわしたりしながら好きだ好きだと迫っていく。
祐仙はあまりのことに逃げ出してしまうが、薬の効き目は間違いなしと信じてしまう。
文楽と言ったら硬いイメージがありますが、
笑あり涙ありで、観客を飽きさせないようにしたいるのであれば、まだ見た事がないので、取り敢えずは、一回見てみたいです。 (2015年07月26日 17時17分10秒)
普段は2部構成でそれぞれ4時間半ですが、夏休みは3部構成で3時間(他に30分休憩あり)です。今回は4700円です、一幕だけみる幕見というのもあり、1500円で2時間ぐらいみられます
(2015年07月27日 17時39分00秒)
PR
カレンダー
 New!
MoMo太郎009さん
New!
MoMo太郎009さん2025秋旅 九州編(9日…
 New!
ナイト1960さん
New!
ナイト1960さん🍐 新作「秀吉の野望… New! 神風スズキさん
インフルエンザ? New! team-sgtさん
付録【キットカット …
 New!
ぬぅ123さん
New!
ぬぅ123さん