-
1

博多リバレインの屋上庭園
博多リバレインに行ってきた。「入って1階のところ」で待ち合わせをしていて,中洲川端の駅とつながっているから「分かりやすい」と言われていた。ところが分からない。もう駅のところから,あっちもこっちも複合施設リバレインで,1階ではつながっていない。なにしろ劇場,ホテル,美術館,ショップ,事務所が3つの大きなビルに分散してる。で,ビルの中のテナントなんかが,それぞれ自己主張してるもんだから,もうどのビルがどのビルなのか分からない。とりあえず打合せを済まして,ショップを見て回った。ビルの内装は豪華だし,世界一流ブランドが迫力のあるロゴをどーんと店先に展示している。けど,ちょっとお客は少ない。大丈夫か?最後にガラス張りで芝生敷きの屋上庭園アトリウムに行った。4階くらいの高さの空間で,3面の壁と屋根部分の全部がガラス張りで,床は石とボードウォークと芝生で仕上げてある。一角にオープンカフェもあって,いい空間だ。しかし・・・暑い。もわん,としてる。セキュリティのためか,ボードウォークで外部バルコニーに出れるはずが,施錠されている。窓も無くて,どこも締め切られていて風が抜けない。正に「温室」だ。そりゃ,暑くなるだろ!どうして?博多リバレインは経営的にいろいろ苦しんでるみたいだけど,どこに行っても「ほっとする」空間がない,ってのが原因の一つじゃないのかな?客に緊張を強いてない?おっとセミが鳴いてる。今年初めて聞くなあ。さて,飾り山笠見に行こうっと。
2004.07.03
閲覧総数 632
-
2

「いのちのパレード」恩田陸を読んだ
「幻想と怪奇」をテーマにした恩田陸の短編集を読んだ。○ストーリー昔話の舞台だと思っていた村が実在した。男と妻は,そこを訪ねる観光ツアーに参加するが,村のはまさに昔話の通りの状態だった。真偽を疑うツアーのメンバーだが,数々の不思議を見て,やがて信じるようになる。だが,その夜・・・-------------バラエティに富んだ作品を描く恩田陸が,あえてテーマを絞って統一感を出した短編集だ。そのテーマとは,かつて「幻想と怪奇」あるいは「異色」とも呼ばれたジャンル・・・ミステリー,SF,ホラーの中間点のような不思議な味わいのあるタイプの小説のことだ。僕は時々恩田陸の作風を「ミステリーではなくてミステリアスだ」と言っているが,このタイプはまさに恩田陸にピッタリで,どの短編もヒネリが利いていて楽しめた。これまでの短編集では,長編に育てる前のアイディア,あるいは予告編のようなものも含まれていたが,この作品はむしろ短編ゆえの面白さがそろっている。例によって結末のはっきりとしない”オープンエンド”な作品もあるが,この短編集に限ってはそうした結末も合っていて,まさに恩田陸の本領発揮という印象を受けた。-------------「観光旅行」:おとぎ話の世界にしか存在しないと思っていたある村に観光旅行に行った人々は,その夜に奇妙なことを経験する。・・・ラストでじんわりと怖くなる,「幻想と怪奇」ジャンルの最もベーシックな味わいを体現した短編だ。「スペインの苔」:彼女はブリキのロボットを大事にしてた。そのロボットの由来と,ロボットがいつまでも動く理由とは・・・淡々とした語り口なのに忌まわしい世界が広がっていく。前半も怖いのだが,世界が歪み始めるような感覚を与える後半も怖い。「蝶遣いと春、そして夏」:死者の魂を山へと送る蝶遣い。この風習がある土地で,少年が経験した夏の物語。・・・他の作家を引き合いにして申し訳ないが,上橋菜穂子の「守り人シリーズ」に出てくる異界〈ナユグ〉のような世界観だ。またヨーロッパ映画のような美しさもある。「橋」:極東のある島国を東西に分断する橋。バリケードの中から,その橋を見張るのが人々の定期的な勤めだった。ほとんど事件が起きたことの無いその場所で,ある時・・・様々な作品で描かれてきた分断された島をモチーフにした短編だ。恩田陸らしいリアリティが光っている一方で,ラストは・・・ギャグだろうか?「蛇と虹」:かつての悲劇を語る姉と妹。2人の記憶の食い違いは何を語るのか?・・・黒と赤の2色のイメージが喚起される短編。だが苦手。「夕飯は七時」:僕たち3兄弟は知らない言葉を聞くと,想像したイメージを実体化させてしまうチカラがある。だが母さんが仕事中なため,おじいちゃんが夕飯を作っていて・・・シュールなユーモア小説なのに,少しもニヒリズムの要素がない貴重な短編だ。絵本にしたら子どもが喜びそうだ。「隙間」:私が隙間という隙間を恐れるのは,少年の頃住んでいた家の物置の扉の隙間にアレを見たからだ。もう一度あの場所に行ってみると・・・古典的な怖い話だ。ストンと終わるのもそれっぽい。「当籤者」:当たった後,2週間逃げ切れば大金を手にするというくじに当籤してしまった男は,誰も信じることができなくなる。果たして自分をねらっているのは?・・・ホラーでもあるが,スラップスティックのようでもある。血潮を発見するシーンは怖かった。「かたつむり注意報」:その街では時々”かたつむり注意報”が出る。注意報のおかげでホテルに閉じ込められた男は,バーで女から昔話を聞くが・・・かたつむりの独特の匂いを思い出してしまった。このホテルではエスカルゴをメニューに入れているらしいが,いいのだろうか?「あなたの善良なる教え子より」:殺人罪で断罪された男から一通の手紙が届く。果たして彼は本当に殺人を犯したのか?手紙から広がる世界は何を語るのか?・・・ある発想をどこまでも突き詰めてしまうとこうなる,という仮想の世界観が怖ろしい。どう終わるかと思っていたら,ちゃんと怖いラストが待っていた。「エンドマークまでご一緒に」:ミュージカルの世界が現実だったら?・・・古典的なミュージカルの主演を主人公にしたメタ的ギャグ作品だ。汗だらけになりながら踊る主人公たちがけなげで笑える。「走り続けよ、ひとすじの煙となるまで」:王国は巨大な列車の中で興され,何十万もの人々を配下に治めた。ある時,列車が動き始め,そこは動く王国となる。だが徐々に・・・宇宙船を舞台にした文明SFはいくつか読んだことがあるが,列車と地上を舞台にしている点が目新しい。恩田陸が好きな,マヤ文明の雰囲気もある。「SUGOROKU」:国中の村々からある街に集められた少女たちは,街はずれの小屋からお城の部屋を目指して,毎日少しずつ部屋を移動する。不思議なゲームのルールは?果たしてこのゲームの目的は?・・・設定だけを考えるとギャグなのに,読んでいるうちにぴりぴりと怖くなってくる。絶品だ。「いのちのパレード」:地平線まで見渡せる場所に生き物たちがやって来る。長い長いパレードの果てにやって来たのは何なのか?・・・本のタイトルにもなっている作品で,読んだことのない不思議な雰囲気を持っている。この短編で終わってくれても良かったのだけど・・・「夜想曲」:重厚なデスクにゆったりとした椅子。その部屋の主に新しい物語を伝えに来たのは?・・・恩田陸の筆は,部屋や家具の手触りや匂いまでも感じさせる。本当に稀有な才能だと思う。この書き下ろし短編は,前の作品さえなかったらしっくり収まったと思う。
2009.11.01
閲覧総数 1826
-
3

「きのうの影踏み」辻村深月を読んだ
辻村深月の日常ホラー短編集を読んだ。○ストーリー子供が出来て,出産のために長いこと田舎の実家に帰っている私を,東京から複数の会社の編集者が定期的に訪ねてくる。何もない田舎の家に巡礼するような人々から,この町には占い師がいるのではないかという噂が流れ始める。笑いごとだと片付けていた私だが,自分の町には実際に占い師がいることを知り,ついにその人物に出会う。----------------リアルとフィクションの狭間にありながら,見事にホラーとして成立している。そのプロとしてのスタンスに感心した。デビュー作から,ほぼライブで作品を追ってきた辻村深月だが,まさか直木賞を受賞して,その後も安定した作品を発表し続けるとは予想していなかった。狭い世界の作品を,頑張って描いているという作家だったのに,あっという間に大家の器を感じさせる状況だ。人は変わるものだ。----------------僕が大好きな女性作家も,純文学風のSFやホラーを発表し続けて長い。たぶんこの人も直木賞が欲しくて仕方がないと思うのだけれど,今回はノミネートさえしなかった。当初は僕も,なんでこの人じゃなくて辻村深月なんだ?,と憤慨したけれど,冷静に見てみると,作品世界の幅がいつの間にか大きく逆転している。自分の周りの世界をベースに作品を描く,というスキルは,本人が成長すれば作品も大きくスケールアップするのだと,改めて感じさせられた作品だった。----------------各編について簡単に感想を述べる。「十円参り」:消したい人の名前を書き,十円玉と一緒に十日間賽銭箱に入れると願いが叶う,そんな噂があった神社の賽銭箱を暴いてみると・・・昭和の香りがする物語から,二重にぞっとする結末まで,非の打ち所がない短編だ。何の情報が無いまま,この作品を手にすると,若干戸惑うけれど。「手紙の主」:作家宛てに届く奇妙なファンレター。支離滅裂な部分がありつつも,作家への執着を見せる手紙は,複数の作家宛てに届いていた。そしてその送り主は,徐々に近付いており・・・エッセイなのか?作品なのか?と迷わせるが,ちょっとしたディテールがありそのリアリティがひじょうに有効だ。この短編はありがちな都市伝説の亜流なので,途中からちょっと興ざめした。「丘の上」:私たちの町は濁流に呑まれてしまった。丘の上からそこに戻ろうとした私たちは・・・ひじょうに短いので,読んでもらいたい。夢のようだが,東日本大震災のイメージもある。「殺したもの」:大学のゼミの合宿で海沿いのリゾート地を訪れた私は,不思議な生き物を目にして・・・白い壁への汚れのビジュアルイメージが鮮烈だ。「スイッチ」:山手線の中で,ゴシックファッションの女性に話しかけられてしまったオレは・・・ホラーのようで,ネットの書き込みを信じれば,リアルにこうした体験はあるようだ。ここまで引っ張らなくても良かったように思うが?「私の町の占い師」:出産のために田舎の実家に戻っている作家の私を,東京から複数の編集者が訪問した。それによりこの町には占い師がいる,という噂が立つ。困った勘違いと同時に,私の町には他にも占い師が存在することを知り・・・エッセイっぽく始まり,それで一度は落ち着いたと思わせて,さらなる謎へと導く。見事だ。「やみあかご」:夜泣きで起きた赤子を,夫を起こさないためにリビングで遊ばせる。大人しくなった赤子を抱いて寝室に戻ると・・・うわー,うわー,新しいホラーだ。「だまだまマーク」:幼稚園に通う息子が〈だまだまマーク〉とつぶやきだした。子供のちょっとした造語だと面白がっていた私だが,その言葉の起源を知ることになり・・・前の短編に続き,現代のホラーとして十分な破壊力がある。怖い。「マルとバツ」:会社帰りのスーパーの前に座っていた小学校ぐらいの少女。私は彼女を数回見かけることになり・・・悪夢系の短い短編。「ナマハゲと私」:大学の〈民俗学入門〉の講義の関係で,同級生たちを秋田の実家に連れて来た私は,ナマハゲに騒ぐ友人たちがどこか恥ずかしくて,1人で自分の部屋でテレビを観ていた。そこに電話がかかって来て・・・良く出来ている。まるでお手本があったのかと疑ってしまうほどだ。逆に辻村深月らしさは薄いかな?「タイムリミット」:1年に1度残酷な隠れんぼゲームが起きる町で,姉妹は学校に閉じ込められる。・・・悪夢系の短編なのだけれど,姉妹を設定したことで切なさが増している。「噂地図」:小学校の時と同じように〈噂地図〉を作成し,噂の元を辿ろうとした女子高生たち。だが彼女たちは〈ルール〉を守らなかった。そのため・・・相手が質問に素直に答える保証はないし,今の時代は噂はネットを通じて広がるし,長さの割りに薄い印象の短編だ。東直己の作品にもっと深い考察がある。「七つのカップ」:私たちの通学路に,その危険な横断歩道はあった。かつてここで娘を亡くした女性が,周辺に現れていた。そして私と友人が体験したことは・・・ホラーに分類されるのだろうけれど,こうした流れの物語があるとは。感心した。
2016.01.05
閲覧総数 4671
-
4

「蔵」宮尾登美子を読んだ
正月はやっぱり華やかなものを,という事で,前から気になっていた女流作家の大家のこの作品を読んだ。○ストーリー新潟の豪農で蔵元の田乃内家にたった一人育った娘,烈,は美しい娘だったが,生まれつき視力が弱かった。祖母,母が倒れ,烈はさらに視力までを失う。田乃内家に様々な事がおとずれる中,烈は叔母の佐穂とひっそりと育っていく。ついに父・意造までが気力を失ってしまった時,烈が決心したことは・・・------------------------華やかさはない,けれども正月にふさわしい静かな美しさはたっぷりあった。新潟の旧家を舞台にした作品に,華やかさを期待してはいけなかったのだろうか?一言で言うとNHK連続テレビ小説の小説版を読んでいるような気持ちになった。明治,大正,昭和と続く田乃内家の歴史が続く中,まあ,とにかく不幸の連続だ。烈の父親の意造は,なかなかの人物で,当主としておおむね立派に振舞う。しかしなんと言っても,この作品の主人公は女性たちだ。祖母,母,叔母,継母,烈と田乃内家の女性たちが,ある時は激しく,ある時は我慢強くドラマを進める。------------------------明治以来の”旧家”というものが,リアリティを失って久しい。なにしろ現代の資産家は,同じ会社員だけど,たまたま”あっち側”にいる人,ってカンジだ。最近”旧家”という設定は,少女マンガか,推理小説の中でしか,お目にかかれないが,どれも薄っぺらくて安っぽい。「蔵」では全編みっちりと,”旧家”が描かれている。そこの人々の考え方・生き方,家の間取りや風習,どこを取っても,リアルな重みを持って描かれている。------------------------もう一つ,この作品に厚みと温かみを与えているのが新潟の方言だろう。宮尾登美子作品としては読みやすい方だということで,全編を通じて会話が主体となっている。当然,そのほぼ全てが新潟の言葉なんだけど,それによって登場人物たちに血肉が通うようになっている。翻訳小説ではまずこの肌触りは出すことはできないと思う。------------------------さて,「蔵」のタイトル通り,田乃内家では,日本酒「冬麗」を醸造している。最後に蔵のさまざまな工程がもっと前面に出るかと思っていたんだけど,もう一つ,というところで別の悲劇が起きてしまって,それはお預けのままとなる。ま,それでもこの作品を読了した時は,日本酒でお祝いをしたくなった。でも正月の街では酒屋は閉まっていた。その先のコンビニでは焼酎しか売っていなかった。おーい,日本の正月だろ!伝統はどこ行った?
2005.01.03
閲覧総数 144
-
5

「アルテーミスの采配」真梨幸子を読んだ
2015年9月に刊行された真梨幸子の長編を読んだ。○ストーリーゴーストライターの名賀尻は,本の執筆のために複数のビデオ女優へインタビューを行う。インタビューの相手は,表向きの作者からの指定で,〈専属女優〉,〈単体女優〉,〈企画単体女優〉,〈企画女優〉という,様々なランクのビデオ女優が選ばれた。名賀尻のインタビューは,ビデオ業界の闇を浮き彫りにして冴えわたる。だが,その女優たちが次々に殺害され,彼は現代の切り裂きジャックとして警察に追われることになる。この事件の裏には〈アルテーミスの采配〉というサイトがあり,そして・・・?-------------良く出来ていると思う。前半は大人ビデオ業界の擬似レポルタージュとして,様々な女性の転落人生が語られる。後半は,名賀尻が出版社に送った告発文をきっかけにした素人探偵たちの捜査が語られる。コインの表裏のような物語が最後に導き出すのは戦慄の悪魔の采配だ。真梨幸子の作品としてはなかなかの出来だと思う。-------------ただし欠点もいくつか見られる。まずは登場人物が多過ぎる。レポルタージュの企画チームで5人,インタビューの対象が5人,そして後半でもまた5人。いろいろな理由で名前が明かされず,ちょっとした特徴で,キャラクターを把握しなければならないことがあり,それによりひじょうな緊張感強いられる。これが作者の意図で,「登場人物リストを自分で作れ」と命じられているようで苦痛に感じる。次に連続殺人が実は○○だったという展開。現代の科学捜査を無視した流れだし,それまでの大人ビデオ女優たちの描写とも乖離していると思った。最後に,女性をビデオ女優へと”転ばせる”テクニックが,あまりにも見事なのでリアリティがない。物語としては面白いのだけれど,計画が全て上手く行ってしまうので,途中からもやもやしてしまう。見事で,長々と凝り過ぎで,コストパフォーマンス悪そうだ。都合悪いリアリティは,完全に無視だしなあ。-------------大人ビデオについて,女優がどのようにそこに”転んで”行くかだけでなく,実際の作品の内容にも言及されているので,そうしたことに敏感な人や年令の方は読むのを避けるべきだろう。ただし真梨幸子が,大人ビデオ業界を「底辺」と決め付けているのには疑問を感じた。確かに”表”とは異なる業界だとは思うが,そこに至った女性たちの運命が,そこまでひどいもので,また這い上がれない状態だとも思っていない江戸時代の吉原と比較するならば,吉原にも身請けがあったが,今のビデオ業界はさらに多様な身の振り方があるので,もっと自由だと思うのだが?-------------真梨幸子らしい作品で,破綻も少ないし悪くはない。
2016.10.08
閲覧総数 2777
-
6

「黒笑小説」東野圭吾を読んだ
東野圭吾のユーモア短編集を読んだ○ストーリー〈僕〉は付き合っていた華子に突然ふられてしまった。落ち込んでいた〈僕〉は,なぜか彼女に愛情の真剣さを示すためにストーカーをするように言われる。華子の行動を監視し,尾行をし,そしてついに・・・-----------東野圭吾の〈○笑小説シリーズ〉の一作だ。ほかには「怪笑小説」「黒笑小説」「歪笑小説」がある。このシリーズの他の作品を読んだ時にも同じ感想を抱いたが,東野圭吾はまじめ過ぎて,ちっとも笑えない。有栖川有栖なんて,普通のミステリー短編に脱力ネタを平気で仕込んでくるし,多くの作家が短編では思いっきり羽目を外していることもある。クラスの真面目くんが一生懸命ギャグを言っている,そんな痛々しさがある。-----------各編について簡単に感想を述べる。「もうひとつの助走」:中堅作家・寒川心五郎は有名な文学賞の候補となった。何回も候補に挙がり落選している寒川は,諦めているふりをしながら実は受賞を渇望している。そんな中,電話が鳴り・・・この手の設定の作品は多くあるので目新しさはない。ヒネリが足りない。「線香花火」:会社員の熱海圭介は,文学新人賞を受賞した。それを親戚に報せ大絶賛された熱海は,同じことを勤務先で語ってしまう。だが同僚や上司の反応は冷たく,それに反感を覚えた彼は・・・そこで終わり?ヒネリどころかオチもなしか?「過去の人」:文学賞の発表会に呼ばれた熱海圭介は,気合いを入れてスーツを新調し,名刺を刷って乗込むが,編集者さえ彼のことを忘れかけていた。それなのに・・・うーん,またオチなし。「選考会」:作家の寒川心五郎は,文学新人賞の選考委員に選ばれて有頂天になる。彼を含め3人の作家は,最終選考に残った4つの小説に対して意見を交わす。激論の末に彼らは新人賞候補を選んだのだが,出版社は・・・文学賞の選考の様子については,他の人も体験を書いているが,そこそこ興味深い。ちゃんとオチがあって救われた。「巨乳妄想症候群」:少女のイラストを得意としている〈私〉は,何でも巨乳に見えてしまうという病にかかる。医師に症状を抑える薬を処方してもらったが,そのため・・・確かにコミックやアニメの女性の体型って異常で気持ち悪いと思っていたので,なかなか共感してしまった。オチもあるし!!「インポグラ」:男性が1日の間,性的に不能となる薬が開発され,世の中の女性たちは浮気防止のためにそれを夫や恋人に飲ませる。当初は大人気だった薬は,ある時から売れなくなる。それは?・・・あの有名な薬からこの短編を考え出したのはさすがだ。短いし面白い。「みえすぎ」:ある朝起きると〈俺〉は空気中のチリ,蒸気,粒子などが見えるようになっていた!そして・・・SFっぽい設定で「もやしもん」みたいだ。このまま探偵になっても面白いと思う。「モテモテ・スプレー」:タカシは知人の博士から,”女性にもてるスプレー”をもらう。だがとにかく女にもてないタカシには,大量のスプレーが必要だった。それはエスカレートし・・・中盤から先が読めてしまう。もっとひねらないとなあ。「シンデレラ白夜行」:継母と姉たちにいじめられているシンデレラは,家事をこなすだけでなく,家計を助けるために働きに出る。その頃,貴族の舞踏会には覆面の美女が話題になっていた。そして王子が登場する舞踏会にも・・・”本当は怖い”系の物語は流行となったので,ダークなシンデレラが登場してもそれほど驚きはない。でもテンポよく進むので嫌いじゃない。タイトルに「白夜行」は不要だったと思う。「ストーカー入門」:華子に突然ふられた〈僕〉は,なぜか彼女に叱責され,愛を示すためにストーカーをやらされる。・・・設定がスラップスティックに振り切れていて悪くない短編だ。でも最後に普通の感覚に戻したのは失敗だと思う。「臨界家族」:川島家の1人娘・優美が大好きなのは,休日の朝に放映しているアニメの少女キャラクターだ。作品の中にも登場する”なりきりおもちゃ”を買い与えた川島は,次の週に新しいおもちゃが発売されたことを知り衝撃を受ける・・・体験談風で東野圭吾の身近にも幼い少女がいたことがうかがえる。オチとしては弱いのだけれど,途中の過程がスラップスティックなのにリアルで楽しめる。「笑わない男」:売れないお笑いコンビ〈拓也と慎吾〉は,手違いで高級ホテルに泊まらせてもらうことになる。2人は自分たちの命運をかけて,沈着冷静なホテルのボーイをなんとか笑わせようとする。2人の行動はだんだんと・・・題名通り全く笑えない短編だ。ヒネリがない。「奇跡の一枚」:女子大生の遙香は父親に似ているためもてない。ところが旅行先で友人と撮った写真の彼女はひじょうに美しくて話題になる。だがその写真をよくよく調べた兄はあることに気付く。・・・写真の秘密はちょっとオキテ破りだ。いい話にしたいのか,ギャグで通したいのか判断が難しいが,この作品の中では悪くない。
2017.11.21
閲覧総数 593
-
7

「ムギと王さま」エリナー・ファージョンを読んだ
短編ファンタジーの名手・エリナー・ファージョンの有名な短編集を読んだ。〇ストーリー若いロタは仕立屋として抜群の腕を持っていたが,元請けの仕立屋にいいように使われていた。隣国を治めている甥に伴侶がいないことを心配した女王は,王国中の若い女性を呼んで舞踏会を開催する。会場に毎日ドレスを届けるロタが会ったのは?ーーーーーーーーーー本来の「ムギと王さま」は20編ほどの短編が収録されていたが,岩波少年文庫に収録する際に,半分だけが選ばれたという昔の大人の都合がある。けれども現代の岩波少年文庫では,まったく同じ「ムギと王さま」というタイトル,同じ装幀イラストで,本来の20編を「ムギの王さま」と「天国を出ていく」に分けて収録している。知っている人は知っているのだろうけれど,検索しても作者も書名も同じなので,細かく出版年数を確認しない限り,どちらがどちらか分からない。古い版で10編ほどの「ムギと王さま」を読んだ僕は,きちんと20編を読み終えるには,またもう2冊を借りないといけないようだ。混乱する。ーーーーーーーーーーエリナー,というかエレノア・ファージョンの作品の魅力は,昔話と現代のファンタジーの間で絶妙に良いとこ取りをしているバランスだと思う。昔話のような単純さと怖いほどの割り切り方を持ちつつ,現代の我々が読んでも納得の行く人々の行動や運命流転が描かれている。単純さと奥行きの深さを併せ持っていて,子供は子供,大人は大人で楽しめる。多くの児童文学は再読なのだけれど,この作品は初見だ。これまでこれを知らなかったのは人生損をしていたんだなあ。ーーーーーーーーーー各編について簡単に感想を述べる。「ムギと王さま」:村の神童だったウィリーは,過去のエジプト王・ラーの持つ金銀よりも,自分の父親が育てたムギの方が貴重な宝だと主張する。エジプト王はムギ畑を焼いてしまうが,残ったのはムギは何千年も残り,ウィリーの父親の畑に実りをもたらす。・・・過去に飛んだと思っていたら最後に戻ってきてすとんと終わる。見事な短編だ。「月がほしいと王女様がないた」:月がほしいと思った王女は,屋根のてっぺんに上り行方不明となる。王国の探偵たちは王女を探し,昼の生き物は昼に反乱を,夜の生き物は夜に反乱を企てる。そして・・・繰り返しも多くてマザーグースのようだ。とてつもなく大きな物語となりかけるのだが?「ヤング・ケート」:ドウさんの女中ケートは,なかなか外出できない。でも機会をみつけて・・・これもマザーグース,あるいは教育的な逸話のようだ。裏の意味がありそう。「金魚」:誰よりもエライと思っている金魚は,海の王・ネプチューンに呆れられて金魚鉢に入れられる。・・・これも短くて切れ味が良い。「レモン色の子犬」:木こりのジョーは,父親の死後に木こり小屋を追い出されてしまう。いじめられている子犬と凍えている子猫を救い,父親と同じような木こりの元でジョーは暮らし始める。その頃,王国の王女がなくしたものを探しており・・・繰り返しが多くて昔話のようだが,ラストの部分などいろいろ考えさせられてしまう。「モモの木をたすけた女の子」:シシリー島の農村の近くで火山が噴火し,村まで溶岩が迫る。村を救ったのは?・・・予定調和の物語だが,味わいがある。「小さな仕立屋さん」:若いロタは仕立屋として抜群の腕を持っていたが,元請けの仕立屋にいいように使われていた。隣国を治めている甥に伴侶がいないことを心配した女王は,王国中の若い女性を呼んで舞踏会を開催する。会場に毎日ドレスを届けるロタが会ったのは?・・・〇〇と思わせて実は?という結末が良い。とても好きな短編だ。「天国を出ていく」:天国を出て行った2人の兄を探す弟は,パリに行き人間たちに温かく接してもらう。だがそれよりも大事なことは?・・・フランスの遊び歌に触発されて書かれている短編だ。かなりシュールな展開なのに,そこはかとなく侘しい味がある。「ティム一家」:ある村にはティム一家が住んでいて,皆は困ったことがあると彼らに相談していた。だがそれは・・・さくっと終わる短編。なるほどね。「十円ぶん」:5才のジョニーは学校の帰りに10円玉を拾う。駅でお菓子を買おうと思ったジョニーは,間違って券売機で切符を買ってしまう。そこで彼が冒険したのは?・・・シュールな部分もあるのだけれど,10円あれば少年はどれだけ楽しめるか,というシミュレーションでもある。通貨を円にしたのは正しいけれど,さすがに今では100円くらいにしないといけないだろうな。一番の傑作だと思う。「《ねんねこはおどる》」:110才のひいおばあちゃんと暮らすグリゼルダは10才だが,2人はとても仲良くしていた。だがグリゼルダが倒れて入院をしていた間に,ひいおばあちゃんは養老院に入れられてしまった。グリゼルダの起死回生の手段は?・・・可愛らしいおばあちゃんと,頑張るグリゼルダの物語だ。このまま終わってしまうのかと思ったら,あることが起きる。でもよく分からない。よく分からないけれど,面白い。
2018.07.17
閲覧総数 1889
-
8

〈深読み読書会〉「孤島の鬼」江戸川乱歩を観た
佐野史郎が司会をしているNHKの〈深読み読書会〉を観た。テーマは江戸川乱歩の奇書「孤島の鬼」だった。〇ストーリー丸の内に勤める蓑浦は,同僚の初代と結婚の約束をしていた。だがその初代に,箕浦の学生時代の知人で医者の諸戸が求愛をし始める。そんな中,どの扉も施錠された家で初代が刺殺されてしまう。箕浦は探偵・深山木を雇って自分でも捜査をするのだが,深山木は返り討ちにあってしまう。箕浦と諸戸は,事件の黒幕に迫るために,諸戸の故郷である紀伊半島の孤島へと向かう。そこで彼らを待ち受けていたのは?ーーーーーーーーーーーなるほど,前フリ通りの本格推理,謎解き,冒険,怪奇,BLの入り混じったキメラ的な作品だ。これは戦時中には「芋虫」と一緒に発禁本になってしまっても仕方がないいやはやスゴイ長編だ。ーーーーーーーーーーー今の時代の感覚だと,キメラなのだけれど,当時ミステリーが多く発表された雑誌〈新青年〉がカバーをしていたジャンルを考えると,あまりズレはない。なんと言うか,西洋から輸入されたミステリーと江戸から伝わる奇譚を合わせた広い範囲が範囲だったと思われる。ただそれにしても,3つ以上のジャンルにまたがっている作品はあまり多くはないだろうし,まして章ごとに場面が転換しジャンルまでが異なってしまうという展開は,さすがに珍しいだろう。ーーーーーーーーーーーむしろ短編が上手かったと言われている江戸川乱歩にとっては,章ごとに異なる作風で長編を仕立てるということの方が楽だったのかも知れない。まるで見世物屋敷のような長編だ。それも乱歩らしいか?ーーーーーーーーーーーさて読んでみるか・・・(実はまだなんだ)。
2019.01.26
閲覧総数 281
-
9

「半端者 -はんぱもん-」東直己を読んだ
『探偵はBARにいる』として映画化される東直己の〈ススキノ探偵シリーズ〉の特別編を読んだ。○ストーリー〈便利屋のデブ〉あるいは〈ススキノ探偵〉が大学生だった頃,札幌の夏は暑かった。〈俺〉は,まだ人の殴り方も知らず,ヤクザとの距離のとり方も知らず,女の扱いも知らない。だが少しずつ,自分が間違っていると思うことへの対処方法を学ぼうとしている。〈俺〉が〈俺〉になった夏の物語だ。-------------〈ススキノ探偵シリーズ〉の〈俺〉は,ススキノの飲み屋の常連で用心棒,主に夜の街の人々のトラブル解決を生業とする〈便利屋〉として登場した。時代がかったダブルのスーツを着ているので,下手をするとコスプレかとも思われてしまうし,ミスも多いのだが,やはり心の深いところではハードボイルドだった。そんな〈俺〉も,最初から出来上がっていたワケではない。作品ごとのつながりはそれほど強く無いが,これまでは時系列的に発表されてきたシリーズだが,突然第1作のさらに前の頃のエピソードを作品にしてきた。当たり前だが,映画化を機会に,読みやすく,若々しい作品を,というオーダーがあったんだろうなあ。-------------この作品は,最近のシリーズとは雰囲気が違う。ただし,それは最初から狙っている内容で,肯定的にとらえたい。この作品でも相棒として,〈俺〉の面倒を良く見てやっている,高田は,相変わらず頼りになる。チンピラとして登場した○○は,〈俺〉と対立しつつも,手際の良さで〈俺〉を感心させ,最後は互いを認め合って別れる。だが何よりも楽しめるのは,まだ若い〈俺〉を覗けることだろう。殴り方を知らない,ヤクザを怖がってしまう,金儲けの方法を知らない,トラブルの解決方法を知らない・・・まだまだ”半端者”の〈俺〉がそこにいる。-------------ストーリーは残念ながら散漫だと感じた。アパートに住む老人の地上げの問題,悪質な約束手形に対する報復の物語,フィリピーナ・ダンサーの謎の失踪,と小さなトラブルが続き,さてこれをつなぐストーリーはナニ?と思って期待をしたが,何も無いらしい。オチは無い。単純に,淡い青春が語られている。そう言うのもキライじゃないけど,ちょっと物足りない。-------------若い頃の〈俺〉は,いろんな部分で「ススキノ、ハーフボイルド」の主人公・省吾をほうふつとさせる。ただ,自分を確立しようと精一杯あがいていた省吾と比べると,中途半端な〈俺〉に対しては,飲み屋や,賭場や,ヤクザなど,周りの人々が本当に優しく扱っているように感じてしまった。これもまた時代ゆえの”ゆるさ”なのだろうか?〈俺〉って恵まれた人だったんだ。-------------〈ススキノ探偵〉のファンは,外せない作品だろうし,『探偵はBARにいる』で興味を持った人にもライトな語り口で向いていると思う。いろんな意味で,タイミングよく企画された作品だと思うな。-------------ところで,このシリーズって,最初は早川のハードカバーで出版されるのが通例だったけど,この作品は最初から文庫版で出てしまった。ハードカバーでそろえているファンは,・・・腹を立てているだろうなあ。
2011.09.08
閲覧総数 229
-
10

セントレア(中部国際空港)で温泉
5時台に起き出して名古屋へ向かった。中部国際空港で打合せだったのだけど,その前にどうしても三重のプロジェクトの現状を確認したかったのだ。名古屋で新幹線を降りて,“駅裏”椿町の喫茶店でモーニングセットを頼む。かつての市場町と花街に,専門学校というカラーが加わっている。どれをとってもJRの巨大ターミナル駅の駅前としては不思議な雰囲気だ。その一角からレンタカーを借り出し,四日市へ向かった。カーナビの現在地設定が狂っているため,画面の表示だとビルの中を走っている・・・・ちょっと混乱したけど,手動で補正をかけて乗り切った。ちょうど10時ごろ四日市には着き,オーナーへの挨拶,先週の進捗状況の確認を行い,所長から報告を受け,さくさくと11時には出発した。10を越えるプロジェクトをこなして来ているけど,ホントに愛着があるのは石川と三重の物件だ。この二つは“相棒”や“ワカゾー”抜きで単独で担当している。もうすぐこれに熊本が加わるけど,この数箇所はなんとか今後もフォローして,成長もサポートしたいと思う。また来ないとね。―――――――――――――――――――――――――――さて,三重県から愛知県へと,伊勢湾の湾岸をぐるりと時計回りに移動した。肝心の中部国際空港,通称“セントレア”だが,例によってこのカーナビは調子悪いので,陸の孤島,じゃなくて,沖の離れ小島として表示されている。しょうがないので常滑市を目標に設定して,後は標識を頼りに走った。画面の表示だと海の上をずんずん走っている。これは補正のかけようがない。ホントは11時頃に着いて,飛行機を見ながら風呂につかりたかった。実際はもう12時くらいだったので,食事をする時間しかなかった。空港はレストラン街がめっちゃ混んでいて,老人ホーム状態だ。主に“コイツら飛行機乗るのか?”って人たちがゾロゾロいる。おかげで,どこの行列も非効率な状況になっている。“ちょうちん横丁”をあきらめて,“Bagel & Bagel”と“Soup Stock”という,東京のどこかで摂れるような食事となってしまった。残念。―――――――――――――――――――――――――――ヒルメシの後は仕事だ。昨日の晩に作っておいた資料を利用して,空港会社の人たちにこちらの提案をぶつける。最初は呆れられていたけど,技術的根拠とこちらの内情をみんなで説明し,(予定しておいた)妥協をしてみせて,なんとかこちらの要望でプロジェクトを計画してもらうこととなった。時間はかかったけど,うまくいった。車を名古屋駅へ返却し,新幹線と特急を乗り継いで,金沢へ移動だ。名古屋から,米原,長浜,敦賀,武生,鯖江,小松と慣れ親しんだ地名を通り抜けていく。施工会社との清算のための出張,ってことになっているけど,内情は僕のもう一つの秘蔵っ子の石川プロジェクトの打ち上げ旅行なのだ。たまには息抜きさせてよ。プライベートにまったくウルオイがないんだし。って最近,息抜きがめちゃ多いなあ。
2005.05.25
閲覧総数 6
-
11

「鏡の花」道尾秀介を読んだ
久々に道尾秀介の作品を読んだ。「光媒の花」とゆるやかにシリーズを形成するらしい。○ストーリー小学2年生の章也は,姉と一緒に,自分が生まれる前に両親が暮らしていていた家を訪ねる。そこには妻に先立たれ,息子は独立し,1人暮らしとなった老人・瀬下が住んでいた。章也はこの家であることを突き止めようとしていた。そして章也と翔子が抱えていた秘密とは?------------6つの短編で構成された連作作品だ。それぞれの短編で語り手が抱えている悩みがあり,それがあるきっかけで解かれるという展開を基本として進む日常ミステリだ。けれども3つ目の短編くらいから,露骨な違和感がゴロリと示されていて,それがまた別のミステリ要素として読者を引っ張る。その謎解きは,「光媒の花」から続く異界からのメッセンジャーとしての白い蝶,そして第六章で語られる物語で解かれることとなる。------------いろいろな作家の作品を読む僕だが,道尾秀介の文章には毎回感心する。自然な会話文,ごく普通の地方都市の情景の描写や,老若男女の心情の描写の的確さ,読者の想像を掻き立てるために一歩手前で筆を止める巧みさ,どれを取っても高いレベルで,最近は本当に全方位にスキが無いという印象だ。この作品では,似たような短編が続くので,どうしても終盤にかけて「またかよ・・・」みたいな中だるみが来てしまう。それも第六章で語られる別展開に向けての伏線となっているので,ゆるせてしまう,というのが,これまたこの作者の恐ろしさだ。もっとも,道尾秀介ならば,もっと面白く緊迫感のある作品があるので,この繰り返しの多い作品は,個人的にはオススメ出来ない。------------各編について,ネタバレの無い範囲で簡単に感想を述べる。第一章「やさしい風の道」:自分の家族がかつて住んでいた家を突き止めた章也は,姉とともにある目的を持ってその家を訪ねる。そこで出会った老人から,聞かされた話とは?・・・バスの乗客,姉弟の微妙な交流,家庭菜園の作物,どの描写も巧い。意外な結末も含め,楽しめる短編だ。第二章「消えない花の声」:栄恵は息子とともに,かつて暮らした海辺の街に一泊をする。そこで彼女は否応無く夫が死んだ事故を思い出すが,意外な事実を知る。・・・この章では一気に老境に達した主人公となり,それに合わせた作風となっているのが見事だ。花の描写も見事。第三章「たゆたう海の月」:瀬下夫婦は1人息子が転落死をしたという報せを聞き,その町へと急ぐ。果たして息子は何かを悩んでいたのか?不思議な蝶の葉書に誘われ,2人がたどり着いた結論とは?・・・この章は重いし,主人公が老人なのでひじょうに陰鬱だ。前の章の内容と合わせると,いろいろと考えてしまう。第四章「つめたい夏の針」:翔子は友人・真恵美の弟・直哉と隠れて仲良くなったために,彼女と気まずくなる。そんな中,2人は夏のオリオン座を見に出掛けるが・・・主人公が若い人だと,感情の振幅があるものの,全体的に透明で明るい物語になる。第五章「かけそき星の影」:妊娠中の葎(りつ)は,母の見舞いの帰りに出会った姉弟と,プラネタリウムに行く。姉弟はある秘密を抱えていて・・・ここまで来ると,「ほう,そう来ましたか?」という気持ちになる。で,どうなの?とも思うけど。第六章「鏡の花」:幼い頃の事故で顔に怪我をしてしまった美代の家は,民宿を経営している。そこに2つのグループが泊まりに来た。その夜,美代は蝶に誘われて,ある所を目指して行ってしまう。美代の家族と,宿泊客たちは,彼女を捜して不思議な体験をする。・・・ここに来て新キャラですか?!と思ったら,やはり原因は旧キャラにある?後半はいろいろ気になって,1つ1つの短編に集中や感動出来ないのが,この作品の欠点だと思う。
2014.03.25
閲覧総数 1911
-
12

「人生相談」真梨幸子を読んだ
〈イヤミス〉の女王・真梨幸子のしかけ満載の連作短編集を読んだ。○ストーリー米田美里は,アパートの隣人から騒音に対するクレームを受けていた。彼女自身はひじょうに気を使って,最低限の音しか立てないように努力をしていたのに。疲れ果て,逃げるように実家に帰った美里は,実家の風呂に入って鼻唄を歌う。その時!!------------真梨幸子は映画化された「殺人鬼フジコの衝動」で名前を知った。それでも長いこと手に取ることは無かったが,〈王様のブランチ〉で紹介されていた「人生相談」で興味を持つようになった。新聞の〈人生相談コーナー〉に寄せられたいくつかの投稿の断片的な情報から,ある事件が浮かび上がってくる。・・・そのプロットを聞いて,「お?いつか読んでみよう」と思うようになった。真梨幸子の作品を,なるべく順番に追ってきて,ようやく当初から興味を持っていたこの作品にたどり着いた。------------こうして読み終えたのだが,確かにこの作品の構成はひじょうに面白い。だが最後まで至っても,短編ごとの時系列,過去に起きた複数の事件についてが不明確だ。このためパズルがピタッとはまる爽快感が得られず,読後感はスッキリしない。あれ?〈ブランチ〉で紹介された「驚愕の真相が見えてくる」という言葉と微妙に一致していない気がするなあ。いろいろな伏線が張られ,タワーマンション(真梨作品恒例の仕掛け),出版社,文章教室,キャバクラ,謎の家,と複数の場所があり,と広い舞台が準備されているのに,あいまいなラストのおかげで,せっかくの作品が活きていない印象だ。傑作になったかも知れないのに,ひじょうに残念だ。------------各編について簡単に感想を述べる。「居候に悩んでいます」:相談者は少女で,家族が住んでいた家に,突然居ついた居候家族に対する怒りと悩みを述べている。現実世界では,どうやらそれから20年近く後のようで,少女の弟と思われる青年が主人公となっている。キャバクラ嬢に貢ぐために,今では彼一人が住んでいる家の売却を検討しようとするのだが,なんと?・・・〈イヤミス〉っぽい始まり方で,期待感はひじょうに高まる。2つの家族の不自然な同居生活,その裏に隠された闇とは?「しつこいお客に困っています」:相談者は接客業で,苦手な客の担当をさせられて困っているというもの。現実では編集者・佐野山美穂の苦労が語られる。小ズルい同僚の岡部,大人し過ぎる作家・樋口義一,そしてエステ通い。〈良い人〉のはずの佐野山だが?・・・前の短編と複数の登場人物が重なっているのだが,まだまだよく状況が見えない。佐野山みたいな人っているよね(笑)。「隣の人がうるさくて、ノイローゼになりそうです」:相談者は隣人から騒音の苦情を受けている。現実世界でも,タワーマンションの受付・コンシェルジュをしている米田美里は,隣人からクレームを受けていた。いろいろな不運が重なり,逃げるように実家に帰った美里だったが,くつろいでいた時!?・・・あまり他の短編とはリンクが無さそうだが,ホラーっぽい仕立てでピリッとしていて楽しめる。「セクハラに時効はありますか?」――」:相談者は過去に部下の女性にセクハラをしてしまったサラリーマン。現実世界ではある会社で2人の課長が部長への昇進を巡って競争している。セクハラの投稿の主はどちらの課長なのか,会社の中でいろいろな憶測が飛び交う。最後に笑ったのは?・・・これもまた他の短編とはリンクが薄そうだ。同じ町の別の事件ということか?「大金を拾いました。どうしたらいいでしょうか」:相談者は札束の入った袋を拾ったと戸惑う人物。現実では食品工場でバイトをしている3人の男女が,休憩時間に話し合っている風景が描かれる。バイトの1人・野山寛治は,新聞記者の川口寿々子が講師を務めている,文章書き方教室に通い,出来れば小説家になりたいと思っている。ある時から川口に連絡がつかなくなり・・・他の短編で名前は出ていた川口寿々子の登場だ。これは過去編ってことだろうが,では現金の出所は???「西城秀樹が好きでたまりません」:相談者はアイドル時代の西城秀樹のファンで,彼が自分に向けて歌を歌っていると主張する。現実世界では,編集者・佐野山美穂が再登場し,樋口の依頼で過去の〈人生相談〉について調べ始める。・・・〈人生相談〉と過去の事件のリンクが見え始める。それを調べている作家・樋口の目的は?「口座からお金を勝手に引き出されました」:相談者は夫にへそくりを盗まれている女性。現実では編集者・岡部が相変わらず愚かな行動をしており,キャバクラ嬢に貢ぐ金欲しさに妻の口座に手を付ける。さらに岡部は人気作家・武蔵野寛治に作品を書いてくれるように頭を下げるのだが・・・舞台はタワーマンションに戻り,いろいろとまずい状況の岡部が無様な姿をさらす。最初の短編の家の話も登場し。でもまだよくわからない。「占いは当たりますか?」:相談者は結婚を控えている女性。親が占い師の言葉を信じて結婚に反対を始めた。現実世界では作家・武蔵野寛治と妻との生活が描かれる。武蔵野の妻のところに,佐野山の同僚・高橋が現れ,過去について質問をする。そして悲劇は・・・えっ?この女性もサイコなのと驚いてしまう。登場人物が全員どこかおかしくない?? 「助けてください」:相談者は亡夫の借金のため逃亡生活を送っている。現実世界では,新聞記者・川口が2つの家族を救うために,同居をさせる。そして20年後,複数の調査結果が明らかになり。・・・怒涛の勢いで物語は進むのだが,あちこち不明な点を残したままなので,普通に読んでいると読者は完全に置いてけぼりになる。いろいろと不親切で損をしているなあ。惜しい,実に惜しい。
2015.12.10
閲覧総数 2102
-
13

「私の家では何も起こらない」恩田陸を読んだ
恩田陸の幽霊屋敷を舞台にした連作短編集を読んだ。○ストーリー街外れの小さな丘の上に建つ古い家で私は暮らしている。この家には過去にいくつかの事件があったので,その調査を希望して訪ねてくる人もいる。だがそれ以外にも,この家を騒がす存在がいる。それは・・・-----------もちろん”何も起こらない”ハズがない。複数の主人公の視点で,ある家の歴史と事件が語られる。中には残虐な事件も含まれるが,恩田陸の文章によって,懐かしい印象を与えてまとまっている。地名も人名も一切言及されないため,舞台となる国も時代も明らかではない。レトロな空気や文化からして,どうやら英国が舞台で,20世紀の初めから中盤が時代という設定のようだ。-----------読み始めてしばらくは,あまり奥行きの無い物語のように思えた。レトロな空気感だけを用いたホラーのように思えたからだ。いくつか短編が進んでから,作者の恩田陸が突きつけてくる内容が見えてくる。「なぜ生者は幽霊に惹かれるのか?」「なぜ我々は古い物が好きなのか?」古い家,古い建物を訪ねて回るのはなぜなのだろうか?歴史を感じて,そしてさらに何を感じようとしているのだろう?-----------そして繰り返し語られる幽霊譚の中から,徐々に死者と生者との境界線があいまいになる瞬間が出てくる。いつしか死者は生者を脅かす存在ではなく,単純に同じ空間にぼんやりと存在しているモノになる。過去,あるいは思い出のように。これは「ネクロポリス」で展開されたテーマに近い。だが死者との交流に特定の場所と時間を必要とした「ネクロポリス」の世界と異なり,今回の作品ではごくフツーの家でそれが可能となる。コワイような,当たり前のような・・・-----------各編について簡単に述べる。「私の家では何も起こらない」:女性作家が住む家に,ある男性が押し掛けてくる。彼はこの家が幽霊屋敷だと主張するのだが・・・読み返すと,この作品のテーマが背景にうまく練りこまれている。家を建てたのは女性作家の叔母。この家で起きた過去の事件AとBが言及される。「私は風の音に耳を澄ます」:貧しく暴力的な両親から逃げて,ある家にかくまってもらっている私。だが人々は私の姿を見て悲鳴を上げるのだった。・・・伝統的なホラー。事件Bに巻き込まれた少女の物語。「我々は失敗しつつある」:我々は本当の幽霊屋敷を求めて,いくつもの家を巡る。だが我々の夢をかなえてくれる本物にはなかなか出会えない。・・・この作品で一番難解な短編だ。単なる幽霊屋敷マニア?それとも?事件Aが言及される。「あたしたちは互いの影を踏む」:念願の持ち家を手に入れた老姉妹。仲良くアップルパイを焼き始めたが,彼女たちの目の前に現れたものとは?・・・どこか乾いている印象のホラー。事件Aの主人公2人。「僕の可愛いお気に入り」:学校で話し相手のいない大人しい少年。彼の友人は可愛い美少女だった。そして彼女はなぜか家の床下に住んでいた。・・・だんだんサイコになってくるホラーだが,ファンタジー風でもある。新しい事件Cの物語。「奴らは夜に這ってくる」:夜になると丘の方向から近付いて来る不思議な音。だが決してそれを見ようとしてはいけない。見たものには必ず不幸なことが訪れる。・・・これも伝統的なホラーだ。家が建つ丘は過去の遺跡だった。「素敵なあなた」:曾祖母が建てた家を見に来た女性は過去の幻を見る。・・・過去と現在が混じり始める。事件A,B,Cが言及される。家を建てたのは女性の曽祖母。「俺と彼らと彼女たち」:街外れのいわくつきの家に新しい住人が来る。家の修理を頼まれた俺は,扉を開けてみて驚く。”古くからの住人”が待ち構えていたのだ。・・・この作品の転換点だ。一見粗暴だと思えた大工の男が,奇蹟を起こしてみせる。この女性も作家。「私の家へようこそ」:古い家に移り住んだ女性は,都会からの友人に家を案内する。彼女と家は見事に調和していた。・・・素晴らしいエンディングだ。ほのめかされる新しい事件が不気味だ。「附記・われらの時代」:自分が住んでいた家をモチーフにして連作小説を書いていた女性作家。彼女の思い出が語られる。・・・テーマをきちんと記しておこうとする気持ちは分るが,蛇足だ。出版される際に書き下ろしで追加したということだが,不要だったと思う。
2010.09.05
閲覧総数 3209
-
14

「鬼の跫音(おにのあしおと)」道尾秀介を読んだ
道尾秀介のホラー短編集を読んだ。○ストーリー掘り起こされた死体がきっかけで取調べを受けている男。彼が隠そうとしている罪は何なのか?鈴虫だけが,その全てを見ていた。------------久々に道尾秀介を読んでみて,感服した。まずはどの短編も,手に取れるような実体感のある”不安感”に満ちている。それは登場人物が感じていたりもするが,間違いなく読者の中に満ちてくる。次は見事なストーリーテリングだ。各短編の始まりはスッと無防備に入ってきてしまって,あっと言う間に読めてしまう。それなのに少しずつ違和感が発生し始めて,そして恐怖の結末へと向かう。なんだか妙にクヤシイけど,とにかく巧い。------------作品の空気は,僕が最初に読んで絶句をしてしまった道尾秀介作品「向日葵の咲かない夏」に近い。どの短編もチリチリとした不安感に満ちていて,S君という友人が登場し,少年か少女が物語に関わり,カラスが悲劇の予兆を告げる。そうした共通のパーツを持ちながら,各短編は驚くほどタイプの異なる構成,ジャンル,そしてロジックとなっている。これは道尾秀介の最初の短編集らしいが,若い作家らしく,まだまだ書き足りない,とでも言いたいようにチカラに満ちている。さすが道尾秀介,他人を不快にさせるテクニックは天下一品だ。------------「鈴虫」:10年ぶりに発見された友人の遺体のそばから,私の所持品が見つかった。私が警察に語った不思議な物語とは・・・ヘンだなと思いつつも,最後に納得させられてしまう。ミステリー的には設定的にはひじょうに凡庸なのに,作品としてはよく出来ている。「ケモノ」:静かな僕の家で,過去からのメッセージが発見された。僕はそれが指し示していると思われる,20年前の事件の舞台へ足を運ぶが・・・真相に近付いても,誰も幸せになれない,という特殊な物語。「よいぎつね」:祭りの夜,女性を襲った僕は,20年後に訪れた祭りで,若い男に遭遇する。・・・タイムスリップモノなのか?人間に対する天罰を語っているのか?不思議な作品だ。「箱詰めの文字」:作家となった僕には秘密があった。それをあばきに来た男を,僕は・・・これまたミステリーとしては,かなりありふれた設定だ。アパートを人々が行き来する,不思議な道尾ワールドだ。「冬の鬼」:彼と暮らし始めてから数日を語る日記文。だがそこには驚愕の事実が隠されていた。・・・1月8日から1日ずつ過去へとさかのぼる形式の短編だ。ありえないほどキツイ条件なのに,見事にホラー&ミステリーとして成立させていて,びしりと割れてしまいそうな緊張感に満ちている。「悪意の顔」:全てを呑み込んでくれる絵画。そこに自分の恐怖を吸い込ませ,クラスのS君とうまく付き合っていこうと考える僕だったが,事件は意外な方向へと動き始める。・・・これだよ!これ!少年のファンタジー世界と,現実の事件がシンクロしていて,同じ場面で違う恐怖感を味わうことが出来る。複数の解釈が出来る短編でもある。
2011.04.26
閲覧総数 1228
-
15

『トワイライト ブレイキング・ドーン Part 2』を観た
恋愛ファンタジー映画シリーズ,〈トワイライト・サーガ〉の最終章を観た。○ストーリーヴァンパイアのエドワードと結ばれたベラは,ついに自分自身もヴァンパイアとなった。だが彼らの娘・レネズミが〈不滅の子〉であることを疑い,ヴァンパイアの王族〈ヴォルトゥーリ〉は非難をする。彼らが粛清に訪れることに備え,ベラたちはヴァンパイアと人狼族から仲間を集める。強力な〈ヴォルトゥーリ〉の襲撃を,ベラたちは耐えられるのか?------------2年と少し前に映画第1作を観た。いろいろと文句を言いながらも,このシリーズの面白さを楽しんでいたが,ようやくこの作品で完結だ。学園ドラマとして始まったのに,あっと言う間に「彼と私」の物語に変わってしまったり,控え目な性格だったはずの主人公が,いつの間にか怖いヴァンパイアママになっていたり,とか,いかにも恋愛ドラマ的に,どんどんと物語の中心が〈私〉へと向かっていくのもご愛嬌だ。とは言え,僕自身も楽しんだが,世界的なヒットになったのも,人狼族,ヴァンパイアの様々な種族など,ファンタジックな大きな展開があるのが,このシリーズの魅力だと思う。------------前作『Part 1』の最後に,瀕死だった主人公ベラはヴァンパイアへと変質(変態?)した。そうしたらいきなり性格ゴーマン!!これまで三角関係だった人狼のジェイコブを「臭い」とか,いくらなんでもひどいと思うんだよね。男性なら特に思うと思う。ま,これも恋愛ドラマの常として,自分以外の視点はどんどん無視されていく。------------ずーっと”イヤなヤツ”だったヴァンパイアの王族〈ヴォルトゥーリ〉たちとの全面対決という展開は,「待ってました」というものなので,ホントにストーリーテリングの上手さを感じる。そのために世界中から,いろんなヴァンパイアが集まってくるという展開ももちろん面白いが,こんなにイッパイいたんだ。しかも南米から来た種族は最後まで薄着で,東欧から来た種族はずっと冬服って,ホントに分りやすいな。ついに訪れた全面対決。どんなドラマが起きて,どんな結末を迎えるのか,ぜひ自分の目で見ていただきたい。------------自分以外でも男性がこっそりと観ているんじゃないかと思う。素直に面白いよね?!
2013.11.22
閲覧総数 34
-
16

東野圭吾の「幻夜」と「白夜行」の比較
東野圭吾の大長編「幻夜」を読み終えた。今回,この作品と「白夜行」の比較をしたいと思う。僕にしてはネタバレをしているので,両方の作品を未読の方はパスをお願いする。----------この作品と比較されることの多い「白夜行」は3年前に読んだ。その頃は東野圭吾を系統的に読むつもりは無かったのだが,中山七里の「嗤う淑女」を読んだことで,似たような悪女のピカレスクロマンがあることを聞き付け,この作品にも手を出した。東野圭吾を読み進めている現在としては,「こんな逆の理由で大傑作を手に取り,東野圭吾ファン,ごめんなさい」という気分だ。----------「白夜行」を読んだ際に,「幻夜」という姉妹編があることは知った。だが,前者が文庫版で900ページ,後者も700ページと知り,”もうお腹一杯”状態だったのでパスをしてそのままとなっていた。東野圭吾を読破することと決意して,とうとう「幻夜」も読み終えた。割と事前情報を入れない主義の僕なので,これが「白夜行」の姉妹編で,同じテーマを描いたパラレルな別作品だと思ったまま読んでいた。ラストが近づくと,どうやらこの2つの作品にはリンクがあり,続編としても読むことが出来るという仕掛けが分かってくる。この是非については,東野圭吾があいまいにしているので,僕としてはそのまま読者が自分の解釈をする,ということで良いと思う。作品を読んだ限りでは,決定的なことは何も描かれていなかった。----------それより気になったのは,2つの作品の相似形と差異だ。男女が関西で出会って,東京へと移り住み,女が社会的に成功を収め成り上がる。だがその裏では,男が彼女のために障害を排除し,ライバルを傷付け,非合法な手段で彼女を支え続けていた・・・という部分は姉妹編と言われるように完全に相似形だ。----------だが「白夜行」の男女は幼馴染で,2人とも貧しく品性の低い親の家で,虐待を受けており,互いをかばい合い,助け合って生きていくという姿が,ピカレスクロマンとして成立をさせていた。それに比べて「幻夜」の男女は,阪神淡路大震災の際に出会い,身寄りを喪った2人が,ある事件から逃げるように東京へと出ていくのだが,ここにあるトリックがあったことが後々分かってきて,ひじょうにイヤな展開となる。「白夜行」の女性・西本雪穂は美しく,さらに冷静で賢い。一方の男性・桐原亮司も売春のあっせんする一方でソフト開発をするなど,なかなか多才だ。2人の関係は雪穂と亮司で五分五分ではなくても,せいぜい六分四分だろう。それが「幻夜」では,女性・新海冬美は大人しそうだがどんどん美しくなり,男たちを手玉に取る。男性・水原雅也は機械加工,金属仕上げの技術は素晴らしいが,それ以外は何もしない人物だ。2人の関係は,七分三分と大きく冬美が支配的で,それだけでなく・・・という設定だ。----------「白夜行」では2人の幼馴染が世界に対して挑んだ戦いの記録と解釈が出来る。「幻夜」ではミステリー要素はより楽しめると思うが,肝心の主人公たちの行動原理が冷え切っていて,中盤以降読んでいるのがツラくなってしまう。海外旅行から帰ってきた冬美が夫と交わす会話などは,もう正気とは思えない。中山七里の「嗤う淑女」に対しては,非現実的で上手く行き過ぎるという批判を述べたが,「白夜行」はともかく「幻夜」に関しては同じような匂いを感じてしまった。ミステリー要素以外はあらゆる部分で「白夜行」の方がレベルが上だと思う。----------さらなる続編で3部作を構成という構想もあるらしいが,またまたレベルを下げるだけならば,止めておいた方がいいと思う。
2018.02.28
閲覧総数 11993
-
-
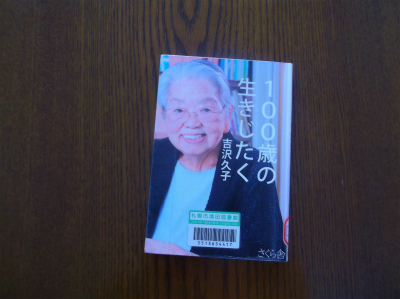
- 本のある暮らし
- 吉沢久子「100歳の生きじたく」/肉ま…
- (2025-02-22 05:18:11)
-
-
-
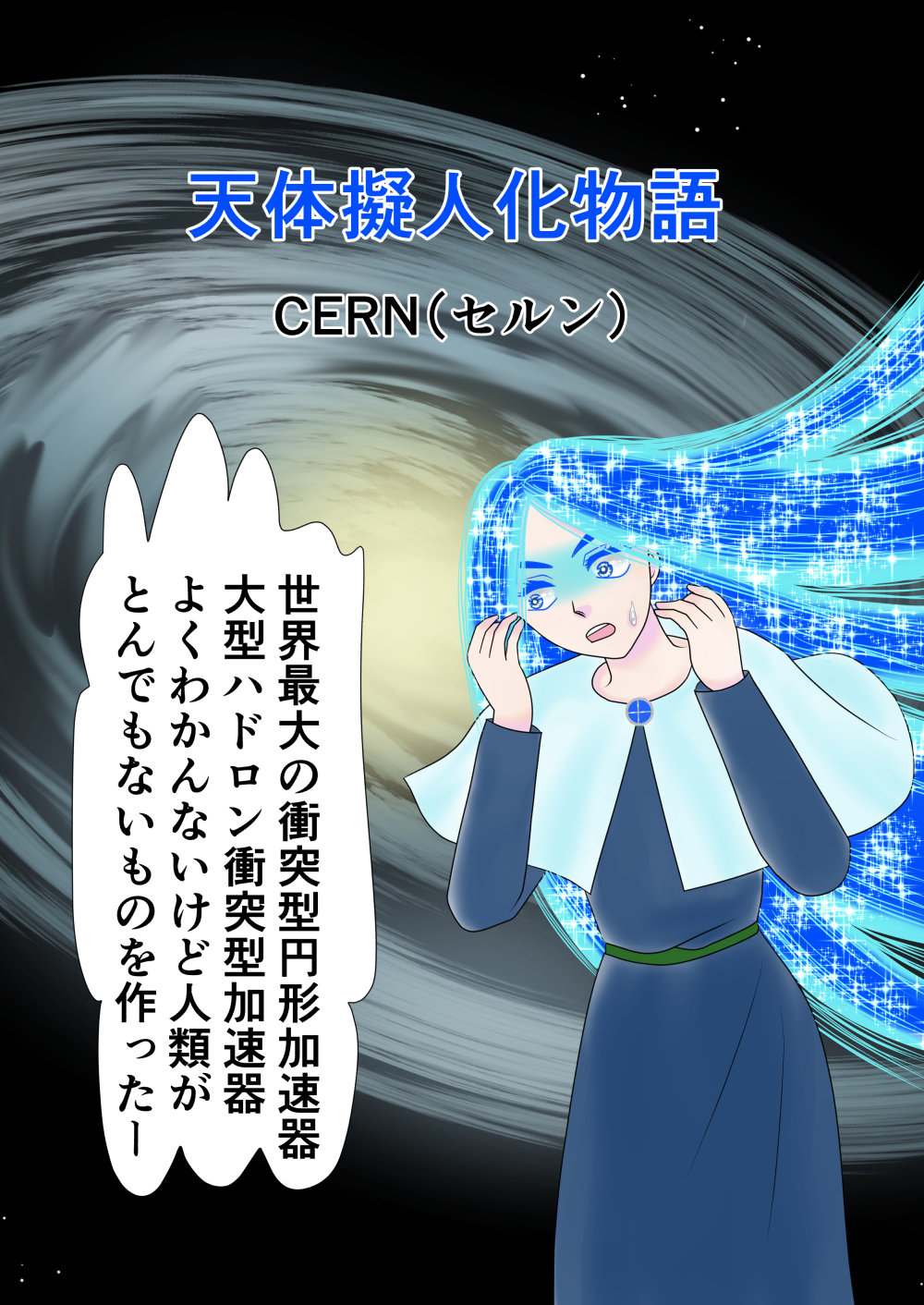
- マンガ・イラストかきさん
- 天体擬人化物語 アルファポリスさん…
- (2025-02-24 17:46:46)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 購入|「THANK YOU SO MUCH (完全生…
- (2025-02-22 20:18:46)
-







