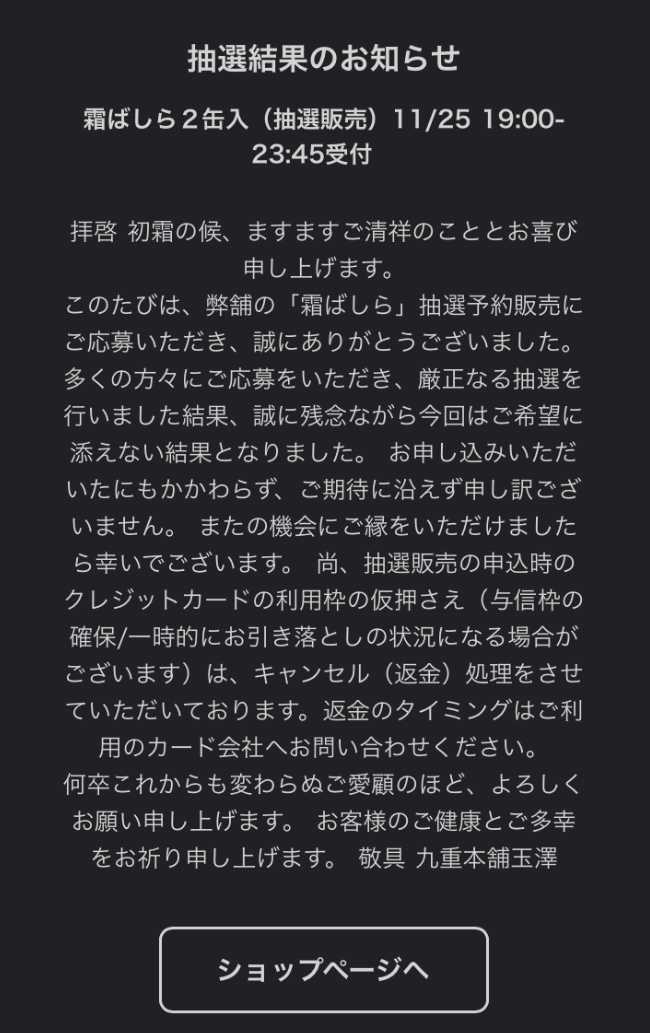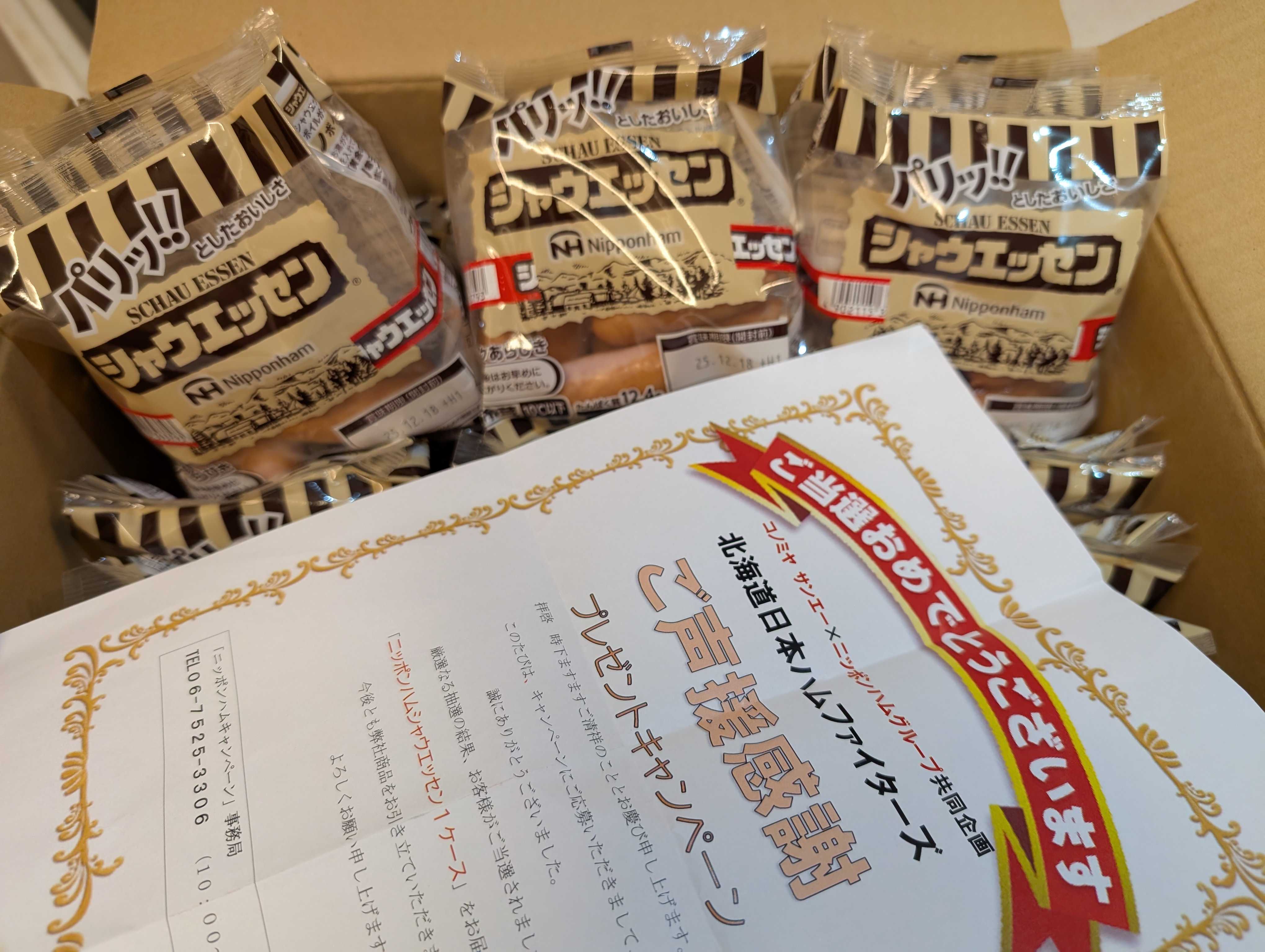2015年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
「リハ栄養学術集会」に参加 その3
第4回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会(in 名古屋)に参加。その3です。今回の口演、ポスター発表の概要です。◆栄養状態と身体機能・嚥下機能との関連性の研究 ⇒相関や関係性あり◆リハと栄養管理を行うことでADLがアップした症例や、複数人数を対象とした発表。 ⇒しかし、栄養管理の未介入例と、リハ栄養管理をした例とを比較した発表は見られず。◆回復期でのリハ栄養の活動報告◆リハ栄養の意識調査◆体組成モニターによる筋肉量増加のモニタリングなどがありました。やはり、リハ栄養管理を「実施した群」と、「実施していない群」を比較するのは難しい。リハ栄養を開始した後では、「しない群」を作るわけにもいかず。かといって、リハ栄養を開始していなければ、そもそも、このような発表はされない。
2015年01月17日
コメント(2)
-
日本ST協会の「基礎・専門プログラム」修了証
日本言語聴覚士協会の「基礎プログラム修了証」「専門プログラム修了証」が届きました。これだけでは、特に何もないのですが、とりあえず、少し達成感です!認定言語聴覚士になるための講座の受講資格が得れただけで、現状では、来年度、受講するかも決めていません。症例報告もあり、内容としては厳しいという話も聞きます。修了証に至るまでに、何度も講習会や学会に行き、受講票はいっぱいになりましたが、それに費やした時間や費用に見合うだけの勉強ができたか?、臨床に活かせているか?というと、感覚的には1/3~半分程度でしょうか。学会参加では、新しい情報の収集や、STとして刺激を受けた場として、役立ったと思います。また、学会発表、地域の症例発表では、自分の臨床などをまとめ、見直すきっかけとして、大変役立ちました。無駄にならないよう、復習もしていきたいです。
2015年01月14日
コメント(0)
-
ディサービスでの勉強会
以前、ディサービスの施設の知り合いのスタッフから、言語聴覚療法についての勉強会をしてほしいと依頼を受けました。迷いましたが、自分の勉強のためとも思い、引き受けました。事前にいくつか質問事項をもらい、言語聴覚士の仕事内容や失語症、構音障害を中心に準備しました。いつものように、準備がギリギリになってしまい、だいぶ、かなり焦ってしまいました。(逆に、これを乗り越えられたら、自信がつくかなと考えながら)結局、STの先輩が以前、他の施設で勉強会を実施したパワーポイントを参考に作成していき、何とか形になりました。いや、形になったかわからない状態で、勉強会が開始となりました。スタッフの方20人ぐらいに対して、まず、講義を1時間弱行い、その後は質問を受けました。質問は少しかと思っていましたが、10件以上の質問を頂き、そのやり取りだけで30分ほどかかりました。非常に熱心に質問して頂けました。その施設や関連施設にはSTはおらず、失語症や嚥下障害で困っていることが多いようでした。あらためて、「失語症の方への対応」など、再考する機会となり、勉強になりました。
2015年01月12日
コメント(0)
-
「リハ栄養学術集会」に参加 その2
第4回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会(in 名古屋)に参加。その2です。今回の学術集会で、一番印象に残った講義は、高畠英昭先生の『脳卒中におけるリハビリテーション栄養』でした。内容は、「絶食により肺炎は予防できるのか?」がテーマです。先生の研究では、脳出血の患者で、◆通常の嚥下訓練を進めるコントロール群(RSSTやMWSTなど)と、◆早期から口腔ケア(ブラッシング、リンシング)、早期離床、早期経口摂取を行う介入群を比較すると、介入群の方が、経口摂取に至る割合が多く、肺炎の発症率も低かったとのことです。いきなり、この方法を取り入れるのは難しいですが、◆早期からの口腔ケア(口腔内への刺激、清潔にする) ⇒口腔ケアの頻度を増やす。間接嚥下訓練。◆早期離床を行うことは重要であることが再認識されました。病態や主治医の指示による絶食期間はありますが、いつでも、経口摂取訓練ができる準備をしておくことが大切だと思いました。「日本リハビリテーション栄養研究会」への入会は無料で、Facebookをされていれば、誰でも入会可能です。この講義資料は、リハ栄養のfacebookからダウンロードできます(現在は)。
2015年01月08日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1