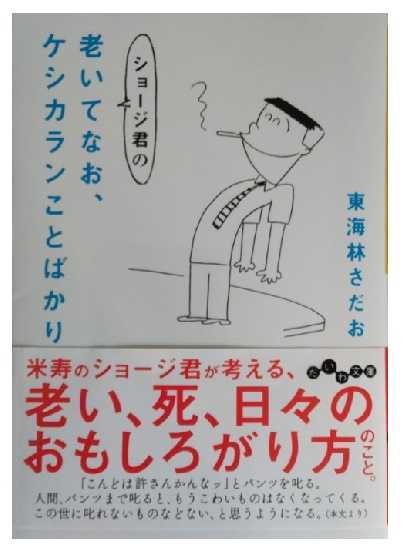全177件 (177件中 1-50件目)
-
「養老先生と遊ぶ」 SHINCHO MOOK
ベストセラー嫌いで「バカの壁」は読んでいないけれど、以前から養老先生の本は読んでいました。 今回、楽しそうな本が出たので買ってみると、「新潮新書風 13歳からの『バカの壁』」というのが付録?でついていました。ほんちゃんの内容とは違うのかな? この13歳からの。。。で、目をぱっちりさせられた言葉が幾つかあったので拾ってみます。 ・たくさん知識があるからといって、それがそのまま「すべてをわかっている」ということにはつながらない。 (その例として、人を安易に殺すことは悪いことだということがわからなくなっている大人たちによる「戦争」をあげています。) ・無理に「個性を伸ばさなきゃ」などと思う必要はない。 ・多くの人が「個性」は脳のなかにあって、からだにはないという勘違いをしている。 (個性は教育で伸ばせるようになるものではない。個性を強調して無理に人と違うようになることより、他人の気持ちがわかるようになるほうがいい、とのこと。) ・現代人の多くは「わたしはわたしで変わらないものだ」と思いがち。でも、それは大間違い。 (人間のからだの大部分は水でできていて、一年間あれば全部入れ替わる。去年のわたしと、今年のわたしは大部分が別物・・・そうだよなあ。「わたし」は刻々と変わっているのです) 自分が正しい、自分は変わらないと思った時点で新しくものを考えなくなる。 子供が失敗しながら歩き方を覚えるように、苦しいながらも学んでいくこと、考えていくこと、体を動かしてみること、それが「思い込み」というバカの壁を越える方法だ。。と理解しました。 昨日の自分と今日の自分が違う、、といったら何か気が楽になるなあ。 このところ引越しの後片付けをちまちまやっていて、昔の自分の書いた文章やら、かかわったことなどの記録が出てくる。それこそ10年前の学生時代のものも! それを見ていると、既に昔の自分は別の人物のように思えてきます。何せ、「ああ、こんなこともしていたんだった」と思うようなことがいっぱい。すっかり忘れてるんだもの。 昔の自分だって、今の自分がこうであることを想像できなかっただろうし。 「こうじゃなくちゃ」と決め付けない「どうせできない」「どうせ関係ない」で片付けないことが、必要なのかも。 煮詰まったら養老先生の言葉を思い出そう! と、付録でない本体の方も面白いです。脳に支配された世界はどうなるかのマンガや、養老先生の生い立ち、一日。などなど。 先生の文章の中で、最後尾を走り続ける男の強味、っていうのも良かった。 最先端をはしっているとイライラする。最後尾を走る覚悟が決まれば競争をきにしなくてもいい、「学問はしょせん自分の才能。それなら他人と並んで走ろうが、一人で走ろうが、さして変わりはない」 隣りがならぶとわざと自分がペースを落とすことで、競争へのエネルギーをかけずにすむ。他人と比べられたり、人からの保証がないと走れない日本人。。。 これが養老式、生き方なんだろうなあ。
2005.05.06
-
C型肝炎・血液製剤関連本
本は読んでいるのに、感想を書く余裕がなく、気がつけば3ヶ月ぶり。 今回は、国が、C型肝炎感染の原因の一つであるフィブリノゲン製剤の納入先を公表したことにちなんだ本を3冊。 ■「白い血液」池田房雄著 潮出版社 血液行政について。薬害エイズや肝炎を引き起こした血液製剤が、実は売血でつくられているという事実。 輸血の血液だけでなく、血液からつくる薬も善意の献血が原料だと勝手に信じ込んでいたから、大きなショックを受けた。 いわばタダ同然の血液を、高い薬にしたてて、設けた製薬会社の罪。100%国内の献血による血液事業の体制をつくらなかった国の罪。 ■「沈黙の殺人者 C型肝炎」 伊藤精介著 小学館 肝炎感染の原因として、注射器をかえない集団予防接種や血液製剤などを取り上げて、医原病としての性格を 見事に浮き彫りに。誰もがその被害者になりうる国民病としての肝炎。肝炎ウイルスは「発ガンウイルス」であり、それらは日本の公衆衛生行政の貧困からおこったことを検証。 ■「検証 C型肝炎」 フジテレビC型肝炎取材班 小学館 上記の伊藤氏をブレーンとして、C型肝炎キャンペーンを繰り広げているフジテレビ。フィブリノゲンによる薬害肝炎をクローズアップさせ、調査報道によって、製剤にウイルスが混入していることを実証した功績は大きい。 取材によって次々明らかになる事実、マスコミ同士の駆け引きなどの番組の舞台裏など、臨場感あふれる。
2004.12.15
-
市民が力をつけるために
HOW TO ものが大好きで、文章の書き方読本をみるとついつい買ってしまう私。 最近手にした2冊の新書はいずれも、NPO(民間非営利活動団体)で活躍されている人が書いたものでした。 NPOっていうのはミッション=自分たちの活動の使命=があって、動いている人たちなので、こうした活動から生まれてきたいろんなノウハウというものは、これまでの慣習を打ち破る可能性が秘められている、ようなきがします。 例えば、地域をよくするために、行政というものは動いているはず。だけど、いわゆるお役所的なものの決め方や、前例主義などは、どうやっても地域のひとたちの声を反映しているとは思えない。私たちの遠いところで物事が決まっていて、その内容もひとごとのように感じることが多いと思うのです。 一方、住民や市民の側。ある人はなんでもお役所がいいようにやってくれると思い、ある人は議員さんに頼めばなんとかねじこんでくれると思い、ある人はなんでもかんでも自分の意見だけぶつけて批判ばっかりで、ある人はまったくの無関心。。。 本当の意味での住民参加とか、市民主体の政治なんてものは、日本人にはなれないことのような気がします。 が、そこへでてきたこうしたNPOは、行政とパートナーシップをとりつつ、行政が汲み取れないような制度のハザマにあるニーズのために動いて、地域をよくしようとする。(NPOも玉石混交ですが) そうした力のある市民が少しずつ生まれているようなのです。 新書の一つ、「市民の日本語(NPOの可能性とコミュニケーション)」ひつじ市民新書。 著者はせんだい・みやぎNPOセンターの代表理事、加藤哲夫さん。 市民活動の経験から、行政と市民が話す場合の「言葉」の違いや、多数決で決まってしまったり声の大きな人の意見だけが通るのではない議論の進め方など、「参加型の議論の方法」「場のつくり方」といったコミュニケーションのノウハウを教えてくれます。 ただでさえコミュニケーションが苦手な人が増えているという。回りの目をひどく気にする人と「自己チュー」と。両脚端ななかで、安心して話せる(糾弾されない)ことを保障された場で、自分の思うことを言う訓練をする。 声をあげるのが苦手な人の声を、 ワークショップ形式でくみ上げる。 人は一人一人感じ方が違うこと、私にしか感じられないことがあること。そのことをみんなが知っていく必要がある。 あなたと私は一緒という部分を確認して終わり、ではなく。 異なる意見をきくことで、自分が排除してきたものが見えるようになる。 他人事を我ごととして感じられるようになる。そんなコミュニケーションのあり方を、著者は提唱しています。市民活動の場で、企業で、行政において、こうした議論をやっていく必要があるのでは、とも。 さらにもう一冊。「自分で調べる技術(市民のための調査入門)」岩波アクティブ新書。 大学助教授であるとともにNPOの運営スタッフでもある宮内泰介さんが著者。 「自分たちのことは自分たちで決める」というあたりまえのことを実現するための「調査」を、自分たちでやってみようと呼びかけています。 行政やマスコミの発表をまるのみして信じるのでなく、本当はどうなのかを自分で調べてみる。そのことが市民に力をつけることにもなる。 そう、物事を調べて問題点を見つけるということは、学者やマスコミだけの特権ではない。フツーの人でも、その気になればできる、いろいろな資料の調べ方や聞き取りのテクニックと注意点、まとめ方などをその方法を紹介してくれています。 私も知らなくって参考になったのは、国会図書館が雑誌や論文の複写サービスをしていて、遠隔地に住む人には郵送してくれるということ。早速、会員になるべく申し込みをしました。 インターネットで調べるときの留意点も。ふと、最近の大学生が、ネットでパパっと調べて、そのサイトの信頼性を吟味せずにレポートをかいてしまうと、大学の先生が嘆いていたのを思い出しました。 コミュニケーション能力と、メディアリテラシー能力と。これからの時代の賢さというのは、これらが求められてくるんじゃないかなあ。。
2004.09.21
-
月光の夏
毛利恒之・著 講談社文庫 この夏、知覧へいった。特攻隊の町だということは知っていました。特攻隊というのが、切羽詰った日本が、アメリカの進軍を食い止めるために、人間が乗ったまま飛行機でつっこんだことも。 今でいえば自爆テロのようなもの。 なんてバカなことをしたんだろうと、日本は人の命をどう考えていたんだろうかと。 記念館で売っていた書籍のなかから、一つ、買ったのが本書。 私は見ていないけれど、映画化されて、多くの人が感銘をうけたそうです。 この本は、プライバシー保護のために多少の創作が入っているかれど、事実をもとにしたドキュメンタリー。 佐賀のある学校のピアノが捨てられるのをとめようとして、女性教員が語った特攻隊員の思い出が新聞やラジオに出て話題になったことが発端。 戦争のために芸術の道を捨てた特攻隊員が、せめて最後にピアノを弾きたいと、この学校を訪ね歩いた。 マスコミが、その隊員はだれか、突き止めようとする過程で、思わぬ歴史の闇にぶちあたる。 当の本人と思われる人が生き残っていて、しかも自分はそんな話は知らないと、語ることを拒否する。。 感動の秘話は、実は本書の導入に過ぎず、著者がとりあげようとしたのは、生き残った特攻隊員の苦悩.、戦争の非情さでした。 特攻隊のなかには機体の不備やエンジン不調など、何らかの理由で、引き返さざるを得なかった人たちが少なからずいたこと。それでも、死ぬことを前提に故郷を出てきた彼らは、すでに「死んだ」ことになっている。本人は改めて出直して、立派に任務を果たしたいと思っていても、軍は「名誉を守る」との口実で彼らの存在を消そうとする。生還兵は福岡の振武寮という寄宿舎に”隔離”され、外部との交流を禁止される。 ピアノを弾きにきた特効隊員は、この語りたくない戦争体験を、ついには告白することになるのですが。。。 戦後、特攻隊員は犬死にしたのだという人が増えたことを、くやしく思っていると述べているのを読んだときに、あっと思いました。 特攻という方法は無謀で無駄なことだったかもしれないが、そのために犠牲になった人たちの命は決して無駄ではない。そのことを忘れてはいけない。 記念館にはたくさんの特攻隊員の写真、遺書や日記。実際に沖縄海域の米戦艦に体当たりしていく飛行機の映像。過去のものとは思えない、戦争の「証拠」に、かなりなショックを受けました。 カタカナで二人の小さな子どもにあてた手紙には言葉もなく。自分は特攻隊のこと、戦争のことを本当には知っていないことに気が付かされました。 テレビのインタビューをみてると、戦争のことを常識としてもっていない若者がいることに驚き。 特攻隊員たちの死を無駄にしないということは、私たちが忘れないということ。 戦争を教訓にすること。 ちょっと間違えたら、あなたの、私の問題だということを、私たちは知るべきだし、戦争を体験した世代にも、若い世代に伝えて欲しい。 その意味でも、本書と、それをもとにした映画は、価値のあるものだと思います。
2004.08.31
-
ニッポンの子育て
井上きみどり・著 集英社文庫 漫画「子どもなんて大キライ!」の著者、きみどりさんが、他のウチでの子育てを聞いて回った、興味津々の内容。 それぞれの家にそれぞれのやり方がある。ほんと、千差万別だな~と驚くばかり。 また取り上げてる視点も面白くて、子役タレント、お受験、十代など、「いまどき」の家庭にお邪魔したかと思えば、名古屋、北海道、沖縄といった地域の特性を見てみたり(実は北海道も沖縄も、冬でも室内があたたかいので薄着だとか、外に出れないので遊び場が大型スーパーだという共通点がある!)、受刑者の子育て、障害児を母親一人で育ててる例など、重いテーマにも足を踏み込んで考えさせられたり。 下町っ子風でキャリアウーマンでもある受験母や、自然体の障害児の母、ギャルじゃない十代の母・・・ 「きっとこんな母親だろーなー」という憶測が裏切られるのが面白い。結構みんなフツーだったりするのです。(何がフツーかというのがまた難しいのだけれど。。) 共通していえるのが、子どもをとにかく大事にしていること。 ただ、それが行き過ぎて、実は子どものためになってないのじゃないか、親の自己満足に子どもを引き込んでるだけじゃないのかという懸念を持って、コメントしてる。漫画を織り込んで、編集者との掛け合いという形でレポートしていて、ノリは軽いんだけど、実は真面目なきみどりさんの素顔が見える。 だいたい、子どもは嫌いって言っちゃいながら、実にまっとうな子育てをしてる著者。その真面目さを照れ隠しするように、漫画をかいてるんだなあ。。 うちの子育てを見たら、きみどりさんはどう表現して、どうコメントするのだろう。他人からはどう映るのかなあ。「もっと育児家事に手間隙かけるべき!」とか言われそう・・ 一番の「へえ~!」は、同じ日本とは思えない?名古屋の子育て(+結婚などの行事)。 親戚づきあい、近所づきあいの意味もあって、お披露目やらなにやら、いちいち使うお金の膨大なこと! 面倒なこと! 驚き、おののきました。結婚相手がこの地域の人でなくて良かったよ。。
2004.08.11
-
中年クライシス
河合隼雄・著 朝日文庫 これは私の思い込みかもしれないのですが。どうも中年という年に差し掛かって、「転向」とまでは言わなくても、「あんな人じゃなかったのに」とその変貌ぶりにがっかりしてしまう人が多いような気がします。特に男性。 年齢的に上を目指す野心が出てくるころでもあると思うし、男性にも更年期のようなものが訪れる、とも聞いたことがあります。 とにかく中年というのは、思春期に負けず劣らず、危うい時期であるらしい。 心理学の専門家としていろいろな相談を受けてきた著者も、そのことを実感。実際の相談例を持ち出す代わりに、文学作品に出てくる中年の心の問題を取り上げて、解釈を行っています。 中年といってもかなり幅があって、低い方では30代も出てくる。とすれば、これは私の問題でもあるなと思いながら心構えのヒントをもらうつもりで読みました。 中で強調されているのが、喜怒哀楽の感情を出すことの大切さ。現代人はこの年になると、変に「分別」ができてしまって、野性を失ってしまっている。適応がよすぎて、そのことがかえって問題になっている例が多いとのこと。著者はいくつかの小説を通じて、夫婦間や子どもとの関係で生じた問題を解決するのにワイルドな部分を生かしていくことが必要なのだといいます。 また、中年の時期に、自分の根源的な問題につきあたる。来るべき「死」に向かって、そのことを考えながら、自分がどう生きるかを見直すこと、 自分は何のために生まれたのかという「片付かない問題」(夏目漱石「道草」)を片付かないものとして認めて、それを生きていくことが科せられる。 ここを苦しみながら、迷いながらも踏み越えた人は、充実した人生の後半を過ごせるのでしょう。 その過程を回避したり、軽んじたりすると、そのしっぺ返しは自分にくるのかもしれない、とも思いました。 そういう時期なんだ!そう思うと、精神的な不安やうつ症状も怖くない気がします。 ただ家族にわかってもらうのは難しいかもしれないなあ。。 自分が思う「あんな人じゃなかった」ような人にならないためにも、目先のことでなく、自分の精神的なものや人生の立ち位置を大事にしたいものです。
2004.08.10
-
ケータイを持ったサル
正高信男・著 中公新書 サルの専門家を自称する著者は、「現代日本人は年を追ってサル化しつつある」といっています。 サル化とは? もともとサルの一種である人間は、努力して「人間らしく」なっていく。ところが、日本人はその努力をしなくなったというのです。 サルは子どもを大事にする、サルは社会的な動物、だと、思い込んでいましたが、実は実は、サルってとっても外に出るのが苦手で、生まれた集団=家族のなかで一生を終えるのだといいます。著者はサルと人間の違いを、うちの外へ足を踏み出して、個人として自己実現をとげて人生を送れるかどうかだといっています。 そこで現代の日本。公共の空間をまるで自分の家のようにして、携帯でしゃべったり、化粧したりする女子高生と、ギャクに外に出るのを拒んで自室にひきこもる若者。さらに、就職はしているけれど、親に頼って生きているパラサイトシングル。それぞれ、違う現象のようにみえていたのですが、これらはすべて「なじみの深い同士のなまぬるい心地よさ」を好んで外のあつれきを嫌っている点では同じ。外の空間を無視するか、外を恐れて内にこもっているかの違いだと、いうのです。なるほど。 なぜこんな子どもたちが出てきたか。著者の結論からすれば、子ども中心の家庭のせい。子どもを、常に新鮮な刺激を与えてくれる「耐久消費財」として、妻が主導権をにぎっている現代の家庭が背景にあります。 つい、100年前までは、子育ては祖父母の役割で、親世代は働き手だった。農業しかり、賃金労働者しかり。戦後の社会でようやく、女性が働かなくてもいいサラリーマン家庭の主婦がうまれる。 異論はあるだろうけれど、著者は母親がずっと家にいてやることが無条件でいいこととされてきた、ということに、著者は疑問をとなえています。 いろいろな実験結果を通じて、人間は40代もすぎると社会的かしこさが衰えることがわかって。40代以降は、人間としては高齢者であること。人生50年というのは今も昔もかわらないこと。ところが、昔なら祖父母のとなる年齢だった50歳以降になっても、現代の親たちは孫ではなく、難しい年頃の子どもと接しなくてはならない。かしこさがおとろえる時期に、そういう子どもと対することが、いろんな難しい問題をうみだしてるのだといいます。 例えば子どもの心がわからないために、子どもをモノでつったり、あなたのためといってしばりつける。母の庇護の元で「いい子」に育った子どもは、心地よい母と子のカプセルのなかから出たがらない。「家のなか主義」にしてしまったのは、現代の社会の当然の帰結点だと。 40代すぎて、社会との接点を失っている女性は、例えば勤めにでている女性と比べて、さらに40代以降の衰えが激しいと分析しているのですが、働いていなくても、何かの活動に参加したりとか、外とのつながりがあればこれらの点はカバーできるのかもしれません。 子どもの自立を妨げる要因は親にもあるのだということ。これは、しっかり踏まえて、しかること、大人との区別をつけることも必要なんだなあ、と読みながら思ってしまいました。 さらに少子化の原因は、「誰かに関する責任を全面的に引き受けることへの心の重荷」という心理的な条件であり、経済的にどうとか、政府が対策をとっても、少子化をくいとめることはできないのではないかといいます。精神的に成長する30歳すぎになって、ようやく子どもをもつだけの心構えができたときを「お産の適齢期」だということを定着させてはどうか。と、提言しています。 なんだかもやもやしていた今の社会への疑問が、頭のなかで整理整頓されたような・・・
2004.07.12
-
こんな夜更けにバナナかよ
渡辺一史・著 北海道新聞社 副題は「筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち」 その昔。といっても10年ほど前。福祉なんかに無縁だったころ、知人が車椅子の障害者の介助をしていると聞いて驚いたことがあります。仕事もしながらなぜ、ボランティアなんてできるんだろう。自分のことしか考えてこなかった私は、不思議でしょうがなかった。と同時に、その人がうらやましく、自分なんて役にたたない人間だなあと自覚しました。 なぜ、ボランティアをするのか。ボランティアの気持ちを探ろうとして、難病の鹿野さんをめぐる人間関係に足を踏み入れた筆者が、結局は自分も巻き込まれ。介助する側、される側の、微妙な人間関係や感情のバランスを知り、障害をもつひとがフツーに生きていくということのすさまじさを描き出しています。 美談やきれいごとではすまされない世界。障害者は決して善人でない。みんなコノヤローと内心思いながら、そういう自分の気持ちと折り合いながら介助に入る。難しいのは、完全に言われるままになってもいけないところ。ある程度適当にあしらいながら、時には意見をしながら、大事なところでは相手を許容する。。。なんと、究極の人間関係が、鹿野さんの周りにはある。人と人とのかかわりが希薄な現代にあって、ボランティア募集のチラシにひっかかる人は、生のてごたえを求めている人のようです。 鹿野さんは、ワガママでなければ生きていけない。先生の立場でボランティアに介助を指導し、夜中でも容赦なく起こしていろいろな欲求を伝える。感謝されたくてボランティアをする人には耐えられないだろう。 普通の人は、迷惑をかけないように、と、生きている。彼だって、難病を患わなければそうやって生きていただろう。でも何もかも人に頼らなければ、人に遠慮していては、生きられないのだ。その代わり、ボランティアがやめていくことや、眠ったら死んでしまうのではないかという怖さを常に背負いながら生きている。24時間人の目にさらされるというストレスを甘んじてうけなくてはならない。 そういったつらさを引き受けたうえで、在宅生活を選んだ勇気。自分らしく生きるなんて、人々がファッションのように言っていることが、いかに難しいことなのか。 筆者は、鹿野さんが病院を出て暮らすことになる経緯を描く中で、北海道を中心とする障害者運動の歴史についても丁寧な説明をしています。人間が生きていくことや、人と人とがかかわる意味を探ったすぐれたノンフィクションであるとともに、障害者福祉の現状、難病患者へのサービスの課題、ノーマライゼーションとは何か、といった、いろんな知識を得ることが出来る一冊。 私もすすめられて借りて読みましたが、買っておいて折に触れて読みたいと思いました。 この本の書きぶりとして、ボランティアと鹿野さんの言葉をつづった回覧ノートの生の声と、当時を知る人たちへの丹念な取材と、自らがボランティアで入ったリアルタイムでの経験とが、うまく融合されています。しかし、鹿野さんをめぐる人たちのなんとユニークなこと。年齢も職業もさまざまだけど、彼ら一人一人の生きてきた人生が合わさって、ものすごい厚みのある内容になっています。 筆者が本を書き終えようとしているところに、鹿野さん危篤の報せ。なんと、筆者は、その死の前後に立ち会うことになります。ボランティアに責任を問わないと約束して、在宅生活に入った彼が、死ぬ間際に家族も、親しいボランティアも遠ざけて。医師と看護士と、雇ったプロの付添い人に見守られて死んだ。この事実を何も思わずに読んだあとで、筆者の指摘に「あっ」と息を呑みました。つまり。下手に在宅で、ボランティアたちに囲まれて死んだ場合、必ず彼ら、彼女らは、そのときの処置をめぐって後悔やら責任を感じてしまうだろうということを、鹿野さんは予想し、万全の医療体制の中で、あえて、「今が死に時だ」として死んだのだろうというのだ。もしそうだったら、、あまりに見事すぎる生き方ではないだろうか。 ワガママを言われ放題であっても、それでもやめずに介助を続けてきた人たちは、やはり、鹿野さんとのかかわりを通じて、いろんなことを得たのだろうと思います。生きるということはこんなに、大変で、激しくて、つらくて、すごいことなんだと。改めて思います。
2004.06.29
-
整体 楽になる技術
片山洋次郎・著 ちくま新書 この本を手にしたのは、原因不明の肩こり(というか、肩甲骨のあたりの疲労)に悩んでいたときでした。あまりに気分が悪いのでつぼ押しマッサージにかけこんだら、その後余計に悪くなって。。。 いつもお世話になっている鍼灸院にいく羽目に。 知らぬ間に身体のどこかが緊張してるんですねえ。 この本のあちこちに、身体をゆるめるためのヒントがあります。 私がまっさきに実践したのがあくび。 頭や目が疲れていると首が緊張し眠りを邪魔するという。意識的にあくびをすると頭の痛み、目の疲れがとれるとか。 唇は閉じる方向のまま、アゴを開こうとするとあくびができるって。なんどもしていると涙がでてきて緊張をゆるめてくれる、ということで、なんどもなんどもやりました。 ストレスがたまるというときには胸の中央部分が緊張してるらしい。現代社会はこの部分の緊張度を高めるそうだ。 慢性疲労症候群といわれている人には、胸がねじれて固くなっている人が多いという。こういうときは呼吸を深くして下腹部に力を集中するといいそうです。 身体の距離感のとれない閉鎖的空間、、、家や学校など、、、で、問題が起こりやすいことを自覚して、最初から適切な距離を持つことは難しいと思っていた方がいいと著者はいいます。完璧よりも、いいかげんに。外部をとりこんでいこうと。 距離を保つためには、身体の内側から声を聞く=耳を傾ける姿勢がいい。首を傾けることで胸の緊張は緩まる。ということだそうです。 内臓と背骨とのかかわりも大きくて、どこかが固まっていると胃腸の動きや睡眠に影響してくる。脊椎や腰椎は、いつも揺らいでいるのがいいそうだ。「身体は呼吸するたびに膨らんだり縮んだりするウオーターバッグである」 背骨がウオーターバッグの中に浮かんでいるっていうイメージがつかめれば、固まらない体をゲットできるかも。 また現代の人の特徴として骨盤底部の緊張が慢性化しているそうです。(仰向けになって尾てい骨のあたりに違和感がある人は要注意だって!) 骨盤の上のほうが縮むことは快感であり、あるがままの自分を認める自信につながる。赤ちゃんの指しゃぶりやあくびは骨盤上部を縮めるらしい。しかし何でも禁止され、我慢をしいられると、ギャクに骨盤の底部が緊張するらしい。底部の緊張を受け入れる体は、他者の評価でしか自分を認められなくなる。抑圧を受け入れ頑張る体勢は、他に評価されることで支えられているが、他に依存しているために非常に不安定。 「骨盤底部のドーピング効果」と名づけられた骨盤底部の緊張の慢性化は、最近特に増えていて。頑張りすぎややりすぎ、言いすぎ、過敏、拒食や過食、感情の起伏の激しさ、、といった傾向が見られると。特に才能のある人がはまりやすい体勢だそうです。自立や前向きを強迫されている身体。その内側の感覚を取り戻そうと著者はいいます。 私の身体も何かの緊張で悲鳴をあげているのでしょうか。 ゆるゆると、まったりと。身体の声を聞いてあげなくっちゃ。
2004.06.14
-
いのちの器
高山文彦・著 角川文庫 副題は「臓器はだれのものか」 就職してから数年たったころでしょうか。天使がほほえむ黄色いカードがあちこちに置かれるようになって。 その裏には、脳死状態、あるいは心臓が停止したあとにどうしてほしいか、自分の意志表示をするようになってる。 あのころからずっと、移植で助かる人がいるんだから、もし自分のカラダが死んだ後でも役に立つなら使ってもらいたい、と、単純に思っていました。 久しぶりにカードを取り出してみると、「心臓停止後に」のほうに○がついてる。 黄色いカードに記入する前にも、腎移植と、眼球の移植のカードがそれぞれあって、まだ結婚する前の旧姓で提供しますと意志表示してる。それも、ちゃんと免許証入れに一緒に入ってて、感慨深かったり。 この本は、安楽死をさせて訴えられた医師、尊厳死を選んだ人とその家族、臓器移植のドナー(提供者)家族の思い、臓器移植を受けることを拒み続ける少女、そして、その少女と交流することになった長渕強の話がかかれたノンフィクション。 背景には、ずーーっと、臓器移植に対する著者の割り切れない思いが流れています。 医療の現場で、どうしても移植をしたい医師がいれば、患者の死をのぞむ方向で動いてしまうことがありうるということ。たとえ生前に意志表示していたとしても、その意志は自分が本当にだめになったときに、という前提。本当はもしかしたら、生き続けようとしてがんばっているときにも、そうした身体の意志を無視して移植が進められる恐れがあるということ、なのです。 本のなかには、提供してよかったという家族や、移植を受けて人のために生きていこうと頑張っている患者さんの手紙も出てきて、移植をすることが全く悪いとは言えない。でも、そうした幸せな移植であるためには、中に入るコーディネーターが、きちっと提供するドナーと家族の立場にたって、防波堤になる必要があると、著者は強調しています。 少しでも家族に迷いがあれば、すすめてはいけない。 家族の気持ちを無視して進めてしまった事例では、母親が看護婦で、移植に同意しなかったら奉仕の精神がないといわれるんじゃないかと思い、医師に押し切られる形になったようです。 安楽死をさせようとして、致命的な薬を投与しても、なお生き続ける患者。 ドナーとなるべく医師に早くから目をつけられ、処置をほどこされながらも生きようとしているのに回復不能と判定され、臓器をとりだされてしまった女性。そして、臓器移植しか生きる道はないといわれながら、人の死の上に自分が助かるのはいやだと拒み続け、なんども生と死をさまよいながらもそのたびに奇跡的に回復した少女。少女は、傍から見ると昏睡状態に陥っているときにも、はっきり意識をもっていたといっています。 人間って、強いんだなあ。生命ってすごいなあ。 臓器移植法という法律で条件が決められ、マニュアルどおりに進められることには著者と同様、反対です。 医者はまず、生きようとしている○○さんという患者個人を尊重するべきで、移植はその派生としてでてくるものでなければいけないと。
2004.05.29
-
子どもを選ばないことを選ぶ
大野明子著・メディカ出版 副題は「いのちの現場から出生前診断を問う」。 これを読んで、いまの管理されたお産への疑問、障害をかかえた子供をどうとらえるか、産み育てる権利・・といった、自分の中で結論が出せないでいた答えの、根拠を得たような気がしました。 著者は産科医。もとは地球化学を研究していたのに、自分のお産をきっかけに、医療を勉強しなおしたという経緯を持つ人です。いまは東京で「自然なお産とおっぱい子育て」を世話する「お産の家」を開いているそうです。(こういうところで産みたかったなあ) 著者自身、出生前診断をどう考えるかで悩んでいたようです。子供を選ぶことに疑問をもちながらも、診断できる可能性を伝えなかったことで先天的障害を持つ子がうまれたときに訴訟に巻き込まれるのをおそれていて「あいまいな姿勢」をとっていたと。(この辺、率直に書いているところがすごい・・・) そうした気持ちをはっきりさせたのが、ほかならぬダウン症をもって生まれた子供たちと、その親たちだったようです。どんな障害をもっていても、この子はこの子だと、受け入れた親に愛されて、ゆっくり育っていく子供たち。障害を個性のひとつとしてみたときに、子供たちが持つ穏やかさ、素直さといった「すぐれた資質」や周囲に与える影響力に、「社会にとって必要だから生まれてくる」ことを確信したといいます。 どんな子供も受け入れる。。というのは難しいことなんだろうと。でも、産む決心をしたのならどんな子でも受け入れる親でなくてはならないと、著者はきっぱりといいます。 うん、それが産むという責任なんだろう。(望まない妊娠は別として) 子供は生まれたとたん、親の占有物ではなくなるわけで、自分の都合で、いる、いらないなどと判断してはならないのだと、私も思います。 本文のほかに、臨床遺伝医の長谷川知子氏のインタビューと、ダウン症の子を持つ親たちの座談会が、さらに著者の考えに対する説得力を高めています。 長谷川先生は出生前診断を「胎児虐待」だといいきってる。将来この子が困るだろうからとか、育てられないからでなく、親がつらいから中絶するのだと。 だいたい、生まれると、自分や相手の親たちから攻められる、そういう子を産んだのは自分のせいにされることへの自己防衛をせざるをえない。それを長谷川先生は否定するのでなく、そういうものだということを明らかにした上で、自己防衛しなくてすむようにケアされることが大事だといいます。 まず、先天的な異常があると、早産や流産というかたちで生まれてこない。自然淘汰される。そこを、生まれてきたということはお母さんがよかったからだよと、この子に生きる力があって、必要だから生まれてくるのだと。 医師が長谷川先生のように説明してくれたら、どんなに前向きに育てられるだろう。 障害があるからといって、医学的に問題がなければ、すぐに母子を分離してしまわないことも大切なようです。生まれてすぐにおっぱいをあげることで、きずなが強くなる。普通の病院ではなかなかかなわないことのようですが。 ダウン症の子供を育てているお母さんたちも、受け入れるまでのハードルは自分自身だったと答えています。それを乗り越えて、いま、自分のところに生まれてきてくれてよかった!と口をそろえてる。 著者自身、いろんな奇跡を経験したそうです。診断を拒むかのように一時的に破水をおこしながら、もちこたえて生まれた赤ちゃん。絶対絶命ながらあきらめずに生まれてきた赤ちゃん。ぎりぎりまでは、子供の生まれる力を信じて、それに逆らわないお産を援助する。助産というのは、そういうものだったのでないでしょうか。病院の都合で、陣痛促進剤を打ったりするのは論外です。 親が選ぶのでなく、子供自身が生きることを選んで、うまれてきたのだと。そういう姿勢で出産、育児というものをとらえることが、いろんな問題を見る基本になることを教えてもらった気がします。
2004.05.16
-
お金じゃ買えない。
藤原和博著・ちくま文庫 リクルートに入社して、客員社員の第一号となった「スーパーサラリーマン」の藤原さん。 しかし、これはいかにすれば、人生で成功するか?といった本ではありません。 「日々のセコセコした時間の流れから逃れて、豊かな時間をゲットするための知恵」「お金では買えない「見えない資産」を増やすヒント」がかかれた本。 というよりも。 順調にキャリアを積んできたかのように見える著者が、自分の苦しかった体験や、生い立ちをつづっている「自分史」の一面があり。 実は、スーパーサラリーマンで、夜も昼もなくやってきた矢先にかかったメニエル病。どうやら、著者が、ただの会社人間に終わらなかった理由がこのへんにあったようです。 自分をふりかえるなかで、「30歳に手が届く時点まで、日本の教育と戦後日本の典型的な中産階級の家庭が作り出した優秀なマシーンだった」「私は20世紀後半の日本が作り出したサイボーグだ」と分析。優秀だから、枠にはまって、どんな仕事でも全力を尽くして、そして成果をあげてしまう。それが本当にやりたい仕事かどうかは置いといて。 実は、自分の中には、クリエイティブに、自分のやりたいことを突き詰めたい自分がいる、ということにメニエルという病気が教えてくれたといいます。心の股先状態が、カラダを通して警告を発していたと。 「ちゃんとしなさい」「いい子にしなさい」という言葉の呪縛は、その子のもっている波長と振動と周波数を、世の中にとって使いやすいように整形してしまう。。。と、自らの体験から語っています。 そんな著者は、飲み会の2次会に行くのをやめ、ゴルフをやめ、テレビも見ないようにして、、、いろんなものをやめていったといいます。トランプのゲームのように。手持ちのカードは枚数が決まっている。何かを捨てなければ、何かを拾えない。「人間の潔さは、どうやって捨てるかに現れる」 この言葉、耳が痛い痛い。 閉塞感を打ち破るために、付き合いや慣性、義理でやってたことから逃げる、避ける、断る。好きなこと以外の回数を減らす。人の目をきにすることを止める。 しなくてはならないことが、いっぱいあるように思えて、でも、それらをこなしきれていない、あせりを感じている今日このごろ。 本当に、それをしなくてはいけないのか。考えてみようかなという気になりました。 いったい、何を自分はあせってるんだろう。 いろんなことをやめてみること以外にも、自分の時間を持つための3つの知恵をあげています。 1.目の前で今会っている人との時間は二度と訪れないと考えること。 2.人生のカーブを山なりに考えない。死ぬまで上昇していくようにイメージする。 3.10年後と今の折り合いをつける。例えば、10年後の夢を、今の仕事に1割まぎれこませる。 人生一度きり。
2004.05.08
-
ルポ「まる子世代」
阿古真理著 集英社新書 「まる子世代」は1964~69年生まれ。まさに、私もまる子世代。そして、筆者と同い年。 東京オリンピックと大阪万国博の間に産まれた、Hanako世代と団塊ジュニア世代に挟まれたこの世代を通して、世の中を見ようというのが本の趣旨。 思い返せば(もう、私もそんな年!)、均等法施行で女性が総合職として採用され始め、私たちが社会に出るころは、まだバブルがはじける以前でいわば売り手市場。女性を表面的には男性と同じように採用していた時期でした。 いい時代だったといえば、そうだったのかもしれない。 この本を読むと、働き続けている人、子育てに専念している人、転職した人、と、立場はさまざまであっても、みな「フツウ」に、まじめに、生きてきている、というのが印象です。 会社の補助的な仕事をしながらも、年数を重ねるなかで、男社会のおかしさ、会社の危なさをを敏感に感じとっているのだけれど、その意見をまともに採り上げようとする会社はいない。 会社にとって、「おんなのこ」の採用は、対外的なパフォーマンスにすぎず、その能力を生かそうとしてこなかったツケが、いろんな面にあらわれてきていると筆者は指摘しています。 確かに男性は女性よりも、仕事に対して責任感をもっているかもしれない。でも、そもそも男社会で、女性には十分なトレーニングがされないままでは、女性は圧倒的に不利。そして、男性のなかにも、会社に寄生して生きている人が何人もいる。女性は総じてまじめだから、手の抜き方をしらずに、「男性並み」の働き方をして、体をこわしてしまっている。 鉱山のカナリヤではないが、女性は少数派だからこそ、その危険性を察知するための、重要な存在だったはずなのだ。それを、いざとなると切り捨てられる使いやすい労働力としてしか見ていない。バブルがはじけた今や、採用さえまともにしない。。。 社会に出て当たり前に仕事をするこの世代が、一方で、家事や育児を重要視して、あっさり仕事をやめてしまう点にも筆者は注目。女性たちの考え方の背景に、その母親世代がいることを、示しています。母親世代はサラリーマンと結婚し、快適な家庭をつくるということを幸せだと認識し、自分の役割である家事や育児を完璧にこなそうとしてきた。フツウに、人並みに、育てられてきたまる子世代は、母親の価値観をすなおに受け取り、その要求にこたえようとしてきた。 (このへん、最近の「負け犬」ブームで、週刊誌のAERAが、やはり、母親の影響力の大きさを特集していな。。) 日本の高度経済成長を支えるために、政策的につくられた「プロジェクトX世代」の父親と、専業主婦の母親、そしてこどもという家庭の形。筆者は「仕事や家事をがんばりすぎる女性がまる子世代に目立つのは、結婚していながら子育ての責任を妻一人に背負わせた父親にも一因があるのでは」といっています。 読んでいて、普段ばくぜんと考えていることを、筆者が文章にしてくれた、そんな印象を受けました。 モーレツ会社員でも、完璧な専業主婦でもないけれど、たまには、「意外とがんばってるじゃん。わたしたち!」と、いっちゃっていいかな?
2004.05.02
-
箸墓幻想
内田康夫著・角川書店 いやあ参ったなあ。 内田さんってひょっとして、ものすごい理解力と第六感をもってるんじゃなのだろうか。 例によって浅見探偵シリーズなのだけれど。 2000年の新聞連載が始まる前に、ここに出てくるホケノ山古墳の発掘があって、物語のカギにもなる鏡が実際に発掘されて、作者自身が驚いたとのこと。 ついでに、この話は、遺物の埋め戻しというのがポイントになるのだけれど、「神の手」といわれるアマチュア考古学者の話を引き合いに出したその後に、石器捏造事件が起こったという。。。 偶然というよりも、作者が現場に足を運んで、関係者からもみっちり取材をした結果、自然と話の中にそういう要素が織り込まれたということなのでしょう。 実際、桜井市のホケノ山を見に行った人(うちのパパさん)が、内田さんが取材に来ていたという話を聞いたそうなので。 箸墓は天皇陵だから掘れないこと、そこからどんな遺物が出てくるかによって、邪馬台国論争の行方が左右されること。 そういうことをきちんと踏まえたうえで、物語が成り立っているので、考古学ファンにとっても読み応えがあるものになってる。 加えて。橿原から飛鳥、桜井にかけての地域にゆかりのある万葉集や伝説がちりばめられ、その上に、戦争という時代に青春を迎えた人たちの人間模様が重なって、物語が奥行きのあるものになってる。誰が悪いのでなく、時代に翻弄された人々が罪を犯さざるをえなかったと。。 そういえば、世代を超えて受け継がれる愛憎の物語は、前に読んだ「はちまん」でも、犯罪の動機になってました。 折口信夫の「死者の書」が、効果的に使われているのが憎い。閉じ込められた死者の思いというものを、古墳を見学するどれだけの人が感じられるだろう。 その思いが、犯人として最後に箸墓に眠る母娘の思いにもつながって、なんとも物悲しくなる。 いやあ、一気に読まされてしまいました。
2004.04.16
-
家庭科が狙われている ~検定不合格の裏に~
鶴田敦子著・朝日選書 私が中・高生のときは、「技術・家庭」という科目で、男子と女子はベツベツに勉強。家庭科で習ったことで覚えているのは包丁の切り方とか、服の縫い方とか。技術的なことばかり。はっきりいって面白くありませんでした。 男女共修になったのは90年代に入ってからとの事。筆者が例としてあげる、おやつを通して食品の安全性を学ぶ授業や、家族や子どもの問題について学ぶ実践などを見ていると、こんな授業なら今でも受けたい! というか、私たちは、学校で、自分たちが生きていくうえで力になるような教育がされてこなかったように思います。公民や政治・経済で環境破壊や食の安全の問題について、知識としては学ぶかもしれない。でも、それを自分の問題に引き寄せて、考える場というものがない。まさに、家庭科こそが、その可能性を秘めた魅力的な教科ではないかと。 筆者は男女がともに家庭科を学ぶ意義を、生活者として生活文化や環境のありかたを批判的にとらえ、安全で健康的な生活を送るために、他人と共同してとりくむための知識や能力を身につけることーと述べています。 そうした思いで筆者がかかわってつくった教科書が、検定不合格にあう。その理由が学習指導要領の項目や配列どおりでないとか、社会的なことに踏み込んでいたりとか、工夫されたものに対してスタンダードでないとダメ!ということらしい。これでは国の思想誘導ではないか、と思ってしまいます。特に、文部科学省が掲げる「家族像」に則してないとして、指摘を受けた点を筆者は詳しく述べています。 国は家族の情緒性=心のやすらぎを与える場としての機能=を強調したい。でも、筆者らは、家族のあり方が多様化していることや性別役割にとらわれない個を大事にした家族関係を示したかった。 国はなぜ、家族のあり方にこだわるのか。 その答えが、第3章の「国は何を狙っているか」。子どもが育つ環境のなかで家族や親の役割を重視することは、86年の臨教審にはじまるといいます。いじめや不登校、非行などの原因を「家庭の機能の衰弱」とし、家庭科教育の見直しを提言。98年には、中教審答申で、家庭教育への提言をしていて、「家庭のあり方を見直そう」「思いやりのある子どもを育てよう」などの項目が挙げられています。著者はひとつひとつは重要なことだが、とした上で、家庭生活に対してああしろ、こうしろといい、努力目標を提示したり自覚を促すことは、国がするべきことではない、と言い切っています。 国の役割は、「人々に指示をすることでなく、子どもたちが確かな判断力をみにつけられる教育、家庭教育に携わることになったときにそれを発揮できる力を育む教育の機会の提供・保障」「家庭教育を困難にしている要因を取り除く施策を講じること」だと。 この辺を読んでいて、私の住む松山市の「子ども育成条例」が頭に浮かびました。条例の文言を読んでいて、なんでそんなことまで行政に指図されないといけないんだ?と腹をたてた覚えがありますが、国の向いている方向が、そのまま市の方向であるともいえるのかもしれない。 筆者は、家庭教育力が低下した理由は、学歴社会や、子どもの数の減少(成熟社会の特徴)、性別役割分担が根強く父親が育児に参加してないこと、などをあて、、「将来親になる中・高生に家族と親との責任を強調することで(教育力が)高まるものではない」といいます。 家庭科は道徳でない。家族の問題は「心のあり方」で解決されるものではないーと、筆者は注意を促します。 国が現在、福祉を縮小して民間サービスにゆだね、足りない部分はボランティアで補うことを奨励している、まさにその政策が、家庭科教育にも波及しているんじゃないか。 愛だの、心だのにまかせて、国は責任逃れをしようとしているのではと、かんぐってしまう。もちろん、ボランティアも重要、ではあるけれど、それは公的な福祉の増進と「車の両輪」でなければならないのだと、筆者はいいます。 精神論を振りかざすのでなく、子どもたちが生きていく力を自分たちで身につけられるような、そんな家庭科教育に期待したいものです。
2004.04.11
-
動機
横山秀夫著・文春文庫 やっと、読みました。「クライマーズ・ハイ」や「半落ち」が話題の横山氏の作品。 「このミステリーがすごい」で2003年版の2位になったという、短編集。 警察ネタ、新聞記者ネタ、裁判所ネタ、、 うーん。その業界の事情を知るには面白いかもしれません。 謎解きも、なるほど、工夫されていると思います。 しかし。 その、犯人の動機というのが、、めっちゃ男の世界!なのが、不満。 例えば、男の義理人情、会社への忠誠。 もしくは、不倫などの男女関係。 ありきたりというか。 この中では「逆転の夏」が、犯罪心理がよく描かれていて、スリリングかなあ。 ちょっとした心のスキが、事件を生んでしまう。 ごく普通の人が一瞬にして犯人になってしまう怖さ。 しかし、なんだか犯人の行動が安直すぎるような気もするのです。 「すごさ」がわかってないのかもしれない私。他の作品も読んでみないとね。
2004.04.03
-
Lingkaran 4号
ソニー・マガジンズ このところ、癒し系=スローライフ系=エコ系、の雑誌が次々創刊していて、○○奥さん、とか主婦○○といった、表紙に字書きまくり!の雑誌と違った奥ゆかしさで書店の棚に並んでいます(アルネとかクウネルとか)。 中でも、今回初めて買ったリンカラン(インドネシア語で輪という意味だそう)は、全編文句なし、お役立ち度とおしゃれ度がいい具合。 この雑誌の面白さは、よく知っているミュージシャンやタレントが、「心とカラダにやさしい生活」を体験しているところ。読者は、そのテーマで取り上げられた人の人生や物事について知るついでに、彼、彼女たちの思いや近況もわかる。相乗効果といいますか。 4号のメインテーマが「自分をつくる仕事」。有機農法の実践者をはじめ、盆栽美術家、サッカー女子公認審判員、女性の杜氏などなど。もしかしたら一般人は一生出会えないような職業の人たち。みんな、それぞれ、自分のペースで、職人芸をこなしていること。日々あくせく追われる様に働いている身にとっては、うらやましく思います。 読みながら、自分の心も癒されたのが辰巳芳子さんの「スープのある食卓」。スープを作る心得が辰巳さんの言葉で書かれているところがいい。野菜の味がそのまま出たスープの滋味というか、カラダにしみいるようなおいしさが、作り方を通して伝わってくる。。 スープ、飲みたい! 作りたい! モノを大事にすること、心をこめて何かを作ること、日々の生活でなおざりにしてしまっていることを、ここらで取り戻さなきゃという気にさせてもらえる雑誌です。
2004.03.29
-
複合汚染
有吉佐和子著 新潮文庫 昭和49年に新聞に連載されたものだというから、ざっと30年前の作品。 「複合汚染」という題名は知っていても、ばくぜんと難しそうな気がして、手に取ったことはありませんでした。読んでみたら、小説らしからぬ、ご本人も出演してのルポを見ているような、書き方。 最初は市川房枝氏の選挙運動の話に始まって、若き日の管直人氏も登場してきて、それはそれで面白いのですが、途中からは、有吉さん自身が精力的な取材で得られた事実をもとに、いかに私たちの自然が、食が、汚染されているかを暴いていく、そんな内容。その説明も、難しい言葉が並ぶのでなく、ご近所のご隠居さん相手の世間話を通して語られるので、ついついフンフンと聞き入ってしまうような。有吉さんの語り口のうまさでしょうか。 それにしても。農薬や化学肥料など、「効率化」が農業をダメにし、そのツケが食の危機として私たちに回ってきている。何より、一番被害を受けているのは生産者であること。さらに、保存料などの食品添加物で腐らない、見た目のきれいさを追い求めた食べ物が出回ったこと。これは、消費者である私たちの責任もある。 最近になって「食の安全」が言われ始めたのではないのでした。 30年も前から警鐘は鳴らされていて。気が付いた生産者は、より自然に近い形で本物の食べ物をつくり、気が付いた消費者は生協運動などを通して生産者を応援し、安全な食べ物を購入してきたのだけれど。 なぜ、いまだにこの問題は解決されていないのだろう。 「日本の農村で最も荒廃しているのは農地より精神だと言う人たちがいるのだが、私は精神主義というのはややもすると妙な方向へ走りがちだから取らない。自分は変な病気になりたくないと思い、親や子や愛する者を病気にしたくないという心さえあれば、それに化学肥料や農薬が何かという正しい知識さえあれば、充分ではないだろうか」 こうした有吉さんの言葉を、農政や食品行政をすすめる人たちに、政治家に、経済界のえらい人たちに、かみしめてほしい。 この本を読むきっかけになったのは熊本の公立菊池養生園の名誉園長、竹熊宜孝さんの講演。自ら体を壊してから食の大事さに気が付き、「医は農に学べ」と自治体の病院に農園をつくってしまった人。 「『苦海浄土』を読んだ人はどのくらいいますか。じゃあ『複合汚染』は?」 手をあげた人は数名。もちろん私も恥ずかしい思いで下を向いていました。 ( 竹熊さんは有吉さんとも親交があり、食の安全に関する大会のときに有吉さんが熊本にかけつけて話をしてくれて、大盛況だったと。それが「複合汚染」の発表後くらいだったようです。) 竹熊さんは、たべないのが養生なのだ、と。食べ過ぎで人々が病気になると医者はもうかる。経済を活性化させるにはそれが一番なのだ、と茶目っ気たっぷりに「説法」していました。 そして「いのちはどこにありますか?」と質問。その答えとしてサツマイモを皆の前に差し出して。 食べ物は私たちの命をつくる、だから大切にしなくてはならない。ということを示してくれました。
2004.03.26
-
ブラックジャックによろしく3&4
佐藤秀峰著 講談社 遅ればせながら読みました。3.4回は、小児科の新生児集中治療室の話。 不妊治療でようやく授かった双子は未熟児。ダンナの方は、子どもたちを認めないという。そして母親のほうが、やっと母性を感じ始めてきたときに、弟の方がダウン症であることがわかる。しかも腸重積で手術が必要。だんなは承諾書にサインをしない。そうしているうちに兄のほうが死んでしまう。母親は離婚の決心をして育てる決意をする。一方、主人公の研修医斉藤は、保育器に入った子どもたちと接する中で赤ちゃんたちをほおっておけず、承諾を得ないまま手術に踏み切ろうとする。 政府の少子化対策は、年金など社会保障の担い手が減って、国の財政がパンクしてしまうのを防ぐため。結局役に立つ=働ける人間しか必要ないのだ。そんな、身勝手な押し付けはほっといていいはずだ。子どもを持たなきゃならないなんてことはない。むしろ、この本にも出てくるように「リスクを背負う覚悟がないなら、子どもなんて作っちゃいけねえ」のだ。産みたくないのに生んだというのは論外で、子どもはきっとかわいいだろう、子どもが生まれると幸せになるだろう、なんて、実は自分自身のために産むことを。そろそろやめなくてはいけないのかもしれない。幻想を持つから子育てもつらくなるのだ。 生まれた時点でその子には人権があり、誰もそれを侵害してはならない。このマンガがすぐれているのは、親や医者の論理でなく、もののいえない子どもの視点が、そこここでシグナルをおくっているところだ。おなかの中にいて、外の世界を楽しみにしている双子の会話。保育器に放されていても、兄は弟を気遣い、弟が衰弱すると兄も一緒に悪くなってしまったり、大人たちがどう接するかを敏感に感じている。小さくても、尊重されるべき、一つの命。 ひどい父親だ、と最初は思うのだけれど、彼等自身が長い間子どもができないことで、世間の冷たい言葉を受けてきたことを知ると、誰も攻められないような気もする。なぜ、自分たちのところに障害を持った子が生まれてくるのか、理不尽だという思い。完全な子しか認めないという、この社会の、そして真っ先に等の親自身の考え方こそが実は差別を生んでいる、、、目をそむけがちな事実。 障害持ってたっていいじゃない、それも個性の一つだよ、なんてことは、他人にはいえないことだ。じゃあ、どうして五体満足で、優秀な子しか、認められないのだろう。それぞれが生まれてくる意味があって、生きてるだけでいいんだ、と、なぜ思えないのだろう。
2003.12.16
-
「世界」1月号&「たくさんのふしぎ」1月号
「世界」岩波書店 今回はHIV・エイズの記事特集に注目。先進国で日本だけが無防備に感染者が増えているということ、世界では8秒に1人がエイズが原因でなくなっていること。もうエイズは終わったんだという意識がどっかであるような今の社会、常識として知っておかなくてはならない事実がたくさん報告されています。 もはや、他人事と思っていてはいけないようです。 子どもにもちゃんと教えておかなくてはいけないんだろうなあ。 イラクの復興支援も大事だけれど、アフリカなどの薬の足りない国に、援助すれば、お金を最も有効に使う形で大勢の人の命を救えるのに。世界会議で「日本は何をしているんだ」と言われていること、政府は知っているのだろうか。 世界平和に向けて、独自に貢献する方法はいくらでもあるのに。 「たくさんのふしぎ」1月号「なぞのサル アイアイ」 島泰三・文 笹原富美代・絵 福音館書店 ♪アイアイ、アイアイ、おさるさんだよ~、のアイアイは、マダガスカル島にすむ、サルの仲間だってこと、みんな知ってるのかなあ。(私は知らなかった!) 子供向けだけど、大人でも「へえ!」って言いたくなるような本です。 文をかいた島さんは、絶滅したといわれていたアイアイの生態を知るために、南の島にいった人。無人島に寝泊りしながらようやく見つけて、夜行性であることや主食が何かなどをつきとめていきます。 サルというよりリスとかモモンガ系。 写真のように細かい描写で、とっても愛らしいアイアイをかいた笹原さんもすごい。 とにかく、わからないことは調べよう・あたりまえの裏には真実がある、、ってこと。
2003.12.12
-
べてるの家の「非」援助論
医学書院 浦河べてるの家 べてるの家は、北海道の浦河町にある精神障害者の人たちがつくった社会福祉法人。この人たちは、町に普通に住むだけでなく、作業所でコンブの袋詰めをしたり、介護保険事業をやったり、自分たちを写したビデオを売ったり。ちゃんと事業として「お金儲け」までしてるのです。 彼らを支援する医者とソーシャルワーカーの接し方がユニーク。彼らの経験を面白がって、どんどん話を聞くんです。決して否定せず、その人の状態を、まるごと受け止める。普通は社会復帰をさせる、とか、病気を治すために薬を出す、というのがこの手の医療・福祉関係の仕事なのだと思うのだけれど。 そういう対応を受けて、そのうち彼らは自分の病気をつけられた病名でなく、自分の個性のようにとらえ、自ら「ウリ」にしていく。どんな妄想を見たか、幻聴さんとどんな話を聞いたか。なんと! 彼らは全国の講演にもひっぱりだこで、臆することなく経験を語っているのです。 浦河でも、べてるの人は怖くて迷惑な人たち、という目で見られていたそう。事業を開始するにあたって、町のパソコンサークルに入ったのが(戸をたたいた最初の人。勇気がある!)よかったようです。同じ仲間として受け入れ、興味をもってくれて。地域でも障害者と話す会というのを開いて、なんと「誤解や偏見大歓迎!」といって町の人たちに声かけをしてる、、 誤解や偏見は誰にでもある。あって当然、だから話をしようよ。ということ。やってみると、意外に町の人たちは、わからずやではなかったようです。「地域の偏見が強くって、福祉が進まない」というのは、偏見が強いものだと先に決めちゃってるのかもしれない。べてるのこのアプローチの仕方は、すっごく参考になると思います。 確かに「わからない⇒怖い」、のであって、一方で彼らがどういう体験をしているのか、興味津々だったりする。私自身とても聞いてみたい。 べてるのやり方の面白いところは、「人生を降りる」ことのすすめ。だいたい、成人して精神を病む人は、ちいさいころから「いい子」で、親の期待を、自分の理想を裏切らないように、生きてきて、心と体があっぷあっぷになった人たちのようです。向上しなくたっていい、降りていく生き方もあるんだ。これを読んで「私も病気になりたい!」と思ったくらい。 障害者が地域を豊かにする主体者となっているという今まで気が着かなかったいろいろな可能性が見えてくる、そんな本。落ち込んでいる時に読むと、非常に共感できます。
2003.12.08
-
母 老いに負けなかった人生
高野悦子・著 文春文庫 岩波ホールの総支配人として、質の高い映画を紹介続けている著者。数年前になくされたお母様を自宅で介護した、その経験を書いています。「介護を変えたら、母が痴呆症から回復した!」という帯の言葉に、お年寄りにどう接するかというノウハウ的なものを期待して読んだのですが、介護体験の本にとどまるものではありませんでした。 母である「明治の女性」を、その晩年の尊厳を持った生き方を通して描いているといった感じなのです。 往々にして介護体験本は、あるおじいちゃん、おばあちゃんが、こうだったああだったという話で、そのおじいちゃんおばあちゃんは、他の誰にも当てはまりそうなのですが、この「母」の場合は、死ぬまで・・そして死んでからも娘に教え続ける一人の女性で、他にかえようのない圧倒的な存在感をもっています。 痴呆のお年寄りを描いた映画を見たことで、著者は介護の心構えを一新し、介護される弱い立場になった「母」を支配しようとせずに痴呆になる前と同じく一家の大黒柱として接するようになります。「説得より納得」。相手の意思を尊重し、説明をきちんとすれば、わかってもらえるという手ごたえをつかみ、お母様はぐんぐんいい状態になる。読んでいると奇跡的なのですが、逆にいえば、今行われている介護というものが、お年寄りの可能性を奪っているのかもしれません。 学ぶことの多い人生の先達としてのお年寄り。著者ももっといろいろ聞いておくのだったと後悔しておられますが、お年寄りの経験は「宝の山」なのでしょう。介護する側が、その宝の一部でも自分が見つけることができるという思いで、かかわることが、大事なような気がします。
2003.10.01
-
温泉教授の温泉ゼミナール
(気が着いたら2ヶ月近く、書き込んでいませんでした。本は読んでいるんですけど。。。。これからボチボチ復活しなきゃ。あまり気合を入れすぎずに) 松田忠徳著 光文社新書 レジオネラ症による死者が出たことから書き起こしています。療養のための温泉で、なぜ人が死ぬようになったのか。。 温泉といいながら温泉ではない、今の温泉事情を詳しく紹介しています。これを読むと、近所のスーパー銭湯に行けなくなりそう。。。。 いまの公共浴場のほとんどが循環風呂になってしまって、水の入れ替えや清掃を怠った結果が、レジオネラ菌の発生につながったわけですが、そうした基本的なことをせずに塩素をどんどん投入しているのが現状。お風呂のぬめりは塩素のぬめりかもしれないってことを、私たちはもっと知る必要がありそうです。 全国の温泉2500箇所をまわった著者だからこそ言える、いいお湯の見分け方。そして、温泉地とはどうあるべきか。一読の価値あり、です。
2003.09.23
-
困ります、ファインマンさん
R.P.ファインマン著 大貫昌子訳 岩波現代文庫 ノーベル物理学賞を受賞したファインマン博士の講演や聞き書きをまとめた本。一昔前にはやりましたね、ファインマンさんの本。 本書の半分がスペースシャトル・チャレンジャーの爆発事故について、調査委員として活躍したときの話。物理学者の立場で、事故原因をつきとめていく過程は謎解きのスリルもあるけれど、何より、事故の原因をNASAの組織的な問題としてとらえたところが面白い。現場では問題点をちゃんと把握して、解決策までたてていたのに、上層部がその重要性に気が着かず、解決されないままシャトルがとんでしまった。「打ち上げありき」で、誰が指示したわけでもないのにつっぱってしまったプロジェクト。NASAが巨大化してしまい、初期のころの顔が見える関係や情熱あふれる取り組みがなくなり、組織として膠着してしまったことの弊害が事故を招いたという・・・・・。これって、どんな組織にもあてはまるのではないでしょうか。 委員会のためにおぜんだてされた視察や聞き取りでは、本当のことがわからないと悟った博士。自ら単独行動で、製作現場に足を運び、技術者たちに直接話を聞くことで、重要な証言を次々と引き出していきます。優秀な人は、自分がどう行動し何をすべきか、わかってるものなんですね。私なんかは、ついつい今までどうやっていたか、人はどうやっているかを規範として、行動してしまうのですが。 本書の他のエピソードでは、子どものころに父親から受けた影響力についてかかれた「ものをつきつめることの喜び」が、子育ての上でも参考になりそう。博士の父親は、一緒に百科事典を読んだり、山を散策したりするなかで、子どもと対話しながらものごとの見方や考え方を、示してくれたようです。 例えば鳥を見て、その名前を知ることよりも、何をやっているかじっくり見てみようじゃないかという。名前を覚えた時点で、思考停止して、知ったつもりになってしまいがちな私たち。本当に知ることの意味、ものごとを観察することの大切さ。 最後の一章「科学の価値とは何か」。地球が宇宙空間に浮かんで回っていること、あるいは人の体を形作る原子たちはが日々生まれ変わっているのに私という人間は継続していることの不思議さを知っている私たちは、昔の人が持ち得なかった想像力や世界観を持つことができた。それはすばらしいことだなのだと博士は強調します。 さらに、科学者は「知らない」ということに慣れっこだと。それが科学の価値だともいいます。つまり、無知であることや疑いを持つことを「危惧するどころかむしろ歓迎」し、大いに論じ、思索する自由を持ち続けること、それが今後の進歩につながる。「その自由を義務として、次世代にも求めていくことが科学者たる私たちの責任だ」と結んでいます。 知らないことをこわがらない。知ったかぶりにならない。疑問を持てなくなること、自由に考えることを制約する社会に対する警告ともとれます。 本書を読んで「自分の頭で考えること」を改めて自分自身に言い聞かせた次第。
2003.07.31
-
青い月のバラード
加藤登紀子著 小学館 お登紀さんの歌。うちの母親が大好きで聞いていました。でも、学生紛争のころのこと、だんなさまのこと、ドラマチックな人生については本書で詳しく知った次第。 全学連の委員長であった藤本敏夫氏との出会いから獄中結婚、死までをつづったこの本。 彼らが出会ったのは私の生まれた1968年。激動の年だったのです。学生たちが理想に燃え、熱くたたかっていたころ。藤本氏は意外にニヒルで心に暗闇を抱えた人だったらしい。 一方、ヒット曲を出す歌手でありながら、早々に結婚し、三人の娘を育てながら歌の世界を広げていったお登紀さん。 藤本氏が出所して一緒に暮らし始めると、求める暮らしのあり方に食い違いが出てくる。嫌いではないけど、一緒には住めない。田舎で農業の実践をやりたい藤本氏と、世界を旅しながら歌を続けていくお登紀さん。とことん話し合って離婚の危機を乗り越えると(理想の夫婦のように見える彼らでも、こうしたあつれきはあったということ。人と人とが一緒に暮らすということは、こんなにも難しいことなのだ)それぞれのやり方を尊重しつつ、一緒に生きていく方法を見出す。「彼は大地、私は風」とお登紀さんは言う。 本書で深く共鳴した部分をかいつまんで。□趣味人、寒河江善秋さんに陶芸を学んでいたお登紀さんが寒河江さんから聞いたことば□ 「人生はいつでも片手を遊ばせておくことだ。そうしたら何か面白いことが向こうからやって来たとき、すぐ片方の手でつかめるだろう」 仕事や家事でいっぱいいっぱいになるな、心に余裕をもっておけという言葉だと受け止めました。□藤本氏が著書『農的幸福論』に記したことば□ 「時間をかけずに純粋理念を実行しようとしたものは、すべておぞましい結果を招いている。すべての思想は、その思想そのものに問題があるのではない。にもかかわらず純粋理念は必ず失敗している」 理想は間違ってはいなかった学生運動が内部分裂で終わってしまったこと。ソ連が目指したものはなんだった?このたびの戦争は? なんでも先鋭化することの危険性。 子ども三人を預けて働いたお登紀さんは、長女が四歳のころから子ども自身に相談しながら何事も決めていったという。仕事との両立にへこたれそうになったとき、お母さんに「どうしようかと迷うのはみんなを傷つけるだけよ。毅然としていなくちゃダメ」と言われたという。 子どもを預けるときにはだれでも迷うし、子どもにすまないと思う。でも、子どもは結構大丈夫なのだ。親の精神が不安定になることのほうが、子どもにダメージを与えるということ。何かのたびに思い出したい。 体中ガンに蝕まれて、最後は肺炎が原因でなくなった藤本氏。自分で酸素マスクをはずし、みんなと抱擁をかわしたという。 死と同時に、パートナーのお登紀さんに、出会ってからの35年がどっと押し寄せて、「これからものすごいことがおこるのだ」と思ったという。彼ののこしたことを受け継ぐ使命。なんて極上のカップルだろうか。
2003.07.24
-
編集会議8月号「絵本に恋して!」
宣伝会議という出版社の「編集会議」という月刊誌。今まで手に採ったこともありませんでしたが。絵本特集ってことで。思わず購入。 佐野洋子さんや松谷みよ子さんへのインタビューが載っている。これだけでもうれしい。最近うちの4歳児と「ちいさいももちゃん」を一緒に読んでいるのだけれど、あらためてその物語の魅力を感じてるところでした。(モモちゃんのお話って、ああ、子どもってこういう考え方が好きだよなあとうなずけるのです。いやいやえんも同じ) さらに「編集会議」らしく、絵本の編集者の座談会を掲載。福音館書店、フレーベル館などの編集者のみなさん、年齢を見ると私と同世代! こういう人たちが絵本を生み出しているんだ。。。。感動・感心とともに羨望。。3年後に出るような絵本をじっくり作っているということ。それを聞いて、絵本を捨てられないわけがわかったような気がしました。他の本と、手の掛けられ具合が違うんですねえ。中身は簡単だし子ども向けということなんだけど、本としての質の高さがこの辺に出てるのでしょう。 特集以外も面白くて。この雑誌が実はあの名編集長花田紀凱さん+2人だけで作ってると知ってまたまたびっくり。よくできてるなあこの雑誌、と思っていたら、そうだったのね。
2003.07.08
-
僕はガンと共に生きるために医者になった
稲月明著・光文社新書 著者は私の住む愛媛の南予の病院に勤務していた医師。自らが肺がんになって、自分のがんが治りにくいものだと知り、残された人生の目標としてHP作成をはじめる。闘病生活をつづった「肺癌医師のホームページ」をもとに作られたのが、この本なのでした。 余命いくばくもないことを知ったとき、日航機事故で自分の死期も知らずになくなった人たちのことを思い、「自分には時間がある」と考えた著者。私だったら取り乱してしまって、毎日泣いて暮らすに違いない。 医師の立場から、ガンというのは一人一人違うこと。告知も、治療についても、そのガンがどういうものかによって、対応が変わってくるということを、説明しています。 がんとたたかうか、たたかわないか。近年、両方の立場から本が出され、患者や家族の心を惑わしていますが、著者は、治らないガンである場合は、病気とつきあいながらよりよい最後を迎えるほうがいいだろう、といっています。 ガンの告知にしても、すべきだという意見を押し付けずに、その後のケアができるかどうかまで考える必要があると。(一般的に助成の方が落ち込みが激しいという分析。その通りでしょう) 一般的な医療については、お年寄りに対しては、薬の多用や無理な治療はやめて、病と共存しながら自然に老いることを目指すべきだと主張しています。 なやんでいる若者たちには自殺をするなというメッセージ。そして、自分の子どもたちのもメッセージを残しています。「親孝行は、社会人として自立した大人になること」。「自分に与えられた能力を精一杯発揮した人生を送ること」 医師として、医療のあり方に提言を残した著者は、精一杯のころの人生を生きる姿を見せることで、父としての役割を果たしたのでしょう。 それにしても、淡々と自分の病状を見つめる日記には驚きです。書くことが自分も、他の人に対しても励ましとなるんだってこと、あらためて感じました。
2003.06.26
-
教えることの復権
大村はま 苅谷剛彦・夏子著 ちくま新書 東大教授でゆとり教育への疑問を投げかけてきた苅谷氏。その奥様夏子氏が、大村はま先生の教え子だったというのです。(秀才夫婦!) 大村はま先生の名前は図書館にずらーっと並んだ実践記録「大村はま国語教室」で知っていましたが、実際どういうことをされてきたのかは、この新書で初めてわかりました。 本書ではまず、夏子氏の記憶にある大村先生の授業が語られ、先生と二人の対談になります。 大村先生は現在、96歳! 年齢を感じさせないしっかりとした思考。言葉の力というものを身をもって伝えているかのよう。 夏子氏は回想のなかで、答えのない「なまぬるい」国語という教科が好きになれなかったことを率直に述べています。知ってるつもりの日本語を授業で学ぶということ。つまらない授業・・ それが中学生になって、大村先生(当時63歳!!!)に出会って、考えが一変します。常に新しい独自の教材を見つけてくる先生。授業は図書室で。例えば「ことば」とは何か、いろんな文章の例を集め、それを分類し、自分なりの辞書をつくっていく。一人ひとりが「研究者」となって、夢中になってやったというその作業。生徒を一人前に扱い、適切なアドバイスができる先生がいてこそなのだろうけれど。夏子氏が語る授業の数々は、知的な作業を経て、着実に自分のものにしていく喜びにあふれていて、とてもとてもうらやましい。 試験にしても、出来具合をランク付けするのでなく、その子その子の病気=わからないところ=を、診断するために行い、診断がついたら有効な治療を施すことが大事といいます。 ひるがえって、現在の教室では、どんな授業が行われているか。「生徒の自主性」を大事にして、楽しく活気のある授業がいいとするのが今の風潮。自由に生徒にまかせるとの口実で全く教えず、盛り上がりだけをよしとして、結果を問わない授業。(この辺は、苅谷氏がずっと主張していることと重なってきます)。「教えなくなった」教師と教育。果たしてそれでよいのか。 大村先生は戦後すぐ、教壇にたつにあたって、ことばの大事さを実感したそうです。
2003.06.16
-
らんどく、状態
(日記を更新していないのに、毎日20人くらいの人が見てくださっている様子。不思議&感謝) 感想を書く間がないので、現在の読書状況報告。 ・らんどく中(進行形) 『レセプト開示で不正医療を見破ろう!』 小学館文庫 『介護保険の教室』 岡本祐三著 PHP新書 『この本読んで! 2003年夏号』 出版文化産業振興財団 ・つんどく中(読みかけ) 『アメリカのイラク戦略』 高橋和夫著 角川oneテーマ21 『メディア・コントロール』 ノーム・チョムスキー著 集英社新書 『混沌からの出発』 五木寛之・福永光司著 中公文庫 『成人病の真実』 近藤誠著 文藝春秋 ・読了 『たかね先生の地域医療論』 矢嶋嶺著 雲母書房 こうしてみると、簡単に読める新書や文庫が多い&自分の関心事の偏りがわかりますなあ。。。。
2003.05.22
-
ちいさいぶつぞう おおきいぶつぞう
はな著 東京書籍 モデルで、お菓子作りが上手で、バイリンガルで、大学のときに東洋美術を専攻したというはなちゃんの仏像本。ところどころに挿絵風に入った直筆イラストが、写真よりも、その仏像の性格を見事に現していて、ほんとうに仏像がすきなんだなあと思わせます。 全国20箇所のお寺を「さんぽ」。どんな気持ちでどういう風に仏像と対面したか、そのときのはなちゃんの感じたことが、ダイレクトに伝わってきて、こちらまでワクワクします。ああ、こんな風に仏さんに接したことなんてないなあ。はなちゃんの「仏像の見方」って、すごいです。 私が参った!と思ったのは、奈良秋篠寺の伎芸天の項。伎芸天ってナミダを流してるらしい!そして、母親のような表情と、そっと伸ばした右手。それを「子どもの手を引く母親の姿を見ているよう」という直感。アフガニスタンの菩薩像との共通点から、視線の先には子どもがいたのだろうと推測し、「母の心に国境はない」ことをつづっています。私も伎芸天は好きで2度ほど見に行ったことはあるけど、「表情がいいな」くらいしか、思わなかったなあ。 さらに日本最古の寺とされる奈良の飛鳥寺。ここの釈迦如来(飛鳥大仏)が、とても間近に座っていて、しかも写真撮影がOK。常に仏像の置かれている空間を丸ごとつかもうとしているはなちゃんは、日本仏像史の会長クラスの貫禄」を感じたという。ガラスケースにとじこもっていない、のびのびと座り続けている仏像に、人生を生きていくパワーまで感じています。 東寺の帝釈天(これは、私もかっこいいと思いました)、興福寺の阿修羅像など、「知的でうちに秘めた思いがにじみ出ている」仏像がじぶんの好みらしい。仏像それぞれに人格を感じていて、読んでいるこちらまで、親しみをもってしまいます。 さらに、感想だけでなく、服装や髪型がこうだから、しぐさがこうだから、仏像の並び方がこうだから、この仏像はこういう種類の仏様だから等々、学問的な根拠をさらっと出してきて、それぞれの仏像の特徴を見事に表現してる。普通の仏像鑑賞の手引きよりすごいかも・・・・
2003.05.06
-
みかんたろう?
寝るときにお話しをしてくれるというしゅん(4歳男)。ひさびさの「おはなしおはなし」のおちゃらけた内容は左←の「みかんたろう」をクリック!
2003.04.29
-
検疫官
小林照幸著・角川書店 ついこの間までだったら「検疫官」ってなんだろうって、興味ももてなかったに違いない職業。でも、昨今の新型肺炎の流行で、「ウイルスを水際で食い止める」という検疫の仕事が、一般庶民の私たちにもピンとくるようになったような気がします。 本の帯に「ここに、日本を守る一人の女性がいる」というコピーとともに、りりしくもやさしそうな女性の写真。彼女こそが、この本の主人公であり、日本人で初めてエボラ出血熱の患者を現場で治療し、日本初の女性検疫所長となった岩崎恵美子氏なのでした。 普通の女医、それも腕のいい耳鼻科医だった井上氏が、50代をすぎて熱帯医学を志し、検疫という仕事を知り、感染症対策の第一線に立つ。普通なら子どもも巣立って、ようやく自分のために、安定した生活が送れるという年代に、あえて発展途上国の医療につき、新しい課題に立ち向かっていく。「この年になってもう自分なんて、」とか「今更無理よ」なんて言ってしまいがちな私には、カウンターパンチでした。 検疫という仕事についても、HPを開いたり、一般の人たちに感染症の注意点を訴えたり、どんどん改革を進めていく。その間にも「患者を実際に見ていなければ、判断できない」という確信をもって、エボラ出血熱の患者をすすんで治療しに行く。現場を知っている強さ。それによって、講演会や学会での彼女の発言がわかりやすく、重みのあるものになる。そうして、おそらくそれまでの男性たちでもできなかった(気づかなかった?)ことを、次々とやりとげていくさまは、読み手をぐんぐん引き込んでいきます。 感染症の怖さや海外旅行に出る際に注意すべきことなどが、基礎知識として得られるのもこの本の魅力。 感染症は人が運ぶ。仙台という土地に全世界の人が集まったサッカーW杯の裏で、大掛かりな生物・科学テロ対策が実施されていたことも私には初耳。読みながら「地上の星」が頭の中で流れてくるような、スリリングなプロジェクト。それを岩崎氏が率先していたということに、また驚かされます。
2003.04.19
-
介護を創る人びと 地域を変えた宅老所・グループホームの実践
加藤仁著・中央法規 まだ私には他人事のような介護の話、だけど。親の年齢からすれば、いつ直面してもおかしくない問題。介護保険が始まって3年がたって、だいたい仕組みもわかってきたけれど、いったいどうするのが本当にその人にとって幸せなのか、とても難しい問題です。 家庭内での介護地獄を救う意味では介護保険制度も役には立っているようですが、その受け入れ先の大規模施設は、大規模ゆえに入所者の立場ではなく管理しやすい方法で、ケアが行われていく。オムツをし、決まった時間に入浴、食事。何もかも、流れ作業で。リハビリの名のもとに行われるボール遊びなどのお遊戯。本当にお年よりは進んでやっているのか。人生の先輩であるお年寄りたちを子ども扱いしていいのか。 この本には介護の現場で「おかしい」と思い、お年寄りひとりひとりに向き合いたいと願った人たちが、自ら介護のための小さな家をひらき、手探りで実践していったその足取りが示されています。全国各地で、響きあうようにこれら「宅老所」「グループホーム」が次々出来始めたという事実が、理想的なケアのヒントがここにあることを示しているようです。 ここに出てくるいろいろな「家」の共通点として、地域の人々が自然にボランティアで参加⇒入所しているお年寄りが、痴呆の人も含めて、自分のできることをすすんでしている⇒どちらがどちらかわからない、介護する側、される側がお互いに必要としあっているー。日中どうすごそうかは各自の自由。ゆるやかな大家族のような、そんな空間。人間らしい生活。自分が暮らすなら、親を頼むなら、こういう場所がいいと誰でも思うのではないでしょうか。 著者は大規模施設を1つつくるなら、こうした小規模な施設を幾つか作るほうがいいのでは、と提言しています。ただ、これらが実現したのは、採算を度外視して理想を求めた人たち(ほとんど女性!)の存在があってこそ、なのです。
2003.04.10
-
らんどくつんどくについて
一昨年の10月から細々と、続けてきた読書日記ですが。ここに来てかけなくなりそうです。 というのも、4月から新しい職場へ変わるに当たって、仕事上必要と思われる本ばかり買ってしまったため。 なかなか読み進めず、感想をかくひまもありません。 いままで読んでくださったかたありがとうございました。 余裕が出来たらぼちぼち書いていこうと思います。 (それまでこのページが消えてないといいのですが) 何か読んでやろうと思われる方は、本ページの「ぶるぶるしゅりこっぱー」をご覧ください。(上記参照↑) 日記はページの下のほう、入り口を見つけてお入りください。 では、しばしのお別れ、です。
2003.03.28
-
今、赤ちゃんが危ない
田口恒夫著・近代文芸社新書 「ヘンな子どもが増えている」という言葉で始まるこの本。著者がいっている「ヘンな子ども」というのは「指差して人に知らせない」「親になつかない」「物とはよく遊べるが人とは遊べない」乱暴でなく成績も普通だが、親友がいなくて異性へのアプローチのしかたがわからない。男の子に多いという。そして、こういう傾向が不可解な犯罪の根っこにあると主張しています。 それは「受胎から生後2年くらいまでの間における『密着育児』をおろそかにしたための当然の結果」だと警告しています。 世の中の様子をみて危機感を感じていた著者が、自分の体調がすぐれない、一言これだけは言っておかなければと、自費出版して訴えた文章がもとになってツくれれたこの本。体の不調をおしてまで著者が言おうとした「密着育児」というのはどういうものか。 人間の人柄の根幹をなす部分がつくられる胎児期乳児期に、母子が密着していること。泣く⇒抱き上げる⇒泣き止む。あやす⇒笑うという交互作用=やりとりを通じて、子どもは母親になつく。安心感と満足感の基礎ができて、はじめて外部の人々に興味をもつことができる。親も子どもになつかれることで「母性」が育つ。 著者は「情が薄い」子どもが親になるとますます情が薄くなり、さらにその子どもが親になると。。。という「性格薄情化」の連鎖がおきているといいます。この流れを断ち切らなければと。 密着育児をしていれば、子どもの情緒が安定して子育てもラクになる。その根拠として、隔離飼育したサルが異常な行動を示すこと。密着育児をしているアフリカの子どもたちの成長が早いことなどをあげています。 それなのに。「親の都合で」「アタマを使って」密着育児を省略・破棄してしまっている。避妊や計画出産、そして産んだ後でも保育所に預けて働く。ここ50年あまりの社会経済の発展がそうしてしまったと。育児休業をとったとはいえ、その後働いている自分にとっては、すごく耳の痛い言葉です。そうなんだろうけれど、そういうわけにはいかない家庭だってあるのだ。 著者も本書の端々で、それの救済策について述べてはいます。子どもをおんぶしていっていい職場環境にする(これは難しい?在宅勤務が最善策かも)。祖父母とともに住む。特に祖父母というのは、無条件にかわいがる存在として貴重だといいます。「強い責任感を持った父親、母親というのは、子どもにとっては有害な存在なんですよ。。。親の能力を超えた。身の程知らずのことなんだと知らせなくちゃいけません」 ここ。ブックマークです。 ついつい、大きくなって大変だから、とか、親として責任があるからという言い訳ですること(しつけや早期教育)って、実は親にとっての都合だったり見栄だったり、世間体でしかなかったりする。子どもにとってはいい迷惑なのかもしれない。 理想的な育児としてチンパンジーのアイの子育てを紹介しています。子どもがくっつくのをいやがらない。子どもはアイにべったりして安心すると動き回る。でもアイはようすをじっと見ていて、危ないことがあるとスーっと引き寄せる。ほかのチンパンジーがきて子どもがいやがってなければ抱かせたり、子どもが困ってると引き寄せたり。。そうなんだ。とにかく子どもをベッタリさせていさえすればよかったのだ。育児書にかいているHOWTOなんて、必要なかったのかも、と、ちょっと後悔。 ただし、「かわいがるほどいい子になる」という言葉を、甘えさせる=子どものいいなりになると混同してはいけないように思います。密着育児=スキンシップ、というのと、わけて考えないと。 今からでも遅くない、子どもが大きくなってからでも、おぶったり抱っこしたり。密着育児のリベンジができるそうです。 仕事もやめられない、祖父母も近くにいない、こんな我が家だけれど、せめて一緒のときは「密着育児」でいこうと思います。反省をこめて。
2003.03.13
-
飛鳥 水の王朝
千田稔著 中公新書 先月(2月)、奈良・明日香村の石神遺跡で見つかった木簡のなかに、日本最古の暦があったと報じられました。持統天皇の時代!この暦、なんと毎日の吉凶をかいてるんです(具注暦といいます)。日付のあとにその日の干支、その後に吉凶をあらわす1文字と、その説明と。びっくりしました。この日は旅行に行かない方がいいとか、蔵開きにいい日だとか。平安時代の貴族たちが、物忌みとか方違えとか、暦にしたがって行動していた、そのルーツなのでしょうか。 この、暦、どういう思想のもとに作られたのか、報道ではまったくわかりません。吉凶とか、方位方角とかに意味を持たせる思想って、たしか道教思想じゃなかったっけ。飛鳥時代の遺跡を道教思想で解いていたのが千田氏。それであわてて本を検索して、この本を見つけました。 2001年秋発行なのでもちろん暦のことはかかれていませんが、近年の飛鳥の新たな発掘成果(キトラ古墳壁画の朱雀・斉明朝の石敷遺構と亀石の発見など)についても触れられています。 で、本書によると。飛鳥時代には、中国ではやっていた道教の神仙思想などが導入されて。舒明のころから天皇の墓は八角形の墳形になる。道教で八方位は宇宙の象徴。天皇こそ宇宙王ということで。称号としての「天皇」(=天の中央である北極星は天皇大帝という道教の最高神)の成立とも連合すると、千田氏は見ています。 天皇の宮がおかれた飛鳥と離宮のあった吉野は、いずれも不老不死の仙人が住む神仙境とみなされていたこと。蘇我馬子がつくった庭には島があって「嶋の大臣」とよばれた。池は海、島は仙人の住む3つの神山。そうした不老不死の楽土である苑池遺構が、必ず天皇の宮から見つかっている。 ここで千田氏は石に注目します。推古天皇の小懇田宮から持統天皇の飛鳥浄御原宮まで、飛鳥の天皇の宮には石敷きがの遺構が存在する。万葉集の和歌にある「百敷きの(ももじきの)」という枕詞(⇒「宮」にかかる)が、宮殿に石が敷き詰められたことをよく示している。千田氏は後漢時代の鏡の銘文の「生くること山石の如し」という言葉をひいて、永遠に存在する岩や砂礫を不老長生のシンボルとみなしていたと考えます。斉明朝の大規模な土木工事によって酒船石の北側の谷状地形で見つかった石敷と亀形石造物。この亀も神仙の住む世界を背負う亀、と徹底しています。 不老不死を解く神仙思想は、永遠の命をのぞむ権力者たちの心をしっかりとらえたんだろーなあ。仏教にしても、蘇我氏が奨励して飛鳥寺をたてたのは長寿のため。自分たちを延命し、統治する世を永らえるためには、何教だろうが関係ないんですね。 (私が疑問に思っていた暦については天武・持統朝に天文・暦・気象をつかさどる陰陽寮という役所が存在していたとのこと。このころには暦の知識が根付いていたらしい) 千田氏は八角墳にしろ、石敷きにしろ、道教の影響を受けてはいても日本にしかない遺構を通じて、この飛鳥の100年が日本の基礎を築いた画期であったことに注目してほしいと述べています。 もともと飛鳥時代というのは好きな時代でしたが、この1冊で概略をつかみなおすことができたかな。(藤ノ木・高松塚・キトラ古墳などの被葬者の推理も楽しめます)
2003.03.10
-
コーチ論
織田淳太郎著・光文社新書 中高生のとき体育会系の部活をまったく経験していない私でも、「運動中に水を飲むな」とか「早く走るにはモモを高くあげて、手を振って」とか「とにかく数をこなせ」とか、聞いたことがあります。ところが、これらの常識とされていることが、実は非常識だったったらしい。それは昔その道のプロ(外国人)が言ったことを誤訳したものであったり、コーチをする人たちの経験でものをいっているだけだったり。全然科学的根拠に基づいていない、どころか、選手たちをダメにしてしまうようなことを、高校野球に代表されるスポーツの現場で行われてきたらしいのです。 この本では、スポーツライターの著者が、今まで行われてきた「無謀な」指導方法に疑問を呈し、本当のコーチングとは何かを探ったもの。ただやたらにしかりつけたり、とにかく根性でやり続けろっていう指導は、本当にそのスポーツにおいて必要な筋肉の鍛え方や技術の磨き方を知らないためにそうなってしまう。自分に自身がない人ほど、声を荒げたり人を脅すのと同じですね。 教えない方がかえっていいことがある。選手たち自身に考えさせ、自分のレベルアップを楽しめる練習を追及する。コーチの役目はそれのサポートであり、ヒントを与え、相談にのってやることであって、経験を押し付けてはいけない。ここに書かれている「コーチ論」はスポーツだけでなく、他の教科や習い事についても同じことが言えそうです。 この本、スポーツをしない人にとっても、巨人の桑田がどうやって復活をとげたか、スケートの堀井はなぜ頂点にのぼれなかったかといった、秘話がうかがえて面白い。 個人的には江戸時代の飛脚たちがやっていた「ナンバ走り」に興味があります。左右交互に足をださない疲れない走りなんだって。桑田復活のヒントになった「踏ん張らす」「うねらず」「捻らず」という古武術の動き。これを取り入れようと暗中模索して、生徒たち自身で動きを開発し、目覚しい躍進を見せた桐朋学園バスケ部の話は感動モノです。
2003.03.05
-
韓国語はじめの一歩
小倉紀蔵著 ちくま新書 テレビのハングル講座で韓日の美女、ユンソナちゃんと黛まどかさんとともに韓国語を教えているのが著者の小倉先生。で、必ず最初に言う言葉が「ハングルはみなさん、宇宙なんですね」。 そうハングルという文字は、まさに天地人の宇宙をあらわすものとして作られた、非常に完成度の高い文字。この言葉にはじまり、小倉先生がいかに彼の地の言葉に魅せられたかが、ひしひし伝わってくる本書。先生は彼の地のことを「韓くに(からくに)」という言葉でよんでいます。その語り口は。詩のようになめらかで、軽やかで。 「はじめの一歩」ということで語学の初心者向けにかかれたものにもかかわらず、単なる語学の本とは違う。 言葉のすばらしさ、韓くにの人々の性質、彼の地にひかれていった自分の若き日々のこと。その国や言葉にあこがれながらも決して近づけない。そのせつなさがあふれていて、この本事体が「韓くに」に対する詩をつづった恋文のよう。(もちろん、韓国の言葉の特徴や基本的な文法はしっかり述べられていますが) 私自身、韓国という国にいつの間にか興味を持ってしまったのですが。この、日本に住む私たちの思いというのは、2000年ほど前に半島からわたってきた、日本の祖先のひとつの系統である、その血筋によるものなのでしょうか。
2003.03.02
-
イラクの小さな橋を渡って
池澤夏樹著・本橋成一写真 光文社 米の武力行使が秒読みといわれる最中に作家の池澤氏がイラクを旅した。なんでわざわざ、そんな危ないところに、と思ってしまったのだけれど、氏の目的は文明発祥地、メソポタミアの遺跡を見るため。そして、ヴィザは意外にもすんなり発給してもらえたというのです。2002年の10月の末のその旅行の見聞をまとめたこの本。池澤氏の文と本橋氏の写真で成り立っていて、一気に読んでしまいました。 静かな本です。 戦争反対を声高に叫んでるわけではなく、氏が実際にイラクを訪れて見てきた彼の地の日常が語られています。遊園地で遊ぶこどもたち、市場の様子、美しい模様のモスクに集う人々、街角の古書市。写真にうつる人々は普通に暮らしている。氏によると確かに経済制裁によって10年ほど足踏みをしてしまっている国だけれど、食事は安くておいしいし、人々は明るく親切。 戦争の危機にさらされていて、どんなに悲惨かと思えば、ごくごくあたりまえの日常。戦争だ、戦争だと切羽詰ったように破壊の道へ走ろうとするどこかの国の異常な熱さと、非常に対照的で。だからこそ余計に切なくなります。この人たちの静かな日常を奪う権利が、あなたにあるのか。 メディアを通してしか知らなかったイラクという国の一部を、この本のおかげで垣間見ることができました。氏も書いているように、具体的な人物を知ることで、戦争が起きたときの彼らの境遇や思いを想像することができる。感情を動かすことが出来る。 戦争を起こすほうは一人一人を見ていない。フセインを排除するのに国ごと攻撃することの理不尽さから目をそらすし、どれだけの人が苦しむかという想像力をもたないようにしているらしい。 私たちはそれではいけない、知らなかったじゃすまされない。「無関心は冷酷よりも更に冷酷」だと氏は述べています。中高生のころによく言っていたのは、誰かがいじめられているとき、それを見ていてとめない人も共犯、ということ。私たちの国は、冷酷な共犯者になってしまうのでしょうか。
2003.02.28
-
モダンガール論
斎藤美奈子著・マガジンハウス 「女の子には出世の道が二つある」。 斎藤氏によると「立派な職業人になること」と「立派な家庭人になること」。で、どっちが魅力的な人生か、どっちも手に入らないか、女の子は揺れ動いてきた。 そんなこと、だれだってわかってる。けれど、斎藤氏の功績(?)は、それが明治大正の祖母の世代、昭和の母の世代もそうであったことを発見したことにあります。(もしかしたら、江戸以前も!!) ここ100年のあいだ、女の子たちが何を考え、何を夢見て生きてきたか。たくさんの雑誌や記録を調べ上げて。女の子たちの「欲望」を通して歴史を見る、という面白い試みをしたのがこの本。 戦前、女性ののぞましい生き方として示されたモデルケースは「女学校→職業婦人→主婦」というコース。しかし戦前はまだ社会が貧困で、このコースを目指せたのは一部の中流階級の助成だけだった。で、戦後50年は、高度経済成長の波に乗って、庶民がこぞってこのコースを目指し、目標を達成してしまう。 戦前の拡大版として全く同じ動きがあったこと。戦後が女性たちのリベンジであったこと。巻末にある年表では戦前と戦後の動きが対比され、女性の100年の歴史がひと目でわかります。まずフェミニズムや良妻賢母思想の普及=専業主婦増加が同じタイミングで出てくる。で、単なる職業者・家庭人にあきたらない女性たちが一段上のスーパーキャリアウーマン、カリスマ主婦を目指し時期も重なる。おもしろ~い。 専業主婦論争、アグネス論争、いろいろありました。主婦がいいんだ、いや働かなきゃ。どの女性も一度は悩んだだろう永遠のテーマです。私自身はどちらがいい悪いじゃなくって、その人の選択なんだと思っているのですが。主婦にしろ職業人にしろ女性は「自分の存在を認められたい。損のない生き方をしたい」と願っているのですねえ。 斎藤氏はこの100年の「女性の欲望の歴史」を振り返った上で、その出世の夢が「男は外。女は内」という性別役割社会の上に成立したという限界を示しています。男女間の階層。戦前においては女性のなかの貧困層と中流階級の間の階層。しかしこのシステムのなかで、女性たちは「けっこう上手くやった」のであって、100年かかって「庶民の娘たちによる階級闘争」が行われたのだと指摘しています。 で、こうして出世欲を満たした女性たちが、次の100年、21世紀に差し掛かって悩んでいる。性別役割分業社会は「制度疲労」がはじまり、人生の上がりとしてのキャリアウーマンやコマダムにもなれない&魅力が持てないとしたら。上がないことをしった女の子たちがいま夢中になっているのが「癒し」と「自分探し」であるのは当然。これからはそのシステム事体が(つまり、男は外。女は内。という前提で成り立っている社会が)変わらなくてはこの先が見えないだろうとしめくくっています。 自分も女性だけに、読みながらいろいろ考えさせられました。 斎藤氏の「発見」のひとつに、女性誌の影響力というのがあります。戦前も戦後も、女性の出世の夢をかきたて、モデルを示したのが女性誌であったこと。いまだってそう。主婦向け雑誌であれば、いかに節約しつつ毎日おいしい料理を手作りするか、収納に工夫をするか、子どもに投資をするか。カリスマ主婦だけでなく読者の代表たちが模範となる生活を示していて、全然できていない自分などをとてもあせらせるのですが。世の中の主婦がみんなこんなことできているわけではないのだけれど、できていないと「失格」であるような気がしてきちゃうんですね。 もうひとつ。戦争について。庶民や女性は内心では戦争には反対であり一部の軍部の暴走だったと思いがちだけれど、実は女性たちも嬉々としてお国のために働いていた時期があったという事実を指摘しています。「国政に女性が参画している高揚感」によって「進歩的な女性知識人が率先して戦争協力に走った」のであり、「軍国婦人の頭の中身は私たちと何もかわらなかった」という事実。戦争という有事になって初めて、階級の差なく女性のすべてが力を発揮できる状況になったという皮肉、悲しさ。 さて、自分も含めて21世紀を女性はどう生きていくのだろう。欲望というと悪いことのようですが、女性の欲望が社会を活性化してきたのだとすれば、欲望すら持てなくなってきたことは却って危険なような気もします。
2003.02.24
-
「国宝鑑真和上展」図録と「あかい奈良」
現在、愛媛県美術館で「国宝鑑真和上展」開催中。あの、鑑真さんの坐像をナマで見ることができました。唐招提寺の大修理に伴って、全国を1年に1回まわっているこの展覧会(初回は2001年東京)、愛媛にきてくれてありがとう。 鑑真さんのあの微笑は、モナリザの微笑みと同じで、きっと後世の私たちには表現できないだろうなあ。本当の姿をみながら作っただけあって、微妙に手の位置、足の位置が中心をずれていること、本展ではじめて知りました。小さな坐像なのに、ゆったりとした包容力があって。そこにいるだけで人の心に感銘を与える、そんな人だったのだなあ。 唐招提寺の他の仏像もたくさん来ているのですが、どれもすばらしい。一つ一つが個性があって、見飽きませんでした。 で、その図録がまたすごい。豊富な写真と論考で、展覧会の感動をもう一度かみしめて。美術・建築・歴史・思想史・・とさまざまな角度から唐招提寺の価値を教えてくれます。(鑑真さんのお顔のアップで、細かいまつげやひげがあるのにびっくり。目で見たときにはぜんぜん気が着かなかった。。) その展覧会場で「あかい奈良」を販売していました。これ、そこらへんの書店では手に入りません。奈良という土地についていろんなことを教えてくれる季刊誌で、写真も美しい。連載は伝統の食材や行事、メジャーでないけどすごい古社寺の探訪などなど。私が購入した刊は、奈良と「火の鳥」の手塚治虫との関係、奈良の近代建築特集、奈良公園のツウな散歩コースなどが載っています。 奈良が好きな人にはたまりません。 ウェブページはこちら
2003.02.20
-
憲法対論
奥平康弘・宮台真司著 平凡社新書 その風貌に今まで拒否反応を示していた宮台氏の本ですが、以前掲示板のほうで紹介していただいた本なので読んでみました。 (で、彼が右にも左にもかたよってない、しなやかな考え方をする人だってことがわかって意外。興味はミーハーでも中身は硬派とみた) この本、随分前に読んだのですが、いざ感想をかこうとして何度もザセツしております。とても示唆に富む意見がそこらじゅうにあるのですが、それを自分の言葉でまとめることができません。 で、感想を。 憲法改正について。おしつけられた憲法だから変えなくてはいけない。時代に合わない。それに反して、世界でも唯一の非戦を訴えた憲法だから、変えてはいけないという意見。しかし、「憲法の成立なんてどのクニでもいい加減」という。問題はその後、成立後にどう動かしていくかにある。 改正するにしても、その前提として民度というか、私たち日本国民が憲法を理解し、関わっていく能力をもっていなければならない。一部の人々にいいように利用され、国を間違った方向に動かしていかれないように、市民が力をつけなければいけない。事実、宮台氏によると故吉田茂首相は安保体制に移行するときに、「戦後復興を遂げた暁には。。」「冷戦体制の終わった暁には。。。」独自外交を展開するべきだと考えていたらしい。70年代の政治家たちは、いずれ「憲法に関わる立法意思の表明に耐えうる力」が育つことを信じていたようです。 で、いまの私たちにその力はあるか。ザンネンながらないとしかいえません。現に私はこの本を読むまで、憲法についていろいろ考えたりすることはありませんでした。まだ改正するに値する国民ではないのではないか。で、あれば。いまの憲法を理解し、かかわり、動かしていくことを考えるのが先ではないのでしょうか。 心にとまった言葉。 豊かさについて。本人がもしかすると別の選択肢をえらべたのかもしれないのに、自分はあえてその選択肢を選んだと思えること。「選択肢の束」が与えたれている社会こそ豊かなのだと。
2003.02.16
-
これが絵本の底ぢから!
谷地元雄一著・福音館書店 例えば。保育園で散歩に行くとき。 ひとりの子が口ずさんだ「ぶたぶた」が、隣の子の「がおがお」を誘う。(絵本の『ゆかいなさんぽ』)そして「ぶたぶた かあこお・くまくま どたじた どんあん。。」と『ぶがぶたくんのおかいもの』の世界になる。 またあるときは。何気なく地図帳を見ていた子どもが「おーっ!オーリーだ!」と叫ぶ。『海のおばけオーリー』に出てくる地図と同じ、北アメリカ大陸の地図を発見。絵本と地図を見比べて「空想の世界と現実の世界の一致」にみんなで驚く。 そしてまたあるときは。保育園の近くの林で白髪頭のおばあさんを見た子の話が発展しておにばばが住んでいるといううわさになる。で、林に行くのを怖がる子がでてくる。そんなとき『くわずにょうぼう』のおにばばがよもぎが嫌いなことをだれかが思い出して、林にもよもぎがあるからおにばばは住めないと言う結論に達して、めでたしめでたし、となる。 などなど。著者の谷地元氏が体験した絵本の「底力」が数々紹介されています。子どもたちが日々の暮らしのあらゆる場面で、絵本の世界に触発され、いろんな方向に向けて発展させているようす。 これってすごい! 室町時代の能狂言を見る人たちや、江戸時代に歌や俳諧をつくる町人たちが、和歌などの古典文学を共通の文化としてもっていたのと同じような。一言で「ああ、あのことね!」と了解し、その言葉の裏に別の物語が潜んでいることを前提として話をすすめていく、そんな世界。 絵本を共通の文化として持っていることって、何て豊かなことなんだろう。 そして著者の主張は「絵本は使える!」。水泳シーズンには水泳の絵本を読むと競って顔を水につけようとする。拾ってきたどんぐりだって食べれるんだと絵本で知ってみんなで殻むきをする。などなど。なんでもやってみよう、自分たちでつくってみよう、どんどん体験しよう・・・という主義で子どもたちとつきあっていくときに、絵本というのは威力を発揮するようです。 著者自身がとても絵本が好きな人なんですねえ。たくさん読んでいて、しかも覚えている。大学時代から大の男の友人たちに読み聞かせをしていたっていうから筋金入り! そう、絵本っていうのは子どもだけのものでなく、大人にとっても楽しく大事なものだったりします。もしかしたら子どもと大人が同じ舞台にたってものをみたり、考えたりできるその土台として、唯一の貴重なメディアが「絵本」といえるのかもしれません。 (ワタクシ的には童謡「赤い靴」の歌詞にある「♪い~じんさん(異人さん)につ~れられて」というのを「ひいじいさんにつれられて」と勘違いしていたという話、「あっ!私も一緒!」とうれしくなってしまいました)
2003.02.11
-
はちまん 上・下
内田康夫著・角川文庫 浅見光彦は知っていても、内田氏の小説を読むのって実ははじめて。○○殺人事件っていうの、なんとなーく触手が動かなかったのですが。これはずばり「はちまん」いろいろ期待させられる題名ではないですか。。 八幡といえば八幡神社。自分が結婚式を挙げたのも、子どもの百日参りをしたのも、なんだかんだで八幡さん。内田氏も解説にかいてありますが日本で最も多い神社が「八幡神社」なんですねえ。 で、内田作品について。日本のあちこちを旅した気分になる。はちまんでは秋田・長野・石川・兵庫・広島・高知・大分・熊本をまたにかけて、事件が動く。高知や大分の宇佐八幡は実際に自分が行ったことのある場所が出てくるのでなんとも楽しい。 事件の裏には終戦を迎えて世の中をよくしていこうと誓った特攻隊の男たちの思いがあり、現在の天下り・政治献金=収賄といった政治の問題やサッカーくじ導入問題がからんでくる。そこに関わる女性の祖母が特攻隊員たちのマドンナであり、巫女の血=もしかしたら卑弥呼の時代から=をひいているという。 地理的にも歴史的にもスケールの大きさを感じさせられました。読みながら地と時を登場人物とともに駆け巡った気分。 八幡というポピュラーで歴史のある神社に関わる人物たちという設定が、物語を無理なくすすめさせたよう。 戦後生まれの自分。先の大戦を経験したいまのお年寄りたちに、青春時代があり、日本をよくしていきたいと思い、歩んできた道のりを知らずにいること、あらためて気がつかされました。愛国心といったときに、どうしてもナショナリズムというか胡散臭い危険なものを感じてしまう私と、戦争を生きた人たちと、日本という国への思いは違うのではないか。 推理小説ではあっても、テーマは謎解きではなく、人と人との「縁」や人間関係の不思議さ・大切さ、といったもののように受け取りました。
2003.02.06
-
経験を盗め
糸井重里著・中央公論新社 聞き上手の糸井氏がさまざまなテーマについて、各界の人々から話を引き出してくれています。思わずあちこちポストイットを貼りまくってしまいました。そのなかからいくつか。・旅のお話 「よく外国のナントカ村というものを紹介した本があって、読むとおもしろかったりするでしょう。だけど僕が子どもの頃に気づいたのは、その村がおもしろいんじゃなくて、じつは書いた人がおもしろいんだと。(略)そう考えると、世界中どこでもおもしろい。出会いは当人の実力なんです」 文化人類学・言語学者 西江雅之氏・眠りのお話 「統計的に八時間眠る人が多いというだけで、生物学的な根拠はないんですよ。一般的に、人間に必要な深い眠りは寝入りばなのノンレム睡眠のときに集中して訪れますから、長く眠ればいいというものでもない。もともと睡眠というのは非常に多様性に富み、個性的なものでしてね」 理学博士 井上昌次郎氏・異文化のお話 「(中身より外見にこだわる・見て見ぬふりができない・年上を敬う・貸し借りをつくってこそ当然・スキンシップ民族・・などなど、韓国とギニアでは共通することが、日本では違うという例がたくさん挙げられたあとで)朝鮮半島まで流れてきたアフリカの文化は、日本まではわたらなかったのか(笑)」 糸井氏 「韓国で講演するとき、私は日本を反面教師にしてほしいと言うんです。家庭内の悲惨な事件が多発する今、日本の悪いところは継承せず、いいところだけ吸収するようにと。日本も、韓国をそういうふうに見ればいいんじゃないですか」 『コリアレポート』編集長 辺真一氏・ゲイのお話 「(自分の中の男と女の両方がわかるという話。で、男のイヤなところ)かたくなで短絡的で単純で、自分の意見を相手に伝えることが最優先で、伝わったかどうかを確認しない傲慢なところ。それから、ものすごくうぬぼれがあって、自尊心が強い。(略)じゃあ女はどうかっていうと、責任という言葉を知らないで生きていて、あなたまかせと言いながら、最終的な決定権は自分がもたないと気がすまない。そして、物差しは自分の中にあって、外にはない」 会社経営 ジョージ氏 ここに出てくる達人たちは、普通ならやり過ごしてしまうことに敏感に反応しているなあと思う。対談を読むことで、36人分の目=物の見方を一挙にもつことができます。満腹、満腹。
2003.02.03
-
子どもと歩けばおもしろい
加藤繁美著・小学館 子育て本を読んでいると最近は「子どもの時代にしっかり甘えさせてやろう。それが子どもの自信になる」というものが多く、一方で「なんでもかんでも子どものいいなりはだめ。子どもが勘違いする」と、その傾向をたしなめる内容のものとがあります。 いったいどっちなんだあ!と、現役子育て真っ最中の親たちは悩んでしまう。(そもそも本を読んでその通りにするっていうのが間違ってるのかもしれないのだけど、いろいろ悩みが出てくるとアドバイスが欲しくなるもの) この本は見た目、その辺の子育て本と変わらないのですが。読んでびっくり。そうした迷いに道筋をつけてくれる貴重な本です。 自分勝手でわがままな振る舞いをしたり、何かできないとパニックを起こす子どもが増えていること。「超わがままタイプ」と「超おりこうさんタイプ」と。前者は「子どもの自主性にまかす」といいながら放置・放任をした場合、後者は子どもの人生のためにという名目で早期教育など過剰に干渉した場合に多い。いずれも「荒れた行動」を起こす子どもたちは、発達段階で自己形成が上手にできないまま来てしまい、「大人たちの価値観と自分の中に育ってきた要求との間で」右往左往しているのだと、著者は指摘しています。 じゃあそれを「しつけの欠如」といってしまっていいのか。地域社会が親とともに子育てに関わっていた時代から、母親の子育ての結果としての子どもというプレッシャーのかかる時代への変化。そして、学校化社会(学校という価値によって人間の幸福までも決定されてしまう社会)に育った今の親たちは、子どもが育つ道筋や大人の関わり方を伝えられずにきたため、学校的価値にしがみついて子育てするしかない。著者はそれら社会の変化事体が子育てを難しくしているといいます。 子どもはどうやって自己形成をしていくのか。本書では子どもの発達段階に応じてその過程を示しています。子どもは1歳半から3歳のころに「第二の自我」が生まれてくる。第二の自我というのは自己主張としての自我に対して「社会に適応する知性としての自我」。この二つの世界を対話させる力が育ってくるのが4歳半をすぎたころ。「こうしたい、でも今はこうしたほうがいい」と、自己決定する力をつけていく過程が「自分づくり」なのだといいます。著者の言い方ではこの自己内対話能力は「一生の財産」。 こうした自己内対話能力がうまく育っていないのが「荒れ」の原因。この時期に親はどう対応すればいいのか。そこで、最初にあげた子どもの要求の受け止め方をどうするかという問題がでてきます。著者は第一の原則として「子どもの自我を受け止めては切り返す。受け止めては意味づける」という関係を根気よく続けていくこと、をあげています。このキャッチボールの心地よさ、大人から返された言葉が子どものなかに「第二の自我」として刻まれていく。「受け止める」と「受け流す」は違う。(受け流すというのは「いやならいいよ。ほしければ買えばいいよ」と子どもの自我に大人が振りまわされる関係)この受け止めるというのがムズカシイ。 子ども中心(受容重視)の大人中心(しつけ重視)のどちらか=厳しくするか甘やかすか、どちらがいいか=といった単純な議論ではない、ということです。私が道筋が見えた、というのはこのところ。そのときそのときの対話を大事にすること。子どもの言い分をしっかり聞き取って共感したうえで、親としての答えを切り返す。子どもの言葉を評価してやる。 こうした日ごろの何気ないやりとりこそが、自分作りの基本になるということに気がついていなかった。驚きと恐ろしさが今更ながらこみあげてきます。 著者は子どもとつきあうのは面白いんだよ、もっと子どもの言葉に耳を傾けようよ、と呼びかけています。だれでも経験する子どものちょっとしたいい間違いや、突拍子もない発想。自分なりに意味づけをしようと「哲学する」子どもたちの言葉。そのオモシロさに気がついて、というのが題名の意味になっているようです。
2003.02.01
-
「考える人」創刊3号
新潮社 伊丹十三特集にひかれて購入。しかし、それだけでなく思いがけない豪華執筆陣で、読み応えのある1冊でした。満足満足。 まずは伊丹十三。エッセイを読んだことはなかったのですが、かなり面白そうなのです。 ちょうど私が生まれたころに「女たちよ!」が刊行されて、かなり当時は話題になったようです。「日常生活に潜む正しい・本物のありかた」をユーモアをまじえてつづる。何より彼は聞き上手・まとめ上手だったらしい。「私自身は無内容な空っぽの入れ物」。。空っぽであるからこそ、人の話、体験したことをなんでも吸収し、新しい視点で「再構成」することができた、ということのようです。たちまち読んでみたくなってネット書店で検索しましたが。。。ほとんど絶版状態になっている模様。なんてこと。 橋本治氏の「いま私たちが考えるべきこと」と次の茂木健一郎氏「仮想の系譜」は、いずれも「自分と他人=他者」について考えさせられる内容。 橋本氏は「自分のことを考える」ことが「他人のことを考える」につながる人と「自分のことを考える」になる人がいることを指摘しています。前者は前近代的な人、後者は近代的な人。ひとりひとりが人権をもつ近代になってはじめて、他人と自分という自覚が生まれ「他の人はどう考えるだろう」と思うことができる。しかし前近代では自分=主権をもたないその他大勢の他者なので、他者は存在しない。といった内容をいつものまわりくどい説明で語っていく。いったい結論がどこへ落ち着くのか、続きを読まないとわかりそうにないのですが、端々にちりばめられた「自分」と「他人」についての考察が、頭にひっかかっる。 茂木氏のほうはもっと明確。今回の題が「断絶の向こうの他者の心」。他者の心をわかることは絶対に不可能だ、というのが結論なのです。人は他人の心を言葉などのコミュニケーションを通して、わかろうとする努力をするのだけれど、そこで「あいつのことがわかった」と思った瞬間に他者との断絶ができてしまう。レベルを貼って、安心してしまう。のだけれど、安易に人の心を「わかった」と思ってはいけない、「わからないものなのだ」ということを真摯に受け止めて、わかろうとする気持ちを持ち続けることこそが、個人が断絶された世界においては大事なのだ。 私たちは子どものこと、つれあいのこと、友達のこと、わかったつもりにはってはいないだろうか。わかったつもりになって、見えなくなってはいないか。人とのかかわりのなかで、常に自分に問いかけたいテーマのような気がします。 他にも9・11後について語られているのが梨木香歩さんの連載と、池澤夏樹氏とギリシャの映画監督テオ・アンゲロプロス氏の対談。 梨木さんは生垣というゆるやかな境界の豊かさを語り、それがイギリスで徐々に減って有刺鉄線のようなクリアな境界になってしまっている例をあげます。シンプルになってかえって行き詰ることもある。白黒つけたいという欲求(フセインは悪だとか)はあるのだろうが、性急にクリアにすることは危険性を伴う。「加速度的」に世界が進んでいくことに疑問符をつけています。 池澤氏の対談では監督のこれまでの映画について、「国境」がテーマになっていることを語り合っています。国境というのはあとでつけられたもので、会話が可能であれば「宗教も肌の色も人種もなにも人と人の間に立ちはだかることをやめる」。 表現者として言っておかなければならないことがある、という切実なものが感じられる、読む方も思わず「考える人」にさせられる一冊、でした。
2003.01.29
-
『読み・書き・計算』で学力再生
陰山英男著・小学館 兵庫県の朝来町にある山口小。ここが教育関係者のなかでは話題になって久しい(らしい)。2000年の秋にNHKの「クローズアップ現代」で取り上げられたこの学校の実践。読み書き計算を徹底して反復学習することで、子どもたちに基礎学力と集中力、できるという自信がつく。その自信がもとになって、全体的な学力のアップに成功した、その実践を中心になって進めてきたのが著者の陰山先生なのです。 名前だけは聞いていて遅ればせながら本を読んだのですが、つい先日の金曜日、広島県の尾道にある小学校の校長として赴任することになったとニュースで知ってびっくり。先生のHPの掲示板には励ましと、惜しむ声とがぞくぞくと寄せられていて、彼の影響力のすごさを知りました。この小学校、陰山先生のもとで働きたいという先生を集め、山口小で行われてきた陰山メソッドを本格的にやっていくらしい。公立小で! そんな時代になったんですねえ。 反復練習。「読み」は、音読・暗誦学習。丸暗記の得意な子どもの時期に、記憶力をつけると自信につながる。「書き」では新出漢字を教科書の進行とは別にさっさと学習して復習の時間をとる。熟語での連想学習が効果的。「計算」は百ます計算というユニークな方法で、加減乗除をひたすら繰り返す。時間を計ってゲーム感覚で行うと、集中力がつき計算も速くなる。 こうした取り組みはいわゆる詰め込み教育とは違うものだと陰山先生は主張しています。授業の最初5~10分ほどのドリル練習、それだけで実際の授業の進行が逆にスムーズになるといいます。準備体操のようなものでしょうか。 山口小の取り組みが成功した条件として、学級の枠を取り払って学校ぐるみの6年間一貫指導で行われたこと、保護者の理解もあり、子どもたちの生活習慣のリズム(ご飯の朝食をとる。夜早く寝る。テレビの時間を減らす)がきちっとしていたこと、などがあるようです。 学級の枠を取り払う例として面白いのが「お話しを聞く会」。全教師が読み聞かせの本をえらび、子どもたちはどの先生が読むか知らないまま本の題名だけでどれを聞くかえらぶ。担任以外の先生や違う学年の子どもたちとふれあうチャンスにもなっているそうです。これって、すぐにでも実践できそうな楽しい授業! 生活習慣がきちんとしてこそ、というのは今の時代に一番大切なことのような気がします。夜遅くまでおきていて朝食も食べない子が、学校で元気に活動できるわけがない、でしょう。 ゆとりとか総合学習とか、目的自体は間違っていないけれど、基礎ができてないままに行ったせいで学力低下・キレる子どもたちという結果が生じている。いまになって見直されつつある基礎的な能力。それは訓練してつけるしかない。勉強を一生懸命することを否定的にいう風潮がありますが、「子どもは勉強したがっている。もっと伸びたがっている」のですね。 計算とか、漢字を覚えるとか、最初の段階でつまづくと自分はダメなんだと思ってしまう。それはとても不幸なことで、だれだってやればできるし、楽しくできる方法があるよ、というのが陰山メソッドなのでしょう。
2003.01.25
-
トゥインクル・ボーイ
乃南アサ著・新潮文庫 空恐ろしさ。世の中で一番怖いのは人の感情なのだと、あらためて思い知らされました。 子どもたちの犯罪を扱った短編が7つ。犯罪であるはずの彼らの行為を、子どもたち自身が悪いことだと思ってはいない。彼等なりの論理、必然性があってごく普通に行われる。。だから怖い。 大人を喜ばせるために他人の馬券を盗む少年。彼は天使のような笑い顔で大人はなんでも許してくれると思っている。あるいは友達の家族の一員になりたくて友達を殺す少年。「機械に寿命がくればそっくり取り替えたらいい」と聞いて、自分と友達を取り替えてもいいと思ってしまう。父親のようになるなといわれ母親から早期教育を受けさせられてきた少年は、自分のタマシイは母親が盗んだんだと信じて、タマシイを取り返そうとする。 それがいい悪いじゃなくって、人と人とのかかわりが必然的に犯罪という結果に結びついていく。これらのどの話も、絵空事でなくすぐ身近にも起こりうると感じさせられます。いまの家族や社会そのもの、その一部を切り取って見せられているような。 子どもというのはこんなに憎らしい面があるんだってことではないようです。彼らも一人の人間として判断しながら動いている。自分の身を守るため、生きていくために考え、行動している。そんな子どもたちの置かれた環境が、親やそのほかの大人たちからの虐待とか放置といった状況になったとき、道徳的に間違った方へ進んでしまうに過ぎない。そうせざるを得なかった彼らの環境こそ、罪なのだと思います。 「子どもは天使などではない。大人以上に優しくもなく、人間臭さを丸出しにしてぶつかってくる。親の個性をそのままに映し出して、嘘偽りのない悪の姿を見せ付けるのだ」 ドキリとさせられる言葉。この著者の人間を見る目の確かさというものに圧倒されました。
2003.01.22
-
絶対音感
最相葉月著・小学館文庫 数年前のベストセラー。文庫化されてようやく手にとりました。音楽に関心があるひとなら知っているという「絶対音感」という言葉も、私は知らないでいて、この本が話題になったとき特別な才能=自分には縁のない話という印象がありました。 ところがこの絶対音感を身に着けている人が、日本人に多いという事実があり、諸外国を驚かせているという。著者は音楽家たちへのアンケートや丹念な取材を通じ、その理由を追い求めていきます。 日本で絶対音感が広まったその最初には、西洋の音楽事情に感銘を受けて日本人もその基礎が身に着いていれば音楽が楽しめるのではないか、と考えたある人物の思いがあったこと。それはピアニスト園田高弘氏の父であり、園田氏が実験台となって絶対音感を身に着けるための教育を受ける。そのメソッドが共感した人々によって広まり、今ではヤマハなどの巨大音楽産業によって一般に普及したという歴史が私たちの前にひもとかれます。 つまり訓練しだいでだれでも持つことが出来る。 ところが著者はその弊害というものを示して見せます。絶対音感や音楽のテクニックがいかに向上しても、人の心を動かす音楽にはならない。日本人の欠点。絶対音感をもつことで音が少しでも狂うと気分が悪くなったり、音の変調についていけなかったり、歌の意味が心に入ってこなかったり。著者は「持っていれば便利。時にはやっかい」という言葉で示している通り。 素人からすれば、音を聞くとたちまちピアノを弾いて再現できるとか聞くとうらやましい。でも両刃の刃なんですね。絶対音感というのはピアノの平均律でのはなし。民族音楽とかピアノ以前の楽器になると通用しない。そうなのだ。私たちが使っているドレミだってある時代に決められた音階にすぎない。オーケストラによって、また時代によって、基準となる音の周波数も変わっているというのだから。実は「絶対」というものはないのかもしれない。 多くの音楽家の話から、結局「相対音感」というものを磨かないと、豊かな表現はできないということがわかってくる。本当にすぐれた音楽家たちは絶対音感を持った上で、それを克服する努力をしているというのです。 単に将来便利だろうからと音楽教室で絶対音感を身につけさせ、それが終わればもう用なしといったふうに教室をやめさせる親が多いという。その先が大事なのに。 この本の最後は絶対音感教育を受けた天才バイオリニストの五嶋みどりとその母、節さんの物語でしめられています。節さんはその教育について批判され、つらい思いをしたり、娘に対してすまない気持ちなどもあったらしい。でも彼女は最後まで自分が引き受けた。教える立場として耳を肥やし、方法を試行錯誤し、必要とあらば娘とともに海外へ渡った。その貫徹ぶりは誰にも批判できないことだと思います。 最初にその教育をはじめた園田氏がわが子へ贈った「絶対音感」。そして五嶋節さんも。著者は「絶対音感」とは物心がつく前に親や環境から与えられた、他者の意志の刻印だと表現しています。そこに親としての思いがあるからこそ、子供たちは受け入れ、悩みながら克服し、音楽家として成功したのでしょう。 とにかくこの本。小さいころピアノを習っていたくせに音楽を知らない私には、とても勉強になる面白い本でした。 音の世界というものを脳科学の分野からも説明しています。生まれたときにはあらゆる音を聞き取る能力を持っていた私たち。音に対する敏感さを失う中で聞き取れない音が増えていく。耳の力をもっと大事に。さしずめわが子にしてやれるのは、こういうことでしょうか。
2003.01.19
全177件 (177件中 1-50件目)