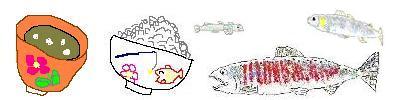魚魚じゃーなる

あゆ
料理
2001年に郡上のとある谷川で撮影しました。
バツグンの透明度で、少々の曇り空でも明るく撮影できた。
2005年に比べると、個体数が多い。
この頃も少ない少ないとボヤいていたが、年々川状況は悪くなっているという事である。
バツグンの透明度で、少々の曇り空でも明るく撮影できた。
2005年に比べると、個体数が多い。
この頃も少ない少ないとボヤいていたが、年々川状況は悪くなっているという事である。
塩焼きは言うに及ばず、他によくやるのは鮎メシ。
昆布だしと醤油のみの味付け。
鮎は塩焼きにしてから小骨を取り、ワタもいっしょに炊くと大変うまい。
できることであれば、炭で焼く事をおすすめします。
昆布だしと醤油のみの味付け。
鮎は塩焼きにしてから小骨を取り、ワタもいっしょに炊くと大変うまい。
できることであれば、炭で焼く事をおすすめします。
5月、橋の上から覗き込むと集団で動く物体が遡上中の鮎である。
産卵の時期が来るまで、遡上先のコケ(川底の石に着く藻類)をたべて成長する。食糧(コケ)確保のために縄張りをつくり、侵入者には攻撃的。この習性を利用したのが、おとりを使った友釣りです。
9月中ごろ産卵のため集団で川を下る。
産卵の時期が来るまで、遡上先のコケ(川底の石に着く藻類)をたべて成長する。食糧(コケ)確保のために縄張りをつくり、侵入者には攻撃的。この習性を利用したのが、おとりを使った友釣りです。
9月中ごろ産卵のため集団で川を下る。


ちちこ
料理
ヨシノボリと呼ばれていると思います。
ちちこは地方名の一つで、他にゴト、セゴトなどと呼んでいます。ものの本によれば、淡水ハゼを代表する種とか(難しいことはよくわからん)。
ちちこの種類もたくさんあるらしいが、実際潜って見ていると川底の石の色で体の色が違う。石にコケが着いているときは黄色っぽいし、増水後のコケが取れた後では白っぽい色。
他の多くの魚もそうですが、涼しくなった10月とかになると何処へ行ったのやら・・というほど見かけなくなります。
ちちこは地方名の一つで、他にゴト、セゴトなどと呼んでいます。ものの本によれば、淡水ハゼを代表する種とか(難しいことはよくわからん)。
ちちこの種類もたくさんあるらしいが、実際潜って見ていると川底の石の色で体の色が違う。石にコケが着いているときは黄色っぽいし、増水後のコケが取れた後では白っぽい色。
他の多くの魚もそうですが、涼しくなった10月とかになると何処へ行ったのやら・・というほど見かけなくなります。
なんといっても佃煮。
これはうまいです。
あと、から揚げもびっくりするほどうまい。
あまいんだよね~
キャンプなどの時は子供にたのむとヨロコンデ採りに行くので、うまい料理がたべれます。
これはうまいです。
あと、から揚げもびっくりするほどうまい。
あまいんだよね~
キャンプなどの時は子供にたのむとヨロコンデ採りに行くので、うまい料理がたべれます。
直径10センチほどのタモで、伏せて採ります。
あと、秘技として30センチぐらいの小枝に釣り糸と針をつけてこの子の口のまえにたらしてやるとどういう訳か食いつきます。
あと、秘技として30センチぐらいの小枝に釣り糸と針をつけてこの子の口のまえにたらしてやるとどういう訳か食いつきます。


あじめ
料理
ドジョウです。
この地方ではキンカンドジョウともいわれています。
チチコ採りをしていると必ずいっしょに採ったりしています。
これを採る漁方があり、このあたりの川では良くやっています。
登り落ち漁という漁方があります。
かなりの量がいっぺんで採れるけど、保護のために1年おきの解禁です。
これを川の中で見かけるとほっとします。
この地方ではキンカンドジョウともいわれています。
チチコ採りをしていると必ずいっしょに採ったりしています。
これを採る漁方があり、このあたりの川では良くやっています。
登り落ち漁という漁方があります。
かなりの量がいっぺんで採れるけど、保護のために1年おきの解禁です。
これを川の中で見かけるとほっとします。
佃煮、から揚げをよくやります。
特にから揚げは絶品。
あまいです。
佃煮も良い。
特にから揚げは絶品。
あまいです。
佃煮も良い。
川底の小石の間から出てくるところをみると、ちちこ同様生活になくてはならない環境だと思う。
近頃は、河川改修工事やダム工事の土砂が川に良く流れ込む。
それらの土砂が彼らのすみかを埋めてしまい、次の年そこに潜るとだ~れもいなくなっている事が多くなった。
近頃は、河川改修工事やダム工事の土砂が川に良く流れ込む。
それらの土砂が彼らのすみかを埋めてしまい、次の年そこに潜るとだ~れもいなくなっている事が多くなった。


あまご
料理
ヤマメに似ていますが、体側に朱色の点々があります。
この魚はほんとうに綺麗。
薄墨色の斑点に朱色の点々、水中で出会うとおもわず見とれてしまいます。
1から2年で成長して産卵します。後出のさつきますの産卵時にも参加しています。
この魚はほんとうに綺麗。
薄墨色の斑点に朱色の点々、水中で出会うとおもわず見とれてしまいます。
1から2年で成長して産卵します。後出のさつきますの産卵時にも参加しています。
旬の頃は4月~5月。
夏は鮎。春はあまご。五月あまごに鮎勝てぬ・・
うまい魚です。
塩焼きは絶品です。
夏、釣りに出かけるとシマとよばれる5センチぐらいの幼魚が釣れます。これは甘露煮にするとバツグンです。
釣り貯めておいて正月のおせちとして甘露煮にしてます。
夏は鮎。春はあまご。五月あまごに鮎勝てぬ・・
うまい魚です。
塩焼きは絶品です。
夏、釣りに出かけるとシマとよばれる5センチぐらいの幼魚が釣れます。これは甘露煮にするとバツグンです。
釣り貯めておいて正月のおせちとして甘露煮にしてます。
ミミズを使ったエサ釣りです。
他にもエサとしては旬の瀬虫(すし屋みたい)、反則技でバッタなどがあり、外道としてイクラがあります。
ミミズは実家の畑などで捕まえて行きますが、釣具屋にちゃんとしたパッケージの物も売っており、飼育販売している人が居る模様(商売として成り立っているのがすごい)。
瀬虫は現場で石をひっくりかえして採取します。
イクラは泳いでいるサケを・・冗談です・・(><)
他にもエサとしては旬の瀬虫(すし屋みたい)、反則技でバッタなどがあり、外道としてイクラがあります。
ミミズは実家の畑などで捕まえて行きますが、釣具屋にちゃんとしたパッケージの物も売っており、飼育販売している人が居る模様(商売として成り立っているのがすごい)。
瀬虫は現場で石をひっくりかえして採取します。
イクラは泳いでいるサケを・・冗談です・・(><)


かわます
料理
サツキマスといわれています。
こう呼ぶようになったのは割りと最近の様で、それまではカワマス・ホンマス・ただ単にマスとか呼んでいたそうです。
僕もこんな魚がこの川にいると知ったのは、河口堰の問題で長良川が注目されていた頃でした。
その後、天野礼子さん著「萬サと長良川」を読んでいよいよ見てみたいと強く思うようなり、あまごを釣りはじめました。
こう呼ぶようになったのは割りと最近の様で、それまではカワマス・ホンマス・ただ単にマスとか呼んでいたそうです。
僕もこんな魚がこの川にいると知ったのは、河口堰の問題で長良川が注目されていた頃でした。
その後、天野礼子さん著「萬サと長良川」を読んでいよいよ見てみたいと強く思うようなり、あまごを釣りはじめました。
2005年5月。岐阜市の長良川で友人が釣り上げる。
すぐその場で3枚におろして塩焼きを食べた。
身はピンク色。脂がのっていてうまかった。
鮭より野生的な味です。
すぐその場で3枚におろして塩焼きを食べた。
身はピンク色。脂がのっていてうまかった。
鮭より野生的な味です。
アマゴの降海型といわれています。
春、伊勢湾辺りから遡上を始め、10~11月に上流で産卵。
この産卵にはアマゴのオスも加わります。
1ヵ月半ぐらいで孵る。
孵ってくる子がもともとサツキマスなのかアマゴなのかは不明。
シラメと呼ばれるパーマークの目立たないアマゴみたいなのも居る。
この写真を撮れたのは奇跡的。
川を見に出掛けたら偶然出会いました。
いずれにしても産卵場所となる”小石が川底にふんだんにあり、そこから湧き水がでている”場所は少ないと思われる。
ダム工事・河川工事や荒廃した山・それらから流入する土砂で、川底は埋まり、産卵し卵が生き残れる場所は少なくなっている。
春、伊勢湾辺りから遡上を始め、10~11月に上流で産卵。
この産卵にはアマゴのオスも加わります。
1ヵ月半ぐらいで孵る。
孵ってくる子がもともとサツキマスなのかアマゴなのかは不明。
シラメと呼ばれるパーマークの目立たないアマゴみたいなのも居る。
この写真を撮れたのは奇跡的。
川を見に出掛けたら偶然出会いました。
いずれにしても産卵場所となる”小石が川底にふんだんにあり、そこから湧き水がでている”場所は少ないと思われる。
ダム工事・河川工事や荒廃した山・それらから流入する土砂で、川底は埋まり、産卵し卵が生き残れる場所は少なくなっている。


おいかわ
料理
きれいでしょ~
こちらは婚姻色のでた雄。雌はじみ~です。
産卵時期は夏。
子供の頃の釣りには欠かせないお魚ですが、
雄が掛かると気持ち悪がって捨てていました。
こちらは婚姻色のでた雄。雌はじみ~です。
産卵時期は夏。
子供の頃の釣りには欠かせないお魚ですが、
雄が掛かると気持ち悪がって捨てていました。
いわゆる雑魚ですが、フライにするとおいしい。
カガシラで釣ってきて夕飯のおかず。
な~んていうのは子供の頃よくありました。
家の経済状況がよくなかったのかな~ 今考えると・・。
でも今は食べなくなった。。
おいしい魚を獲れるようになった事もあるけど、ゼータクになったんだなー。
カガシラで釣ってきて夕飯のおかず。
な~んていうのは子供の頃よくありました。
家の経済状況がよくなかったのかな~ 今考えると・・。
でも今は食べなくなった。。
おいしい魚を獲れるようになった事もあるけど、ゼータクになったんだなー。
最近は潜ってもあまり見かけなくなりました。
後で出てくるウグイはよくいますが。。。
後で出てくるウグイはよくいますが。。。


しらはえ
料理
おいかわの雌。
自然界では雄がハデ~なのありますね。
しらはえの『はえ』って『早い』が語源みたい。
『白くて早い魚』ってなところでしょうか。
もちろん名付け親はそこら辺のガキだったのでしょう。
たぶん、早くて捕まえれないから「あいつはえ~(早い)な~ チキショウ!」なんて言っているうちに しらはえ って呼ぶようになんたんでは?
素人考えですけど・・。
自然界では雄がハデ~なのありますね。
しらはえの『はえ』って『早い』が語源みたい。
『白くて早い魚』ってなところでしょうか。
もちろん名付け親はそこら辺のガキだったのでしょう。
たぶん、早くて捕まえれないから「あいつはえ~(早い)な~ チキショウ!」なんて言っているうちに しらはえ って呼ぶようになんたんでは?
素人考えですけど・・。
フライ。
甘露煮。
甘露煮。
後で紹介する「むつばえ」といるところがビミョ~に違う。
「しらはえ」は割りと浅い所。「むつばえ」は淵。
大雑把ですがそんな感じで良く見ます。
食べるものが似ているから一緒には住みづらいのか?
本人たちに聞いてみたい所だけど・・
「しらはえ」は割りと浅い所。「むつばえ」は淵。
大雑把ですがそんな感じで良く見ます。
食べるものが似ているから一緒には住みづらいのか?
本人たちに聞いてみたい所だけど・・


むつばえ
料理
図鑑等では、かわむつと呼ばれています。
最近この魚は多いですな。
この辺りでは、かわむつ・しらはえ(おいかわ)・いぐいがいわゆる雑魚。
子供の頃の釣りでは、あまり釣った覚えがない。
ただ単に覚えていないだけかも知れないけど。。
しらはえの方が覚えてるな~
写真は、獣か何かの肉片か?
潜った淵に浮遊していて魚が集まっていた。
最近この魚は多いですな。
この辺りでは、かわむつ・しらはえ(おいかわ)・いぐいがいわゆる雑魚。
子供の頃の釣りでは、あまり釣った覚えがない。
ただ単に覚えていないだけかも知れないけど。。
しらはえの方が覚えてるな~
写真は、獣か何かの肉片か?
潜った淵に浮遊していて魚が集まっていた。
この魚は~料理したのかな~
多分、子供の頃釣って母親が煮魚作るときに他の魚と一緒に料理していたと思うんだけど・・
今度会ったとき聞いてみます。
多分、子供の頃釣って母親が煮魚作るときに他の魚と一緒に料理していたと思うんだけど・・
今度会ったとき聞いてみます。
産卵は4~8月。
雄の腹が赤くなり、背びれ胸びれが橙になる。
口の辺りに「追星」といわれる、ブツブツができる。
雄の腹が赤くなり、背びれ胸びれが橙になる。
口の辺りに「追星」といわれる、ブツブツができる。


かぶ
料理
カジカですな。
かぶはここら辺の呼び方。
野菜のカブみたい? なのでこう呼ばれているらしいけど・・
この魚、4・5年前の某川にはほんと呆れるほどいた。
この写真は夜潜って撮影したけど、川底の石ころみたいに辺り一面という感じていたので、とても楽して写真が撮れた。
かぶはここら辺の呼び方。
野菜のカブみたい? なのでこう呼ばれているらしいけど・・
この魚、4・5年前の某川にはほんと呆れるほどいた。
この写真は夜潜って撮影したけど、川底の石ころみたいに辺り一面という感じていたので、とても楽して写真が撮れた。
塩焼きが一番。
白身でうまい。
白身でうまい。
その後、某川はダム工事がその上流で本格的になった。
小砂利が川底一面に敷き詰められたとても美しい早瀬。
おそらくその石のすき間などが、彼らや他の魚の住処・隠れ家だったと思う。
この写真を撮った翌年の夏、泳ぎに出掛けたら川が土砂で埋まっていた。
小砂利が川底一面に敷き詰められたとても美しい早瀬。
おそらくその石のすき間などが、彼らや他の魚の住処・隠れ家だったと思う。
この写真を撮った翌年の夏、泳ぎに出掛けたら川が土砂で埋まっていた。


くろざす
料理
ものの本によれば、ギギということになるのですが、ここいらでは「くろざす」と呼ばれています。
本来はクロザス=ネコギギらしいのですが、良く似ているためこう呼ばれているのか? と思います。
漁師さんの網に掛かっていました。
ナマズの仲間とかで、大変美味いそうです。
本来はクロザス=ネコギギらしいのですが、良く似ているためこう呼ばれているのか? と思います。
漁師さんの網に掛かっていました。
ナマズの仲間とかで、大変美味いそうです。
食べた事ありませんので・・。
山を一つ越えた川で、むか~し鯉釣りをしました。
その時良くこの魚がかかりました。
針を外そうとして触ると、チク~ 良く刺されました。
「ざす」というのは「刺す」の事か。
で、黒っぽいので「くろ」
山を一つ越えた川で、むか~し鯉釣りをしました。
その時良くこの魚がかかりました。
針を外そうとして触ると、チク~ 良く刺されました。
「ざす」というのは「刺す」の事か。
で、黒っぽいので「くろ」
これを始めてみた時は、おどろきました。
この形、奇妙ですよね~
サメか? と思った。(小学生の頃だった)
川にサメなんかいるわけないんだけど・・
この形、奇妙ですよね~
サメか? と思った。(小学生の頃だった)
川にサメなんかいるわけないんだけど・・


あかざす
料理
標準和名・こういうらしい・はアカザ。
これはカワイイで~。
やはりナマズの仲間なので、夜行性が強いらしいが、
昼間、イカリで大暴れすると、びっくりしてウロウロしているのを良く見ます。
そういう時はカメラなど持って居ないから、あ~あ~ とシュノーケルに向かってさけんだりしてます。
日本固有種。
これはカワイイで~。
やはりナマズの仲間なので、夜行性が強いらしいが、
昼間、イカリで大暴れすると、びっくりしてウロウロしているのを良く見ます。
そういう時はカメラなど持って居ないから、あ~あ~ とシュノーケルに向かってさけんだりしてます。
日本固有種。
食べた事ないのでなんとも言えませんが、
聞いた話によると、甘露煮にするといいらしい。。
聞いた話によると、甘露煮にするといいらしい。。
良く見かけるのは7,8cm位のが多い。
これも、あかざすと言うくらいだから刺します。
痛いです。
この写真は夜。
いたいたと近づいたら石の下に隠れようとしたのか?
でも、思ったよりすき間が無く、顔だけコンニチハしてます。
これも、あかざすと言うくらいだから刺します。
痛いです。
この写真は夜。
いたいたと近づいたら石の下に隠れようとしたのか?
でも、思ったよりすき間が無く、顔だけコンニチハしてます。


だえんぼ
料理
カマツカと言われているお魚です。
鎌の柄ということでカマツカらしいですが、ここら辺の、だえんぼ、の言われは良く分かりません。
砂のある川底にいます。砂を吸って、エラから吐きます。その時砂の中のエサを食べます。
何処で潜っても比較的良く見ます。
鯉の仲間。
鎌の柄ということでカマツカらしいですが、ここら辺の、だえんぼ、の言われは良く分かりません。
砂のある川底にいます。砂を吸って、エラから吐きます。その時砂の中のエサを食べます。
何処で潜っても比較的良く見ます。
鯉の仲間。
塩焼き。
淡白でうまい。
大きいもので10センチぐらい。
身が多いので食べでがある。
淡白でうまい。
大きいもので10センチぐらい。
身が多いので食べでがある。
今頃潜ると、川の中は鯉とカマツカが幅を利かせてるんじゃないかな~
鮎は行ってしまったし、あまごは産卵でいそがしい。
ほかの魚たちも、草陰でおとなしくしてるし。
鮎は行ってしまったし、あまごは産卵でいそがしい。
ほかの魚たちも、草陰でおとなしくしてるし。


くそんぼ
料理
他にドロバエとも呼びます。
同じような地域でも別の呼び方をすることはよくあります。
呼び名の意味合いに、微妙な共通点があるのは興味深いところです。
標準和名はアブラハヤです。
子供の頃の釣りでは、良く釣れた魚のひとつです。
他にウグイ・シラハエも同じく良く釣りました。
同じような地域でも別の呼び方をすることはよくあります。
呼び名の意味合いに、微妙な共通点があるのは興味深いところです。
標準和名はアブラハヤです。
子供の頃の釣りでは、良く釣れた魚のひとつです。
他にウグイ・シラハエも同じく良く釣りました。
獲物は持って帰り、その晩のおかずとなって出てきました。
甘露煮が多かったようにおぼえています。
今は贅沢になってしまい、ぜんぜん食べませんが、その頃はちゃんとおかずとして歓迎されてました。
甘露煮が多かったようにおぼえています。
今は贅沢になってしまい、ぜんぜん食べませんが、その頃はちゃんとおかずとして歓迎されてました。
写真は2,3年前。
ガラス瓶に練り餌を入れ、一晩川に沈めておきました。
クソンボの他には、ウグイ・シラハエ・ムツバエがいました。
ガラス瓶は一般に、セルビンとも呼ばれているとおもいます。
ガラス瓶に練り餌を入れ、一晩川に沈めておきました。
クソンボの他には、ウグイ・シラハエ・ムツバエがいました。
ガラス瓶は一般に、セルビンとも呼ばれているとおもいます。


いぐい
料理
標準和名はうぐい。
これも子供の頃良く釣った。
雑食で何でも食べる。
ミミズやソーセージがエサでした。
春が産卵時期。この頃釣れると、腹の辺りが橙。
これも子供の頃良く釣った。
雑食で何でも食べる。
ミミズやソーセージがエサでした。
春が産卵時期。この頃釣れると、腹の辺りが橙。
ある所では田楽などの料理もあるとか。
しかしこの辺りは甘露煮。
しかしこの辺りは甘露煮。
潜れば必ずいます。
なれないとイカリで鮎と間違えてこの魚を掛ける人もいます。
20センチぐらいのだと分からないらしい。
なれないとイカリで鮎と間違えてこの魚を掛ける人もいます。
20センチぐらいのだと分からないらしい。


はざこ
料理
すんませ~ん m(__)m
暗くて良く分かりませ~ん。。が!
よくよく見てください。
小豆色の物体が・・
でもしっぽしか写せませんでしたぁ 重ね重ねm(__)m
サンショウウオです。
これは小さめで、50センチぐらいか?
暗くて良く分かりませ~ん。。が!
よくよく見てください。
小豆色の物体が・・
でもしっぽしか写せませんでしたぁ 重ね重ねm(__)m
サンショウウオです。
これは小さめで、50センチぐらいか?
・・・。
いろいろと地元では言われております。
曰く。
歯が一枚刃でなんでも噛み切るから怒らせると指たべられちゃうぞ! とか、さわるとかぶれるとか、頭からぴゅ~ と不思議な液体を出すとか・・。
はざこにとってはメーワクな話です。
普段はあまり縁の無い生き物なので、そういう伝説(?)があるのだろう。
しょっちゅう潜って見かけるけど、これと出会うとやっぱドキッとするな~
曰く。
歯が一枚刃でなんでも噛み切るから怒らせると指たべられちゃうぞ! とか、さわるとかぶれるとか、頭からぴゅ~ と不思議な液体を出すとか・・。
はざこにとってはメーワクな話です。
普段はあまり縁の無い生き物なので、そういう伝説(?)があるのだろう。
しょっちゅう潜って見かけるけど、これと出会うとやっぱドキッとするな~
この商品説明はオークション プレート メーカーで作成しました
~ http://auction.gn.to/ ~
魚 魚 じ ゃ ー な る 。
ひ と ま ず 今 年 の 分 は 、 こ れ に て 一 件 落 着 ぅ ~
と な り ま し て 、 残 す と こ ろ の 恋 、 も と い 鯉 と ウ ナ ギ は
越 冬 準 備 と い う こ と も あ り 、
来 年 の お た の し み と 相 成 り ま し た 。 。
楽 し み に し て た 人 い る ~ ? い な い か 。 。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 株式投資日記
- 今日も株式資産は減少したが、それで…
- (2025-11-19 17:03:00)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 〈急増するクマ被害〉「腹破らんでく…
- (2025-11-19 17:00:04)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 2025 Xmas★ウェッジウッド アドベン…
- (2025-11-19 11:35:32)
-
© Rakuten Group, Inc.