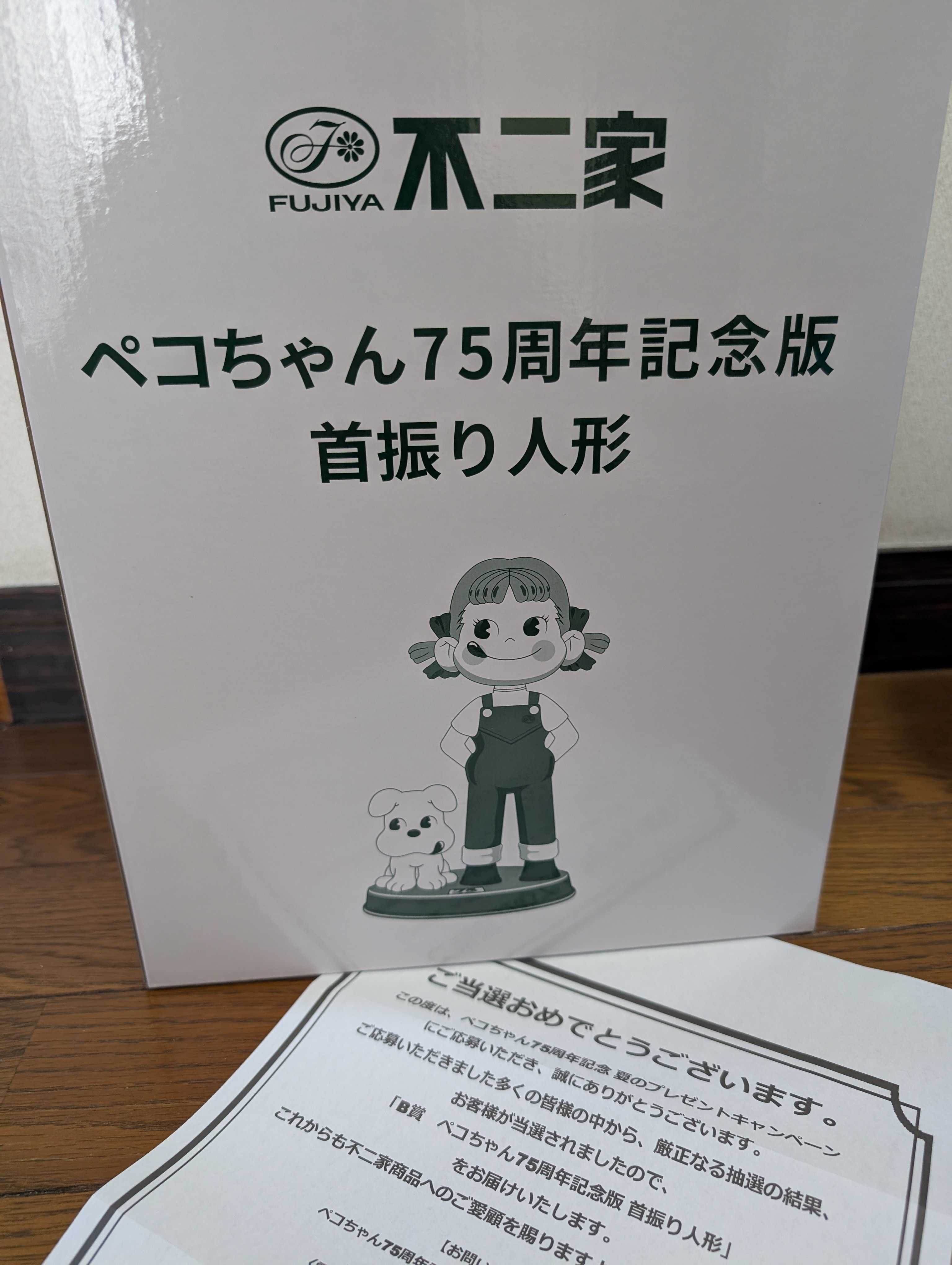・西洋理容 “BARBER(バーバー)”
語源はラテン語のBARBA(髭(ひげ))からきています。
BARBER(バーバー)とは、外科医を兼ねた理髪師の事で、当時のヨーロッパの教会の僧侶は大昔の使徒にあやかって顎鬚(あごひげ)をボウボウと生やしていました。しかし余りのも見苦しいので、1092年ローマ法王が「僧侶は髭を綺麗に剃ること」と法令を出し、その結果、僧侶や教会で理髪師を雇って髭を剃りました。また、当時の僧院では僧侶に医者を兼ねた人が多く、彼らは外科の手術もやっていました。しかし、1163年「教会は流血を忌む」という趣旨の法令が出て、外科手術を教会外で医学僧侶から教えを受けた理髪師が行うようになりました。
それ以降は、理髪師の親方が弟子に伝え、オデキの膿(うみ)の切開、脱臼、骨折治療、手足の切断、抜歯、蛭を用いた高血圧治療等を行いました。もちろん大学で教育を受けた医者もいましたが、それは僅かで彼らは「長服の外科医」と呼ばれ、理髪師は「短服の外科医」として区別されていました。
その後、「長服の外科医」が増え、理髪師は散髪だけやるようになりました。
サインポールを創案したメヤーナキールは「長服の外科医」で「短服の外科医」にも広まったサインポールは理髪師の看板として残り、青色を加えて現在でも理容店の看板として使用されています。
© Rakuten Group, Inc.