・日本の理美容は髪結いの「床屋」から
開祖・藤原采女之亮(ふじわらうねめのすけ)
壇ノ浦で平家が滅亡した約80年後の鎌倉時代の中期、京都に藤原基晴という武士がいました。基晴は京都御所の宝物殿の最高責任者として当時の亀山天皇 に仕えてきました。ところがある日、唐から送られた宝刀「力王丸」(「九竜丸」という説も)が紛失してしまい、基晴はその責任をとって辞職、三男の藤原采女之亮を連れて宝刀を探すたびに出て、長門の国(下関)へとやってきました。当時、長門の国には各地から続々と武士が集待ってきていました。蒙古襲来に備え、沿岸を固めなければならなかったのです。基晴は、戦勝祈願のシンボルでもある宝刀は、これから戦の始まろうとしている長門の国近辺に持ち込まれているに違いないとにら んだのです。基晴・采女之亮親子は宝刀を探すかたわら、当時下関で髪結いをしていた新羅人からそのからその技術を学びました。当時の髪結いは呼ばれた家へ出向いて行くというかたちで、髪を結っていたのは裕福な人がほとんどでしたが、技術を学んだ基晴親子は武士を客とした髪結所を唐戸に開き生計を立てながら宝刀探しを続けました。これが床屋の始まりです。やがて基晴は死去し、采女之亮は床屋を続けながら宝刀を探し続けました。そしてついに宝刀を探しだし、天皇に奉還することできたのです。その後采女之亮は鎌倉に移り住み、幕府から京都風の髪を結う髪結職として重用され、藤原家は代々その職を受け継いでいきました。こうして藤原采女之亮は「理容の開祖」と言われるようになったのです。

理髪開祖・藤原采女之亮霊神
子孫は髪結を業とし、17代目の北小路藤七郎は元亀3年(1572年)、三方原の戦いにおいて、武田信玄相手に敗退中の徳川家康の軍勢を天竜川渡河の道案内をし、無事対岸に着岸した。その勲功に笄(こうがい)(別説、脇差ともある)と銀銭壱銭を賜り、以後壱銭職と称えるようになりました。その後、江戸開府とともに召出され「御用髪結」をつとめ、21代幸次郎のとき江戸髪結株仲間(組合)を申請し、これを享保12年(1727年)江戸町奉行大岡忠相に差出した、とあります。「壱銭職由緒書」の果たした役割は江戸時代の髪結職仲間が結成されるようになり仲間の団結と業組を尊ぶ精神を伝承したものと思われる。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
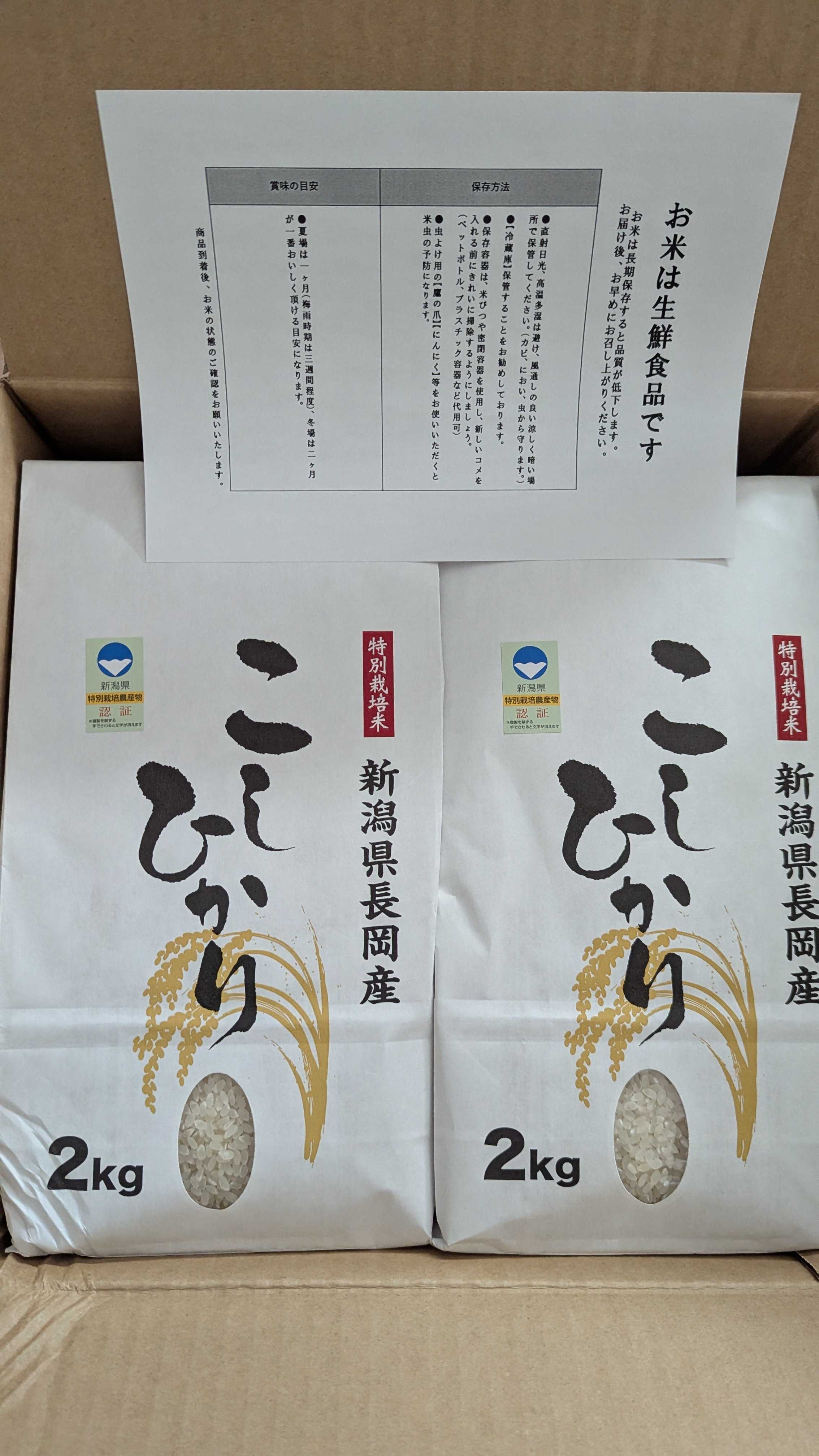
- 株主優待コレクション
- 株主優待品到着 8566 リコーリース
- (2025-11-15 13:10:04)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- 楽天写真館
- 15 日 ( Saturday ) の日記 それ…
- (2025-11-15 07:24:38)
-
© Rakuten Group, Inc.



