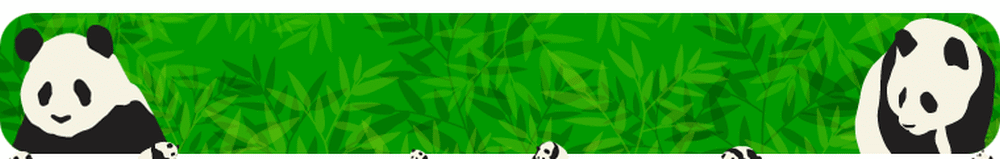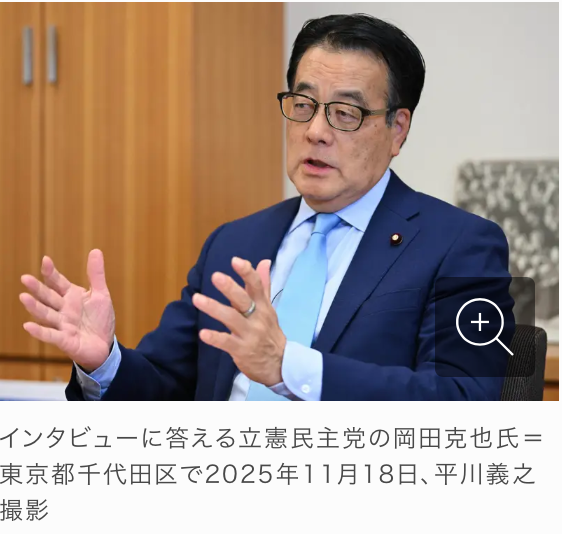全1362件 (1362件中 1-50件目)
-
忘れない
気仙沼市の幼稚園では1人の卒園児の行方がまだわからない中で卒園式が行われたそうです。さっちも先日卒園児を送り出したばかりです。1人1人に保育園生活で撮った写真を卒園式で渡しています。手作りアルバム製作は帰宅してからの過酷な作業だけれども「卒園アルバムを見て自殺を思いとどまった子がいる」と先輩から聞いて何もできない、してあげられないけど、せめて。。。と、心をこめて作ります。でも今年ばかりは「これが何になるの?」と手が止まり。自問自答しながらの作業でした。アルバムの最後に2010年の10大ニュースと以下の文章に考えている子どもたちの写真を添えて載せました。そのことで卒園児の保護者様方が、謝恩会で自分の思いや意見を話して下さいました。瓦礫の中から波間から拾いだしたひとかけらの思い出が私たちの大きな共通の道しるべとなり得ることを、さっちは信じていきます。どんぐりころころ(3番と4番は2010年度○○○組作詞)どんぐりころころ どんぶりこ おいけにはまって さあたいへんどじょうがでてきて こんにちは ぼっちゃんいっしょに あそびましょうどんぐりころころ よろこんで しばらくいっしょに あそんだがやっぱりおやまが こいしいと ないてはどじょうを こまらせたそのときあらしが やってきて どじょうとどんぐり びっくりこたいふうあめかぜ ふかれて ふたりでおやまに かえったとさやまからいけまで とんねるを ほったらいつでも あえるよね○○○ぐみさんが かんがえて ふたりのしあわせ まもられた【おおきくなってからよんでね】↓年が明けてのことで、10大ニュースには入っていませんが・・・先生がこのアルバムを作っている頃、日本でとても大きな地震と津波と原発事故がありました。たくさんの人が亡くなって、まだ救助されていない人もいる中で、皆の可愛い写真に触れていました。作りながらつくづく思ったことです。いつ何が起こるかわからない世の中、精一杯生きること、それから人との縁を大切にすることが、どんなに大切かということ。昔の人も今の人も、有事には肩を寄せ合い同じ光景を紡ぎだすことを、思い知らされました。日本は地震が多いとはいえ、未曾有の大災害に、皆のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんたちは、どんなにか心を痛められたことでしょう。何か行動を起こされていたかもしれません。今しばらく復興に時間がかかることと思います。でも、きっと前を向いて皆で支え合って、(この子たちにどんな未来をつないでいくか)最良のことを考えて進んでいきます。どうか、安心して育ってください。そして、いつかこの頃のことを、お家の人たちに聞いてみて下さい。○○○組さんたちが この「どんぐりころころ」の歌を作った時、「そうしたら家族と会えないよ」という意見が出て、トンネルを考えだしたね。穴掘り名人の皆も、山から池までトンネルを掘るのは大変難しいです。体力も根気も資金も技術もいります。勉強することや仲間を作っていくことは、自分のためでも人のためでもあります。可愛く首を傾げた皆。形ある物はいつかなくなるけれども、見たこと聞いたこと感じたこと全てがあなたの内なる力になっていくことを願います。
2011年04月03日
コメント(0)
-
強迫性障害とそこらにある菌
以前書いた日記『臨床例っていうか何ていうか』・・・って。なんちゅうタイトルでしょ。まぁそれはいいとして。最近は発達障害について暇を見つけて勉強しているさっちですが。。あの日記を実証するような本が発売されています。英語わかる人どーぞ。http://www.amazon.com/Saving-Sammy-Curing-Boy-Caught/dp/0307461831#noophttp://www.amazon.co.jp/gp/aw/d.html?qid=1267627778&a=030746184X&sr=8-5洋書なので。。英検2級のさっちには、ここなくしては知り得なかったサイトです。『洋書ファンクラブ』。多謝!!サンキューです。日本語わかる人、ぜひどーぞ。↓『重症の強迫性障害から奇跡的な回復を果たした少年と母の実話』http://watanabeyukari.weblogs.jp/yousho/2009/09/saving-sammy-ac.html※渡辺由佳里さんに興味を持った方、作品サンプルです。↓http://watanabeyukari.weblogs.jp/poems/2009/05/index.htmlさっちが担任した中にも、つらくなった子がいて(Aちゃんとします)。何だか身体の中からムズムズと何かが起きているんだろうということは感じたけどどうしてあげることもできず。同じことを繰り返し訴えたり。お昼頃腹痛で食事がなかなか進まなかったり。クラスのお集まりに参加できなくなってたし。さっちも、あの頃は、つらかった。。ちょっとこの機会に検索してみたら『PANDAS』という可愛い感じの言葉に行き当たった。「パンダの複数形」ではなくて「溶連菌感染後自己免疫性精神神経症候群」。長い!!・・・これだったんだぁ、保育士じゃなくても気付いてる人、いたんだぁ。なんてビックリした。(しかし言い出しっぺの人は1995年位らしい。鋭いな)とは言っても、医学的にもよくわかっていないことも多いようで異論も多いみたいだし、「まれになることが」って話だった。だからあの日記へのアクセス数多かったのかな。多かれ少なかれ、「なる」っていうふうに書いてたからね。他の子たちも少し様子が違ったから。誰でもなるもんだと思ってた。溶連菌恐るべし、と思ってた。だから、抗生物質飲めば治るという軽い扱い(腎炎とかは知られてるけど)は違うんじゃないかと思って日記に記録してみたのでした。手足口病だって、実際なってみると辛いんだから。子どもの病気だけど、以前さっち罹ったん。だるーい虚脱感あって。すごく気分悪かった。微熱と発疹だけしか表面に出ないけど数字やちょっと見で計り知れないもの、、表面に出ないことって案外大事なのだと、あの時学んだ。まぁそれが何であるか、よくわからんのだけど。話がそれちゃった。よくわからんついでに事例をもう一つ。発達障害の薬(コンサータかなぁと思います)を飲み始めたばかりの子がAちゃんみたいな様子になった。ちょうどクラスで溶連菌感染症が出ていた頃だった。投薬前はクラスの中でとても落ち着いていた状態だったのでかつてないほど障害が悪化しているような様子に戸惑って。これは何なのか、わかる人は教えて下さい。何かが合わさって脳に悪さをするのでしょうか。。ずっと気になってました。もしかして溶連菌って様々な障害を引き起こす原因の1つなのでしょうか?体質みたいな、元々ある素因を誘発・増強するものなのでしょうか?
2010年03月20日
コメント(0)
-
本当に悪い子なのだろうか。。
そのことが、まず頭を過った。保育園に置き換えて考えてみた。例えば、クラスにいるチョロチョロする子は少し年齢が上がってもそうならば「ちょっと『多動』だね」と仲間内で話す。子ども集団の中で様子をみていく。どんな時チョロチョロするのか?友達関係はどうなのか?どんなことにこだわりを持つか?抱きにくくはないか?発達の道筋はどうであったか?そして、必要な手立てが明らかになっていく前でもできるだけ早い段階で、気になる子は保健師さんなどに相談する。保護者さんも気にしておられるかもしれないのでできるだけ早く信頼関係を作り、家庭や地域での子育ての悩みなどうかがう。たとえ保護者さんの職業がお医者さんであっても看護師さんであっても近くにいるわが子のことは、どうしても見えにくいこともある、と感じる。特別支援。。支援が必要な子どもがいる。最近増えてきた。。というか、以前からいたんだ。(なぜだろう)と気になるあの子。。今思えば、あの子もだった。。その時の精一杯の手立てをしたつもりである。しかし、無知だった。その子の『困り感』に徹底的に添えたか、と問うと「否」。できるだけわかりたくて、近いところまでは行けたけれど。。知識も何もない、まっさらなところからのスタートで、一人一人を把握するまでにとても時間がかかった。発達障害は単独でなく併せ持っている子も多い。(例えば『ADHD』と『アスペルガー』)診断名が同じでも、もちろん、一人一人は違うのでその子のことをわかろうとする熱意はとても大事。というか基本。いわゆる早期教育のやりすぎで、アスペルガーっぽくなっている子も中にはいる、とも聞く。そして、ボーダーラインの子も含め、クラスに何人か支援の必要な子がいたとすると学級崩壊に近い様相を呈してくることもある。その子に応じた保育のやり方がある。園外に療育の場もある。周囲の理解の中で育つと、社会の中で自分なりに歩み特異な才能を発揮していけたりするんだけどな。何もかも担任のせいにしていれば簡単な話だろうけどな、なにせ、先進国の中で日本は保育士がたーくさんの子どもをみているわけで。国の最低基準で保育士1人がみることができる子どもの数は年齢別に決められているのだけれども自治体によっては手厚くしてあるところもある。保育士の努力だけではおさまりきれない。心の病気になったりされる。保育が大変なのは耐えられるけれど、周囲の理解がないのにはゲンナリされるみたい。いわゆるお受験して入るような園の保育を見せてもらったことがある。違和感を覚えたのは、子どもたちが皆同じような感じなこと。障害を持っていたり、ヤンチャだったり、チョロチョロしてたり。。の子どもがいなかったのだ。その中でなされた保育は、さっちの心に響かなかった。色々な人がいるのが当たり前の中で育つのは社会に出ての当たり前の基準になっていく。さっちも、自分なりに、たくさん今、勉強させてもらっているところ。。どの子にも日が当たるような保育を受けさせてあげたい。いや、その権利がある。誰かの努力だけでその場をやり過ごしスルーしていってはいけない。突然丁寧語になりますが。。スルーしていっては、親や子や先生まで心を病むことにもなるようです。虐待や引きこもりなどにもつながったりします。社会の色々な問題が、この小さな子どもたちに関わっていく姿勢を変えるだけでもずいぶん改善されると思われます。学校関係が手厚くなってきているけれど保育園は、まだまだ。。改善の余地があると思います。この機会に。。と思っているのはさっちだけではないでしょう。
2010年03月20日
コメント(0)
-
さっちが応援している彼女(その後)
外部に相談してみたり相変わらず、潜入調査したり(もぐり込むの、嫌いではない)なんでこんなにスリリング1人でもやったるわ!と踏ん張っていたけれど事実に勝るものはなし。でしたあの、やはりどんなに出世した人でも失脚する原因は誠実でないこと、人権感覚が「ん?」・・・なこと。が多いわな。それくらい、人の心を踏みにじる行為は、人類共通に近い「なんちゅー酷い人ッ」という、大きな共感を呼ぶのであった。『いい人』の仮面をかぶっていても、だんだんバレるものです。悪いことは、できませんな事実がたくさん積み重なっていく中で周りの人たちもだんだん、彼のおかしさに気付いて援護。。というか、誰かのため、、を超えて自分が言いたいから言うんだって主体性・・・言葉の勢いが、違う。あの物静かなあの人まで、まっすぐな声で公正さを漂わせ、彼への糾弾を。。あの事なかれ主義かなと思ってたあの人まで、自分の言葉で、違う角度から、彼に届くことを諦めずに語る語る。。あの人なんか、まとめて人格否定された無礼さに、絶句して、泣いてしまった。。今までこんなことはなく、こんな人(たち)であることを、知らなかった。なぁんか気持ち悪いんだけどだんだんみんな、「さっち化」していっているような・・・形勢はこちらが優勢。。少なくとも頭数では圧倒しています。「今回の、一連のことで、色々辛いこともあった(「ある」だね・・・現在進行形)けど良いことも少しは、ありましたね。本当の仲間が誰なのか、わかったりどこかで気付いたりしてくれるはず、という信頼を、あきらめないことそんなことに気付かせてもらいましたね。。」そんな話を、今夜は彼女と、できました。そして、ゆっくり、取り上げられたものを、取り戻すんだ。まだまだ終わってないけれど明かりがね、灯ってますよ。彼はじき、失脚するかもしれない。そこを狙っているのでは決して、ない。改めてもらうだけでいいんだ。それも、大したことではなく、少しの努力や工夫で可能なこと。そのくらいは、彼の力量なら、難なくできるでしょってところ。失脚なんか、しないで済むように、色々なアプローチをしてきたけれどそんな配慮さえ無下にするならば仏の顔も三度まで。。お引き取りいただくしか、ない。←生意気ですがさっち、なんか、職業、間違えたかな~。
2009年11月12日
コメント(2)
-
30代の男性に多いという。。
珍しく、病院行きです。飲み食いできない、しゃべれない、喉が痛ーい『扁桃周囲炎』保育園を休めなかったのでマスクをして筆談。。「おはようございます」「今日は無口です」「首から下は、元気です」「給食やおやつや、飲み物いっさい、与えないでください」笑う同僚。不思議がる子どもたち。そう。さっちはわりといつも元気でインフルの人を看病してもうつらないような、そんな保育士。相棒に「今日は悪いけど、2人分しゃべって」と頼む。良くしたもので、ジェスチャーや表情や、「うん」「ううん」「へー」そんな感じでも、大部分の保育は何とかなった。特に、マスクから出ている目の表情をよく見て、言いたいことを察してくれた子どもたちに、キュンそれにしても、病気慣れしていない。「ゴクン」と飲むと右の喉に激痛が走る。喉だけでなく耳にも激痛が・・・。(神経が近い関係で、耳の痛みは喉からの偽物の痛みだけど、でも痛いのは事実)切り裂かれるような、刺されるような、殺されるぅーー感じの痛み。痛くて眠れない。。ヨダレが出ます。。飲むと痛いので、ヨダレを出します。昼はこっそり、夜は堂々と。水が飲めないのに、こんなにヨダレが出たら?人間は、水を飲まないと3日で死ぬとか聞きます。さっち、2日目ですけど、大丈夫でしょうか神様。。普通、熱が出るみたいだけど熱が出ません。熱が出ないから、お医者さんからの扱いが軽いような気がするのは気のせいですか、神様。。「はい終わり~・・・あれ?・・・モシカシテ、クチガ、アケニクイデスカ?彼女、時間、ある?なら、点滴打っときましょうね~、楽になるから」うっかり見落とされそうになるほど、さっちって口がでかいですか、神様。。「食後」に薬を飲むためにおかゆを試みましたが、あまりの痛さに5口で断念しましたから、痩せますかね、神様。。さっちの喉は弱いと思うので、今後気をつけると同時に今度こうなったら、入院を希望しよう。世間の皆様は「扁桃炎」で食い止めてください。「扁桃周囲炎」→「扁桃周囲膿瘍」までいったら、喉を切られたりするそうです。おっそろしー。
2009年11月02日
コメント(2)
-
さっちが応援している彼女(選挙じゃないよ)
「マジメでいても、損するだけだから」彼女が息子に言った言葉。息子は、中学生。母に似てマジメな子。母の言葉は、彼の人生できっと忘れられない言葉となる。彼女にそんなことを言わせてしまう者がいて(「彼」と仮称しておきますね)パワハラし放題の「彼」と、さっちはずっと闘っています。「家族に何もしてあげられない自分」「職場や顧客に迷惑をかける自分」そうやって自分を責める彼女。人との絆が切れることが何よりももったいないこと。取り返すんだ、一緒に。世の中全体に足りないものがあるとずっと思ってきた。基準が低い中にいると、それがラインとなって。。人権感覚が鈍い集団だと、何だかおかしい社会になってくる。反対に、人権感覚が鋭い人は、世の中がよ~く見えるんだと思う。(あんまり先に行っちゃって世間とずれること多々^^)彼女に明るい展望を話したい。でも行き詰まって、幾度か相談に乗ってもらった人がいて今回、信頼できるその人から「耳より情報」が得られた。「彼」については昨年度から顧客の評判が悪くじき、左遷させられるだろうという話。「彼」は外面がいい。人当たりがソフトである。それなのにわかる人にはわかっていた、見る人は見ている、世の中、捨てたもんじゃないと思えた。というか、こんな苦しくなってくる世の中だからこそ、そういうことに敏感になる感性も磨かれる。。という側面も、さっちは保育の中で学んでいるのだけど。もう一つ、明るい?展望というか彼女のことで彼女の会社に乗り込み色々話していくうちに会社のお偉いさんが丸秘な情報を漏らした。→さっちからすれば「耳より情報パート2」であった。本当にうっかり、だったんだろう。隣の部下の人が慌てて訂正していた。さっちの雰囲気が相手を油断させるような雰囲気だったのか、それとも、彼女のことを本気で思ってるだけの女だとわかったのかそんなとこなんでしょうけど。「耳より情報パート2」があって、「彼」の酷い行動の意味が裏付けとれた。推理小説みたい。。さっち、ホント大人しい奴で。。乗り込んだり、歯向かったりするようなキャラじゃなかったけど保育で一生懸命家庭訪問したり、色々なお節介を継続してきて今回のことも、似てたから、できてしまった。相手の懐に飛び込むなり、何かアクション起こせば(アクションの中には、「敢えて待つ」こともあるけど)現状打破できるけど他のことでもそうなんだね。色々、おかしい基準の中にいると「周りが正解で、自分1人が間違ってるんじゃないか」そう思いがちだけど他の人に聞いてみたりして何か、人とのつながりの中で自信を取り戻してほしい。なんて偉そうに書いて、さっちは彼女よりだいぶ年下のくせにね。でも、いいんだ。劣等感は自分への差別だそうだ。彼女にも彼女の息子にも安心してマジメでいてほしい。今までマジメに生きてきて良かったと思ってほしい。
2009年08月29日
コメント(3)
-
幼児に因縁
大人気ないところもい~~っぱいあるさっちですがここはこらえるところ。。というガマンどころはガマンしてみます。北風より太陽。押してもダメなら引いてみな、です。しばし見とれるくらい、幼児と本気でケンカしている大人を目撃したことがありますか。ショッピングでだだこね系とかも、たまに見ますけど。。目撃談その1。。ご年配の女性対3歳児(あらまぁ、本気だわ)と成り行きを見ているさっちの視線に気付いて、その女性は「この子はね、ホントは私を好きなのよ。だから突っかかるのよ」と言い訳されていたっけな。どうも見た感じ、3歳児が優勢だった。社会的権威は、その子には通じないのであった。目撃談その2。。30歳くらいの男性対5歳児わが子じゃない子どもを「自分が叱ってやる」と言って説得?されたんだけど、、何だか全然通じなくて。その子はキョトンとしていた。キョトンと発した質問の一つが、その男性にとっては、ちょい危険なワード入りだったもんだから・・・ヒヤリ。。2人の中に割って入って軌道修正をはかったさっちでした。言葉が通じない。。難しい言葉を使ってるわけじゃないんだけど、気持ちが通じない。これってナンダロウ。「大人だから」という上から目線。。誰しも多少は持っていると思うけど子どもは「子どもっぽい」=「経験不足、発達の途中にある」ことで色々な問題を解決できないのかなぁ、と思いがちだけど何か違う。。とさっちは思います。例えば、言語の発達がゆっくりの子どもさんが保育園にいるとして周りの子どもたちは、その子の言葉を、どうにかわかろうとする。わかろうとしていくと、何だか通じていく。言葉を発する側もただ、周りに何事かを投げかける、感情をバーンと出す、叫び一つとしても、しぐさ一つとしてもその意味するものを、何事かを訴えるものであることを、幼い子どもたちが感覚を研ぎ澄ませて、わかろうとする。0歳児さん同士も、目で会話していたりする。発信する側、受け止める側、信頼という名の見えない糸が見えたりする。モンスターペアレントが増えてきているという。医療関係の仕事に就く友も「最近は大変」と言うので「患者さんからクレーム?」と聞くと「ていうか、患者さんのご家族」だって。聞いてみても聞いてみても、何とも納得しがたいクレームはクレーム自体を見ても見えてこずクレーマーには深い悩みがあるのかも、、などと違う角度から見ると少し見えてくるかな。対人関係をうまく作れない人も中にはいらっしゃる。誰からも話を聞いてもらえない人は、話をわかってもらえない人は他人の話から経験を得られない人は、どんなに生きにくいだろう、寂しいだろう、イライラするだろう。「俺は強い」なんて口にしないでも、本当は一緒に生きていけるのに。しかし悠長なことを言ってられない時もあって。。因縁以外の何物でもないと思われる事柄からはその場でできる最良の方法で心尽くして子どもを守らなければならないけれど。怖そうな人にもツカツカと歩み寄って至近距離でよく話を聞く。「何だ、おまえは。名を名乗れ」と言われれば「○○○○と申します」ヨロシクね~♪じゃないけれど。矛先こっちで、「はい。あーそうでしたか」と怒られさっち。人間、言うだけ言うと気持ちスッキリでしょう。さようなら~。そして、そうやってよく聞いた話を詳細に、記録に残すのであった。只今、記録を分析中だけど、そもそもの怒りの原因、大体のとこ、つかめましたよ。ちょい、複合的だった。もっと深い要因かもしれず。。これからわかるかな。
2009年04月15日
コメント(0)
-
悩む力を書いた人
紅白をぼんやり見ていた大晦日。カンサンジュンさんの「職にあぶれた人」って言葉が衝撃だった。ゲスト審査員で彼が呼ばれたことが、この一言だけで意味をなした気がした。うわあっ、と思った。「職にあぶれた」って、ずっと昔のことを指す言葉のようなそんな意味合いに、自分は捉えていたことがわかった。この寒空、放り出された人たちが沢山いること、頭ではわかっていたつもりなのに。突きつけられる言葉っていうのは直接自分を非難する言葉ではなかったりする。こういう角度から来る。世の中で弱い立場に置かれている人たちのことをいつも頭に置いているだけじゃなくてどうして!!という怒りと、変えたい!!というパワーがさっちには足りないんだよ、浅い共感だけではダメなんだよって。保育園の中。。「仕事、なかなか見つからなくって」といわれる保護者さんがいらして「何かないかしら」と他の保護者さんたちに聞いてみたことがある。その時、職さがしに本当に親身になって下さったのはその保護者さんと仲が良いわけではない、自分も必死でこの地で職を求め探してきたSさんだった。そのことをさっちはSさんのお義母さんに伝えた。お義母さんは「うちのお嫁さんは、よそから来た人だけど今は私より、この土地のことを知っているもの」って胸を張られた。そのことをまた、さっちはSさん・・・だけでなく発表会の場、大勢のお客さまの前で伝えた。お義母さんとお嫁さんのSさんと、職探していた保護者さんと他にも職を探して下さっていた方、全然知らなかった方、会場があたたかい空気で包まれた。子どもたちも胸を張っていた。大人たちのそういうつながりは、子ども心に誇れるものなのだろう。あの時は、ここまで「職にあぶれた」人が増えるとは思ってなかった。あの時、美談で済ましたのではないか、自己満足だったのではないか。自分の浅さを恥じて新年を迎えた。親さんの経済状態、職の内容や、あるなしによる心身の状態、子どもたちにダイレクトに懸かってくる。底知れぬ不安、苛立ち、虚無感、、子どもには、いいお母さんでいよう、いいお父さんでいたい、とそんな思いを突き破る、滲み出る心の叫びを子どもは敏感に察していく。どんな時でも笑顔を絶やさないお母さんでいても、がんばってもお母さんの辛さは、大好きなお母さんの辛さは伝わるんだ。こんなことがあった。子どもが明るいホームドラマを見て「どうして家は、こんなふうじゃないの」って泣きじゃくった。あの子が荒れるしかない時期、抱きとめ、抱きしめ、必死に保育をしていくしかなかった。そういう時、さっちも今ならもっと、家庭に出向いていける。思いが聞こえる場所に立っていなくては、大事なことが見えないから大事なことを手がかりに保育を作っていくよ。「どうして」という叫びに打ちひしがれながらも、そこから元気を絞り出す家族。あの時、さっちは何もできなかったけど。。事実を見据え、信じきるように。。と教えられたよ。時間がかかっても。労働者として保育園のことも、日記で書いてきたけど弱いところから切られるし低いところに合わせられる。人の絆が切れやすくなる。そうやって得をするのは誰かな。怒りの矛先はどこへ?
2009年01月03日
コメント(2)
-
大晦日に、つい・ふと日記
「魔がさした」「でき心」・・・とかいうところの『つい・・・』という言葉「思い立って」「ひらめいて」・・・とかいうところの『ふと・・・』という言葉これはどっちなんだろうな~と思いつつ、2日目のカレーをいただく。ジャガイモがなかったのである。ジャガイモ成分が欲しかったのである。ちょうど家に「じゃがりこ・サラダ味」があったことを『つい』あるいは『ふと』思い出した。はい、入れてみました^^ジャガイモは煮込んでとけちゃったよ、ってふりをした。前科?伏線?があった。ポテトサラダが食べたかったのにジャガイモもポテトもなかった。はい、「じゃがりこ」にお湯を入れてふやかして混ぜてみました。あら、マッシュポテトさん、こんにちは。。さっちの発案ではなくて、何かの雑誌で読んだのを思い出したのです。小さな偽造。小さな秘密。将来『ふと』した瞬間に『つい』やっちゃったのよ、と打ち明ける時は来るのでしょーか。どこやら知らぬが 我から出たもの オナラに似てるね 羞恥心(某歌手グループではない)アホだねホントはマジメなのよ。「つい」と「ふと」の間。。「つい」、(の部類)だよなぁと遠いところから見て思っていたこと、例えばリストカットやアームカットで生きている自分を確かめる人にとっては「つい」でなく「ふと」切るのだろうか。もっとヘヴィな「ふと」がこの不況の世の中、塊となって噴き出すように思えて怖い。そのことが人たちを救うことにつながればいいけど。。鈍感なさっちが予想できるくらい必然なことになっていっている。今年度、さっちは担任する子どもたちとのコラボの中(保育はコラボだ♪という自論^^)、米粒一粒にこだわる過程を経てきた。子どもたちの姿に感動しただけでなく、自分も一緒に育ってしまえ、と思った。手間のかかること、大変なこと、面倒なこと・・・が、とても楽しい。もっともっと面倒くさい企画を思い立ってしまう。疲れるけど疲れない。次の元気がポンと出てくる。このサイクルは何だ?と考えてきた。まだ結論は出ない。けど思うんだ。今さっちは自分の土地を持たない。将来持てたら土から遠い人に、土を少しずつ贈りたいなぁ。それと種。ふと、種をまいてほしい。縁あって、このことを読んだ人たちに(ああ、そういえば・・・)と、いつかその時がきたら思い出してほしい。※じゃがりこは芋さんの命が入ってるけど、ちょっと疲れてる命なのかもしれない。ジャガイモってのは本来油で揚げないほうが良いみたい。※種だってF1種じゃないほうが良い。
2008年12月31日
コメント(4)
-
太田総理んとこで卓郎ちゃんが石油はあと150年分はあるって話してたけど
Re:BBC-今なぜ「イラク」だったのか? な(4/21) とべとべさっちさん ほ~。。そうでしたか。なら、アメリカは「もうこれだけしかないんだよ」って、希少価値作戦で、儲けるのですね?いっぱいあっても「もう、こんなにちょっとしか」って、そんなウソ、誰にもわかんないんですね?一部の人たちに意のままに操られる大勢の人たち。貧富の差、拡大しまくり、文明は止まる?儲けたアメリカ(イスラエルかな?)が、その間、代替エネルギーを開発する?しても、自分たちのためにしか使わないかもね。こんな世の中、いや!もう、さっち、石器時代に戻って暮らしても、いいや。。って、アメリカの思うつぼじゃん!こんな理由で、かけがえのない命が奪われたの。。戦争、また起こる。今度は世界戦。←大げさですか?(2003年04月21日 23時26分58秒)さっき仕事疲れで横になりつつテレビを見ていたら森永卓郎さんが言ってたんだ。「石油は・・・」どこかで聞いたことあると思ったら5年前の五郎さんの日記でした。(※リンク仲間です)当時、上記のようなコメントを残していました。世界戦はスポーツ(オリンピック?)くらいにとどまってさっちの予想がはずれると良いですが。。物価が上昇して嫌~な世の中。今日の夕方、Mちゃんのお父さんが珍しくお迎えにみえた。「わぁお久しぶり!どうされてましたか」と挨拶すると「どうにか生きていました」ってガソリン値上がりで痛手を被った業界にいらっしゃるのです。「どうにか」って他人事ではなく、交通手段が少ない田舎ほど痛手を被る率が高そうで。さっちも、出勤用にバイクを買おうかなぁ。。中古のを。。なんて思ってたりします。イラク戦争によって世界がどうなるか、わかっていたはずって森永さん。1つの重要な情報だけを隠すことで効果的に人心は操れるのかな。恐ろしいことです。代替エネルギーは必要だとしても、今のやり方って・・・。さっち、子どもたちと菜園活動に力を入れています。将来食べ物に困るような気がするからです。戦時中みたいね。里芋は逆さまに植えるほうが良いって。なぜかな?根っこがぐる~んとはっていって、生長に時間はかかるけれど、たくましい根っこなぶん、実りが豊かになるって。
2008年06月20日
コメント(2)
-
一匹も虫を殺さぬ子が良い子?
美意識について考えている。美意識なんていうのは「誇り」と同じで、気をつけないと(フフン、アタシはアンタたちと違うのよッ!)ってな排他的ツンツン&その狭い世界だけで終結してしまう種類の自己満足・・・になりがちなので気をつけましょう。何をもって美しいと感じるかのという基準、さっちの場合、これは人との出会いでしか、本当に深まらなかったように思う。たまたま、このような環境にいて様々な人と出会わせていただいたことで今までの出会いの中のキラキラも、見つめ直して何かに気づいたり推測したりできるのかな。さっちは小学校低学年までは『勧善懲悪が世界の基準!!』な思想をする子だった。そして、書くのも恥ずかしいが心の美しい人が主人公の童話などを読みあさりそんな「良い子」な主人公たちには素晴らしいことが起こるという法則を鵜呑みにし『ワタシは美しい心でいる』ことを決意。そのためには『人の悪口を言わない』それで悪口を言いたいような人に出会ったら?『カワイソウな人だもんね~』と思うことにしたり。←嫌な子ねッ!(笑)虫も極力殺さなかった。困っているアリさんを助けたりしていた。ずいぶん長くがんばったような気がする。しかし自分がそのような世界に居続けるのは何だか苦しかった。4年生の時、親友Aちゃんに(悪の道に?)引っ張られ、やめたんだ。人の悪口を言うのって、なぁんて楽しいのかしらッとビックリしたなぁ。楽になった。Aちゃんにどのように引っ張られたかというと「○○ちゃんってヒドイよね」とさっちの気持ちを共感の言葉で代弁してくれたの。Aちゃんはいわゆるお勉強はできなかったけどさっちは度々『負けた・・・』と感服するようなものの見方をする、なんだか素敵な子だった。勧善懲悪・アタシはアンタたちとは違うのよ的ナルシスト~な世界ってのは何だか違うよなぁ?と、Aちゃんといるといつも感覚的にわかった?というか実感できた。(今でこそ、ずいぶん長くがんばったことで、もったいなくて認めたくないけどさっちは自分だけ良い思いをしようと私利私欲のためにやってたなぁとわかるけどさ)試しに時々母にAちゃんちより自分ちのほうが素晴らしいんだよねぇみたいなこと言っては母からもガツンとやられてた。Aちゃんの生い立ちや家庭の現状などを母は知っていて、さっちに語ってくれた。そのことと、Aちゃん自身から聞く話、色々。。「赤ちゃんの頃、入院して・・・」などという話はAちゃんのお母さんを通しての言葉だったろうけどそんな話を時々聞いては自分の中に積み重ねてはAちゃんから度々ハッと目を開かせてもらうことの謎を解いたつもりでいた。実際、小さなケンカはしたけどAちゃんのほうが大人で助かったみたい。「さっちとAちゃんは違うけど、全然違うけど友達だな」5年生の時の担任の先生が言ってくれた。それがすごく嬉しかった。家を離れる前の高校生の頃まで、さっちはAちゃんを頼りにしていた。この先も、大人になっても素敵なAちゃんは幸せになるって、さっちは思ってたんだ。さっちは今、Aちゃんと連絡がとれない。同級生の誰も、Aちゃんと連絡がとれない。同窓会は楽しいけれど、いつもAちゃんが来ないのでさっちは心に穴があいてるって感じるよ。なぜAちゃんとのつながりが切れてしまったんだろう。Aちゃんは、Aちゃんの素晴らしさを認められるべき場で認められなかった。そのことがAちゃんを生き難くさせた。そこに尽きる。Aちゃんは決して弱い子ではなかったけど・・・「お父ちゃん、星になって見ててくれるかな」「うん。おーい!!」目に涙をためながら星空に向かって2人で叫んだあの日。でも、おばちゃん(Aちゃんのお母さん)がいるもんね、と思っていたけどおばちゃんまでも、あんなに早く逝ってしまわれた。。そんな時に、そんな時にさっちは地元にいなかった。その後さっちはどうにか保育士になり。出会う人や環境で多少とも決まる人生もあるならと、さっちが来たからもう大丈夫だよ、という思いで保育にあたっている。全然大丈夫じゃないんだけど、心の中にその言葉を置いていると(あっ、またやっちゃった。あべこべだよね、さっちを鍛えてくれる子どもだ☆さっちを大丈夫な先生にしてくれる子どもだ☆)という出会いに気付き、素直な心で臨める。関われば関わるほど価値観と価値観とのぶつかり合いを感じる子どもほどいつもAちゃんを後ろに感じるんだ。Aちゃんを生きにくくさせたのは、本当の本当は何でもないこと。私たちはちょっと遠い将来を見据えて保育を創るけれど人間というものは変な言い方だけど、子どもと大人との区切りない存在で『人間』であって一生誰かに保育されたり、自分を保育したり(保育し直したり?)するんだ。突然の天災、戦争、、それまでの自分を保つに余りある出来事がいつ何時起こるやも知れぬ、世間でいわれる分別のつく『大人』という状態は実はとても不安定なものなんだ。『良い子』な大人をやっていくのに仮面を感じる人は、よく想像をはたらかせ『良い子』でない自分とも、しっかり向き合っていたほうがいい。何か、見てて腹立つ人っているじゃん。そんな人からも自分を学べる。子ども時代、失敗を許されなかった人は、そんな環境を正面から見つめて自分を保育し直すといい。捕らわれた心は捕らわれなくても良かった心だったね?親さんも捕らわれた心をどこかで貰って、ずっと持ってなくちゃって思ったのかな?違う美意識や価値観もある。真似したいことや、やりたいことは何だった?自分が自分のままで良い、の許容範囲は社会の中でけっこう広いもんです。間に合うよ。
2008年06月17日
コメント(2)
-
たりないものを数えるは、ナントカ皿屋敷
秋葉原の事件の報道。。牛丼店に逃げ込む人々の映像を目にして(あの時と同じだ・・・)居酒屋に逃げ込むさっちの映像が重なった。1つ前の日記で、あれは夢だったんだけど擬似体験みたいで、気色悪く1週間を過ごした。他にすぐ重ね合わせられたことといえば。。最近、時の記念日ということでクラスで時計を作ったの。保育日誌でその日の反省に『今日の製作あそびは容易であると思っていたけれど勘違いしたり早まったりして失敗する子が予想以上に多かった。やり直しがきくようにクラスの人数の1割くらいは余分に素材の準備をしていたがもっと多目に、2割くらいは失敗するかもしれないと仮定して、準備すべきだった。』と書いたんだ。そうすれば、子どもも安心する。さっちも、安心して失敗させられる。こうも書いた。『失敗する子は同じ活動を2回繰り返すことになるが2倍経験させてあげられるということになり、最初から失敗させないようにするより、かえって良いと思われる』さっちの視点で失敗という名詞を使ってしまうけどあの子たちにとっては以前重ねそこなった経験を今、取り戻しているというそれだけのことなのかなぁと思った。これを社会に置き換えよう。失敗したり、ちょっとしたボタンの掛け違いがあったりと行き詰まることは誰しもあるけれど一人一人の感受性を超えて、八方塞がりな未来が身近なものになっているように思う。さっちの保育の反省のように保障が足りないのだ。何かあってからでは遅いこともある。何かあった時、何がきっかけ?って言っても入るスイッチをたくさん持たされてる人も多くなっていると思われる。(保育士としては、その芽。。彼の小さい頃のことが気になる)こんなこと、以前にも書いたと思うけど歴史は繰り返すというけれど今の世の中、格差社会というか。。それ、ごまかすために昔で言う「士農工商」みたいなことが起こってるような。。武士の次に農民は位が高いんだからな、と言われても農民の暮らしはどうだったか。不満を募らせると昔は一揆が起きたりして団結していたように思うけれど今は人と人とがバラバラな感じ。本当にそれは糾弾すべきことなのかなんて現実の世界では、さっちなら仲間がいないと口に出しにくい。1人であれば、そもそも本当に糾弾すべきは何者なのか?なんてことからうまく頭の中、整理できなくてやり方を間違いそうだよ。「誰か」のせいにするのは簡単だし楽。その「誰か」は身近な誰かになりがちだけど視点を変えたら、個人の力ではどうにもできない大きなうねりの中で遠くにいる「誰か」が見えにくくなっているのかもしれない。うまく言えないけど。。権利ばかり叫びたくなる時ほど頭を冷やして「誰か」の術中にはまってはいけない。世の中はうまくいかないことのほうが多いけどうまくいかないことでいちいちくさっていたら面白くないから(それでも自分は)というものを持ちたい。そこに至るまで。。過去、世の中から見捨てられたように苦しい思いで生きてきた人たちは自分を嫌いになったりしたのかな、近くにいる人を恨んだりしたのかな、誰かに八つ当たりしたくなったのかな、それでも今胸を張って生きているのだとしたらそれをどうやってしのいできたのか。本当の強さというものはそこで、それは人種や国を超えて通用すると思う。甘いかな。○○さえあれば。。という考え方は彼女さえいれば。。という犯人の考え方にかぶるかな。でもそう簡単には今までのやり方では通用しないとしても過去からエッセンスをいただければ、新しいものを組み立てる元気は出てくるように思うんだ。格差による差別に負け続け、最後自分に負けるのは格好悪いから何か悪あがきしたくなるじゃん。でも、同じ悪あがきなら社会のためになることをしたほうが良いに決まってる。あの日をわざわざ選んだのだろうか。わからないけど。。殺めた人は帰ってこない。犯罪の行為や名前が大々的に報道されることで(有名になった)なんて喜ばせる素地がマスコミやさっちの心の中にあるんじゃ?と悩みつつ書いてます。
2008年06月15日
コメント(2)
-
俺ぁ悪くねぇぞって、キャーって女の悲鳴出す(≒愚痴る)
追いかけられる夢を見た。追いかけてきたのは3人組。1回は確かに(撒いた)という手応えがあったのだが敵はなかなかシツコイのだった。オマケに足も速かった。さっちはしかし(自分はすばしっこい)という自覚が夢の中でもあり、あきらめずに逃げた。だって俺、何も悪くねぇし。(※自分は悪くないって思う時はなぜか「俺」になるさっち)人がいたら「キャー!!!」と叫んで(私は被害者よ)とアピールするのを忘れなかった。「助けてください!追われています。ここに匿って!!」と居酒屋らしき厨房に逃げ込み、息をひそめていた。少なくとも今のうち、心臓のドキドキをおさめなくちゃならない。居酒屋の従業員さんたちはビックリしていたけどどうやら良い人そうね、敵にさっちを引き渡しはせず様子を見ているな、、などと観察しているところで目を覚まして助かったぁというのと同時にチェッと思った。結末が見たかった、傍観者としての俺だか私だかがいるのであった。小さい頃はよく追いかけられる夢をみたけどな。たぶん、現実の生活での『ビビリ』が出たんじゃないだろうか。分析するに、思い当たるのは3つ。1つは後々「あれでハクがついたよね」って思える経験になるのかなぁ。。ってな場にデビューすること。脅し、、じゃなかった、推薦を受けたのでした。2つめは今まで逃げてたことに、ちょっと近づくってこと。こうと決めるまでが長くてうだうだ言ったりグズグズしたりするんだな。結果、スローなさっち。トホホ。。まぁこれは少し面倒だけど、楽しみでもある。3つめは今、孤軍奮闘していること。気が張って元気だけど、仲間を取りこめるか不安もあるの。さっちは何も持たない。発言なんか弱い。軽く見られがち・・・。くそぅ~!!負けるじゃんの!!対策は、「堂々と愚痴る」愚痴る機会だけは逃さない。。←妙に、これが上手で(笑)
2008年05月31日
コメント(4)
-
手応えズッシリ
どんな時、この子はデキル。。と感じるか?難しい漢字を書く子などは、かえって心配になるさっちです。今日、ニワトリ当番の2人の子と洗いものの仕事をしていた時、1人の子、仮にYくんとします。Yくんが「あれ?砂場がキレイになってるね?柔らかそうね」と言った。「うん、そうよ。○○先生が耕してくれてたからよ」と、さっち。※砂場はそうやって定期的に消毒することになってます。「そう!じゃあ、すぐボクたち遊べるね!ふわふわだから、お山とか、すぐ作れるね!!」Yくんはそう言い、相棒のAちゃんも素敵にニッコリした。日常のひとコマ。。それだけのことなんだけど。。そのちょっと前。包丁でエサを切る仕事をしている時、包丁使いが繊細な、Yくんの切ったキャベツを「トンカツの横に置いてもいいくらい、細く切ってあるね」と言ったら「だって、ボク、ママのお料理してるところ、いつも見てるもん」と。更にその前日。Yくんは絵を描いた。お父さんの仕事場に付いて行った時の絵だった。お店の品物がたくさん並んでいた。縦、横、きちんと揃えて並べて描いてあった。隣のお店のことも描いてあり、そこには子どもが好きそうな品物があった。Yくんが言うにはお父さんの売り場には「あまり、お客さん、来なかった」そうだ。ドキンとしつつも、でもその時のお父さんのことを見たまま感じたまま、そのまんま、描いてあるんだなぁと思った。お父さんへの気持ちが伝わってきた。仕事の、報われない辛さも、Yくんなりに感じているのだ。お父さんのお店の品物を口にし、「おいしかった」に込められた深み。・・・そんなことがあっての今日のYくんの気付きや言葉に、さっちはハッとさせられたのだ。さっちは耕すという経験を、菜園活動でさせている。そのことから、どんな実感を得ていくのか、思いを馳せながら、させている。でも家族の姿から学ぶ子には、かなわないって思う。だから生活に関わる絵を描かせて、学びをより確かなものにはしているんだけど。。どうだろう、さっちがこの子から学ぶ、人としての姿勢!例えば。。がんばっていることにエールを送るのは簡単だががんばりたいのにがんばれない時もある切なさの、保育者の受け止め方など芯を持たないと、と考えさせられる。保育所保育は、この子の育ちの、少しでも補完になればいいなと思う。応援団みたいな、というより、影武者?黒子??みたいな気持ちに、なる。この子や他の子が描いた、家でのくらしを描いた絵をクラスの皆に紹介した。今はアホな(敢えてアホと書く)プライバシーがどうとかの世相で家庭訪問を行っていない園も多いと聞く。ましてや、こういう絵の紹介ってのは、プライバシーをさらすことにならないかって意見も。アホなのは。。自分のくらしを、どこから子どもたちは「恥ずかしい」「劣る」とか思うんだろうってこと。それは周りの大人の「カワイソウ」「下流」とかいう捉え方、価値観によるところが大きい。なので、放っておいては、価値観はそのままなのだ。さっちもこの仕事をしてなかったら、色々に出会わなかったら、そのままだった。格差社会であるのに都合の良い人間の、自分も一部であることに恥じつつ、さっちはそれができるところにいると思うので今までの価値観を覆す、人との違いを認め合う心や自尊の心や何からでも学ぶ力や生きる力そういう真に強い精神力を少なくともクラス集団に、つけていきたい。そういうことに関しては、大人には伝えられないけど子どもたちになら大丈夫、ということも多い。この人はどんな人か?というアンテナは、ぼーっとしてるわりに、さっち、正確みたい。なので、「きちんと伝えきる」余裕がない時には、さっちも口をつぐんだりぼかしたりと本当に『機微』の世界だ。でもプロだもん。やるさ。しかし、ただでさえ、手探りなのに。。家庭にも出向かないと、その家庭の空気感、本当のことがわからない。本当は一度行くだけでも、わからないことはいっぱいあるけど、一度でも行かないより随分マシ。相手のテリトリーに入って話し込むと、そんなに悪い人って世の中いないよなぁとわかるし。教育って実は安心感がとても大切で。自分のやり方で大丈夫なのかなぁと若干の疑いを持ちつつ、安心と反対の方向に舵を切らないように気をつけ、アバウトに、じわじわ進もう。
2008年05月02日
コメント(0)
-
小突かれるたびに削がれてきた自尊
以前から思っていたんだけど。。暴力をふるう子はどんな子かといえば往々にして、気が小さい。世の中の色んなことにうまく立ち回れずに些細なことにもジグザグにぶつかっていって本人も周りも傷だらけ。それなのに、、痛いのに、、世の中の色んなことを許せずにいるのはどうしてだろう。・・・。許されてこなかった子が多い。今はそうじゃなくても、うんと小さい頃愛してほしい人から邪険にされていたりするんだ。邪険にする側の人も実は小さい頃。。世代連鎖。この鎖を断ち切れ!周りの理解を得て、うんとうんと安心させてあげたい。乗り越えたかと思っても普段は落ち着いてきても何か心がキューッとなる出来事があった時には或いは、とっさの時には脆いんだってことも知っている。脆さが付きまとうから、誰かがそばにいてほしいし誰かがそばにいるのと同じくらい、幸せになってほしい。誰もが当たり前に持っていると誤解していることは本当は当たり前じゃないってこと。概念が覆される相手といつか出会うけど最初から否定した、閉じた心では気付かないかもしれない。そのままいって将来誰かから、夢にも思わない加害を受けることも巡り巡ってあるかもしれない。加害も自害も本質はとても似ている。
2008年04月23日
コメント(2)
-
上下関係
子どもたちはどこで上下関係、わかっていくのかな。家庭訪問に行くと「私の言うことは聞かないけどおばあちゃんの言うことは聞くんです」って。家族でも人を見て行動していると言えそう。使い分け。それは生きる知恵でもあると思うけど。。例えば保育園で(○○先生の言うことは聞いておこう。△△先生のは聞き流しちゃえ)なんて思ってたりしたら、やっぱり嫌だなぁと思う。それは私たちに原因があるのでは?○○先生が担任の先生で、△△先生があまり触れ合う機会のない先生だとしたら触れ合う機会を多く持ったり、具体的に話題にしたりすれば良いのかな。○○先生がベテランの先生で△△先生が新人の先生だとしたら?職員が△△先生を軽くみていないかということが問われる。△△先生の不慣れな部分を助けるのはもちろん、△△先生から受けた良い刺激を自分の保育に反映させているか?自分自身どんな人からも学びを得る心であるか。そういうことを問われているならば改善の余地あり。子どもたち同士、クラスにおいても異年齢児間においても強い者がはびこり弱い者を駆逐するの図にはしたくない。そういうの、おかしいよって、もうちょっと良いつながりが持てるんだよって言葉で教えるよりも私たち職員集団が人として尊敬し合う姿を見せたいとこ。いけないところは教えてもらい、意見の違いは争わずに話し合い。。声を荒げないでいたいものです。キレイゴトなのかもしれないけど、でも。何か今、そう思ってる。幸いにしてさっちは人を駆り出すのが好きというか人にいてもらわなきゃ困るというかよく子どもたちに何か伝えたい時に即興の小芝居(寸劇?)で他の先生を巻き込みがちなので、そんなとこで仲良く分担したり協力したりするって楽しいんだよ、誰にも持ち味があるって面白く素敵なことなんだよ、って。ホレ、先生たちって生き生きお仕事してるでしょ♪ってのも見せたいけどその前に、これ。だな。職場で立場は色々違うけどその違いが人を軽く見ることと結びつくってのは、いただけない。パワハラって言葉がある。子どもたちに何かしてほしいと思った時、『怖い先生』で言うことをきかせるか『この先生たち、みんなダメって譲らないな。いけないのかな』と感じとらせるのか(もちろん子どもたちと具体的な事例を通して話し合うのがベストだけど緊急の場合)同じ「雰囲気」でも後者のほうが子ども自身の学びは深まると思う。何かとっても頭良い人がトントンと出世して失言で失脚する。生きてきた道のりで、何かが足りなかったのかな。何か大きな企業がドンドン物をつくって営利だけに走って失脚する。消費者や労働力を軽視し、のぼせ上がってきた報いかな。保育も積み重ね。自分はクラスのお山の大将になってないかな。人生の入り口でさっちと出会ってしまった子どもたちに損はさせたくないなぁ。
2008年04月21日
コメント(0)
-
かたまってないんですけど
自由とは、のびのび~できるぶん、責任は自分。。ちょっとしんどい。それでも自由がいい。誰にも邪魔されずに、これをがんばろうって邁進できる。ぼーっとしていて叱られるのは納得できるけど今これをやるのだ!!とがんばってるのを否定されるのはへこむもんね。自由である分のしんどさなんて、苦労のうちに入らない。忙しいのは確かだけど、何より心が軽い。・・・なぁんて話を主任としてる今日この頃。・・・なぁんて話を他の園の仲間にも伝えてる今日この頃。自分がしっかりしてなくちゃいけない。芯がなくちゃ人を説得できない。そういうプレッシャーはあって。保育と家庭訪問の合間を見つけ、仲間と話すことが多くなった。人間関係がうまくいっていれば、わりと、お仕事人生は大丈夫みたい。そんな新年度。前の日記と日があきましたがさっちは家族から「引き受けるな」と止められたけれどまたまた年長クラスの担任になった。家庭訪問に伺うと「また年長さんで、先生、大変ですね」と同情される。見るからに忙しい年長クラス。でもダイレクトに手応えがある年長クラス。文字を持たせたいなぁと。何かにつけ黒板に書くさっち。お当番さん2人の名前を書くと「こ」という同じ字が含まれていた。「こ」の付くもの、他にあるかな、と投げかける。(頭音言葉あそびというシロモノ)「う~ん」「う~ん」と考え始める。「・・・腰!」「・・・口内炎!!」なかなか愉快なセレクト(笑)お昼寝から目覚めて「先生、コンソメスープもあったよ」って言う。半日中考えていたようで、76個の単語を見つけた子どもたちだった。どうも100個を目指してるみたい。今は、年長さんになった喜びに満ち溢れ、はりきって前のめりな日々のよう。人の話を聞けるって、人を尊重していることだと思うのでそういうクラスになってほしいなと思います。
2008年04月20日
コメント(0)
-
ビックリ人事
どうなるのかな~っと皆で話してて異動してきた謎の○○さんの役でさっちは小芝居をして、大ウケ。いざ本物の○○さんが来られたら小芝居と同じようになんでワタシが??という不思議そうな、なんとも微妙な顔をされていてププッと笑ってしまったさ。皆の目も笑ってた。廊下に出ると△△先生と▽▽先生が眉をハの字にして何やら真剣に話されていたから「どーちたの?」と聞いたら「あのねぇ」と同じテンションで返して来られた。そこからまた小芝居は続くのであった。さっち、新年度早々ちょっとゆるんでる。昨年度はクラスの▽▽先生と、子どもたちによく小芝居してみせた。(小芝居と寸劇って違いがよくわからんのだけど?)さっちが仕掛ける小芝居に乗ってくるのは彼女だけではなかった。小芝居仲間を発掘できて嬉しいわ。
2008年04月01日
コメント(0)
-
『スタンドバイミー』
堀北真希が表紙に出ていたので思わず手にとった週刊少年マガジン。なぜ手にとって見たかというと?ドラマ「東京大空襲」を見た後だったから。よしよし、真希ちゃん、ここにちゃんと生きていたね~♪と、わかっているのにホッとした直後新連載の「スタンドバイミー」という漫画が目に入った。表紙に『大型新人』と見出しがついていたけど?新人なのに、このページに来るというのは本当に『大型』なのかなぁと思いつつ目に飛び込んできた自衛隊の絵。まさか、また戦争のことが描いてあるとは。。日本で「昔あった」戦争ではなく。。秘密裡に行われているとはいえ、徴兵に強制力を帯びた設定であった。この先の展開が怖い。さっちが感じる怖さはこの漫画を読む少年たちが感じる怖さと同じではないかもしれないけど。
2008年03月19日
コメント(2)
-
スタンダード
奇をてらわない。私立であっても公立のような幼稚園がある。こんな習い事をさせてますってなのばかりで食傷気味なところ子どもたちの遊びを余裕もって保障してある。普通である。変に方向づけてないぶん、これから何色にでも染まる。何色に染まるかを子ども自身が選びとれるようなニュアンスの、何色にでも染まる、なのよね。そのことに、さっちはかなり魅力を感じるのであった。
2008年03月08日
コメント(2)
-
普通の公立の学校の先生だった。
恩師の写真が少しお年を召されてでも柔和なあのほほえみの恩師の写真が今なぜ私と出会っているのだろう。写真と、文と。最近思いがけなく目にしたのだった。うわ、すごかったんだ先生、知らなかった。すごい人の授業を受けていたんだ、でもそんなすごさなんて微塵も感じさせなかったよね、先生。そんな問いかけを写真に向け、してみている。今夜はNHKで教育についての討論番組をチラチラ見ながら色画用紙を切っている私。この今の私を作ってきた要素としての恩師。先生、あの授業は他の普通の授業と同じように大人しく受けていた私だけどううん、私たちだけどいつまでも心から離れないのはなぜでしょうね。たぶん、、、とさっちも推測するところまでは来ています。ついこの間までは、手作りの教材だから自分で作った教材だから思い入れがあるから子どもにもその分の熱が伝わるんだろうと。それだけではなくて先生、先生もある事実から刺激や熱や色々を受け取り感動という動機をもらった。その感動そのままに作ったんだよね?教材。それを作るに至るまでも様々な事柄だけでなく何より「人」に出会い、生きざまたちが重なって織り成された珠玉であるけれど朴訥なあの授業。。外部から人を呼んで授業に参加していただくってことも先生ご自身の感動を軸とした生の人と人とのつながりあってこそのあのあったかい時間。忘れられるわけがない。だからなんでしょう、先生。担任と副担任、何か楽しそうに忙しがっていたよね。先生たち、学校、ホント、楽しそうだった。子どもたちに生き生きと働く(学ぶ)ことの素敵さを私も見せていきたいな。できるかな。討論番組で子どもたちの未来への可能性を摘まないために教育の底上げを!というようなことを1人の女性(作家さん)がおっしゃっていた。強いていうならば「どこからでも育ってみせる」と思っている人間ばかりではないかもしれない。今は特にそうかもしれない。さっちは早くからそう思ってきたことを自分が本来持っている力だと捉えてきたけれど本当は周りにそれを許してもらっていた、育ててもらっていたんだろうなと想像して少し幸せ気分に浸っています。人生、小さな事柄においては自分の第一希望通りに進まないことがほとんどだけどもっと大きな事柄に、、もっと単純で大きな人生の道すじにおいては気の持ちようというか、周りがどうあろうと、わりと思い通りに生きていけるみたい。どこから育ってもいいんだよ、どんなことからでも育つ、そんな生きる力を持たせてあげられるかなぁ。それさえも許されない世の中にだけはNO!を突きつけて。できない状況なら頭の中で文句をいっぱい言えばいい。歌に、物語に、ベールをかけて隠して言ってもいい。もう一度見直すと先生の顔、まじめな中にも「へへ~んだ☆」ってな具合に顎を上げちゃって「どんなもんだい」って言ってるようにも見えてきた。
2008年03月08日
コメント(0)
-
荒療治
膿を出すまでの一時期、耐えろよ日本人。膿を出すまでの一時期、耐えろよ地球人。本当に出さなければならない膿なのかなぁ。他に方法があるんじゃない?バイキンのついた手で触るから出るんだよ膿。ていうか、膿まで偽装されてたりして。何かを変革するための急激な変化で今までのバランスがたやすく壊れて生き難くなっているとしたらどこか変だぞ。人たちを釣ろうと思う時、自分ならどんな餌をまくだろうね。あああ、デビルさっちだわ(笑)
2008年03月05日
コメント(2)
-
動物でーす♪
内輪と外部では評価の全く違う人がいる。外ヅラは良いのだけど、何というか。。小賢しい?というの??さっちはズルイ人ってのはどうも苦手だな。人に押し付けたことを自分の手柄にしたりすることを続けていたらどよよんとしたズルイ空気を身にまとうことになる。そんなのって早かれ遅かれ、いずれ皆にバレル。余談だけど以前、インフルエンザとか風邪とかに罹っている人ってそばに寄るとわかるって日記に書いたような気がする。空気みたいなもんでわかるの。その後、テレビ番組で本当にそんな能力が人にはあるって。自覚している人も結構いるっていうのを聞いてビックリしたことがある。。犬も癌がある人が嗅覚でわかるって。・・・さっちは動物に近いのか!!バレル限界。。臨界点って、あるのかな。同じ瞬間に電話をかけたりメールを送ったり親しければ、相手を思う波長が時間的にも合うことがある。隠されたものがポロポロと出てくる世相。世の中の色々な悪いこともばれてほしいけど、ばれる過程であちこちに迷惑かけて、、良い人がとばっちり食って。。半端に悪い奴はたやすくばれるけど、本質というか本当の本当に悪い奴は悪さが巨大でばれるのを強大に封じてあったりするというかそういうシステムを作った「仕掛け手」であったりするというか。。そういうのはズルイの極致でさっちは大嫌いだ。だからどうするって具体的なことは、頭の中で自由に泳がせてあげよう♪2つ以上目が付いていたら困る、か弱い動物ですもん(笑)
2008年03月04日
コメント(0)
-
窒素だらけ
日本で水や野菜に含まれすぎている窒素でWHOの許容摂取量を子どもも大人も超過しているって。日本って基準値がないって。あったら困るのかいな。どうして自分で自分の首をしめるような施策をとってきたかというと一人一人の健康のかけがえのなさより当面だかずっとだか勝るものがあったんでしょーか。
2008年02月25日
コメント(0)
-
かげふみの奥義
日曜出勤してきた。厚着をして靴下は2枚はいて、極力ヒーターを使わないようにしていたが寒い。。少しだけ点けてしまった。ちょうどヒーターの灯油が切れていたので入れながら、しばし物思いに耽る。4か月ぶりにインド洋での給油活動が再開されたことが目立たないニュースになってしまっているような気がする。そこまで給油したいんかい!!とツッコミを入れたくなるような経過をとっての再開だっただけにさっちは注目していたんだけど。どうして隠れてしまったのかは、書かないでもいいね。「かげふみ」という遊びがある。鬼に自分の影を踏まれないようにと逃げてばかりいては疲れるだけ。自分の影を消すために一番有効なのは。。自分の影より大きな影の中に身を置くことだ。「上手に隠れたね、○○ちゃん、すごいぞ~☆」と傍観者としては、その作戦を褒めたいところだけど遊び仲間としては、「隠れてばかりじゃ面白くないよ!ズルイ!!」と大きな影から引っ張り出したいところだ。当面の危機が去ると、子どもならば、すぐ出てくるんだけどね。大人は、どうかねぇ?うが~~った見方をしてみるよ。「なんてつまらん奴だ、情けない奴だ、卑怯な奴だ」と『敢えて』思われることで、成果をあげたり得をしたりすることも世の中にはある。色々な視点でものを見れば、ある。あまりに、あまりにお粗末すぎて最初の最初からシナリオがあったのかと思うくらいで。影を演出?そんなこと思うのさっちだけだろうか。あれくらいの犠牲、屁でもないって、、そんな冷酷を思うと嫌でたまらんけど。例えば保育中、子どもたちに手を洗いに行かせたい時。ドタバタ逃げちゃうワンパクちゃんたち。そう来たか、ならば1人だけと手をつなぎ「お先~」と行きかけ様子をみよう。ありゃ、皆そっち行っちゃったか、ならトンネル作って皆も巻き込んで遊びにしよう、遊びにしながら手洗い場まで導こう。小さな子どもたちがどのような動きをしても良い。思いがけず遊びのバリエーションが増えたりするのは得だと思える。人間と人間だもん。思い通りに動かすなんて思い上がりだ。さっちは結局、手を洗わせることができていくんだけれど手を洗ってもらいたいなら、自分を柔かく。機転をきかせたり努力したりするよ。そういうのがデビルな方向に向いたら怖いよねっていうのは常日頃から思ってる。たぶん、それだけなんだ。。。と横道に逸れましたが『敢えて』マイナス評価を受け、叩かれることよりも怖いものがあるとしたら影に隠れ続けるのかなぁ、大人は。そゆことない?でもね、お日様は動いちゃうから☆
2008年02月24日
コメント(0)
-
ままごとどうぐ~製作展での掲示より(抜粋)~
食事の時間は皆で顔を合わせる時間。仲間の心を感じる時間。お家の人を思い出す時間でもあり、恋しくて泣いていた春がありました。今は家族のことや園外の出来事を友達と語り合う楽しい時間となっています。言葉も増え、おしゃべりに余念がない子どもたちです。ままごとあそびは生活あそび。一人一人の生活が出るあそび。「どうぞ」とふるまう、片付ける、しょうゆをかける・・・そんな一つ一つの動作や言葉も、仲間がいるから生まれます。家族の姿を仲間に返しているのだと思います。製作展では食材も自分たちで作ったものを展示し、より思い入れのある道具にして翌日より実際使ってあそばせていきたいと思います。クッキング、菜園活動、ニワトリ当番はもとよりジェンダーフリーにからむあそびでもあると捉えています。
2008年02月17日
コメント(0)
-
長崎原爆資料館~隠したい歴史・明かしたい歴史~
大人1枚300円。券を買っていざ、入場と思いきや右手を見るとボランティアの案内人の方がいらっしゃるでは。「どーする」「無料だってよ」「じゃ」「うん」ってことで「お願いしまーす」となったのだった。先導して下さり、一同、グルグルな坂を降りていった。さっちたちだけでは斜めに見て終わっていたかもしれない部分が具体的に詳しく解説付きで。本当に案内を頼んで良かった。後ろに気配がし、振り返ると人だかりができていた。こ、これは『もらい解説』じゃあないの。そんなんなら、皆頼めば良いのにね(笑)人だかりは歩を進めるごとに増えていき、さながら黒山である。話に引き込まれ、質問も活発に繰り出されるほど。案内された方、何者かと思った。どこかで見たようなお顔であるが、それはまたのお楽しみでいつかわかる(ああ、そうだったのね!)に取っておくことにしよう。その場で積極的には尋ねることはできなかったが、被爆二世でいらっしゃることはわかった。その方が語られるいちいち重みのある言葉の中でも本当に悔しそうだなぁとひしひし伝わったのは『浦上天主堂』である。浦上天主堂にはここに来る前に行っておいたのだけど今はキレイに建て替えられている。中には素敵なステンドグラスもあり、うっとりさせられた。原爆を思わせるものとしては坂の途中に、首のない像が残されていたりは、した。どうして天主堂そのものが、そのまま残されなかったのだろう。どうして一部が、ここ資料館に来ているのだろう。そのことは悲しみではない、静かな熱い怒りでしか語られないし語るべき方の口から語られ、縁あって聞いた者の心をうつ。『このまま残すべき』な遺産を、『このまま』にさせないで介入し、価値をそぐ者がいて、流される者がいて、タッチできない者もいて・・・ここだけじゃないのだろう。そう思えた。歴史の事実をもし正しく知りたいならば彼のような語り手を探すことが早道なのかもしれない。本当にその通りであるのか、それだけなのか、などなど少し疑いを持つことだ。過小や過大や色々な捻じ曲げを超えて(間を埋めるのは人の力だ)実感の伴った評価、歴史観を持ちたい。行って良かった。悟られたくないことを隠すたやすさと、隠しきろうとしても滲み出る本当を知った。
2008年02月09日
コメント(0)
-
餃子の毒より危ないもの
○○○保育園職員旅行について節分も終わり「春よ来い♪」と子どもたちに歌いかけながら、今年度ももうすぐ終わることをしみじみ感じます。特に○○先生におかれましては、意味深い1年であったことと思います。1日1日を大切に勤務されているお背中に、私たちも元気をもらってきました。色々なことがありましたね・・・。<中略>1年間力を合わせて保育園をつくってきた仲間との旅行を計画致しました。<中略>今、中国製の冷凍ぎょうざなど、食の面で中国と日本との間が再びギスギスしてくるような世の中の雰囲気があります。日本はしかし中国から様々な文化を継いできました。ランタンフェスティバルは近年規模を大きくされたとのことですが良い文化・素敵な文化だと認めてこそ「一緒にしよう」「私たちもしましょう」となるのではないでしょうか。原爆を投下された長崎の切なる願いは『平和』であります。様々な文化が共存する異国情緒あふれる街並みを歩きながら私たちも子どもたちの未来に一番大切な何かを願う強い心を長崎からいただいてきましょう。
2008年02月04日
コメント(0)
-
協調性の/犠牲になったよ/きなこもち
相次いで、先輩たちから電話で相談を受けた。女は長電話になりがち。目の前には湯気がもったいなくあがっている。食べようとしていたきなこもちが黒砂糖の小さなかたまりがホロホロとおいしそうなきなこもちがみるみる固くなってしまうのを見ながら話していた。相手に、きなこもちを悟られてはいけない。「そうですね」ばっかり言っていた。終わった。もうかかってこないねと無意味に左右確認。「私の可愛いきなこもち」だとか「ごめんね、きなこもちちゃん」とかなでなでしてあげたい思いで、ひと口かみついた。Oh no!!歯の詰め物が取れちゃった(泣)ボンドや糊は塗ってすぐに貼り合せるのではなく少し時間を置いてからのほうが、粘度が上がるのか、よくくっつく。もちも然り。気をつけましょう。
2008年02月02日
コメント(0)
-
冬は本当に鬼なのか
1月が行っちゃった。どうなることやらと思ったぶん、ホッとしている。2月が来ると、春はすぐそこ。先生たちも人の子。病欠もある。忌引きもある。それが重なる時もある。お休みの分を皆で何とかカバーできた。最後には皆ヘロヘロに疲れていたけど。研究会もうまくいった。味方がいっぱいだった。この会場にも、今までのどの会場にも園内研修での、うちの園長以上に鋭く突っ込んだ質問をする人はいなかった。園長、厳しい。求められるものが大きいので日々へこむさっちなのであった。今回の結果から「どこでも大丈夫ね」のお墨付きをいただけた。いつもがアレだから、さっちの発表力にイマイチ不審を抱かれていた。でもカッコよく発表しようなんて無理で、結局いつものさっちだったんだけどまぁ、結果オーライ、合格点だったようです。実力も伴わないうちから担ぎ上げられる時は余裕がないんだろうと思う。幾度か場数を踏んで、情けない思いもしてきたから何とかできるようになった今があるんだね、きっと。普段が普段だからカッコワルイことを恐れないでいけた。人見知りで大人しいのに、時々無謀。わかるまで聞いて1つでもヒントを得ようと追いかけて粘って聞きだしたあの日。。しゃべくり過ぎて司会者にやんわり止められたあの日。。その道で一番偉い人に直に熱血な手紙を渡した採用2年目のあの日。。嗚呼。思い出しても恥ずかしい。「何奴?」とギョッとされつつも、受け入れてくださったことに感謝です。さっちも懐の広い人になりますです。
2008年02月01日
コメント(0)
-
ラッセルだったのか
よく保育で「科学的なものの見方のできる子どもに」と言われる。事実を事実としてとらえる力を・・・云々。そのことってどういうこと?というのを説明する時にクラスに○○ちゃんという子がいて、、というところから話すことはできるんだけどいつも説明が長くなる。そもそも、「科学的なものの見方」ってどこから来たのかなと思ってた。たぶん、これだろうと思う。↓碧海純一「科学的なものの考え方と科学万能主義」『ラッセル協会会報』n.5(1966年7月)p.1-2(=巻頭言)http://www005.upp.so-net.ne.jp/russell/AOMI6-01.HTMつまり科学的なものの考え方とは『ゆるやかな経験主義と穏健な懐疑主義とのむすびついたもの』で科学万能主義ではないよ、ってこと。『ゆるやか』とか『穏健』とかいう言葉からさっちが受ける印象は「女性的」だったり「日本的」だったりする。まぁそういうもののほうが平和にほど近い道を歩む気は、するんだな。って、この感覚的な判断の仕方ってどうよ?これも説明するのが面倒だけどじっくり検証・文書化すれば『ゆるやかな経験主義と穏健な懐疑主義とのむすびついたもの』かも、わからん。さしあたって、バートランド・ラッセル。覚えておこう。
2008年01月14日
コメント(2)
-
浜崎あゆみさんと下ヨシ子さん~点と線~
下ヨシ子さんの預言インタビューが掲載された雑誌があった。2008年の日本の芸能界。中心にいるのは浜崎さんだと。『CDが売れるとかいうのではなく、もっと衝撃的な中身だと思います』・・・※主婦と生活社発行 週刊女性2008年1月1日号より抜粋(『』が目印ね)何となく覚えていて、出てみてアッ、このことだったのか。。と思った。左耳の聴覚をほぼ失っているという事実は少なからずショッキングだったが浜崎あゆみさんの発表の時期や、今後限界まで歌を続けるという意思表明に対してうがった見方をする輩が後を絶たない。されど芸能人、自分の見せ方にこだわるものなのじゃないかしら、とも思う。別に「あゆ」のファンではないけれど。。さっちも自分に喝を入れるために「これから○○をがんばります」なぁんて宣言することもあるから・・・しがらみの少ないところでそれは楽々と^^ナショナルがなくなってパナソニックに統合とかってニュース。CMキャラクターは浜崎さんでしたよね。撮影に海外に行ったことさえもニュースになった。今が良いと判断すべき材料。。人は迷ったらどうする?・・・ということで下ヨシ子さん登場なのではと仮定してみた☆エイベックスさんも松下さんも相談してたかもよ?下さんに、って。政治家や芸能人で下さんを頼る人は多いって話。それだけではなく、下さんという人はもともと実業家とのことで、さっちは知らなかったんだけど、上記の記事の中にあったのだけど『ビニールやペットボトルのキャップとかを油に変える装置』を発明したグループの一員だったり『発泡スチロールを溶かす装置』の特許を持っていたりもされるらしい。これは、思った以上に色んな世界に顔が利く、、というか鼻が利く?(笑)先見の明というの?嗅覚鋭い人とみた。その分、各界から情報も集まりやすいでしょう。何も、下さんがずるいことしたって言ってるんじゃあ、ないよ。情報なり預言なり、誰しも、自分が持っているものを今がちょうどいいね、と思う時、出していいと思う。(色々制約はあるけどね)超能力者、霊能者、ヒーラーなどの肩書き。元々持ち合わせた才覚に情報まで集まると、的中率も右肩上がりなのかしら。。世の中を色んな側面から知っていれば、おのずと見えるものもあるでしょう。ってか、彼女って何者?(笑)競輪のレースを10レース中8レース的中させた女性。さっちの基準は、「本当に偉い人はむやみに威張らない」下ヨシ子さんはどうなのだろう。まだ、よくわかんないや。わずか2ページの記事だもの。。って、そこから想像を広げるさっちもさっち(笑)そのわずか2ページの中に『国が国民をいじめる』とか、政治で『4月に何かがある』とか気になるワードも散りばめられていた。機会があったらご覧くださいな、192~193ページ。ともあれ自分に芯がなければ、持ち物だけ多くても生かされないんじゃないかな。どっちに進んでいきたいのかもわからないなら、迷子も救出しにくい。世の中色んな人がいて考えさせられるものがあります。小さくても心に引っかかった情報が、いつかどこかで日の目を見ることもあるかなぁ。。色んな出来事、色んな人・・・森羅万象、どこかでつながってるんでしょうね。
2008年01月13日
コメント(0)
-
肥えた?
お正月は2日から仕事だったので、正月ボケはナシ!本業は4日からだったけど、まだ子どもたちの登園は少なく。今週からは通常どおりの日々かな。ふと鏡を見ると、何だか顔が丸くなったような??(T◇T)体重計にそっと乗る。そっと乗っても器械は正直だ。・・・七草粥ダイエットでもするか。。そうよ。健康は美に結びつくのだわ、きっと(´▽`)出張に行った時、容器の可愛さにつられて買ったお弁当。素材にこだわり丁寧に作られたヘルシーなお弁当だった。ご婦人お好み幕の内『出雲美人』のおしながき◎島根ワインのちらし寿し・・・赤ワイン、寿しごはん◎煮物・・・鶏の旨煮、竹の子、いんげん豆、椎茸、人参◎魚味噌漬け◎朝鮮人参かき揚げ・・・朝鮮人参、季節野菜◎チーズ◎蟹◎野焼き蒲鉾◎和菓子これで577キロカロリー。さっち、お正月中、その倍くらい食べてたような気がする。。七草粥食べても、新年会でリバウンドするのは間違いない。保育でダイエットかな、やっぱり。こんなさっちでも、今年も健康でいられますよーに。
2008年01月07日
コメント(2)
-
自分は小さい
歌が上手い人は声がフラットしない。って「フラッと」じゃないよ、「♭」。自分に聞こえる自分の声は、人に聞かせている声と同じじゃない。自分の出していると思っている音より若干低い音しか本当には出ていない。この音を出そうと思う音より少し♭してしまうんだ。だから気持ち、高めに、♯に歌うと良い。・・・とわかっていても、歌が上手いわけではないワタシ(笑)自分は不器用だから。。と今年は不器用な分を上乗せしてがんばってみました。そして、これだけやれば、人は息を呑むのだとわかった。いつも名前のわりに、飛べないニワトリさっちなんだけど努力と人の助けで、どうにかこうにか飛び方のコツをつかみつつあります。いい先生になりたい。願い続けたら、どこにいたのか、仲間が出てきた。それでいいんだよ、もぅちょっとだよ、子どもにかけるように言葉をかけてもらうの幸せ。苦しいこともあるから翼、大事にしよう。鯉の価値は泳ぎっぷりで決まるって誰が言った言葉だったかしら。。何が本物かって、それは本当の苦しみ悲しみを知った人たちに本当の喜びがわかるように本物は、そんなところに、たとえ認められなくても存在しているみたい。何が本物やら?さっちがお取り寄せしたくなるくらい好きなお菓子『博多通りもん』も年内の販売再開は困難だって。アーア。。(「香料」と記載すべきところを「ミルクパウダー」と記載していたからだって)色々ある世の中。何かちょっと価値観が変わったり何かちょっとキッカケがあったりすると流されて流されてどんどん行っちゃう。自然に任せていては変なほうに行っちゃうことも多いからちょっと考えて舵をとろう。今年も終わります。空から見ると小さくてかわいい人間の一人一人。みんな何かを思って生きてる。皆様方にとって良い一年になりますように。平和な一年になりますように。
2007年12月31日
コメント(3)
-
さっちゃんは先生になっても、さっちゃん。
昨日、長い長いクラスだよりを発行。A4で8枚だったので、余白を設定し直し、枚数を少なくした。紙がもったいないし、かさばるから。こういうのも将来はメルマガ形式になっていくのかなぁ。。おばあちゃんもおじいちゃんも家族で手にとって回し読みなんていうのはアナログなことなのかなぁ。。地元中の地元!な保育園にいた頃(異動で、です)クラスだよりを発行するのが恥ずかしかった。担任している子のご家族は小さい頃からのさっちを知っていらっしゃる。特におじいちゃんおばあちゃん世代は「さっち先生」でなく、「○○さんちのさっちゃん」なのだ。それでも「先生」と呼んで下さるし「さっち先生に、頼む」と、わざわざ私をご指名下さり。。顔を立てて下さることを(おじちゃん、ごめんね)と感謝していた。そんな、例えばおじちゃんの、地元で根をはって生きてこられた軌跡を肌で感じて育った自分。保育園から見たら「○○ちゃんのおじいちゃん」で○○ちゃん中心な見方をするがさっちが知らないだけで、皆、それぞれの人生があり。学ぶべきことはいっぱい。「○○さんちの」にも助けられた。「○○家」で真面目に生きてきた祖父母や両親を通し、さっちを見る人もある。(これは逆の場合は大変で、そういう見方でその人そのものを見誤ることもある危険は孕むが)それまで先生先生した文章を書いていたことに気付き、改めた。保育士たるもの、こうなければ、、からの脱却。等身大の自分。つまり、『偉そう』な文章を書かなくなっていった。上司から二週間ほど前、ご自身が昔書かれたクラスだよりを見せていただいた。それこそ「○○県の○○先生」と一目置かれている方である。さすがにとても立派な文章だったが、その時(あ、こんな感じでさっちも書いていたな)と思った。立派な文章で、ストレートに言い切るのはすごいと思う。一方、人を遠ざける鋭さをも内包している。「わかってるけど現実はねぇ」とする読み手との間に距離を置いたり「その通り。正論です」で留まって、読み手が自分なりに考える余地を少なくしている。しかし、時には渇望している。「人間、そうでなくちゃ」という正論を欲している。ストレートに言い切れないことで世の中はいっぱいだから希少でまぶしい。周りの色々に思いを巡らしすぎて、言い切れにくくなっているのかなぁ。宝探しは好き。そこは変わらない。さっちは保育士としての視点だけでなく生活者としての自分の視点を捉え直させてくれる出会いからあの子のあの暮らしそのものから答え合わせをしているみたい。
2007年12月29日
コメント(2)
-
あちらは留守にしてますが
他のサイトで日記を書くとお前は何者だ??ということで記事によっては似たり寄ったりな人たちが押し寄せてきたりしてました。怖。というか何か、すごい時間的余裕のある人が多いなと感心。そのエネルギーでもっと別のものが生産できるんじゃ?ともったいなく思う。次々に押し寄せる似たりよったりな反論コメント。それは楽天も変わりないと思うんだけどね、最近ず~っと、さっち大人しいから。怖。に対抗するためつかみどころのなさを醸し出してみたりいや、大した者ではございませんからお構いなくを醸し出してみたり明らかに言い負かすことは簡単だとわかっていても何か、この人言い負かしたら、次の人が現れるのよね。。と分かっていると面倒臭い。そんな暇ない。どうしてここまで常識が通用しないのかな。案外、寂しがりやさん??時々、想像していた。雇用主を考えると可笑しくて小説みたいだけどもしかしてあの人たち、そういう仕事なのかしら。。とも思ってみる。しらみつぶしに、さっちみたいなのを探し出して、構う。だからあんなに熱心なのか!ノルマがあるのかも?しかし最近、世論に負け★が続いてるだけに雇用、増やしているのかな。どうかな。その雇用形態。雇用柔軟型に甘んじているとしたら本末転倒だ。・・・おっと、想像が行き過ぎたかな。行き過ぎた格差社会の背景。。今、非正規労働者が多い訳は1995年に日経連が労働者を三種類に分ける提言をしたことによるそうだ。(それ以前、、提言の前に何らかの大きな意思が動いたってことでしょうね)1.長期蓄積能力活用型2.高度専門能力活用型3.雇用柔軟型エリートか、スペシャリストか、使い捨てか。。使い捨てを低賃金にして得するのは誰か。。さっち、以前に、教育でもそんな動きがあるって日記書いたと思うけど。(できんものはできんままでけっこう、ってな動きを書いた日記)財界も教育界も、全部つながってるんだね。意に沿いやすい、騙されやすい、そういう人を大量生産したい感じで嫌ね。そんな世の中、ロクな方向を向いてないと思うから。
2007年12月28日
コメント(0)
-
M-1グランプリにはエントリーしていません。
発表会が終わった。無事終わった。と日記には書きたいところだが無事と言い切っていいものだろうかと思って。変な汗がいっぱい出た本番であった。ステージ上でお子たちは色々やらかしそのたびにお客さん大喜び。トホホ。。例えば最初のプログラム。1人だけ、違うほうに行き、動かず。もう1人がそちらに行ったのでオイデヨと誘いに行ったんだとホッとしたらミイラとりがミイラに、、の図だった。2人でニヤリ。モウ!と思い、さっちが迎えに行ったら2人で逃げた。そのようなことの数々で・・・マジメなお子はおらんのかと泣きたくなった。もう1つのプログラムの時は入場の時から会場の空気が妙だった。さっちが思うに、マイペースなお子たちにお客さんは期待いっぱいで(笑える期待であった。。)しょっぱなから期待以上におかしかったらしくちょっとのことで笑いやすくなってらっしゃった。アドリブで迫るお子たちにはアドリブで応えるしか、ない。終わって、お帰りの時間。部屋まで迎えに来られた保護者の皆様はニコニコだった。あれで良かったのだろうか。少なくとも、面白かったらしい。さっちは運動会の時も他のクラスの保護者様から「さっち先生は宴会の司会とか上手でしょ」と言われたが誤解である。そんなのやったことないって!(泣)あと3ヶ月。ヤンチャ盛りへの、ひたすら臨機応変な日々は続く。負けるもんか。クスン(ノ_・。)
2007年12月23日
コメント(0)
-
職場のパソなのに~~やってもうた。。
プリンタの調子が悪く、たまっていたjobを消そうとして間違ってプリンタのアイコンを削除!!そういうことしちゃダメだった。それは消した瞬間、嫌~な感じがして、わかった。あっ、しまった!と、とっさの悪あがき。「削除中」と表示のアイコンのコピーをとって貼り付けた。体裁はとれ、表面上はうまくいきそうだったけど、ダメだった。ニセモノだと見破られ、印刷できないの。どうしようと悩むというかボーッとなった。みるみるうちに元のアイコンはいなくなった。大変、寂しかった。生き物ではないはずのアイコンを想うと頭の中で子牛を乗せて荷馬車が揺れ♪たり、異人さんに連れられて行っちゃった♪りした。園長先生に侘びを入れ、CD-ROMを探してもらったが、ない。ネットで入手すれば良いのだけどこれは個人用のパソではないので、何かインストゥールのやり方が違う感じがしてどうもUSB接続ではないみたいだし。役場の人に連絡すると、すぐ駆けつけて下さった。機能していないニセモノアイコンの説明をするのが恥ずかしかった。『システムの復元』も試みたことは内緒にしていた。「あっ、たぶん大丈夫です」と、チョチョイと修復してくださった。師走で忙しいはずなのに余分な仕事をさせてしまって、気の毒で仕方なかった。あなた様は神様ですか?と思った。園長先生から叱られはしなかった。人の情けが身にしみる。「やってしまいました」黙ってはいられない性質で同僚にも眉をハの字にしてトホホ顔で話した。「あらぁ」の後ろに「バッカねぇ」が仄見えるが、それもあったかいものだった。今日は小さく幸せだ。寝る時、泣こう。
2007年12月18日
コメント(0)
-
人生デンジャラスは7の人
どうせいつも微熱で終わるので測らなかったし病院にも行ってない「たぶん風邪」も1日で上手に治して。夕方からゴソゴソと発表会の準備をした。ジャンボ絵本を作ったり、プログラムを作ったり。園に忘れ物を取りに行ったついでにホールのピアノをポロロン♪鍵盤が冷たいッ。。寒くて手が動かないなぁ、、と下手くそなのを寒いせいにした。簡単な曲を弾いてお口直し。下手くそで終わるのは嫌だからね(´▽`)ひと休みして。明日は月曜日ね~と、バッグの中身を整理していてトンデモナイモノを見つけた。・・・正確には、一枚の文書を見直し、「トンデモナイコトに気づいた」、、です。出張を1か月間違っていた。来月の○日だと思ったら今月だった。確かに文書を見て「あっ、1月○日ですねぇ、はいはい」と園長先生に言ったはずだ。どうして間違ったんだろう?無意識に、真実を認めたくなかったのかなぁ。発表会の前で時期的に忙しいもん。出張の内容は、研修会の打ち合わせで、下準備がどっさり必要。あああ~、今頃気づいて。。余計、忙しいじゃん!!と、ガッカリしたのでした。でも出張さぼらずに済んだじゃん?神様が助けてくれたのかなぁ。そういえば、さっちは6の付く日に生まれたけど6の付く日生まれの人は「危機の一歩手前で免れる」運命だそうだ。だから危機も免れるけど、危ないゾーンに行かないので大成功もないらしい。
2007年12月10日
コメント(0)
-
寝せのプロ?より~子守唄と絵本~
よく思うのだけれど保育士ほど子どもを寝かせる経験の多い職業はないのでは?もし定年まで勤めたとして、のべ何人を寝かせることになるのか。。ざっと計算してみたら、何十万人、寝せることになるようで。。あ・・・軽く眩暈が。それにしても、この季節。。風邪で寝苦しいお子たちなのである。ウ~ンとうなされた時、「よしよし。。どうしたぁ?。。」と背中さすりなどの対応のため寝ている子どもたちの至近距離で、背中を丸めてお便り帳を書いているワタシ。。クラス皆でひと部屋に寝ているため1人がワ~~ン!!!と泣くと、他の子も起きがち。起きだすだけなら良いけど、まだ眠いのに~!と他の子までウワーンと泣いて、、「大変なことになりますよ」になる。そんな時、自分の身体の手も足も肘もどこでも使えるところは全部使う。さすったりやさしくトントンしたりすると安心してまた眠りに入りやすいから。ふと見ると部屋にはお便り帳が、あちこち散乱・・・「ワーン」の軌跡である。そこにある物も満足に動かせないジレンマ。。トイレに行けない生理的苦痛も相まりお昼寝中っていうのは見かけと裏腹に、なかなか苛酷な時間だ。でもね。。鼻水が固まって鼻の穴が塞がっていたりする寝顔も可愛い。この栓を取ってあげるのが密かな楽しみだったりする(笑)お昼寝といえば。。だいぶ前の日記で子守唄の意味を少し書いたのがあったはずだけどさっちは1日の園生活の中で1つも絵本と子守唄を提供しないってのは食事を食べさせてあげないみたいな罪悪感を感じる。あれから数年たって読みつづけ、歌いかけ続けたらどうなるかがほんのりとわかってきた。担任したクラスの子の数年後も、伸びやかによく歌っている。午睡の時にしか歌っていなかった歌を数年後いきなりピアノ伴奏してみたら初めてなのにいきなり声を揃え、スラスラと歌い出したのにはビックリした。心のどこに残っている記憶なんだろう。こんなことが去年もあったなぁ。「だって○○組の時、さっち先生がお昼寝で歌ってたでしょ」当然のような顔。「それもあるけど、皆が静かに聞いてくれてたからよ、頭の中で考えながら」と返した。(ちなみにさっちは子守唄と名のつかない歌も、子守り唄にしていたりしてます)双方向に思いが行き交っていたからこその落ち着いた歌いっぷり。「なんか、みんな、すごいね」と話した。子どもたち、シィンとなって聞いていた。絵本。集中力やイメージする力がついている。ごっこ好きな子になっている。遊びを豊かに創り出せる。ステキなのは、人の気持ちに寄り添うこと。小さい頃から一緒にいた仲間との別れで涙を流す。仲間がもうすぐ引っ越すとわかった日から食欲が落ちたりする子までいた。給食を前にハラハラと泣く子の手をずっと握るのは、その引っ越す仲間であった。お母さんに「寂しい」と訴え、家族で引っ越した子の話をしみじみとした家庭もあった。子どもたちのそんな姿に大人も心うたれてしまう。。忙しくて心身キリキリしている時、イライラしてしまう時歌うことで自分も楽になって。絵本もだけど、子どもたちの反応をその場でダイレクトに感じ充実感で満たされ。イライラした気持ちも替え歌にして歌っちゃったりしてまたスッキリと子どもたちに向き合えたりする。さっちから叱られても、この子たちはさっちから嫌われてるとは思ってないなぁ。そのことが嬉しい。親やじいちゃんばあちゃん、ご近所の人たちの肉声の中で自分自身そのように育ててもらった。メディア漬けだったりしてもし小さい頃に肉声から遠い保育を受けてきた人がいたら我が子に接する時に取り戻すといい。休み休みでもいいから続けることで子どもにも自分にとっても、良い。ちょっとやそっとじゃなくならない生きる力に通じる。取り返せるから心配しないで。
2007年12月07日
コメント(0)
-
象がいい~と、ジャムがいい~と、通りゃんせはダメェ~の関係
家族が買ってきた微妙な象の置き物にデジャ・ヴ。今思い出し、開かずの扉を開けたら。。あったよ象さん。木か布かの違いなのであった。あったよ象さんのほうは、ビニールにくるまれ、まだ開封さえ、されていなかった。。今回のも、何年後かに見て、ワーイ、新品☆な予感(笑)人にはそれぞれ、おみやげ選びに関して傾向があると思う。さっちは、ジャムなどの小瓶に弱い。なぜに?単に美味しそうねぇという直感とご飯大好き人間ゆえの、パンの文化への憧れがいつも心の片隅にあるのと大きいなら買わないけど、小さいならまぁいいか、という量の問題とこの瓶カワイイ~、再利用できるかも的な見通しの甘さによるものとささやかなおみやげを買ってるわワタシ的なナルちゃん魂をくすぐるのと。。色々重なって、色とりどりに私の心を揺さぶるの。象が呼んだからそこに象があるから・・・ってな理由にも、少し掘り下げて考えるといくつか箇条書きにできるのだろうということは想像がつく。さぁて。『通りゃんせ』であるけども保育園で普通に歌っていた。「帰りはこわい」ってとこで緩急つけて歌うのが好きだった。でもこの歌、歌っちゃダメな歌だった?というのを聞いてええっ。。と色々調べてみたけれど自分の中で(いいんじゃ?)という結論に達し今後も歌うことになりそうだ。そのことで誰かがダメっていうのをいちいち自分も真似しなくていいし納得したら真似すればいいかな。。と考えた時象とジャムのことが頭に浮かんだ。人にはそれぞれ傾向がある。気になるところもそれぞれでしょうよ?ダメって最初言った人の前に、ダメじゃないのかなぁ~気になるなぁ~とふわふわ思った人が何だかいるような気がしてる。最初の最初ッから「ダメです」じゃなかったはず。と思えた。人の噂じゃないけれど自分のところに届いた時に、そもそもと違う、何か変なことになってないかな。
2007年12月06日
コメント(0)
-
気になるおしゃべりさん
身近にいる、よくしゃべる人の中に気になる人はいないだろうか。どんどんどんどんしゃべっていかれ、こちらは相槌をうちながら聞いていて。。聞きながら何か引っかかるものがある。自分のことばっかり延々と話され、その内容もさることながら口をはさむ隙もない。やっと口をはさんでも適当に無視されてるような。。ん~~??ワガママなのかなぁとチラッと思う。よく自分や家族の自慢ばかり話す人がいてそんな人は自信がないのかなぁって感じをさっちは受けるのだけどそれとはちょっと違うような気がする。話の内容や話し方が明るくても、何か気になる。何をそんなに聞いてもらいたいのかなぁ。いくら話しても安心しないのかなぁ。理屈はわからないけど、聞いてあげなくてはいけないような気がする。(そのことが本当に言いたいこと?)と思っても遮らないほうがいいような。話したいだけ、話してくれたらいい。本能みたいな部分で、そう感じる。積極的でなくても。。少なくとも、(いるよ)(見てるよ)という位置に。答えが明快に見つかるなんてことは少ない。答え合わせみたいに、ジグゾーパズルのピースがカチッと合ってあっ、解けたぁ♪と思っても、まだピースの周りはふわふわしてる。ふわふわのままでも、どうにか明るいほうへ漂っていくと、いいね。と言いつつ、私が、私が、、な内容になりがちな自分の日記に今気付き、ガーン!!さっち、実生活では聞き役が多いんだけど。。(お子たちには、言葉のシャワーかける側かな)みんなわりとそうなんだろうか。。
2007年12月05日
コメント(0)
-
アサショウリュウと書いてほとぼりと読む
東国原知事のあの発言はどう収拾がついたんでしょう。徴兵制発言。丸く収めようとしても後味が。。何だかなぁ。夏にちょうど宮崎に行く機会があった。知事登場。(ん?何か、声が割れてる、、)と思ったらその後の報道で、あれは病気だったとのことを知った。もぅいつの間にか良くなってらっしゃるみたいね。あの時。知事は県と市の財政の違いを話された。わかりやすい話で、笑い声たてる人も多かった。ウケを狙ってるなぁ。。とさっちは思った。かくいうさっちも(どんな話をするんだろ?)と耳を敏感にして聞いていた。このような好奇の目たちを意識して話されているのには違いないだろう。『わかりやすい』ということのマイナス・イメージを珍しく持ったのが最近ではコイズミさん。数年前から、さっちが心配していたことが、この人で決定的になったな。格差が今後益々開くとか低いほうに合わせられるとか、そんなの。 あの頃。 民が善玉で官が悪玉みたいな感じで捉える人が多くなって 働いても働いても、いち公務員は肩身が狭かった。 さっち、今も引きずってるかな。。なのに 郵政民営化を今頃アソウさんが批判してる!反動が来る。反動。。「美しい国」はわかりにくかった。でも部分的にはこれまたわかりやすく右寄りなアベさん。強引に通した法案の数々。。今はどうよ。『わかりやすい』の反動って何だろう。若者は軍隊に行け!・・・一見とんでもない。でも、今なら行く人も結構いるかもしれないというのが怖い。もし数年でも安定した収入があるなら?行くことにより何かの保険がついたりの特典があったら?チラッとでも軍服着た自分を想像しはしないだろうか。兵士はなぜ兵士になるのか。それは、そんな境遇を人為的につくれば可能。選択肢を狭くするというか。そんなに難しくなく人為的につくれるもんなんだなと、、思ってしまった。色んな人のくらしに思いを馳せると、そうならなくてもいいはずだったのでは?と考えてしまう。だから何か世の中の流れをつくろうとがんばってる人たちに逆風がきつい時は、真逆な意思の邪魔者があるってことで。明らかに自分に不利なこと→わかりやすい。巡り巡って自分に不利なこと→わかりにくい。世論。人々がついてくるまではタイムラグがある。でも時間おいてもダメなこともある。「決定的」な、下手な発言や行動をしないには本心から、人間を尊敬することだな。それは世界で通じる賢さだと思う。・・・悪いことをする人の心情を推し量れる自分って結構なワルなのかもしれないわ。。
2007年12月03日
コメント(0)
-
『せかいでいちばんつよい国』にウサギがピョンピョンとんできた
『せかいでいちばんつよい国』デビッド・マッキー作 なかがわちひろ訳光村教育図書(株)から出ている絵本。以前から気になっていたけど、やっと読んだ。多くの人の頭の中に思い浮かぶんじゃないかな。これって「あの国」や「この国」が風刺されているんじゃ?と。「あの党」や「この党」にも置き換えられるかな。他にも色々。。でもそうやって「自分は違うところにいるもんね」と線を引くと大抵の場合、学びが浅くなる。そして自分は偉いと変に誤解する。あんまり自分を高いところに置かないほうがいいみたい。去年の今頃、灰谷健次郎さんの『太陽の子』を読んだ。読んだことを上司に話すと「あぁ、昔流行ったよ。『兎の眼』とかね」(昔なのかぁ)と思いつつ、流行から遅れついでに一年置いて、今年は『兎の眼』を読んでみた。読後感。。明るい兆しが見えて終わっているのだけど、1つスッキリしないこと。それは、「自分は違うところにいるもんね」と線を引く人の存在。う~ん、、何と言ったらいいんだろう。種類が2つあって。まず、(自分はその問題に関係ない)と無関心な人がいる。これは、イジメ問題などでよく言われる「傍観者」というような立場で明らかに、改善の余地あり、と読者に感じさせるもの。これはわかりやすい。もう1つが、(今まで見えなかったものが見えるようになった自分とは分かり合えない)とあきらめているような、、これも人の絆を切るほうにいっちゃう。本当は自分だって、少し前までは(見えなかった側)にいたのに。。せめて自分に近しい人ぐらいは、簡単にあきらめないで、つながりを切らないでと思う。そんなに世の中、悪い人はいない。そして、そんなに世の中、立派な人もいない。何かと出会って、触れて、少しずつ変わっていく。わかんないけど、さっちも母などに対して(昔ふうの教育を受けてきたから、何か考え方に根深い違いがある)と思う。でも、母から昔の話を聞いてみると、理論はなくっても生活の中に(すごいなぁ)と感じる事実がある。母のそのまた母の時代のことなども、聞くと面白い。面白がると、母も面白そうに話す。例えば、ハンセン病。強制隔離とか、さっちたちは勉強し(酷い)と思う。そして(たぶん母たちも差別意識ありありなんだろうな)と思い込む。うん。ここ↑が落とし穴。何だかね、その時代の人々を一緒くたにしちゃいがち。でもよく聞いてみると昔、母の実家の近所でハンセン病の人を匿っておられたそうだ。エエッ!ばれるでしょ?とさっちなぞは思うのだけど「そこの家の人たちが、いないと言うんだから隠したいんだろう」と村中の暗黙の了解で、誰も告げ口しなかったそうだ。かと思うと「ハンセン病だけど普通に農作業して働いていた人もいた」エエッ!どうして?いいのかいそれで、、ってさっちはまた思うのだけど「そこの家の人たちが、違うって言うからそれ以上詮索しなかった」。。。いい具合に大雑把で、好きよ。そういうやり方、ある意味冒険だけどさ(笑)国がどうこう言う前に実感として近所の人たち、別に感染もしないし大丈夫っぽい、と何となくわかるんじゃないかな。さっちには、できないかもしれないな。すごい。と思った。家族が当たり前に一緒に暮らせる世の中には、本当にはまだなっていない。子育ては無理では?と、例えば障害を持っている人から我が子をやんわり?引き離したり。進みたい人生に、身を置けたらいいな。邪魔者は、やさしい顔してるかもしれない。それにしても同時期に読んだ2冊は混じる。さっちの頭の中は、渦を巻いているんでしょう。
2007年12月01日
コメント(0)
-
荒らさない荒らしとゆーか
とある有名ブログで実験をしてみました。(楽天ではないです)日記が気に入ったら拍手アイコンをクリックします。↓ブログ管理人にメッセージを送りたい人のために「名前」「本文」記入欄が現れます。↓ここで、「名前」欄に名前を記入せず、本文の出だしを記入します。「名前」「本文」と続けて文章になるように。これをしばらく続けた結果、昨日の日記あたりから「名前」から本文を始める人が多くなってきたみたい♪♪愉快犯さっち。「ちっちぇ~」し、「それが何か?」って言われればそれまでなんだけど(笑)
2007年11月30日
コメント(0)
-
製造年月日の表示を求む!
柿の葉寿司を食べてみました。まさか柿の葉自体がネタではなかろうかと変な心配をしていたけれど(←あほ)杞憂でした。美味しい^^(柿の葉って丈夫なのよね。さっちも保育室の柿の木の壁面飾り、葉っぱは本物を使って手抜きしてます)柿の葉寿司は金沢の。奈良にもあるって。色んな地域の色んな食品。中国って、大丈夫かいなと思っていたけど最近日本の食品も表示が偽造されていたりして安心できません?かな。さっちが去年・今年と「これ、嘘でしょ」と思ったのが某メーカーの「栗豆腐」です。天津甘栗を使用してあります。これは豆腐じゃなく「栗ようかん?」ではないかい??でも『好意的』に思いがけず、デザートとして美味しくいただきました。今年は(これ去年見たような?)と食べてみて(やっぱりアンタだったね!)と再会を嬉しく思ったのでした。話は戻って、、「賞味期限」について。生ものに表示される「消費期限」を過ぎた食品はともかく、「賞味期限」を過ぎたものを売ってはならないという法律はないと思うの。以前さっちは色んなメーカーさんから賞味期限について「長めに設定してある。表示してあるのより1.5倍くらいの期間は、まず大丈夫」という話を聞いていました。(もし短めに賞味期限を設定するなら、その分添加物減らしてくれたほうがありがたい。。と思うのはワタシだけ?)だから思うに、「製造年月日」も表示してほしいな。今の表示の仕方では、どこから1.5倍を計るのか分からないから。そうしたら消費者自らの判断で、お腹痛めたりしても食品会社の責任にはならない。そういう判断って人間らしい行為です。大丈夫かどうか目で確かめて匂いをかいで、、大人が日常の中でやってみせなければ子どもたちは最初からやらないんじゃないかなぁ。もったいないもんね、捨てるの。腸炎ビブリオとかアニサキスとか少~し頭に置いても美味しいもんは美味しいっしょ。モグモグ(^~^)
2007年11月25日
コメント(0)
-
おひさしぶりです
勤労感謝の日です。皆様、おつかれで~す。時にはホッとできたら良いですね。心身の健康には気をつけて良い仲間の中で生きていけたらいいですね。さっちが仕事してるのは、もちろん生活のためですが意欲的に仕事をしていくに、原動力となる対象すべてに今日は感謝いたします。今年度は4月3日で日記が終わってる、、典型的な3日坊主のさっちも外部に保育の姿勢を認められるようになってきました。中学の先生や高校の先生から褒められたり握手を求められたりして。。・・・スタア?(笑)はい、ちょっとテングになってました。この、誰かを感動させる自分と日々へなちょこな保育をしている自分と何か隔たりがあるんちゃう?と考えこんだりもして。どうも過分な評価をいただいていると思えます。ちょい、プレッシャーです。。プレッシャーを感じている時、見知った顔がチラッと見えると途端に安心する。仲間って大切でありがたいですね。でもそういう仲間がその場にいなかったら、初対面なその場にいる人がわかってくれることを信じてひたむきに事にあたるしかありません。園長から何回も注意を受けたこと↓「さっち先生はね、、話が脱線しがちだから、よく整理してまとめて発言するように」自覚あり(泣)話しているうちに、どこにたどり着きたかったのか、いつもわかんなくなっちゃうの。みんな話すの上手だな~と思う。なんで自分はできないかなぁ。。年が明けてからもイヤーンな場に2~3、引っ張り出される予定。ビビり屋で口下手なさっちゆえ、内心不安でいっぱいですがどうせしなくてはならないことなら自分を良く見せようなんて浅はかな考えを封印しそのまんまで勝負したいです。・・・と宣言することで自分を追い込むのであった。初めてのことは、いつもこうやって乗り越えてきたから今度もどうにか逃げずに行けるでしょう。そうやって初めてのことじゃなくなると、今度からは少し気が楽。だもん。
2007年11月23日
コメント(0)
-
臨床例っていうか何ていうか
溶連菌感染症について。さっちが思うに罹った子は多かれ少なかれ「気持ちが沈む」何だかブルーな雰囲気が漂っているのだ。気ままな家庭と違い保育園という集団生活だからってのもあるのかな。そんな様子の子の舌を見たりして「もしかして」と疑ったらそうだったり。。「治りつつある状態」「罹った形跡がありますね」の診断がおりたりしてね。そんなこと医学書とかに書いてないかもしれないけど。。子どもたちにしてみたら見た目以上に「気持ちが弱る病気」なんだと思う。給食とかの様子でわかる。身体の中で起きているモヤモヤ?を言葉に表しにくいみたいだけど。大人でも気持ちが鬱々したら、「もしかして」の溶連菌感染症かもよ?お薬はきちんと飲んで完治させましょう。
2007年04月03日
コメント(0)
-
行く人来る人来れない人
お昼ごはんを子どもたちといただいてから異動される先生方を玄関で見送った。別れと出会いの4月です。出会い、、なんだけどうちの園に異動して来られる先生のお1人がみえなかった。しばらく病気で休まれるとのこと。。何だか不安なさっちです。異動は、行く側も受け入れる側もドキドキです。担任決めの職員会議。これをしないと仕事が進まないからお1人不在のまま行われた。夜は2回目の送別会。(1回目は内示の段階でしているからです)「どうだった?」新しい赴任地のことを聞きまくり(笑)昨年度は色々あったけど乗り越えてきた仲間たちとサヨナラ。ホント、濃い一年だった。
2007年04月02日
コメント(0)
-
何に対して謝るのか
ブッシュが謝ったけど自国民に向けてだった。イラクに向け謝ることが彼が死ぬまでにあるだろうか。日本でも一回謝ったものを訂正したり起こったことをなかったことにしたり自国は「美しい国」なんだよ、と言わんばかりの怪しい動きがあって嫌だわ。。と思ってるさっちです。国内で不誠実なふるまいが平気でできるならば国外では余計にそうだろう。。と勘ぐり勘ぐり。保育士として見るとあなたの子どもさんの良いところは?と問うと「やさしいところ」それは大多数がそうおっしゃるの。しかし保育園で、友達の中で本当にやさしいか?と考えるとう~ん。。子どもたちはどの子も「やさしさ修行中」。我が家で家族にやさしい子が「自然と」友達にもやさしくなる、、そのことをさっちは敢えて否定する。そのことは大切な基礎だと思うけどそこ止まりになっている、育ちそこなわせている環境ではないかと今一度確認が必要ではないかと思う。安心はできない。昔もだと思うけど、突然キレル園児さんも普通にいます。1分前にはやさしい行動をしていたのにと極端さに驚くことも。色んな子がいるし、いていい。その子に合った保育をしていくだけ。とても。。とても冷たい言動をとることも子ども集団で、ある。その場の1人1人の心情を思い、ショックを受けつつもわかりやすい言動をしてくれる今、今は育ち時、チャンスでもある。「○○ちゃんのお姉ちゃんは学校でいじめられて熱が出るほどだったよね。先生も誰も大人が見ていないところでいじめられていたんだ。先生や大人が見ているところではできないくせにどんなにお家の人の前で良い子でもイジメをしていた子たちの心は真っ黒だと先生は思う。ずるい。卑怯だと。せっかく生まれてきたのに。みんなせっかく生まれてきたのに。○○ちゃんが今言ったこと、したことも、お姉ちゃんを悲しませた子たちのやり方に何だか似ていて先生は心配しているよ。。」その子から「ごめんね」がキレイに出ないで、かえってホッとした。すぐに出る「ごめんね」は、さっちに対しての「ごめんね」だったりもするから。『とりあえず』謝る時ってどんな時かな。簡単に訂正できるようなふうな『とりあえず』に見せかけると、、便利なんだろうな。気まぐれに、自分の快を得るためだけの謝罪を、やさしい行動を、さっちもしていないかな。
2007年04月01日
コメント(2)
全1362件 (1362件中 1-50件目)