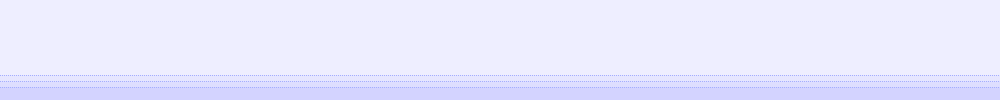新説【竹取物語】・・・1
k_tombowの『新説・竹取物語』
k_tombowの『新説・竹取物語』
k_tombowの『新説・竹取物語』
妖精は宇宙人か? なんていう“思いつき”を連載中に、
『かぐや姫』 についての、リクエストを頂戴しました。
いずれ気が向いたら・・・と思っていたのですが、
この際、少しずつでも、書いてみようかと、思い立ちました。
そのようなわけで、これまた気まぐれに、
ぼちぼちと、思いつくままに書いてみます。
ストーリーを決めてあるわけではありませんので、
さて、どんな進行になりますやら。
なお、時代考証などは、思いっきり無視して、進行します。
結末は、もしかしたら 『つまらない落ち』 が、待っているかもしれません。
それと、 18歳未満の方は、保護者同伴で お読みくださいますように、
お断りいたしておきます。
未成年者注意 の部分は、 セピア文字 で表示します。
お子さんに内容の質問をされた場合には、次のようにお答えください。
「大きくなったら、解るから。大人になるまで、待ちなさいね。」
なぁんて、思わせぶりに・・・。
楽天さんに『削除処分』を受けちゃったら、どうしましょう。
【助命嘆願】を、出して戴けますか?
いや・・・そのぉ・・・『文学作品』ですから、多少のことは、大目にみて戴けるかと。
期待外れであっても、クレームはいっさい受け付けません。
『誇大広告だ!』 とか、 『不当表示だ!』 はもちろんのこと、
『もっと過激に!』 といったご要望も、無視いたします。
たっぷりと条件を付けたところで、始まり始まりぃー!
★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●
夕焼け空の紅色を、名残の色に纏いながら、
日増しに暖かくなる、春の宵を割るように、
大きな満月が、ゆらりと姿を現した。
満月は、天空に上るにつれて、白さを増した。
輝きが、凄絶な蒼さを感じさせるのは、冬が夜空を支配しているからだろうか。
しかし流石の冬も、次の満月の頃には、
朧を揺らす春風に、その力を譲り渡していることだろう。
★ ● ★ ● ★ ●
のどかな山里の、小高い丘の麓で、その満月を見上げる
ふたつの影があった。
(今日のところは、ここまでで・・・。 って、この先は、まだ考えていなかったんだろ?)
(だって、いきなりのスタートだったんだもの。)
時々、こんな 『一人つっこみ』 が入ります。

新説【竹取物語】・・・・・・《2》
若い男は、職人のような装いだったが、
若い女は、公家の娘のような、上品な雰囲気を、漂わせていた。
満月の白い光は、二人の影を、斜面に咲く蕗のとうに、
柔らかく投げかけている。
春間近ではあっても、長時間佇むには、少しつらい。
身体を寄せ合っても、温もりは、月に吸い取られるようだった。
陽が落ちてから、数時間は過ぎているだろう。
二人は、それぞれの家人が休んでから、そっと屋敷を抜け出して来たのである。
(ところで、どうして満月の夜なの?)
(満月の夜を選ぶのは、もちろん、足下が見えるからさ。)
(単純。)
(だって、昔は街路灯なんてなかったし、二人とも栄養が偏っていて、
暗いところが見えにくくて・・・。)
(色気、ないじゃないか?)
(現実は、そんなものさ。)
このようにして、何度かのデートを繰り返した二人だが、
将来を語り合うには、遠慮が先立った。
身分の違いを想い、どちらからとも『将来』を切り出せないままに、
逢瀬を重ねていたのである。
しかし会うことができるのは、27日間に1度だけ。
満月の夜だけである。
最初の出会いから、まだ6回も会っていないのに、
秋が過ぎて、冬が過ぎ、春が訪れようとしている。
娘は、周囲からの縁談を断り続けて、いぶかしがられながら、
まもなく18歳を迎える。
そもそもの、二人の出会いは、供を連れて買い物に出かけた娘が、
いつもの店に立ち寄った、1年前にさかのぼる。
都に修行に出ていた店の2代目が、たまたま戻って、娘の応対に出たのである。
そこでその・・・『一目惚れ』というわけである。
相思相愛になったのは良いけれど、店に出向いても、
ただ黙って、見つめ合うばかり。それ以上の進展など、あろうはずもない。
しびれを切らした娘のほうから、男にそっと、合図を送った。
『次の満月の夜に』という。
満月が見られない雪の夜には、わずかな雪明かりを頼りに、
半時(1時間)にも足りない時の出会いを、楽しんだこともある。
そのようなわずかばかりの回数を重ねて、今、この朧な月を、
見上げているのである。
(『小高い丘の麓』って、言ったよね?)
(うん。どうして?)
(冬なんか、寒くない?)
(丘の麓に、粗末な作業小屋があったのさ。)
(それを先に言ってよ。)
(外で会ってるなんて、どうして考えるの?)
(月を見上げる、って言うから。)
(成り行き任せだから、後でフォローすることもあるわい。)
二人は、次の出会いを約束して、名残を惜しみながら、
小屋を後にした。
月は二人の影を、長く伸ばして、山の端に隠れようとしていた。
梟が『ホウホウ』と鳴いて、帰宅をせかす。
二人は、梟の眼を羨んだ。
夕暮れとともに巣へ帰る、雀のような自分たちの眼が、
なんとも、もどかしかった。
(今日はここまで。)
(まだ、1日分も進んでいないじゃない?)
(あわてるな。)
(でも、こんな展開じゃ、いつまで続くかと想っただけで、ダレちゃうよ。)
(次から、スピードアップしようか?)
(頼むわ。それと、『二人』には、名前もないの?)
(そうか。忘れていたよ。男には、“継男(つぐお)”で、
娘には“清”なんて、どう?)
(その心は?)
(家業を継ぐ男と、『清少納言』は“清”が名前だろうから、それにあやかって・・・。)
(ひどい安易さだ。)
(だから、思いつきで進めている話だから。)
(こんなのばっかり・・・。)
と、こんなところで、次回からは、『つっこみ』の会話も少なくして、
スピードアップを心がけてみましょう。

新説【竹取物語】・・・・・・《3》
逢魔が時を過ぎると、あたりは急速に暗さを増す。
闇をすかしても、人影さえも見えない。
隣に立つ人の気配も、わずかな衣擦れの音で、それと解る程度である。
都でも、あまたの“物の怪”が出没しているということで、
その騒動が、遠く離れた南の国にも、噂として伝わっていた。
“鼻をつままれても判らない”闇夜が、普通のことだった。
夜に出歩くには、行灯の光だけが頼りだが、人目を忍ぶ二人の出逢いには、
その光さえも、憚られた。
明かりを頼るには、満月以外に、適する日がなかったのである。
咲き乱れた菜の花も、終わりを告げていた。
粗末な小屋に漏れ入る、月の白い光が、二人の身体をも、白く輝かせた。
『清』の柔らかな身体を、月の光がさらに丸く包んで、足下に優しい影を落とした。
昼に見る姿とは、人が違ったような『清』を見て、『継男』は気持ちを抑えきれなかった。
『清』の眼も大きく開かれて、きらきらと、月の光を映している。
(この色は、18歳未満の方は、保護者同伴で・・・ね。
え? 手遅れでした? 申し訳ない。)
それからも、二人の忍び逢いは、月ごとに続けられて、夏が過ぎる頃まで続いた。
『継男』は、『清』の異変に気づかなかった。
が、秋の気配が深まる頃に突然、『清』が姿を見せなくなったのである。
供を連れて顔を出していた、『継男』の店にも、足が途絶えた。
いきさつに思い当たるところがなく、『継男』は悩んだが、
探るには、身分の違いが障害になり、『清』の屋敷の周囲をただ当てもなく、
彷徨うばかりだった。
『清』の消息は、そのまま途絶えてしまった。
だがやがて、屋敷を追われるように出された『清』は、供も連れずに、
ひとりで『継男』の店を訪ね、そのまま彼に救われるように、
何事もなかったように、夫婦になったのである。
消息を絶った期間について、『継男』は一度だけ、尋ねたことがあった。
だがそのときに、『清』が涙にくれて応えを拒んだために、
それ以降は、不審を感じながらも、その話題を避けていた。
何よりも、1年半ぶりに出会えて、妻に迎えることができた幸せを、
大切にしたかったのである。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『清』が『継男』の前に、再び姿を見せた時から、1ヶ月ほど遡った、
満月の夜のことである。
昼の朧が、そのまま続いたように、月も潤いを持って、大きな虹色の傘を掛けていた。
都から遣わされた官吏の『憶良』という男が、妻とほの暗い明かりを頼りにして、
読書にふけっていたときに、かすかに子供の鳴き声を聞いたのである。
「なぁ、どこかで子供の泣き声がしていないかのぅ?」
「あなた、子供が亡くなってまだ三月。気の迷いでしょう。」
「うむ。あの子を失ってからというもの、火が消えたような寂しさで、たまらん。」
「流行病で、村の子供が次々に亡くなって、『かわいそうに』と思っていたら・・・。」
「まさか、吾子が亡くなるとは、思いもせんだて・・・。」
「おや? あなた、やはり子供の・・・。」
「しかしいくら満月とは雖も、こんな夜更けに、子連れが山の上を歩くかのぅ。」
「狐が、悪戯をしているのでしょうか。」
「麓の小屋では、時に人を誑かそうとする“悪狐”がおるようだが。」
「さてさて、迷い旅人でも騙されていなければ、よろしいですわねぇ。」
「気がかりじゃ。様子を見てくるとしようか。」
「お頼み申します。」
山の上とは言っても、小高い丘の上に建つ、貧しい官吏の家である。
冬は寒さをどうにか耐えて、梅雨には雨を凌ぐほどの粗末な小屋でしかない。
静かな夜には、かなたのかすかな物音さえ、壁の隙間を擦り抜けて、
入り込む。
いつもならば、塩を舐めながら濁酒でも飲んで眠ってしまう憶良だが、
月明かりに誘われるように、読書にふけっていた。
彼『憶良』は、大変な子供好きとして知られ、吾が子や、村の子供たちと遊ぶことを、
無上の楽しみにしていた。
村人たちも『憶良』の優しさを心得て、赴任当初から親しみを寄せてくれていた。
その『憶良』が、目に入れても痛くないほどに、大切にしていた息子を、
3ヶ月ほど前に、亡くしたのである。
そのようなときに、子供の泣き声を聞いたのであるから、
様子を見ずにはいられない。
「麓の小屋の裏には、竹林もあるし、森もある。
狐ならば、こんな山の上に来ずとも、よかろうに・・・。」
ひとり愚痴をつぶやきながら、月明かりに白く照らされた細い道をたどり、
麓の作業小屋まで、降りていった。
次第に、赤子の泣き声が、近くなる。確かに、狐の仕業ではなさそうである。
彼に与えられた、わずかばかりの耕地に迫るように、竹林が覆い被さっていた。
赤子はその中で、泣いていた。
『憶良』が、数日前に伐り取った竹の根本を見やると、そこには高貴な身分を感じさせる、
あでやかな着物に包まれた、珠のような赤子が、そっと置かれていた。
まだ近くに誰かが居そうな気がして、『憶良』は竹林の奥を、透かして見た。
月の光が、揺れる竹の葉陰を落とすばかりで、人影を窺うことは、できなかった。
『憶良』は、失った子供に替えて、“神仏がこの子を授けてくれたもの”、
と思うことにした。
赤子の生まれが高貴であることは、衣装だけでなく、
竹で編まれた埋籠に添えられた“匂い袋”からも、偲ぶことができた。
『なにか、特別に訳ありな“公家”のような家柄が、儂にこの子を託そうとしたのだろう。』
という予測は、『憶良』にも、容易に察せられた。
「麓の竹林に、可愛らしい赤子が居ったぞよ。」
「狐の子ではなくて、ヒトのお子でございましょうや?」
「おう、珠のように、元気で可愛らしい子じゃ。」
「御衣装が、何とも高貴そうだこと。」
「それに、匂い袋も、得も言われぬ佳きものであるし、のぅ。」
「あら、なんと芳しいこと。」
「今になって気づいたか?」
「あなたがお入りなさってから、気づいておりましたが、匂い袋とは。」
「いずれ、何処のお方か、手懸かりになるやも知れん。大事にな。」
「その日まで、この子は大切に、お預かりいたしましょう。」
「それにしても、なんと芳しい(かぐわしい)ことよ。」
「女の子ですから、“芳姫(かぐわひめ)”とでも・・・。」
「それがよかろう。」
この日を境にして、『憶良』の家庭にはまた、以前のような明るさが、
戻ったのである。
子供好きの『憶良』には、かけがえのない珠玉が、転げ込んだのだ。
この後間もなく『憶良』は、後世に残る、和歌の一首を詠んだ。
“銀(しろかね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる宝 子にしかめやも”
(お? ようやく、『かぐや姫』の登場だね?)
(登場は良いけれど、何だ? 匂い袋が芳しいから、『かぐや姫』だって?)
(竹から産まれたっていう物語は、“竹籠”に入れて捨てられていただけかい。)
(ひどい展開になって来ちゃったなぁ。)
(それよりもひどいのは、『かぐや姫』の育ての親は、『山上憶良』だってぇの?)
(時代が、無茶苦茶になりそう・・・。)
(細かいことに、こだわるな。)
(それで良いの?)
(どうせ『憶良』の憂さ話《うそばなし》だもの。)

新説【竹取物語】・・・・・・《4》
憶良夫婦に大切に育てられた『芳し姫』(かぐやひめ)は、
健やかに成長するにつれて、いよいよ光り輝きをいやますように、
高貴な雰囲気を、全身に纏うようになっていた。
幼友達と遊んだ日々が、いつしか遙かな思い出の中に、
閉じこめられようとしていた。
育ての親・憶良たちは、かぐや姫に生い立ちを伝えてはいなかったが、
狭い住まいの中には、その佇まいに相応しくない調度品や、
いつまでも大切に保存されている、赤子の衣類などが、
自然と目にとまり、違和感を覚えるとともに、友達の振る舞いにも、
よそよそしさを、感じ始めたのである。
里人たちは、かぐや姫が成長するにつれて、その自然に身に付いた雰囲気の中に、
身分の違いを感じさせられて、疎遠になるわけではないのに、
なぜか、近づきがたさで、顔も合わせられなくなっていた。
かぐや姫は、今までのように人々と接したいのだが、
人々の方が遠ざかる。
理由が判らないままに、少しずつ外に出る機会が減っていった。
里人の噂は、『芳しい姫』からやがて、『輝かしい姫』という意味を込めて、
『かぐや姫』とされて口の端に乗り、都にまで届くようになった。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
実家を追われて『継男』に嫁した『清』は、それなりに幸せだったが、
残してきた娘を忘れたことは、なかった。
折に触れて、人を介して様子を探らせたが、状況はなかなか、
漏れ伝わってこなかった。
ただひたすら、無事な成長を、祈るばかりだった。
そうこうするうちに、1年も過ぎた頃に、
「娘は、とうの昔に捨てられたようだ。」
という噂が、耳に届いた。
どこに捨てられたやら、と気に掛かり、手を尽くして行方を求めようとした。
しかしその苦労は、必要がなかった。
噂が駈け巡りやすい田舎のこと。
子供好きの官吏が、『竹から産まれた珠のような女の子』を、この上なくか可愛がっている、
と言う評判を、すぐに探り当てることができた。
都から来た公務員が、拾ってくれたのだ。
『清』の両親も、赤子の将来を託す相手として、場所を選び抜いて捨てたのだろう。
そのことが予想できて、勘当の身でありながらも、
『清』は両親の愛情を、暖かく感じることができた。
その両親の気持ちと、『清』を受け入れてくれた『継男』の心を思い、
彼女は娘に会いたい気持ちを、抑えつけていた。
健やかに成長しているということが解るだけで、満足するしか、
仕方がなかったのだ。
育ての親・憶良夫妻から娘を取り上げることも、
自分たちの娘だということで、『継男』に頼って引き取ることも、
悪影響の方が、強いと思われた。
『清』が、そっと娘の成長を見守り続けることが、
総てが幸せになれる方途だと、思われたのである。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
都では、噂の『芳し姫』、『輝く姫』を一目見たいと、
若者はおろか、おじ様族までが、期待をふくらませ始めていた。
片田舎に置いておいたのでは、その姿を見ることは叶わない。
そこで急遽、憶良一家を、都へ呼び戻すことになった。
京の外れ(今の京田辺市付近)に屋敷も用意して、迎え入れる準備は、整った。
憶良は官僚である。
上からの命令には、無条件で従わなければならない。
『かぐや姫』を連れて、都に戻った。
住まいの周囲は竹林に囲まれて、下向先の筑紫国に、よく似た雰囲気だった。
かぐや姫も、竹の葉が擦れ合う囁きを友にできる環境が、好ましかった。
だがここでも、外を歩くには、鬱陶しい雰囲気であることが、
たちまちにして知れるようになった。
かぐや姫が屋敷から出歩いたのは、わずかに数日ばかりでしかない。
すれ違いざまに、ちらりと彼女の顔姿を見た若者から、
「噂に違わない『輝かしい姫』であった。」
と喧伝されると、彼女の周囲にはいつも、多くの高貴な若者たちの姿が、
見え隠れし始めた。
憶良を呼び戻した目的が、『かぐや姫』を見ることにあったのだから、
これは当然の成り行き。
だがこの出来事が続くとともに、かぐや姫の“閉じこもり生活”が、
再現されることになった。
竹林から覗き見える月を仰いでは、ため息を漏らす日が、繰り返されるようになった。
そして、ついに“結婚”を申し入れてくる若者も、
続出するようになった。
(良いのかなぁ。)
(何が?)
(かぐや姫の育ての親が、山上憶良だなんて決めつけちゃって・・・)
(今更。ここまで来ちゃったら、仕方ないじゃないの。)
(突っ走るか? このまま・・・。)
(誤解されないように、“山上憶良”の、本当の経歴くらいは、紹介しようか。)
(その方が良いと思うよ。)
---------------------
ということなので、 山上憶良って、どんな人?
憶良は、百済からの渡来人で、近江(滋賀県)の栗田氏に属していたのでは?
とされる。660年に生まれて、733年頃に、74歳で没したと、
記録に残っているらしい。
第7次遣唐使に任命されて、長安にまで行き、故郷を偲んで歌を詠んだりして、
主の栗田氏帰国と前後して、704~707年頃に帰国した。
714年(和銅7)に従五位下(下級官僚)に叙されて、
その後に、伯耆守(鳥取方面=赴任したかは、不明)に任命される。
(後の)聖武天皇の侍講に任命されてから、筑前守を経て筑紫に差し向けられ、
大伴旅人らを、歌の友として過ごした。
筑前守などという位は与えられていても、実際の暮らしぶりは貧しくて、
酒を飲むにも、塩をかじる程度で、口に入れるものもなく、
冬の寒さを忍ぶすべもない生活だった。
詠んだ歌は後世に残ったが、暮らしの貧しさを嘆き、
死を畏れる歌が多い。
子供を愛する歌も数知れず残したが、看病の甲斐もなく我が子を失ったときの詩歌は、
写生的な描写がされている。
それほどに、嘆き悲しみが、深かったということだろう。
世の人の 貴(たふと)び願ふ 七種(ななくさ)の 宝も我は 何せむに 我が中の 生れ出でたる 白玉の 我(あ)が子古日は 明星(あかぼし)の 明くる朝(あした)は しきたへの 床の辺(へ)去らず 立てれども 居(を)れども 共に戯(たはぶ)れ 夕星(ゆふつづ)の 夕へになれば いざ寝よと 手をたづさはり 父母も うへはな離(さか)り 三枝(さきくさ)の 中にを寝むと 愛(うつく)しく しが語らへば いつしかも 人と成り出でて 悪(あ)しけくも 吉(よ)けくも見むと 大船の 思ひ頼むに 思はぬに 横しま風の にふふふかに 覆ひ来たれば 為(せ)むすべの たどきを知らに 白たへの たすきを掛け まそ鏡 手に取り持ちて 天(あま)つ神 仰(あふ)ぎ祈(こ)ひ祷(の)み 国つ神 伏して額(ぬか)つき かからずも かかりも 神のまにまにと 立ちあざり 我(あれ)祈(こ)ひ祷(の)めど しましくも 吉(よ)けくはなしに 漸々(やくやく)に かたちつくほり 朝な朝(さ)な 言ふことやみ 玉きはる 命絶えぬれ 立ち躍り 足すり叫び 伏し仰(あふ)ぎ 胸打ち嘆き 手に持たる あが子飛ばしつ 世の中の道
我が子の成長を楽しみにしていたのに、こんなことで手から失うとは・・・。
これが人の世なのか。
と、愛息・古日を失った嘆きを、著している。
噛みしめて読めば、今も憶良の悲嘆が、ダイレクトに伝わってくる歌である。
この憶良は、まもなく妻にも先立たれる。
老いてからはさらに、貧しい暮らしぶりだった様子も窺われる。
それが、憶良の望むものだったかは、解らない。
だが『沈痾の時の歌』を詠んだときには、 藤原八束 が見舞いの使者を送っている。
歌人としての憶良は、相応の評価を受けていたとも思われる。
このことと、貧しい暮らしぶりとが、なかなか結びつきがたい。
だがこの『貧窮問答歌』(びんぐもんどうか)に代表される暮らしぶりが、
当時の“下級官僚”の、普通の暮らしぶりだったのかも知れない。
現代のように、物が行き渡る“豊かな社会”ではなかったのだろう。
『かぐや姫』についての、本来の“竹取物語”は、最後に、
あらすじで紹介します。

新説【竹取物語】・・・・・・《5》
『かぐや姫』は、16歳を過ぎて、まもなく17歳になろうという頃になっていた。
次第に、かぐや姫を産み落とした、母の年代に、近付いていたのである。
周囲の娘たちは、15になろうかという頃には、嫁ぎ先も決まり、
子供を抱く女性も多かった。
そのような中で、『かぐや姫』ばかりが、見合いにも応じようとしない。
月を見上げては、深くため息を漏らすばかりで、若い男どもを近寄らせようともしない。
憶良夫婦も、言の葉には乗せなかったが、美しく育った娘の嫁ぎ先を、
気に病み始めている。
「身体が悪いのではないか?」
「悪い物に、とり憑かれているのかも知れない。」
かぐや姫に相手にされなかった男たちの間から、知れずにそのような噂が、
密かに広がり始めた。
『かぐや姫』は、深い恩義がある憶良夫妻のために、
“育ての親”を幸せにできる男の出現を、待ち望んでいたのだ。
だが、あまりにも身分の高い人からの申し出では、憶良と会えないような、御殿の中に、
引き入れられてしまうことに、なりかねない。
子供を失った憶良夫妻を、このまま見捨てるようなことになっては、
自分だけで、幸せを感じることはできない。
そのような思いが強く、身分の上下にかかわらず、縁談を避けてきたのである。
しかし“悪い噂”までが流布されては、還って憶良たちに迷惑が及びかねない。
そこで、条件を付けて、男たちの申し込みを、受けることにした。
但しこのときにも、かぐや姫の気持ちの中には、
“とうてい叶えられそうのない無理難題”を条件につけることで、
嫁ぐことを避けようという意識が、強かった。
だがこのときに、憶良には『“琵琶の奥”に天女たちが舞い降りた』と言う情報が、
内密に伝えられていたのだ。
その得体の知れない者たちが、“姫”を奪い、天空に連れ去ろうとしている、
と、憶測を交えて知らされて、不安に駆られてしまった。
(万葉集に、“天女との遭遇”が、記されていると言うんだけど。)
(あの時代には、宮中を揺るがすような“物の怪”なんかも、随分出たらしいからね。)
(今と違って、“漆黒の闇”というのが、身近にあったから、
想像力が働きやすい条件が、揃っていたんだろうね。)
(天女伝説との出会いが、かぐや姫とどこで結びつくの?)
(かぐや姫が月に帰ると言うことと、天空から舞い降りる天女との関連は、
“物語”の重要な要素だったみたいだよ。)
(へぇ、そうなの? ところで、つまんないね。)
(何が?)
(ダジャレが足りない。)
(かぐや姫が悩んでいるときに、ダジャレなんて出せるかい?)
(ま、月に期待しとこうか。)
(次に期待・・・か。)
(ダジャレは、憶良入りさせとく?)
(まあ、その辺にして、次・・・行くよ。)
かぐや姫を自分の手元に置いたのでは、守りきれない。
力のある貴族の元に嫁がせれば、武辺の者たちが、きっと守ってくれることだろう。
憶良はそう考えて、寂しさをこらえて、嫁ぎ先を早急に選ばせようと、
かぐや姫を、せき立て始めていた。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
かぐや姫に結婚を申し込む“勇気ある男”たちは、
今までのいきさつもあって、同時に押しかける愚行を憚った。
籤を引いて、順番に憶良を通して、かぐや姫との出会いを求めたのである。
その一番手として名乗りを上げたのが、『石作皇子』である。
(これって、実在の人物なんだって?)
(そうだってね。知らないけどね。)
(じゃぁ、かぐや姫も実在の?)
(だと、面白いね。知らないけどね。)
皇子は、初めて間近に見る『かぐや姫』の美しさに、息を飲んだ。
ほの暗い憶良の屋敷の中で、姫がおわす場所だけが、輝いているように思われた。
『条件を成し遂げれば、嫁になると言うことだが、どんな条件を出されるやら』
という不安よりも、この美しい女性を嫁にできるかも知れないという、
期待のほうが大きく膨らみ、皇子は息苦しさを覚えながら、姫の言葉を待った。
「お願いは、ひとつ。“御仏の御石の鉢”が、どこぞにあるという。
それを、憶良様に残したいと思いまする。
見事、探し当てて持ち帰らば、あなた様に嫁しましょう。」
これが、『石作皇子』に告げられた課題だった。
皇子も、噂に聞いたことはあったが、“鉢”の所在どころか、その存在の真偽も、
見当もつかない。
『この姫は、叶えられようのない無理難題を、申し出たのではないのか?』
ちらりとその思いが脳裏を過ぎったが、姫の輝きに目が眩んだ皇子には、
その困難さを、深慮する余裕がなかった。
「きっと、その望みを叶えて、ご覧じ(ごろうじ)ましょう。」
「期限は、次の月が満ちる時までですよ。」
ほぼ1ヶ月の期限を、設けられた。
長いようで、短い期限である。
これは、『かぐや姫』の思い遣りから出た、期限でもあった。
到底叶えられない条件であることに気づけば、無理をせずに諦めるだろう、
といった気持ちが、込められているのだ。
しかし皇子は、その思いに気づくことなく、知人のつてを頼り、
わずかな情報でも寄せられれば、遠く離れた辺地にでも、馬を駆せた。
八方に探索の手段を巡らせて、情報を求め、報奨金も提示したが、
芳しい展開に持ち込むことができないままに、
天空の月が、日ごとに丸みを増していった。
“明日が満月”というその日に、『石作皇子』が息を弾ませて、
憶良の屋敷に飛び込んだ。
「ついに見つけましたぞよ。これが姫のお望みの“御仏の御石の鉢”でありましょう。」
大切に抱えた包みを、『かぐや姫』の前に、ズイッと、押しやった。
“御仏の御石の鉢”は、釈迦が持っていた石の鉢だと言われるが、
もちろんそのような物が、日本にあるはずもない。
しかし、『かぐや姫』が出した条件は、“本物”にこだわるものではなかった。
“打っても割れぬ石”という、いいつてにそぐわしい物であれば、
認めるつもりで、その“鉢の包み”を開いてみた。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
憶良の屋敷を、心配そうに覗き込む、4人の若者の姿があった。
『かぐや姫』に次の申し込みを待つ、候補者たちだった。
「石作皇子は、よくぞ困苦を乗り越えて、宝を見つけたものぞ。」
「いや待て。真贋のほどは、誰も見て居ず、知れたものではない。」
「そうよ。まだ我らが望みが、潰えたとは言えまい。」
「様子を見ようではないか。」
「もしもの時には、お次は『車持皇子』殿であるな。」
「おう、そのように。」
「次の“難題”は、どのようなものを、お考えであろうか・・・。」
「思いも及ばぬわえ。いずれにせよ、期待に応えてくれようぞ。」
「怪我の無きようにな。『石作皇子』のあの様態を、見申したかな?」
「ひとかたならぬご苦労が、偲ばれるような、やつれようであったな。」
「見つからぬ物は、いかように無理をしても見つからぬ。
お主が叶わねば、我らが控えておりますれば、無理は要せぬことと。」
「それよりも、『御仏の御石の鉢』は、本物であろうか。」
そのころ、『かぐや姫』が、“鉢”を静かに見つめていた。
『叩いても割れるはずのない鉢』を、見つめていた。

ホームへ戻る 続く(次ページへ)
『かぐや姫』 についての、リクエストを頂戴しました。
いずれ気が向いたら・・・と思っていたのですが、
この際、少しずつでも、書いてみようかと、思い立ちました。
そのようなわけで、これまた気まぐれに、
ぼちぼちと、思いつくままに書いてみます。
ストーリーを決めてあるわけではありませんので、
さて、どんな進行になりますやら。
なお、時代考証などは、思いっきり無視して、進行します。
結末は、もしかしたら 『つまらない落ち』 が、待っているかもしれません。
それと、 18歳未満の方は、保護者同伴で お読みくださいますように、
お断りいたしておきます。
未成年者注意 の部分は、 セピア文字 で表示します。
お子さんに内容の質問をされた場合には、次のようにお答えください。
「大きくなったら、解るから。大人になるまで、待ちなさいね。」
なぁんて、思わせぶりに・・・。
楽天さんに『削除処分』を受けちゃったら、どうしましょう。
【助命嘆願】を、出して戴けますか?
いや・・・そのぉ・・・『文学作品』ですから、多少のことは、大目にみて戴けるかと。
期待外れであっても、クレームはいっさい受け付けません。
『誇大広告だ!』 とか、 『不当表示だ!』 はもちろんのこと、
『もっと過激に!』 といったご要望も、無視いたします。
たっぷりと条件を付けたところで、始まり始まりぃー!
夕焼け空の紅色を、名残の色に纏いながら、
日増しに暖かくなる、春の宵を割るように、
大きな満月が、ゆらりと姿を現した。
満月は、天空に上るにつれて、白さを増した。
輝きが、凄絶な蒼さを感じさせるのは、冬が夜空を支配しているからだろうか。
しかし流石の冬も、次の満月の頃には、
朧を揺らす春風に、その力を譲り渡していることだろう。
★ ● ★ ● ★ ●
のどかな山里の、小高い丘の麓で、その満月を見上げる
ふたつの影があった。
(今日のところは、ここまでで・・・。 って、この先は、まだ考えていなかったんだろ?)
(だって、いきなりのスタートだったんだもの。)
時々、こんな 『一人つっこみ』 が入ります。

若い男は、職人のような装いだったが、
若い女は、公家の娘のような、上品な雰囲気を、漂わせていた。
満月の白い光は、二人の影を、斜面に咲く蕗のとうに、
柔らかく投げかけている。
春間近ではあっても、長時間佇むには、少しつらい。
身体を寄せ合っても、温もりは、月に吸い取られるようだった。
陽が落ちてから、数時間は過ぎているだろう。
二人は、それぞれの家人が休んでから、そっと屋敷を抜け出して来たのである。
(ところで、どうして満月の夜なの?)
(満月の夜を選ぶのは、もちろん、足下が見えるからさ。)
(単純。)
(だって、昔は街路灯なんてなかったし、二人とも栄養が偏っていて、
暗いところが見えにくくて・・・。)
(色気、ないじゃないか?)
(現実は、そんなものさ。)
このようにして、何度かのデートを繰り返した二人だが、
将来を語り合うには、遠慮が先立った。
身分の違いを想い、どちらからとも『将来』を切り出せないままに、
逢瀬を重ねていたのである。
しかし会うことができるのは、27日間に1度だけ。
満月の夜だけである。
最初の出会いから、まだ6回も会っていないのに、
秋が過ぎて、冬が過ぎ、春が訪れようとしている。
娘は、周囲からの縁談を断り続けて、いぶかしがられながら、
まもなく18歳を迎える。
そもそもの、二人の出会いは、供を連れて買い物に出かけた娘が、
いつもの店に立ち寄った、1年前にさかのぼる。
都に修行に出ていた店の2代目が、たまたま戻って、娘の応対に出たのである。
そこでその・・・『一目惚れ』というわけである。
相思相愛になったのは良いけれど、店に出向いても、
ただ黙って、見つめ合うばかり。それ以上の進展など、あろうはずもない。
しびれを切らした娘のほうから、男にそっと、合図を送った。
『次の満月の夜に』という。
満月が見られない雪の夜には、わずかな雪明かりを頼りに、
半時(1時間)にも足りない時の出会いを、楽しんだこともある。
そのようなわずかばかりの回数を重ねて、今、この朧な月を、
見上げているのである。
(『小高い丘の麓』って、言ったよね?)
(うん。どうして?)
(冬なんか、寒くない?)
(丘の麓に、粗末な作業小屋があったのさ。)
(それを先に言ってよ。)
(外で会ってるなんて、どうして考えるの?)
(月を見上げる、って言うから。)
(成り行き任せだから、後でフォローすることもあるわい。)
二人は、次の出会いを約束して、名残を惜しみながら、
小屋を後にした。
月は二人の影を、長く伸ばして、山の端に隠れようとしていた。
梟が『ホウホウ』と鳴いて、帰宅をせかす。
二人は、梟の眼を羨んだ。
夕暮れとともに巣へ帰る、雀のような自分たちの眼が、
なんとも、もどかしかった。
(今日はここまで。)
(まだ、1日分も進んでいないじゃない?)
(あわてるな。)
(でも、こんな展開じゃ、いつまで続くかと想っただけで、ダレちゃうよ。)
(次から、スピードアップしようか?)
(頼むわ。それと、『二人』には、名前もないの?)
(そうか。忘れていたよ。男には、“継男(つぐお)”で、
娘には“清”なんて、どう?)
(その心は?)
(家業を継ぐ男と、『清少納言』は“清”が名前だろうから、それにあやかって・・・。)
(ひどい安易さだ。)
(だから、思いつきで進めている話だから。)
(こんなのばっかり・・・。)
と、こんなところで、次回からは、『つっこみ』の会話も少なくして、
スピードアップを心がけてみましょう。

逢魔が時を過ぎると、あたりは急速に暗さを増す。
闇をすかしても、人影さえも見えない。
隣に立つ人の気配も、わずかな衣擦れの音で、それと解る程度である。
都でも、あまたの“物の怪”が出没しているということで、
その騒動が、遠く離れた南の国にも、噂として伝わっていた。
“鼻をつままれても判らない”闇夜が、普通のことだった。
夜に出歩くには、行灯の光だけが頼りだが、人目を忍ぶ二人の出逢いには、
その光さえも、憚られた。
明かりを頼るには、満月以外に、適する日がなかったのである。
咲き乱れた菜の花も、終わりを告げていた。
粗末な小屋に漏れ入る、月の白い光が、二人の身体をも、白く輝かせた。
『清』の柔らかな身体を、月の光がさらに丸く包んで、足下に優しい影を落とした。
昼に見る姿とは、人が違ったような『清』を見て、『継男』は気持ちを抑えきれなかった。
『清』の眼も大きく開かれて、きらきらと、月の光を映している。
(この色は、18歳未満の方は、保護者同伴で・・・ね。
え? 手遅れでした? 申し訳ない。)
それからも、二人の忍び逢いは、月ごとに続けられて、夏が過ぎる頃まで続いた。
『継男』は、『清』の異変に気づかなかった。
が、秋の気配が深まる頃に突然、『清』が姿を見せなくなったのである。
供を連れて顔を出していた、『継男』の店にも、足が途絶えた。
いきさつに思い当たるところがなく、『継男』は悩んだが、
探るには、身分の違いが障害になり、『清』の屋敷の周囲をただ当てもなく、
彷徨うばかりだった。
『清』の消息は、そのまま途絶えてしまった。
だがやがて、屋敷を追われるように出された『清』は、供も連れずに、
ひとりで『継男』の店を訪ね、そのまま彼に救われるように、
何事もなかったように、夫婦になったのである。
消息を絶った期間について、『継男』は一度だけ、尋ねたことがあった。
だがそのときに、『清』が涙にくれて応えを拒んだために、
それ以降は、不審を感じながらも、その話題を避けていた。
何よりも、1年半ぶりに出会えて、妻に迎えることができた幸せを、
大切にしたかったのである。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
『清』が『継男』の前に、再び姿を見せた時から、1ヶ月ほど遡った、
満月の夜のことである。
昼の朧が、そのまま続いたように、月も潤いを持って、大きな虹色の傘を掛けていた。
都から遣わされた官吏の『憶良』という男が、妻とほの暗い明かりを頼りにして、
読書にふけっていたときに、かすかに子供の鳴き声を聞いたのである。
「なぁ、どこかで子供の泣き声がしていないかのぅ?」
「あなた、子供が亡くなってまだ三月。気の迷いでしょう。」
「うむ。あの子を失ってからというもの、火が消えたような寂しさで、たまらん。」
「流行病で、村の子供が次々に亡くなって、『かわいそうに』と思っていたら・・・。」
「まさか、吾子が亡くなるとは、思いもせんだて・・・。」
「おや? あなた、やはり子供の・・・。」
「しかしいくら満月とは雖も、こんな夜更けに、子連れが山の上を歩くかのぅ。」
「狐が、悪戯をしているのでしょうか。」
「麓の小屋では、時に人を誑かそうとする“悪狐”がおるようだが。」
「さてさて、迷い旅人でも騙されていなければ、よろしいですわねぇ。」
「気がかりじゃ。様子を見てくるとしようか。」
「お頼み申します。」
山の上とは言っても、小高い丘の上に建つ、貧しい官吏の家である。
冬は寒さをどうにか耐えて、梅雨には雨を凌ぐほどの粗末な小屋でしかない。
静かな夜には、かなたのかすかな物音さえ、壁の隙間を擦り抜けて、
入り込む。
いつもならば、塩を舐めながら濁酒でも飲んで眠ってしまう憶良だが、
月明かりに誘われるように、読書にふけっていた。
彼『憶良』は、大変な子供好きとして知られ、吾が子や、村の子供たちと遊ぶことを、
無上の楽しみにしていた。
村人たちも『憶良』の優しさを心得て、赴任当初から親しみを寄せてくれていた。
その『憶良』が、目に入れても痛くないほどに、大切にしていた息子を、
3ヶ月ほど前に、亡くしたのである。
そのようなときに、子供の泣き声を聞いたのであるから、
様子を見ずにはいられない。
「麓の小屋の裏には、竹林もあるし、森もある。
狐ならば、こんな山の上に来ずとも、よかろうに・・・。」
ひとり愚痴をつぶやきながら、月明かりに白く照らされた細い道をたどり、
麓の作業小屋まで、降りていった。
次第に、赤子の泣き声が、近くなる。確かに、狐の仕業ではなさそうである。
彼に与えられた、わずかばかりの耕地に迫るように、竹林が覆い被さっていた。
赤子はその中で、泣いていた。
『憶良』が、数日前に伐り取った竹の根本を見やると、そこには高貴な身分を感じさせる、
あでやかな着物に包まれた、珠のような赤子が、そっと置かれていた。
まだ近くに誰かが居そうな気がして、『憶良』は竹林の奥を、透かして見た。
月の光が、揺れる竹の葉陰を落とすばかりで、人影を窺うことは、できなかった。
『憶良』は、失った子供に替えて、“神仏がこの子を授けてくれたもの”、
と思うことにした。
赤子の生まれが高貴であることは、衣装だけでなく、
竹で編まれた埋籠に添えられた“匂い袋”からも、偲ぶことができた。
『なにか、特別に訳ありな“公家”のような家柄が、儂にこの子を託そうとしたのだろう。』
という予測は、『憶良』にも、容易に察せられた。
「麓の竹林に、可愛らしい赤子が居ったぞよ。」
「狐の子ではなくて、ヒトのお子でございましょうや?」
「おう、珠のように、元気で可愛らしい子じゃ。」
「御衣装が、何とも高貴そうだこと。」
「それに、匂い袋も、得も言われぬ佳きものであるし、のぅ。」
「あら、なんと芳しいこと。」
「今になって気づいたか?」
「あなたがお入りなさってから、気づいておりましたが、匂い袋とは。」
「いずれ、何処のお方か、手懸かりになるやも知れん。大事にな。」
「その日まで、この子は大切に、お預かりいたしましょう。」
「それにしても、なんと芳しい(かぐわしい)ことよ。」
「女の子ですから、“芳姫(かぐわひめ)”とでも・・・。」
「それがよかろう。」
この日を境にして、『憶良』の家庭にはまた、以前のような明るさが、
戻ったのである。
子供好きの『憶良』には、かけがえのない珠玉が、転げ込んだのだ。
この後間もなく『憶良』は、後世に残る、和歌の一首を詠んだ。
“銀(しろかね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる宝 子にしかめやも”
(お? ようやく、『かぐや姫』の登場だね?)
(登場は良いけれど、何だ? 匂い袋が芳しいから、『かぐや姫』だって?)
(竹から産まれたっていう物語は、“竹籠”に入れて捨てられていただけかい。)
(ひどい展開になって来ちゃったなぁ。)
(それよりもひどいのは、『かぐや姫』の育ての親は、『山上憶良』だってぇの?)
(時代が、無茶苦茶になりそう・・・。)
(細かいことに、こだわるな。)
(それで良いの?)
(どうせ『憶良』の憂さ話《うそばなし》だもの。)

憶良夫婦に大切に育てられた『芳し姫』(かぐやひめ)は、
健やかに成長するにつれて、いよいよ光り輝きをいやますように、
高貴な雰囲気を、全身に纏うようになっていた。
幼友達と遊んだ日々が、いつしか遙かな思い出の中に、
閉じこめられようとしていた。
育ての親・憶良たちは、かぐや姫に生い立ちを伝えてはいなかったが、
狭い住まいの中には、その佇まいに相応しくない調度品や、
いつまでも大切に保存されている、赤子の衣類などが、
自然と目にとまり、違和感を覚えるとともに、友達の振る舞いにも、
よそよそしさを、感じ始めたのである。
里人たちは、かぐや姫が成長するにつれて、その自然に身に付いた雰囲気の中に、
身分の違いを感じさせられて、疎遠になるわけではないのに、
なぜか、近づきがたさで、顔も合わせられなくなっていた。
かぐや姫は、今までのように人々と接したいのだが、
人々の方が遠ざかる。
理由が判らないままに、少しずつ外に出る機会が減っていった。
里人の噂は、『芳しい姫』からやがて、『輝かしい姫』という意味を込めて、
『かぐや姫』とされて口の端に乗り、都にまで届くようになった。
実家を追われて『継男』に嫁した『清』は、それなりに幸せだったが、
残してきた娘を忘れたことは、なかった。
折に触れて、人を介して様子を探らせたが、状況はなかなか、
漏れ伝わってこなかった。
ただひたすら、無事な成長を、祈るばかりだった。
そうこうするうちに、1年も過ぎた頃に、
「娘は、とうの昔に捨てられたようだ。」
という噂が、耳に届いた。
どこに捨てられたやら、と気に掛かり、手を尽くして行方を求めようとした。
しかしその苦労は、必要がなかった。
噂が駈け巡りやすい田舎のこと。
子供好きの官吏が、『竹から産まれた珠のような女の子』を、この上なくか可愛がっている、
と言う評判を、すぐに探り当てることができた。
都から来た公務員が、拾ってくれたのだ。
『清』の両親も、赤子の将来を託す相手として、場所を選び抜いて捨てたのだろう。
そのことが予想できて、勘当の身でありながらも、
『清』は両親の愛情を、暖かく感じることができた。
その両親の気持ちと、『清』を受け入れてくれた『継男』の心を思い、
彼女は娘に会いたい気持ちを、抑えつけていた。
健やかに成長しているということが解るだけで、満足するしか、
仕方がなかったのだ。
育ての親・憶良夫妻から娘を取り上げることも、
自分たちの娘だということで、『継男』に頼って引き取ることも、
悪影響の方が、強いと思われた。
『清』が、そっと娘の成長を見守り続けることが、
総てが幸せになれる方途だと、思われたのである。
都では、噂の『芳し姫』、『輝く姫』を一目見たいと、
若者はおろか、おじ様族までが、期待をふくらませ始めていた。
片田舎に置いておいたのでは、その姿を見ることは叶わない。
そこで急遽、憶良一家を、都へ呼び戻すことになった。
京の外れ(今の京田辺市付近)に屋敷も用意して、迎え入れる準備は、整った。
憶良は官僚である。
上からの命令には、無条件で従わなければならない。
『かぐや姫』を連れて、都に戻った。
住まいの周囲は竹林に囲まれて、下向先の筑紫国に、よく似た雰囲気だった。
かぐや姫も、竹の葉が擦れ合う囁きを友にできる環境が、好ましかった。
だがここでも、外を歩くには、鬱陶しい雰囲気であることが、
たちまちにして知れるようになった。
かぐや姫が屋敷から出歩いたのは、わずかに数日ばかりでしかない。
すれ違いざまに、ちらりと彼女の顔姿を見た若者から、
「噂に違わない『輝かしい姫』であった。」
と喧伝されると、彼女の周囲にはいつも、多くの高貴な若者たちの姿が、
見え隠れし始めた。
憶良を呼び戻した目的が、『かぐや姫』を見ることにあったのだから、
これは当然の成り行き。
だがこの出来事が続くとともに、かぐや姫の“閉じこもり生活”が、
再現されることになった。
竹林から覗き見える月を仰いでは、ため息を漏らす日が、繰り返されるようになった。
そして、ついに“結婚”を申し入れてくる若者も、
続出するようになった。
(良いのかなぁ。)
(何が?)
(かぐや姫の育ての親が、山上憶良だなんて決めつけちゃって・・・)
(今更。ここまで来ちゃったら、仕方ないじゃないの。)
(突っ走るか? このまま・・・。)
(誤解されないように、“山上憶良”の、本当の経歴くらいは、紹介しようか。)
(その方が良いと思うよ。)
ということなので、 山上憶良って、どんな人?
憶良は、百済からの渡来人で、近江(滋賀県)の栗田氏に属していたのでは?
とされる。660年に生まれて、733年頃に、74歳で没したと、
記録に残っているらしい。
第7次遣唐使に任命されて、長安にまで行き、故郷を偲んで歌を詠んだりして、
主の栗田氏帰国と前後して、704~707年頃に帰国した。
714年(和銅7)に従五位下(下級官僚)に叙されて、
その後に、伯耆守(鳥取方面=赴任したかは、不明)に任命される。
(後の)聖武天皇の侍講に任命されてから、筑前守を経て筑紫に差し向けられ、
大伴旅人らを、歌の友として過ごした。
筑前守などという位は与えられていても、実際の暮らしぶりは貧しくて、
酒を飲むにも、塩をかじる程度で、口に入れるものもなく、
冬の寒さを忍ぶすべもない生活だった。
詠んだ歌は後世に残ったが、暮らしの貧しさを嘆き、
死を畏れる歌が多い。
子供を愛する歌も数知れず残したが、看病の甲斐もなく我が子を失ったときの詩歌は、
写生的な描写がされている。
それほどに、嘆き悲しみが、深かったということだろう。
世の人の 貴(たふと)び願ふ 七種(ななくさ)の 宝も我は 何せむに 我が中の 生れ出でたる 白玉の 我(あ)が子古日は 明星(あかぼし)の 明くる朝(あした)は しきたへの 床の辺(へ)去らず 立てれども 居(を)れども 共に戯(たはぶ)れ 夕星(ゆふつづ)の 夕へになれば いざ寝よと 手をたづさはり 父母も うへはな離(さか)り 三枝(さきくさ)の 中にを寝むと 愛(うつく)しく しが語らへば いつしかも 人と成り出でて 悪(あ)しけくも 吉(よ)けくも見むと 大船の 思ひ頼むに 思はぬに 横しま風の にふふふかに 覆ひ来たれば 為(せ)むすべの たどきを知らに 白たへの たすきを掛け まそ鏡 手に取り持ちて 天(あま)つ神 仰(あふ)ぎ祈(こ)ひ祷(の)み 国つ神 伏して額(ぬか)つき かからずも かかりも 神のまにまにと 立ちあざり 我(あれ)祈(こ)ひ祷(の)めど しましくも 吉(よ)けくはなしに 漸々(やくやく)に かたちつくほり 朝な朝(さ)な 言ふことやみ 玉きはる 命絶えぬれ 立ち躍り 足すり叫び 伏し仰(あふ)ぎ 胸打ち嘆き 手に持たる あが子飛ばしつ 世の中の道
我が子の成長を楽しみにしていたのに、こんなことで手から失うとは・・・。
これが人の世なのか。
と、愛息・古日を失った嘆きを、著している。
噛みしめて読めば、今も憶良の悲嘆が、ダイレクトに伝わってくる歌である。
この憶良は、まもなく妻にも先立たれる。
老いてからはさらに、貧しい暮らしぶりだった様子も窺われる。
それが、憶良の望むものだったかは、解らない。
だが『沈痾の時の歌』を詠んだときには、 藤原八束 が見舞いの使者を送っている。
歌人としての憶良は、相応の評価を受けていたとも思われる。
このことと、貧しい暮らしぶりとが、なかなか結びつきがたい。
だがこの『貧窮問答歌』(びんぐもんどうか)に代表される暮らしぶりが、
当時の“下級官僚”の、普通の暮らしぶりだったのかも知れない。
現代のように、物が行き渡る“豊かな社会”ではなかったのだろう。
『かぐや姫』についての、本来の“竹取物語”は、最後に、
あらすじで紹介します。

『かぐや姫』は、16歳を過ぎて、まもなく17歳になろうという頃になっていた。
次第に、かぐや姫を産み落とした、母の年代に、近付いていたのである。
周囲の娘たちは、15になろうかという頃には、嫁ぎ先も決まり、
子供を抱く女性も多かった。
そのような中で、『かぐや姫』ばかりが、見合いにも応じようとしない。
月を見上げては、深くため息を漏らすばかりで、若い男どもを近寄らせようともしない。
憶良夫婦も、言の葉には乗せなかったが、美しく育った娘の嫁ぎ先を、
気に病み始めている。
「身体が悪いのではないか?」
「悪い物に、とり憑かれているのかも知れない。」
かぐや姫に相手にされなかった男たちの間から、知れずにそのような噂が、
密かに広がり始めた。
『かぐや姫』は、深い恩義がある憶良夫妻のために、
“育ての親”を幸せにできる男の出現を、待ち望んでいたのだ。
だが、あまりにも身分の高い人からの申し出では、憶良と会えないような、御殿の中に、
引き入れられてしまうことに、なりかねない。
子供を失った憶良夫妻を、このまま見捨てるようなことになっては、
自分だけで、幸せを感じることはできない。
そのような思いが強く、身分の上下にかかわらず、縁談を避けてきたのである。
しかし“悪い噂”までが流布されては、還って憶良たちに迷惑が及びかねない。
そこで、条件を付けて、男たちの申し込みを、受けることにした。
但しこのときにも、かぐや姫の気持ちの中には、
“とうてい叶えられそうのない無理難題”を条件につけることで、
嫁ぐことを避けようという意識が、強かった。
だがこのときに、憶良には『“琵琶の奥”に天女たちが舞い降りた』と言う情報が、
内密に伝えられていたのだ。
その得体の知れない者たちが、“姫”を奪い、天空に連れ去ろうとしている、
と、憶測を交えて知らされて、不安に駆られてしまった。
(万葉集に、“天女との遭遇”が、記されていると言うんだけど。)
(あの時代には、宮中を揺るがすような“物の怪”なんかも、随分出たらしいからね。)
(今と違って、“漆黒の闇”というのが、身近にあったから、
想像力が働きやすい条件が、揃っていたんだろうね。)
(天女伝説との出会いが、かぐや姫とどこで結びつくの?)
(かぐや姫が月に帰ると言うことと、天空から舞い降りる天女との関連は、
“物語”の重要な要素だったみたいだよ。)
(へぇ、そうなの? ところで、つまんないね。)
(何が?)
(ダジャレが足りない。)
(かぐや姫が悩んでいるときに、ダジャレなんて出せるかい?)
(ま、月に期待しとこうか。)
(次に期待・・・か。)
(ダジャレは、憶良入りさせとく?)
(まあ、その辺にして、次・・・行くよ。)
かぐや姫を自分の手元に置いたのでは、守りきれない。
力のある貴族の元に嫁がせれば、武辺の者たちが、きっと守ってくれることだろう。
憶良はそう考えて、寂しさをこらえて、嫁ぎ先を早急に選ばせようと、
かぐや姫を、せき立て始めていた。
かぐや姫に結婚を申し込む“勇気ある男”たちは、
今までのいきさつもあって、同時に押しかける愚行を憚った。
籤を引いて、順番に憶良を通して、かぐや姫との出会いを求めたのである。
その一番手として名乗りを上げたのが、『石作皇子』である。
(これって、実在の人物なんだって?)
(そうだってね。知らないけどね。)
(じゃぁ、かぐや姫も実在の?)
(だと、面白いね。知らないけどね。)
皇子は、初めて間近に見る『かぐや姫』の美しさに、息を飲んだ。
ほの暗い憶良の屋敷の中で、姫がおわす場所だけが、輝いているように思われた。
『条件を成し遂げれば、嫁になると言うことだが、どんな条件を出されるやら』
という不安よりも、この美しい女性を嫁にできるかも知れないという、
期待のほうが大きく膨らみ、皇子は息苦しさを覚えながら、姫の言葉を待った。
「お願いは、ひとつ。“御仏の御石の鉢”が、どこぞにあるという。
それを、憶良様に残したいと思いまする。
見事、探し当てて持ち帰らば、あなた様に嫁しましょう。」
これが、『石作皇子』に告げられた課題だった。
皇子も、噂に聞いたことはあったが、“鉢”の所在どころか、その存在の真偽も、
見当もつかない。
『この姫は、叶えられようのない無理難題を、申し出たのではないのか?』
ちらりとその思いが脳裏を過ぎったが、姫の輝きに目が眩んだ皇子には、
その困難さを、深慮する余裕がなかった。
「きっと、その望みを叶えて、ご覧じ(ごろうじ)ましょう。」
「期限は、次の月が満ちる時までですよ。」
ほぼ1ヶ月の期限を、設けられた。
長いようで、短い期限である。
これは、『かぐや姫』の思い遣りから出た、期限でもあった。
到底叶えられない条件であることに気づけば、無理をせずに諦めるだろう、
といった気持ちが、込められているのだ。
しかし皇子は、その思いに気づくことなく、知人のつてを頼り、
わずかな情報でも寄せられれば、遠く離れた辺地にでも、馬を駆せた。
八方に探索の手段を巡らせて、情報を求め、報奨金も提示したが、
芳しい展開に持ち込むことができないままに、
天空の月が、日ごとに丸みを増していった。
“明日が満月”というその日に、『石作皇子』が息を弾ませて、
憶良の屋敷に飛び込んだ。
「ついに見つけましたぞよ。これが姫のお望みの“御仏の御石の鉢”でありましょう。」
大切に抱えた包みを、『かぐや姫』の前に、ズイッと、押しやった。
“御仏の御石の鉢”は、釈迦が持っていた石の鉢だと言われるが、
もちろんそのような物が、日本にあるはずもない。
しかし、『かぐや姫』が出した条件は、“本物”にこだわるものではなかった。
“打っても割れぬ石”という、いいつてにそぐわしい物であれば、
認めるつもりで、その“鉢の包み”を開いてみた。
憶良の屋敷を、心配そうに覗き込む、4人の若者の姿があった。
『かぐや姫』に次の申し込みを待つ、候補者たちだった。
「石作皇子は、よくぞ困苦を乗り越えて、宝を見つけたものぞ。」
「いや待て。真贋のほどは、誰も見て居ず、知れたものではない。」
「そうよ。まだ我らが望みが、潰えたとは言えまい。」
「様子を見ようではないか。」
「もしもの時には、お次は『車持皇子』殿であるな。」
「おう、そのように。」
「次の“難題”は、どのようなものを、お考えであろうか・・・。」
「思いも及ばぬわえ。いずれにせよ、期待に応えてくれようぞ。」
「怪我の無きようにな。『石作皇子』のあの様態を、見申したかな?」
「ひとかたならぬご苦労が、偲ばれるような、やつれようであったな。」
「見つからぬ物は、いかように無理をしても見つからぬ。
お主が叶わねば、我らが控えておりますれば、無理は要せぬことと。」
「それよりも、『御仏の御石の鉢』は、本物であろうか。」
そのころ、『かぐや姫』が、“鉢”を静かに見つめていた。
『叩いても割れるはずのない鉢』を、見つめていた。

ホームへ戻る 続く(次ページへ)
© Rakuten Group, Inc.