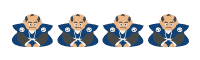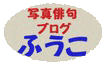2004年メダカと愉快な仲間たち
●6月3日(木)
クロメダカは孵化率が低いながらも順調に稚魚が孵り、ようやく50匹を超えた。一方、4月中旬まで日光の差さない所にいるヒメダカは、5月初旬から遅れを取り戻すようにガンガン卵を生み、瞬く間にクロメダカ稚魚数を上回っていく。多分100匹くらいは孵っているか。
今年度のクロメダカ孵化1号から卵を移してきた小型のプラスチック水槽が狭くなったので、5月16日に第2弾の小型水槽を用意したのだが、孵化まで2週間(14日)ちょうどかかった。ヒメダカは例年のごとく10日で孵化する。やはり生存本能という点において、クロメダカはヒメダカに劣るようだ。
●5月1日(土)
↓の孵化以降も順次クロメダカが孵化し、現在10匹ほどが確認できる。しかし親メダカが3コ4コと産んでいる総数は20を超えているので、孵化できなかったか、孵化直後に死んでいるのだろう。生き残り率はヒメダカの方が高いようだ。♂♀の比率はやはり3:3だったが、昨秋もっとも遅い孵化組の生き残り♀1匹はまだ産卵の気配を見せない。
庭に埋まった甕の中のヒメダカも先日からようやく産卵開始(例年通り)。GW明けくらいからこちらも孵化する予定。
●4月17日(土) 花盛りの孵化
嘘みたいだった産卵から17日目の今朝、ようやくメダカが孵化した。卵の中で黒い稚魚の成長が見えていたのに、寒い日もあったせいか、約10日という卵の期間から大幅に遅れての孵化。4月1日産卵の2コも孵化したようで、卵が消えていたが、目視では2匹しか確認できなかった。
昨年春に初挑戦したクロメダカ飼育であったが、昨年冬に第1世代10匹はすべて★。その年孵化の第2世代は、夏前に孵った2匹が♂、夏以降に孵った4匹は♀3匹、♂1匹のよう(推定)。まだ1年目で、しかも個体自体が小さいのに、2つ3つと断続的に産卵する1匹がいる。その1匹の産卵を、夏前孵化のやや身体が大きい2匹の♂が常に狙っているのが現状である。
●3月31日(水) 桜満開
嘘みたいな話だが、今日、クロメダカ♀1匹の腹に卵が1コ……ありえない!と思いつつも、幻ではないので、急いでその♀を網で掬い、卵を別の小さな水槽に移動。1コの産卵ってことはないはずなので、水草に付いてないか探すが、水草の森からは捜索できず。もし、♂が放精していたら、約10日後には孵化するはず。3月の産卵は、長いメダカ飼育歴で初めて。明日も出産するか要注意。それにしても、こんな現象も異常気象のせいだろうか?
●3月5日(金) 啓蟄
天気がよく暖かいので、ガラス越しの室内に居るクロメダカはわりと元気に動いている。半分土に埋められた睡蓮の甕はまだ1日中日光が射しこまないので、そこにいるヒメダカはじっと底の方に沈んでいる。こうやって毎年ヒメダカは世代交代していくのであるから、本当に丈夫な生き物である。
年末に12匹が生き延びた第2世代のクロメダカはいつしか6匹まで減少。このクロメダカの水槽には、昨年夏、よく行くテニスコートそばの人工池で抜いてきた芹(らしきもの)と名前のわからない薄のような水生植物も入っている。既に完成している水槽の小石に植えつけるのもどうかと思い、別に植えて水に沈めたものである。500mlのペットボトルの底3分の1くらいを切り取り、そこに土を入れて最上部に小石を敷き詰めたところに植えてある。
ほんの少し根を付けたまま抜いた数センチのものだが、さすが水生植物は頑丈で、ひと夏見事に育った。芹(らしきもの)はペットボトルの容器から根をはみ出すほどに成長した。秋には両方とも枯れたが、今日見てみたら、芹ももう1つの草も芽を出して、今にも水面に顔を出しそうである。土の隙間にはいつしか気泡もできていて、枯れ果てたと思った根が確実に呼吸し生きていることを示している。春はすぐそこである。
© Rakuten Group, Inc.