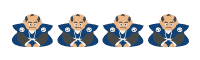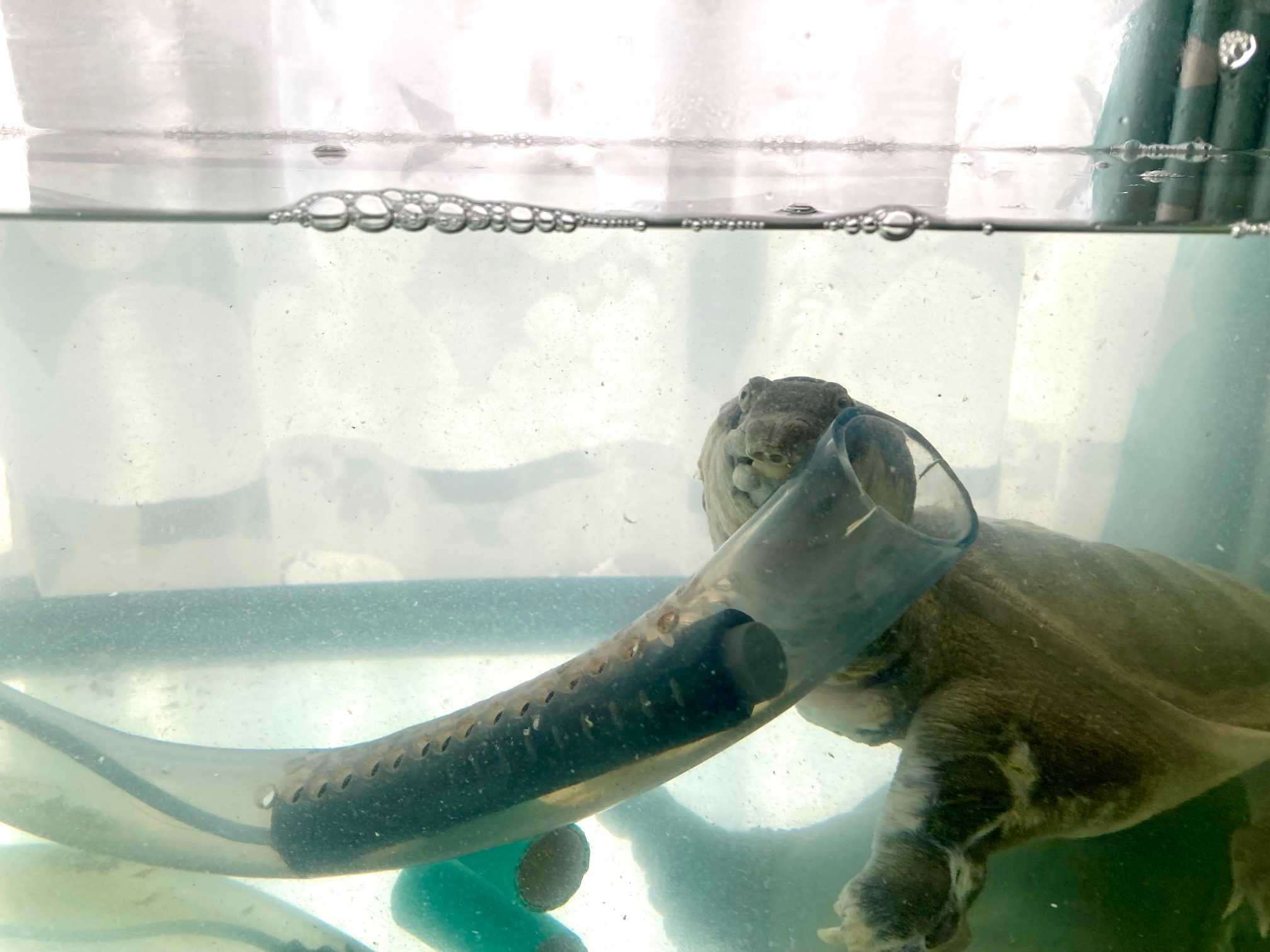全1010件 (1010件中 1-50件目)
-
結局今年も
先日、まだ出ない!と叫んでいたハス。15日に芽が出て、あれよあれよという間に伸び、気が付けば昨年同様に開花した。モノの本によれば、芽が出てからおよそ3週間ということだが、なんと2週間で開花。ただし、150cmほどと昨年よりも低い。
2013/07/29
コメント(0)
-
ハスの花芽が出ない
去年はそろそろだったよな・・・なんて思ってブログを見ると(というかブログ更新が1年ぶりだし)、昨年は29日に開花していた。ということは9日頃には芽が出ていたわけで、既に5日遅れている。昨年と違うのは、日射時間。昨年まであった南側の親戚(大叔父)が土地を手放し、別の家が建ったことによる。日光に曝される時間が4時間ちょっとでは難しいだろうか。 逆に東京の暑い夏が苦手なヒツジグサは順調で、1つ咲いては新しい花芽が出てまた咲いて、と既に3巡目の開花が始まった。 ヤエオモダカもちょっと咲きが遅い。頑丈なサジオモダカは2巡目。同様に頑丈なコナギも順調に生長中。カキツバタは5月下旬に無事開き、水面下で生長中。
2013/07/14
コメント(0)
-
室町の紀行文
ちょっとしたご推薦をいただいて、埼玉県A市の博物館で、道興准后『廻国雑記』について講演をしてきた。本務校で1限の授業を行って、そのまま出発したら余裕で到着!などと思っていたら、武蔵野線へアクセスするバスが来ない、来ない、来ない・・・。大学前で早くも40分のロス。ようやく来たと思ったら、渋滞・・・。連休初日とあって、世間様は行楽日和なのだろうが。 鎌倉がらみということもあって目は通していた作品だが、お話をいただいてからちょくちょくと読むたびに、あれこれと思うところが出てきて、先行論文を見ようかなって思うと、これがまた少なく。いやぁ、もっと取り上げて良い作品じゃないかな? 日々雑務に追われてグダグダしている私に声をかけてくださった先生、本当にありがとうございます。 90分の講演を無事終え、また、学芸員の方からも過分な評価をいただき、気分の良いまま舞台鑑賞へ。本日はかなり有名な外国文学作品の舞台化。こちらは、予想に反してちょっと拍子抜け。
2013/07/13
コメント(0)
-

ハスの立ち枯れ(涙)
学生は夏休みに入ったが、佐藤は普段どおり出勤。オープンキャンパスやらなにやらもあって、今年はついにインカレの引率にも行けなかった。 ところで、先日のハスA(真如蓮)に続くハスBは、立ち枯れてしまった。容器の縁に沿ってピッタリとくっついていたので、気にはなっていたのだが、花芽をあまりいじってはいけないとものの本に書いてあったので、そのままにしていたところ、こんな無残な姿に。途中までの様子だとピンクのハスになりそうな感じだった。もう1つの紹介は、サジオモダカ。ハスの栽培のために、田んぼの土を購入したところ、注意書きに「色々な水田雑草の種やミジンコ類も混じっている」とあった。実際、ハスを育て始めると、水底に雑草がどんどん生えてくる。その多くはアゼナだったが、中に、「これは!?」と思うような芽が出たので分けておいたのだった。ミズアオイかも!?と期待に胸膨らませていたところ、サジオモダカだった・・・。セリの左隣に匙型の葉っぱを伸ばしているのがそれ。長く伸ばした茎(50cmくらい)の先端に小さな薄いピンクの花を付け始めている。
2012/08/10
コメント(0)
-

けふのさへづり
先日の予測どおり、土曜日が開花初日、本日が開花2日目となった(写真は明日にでも)。 蕾の段階から緑の色味が強い白、丈160cm超の大型、そしてこのさっぱりとした香り・・・先日紹介したハスAはまさに「真如蓮」であろう。 かの萬福寺では、品種名の書いてあるハスと品種名が諸般の事情で判らなくなったハスとが売られていた。ゆっくり選ぶような時間的余裕がなく、博打的要素もある、「品種不明タイプ」(しかも安い)を購入したのだが、白系のオーソドックスな「真如蓮」に当たったというわけだ。 白蓮の貴公子のニックネームにふさわしい、清々しい香り。悪く言えば、タイガーバーム?歯磨き粉?いやいや、スペアミント系と呼んで差し上げよう。爽やかでちょっと甘い香りがかなりの勢いで漂っていた。珍しい品種ではないが、調べてみたら、江戸時代から続く、日本固有種ということで、ちょっと嬉しい。育てやすいらしい。 気になったのは、「花上がりが良い」と書いてあること。うちは目下この1輪しか上がってきてないのだけど・・・。今から蕾が出ても、次は8月下旬じゃん!やはりガマ(品川区自生種)との同居がいけないのかと思い、ガマを植え付けている鉢を、思い切ってズボッと引き抜き、空いたところにはケト土と赤玉土を練った土を補充しておいた。これで地下茎もちょっとは伸びやすくなるだろう。作業中にアゲハなどの蝶類ほかアブハチ類が多数来訪した。シオカラ(←もしかして、我が家の出身?)も飛来。 ちなみに、数日前、ハスB(←2つ買ったのかよ)の蕾が上がり始めた。こちらは小ぶりな様子で、もしかしたら茶碗蓮と呼ばれるような小型蓮かもしれない。 それと、クロメダカ・ヒメダカ・ヤゴ(ジモティー)・ヌマエビ・タニシ(共に品川区産)、鈴虫は今年も元気。ついでに新入荷のオオクワガタ番いがガンガン産卵中。 もちろん、チャオもマサオも元気。
2012/07/29
コメント(0)
-

けふのさへづり
萬福寺にて購入したハスA(品名は不明)がついに佐藤の身長を超えた。蕾の様子だと、どうやら白系っぽい。花芽が出て2週間近いので、今週末には咲くだろう。ちなみに、一緒に写っている、すっと伸びた葉っぱは、品川区産ガマ。植木鉢に植えた上で、ハスの鉢に同居させたが、共に巨大化している。ガマは既に2mを超え、計測不能。
2012/07/24
コメント(0)
-
フェルメール第二弾
非常勤の授業も前期は残すところ、あと1週となった。今春発売された『うた恋。3』ほか、あれこれと貸し出していた本(古典がらみの漫画)が戻ってきた。一昨年、思いも寄らぬ荒い扱いでボロボロになってしまった『うた恋。』も、痛みの度合いはほとんど進まなかったようで、ちょっと安心。やはり貸し出すときに、よく言い聞かせないとダメだな。 小雨交じりの天気で、これならば空いているだろうと、今週も上野駅で途中下車する。本日のお目当ては東京都美術館の「マウリッツハイス美術館展」。入場の並びもなく、順調に会場内へ。風景画・歴史画と想定内の混雑レヴェルで、空いてはいないもののギュウギュウ状態ではなかった。ルーベンス・レンブラントと続いて、フェルメール1作目「ディアナとニンフたち」。やはり混んでいる。だがそうひどくはない。のろのろと進む列に身を任せながらご対面。画面向って左側に窓があるタイプではなく、初期に取り組んだ歴史物だ。だが、対面して瞬時に感じる、画面の中の様々な直線が形作る構成美。まさにフェルメールの世界だった。有名な、風俗画タイプではないせいで、客足も早く流れていくので、流れに逆らいじっくり鑑賞できた。 興奮冷めやらぬまま1つ上の階に上がると、またしてもフェルメールが!出ました「真珠の耳飾りの少女(青いターバンの少女)」。今回の最大の目玉だけあって、こちらは最前列で観たい人の列と、後ろからでもいい人の列に分かれている。最前列で観たい人の列がずーっと続くはるか彼方にその絵は鎮座ましましていた。もちろん、そちらの列に並び、待つこと20分。並んでいる途中でもチラチラと人垣の隙間から眺めてはいたけれども、実際に正面に立つと、空中の埃が浮かび上がるような光の加減と、やはり画面の至る所に顕れる直線の交錯による構成美。フェルメール作品トップの人気を誇るだけある、今にも話しかけそうな唇と闇から浮かび上がる耳飾り、画面上部で存在をアピールする青いターバン。あぁ、何もかもが美しい。ため息、またため息。最前列から離れ、後ろからでもいい鑑賞スペースでさらに鑑賞。 それにしても、先週のベルリンのものとはどうしてこうも違うのだろう。
2012/07/20
コメント(0)
-

今日もオモダカ
連日の暑さに、オモダカもぐんぐん成長。葉っぱの一番大きいところで、高さ50cmを越えた。いや、ホント、丈夫だワ。 オモダカの奥に見えるのはゴーヤ。既に3m越え。ちらほらと黄色い花を付け始めている。 午前中の日射しを浴びていたら、みるみる焼けてしまった。って、既に黒いけど。昼からはテニス。このくそ暑い中、よくやるよ・・・って毎年代わり映えしない自分へのツッコミ。
2012/07/16
コメント(0)
-

オモダカ開花
ヤゴ水槽で栽培している、オモダカが開花した。だが、しかーし。八重咲きの園芸品種だった。小指の先ほどのごくごく小さい白バラのような感じで、これはこれできれいなのだけれど、自生種だと思っていたので、ちょっと残念。 次の写真はシオカラトンボのヤゴの羽化。こちらは大きめのヤゴを入れた、ハスの鉢のもの。寝坊だったらしく、6月7日朝6時の時点でこんな状態。今年2頭目の羽化で、ハスの立ち葉に掴まって羽化していた。こういう写真はなかなか撮れないので、お寝坊さんに感謝。 この後も順調に羽化している。ハスはもっとも高い立ち葉が150cmほどになり、7月13日には花芽が水面から顔を出し始めた。今月末くらいには開花する予定。
2012/07/15
コメント(0)
-
フェルメール第一弾
非常勤からの帰り道、上野で途中下車して国立西洋美術館へ。本日はフェルメールin上野の第一弾で、「真珠の首飾りの少女」を鑑賞する。 駅の広告などで見かけられるように、このフェルメールばかりか「ルターの肖像」も日本初公開だ。混雑が心配されたが、まったくの杞憂であり、たっぷりと鑑賞できた。 それにしても、「真珠の首飾りの少女」はちょっと期待はずれだった。画面向って左に窓が描かれ、フェルメールらしい光と影のコントラストが浮かび上がる。確かに、いかにもフェルメールなのだけれども、なんかちょっと違う……って感じてしまう。黄色の色使いとか、平面上の構成美とか、フェルメールっちゃあフェルメールなんだけど。 画集で見ていたときには気にならなかった、鏡に向かい合う女。これ、実際に見ると、鏡と向き合っているように見えないのだ。女は鏡ではなく、窓の向こうの何かに向って首飾りを見せているように思えてしまう。 それと、結構カットされてしまう机の下の、謎の白い物体。暗がりになるはずなのに、なぜか一箇所だけ異様に明るい(白い)のである。それより何より、「ミルク壺」にしても「手紙」にしても「青いターバン」にしても感じられる、一連の動きの中の一瞬を切り取ったかのような、静謐にして緊密な空間が感じられないのだ。なんだろう、この奇妙な違和感。15分以上、フェルメールの前で、行きつ戻りつしながら見たのだけれど、この違和感は最後まで拭い去れなかった。 それにしても、この夏は、上野にフェルメールが3点も来ている。春には渋谷に1点来ていたし、なんか日本の財力ってホント怖ろしい。
2012/07/13
コメント(0)
-
メダカ他いろいろ
今年は寒さが厳しかったせいか、3月下旬になっても水温が上がらず、恒例のメダカ水替えが行えなかった。基本的に屋外飼育のため、メダカは冷たい水底でひっそりと生き抜いている。それも本日で終わり。一昨日から汲み置いた水を使って、朝からメダカ水槽の大掃除に取りかかった。 まずはヒメダカの鉢から。ヒメダカを避難させ、アナカリスを取りだし、増えまくったサカマキガイは底砂と共に庭土の養分になってもらい、スイレンの株分けを行う。ヤゴが数頭見つかったので分けておく。スイレンは元気な株を3つ残してあとはドロドロに溶けた葉と茎と共に土に還ってもらう。この鉢には、最も大きな株を残し、ヒメダカも戻す。ついでに他の水槽で増えたタニシ(品川区産)を投入。 続いて、トンボが卵を生み付けやすいようにセットしておいたトロフネをあさる。夏から秋にかけて順調に育ったヤゴ達。沈めた枯れ葉がドロドロになっていて、それを掬い出すとヤゴがうじゃうじゃ。その数40頭以上(というか、30を過ぎたあたりで数えるのを放棄)。ひとまずそれらと同居のタニシをプラケースに避難させ、トロフネをリセット。今年はオモダカの苗を入手したので、それも植えて、大きめのヤゴを除いて戻す。 続いて、クロメダカのトロフネへ。今年の冬を生き延びたのは10尾ばかり。増えたセリ(品川区産)・アナカリスと共に、クロメダカ・タニシも掬い出す。残念ながらヌマエビは1尾も生き残らず、すべて★に。この水槽にもヤゴが10頭ほど生き延びていたので、それらはヤゴ水槽へ。セリは株分けして、芽吹き始めた部分を少し残して、後は土に還ってもらう。株分けしたスイレンもここに転入させた。 次に昨秋のクロメダカ稚魚を入れておいたプラスチック樽にとりかかる。厳冬にもなんとか耐え抜いて育ったやつらをクロメダカ水槽に移し、ガマ(品川区産)の株分け。昔、白菜の漬け物を作っていたプラ樽なので容積が大きく、やはりここからもヤゴが見つかる。もはや数える気力もナシ。既に芽吹き始めたガマの株を2つ残し、元の鉢に植え直し、鉢ごと樽に再投入。この鉢を埋めるように、粘土質の田土を大量に投入していく。 実は、今年の研修旅行で萬福寺をコースに入れた裏の理由がある。それはこの寺で廉価で分けてくれるハスを入手したいためであった。激安のレンコンをこの樽で育てたかったのだ。長らくの夢がついに現実のものとなる!田土もこのために前もって入手しておいた。準備はばっちり!ということで、東京に戻って以来水に浸しておいたレンコンをセットした。この樽には、大きめに育ったヤゴを住まわせる。一部のタニシも同居。あぁ、ハスの立ち葉でヤゴが羽化し、ハスが無事に咲きますように! 最後に、カダヤシ水槽(小ぶりなプラケース)。何も手を加えていないので、昨年カダヤシはいっさい増えておらず、同郷のミナミヌマエビ・タニシがいるのみ。このカダヤシには、萬福寺の枝分かれしたレンコンと共に新しい鉢に引っ越してもらい、ミナミヌマエビとタニシのみでリセット。 ここまでで、昼を軽く過ぎていた。ホテイアオイを購入し、ヒメダカ・クロメダカの水槽に浮かべると、春の大掃除は終了。みんな、無事に成長しますように。
2012/04/29
コメント(0)
-
本年度第一子
研修旅行から戻ってきたら、本が届いていた。『古代中世文学論考』26集で、奥付は本日26日。 論文タイトルは「『新続歌仙』撰者考―宗尊親王との関わりを中心に―」。36人秀歌撰の1つ『新続歌仙』が誰の手によるものなのかを考察したものだ。選ばれた歌人36人の中で、唯一、正元2年の段階で勅撰集作者となっていない宗尊親王の採録歌などをふまえて考えてみた。和歌関係の先生方には、連休頃にお送りする予定。
2012/04/26
コメント(0)
-
研修旅行最終日
あっという間の4日間で、本日は最終日。バスで黄檗へ。 京都で最も好きなところの1つ、黄檗宗萬福寺に全員で参詣する。この中国風禅宗の寺は、ある意味、キッチュ(失敬な!)。金色の布袋様を拝み、どこか中国風な作りの数々に、「おまえ達、屋根の上も見ろ~」と叫ぶ自分。通常の寺では見られない意匠があちこちに施されている。 法堂(ハットウ)に移り、座禅体験を行う。その後、清々しい気持ちのまま、向かいの普茶料理の店に移動する。中華風精進料理の店「白雲庵」だ。1学年上の研修旅行も、この萬福寺を訪れたが、昼食はこの普茶料理の松花堂弁当にしたとのこと。それじゃあ、普茶料理の良さは味わえないじゃん!ということで、引率者権限で、今年の学年はランチコース料理に。 あ~、美味美味 現在は野菜くずは使わないけれども、雲片(ウンペン)が象徴するように、みんなで取り分ける精神、すべてを食べきる精神。これを体感できるところが良い。 ちなみに、今回のご飯は「桜ご飯」だった。桜の塩漬けを用いた炊き込みご飯だ。筍ご飯かと思っていたが、まだ、桜の時期らしい。前に来た2回は、6月下旬の時がグリンピース(?)、9月下旬の時が栗ご飯だった。できることなら、1年すべてを制覇したいものだ。 普茶を食べ終え、一路京都駅、そして東京へ。無事研修旅行も終わった。
2012/04/25
コメント(0)
-
研修旅行引率
勤務校の学生引率で滋賀・京都へ。初日は、三井寺と琵琶湖博物館を廻って、保育実習をお願いしている施設でのオリエンテーション。 2日目の昨日は、朝のうち少し小雨交じりだったものの、みるみる晴れて、かんかん照りに。クラスを2つに分けて、片方のグループが保育園に、もう片方のグループが京都での自主研修に入る。自分は、保育実習のグループの方に参加し、子どもと関わる学生の姿を見学する。今回お世話になる保育園は、ユニークな保育方針と恵まれた環境で、この世界では割と知られたところである。 3時過ぎに実習を終えて、バスに拾ってもらい、京都自主研修組と合流して、一路、大津京跡へ。大津京跡を車中から見学して、近江神宮へ。 バスガイドさんも「初めて来ました、どうしてここを?」 ハイ、佐藤のリクエストです。わずか5年とはいえ都の置かれた地。こういう機会じゃないと観られないし、宿泊地から遠くないので、見学コースに組み込んでもらったのだ。まぁ、学生はあんまり楽しくないだろうけれど。 3日目は、京都自主研修組と共に行動。前日同様、保育園で保育実習組を下ろして、三十三間堂に移動。今年の大河ドラマに合わせて、コテコテの観光地を選択。市内観光のアクセスの便利さと、意外と行ったことのない学生が多かったことで決めた場所。 学生と別れて、時間調整のため、今までお参りしたことのない、誓願寺に立ち寄る。新京極の端にあり、これまで錦天満宮も蛸薬師もお参りしているのに、行ったことのなかった寺。“山までは見ず”ってところだろうか。謡曲にもある誓願寺は、予想どおり小さな寺で、朱印をいただくと終了。少し時間が余ったので、蛸薬師にも立ち寄る。マスコット(?)のタコを撫で撫でして、裏庭へ。ここは小さな坪庭があって、メダカとスイレン鉢がたっぷりあるので、メダカ飼育者としては、ぜひぼんやりした時間を送りたいところ。 予定の時間になって、佐藤的メイン中のメイン、壬生寺へ。フフフ、ご存知の方も多いだろうが、この時期、壬生寺は、「壬生大念佛会」いわゆる壬生狂言を開催する。壬生狂言は熱田と横浜で観たことがあり、視聴覚教材も持っているのだけれども、うちの研修旅行がこの時期にあたっているため、是非とも本場で観たかったのだ。街中の普通のうどん屋でうどんをすすり、早々に並んで、待つこと45分。無事、最前列を確保でき、ふと足元を見ると、蜘蛛の糸(鉛の芯付き)が。どうも昨日の演目に「土蜘蛛」が入っていたらしいが、拾われなかったのだろう。お金が貯まると言われるお守りなのに。勿論ゲット。 最初の演目は定番の「炮烙割」。2人の男(鞨鼓売りと炮烙売り)のやりとりが続き、舞台正面の欄干に、素焼き(?)の皿が山と積まれる。解説によれば、その数1000枚。瞬く間に、炮烙売りの男が皿の山で見えなくなる。と、そこへもう鞨鼓売りが再登場して、ガンガン皿を落としていく。素焼きの皿は粉々に砕け、もうもうと立ち上る赤茶色の土煙が観客席に舞い上がる。ありがたや、ありがたや~。学生にもさんざんアナウンスしたのだが、これを観に来た者はいなかったようだ。残念。 本日の演目は、この後、花盗人・道成寺・・・と続くのだが、時間の関係で席を立ち、南に下って京都水族館へ。京都の自然をアピールする、今年3月にオープンしたての水族館である。日本周辺の海を1つにまとめたという“ウリ”の大型水槽は、なんだかごちゃごちゃして、ちょっとビミョウ。里山を模した巨大ビオトープはまだまだ植え付けが始まったところで、今ひとつ。これから初夏にかけてぐんぐん成長していくことだろう。手入れが大変だろうけれど。里山らしさを出すためか、クロメダカの群れが泳ぎ、すでにアメンボが来ていた。 学生集合の20分前に京都駅前にて添乗員さんと合流。三々五々戻ってくる学生を迎え、さらには保育実習を終えた学生のバスに乗り込み、一路、将軍塚大日堂へ。またまたバスガイドさんから「珍しい場所を回りますねぇ」とコメントをいただく。ガイドさんも仕事では1回しか来たことがないらしい。ここもまた、車でないとなかなか行けない場所なので、組み込んだ場所だ。ガイドさんの説明に佐藤が解説を加え、夕刻、日の沈む京都市内をみんなで見下ろす。「京都でも指折りのパワースポットで、カップルがよく来るんだよ」と言うと、さすがに学生も盛り上がる。みんな、良い恋愛ができますように(祈)。 遅咲きのしだれ桜があちこちに植わっていて、庭園も見事だった。大日堂は秋ももちろんだけれども、この時期も良いかもしれない。 かくしてハードな1日が終わり、かと思いきや、実習でお世話になったところの園長先生に来ていただき、夕食後に振り返りの講習会。学生が居眠りしたらどうしようなどと思っていたが、杞憂だった。実習を終えたばかりということもあり、保育方針や保育の視点について、しっかり話を聞いていた。実りある実習になったようである。
2012/04/24
コメント(0)
-
狂言の会@四谷
高校以来の友人からの突然の誘い。聞けば、大学時代の同級生が狂言方に弟子入りして、小さな狂言の会をしているとのこと。そりゃ、行かねばなるまい、ということで、四谷へ。 大蔵千太郎とその弟子、という会で、通常の装束は着けない袴狂言。本日の演し物は「土筆」「棒縛」。友人のそのまた友人は「棒縛」に出演。以前、渋谷JeanJeanで行われていた狂言ライブ以上の臨場感で、なんか、どこに目を向けて良いやら困ってしまうほどの近さの舞台だった。役者の息づかいをしっかり感じ取れる空間で、それでも大蔵宗家のきちんとした型を提示する狂言の会であった。 千太郎さんの狂言は半年ぶりくらいだろうか。観る度に、お父様に似てきている気がする。アフタ狂言では、出演者を交えての軽い飲み会で、替えの型とか、本日拝見してちょっと疑問に思ったことを、あれこれ教えていただいた。自分みたいな素人にも、丁寧に回答してくださる千太郎さんに感謝である。軽いワークショップもあり、古典芸能が遠い存在ではないということを感じられる公演だった。 会場を出て、友人とサシで飲み直していたら、あっという間に11時30分過ぎ。慌てて帰宅。
2012/04/12
コメント(0)
-
本屋大賞
先般、ここの日記で記した『舟を編む』が本屋大賞第1位を獲得した。2位を突き放しての大賞受賞だ。取り上げた作品が大賞を取るというのは、非常に嬉しい。先月の日記で記したように、辞書編集の末端に籍を置いた者でなくても、長い年月をかけて1つのものを作り上げていくという行程が丹念に描かれていて、面白く読めると思う。 本年の本屋大賞の上位作品も、良い作品が並んでいた。が、やはり、これが一番というのは非常に納得できる結果だった。
2012/04/11
コメント(0)
-
安宅@目黒
怒濤のオリエンテーション期間も本日で終了。定刻過ぎまでがっつり働き、「香川靖嗣の会」へ。狂言「川上」には間に合いそうもなく、だからといって必死に間に合わせようという気持ちもなく、目当ての「安宅」に丁度間に合う形となった。 香川靖嗣はなんていうのか、とにかく好き。きりっとした硬質の透明感っていうのか、舞台の1つ1つが洗練されている。本日のパンフレットに「硬質の清潔感(by小林責)」という言葉があって、まさに「そのとーり!」。ご本人の挨拶文によれば、「安宅」のシテは「不似合いな曲」なのだそうだが、いやいや、とんでもハップンでございますわよ。 そもそも、現在の喜多流では、同山ドウヤマの見栄えは言うまでもなく、そこに小柄なのに一際きりりとした重厚な弁慶だから、非常に格調高い舞台であった。ここ最近では、宝生の大坪喜美雄シテの「安宅」が感動的だったが、それとはまたひと味違う透明感のある舞台だった。もう、ホント、ご馳走様でした。
2012/04/07
コメント(0)
-
入学式
授業時間数の関係で新2年生は既に2日からオリエンテーションが始まっている。で、本日が入学式。全国の短期大学が苦戦する中、おかげさまで、本学は定員充足率も110%を超えた。新入生諸君、頑張れよ。 式典の司会を任されてはや十余年。今回初めてお見えいただいた来賓の方に「プロの司会者かと思った」と言われてしまった。んー、喜ぶべきなのか? 入学式終了後は新入生のオリエンテーション。そして気が付けば、6時間以上立ったまま、飲まず食わずだった。どうしてこれで痩せないのよ?<自分
2012/04/04
コメント(0)
-
女流ダブルヘッダー
怒濤の年度末(研究日なんて皆無な出勤)を終え、年度初めは唯一の休日日曜日、オー、ビューティホー、サンデー銀座にて和泉の狂言を鑑賞する予定であったが、一昨日、恩師2号(って誰よ)からのお電話で、金春会に赴くことに。私の恩師の女子大での同窓生が、なんと金春の富山禮子さんだったという驚きの事実。そして本日が舞納めとのこと。しかしながらお師匠さんのお体の具合がよろしくなく、不肖、この私が代理で伺うことになった。えぇ、富山さんの舞納めとあらば馳せ参じますとも。ということで、女流能楽師を引っ張ってきた富山さんのお舞台を鑑賞して、その後、銀座へ。女性が活躍するということが今もって大変な世界ではあるのだろうけれど、そして、女性が演じることでその特質が上手く出るのかという問題も今なお残ってはいるのだろうけれど、様々な女性の形を考えさせられた一日だった。
2012/04/01
コメント(0)
-
宝生五雲会
雨交じりの本日は、グラウンドの使用に関して、地域の方との話し合いに参加(こういう仕事もあるのだよ)。その後、研究室の汚れを綺麗にしたり、紀要の刊行の最終チェックをしたり、とバタバタしているうちに2時をまわる。 「げっ、もうこんな時間!?」 ということで、水道橋に向かい、宝生の五雲会に行く。楽しみにしていた武田孝史の「祇王」にタッチの差で間に合わず、もう一つの楽しみだった高橋亘の「海人」のみの鑑賞となった(いや、今日は「竹生島」も「箙」も楽しみだったのだけれど)。宝生は全体に地味(←失敬な)だけれど、かえってそのシンプルな謡と舞が良い場合もある。「海人」で言えば、「シンクロかよ?」と突っ込みたくなるような奇妙な舞もなく、ひたすら謡を聞かせ、舞を見せるという、なんか朴訥とした職人さん的な見せ方が良い。 今回の「海人」は、ここ数年で観た高橋さんの舞台で一番の出来ではなかろうか。丁寧さと情熱を併せ持った「海人」で、<玉ノ段>では久しぶりに泣いた。 この「海人」のシテ(前場)は曲見シャクミの面をかけるが、なんかちょっと違うような気もした。多分、曲見なのだろうけれど、それにしては少し艶のある雰囲気だったのだ。んー、なんかちょっと色っぽい?後場の龍女は一転、風格を漂わせたものだった。 地謡がもう少し揃うともっと良かったのだが・・・ブログの記録をすっかりさぼっていたので、今年に入ってから観た能の記録も。[1月8日宝生会月並能in水道橋]翁 山内崇生・金森良充・山本則俊宝の槌 山本泰太郎羽衣<盤渉バンシキ> 三川泉鉢木 水上輝和*少年だった金森君がもう千歳を務める年齢になった。はぁ~、おじさんも年を取るわけだよ。*今回はアメリカから留学している女子学生を連れていった。彼女は、向こうの日本語教材で「羽衣」を勉強したとのこと。同年代の日本の若者で「羽衣」の話は何割くらい浸透しているのだろう???考えるだに恐ろしい。*「鉢木」はしなびた常世っぷりが秀逸。ワキが森さんあたりだとなお良かった気もするが。[1月9日梅若玄祥舞台生活六十周年記念祝賀能in千駄ヶ谷]松山天狗 梅若玄祥土蜘 梅若玄祥*楽しみにしていた「松山天狗」。観世では近年の新演出で、筋立ては面白い。ただ崇徳院の装束で、冠の巾子が異様に長い。何十センチあるのだろう?そのため、塚の作リ物から登場する際に、頭を下げなくてはならなかった。上皇が西行を前にして頭を下げるのはどうなのだろう。*舞台60周年だから派手にやるかなと密かに期待していた「土蜘」。そんな佐藤の期待を裏切らず、前場の怪しい僧の段階で4発、後場の土蜘蛛の精にいたっては14発も蜘蛛の糸を撒き散らした。ワキの宝生欣哉は、蜘蛛の糸でよれよれ。もうグルグル巻きで、この人、勝ったの?負けたの?っていうくらい。能舞台全体が真っ白になるほどで、もう笑うしかない。いや、もう嘘偽りなく笑えた。めでたい祝賀能にふさわしい舞台だった。[1月28日宝生流企画公演 時の花・冬]福の神 山本東次郎高砂 小倉伸二郎*企画公演「時の花」の第1回公演は、開演前に雅楽演奏をロビーで行うというもの。若手で注目される(←自分目線)小倉伸二郎による高砂。公演パンフレットがいつもの宝生流とは違って、カラーで、しかもオシャレ。伸二郎さんのアップなんかもあって、通常の能の公演とは異質だけれども、なんかその異質さが嬉しい。第1回公演で思い切った人選をしていると感じながらも、内容は期待以上。前回観た、伸二郎さんの「高砂」はシャープさが際だって良かったけれども、その時とは違う重みが出ていて、初春の播州の爽やかな風を感じた舞台だった。*「福の神」はめでたい第1回にさらなる花を添えた作品。派手ではないのに、めでたさ100%という山本東次郎らしい舞台だった。現在「福の神」で一番観る価値のあるのが東次郎さんではなかろうか。
2012/03/17
コメント(0)
-
卒業式そして謝恩会
昨年は卒業式・謝恩会は中止となり、昨年10月末に卒業生の集いを開き、一応の卒業式をすることができた。 今年は15日卒業式・16日謝恩会と、つつがなく送り出せた。毎年のことだが、15日は、通常の卒業式とソフトテニス部の謝恩会、そしてその2次会と、怒濤の一日となる。今年の卒業式は、佐藤の生まれた年からうちの短大に勤務して、最後は学長を務めた先生が退任でもあったので、美しい卒業式にしたかったが、音声関係でアクシデントがあり、冷や汗。まぁ、式典の司会も12年間自分が担当しているので、そういった動揺は隠し通して、事なきを得た。 16日の謝恩会(卒業記念パーティー)ものどかなムードで、楽しかった。うちの専攻はほとんどの学生が幼稚園教諭・保育士として社会に出て行く。これまでは学生目線であれこれ自由気ままにやっていただろうが、これからは子どもを育て導く立場になっていく。学生気分を捨てて、新しい職場に臨んで欲しい。 パーティー会場のすぐそばに出光美術館がある。まもなく終了の展覧会に駆け込みセーフ。
2012/03/16
コメント(0)
-
フェルメール3発
本日は朝から県庁に赴き、教員免許の受領。自分の免許、ではない。卒業生のもの。教職の教員が受け取りに行く大学ってどれくらいあるのだろう?貴重だぞ、S学院の諸君。大学に戻って、シラバスの原稿を印刷会社に渡し、明日の会議の準備をしたら、もう夕方。あぁ、こうして今日も日が暮れる・・・ フェルメールの絵を観に渋谷へ。終了間際だけれども、閉館時間近くなので混雑もさほどではない。今回は3点、しかも修復後の世界初公開という「手紙を読む青衣の女」も来ているとあって、本日が2度目の鑑賞。 今回は上記の絵の他に「手紙を書く女」「手紙を書く女と召使い」と、手紙にまつわるフェルメールが揃うということで、展覧会のタイトルも「フェルメールからのラブレター展」。ちょっとやりすぎな観がなきにしもあらず。 この中では、最も完成度が高いと思われる「召使い」が面白い。静謐感と構成美の極致、ただそこにあるだけでひれ伏しそうになる。いやぁ、素敵ザマス。 意外というか、「手紙を書く女」は生で見た方が綺麗だった。もっとぼんやりしているかと思ったら、テーブルに載った真珠の粒などがくっきりと光を放つかのように見える。 「青衣」は修復の過程を説明するプレートが1枚と控えめ。もう少し、詳しく知りたいところだった。絵自体は左側からの光というよくあるタイプで、青みは思ったほど濃くない。意外とあっさりしていた。 今回の展示は40点と点数も多くないし、部屋の構成も簡素だったけれど、その分、1点1点をじっくり眺められるので、良かった。中では、デ・ホーホとヤン・ステーン。まぁ、ネーデルラント絵画史では王道。王道だからこそ、やはり目を惹く。ヤン・ステーンは絵のあちこちに象徴的な物が配されていて、絵からなかなか離れられない。もちろん、その象徴するものが何かわからないものが多数なのだが、“何かありげ”な感じがして面白い。今回のフェルメールは3カ国から同時来日。夏にも大物が来るし、んー、ジャパンマネー、おそるべし。
2012/03/12
コメント(0)
-
舟を編むby三浦しをん
ブログ更新をずっとさぼっている間も、粛々と読書生活は続いていた。そんな中、これは!と思ったのが、本日の日記タイトルの作品。目頭を熱くさせながら一気に読了。その後、あちこちでも話題になり、次回の本屋大賞へのノミネートも決まったそうな。 『大渡海』なる中辞典を編纂する編集者達を描いたこの作品。何をするにもとろいが、言語感覚に卓越した主人公とその周りの人々を描く。辞書編纂の裏側が垣間見られる上、登場人物それぞれの書き分けもしっかりして、非常に面白かった。 ・・・とまぁ、普通なら「面白かった~」ですむのだけれど、この辞書編纂の裏側、という点で、自分のような人間にはさらなる思い入れを抱いて読んでしまう。というのも、修士の頃から日本国語大辞典第2版の下働きをしていたからだ。 いつも用例カードを手放さない松本先生は、辞書編纂のために大学教授職を早期退職となどとあり、「ん~、M先生そのまんま(亡くなってはいませんけど)」などと重ね合わせてしまう。夕方来て終電ぎりぎりまで働く院生って、オレだよ、オレ(という学生多数)。怒鳴っている元編集長とか、営業に回ったチャラオとか、ファッション雑誌から回ってきた女性編集者とか。この作家はニッコクと何かあるのかと思っていたら、末尾の謝辞にあそこの編集部の方々の名前が並んでいた。なるほど。 もちろん実在の人物そのものではなく、あくまでも登場人物の参考ではあろうが。 そうした点を除いても、人物の描写や、人々が辞書の編纂に向けて奮闘する様子が胸を打つ。言葉の海に漕ぎ出す舟を編む。そういう部分がひしひしと伝わるから思わず泣けてしまうのだろう。辞書を作る国語学者の視点ではなく、編集者側からの視点というのも面白かった。ここ数か月で一押し。
2012/03/10
コメント(0)
-
双子出産
ここのブログも気が付けば10か月も放置していたのだ。まぁ、佐藤はそれなりに元気である。と、このブログで安否を気にする方もいないだろうが。さて。現在の短大に勤めた年の5月、いきなり目白に呼び出され(いやいや、お声をかけていただき)始まった「Project-NAGATO」。*本文校訂と脚注、そして論文集で完結した3冊本*本文表記の確定を行った4冊本*これで終わりと思いきや、自立語索引*まだまだ終わらぬ、延慶本との本文対照そしてそして、索引から関わっていただいた小川栄一先生による『長門本平家物語に関する基礎的研究』(科学研究費補助金基盤研究C:20520182)が刊行された。索引と本文対照を利用して、「考察をせぃ」ということで、ながらく気になっていた「鬼瓦」の話と延慶本・長門本の和歌の位置の異なりについての話の2編を発表させていただいた。どちらもすっきりとした結論と言うよりは、問題提起になってしまった観がある。16年かけた集大成というには、ちと寂しいが、まぁこれで「Project-NAGATO」も本当の完結だろう。 ということで、本日、双子の出産。週明けには、まったく分野の異なる子がもう1人誕生する予定。
2012/03/09
コメント(0)
-

メダカその他近況
昨日の雨交じりから一転、本日は暖かな一日となった。久しぶりに3時間テニスで汗を流す。最後の1時間はシングルスなんかもやっちゃったりしてクタクタになった。んー、まだ走れてるぞ、自分。 先日、再セットしたメダカ水槽は29日から抱卵が始まったため、ヌマエビとはしばしのお別れ。写真は株分け直後のセリのような植物(今年で6年目の品川区産)とその周りで遊ぶクロメダカ。植木鉢の縁に着いている小さな巻き貝はヒメタニシ。このヒメタニシもヌマエビ同様品川区産で、昨年我が家で生まれたもの。現在は親サイズが4頭、秋に生まれた稚タニシが10頭ほどいる。 去年至る所に産み落とされたヤゴは、体格にかなりの個体差があって、間もなく羽化しそうなものから、まだ数ミリのものまでばらばら。無事に越冬できたということは、ウスバキトンボではなかったようだ。ボウフラ等が手に入らず、共食いの畏れもあるけれど、何頭かは無事羽化するだろう。
2011/05/04
コメント(0)
-
普通に授業
文部科学省では「大学」の授業回数について、本年は震災の関係で弾力的に扱うようにお達しが出たらしい。ここでポイントなのが「大学」ってところで、どうやら短期大学はそのお達しの埒外にあるようだ。 うちの学生にも、連休の間なのに……と文句を言うヤカラがいる。「世の中には、(授業回数の確保のために)祝日も授業を行っているところもあるんだよ」と諭す(毎年のこと)。 まぁ、文部科学省が良いと言っても、厚○労イ動省が許さないだろうけれど。 ところで、この◆生労イ動省だが、やることが極端だ。そもそも、授業回数の確保について病的に厳しいのは、ほとんどチェックをしないできたために、無法状態となった専門学校などがあり、それが総務省に指摘されたことの反動だ。元々がいい加減だったのに、手のひらを返すように厳しくする体質があそこにはある。 そう思うと、今騒がれ始めているユッケ問題も、生食用ではない肉の管理体制など、ここのお役所がきちんとしていないことも関係してこないか。被害にあった方々は本当に気の毒である。
2011/05/02
コメント(0)
-
天恵あるいは自分へのご褒美
実は1か月ほど前に、某所に論文を投稿した。相模原の非常勤に通い始めた頃から取りかかったテーマなので、5年越しとなる。中断の時期を経ながらも、昨年夏には一応の形になった。その後、もう少し絞ろうと思いながら放置していたため、忙しさの反動か、勢いで(ヤケクソともいう)投稿してしまったのだった。 忙しくはあっても、自分の扱う文学作品を考えられる時間を作ると、自然と気持ちも盛り上がるもので、「あぁ、やっぱソウソンはいいワ~」なんて思っていた矢先、昨晩突然に、ある先生からご連絡が。なんと『文応三百首』の写本が入手できるかもしれないと。なんですとぉ?!ということで、早速売り手の方に連絡を取って様子を尋ねる。その話で「それはおそらく混態本B群と分類したグループであろう」と推測できた。互いの都合が丁度あったため、その日のうちに合流、実際に目にすると、予想通り、混態本B群であった。楮紙系の写本が多い中で、これは鳥の子列帖装で、金箔を散らしたなかなかの料紙。字も江戸前期で、なかなか品のあるものだった。 別筆の合冊本をばらした状態ということで、『宗尊三百首』としてはちゃんと揃っているのだが、表紙もなく、ところどころ虫損も著しい。そんなわけで信じられないくらいの低価格でお譲りいただけることとなった。 帰りの電車でも、思わず顔がにやけている自分(アブナイ人)。 研究とは無縁の生活が続き、気分的にもモヤモヤした状態が長らく続いていたところ、「もうちょっとしっかりやれ」という天の叱声であろうか。頑張らなくちゃ。 ちなみに、混態本B群は、久松潜一先生旧蔵コクブンケン本と久保田淳先生所蔵本が判っていて、これで3冊目となる。
2011/04/29
コメント(6)
-
フェルメール
この2か月は度々書いているように、怒濤の日々で、出光で行われていた、「酒井抱一生誕250年 琳派芸術」も前期をまず行きそびれ、後期は駆け込みで行こうと思っていたところで地震に遭い、結局行けなかった。落ち込みまくり。 で、本日はフェルメールの「地理学者」を観に渋谷に行く。こちらもようやくの鑑賞。 「地理学者」は各種テレビでも取り上げられている、東京初上陸の作品。「待ってましたっ」と声をかけたくなる作品の登場である。いやぁ、ここ数年、フェルメールが続々と東京にやってくる。ありがたいことだ。 今回の展示はフランドル絵画をテーマ別に分類している。始まってすぐの寓意画とか興味深い。絵の中に配されたものが色々な意味を持っているということで、しばし足を止める。3つめの展示室が風俗画と室内画のブロックで、さっそく「地理学者」の登場。あぁ、美しい!フェルメールらしい、向かって左の窓からの光が射し込み、空中の塵さえもが浮かび上がってくるよう。そして、そのシンと静まりかえった雰囲気。背後に配置されたものが緊密な構成を浮かび上がらせている。人がいなければ、何時間でもそこに立っていたくなるような素晴らしい作品だった。 フェルメールがらみの展覧会は、最後の目玉としてかなり後の方にフェルメールを持ってくることが多いようだが、実はこれをやってくれると、観客の何割かは鑑賞に疲れ、軽く流していくようになる。しかし、今回は展示の中ほどで、観る方もまだまだ元気な状態であり、多くの人が長らく鑑賞しているため、なかなか列が進まない。しかも、長く立ち止まるのも他の人に迷惑をかけてしまう。なので、しばし鑑賞の後は、列から離れ、人の切れ目から鑑賞せざるを得なかった。まぁ、朝一番とはいえ、日曜日に出かけているのだから仕方がない。あぁ、もう少し背があったら!
2011/04/24
コメント(0)
-
ママ・ミア
新入生とともに行くフレッシュマン・セミナー。今年は震災の影響で1泊2日の旅行を取り止め、学内でのセミナーに変更となった。2年生はこの時期研修旅行に旅立っているので、人少ない大学にてセミナー開催の運びとなった。担任その他、セミナーに関わる教員も学内にて代替企画を進める。 初日の19日は、まず学長の講義。文部科学省が提示する最新の話を織り交ぜているのだけれど、学生達はちゃんと理解できただろうか?就業意識とか、とても大事な話なんだけど。まぁ、おかげさまで担任クラスの学生は静かにきちんと聴いていたので、一安心。 午前後半は、各学科専攻独自の企画を立てた。うちは絵本と紙芝居の魅力という講義と実演を兼ねたものを行った。鴨川であれば、家畜農場の体験学習だったところを、保育士・幼稚園教諭としての技能を学ばせるために、このプログラムに変更した。 講師でお招きした先生にも同席していただき、昼食を摂り、午後は全体での能力開発セミナー。体験型で、かなり盛り上がっていた様子。 そして2日目の今日は芸術鑑賞。汐留の四季劇場「海」に赴き、ミュージカル「マンマ・ミーア」を鑑賞する。「原曲の発音だと“ママ・ミア”だよね~」なんて、学生はそんな話は全く興味なし。ストーリーもなかなか面白かったけれど、アラフォー世代ならわかるだろう、そう、アバの名曲の数々。ヤバイ、ヤバ過ぎる。元歌で歌えちゃう自分がいる。 今回のミュージカルでアバの曲に興味を持った学生も出て、アバのCD(←持ってるのか!)を貸し出すことを約束する。学生が楽しめる、これが何より。 学生をみな帰して、教員は反省を兼ねての食事会。何かあったときのために大学に残ってくださっていた学長も合流し、和やかな食事会となった。途中、各学科の研修旅行から戻った連絡が入り、無事にイベントも終了。 学生さんはお疲れ様、そして先生方、お疲れの出ませんように。
2011/04/20
コメント(0)
-
ギターリサイタル
本務校の系列で、幕張に中学高校がある。そこの今年卒業生である岡本拓也君がギターの国際的なコンクールで2位となり、このたびめでたくウィーンに留学することとなった。昨年の職場の記念式典(創立70周年)で司会進行スタッフとなった関係で、その青年とも知り合いになった。これがまた礼儀正しいきちんとした青年で、オヂサンとしては思わず応援したくなっちゃうわけだ。で、本日は彼の渡欧記念リサイタル。 母がクラシックギターをわりと好きなので、ばぁさん3人(母及びその知人と父方の伯母)を引き連れて、ヤマハホールでのリサイタルに行く。銀座で早めの夕食をいただき、いざヤマハホールへ。ここのホールも改装されて、音の感じがさらに良くなった気がする。小ぶりのホールで、雰囲気も良い。 岡本君のギターはなんていうか、爽やか。ロドリーゴとか、アンダルシアの風(行ったことないけど)が吹いているっていう印象を抱かせる。まだレパートリーは多くないようであるが、これからさらに研鑽を重ねて、日本に戻ってきて欲しい。頑張れ~。
2011/04/16
コメント(0)
-
松戸へ
怒濤のオリエンテーション期間(タンニンなもんで)が終わり、通常の日々が始まっていく。本日は、松戸への初出勤。 8時に上野に着き、常磐線に乗り換えたところ、あちこちで携帯電話が。 来たーっ!地震である。かなり大きい。発車を待っていた電車も揺れている。うわぁ、電車ってこんな揺れ方なんだ。こえ~。案の定、しばらくは様子を見るということで、上野で足止めをくらう。う~、初日から遅刻か?まぁ、みんな遅刻だろうけれど。 多くの学生と共に大学へ。先日の面接及び打ち合わせの時に確認しておいた非常勤講師の部屋へ入る。ここの大学は、非常勤講師のための事務職員を置かない上、当日用のコピー機も置かれていない。専任の教員が来てくださるわけでもなかった。非常勤先が変わるたびに、なんか寂しくなってくるなぁ。 1・2限ともに同じ教室で、1限の時点で容易に予想はついたのだけれど、2限は学生が入り切らなくなっていた。講師室まで走って戻り、空き教室の確認を教務課にしてもらい、学生を引き連れて移動。今年も唯一、古典をガチでしゃべれる授業とあって、初回から突っ走らせていただきました。慌ただしい1日だったが、なんとか終了。
2011/04/12
コメント(0)
-
入学式
計画停電などの懸念もあったが、入学式が無事に挙行された。世間では、入学式の延期(結果的に授業開始も延期)というところもあるが、厚生労働省のからむ学科のあるところはいずこも大変だねぇ。 いつものごとく司会役のため、式の間中、ずっと立ちっぱなし。だが、今年まず気になるのがは、こども発達専攻入学生の顔ぶれ(担任クラスの学生ってことで)。どんな学生たちが来るかと、舞台の上から観察する。2年間よろしく。
2011/04/04
コメント(0)
-
観世会春の別会
久しぶりに、松濤での観世会春の別会に行く。何度か購入している武田さんのところからのお知らせで購入したため、私のような者にはもったいない良席。2月末から怒濤の日々で、休日がほとんどない状態ではあったが、折角入手できたチケットなので、気合いを入れて渋谷へ。 11時から始まった最初の曲は、シテ武田志房の「鷺」。神泉苑に鷺が舞い降りる。鷺の天冠を戴いたシテは文字通りの爺さん(失敬な)なのに、さーっと現れる姿は、鷺というよりも鷺の精といった趣。帝の言葉に従うといった並の鷺ではないあたりを早くも予感させるような格調高い姿だ。 地謡の揃いもよく、華やかで「鷺」の雰囲気を引き立てていた。 狂言をはさんで、続いてはシテ関根知孝の「卒都婆小町」。なにげに期待しているシテ方さんなのだが、こちらが気力体力ともに充実していないせいで、こうした老女物は正直きつかった。ワキ方との仏法に関わる問答のあたりで意識が何度か飛んでしまった。 次の休憩で前の席の方が帰ったため、続く仕舞4番と「融」は視界が開けてさらに見やすくなった。観ているこちらも緊張するゾ。 ラストはシテ津田和忠の「融」<思立之出・十三段之舞><十三段之舞>は最後の[早舞]が長く、そして緩急に富んだものとなる小書。その時間は15分を越え、途中で揚げ幕の手前まで戻って立ち止まる<クツロギ>の型も組み込まれていく。見せ場はたっぷりなはずなのだが、なかなか満足のいく舞台は少ない。気力体力が充実して、なおかつ、囃子方も渾然一体となって、源融の霊が遊び舞うさまを格調高く表現しなければならないからであろう。そのため、スタミナ切れかと思われるような場合も少なくない気がする。今回の<十三段之舞>も、後半やや息切れかと感じた。 観世会による特別義援能のお知らせがあり、予約をする。そして、能楽堂の外では、宗家が自ら募金の呼びかけをしていらっしゃった。心ばかりの寄付をすると、宗家から手が差し出されて「ありがとうございます」のお言葉をいただく。<いや、たいしたことじゃないんで、エヘヘ>とか思って、ひょいと右を見たら、祥六さんも募金箱を手に、立っていらっしゃった。<うひ~、宗家より祥六さんがよかった~>
2011/04/03
コメント(0)
-
新年度開始
新年度の始まりである。ついに、年度末との切れ目というか、切り替えがまったくないまま、新年度に突入である。年度の終わりに処分したい書類がまだ手つかずの状態で放置されている。大丈夫なのか、自分。 本日をもって、正式に発表すると、自分の所属する人間生活学科こども発達専攻が2012年度から定員を増やすことになる(計画中)。定員増の場合は、学科新設に準じた書類の提出があり、担当教員の履歴もすべて再提出となる。文部科学省だけでなく、保育士養成課程の関係で厚生労働省にも提出する書類があり、3月後半はこれが最大の仕事だった。はぁ~、なんとか終わった。 さて、(実際の辞令交付は数日後だが)本日をもって、ワタクシ、教授になった。佐藤智広教授の誕生である。フフフ、権力使いまくるぞぉ!・・・・・・嘘である。 この2年間、丁重にお断り申してきたのだが、空席が2つになってしまい、さすがに教員構成に問題が出るため、お受けすることとなった。普通の大学なら、給与のこととか待遇のこととか、はたまた人事権やら学内政治やらがあるのだろうけれど(白い巨塔か?)、ここでは、給与体系が(事務職も含めて)1本、ある意味、非常にクリーンだ。そのため、勤務年数からいうと、既に2年前に昇任していなければならないところを、年齢的にふさわしくないと自ら断ってきたのだった。 そして、教授になるという前提で、本日より、図書館メディアセンター長・FD活動委員会委員長・カリキュラム委員会委員長・紀要委員会委員長(継続)となった。なんか、学部長クラスの肩書きがばばーんと並んでいる。かと思うと、教員免許申請もするし、シラバス・学生便覧の印刷の手配もするしで、極めつきが今度の新入生の「担任」。いつもなら、教務関係の古株として、履修の注意や課程(教職・保育士)の説明でちょちょっと登場するだけなのに、今回は、オリエンテーション期間中、ずっと新入生に付き添いながら、2年生の教務の説明もこなさなくてはならない。 身体保つかなぁ、43歳の春。厄年か?
2011/04/01
コメント(0)
-
年度末
22日に完了予定だったはずの仕事のフォローがあり、また例年のようにシラバスと時間割作成があり、社会人入学生の既修得単位認定の準備やら、非常勤の先生方への準備やら、結局日曜祝日を除き、連日の出勤。学内での最長滞在時間は13時間を記録した。働いたなぁ、自分。 職場周辺は計画停電の地域に入っているため、昼前後に停電の時間帯の来る日は、仕事も滞る。だが、ヒトもすぐに慣れるもので、停電の時間帯には端末などを使用しない仕事(いわゆる力仕事ってやつですね)ができるよう、上手く配分できるようになった。それにしても、力仕事って???
2011/03/31
コメント(0)
-
壁面作成
卒業式を挙行できなかったため、卒業生への配送などを行いつつ、新年度への準備が進む。で、本日は、新2年生の有志を募り、壁面(幼稚園などでよく見られる壁の飾り)の作成を行う。集まってくれた6人に様々な材料を提示し、「新入生や子育て支援センターを新たに利用する方々に向けた、4月の壁面」を課題として、壁面作成にとりかかった。 佐藤の(本来の)研究分野からすれば、こうした内容のものは正規の授業では行えないけれども、こういうフリーの時間を使うならば問題ない。本年度の学科予算で買い貯めてきた様々な工作素材を使って、学生が互いに意見を出し合って4月らしい壁面ができあがった。 ねぎらいのランチを振る舞い(本八幡だけど)、再び職場へ。あれやこれや、教務がらみの仕事に勤しむ。
2011/03/28
コメント(0)
-
メダカさん、しばし待て
この1週間は舞台鑑賞漬けの日々の予定であった。本日も宝生会春の別会能第1日であったが、早々に中止(7月に延期)の英断が下された。 ここ数年、別会第1日目の午前にマサオのお目覚め&クロメダカ水槽のリセットを行っている。しかし、今年はいつになく気温が上がらず、こちらも延期。持ち帰りの仕事をやったり、本を読んだりして、のんびり過ごす久々の一日となった。
2011/03/27
コメント(0)
-
公演中止
昨日の公演同様、一仕事終えた自分へのご褒美予定だった能楽鑑賞。だが、先般の地震の影響で、3月の国立劇場系の公演はすべて中止。 実は18日に大劇場で鑑賞予定だった歌舞伎公演も中止だったので、本日もないのは既に承知の上で、仕事に出たのだが・・・・・・。昼過ぎに自宅から電話があり、公演中止の連絡が入ったとのことであった。いや、わかってるけど、っていうか、この時間に自宅に電話しても、普通、連絡取れないんじゃあ・・・・・・宝生会は早々に連絡をくださったけれど・・・・・・ 本日予定されていた公演は狂言「川上」と能「調伏曾我」。「調伏曾我」は平成21年度の公演予定(22年3月)にも当初組まれていたのに、上演されなかったもの。今年もまた流れてしまった。滅多に上演されない曲で、<不動>の面を使用する点でも興味深いが、どうも縁がないようだ。
2011/03/24
コメント(0)
-
久々の舞台鑑賞
14・15日は震災後の様子見ということで特別休暇、その後16日からは連日の出勤が続く。千葉県内でも被災なさった家庭があるという。1日も早く、復旧されることを祈る。 22日に仕事のとりあえずの完了予定があったので、本日は自分へのご褒美用に予約購入した舞台鑑賞。シアターコクーンにて、こまつ座公演(井上ひさし追悼ファイナル)「日本人のへそ」を観る。 掛詞というか、音の連想によって紡がれていく言葉言葉言葉。謡曲や歌舞伎台本にも似た言葉の響きが耳に心地よい。この辺りは、井上ひさしの真骨頂であろうか。 舞台は、吃音治療のための芝居という設定で始まる劇中劇と思っていると、第1幕ラストで、その吃音治療という設定さえも劇だったという入れ子型構造の展開。そこに殺人事件もからみ、第2幕は犯人捜しへ突入。二転三転するスピード感ある展開が面白い。追悼公演ということで、19年ぶりの上演とのこと。吃音を扱う点で公演を避けていたのだろうか、かなり面白いストーリーだと思う。もう1公演くらい、チケットを取っておけば良かった。
2011/03/23
コメント(0)
-
震災の翌々日
宝生会は普通通り能の会を開いたのだろうか。もちろん行く気は起きない。 学長と相談して朝一番でソフトテニス部の謝恩会の中止を決める。飲食の手配をしていた業者にキャンセルの電話をかけたところ、どこもキャンセル料の請求などもなく、受けて下さった。お見えになるはずだった外部の方々にも連絡をし、寮のソフトテニス部学生に連絡を取る。 これまでここの日記で記しているように、勤務先はソフトテニス部の学生を積極的に受け入れている。例年、高校卒業式を終えるとただちにこちらに来てもらい、4月以降の大会に向けて練習を始めているのだが、今年の新入生のうちの2名の実家が、宮城と岩手、それもテレビで報道される町の出身だったのだ。2人とも親御さんと連絡が取れないまま今日まできていたが、今日になってようやく無事だったと確認が取れた。家の被害は大きかったようだが、ご家族の無事が確認できたことが幸いであった。
2011/03/13
コメント(0)
-
震災の翌日
東北から北関東のいたましい災害を気にしながらも、大切な学生を預かる教員としては出勤しなければならない。昨日から各担任がクラスの学生の安否を確認し、自分もソフトテニス部の学生を含めた寮と連絡を取っていた。クラス全員の連絡を確認するため、昨晩から一睡もしていない教員もいた。各担任の先生がさっさとこういう行動を取るというのは大きな大学ではないことかもしれないが、誇って良いことと思う。 研究室に入ってみたら、オレンジ色のミシマが数冊落下。よりによって、その下にあったノートPC(大学からの支給品)を直撃したせいか、スクリーンには、右端から左に向かって蜘蛛の巣のような亀裂が写っていた。こんな小さな部屋なのに、自宅よりも被害が大きい(涙)。 千葉県もあちこちで被害が出ていて、九十九里方面ばかりか、東京湾岸にも甚大な被害の出ていたことを知る。意外だったのは東京ディズニーランドの被害も報道された浦安市。東京の隣であるし、揺れ自体はそれほど大きくなかったはずだが、海岸線近くは道路がゆがみ、液状化現象も起こっていたという。断水も起こっているらしい。ほんのちょっとのところ、目と鼻の先でこういうことが起こっている。これが浦安ではなくて、東京の海岸沿いだったら、被害の規模も桁違いだろう。
2011/03/12
コメント(0)
-
祈り
悪夢の大地震から1週間が経過した。手をさしのべることもできず、ただただ無力であることを痛感し、安心できる生活が陸奥の地に1日でも早く訪れることを祈るばかりである。 11日当日、自分は幸いなことに出勤をしていなかった。3月に入って、研究日も関係なく毎日出勤している中で、たまたま自宅で持ち帰り仕事をすればよいという日だった。2時過ぎにちょっと人に会う約束があり、大井町にいた時に地震に遭った。ビルがゆらゆらと揺れたので尋常ではないと思いつつ、免震構造のためか、正直ここまですさまじいことになっていると、その時は思わなかった。だが、JRも私鉄もすぐにストップで人々がわらわらと駅前にあふれ、そうかと思っているうちに台場の方やら湾岸の方で煙が上がり始め、これは想像以上かもと思って急いで帰宅した。 自宅もおかげさまで被害は皆無であった。家にいた母は、巨大な揺れに肝をつぶしていたようだが、築65年のぼろ屋は何とか持ちこたえ、鍋が1つと、2列に重ねていた本のうちの数冊が落ちたのみ。ご先祖様(建てたのは祖父の弟)に感謝である。その一方、テレビの向こうに流れる東北の光景は、おもわず「逃げろっ」と声をかけてしまうほどの凄絶なものだった。 さて、我が家のチャオは佐藤のベッドの上で寝ていた。動物的本能はないのか?と疑問に思う。そう話していて、ふと気づいたのが、昨日10日のできごと。昨日、母がちょっと玄関の戸を開けた瞬間にダッシュで家を抜け出したのだ。だが、外での生活に慣れないチャオは裏庭から少し歩き回ってすぐに戻ってきた。通常、脱走はほとんどない猫なので、もしかしたら異変を察知していたのかもしれない。
2011/03/11
コメント(0)
-
あーあ
2012年年末に公開予定のスーパーマン映画(予定タイトルはSuperman: The Man of Steel)の主役はヘンリー・カヴィルに決定。なんとイギリス俳優からの起用で、ここのところ、バットマン(クリスチャン・ベール)、スパイダーマン(アンドリュー・ガーフィールド←2012年公開予定)と、アメコミの大御所がイギリス人に持っていかれている。もはや、アメコミ界は、愛国主義の塊キャプテン・アメリカ(クリス・エバンス)しか残されていない。いや、国籍はどっちだっていいのだが。今回のヘンリー・カヴィル、実は2004年の段階で、2006年公開のスーパーマン・リターンズの主役候補に名を連ね、かなり有力な俳優の一人だった。あのときは、ブランドン・ラウスに持っていかれたので、今回は名誉挽回といったところか。だがしかし、それにしても、いやはや……どうなの、あのルックス?昨日夜というか、今日の夜中から、メール経由で海の向こうからそういう情報がどんどんと舞い込んできて、まさにそれは2004年10月の出来事と同じではあったのだが、まさかという思いとウソであるようにという思いが相半ばして、悄然として一日を過ごした。そして、検索をかければかけるほど、ヘンリー・カヴィルの名が挙がり、最有力候補と目していた俳優のファンサイトでも「残念!」のお知らせが入ったので、もうこれは動かぬ事実なのだろう。あーあ。って、約1ヶ月ぶりの更新が、こんな記録っていう自分も一体???
2011/01/31
コメント(0)
-
非常勤終了
長いようで短かった狭山通いも本日で終了。タクシー(行きだけ)&特急(帰りだけ)となにやら見た目的にはリッチな非常勤生活であったなぁ。私の膨大な(自主課題という名の)宿題のサポートをしてくださった司書さん、どうもありがとう。どういう割り振りなのか、変体仮名の基礎の授業と、古典作品の読解の授業とが、クラス指定で同じ顔ぶれの学生30名を相手にするものだった。こちらは、言い忘れたことなどを連絡するのにちょうど良いのだが、学生さんには迷惑だったろう、ごめんよ。本務校では決してできない、日文の専門科目とあって、後期は特に楽しく授業ができた。あとはこの指定30名が、来年になって「出来が悪い」と言われないことを祈るのみ。授業が終わって……「こんなに図書館に通うとは思いませんでした」……はい、私の愛の形です「能のチケット、ありがとうございました」……楽しんでもらえれば幸いです「市ヶ谷で、先生の説話の授業が受けたいと思いました」……落としてやろうか「○○○先生に『うた恋い。』紹介したの、先生ですよね?」……あちらのブログの愛読者だそうでそれではみなさん、ごきげんよう♪
2011/01/18
コメント(0)
-
十二夜
今年の初鑑賞舞台は、渋谷コクーンでの「十二夜」。双子の男女を演じるのは松たか子。ノーブルな感じというか透明感があるので、こういう2役には合っているのかもしれないが、周りの顔ぶれからするとちょっと力不足の印象が拭えない。意外と言っては失礼だが、モデルのりょうのオリヴィアが面白かった。もっと気取った感じかと思っていたが、コミカルな部分もちゃんと丁寧に描いていて、予想以上の出来。ちょっと他の舞台も観たくなった。演出の串田和美が、執事マルヴォーリオも演じる。所々、原作にはない笑いが織り交ぜてあり、セット造りも凝っていた。オリヴィアに恋するオーシーノが石丸幹二。サックスでサビ部分を吹かせたり、ソロの歌を入れたりと、石丸幹二の見せ方を串田和美がよく心得ていると感じる。そして、道化フェステが笹野高史。道化の名の通り、笑いがあるのに必ず一抹の寂しさを漂わせるところが、舞台をぎゅっと引き締めていた。
2011/01/15
コメント(0)
-
神保町へ
最近すっかり足が遠のいている神保町。その先の宝生能楽堂やら、明治大学坂下のスポーツショップには行っているのに。非常勤先から勉誠出版へ。自分の教員生活とほぼ同時に始まったプロジェクト・ナガトもついに佳境で、本日はこの春刊行予定の本の打ち合わせだった。国会図書館所蔵の本を底本にした翻刻を中心とする本文篇、長門本を扱う論究篇、そして自立語索引と、これ以外に何があるのかと思うだろうが、まだまだプロジェクトは終わらなかった。編集担当者によれば、新年に広告も出たらしいので、ここに書いても差し支えないだろう。延慶本との本文対照表が分冊で刊行されるのである。なんだかよくわからない編集ソフトを使いながら悪戦苦闘した日々。あぁ、あんな日もあったねぇ……と遠い目をして語れる日は来るのだろうか。
2011/01/11
コメント(2)
-
表向きの仕事始め
本日は年初の教授会。といっても、既に勤務3日目。なんだかんだ、出ている。きっと仕事が好きなんだろう(注:もちろん「仕事」が文学研究を指すわけではない)。年度末に向けてのあれやこれやが議題に挙がり、粛々と方向が決まっていく。そして昼食を兼ねた教職員の懇親会。今年は幹事のチーフ(15年も勤めるとねぇ、サメザメ)なので、私の趣味を前面に押し出し、座席を決めるくじは紙縒、テーブルは青・朱・白・玄・黄の5色とそれに関わる聖獣を登場させた。ウケは今ひとつの感(涙)。こちらも予定通り、滞りなく進み、飲み直しもせずに一路帰宅。大急ぎで着替えて、ナイトテニスへ。軽く酒気帯びであった(良い子は真似をしてはいけません)が、寒さに負けず2時間乗り切り、今度は本当の飲み直しへ。3杯目までは麦酒であったが、さすがに身体の芯が冷えたせいであろうか、焼酎のお湯割りに変更。こういうところに老いを感じる今日この頃。
2011/01/08
コメント(0)
-
テニス漬け
親戚の出入り(といってもほとんどご近所さんだが)もようやく落ち着き、今日は昼と夕方とダブルヘッダーのテニス。でそのまま、新年会へGO!健康なのか不健康なのか、神のみぞ知る。
2011/01/05
コメント(0)
-
赤い指
昨春の連ドラ「新参者」が好評だったためか、あるいは、単に東野圭吾が“売れ筋”だからか、加賀恭一郎シリーズの『新参者』作中時間のちょっと前に該当する作品『赤い指』が単独ドラマとなって放映された。加賀恭一郎は前作同様、阿部ちゃん。いやぁ、加賀恭一郎が似合っている。前に書いた気もするが、自分はこのシリーズを映像化するなら阿部寛だろうとずっと(それこそ『雪月花』から)思い続けていたので、単独でも嬉しい。ところで、昨春の初回放送の記事で書いたように(4月18日の記事参照)、連ドラ「新参者」の時は、従兄弟の松宮君が加賀父子の関係を知らない設定(『赤い指』を経験していない設定)だったのに、今回の「赤い指」は人形町での活躍よりも前の時間を描いている。こういう雑な設定は何とかしてほしいものだ。それとも、松宮君が極端に物覚えが悪いという設定なのだろうか(苦笑)。3月には加賀シリーズの新刊も出るとのこと。待ち遠しい。
2011/01/03
コメント(0)
-
初打ち
新年早々今年もテニスの初打ち。天気も良く暖かい。だからって、半袖・短パンになっちゃうっていうのもどうだろう(自責) 3時間ほど汗を流して、昨日のアルコールもすっかり抜け、気分は爽快。あぁ、こんな日が続けばいいのに。 さて、今年の読了第1作は島田荘司『写楽 閉じた国の幻』(新潮社、2010年)。いわゆる写楽探しの1作であるが、現代と当時の2つの場面を描き、非常に緻密な構成になっていた。資料も実際のものを多用しているため、かなり説得力をもったものであった。ただ、現代の謎解きを進める主人公の設定や、折角出された写楽の正体が、結局その人の描いた他の作品がない、という点で、長らく支持されている説と変わりなくなってしまっているのが残念。それと先年報告された扇面の直筆画はどうなるのかという問題も関わってくる。今年は東博で写楽展も開催される。写楽熱は再びか?
2011/01/02
コメント(0)
全1010件 (1010件中 1-50件目)