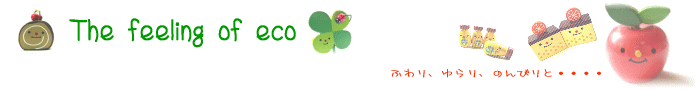テーマ: 障害児と生きる日常(4490)
カテゴリ: second sonーSoraー
Shungoの時から入れてもう7年目の小学校生活ですが
先日初めて定例研究会というものに参加してきました。
通ってる小学校で開催される講座が
「通常級における発達障がい児への支援」についてだったので
何かの参考になればという軽い気持ちで
講演をされたのは阿部利彦さん
埼玉県所沢市教育委員会学校教育課健やか輝き支援室支援委員
星槎大学非常勤講師
北海道&沖縄での話をおもしろおかしく話してくださいました。
講演を重ねていらっしゃる方らしく
つかみの話も上手でしたし、途中笑い話も混ぜながらぐいぐい引き込まれました。
定例研という事もあり、先生が多いのかと思っていたら
意外にも親の参加も多く先生も驚かれていました。
私も場違いだったらどうしようかと思っていたけど
同じクラスのママ達もいたし母親率高かったです。
お話が先生方向けを考えてこられていたので
家で何か・・・というような参考になる話はありませんでしたが
クラスでの授業の取り組みをどうするかのヒントや
普通の子と関わり中での問題への対処のヒントや
また親もそれによって子どもも問題を抱えていることが多いことなど
ストレス・疲れをうまく取り除くことが大事などの話も・・・
クラスの中でのいじめの構造
傍観者・実際にいじめる行動をする子・それを裏で操る子
そういう子達それぞれにどう対応していくかなど・・・
割合でいえば発達障がい児がクラス一人だとすると
落ち着かない子が7~8人、ネグレストや虐待にあってる子が二人等
クラス配置図で見せてもらうと驚きと衝撃でした。
それがそのままどの学級にも当てはまるって事はないと思うけど
Shungoの時を考えれば、あ~そうだったの・・・って思うこともあったり。
そんな中で一つ重要な話が・・・
いじめの問題等が発生した時に
障がいについてクラスに理解を求めようと思い、障がいについて説明したり
本人がカミングアウトしたりというようなことは
絶対にしないで下さいと話されました。
いじめの原因として、「障がいのある子が特別扱いされている」
という考えを多数の普通級の子が持っている
それなのに特別なんだと更に伝えれば反発しか芽生えず
表面上は理解を示しても心の中では理解していず
また違う事で排除する行為が行われると言われます。
そして、はっきりおっしゃいました。
「説明やカミングアウトをしているのをテレビで見かけて
やってみようと思う方が多いですが
あれにはずっと後々もフォローにすごい労力を注ぎやっているのです。
テレビでは簡単に理解を得られているように見えますが
そんな生半可なことではありませんから」と・・・。
そうだったんだ・・・・。
障がいをもっていることを理解してほしいという思いで考えてしまうけど
実はそれは無理を押し付けけてるだけだったりするのかと・・・とね
特別扱いじゃなく普通にいられたらって思うけど
出来ない事への手助けを「あの子だけ」ってとられてしまう
またお世話係みたいな子が出来てしまって、その子に負担がいったり・・・
当たり前であってほしいと願うことが難しいんだな・・と再確認した感じです
先日初めて定例研究会というものに参加してきました。
通ってる小学校で開催される講座が
「通常級における発達障がい児への支援」についてだったので
何かの参考になればという軽い気持ちで
講演をされたのは阿部利彦さん
埼玉県所沢市教育委員会学校教育課健やか輝き支援室支援委員
星槎大学非常勤講師
北海道&沖縄での話をおもしろおかしく話してくださいました。
講演を重ねていらっしゃる方らしく
つかみの話も上手でしたし、途中笑い話も混ぜながらぐいぐい引き込まれました。
定例研という事もあり、先生が多いのかと思っていたら
意外にも親の参加も多く先生も驚かれていました。
私も場違いだったらどうしようかと思っていたけど
同じクラスのママ達もいたし母親率高かったです。
お話が先生方向けを考えてこられていたので
家で何か・・・というような参考になる話はありませんでしたが
クラスでの授業の取り組みをどうするかのヒントや
普通の子と関わり中での問題への対処のヒントや
また親もそれによって子どもも問題を抱えていることが多いことなど
ストレス・疲れをうまく取り除くことが大事などの話も・・・
クラスの中でのいじめの構造
傍観者・実際にいじめる行動をする子・それを裏で操る子
そういう子達それぞれにどう対応していくかなど・・・
割合でいえば発達障がい児がクラス一人だとすると
落ち着かない子が7~8人、ネグレストや虐待にあってる子が二人等
クラス配置図で見せてもらうと驚きと衝撃でした。
それがそのままどの学級にも当てはまるって事はないと思うけど
Shungoの時を考えれば、あ~そうだったの・・・って思うこともあったり。
そんな中で一つ重要な話が・・・
いじめの問題等が発生した時に
障がいについてクラスに理解を求めようと思い、障がいについて説明したり
本人がカミングアウトしたりというようなことは
絶対にしないで下さいと話されました。
いじめの原因として、「障がいのある子が特別扱いされている」
という考えを多数の普通級の子が持っている
それなのに特別なんだと更に伝えれば反発しか芽生えず
表面上は理解を示しても心の中では理解していず
また違う事で排除する行為が行われると言われます。
そして、はっきりおっしゃいました。
「説明やカミングアウトをしているのをテレビで見かけて
やってみようと思う方が多いですが
あれにはずっと後々もフォローにすごい労力を注ぎやっているのです。
テレビでは簡単に理解を得られているように見えますが
そんな生半可なことではありませんから」と・・・。
そうだったんだ・・・・。
障がいをもっていることを理解してほしいという思いで考えてしまうけど
実はそれは無理を押し付けけてるだけだったりするのかと・・・とね
特別扱いじゃなく普通にいられたらって思うけど
出来ない事への手助けを「あの子だけ」ってとられてしまう
またお世話係みたいな子が出来てしまって、その子に負担がいったり・・・
当たり前であってほしいと願うことが難しいんだな・・と再確認した感じです
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[second sonーSoraー] カテゴリの最新記事
-
もう9月です・・・はやっ 2012/09/11 コメント(2)
-
続いてます 2012/04/25
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(88)myselfー ecoー
(64)husbandーDarlingー
(1)eldestーShungoー
(113)second sonーSoraー
(258)familyー家族ー
(25)introduce-紹介-
(2)Book-絵本ー
(3)Toys-おもちゃー
(3)Games-ゲームー
(1)other-その他-
(4)アフィリ&テンプレート
(4)© Rakuten Group, Inc.