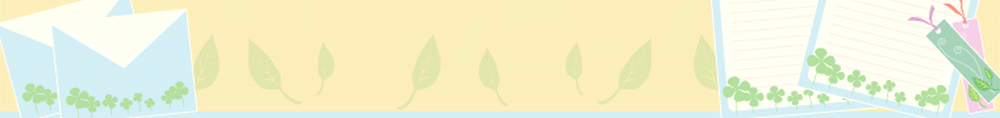全38件 (38件中 1-38件目)
1
-

可能性
保育をしていて、一人ひとりの子どもと深く向き合いたいって思う気持ちは強いけれど、子どもに手をかけすぎてそれが逆に成長を妨げているって思うことがあります。そして子どもの出来ることを育児書や思い込みから「ここまで!」と線を引いてしまっていることもあります。この写真はうちの保育園ではありませんが、九州にある保育園の3歳児の子供たちです。3歳児で連続前回りや後ろ回りが何度もできます。出来る子は一人ではありません。クラスのほとんどの子が出来るようです。年長ではもっとすごいです。よっぽど体育に力を入れている園かと思いましたが、話を聞くと、「教えていません!」ですって・・・。普段の遊びの中で身につけているとのこと。でも任せっきり保育ではありません。ちゃんと子供が伸びるわけがあります。保育者の声掛けや環境が関係してきます。そしてこれは雲梯で遊んでいる写真です。雲梯の上も歩いたり走ったり普通にしています雲梯の上って結構怖いです(個人的に)初めての体験の時はもちろん子供は怖がります。でも子どもが怖くなって保育者に抱っこを求めてきても手をかしません。わたり方を伝えても決して手は出していません。これは意地悪ではありません。抱っこをすることは簡単です。でもそれでは自分でできたという満足感を子供は味わえません。そしてやる気も育ちません。そこで手を出してしまうと子供の可能性をつぶしてしまうのです。これは私も保育経験から感じています。自分で渡りきった時、できた時もう一度やってみよう!!「先生見ていて!!」っとキラキラした目をして再びチャレンジしています。子どもの可能性って私たちの思っている以上です。
2008年07月27日
コメント(4)
-
夢
昨日は七夕でしたね。織姫と彦星は会えたでしょうね。七夕といえば短冊です。うちのクラスの子ども達にも願い事を言ってもらいそれを私が書き、短冊にし笹に飾りました。まだ3歳の子供なので、分かるか不安もありましたが、みんなそれぞれ願い事がありました。その中の一部を紹介したいと思います。「ショベルカーのおじさんになりたい」「きものが欲しい」「かわいいはっぱになりたい」「プリキュアになりたい」「あんぱんまんになりたい」などなど。子どもの夢って素敵です。私も、どんなことでも何歳になっても夢を持って生きていきたい。そう感じた七夕でした。
2008年07月08日
コメント(0)
-
愛着関係
0・1歳の頃の親との愛着がその子どもの人生を決めるといっても言いすぎではない。愛着関係は親、いない場合は育ててくれる大人でも成り立つ。この時期の経験がとっても大切。この時期に安心感が育たないと他の部分も限られた成長しかできないと言われている。また、愛着関係があった子はこれから先の人生のつまずきに耐えられる力が大きいと言われている。我慢して育った子も安心感が持てなかった子も、思春期になると曲った方向に行ってしまうことが多いといわれている。今は3才児の担任であるが、0・1歳で愛着関係のなかった子の時間を取り戻すことは難しい・・・。現在もそういう状態であるから余計に・・・。保育の難しさを感じる今日この頃・・・。
2008年05月31日
コメント(1)
-

ベビーアクアティクス
子どもの眠りを誘うには、心地よい疲れと安定した心が必要です。保育園でも日中散歩に行ったり沢山身体を動かした後の睡眠は子どもたちにとってと~っても気持ち良さそうです。ついつい私も同じ布団の中で一緒に眠ってしまうことも・・・。この前ある雑誌の中にベビーアクアティクスについて書いてありました。(親子で(赤ちゃんと)一緒にプールに入って遊んだりするそうです。)そして、そのベビーアクアティクスの中で、プールで眠ってしまう赤ちゃんがいるそうです。親はせっかく来たのだから!!といって起こしてしまう人もいるそうですが・・・。でも眠ってしまう赤ちゃんは、前にある、心地よい疲れと安定した心のこの二つが完璧な状態です。そしてプールで気持ちよく眠れる赤ちゃんはママのおなかの中で快適な時を過ごしたことを証明しているのだそうです。また、閉じた瞼の奥で眼球がよく動いてる状態のときには、皮膚が「水」を学び、水の音やママの声が耳の奥に穏やかに響いているといわれてるそです。試しに眠った子を水面でゆりかごのように動かしてみると、足を伸縮させ、まるで泳ぐようなしぐさを見せるそうです。ママの声と水の流れのハーモニーを聴きながら表情も変化させているのでしょうね~。きっと水の楽しさが眠りの心地よさに勝ったときにプールで眠ることはなくなるのはないでしょうか。子どもの眠っている姿を見ると心がとっても優しくなれます。不思議な力をもってます。自然と笑みが出てきます。
2008年03月25日
コメント(1)
-
心のゆとり
子どもの数は減っているのに、子どもの虐待件数は増える一方です。そして子育てをしながら悩み、時には思うようにいかない子どもに苛立ってしまう。こういう経験は殆どの方があるのではないでしょうか。育児ノイローゼになるのが分かるという人も私の周りにもいました。でも子育てが楽しいといえる人はそのような気持ちも感じながらも子どもを型にはめないで成長を素直に喜べたり、子どものつぶやきに耳を傾け、それを楽しいと感じることができるのでしょう。話は変わりますが、先日、阪神淡路大震災に実際にあわれた方の話を聴く事ができました。その人は当時高校生。まだ小さい妹がいました。地震により、家から避難しなくてはいけなくなり体育館で避難をすることに・・・。初日は「小さいのに大変ね。」と周りの方も優しい声をかけてくれたようです。けれど、日にちがたつうちに、「子どもうるさいんだよ」などという声が聴かれたり、配給のおにぎりも子どもなんだからといって、半分に減らされるなどという悔しい経験をしたと涙ながらに話してくれました。でもその人は震災のときに体育館で妹や他の子どもを見ていてエネルギーを感じて辛い中にも元気を貰ったと話してました。私は震災にあったことはないのでどんな精神状態になるのかははかり知れません。人間って自分に心のゆとりがないと、人には優しくなれないのでしょうか。きっと人にゆとりがある時とない時の気持ちは違うでしょう。でも辛い時こそ支えあえる人でありたい。
2008年02月16日
コメント(5)
-
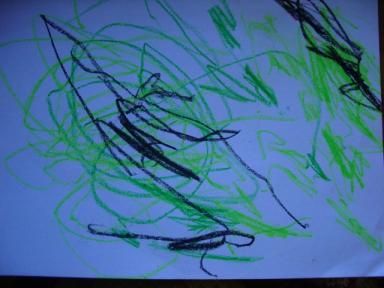
表現力!
1ヶ月位前のことですが、子どもたちが思い切りなぐり描きが楽しめるようにダンボールを切り、いくつかつなげ4畳ほどの大きさにしてその上に乗りながら描けるようにしました。みんな思うままに細い線や力強くて太い線、○やナミナミなど描いています。思いっきり描くという経験が大切です!大人が共感していくことで子どもの自信や色々な事をやってみようという気持ちにまでもつながってきます。残念ながらダンボールの写真は撮れなかったです・・・。今日は画用紙にですがしっかり撮ってきました。1歳9ヶ月の子の作品です!力強いです!手にまでクレヨンがしっかりとついてました。そしてこの子はもうすぐ2歳です。描きながら「みて!」「すべり台だよ」っと見せてくれました。何気ないこの言葉!見逃しません!すごい!!見立てて描く!という事はスゴイ事なのです!この子は初めて見立てて描きました!私もビックリして「すごい!」と感動するととっても嬉しそう!真剣な顔つきから笑みに変わりました!さらに描き加えて何度も「みてみて!」と声かけしてきます。こういう子供の成長を見れるときってホント保育士やっていてよかったなっと感じます。涙が出そうです。そしてこの子は2歳9ヶ月の子の作品です!「ママ」「○○クン!」など自分の家族の名前をいって説明しながら描いています。車の絵も描いたようなので、きっと車でみんなでお出かけしたときの事を描いてるのでしょう。この年齢でここまで描けるのも珍しいですが、スゴイ!!!この絵について質問していくとさらに想像力が膨らみ色々とお話してくれます。子どもの絵って楽しいです!こういう経験していく事が大切です!想像力、表現力伸ばしていきたいですね。
2008年01月18日
コメント(0)
-
障害って?
障害児、障害者っていうけど、そもそも障害ってなんなのでしょう。昔教わった先生の言葉を思い出しました。その先生は「障害は誰でも持っている」「みんなの障害はなんですか?」と問いかけてきた。「目が悪い」「○○が苦手」などなど・・・。「その障害とどう違いますか?」と再度問いかける。きっと誰もが障害を持っているのに特別な人と分けて考えてしまっている私たちの考え方について言いたかったのであろう。その先生はこうも問いかけてきた。「もしお腹の中に赤ちゃんがいるといして、その子がダウン症だと分かったらあなたならどうしますか?」と・・・・。
2008年01月13日
コメント(0)
-
子どもの行動の原因を知る
2歳になると(個人差はありますが)自己主張もますます強くなり、なんでも「自分で!!」とやりたくなってきます。このことは何回かこのブログにも書いてあるので程々に・・・。でも「自分で!」という思いはあるのにまだこの時期はそれに伴った手指の発達は十分ではありません。当然、気持ちはやりたいのに「できない!」できないから苛立ち泣いたり保育者に八つ当たりしたりします。そしてそのままにしておくと、段々と自分でやるという意欲がなくなってしまいます。そうなると自分でやろうとする気持ちにさせるのには簡単にはいきません。でもこういう気持ちが続いている子がクラスにいます。(自分で!という時期にもっとよい介助方法はなかったのか反省・・・)以前は「自分で!!」っとあんなに張り切っていたのに、できないからパンツはくのにも靴を履くのにも保育者がやってくれるのを待っています。その物に見向きもしません。そんな時どうしたらよいと思います?その子は遊びでも、できないのであえてパズルやひも通しといった手指を使う遊びをしようとはしません。(手先が発達していないから当然オムツやズボンも一人では履けません。)そこで、手指の発達を促すような遊びを(その子が興味を示すような簡単なそして楽しそうな)促していこうとクラスで話あいました。そしてもう一つ。自分で!という気持ちになるように=○○したい!と思えるようにする。「自分で!」という思いの始まりは私は、興味のあるものがあり、それに向かってこうしたいああしたい!という子どもの思いから来るものではないかと思います。戸外に出かけるときにも子どもが「外にいきたい!」だから早く靴をはきたい!というように・・・。保育者の声かけも大切ですし、子どもの動きや気持ちを少し待ってあげるということも大切だと思います。集団の中でいるとなかなか一人を待つってことが難しいですが、子どもを見守ったり待つということ大切にしたいと思った一日でした。
2007年12月17日
コメント(0)
-

声かけ
落ち込んだ時、悩んでいる時、これから何かをはじめようとしている時、どうしようもない時に救われる言葉がある。言葉って人に気持ちをプラスにさせることができる。逆にマイナスにさせてしまうこともある。子どもにも同じことが言える。いや大人以上に影響力は強い。純粋な子どもへの声かけは特に大切。言葉がまだ理解できない赤ちゃんでも私たちが赤ちゃんに対して話す言葉、声かけ、表情によって心地よいものとそうでないものと明らかに区別することができる。赤ちゃんって私達ができないようなことも敏感にわかったりもする。不思議な力を持っている。(余談ですが、赤ちゃんに自分のママの母乳を含ませたガーゼと違う人の母乳を含ませたガーゼを左右に置いておくと、間違いなく自分のママの母乳のほうに振り向いたりもする。)今のクラスの子どもたちもとっても敏感で大人の気持ちが実は分るのでは?という感覚にもなることがある。気持ちだけでは足りないこともあるし、子どもを褒める時などに、(「スゴイ」など)思ってもいないことを言っても伝わらない。言葉と気持ちがつながってこそ響く。本当にスゴイ!と感じて伝えたときの子どもの反応は明らかに目が輝いている!!大人が発する言葉によって自分でやろうとする気持ちがでてきたり、褒められることによって、自信がつき、みるみるうちにその部分が伸びていく。言葉(声かけ)が子どもに対してどんなに大切か身にしみて感じているので、仕事が終わって「なんであんな言葉を言ってしまったんだろう」と後悔することも・・・。
2007年11月23日
コメント(7)
-

実体験
上の写真はうちの保育園で作っている作物です。実際は畑もあり、幼児クラスは実際畑に行って育てています。今は実体験できる経験が少なくなってきましたね。だから想像力が育たなくなったのでしょうか・・・。公園での遊びも今と昔とでは変わり、自由に遊びに行けなかったり、遊び方もかわってきました。箱型ブランコやジャングルジムは無くなり、シーソーも昔とは変わってきてます。(下にタイヤをつけたり・・・)危険なものはすべて取り除け!という時代になってきました。はたしてそれで今の子供たちは公園で何を学んでいくのでしょう。遊びの中から自然に身につけていくことが大切です。箱型ブランコは乳児にとっては大切な経験です。まだ、握るという運動機能が発達していない乳児は普通のブランコは危険です。あのバランス感覚を経験させるということはこの時期貴重な体験です。それなのにそういう経験ができない。アスレチック一つとっても落ちないように今は作られています。これでは落ちないようにどうしたらよいのか?と考える経験もできなく、ただただ登っては降りての繰り返し。危険なことは大人にとってもはらはらしますが、使い方を教えることも大切ですし、なにより、危ないからどうしよう?考えて行動するという経験が少なくなってしまいます。遊びの中から考えるという経験が乏しくなってきてます。今、家の近くの公園は工事中です。どんな公園になるのかな??と期待と不安と感じながら完成を待っています。
2007年09月16日
コメント(2)
-
おまじない
子供たちは色々な理由で泣いて懸命に大人に自分の気持ちを伝えてきます。今日も色々な涙を見ました。そして私のところにきて、伝えたい思いを動作やしぐさ、片言の言葉で伝えようとします。そんな時、私たちは、子供の気持ちを代弁して気持ちをわかってあげることが大切だと思います。他児とのおもちゃの取り合いで取られた子パズルで遊んでいてうまく出来なくて泣いた子などなど様々な理由で泣きます。それぞれ成長段階でこういう経験はとても大切だと思います。その中の泣く理由の一つで、痛い思いをして私たち大人のところに来る子がいます。その子供に「痛い痛い飛んでけ~!」「痛い痛い○○に飛んでいけ~」などと痛がってるところをさすりながらおまじないをすると、不思議とすぐにケロっとしてどこかに行きます。だれもが知っているこのおまじないすごいものを持っていると思いません?本当に痛い思いが飛んでいくような、いや本当に飛んでいってるようです。改めて凄いな~と感じました。言葉のパワー、おまじないパワー、共感することのパワー、スゴイな!!
2007年09月06日
コメント(0)
-

散歩~2
散歩していて気づいたことなのですが、子供たちと散歩に行く時って行く場所は大人が決めるということ、そして安全面から考えて、大人が先に前を歩いたり、一緒に手をつないで大人の行こうとしている方へ導いてしまうことが多いです。とくに集団の中では安全面に考慮して子供の前と後ろにつきます。でもそれでは子供の行きたいところには行けない。安全な場所ではなるべく子供の行きたいところに行けるようにしたいなっと感じました。散歩も大人の見方ひとつでも変わってくるもので、子供を先頭にすると、子供の歩き方や笑顔などホント違っていました。飛び跳ねるように先頭を歩き、うれしそう。(もちろん安全なところでね)よくハイハイから歩けるようになる頃には自分の所にきて欲しいため子供が一人立ちをし、歩き始めると「おいで○○ちゃん。」とつい自分のほうに呼んでしまいます。大げさかもしれませんが、せっかく子供が行こうとしている方をさえぎってしまっては自主性が育たないのでは無いかと思います。(もちろん呼ばないでという事ではないです)子供の自主性をもう少し大切に見守ることも時には大切なのかな・・・。
2007年08月10日
コメント(0)
-

散歩にいきました!
ここ最近梅雨らしい天気が続き外に出れずにいました。今日もジメジメした天気が続いてますが、思い切って散歩にいきました。うちのクラスの子どもの年齢は月齢によって成長が大きく違います。「散歩にいきたい」と話せる子もいますが、「あー」とナンゴを話すだけの子供もいます。話すよりも言葉の理解のほうが大切だと思いますが、うちのクラスの子供たちは殆どの子供は簡単な言葉は理解できるようになってます。私が「さんぽに行こうか!」と声を掛けると、みんな大喜びで外の方へ向かいます。話せない子供も「ん~ん」と外の方を指差しし早く行きたいようです。今日行った所は保育園から200mくらいの距離ですが、200mの中に色々な発見をする子供たち。以前も散歩のことを書きましたが、今日も花をみたり、葉っぱを触ったり・・・。色々な発見をしてます!(発見に共感することで、(当たり前にしている事だと思いますが)その事が子供にとって大きな自信につながります)ある子は、てんとう虫を手にとり、じーっと見つめた後、「パンダ!!!!」と私に伝えています。「ぱんだ!????」と??思い一緒にじっと見てみると、頭の部分が白黒(パンダみたい!)になってるではないですか!!スゴイ発見!!!観察力と表現力に驚きました。てんとう虫を見ている時の子供の顔、今でも目に焼きついています。漫画ではないですけど、目がキラキラ☆してました。後になって今日の出来事を振り返り、子供の頃って色々な物に興味を示し、色々な感動や気付きがあるのにだんだんと物事が当たり前の事としてしか見れなくなり感動が薄くなっていっているなーと考えさせられました。毎日子供と関わっていると子供から学ぶことってホント沢山あります。子供のように新鮮な気持ちで物事を見れたらよいな。
2007年07月23日
コメント(1)
-
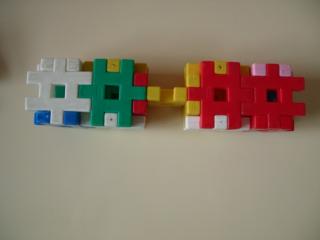
創造力ってスゴイ!
ブロックの話が遅くなってしまいました。去年受け持った1歳児クラスの子供達は2歳児クラスへ進級しました。今年も担任は1歳児クラスとなりました。4月(今年のクラスのはじまり)はこんなに小さかったのかと思い、改めて子供の一年の成長の凄さに驚いてしまいます。このBブロック一つとっても遊び方は成長段階で代わりますね。去年受け持ったクラスを例にとると、まず、上のブロックの型同士をはめて遊ぶところから始まり、そして写真のように四角い立体をつくれるようになります。(ちゃんと形を選んで組み合わせないとこの形にはなりません)始めは何度も私たちが教えますが、これは子供一人で作ってます。そして、この写真を作った子供は「電車」に見立てて、床に寝転び、滑らせて遊んでいます。最後にこの写真は「パオー!!!!」と言いながら作り上げています。きっと「ぞうだな」っと思い「すごいね。ゾウさん??」と聞くと「うん!」と一言。曲がっているところはゾウの鼻なのでしょうね。でもそれにしてもこのクラスの子供は創造力が豊かだなーっと関心した一年でした。こういう創造力は勝手に育つ部分もあるかと思いますが、私は、大人がしっかり配慮していく事が大切なのだと思います。今は戸外は危険な物や人が多く、出かけるのをためらう人が多いですが、やはり、自然との触れ合いが一番大切なのだと確信しています。幸いうちの保育園の周りには団地の中にどんぐりの木や桜、みかんの木やすずらん、芝生、色々な自然があります。今年のクラスもたーーくさん外に出かけるぞ!
2007年04月16日
コメント(2)
-
15日の日記
はじめて携帯から日記かきます! こんなこともできるんですね。 前回の話の続きですが、一歳にとっての考える力とは?? 自分で食べたい!自分で履きたい!まだ一人では出来ないけど、自分で!!という事が増えます。 こういう意欲は大切にしたいですね! 時間がなくて付き合っていられない時もあるかと思います。 特に保育園のように集団の中では一人ひとりの対応は難しいことがあります。 でもこの意欲を潰してしまうと、何に対しても意欲がなくなってしまう、そして、大人のやることを待ってしまうのではないかと思います。 自分でやろうとする意欲を大切に。ずっと見守っていくと、出来ない時はぐずる事もありますが、素直にできないと伝えてきたりもします。そんなとき『一緒にやろうね』など気持ちを共感していく事が大切かと思います。 また、自己主張がでてくる時期も大切にしたいですね。 次回は考える力を大切にした遊び。私の保育園の子供の実際に作ったブロックを紹介したいと思います。 スゴイ!です!
2007年02月15日
コメント(0)
-
考える力
最近忙しくブログを怠けてしまった。最近は子供も大人も考える力や想像する力が欠けているから、その場の感情で行動してしまい、こうしたらこうなるという想像がつかずに、犯罪がふえているようです。そもそも考える力をつけさせるには私たちは子供にどのような声かけや、対応をしたらよいのか。生まれた時からそれは始まっていて、0歳児の子に、ミルクを決まった時間になったら与える。という対応をしていたらどうなるでしょう。子供は泣かなくてもミルクが飲めるので、泣きませんが、それでは、要求の出し方も分からなくなります。大切なのは、赤ちゃんが出す要求に優しく語りかけ、要求を満たしてあげることなのです。(この頃の子供の要求は全て満たしてあげることが大切です。)なんでも大人が先取りしてしまっては子供は考える力が育たないと思います。泣くという行動はとても大切です。泣く事が赤ちゃんの仕事っていうのには訳がありますね。こちらも大げさかもしれないが、「よく泣いてくれた!」くらいの気持ちでいたいですね。次回は1歳児の考える力についてブログにのせたいと思います。最近は寝不足で、今目が半開きなので…。このへんで。
2007年02月13日
コメント(0)
-
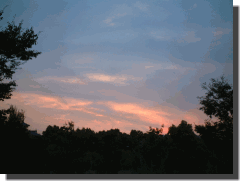
あっという間!
月日って過ぎるの早過ぎますよね。クリスマス、年末、お正月…。普段は有休など取れない職場ですが、冬休み7日もらいました。(土日入れてですが)本当あっという間で、これといって何をしたわけではありません。なんだかあっという間にすぎてしまい何をしていたんだろうともったいない気持ちになります。一日いちにちはあっという間に過ぎてしまっても一日ずつ過ぎれば季節はかわり、木も衣がえ。日も少しずつ長くなってきています…。ぐーたらな休みが終わり5日の休み明け、子ども達に会いました。(一歳クラスですが、もう2歳過ぎの子が殆ど)「明けましておめでとうございます」と子どもに挨拶すると、なんだか照れくさそうにして、おじぎをする子や、お家で;あけましておめでとう:をした事を「ばーばーとこでやった」とか話たり…。まだ分かっていないだろうけど、いつもと違う挨拶だな。って子どもながらに感じたんだろうな。久しぶりの再会で私もですけど、子ども達もとっても嬉しそう♪みんな抱きついてきて可愛かった~♪久しぶりといっても約1週間。私は何も変わらず(唯一生活リズムが変わったかなー)でも子ども達の1週間ってすごい成長があるんです。言葉が上達している子や今までやろうとしなかったことをやろうとしたり、(やらなくなる事もありますがそれも成長の一つです)改めて子どもの一日って大切で重い物なんだなと感じました。大人になると日々の中で様々なことを吸収することが少なくなっているように感じます。色々なことまだまだ学ばなくちゃな。なんて思いました。具体的にしないと動けないから目につくことからやっていこう!今年も宜しくお願いします!
2007年01月11日
コメント(1)
-
PART~3
脳の話が続きますが…。人間の脳は「前頭葉」「側頭葉」「後頭葉」「頭頂葉」に分かれますが、人間が他の動物と比べて最も発達しているのが「前頭葉」にある「前頭連合野」です。ここは人間らしさや理性判断、創造などと関係しています。私たちの喜怒哀楽はここでコントロールされています。私たちは、何気なくおしゃべりをしていますが、言葉は自分の考えを相手に伝える手段として大きな役割をしています。話すときには感情や思いを選択し、時には心を込めて話し、自分の言葉が相手に伝わるように話そうとしています。言葉の出始めは子どもによって様々ですが、話すようになってから子どもは意思を懸命に伝えようとしてきます。意思の疎通は発達するによって上手になります。これは大脳の左側の言葉中枢が発達するからです。赤ちゃんの脳の左右のうち左が優位で、身のこなしや言葉の発達とも連携しています。感情を司る前頭連合野も発達し、左の前頭連合野で楽しいことを、右では悲しいことを感じ、思春期までつづくそうです。2~3才を過ぎると左右の脳の真ん中の脳りょうが発達し、左右の脳球は互いに連携を保ちながら発達していきます。つまり、2~3才には脳神経細胞の調整によって感情を抑制できるようになっていきます。そして成長につれ、わがままや自我を抑えられるようになるのだそうです。脳がまだ未熟な時期にわがままがでるのも当たり前ですよね。自分をだせ、わがままがいえる大人がいるということはとても大切ですね。わがままで正直「もーー!!」と思ってしまっても「成長の過程で当たり前!」「ちゃんと成長しているんだな。」と思えたらよいですね~。人間にとって「人間らしさ」の根本といってもよい「前頭連合野」を刺激し、発達させるためには人との関わりがとても大切なことが分かってきたそうです。人間交流が希薄な時代となってしまいましたが、子供も大人も人との関わりや、ふれあいをもっと大切にしていきたいですね。
2006年12月29日
コメント(0)
-

PART~2
今、大人もはまっている人が多いと多いますが、DS(ゲーム)が手に入りにくくなるほどの大人気!その中で、脳トレーニングは特に人気です。脳を鍛えるといった表題のものが沢山でていますね。雑誌などでも子どもの教育分野に精力的に取り組んでいて習い事一つとっても、「習い事に向いているタイプの子どもはどんな子どもか?」など具体的に書いてあります。こういう記事を鵜呑みにしてしまいがちですね。そして、どれが正しいのか分からず、ただでさえ育児に不安を抱えている人が多いのに、ますます混乱してしまう人が多いようです。色々な情報によってますます混乱してしまう。これが今の現状なのです。「人よりも早く」といわれたり、「せめて人並みに」といわれたり、「放っておくと置いてかれる」と何かやらないと子どもは育たないという恐怖感にあおられている。こんなあおられて子育てって楽しいのだろうかと考えてしまいます。また、ある種の刺激の入力を一定期間遮断するとその刺激に反応する脳の特定部位が能力をなくすことが知られており、その瞬間を臨界期といいますが、視覚や聴覚については明らかですが、言語習得や音楽などの早期教育とそれを結びつける傾向があります。でも、視覚・聴覚を例にとると、目の不自由な人は視覚系のかわりに、触覚機能の発達へ。聴覚系は、視覚情報の発達へ。つまり何かを失うと別の能力をもっていきます。それなのに、これがダメなら全部ダメということを臨界期はあおりすぎているように感じます。早期教育よりも、もっと今ここにいる子どもをみて欲しいと思います。生活の中には生きる力を育てることが沢山あるように思います。大人がそれに気がつき、子どもと向き合っていけば、自然と子どもにとって何をしたらよいのか分かってくるのではないかな?と考える今日この頃です。子育てが大変だという思いばかり先行してしまう世の中になってしまっており、政府は少子化対策を色々考えているようだけれど、私はそれより、子育てというものが「楽しい♪」と思える世の中になれば一番だと思います。そう思えるような対策をとって欲しいな。
2006年12月12日
コメント(1)
-
脳科学と保育part1
現在、情報化していく社会の中で(子育て情報)テレビをみては良くないとかゲームをやってはいけないとか色々な情報が飛び交っています。でもこれって、科学的証拠は無いのです。情報の統計はあっても…。これって保育者として親にいけないという科学的な根拠がなくて戸惑う事があります。でも科学的のものより現場の(実際の保育で子供と関わって感じること)のほうが大事だなと思うことも沢山あります。が、今回は科学的な目線と現場の目線から脳の機能と保育の関係について触れてみたいと思います!一歳までの言葉の発達は、周りの大人の態度は関係ありません。沢山語りかけると赤ちゃんは言葉が出るのが早いというのはウソです。言語能力はある程度生まれつきのものです。言語の発達が大人に関係するのは、一歳半くらいの単語が爆発的に増えていく、とても短い時期です。昔おばあちゃん子は言葉が遅いと言われていましたが、あれはどうしてか?赤ちゃんの要求を先取りして、やってやるので、言葉を出す必要がないから遅れます。 これは良い事?悪い事?私は悪いこととは思いません。言わなくても思いが通じるって素敵♪恋人のよう!笑以心伝心♪そして最近私は知ったのですが、脳って削りながら成長するようです。1980年代に神経細胞(ニューロン)やシナプスが一時期急激にふえ、そのあとまた減少するという過程が明らかになり、脳の発達は先天性遺伝子によってつくられた組織が環境とのやり取りで無駄を削って成長することが分かりました。シナプスは刺激によって大きく広がると考えられていますが、実は無駄を削りつつ新しい回路をつくっていくのです。例えば日本の赤ちゃんでも生まれつきRとLの区別ができるのですが、成長と共にその能力は失われていきます。それは日本の生活には邪魔なことだからです。早期教育論者は増える過程を重視していますが、実は無駄を削ることによってより高度な能力を獲得するようです。なんでもやればできるという事ではなくて、何を得ようとするかきちんと考えていかなくては…。お稽古事をなんでもかんでもやればよいというわけではないようですね。「やれば伸びる」というわけではないようです。次回のブログに続く…。
2006年11月20日
コメント(0)
-
ケガ
最近の子供はけがをしやすいと思います。そして、けがをしないように!と大人は考えてしまいます。でもけがという経験で学ぶことは沢山あるのだと思います。0歳児を例にあげると、子供は狭いところが大好きです。押入れなんかは楽しくて仕方がない。始めは必ずやってしまうことが、頭をうってしまう…。でもそんな経験をして、だんだんと自分で「ここは頭を下げないとまた痛い思いをするな」と考えてしゃがんで入るのでしょうね。他にも転んで経験する事など…。色々です。もちろん大きな怪我は大人の責任でしょうが、ケガを恐れてばかりでは経験が乏しくなってしまい逆に大きな怪我につながってしまうのではないでしょうか。子供のころに十分身体を動かしていないと柔軟性もなくなってしまいます。最近は身体が硬い子供が多いです。赤ちゃんのころから硬い子もいますが。(ホント!)柔軟性と怪我とはとても関連していて、柔軟性が無いと自分の動かせる運動の幅も狭まってしまい思うように身体が動きませんね。あっ、私も今とっても身体硬いです。最近ストレッチやヨガで身体を少しでもやわらかくしようと懸命です。皆さんも柔軟性あります??頑張ってやわらかくしましょう。
2006年11月16日
コメント(0)
-

見通し
明日は11月1日。11月になるのに私の今日の保育の格好は、半そで長ズボン 裸足である。本当に温暖化を身にしみて感じるこの頃である。蚊もまだ飛んでいて子供たちの体には蚊に刺されのあとが毎日見られる。このままだと日本の四季はどうなってしまうのでしょう?いつからが春?夏?秋?冬?…。環境汚染今は目に見えない…。実感がない…。などと言っていられなくなっている。ここ何年かで随分変わってきているように感じる。そう感じるのは私だけでしょうか?石油も世界で使いすぎて底が見えてきている。今ある事だけに目がいってしまうのはどうしてなんでしょうね。ちゃんと環境などを考えて行動している人も多いですが…。保育も、今いる子どもを受け止めながらも何年か後の姿を見通して保育することが大切なんだろうな。
2006年10月31日
コメント(1)
-

すっぱい葡萄
家の近くで(車で30分くらいですが)葡萄やなしを販売している農家を今年初めて見つけて、そのおかげもありマスカット、や巨峰、種無しの物など沢山たべる事ができました。うん。どれも甘くてとっても美味しかったです。最近の葡萄はどれも甘くて美味しい!!でもイソップの寓話には「すっぱい葡萄」がでてくる。そのストーリーは…。「ある日キツネが野山を散歩していると熟した山葡萄を見つけた。とても美味しそうなのでキツネは何とかして捕ってやろうとあれこれトライするが高い所にある葡萄がどうしても捕れない。そしてとうとう無理だと思うとキツネは「どうせこの葡萄はすっぱくてまずいにきまっている。」と言ってその場を去っていく。自分でも美味しそうだと思い食べようとしたのにも関わらずどうやっても手に入らないと分かると「すっぱくて、まずい」と決め付けて、無理やりにでも納得させる。自分の思いや欲求や願いが叶わなかった時生じたストレスを最小限に抑えるため、自分に良い言い訳をして自己防衛をする。こうした行動は誰にでも大なり小なりあるのだと思う。子どもは比較的正直に「すっぱい葡萄」を表現する。ところが、大人になると様々な理屈をつけて自己防衛というよりも自己正当化を図ろうとする。ある程度の自己防衛は必要かもしれないしかし、それが行き過ぎて自分の都合のよいように理屈をこねて無理にこぎつけると単に見苦しいだけでなく自分の為にもならない。時には事実をスナオし認めた上で、気持ちを切り替えたり上手くいかなかった理由を考え新しくチャレンジすることも大事。「すっぱい葡萄」でたとえるなら、届きそうな葡萄を他に探すか熟して落ちる時期を待ってみるか「すっぱい」と言い訳して済ませずに次のステップを試みるのも手で、「すっぱい」や「失敗」は成功のもとなのだから。
2006年10月05日
コメント(9)
-

友だち
今日は秋晴れでとっても気持ちが良い天気でした。もちろんお散歩へ!GO!!!今日いった公園は芝生が一面に敷かれています。思わずゴローンとねっころがりました。青空で気持ち良い~青空って好きです!散歩道では安全面に気をつけながら子どもたちのペースで自由に歩けるようにしたいです。保育者が何も言わないでもなんと写真のように子どもたちから手をつなぎ始めました。初めは2人がつなぎ、それを見て「ぼくもわたしも」といつの間にか長く…。つなぎ方も上手で長い間つないでいます。(しばらくすると自分のペースになりますがね)保育者がトトロの「さんぽ」を歌うと子どもたちも口ずさみとっても楽しそう♪今まで一人遊びや保育者との関わりが多かった子ども達も最近は友だちとの関わりも多くなってきました。自分の気持ちを十分満たしてくれる大人がいる事で、子ども達は色々なものや事に積極的に関わろうと出来ます。友だちへの関心もその一つですね。まだまだ自分中心の世界ですが、このような成長を大切に、大いに喜んできたいです!見ていて幸せな気持ちになりました。
2006年09月28日
コメント(0)
-

子育て下手と自然
2005年の統計によると、児童虐待件数は3万4451人。統計をはじめた1990年と比べると30倍以上にも増えている。子どもの出生率も下がる一方…。将来日本はどんな国になってしまうのだろう?そもそも子育てと言うものに対して最近は「大変」「どうやって育てたらいいのか分からない」というマイナスの思いを抱いている人が多いのではないか?今は理解できない事件を起こす若者も増えている。育児が下手になっているのではないだろうか?その原因はいろいろあると思うけれど、私は自然から離れたことが原因の一つだろうと思う。最近のお母さんが、自分の子どもに話しかける言葉で一番多いのが「早くしなさい!!」だそうです。「早く支度しなさい!」「早く早く早く!!」農業社会や自然社会では、時間は自然に従っている。農業は早く育て!と思っても早く育つわけではない。今は自由に外で遊べないが、昔は外で遊んでいても、陽が沈めば家に帰ったり…時間の感覚も自然に従っている事が多かったのではないか。農業では早くできるものもあるが、じっくり育つものもある。こじつけではないが、人間もじっくりやる人もいれば、テキパキする人もいることが当然と考えやすかったのではないか。自然の流れに身を任せるしかないという感覚が身につきやすかった。現代は、山が自然から離れていき、保水力や川の栄養源となる力をなくしている。自然も自然離れさせられている。だからわたし達に分かりにくくなっていく一方。自然には競争はないけど、お互いが支えあって共有する力がある。それが人間にも必要なのに、分かりにくくなっている。自然による災害をみても人間が自然を支配する事なんてできない。もっと自然と対話し、自然と仲良くしないと(自然に近い生き方をしないと)子育てだって難しくなる一方。
2006年09月13日
コメント(6)
-

お絵かき
今日の保育は、「散歩に行こう!」「お茶とござもって!♪」っとピクニック気分で私の心はワクワクでした。(実際は近くの団地内を探索する程度なのですがね!)準備も整っていざ!っという時に大雨が・・・。天気予報は曇りと晴れマークだったのに!仕方なく室内で過ごしました。お絵かきや小麦粉粘土や太鼓橋をしました。この時期(1歳児)の子ども達のお絵かきって思いっきり描くことに楽しさを感じますね。決められた紙に描くよりもどことかまわず思い切りかきたいんですね!床や壁などに描いたらどんなに楽しい事でしょうね。(私もやってみたい)実際に描かれては困るので、今日はダンボールを広げて床一面に敷きクレヨンで思い切りかけるようにしました。描きながら「わ~~」「あんぱんまん!」「ん!ん!」などと声をだしたり、描いたダンボールの上を足踏みしたり…なんだかとっても楽しそうです!こういう経験大切にしたいです。言い訳ですが、急な雨でお絵かきの準備を急いだので、窓や壁までは保護する事ができず、終わってみると窓にグルグルとクレヨンで…。わーーーーーーーーー!雑談ですが、幼児のお絵かきって作品展などの決められたお絵描きに大人は目を向けてしまいますが、子どもが描きたいときに描いている自由画帳の絵に本当の子どもの心が詰まってます。見逃さないようにしたいですね!
2006年09月08日
コメント(2)
-
寿限無
寿限無(じゅげむ)とは、早口言葉、あるいは言葉遊びとして知られる古典的なネタであり、落語の前座話として有名。生まれた子にめでたい名前を付けたいと言う話になり、とにかく「長い」名前を付けようととんでもない名前を付けた、という笑い話。縁起のいい言葉を紹介してもらいどれにするか迷って全部付けてしまった、という筋の場合もある。最近テレビや絵本の中でこの「寿限無」が流行しマスコミが「子どもたちが落語を楽しんでいる」と報道をしているようです。でもある落語家のエッセイにはそのことにより、困ったことがおきているとありました。実演にでてくる「寿限無」の名前がテレビとは違う時に「違う!」と叫ぶ子ども達が増えてきたそうです。その落語家はあえて流行っている「寿限無」を演じることを少なくしているそうです。それは、子ども達に「言葉の滑稽さ」よりも落語がつくりだす「世界に浸る快感」を体感して欲しいからだそうです。落語の面白さは「間」「言葉」だけでなく「目線(眼力など)」一挙一動が大きく影響し「落語の美味さ」を形成するところにあるそうです。話は飛びますが、親から自分の子どもの「言葉数が少ない」とよく相談があります。子どもの成長によってそれぞれ違いますが、私は大人の言っている事がどれくらい分かっているかという事のほうが大切なのだと思います。自分の子どもの発達はちょっとしたことでも気になりますよね。でも、目で見えたり耳で聞くことばかり目がいってしまうと本当に大切な部分を見逃してしまうこともあります。(そればかりに目がいっているわけでは無いと思いますが。)子どもの表情など視たり発する声を聴いたり、それと同時に大人も、表情豊かに接していきたいなと思います。「寿限無」ではないですが言葉の面白さも楽しいですが、イメージしたり、感じたりと…そういう世界をもっと大切にしていきたいですね。
2006年08月14日
コメント(4)
-
生きる力
前回の日記のコメントに書いたように国や人によってそれぞれ対応が違いますが、人間形成の上で、最も大切なのが生きる力のように思います。幼児期の豊かな生活体験は生きる力の基礎をつくるのにとても大切だと思います。でも私は乳児期の育ちの方が重要なのではないかと感じます。0・1歳児時期の「人間への信頼関係」を獲得したかどうかでその後の生き方に大きく影響しているからです。生きる力は教えて得るものではないです。0・1歳の子どもたちが経験する中で、子どもが困った時こうして欲しいと思ったときに大人がどう援助するか…で育っていきます。(こうして欲しい時に 大人が敏感に気付き、それに合った対応をし、発展させるように援助すること)例えば、言葉で言い表せない思いを子どもは、指差しや「あー」などの声で訴えたりします。そのような時大人は子どもの気持ちに共感したり、気持ちに添った対応をしたり…泣きの中の気持ちも分かってあげたいですね。うちのクラスの子ども達は言葉が話せるようになってきて懸命に今大人に伝えようとしています。何を言っているのか分からないときも正直…。ごまかして「○○ね」などというと、「違う~!」と怒ることも…笑また、大人が子どもの成長する力に大きな信頼をもつ事で「自分は信頼されている」という気持ちが得られます。この気持ちが「生きる力」になっていくのだと思います。色々な子どもを見ていて大人の気分で子どもに対しての対応を変えるのではなくて、子どもの年齢や一人ひとりをきちんと見てその子にあった対応をする事が大切なのだなと思います。信頼関係は色々な成長の根底なのだと思うと仕事の重みを感じます。
2006年08月07日
コメント(2)
-
ハイハイ
今日は0歳児クラスに遊びに行きました。人見知りは6ヶ月頃から始まるといわれていますが話かけても泣かずに笑顔を見せてくれる子が多いです。でもそれって安心できる大人が(0担任)そばに居てくれるからなのでしょう。0歳児の時期の安心感と信頼関係はまたの機会に…。赤ちゃんはよくハイハイしています。つい大人はその姿をみて、「○○ちゃん~!」と手をたたいてまで、こっちに呼んでしまいます。でもせっかく赤ちゃんが自分で何かを見つけ自分で物に向かって動きだしているのに大人の思いで自分の方へ呼んでしまっている…。これも自主性を育たなくさせている原因なのでしょうか。ハイハイから自分で立って歩けるようになり、自分で立って行きたい所にいけるようになる事って子どもにとってとてつもない喜びなんだろうなと思います。
2006年08月01日
コメント(2)
-
裸足保育
うちの保育園では裸足保育をしています。裸足は子どもにとって... 足の親指から直接触れる感触を通じて脳の発達や自律神経の発達に大いに関係していきます。また、「直接感じる」ということはとても大切です。実際私も裸足になって毎日過ごしています。そうすると、今まで感じられなかったことが感じられるようになりました。暖かい冷たい、ざらざらツルツル、気持ち悪い気持ちいいなど…。昨日は砂場で裸足になってみました。子どもの頃の相撲大会を思い出しました。あの時感じた感触なのです!冬は裸足で寒いけれど、子ども達はずっと裸足です。不思議と毎年していると慣れて、私自身も風邪を引かなくなりました。自律神経が鍛えられた!?他にも、スリッパを履くよりも裸足のほうが足全体で踏ん張れる。指の力も自然に使っているのです。色々なことを学び、色々なことを感じられました。大人になると色々なことを感じる大切さを忘れてしまっているような気がします。子どもから学ぶ事って本当に沢山あります。子どもの立場になって物事考えたり感じたり、そういうことって保育者にとって大切なんだなっと改めて思いました。
2006年07月26日
コメント(2)
-
子どもの気持ち
うちのクラスの子どもの中のT君の話ですが・・・。オムツを変えるのが大嫌いで、トイレへは比較的好んでいくのですが、オムツやズボンを履く時には怒っています。そんな時無理に履かせる事も出来ます。実際そんな時もありました。でも・・・抱っこして、ギュウと抱きしめ「オムツはくのいやだったの?」などなど話し掛けわたしも「そんなにいやならいいよ!」なんて心の中で思っていました。そんな時急に抱っこから降りようとし、自分で履き始めているではないですか。わたしは驚きました。決して「履こうよ」とは言ってないのに…。この子は他の行動の中で、保育者に抱っこを求める事が時々ありますが、上の空で抱っこをしていても長い間抱っこしても満足しません。でも心をこめて抱っこをすると(どうして抱っこをもとめるのか考えたり)短時間でも子どもは満足し、自分から降りて遊ぼうとしています。わたしの中で色々な思いがわいてきました。子どもの思いは色々…一人ひとり子どもは違いますが、大人が一人ひとりのことを真剣に考え、知り、合った対応をすることが出来たらいいな改めて考えています。 知ろうとする事が大切なのかな。
2006年07月11日
コメント(2)
-
自分で
子どもに生きていく力を身に付けさせるためになにが出来るのだろう?そもそも生きる力って…。物事に対する意欲もその一つかな?よくわたし達大人は、自分の都合(早くして欲しいから)つい「まだ?」「早く」っという言葉をよく使ってしまう。せっかく子どもが自分でやろうとしている事でもつい手を出してしまう(大人がやった方が早いので)今うちのクラスの子ども達はジブンデズボンを履こうとしたり、ジブンデやろうとする姿が見られてきました。「はやくー」と思ってしまう事も正直あるけれど、今は待って、ズボンを上げる時、お尻のほうが上まで上がっていないけど、そっと直してあげ、ジブンデできたという気持ちにさせてあげ、できて嬉しい気持ちに一緒に喜んでいくそんなふうにしたい。でもこれってわたし一人が思っていてもダメなんですよね!クラスの担任みんなが同じ気持ちで同じ対応していかないとですね!
2006年07月04日
コメント(0)
-
自己主張ってスゴイ
とうとううちの園でも水遊びが始まりました。(幼児クラスではプール開きとよんでます)子どもってなぜか水が大好きですよね。1歳児という年齢を考えて水に入っている時間は7分程度くらいなのですが、もっと遊びたい!っと出そうとすると「イヤ~!!」と大きな声をだしたり、泣いて訴えたり・・・。この時期の子どもたちは玩具の取り合いなどもよく見られたり自己主張が強くて…。でもこの自己主張こそが大切なんですよね!うちのクラスの目標「ありのままの気持ちが出せる子」とあるくらい大切なんですよね。「困った子」という目線ではなくて成長を喜んで、子どものイヤな気持ちに共感していきたいです。そうするとなぜだか私も疲れない!(あまりにも強くて笑ってしまう事も)気持ちの持ちようでこんなにも変わるんだな~うちのクラスの子ホントみんな自己主張つよい!!実際強すぎると寄り添えないことも多々あるんですがね。「いけないな」と反省です。
2006年06月30日
コメント(2)
-

積み木~Part2
積み木は色々な遊び方がありますが、本来の遊び方は・・・。積み木を何かに見立てて遊ぶものです。私は今の子ども達を見ていてホントに感動し、驚きました。今まで積み木を積んでは崩し・・・。っと遊んでいた子どもたち(子どもって崩す方が楽しいようで、友だちがせっかく積み上げたものをすぐに崩したり… 「あーあー」といいながら何度も何度も…。ところがある日遊び方が違ったのです。1歳3ヶ月の子が一つの長細い積み木を手に取り横にし、「ブーン」とその積み木を走らせました。私はこれを見た時成長に感動して他の担任に思わず声を震わせながら「見てみて!!」と叫んでしまいました。そして2歳の子は写真のように積み上げ「トラック」と言っています。それを見て他の子どもも「アンパンマン」といいながら積み木を積んでいます。子どもたちは木のぬくもりを感じながら自然と何かに見立てて遊び始めています。子どもの発想を大切にし、創造力が伸ばせるように私たちは寄り添っていきたいですね!
2006年06月25日
コメント(0)
-

積み木~Part1
子どもが積み木を積むってことってすごい事なんです!ブロックは手の力を入れて遊ぶのに対して積み木は力を抜いて遊ぶものです!目で見てバランスを感じながら力を抜き、積み上げていく・・・。なんだか簡単なようで、すごい難しいことなんだと思います!子どもの今までできなかった事が出来るようになることってホント感動します!この感動を忘れずにいたいです。わたし達は今当たり前にできる事でも出来るようになるまでには一つひとつ感動があるんですね。子どもの成長を子どもと一緒に喜んでいきたいな!
2006年06月23日
コメント(3)
-
高い所大好き
私のクラスの部屋は子ども達がそれぞれ落ち着いて遊べるように仕切り棚を使ってコーナーを作ってます。(絵本コーナー ママごとコーナーなど)でも困ったことにその棚に登ってしまいます。こちらとしては危ないし、登る所ではないので登ろうとすると、登るところではないことを伝え降ろします。それでも一向に止めようとしません・・・。注意しないで良い方法は無いかとずっと考える毎日でした。でも分かったのです!子ども達は身体を動かす事に満足感を得てないことに!遊びの中で上り下りをする遊びをしたり、雨で身体を十分に動かせない日でも身体をたくさん使うようにしました!今日も園庭をこれでもかこれでもかといくらい走りました。(追いかけっこ)1歳児なのにこんなに走れるのか…私のほうが汗いっぱいかきました!すると自然と部屋で仕切り棚に登ろうとする子がいなくなったのです。教え込む保育ではいけないんだなあっと改めて感じた一日でした。もちろんお昼ねは子ども達と一緒に寝てしまいました。
2006年06月21日
コメント(0)
-
散歩
今日は近くの公園まで子どもたち(1歳児)と散歩に行ってきました。散歩の途中で子ども達は花を見つけたり、花のそばを飛んでいる蝶を見つけて指さししたり、「あー」などといって私に教えてくれます。静かな木陰に行くと、小さな小鳥の泣き声までにも気づきます。こんな子どもたちの気づきを見逃さないで共感していく事で子ども達は自信を得て、言葉やいろいろな世界が広がっていきます。 子ども達の成長には驚かされますが一日一日子どもたちの成長大切にしていきたいと思う今日この頃です!さ!明日も天気良さそうなので散歩に行って子ども達と一緒に楽もう!
2006年06月19日
コメント(0)
-
ブログはじめてみました
ブログをはじめてみたい!と思い続け数ヶ月…。ようやくはじめてみました。ブログには保育園で働いていて感じた事、また日々の生活で感じた事を記録していきたいと思います!!
2006年06月17日
コメント(2)
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
-

- シングルマザーの子育て
- もうどうしたらいいか分からない
- (2025-11-14 23:09:22)
-
-
-

- 子連れのお出かけ
- 谷津干潟 ぶらっと観察会 空飛ぶ宝…
- (2025-11-07 07:53:33)
-
-
-

- 0歳児のママ集まれ~
- ☆寝かしつけ ベビーキャップ☆
- (2025-11-16 21:36:26)
-