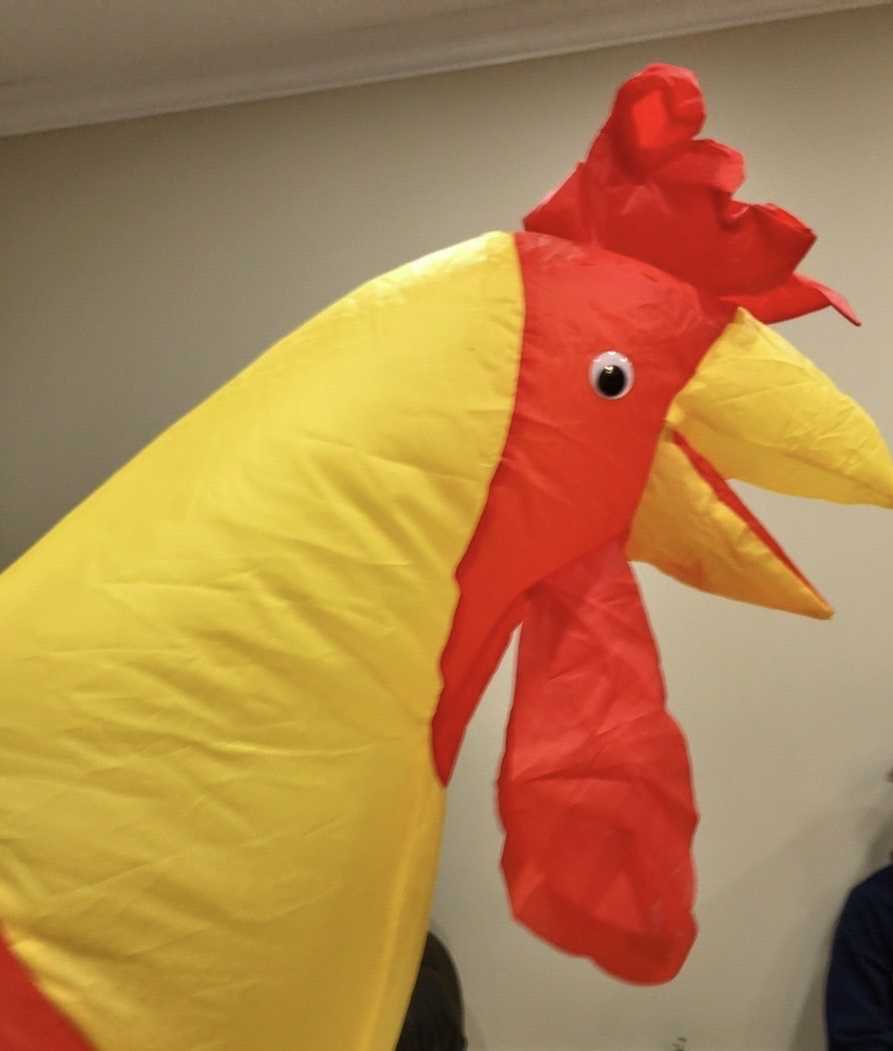-
1

ラジオ深夜便 ▽みんなの子育て☆深夜便 情報
ラジオ深夜便 ▽みんなの子育て☆深夜便 情報■2023.03.02 01:05~▽深夜便アーカイブス【みんなの子育て☆深夜便 ことばの贈りものアンコール 20221度放送分より】「母ちゃん ありがとう!」】(初回放送:2021.8.27)エッセイスト 内田也哉子(樹木希林の娘)■2023.03.01 01:05~▽深夜便アーカイブス【みんなの子育て☆深夜便 ことばの贈りものアンコール 2021年度放送分より】「それでも面白がって生きていく】(初回放送:2021.6.25)■2023.02.23 00:10~ ▽みんなの子育て☆深夜便 子育てリアルトーク・後半「子育て事件簿 第6段」■2023.02.23 01:05~ ▽みんなの子育て☆深夜便真夜中の絵本 「うどんのうーやん」作:岡田よしたか 「いちごばたけの ちいさなおばあさん」作:わたりむつこ 「ぞうくんのさんぽ」作:なかのひろたか▽#絵本でつながろう■2023.02.23 02:05~ ▽みんなの子育て☆深夜便みんなの音楽「リクエスト特集」■2023.02.23 03:05~ ▽みんなの子育て☆深夜便みんなの音楽「リクエスト特集」■2023.02.23 04:05~ ▽みんなの子育て☆深夜便ことばの贈りもの「母乳で小さな命を守りたい」 「」作:https://www4.nhk.or.jp/shinyabin/x/2023-02-23/05/67626/3740120/ 午後11時05分~ 午前5時00分ラジオ深夜便▽みんなの子育て☆深夜便 子育てリアルトーク・前半午後11時05分▽みんなの子育て☆深夜便 子育てリアルトーク・前半「子育て事件簿 第6弾」 ▽天気概況・明日の日の出【アンカー】村上里和,【出演】詩人・児童文学作家…工藤直子,シンガーソングライター…新沢としひこ午前0時10分▽みんなの子育て☆深夜便 子育てリアルトーク・後半「子育て事件簿 第6弾」 ▽天気概況・世界の天気と予想気温【アンカー】村上里和,【出演】詩人・児童文学作家…工藤直子,シンガーソングライター…新沢としひこ午前1時05分▽みんなの子育て☆深夜便 真夜中の絵本「うどんのうーやん」 作:岡田よしたか 「いちごばたけの ちいさなおばあさん」作:わたりむつこ 「ぞうくんのさんぽ」作:なかのひろたか ▽#絵本でつながろう ▽深夜便のうた・天気概況【アンカー】村上里和,【出演】俳優…小池徹平,埼玉東萌短期大学幼児保育学科の学生午前2時05分▽みんなの子育て☆深夜便 みんなの音楽「リクエスト特集」 ▽天気概況【アンカー】村上里和午前3時05分▽みんなの子育て☆深夜便 みんなの音楽「リクエスト特集」 ▽天気概況・各地の天気と予想気温【アンカー】村上里和午前4時05分▽みんなの子育て☆深夜便 ことばの贈りもの 「母乳で小さな命を守りたい」 ▽誕生日の花・番組予告【アンカー】村上里和,【出演】日本母乳バンク協会 代表理事…水野克己,【きき手】江崎史恵
2023.02.19
閲覧総数 37
-
2

子育て爺[臨時追加]どう防ぐ子供の自殺
NHKラジオで、「どう防ぐ子供の自殺!」の放送がありました。詳細は次の各ページです。●「どう防ぐ 子どもの自殺」① ~知ってほしい! 子どもの現状~●「どう防ぐ 子どもの自殺」② ~見逃さないで! SOSのサイン~●「どう防ぐ 子どもの自殺」③ ~子どもの不登校の対応は?~●「どう防ぐ 子どもの自殺」④ ~ネットやSNSに気をつける~●「どう防ぐ 子どもの自殺」⑤ ~子どもの幸福度を高めるには~ここでは、その抜粋です。「子どもの自殺」は時として、理由もなく予兆もなく突発的に起こったと語られることがあるが、何らかの「シグナル」やSOSが出されていることが多い。それをまわりの大人が気づいていないのがほとんど。子どもは、大人に比べて自分の考えや思いを言語化するのが苦手。自殺の予兆の4つのサイン 行動 睡眠 食欲 体調この4つの面に出てくることが多い。SOSのサインに気づいたら、子どもに“心配しているよ”と声かけすることが、時として命を救うことにつながる。●行動では・学校に行きたがらなくなったりする・勉強に身が入らなくなり、成績が落ちたりする・身だしなみに構わなくなったりする・イライラしやすくなったり、暴れたり暴力をふるったりする・ゲームやネットに依存するようになったりするこの5つが、子どもに現れる主な行動でのSOSのサイン。本人よりも周囲が気づきやすいのが行動面のサインの特徴。心の病気の場合は、早期発見早期治療が理想。●睡眠では、・ふとんに入ってもなかなか寝つけない・遅くまで夜ふかしをしている・朝起きるのがつらそう、なかなか起きられないなどがサイン●食欲は・睡眠とともに、食べることは心身のバロメーター・いつも遊んでいた友達と不仲になったり、いじめられていたりすると活動量が減り、食事の量が減ってくることもある・食事の量や好き嫌い、食事の際の表情や会話などにも目を向けるとよい●体調面では・元気がない・顔色が悪い・腹痛や頭痛、めまい、吐き気などを訴えるなどには注意が必要。心の変調が、当初体調に出てくることはよくあること。緊張すると頭やおなかが痛くなったり、下痢や便秘をすることはめずらしくない。サインやSOSがあったと思ったら――対処の仕方――学校であれば「スクールカウンセラー」が相談にのってくれる。また、緊急時であれば、保護者からでも子どもからでも、心のSOSを相談できる相談先が電話・SNSを通じて整備されている。例えば「チャイルドライン」や「24時間SOSダイヤル」などがある。次に、不登校実は、子どもの不登校と「子どもの自殺」には密接な関係がある。学校生活がつらいにもかかわらず、不登校を選択できなかった子どもたちが自殺に追い込まれている、というケースが多い。時期としては「長期の休み明け」、例えば4月の「新学期」や9月の「夏休み明け」に子どもが命を絶つことが多い、ということがわかっている。長期の休みが明け、学校に行き始める時期は生活環境が大きく変わり、大きなプレッシャーや精神的動揺が生じやすい。学校がつらくても不登校を選択できない子どもは自殺につながりやすい。別の視点で見れば「不登校を選択することで、自殺しなくてすんでいる」子どもたちが実は相当数いる、ともいえる。子どもたちが「学校に行きたくない」というシグナルを言葉や体調で示したときに、それを感じ取って真剣に向き合ってあげることが大切。無理をさせず、学校を休ませることも大切な選択肢の1つ。親やまわりの大人の対処方法。ポイントはいくつかある。特に大きなものを3つ。1.◆ 無理やり学校へ行かせたり、叱ったりするのはよくない。◆ 「そんなにつらいなら休んでいいんだよ」「また学校に楽しく行けるように相談していこうね」などと伝えてあげる。親が自分のつらさを理解してくれている、自分の味方でいてくれると実感できることにつながる。これには大きな意味がある。自分がひとりではないと感じられるから。2.◆ 問いつめずに子どもの話を聴くこと。「問いつめずに子どもの話を聴く」とは、「何を言ってるの、休むなんて許されない」とか「理由をちゃんと言いなさい」とか、「勉強ができなくなって落ちこぼれちゃうよ」などと強い言葉で責めたり、問いつめたりしがち。しかし、子どもは学校に行けなくなるほどのつらい気持ちを抱えてる。その中で親からも問いつめられたり責められたりすると、「自分の気持ちをわかってくれない」「何も話したくない」と心を閉ざし、逆効果になってしまう。それが自殺につながることもある。まずは子どもの話を聴いてほしい。3.◆ 学校に行かない選択肢を選んだら、学校以外で学べる環境を整えてあげること。学校に行きたくない理由として「勉強や授業がわからない」ということも少なくない。そういった場合には子どもの“ひっかかり”に応じた個別学習の環境整備が望ましい。勉強や授業が学校に行きたくない要因でなかったとしても、学校を休んでいる間に授業が進んでしまって学校の勉強についていけなくなるのでは、という不安は子どもにとって大きなもの。――親御さんの立場からすると、不登校がいつまで続くのかと心配になってしまうかもしれない。学校に戻ったときに学業に追いつけるのか、そして友達関係が回復できるか不安だと思う。まずは、○ 学校に行きたくないことが決して特別なことではない○ 子どもが怠けているとか、子どもが弱いとかそういったことでもなく、誰にでも起きることということを知っておきたい。不登校の児童・生徒の数は約34万人といわれ、年々増加してきており、毎年のように過去最多を更新している。よく、不登校対策で「無理に学校に行かせないでください」「学校に行け行けと言わないであげてください」と言う、それは自殺対策にもなる、ということも知っておきたい。児童・生徒の自殺の7割は高校生である。高校生が、自殺のリスクがより高くなるということを家庭でも学校でも認識していく必要がある。孤立を防ぎ自殺を防ぐためにも、周囲が味方であって本人のことを大切に思い、心配していることを本人にわかる形で明確に伝え、話しやすい環境や方法を整えて、よく話を聴いてあげることが大切。――ポイント――「学校に行かない」という選択肢を与えることで助かる命がある。つらい気持ちに気づき、受け入れ、よく話を聴くこと。最近では対面型の「いじめ」だけでなく、ネット上でのいじめが大幅に増加している。携帯電話やスマートフォンが子どもたちの間にも急速に普及し、子どもたちの携帯電話のメールやインターネットの利用が増加している。それに伴い、インターネット上の掲示板やSNS等を通じて特定の児童・生徒に対するひぼう中傷が行われるなど、「ネットいじめ」という新しい形のいじめ問題が生じている。文部科学省の報告では、ネットいじめの件数は8年間で2.5倍まで増加しているという。ネットいじめのやっかいなところは、1つは学校だけではなく、家にいても休日でもいじめられるので、精神的により追いつめられるということ。書き込まれた内容は簡単に消せず、残ってしまうし、場合によると簡単に拡散したり、されたりする。LINEやクローズドのSNSでは大人が簡単には見つけられないので、いじめの把握が遅れることも多い。いじめには「いじめの4層構造」という概念がある。● 「被害者」● 「直接の加害者」● いじめ行為をはやしたてたり、けしかけて助長させる「観衆」● いじめ行為を黙認して、止めるための行動をしない「傍観者」その4層があるとされる。直接の加害者も、観衆も傍観者も、責任の大小はあれど「いじめの加害者」と見なされる。ネットいじめでも同じで、例えばグループLINEで嫌がらせを放置しているだけでもいじめに加担していると見なされる。いじめていたり、いじめられている当事者でなくても 、間接的な加担をしていないか、関心を持つべき。まわりの大人の対処方法学校など、当事者以外から目撃がされやすい対面型のいじめと違って、ネットいじめは、親や学校の先生など周囲の大人が気づきにくい。子どもには ふだんから「SNSや、ネットの掲示板の書き込みなどで(よその子のことであっても) いやなことがあったら、必ず一緒に解決するから教えてね」と伝えておくことが大切。そして、何らかの兆候や訴えや、子どもからのSOSをキャッチしたときには、学校とも共有しての対処が必要。担任の先生以外にも、スクールカウンセラーや保健室の先生もいる。話しやすい先生に相談するのもいい。知り合いに相談しづらい場合には、国などにも相談窓口がある。いじめがSNS上で起こっている場合には、フォローを解除したりブロックするなど、相手から距離をとることが必要。また、「いじめ投稿をネットの管理者に報告する機能」も使うことを検討のこと。ソーシャルメディア企業には、ユーザーの安全を守る義務がある。 ――管理者や企業にいじめを報告する際に行うことは――。“テキストメッセージ”やSNS投稿の“スクリーンショット”などを保存して、「状況証拠」を集めておくことも有効。いじめをなくすには、いじめの存在を特定する必要があり、そのためには報告することが重要なカギになる。実際に身の危険を感じたときは、警察や、文部科学省・法務省などの緊急サービスに連絡をすること。 ネットやゲームをする時間が長くなっている――そのほかに、ネットに関する課題や問題点――ネットの問題点としては、「子どもがネットやゲームをする時間が長くなっている」ことが挙げらる。2020年のコロナ禍で行った調査では、勉強以外で使うスマホやゲームなどの時間が1日4時間を超えた子どもは、小学生で12%、中高生では25%もいた。はい。また、コロナ禍前よりもスマホ・ゲームなどの使用時間が増えた子どもの割合は、全体の4割になった。外遊びや、リアルな友人との交流の機会が失われてしまうことも問題。傷つく経験や、我慢する経験の少ないまま大人になっていくと、イライラしやすくなったり、社会の中で傷ついたりするととたんに精神的な危機に陥って、自殺につながるケースも多くなる。 ――依存の問題は――ゲーム依存やネット依存など「依存症」のリスクは問題。依存症も自殺につながる要因となるので、注意。 ――ポイント――ネットは子どもに大きな可能性を与える一方、いじめや依存のリスクもある。自殺につながることもあるので注意。子どもの幸福度を高めたいユニセフが、先進国38か国の子どもの「精神的幸福度」ランキングを発表した。日本は38か国中、37位。ワースト2位だった。「子どもの多様性」を大人や社会が受け入れ、子どもたちに無理を強いることなく、のびのびと生きていける社会をつくっていくことが大切。子どもも親も悩んだり行きづまったときには、気軽に、さまざまな方法や場所で相談や支援にアクセスできる、そんな「相談支援の多様性」も大切。本人にとってよい経験を積み重ねることも大切。特別な経験である必要はない。例えば、小さな成功体験でもよい。「できていることをほめられる」「行動をほめられる」、「ありがとう」や「役に立った」と言われて人と人とのつながりの中で認められ、感謝されることがよい経験となり、それが、自殺を防ぐことにもつながっていく。いじめ問題は深刻化している。いじめ被害を受けた子どもの自殺が時折報道されるが、それだけではなく、幼少時にいじめ被害を受けると、大人になってから「うつ病や不安障害などを発症するリスクが上昇」あるいは「自殺の発生リスクが上昇」することがわかっている。早期に発見し、見逃さず、早期に適切な介入をすることが、子どもたちの自殺予防にとって重要。注意したいのが「ヤングケアラー」の問題。ヤングケアラーとは、障害や病気のある家族に代わり日常的に家事やきょうだいの世話をしている、また、障害や病気がある家族の介護・介助・看病・身のまわりの世話などをしている子どもたちのこと。小学6年生を対象に実施した調査では、本来大人が担う家事や介護などを家族に代わって日常的に行っている、と回答した子どもはおよそ15人に1人という結果が出ている。ヤングケアラーになると、本来の子どもらしい経験が制限され、大きな精神的負荷が子どもにかかってくる。――家庭という、極めてプライベートな所で起きていることをどう解消していけばいいのか。周囲の大人が、子どもが出す小さなサインに気づいていこうとする意識を持つこと。注意して手を差し伸べてほしいとも。まわりで悩んでいる人がいたらやさしく声をかける、声をかけ合うことで、不安や悩みを少しでもやわらげることができるかもしれない。覚えて実践 TALKの原則実は、死にたい気持ちを持った人に対応する際に有用な「TALK(トーク)の原則」というものがある。―「T」「A」「L」「K」でTALK。それぞれに意味がある。◆Tell・・誠実な態度で話しかける◆Ask・・自殺についてはっきりとたずねる◆Listen・・相手の訴えに傾聴する◆Keep safe・・安全を確保するそれぞれの頭文字をとって「TALKの原則」。――誠実な態度で話しかける「Tell」、自殺についてはっきりとたずねる「Ask」、相手の訴えに傾聴する「Listen」、そして、安全を確保する「Keep safe」でTALKの原則ということ。これ、しっかりと覚えておきたい。TALKの原則を実践し、悩んでいる人によりそい、かかわりを通じて孤独・孤立を防ぎ、支援することが重要。自分は世の中で居場所も役割もない、自分を必要としてくれる人もいない、自分が生きていてもまわりに迷惑だ、自分が死ぬのが一番の解決策になる……そういった考えに追い込まれている人の負担感を和らげ、自分が誰かに必要とされている、自分が社会に居場所がある、自分を心配してくれる人がいる、そういった再確認をさせてくれる人が増えていくことが大切。――ポイント――子どもの幸福感を高め、社会全体で子どもを救う「セーフティーネット」を作ることが自殺予防につながる。
2025.08.29
閲覧総数 12