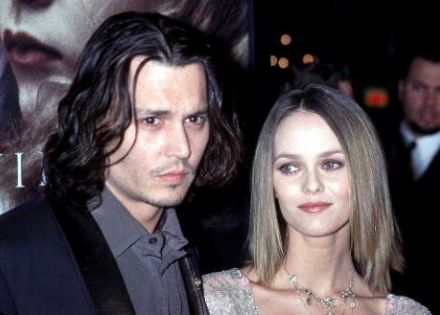3
バラの収穫が終わりに近づく頃、戦争の足音は日に日に高まりつつあった。救世主であるロシア軍はすでにドナウ河の手前まで迫ったという噂だ。カザンラクやカルロヴォといった、バラの谷ではとりわけ大きな村とは違って小さなこのロザヴォの村にもトルコ兵の姿が増えた。元締めはカザンラクから派遣されたセリクの父親だ。
そんな中、火の手は村の西端で上がった。
使徒ヴァシルを中心とした組織の仲間や村の協力者が密かに集まっていた学校を、トルコ兵が囲み火をかけたのだ。
湿った夜気のせいか火は思ったほど燃え広がることなくやがて鎮火したが、トルコ兵が押し入った時には、半分崩れた学校の中に人影を見つけることはできなかった。トルコ兵の動きを察知していた活動家たちは、かねてから用意していた秘密の通路を使って逃亡した後だったのだ。
彼らの追跡と同時に村人たちが、モスクとして使われている教会に集められた。そこには蒼白な顔をしたアルシアとその両親の姿もあった。
少し前、夜空を赤く染める炎に村の異変を感じた私は幌馬車から出て、近くにあるアルシアの家へと向かった。彼女は両親と共に役人に連れて行かれるところだった。
「ローラン!兄さんとヴァシルが…!」
大粒の涙をその大きな目からこぼしながら、アルシアは駆け寄った私の腕を必死に掴んだ。彼女の兄はヴァシルの右腕として活動に参加していたのだ。危ういところを逃げ延びた彼らは、バルカン山脈北側の村エタルへ逃げるため、シプカ峠に向かったという。
尚も私に取りすがろうとするアルシアを、トルコ兵が容赦なく引き離す。
「ロマに用はないっ。邪魔だ、どけ!」
役人が私に銃剣を突きつけ、アルシアを引き立てていった。流浪の民ロマは故郷を持たないゆえに独立運動に関わることは一切ない。それ以前にどこの国でも、貧困や犯罪の温床として忌み嫌われ、家畜以下の扱いを受けることには慣れている。
羊たちがうずくまって休むトラキア平原を北に向かうと、夏でも頂上にうっすらと雪を頂くバルカン山脈が迫る。その山裾の集落がシプカ村で、更にその先にはバルカン山脈越えの交通の要衝、シプカ峠がある。ここは古くからトラキア平原と北のドナウ平原を繋ぐ街道として多くの旅人が行き交った。
ヴァシルをはじめとする活動家たちは、このシプカ村のどこかに身を潜めているに違いない。
私は闇と一体になりながら、目を閉じて空気に交じる匂いを胸に深々と吸い込むと、鋭い嗅覚を頼りに、夜のシプカ村へと馬を走らせた。特殊な能力を持つ私がヴァシルとアルシアの兄の居場所を探り当てるのは、さほど難しいことではなかった。
村人たちが集められているモスクで、組織の使い走りをしていた村の少年を使ってアルシア宛の手紙を届けさせた。
少年が裏口のトルコ兵の気を逸らせている間にモスクを抜け出したアルシアが、不安と緊張の色を滲ませたまま、指示した酒場の裏に現れる。
「ヴァシルたちはシプカ峠に向かう途中のモスクに潜伏している。あのモスクは表向きだけで、地下に隠し部屋がある。正教会の祭壇が残っていてシプカの活動家たちの根城になっている。ただ、すでにトルコ側はモスクを嗅ぎつけた。急がなければ…。さあ、乗って」
彼女を馬上に押し上げた瞬間、馬の前に立ちはだかった男がいた。
「アルシア、君がこんなことをするなんて残念だよ。僕は君と君の家族を助けると約束したのに。それは何故か、君にもよくわかっているよね…」
セリクは、普段の温厚な彼とは打って変わって感情を抑えた低い声で言い放った。ニコニコと愛想をふりまくいつもの笑顔は今は影を潜めている。
彼はゆっくりと馬に近づき手綱を手にかけると、馬上のアルシアを鋭い眼差しで見上げた。
「セリク…、あなたは村人たちの味方だと思っていたのに…」
「味方だよ。できる限り、この村の人たちを助けたい。だが…」
手綱を握ったまま、呆然と彼を見下ろすアルシアに、彼はさらにたたみかけた。
「僕はずっと君を見つめてきた。美しい君を僕の花嫁にしたいと…。もし君が僕との結婚を承諾してくれるなら、僕は君の兄さんとヴァシルを見逃すよう父に頼むことができる。だが拒めば、優しい兄さんと君の愛する若者の命は、シプカで散ることになる」
それは、明らかに脅しだった。セリクはふたりが恋仲であることを知っていたのだ。
アルシアの兄とヴァシルの命は、今やセリクという男の手に握られている。アルシアに、選択の余地はなかった。
彼女は唇を噛みしめると、毅然と前を向いて言った。
「わかりました。あなたの妻になります。ただ、見つかった時は共に逃げると私たちは約束したわ。ヴァシルは私を待っているはず。だから最後にひと目だけでも彼に会わせて!」
セリクを見返すアルシアの目は、否と言わせないほどの強い光を放っていた。暗闇の中でも燃えるような赤い髪が意思を持つかのごとくうねり、青い瞳は強い怒りのためにその濃さを増していた。気圧される形でセリクが馬の前から身を引いて頷く。
「いいだろう。父には彼らに降伏を説得させるために君を向かわせたと言おう。もちろんそうできるのなら、それにこしたことはないが…。ただし、君が戻るまで君の両親は拘束させてもらう。あわよくばヴァシルと逃げようなどと思わないことだ」
「わかってるわ…」
セリクの狡猾さに対する怒りを抑えながらアルシアが低い声でそう返すと、私は彼女の後ろに乗ろうと鐙に足をかけた。
が、強い力で引き戻される。
「お前が行く必要はない、ローラン。代わりにこいつを行かせる。わかってるな、彼女に乱暴はするなよ」
後ろに控えていたトルコ兵にセリクが念を押すと、心得顔の兵士が馬上のアルシアの前に座る。セリクと睨み合う私は、観念して彼女に言った。
「急ぐんだ、アルシア!」
涙の跡を拭ったアルシアが頷くと同時に、兵士が馬腹を力強く蹴った。勢いよく走り出した馬に危うくぶつかりそうになったセリクはかろうじてかわすと、舌打ちをして私を睨み付けた。
「何者だ、お前…。ただのロマではないな」
セリクの背後には、護衛の兵が彼を守るように数名張り付いていた。
〜つづく〜 (次回最終回)
タグ: ブルガリア